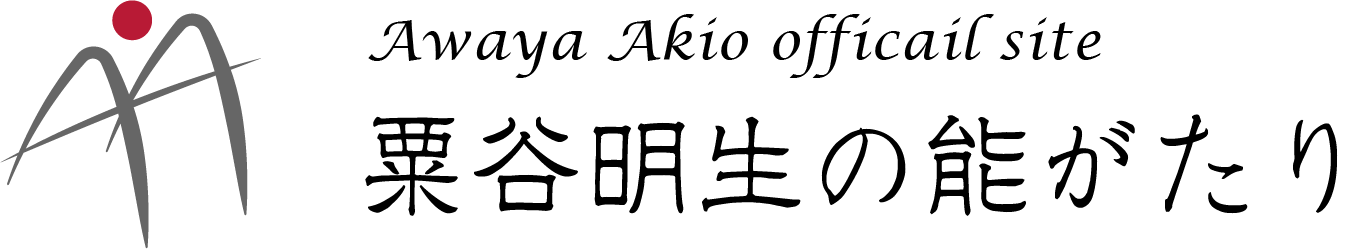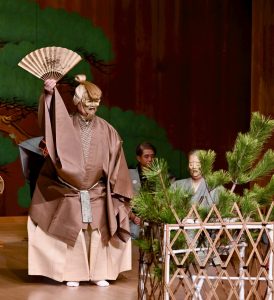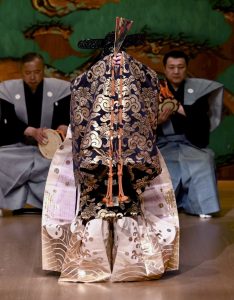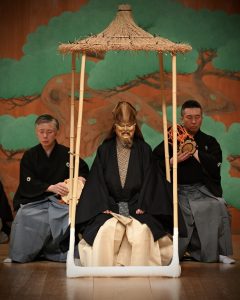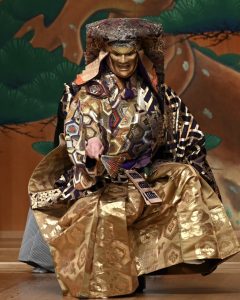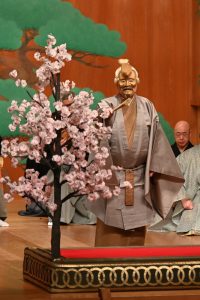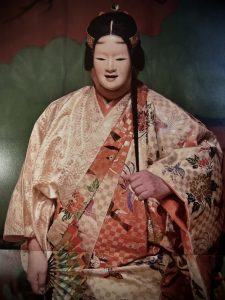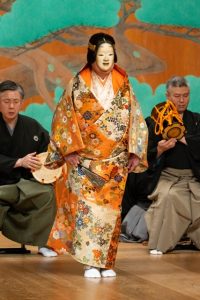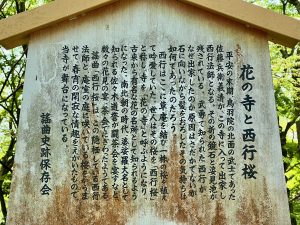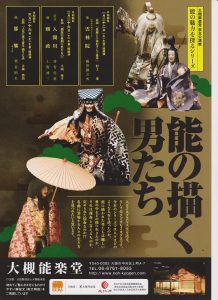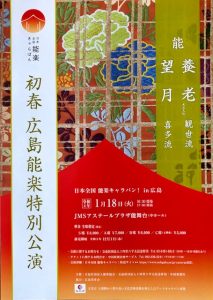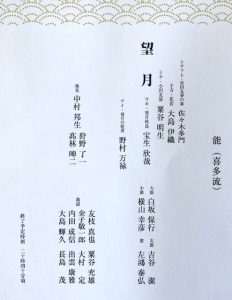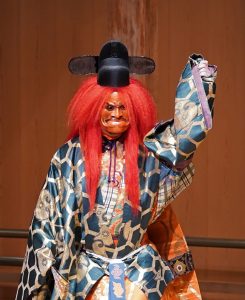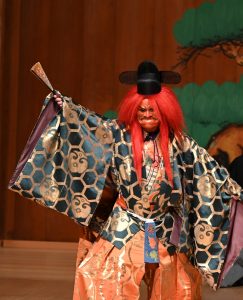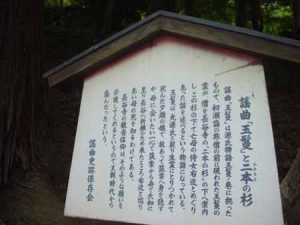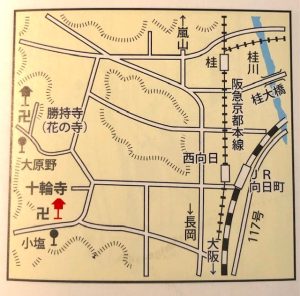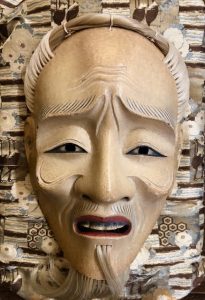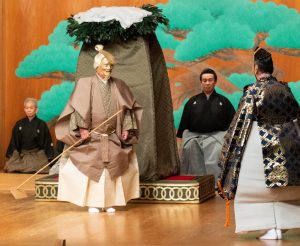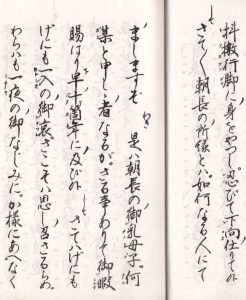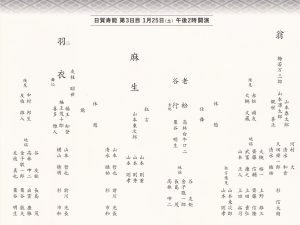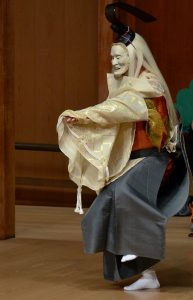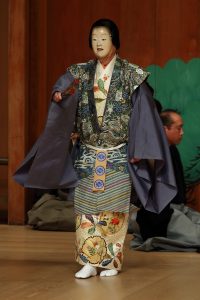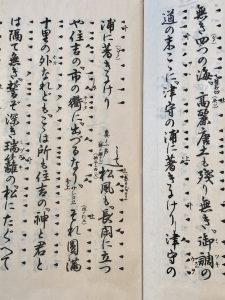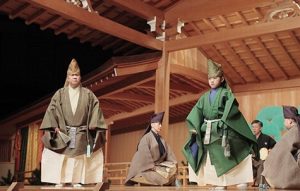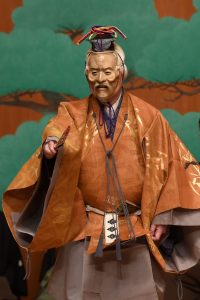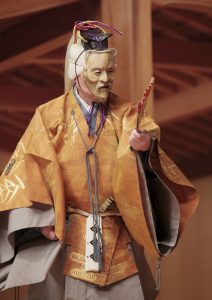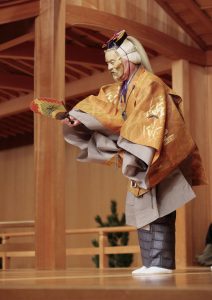『高砂』を勤めて 珍しい小書「作物出」投稿日:2025-05-26

『高砂』を勤めて
珍しい小書「作物出」
夫婦仲の悪いお話の『鉄輪』を4月28日(令和7年 広島蝋燭薪能)に勤めたあと、2週間後の5月11日には、真逆の夫婦円満の秘訣を話す『高砂』を「喜多能楽堂令和改修竣工記念能」にて勤めました。
喜多能楽堂は老朽化に伴い、2年前(令和5年)から大規模改修工事を実施し、この度、無事竣工、4月1日に正式オープンとなりました。その間、喜多能楽堂が使えなくなり、皆様にはご不便をおかけしました。新しく生まれ変わった能楽堂は響きがよく、耐震対策も整いました。皆様のご利用をお待ちしております。
『高砂』は本脇能と言われ、喜多流は脇能の中でも重く扱っています。脇能とは『翁』の脇にあるという意味合いがあり、本来は翁付高砂として、一人の大夫が両方を続けて勤めますが、最近では時間や費用の問題等があり、『翁』だけ、『高砂』だけと別に演じられることが多くなりました。今回、『翁』は素謡で、シテは『高砂』とは別の人間が勤めましたが、『翁付高砂』という正式な形に近い番組立てとなったと思います。
まずは『高砂』のあらすじを記しておきます。
阿蘇の宮の神主友成(ワキ)は播磨国高砂にて老人夫婦(前シテとシテツレ)に高砂の松の謂れ、松の長久のめでたさ、相生(相老)の夫婦の情愛、和歌の徳の話を聞きます。やがて夫婦は高砂住の江の神だと告げ、住吉で待つと言って沖に出てしまいます。(中入)
友成と従者(ワキツレ)が舟にて住吉に渡り待っていると、住吉の神(住吉明神・後シテ)が現れ、颯爽と舞を見せ、この世を寿ぎます。
『高砂』の老人夫婦、尉と姥は、今で言う遠距離恋愛で、住吉に住む尉は高砂に住む姥のところに通っています。ワキが老夫婦に高砂と住吉に分かれて住む理由を尋ねると、二人は高砂、住の江の松だって相生の覚えがあると言われる、まして人間だって、遠く離れて暮らしていても、お互いに心が通いあっているから相生(相老)の夫婦なのだと答えます。
「離れていても」でなく、「離れているからこそ」夫婦円満である、それが秘訣、理想と謡う詞章に、なるほどと納得してしまいます。今の世でも通じるのではないでしょうか。
「同棲は神が作り、悪魔が結婚を作った」と、面白いジョークがあり、これには、思わず吹き出してしまいましたが、「いやこれは真実!」と思うと、笑えず頷いてしまいました。
話しを戻します。
今回は珍しい「作物出」の小書付きです。
「作物出」は雄株(黒松)と雌株(赤松)が一つの根から寄り添うように生えている「相生の松」を舞台正面先に置きます。今も高砂神社にはそのような雌雄一体の相生の松があるようです。本来ならば、その相生の松と同じように、黒松と赤松を用意しなければいけないのですが、昨今なかなか赤松が手に入らないようで、今回は黒松だけで作りました。作り物の松を見ていると、なんだか男が2人寄り添うように見えて、正直、あまりしっくりしませんでしたが、今のご時世では仕方のないこと、と諦めた次第です。
この大きな松の作り物を舞台正面先に置きますので、正面からご覧になる方にはシテの姿が見えづらくなります。そのため通常のクセの上羽後の「掻けども、落葉の尽きせぬは」の杉箒にて落葉を掻く型に変えて中啓で舞う型になるのが教えです。我が家の伝書では、その替わり、下げ歌の「落ち葉衣の袖添へて、木蔭の塵を掻かうよ」で掻く型をするように伝えられています。落ち葉を掻く型は長久の「久」の字を逆さまに書くように杉帚を動かす型で、とても意味深い型なので、ここを割愛させたくない先人達の工夫と思われます。
今回午後の公演のため下げ歌を省略し演能時間を短縮したため、私は杉箒で掻く型を、上げ歌の「木の下蔭の落ち葉かく」の謡で、通常の正面先ではなく常座で行いました。また、クセの後半は中啓で舞う型となるので、序にて杉箒を捨て、肩上げしている両袖を下ろし、中啓で勤めました。作り物の松を讃美するように招き扇をします。
小書『作物出』は私の知る限りでは粟谷能夫が厳島神社神能で勤め、その後、長島茂氏が勤めていますが、久しぶりの演能となりました。勤め終えて、演者は演じにくい、観客は見にくいという、この演出はやはりあまり演らない、人気のない小書であった、と実感しました。
もちろん、最初に相生の松が置かれることで、この場所が播磨国高砂の地であると想像しやすくなりますが、見せ場の杉箒で掃く型が舞台正面先で行えないのは、どうも物足りなく、やはり杉箒で掃く型の方に軍配が上がるように思いました。ご覧になられた方々のご意見をお聞きしたいです。
後場は、昔結婚式でよく謡われていたワキとワキツレの待謡
「高砂や此の浦船に帆を掲げて・・・・・・はや住の江に着きにけり」
で、舞台は高砂から摂津国住吉に移ります。
すると住吉の神が颯爽として現れます。演者としては祝言の意識を重視し、力強く、スピード感溢れるスムーズな動きで舞うことが最優先されます。
『高砂』という能の老夫婦、尉と姥は喜多流(下掛り)では高砂住吉の神の化身という設定ですが、上掛りでは老夫婦を松の精としていて、多少ニュアンスの違いがあります。
この能は、相生の松の長久、老夫婦の和合、和歌の讃美と、多くを語り尽くして、国の恒久平和や民の幸せを願うという流れで、盛り沢山です。作者・世阿弥も申楽談儀に「相生(能『高砂』のこと)もなお尾鰭(おひれ)が有るなり」といっているほどで、盛り込み過ぎの感がないでもありませんが、世阿弥の時代、和歌は重要で、万物を表現し、平和や繁栄につながるものとして大切にされていたので、後シテが和歌の神でもある住吉明神として現れて舞うというのは自然で説得力があるように思います。
また、前シテの老夫婦も神の化身ですから、よぼよぼの老人として演じません。前も後も全体にさわやかに、春風が吹くように、サラッとして颯爽と力強く、スピード感をもって演じます。謡も、すべて強吟ですが、妙に堅すぎて重々しくなり過ぎては落第です。
私の『高砂』の初演は平成15年、翁付で、厳島神社神能にて奉納しました。今回、それから実に22年ぶりの再演です。ツレの姥役は数回経験していますが、式能にて、父・菊生の『高砂』でツレを勤めた時のことが強く印象に残っています。謡が硬質でありながら、何ともサラリとした心地良い軽さで、父との連吟は、今でも良い思い出となっています。
小書「作物出」になると、面は「三日月」に代わり、白色大口袴は白色半切袴となると伝書にありますので、より強さが強調されます。残念ながら今回は粟谷家の都合により面は常の「邯鄲男」で勤めましたが、半切袴は使い勝手の良い白色青海波模様が修理で使用出来なかったため波模様にしました。写真をご覧下さい(左長島 茂 右粟谷明生)。
『高砂』には祝言謡が多くあります。先に述べた結婚式で謡われる「高砂や此の浦船に帆を掲げて・・・」の待謡や、「四海波静かにて、国も治まる時つ風・・・」の初同、最後の「千秋楽は民を撫で、万歳楽は命を延ぶ。相生の松風、颯々の声ぞ楽しむ」は謡曲愛好家の皆様には親しまれている謡です。喜多流の「祝言小謡集」には『高砂』から5か所も抜粋されているほどです。能『高砂』をご覧になる方は、これらの祝言謡を気持ちよく聞いて心が晴れやかになってお帰りになれるのではないでしょうか。その意味で『高砂』はやはり最高位の祝言能で今回の竣工記念能で選曲された所以でもあります。私たち演じる側も春のさわやかな風が吹くような陽な気持ちで謡い、勤めるのを忘れてはいけない、と改めて思いました。
出演者
シテ 粟谷明生
シテ連 狩野祐一
後見 内田安信 佐藤 陽
ワキ 宝生常三
笛 藤田貴寛
小鼓 森澤勇司
大鼓 佃 良勝
太鼓 小寺真佐人
(2025年5月 記)
写真提供 粟谷明生
写真撮影 新宮夕海
写真『高砂』作物出 シテ長島 茂 撮影 前島写真店
『鉄輪』を勤めて 丑の刻詣にかける女の復讐心投稿日:2025-05-13

『鉄輪』を勤めて
丑の刻詣にかける女の復讐心
鉄輪(五徳)を頭に載せ、しかもその上に蝋燭まで立て、怖い形相の面をかけて現れる後シテ、この異様な姿は鮮烈で、『鉄輪』をご覧になった方はいつまでも心に残るのではないでしょうか。その『鉄輪』を広島蝋燭薪能(令和7年4月28日 於:広島護国神社特設能舞台)で勤めました。
この日は生憎午前中が雨で、夕方からの演能が危ぶまれましたが、午後から晴れてきて、何とか「蝋燭薪能」を催すことができました。たくさんの蝋燭が灯されたなか、幻想的な能をお楽しみいただけたのではないでしょうか。しかし、舞台はそれまでの雨によって良いコンデションとはいえず、演者側には難儀な面がありました。屋外の演能ではいつも天候が気にかかります。
まずは『鉄輪』の物語を簡単にご紹介します。
貴船神社の神職(または社人)(アイ)が丑の刻詣をする都の女に神託を告げようと触れる、狂言口開けで始まります。
女(シテ)が遠路はるばる丑の刻詣に貴船神社にやってくると、アイが「火を灯した鉄輪を載せ、顔に丹(赤)を塗り、赤い衣を着て、怒る心を持てば願いが叶う」と神託を告げます。女は最初は人違いだと言いますが、みるみるうちに気色が変わり、姿を消します。(中入)
男(夫・ワキツレ)が登場し毎夜、悪夢を見ると言って安倍晴明(ワキ)に占ってもらうと、女の恨みで今夜にも命を落とすと言われます。男はすぐに晴明に祈祷を頼むと晴明は後妻と男の人形を棚に飾り祈祷を始めます。そこへアイが言った通りの形相で鬼になった女が現れ、捨てられた女の哀しみ、恨みを訴えます。そして後妻の形代の髪をからめ打ち据えます。さらに男の形代に迫ると、三十番神が鬼女を攻め、ついに鬼女は衰え、「時節を待つべし」と言って消え去ります。
丑の刻詣は丑の刻、すなわち午前2時という深夜に、人目を忍んで参拝し、恨む相手を呪い殺す祈願をすることです。詞章には「通い馴れたる道の末・・・」から道行の謡が始まり、糺の森や市原野辺を通り「程も無く、貴船の宮に着きにけり」と、いとも簡単に着いたように書かれていますが、都の女が貴船神社までの道のりを、いくら通い馴れた道と言っても、深夜、暗闇の中、一人で行くのはとうてい無理です。それをするというのは相当の思い込みがあるのだろうか、恐ろしいと、前回の演能レポートに書きました。
都から車で4、50分ほどの距離を、女は何時間かけて都へ行ったのでしょうか。3時間から4時間かけて? それも7日間も? と考えると、女の復讐心の恐ろしさに身が引き締まる思いがしたものです。
今回、4月18日に厳島神社の神能を終えてから、京都に入り、貴船神社所縁の地を巡ってきました。京都市内から鴨川沿いに糺の森を抜けて、深泥池(詞章では御菩薩池・みぞろいけ)を横に見ながら、深草少将に掛けて草深い市原野辺、小野小町終焉の地・小野寺に行き、鞍馬川にかかる橋を渡って貴船神社へと、ほぼ詞章の通りに巡ってみました。
今回、舞台で道行を謡う時も、実際にたどった道の景色が体の中に浮かんできました。
それで分かったことがありますので、ここに補足しておきます。
実は前回の演能レポートまでは、都の女は毎夜、市内から貴船まで歩いて通っていた、と思っていましたが、これはやはりどう考えても現実的ではありません。
貴船神社には本宮、結社(中宮)、奥宮と三社あります。多分、『鉄輪』の女は本宮下にベースキャンプを構えて、そこから深夜2時頃に奥宮まで、何日か通い、丑の刻詣をしたと考えるのが良いかと思います。高い山を登る登山家がベースキャンプを張るように、です。
本宮は華やかなところで、赤い鳥居がたくさん並び、参拝する人で賑わっていますが、奥宮まで行く人は多くはないようです。私も以前に訪れたときは本宮どまりでしたが、今回は奥宮まで行き謡曲史跡保存会の駒札を写真におさめました。やはり演能後より前にゆかりの地に行く良さを感じています。
それにしても、女をそこまで追い込む強い復讐心の要因は何なのでしょうか。
浮気した夫への恨み、夫を奪った女への恨み、夫に戻ってきてほしいと思う気持ちもあったが、あんな女に騙された夫はやはり許せないと思うのでしょうか。「或る時は恋しく」「または怨めしく」と揺れ動く女心をシテと地謡で謡います。
女は鬼女となって、捨てられた女の恨みを晴らすべく、「いでいで命を取らん」と新妻の形代に襲い掛かり、散々に打ち殺してしまいます。夫の方には清明の祈祷が強く効いてなかなか近づけません。もしかすると女の心の中に「夫は悪くない、悪いのは新妻」と夫を庇う気持ちが少しはあったのかもしれません。このような女の揺れ動く心、裏切った夫を恨む以上にもう一人の女を強く憎んでしまうというのは面白いところです。現代の夫婦関係、男女関係にも通じるように思われます。
さて、この女の気持ちを表現する面について、伝書には、前シテが泥眼、後シテが生成(なまなり)と書かれています。
前シテの泥眼は『葵上』の六条御息所(シテ)にも使われ、目の淵に金が入っている面で、普通の女とはどこか違う、強い気持ちが表情に出ています。『鉄輪』の女は登場するときは笠をかぶっているので分かりにくいですが、神託を聞いて、自分であると、慎み深い女から気色変じ、「怨みの鬼となって人に思ひ知らせん」と笠を捨てる瞬間に泥眼の面が良く効いて見え、顔色の変わったのが分かります。後の鬼女を予感させるのに、ふさわしい面です。
後シテは、今は「生成」と「橋姫」のどちらかを選択しています。今回は二つの「橋姫」を用意しましたが、諸事情を考え、粟谷家蔵の面を使用しました。
「橋姫」は面の上半分が白色、下半分が赤みを帯び、鼻筋などに赤が塗られ、どっしり存在感もあって、怒り爆発の怖いお顔です。「生成」も全体に赤みがありますが、少し笑っているようで、頭に小さな角が2本生えていて、とても不気味です。
父・菊生が、女房の怒りも「橋姫」のうちは怖いが、なだめればどうにか許してくれるだろう、しかし「生成」になったらもうオシマイだ、手遅れになるから気を付けなければ、と話していたことを思い出します。とにかく、怒りの表情に笑みが見えたら怖い、もうアウトらしいです。恐ろしい心に残る忘れられない言葉です。
それでか、父の『鉄輪』では「生成」は一度ほど、ほとんど「橋姫」にしていたようです。私も一度「生成」を使ってみようかなと思わないでもありませんが、やはり使いこなせないだろうと、遠慮してしまいます。
「生成」に「り」をつけて「生成り」と書くと「きなり」と読み、脱色や染色をしていない糸や布のことを言うようですが、これは「なまなり」と読ませる面の「生成」とは別物です。面のほうは未完成で、まだ十分に成りきっていない様を表します。すなわち角が生えた本当の鬼「般若」になる以前のお顔ということです。『道成寺』や『葵上』で使われる、立派な角が生えた「般若」と比べると、「生成」の角は小さいですが、何か煮え切らない、それでいて不気味な表情がとても怖ろしいです。
『鉄輪』という能は、面や出で立ちも特異で、作り物もあって、分かりやすい設定です。
ご覧になって、女性なら胸のすく思いがするでしょうが、演じている私は、この女は自分の恨みばかり述べて、男を悪者にしているが、本当のところはどうなのだろうと、男の言い分が全く書かれていないので、気になります。
なぜ女は夫に捨てられたのか。
口うるさかったから? 金遣いが荒かった? 暮らしぶりがだらしなかった? 老いた見苦しい体型に嫌気がさした? もしかして、子が産めないことで離縁ということもあったかもしれません。今はそのような理由は許されないでしょうが、昔はそれで里に帰されるなどということがよくあったようです。
こんなふうに考えるのは男の側の発想と分かっていますが、捨てられた女を演じる男の役者として、女と男の矛盾する心を感じながら演じるのが、また面白いのです。
鬼女となった女は、祈祷によって退散しますが、「今回はあきらめるが、また来るから!」と言い残して消えていきます。執念深く、怖ろしさを残したままの終曲です。
この能の題材となった平家物語「剣の巻」では、その後、女は男を殺し、しかも男の家族、新妻の家族も殺してしまう凄惨な結末です。『雨月物語』の「吉備津の窯」も同じようなお話ですが、最後、男は殺されています。伝説や小説は徹底的に悲劇を描くことが多いですが、能はそこまでの結末は描きません。また来るかもしれないと余韻を残し、あとはご覧になる方の想像に委ねます。
私も、女が男を殺してその後どうなるのだろう、恨みを晴らすことができて魂は鎮まるのだろうか、元のやさしい女性に戻れるのだろうか。いやいや、残酷な殺人者になってはお終いだろう、などと想像はしますが、能がそこまで描かないところを好ましく思います。
貴船神社の鉄輪伝説の最後に「丑ノ刻詣りは祭神が国土豊潤のため丑年丑月丑刻に降臨されたと伝える古事によるもので、人々のあらゆる心願成就に霊験あらたかなことを示すもので、単にのろいにのみとどめるべきものではない」と書いてありました。貴船神社も丑の刻詣は悪い印象ばかりではない、のろいだけでは物事は解決しないと言いたいのでしょうか。
若い時には考えもしなかったいろいろなことを思う『鉄輪』になりました。
しかし、ご覧になる方は深く考えず、男女の仲のお話、こんなお話もあるのね、女性への対応はよくよく考えなさいよ、という昔の人の忠告なのかな、などと所詮、「これは他人様のお話」とクールに受け止めて楽しんでいただくのが一番、かと思います。
私の『鉄輪』の初演は昭和63年(33歳)妙花の会、再演は平成15年(48歳)粟谷能の会で、今回が3回目です。再演の時の演能レポートで詳しく書いていますので、ご興味のある方はサイトの「演能レポート」でご覧ください。 (2025年5月 記)
写真提供 広島護国神社 シテ粟谷明生
アイ 野村裕基 小鼓 横山幸彦 大鼓 亀井広忠 太鼓 吉谷 潔
能面「橋姫」 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
能面「生成」 撮影 粟谷明生
『石橋』を勤めて 弟子の子獅子の披キに立ち会う投稿日:2025-03-18

『石橋』を勤めて
弟子の子獅子の披キに立ち会う
第107回・粟谷能の会(2025年3月2日 於:国立能楽堂)では、『景清』に続き、『石橋』連獅子を、私の弟子の佐藤陽に子獅子を披かせることとして企画しました。
『石橋』は前場を省略して、ワキの寂昭法師(俗名・大江定基)の名乗りの後、すぐに獅子が登場して舞い遊ぶ、後場のみの半能形式が主流です。今回は前場もある本能で催し、特別にご許可をいただき、前シテを私が勤め、後シテの親獅子を長島茂氏にお願いして、前後のシテを別人で勤めました。
『石橋』連獅子について簡単にご紹介します。
寂昭法師(ワキ)が清涼山の石橋を渡ろうとすると、童子(前シテ)が現れ、石橋をたやすく渡ろうと思うな、神仏の加護がなければ渡れないと制止します。そして、橋の向こうは文殊菩薩が住む浄土、妙なる音楽と美しい花が舞い降りてきて、やがて奇瑞が現れるから待つようにと告げると姿を消します。(中入)
続いて、仙人(アイ)が現れ、獅子の舞楽が始まる予告をすると、文殊菩薩の使者である獅子が親子(後シテ・ツレ)で現れ、石橋の上を飛び跳ね、咲き乱れる牡丹の花に戯れ、勇壮な舞を見せ、泰平の御代を愛でて獅子の座に帰ります。
粟谷能の会での本能は、平成13年に従兄の能夫が前シテを尉にて後場の親獅子を、子獅子の私とで勤めていますので、今回が2回目となります。
前場は動きのない居グセの謡が重い習いで、石橋のすさまじい景色を謡い上げます。
石橋の幅は一尺(30センチ)もなく、長さは三丈(9メートル)、谷をのぞめば千丈(3キロメートル)もあり、苔むしてつるつる滑る危険極まりない橋であることを勢いある強い謡い声で紹介します。そして徐々に奇瑞への期待感が高まり、獅子登場のお膳立てができるのです。
前シテは、喜多流では通常、老人の樵ですが、替えとして童子にする演出もあります。今回は初番が『景清』で老人のため、重なるのを避けて、童子で勤めることとしました。また童子の扮装を水衣に側次(そばつぎ・ベストのようなもの)を羽織り、より唐(中国)らしい演出にしました。
そして『石橋』の見どころは、やはり後場の勇壮で豪華、躍動美あふれる獅子舞です。
単に暴れる荒さを消し、端正な姿勢と俊敏な動きで、獅子を演じるのが演者の心得です。
獅子舞は両手を広げ、面(おもて)を左右に振り、上体を反らしすぐに屈んでお辞儀のような恰好をします。この獅子舞独特の動きは、獅子が顔を左右に激しく振るので、「嫌、いや!」と、何かを拒絶しているように見えますが、これは牡丹の香りを嗅いで楽しんでいる様子を表現しています。親獅子はゆったりどっしりと、子獅子は機敏に軽やかに舞い遊ぶイメージで勤めます。
今回、子獅子を披いた佐藤陽は能楽師の家の子ではなく、東北大学学友会能楽部喜多会にて能を学び、能楽師の道を志し、長年私の元で修業し職分となりました。『道成寺』を披いてから時間も経ったことから、『石橋』子獅子を披くことを勧め今回の番組となりました。
『石橋』は特別重い習いとして大事に扱われ、『道成寺』を披いた後でしか勤められない風潮がありますが、これには違和感があります。
喜多流が大事に扱うのは、赤頭を巻き毛にてして一人で勤める「一人獅子」が大事であって、ツレとしての子獅子は別物と考えるべきです。若く体のキレがあるうちに、早めに獅子を経験させることがご覧になる方への正しい在り方だと思います。昔に比べて披キが遅くなっている昨今、江戸期や明治大正の伝承をそのまま鵜呑み状態にしておくのは、次世代にはハードルが高すぎるように思います。
年齢45歳の佐藤陽に子獅子の初演は正直肉体的にもかなり厳しいものがありました。
獅子舞は狭い視界、重い頭と動きにくい装束、そして何よりも正面先に置かれた一畳台に飛び上がり、旋回するのは見た目より運動量が多く体力が必要です。最初は歯が立たない状況でしたが、当日はどうにか粗相無く勤め、安堵しています。
今後はもう少し早く披けるような喜多流の思考と体制の改善が必要だと、以前から考えておりましたが、いよいよ本腰を入れて取り組むべきと思いました。
楽屋裏話を一つ。舞台に最初、牡丹を飾った華やかな2台の一畳台が置かれますが、伝書には2台の間、一尺ほど離して置く、と記載されています。私自身、披キ(父が親獅子)の時も、また友枝昭世師や粟谷能夫との共演でも、一畳台を離したことはありませんでした。高林白牛口二氏に伺うと、間を開け危険が増すことで、より演者への高いハードルを課し緊張感を高めるため、と教えてくださいました。今回は、未熟な弟子の披キでもあり、離すことはしませんでした。そもそも石橋自体左右に離れていることはないわけで、離す設定をご覧になる方はどう思われるのでしょうか。この伝書の記載も観る側よりも演者中心の思考ではないかと、気持ち悪さを覚えます。


今回の粟谷能の会は満席となり大変喜んでおります。
佐藤陽の披キのため、東北大のOB・OGの皆様が多く来て下さり、佐藤陽への応援に感謝しています。また、『景清』『石橋』連獅子の番組編成が良かったことも集客につながったように思います。
来年は秘曲『伯母捨』を私、粟谷明生が披きます。
老女が月の美しさを讃え、月の光の下で昔を偲んで、静かに舞います。
今回の番組とは異なり、とてもゆっくりと時間が流れますが、これが正に能の神髄と言われる最高位です。
心躍る能を、これからも企画し、来年の「第108回粟谷能の会」へのご来場をお待ち申し上げております。
写真撮影 新宮夕海
能面獅子二点 撮影 粟谷明生
笛 一噌隆之 小鼓 観世新九郎 大鼓 亀井洋佑 太鼓 金春惣右衛門
(2025年3月 記)
『景清』を勤めて 豪の者・景清の揺れ動く心投稿日:2025-03-18

『景清』を勤めて
豪の者・景清の揺れ動く心
今年の第107回粟谷能の会(令和7年3月2日 於:国立能楽堂)は、初番に『景清』、狂言「秀句傘」を挟み、『石橋』で締めくくる番組編成としました。私は『景清』でシテを勤め、『石橋』では前場もある本能を企画し、弟子の佐藤陽に子獅子(シテツレ)を披かせ、親獅子(後シテ)を長島茂氏にお願いして、私は前シテを勤めました。粟谷能の会や『石橋』については改めて記すこととして、まずは『景清』についてレポートします。
私の『景清』の初演は平成24年の粟谷能の会で56歳の時、それから13年の時が流れて、今回、69歳での再演となりました。亡父・菊生の十八番だった『景清』を思い出し、父の芸を真似ながら、私自身の景清を演じられたら・・・と思い勤めました。

まずは『景清』の物語を簡単にご紹介します。
平家の武将・悪七兵衛景清(シテ)は宮崎に流され盲目の乞食となり、日向の勾当(こうとう)と名乗り暮らしていました。
そこへ娘・人丸(シテツレ)が従者(ワキツレ)を従え訪ねてきます。景清は自分の娘であると知り驚きますが、乞食の身を恥じて他人のふりをします。
しかし、里人(ワキ)のとりなしで、景清は娘と対面し、屋島の合戦での三保谷四郎との錣引き(しころびき)の武勇伝を語り聞かせますが、やがて時も過ぎ、涙ながらに別れを告げるのでした。
景清は平家の武将ですが、さほどの武勲があるわけではありません。平家物語ではわずかに「錣引き」の話が数行あるくらいで、これも錣を引きちぎった力の強さはあっても、所詮相手に逃げられ、屋島の負け戦の一コマなのです。義経や頼朝の暗殺を企て源氏滅亡を志すも失敗に終わる、人生の負け組大将のような人物を能は描いているように思えます。
景清の姓は伊藤とも藤原とも、また平景清とも言われていますが、やはり通り名の「悪七兵衛景清」が一番だと思います。この「悪」は「悪い」ではなく「強い」の意味ですが、景清の様々な伝説の中の、「源氏の栄える世を見ぬために両眼を自らえぐった」という話が、一番景清らしい、と私は思い景清を演じています。
勾当というのは、平家語りをする盲目の琵琶法師の、検校、別当につぐ位の者のことですが、
能のシテ景清が僧ではないのに角帽子(出家者の象徴)を付けているのは、もしかすると、盲僧が景清を語る伝承からの逆輸入かもしれないと思うようになりました。ここは定かではありませんし、相模国の娘人丸の事もいろいろな伝承があります。それら様々の伝承から能『景清』の景清像が造形されているように思われます。
景清を演じるにあたり、どの辺に焦点を定めるか?
「麒麟も老いぬれば駑馬にも劣るが如くなり」と謡われるほどの惨めな姿の景清です。
敗将、盲目、老体、乞食、と多くの負を背負っています。自ら両眼を潰すほどの強い意志と、肉体は衰えても枯れ果てぬ気骨が横溢していますが、そこには将来への明るい光はなく、絶望的な状況があるだけです。豪の者でありながら、景清の揺れる心、その底に見える暗黒の悲劇を皆様に想像していただくために、どのように勤めたら良いか・・・、と考えました。
景清の心中を最初に表現するのが、「松門の謡」といわれる謡です。
引き回しをかけられたまま、藁屋の作り物の中で次のように謡います。
「松門独り閉じて年月を送り、自ら清光を見ざれば時の移るをもわきまえず、暗々たる庵室に徒に眠り。衣寒暖に与えざれば。膚(はだえ)は髐骨(ぎょうこつ)と衰へたり」
この「松門の謡」について、14世喜多六平太芸談に「丁度、鎧の節糸が古くなって、ぶつぶつ切れたように謡え、と伝えられています。妙な言い方ですが、良く心持ちを言い表しています。(中略)松門をひとつ上手く謡って聞かせてやろうなんて気持ちで朗々とやられたんでは、もうお終いです。どこまでも低音で、呂の音を主に腹の中で謡う・・・」
と、書かれています。私ここまでは素直に納得出来るのですが、次の最後の言葉が、どうも気になっています。
「聞こえても、聞こえなくとも、そんな事は何方でもいいのです。」
この言葉、昔はそれで良かったのかもしれませんが、しかし今は、それでは通用しないと思います。「謡が聞こえなかった・・・」と、お客様に言われたら、それこそ本当のお終いです。
国立能楽堂の隅々のお客様まで、老体景清の声が、心情が、伝わるために能役者は言葉に潜む言霊を、謡の調子、高低、強弱、緩急、陰陽、様々な技を絡めて演じなくてはいけないと思います。謡本に記された節だけ見ても到底謡えるものではありません。口伝によってさまざまな謡い方が伝えられていますが、私の「松門」は『景清』を得意とした父の謡い方を真似ています。初演の時も父はすでに亡く、直接教えを乞うことはできませんでしたが、父の松門は身体の奥深いところまで、染みこんでいます。今回の再演では初演の時よりは余裕が出てきて、基本は真似ですが、自分の思いも少し載せられたかな、と思っています。




『景清』は台詞劇、舞が全くない、能として珍しい曲です。それでも、床几にかけて語る三保谷四郎との「錣引き」の闘いの場面では、熱が入り、不自由な体ながら、思わず立ち上がり、様々な所作が入ります。しかしその動きは、老体と盲目のため、健常者の動きとは異なります。例えば、左方を刀で斬る時は、右手を左方向に動かしますが顔は逆に右へ向けます。反対に、右方向を斬る時は、手は右、顔は左に向けます。
この動きについて、「盲目は目でなく耳で見る」が、父・菊生よりの教えです。
また、前に進みたいが、足が思うように動かない忸怩たる思いを、特別な「抜く足」にて表現します。演者はこれらの不自由な動きを体に染み込ませ、スムーズに動けるように稽古し、舞台で不自由な動きが違和感なく自然に見えるように演じなければ失格です。
最近私は、お能をだれず、飽きずに見ていただきたいと願い、とりわけ、粟谷能の会では、演能時間があまり長くだれないように心がけています。作品の良さを壊さず、短く出来るところは短縮して演出しています。
今回、謡の短縮はしませんでしたが、ツレの登場の出囃子を少し短くし、正面前で謡う次第(出囃子)を橋掛りで謡うように変えました。これは、単に時間短縮になるだけでなく、道行らしい効果もあったのではないでしょうか。
それに『景清』という能は、分かりやすい場面展開、また景清の揺れ動く心を細やかな型で表現するなど、舞がない割にはだれない演出になっていて、それにも助けられ、飽きずにご覧いただけたのではないかと思っています。
「え! 終わったの?」
と、お客様に感じていただけたら、私の思う壺です。
能は日常生活に比べると、かなりゆっくりとした動きで舞台は進行します。もちろん、日常生活とかけ離れた時空をお楽しみいただけるのは、能ならではの雰囲気で良いことです。ただし、演者側はそのスローペースに胡座をかかず、舞台にだれる空気感が出ないように努めるべきと思っています。
さて、錣引きの語りが終わると、いよいよ最後の場面です。ワキにこの物語が終わったら娘を故郷に帰してくれるようにと約束しての語りでした。もう自分の命はそう長くないと悟っている景清は「亡き跡を弔ひ給へ」と頼み、「さらばよ」と娘の背中を押して帰します。これも切ない親心なのです。「さらばよ 留まる」「行くぞ」との一声が親子の形見となるとして終曲します。
現代のTVドラマなら、娘との再会で「めでたし、良かったね」と終わるのでしょうが、室町時代に作られた能は娘と再会しても、すぐに別離となる哀れな悲劇を描いていきます。
能は勝ち組より負け組に焦点を当てて戯曲することが多く、『景清』は一番の負け男の鎮魂能と言えるかもしれません。
この最後の場面で、見所からすすり泣く声が聞こえてきました。あるご婦人は「主人が泣いて泣いて恥ずかしかった」と仰っしゃいます。以前、父・菊生が「結婚式では、男親は娘とバージンロードを歩き、最後に娘を奪っていく憎っくき男に手渡さなければならい、ここは残酷なシーンだよ。だけどそのとき、父親は相手の男をにらみつける度胸はないのね、必ず視線を外してる。そこで『景清』の別れの場面では、パージンロードの父親のように、視線を落とす型をしている、何でもお能に応用するんだよ」と言っていたことを思い出します。
娘との別れ、どうも『景清』は男親の涙腺を緩めるようです。また、ある女性からは「人丸になった気分で見ました。切なくなりました・・・」と言われました。能『景清』は、男性は景清に、女性は人丸に心を寄せてご覧になるようです。このように、優れた能は老若男女全てに適応しているのです。
ここで装束のお話をします。
能『景清』の装束(着物)は着流し姿と大口袴姿の2通りがあります。前者は乞食として、後者は武将としての側面を強調しています。喜多流は武将として白色大口袴を着用し、私もそのようにしました。面は景清の専用面をかけますが、これにも顎髭が有る無しで2通りあり、髭がある方を使います。専用面があるのは『景清』のほか、『頼政』、『弱法師』、『鬼界島』、『蝉丸』などがあり、いずれも個性的な人物像を描き出しています。『景清』の専用面は負け組でありながら、まだどこかに負けん気、強さを表し、それでいて盲目の哀しさも秘めているような面です。頑固な老いぼれ武将に似合う装束と専用面(粟谷家の能面「景清」)は、もし次回勤めるときでも、多分変わらないでしょう。私には不動のお決まりです。
今回、共演者に恵まれたと喜んでいます。ツレ・人丸の狩野祐一さん、ワキの宝生欣哉氏、地頭の長島茂氏、囃子方(笛・松田弘之 小鼓・鵜澤洋太郎 大鼓・亀井広忠)、地謡陣、舞台を盛り上げてくださった皆様、そしてご覧になってくださった方々、皆様に感謝申し上げます。
今回の『景清』は再演であったため、少し余裕が出てきて、謡い方や動き、表現法に再発見がありました。加齢すると、瞬発力や持久力などが落ち、身体のキレも悪くなります。確かに衰える面もありますが、69歳だからこそできることもある、と感じています。身体は衰えても、その代わり謡(口)は若い時より、重みを増して良い謡に成長する、と言われていますが、そのことがじんわり分かるようになりました。50代の初演、60代の再演を終え、次は2、3年後に70代の『景清』もご覧いただきたいと、新たな目標が出来ました。
写真撮影 新宮夕海
(2025年3月 記)
『弱法師』を勤めて投稿日:2024-10-15

『弱法師』を勤めて
効果満点の小書「舞入」
能『弱法師』は盲目の青年・俊徳丸(シテ)が「目は見えなくとも心の目で何でも見えるぞ!」と悟りながらも、世の辛さを知り挫折する物語です。父・菊生が得意とした曲でいろいろ教えて貰った曲、私も大好きなこの曲を、「初秋ひたち能と狂言」(令和6年9月29日、日立シビックセンターにて)で勤めました。
『弱法師』を勤めるのは今回が4回目です。初演は平成4年の粟谷能の会研究公演、続いて平成15年の秋田まほろば能、平成26年の厳島神社・桃花祭の神能で勤めています。初演以外、今回も含め3回の公演ではいずれも小書「舞入(まいいり)」の特別演出で行いました。
まずは簡単に『弱法師』のあらすじを記しておきます。
高安左衛門尉通俊(ワキ・宝生常三)はさる人の讒言(悪口・誹謗中傷)を信じ、我が子の俊徳丸を追い出しますが、不憫に思い天王寺にて7日間の施行(善行を積むために人に物を施すこと)を行います。そこに、盲目となり弱法師(足弱の乞食・喜捨を受ける芸能者)と呼ばれるようになった俊徳丸が現れます。通俊が施行を勧めると俊徳丸は素直に受け入れ、梅の花を袖に受けるなどして優雅なふるまい見せます。それを見た通俊は弱法師が我が子と気づきますが、人の目を気にし、その場では名乗らず、日想観(じっそうがん)を拝むよう勧めます。盲目ながら心の目で見えると舞い狂う俊徳丸。やがて夜になると、通俊は父と名乗り、俊徳丸を高安の里に連れて帰ります。

小書「舞入」は通常右手で扱う盲目の杖を左手に持ち替え、右手に中啓(ちゅうけい=扇)を持ち、杖を突きながら、常の「イロエ」(軽く舞台を一巡する)を中之舞に替えて舞う演出です。「盲目の杖」の扱い自体難しいうえに、「舞入」では利き腕ではない左手で杖を扱うので、さらに難度が上がります。これを嫌い、小書を避ける人があるくらいで、この小書での演能はそう多くありません。私はこの小書で3回目、何度も稽古して慣れて来たためか、杖の扱いはさほど苦にならなくなりました。
「視界が狭い中でたいへんですね」などと言われることがありますが、専用面「弱法師」は目が横に切れているので、不思議と視界は広く、よく見えます。演者はよく見える面の内側で、目を半眼に閉じて盲目の気持ちで舞っているのです。

喜多流の『弱法師』、というより、これを得意とした父や第十四世・喜多六平太先生の主張は、弱法師は天王寺まで毎日通い慣れているから、その道中のことは、たとえば、どこに石があって危ないとか、樹木が飛び出しているとか、全て分かっている、盲目といっても、不自由そうに恐る恐るよろよろと歩くのではなく、むしろタッタとリズム良く、全体にサラッとした気分で勤めるのが吉、というもので、私もそのように思います。謡を落ち着き過ぎて重苦しく謡ったり、囃すのは、妙にハンディキャップを誇張するようで、どうでしょうか?私はあまり感心しません。
『弱法師』は若いうちにはできない曲ですが、かといって、背中が丸くなった年配者でも似合いません。昔、喜多流の愛好家の女性が「俊徳丸は青年です。背中が丸まった姿で出て来てはいけません」と、話されたことが強烈に頭に残っています。ですから、盲目といっても若者らしい溌溂とした動きも必要で、盲目の不自由さとの兼ね合いが難しいところなのです。

この曲のクライマックスは何といっても日想観を拝するところです。日想観とは、時正の日(昼と夜の長さが同じ日)に西に向かって手を合わせ、落日の有様を見て、西方浄土を願うことです。弱法師・俊徳丸も西に向かって手を合わせ「南無阿弥陀仏」と唱えます。やがて「イロエ」に変えて中之舞を舞い、舞のあとはすぐに「住吉の松の木の間より眺むれば・・・」と上羽の謡となり、続いて「狂い」の舞どころとなります。淡路、絵島、須磨、明石、紀の海まで、盲目なりとも、心の目でよく見える、「満目青山は心に在り」「おお、見るぞとよ、見るぞとよ」と気持ち昂り狂うのです。さらには難波の海の名勝、南は住吉の松原、東は緑の美しい草香山、北は長柄の橋と、有頂天になって謡い舞います。今でいえば路上のラップ・ライブの趣でしょうか。この曲のもっとも心躍るところです。
しかし、盲目の悲しさ、「目では見えないが、心の目で見えるのだ!」と達観し狂う弱法師・俊徳丸ですが、やがて境内の貴賤の人に突き飛ばされ、よたよたと倒れ転んでしまいます。「やはり弱い法師だ!」と揶揄われ笑われ恥ずかしめを受けると「もう浮かれたりはしない!」と心を痛め挫折します。
「舞入」という小書は、日想観を拝し心が昂っていくなかで舞い、狂いの頂点に繋げる、ご満悦の演出であり、後の挫折感と対比させる効果満点の演出であると、3回目にして、より強く感じることができました。今回の一番の収穫です。

以前の演能レポートにも書きましたが、作者・観世十郎元雅の能には「影」があり、それが魅力になっていると思います。『弱法師』しかり、『隅田川』、『歌占』しかりです。
『弱法師』は最後、親子再会で良かった良かったということになっていますが、そこに「影」が見えます。今回の演能にあたり、通俊の台詞から想像される状況が気になりました。
まず、「さる人の讒言」により、我が子を追い出しますが、さる人とは誰なのか・・・、何となく女性の匂いがします。謡曲大観の著者・佐成謙太郎氏は義母と解説されていますが、私も同感です。通俊の後妻が実の子可愛さのあまり、前妻の子・俊徳丸を邪魔にしたといったことが想像されます。人形浄瑠璃や三島由紀夫の近代能楽集など、『弱法師』の筋を採り入れたものがありますが、ドロドロした家族模様が展開されているようです。能『弱法師』には細かい事情は書かれていませんが、そういう物語を想像させる何かがあるのでしょう。
次に、我が子と分かっても直ぐに名乗らない通俊に違和感を覚えます。自分が追い出したことで盲目にしてしまったという慙愧の念にかられないのでしょうか。人の目が気になるので、夜になってから名乗ろうとする通俊は、プライドが高く、見栄を気にする男、ごく普通の真っ当な父親とは思えません。
そして最後、とどめの一撃は、夜が明けぬ前にと、供人(アイ)に合図して、俊徳丸を連れて帰させることです。自ら手に手を取って連れ帰るのではなく、自分は後から行くからと、幕から離れた常座でユウケンし、脇正面を向いて留拍子を踏んで終曲します。
この終わり方、これから俊徳丸はどうなるのだろうか、家に連れ帰ってもらっても、複雑な家族関係の中で幸せになるのだろうか、通俊は味方になってくれるのだろうかと、不安になります。
お能はどんなに悲しいお話でも祝言の心で終わるのがいいとはよく言われます。元雅はもっと具体的に物語を展開したかったかもしれませんが、ここは能の様式で露骨には書けなかったのでしょう。日想観の高揚感を描き、親子再会をめでたしとしながら、でも、深く読めば、子供を捨てる行為は許されない、悪しき行為だというメッセージ、強烈な香辛料をまぶしていると感じさせられます。こういう『弱法師』という能が私はたまらなく好きで、元雅のメッセージをちゃんと伝える演者でありたいと思うのです。
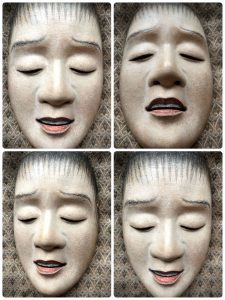
天王寺は大阪市天王寺区にある聖徳太子建立の寺。境内は相当広く、「踵をついで群集する」とあるように、昔も今も、多くの人で賑わうところです。貴賤を問わず、病や障害も問わず、懐深く人を受け容れるところです。昔は「悲田院」といって、貧しい人や孤児を救う病院のような施設もあったようです。日想観を拝む行事は今でも行われています。昔は、天王寺の境内から西を拝むと、能の詞章にあるように、難波の海に沈む太陽を拝むことができたといいます。最近では宅地開発され、日が沈む様子は拝むことができても、海は見られなくなっていますが、時正の日には多くの人が西に向かって手を合わせているようです。
このような懐深く慈悲深い場を能の舞台とし、現実に起こりそうなことを、真っすぐに描き切る現在能『弱法師』、元雅の能は世阿弥(元雅の父)の夢幻能とは違う味わいがあります。
父・菊生は晩年、身体が弱くなってきた時に、『景清』しかできないと言って、『景清』ばかり演っていました。銕仙会の荻原達子様に「父は『景清』しかできません」と、申し上げたところ、「いいの、いいのよ。『景清』が十八番という役者がいても。どこへ行ってもそれを演って、名優として成り立つ。『景清』しかできないではなく、『景清』が得意というのはとても良いことですよ。アッ君、覚えておいてね」と、言われたことが印象深く、よく覚えています。私も今回『弱法師』を勤め、来年は7月に高知で、9月に宇都宮でと、『弱法師』の演能が続きます。父の『景清』ではないですが、明生の『弱法師』、それも「舞入」の『弱法師』を広く皆様にご覧いただけるようになりたい、今そんな思いでいます。
なお、今回の『弱法師』は時間の制約があったため、一声の後のサシコエと天王寺縁起を語る序、サシ、クセを省き、短縮版にしたことを記しておきます。見所に外国からの留学生もちらほら、初心者が多い公演では、作品を壊さずに少しコンパクトにしてご覧いただくこと
も必要かと思っています。
『弱法師』舞台写真提供 日立シビックセンター
「弱法師」能面石塚シゲミ打 撮影 粟谷明生
(2024年10月 記)
『頼政』を続けて勤めて投稿日:2024-05-28

『頼政』を続けて勤めて
今年(令和6年)の春は、能『頼政』を「広島蝋燭薪能」(4月26日)と「喜多流自主公演」(5月4日)と続けて2回勤めることとなりました。
私の『頼政』の初演は「第61回粟谷能の会」(平成9年)で、続いて「能楽座静岡県舞台芸術公園楕円堂公演」(平成12年)と「粟谷能の会・福岡公演」(平成15年)の2回はいずれも父の代演で、福岡公演は後シテだけを勤めています。今回21年ぶりに、しかも2回連続で勤め、いくつか感じることがありました。
今回の連続2回公演は、屋外と屋内の演能の違いを実感しました。「広島蝋燭薪能」は屋外で生憎の空模様、私の『頼政』のときは雨に降られませんでしたが、途中小雨により10分ほどの中断がありました。屋外の能はご覧になる方には開放感がありますが、演者には舞台の寸法や滑り、また音響や視界など通常とは異なる不便さが正直あります。特に天候の心配をしながら自分自身のモチベーションが下がらないように気をつけなければいけません。
一方、自主公演は屋内の観世能楽堂で催され、屋外のような開放感はありませんが、お舞台の滑りも音響もよく、演じやすさを実感しました。そもそも能は屋外で行われていたものです。屋根のある能舞台を、能楽堂という建物の中に入れるのは不自然ではありますが、最善の対策がなされている能楽堂の能舞台が、能楽師にとっては一番勤め易い、と思うのは私だけではないでしょう。
いつものように、簡単にあらすじをご紹介します。
京都から奈良へと旅する旅僧(ワキ)が宇治の里にやってきます。地元の老人(前シテ)に会い、宇治の名所を尋ねると、老人は答えながら、やがて平等院へ案内します。平等院には源頼政が自害した扇の芝があり、自分がその頼政の霊だと明かして消え失せます。(中入)
夜半、法師の姿に甲冑を帯びた頼政の霊(後シテ)が現れ、平等院に布陣して橋板を外して平家方を待ち受けていたが、馬を巧みに扱い川を渡ってくる田原又太郎忠綱の軍に攻められたと、その様子を語ります。そして、頼みにしていた頼政の子、仲綱と兼綱兄弟が討たれると敗戦を覚悟し、扇の芝の上で辞世の歌を詠んで自害したと語り、僧に回向を頼み消え失せます。
能『頼政』を勤めるときにいつも念頭に浮かぶのは、なぜ、頼政は76歳という老体にも関わらず、以仁王に平家追討の令旨を出させ、決起したかということです。過去の2回の演能レポートにくわしく書きましたので、それをご覧いただきたく、ここでは詳しく書きませんが、源頼政は源氏でありながら平家方につき生き延びてきた複雑な人生の持ち主なのです。なかなか官位が上がらなかった頼政を従三位に引き上げてくれたのは平清盛でしたが、清盛の後白河法皇を幽閉するなどの暴挙、平家の横暴なやり方に批判的になっていたところへ、息子の仲綱が愛馬のことで平宗盛に辱めを受けたことが、これまでの鬱屈した思いに火をつけてしまいました。しかし残念なことに、決起した頼政でしたが、すぐに清盛に知られるところとなり平等院にて自害します。その時に詠んだ辞世の歌、
「埋もれ木の花咲く事も無かりしに 身のなる果ては哀れなりけり」
には、頼政の万感の思いが込められています。
この辞世の歌が、この能のテーマではないでしょうか。


能では最後の最後、橋合戦の仕方話をした後に、芝の上に扇を敷き、刀を抜いて、この歌を謡いあげます。この場面、以前は老武者の人生の哀感を、少し静かに謡っていましたが、68歳の再演にあたり、命をかけ闘い破れた老いた男の心境は、力強い絶叫の方が似合うのではないかと、高音で張り上げ謡ってみました。老人に大声は似合わない、老人は大声が出ない、のかもしれませんが、能は芝居であり演劇です。老武者頼政の強い思いを大絶叫することで、ご覧になる方々に強く伝わればよいのではないでしょうか。今年には69歳になり、周りから古稀と言われるようになったからこその発見でした。
実際、歴史は頼政の決起により、頼朝が立ち上がり、怒涛の勢いで平家を倒し、世の中は平家の時代から源氏の時代へと変わっていきました。頼政がそのきっかけを作ったことは確かです。頼政は決して、埋もれ木の花咲く事も無かった、人生ではなかったのですが、本人は知る由もありません。
実際、頼政は従三位まで上がった武将であり、歌人としても優れた人であったのですから、最後の決起は複雑で執心の残るものだったのでしょう。後シテの出立にもそれがよく現れています。老体でありながら、頭巾をかぶった法体であり、肩脱ぎした軍体という異様な出立。しかも面は「頼政」専用面で目に金環が施され、この世の者とも思われない強い異様な表情です。すべてがシュール。こうして造形された能『頼政』を演ずるには「若さ」は「敵」である、と初演を思い出し、今だからこそ判るのです。
後場では、サシの「そもそも治承の夏の頃・・・」から始まる、床几に腰掛けての戦の仕方話が聞かせどころ、見せどころです。ここは落語の噺家のように一人で何役も演じます。シテは最初、三井寺を目指し宇治に落ち行く頼政自身ですが、敵軍の田原又太郎忠綱にも変身し、橋桁を外されたにもかかわらず、宇治川の急流を果敢に馬で渡って攻め上がる様子を見せ、また頼政に戻って味方の戦いぶりを描きます。床几に腰掛ける演出は老体でもあり、指揮官でもある姿を想像させますが、この床几に腰掛け闘いを一人で演じる場面は、演者にとって技芸の見せどころでもあります。
この仕方話の前に、地謡「蝸牛(かぎゅう)の角の争いも」(ちっぽけな争いも)、シテ「儚かりける心かな」といった謡が入ります。執心に迷う頼政に、所詮、それはかたつむりの角の争い、ちっぽけなものなのだ、人生は儚いと述懐させるところに、作者・世阿弥のウイットを感じさせられます。少し冷静に悟ったかのような頼政ですが、仕方話をしながら徐々に気持ちが高ぶり、「埋もれ木の・・・」の辞世の歌で心の叫びになる・・・、修羅道に苦しむ、他の修羅物とは異なる構成がこの能の特徴の一つでもあります。
最後に楽屋裏話を一つ。今回演じるにあたり一つ疑問に思ったことがありました。前場の名所教えで、恵心寺を紹介した後に、シテが「月こそ出づれ朝日山」と謡います。その後の地謡は「雪さし下す(くだす)島小舟」と続き、美しい景色、優れた名所と賞賛しますが、さて月が出る時刻は、なんどきなのだろうか?
「雪さし下す」つまり月の光で雪が下りたように見える、その時刻は何時なのでしょうか。
あれは夕刻の月ではないか・・・。
いや頼政が自害した5月26日は満月ではないので月光が雪に見える程のことはない・・・。
いろいろな意見が出ましたが、結局よく分からず最後は、高林白牛口二師が常に仰る
「理屈に合わなくとも良いのです。それが能なんです」が、オチとなり一同笑って終わりました。能には謎めいたところがいろいろあります。納得いかないことを調べ、時には腑に落ちることもあれば、今回のように答えが出ないこともありますが、あれこれと仲間内で話すことの大事さ、面白さ、を体験しました。


今回、広島での演能の前に平等院を訪ね、釣殿、頼政の墓、扇の芝などを見て回りました。観光客で混雑していましたが、扇の芝に目を止める人は無く寂しい限りです。それでも、ここで自害したのかと写真を撮り、宇治川の急流を目の前で見て、ここを馬で渡ったのかと、また改めて感心しました。平等院には既に何回か行っていますが、やはり演能直前に訪ねるのは大いに刺激にもなり、特に朝日山の位置が判ったことは、私には大きな思い出となりました。


20代~30歳までは、指導者に教えられた通りに勤めれば良いでしょう。しかし、そこで留まっていては成長が止まります。様々なものを貪欲に吸収し、教えられたパッケージ通りに勤めるだけではなく、もっと先に踏み越え、殻を破り、演劇としての能を追求することの大事さを痛感しています。そして何よりも能という難解な演劇を、ご覧になる方に少しでも分かり易く伝えることの大切さを噛みしめています。もう少しで69歳。今だから判るのかもしれない・・・、と、私も頼政のように心の内で叫んでいます。
(2024年5月 記)
写真提供 新宮夕海
『嵐山』を勤めて 〜桜の花から真の花〜投稿日:2024-05-01

『嵐山』を勤めて
桜の花から真の花
前日の嵐が嘘のような、快晴に恵まれた春のひととき、「国立能楽堂定例公演」(令和6年4月10日)で、『嵐山』を勤めました。
能『嵐山』は桜(造花)を左右に配した一畳台の作り物を舞台の正面先に置いて、桜満開、
春爛漫の京都嵐山の光景をご想像していただくところから始まります。
まずは簡単にあらすじをご紹介します。
大和国・吉野山の桜は有名ですが、京の都からはあまりに遠いので、都近くの嵐山に吉野の桜を移し植えました。
春になり桜の開花が気になる帝が嵐山に勅使(ワキ)を向かわせます。
そこに老人夫婦(前シテ・前シテツレ)が現れ、木陰を清め桜に向かって祈念しています。不思議に思った勅使が尋ねると、吉野の桜を都に移すときに、木守と勝手の二神もこの嵐山に来られたと語り、実は自分達こそ木守・勝手の神であると名乗り、雲に乗って南の方に飛び去ります。(中入)
その後、蔵王権現の末社の神(アイ)が現れ舞を舞い、続いて木守と勝手の明神(いずれも後シテツレ)が神体として現れ、嵐山の美景を眺めながら舞楽を奏すと、最後に蔵王権現(後シテ)も現れ、衆生の苦患を助け国土を守ると誓い、栄える御代を祝福します。
『嵐山』は脇能です。脇能は神が出現する能で、正式五番立の最初の演目『翁』の脇に演じられることからこの名があります。脇能は喜多流では「真」「行」「草」の三段階に分けられ、『高砂』や『弓八幡』は本格的な脇能の構成で、演者達には気品と力強さが求められる「真」の脇能となります。それに比べて『嵐山』は穏やかで、華やかさが求められる「草」の脇能です。装束も、「真」の脇能の前シテは大口袴をはくのに対して、『嵐山』のように「草」の脇能では着流し姿となり、少し軽い扱いとなります。
従って、前シテの尉は、『高砂』のような強く硬質な尉ではなく、ほんわかと、柔らかな雰囲気の尉を勤めるのが演者の心得です。
謡についても、『高砂』は終始、強吟で謡いますが、『嵐山』は柔らかい和吟が主になります。後場は、「下り端(さがりは)」の、ゆったりとしたリズムに乗って木守・勝手明神が現れ美しい神遊びの趣の舞を見せ、最後に蔵王権現が登場すると、強吟の大ノリのリズムとなって豪快な謡になりますが、全体には柔らかい雰囲気で終始します。今回囃子方の方々にも、全体に「草」の脇能らしく、柔らかく囃していただくようにお願いし、それに応えていただきました。
『嵐山』は、前場の尉(前シテ)と姥(前シテツレ)は木守明神と勝手明神の化身として現れ、後場でそのまま木守・勝手の二神を演じれば理にかない判りやすいのですが、後シテは蔵王権現という全く別の神になり、木守・勝手の二神は別人が勤めます。従って、多くの能役者を必要とします。
今回、前シテの尉と後シテの蔵王権現を私が勤め、前ツレの姥を谷友矩君、後ツレの木守明神を狩野祐一君、勝手明神を金子龍晟君に勤めてもらいました。彼らは二十代半ばから三十代前半の年齢で、今回、意識して若手を起用いたしました。後ツレの二神が登場し、嵐山の辺りの美景を紹介し相舞になりますが、ここは二人が呼吸を合わせ美しく舞う見せどころです。若い二人は喜多能楽堂が改修工事で使用出来ないため、国立能楽堂の研修舞台を拝借して稽古を重ね、よく揃って立派に舞われたので、よい勉強になったのではないかと思います。次代を担う若手を起用して経験を積んでもらうのも、我々世代の役目、そんな年齢になってしまったかと、複雑な心境です。
この後ツレ、喜多流では勝手明神が「小面」に天冠、長絹姿で女神、木守明神は「邯鄲男」に狩衣姿で男神の扮装で現れます。勝手神社などに伝わる話では、本来、木守明神が女神で勝手明神が男神とされています。木守は子守に通じ、子守明神とも呼ばれ、子授け祈願されたとの史料もあるようで、女神が本来のようです。宝生流と金春流は本来のように木守を女神、勝手を男神としていますが、喜多流と観世流は逆になっています。いつから、なぜそうなったのかは不明です。私は現行の通りに演っていても、あまり気になりませんが、子守明神に子授け祈願などでお参りされている方々には、喜多流の舞台演出には違和感を持たれるかもしれません。
後シテの蔵王権現は早笛に乗って突如姿を現したかと思うと、短い舞を舞い、あっという間に留拍子を踏んで終曲となります。舞働も神舞も舞うことはなく、演者としては少し物足りなさを感じますが、その短い時間に蔵王権現の威厳、荘厳さをお見せするのが大事な心得のようです。荒削りにならないように演じるには、若い能役者よりも逆に歳を重ねた者の方が似合うのかもしれません。
今回の装束は敢えて紺色狩衣も赤半切袴とも「立涌」(たてわく)柄に揃えてみました。結果は悪くはありませんでしたが、特別効果が出るものでもないことを学びました。
面は「不動」でも良いかと思いましたが、従来通り「大飛出」にしました。短い時間に強い威厳と荘厳さを目立たせるには、ご覧になる方の目に飛び込んで来るような扮装選びも大事な技で貴重な仕事だと思います。
私にとって『嵐山』はツレ役の姥や勝手明神の経験はありますが、シテ役は稽古能の経験もなく、今回が初演でした。どうも喜多実先生の指導法の影響でしょうか。先生は『嵐山』よりも『弓八幡』や『養老』を稽古し、『高砂』を目指すのが良いとお考えになられたと思います。『嵐山』は若うちに稽古し、披露しておいた方が良い曲ではないことを、今回勤めて判りました。脇能は『弓八幡』→『養老』→『高砂』の順番に、稽古を重ねていくのが吉、これは喜多実先生のお考えでした。この順番で、それぞれのツレやシテを十分稽古・体得し、年を経てさまざまな経験をした後に、『嵐山』の柔らかい前シテの尉、短くコンパクトに豪快さを示す後シテが出来上がるもの、と思います。
『嵐山』の作者は金春禅鳳、世阿弥の娘婿・金春禅竹の孫ですから、世阿弥にとっては曽孫にあたります。世阿弥からだいぶ時代が新しくなり、観世小次郎信光の時代に近いのではないでしょうか。世阿弥や禅竹のような渋い味わい深い能が流行らない時代となり、楽しく華やか、登場人物も大勢で賑やか、見て判りやすい演出が優先された時代です。
『嵐山』の脇能は、堅さより柔らかさ、これを演じる者も三役も意識することが大事だと思いました。最後の謡「光も輝く千本の桜、榮行く春こそ久しけれ」で、全体に春爛漫の桜を愛で、明るい「陽」であり軽めの「草」の能になっているのです。ここに「陰」は似合わない、と意識することが勤める者には肝要です。
前シテの出は「真之一声」です。荘重な一声の出囃子となりますが、「陰」(陰気)の謡になってはいけないはずです。ところが「真之一声」を音程低く、重々しい鈍重に謡う能役者がいます。「真之一声」は脇能のほかには『松風』で使われます。こちらは松風・村雨姉妹の海女乙女が汐汲みという重労働をさせられている訳ですから、暗い重々しい雰囲気で「陰」の謡が吉ですが、『嵐山』は祝言能で、重々しさは必要なく、明るく「陽」の心意気で謡わなくてはいけません。姥役の谷友矩君にこのことを伝え、一緒に明るく謡えたことを嬉しく思っています。通常の「真之一声」は「掛」「一段(越之段)」「二段」と三段の構成ですが、今回は特別に時間短縮を優先し、お囃子方のご協力を得て「掛」でシテツレとシテが登場する演出にしました。
禅鳳の『嵐山』は楽しく華やかに、判りやすく、を目指していたようで、前場も通常の序・サシ・クセがないコンパクトなつくりです。私は最近、ダラダラと間延びしがちな部分を演らない、を演能のテーマの一つにしています。演じる側が自流のためのルールばかりを優先するのではなく、見る側の立場にたって、今の時代に似合う能を勤めるのが、第一ではないかと思っています。
それからもう一つ、間狂言について私論です。アイは前場と後場を繋ぐお役目で、後場の登場人物の着替え時間を作ってくださいます。ただし『嵐山』のように前後で役者が変わる場合は、装束付けのため、という大義名分はなくなります。であれば、もう少し短く、コンパクトなアイの語り、舞も再考されて良いのではないでしょうか。これはこれから狂言方の方々とも相談して、今後の課題にしたいと思っています。
明るく「陽」な祝言能としての『嵐山』。地謡も囃子方も「陽」な雰囲気でサクサクと謡い、囃してくださいました。役者全員が緊張感をもって、軽くサラリとお勤めくださり、感謝しています。舞台上のすべての能楽師の技が一つになり、ご覧になる方に楽しんでいただき、そこに感動が生まれたら、それが世阿弥の説く「真の花(まことのはな)」です。これからも「真の花」を目指さねば、と桜が教えてくれました。これからも精進し良い舞台を勤めたい、と新たに思いました。
写真提供 新宮夕海
嵐山出演者
ワキ 福王和幸
囃子方 笛 槻宅 聡 小鼓 観世新九郎 大鼓 柿原弘和 太鼓 前川光範
間狂言 高澤祐介 地頭 長島 茂
(2024年4月 記)
『融』を勤めて 小書「曲水之舞」投稿日:2024-04-01

『融』を勤めて
小書「曲水之舞」
第106回「粟谷能の会」(令和6年3月3日)では、観世銕之丞氏をお迎えしての異流共演『蝉丸』のシテ・逆髪と『融』のシテを勤めました。一日に能二番を勤めることは、以前ならさほど苦にならなかったのですが、68歳になった今、体力と記憶力に気を配り精一杯勤めようと心に期し、両曲とも無事終えることができ、今はほっとしています。

まずは今回の『融』のあらすじです。
前場では、融の霊が汐汲みの老人(前シテ)となり、荒れ果てた六条河原の院に現れ、旅僧(ワキ)に河原の院の謂われ、そして都の周りの景色を教え、汐汲みを見せると、姿を消してしまいます。(中入)
後場は月の世界より舞い降りた融の霊(後シテ)が遊楽遊舞に興じていた頃を懐かしみ、舞い遊び、夜があける前に月に戻っていくのでした。
融は第52代・嵯峨天皇の皇子で皇位継承権がありながら、藤原基経に阻まれ天皇になれず降下し、源姓となります。その鬱憤を晴らすように、源融は六条河原の辺りに贅をつくした邸宅・河原の院をつくり、陸奥の塩竃の浦を模した庭に、難波から海水を運ばせて塩を焼かせ、その景色を楽しんだといわれています。しかし、融の死後、年月が流れ、素晴らしかった邸宅も廃墟と化しています。

融の霊はその旧跡に月からやって来て、最後に月に帰って行きます。前シテの一声の謡「月もはや」で現れ、ワキと問答をしていると月がやや高く上がって明るくなり「月こそ出でて候へ」と喜びます。月に照らされた周りの名所を教え、後場でも月の明かりに恍惚として舞い遊び、やがて、月が傾いて明け方になると「月もはや」と謡って、月の都に帰って行きます。「月もはや」で始まり「月もはや」で閉じられる、まさに月と共にある融とその詩情で作られていて、『融』のキーワードは「月」なのです。

前場は源融の霊が汐汲みの老人となり廃墟となってしまった河原の院に現れ、悔しく無念な気持ちはあったでしょう。ただ能『融』は不思議なことに、融大臣の無念な執心を晴らす仏教的な背景がまったく感じられません。それはワキの旅僧が一度も読経しないのが要因で、私はワキが普通の旅人でも良いと思いますが、敢えて旅僧にした訳が知りたいです。

今回の粟谷能の会では二番の演能となり、時間的な制約があることから、通常2時間近くかかる『融』を1時間15分ほどに短縮してご覧いただくことにしました。
短縮したところは2か所です。まず、前シテが登場して「月もはや、出潮になりて塩竈の。うら寂びまさる、夕べかな」と謡った後のサシコエ、下歌、上歌を省略しました。うら寂びまさる塩竈に自らの老いを重ねて嘆くところです。
次に、初同(地謡の最初の謡)の最後の謡「千賀の浦曲(うらわ)を眺めん」のあとのワキ謡とシテの語り、二同(地謡の2番目の謡)を省略しました。河原の院の謂れを語り、荒れ果てた姿を目の当たりにして、昔恋しいと慕っても願っても甲斐ない・・・と謡うところです。

通常の2時間近い演能に慣れている方が、省略したところは大事な場面で外せない、本来の能の姿を大切に壊すべきではない、と仰っしゃるのは分かります。その通りだと思いますが、先に述べたように、融の執心よりは月と融の詩情をテーマに決めて、全体の作品を壊さないように配慮した短縮版『融』も、これからは有りではないかと思います。


今、若者は映画など動画を倍速、三倍速で見るようで、タイパ(タイム・パフォーマンス)を重視する時代のようです。そのような意識を持たれる方には、2時間の能はあまりにも長く感じられるのではないでしょうか。これからの時代、粟谷能の会は能二番立の場合、一番は正規通り、もう一番は短めでという番組が良いと考えています。1時間40分の『蝉丸』をご覧になり、狂言の後に、1時間15分ほどの『融』をご覧になって、一日に二番「どちらも、それぞれ面白かった」と感じていただける興行を目指していきたい、と思っています。
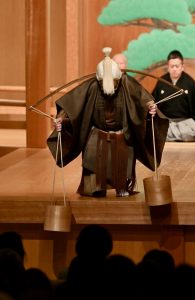

私の『融』の初演は平成4年「妙花の会」、平成28年の「粟谷能の会」で再演し、2年後に「初秋ひたち能と狂言」でも勤め、今回が4回目です。過去3回とも早舞は「クツロギ」(橋掛りに使う特殊演出)で勤めていますが、今回の小書「曲水之舞」は最初に橋掛りを使う演出で重なるので「クツロギ」は出来ませんでした。


喜多流の『融』の小書は「曲水之舞」「笏之舞」「遊曲之舞」「遊曲」があります。
「曲水之舞」「笏之舞」「遊曲之舞」は、いずれも早舞の前にイロエやハタラキ的な短い舞が加わりますが、「遊曲」は早舞が無くなり、イロエだけの特別に重い習となります。



今回の「曲水之舞」は通常の早舞の前に曲水の宴を想起させる型が入ります。流れる盃を両手で掬い、その後は、左手で右袖(袂)を持ち、右手の中啓(扇)を盃と見なす演出で、早舞となるまで、終始右手で盃を持っている構えで舞います。盃を両手で掬うと、まずは水上(川上)を想定する幕際まで、右手を少しずつ上げながら行きます。そして、ゆっくり振り返り下に流れる曲水を見て、その流れに盃を流すように、また融自身が流れる盃になったような心持ちで幕際から徐々にスピードを上げて本舞台へと入り、円を描くように丸く廻ります。ここまでが曲水之舞で、その後に通常の早舞となります。今回は時間短縮もあり、掛を省略して三段構成で勤めました。



最初に橋掛りを使う小書「曲水之舞」は、同様に橋掛りを使う「クツロギ」と重なるので、敬遠されあまり多く演じられていません。父・菊生の『融』は「曲水之舞」しか演じていませんが、写真を見ると今でも当時の舞台が脳裏に浮かんで来ます。今回の短縮版『融』を父はどのように思っているのだろうか・・・、少し気になります。


後シテの格好ですが、通常は色鉢巻きを頭に巻いて面を付け、頭に初冠を載せるだけですが、今回はそこに観世銕之丞家より「馬毛頭」(ばすかしら)を拝借して付けました。
昔、野村萬先生がまだ万之丞時代、観世寿夫先生が『融』をお勤めになる際に、「面と初冠だけでは、人間の生の部分が見え過ぎて、夢の世界の融の霊には似合わないのでは?」と仰っしゃられたのを受けて、寿夫先生が工夫されて「馬毛頭」を付けられたのが最初だと能夫から聞いています。そのお姿は『観世壽夫 至花の風姿』でご覧になれます。
実は喜多流で初めて、寿夫先生の真似をして、馬毛頭に似た黒い毛(黒垂)を付けたのは私で、しかも初演のときでした。若輩ながら、自分の立場で、自分の出来る範囲内で、より良い演出をしたいと思い始めていた頃でした。当時は「あのような、奇を衒うことはしないほうがいい」など、陰口もあったようですが、時が過ぎると今ではそれが普通となり、陰口をたたく者もいないでしょう。いつの世も最初に挑む者に陰口は付き物ですが、今回の初番『蝉丸』の逆髪のように、自分の思う通りに演じたい、を貫いて生きている私はたいへん恵まれ、少し変わり者なのかもしれません。
演能は、より良い演出、より想像しやすい姿をご覧いただくのが大事で、最優先だと信じています。これからも、良いと思うことは周りを気にせず、我が道を邪魔されずに進みたいと思っています。

最後に、後シテは本来「指貫」を穿きますが、今回『蝉丸』のツレ・蝉丸で銕之丞氏が「指貫」を穿かれましたので、二番「指貫」が続くのは良くないため、ゲストを優先して、私が「色大口袴」を穿いたことを記しておきます。
(2024年3月 記)
撮影 新宮夕海
ワキ 宝生常三
笛 一噌隆之
小鼓 観世新九郎
大鼓 亀井洋祐
太鼓 小寺真佐人
(『融』については、演能レポート「『融』を演じて 月の詩情に寄せた名曲」(平成28年3月)に詳しく書いていますので、合わせてご覧ください。)
http://awaya-akio.com/2016/03/06/post480/
『蝉丸』を勤めて投稿日:2024-03-26

『蝉丸』を勤めて
異流共演と狂女・逆髪
能には、心の中が屈折している主人公を扱った演目が多くあります。「第106回 粟谷能の会」(令和6年3月3日)で勤めた『蝉丸』のシテ・逆髪(さかがみ)とシテツレ・蝉丸は屈折の特上クラスの人物で、しかも姉弟です。今回、弟の蝉丸を観世流の観世銕之丞氏にお引き受けいただき、姉の逆髪を私が勤める異流共演が実現しました。
実は数年前、大槻能楽堂自主公演で銕之丞氏と私の異流共演『蝉丸』が企画されましたが、折悪しくコロナ禍で、公演中止となりました。この企画を是非復活したく、今回の「粟谷能の会」で出来ないものかと銕之丞氏に相談しましたところ、快諾してくださり実現に至りました。大槻能楽堂自主公演では観世流の地謡で、私一人が異流で加わる演出でしたが、今回は喜多流の地謡となりました。この異流共演で舞台上になにか面白い化学反応が起きるのではないか、と期待していました。予想通り、ご覧になられた方々からは、二人の個性のぶつかり合いがとても面白かったとご感想をいただき、企画実行出来たことを、改めて喜んでいます。
私の記憶に残る異流共演は、観世銕之丞氏のお父様と私の父が以前中尊寺の白山神社能舞台にてシテ・建礼門院を先代・観世銕之亟先生、ツレ・後白河法皇を父菊生が勤めた『大原御幸』です。今、無事に終えると、今回はあの衝撃的な『大原御幸』の続編のようにも思えて、思い出に残る舞台となりました。また『蝉丸』の異流共演はシテ・逆髪を友枝昭世師、蝉丸を大槻文蔵先生が勤められた映像が、とても勉強になりました。
先日、写真の整理をしていましたら、祖父・粟谷益二郎(本名・益次郎)が『蝉丸』の逆髪を勤めている貴重な写真がありました。姉弟の再会場面、「互いに手に手を取り交わし」と手を差し出す益二郎に「姉宮かと」と受けておられる蝉丸は金春流の桜間金太郎先生でした。このモノクロ写真は、祖父が大正時代に既に『蝉丸』で異流共演を勤めていたことを教えてくれ、今回の企画が特異なことではないと証明してくれました。それで俄然、逆髪を勤める気持ちが強くなり自信にも繋がりました。
はじめは異流共演に不安を感じていましたが、『蝉丸』は観世流と喜多流で詞章の違いがさほど多くなく、それほど演りにくいことはありませんでした。ただ一点、藁屋の作り物が脇座から笛座前に置き替わると、藁屋を見て謡を覚えている私には最初、どうしても違和感があり、謡を間違えることが多く、正直慣れるのに時間がかかりました。
今回、クセの上羽(クセの中でシテが謡うところ)「たまたま言訪ふ ものとては」は、喜多流ではシテの謡ですが、ここは蝉丸の心情ですのでツレが謡うように変えました。
またチラシや番組に記載しませんでしたが、銕之丞氏から「替の型」で勤めたいとの、お申し出がありました。「替の型」は喜多流には無く、観世流にある小書(特別演出)の一つで、蝉丸の位が上がりシテと同等に扱われ、作り物(藁屋)の位置が変わり、蝉丸の装束が大口袴から指貫になる、など演出が変わります。本来、脇座前に置かれる藁屋は、大小前に置くこともあるようですが、今回は銕之丞氏のご希望で笛座の前に斜めに置きました。蝉丸がシテと同等になるため、観客からよく見えるように、目立たせる演出です。逆髪と蝉丸の両シテの意識は、まさに異流共演に相応しい演出となりました。
私の『蝉丸』の演能はツレ・蝉丸役が2回、シテ・逆髪役が1回です。今回、逆髪の再演にあたり、屈折した逆髪をどのように演じたらよいか悩んでいたところ、鑑賞講座(1月18日開催)で話された銕之丞氏のお言葉で、逆髪の輪郭がはっきりし、悩みが消えました。

能『蝉丸』は皇族として生まれながら不遇の境遇にある姉・逆髪と弟・蝉丸の悲運の物語です。逆髪は毛が逆立つ狂女、蝉丸は生まれつき盲目の身です。
盲目の蝉丸は父・帝の命令にて逢坂山で出家させられ捨てられます。供してきたワキ・清貫が勅命とはいえ蝉丸を出家させ捨ておかなければならないことの悲しさに沈んでいると、蝉丸は「これは前世の戒行がつたなかったゆえ、この世で過去の罪障を償い、後世で救われるようにとの、父帝の思し召し、真の親の慈悲だから嘆くことはない」と清貫を慰めるほど、多分に仏教的で内省的、運命を受け容れる諦念が見えます。それでも清貫一行が立ち去ると、さすがに寂しく、泣き悲しむ蝉丸です。
それに対して姉の逆髪は違います。生まれつき逆立つ髪を、宮中の女官達から白い目で見られ、陰口を叩かれていたかもしれません。実際に髪が天に向かい生え伸びるなどあり得ませんから、きっと現代のイメージでは天然パーマ、縮れ毛、その程度のものと思いますが、真っすぐな髪がもてはやされた時代に縮れ毛は異様に見られ、敬遠されたのではないでしょうか。そんな環境下にあった逆髪の心は屈折し、時には自閉症のように、また逆に落ち着いてじっとしていられない性分もあったのかもしれません。外と内への心のバランスが崩れ、最終的には自分の思うままに宮中で行動し、遂には放浪の旅にも出てしまうのです。
逆髪は登場すると自分の髪は逆さまに生え上り、いくら撫でつけても下がらないと謡い、童どもに笑われると、身分の低い者が私のような高位の者を笑うなんて、あなた方が逆でおかしい、と嘲罵し、あっけらかんとしています。周りから何を言われても、自分を正当化し、気にせず勝気な性分です。弟と再会して、お互いの境涯を嘆き合いますが、時が経つとまた逆髪は彷徨いたくなるのです。蝉丸が引き留めても、行く当てが決まっているわけでもないのに、立ち去ります。自分の気持ちに正直であり、その意識はまっすぐでも一方通行です。このあたりが周りから狂人と見られる所以ではないでしょうか。そのような逆髪をどのように演じたらよいのか分かりませんでしたが、銕之丞氏の「能『蝉丸』は姉と私なのです」の一言で判りました。
作者・世阿弥はハンディキャップがある二人の姉弟の悲劇を、勝気な姉と内省的な弟という性格や行動の違い、動と静、陽と陰を描き分けて作りました。蝉丸の琵琶の音にひかれて、二人が再会する劇的な場面で観客の涙を誘い、最後は、藁屋に蝉丸一人残して、会者定離の理をも表し、また涙を誘う、さすが世阿弥と感心させられます。このような昔話ですが、現在の我々の生活とかけ離れたものではありません。ハンディを背負った人、悩みを抱えている人達がそれぞれの性格に合った、それぞれの生き方をしていけば良いのでは?と、語りかけているように思われます。能は現代にも通じ、決して古臭いものではないのです。
では能役者として動的で勝気な逆髪をどのような格好(面・装束)で演じたら良いのか、
また逆立つ髪をどのようにご覧にいれたらよいのか、いろいろ悩みました。
我が家の喜多寿山の伝書に
「シテ(逆髪)ノ出立、玉葛ノ後ト同事、但シ左右共髪ヲ分ケ前ヘ下ル」
とあります。『玉葛』の後シテは唐織着流姿で片方(左)だけ髪を前に垂らしますが、逆髪の出立は唐織肩脱着流姿に鬘を前に左右に分けて垂らすのが喜多流の基本形です。しかし近年、鬘を黒頭に変えたり、唐織ではなく摺箔に大口袴、または緋色の長袴などに替える出立も多くなされるようになりました。
喜多流の基本形である鬘を左右に分けて垂らす姿は綺麗ですが、勝気な狂女としての逆髪を想像いただくには難しいと思い、今回は黒頭をつけることにしました。黒頭の代わりに観世銕之丞家より馬毛頭(ばすかしら)を拝借する選択もありましたが、次の演目の『融』に馬毛頭を使いたいこともあり、出る寸前まで悩んだ末、先に紹介した祖父・益二郎の黒頭の写真の姿が力となり黒頭に決めました。
袴は宮中の人らしく緋色の長袴にしました。都から逢坂山に放浪の旅をする逆髪が、引きずるほどの長い袴を穿くのは理にあわず、不適かもしれませんが、そこは写実ばかりではない、能ならではの演出と割り切ることにしました。ただ今回、右足の長袴がからまったまま出てしまい、とても動きにくく往生しましたが、それも最終的には自己責任、自分自身の注意不足と反省し、以後気をつけたいと思いました。
面は、本来喜多流は「小面」ですが、狂女の逆髪には可愛らし過ぎると思い、愛用の石塚シゲミ打の「増女」を拝借しました。「小面」より少し大人で、艶がある表情がとても好きで気に入っている面です。
今回は銕之丞氏がしっとりと内省的な蝉丸を演じてくださったので、その対照を鮮やかに観ていただきたく、舞の動きも謡も、やや快活に勤めました。
銕之丞氏の圧倒的な存在感は、観る人を魅了したことは間違いありません。朝早くから楽屋入りされた銕之丞氏のお陰で楽屋の空気がきゅっと締まって緊張感が漂いました。とてもよい空気感で一日が始まり、公演が終わるまで緊張感が持続したことに感謝しています。
地謡の面々も、特別な緊張感でエネルギーをもって謡ってくれました。
異流共演の試みは、いろいろな意味で素晴らしい効果をもたらし、実現出来て本当によかった、と喜んでおります。
観世銕之丞先生、いろいろお世話になり、厚く御礼申し上げます。
また、大鼓の亀井広忠氏、小鼓の鵜澤洋太郎氏が、銕之丞氏の謡には観世流に合わせ、私の謡には喜多流でお付き合いいただくという、巧みに打ち分けられた技に、改めて感謝と御礼を申し上げます。『蝉丸』の出演者の皆様、異流共演を盛り立てていただきありがとうございました。 (2024年3月 記)
写真撮影 新宮夕海
(なお、ツレ・蝉丸を勤めたときの演能レポート「『蝉丸について』」(平成19年3月)も合わせてご覧いただけると幸いです。)
『敦盛』を勤めて 〜若やいで美青年を演じる投稿日:2023-09-06

『敦盛』を勤めて
若やいで美青年を演じる
8月の喜多流自主公演(令和5年8月20日 於:観世能楽堂)で『敦盛』を勤めました。
『敦盛』の初演は平成7年10月の「粟谷能の会」でした。稽古能では勤めていますが、公開ではこのときが初めてでした。その後、半能で勤めたこともありましたが、正式には今回が2回目、実に28年ぶりとなりました。『敦盛』はシテが16歳の青年ですので、20代~30代の若いうちに一度は勤めておくべき演目ですが、私は機会がなく少し遅めの40歳での披きとなりました。
再演に際して、私は面や装束は出来る限り前回と重ならないよう、違うものを選ぶようにしていますが、今回は40歳初演の時と同じ面と装束を選び、若い頃の雰囲気そのままを再現出来れば面白いのではないかと思い、敢えて同じものにしました。鏡の間で自分の姿を見ていると40歳の時に戻るような不思議な気分を味わい、とても面白く感じました。
『敦盛』の物語は、蓮生法師(ワキ)の名乗りから始まります。源氏の武将・熊谷次郎直実は、一の谷合戦で16歳の公達・平敦盛を手にかけたことで、世の無常を感じ出家して名を蓮生法師としました。蓮生が敦盛の菩提を弔うため、再び一の谷を訪れ弔っていると、遠くから笛の音が聞こえ、数人の草刈男(前シテ・シテツレ)が笛を吹きながらやって来ます。身にそぐわない風流な男達と笛の故事などを話すうちに、男達は立ち去りますが、一人(シテ)が居残り、実は自分は敦盛の霊であるとほのめかし、弔ってほしいと頼み消え失せます。
『敦盛』のワキは行きずりの旅僧ではなく、敦盛の因縁の敵、熊谷次郎直実すなわち蓮生法師に設定しています。かつて戦で敵同士であった二人が、敦盛は霊として、直実は出家の身・蓮生として、再会することで、劇的に面白くしています。
舞台進行はワキが名乗りのあとに一ノ谷にて弔いの念仏を唱えていると遠くの方から笛の音色が聞こえて来ます。すると「ああ面白い、笛の音が聞こえてきた」と、謡いますが、本来は笛の音は鳴りません。今回はご覧になる方々に実際に笛の音色が聞こえた方が舞台の進行と状況が分かり易くなると思い、笛の杉信太朗氏とワキの宝生欣哉氏にご協力いただき、ワキの念仏の後に短いアシラヒ笛を吹いていただきました。これにより、シテとシテツレの「草刈笛の声添えて」の次第の謡で、笛を吹きながら現れたなあ、とご覧になる方々が想像して下されば・・・と思っての工夫、演出でした。
この演出は喜多流にはありませんが、金剛流に「青葉之会釈」という小書で存在しますので、まったく新しい演出ではありません。能は観客の想像に委ねるところが多い少し不親切な演劇です。演者はそこにあぐらをかくのではなく、少しでも分かり易くご覧いただけるような工夫は必須です。逸脱しない範囲内で、できる限り分かり易くご覧いただけるように考え対応することは、今の時代とても大事だと思っています。ブログやフェイスブックに能を紹介することで、自身不親切な部分に気づくことがあります。今回も投稿がきっかけで笛の演出が実現出来て、とても有意義だったと思っています。私にとって演能レポートは、頭の整理と過去の演出の見直し、それだけでなく、新たな発想が生まれることにもなり、とても楽しいライフワークです。
後場は、蓮生が敦盛の霊を弔い念仏を唱えると、武将姿の敦盛の亡霊(後シテ)が現れ、平家一門の栄枯盛衰を語り、合戦前の宴を懐かしみ、そして舞を見せ、最後は討死の有様を見せます。敦盛は敵の蓮生に巡り会いましたが、今は敵ではない蓮生法師に回向を頼み消え失せます。
後場は舞いどころが多く、修羅能の武将は「カケリ」を舞うのが定番ですが、『敦盛』は正規の舞「男舞」を舞う特異な曲です。カケリは舞とも言えないほど短く激しい動きですが、男舞は少しスピーデイーに舞をみせる趣向です。喜多流の敦盛は美青年、16歳の未熟な男として、大人の男に成っていないため、正式な舞の構成の五段の寸法ではなく、短く三段で済ませます。明日、死ぬかもしれないという戦の前に、管弦の宴を催す平家方の優美さ。戦さ場にも女性たちを同行させる平家の人達に対し、荒々しく戦場を駆ける坂東武者では、その勝敗は見えていたのではないでしょうか。
敦盛は宴で笛を吹き、その笛を陣中に置き忘れ取りに戻ったのが命取りとなります。敦盛が一人逃げ遅れ、熊谷次郎直実と相まみえるようになったのは、笛への愛着、そして何よりも大事なものを置き忘れた不徳のいたすところです。
カケリを男舞に変えて、音楽好きの貴公子・敦盛を強調した世阿弥の演出は冴えています。しかし、修羅能でありながら、修羅能らしくないところを演じなければいけないのが、演者の注意点かもしれません。後場は平家一門の栄枯盛衰を語りますが、敦盛が修羅道に堕ちて苦しむ様は無く、直実に殺される戦闘場面も短く作られていて、「敵はこれぞと討たんとするに」と、太刀を抜き、討ちかかりますが、すぐに弔いに感謝して太刀を捨て同じ蓮(はちす)に生まれよう、敵ではないと言い終曲します。全く修羅能らしくないのです。
能は、特に世阿弥は、強い武将を描くより、優美で、美しく散っていった貴公子を描いて名作を多く残しています。『清経』『通盛』『忠度』など、能は亡びの美学、亡びる者への鎮魂の意味があるようで、平家の公達の能を演じると、いつもそのことを感じます。
敦盛が腰にさしていた笛のことを『平家物語』(敦盛最期)では、鳥羽院が敦盛の祖父・忠盛に与えたもので、それが父・経盛に相伝され、才能ある敦盛に与えられたもの、名を「小枝」と言う、と書かれています。一の谷の合戦で源氏の陣地であった須磨寺には、敦盛が愛用した笛「小枝の笛」が「青葉の笛」と呼ばれ、今でも宝物館に展示されているようです。
能『敦盛』の詞章には、前場で笛づくしの謡がありますが、そこには「小枝、蝉折、様々に、笛の名は多けれども、草刈りの吹く笛なれば、これも名は青葉の笛と思し召せ」と謡い、敦盛の笛が「青葉の笛」なのか「小枝の笛」なのかは、はっきりしません。前シテを草刈男としたのは、草刈笛の説話もあるようですが、「青葉の笛」のイメージも重なっていたのかもしれません。
28年ぶりの『敦盛』、演じるにあたり一番心掛けたのは、クセの仕舞どころや男舞、キリの仕舞どころなどで、若い貴公子になるために、もうすぐ68歳の私が、懸命に若やいで舞おうとしたことです。若いころなら、何も考えずに若々しくできましたが、今はそこに意識を集中して若々しく演じる、そこへの挑戦でした。
『敦盛』はもしオファーがあればまた懸命に勤めますが、おそらく、これが舞い納めとなるでしょう。来年は『頼政』が2回、予定されています。同じ平家物語を本説にしている能でも、『頼政』など、年寄系の能にシフトし、老武者の心を演じたいと考えています。
『敦盛』の出演者(敬称略)
ワキ:宝生欣哉 後見:友枝昭世・内田安信 笛:杉信太朗 小鼓:大倉源次郎 大鼓:佃 良勝
(2023年9月 記)
『三輪』を勤めて 三輪明神を男神と意識投稿日:2023-03-24

『三輪』を勤めて
三輪明神を男神と意識
第105回・粟谷能の会(令和5年3月5日、於:国立能楽堂)で『三輪』を勤めました。私の『三輪』初演は平成6年、広島花の会で、その後、平成19年に粟谷能の会(粟谷菊生一周忌追善)にて小書「神遊」に挑戦し、平成29年に広島薪能で勤め、今回は4回目です。小書への取り組みは、新しい視点から能を深く掘り下げる作業ができるので、色々と勤めて参りましたが、特に小書「神遊」は若い頃からの憧れでもあり、その経験がその後の演能にとても役に立っています。しかし今回は敢えて小書を付けず、『三輪』の本質を知りたいと選曲しました。
故・観世銕之亟先生(観世静夫先生)は「能を大別した時、神の能と仏の能があり、私は神様の出現する能の方が大好きです」と、おっしゃっておられました。今回勤める『三輪』はシテが三輪明神、ワキは高僧の玄賓僧都(げんぴんそうず)で、神様と仏様の両方が絡んでおり、また、三輪明神が男神と女神の諸説あり、どちらを想定するかで演じ方も変わると思います。
「神と仏」「神と衆生」「男と女」、現代人ならば、しっかり区分けしたいところですが、逆に分けない曖昧さが能『三輪』の魅力であり面白さかもしれません。私は今まで女神を想定して勤めてきましたが、今回は男神の意識で勤めてみました。
この観点に立てたことで、今回新しい試みが出来て、しかも少し本質に近づけたという手応えを感じ、素直に喜んでおります。
三輪明神を男神と考えると、おのずと装束選びも違ってきます。私は演能の手引きとして、伝書を主体に、諸先輩からの伝承と、そして演能写真も大きな手掛かりにしています。『三輪』で、心を動かされた写真が二枚あります。一枚はモノクロの観世寿夫氏の大口袴を着流しに替え、蔓帯をしないお姿です。「寿夫先生は、三輪明神に王朝風の蔓帯は似合わないと考えられ、外されたのだ」と従兄の能夫が説明してくれ、能は決まり事でがんじがらめではなく、色々な工夫が出来る余白があることを教えてくれました。能の可能性に目覚めた一枚です。今回は男神として演じるために着流しにはいたしませんでしたが、蔓帯は外しました。
そしてもう一枚は56世梅若六郎先生の写真集の白地狩衣に浅黄色の大口袴、面は「十六中将」の男顔のお姿です。
これを見たときは、さらにすごい衝撃が走りました。通常の緋大口袴に長絹の女姿とがらりと違って、まさに男神を具現しています。この写真は男神を意識した演出の大きな原動力となり、白地の狩衣と浅黄色の大口袴の装束はすぐに決まりました。面は敢えて女顔にこだわり、本来のかわいい「小面」ではなく、クセの詞章を考えて、やや艶のある大人びた「増女」にしました。
ここで、『三輪』のあらすじを簡単に記しておきます。
三輪山に住む玄賓僧都(ワキ)の庵に、三輪明神が里女(前シテ)に取り憑いて、樒(しきみ:仏前草木)と閼伽の水(あかのみず:仏前に供える水)を毎日供えに通っています。里女は玄賓に取り次いでもらうと、僧に救済を求め、衣を一枚所望します。受け取って帰ろうとすると、住処を尋ねられ、里女は三輪明神の神詠を引き、杉の立つ門を目印に訪ねて来て、と言って、姿を消します。
【中入】
玄賓が教えられた場所に行くと神木に与えた衣がかかっていて、金色の文字で歌が書かれています。読むと、女の顔をした三輪明神(後シテ)が現れ、衆生(人間)の罪を助けてほしいと願います。そして、神代の昔物語は衆生のための方便であると語ると、神婚譚や天の岩戸の前の神楽を再現して見せ、最後に三輪と伊勢の神は同体である、と告げ、夜明けと共に姿を消すのでした。
能『三輪』はなかなかわかりにくい曲です。演ずるにあたり私のいくつかの疑問の私なりの答えをご紹介いたします。
先ず、三輪明神はなぜ里女になり、しかも神が仏に救いを求めるのか?
神はつい万能と思ってしまいますが、能の世界では神が人間界に降りられ力を発揮するには、人に取り憑かなければならない設定が多いです。
能『三輪』では、高僧の玄賓僧都に毎日樒・閼伽を供え、「憂き年月を三輪の里に過ごしている」と嘆く仏を信仰する里の女に三輪明神は取り憑きます。そのため神が玄賓僧都に救いを求める不思議な現象となりますが、これは神が人間救済のために、身を犠牲にし、時には人間になって、人間の迷える心、老いの苦悩も共に苦しみ、我々衆生を救済して下さる、と考えると何とも有難いお話で、腑に落ちます。
ということで、三輪明神は里の女の嘆きを助けるために天より降りられ取り憑いた、と考え勤めました。
次に後場の見どころとなる二つの昔物語、神婚譚と天の岩戸隠れの話をどうしてここで紹介されたのか?
答えのヒントは序のシテと地謡の謡にあります。「それ神代の昔物語は末代の衆生の為、済度方便の事業(ことわざ)、品々以て世の為なり」と、昔物語は人々を救う手立てであるということで、神婚譚や天の岩戸隠れの話を選ばれたのは三輪明神の済度方便のお考え、と思うと、これも腑に落ちます。
この神婚譚のクセはとてもエッチで面白い内容です。大和に住む夫婦の女が、夜にしか来ない男に「昼もいらして」とおねだりをすると、男は「昼は恥ずかしい、そんな事を言うならもう会わない」と別れを告げます。女は別れを悲しみ男の住処を知ろうと裳裾に糸を付け、糸を手繰って住処に辿り着くと糸は杉に絡まっていました。能に「蛇」の詞章はありませんが、説話では杉の下に蛇がいたとされています。女は「私の相手は杉?」「えっ、私は蛇と・・・・・」。
こんなエロチックなお話を三輪明神が謡い舞って玄賓に見せますが、ここはさらさらと、軽快に進めると舞台効果が上がると思い、地頭の友枝昭世師にお願いして軽く謡っていただきました。これはとても好評で、自身満足しています。
神婚譚の後、玄賓は「もっともっと聞かせて、見せて」とねだるので、明神はさらに続けます。
天照大神が岩戸隠れをなさり、世の中が暗闇となったため、岩戸から出てきていただこうと、八百万の神たちが岩戸の前で楽しそうに歌声をあげたのが神楽の始まりであると、その有様を見せます。
「神楽」は、御幣を使って舞う流儀もありますが、喜多流は中啓(扇)で舞います。これは三輪明神が巫女に取り憑いて舞うのではなく、明神自身が舞われることを意味します。能の基本的な作風は、前場で化身として現れ、後場で本来の姿になって登場するものです。喜多流の『三輪』は前場で里女に取り憑いて現れ、後場で本来の三輪明神が出現するので、正に基本形、理にかなっていると思います。
『三輪』の神楽は神楽と神舞の2部構成です。私は前半の神楽は天鈿女命(あまのうずめのみこと)のイメージで、リズム良くワクワクするような雰囲気で舞い、後半の神舞はガラッと変わって、手力雄命(たぢからおのみこと)が岩戸を開ける情景を力感溢れる舞でお見せしたいと思いました。神楽は地謡の声が入らず、囃子方4人とシテだけの世界となります。シテは笛や小鼓、大鼓、そして太鼓の音色に合わせて舞いますが、ここは能役者の舞の技量が計られるところです。今回のお囃子方(笛・松田弘之、小鼓・鵜澤洋太郎、大鼓・亀井広忠、太鼓・小寺真佐人)の素晴らしい神楽に乗って舞うことが出来たことも、大きな喜びでした。

『三輪』のシテは一人で何役もこなします。前シテでは里女になり、神婚譚では妻の女と夜しか来ない男にもなります。神楽で天鈿女命と手力雄命になり、最後は岩戸を開けて姿を現す天照大神にもなってしまい、一人六役です。それを三輪明神として姿、恰好を変えずに目まぐるしく変化・展開するのですから、ご覧になる方は「今、何に変身しているのか?」を、常に想像して見ていただけると、舞台進行がお分かりになるのではないでしょうか。
最近、加齢してせっかちになったのかもしれませんが、能の演能時間が必要以上に長く感じることがあります。
地謡で昔、父・菊生と一緒に謡っていたときは、すべてが乗りよく謡っていたように思い出します。静かにゆっくりでもテンポ良く、ご覧になる方がワクワクするような、観ていて、聞いていて楽しくなるように、それが悲劇であっても同様に演じたいです。演者も観客も心の興奮が起きる舞台こそ、世阿弥が説く「華(花)」です。
「えっ、もう終わったの?」と、ご感想をいただけたら、演者たちの勝ち、「まだ演るの?」と観客に時計を見られたら演者たちの負け、と思っています。今回、80分の演能時間を「区間新記録ですね」と、仲間から冷やかされましたが、「その通り! 新記録」と、笑って答えました。
今回も様々な新しい試みをいたしましたが、いつも一緒になって考え協力してくれる仲間がいることが有難く、感謝しています。仲間がいるから今日までやってこられた、とつくづく思います。多くの人の支えがあって私の今があるのです。
能には面や装束、型など、色々な決まり事がありますが、実は幅広く対応する懐の深さを備えていることを教えてくれ、様々な工夫をし、挑むことの喜びを熱く語ってくれたのは、今残念ながら休演中の従兄の能夫です。能の懐の深さを知ったことが、私がこれまで演能を続けてこられた一因で感謝しています。
能夫の復帰を願っています。
写真提供 『三輪』撮影 新宮夕海 (2023年3月 記)
『大江山』を勤めて投稿日:2022-12-26

『大江山』を勤めて
騙されるのは鬼 騙すのは人間
鬼退治を題材にした能『大江山』を喜多流自主公演(令和4年12月18日)で勤めました。『大江山』の初演は平成11年6月、同じ喜多流自主公演で、今回は実に23年ぶりの再演です。お相手のワキ(源頼光)は初演のときと同じ殿田謙吉氏で、お互い23年の齢を重ねての共演となりました。
まずは、物語のあらすじを簡単に記します。
「大江山の鬼を退治せよ」との勅命を受けた源頼光一行が山伏姿に変装して大江山に向かいます。大江山に着くと、血染めの衣を洗う女(アイ)の案内で、鬼の頭領・酒呑童子(前シテ)に近づき、一夜の宿を乞います。童子は出家の人には手を出さないと決めているとして、一行を素直に迎え入れ、酒宴を開き歓待し、やがて泥酔して寝室で眠りにつきます。
(中入)
夜更けを待って、武者姿となった頼光一行が寝室に討ち入ると、童子は身の丈が2丈(6メートル)の鬼(後シテ)になっていて、自分を騙したことを怒り、凄まじい勢いで襲いかかります。しかし、ついに鬼は首を討たれ、頼光一行は喜び勇んで都に帰ります。
酒呑童子は『大江山絵詞』や『御伽草子』、『酒呑童子絵巻』などに、財宝を盗んだり、京の女をかどわかしたり、悪事を働く鬼として描かれています。ゆえに「大江山の鬼を退治せよ」との勅命が下り、鬼退治の武勇伝が出来るのも自然です。
しかし、能『大江山』の前場の酒呑童子にはその悪い鬼のイメージがありません。お酒が好きで呑むと赤ら顔となり、童心を失わず、無邪気で、敵意も害意も示さず、素直に心開いて身の上話をし、自ら歌い舞って酒宴を盛り上げます。このあたりが、この能の見どころにもなっています。私も酒好きなので、酒呑童子の気持ちになって楽しく勤める事が出来ました。
さて、童子の身の上話に耳を傾けてみると、どうやら、彼らはもともと比叡山を栖にしていた先住民族のようです。そこに大師坊(天台宗の開祖・最澄)という似非者がやってきて、根本中堂(延暦寺)を建て、麓には七社の霊神を祀り、仏たちも組みして「出て行け、出て行け」と責め立てるので、ついに追い出されてしまい、それからは飛行して転々としたが、都が懐かしくなって都にほど近い大江山に隠れ住み着いた、と語ります。
この経緯を素直に読めば、悪は大師坊となりそうですが、追い出された大江山の童子たちが、悪事を働くと悪者にされ、退治される運命になります。しかも、退治する側の頼光一行は武者であることを偽り、山伏姿になって近づき、うまい酒と偽って、鬼が飲めば五体の自由を失う酒を飲ませてしまいます。また、隠れ家は人に知らせないから安心しろ、と約束しながら、それも守らず鬼退治です。
このように、騙されるのは鬼 騙すのは人間、です。
無邪気に山伏達を信じ歓待した鬼は怒りに震え「情け無しとよ、客僧達。偽りあらじと云いつるに。鬼神に横道無きものを」の名セリフを吐いて襲い掛かります。
しかし、最後に勝つのは騙す側で、騙される側は退治されてしまいます。なんという理不尽。ときの権力者が領土拡大をしようとするとき、そこに住み着いていた先住民族や抵抗勢力は邪魔者です。そのとき、邪魔者を悪者・鬼に仕立てあげ、排除すべき存在として正当化し、追い出すというのは権力側の上手いやり方、現在にも通じるかもしれません。
能の作者はパトロンでもある体制側に逆らうことはできませんから、『大江山』では後場で胸のすくような鬼退治を見せて、体制側に軍配を上げます。それでも、前場で、退治されるべき鬼をただ悪者にするのではなく、愛すべき存在として描くことで、権力に対し秘やかな抵抗を試みている、と私は思います。
とはいえ、能『大江山』は物語がシンプルで、動きもあり素直に楽しめる能です。
ワキと従者(ワキツレ)の六人が舞台狭しと向き合って連吟するスタートは、勇壮な鬼退治の物語の始まりを予感させます。大師坊が追い出しを謀ったときに、童子が抵抗して「一夜に三十余丈の楠となって奇瑞を見せよう」とした話や、比叡山を出てから霞に紛れ、雲に乗り、筑紫や彦山、大山、白山、立山、富士と飛行した話など、空想的、童話的な要素もあり面白いところです。アイの洗濯女と剛力のやり取りも、おとぎ話そのままで面白く楽しめます。もちろん、後場の鬼と頼光らとの戦いぶりは見ていて心躍るところです。
ご覧になる方には、この鬼退治の能をただただ楽しんでいただければ良いのですが、ここに書いたような裏話を少し心にとどめて見ていただけたら、と、これは演者としての思いです。
今回前場の装束は、初演のときと全く同じでは面白くないので、半切を変えてみました。
面は粟谷家に、かわいい顔の出目半蔵打の名品の「童子」がありますが、酒呑童子の本性が見え隠れするような表情がほしくなり、少しひねくれた感じの「童子」を拝借して勤めました。
謡い方も、本来は面の「童子」に合わせて謡うべきですが、この曲は特別で、体の内に鬼という荒い正体を抱えているイメージが観る側に伝わらないと演者としては失格です。やや荒く強く「童子なのに、なんだか不気味」と、思っていただけるような謡い方が吉だと思います。
後場の装束も、以前勤めた『羅生門』と同じでは代わり映えしないので、金地に紺色の派手な法被を拝借して、面も通常の「顰(しかみ)」ではなく、よりスケールの大きな「大顰(おおしかみ)」を拝借しました。
鬼の動きは豪快に荒く、大きな動きで演じるのが心得ですが、ともすると速く動けば良い、と誤解しがちです。鬼は適度なスピードと型の切れが演じるうえで大事です。動き過ぎるとかえって小さく見え逆効果になることを、演者は早めに体得することが大事だと思っています。
今回、久しぶりに『大江山』を勤めて、私自身は楽しく勤められました。幽玄の能とは違って、演技的にはストレート勝負ですが、この曲に込められた裏側を知っていただけたら、酒好きの酒呑明生としては、とても嬉しく心地よい酔いに浸れそうです。
写真提供
新宮夕海 前島写真店 (2022年12月 記)
『杜若』を勤めて投稿日:2022-07-11

『杜若』を勤めて
メインは杜若の花の精
初夏の水辺に美しく咲く杜若。本格的な夏の暑さの前の涼しげで凛とした姿に目を楽しませる人も多いのではないでしょうか。かく言う私もその一人ですが、そう感じるのは大人いや高齢者の証なのかもしれないと微妙な心境でもあります。
その杜若の精をシテにした能『杜若』を6月の喜多流自主公演(2022年6月26日)で勤めました。『杜若』にはちょうどよい季節の演能のはずでしたが、当日は猛暑、異例の早い梅雨明け宣言が出るほどで、初夏の情緒とは程遠い状況でした。それでもこの時期に、『杜若』を勤めることができたことを喜んでいます。
私の『杜若』初演は昭和62年6月27日の「妙花の会」で、ちょうど35年前でした。当時の動画を見ると、笛・一噌仙幸先生、小鼓・鵜澤速雄先生、太鼓・観世元信先生がいらっしゃり歴史を感じますが、皆様あちらに行かれてしまい、今は大鼓の佃良勝先生お一人になってしまいました。残念至極です。
2回目は初演の7年後、平成6年7月30日「青森薪能」(外ヶ浜)にて、そして3回目はそれからかなり時が経ち21年後、平成27年8月30日「唐松まほろば能」(秋田県大仙市)と、両方とも小書「働キ」で、曲(クセ)などを省略する特別演出で勤めました。
今回はそれから7年後で4回目。久しぶりに小書無し、省略無しで勤めました。
まずは『杜若』の簡単なあらすじをご紹介します。
諸国一見の僧(ワキ)が都から東国へ旅を重ねて三河(愛知県)に着くと、沢辺に杜若が美しく咲いています。見とれていると里女(シテ・杜若の精)が現れ、昔ここで在原業平が「かきつばた」の五文字を各句の頭に置いて、
「唐衣 着つつ馴れにし 妻しあれば 遥々来ぬる 旅をしぞ思ふ」
と歌に詠んだ故事を教え、僧を自分の庵に案内します。(物着)
女は冠(業平の五節舞のときの冠)と唐衣(二条后・高子の御衣)を着て僧の前に現れ、自分は杜若の精であり、業平は歌舞の菩薩の化現であるので、その詠歌の功徳により非情の草木も成仏したと教え、僧に舞を見せながら消えてゆきます。
ご覧になる方は、まず、脳裡に紫色のスクリーンを張り、尾形光琳の絵のような美しい杜若を思い描いて、あるときは花の精、あるときは・・・、花の精→業平→高子→歌舞の菩薩と、万華鏡を回すように見ていただく感覚ではないでしょうか。かといって、どの部分が業平で、高子でという、はっきりした区別はなく、それは見ていただく方のご想像にお任せして、その変化をご自由に楽しんでいただければ良い、と思います。
私自身は演じていて、『杜若』という能は、やはり花の精がメインだと今回勤めて感じました。
前半は「伊勢物語」の九段「東下り」の中でも、三河の八つ橋に着いたときのこと、杜若が美しく咲いている光景を見て、「かきつばた」の歌を詠じた話です。いろいろな恋の物語がある「伊勢物語」の中からこの箇所の杜若に着目し、能の題名も杜若、シテも杜若の精にするあたり、作者・世阿弥の才を感じさせられます。杜若の美しい情景に心を寄せながら、業平と高子の恋の香も少し混ぜ、全体に「伊勢物語」の雰囲気を立ち昇らせているのは世阿弥の若いときの感性という気がします。
後シテの姿は前回同様、初冠に「日陰の糸」を垂らし、杜若の花を挿頭しました。まさに花の精を象徴する形です。「日陰の糸」はおしゃれで華やかさが増しますが、喜多流では使用しません。他流では珍しいものではありませんので、喜多流にはなくとも「能にはある」という友枝昭世師のお言葉をお借りして、私も「能にはある!」を信条として拝借して付けて勤めました。
「伊勢物語」を本説にした能は、『井筒』、『雲林院』、『隅田川』などありますが、どれも「物語」があり単純ではありません。それに対して、『杜若』は深刻な恋の悩みやメッセージがあるわけではなく、絵画のようで、他のものとは趣が違います。
観世流の梅若桜雪(六郎)氏は「これはただ単に観て何かを感じていただく、それが杜若の精であってもいいし、業平の姿を重ねてもいい、理屈抜きで何かを感じとってもらう作品」と、書かれています。亡父・菊生も「あまり深刻にならず、綺麗に気品をもって、そしてところどころに女性の優しさを盛り込めるといい」と言っていまして、私もまさにその通りと思っています。
今回、お相手いただきましたワキ(旅僧)の福王和幸氏は、坦々と軽い感じで謡ってくださいまして、とても演りやすく感謝しています。このワキは特別に偉い僧でもなく、花好きで、美しい杜若を愛で、そこに現れた女性に軽く問答をする役どころです。若者が『杜若』を手がけると、どうしても慎重に演じる意識が強くなり鈍重で堅くなってしまいます。しかし、この軽みがこの能には必須で、軽くさらり演じるところに、この曲の本線があるように思います。
この能は世阿弥作(一説)とされていますが、舞台上で物着をする構成で、やや古い作品ではないでしょうか。世阿弥が複式夢幻能を完成させる前の段階の作品ではないかと感じます。
複式夢幻能では前場と後場の2部形式で、舞台上で装束を替えることを避けました。
『杜若』の場合は舞台上で長絹を着て初冠を付け、太刀をはき、と後見は懸命に短時間の着付けを目指しますが、ご覧になる方には、着替える時間が長いと感じられる方もおられるようです。そのストレスを解消するために、中入りしてゆっくりと装束替えをする複式が生まれたのではないでしょうか。
そして最後、「御法を得てこそ帰りけれ」で終曲しますが、演じ終えて、自分はどこに帰っていくのだろう?と、正直、心もとなくなりました。
僧の夢の中に帰るのでもなく、死者としてあちらの世界に帰るでもなく・・・。シテは杜若の花の精で、現実の女でもなく、死者の化身(霊)でもなくというのも、何か説得力がなく、整理されていないような、未完成な印象を受けます。
ここからいろいろ改善を試み、複式夢幻能という形が確立されていったのでは・・・、そんなことは深く考える必要はない、と先人にお叱りをうけそうですが、気になった自分がおかしくてたまりません。
今回は初回以来久しぶりにクセを舞いました。2回目、3回目は演能時間のこともあり、序からクセまでを省略し序の舞に工夫をこらす演出にして演出効果をあげましたが、序からクセには「伊勢物語」はどのようなものかを語る美しい詞章が連なり、クセの舞は長い二段曲(にだんぐせ)で型も多く、非常に遣り甲斐があり面白い見所でもあります。今回、ここを省略無しで正式に勤めたことで、作者の本来の思いを身体で感じ取ることが出来ました。
クセの舞は謡と型がきれいに合っていないと失格です。遅れたり早すぎては駄目で、演者が謡のスピードに合わせてしっかり型をはめていかなければなりません。この意味で、若い能楽師にとって『杜若』は課題曲にもなっているのでしょう。しかし、齢を重ねた今、単に謡と合わせるという基本的な運動能力にとどまらず、何かを加わえて世阿弥の意図を引き出す、それが役者の魂、役者の華、というエネルギーの発散によって表現されなくてはならない、と偉そうに勝手に思っています。


クセの舞の中、「秋風吹くと」のところで、亡父・菊生が好んだ替之型で勤めました。蛍が飛んでいるのを見廻しながら「秋風吹くと」で扇を左肩へうけ、遠くの空を見るような所作です。これは「伊勢物語」四十五段、男を思いながらも病んで亡くなった女を悼む歌から「飛ぶ蛍の 雲の上まで行くべくは 秋風吹くと・・・」と謡われるところです。父が好きだった『杜若』。父のかわいらしい所作を思い出しながら真似てみました。
今回の面は、最近愛用している「小面」を使いました。父は堰(せき)の銘が入った小面を愛用し、「違う小面を使うと、浮気しちゃ嫌よ、と言われそうで、いつもこれを使っています」と、宮中の美智子皇后様にもお話したのは有名ですが、私も同じようになってきたのかな? というわけで、特に銘は入っていないこの小面が気にいっています。
今年は3月に粟谷能の会にて粟谷菊生十七回忌追善能を催しましたが、演能のたびに、父の姿がまぶたに浮かび、今も私の中に生きているのだと感じさせられます。父の能を思う猛暑の夏となりました。
写真提供 シテ粟谷明生 撮影 新宮夕海
モノクロ写真 シテ粟谷菊生 撮影 あびこ喜久三
三役
ワキ 福王和幸
笛 栗林祐輔
小鼓 観世新九郎
大鼓 大倉慶乃助
太鼓 金春惣右衛門
(2022年7月 記)
『夕顔』「山の端之出」を勤めて投稿日:2022-05-25

『夕顔』「山の端之出」を勤めて
夕顔の不安と哀しさ優雅さ
国立能楽堂の5月の定例公演(2022年5月11日)で『夕顔』を勤めました。
源氏物語の『夕顔』の巻を本説として、夕顔という女性の霊を主人公にした曲は『夕顔』と『半蔀』の2曲があります。私、3月の粟谷能の会にて『半蔀』を、今回、5月に『夕顔』と、短い間にこれらの2曲を勤める事となりました。これまで同じような曲が続く事を避けてきましたが、今回このようになってしまったのは私の不徳のいたすところです。それでも勤め終えてみると、両曲を見比べるよい機会になり、面白い発見もありました。
さて、夕顔はどのような女性なのでしょうか。頭中将にみそめられ玉蔓を生みますが、中将の妻の右大臣家から追われ、五条あたりの荒家に隠れ住むことになります。そして光源氏との出会いとなり、誘いに乗って逢瀬を重ね、なにがしの院で物の怪に取り憑かれ儚く短い一生を終えます。
能『半蔀』(作者は内藤左衛門)は源氏と夕顔の出会いに焦点を当て、夕顔が源氏との恋を懐かしむ様子を、夕顔の花と重ねて美しく戯曲されています。
一方、『夕顔』(作者は世阿弥)は夕顔という女性の霊が、儚く亡くなる悲しい出来事を主軸に、源氏の誘いに自らをコントロールできなかった自身の過去を懺悔し、僧に弔いを願う展開です。光源氏との深い契りを忘れられず、僧の弔いで成仏するという、夕顔の心の揺れ動きを主題として構成されています。
今回の『夕顔』は国立能楽堂から小書「山の端之出」で出演を依頼されました。
この小書は、シテ(女・夕顔の霊)の「山の端の心も知らで行く月は 上の空にて影や絶えなん」の謡を見所の鑑賞者にはご覧になれない幕の内から謡います。
すると、ワキ(旅僧)が「不思議やなあの四阿(あずまや)より、女の歌を吟ずる声の聞こえ候、暫く休らひ歌の主をも見ばやと思ひ候」と、受ける形になり、通常の謡の順序が逆になります。
この「山の端の・・・」という歌は「山の端の心=光源氏の心」も知らないで「行く月=行く私」は上の空・・・と、夕顔が源氏に誘われ、なにがしの院に行くときの不安な気持ちを詠ったもので、夕顔の心情を表す大事な歌です。小書「山の端之出」はここを強調する演出です。
演者としては、幕の内から見所の隅々まで声を届かせる声量が必須です。もちろん能における女性の声として届かせなければいけません。鑑賞者に謡が聞こえなかったら演者失格です。終演後、よく聞こえました、とのご感想をいただき、ほっと安堵しております。
この小書、本来はワキの言葉の後に、囃子方の囃す一声にてシテの登場となりますが、今回はアシラヒ(囃子による明確なリズムを伴わない演奏)を打っていただき、姿を見せると「巫山(ぶさん)の雲は忽ちに・・・」と、鼻歌を口ずさむように謡いながら登場することにしました。以前はこの歩みながら謡う事は平気でしたが、馬齢を重ね肉体的にきつく感じるようになったのは少し残念でした。とは思いながらも、どうにか粗相なく出来た事を素直に喜んでおります。また今回は、下げ歌と上げ歌を省略しました。遠くから「山の端の・・・」の歌が響き、女の姿が見えて鼻歌が聞こえてくるとすぐに、旅僧と女の問答となる方が、作品が引き締まると思ったからです。今回、小鼓の観世新九郎氏、大鼓の亀井広忠氏に、この事をご理解いただき、私の「山の端之出」にご協力いただけたことに感謝しております。
『夕顔』の舞台は、源融の大臣の住んでいた河原の院です。今は廃墟となった「なにがしの院」を序やサシ、クセにて繰り広げます。
このクセは居グセです。動きがほとんどなく、見る側は地謡の詞章を聞き、動かないシテの心情を想像します。作者の世阿弥は見る側が源氏物語の夕顔の巻を知っていることを想定して作っています。私も夕顔の巻を知らない青年期は、内容がわからず、つまらない能だと敬遠していましたが、今はそれなりに面白く思うようになりました。しかし、こんな難しい課題を戯曲にした世阿弥の手腕にはただただ感心すると同時に、見る側の鑑賞力も期待されているのだと感じさせられます。
後場は読経に引かれ、シテ(夕顔の霊)がゆっくり現れ「あら有難の御経やな」と、僧に感謝します。この「あら有難の御経やな」の謡は下掛り(金春、金剛、喜多流)にしかなく、上掛り(観世、宝生流)は、いきなり「さなきだに女は五障の罪深きに」と謡い出します。上掛りにない「有難の御経やな」を敢えて謡う喜多流の演出は、旅僧への感謝の気持ちが、込められていて、これが本曲のテーマになっているのではないでしょうか。
ここは丁寧に思いを込めて謡いたいところです。
供養と読経を経て、「優婆塞が行ふ道をしるべにて 来ん世も深き契り絶えすな」と謡うと、夕顔は序ノ舞を舞います。序ノ舞は能という芸能でしかできない表現です。演者は決められた型の舞を寸法通りに舞うだけです。鑑賞者はその舞から自由に想像し、演者は想像力に委ねます。
例えば、昔を懐かしんでいる、いや過去を後悔して改心している、読経のお返しにきれいな舞を見せる感謝の舞、読経により成仏できた喜びの舞と、といろいろな見方があって良いと思います。そこが能の面白さ、能でしか味わえない世界ではないでしょうか。
このところ私の演能は序ノ舞が続いてしまいました。粟谷能の会の『半蔀』、喜多流自主公演の『西行桜』、広島蝋燭薪能で『羽衣』、そして今回の『夕顔』、私自身も少し食傷気味で、本三番目物ではありますが、定型の型ではなく、袖をかつぐ型など、やや派手な印象の替の型の序ノ舞にしました。
序ノ舞が終わると「お僧の今の弔いを受けて、数々嬉しや」と夕顔は「笑みの眉」を開き、変成男子となって解脱・成仏します。現代の女性からは、「男子に変わって成仏? なにそれ!」と、お叱りを受けそうですが、当時の仏教思想、法華経では、女性の救済は男性に変成してはじめてなされるという考え方なのです。ご不満に思われる方はたくさんおられると思いますが、ここは能という演劇として受け止めて、夕顔の哀しさ優雅さを鑑賞していただきたいところです。
そして夜が明けぬ間に、夕顔の霊は姿を消して終曲します。
通常は常座で留拍子を踏んで終曲となりますが、今回は、敢えて視覚的にも分かりやすくご覧いただきたく、謡の中で入幕としました。
演じるにあたり、面は本来「小面(こおもて)」、若い女性の面が決まりですが、私の夕顔像には似合わないと思い、やや大人びたきれいな女性の「宝増(たからぞう)」にしました。
装束について、『半蔀』も『夕顔』も伝書には白色や紫色の長絹に緋大口袴と記載されています。今回、3月の『半蔀』の白色長絹に緋色大口袴と変えてみたく、少し冒険でしたが浅黄の大口袴にしました。ご覧になられた方はどのように思われたでしょうか。
短い期間に2曲を勤めることで装束を替える発想が起こった事が面白く、私自身、装束選びを楽しめたのは貴重な経験でした。
今年の私の演能は上半期に集中してしまい、あとは6月喜多流自主公演『杜若』、12月喜多流自主公演『大江山』を残すところとなりました。
コロナ感染症は、いまだに終息したとは言えない状況です。そのなかで、私自身は感染しないように気をつけてきましたが、もし感染したら・・・という不安が常にありました。
コロナ対策により、感染していなくても濃厚接触者となってしまうと何日かの自宅待機が義務づけられ、舞台に立てない事も起きるかもしれません。これから代演者の手当てが出来ず、興行が中止になることもあり得ます。PCR検査で陽性になり、症状が出て苦しいならば仕方がありませんが、何の症状もなく、ただ濃厚接触者であるというだけで舞台に立てないという状況はどうでしょうか。
医療従事者や保育士などでは待機日数の縮小も考慮されました。
演劇の世界が、これからコロナ対策をどのように考え対処するか、少し角度を変えて考える時期が来ているのではないでしょうか。 (2022年5月 記)
写真提供:国立能楽堂
『西行桜』を勤めて ー西行に会いたかった桜の精ー投稿日:2022-05-06

『西行桜』を勤めて
西行に会いたかった桜の精
厳島神社の桃花祭・神能での奉納(4月16日~18日)を終えた翌日、京都に立ち寄って、勝持寺など西山方面の寺々を巡ってきました。
勝持寺は西行法師が出家し庵を結んだ場所です。境内には100本もの桜の木が植えられていて「花の寺」として親しまれています。西行が植えた枝垂れ桜は「西行桜」と呼ばれ、能『西行桜』の舞台となっています。
鐘楼堂の隣にある西行桜は花の盛りは過ぎていましたが、他の桜が少し残って私を迎えてくれました。5日後の喜多流自主公演(2022年4月24日)で『西行桜』を勤めるにあたって、演能前、「西行桜」に能『西行桜』の成功祈願をしてきました。
能『西行桜』の物語は都の西山にある、西行の庵(現在の勝持寺)が舞台です。世俗の騒がしい花見客をあまり快く思っていなかった西行(ワキ)は花見禁止令を出しますが、それを知らない都の花見客達(ワキツレ)は、今日も大勢で訪れ、当然のように案内を乞います。西行は無下に断れず、花見客達を庭に招き入れますが、静かな環境を破られた思いを、
「花見にと 群れつつ人の来るのみぞ あたら桜の科(とが)にはありける」
(花見を楽しもうと人が群れ集まるのは桜の罪なのだ)
と、歌に詠み、そして花見客達と一緒に桜の木陰で一夜を明かすこととなります。
本来、一緒に眠るのですから、花見客達は舞台に留まらなければいけないのですが、能はその後、老人(シテ・老桜の精)と西行(ワキ)の二人だけの世界を繰り広げるために、敢えて花見客達を切戸口から退場させます。そして西行の夢の中に老人が現れ、舞台は二人に焦点が絞られ展開していきます。
老人は西行に
「いや浮世と見るも山と見るも、ただその人の心にあり、非情無心の草木の花に浮世の科はあらじ」(いや違いますよ、すべての現象はその人の心次第、草木には心が無いのだから、花に罪は無いでしょう)
と、西行の詠歌に異議を唱えます。西行はすぐに納得し、老人の正体を尋ねると老人は老木の桜の精と明かし、会えたことを喜び、都の花の名所の数々を紹介します。そして名残を惜しみ舞を舞い、夜明けと共に姿を消し、西行の夢はそこで覚めて、終曲します。
能『西行桜』は最初に、桜の木(塚)が舞台中央に据えられ、西行と従者(アイ)が登場し、アイの花見禁止令の触れから始まりますが、シテはその作り物の中で待機しています。作り物の引き廻しが下りて姿を現すまで、25分ほど、舞台進行の3分の1強が西行と花見客とのやりとりに費やされ、その間、シテは狭い作り物の中でじっと待機を強いられます。装束も面もきちんとつけた状態なので、じっと動かないでいるのは思いのほか難儀です。実際、脚が硬直して、作り物から出てよろけてしまうことも過去にはあったようです。
父・菊生は『西行桜』を勤めておりません。長い作り物での待機や、観世寿夫氏の最後の舞台が『西行桜』だったことが気になり避けて、生涯『西行桜』を勤めることはありませんでした。一度は甥の粟谷能夫に勧められて平成10年「第63回粟谷能の会」で勤める決心をしましたが、気弱になり『羽衣』舞込に変更してしまいました。そのとき、能夫の「あたら『西行桜』の科にはありける」と放った言葉は面白く、今でも懐かしく思い出されます。
さて、『西行桜』を勤めるにあたって、この老人、爺さんはどんな爺さんなのだろうか、どのような気持ちで勤めたらいいのだろうか、とずっと考えてきました。
老人は西行の「桜の科」という歌に対して文句をつけに現れますが、実はそれを口実にして、西行に会いたかったのではないでしょうか?
西行も桜の精の抗議に対して「これは理(ことわり)」とすぐに非を認め、よって論争にはならず、老木の精も「有難や上人の御値遇に引かれて」と、会えた喜びを素直に吐露しています。
春を満喫し、桜の名所を教え、西行と過ごす時間を楽しみますが、時の流れは速く、すぐに別れが訪れると思うと名残惜しくなるのです。シテ謡の「あら名残惜しの夜遊やな、惜しむべし、惜しむべし、得難きは時、逢ひ難きは友なるべし・・・」は正に老桜の精の心情ですが、この言葉は、そのまま私自身にも、また観客の皆様にも身に沁みる言葉ではないでしょうか。西行と過ごすその時だけでなく、人は人生そのものを惜しむのである、と作者・世阿弥が発信しています。それが自然と素直に私の身体に浸透するようになったのは、人生の残り時間を意識するようになってきたからでしょうか、時間の大切さを痛感します。
老木の桜の精が舞う序ノ舞、正直私はこの舞がなにを伝えようとして設定されたのかは、まだ判りません。西行に夜遊の舞を見せているのか、西行に会えた喜びを身体で表現したかったのか・・・。ただ演者としては、老木の精らしく舞うことだけを考えていましたが、その真意はわからないままです。
きっとご覧になる方の自由な想像でよいのでしょう。それが能にしかない表現方法なのだ、と納得しています。
今回、特に気なったことがありました。それは、後夜の鐘の音が響き渡り、春の夜が明け始めるときに、シテが「待て暫し夜はまだ深きぞ」と、ワキに向かって行う巻サシヒラキの型(動き)です。喜多流のこの型は、まるで桜の精が西行に向かって「待て暫し」と言っているように見えてしまいます。しかし、それは違います。老桜の精が「夜よ、まだ明けないでくれ! もう少し待ってくれ! もう少し時間をくれ!」と、昇ろうとする陽に、時の流れを止めるように叫んでいる、そのように解釈したいのです。よって今回は従来の型ではなく、東の空(幕方向)に向かって謡う型に変えました。
これについては、いろいろ議論があり、「待て暫し」は西行の言葉と解釈される方もいらっしゃったようですが、朋友・森常好氏が「あれはワキの台詞ではない、老桜の精の言葉」と明言してくれたことが力となり、友枝昭世師とも相談して型を変えて演じました。
今後、型を変えるか、従来通りで進むかは演者の自由です。但し、ご覧になる方が誤解をなさるような表現は改善すべきだと、私は思いますが、どうでしょうか。
楽屋内の話ですが、桜の作り物は以前は塚の榊の中に桜の花をいくつか載せるだけでした。ある時、観世寿夫氏の「西行が植えた桜は枝垂れ桜である」との言葉から、枝垂れ桜を模して枝先を垂らし桜の花をつけるようになりました。今、喜多流でも枝垂れ桜をさすようになりましたが、これも銕仙会に傾倒していた能夫が最初に喜多流に導入したと記憶しています。良いものは真似る、先ほどの「待て暫し」の解釈同様、それが演者の正しい舵取りだと思います。今回はもう少し桜を多く飾って華やかさを増やしたかった、と少し後悔しています。
面や装束は原則として伝書に記載された物を着用しますが、柄や色などは演者の好みの選択が許されます。
桜の精というと、若く美しい女性を想像したくなりますが、皮肉なことに、『西行桜』の精は男の老人です。西行と対峙させるのは年の功を経た男性がよいと世阿弥は考えたのでしょう。桜の花はパッと咲いて散ってしまう、その華やかさ、美しさに目と心を奪われがちですが、実は綺麗な花を支えているのは幹です。今回はその幹を演じる、気持ちで勤めました。
その幹の色、桜をよく見ると黒く見えてきます。
観世寿夫氏が黒っぽい狩衣を着られたと聞いていますが、まさに幹をイメージされていたのではないでしょうか。銕仙会では寿夫氏の教えを守り、この狩衣を黒っぽいものにしているようで、私も黒色で、と思いましたが、似合う黒色の狩衣がないので、我が家にある濃い茶色の狩衣を着ました。黒ではありませんが、桜の幹になるという私の心は変わりません。
また老人の桜の精の烏帽子は、喜多流では色によって持つ中啓(扇)が変わります。
黒色の黒風折烏帽子を被ると紅無の中啓となり、金色の金風折烏帽子では紅入の中啓になり、これもどちらを選ぶかは演者の自由です。黒色ならば枯れた墨絵の世界で老木の桜の精、金色ならば少し華やかなイメージになります。今回は華やかさを前面に出したく金風折烏帽子にしました。
面は通常通り粟谷家所蔵の「石王尉(いしおうじょう)」にしましたが、私の思う老桜の精の雰囲気と似合わなかったように思え、少し心残りです。西行の歌に文句をつけるひねくれた老人には石王尉の顔は似合いますが、西行に会えて喜びに満ちた雰囲気には、下向き加減な人相はどうも似合いません。観世流ではより柔和な表情の「皺尉(しわじょう)」を使うようですが、こちらの方が私の描く老人に近いように思えます。
能役者にとって、春の『西行桜』、秋の『遊行柳』の老木の精はいずれ演らねばならない目標となる演目です。しかもこの二曲はどんなに達者な演者でも3~40代では手に負えませんし、若者が演じては似合いません。この曲は若者を寄せ付けない不思議な力を持つ作品です。
確かに私も、馬齢を重ねてようやく、老い木の気持ちが分かるようになり、「ああ、『西行桜』を勤める歳になったのだな」と、つくづく自身の老いを感じています。
今回66歳の初演は少し遅いのかもしれませんが、この年になって判る老いの世界観を味方につけて勤められた事は喜びで、自分には適齢期であったと思っています。
一曲一曲の演能の大切さ、惜しむべしは時です。
後夜の鐘の音が聞こえるまでは舞い続けなければ・・・。
己の人生で、いつどんな鐘が聞こえて来るのか、春宵一刻値千金、春の夜の夢のなかに、しばしまどろみました。
能『西行桜』写真提供 新宮夕海
小鼓:大倉源次郎 大鼓:亀井広忠
勝持寺 石王尉 撮影 粟谷明生
(2022年4月 記)
『邯鄲』小書「傘之出」を勤めて投稿日:2022-04-23

『邯鄲』小書「傘之出」を勤めて
大槻能楽堂自主公演能「能の描く男たち」
大槻能楽堂自主公演では毎年様々なテーマで企画し、斬新な催しを行っています。今年最初の3回シリーズは「能の魅力を探るシリーズ・能の描く男たち」、その第3回『邯鄲』(2022年3月26日)でお招きをいただき、シテを勤めました。ちなみに第1回(1月)は『頼政』で源氏の決起を促し果てた源頼政を、第2回(2月)は『雲林院』で二条の后を愛した在原業平を、そして私の『邯鄲』で人生に迷う盧生青年をと、能の描く男たちをご覧いただく企画でした。
この大槻自主公演を主催する観世流の大槻文蔵先生とは、父・菊生が流儀を超えて親しくさせていただいていて、亡くなる2年前までは毎年、この自主公演にお招きいただき、父は喜多流を代表してシテを勤めておりました。私も地謡で謡うことが多く、大いに勉強させていただきました。私自身は父が亡くなった2年後の平成20年(2008年)に『采女』を勤めさせていただき、今回は2回目です。実は2年前に『蝉丸』で観世銕之丞氏の蝉丸と私の逆髪で異流共演の企画がありましたが、コロナ感染症により中止になり残念でした。
大槻文蔵先生が他流の能楽師を招いて流儀を超え意欲的に取り組まれている会、この貴重な会からの出演依頼は光栄であり名誉なことで、大変嬉しく、私なりに精一杯勤めさせていただきました。
『邯鄲』は「邯鄲の夢」の伝説がよく知られ、能もとても分かりやすい三段構成です。人生に迷う盧生青年が高僧の教えを乞いに向かう第一段、宿に着いて、悟りが得られるという枕を紹介され、眠りに落ちると、王位について豪華絢爛な宮廷生活に浸る第二段、やがて夢が覚めて悟りは・・・という第三段、まさに、迷い、夢、悟りという序破急が利いた能になっています。迷いは沈鬱なムード、夢は豪華、最後は愁嘆と、これもくっきり謡い舞い分けるというのが、これまでの常識でした。確かにそれは大事なのですが、今回、最初の「迷い」のところが気になりました。
私の『邯鄲』は今回で四回目ですが、過去の三回は、悩み深く真摯ながらも、暗く陰湿な青年像を思い描いて演じてきました。しかし、盧生青年は決して心病んでいるのではなく、どのように生きたいかを非常に前向きに考えている。仏の道にも入らず呆然と暮らしているようでも、高僧がいるという羊飛山に行こうと一歩踏み出したではないか。であるならば今回は、病的で暗い盧生ではなく、羊飛山に向かう意志の強さ、少し拘りのある頑固な求道者としての盧生を演じてみたいと思いました。私も馬齢を重ね、人生の様々な経験をしていくうちに、そんな若者の迷いの中にも希望や輝きがあるように感じられてきたのです。そうすると自然、次第の強吟「浮世の旅に迷ひ来て」の謡も、従来の低く陰湿に謡うのと変わってきます。シテの登場する次第のノリも重々しくならないようにお囃子方に私の思いをお伝えしてご協力いただきました。羊飛山への道行も、求道者の心が決まって希望に満ちているという面もあるのではないでしょうか。父・菊生もそれほど陰鬱にならず、強く求道者のようなイメージで謡っていたように思い出されます。
今回は「傘之出」という小書で勤めました。
(「傘之出」についてくわしくは、平成20年の演能レポート「小書・傘之出の演出と展開」をご覧ください。さらに、平成22年の演能レポートで小書「働き」と「傘之出」を比べています。そちらも見ていただければ幸いです。)
「傘之出」という小書は、初同(最初の地謡)の「一村雨の雨宿り」から発想されたようで、シテの盧生は傘をさして登場します。傘をささない場合よりは、足取りが自然に重くなるので、謡や囃子をそう重くしなくとも、迷う盧生の姿を傘がより強く演出してくれます。

「傘之出」で常と最も違うところは最後の場面です。常は「・・・悟り得て。望み叶へて帰りけり」の「帰りけ~り~」を上音で陽の心持ちで謡い終曲します。めでたしめでたし、盧生はどうやら悟ったらしい、とご覧になる方の気持ちも明るく終わります。それに対して「傘之出」になると、「帰りけ~り~」を下音に下げ、悟ったのかどうか、不安を感じさ、さらにそれで終曲とならず続きがあります。アイ(宿の女主人)が「さあらばお傘を参らせ候べし」と傘を差し出し、シテが「近頃祝着申して候」と返すと、アイが「また、重ねて御参り候へや」と声をかけて止める形となります。お客様はそこで盧生は悟ったのか、まだ悟っていないからもう一度来なければいけないのか、などと様々に想像できる終わり方です。
こう考えると、「傘之出」の演出は陰陽でいえば、どちらかというと陰の世界、最初の盧生の迷いや道行をあまり明るくしてはちぐはぐになるかもしれず、その辺の兼ね合いが難しく課題が残るところです。ご覧になった方はどのように感じられたでしょうか。
今回は、次第や初同を従来の重々しく謡うのではなく、ややサラリ、と軽く明るく謡うことによって、従来と違う舞台となったと思います。演者がどのような意図で勤めているのかを見ていただきたい。従来の固定観念に縛られず、頑迷固陋にならず、なのです。実際、シテ方五流あればそれぞれ違う演出があり、同じ流儀でも一人ひとり違います。同じ人間でも年齢によって変わっていきます。66歳になったジジイ(私)も、日々変化しています。その新鮮さを大事にしたいです。能は古典芸能とはいえ、伝統を重んじながらも守りに入るのではなく、柔軟な発想をもち、変化しながら伝えていくもの、と思うのです。そうでなければ時代に取り残されてしまいます。
能『邯鄲』で盧生が起こされる印象的な場面が2か所あります。
一つは邯鄲の枕で眠っている夢の中で、勅使(ワキ)が扇でパンパ~ンと一畳台を叩いて起こし、盧生が王位を譲られたことを告げる場面。以前、宝生閑先生の叩き方のタイミングや美しい所作が素晴らしかったことを思い出します。今回はワキが福王流だったため、2回、パン、パ~ンと叩かず、1回は音なしで2回目に大きく音を立て叩く型でした。宝生流に馴れていたせいか、2回で合わせるタイミングで身体が覚えてしまったようで、今回の起き方は新鮮に感じられました。
もう一つは、宿の女主人が廬生を起こす場面です。廬生が一畳台に飛び込み横になっているところに女主人はすっと近づき、中啓で叩き起こします。その後すぐに後ずさりして「あら久しと御休み候、粟の飯の出来て候。とうとうお昼なれ候へや」と廬生に声をかけます。この起こした後の処理ですが、早めに声をかけるのがお狂言の教えのようですが、私は逆にゆっくり後ずさりして、ゆったりと声をかける方が、盧生が壮大な夢を見ていた余韻が伝わり演劇的な効果は上がるのではないか、と思っています。アイの分担に口出しするのはどうかとも思いましたが、ひとつの考え方があることを残したく、敢えてここに書かせていただきました。
『邯鄲』「傘之出」は特にシテとアイとの掛合が多い能で、互いに呼吸を合わせることが大事です。たとえば傘を手渡すところや、最後の「また、重ねて御参り候へ」と声をかけるタイミングなどは、今回、申し合わせもなく、簡単な打ち合わせ程度だったにも拘わらず、私の意図をよく理解してお相手くださいました小笠原由祠氏に感謝しています。
今回の大槻能楽堂自主公演は観世流ではなく、他流である喜多流が演じる公演でした。シテの私はもちろん、地謡陣も光栄であると同時に緊張して臨んだことは間違いありません。大槻文蔵先生のお考えは他流の能を見て学ぶ、我々喜多流も見習うべきです。見られる緊張がよい刺激になり地謡陣もエネルギッシュに懸命に謡ってくれました。お客様から「本気度がガンガン伝わってきてよかったです」という感想をいただきました。いつも本気でやっているつもりですが、やはり他流の目が光っている時は場では、エネルギーの入り方が違ってくるのでしょうか。
最初に文蔵先生から『邯鄲』のご依頼があった時、「今、喜多流ではちょうどよい年ごろの子方が居ませんが・・・」と申し上げましたところ、先生が「子方はこちらに居ますから、それでよければやっていただけませんか」と有難いお言葉。文蔵先生の弟子の齊藤信輔氏のお嬢さんで齊藤葵さんが子方(舞人)を勤めてくださいました。これは一つの異流共演です。葵さんには立派に勤めていただき感謝しています。
私も『邯鄲』子方を9回勤め、その頃のことが懐かしく思い出されます。シテは平成元年初演、平成20年に小書「傘之出」で、平成22年に小書「働」で勤め、今回が4回目。他流試合のような演能ながら、
多くの方々のご協力のもと勤めさせていただき、良い思い出になりました。
(2022年4月 記)
写真提供 邯鄲 撮影 森口ミツル
モノクロ写真 邯鄲 子方 粟谷明生 シテ 友枝昭世
『土蜘蛛』を勤めて投稿日:2022-03-28

『土蜘蛛』を勤めて
豪快に蜘蛛の糸を撒く
第104回 粟谷菊生十七回忌追善 粟谷能の会(2022年3月6日、於:国立能楽堂)で、『半蔀』と『土蜘蛛』の2曲を勤めました。粟谷能の会のことや『半蔀』についてはすでに書きましたので、ここでは『土蜘蛛』についてレポートします。
能『土蜘蛛』は鬼畜・妖怪退治の風流能(見た目が派手なショー的な能)です。作者は不明ですが、劇的、ショー的な能が流行する時代の作品で、そう古いものではないようです。
病に伏している源頼光(シテツレ)のところに侍女・胡蝶(シテツレ)が見舞いに行くと、いつの間にか僧(前シテ・土蜘蛛の精魂が僧に化けた者)が現れます。僧は頼光と言葉を交わしながら近づくと、たちまち蜘蛛の本性を現して千筋の糸を投げかけますが、頼光に斬られ退散します。
警護の独武者(ワキ)が事情を聞きつけて駆けつけると、夥しく血が流れているので、血を辿って蜘蛛の退治に出かけます。独武者が郎党(ワキツレ)を連れて葛城山の古塚に着くと、中から土蜘蛛の精(後シテ)が姿を見せ、蜘蛛の糸を繰り出しますが、遂に独武者に斬り伏せられてしまいます。
この『土蜘蛛』は演能時間も50分ほどと、とても分かりやすい能で、実際に蜘蛛の糸を次々に撒く演出は無条件に面白く、人気曲となっています。
勤めるにあたり、まずはこの蜘蛛の糸(巣)の準備が肝要です。5間5双(ごけんごそう)の大きいサイズと、3間3双の小さいものがあります。通常喜多流では9個ほどの投巣ですが、近年投巣が多くなる傾向で、今回は15個ほど用意しました。余談ですが、蜘蛛の糸はなかなか高価なので土蜘蛛の演能が経済的に厳しいことをお弟子様に話しました。すると、お弟子様がお仲間を集めて「蜘蛛の糸の会」を立ち上げ、資金集めをして下さり多く撒くことが出来ました。ここに、ご協力の皆様に感謝御礼を申し上げます。
この蜘蛛の糸を投げかける演出ですが、健忘斎の伝書には前シテに投巣の記載はなく、後シテのみ投巣の記載があります。高林呻二氏は「前シテで投げないのは初心の型で、高林家に伝わっている伝書では、朱書きで巣を投げる、と書き足しています。江戸時代には前シテも投巣していたようです。祖父のお弟子様が幅一センチほどの糸を5~6本まとめて投げていたようですが、今のような形のものではありません。現在の蜘蛛の巣の演出は金剛流の小書・千筋之伝に限られていた、と聞いています」と、教えてくださいました。
いつの時代も能を面白く観ていただくための工夫がなされていて、今日まで能という芸能が継承されている事を、改めて感じました。
『土蜘蛛』の後シテは通常、赤頭に赤色系の半切袴を着用しますが、『半蔀』が緋色の大口袴を穿くため重なるので、今回は敢えて紅無の装束にして黒頭としました。面も粟谷家所蔵の赤色の強い「顰(しかみ)」ではなく、石塚シゲミ氏の打たれた赤みの弱い面を拝借いたしました。
『土蜘蛛』のような鬼退治物は、鬼を退治してめでたしめでたしと終わりますが、さて、悪いのはどちらでしょうか。昔、蜘蛛族という先住民がいて平和に暮らしていたところに、侵略者がやってきて、彼らを奥地に追い出してしまったとしたら・・・。
戯曲はいつも征服者側が作っています。先住民を異界の者、鬼として悪者に仕立て、鬼退治をして、為政者側を勝者にします。今行われている戦争と同じだと痛感します。
能には、「それでいいの?」という問いかけ、先住民の恨みや哀しみのメッセージが隠されているはずです。これは能『大江山』、『紅葉狩』などの鬼退治物に共通しています。ご覧になる方はそこまでお考えにならなくてもよいかもしれませんが、演じる私はどうしても意識してしまうのです。
ようやく「粟谷能の会」を終えて、ほっとしています。今回、一人でいろいろな手配をし、宣伝もして、何とか多くの方にご来場いただきたいと、心を砕いて参りました。当日は二番を勤めるのは・・・と、不安もあり、なかなか大変でしたが、それでも多くの方々の力添えを得て、よい形で終えることができ、関係各位、観てくださった方々には感謝してもしきれない気持ちで一杯です。
来年も国立能楽堂で「粟谷能の会」を催すべく、会場を確保し、着々と準備を進めているところです。皆様の変わらぬご支援を心よりお願い申し上げます。
写真提供 新宮夕海
(出演者)
頼光 佐々木多門 太刀持 佐藤寛泰
独武者 森 常好
笛 杉 信太朗 小鼓 鵜澤洋太郎 大鼓 亀井洋佑 太鼓 金春惣右衛門
(2022年3月 記)
『半蔀』を勤めて投稿日:2022-03-28

『半蔀』を勤めて
源氏と夕顔の出会いが焦点
第104回・粟谷能の会を2年ぶりに、平成4年(2022年)3月6日、国立能楽堂において、無事開催することが出来ました。昨年、粟谷新太郎二十三回忌追善として企画していましたが、コロナ感染症拡大により断念し、同じ番組編成で、今年、粟谷菊生十七回忌追善として開催することになったものです。
当初、粟谷能夫が新太郎(能夫の父)の追善能で『檜垣』という秘曲に挑戦し、私が『檜垣』を謡った後に『土蜘蛛』を勤める予定でしたが、能夫の健康が優れないため曲目を『半蔀』に変更していました。しかし残念ながら、昨年未に粟谷能の会への出演が難しいと能夫本人が辞退したため、私が『半蔀』と『土蜘蛛』の2曲を勤めることとなりました。
今年に入り、コロナ感染症はオミクロン株に替り、2月には東京都の感染者数が2万人を超え、これまでにない非常事態となって、粟谷能の会の開催も危ぶまれました。そんななかでしたが、感染対策をしっかりたて、多くの方々にご協力をいただき、無事開催にこぎつけたこと、そして、多くの方々が能楽堂に駆けつけてくださり、盛況のうちに終わることが出来たことが、何より嬉しく、皆様に感謝申し上げる次第です。その後、粟谷能の会鑑賞者の感染の報告もなく、安堵しているところです。
ではまずは、『半蔀』についてレポートすることにいたします。
『半蔀』は喜多流では「はしとみ」と読み、「はじとみ」と濁りません。中学生のとき、漢字の読み方テストで「はしとみ」と書いて、×点をもらったことを思い出します。
私の『半蔀』の初演は昭和59年の青年喜多会、その後、平成16年に横浜能楽堂で小書「立花供養」で勤め、平成30年に厳島神社のご神能、そして今回で4回目になります。
シテは「源氏物語」に出てくる夕顔の女、清楚で、どこか哀愁を含んでいる可愛い女性です。
能『半蔀』はその夕顔が光源氏と出会ったときに焦点を当て、歌を取り交わし、契りを結んだ嬉しくも儚い恋の思い出がテーマとなっています。
紫野に住む僧(ワキ)が立花供養をしていると、美しい女(前シテ)が現れて夕顔の花を手向け、名も名乗らずに消え去ります。光源氏と夕顔の物語を聞いた僧が五条あたりで読経して待っていると、半蔀を押し開き、夕顔の霊(後シテ)が現れます。光源氏と歌を交わしたときのことを語り、舞を舞い、夜が明けぬ前にと半蔀の内に入ってしまいますが、それは僧の夢だったと終わります。
このように、最も三番目物らしい優雅な美しい能です。演じる側としては、前場で僧と少し会話をし、すぐに中入り、後場も序ノ舞を美しく舞うことで、それほど負荷がかかるわけでもなく難しいという感じはしません。観る側もその優美さに浸って下さればいいのですが、深く味わおうとすれば、「源氏物語」の夕顔の巻のお話が頭に入っていることが必須条件になります。
では、夕顔の巻で、夕顔と源氏の出会いはどのようなものだったのでしょうか。
源氏があるとき、源氏の乳母のお見舞いに行くと、その近くに何やら清げな住まいがあり、そこに美しい白い花、夕顔が咲いています。源氏が「ひと房折りて参れ」と命じ、従者の惟光が折りに行くと、女童が香を焚きしめた白い扇を差し出して、これに置いて持って行って、というのです。そこには「もしかして源氏の君?」と問うような歌が書かれていました。
源氏はそれを見て、気の利いた詠いぶりに興味を惹かれ、
「寄りてこそ それかとも見めたそがれに ほのぼの見つる花の夕顔」
(寄ってみなければわかりませんよ。黄昏時にほのぼのみた夕顔の花なのだから)
と返歌します。それが出会いでした。その後、逢瀬を重ねますが、あるとき、夕顔は物の怪に取り憑かれ、儚く亡くなってしまいます。
能『半蔀』は亡くなる悲しい出来事には触れず、この出会いのころを、後場のクセから序ノ舞、キリまで描いていきます。シテは時には夕顔の花の精、またある時は夕顔、そして光源氏や従者の惟光にも変わり、一人四役を、姿や格好はそのままに、謡い舞って演じ分けます。ちょうど噺家が長屋の熊さんやご隠居さん、おかみさんを演じ分けるのと同じです。ご覧になる方は、「今はだれ?」と想像して鑑賞していただけるとよいのです。
ただ能は、夕顔の女本人と夕顔の花の精とが二重写しに戯曲されているため、花の精か現身か少しわかりにくいかもしれませんが、こういうところが能らしい表現なのです。
序ノ舞は在りし日の思い出にひたり、苦の縛りがとれて、楽しく舞いますが、それはほんのいっときのこと。シテの「折りてこそ。それかとも見め。黄昏に」の謡(源氏の歌の「寄りてこそ」がここでは「折りてこそ」に)を受けて、地謡の大ノリ「ほのぼの見えし。花の夕顔、花の夕顔、花の夕顔」と「花の夕顔」を3回唱えて、あの出会いの喜びを謳い上げたかと思うと、すぐに「東雲の朝間」になり、僧の夢の話となって、夕顔は消えてしまします。
あっという間の出来事、なんと儚い、人生の儚さも感じてしまいます。
話は前後しますが、能『半蔀』は中入り後、半蔀の作り物が舞台に据えられます。同じ夕顔を題材にした能に、世阿弥作の『夕顔』がありますが、この能にはそのような作り物がありません。
半蔀の作り物は、夕顔の花や瓢箪の蔓がからめられた板戸の上半分が下から上に押し開かれるもので、まさに能『半蔀』を象徴するようなものです。後場で半蔀が開かれ、夕顔が出てくる場面は「御姿 見るに涙も止どまらず」と地謡が謡い最も美しく印象的なところです。
『半蔀』の作者は内藤左衛門という武士で、世阿弥よりずっと後の人です。幽玄の能を完成した世阿弥の後に観世小次郎信光など、能を劇的、ショー的に面白くしようとする流れがありますが、内藤左衛門もその流れにあって、源氏と夕顔の出会いに焦点を当てて分かりやすく、しかも詩的に美しくつくり、作り物も効果的に配しています。
その作り物を通常は本舞台(常座)に出しますが、舞台が狭くなり少し窮屈な感じがして舞いづらくなります。そこで今回は橋掛りの一の松のあたりに置くことにしました。国立能楽堂の橋掛りは長く横幅もあるので好都合です。こうすることで、本舞台が広く使え、序ノ舞をゆったりと大きく舞うことができます。私はこのようにすることが多く、4回の『半蔀』で通常通り常座に置いたのは、青年喜多会のときの初演だけです。
また、前場の出について、通常はワキが舞台中央にて読経を終え脇座についてから、囃子方のアシラヒとなり、シテはゆっくり出ますが、今回はワキが「敬って申す」と花の供養を始めるところで幕から出て、三の松あたりに止まり、静かにお経を聞く姿をご覧いただけるように演出を替えました。お経を唱え供養してくれていることを喜んで出てきた風情です。
この前場のアシライ出や後場の作り物の設置、しかもシテが作り物の中に入って出る演出などで時間短縮となり、通常は1時間30分かかるところが1時間15分ほどで終曲となりました。これからの時代、このくらいすっきりした演出も良いのではないかと思っています。
『半蔀』はシンプルな美しい能です。シンプルであるからこそ、演者は美しい謡声ときれいな舞の動きを披露するに尽きるのではないでしょうか。能にフィギュアスケートの採点のような技術点・芸術点があるとしたら、『半蔀』は技術点の占める割合が相当高いと思います。振り返ると昔の謡い方は粗削りで、ワキとの会話の感情表現もずさんだったな、と反省しています。これらを直してハイレベルな謡にして、また加齢と共に丸くなる背中や、足腰の衰えなど、これら老いの現象に抵抗して美しく舞い、あまり巧まず、坦々と勤めることで、『半蔀』という能は三番目物らしい優美な能になるのではないでしょうか。
写真提供 吉越 研 新宮夕海
出演者 小鼓 飯田清一 大鼓 亀井広忠
(2022年3月 記)
『望月』を勤めて投稿日:2022-02-04

『望月』を勤めて
生の舞台を催す意義
コロナ感染症のオミクロン株が猛威を振るって、なかなか先が見通せないこの頃です。
令和2年(2020年)以来、コロナ感染症により文化芸術活動が大いに制限されたことから、国が対策として「文化庁アートキャラバン事業」(令和2年度)を企画し、活動を支援しています。能もその事業の対象となり、「日本全国能楽キャラバン!」と称して、全国各地で多くの公演を行ってきました。その一つ、広島での公演(令和4年1月18日、於;JMSアステールプラザ)で『望月』を勤めました。
(実は、昨年10月に勤めた『竹生島』もこの事業の一つとして実施されたものです。)
能『望月』は能『放下僧』同様、仇討ち物語の現在物ですが、獅子舞があることから喜多流では特に重い習いの曲目となっています。
シテの小沢友房が主君・安田友春の妻(ツレ)と子の花若(子方)とで、主君の敵の望月秋長(ワキ)を討つわかりやすい物語で、見どころ満載の能です。
物語は、シテの小沢が主君が討たれたときにその場に居合わさず、思い空しく守山の宿屋の亭主となっている独白から始まります。そこへ、主君の妻と子が宿を求めてやって来て、涙の対面となります。そしてあろうことか、同じ宿に主君の敵の望月までやって来るのです。友房は奮い立ち、友春の妻を盲御前(めくらごぜ)に仕立てて、望月に酒をふるまい酔いに乗じて仇討ちを遂げようとしますが、この計略を練るところから実行までの舞台進行がまさに緊迫した場面の連続となります。
前場はそれぞれの役者の謡の技芸で緊張感を高め、後場は逆に子方の鞨鼓の舞とシテの獅子の舞を見せながら、視覚で楽しませる構成です。喜多流は実際に望月をとり押さえ問答をするスリリングな場面や、最後は笠を望月に見立てて短刀を抜いて斬り刺す型もあり、かなりリアルな演出となっています。
このような曲では、シテは芝居心を持ちながらも能の結界を超えずに演じるのが心得です。この難しい心得は稽古はもちろんですが、年齢を重ね、場を積むことで少しずつ味わいが出せるようになっていくもののようです。
また、『望月』には適齢期の子方が必須です。私の披きの時(平成12年)は息子の尚生が子方で、シテとして親としてどう導いたらいいかに心を砕きました。2回目(平成29年)は大島伊織君が子方を勤め、ツレがお父様の大島輝久氏で、親子でよく研究されて上出来の舞台をつくってくださいました。そして今回は3回目、子方は今度も大島伊織君です。前回は小学校2年生で子方適齢期、その後6回『望月』子方を勤めて、中学生になった今回で子方は卒業となりました。彼の成長がまぶしく感じられ、伊織君の最初と最後の『望月』子方にシテとして共演できたことを正直嬉しく思いました。
能で獅子を舞うのは『望月』と『石橋』だけです。同じ獅子の舞でも二曲は違います。
『石橋』は霊獣のような獅子が牡丹の飾られた一畳台で軽やかに遊び戯れ、速さと強さが求められます。一方『望月』の獅子は人間(武士)が変装し、敵の望月の様子を見、仇討ちのチャンスを窺うもので、動きも『石橋』よりはややゆったりと、人が演じる柔らかさが必要となります。今回、膝の具合が悪く難儀でしたが、まあどうにか舞えたかな、と思っています。体力的なこと、そしてこれから喜多流に子方になれる子供がいない状況を思うと、今回が『望月』の舞い納めと感慨深いものがありました。
今年1月、コロナのオミクロン株急拡大により、広島は全国でもいち早く、「まん延防止等重点措置」適用になりました。公演を無観客にして映像で有料配信する案が出されましたが、私は生の公演にこだわり、リスキーでも有観客での演能を主張しました。
能の映像配信は、生でご覧になるものとは雲泥の差がある、と思っています。もちろん資料として映像で残すことは価値あることですが、しかし舞台での息吹、緊張感、空気の揺れ、能空間の全容、それらすべてを生で丸ごと味わっていただいてこそ、能は成り立つのです。
当日は予想を上回るご来場者で、お客様がリスクを負いながら、勇気をもって心強く鑑賞に来てくださったことに、演じていて胸が熱くなりました。まさに一期一会の舞台、大切なひとときを共有出来たことが喜びです。
そして今回、アステールプラザが閉鎖せず、スタッフが全員協力してお客様をお招きしてくださったからこそ開催出来たと思っております。
関係者の皆様、ご来場のすべての方々に感謝申し上げます。
有観客で演じる素晴らしさを改めて噛みしめています。
(今回も能楽協会関連の公演のため演能写真の掲載が出来なかったことを申し添えます。)
写真 『望月』 後シテ 粟谷明生 平成29年
『龍虎』を勤めて投稿日:2022-01-19

『龍虎』を勤めて
龍と虎の爽やかな闘い
「虎の尾を踏み、毒蛇の口を逃れたる心地して・・・」とは、
武蔵坊弁慶ら源義経一行が厳しい関所の詰問をくぐり抜け、陸奥の国に落ち延びていく能『安宅』の最後の謡です。
虎の尾を踏んだり、毒蛇に噛まれるのは危険極まりない行為でご免こうむりますが、令和4年寅年のはじめ(1月8日)に、国立能楽堂普及公演にて、虎をテーマにした稀曲を勤めることが出来たのは幸いでした。
『龍虎』は観世小次郎信光作の龍と虎の勢いを争う闘いが見どころの風流(ショー的)の能です。当時人気だった「龍虎図」(龍と虎が向き合ってまさに闘い出さんとしている図)から発想して能の物語に面白く作ったもののようです。
物語は、諸国を巡った僧(ワキ)が天竺(インド)を目指し、まず唐(中国)に辿り着くところから始まります。僧が雄大な景色を眺めていると、樵の老人(前シテ)が若者(前シテツレ)を連れて現れます。老人は僧に天竺を目指すより自国に心を向けよ、と話し、竹林の巌洞に住む虎と、空高い雲より現れる龍も、人間同様に儚く闘うこと、そして中国の皇帝の龍と虎の故事を語り、ここで待っていれば闘いが見られると言い残して家路につきます。
前場は動きが少なく、静かな場面が続きます。ご覧になる方はやや退屈するかもしれませんが、よく耳を傾けると「心せよ、胸の月、よその光を尋ねても」(自分の胸、自国に心を向けよ)や、「争いは人の身も異らぬ(かわらぬ)ものを」、「畜類の闘ふ事も理や」などの真実をついた謡の聞きどころがさまざまにあります。
後場はガラリと景色が変わります。一畳台が舞台中央に運ばれ、その上に竹葉を葺いた山(岩屋)が置かれます。
僧が竹林を眺めていると、太鼓の撥音とともに、峰より雲が湧き上がり、龍(後ツレ)が勢いよく姿を現します。すると、岩屋にいた虎(後シテ)も負けじと飛び出して、悪風を吹き出し、激しい闘いの場面となります。
前場の曲(クセ)で「龍吟ずれば雲起こり、虎嘯けば(うそむけば:吼えれば)風生ず」と謡われた通り、龍は雲を虎は風を起こし、力が伯仲する両者は互いに譲らず、舞台狭しと闘いを繰り広げます。そしてついに勝負はつかず、いつしか龍は雲居に昇り、虎は巌洞に入って、僧の前から姿を消した、と終わります。
『龍虎』は何か特別なメッセージがあるわけではありません。凄惨な闘いというよりは、単なる畜類の威勢の競い合いの能で、深い心持ちなどもありません。サシの謡に「勢い妙にして・・・畜類と雖も位高く」と謡われるように、両者がじゃれ合うような妙なる風情もあります。平物なら平物らしく、爽やかにサラリとした舞台進行を心がけました。
装束について、前場でシテがワキの僧を見て「見馴れ申さぬ御姿なり」と謡うので、シテと日本の僧のワキの姿が違うことを意識して、今回は敢えて、水衣の上に側次(そばつぎ)を付けて唐人らしい雰囲気にしました。
面について、後ツレの龍は通常「黒髭」を付けて登場します。
龍がシテの代表的な演目に『竹生島』、『春日龍神』、『岩船』などがあり、またシテツレとして活躍する演目には『絃上』や『張良』がありますが、面は全て「黒髭」です。『玉井』のシテは大龍王ですので特別に「大悪尉」に代えます。今回は伝書通り「黒髭」にしました。
一方、虎の方は、謡本には「顰(シカミ)又は獅子口」となっています。伝書には、後シテ面「顰」にては取り合わせ悪し、口を明けたる面にては乗り合い悪しき也、長霊ベシミを用いても宜し、となっていますが、近年先人たちは「獅子口」を使われていましたので同様にしました。
また、虎も龍もそれぞれ虎、龍の立物を頭に戴き、どちらも本来「赤頭」ですが、我が家の伝書に「虎は白頭、紺半切にても宜し」と書いてありましたので、白頭に黒色竹模様の半切にしました。近年は、両者を区別するためか、虎を白頭にすることが多いようです。
さて、能のシテがこの世の動物になるのは、『小鍛冶』の狐などありますが、この狐は稲荷明神という神の使いです。シテが聖獣でもないこの世の虎に扮する『龍虎』は珍しい戯曲だと思われます。実際に演能の機会も少なく、もちろん私も今回が初演です。
ちなみに、国立能楽堂でも今回を含めて5回しか演じられていません。そのうち3回は喜多流で、1988年11月に香川靖嗣氏、2008年12月に出雲康雅氏、今回の私となります。他には、私が十代の頃に青年喜多会で大島政允氏が勤められた記憶があります。
今回、稀曲の『龍虎』を生涯に一度でも勤める事が出来、それなりに勉強になったことは確かで、寅年のはじめに、『龍虎』で虎に扮したのは何か吉運になるかもしれません。勇猛なパワーとエネルギーで、龍というよりはオミクロン(新型コロナウイルス感染症の変異ウイルス)を追い払い、よい年になるようにしたいと思いました。
写真提供 国立能楽堂
前ツレ 谷 友矩
後ツレ 佐々木多門
小鼓 鵜澤洋太郎
大鼓 谷口正壽
(2022年1月 記)
『羽衣』を勤めて投稿日:2021-10-31

『羽衣』を勤めて
横浜かもんやま能で小書「霞留」を
横浜能楽堂で催される「横浜かもんやま能」(2021年10月16日)で、能『羽衣』を「霞留」の小書(特別演出)で勤めました。横浜能楽堂でシテを勤めるのは久しぶり、2004年に能『半蔀』を小書「立花」で勤めて以来、実に17年ぶりとなりました。立花では生花を川瀬敏郎氏に生けていただいたことを思い出します。
横浜能楽堂は和風の落ち着いた雰囲気があり、舞台に立つと、その和の空気感が身体に沁み込んできて、とても気持ちよい舞台です。


「横浜かもんやま能」は伝統があり、今回の催しが37回目となりました。井伊掃部頭(かもんのかみ)直弼ゆかりの「掃部山公園」で薪能としてスタートし、公園内に「横浜能楽堂」が建てられると、能楽堂で催されるようになり、直弼公とゆかりのある喜多流と観世流・銕仙会銕之丞家の二家が交替で勤め、狂言は大蔵流・茂山家と決まっています。
今回は、昨年の催しがコロナ感染症の影響で、今年に繰り延べになり、私が勤めることになりました。
では本題に入ります。
能『羽衣』の小書は、喜多流では「舞込」と「霞留」の二つがあります。正確には「雲井之舞」と称して演じられた小書、これは、喜多流十四世宗家・喜多六平太先生が大正4年12月8日、天皇御即位の天覧能に勤めた特別の小書ですので、現在は演能されることはありません。また「物着」の小書もあるようですが、伝書には記載されておりませんので、現在の小書は「舞込」、「霞留」の二つです。
『羽衣』は能のなかでも最も人気曲、ポピュラーな曲でよく演じられていますが、通常の小書なしの演能はあまり演られることがなく、小書「舞込」が多く、「霞留」は意外と少ないです。
私の『羽衣』も通常の演能は稽古能で勤めただけで、あとは「舞込」が6回、「霞留」は1998年(平成10年)10月の粟谷能の会以来2回目です。
1998年の演能レポートに、かなり丁寧に書いていますので、今回は簡潔にレポートしようと思います。
通常や「舞込」では、まず最初に舞台中央先に羽衣(長絹)を松の作り物に載せて出しますが、「霞留」では松の作り物を出しません。では、羽衣はどこに置くのでしょう。伝書には「一の松の松に掛ける」と書いてありますが、現在は一の松近くの橋掛りの欄干に掛けます。天女が降り立つ目印、依代的な意味もある松ですが、一の松が欄干から遠いとワキが羽衣を取りにくく、また松から落ちるハプニングも想定されますので、演者の工夫で欄干に掛けるように変わったと思われます。申楽談儀「してみて善きに就くべし せずは善悪定めがたし」の通り、自然の成り行きと納得しています。
ご覧になった方は、作り物の松が出ないことをどう思われたのでしょうか。
作り物が舞台中央先に置かれると、「シテが舞っている姿が見えない」と、言われることがあります。物語を象徴する作り物、舞台先に置かれるのには意味があるのですが、確かに邪魔かもしれません。演者としては作り物がないとのびのびと舞える反面、作り物があることで、自身の舞台での位置がわかる利点もあり一長一短ですが、「霞留」は作り物を出さないのが決まりです。
また、通常や「舞込」では、ワキの「衣を返し与ふれば」の後にすぐに物着になりますが、我が家の伝書には、「霞留」になると、ワキの謡の後に「少女(おとめ)は衣を取り返し」と謡の言葉を変えて入れ、「天の羽衣風に和し」と続き、次第「東遊の駿河舞・・・・此時や始なるらん」を謡ったあとに物着となり、その後は序の「それ久堅の天といっぱ・・・」と変わります。今回は「少女は衣を取り返し」の謡を入れない近年喜多流の方々がやられている形式で勤めました。
序之舞は、「舞込」は黄鐘調ですが、「霞留」は盤渉調(高い音色)となり、華やかな感じが強調されます。また序之舞の構成も、最後が破之舞の位となり、すぐに「東遊の数々に・・・」の仕舞どころとなるのも「霞留」の特徴です。
天女が最後に「国土にこれを施し給う」と宝を国土に施す型がありますが、「霞留」では、扇(中啓)を舞台に落とす型となります。普通は立ったまま落としますが、中啓が閉じてしまったり、良い場所に落ちなかったり、と見苦しくなることもあるので、今回は膝をつき下居して綺麗に落ちるように試みました。その後は扇を持たずに舞いますが、これは珍しいことです。
最後、幕に入る型が「舞込」と「霞留」では大きく異なります。
「舞込」では、三保の松原、愛鷹山、富士の高嶺を眺め、橋掛りの三の松のあたりでくるくると回って、「霞に紛れて失せにけり」の謡と共に名残惜しそうに下界を見ながら消えるように後ろに下がりながら入幕します。
それに対して「霞留」は、最後の地謡の「失せにけり」を謡わずに「霞に紛れて」で謡を止め、お囃子が囃すだけの残り止め(のこりどめ)となり、天女は地上を振り返らず、幕に向かいスーッと消えるように、天女は月の世界へと上っていくイメージで入幕します。地上への未練や後腐れなく、お囃子のかけ声と音色だけで消えていく特別な演出で印象的です。
このように、二つの小書では細かな違いがあります。「霞留」について、実は我が家の伝書に書いてあるのは作り物を出さないことと、序之舞を盤渉調にすることだけで、扇を落とすことや残り止めにすることは書いてありません。これらは先人たちの工夫の積み重ねで、やはり「してみて善きに就くべし」です。
私は『羽衣』を何回か演じてみて、「舞込」も「霞留」もそれぞれに良さ、面白さがあると思っています。今回も、いろいろなやり方(小書・特別演出)があって、日々時の流れとともに能の演出も幅を広げているのだと、感じました。
今回の装束は前回の『羽衣』で白色腰巻と白色長絹にしたので、今回少し変えて、白色腰巻に赤色長絹にしました。冠には喜多流のお決まりの赤色の牡丹を挿しました。
通常は冠に月輪を挿しますが、小書になると赤色の牡丹を挿すのはなぜか、以前の演能レポートで今後の研究課題と書きましたが、まだ解明出来ずにいます。どうも年を重ねて大らか、いや鈍感になったようで、能にはいろいろな可能性があっていいと、最近はあまりこだわらなくなりました。これがよいのか、そうではないのか・・・・。
さて、最後に面を「小面」にするか「増女」にするか迷いました。可愛らしく可憐な乙女のイメージで喜多流本来の「小面」で勤めたい気持ちもありましたが、前回が「小面」でしたので、変えて「増女」にしました。当然、謡や舞の動きなどはややゆったり、可憐よりも落ち着いた品格ある風を心がけて勤めました。
「疑いは人間にあり、天に偽り無きものを」という名セリフ、数ある羽衣伝説と違い、舞を所望するだけで羽衣を返すという清らかで上品な作り、美しい天女の舞姿、天から音楽が降り注ぐような詞章、何度ご覧になってもさわやかで晴れやかな気分でお帰りになれる曲ではないでしょうか。人気曲であることが改めてわかります。
10月に『竹生島』を井伊掃部頭直弼が創案した小書「女体」で勤め、1週間後に直弼公ゆかりの「横浜かもんやま能」で『羽衣』を勤めることが出来ました。直弼公とのご縁を感じながらも、直弼公だけではなく、先人たちや多くの鑑賞者の方々に支えられてきた能なのだ、と改めて思いました。
(2021年10月 記)
写真提供 新宮夕海
『竹生島』を勤めて 「女体」という特別演出投稿日:2021-10-20

『竹生島』を勤めて
「女体」という特別演出
琵琶湖内の北側にある小さな島、竹生島を舞台とした能『竹生島』を秋麗特別公演(第一部)(2021年10月8日、於:喜多能楽堂)で勤めました。
『竹生島』は初番目物(脇能)で、島の寺院に祀られている弁財天や水中にすむ龍神が登場し、衆生済度、国土守護を約束する祝言能です。
脇能とは『翁』の脇に置かれ、神をテーマにした作品で『高砂』『養老』などがポピュラーです。江戸幕府が奨励した江戸式楽の正式な番組は『翁』付脇能(一番目物・神)から始まり、修羅物(二番目物・男)、髷物(三番目物・女)、四番目物(狂)、五番目物(切能・鬼)の五番立てで、各曲の間にはそれぞれ狂言が入り相当な時間がかかります。現在は正式五番立てが行われるのは稀になりました。
今回は、五番立てのうち、最初の一番目物のブロックを正式にお見せしよう、と企画され『翁』、能『竹生島』、狂言『大黒連歌』の番組となりました。

(写真 秋麗特別公演番組)
『翁』は「能にして能にあらず」と言われ、猿楽の能を奉納する前の御神事です。喜多流では千歳が面箱を持ち上げて先頭に登場し露払いの千歳之舞を舞うと、翁太夫が舞台上で翁の面を付けて翁之舞を舞い、面を面箱に戻して退場します。次に三番叟(三)がもみの段と鈴の段を舞い神事は終わりますが、すぐに続いて脇能『竹生島』が始まります。そして最後はおめでたい内容の脇狂言『大黒連歌』、これを一気に通して行います。

(写真 粟谷明生素袍姿 厳島神社にて)
『翁』は太夫以外は皆、囃子方も地謡、後見も侍烏帽子を被り素袍姿となりますが、続く『竹生島』も『大黒連歌』もそのままの姿で勤めますので、この珍しい光景も見どころのひとつで、このような正式な形をご覧いただけたのは意義があった、と思っています。
さて能『竹生島』の話をいたします。
今回は小書(特別演出)「女体(にょたい)」で勤めました。
通常は中入で、前シテツレ(女)が宮に入り弁財天に変身し、前シテの老人は本幕に入り龍神に扮して登場します。
それに対して、喜多流の「女体」(観世流とも共有)では、後場の配役が逆になり、シテの老人が弁財天を、シテツレが龍神を勤めます。
弁財天といえば七福神の神様の一人、琵琶を片手にした紅一点で、女神のイメージですから、老人(男)が逞しい龍神に、女が弁財天に変身するのが自然で、「女体」になり、男が女神になり女が龍神になるというのは、ねじれた印象がぬぐえません。地謡が「社壇の扉を押し開き御殿に入らせ給ひければ」と謡っているのに女が宮(御殿)に入らず幕に消え、「翁も水中に入るかと・・・」と謡われているのに宮に入るのも不自然です。その点、金剛流の「女体」は、前の老人をツレ、女をシテと、前後両方の役柄を変えて理に適うようにしています。
ではなぜ、喜多流は後のシテとツレを入れ替えるだけ、敢えてねじれたままにしたのか、今回その謎解きができたような気がしました。

(写真 宝厳寺弁財天)
竹生島にある宝厳寺(ほうごんじ)の本尊は弁財天です。そのお姿は変わっていて、一見、美しい女性の姿に見えますが、腕は八本、頭の上に小さな鳥居と男の顔が見られ、蛇も載っています。蛇を男性自身とも解釈すると竹生島の弁財天は女のようであり、男のようでもある、両性具有の神、つまり男とか女とか、そういう性を超越した存在なのかもしれません。そう考えると、老人が弁財天になっても何の不思議もなく、金剛流のように理に適う演出にしなくても済むのかもしれません。今回、そんな神々の世界が面白く思えました。
この小書「女体」は井伊掃部頭(かもんのかみ)直弼が創案したものです。直弼公は大変な能の愛好家で、能面や能装束も多く収集していたようで、知識も豊富だったものと思われます。竹生島の弁財天への信仰も厚く、病気平癒のお礼に能面を寄進し、宝物館にはその能面が展示されているほどです。また井伊家の能面や能装束は現在、彦根博物館に所蔵・展示されてもいます。
直弼公は「女体」を作るにあたり、いろいろな工夫をしています。
まずは『翁』付きに限ってですが、シテの出を通常の一声ではなく、真之一声の囃子に変えて能『白髭』の「釣りの営みいつまでか、暇も波間に明け暮れん、棹さし馴るる蜑小舟、渡りかねたる浮世かな」の謡を入れています。これは『翁』付脇能の場合、シテの登場は真之一声、という約束事から考えられた演出です。
今回は、このコロナ禍の時期に、『翁』から狂言まで休憩なしの連続長時間公演では、ご覧になる方のご負担も大きいだろうと思い、可能な限り時間短縮を図りました。
『翁』や狂言での短縮は難しいので、能『竹生島』を短縮しました。アイ語りは、その間、宮の中で装束を替えなければならないので短くすることができません。そこで、真之一声の最初(掛り)を囃し(能『白髭』の謡はなし)、その後通常の一声につなげる形にしました。
また、後シテの弁財天の舞(楽)を本来の五段構成から三段に短くし、直弼公の創案された通り盤渉調(ばんしきちょう)で勤めました。盤渉は水に関連した作品に囃され、音色が高くリズムも乗りよくなるので、今回の演出に似合っていたと思っています。
話は前後しますが、最初に舞台正面に運ばれる宮の作り物についてです。一畳台の上に宮を載せるのが本来ですが、今回は一畳台を省いて宮だけにしました。実は私の足の不具合があり試演してみました。通常の一畳台の上での装束替えはシテが高いところにいるので、後見にとって大変付けにくく苦労します。今回、物着に関してはスムーズに出来ましたが、一畳台がないと、やはり少し華やかさに欠けて見えたかもしれません。気になるところです。
また通常、前ツレと後ツレは同一人物が演じますが、「女体」では別々になります。今回は前ツレの女を佐々木多門氏、後ツレの龍神を友枝雄人氏が勤めてくれました。「女体」のツレは中入りしてから十分に時間があるので、別人が勤めなくとも可能ですが、これも直弼公のお考えなのでしょうか。私は同一人物でも可能だと思っています。

(写真 能面三光尉 増女)
後場の龍神は勇壮に舞い、豪快さがあって見栄えが良いですが、舞は舞働で短く、物足りなさを感じ、弁財天を後シテにする「女体」が考えられたのでしょうか。
「女体」では弁財天にシテらしさ、シテとしての風格を出すために、後半を少し作り変え工夫しています。弁財天の舞が終わると、早笛に乗って龍神が出現し舞働を舞い、通常は早めに弁財天を送り帰し、龍神が脚光を浴びる演出ですが、「女体」では、弁財天が留まって最後まで中心的な役割を演じます。通常、龍神が謡う「もとより衆生済度の誓」を弁財天が謡い、その後の「或いは天女の形を現じ・・・」、「又は下界の龍神となって」の地謡に合わせ、国土を守っているのは私なのだと、大らかに説明し、舞台上で堂々たる、ゆったりとした動きを見せます。最後、龍神が勢いよく幕に入った後も、弁財天がどっしりと私が一番偉いのだと主張するかのような終曲です。
後シテ・弁財天の面は、石塚シゲミ打の「増女」を拝借しました。冠には「月輪(がちりん)」を挿し、瓔珞を垂らすのは常の通りです。
今回は『翁』付の正式な一番目物の試みと、特別演出「女体」のことを中心にレポートしましたが、前場の長閑な春の風情、琵琶湖を船で竹生島まで漕ぎ渡るときの湖上の風景を謡い上げるところなど、なかなかの名文で聞かせどころです。十分に楽しみ味わっていただきたいところです。
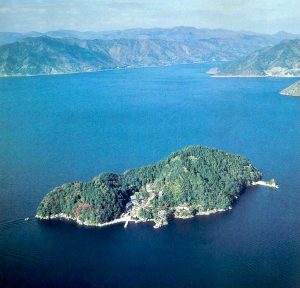
(写真 竹生島全景)
現在、竹生島までは長浜港や彦根港からの航路があり、25分~35分で行けますが、この能では志賀の真野のあたり、琵琶湖の南の方から乗船しているようで、かなり長距離の航路です。老人が漕いで行くには少々難しいのではないかと思っていましたが、当時は帆船もあったようで、それならば渡れると納得しました。
(竹生島を訪ねた、写真探訪「竹生島参詣」をご覧ください。)
今はJR湖西線ができ、琵琶湖の西側を北上する電車がありますが、それに乗って琵琶湖を眺めていると、まさに、能『竹生島』の謡の景色が、志賀の浦、近江の江、花はさながら白雪のよう、山は都の富士のよう、春の日に比良の嶺颪(ねおろし)などが自分の中に見えてくる感じがします。京都や琵琶湖周辺の、その地の位置関係を熟知している人にとっては、身近な心地よい船旅が想像でき、楽しい気分にさせられるのではないでしょうか。
能では、竹生島に着く前に、「月海上に浮かんでは兎も浪を走るか」(月の影が湖上に浮かべば、月の中の兎も浪の上を走るかのようだ)の謡があります。昔は月に兎がいる、と思っていたため、このような詞章が生まれたのでしょう。
「釣り船を漕いで白波が立ち、そこに兎がぴょんぴょん飛び跳ねるのを追うように面を切るんだ!」と、父が教えてくれたことを思い出します。
昔、中学生のころ、「女体」の2文字を見ただけで、なんとも不思議な気分になり、男子校の仲間と「にょたい!」などと口にしてクスクス笑いあったことがありました。あれから50年! 毒舌漫談の綾小路きみまろの「あれから40年!」ではないですが、月日の経つのが早いのに驚かされます。2002年に『竹生島』を勤め、およそ20年後に井伊直弼公が創案した「女体」を勤めることが出来、能楽師人生、ありがたいことだと感じています。
ご報告
この度の能『竹生島』の演能写真は、主催の能楽協会と協会依頼の撮影者との契約にblog、SNS等での公開が含まれていないため、現在のところ、演能レポートへの掲載が許可されずにおります。
私が個人的に依頼した撮影者の写真であれば、掲載も可能だったのですが、今回、依頼していた方が前日体調を崩されて撮影ができませんでした。
今後は協会に契約内容の変更を申し入れたり、当日、不都合が生じた場合は代行者を立てるなどして、一期一会の演能写真を皆様にご覧いただけるように対処して参りたいと思っております。
(2021年10月 記)
『鵜飼』を勤めて投稿日:2021-10-04

『鵜飼』を勤めて
名曲ゆえの多彩な楽しみ
粟谷 明生
殺生禁断の地で密漁をした罪で捕らえられ殺された鵜使いの物語、能『鵜飼』を喜多流自主公演(2021年9月26日)で勤めました。この会も、コロナ感染症のために1年順延になったもので、本来は昨年の9月に予定されていたものです。
『鵜飼』を勤めるのは今回で3回目です。初演は26歳(1981年)のとき、2回目は54歳(2009年)、そして今回が丁度65歳の最後の舞台でした。
初演のときは、今思い出すと恥ずかしながら、ただ教えられるまま、型通りに真似て吉と思っていました。能は不思議なものでそれでも一応成立してしまいます。が、そこが演者にとって落とし穴であることは後日知ることとなりました。
再演のときは、能『鵜飼』のゆかりの地、石和温泉の「遠妙寺(おんみょうじ)(鵜飼山)」にも行き(「写真探訪・『鵜飼』ゆかりの地を訪ねて」をご覧ください)、この曲はどういうものなのか、主人公の気持ちや背景なども考えて臨みました。そして「鵜之段」を演じていて、鵜使いが暗闇の中、松明(篝火)の光に集まる魚を捕えようと懸命に鵜を操るときに、闇を晴らす月が出てくると、あたり全体が明るくなって篝火の効果がなくなる、鵜使いには月は邪魔ものなのだと気づかされました。
鵜使いが月を嫌う気持ちが分かり、その発見が面白く、当時の演能レポートに、能『鵜飼』は「暗闇」と「月」がキーポイントと書きました。暗闇という迷い多き衆生の世界と真如の月という明るく正しい世界、この対比された言葉を追うことで、『鵜飼』が描く謎解きが一つできたような気がしました。このように能は演じてはじめて謎が解けることがあり、それが楽しみとなりました。
今回もやはり再演の時に面白く感じた「暗闇」と「月」、「人間の心の闇と光」、これがテーマであることを再認識させられました。
シテ(鵜使いの霊・老人)が登場して最初に謡う一声「鵜舟に燈す篝火の、後の闇路を如何にせん」には、鵜飼という殺生をしている人間の、その後の闇路、報いをどうしたものかと怖れる気持ちが込められ、最初にテーマを表白していることが分かります。
七夕の牽牛、織女の二つの星は月に誓って夫婦になり、雲上人は月を愛で、月の無い夜を嘆くのに、それに引き替え自分は、月の夜を厭い、闇になる夜を悦んでいる、それでも篝火が消えて闇になると悲しい・・・と、鵜使いの老人の思いが展開します。
この能のシテの最初の一声、さりげなく謡ってしまいますが、ここに大事なエキスが隠れていることを知りました。
『鵜飼』は、清澄の僧(ワキ)が甲斐の国への旅の途中、石和に到着し、鵜使いの老人(シテ)に出会います。老人と僧が問答していると、従僧(ワキツレ)が、あの鵜使いは2、3年前に一夜の宿を貸してくれた者だと気づきます。老人は、その者は殺生禁断の川で鵜飼いをして捕らえられ、罧(ふしづけ:簀巻きにされ沈められる)にされ死んだと語り(「語り」)、自分がその霊であると明かし、弔ってほしいと頼みます。
僧が懇ろに弔うことを約束して、鵜を使う様を見せてほしいと言うので、老人がその様子を見せるのが「湿る焚松(たいまつ)振り立てて」から始まる一番の見どころ「鵜之段」です。
鵜使いにとっては、殺生はいけないことと言われても、長年やって来た生業であり、鵜を使って行う漁は楽しいものでもありました。鵜使いが荒鵜どもを「ばっと放せば」に続く地謡「面白の有様や、底にも見ゆる篝火に驚く魚を追い廻し、かづき上げ掬ひ上げ・・・」は軽快に運んで謡います。シテも右手に松明、左手に鵜をあやつる縄に見立てた中啓を持って、きびきびと舞います。老人といっても、長年の労働作業はお手の物です。きびきびと手際よく動く意識が肝心です。
それでも「鵜之段」の終盤、「不思議やな・・・・」から「月になり行く悲しさよ」と謡は締まり、シテの心も沈んでいきます。そして「闇路に迷ふ此の身の名残惜しさを如何にせん」と消えていきます。
最初の明るく楽しい雰囲気から闇に沈む心、ここにも暗闇と月の対比が鮮やかです。
中入りは、静かにスーッと闇に消えていく風情が大事ですが、今回は通常通り常座で止めず、そのまま橋掛りに入り、三の松で一旦立ち止まり振り返り、娑婆への名残惜しい気持ちを表現する型を試みました。
後場は前場とはうって変わった趣向となります。
太鼓も加わり賑やかに囃す早笛に乗って登場する後シテは、なんと閻魔王。
「悪い事をしたら地獄に堕ちるよ」「嘘ついたら閻魔様に舌を抜かれるよ」「物を盗んだら鬼に叩かれるよ」などと子供の頃に言われたことを思い出します。閻魔王は冥途の番人で、生前の善行悪行を判断して、極楽行きか、地獄に堕ちるかを審判する偉い鬼です。
謡本には後シテ「閻魔王」と書いてありますが、詞章には閻魔という言葉はなく「悪鬼」と書かれています。それでも、鉄札(悪行を記したもの)や金紙(善行を記したもの)を見て判断できるのは閻魔王だけです。能の世界での悪鬼は閻魔王、そしてそれに仕える眷属を含めた者の大きな枠内と考えて勤めました。
殺生を生業とする者を主人公にした能には『鵜飼』のほかに『阿漕』と『烏頭』があり、これを三卑賤と呼んでいます。『阿漕』と『烏頭』は後シテも前シテと同一人物で、地獄で苦しむ様を見せ救いがない描き方ですが、『鵜飼』は後場では閻魔王がシテとなって、鵜使いが生前、僧に一夜の宿を貸したという功徳により、地獄に堕ちるところを改め、極楽に送り変える、と豪快に紹介する、前の二曲とは全く違った構成です。
よく「前と後、全くの別人格をよく演じられますね」と、言われますが、能楽師は基礎的な型を稽古し、それを積み上げていくので、それらを一つにまとめてもあまり違和感は無く演じることが出来ます。
以前写真探訪で訪れた「遠妙寺(鵜飼山)」の当山の由緒に、日蓮上人が弟子の日朗、日向上人と当地を廻ったときに、鵜使いの霊に出会い、法華経一部八巻、六万九千三百八十余文字を河原の小石一石に一字ずつ書き、川に沈めて施餓鬼供養した、この縁起によって謡曲『鵜飼』は作られたというようなことが書かれています。これから考えると、『鵜飼』という能は、殺生することの罪、それによる苦悩を描くというよりは、法華経を信じれば救われるということがテーマで、宗教宣伝曲となっていることが分かります。ただ、ここをあからさまにして、あまりに説教臭くなっては面白くありません。能の戯曲者が救済劇を巧みに入れ込んで面白いお話に仕上げているところが人気曲になるゆえんです。説教がましくないけれど、これを楽しく観て、「日蓮さんも良いかもしれない」と、なるかもしれません。
『鵜飼』が他の二曲のように四番目物(狂い物)の能に分離されず、切能に分類されているのも、さもありなんです。ご覧になる方は、最後の演目で閻魔王の豪快な救済劇を楽しみ、ああ、胸がすっとしたとお帰りになれるわけです。
演者にとって、後場はいかに力感が出せるかが勝負です。スピード感よりは重みがある力強さ、重厚感のある動き、舞が大事です。
閻魔や悪鬼に使用する面は「小べしみ」と呼ばれ、真っ赤な顔をして口をへの字で結んで、なにか我慢を強いられているような強い意志を感じさせる面です。面は粟谷家所蔵の是閑打の烙印がある名品で勤めました。閻魔王には似合っていたのではないでしょうか。
『鵜飼』の鵜使いは最後、閻魔王に救われますが、前場の「語り」、なぜ鵜使いの老人が罧の刑に処せられて殺されたかを生々しく語る場面も見せ場、語りの聞かせどころです。
禁止されていることを守れない人は、今の世にもいます。
例えば、有刺鉄線が張られ立ち入り禁止の看板があっても、無視して、釣り糸を垂らす釣り人。たぶん、そこはよく釣れるポイントなのでしょう。「ここは立ち入り禁止では?」と言われても「誰にも迷惑はかからないだろ」とか「そりゃ入っちゃいけないのは分かっているけれど・・・」などと悪びれもせず答える、などということありますね?
能『鵜飼』の老人も「殺生が良くないことは知っているよ」「禁漁区なのも知っている、でも・・・」とやってしまう。捕まっても、手を合わせ神妙な面持ちで、「殺生禁断の地とは知らなかった、これからは気を付けます」と、嘘の釈明をするところがありますが、ここは昔も今も変わらない人間の嫌な部分を見せつけるように演出されています。
そしてルール違反をする人を取り締まるというのも、今も昔も同じです。
『鵜飼』では石和村の者が「一殺多生」の理を掲げて、密猟者の鵜使いを見せしめにしようと、残酷な罧の刑に処します。見せしめとして一人を殺しても、他の多くの人が生きられるならいいではないか・・・・。その理念で行われた残酷な処刑は過去の歴史にもいろいろあったのではないでしょうか。現在のコロナ禍で、要請に従わない店は「店名を公開します」と脅し、一店を見せしめにして、他の店に守らせようとするのと似ていますし、自粛警察のように、取り締まる資格もない者が違反者を取り締まるという不思議な現象も起こります。
能は室町時代に作られた芸能ですが、作品テーマは現代にも通じていて、決して古臭いものではないのです。『鵜飼』という作品がそれを証明しています。
今に通じる能『鵜飼』、前場の一声や「語り」、「鵜之段」、後場の閻魔王の豪快な舞、どれをとっても楽しめ、コンパクトに構成された見どころ満載の能、『鵜飼』はつくづく名作だと感じさせられます。人それぞれ、時代が変わっても、共感できるものがあります。名曲は懐が広く、観る者が問いかければ、ちゃんとその分だけ、返答してくれます。
30代から50代までは肉体はいくらでも酷使できる、体はいくらでも動くもの、と思っていました。しかし、60代半ばともなるとそうはいかなくなり、身体の故障も多少増えて来て困っています。昨今はコロナ禍で、モチベーションが下がるなどの負も背負いました。それでも「年月を経て習得できる技もある」「年齢を重ねることで表現できることもある」と自らを鼓舞しています。
父・菊生はよく、お能は謡10年、舞3年と言って、謡が大事、謡の技の習得が大事と言っていました。だから老いて体が動かなくなってきたときこそ、味わい深い謡で勝負する、先人も皆そうやって老いにあらがっていたように思います。
私も老いの入り口にあって、3回目の『鵜飼』を勤め、能の懐の深さ、この年になって分る能の魅力にも気づかされました。馬齢を重ねることも満更捨てたものじゃない、と思い、いや思いたいと日々過ごしています。
コロナの時代、うがいをしながら、うがいの語源は鵜飼だ!
鵜が飲み込んだ魚を吐き出す姿に似ていることに由来している、と思うと、今の時期に『鵜飼』を勤めたのも何かのご縁かな、と、ふと口元が緩みました。
写真提供
前島𠮷裕
新宮夕海 (2021年9月 記)
『玉葛』を勤めて 20年ぶりの再演で感じたこと投稿日:2021-07-07

『玉葛』を勤めて
20年ぶりの再演で感じたこと
粟谷 明生
源氏物語で、夕顔と頭中将との間に生まれた娘、玉葛をテーマにした能『玉葛』を、6月の喜多流自主公演(令和3年6月27日)で勤めました。平成13年2月の広島「花の会」以来、実に20年ぶりの再演です。
前回の「広島・花の会」では他の演目との兼ね合いもあり、装束を常と変えて演じましたが、今回は通常通り、前シテ(里女)は水衣に腰巻姿、後シテ(玉葛の霊)は唐織肩脱ぎの狂女の出で立ちで勤めました。
能『玉葛』は三番目物(夢幻能)と四番目物(狂女物)の二つの要素を取り入れた特殊な構成の能です。
夢幻能とは、前場の主人公(シテ)が仮の姿で現れ、僧(ワキ)に昔語りをすると、僧の弔いにより後場に亡霊(後シテ)が昔の姿で現れ、舞を舞い夜明けと共に消え失せますが、それは僧の夢であった、と構成されています。
狂女物は生きている者の狂い(狂いとは、思いが一点に集中しすぎること)を見せる能で、舞は優雅な「舞」ではなく、「カケリ」と呼ばれる短時間の緩急ある立ち回りの動きで心の乱れを表現します。
狂女は一般に現在能に登場しますが、『玉葛』では現身の人間ではなく、玉葛の亡霊が狂乱してカケリを舞うので異色作品です。基本的な戯曲構成ではないのに、今にそのまま継続されていることに改めて驚いておりますが、その特別な魅力が何なのかは、正直まだわからないでいます。
能『玉葛』のあらすじを簡単に記しておきます。
初瀬の長谷観音に参詣する旅僧(ワキ)が小舟に棹さす女(前シテ)に出会い、御堂と二本(ふたもと)の杉に案内されます。
女は玉葛が筑紫から都へ逃げ上り、この初瀬で母・夕顔の侍女だった右近(今は源氏に仕えている)に出会ったこと、そして玉葛の薄幸流転の人生を語り、実は自分がその玉葛の霊であると明かし、消え去ります。
(中入)
後場は玉葛の霊(後シテ)が現在物の狂女物の『班女』同様に肩脱ぎの格好で、しかも髪を乱した狂乱の風情で現れ、妄執を狂い見せます。やがて昔の事を懺悔して妄執を晴らしたように見せますが、僧の夢はそこで覚めるのでした。
玉葛は夕顔と頭中将との間の娘ですが、夕顔は早々に頭中将とは疎遠になり、後に源氏と逢瀬を重ねるようになります。その折に物の怪に襲われ、はかなく亡くなってしまいます。源氏はうろたえますが、あまりにも突然なこととて、夕顔は秘密裏に荼毘に付されます。
母の行方がわからないまま、玉葛は乳母に育てられ、4歳のときに、乳母の夫の赴任先の筑紫に下ります。二十歳になると玉葛の容色の美しさに求婚者が多く、このまま、高貴な人の娘を田舎に埋もれさせるわけにいかないと、乳母らは玉葛を連れて都に逃げ上ります。
その後、母との再会を願い初瀬詣をすると、奇跡的にも夕顔の侍女だった右近に巡り合います。右近から事情を聞いた源氏は、夕顔の遺児・玉葛が美しい娘に成長したことを喜び、紫上と相談のうえ、養父として彼女を六条院に引き取り、万事を花散里に託します。
都でも、玉葛は多くの男性から求愛されますが、ついに鬚黒大将の妻になり、何人かの子供にも恵まれ、平穏な生活を送るようになります。子供たちが大人になってからのことも少しふれられますが、源氏物語のなかに描かれる玉葛はざっとこのようなところです。
では、玉葛は何に苦しみ、狂乱するのでしょうか。
ワキの僧が「たとひ業因重くとも、照らさざらめや日の光」と謡い、
後場のシテと地謡の掛け合い、
「払へど払へど執心の 長き闇路や黒髪の あかぬやいつの寝乱れ髪」や、
「げに妄執の雲霧の 迷もよしや憂かりける」の謡は、
暗い闇の「負」や「陰」を想像させます。
美しさゆえに多くの男の心を迷わせた、その業因が玉葛の狂乱の原因だと解説書には書かれています。今の世では考えられない世界観ですが、そういう事もあるのかもしれません。
ただ私は、多くの男性というよりは、とりわけ光源氏からの思慕に悩み苦しんだと思って勤めました。養父としてわきまえているように見せながら、執拗に玉葛に懸想してくる源氏。後半「寝乱れ髪」と謡われるように、ついに添い寝までするに至っては、それは事件であり、玉葛にとって衝撃の第一ではなかったでしょうか。
能『玉葛』の作者、金春禅竹はそこに焦点を当てて戯曲したのではないか、と思います。
その玉葛にふさわしい面をどうしたらよいのか、悩みました。
喜多流では江戸時代から、前シテも後シテも「小面」と決まっていますが、後シテの心の乱れをかわいい表情の小面で表現するには難し過ぎます。前回は苦悩に眉根を寄せた粟谷家所蔵の「玉葛女」を使いましたが、今回は心の乱れは身体で表現し、面は美しくきれいな表情、しかも、やや色気のある面にしたく、石塚シゲミ氏の打たれた「増女」を拝借しました。この面は何回か使わせていただいていますが、自分に似合う面と思えるので、安心して使え重宝です。
また今回、作品のメインとなる曲(クセ)の部分を常とは違う舞曲(まいぐせ)にしてみました。
「クセ」には、シテは動かず座ったままで地謡が物語を進行させる「居曲(いぐせ)」とシテが立って舞う「舞曲(まいぐせ)」の二つがあります。
『玉葛』は通常は居曲ですが、今回の自主公演は初番『小督』、三番目『阿漕』と居曲が重なってしまったので、私の『玉葛』は「替えの型」があることを根拠に、舞曲で勤めました。
クセの前半は船に乗って松浦潟、浮島、響の灘を渡っていく風情を、シテは座ったままで地謡が謡い聞かせます。
「かくて都の内とても我はうきたる舟の上」から動き出し、「初瀬の寺に詣でつつ」と合掌して、シテ謡「年も経ぬ 祈る契りや初瀬山」の上羽の後は、常の通りの舞の基本的な型が続き、最後は元の場所に戻り、ワキに弔いを頼む型で終わります。
20年ぶりの再演となった『玉葛』。前回の演能レポートは「漠としたわかりにくさとは?」と題して、この偏屈で厄介で難しい『玉葛』と格闘していたことを思い出させてくれます。若い時は考えすぎて上滑りしているところもあったかなと、懐かしくも面はゆくもあります。
後場は一声を謡い、カケリを舞い、仕舞どころとなって終曲する、とても短くコンパクトに作られているので簡単に勤められそうに見えますが、実は曲の深いところの表現が難しく、演じる者の生き様、経験などが裏打ちとなるように思えます。
曲目の真意を観る方に伝える、その難しさをより強く感じました。
父・菊生が「若いうちは青い鳥を探しに外に行きたがるが、実は青い鳥は身近なところにいたことを知るんだよ」と、話してくれたことを思い出します。
今回は、いろいろ工夫するというよりは、基本型に戻ってさりげなくやる、それを通し、そのことの難しさを感じた『玉葛』でした。
(令和3年7月 記)
能「玉葛」 写真提供 新宮夕海
『小塩』を勤めて投稿日:2021-05-31

『小塩』を勤めて
夢か現か、業平の恋と懐旧
粟谷 明生
平安時代の和歌の名手、しかも美男子(イケメン)で色男といえば、まず思い浮かぶのが在原業平です。業平自身が登場する能は『小塩』と『雲林院』の二曲だけで、『小塩』は喜多流では、しばらく演能が途絶えていましたが、十五世宗家・喜多実先生が復曲され謡本も販売されるようになりました。その後、何回か演じられ、今はかなりポピュラーな演目となりました。
その『小塩』を喜多流自主公演(令和三年五月二十三日、於・喜多能楽堂)で初めて勤めました。自主公演は新型コロナ感染症の影響で、昨年度の公演予定がすべて一年繰り延べになり、今回の『小塩』も本来なら昨年の五月に勤めるはずだったものです。
まずは、『小塩』のあらすじを簡単にご紹介します。
桜が満開の大原野(京都)で花見をしている都人(ワキ)の前に、桜の枝をかざした老人(前シテ)が現れます。都人は老人に声をかけ、桜花を共に愛でますが、老人(地謡)が、
「大原や小塩の山も今日こそは 神代の事も思ひ出づらめ」
と、古歌を詠むと都人はその歌の作者を尋ねます。
老人は二条の后がこの大原野に行幸された時、在原業平が后との昔の契りを想い詠んだ歌だと答え、そのまま名乗らず夕霞の中に消えてゆきます。(中入)
都人は先程の老人が業平の霊であると判ると再会を待ちます。
すると花見車に乗った業平が現れ、自らの和歌を詠じて舞を舞います。そして二条の后に供奉してこの大原野に来た昔が忘れられないと語ると、春の夜の夢の如く消え失せてしまうのでした。
『小塩』の舞台となっている大原野小塩山は京都市西京区西部にあり、それほど高くないこんもりとした山です。大原野には業平ゆかりの「十輪寺」があり、境内には業平の墓と伝えられる小さな塔が建っています。毎月5月28日には業平忌の法要が行われているそうです。
大原野には『西行桜』ゆかりの「勝持寺」もあり、両方のお寺を巡ったことを思い出します。
以前は、演能前に謡跡めぐりをして演能資料集めをし、謡曲保存会の駒札を見つけると喜んでカメラに収めたりしていました。最近はなかなかそういう事も出来なくなっていましたが、コロナが収束したら、またカメラを持って出かけたいと思います。
ちょっと脱線しますが、京都在住の喜多流能楽師の高林呻二氏からの面白い情報がありましたのでここに記しておきます。
「寂光院の大原は“おはら”、小塩の大原は“おおはら”と読み分けていたのですが、デュークエイセスの“女ひとり”の辺から“おはら”も“おおはら”と呼ぶのが主流になったようです」
なるほど、京都人が“おおはら”と呼ぶのはもともと大原野の方だったということ、地元の人でないと分らない感覚です。
大原野には藤原氏を祀る大原野神社があります。
能『小塩』は、その藤原氏出身の二条の后(藤原高子)が行幸された時に、昔恋仲だった在原業平も同行していて、あらすじにも挙げた
「大原や小塩の山も今日こそは 神代の事も思ひ出づらめ」
と詠いかけるのですが、この、業平が后との恋を懐かしんで詠んだ和歌をテーマに、金春禅竹が作ったと言われています。
ここでの「神代の事」というのは、藤原氏の祖神(大原小塩山の祭神)である天児屋根命(アメノコヤネノミコト)が皇祖・瓊瓊杵尊(ニニギノノミコト)に従って降臨されたことを表しています。つまり、その神の子孫である御息所(二条の后)が参拝することで、降臨した昔のことが思い出されるでしょうという、懐の大きな歌です。業平が家来として、藤原氏や御息所を賛美するような歌でもありますが、二条の后との懐かしい恋の思い出を晴れやかに詠ったとも見て取れます。
これは業平52歳、后(高子)35歳のこと、17歳違いの二人が駆け落ちして17年経っての出来事です。
在原業平が歌人でイケメン、色好みの貴族だったことは知られていますが、勇猛な武官であったことはあまり知られていないようです。弓も上手で力強かったようです。
業平の父は平城天皇の皇子・阿保親王ですが、嵯峨天皇との対立に敗れ、大宰府に左遷されます。その後、都に戻りますが皇位継承の争いを避け臣籍降下を願い出て、在原朝臣を名乗ります。阿保親王には男の子が何人かいて、次男が能『松風』にも描かれる行平、業平は五男で最後は中将の官位につきます。いずれも、皇族の出ですが、政治のひのき舞台からは退き、その憂き思いが和歌の世界で開花し、伊勢物語などに多くの名歌を残したといわれています。
伊勢物語で描かれる業平の最も熱き恋は二条の后・高子との恋。伊勢物語の六段には、昔男(業平らしい)が女(高子らしい)を連れ出して芥川のあたりに籠っていると、雷が鳴り雨も激しくなってくる、男が女を奥に押し入れ、戸口で見張りをしているすきの、夜も明け方に鬼が女を一口に食ってしまった、男が気づいたときには女の姿はなし、男は足摺りして泣いたけれども甲斐なしであった、とあります。この鬼は実は高子の兄たち(藤原国経、基経)で、妹を取り戻しにやって来たのでした。
このようなエピソードが語られるように、業平と高子の恋は、駆け落ちまでしたけれども、はかなく、実ることはなかったのです。
能『雲林院』の現行曲は世阿弥が改題したもので、『小塩』と同じように、女物の本三番目物に準じる、三番目物として、しっとりとした曲趣になっていますが、もともとの曲は、今述べた、芥川の鬼にとられた事件に焦点をあて、後場には業平は登場せず、シテが兄の基経、ツレが高子で、古作の能らしい素朴な作りになっています。
世阿弥改題の現行曲は鬼の能をやめ、後は業平をシテにして優雅に作り変えていて、二人の駆け落ちなどの事件性はないのですが、その頃の恋の話に主眼が置かれます。
それに対して、『小塩』は満開の桜を愛でながら、駆け落ちから17年後、大原野で再会した時の話を据えて、事件からある時間がたった人間の思いに光を当てています。このところが、『小塩』という曲の主旨なのでしょう。穏やかで、昔を懐かしむ風情があります。
能を私流に陰陽で分類すると、『小塩』は陽で、『雲林院』は陰になるように思われます。
前シテの老人も花を愛でて陽気な感じですし、後シテも自らの和歌を聞きながら、気持ちよく序の舞を舞います。
後場の一声の和歌にもその違いが現れます。
「月やあらぬ春や昔の春ならぬ 我が身ひとつはもとの身にして」
歌の意味は、月も春も昔のままというわけではないのか、私だけは元のままなのだけれどといったところで、これも、伊勢物語の第四段や古今和歌集にも登場する業平の歌です。『小塩』では下の句が「我が身ぞもとの身も知らじ」となって、私の当時の姿を見知るはずもあるまいとワキに語り掛ける格好になっています。
この和歌の謡い方に違いがあります。『小塩』が声の調子を張って高音で謡うのに対して、『雲林院』では調子を抑え、低音で謡います。これも、『小塩』が陽で、『雲林院』が陰とする根拠のひとつです。
これまで喜多流の『小塩』は三番目物として大事に扱い、シテ謡も地謡も、比較的大事にゆっくり丁寧に「陰」を基本にしていたように思われますが、どうも不似合いに感じました。業平の二条の后への懐旧と遊舞の舞に多少翳りはありますが、それよりは逆に衰えぬ色好みの輝きを舞台上に押し出す「陽」の気で演じた方が良いのではないかと思います。これまで、初同は重い感じで謡っていましたが、地謡に「もう少し陽気な感じでさらさらと謡ってほしい」と、お願いし、囃子方の皆様にもそのように位を合わせていただきました。
後場の一声、シテの「月やあらぬ・・・」の和歌の謡は聞かせどころですが、節づかいが難しい謡で、きれいに華やかに、しかもうるさくなく張って謡わなければいけないので難所です。また、序の舞の位も普段より軽めにサラリと囃していただきました。
この曲は全体にあまりベタつかず、陽の気持ちで、軽くサラリと演じることが心得だと思います。
さて、前場に戻ってみましょう。時は春、桜が満開の大原野です。桜の枝をかざした老人(前シテ)が登場して、長々と謡います。ここがご覧になる方には退屈なところかもしれませんが、よくよく謡の中身を聞いてみると、なかなか身に沁みることが多いのです。
まずは次の詞章。
「年経れば齢は老いぬ然はあれど 花をし見れば物思ひも無し、と詠みしも身の上に、今白雪を戴くまで、光に当たる春の日の、長閑けき御代の時なれや」
(年月が経って老人になっても、花を見ていると何の物思いもないと、詠んだ人の心がよくわかる。今白髪の老人になったが、光り輝く春を楽しむことができるのは長閑な聖代のおかげでありがたいことだなあ)
歳をとっても、花を見れば物思いも無しなどと、いいではありませんか。
そして次は、満開の花盛り、それに誘われてやって来た老人が、
「老な厭ひそ 花心」を繰り返し、花たちよ、花見に集うみなさんよ、どうぞ老い人を厭わないで、と謡います。老人でありながらおちゃめで華やかな風情。これもいいです。
これらの老人の謡は少し熱っぽく開放的に、軽快、陽気に謡いたいものです。
このあたり、今まではあまり気にせず謡っていましたが、近ごろ・・・私も髪の毛が白くなり四季の花を見ては感傷に浸るようになって、この老人の心境が痛いほど分かります。
謡の「老いの世界」がようやく分るようになってきて、加齢するのも悪くないかと思ったり、しかし加齢は体力低下のマイナス面もあり、嬉しいやら悲しいやら複雑な心境です。先人たちが、年を取って体力が衰える分、謡の力をつけていくのだ、と話されていたことを思い出し、これもしみじみと分かるようになりました。
後場は作者禅竹が、業平の名歌をこれでもかと、まるでパッチワークのように貼り付けています。十五歳のとき、奈良の春日野に鷹狩りに行って、気になる姉妹を目にして詠んだ歌。
「春日野の若紫の摺衣 忍ぶの乱れ限り知られず」(伊勢物語初段)
(春日野には紫草のみならず、あなたの匂い立つ若さが充ち満ちて、私の心も、お二人の美しさつややかさに染まってしまい、この布の忍摺模様のように、私の心は限りなく乱れ、野の草々ならば、やがて静まるものの、この布模様は消えてはくれないのです。)
なんとオマセ。なんと女たらし、なんと和歌の天才。着ていた忍摺模様の狩衣の裾を切って歌を書いてやったといいます。若い時にこんな歌を詠み、それに磨きがかかって、五十代には「大原や小塩の山・・・」のような、あの大きな詠いぶりとなるのでしょう。
そして、まだまだ伊勢物語の和歌は続きます。
「みちのくの忍ぶもぢずり誰故に 乱れ初めにし我ならなくに」(初段)
「唐衣きつつ馴れにし妻しあれば 遥々来ぬる旅をしぞ思ふ」(第九段)
「武蔵野は今日はな焼きそ 若草の妻もこもれり我もこもれり」(第十二段)
和歌をこんなに貼り付けていいの? と現代人の私たちは思ってしまいますが、昔は伊勢物語がよく知られていて、耳に快かったのかもしれません。皆様はどう思われたでしょうか。
後シテの面について、復曲された喜多実先生は「源氏」を使われましたが、私は伝書通り「中将」にしました。「中将」という面はこの曲と『雲林院』の在中将・在原業平を想像して打たれた作品です。眉間にしわを寄せ、もて過ぎて苦悩している業平の面影を浮かべる面です。
「源氏」や「十六中将」よりやや年齢が高いお顔で、今回は「中将」が似合う、と思い選びましたが、また機会があれば、もう少し若い面をかけて、装束も今回は白色の狩衣にしましたが青色系も似合うと思います。また業平は武官なので、太刀を佩く(はく)のが理にかなっています。但し、「花見車の出入りに支障をきたす」との教えがあり今回はやめましたが、これも工夫をして太刀を佩いてみたい、などと思案しています。
さていよいよ終盤です。最後は、「まどろめば・・・夢か現か世人定めよ・・・」と舞い納め、業平の霊は姿を消します。ここにも伊勢物語にある、業平と斎宮との恋の歌を織り込み、能『小塩』は業平のお話をすべて夢、幻、として終曲します。世の中には良いにしても悪いにしても結論が出せない現象がある、それを夢のように現のように、人は夢幻のうちに溶け込ませて生きていくのかもしれません。
今回の『小塩』は最初に述べたように一年繰り延べになっての演能でした。この一年、コロナウィルス感染症で、ほとんどの能の催しは中止や延期を強いられました。どんなに日頃体を鍛錬していても、舞台に立たないでいると、お能の体が鈍ります。アスリートと同じです。能楽師も苦しい一年で、まるで夢、幻のようでもありますが、これからは、能の公演を中止・延期するのではなく、十分な対策を立てながら、演能活動を行なわなければいけない、と老いと闘いながら、気持ちを引き締めています。
(令和3年5月 記)
写真提供
前島写真店 2,7,8,13
石田 裕 1,3,5,6、9,10,11,
あびこ喜久三 12
謡蹟めぐり 4
『氷室』白頭を勤めて投稿日:2020-07-16

『氷室』白頭を勤めて
コロナ下で能の美意識を思う
粟谷 明生
今年(令和2年)3月以来、新型コロナウィルス感染症による自粛要請で、能だけでなく、音楽、映画、演劇などの芸能活動が軒並み中止に追い込まれました。国立能楽堂での公演も6月まですべて中止、7月から感染予防対策を講じて再開されることとなり、私はその第1回目として定例公演で、能『氷室』を勤めました。私としては、3月の粟谷能の会の『朝長』以来、実に4か月ぶり、久しぶりに舞台に立てた喜びを感じています。
舞台を勤める仲間も、久しぶりに会えて笑顔をかわし、全員が揃って舞台を創り上げる喜びをかみしめていました。一人の代演もなく、予定された出演者で気持ちを合わせ、舞台を無事勤められて、気持ちよいスタートがきれたことを嬉しく思っています。
当初、7月の公演も出来るかどうか危ぶまれ、実施するとしても、ソーシャル・ディスタンスを保つために観客は100人ぐらい、と聞かされましたが、その後、100人が300人となり、国立能楽堂の全客数のおよそ半分で公演ができることとなりました。当日の客席は前後左右を空け、市松模様のように座っていただきましたが、満席となり、みなさまがコロナ下にあっても駆けつけてくださったことに、ただただ感謝申し上げる次第です。
では能『氷室』ついて記します。
『氷室』は脇能に分類されますが、氷室を守る氷室明神(後シテ)の面はベシミ系で、「三日月」や「邯鄲男」などを使用する『高砂』や『弓八幡』、『養老』の神々の形相とは異なります。これは氷室明神が清浄な氷を神格化したものと考えられますが、私は液体の水から固体の氷への変貌を、強く口を結ぶ「べしむ」表情で表現しようとしたのではないか、と考えています。とにかく脇能としては特異な面の選択です。
先ずは簡単にあらすじをご紹介します。
亀山院に仕える臣下(ワキ)が丹後国の久世戸に参詣した帰途、氷室山に立ち寄ると、氷室守の老人(前シテ)と若い男(前ツレ)が現れます。老人は年々捧げる氷の謂れや氷室がこの地にあることを語り、夏でも氷が溶けないのは君徳によるものだと讃え、臣下に氷を献上する祭を見るように勧めて氷室に隠れます。<中入>
氷室明神に仕える神職(アイ)が雪乞いや雪まろめを見せると、やがて音楽と共に天女(後ツレ)が降りて舞楽を舞い、氷室明神(後シテ)が氷を持って氷室から出現します。明神は氷の威力を見せ、君に捧げる氷の守護神となり、臣下を都に送り届けます。
このような内容で、氷を守る氷室明神と夏でも氷が溶けない君徳を寿ぐ、脇能です。
『氷室』は初演でしたが、今回は小書「白頭(はくとう)」で勤めました。
「白頭」は前場に変わりはありませんが、後場の装束や面、謡い方や動きが少し変わります。
まず、頭(かしら)の毛が赤色から白色になり、装束は白色の袷狩衣となります。面は常は「小ベシミ」ですが、白頭になると老いた顔の「悪尉ベシミ」に替わります。謡い方もどっしりと速度がゆっくりとなり、動きも重々しく遅くなります。
初演は小書無しの通常の演出で勤めるのが本来ですが、私自身、白髪も増えて徐々に高齢者の仲間入りです。速い動きよりもゆったりとした動きの方が今の自分の体力に似合っているので小書「白頭」で勤めさせていただきました。
演ると、やはり冷たい氷室のイメージ、氷室を守る氷室明神を想像するとき、赤い毛の赤ら顔の形相ではなかなか難しいと思いました。小書「白頭」の演出が本来の姿ではないでしょうか。
話は前後しますが、前シテの老人は『高砂』同様、「小尉」の面をつけ装束は水衣に白大口袴、雪を掻き集める「柄振り(朳)(えぶり)」と呼ばれる小道具を持って登場します。
ワキに問われるまま、氷室の謂れや夏でも氷が溶けない君徳を語った後、「夏の日になるまで消えぬ薄氷」から始まるクセは居グセで地謡が話を進めます。
そして上羽(シテ謡)の「然れば年立つ初春の」で「柄振り」を持ち、地謡の「雪のしづりを掻き集めて、木の下水に掻き入れて、氷を重ね雪を積みて・・・」に合わせて、雪をかき集め、氷室に見立てた作り物の塚に雪を投げ込む型をします。全体に動きが少ない中で唯一、前場の見どころです。
演者にとってこの「柄振り」、実は意外と扱いにくく難儀します。「柄振り」は土の表面をならす道具で、柄の先についた横板の掻く部分(土に当たるところ)が常に下になるように持たなければなりませんが、面をつけるとこれがなかなかうまく持てません。いい位置を保つのが難しいのです。「柄振り」を使う曲は『氷室』以外にはなく、不慣れですが、今回は稽古でも本番に使う柄振りが使えたので助かりました。
今回、中入り前の地謡「薄氷を踏むと見えて」で、特別に『天鼓』の宮殿に上るときの「抜く足」の型を取り入れてみました。老人が薄氷の上を浮遊するように氷室に入る感じが出せれば、と試みてみましたが、どのようにご覧になられたでしょうか。
後シテの登場は塚の引き回しが外され、氷室明神が両手に大きな氷を持って現れます。
この氷の小道具が意外と大きく扱いにくく、稽古では何も不具合を感じませんでしたが、いざ袷狩衣を着ると重い袖が邪魔で、よりいっそう重く不自由さを感じました。
塚から出て、舞働とキリの仕舞を舞い、氷をワキに渡すと一曲も終わりです。今回は福王流のようにワキが氷を持って先に入幕する演出を下掛宝生流宗家・宝生欣哉氏のご許可を得て殿田謙吉氏に勤めていただきました。都に氷を運ぶワキを、シテは後ろで見送り見守る演出で、お客様にはわかりやすかったのではないでしょうか。
さて今回は、コロナウィルス感染下にある演能についても書き留めておきます。
まず、お客様には検温、マスク着用、消毒、などのご協力をいただき、主催者の国立能楽堂は、至る所に消毒液を置き、座席の周りに十分な空間がとれる対応をしていました。
感染予防のため、密集、密閉、密接を避ける東京都からの要請にも応え、舞台からお客様までの距離は十分空けて、飛沫感染の防止対策は万全に近い状態でした。お越しになられたお客様にご心配をおかけするようなことはありませんでした。
近頃、舞台上で地謡がマスクをしたり、互いを仕切るパーテーションを置いたり、換気のため切戸口を開け放すなどしているようですが、これはお客様に対する安全対策ではありません。これらは実は能楽師同士が感染しないためのガイドラインに沿った処置にほかなりません。我々、出演者は政治家や都庁に勤務する方々と同様、日頃から感染に気をつけて健康です。当日の楽屋入りの際には検温をし、楽屋ではマスクをして、ソーシャル・ディスタンスを保ち、万全の対策で待機していました。そしていざ舞台では、お互いを信じ、気持ちを張り詰め、よい舞台を勤めることだけを考え一致団結しました。この思いが能役者には大切で忘れてはいけない役者意識、魂でもあります。
演者が自身と隣の身を守るためにマスクをして、パーティションを置けば、当然舞台の空気は変わります。お客様はそれを見てどうお思いになるのでしょうか。能役者さんの安全も大事ですね、そんなにまでして観客に対して気をつけて下さるんですか、と好意的に受け取って下さる方もいらっしゃれば、リスクを背負って観に来ているのだから従来通りの美しい能舞台を繰り広げてほしい、と思われる方もおられるでしょう。この問題は賛否両論です。それは十分承知です。ただ私は、お越しいただいた皆様に、出来る限り従来の本物の能をご覧いただきたい一心でした。演者はマスクをしない、パーテーションも置かない、切戸口も閉める、私の思う能の美意識を損なうような演出は行わない、それを最優先にしたのです。
地謡も常の通り、二列八人で謡ってもらいました。二列八人では危険だから一列五人で、と仕方なく対応される方もおられるでしょう。それはそれで結構です。
しかし地謡は人の声の力です。二列八人を変えれば力量が変わってしまいます。
人数が減っても謡える人が揃っていればいい、とおっしゃる方のお考えもわかりますが、後列の四人が地頭を中心に、隣同士で「機(気)」を感じ息を合わせて前列の四人に声と機で伝え、その結果、八人の声が一つになって聞こえるのが地謡です。西洋音楽のようなきれいに一つにまとまる音ではなく、ゴツゴツした、いろいろな音が混ざり合い、それが一つの塊となって聞こえて来るのが良い地謡です。
歴史を訪ねれば、地謡はいろいろな形で謡われてきました。喜多流の謡本には地謡ではなく「同音」と書かれています。これはワキも一緒に謡っていた名残です。
今、地謡は二列八人が定着しています。それは年月を経て、この形が「吉」として伝わってきたからです。その能の美意識に立ち返ると、コロナ下であっても、削ってはいけない、損ねてはいけないものがあります。
今回、私のこのこだわりを演者の皆様に、もし感染が心配な方は出演をご辞退されても構わないのでお申し出てください、とあらかじめ伝えましたが、皆様、私のこだわりに賛同して下さったことを喜んでいます。
久しぶりの舞台に取り組めた喜びもあり、出演者全員がいつもよりとても気が入り、一つの塊のようになって勤めて下さって、よい舞台が出来たと確信しています。これは当たり前のことかもしれませんが、日頃忙しさの中で忘れかけていた大切なことを、コロナが再確認させてくれたように思います。
それでも、能の様式美を損なわない範囲で、東京都の要請に応える対策としてできることをいくつか試みました。できるだけ密にならないようにと、ワキとワキツレの連吟が終わると、常はワキツレは地謡前に一曲が終わるまで着座しますが、今回はすぐに切戸口から退場しました。また後場では、天女(後ツレ)も舞い終わるとそのまま、橋掛りから退場してもらいました。また、東京都からの演能時間の短縮化に応えて、すべての登場の出囃子を一部省略し演能時間を短縮しました。
3月から演能が出来ず、これだけ長期の休みは初めての経験です。舞台があることが日常だったのが、そうではない事態を突き付けられ、舞台や公演、お弟子様の稽古までが次々と中止、延期となっていく中で、今後どのように舞台を再開し、生活していくのか、と悩みました。
今回は国立能楽堂だからこそ、採算度外視してでも出来る、入場者半数でのスタートですが、一般の個人能楽師主催の会では再開へ踏み出すことが難しく、公共機関も感染を怖れて公演には前向きではない状況です。
しかし、それでは停滞どころか死滅に向かってしまいます。この苦しい状況でも、どうにか動き出さなければなりません。今、再発見したことを無駄にせず、苦しい時代を潜り抜けてきた先人たちを見習い、自分は己の能を貫ぬかねばならない、と思いを強くしているところです。
『氷室』出演者を記載しておきます。
前後シテ 粟谷明生
前シテツレ 佐藤 陽
後シテツレ 友枝雄人
ワキ 殿田謙吉
ワキツレ 則久英志
ワキツレ 野口能弘
アイ 大蔵彌太郎
アイ 吉田信海
笛 竹市 学
小鼓 鵜澤洋太郎
大鼓 山本哲也
太鼓 桜井 均
後見 中村邦生
後見 狩野了一
地頭 長島 茂
地謡 金子敬一郎
地謡 内田成信
地謡 粟谷充雄
地謡 佐々木多門
地謡 大島輝久
地謡 友枝真也
地謡 塩津圭介
以上
(2020年7月 記)
写真 能『氷室』 提供 国立能楽堂
『朝長』を勤めて投稿日:2020-03-18

『朝長』を勤めて
前シテの語りに挑む
粟谷 明生
昨年(2019年)の12月ごろ中国で発生した新型コロナウイルスが、今年に入って日本にも上陸し、2月の後半には感染拡大を防ぐための正念場として、各種イベントの中止などが要請されました。ちょうどその折も折、3月1日は国立能楽堂にて粟谷能の会でした。
国立能楽堂主催のイベントはすべて中止か延期となりましたが、粟谷能の会は最善の注意を払って実施する決断に至りました。
皆様には、具合の悪い方はご入場をお控えいただき、マスクの着用、手洗い、うがいの励行などを呼びかけ、注意を払ってお出かけくださるようお願いいたしました。当日は、欠席の方もございましたが、ご来場いただきました皆様のお陰で無事開催でき、今のところ、とりたてて問題は起こっておらず、ほっと胸をなでおろしているところです。
非常事態にも関わらず、ご来場いただいた皆様、よい舞台をつくってくださった囃子方の皆様、ワキの森常好氏、アイの野村萬斎氏、地謡、後見の方々には感謝申し上げます。
では私がシテを勤めた『朝長(ともなが)』について記していきます。
朝長は源氏の武将・源義朝(よしとも)の次男です。義朝親子は平治の乱で平清盛と戦い、敗北して都落ちします。
能『朝長』では、長男の悪源太義平は平家方に生け捕られて斬首され、三男の頼朝は弥平兵衛に捕られて都に送られ、父義朝は野間の内海に落ち行き、頼みにしていた長田に裏切られ討たれたと、史実通りに描いています。ところが朝長に関しては、膝に矢傷を負い、美濃の青墓の宿に着くと、史実では、父義朝によって不甲斐ない息子として斬られてしまいますが、能では、「味方の足手まといになりたくない、雑兵などに討たれて犬死するくらいならば・・・」と、潔く自害する演出になっています。
作者はなぜ、史実を曲げて戯曲を作ったのでしょう。私の推察では16歳という、まだ若い我が子を実の父が斬るという無惨な史実を、自害する演出に変える事によって、より朝長の健気さ、将来ある若者の痛ましさがクローズアップされる、と考えたからではないかと思います。
『朝長』の舞台進行は、朝長が自害して10年の月日を経て、元乳母子(めのとご:養育係の子)として朝長に仕えていた嵯峨清涼寺の僧(ワキ)が、都大崩れで重傷(おもで)を負って自害した朝長を弔おうと、青墓の宿に向かうところから始まります。
そこに青墓の長者(前シテ)が現れます。謡本には名は記載されていませんが、大炊延寿(おおいのえんじゅ)と考えられます。青墓の宿の女主人でそれなりの経済力もあり、源氏の応援者で、義朝とは深い関係にあったように思われます。都落ちした義朝親子が敗走の途次、長者を頼みにして訪ね、一夜を明かしますが、その夜、朝長の自害という事件が起こります。長者は朝長の最期に居合わせ、惨事を我が子のことのように嘆き、その後も弔い続けています。
前場は、朝長にゆかりのあるシテとワキの二人が出会い、朝長の死を嘆き、語り合う様子を丁寧に描いていきます。
ここに喜多流と他流との演出に少し違いがあります。まずは登場の場面で、上掛りはシテが侍女や伴の者(男ツレ)を連れて登場しますが、喜多流はシテ一人で出ます。まだ物騒な戦乱の世でしたから、長者は伴の者を連れて出なければならない事情があったのでしょうが、喜多流は一人、伴を連れていません。これは青墓の長者に焦点を当てたいと考えた喜多大夫の意図のように思えます。今回、最初はどこの誰ともわからない僧へ警戒心を持ちながらも、僧が朝長の乳母子であると分かると、次第に心を許して、問われるままに、朝長の最期の様子を語る、そのようなシテの心の動きがご覧になる皆様に伝われば、と勤めました。
もう一つの違いは、ワキの僧の役名が流儀により異なることです。福王流は「御傳(おんめのと)」と、名乗りますが、下掛宝生流は「御乳母子(おんめのとご)」です。「子」が付くと付かないでは大きな違いがあります。乳母子は養育係の子なので、朝長と年齢もそう変わらず、昔一緒に暮らし遊んだ間柄になりますが、御傳では、朝長から見たらおじさんのような存在で、やや遠い感じになります。今回は下掛宝生流の森常好氏でしたので、喜多流の謡本と同じで、私としては演じやすく感じました。
さて、前場の地謡の位(スピード)をどうするか・・・。
実は『朝長』の謡の位は確固たるものがあるわけではありません。喜多実先生(十五世喜多流宗家)時代の謡と、父菊生が謡っていた位取りは違いました。結論から申しますと、シテの語りの位に地謡や囃子が合わせれば良いのです。
私はあまり重苦しいべたつく感じではなく、むしろ強い気持ちを前面にぐんぐん押すように謡いたいと思いました。初同(地謡が初めて謡うところ)の「死の縁の所もあひに青墓の・・・」(「死」という縁で出会った青墓の地・・・)の謡は、悲しさをじっくりじんわり謡うのではなく、やや強く張り上げる勢いある地謡を望み、地頭の長島茂氏や副地頭の金子敬一郎氏、小鼓の鵜澤洋太郎氏や大鼓の亀井広忠氏に私の気持、意図をお伝えしました。そして私の思う位で謡い囃してくださった事にとても感謝しています。
初同が終わると、ワキに「朝長の最期の仕儀を語って」と所望され、シテの語りが始まります。この語りはその場に居合わせた者のみが知る迫真の語りで、能『朝長』でもっとも大切な見せ場であり、聞かせどころです。
「八日の夜に入りて、あらけなく門(かど)を敲く音す」と、義朝親子ら武具(もののぐ)した武人が「あらけなく」やって来て、一夜の宿を頼む緊迫した場面から始まり、やがて、膝の口を射られて重傷を負った朝長の自害の話に移っていきます。
「夜更け、人静まって、朝長の御声にて、南無阿弥陀仏」との声。
「こはいかにとて鎌田殿参り『朝長の御腹召されて候や』と申されければ、
義朝驚きご覧ずるに、はや、
御肌衣(おんぱだぎぬ)も紅(くれない)に染みて、目も当てられぬ有様なり」と。
そして、鎌田殿が朝長を抱きかかえ、義朝が「何とて自害するぞ」と問うと、朝長は苦しい息で、膝の口を射させられ、もう一足も歩くことができない、敵にあって犬死するよりは自害したほうがよい、雑兵の手にかかることはあまりに口惜しい、「ここにてお暇賜はらんと」と、シテが語り終えるや、地謡が「これを最期のお言葉にてこと切れさせ給へば・・・」と、続いて謡います。
シテの語りは、最初は青墓の長者の語りですが、あるときは朝長となり、あるときは義朝となるような、その場の様子がリアルに想像できるように謡わなければなりません。父菊生が「御肌衣も紅に染みて・・・の謡は、床がみるみるうちに真っ赤になっていくのが想像できるように謡わなきゃダメだ」と話してくれたことを思い出します。
実はこの大切な語り、かなりの悪条件のもとで謡わなければならず、シテは大変苦しいのです。次第で登場して名乗り、サシコエ、下げ歌、上げ歌と謡って、正面先に出たあとは、ずっと座ったままです。ワキとの問答によってお互いの素性や朝長との縁がわかり、初同、語り、そのあとの地謡まで、ずっと窮屈な唐織の着流し姿で座り続けなければならないので足が痛くてたまりません。
難しい語りをこの肉体的苦痛に堪えながら演じるのですが、不思議なもので、語りを謡っているときはさほど痛みを感じません。語り終えると、安心するのか、急に足の痛みが襲ってきます。
今回は足の痛みを少しでも和らげたいと思い、大きめの、生地が柔らかな唐織を観世銕之丞氏から拝借しました。いつも大事な物を貸してくださる銕之丞氏には本当にお世話になり感謝しております。
シテが語り終え、「これを最期のお言葉にて」と、「悲しきかなや」の段、「かくて夕陽(せきよう)影映る」の段、これらをどのように謡い分けるか。今喜多流では確固たる決まりはありません。
昔、父菊生にどのように謡い分けるのかを尋ねたことがありますが、答えは「その場の雰囲気だよ」の一言でした。何かはぐらかされたように思っていましたが、今それが正論と判りました。
能は常にシテの謡を受けて地謡が謡う、シテが強く謡えば強く、シテがじんわり謡えば柔らかくなのです。シテの謡に合わせる事は、判っていたつもりでしたが、今回の『朝長』がそれを更に教えてくれたように思います。
細かいことですが、 「これを最期のお言葉にて」の謡、父菊生は「こーれーを・・・」と1音1音ずつ音を上げて謡っていました。音を少しずつ上げる事で謡がホットになるのです。逆に平坦な音の並びではクールで熱が伝わりません。父が「僕の謡を浪花節みたいだ、と言うが、浪花節で結構じゃないか・・・」と言っていたことも思い出しました。私も数多く『朝長』の地謡を経験してきましたが、今は菊生風が一番だと思っているのです。そして、この事を地謡陣に伝えると「はい、菊生先生のパターンですね」と、すぐに了解してくれたのは菊生の謡が今に伝承されている、と息子ながら嬉しかったです。
そして、もっとも難しい「悲しきかなや」の段です。人間もみな、死すれば骨となって苔底に埋もれていき、会いたくとも会えず、声を聞きたくても聞くことができない、ただ仏も衆生もそれを憐れむ心が大切なのだ、そうすれば亡魂も哀れと思うだろう・・・と、これを聞くとき私は、青墓の長者も僧も悲しかっただろう、そして16歳という若さで自害しなければならなかった朝長も無惨で悲しかっただろう、仏もそれを救うことができない、強烈な絶望感がありながら、弔うものと弔われるものが強く支え合っている、これが自然の摂理なのだと、諦めとは違う強いものを感じます。だからこそ先に述べたように、やや強い謡が必要なのです。
次の「かくて夕陽影映る・・・」では、それまでの緊張感からやや解き放たれて、ふと空を見上げると陽が落ち夕暮れです。シテは僧を伴い青墓の宿に帰り、僧を大切にお世話するようにと申しつけ中入りとなります。「かくて夕陽」からは情景描写となり、柔らかな雰囲気となります。前の「悲しきかなや」をやや堅く強く謡うことで「かくて夕陽」の穏やかさに効いてきます。
能『朝長』の前場は動きがないので退屈してしまうかもしれませんが、このような凝縮されたよい詞章に耳を傾け、情景を想像する訳ですから、演じる者にもご覧になる方にも大曲、という事になるのでしょう。
後場は、ワキが観音懺法を読み弔っているところへ、「あら たっとの懺法やな」と後シテの朝長の霊が現れます。そして、源氏の、とりわけ父や兄、弟の悲運を語り、長者や僧の弔いに感謝し、自害になるまでの様子を再現します。しかし、後場は前場の語りほど重苦しくなく、どちらかというとさらりと描かれています。演者としては、常の型付通り演じればよく、それほど難しいというものではありません。
また、「前シテと後シテがまったく別人格を演じ分けるのは難しいでしょう?」と聞かれますが、
「さほど苦にはなりません」とお答えしています。
後シテの面は伝書には「中将」と書かれています。16歳の朝長に大人顔の「中将」は不似合いですが、『朝長』という曲を大事に扱う、位の高さからの配慮だと思われます。朝長は16歳ですから、そのものズバリの面「十六」を使用するのが理に適うのですが、どうも「十六」ではかわいらしく、能『朝長』には軽すぎるように思い、我が家にある「今若」にしました。「今若」は凛々しい顔で、朝長にはやや強すぎるかもしれませんが、潔く自害する強さも持ち合わせているので適当だと決めました。
最後に、『朝長』の作者について考えてみます。喜多流の謡本では作者は世阿弥となっていますが、昨今の研究では、命の尊さをテーマに、世阿弥とは異なる作風で悲劇を得意とする、世阿弥の長男・観世十郎元雅の作ではないかという説が有力になっています。
前シテと後シテが同人物でないことや、また史実を曲げての演出は世阿弥らしくありません。朝長が父に斬られたのではなく自害した演出も観音懺法で弔う演出も工夫のひとつだと思います。
観音懺法は実は平安末期にはまだ存在していませんでした。元雅の時代に流行っていた観音懺法を取り入れることで、観客に親近感を持たせる効果を狙ったものと推測できます。
私も演じていて『朝長』の作者は世阿弥ではないと感じ、元雅作に賛同します。それに、元雅は前シテと後シテを別人格で描く先駆者ではなかったかと思います。それ以前の作品で、このような配役は見当たりません。元雅は世阿弥が確立した複式夢幻能の定型を打ち破り、能の新しい可能性を切り拓いたのではないでしょうか。以前、前シテの青墓の長者を弔いの場に残し、後シテの朝長の霊を別の役者が勤める演出もありましたが、どうも説明的で、現行の演出の方が能として完成度が高いと思います。
今回、能『朝長』を勤めて、『頼政』、『実盛』の三修羅といわれる大曲を勤められて感慨深いものがあります。修羅能はあと一曲『兼平』を残していますが、そのうち勤めて修羅能全曲制覇をしたいと思っています。ここまで舞台を踏むことが出来たのは、ひとえに健康に恵まれ、お客様に恵まれ、一緒に作品を創り上げる能の仲間に恵まれたから、と感謝の念で一杯です。命の限り、能というものに挑戦していきたい、と『朝長』を勤め終えて思っています。
(令和2年3月 記)
『谷行』素袍を勤めて投稿日:2020-02-04
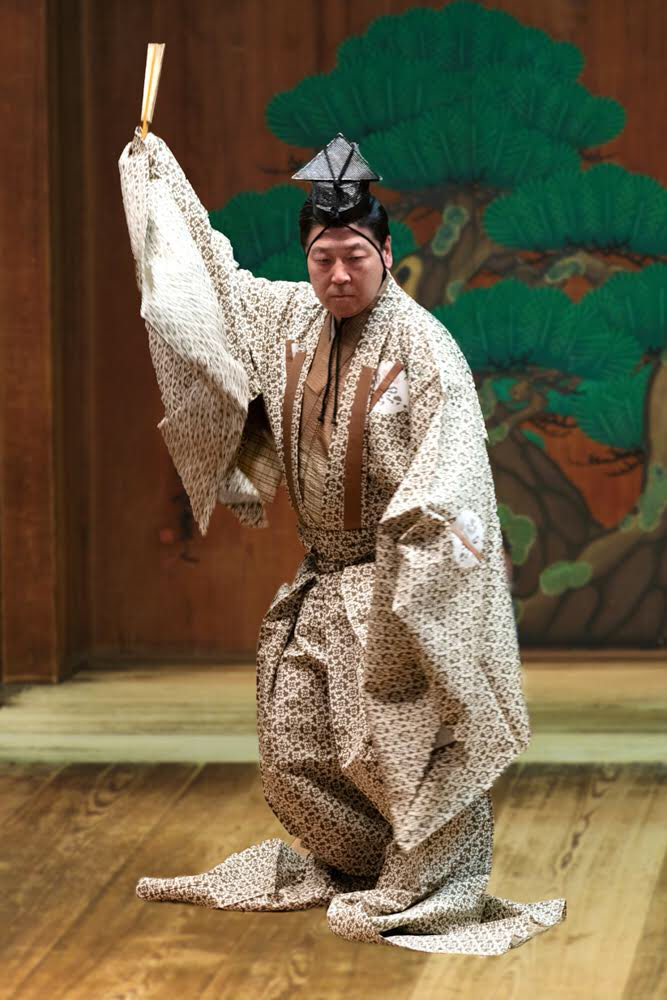
『谷行』素袍を勤めて
令和2年1月25日 「大槻能楽堂リニューアル記念日賀寿能」にて、仕舞『谷行』を「素袍」の小書にて勤めました。
昨年9月7日の能楽座公演での仕舞『熊坂』小書「長裃」に引き続き、今回の仕舞とで、喜多流にしかない珍しい仕舞小書の二曲を勤められたことは、とても良い勉強となりました。
今回の大槻能楽堂リニューアル公演の晴れの舞台にて、大槻文蔵先生より『熊坂』「長裃」か『谷行』「素袍」のどちらかで、とのご依頼を受け、「長裃」は父が前回の改修工事記念公演にて勤めたので、親子で同じものも記念になるかと思いましたが、まだ勤めた事のない『谷行』素袍の方が勉強になると思い、演らせていただきました。
長裃や素袍はとても動きにくい扮装です。
何故、動きにくい環境で、動きの速い仕舞を舞わなければいけないのか?
何故、それが喜多流にだけにあるのでしょうか?
先人からの話では、室町時代よりある四座(現在の観世、宝生、金春、金剛)より後に出て来た喜多大夫への、江戸期の将軍や殿様からの技芸の採点であり、からかい半分の嫌がらせでもあったのではないか、と聞いていますが、確かではありません。
当然、指名された大夫は、不自由な状態でも、恙無く舞わなければいけません。
そこで常とは違う型を駆使して勤めたものと考えられます。
さて、『谷行』素袍の型ですが、通常の型と少し違います。
素袍は当然、侍烏帽子を被ります。素袍の長い袴を引きずり、両袖が長く大きな袂はとても舞いづらいものです。
そこで、本来の両足や片足飛びの型をせず、足払いの型に替えたり、飛ばずに裾払いでこなし、しかしあまりに消極的に見えてはいけないので、そこを大胆に粗相なく舞う事を、第一とします。
ではこの小書を私はどのように伝承しているのかを、ご紹介します。
亡くなりました伯父の新太郎が勤めることになり、喜多実宗家に習いに行くと、「自分は知らないので兄の後藤(得三)のところに行ってくれ」、と言われたそうです。
新太郎は後藤先生に直伝を受け、その教えが菊生から能夫へと伝わり、そしてこの度、私が披かせていただく事となりました。
この小書で舞う時の地謡は、舞い手が素袍を着ているからといって、丁寧にゆっくり謡うのは良くありません。やや速く謡う心持ちの方が良いようです。動きにくいだろうと思いゆっくり謡うと、妙な鈍重感が生まれ、キリッとした鬼神の俊敏性が見えずよくないのです。少し速めに謡われる中で、両袖と裾のさばきを巧みに見せるところが、演者の心得だと思っています。
もう舞うことは無いでしょうが、これから舞う人へのメッセージと思い、ここに書き記しておきます。
このような晴れの舞台で『谷行』の「素袍」を勤めさせていただきました大槻文蔵先生に心よりお礼を申し上げます。
(『谷行』素袍 写真 シテ 粟谷明生 撮影 森口ミツル)
『羅生門』を勤めて投稿日:2019-12-24

ワキ方が大活躍する
『羅生門』を勤めて
「第3回下掛宝生流能の会」(2019 年12月21日・於国立能楽堂)にて『羅生門』を勤めました。
『羅生門』はワキ方が活躍する稀曲で上演頻度が低い能です。
喜多流での『羅生門』の演能は近年では、1983年に友枝昭世師が「穂高光晴の会」で、これが私の記憶では最初で、その後に亡父 菊生が1987年65歳にて「国立能楽堂定例公演」で勤めています。二回ともワキは宝生閑師が勤められています。
今回の『羅生門』は喜多流としては32年ぶり、3回目となります。ワキは殿田謙吉氏が披かれました。ここでシテとして、貴重な機会を与えていただきまして、会主の宝生欣哉様に、厚くお礼と感謝を申し上げます。
父は65歳、私は64歳と不思議と年齢が近く、自然と父を意識してしまい、同じ面「顰」と装束を着て、父の鬼を思い出しながら、また父に負けないように、と思い勤めました。
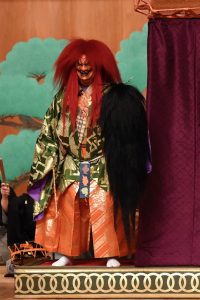 2
2
『羅生門』は前場と後場のある複式能です。
前場は、源頼光(主ワキツレ)が先頭に立ち、平井保昌(ワキツレ)や大勢の頼光の郎党(ワキツレ)を従えて登場し、屈強の兵を想像させてくれます。ワキの渡辺綱は最後に、しんがり、として登場します。
春のひととき、綱が頼光や保昌に酌をして酒宴を楽しんでいると、保昌が羅生門に鬼が出るという噂話をはじめます。それを聞いた綱は鬼などいないと、反論し口論となり、遂には綱が羅生門に行き標(しるし)の札を置いて来ることとなります。今の夏の夜の肝試しみたいです。
 3
3
後場は綱が一畳台に上がり、宮の作り物の中に札を置いて帰ろうとすると、シテ(鬼)が姿を現し、綱の兜を掴み、奪い取ります。
 4
4 5
5
兜を持った鬼が現れると、綱に兜を投げ捨て、その後は両者の闘いとなり、腕を斬り落とされた鬼は、また来る、と叫びながら虚空に逃げ去ります。
物語はわかりやすく演能時間も50分ほどの短い演目なので、どなたでもお気軽にお楽しみいただける作品です。
この曲のシテは謡が一句も無く、しかも勤めるのは後場だけです。
後場の出番も短いため、あまり重圧を感じる事なく勤められますが、往々にしてあまり気が入らないような事もあるようで、ここはモチベーションをいかに上げて荒々しい鬼に扮するかが大事です。そして日頃ワキ方の皆様がシテにうまく対応してくださる様に、この曲こそ、シテはワキが演じやすい様にお相手する事が使命で、大事な心得だと思いました。
『羅生門』のシテには珍しく面白い演出がいくつかあります。
 7
7
後場でワキは鍬形をつけた黒頭を兜と見立て登場します。
手に持つ札を宮の作り物の中に差し入れるとシテは後ろから兜を掴む型となります。
ここの型は引き回しを下ろさずに後見が掴むやり方と、シテの首元まで下ろし鬼の形相を見せ、シテ自身が掴み取る二通りが伝書に書かれています。
 8
8
友枝昭世師は後見に取らせ、亡父は自身で掴んでいました。今回は父を真似てシテ自身が奪い取る型で演りました。
鬼の姿を見せて、片手でワキの兜の黒頭を掴み実際に引き千切るように奪い取ると、すぐに引き回しを引き上げ鬼は姿を隠しますが、ここは後見2人の息のあった所作が腕の見せ所で、今回とても上手くこなしていただきました。
 9
9
作り物から出て台に上がり姿を見せた鬼は、持っていた兜の黒頭を実際に投げ捨てます。喜多流ではあまり投げ捨てる型はありませんが、ここは大胆に、鬼らしく投げ捨てます。
そして黒頭を捨てた鬼は一畳台より飛び降り、綱への威嚇を表す舞働となります。型は『紅葉狩』や『船弁慶』と同様で動きの寸法も変わらず、ここに敢えて工夫はしませんでした。
 10
10 11
11
最後に両者の闘いとなり、綱に斬られた鬼は遂に片腕を斬り落とされて「脇築土に上り(わきついじにのぼり)」の謡に合わせて片足で台の上がり下りをして幕に走り込み消えます。退治した綱は名を挙げた!と脇留で終わります。
 12
12 13
13
今回ワキを披かれた殿田謙吉氏は今年還暦を迎えられ、私と同年代です。亡き宝生閑師に師事されました。殿田氏とは平素から舞台をご一緒する事も多く、お互いによく話合い舞台をつくることができた、と喜んでいます。
 14
14
今回の公演が無事に終わると、さて次はいつかな? 今回頼光を勤められた尚哉さんの綱かな、それはいつだろうか・・・私はそれまで舞台生活を続けていられるだろうか・・・と思うと少し寂しくもなりますが、芸は継承される、と信じ、私自身は可能な限り芸道精進を心掛け、これからも健康な身体で舞台を勤めたいと、令和元年最後の能を勤めて思いました。
 15
15
短い『羅生門』の鬼でしたが、とても貴重な時間を過ごせた事を感謝し、良き年を迎えたいと願っています。
(令和元年12月 記)
写真提供
前島写真店 成田幸雄 1,6,
新宮夕海 2.3.4.5,7.8.9.10.11.12.13.14.15
『雨月』を勤めて投稿日:2019-12-04

『雨月』を勤めて
住吉明神が描く風情と和歌の徳
11月喜多流自主公演にて能『雨月』(シテ)を勤めました。
『雨月』は上田秋成の雨月物語と関係ありますか?
と、お尋ねを受ける事がありますが、まったく関係ありません。
能『雨月』は能『高砂』と同じく、摂津の住吉神社の住吉明神を取り上げた演目で、前場と後場の複式構成となっています。前場に老夫婦が登場しますが、シテの老翁は摂津・住吉明神の神霊ですので、シテツレの姥は播州・高砂明神の化身とも考えられます。しかし、ここは敢えて住吉明神だけに焦点を当てた方が、良いようです。
舞台進行にあわせてご紹介します。まず板屋の作物の中にシテとツレが入り引廻で隠して地謡座前に置かれます。
ワキの西行法師が嵯峨野から住吉大社へ参詣する旨を謡い終えると、すぐにシテは「風枯木を吹けば晴天の雨・・・」と謡い出します。ワキがこれを聞き尋ねてくるきっかけとなる大事な謡です。ワキは宿を所望しますが、老翁はすぐに断ります。すると即座に姥にたしなめられるのは能『鉢木』も同様です。無碍に断る老翁や主人に姥や女房は「だからあなたはダメなのよ!」とたしなめる、これは現代に通じます。
曲名になっている『雨月』は雨と月、どちらが楽しいか?からきています。
「軒を葺いて雨音を楽しもう!」と言い張る老翁に、姥は「月を見て楽しむには軒を葺かない方がいいわ!」と譲りません。まさに今も変わらぬ夫婦の姿です。「能は現代に生きている!」を証明してくれて面白いです。
ふと口ずさんだ「賤が軒端を葺きぞ煩う」の歌の下の句に、良い上の句を繋げば宿を貸そう、と言い出す老翁に、西行法師はすぐ「月は漏れ、雨は溜まれと、とにかくに」と上の句を付けます。老翁は喜んで「月は漏れ、雨は溜まれと、とにかくに、賤が軒端を葺きぞ煩う」を詠吟しますが、ここは住吉の神が大好きな和歌を楽しく朗詠する気持を膨らませて謡うところで、前半の一番の聞かせところです。一曲のテーマである「和歌の徳」を前場では音として観客の耳に届ける大事なところだと思い勤めました。
見事な歌心に感心した老翁は宿を貸すことにします。そして村雨が降ってきたと思ったら風の音だと、思わず老翁は作物から出て、動き舞となります。砧を打ち、落ち葉を集めて秋の名残を惜しみますが、伝書にはあまり舞う意識を持たないように、と記してあります。なるほどあまり動き過ぎては、秋の風情には似合わない、この様な感じは実際に舞台にて、演じてみてはじめて解ることで、貴重な経験が出来たと喜んでいます。夜が更けると西行法師に休息をすすめ、老夫婦は姿を消し中入となります。
能『雨月』は「風情の能」と、教えられていますが、これは特に前場に関しての教えのようです。秋の情緒ある風景描写と和歌の称賛がこの曲のテーマです。派手な動きがなく地味で渋い能ですので、はじめて能をご覧になる方には少々退屈に思われるかもしれませんが、演者の能楽師としては、この曲をどのように勤め終えるか・・・どのように通過するかが、シテ方能楽師の中間テストのように思われます。落ち着いた曲の風情を醸し出すには、若年では中々難しく、父の言葉「秋の到来を少し寂しく感じるようになって・・・、そしてようやく手掛けられる曲なのかもしれないなあ」を思い出しました。
この度、64歳にて初めて『雨月』を勤めさせていただきましたが、最初は喜びの反面、この曲が選定された事が馬齢を重ねた証であるように思えて、中々複雑な思いでいました。勤め終えて、年を経た者でなければ手に負えないところに少し手応えを感じられたことを素直に喜んでいます。この曲の持つ不思議な力、これを体に染みこますか、撥ね除け通り過ぎるか、そこが今後の能楽人生の大きな分岐点にもなるような、そんな大事な曲だということも、演じて知りました。
さて中入り後、少し寝てしまい目を覚ました西行は、先程の老人夫婦は見当たらず、自分一人松の下に居ることに気づきます。すると、住吉神社の宮人に乗り移った住吉明神が「石王尉」と呼ばれる老人の面を付けて現れ、自ら名乗り、弊を持ち祝詞をあげて、和歌の徳を讃え舞を舞います。
普通、祝詞はあまり抑揚を付けずに平坦に謡うようにしていますが、『雨月』の祝詞は住吉の神の感情が幾分出た方が良いと思って勤めました。
最後は神が宜祢(きね)に乗り移り、神の思いが言葉を超えて、思わず舞い出す風情で舞います。
喜多流の後シテの舞は「真之序之舞(しんのじょのまい)」です。他流では「働き」の演出もあるようです。「喜多さんの真之序は仰々しいな」と、お囃子方からもご指摘いただきましたが、従来通りで勤めました。
住吉明神を扱った曲目に有名な『高砂』がありますが、こちらは「神舞」を舞います。
『高砂』の後シテの使用面について、伝書には「邯鄲男」又は「三日月」と記されていますが、これらのお顔立ちは、若さと力強さを感じさせてくれますので、舞も当然キビキビと早い「神舞」です。一方、『雨月』や『白楽天』の後シテの住吉明神は面「石王尉」を付けて老体として登場しますので、落ち着きながらも力強い「真之序之舞」を舞うというのが喜多流の主張のようです。今回は神力を備えたパワーある老人であるかのように舞いたいと思い、お囃子方にはそれなりのスピード感でお願いしました。
能『雨月』は四番目物にも脇能でも扱える曲です。この曲の舞台進行は、前場では老翁と姥と西行の3人で展開しますが、後場には姥は登場せず、ワキもシテに絡む事はありませんので、脇能の扱いが吉と私は思い、今回は初番でもあるので、脇能扱いとして勤めることとしました。真之序之舞もややサラリと住吉の神様が喜んで舞われているような雰囲気で勤めたく、その旨をお囃子方にお話するとご理解いただき、とても上手く囃して下さいました。ここに感謝申し上げます。
後場をご覧になる時に注意しなければいけないのは、シテは老体で登場しますが、住吉の神様が老いているのではないということ。老人に取り憑くのがお好きなのです。
神が老人に取り憑いているので、演者としては単に老いた風体を真似るのではなく「不思議な力を持っている爺さんだなあ」と思わせる演技が必要です。これは前場のシテにも言えることですが、特に後シテの住吉明神は、西行法師が嵯峨野からわざわざ住吉まで来て参拝してくれた事への喜びと、更に和歌の徳を伝えようとし、次第に言葉だけでは済ませられなくなり、遂に思わず身体を動かして楽しく舞ってしまうのです。そのような気持ちで勤めました。
舞い終えた神は西行法師に念を押すように詰め寄るかと思うと、急に宮人から離れます。取り憑かれていた宮人は正気に戻り、本宅に帰宅したと終曲しますが、このもぬけの殻となるところがクライマックスです。ここをうまく見せるためにも、それまでの老体の動きが力強くなくては、変化が強く表れません。それまでのパワフルさが必要なのです。宮人は正に薬を飲んでパワーを発揮するかのように舞い謡い、神が離れると途端に、薬の効き目が切れ力を失ってしまう・・・、これも現代に通じるように思えてなりません。
今回、はじめて「石王尉」を付けました。この面は『西行桜』では桜の精、『遊行柳』では「柳の精」となりますが、『雨月』や『白楽天』では住吉の神となります。
この面が『雨月』の住吉の神では、なにを思われているのか、何を伝えたいのか、と、お顔を眺め、自身に問いかけていますが、未だに答えはわかりません。まだその域に至っていないようです。
父が勤めた『雨月』の写真の裏に、「膝故障 具合悪し」と記されていましたが、私も左足不良での演能となり、思わず苦笑してしまいました。終演後、先輩方にご挨拶に行くと、「菊生先生に似ていたよ。おとうさんそっくり」と言っていただきましたが、父が勤めたのは74歳の時、私は64歳、この隔たりがあるうえで、父似が、嬉しいような、そんな老人に見えたか、親子だから仕方ないか・・・、とこれまた複雑な気持ちがこみ上げ苦笑しながら、自身の能への道にあと何回テスト曲が来るのだろうか、と期待と楽しみを感じ、健康で能の道を歩いて行きたい、と改めて思いました。
(令和元年11月 記)
写真提供
(前島写真店 成田幸雄)1,4,5,6、9、12,13
(石田 裕)2,3,7,8,10,11,14
仕舞『熊坂』長裃を披いて投稿日:2019-09-15

仕舞『熊坂』長裃を披いて
能楽は本来、能面や能装束を着用して演じられますが、それらを使用せずに能の一部分をシテ(主人公)が一人で舞う事もあります。地謡に合わせて舞うのを「仕舞」、お囃子方が入るのを「舞囃子」と言います。
仕舞や舞囃子は通常、全員紋付袴姿で舞台を勤めますが、演能の場所により、また演目が高貴、高尚になると、敬意を表す意味もあり、紋付の上に裃や素袍を着て勤めることがあります。
裃は上半身に肩衣を付け、下半身は袴をはきますが、袴には短い袴と長い袴の二つがあり、短い袴を「半裃」、長い袴を「長裃」と呼びます。
喜多流にはこの「長裃」を小書の特殊演出として仕舞や舞囃子で勤めることがあります。
仕舞は『熊坂』で、舞囃子は『高砂』です。これらは喜多流独自のもので、他の流儀にはありません。両曲とも動きが激しく、動きにくい「長裃」での演能は演者の舞い方の工夫が必須で、そして粗相をしないように細心の注意を払っての勤めとなります。
その仕舞『熊坂』を「長裃」の小書にて、令和元年9月7日 「第25回能楽座自主公演」にて披かせていただきました。
今回の能楽座自主公演は、昨年亡くなられた笛方の藤田六郎兵衛氏を偲ぶ会で、各流儀の方々が集合し、舞囃子、独吟、仕舞、狂言、能と披露され、私もその一人に加えていただきました。
『熊坂』の仕舞は、暗闇の中、高齢(63歳)の熊坂長範が若い牛若丸を相手に薙刀を振りまわし奮闘しますが、翻弄され、最後は敗れた無念さを左手で足を強く叩き悔しがり終わります。
牛若丸を登場させず、熊坂一人で演じるところが能らしい演出です。
激しい動きの型に、長い裾は動きにくく苦労しますが、裾を上手くさばき、粗相無く勤めるのが演者の心得です。
亡父菊生が「通常の飛ぶ型を綺麗な裾さばきに変える、そこが一番の見せどころだよ」と教えてくれたことを思い出し、地謡に普段よりも幾分しっかり、ゆっくり謡っていただき、型の速さより、どっしりとした重厚感のある薙刀さばきを心掛け、敢えて父の茶色の裃を着て勤めました。
事前に実際に長裃を付けて数回稽古し、どうにか無事に舞い終えることが出来ましたが、後日自身の動画を見ると、もうすこし軽快な裾さばきがあってもよかったかな、と反省もしています。さて、この小書はどうして喜多流だけにあるのか、正直はっきりした事はわかりません。
流儀の重鎮・高林白牛口二氏は「残念ながら、喜多家の伝書は明治維新、震災、戦災などで散逸してしまったので書き物としては残っていない。また弟子家にその秘技を教えてはいなかった、と考えられるので結局なにも残っていないのが実情です」
と、教えて下さいました。父が「殿様は不自由な格好でどのくらい舞えるか、技量を見てみたかったのだろう。半分嫌がらせかもしれないなあ。しかし、そこを粗相無く、見事に舞わなきゃなあ」と、話してくれたことも思い出しました。
この度の「長裃」の披きに続き、来年1月25日(土)には大槻能楽堂改修記念能にて、仕舞『谷行』素袍を勤めることとなりました。珍しい仕舞の小書を勤められる幸せを感じております。次回も精一杯、活発にそして粗相無くを心掛けて勤めたい、と思っております。
写真 仕舞『熊坂』長裃 シテ 粟谷明生
撮影 新宮夕海
『岩船』を勤めて投稿日:2019-07-01

シンプルな祝言・脇能
『岩船』を勤めて
粟谷 明生
令和元年の6月・喜多流自主公演(6月23日)で『岩船』を勤めました。『岩船』は御代を祝賀する脇能でシンプルな物語です。前シテは童子(天探女・あまのさくめ)ですが、後場には登場せず、後シテは岩船を守護する龍神として現れます。見どころは、後シテの龍神が櫂棹を持ち、海上を軽快に動きまわる舞となります。
写真 前シテ 撮影 新宮夕海
まずは簡単な『岩船』のあらすじからご紹介いたします。時の帝より、摂津国住吉津守の浦(今の大阪市住吉区)に新しく浜の市を作り、高麗(こま・朝鮮)や唐土(もろこし・中国)の宝を買い取るようにとの勅命が下り、命を受けた勅使(ワキ)が津守の浦に着くと、宝珠を持つ童子(前シテ)に出会います。
写真 前シテ 撮影 新宮夕海
童子は唐人風ながらも大和詞(ことば)を話し、勅使に御代を賞賛し、帝への捧げ物として宝珠を託します。そして住吉の浜の市の繁栄を寿ぎ、周囲の景色を楽しむと、やがて宝を積んだ岩船がやってくると語り、実は自分は岩船の漕ぎ手の天探女だと名乗り嵐のように消え失せます。
写真 後シテ 撮影 石田 裕
後場は、海中から龍神(後シテ)が現れ、天探女と協力して住吉の岸に岩船を寄せて、船中から宝を運び出します。金銀珠玉が津守の浦に山のように積まれ、そして、神の加護により御代は千代に繁栄すると寿ぎ終曲します。神の住む住吉の市の繁栄、そして岩船がもたらす天から帝への宝のプレゼント、それが作品のテーマとなっています。
前シテの「天探女」とは何者でしょうか。
文字通り、天を探る、天の動向や人の心を探る力がある女神で、古事記や日本書紀にも登場しますが、「天邪鬼」の語源・由来になったとも言われ、あまりよいイメージの女神ではないようです。しかし能『岩船』の「天探女」にはそのようなイメージはなく、あくまでも日本の帝に捧げ物をするためにやってきた女神、という設定です。
写真 前シテ 撮影 石田 裕
能『岩船』の前シテ・天探女は、舞台では能面「童子・どうじ」をつけ可愛い少年のイメージで登場しますが、天探女は女性です。男子の童子として登場することに違和感を持っていましたが、「神は何にでも取り憑ける」と考えると、すんなり腑に落ち演じることが出来ました。
中入前に、自分は「天探女」で岩船の漕ぎ手と正体を明かしますが、後場には登場せず、後シテは一転して、龍神となり登場します。
このように前シテと後シテが全く違う設定は、例えば『鵜飼』『朝長』や『船弁慶』などにもあり、珍しくはありませんが、これが能の大胆な面白い演出方法です。
『岩船』も後場に前シテとは違う龍王を登場させ、そこに焦点を当てたのは、やはりとても奇抜な演出で、演じると、とても面白いと感心してしまいました。
写真 前シテ 石田 裕
さて、曲名『岩船』の岩船とは何でしょうか。正式には「天の岩船(あまのいわふね)」と呼ばれ、諸神が高天の原から天降りになさった時に乗られた船と言われています。この船に、神々が宝をたくさん積んでやって来て、帝に捧げ物をするのですから、七福神が乗っている船をイメージしてもいいかもしれません。
しかし、「天降る」ならば、海の上を「えいさら、えいさ」とやって来るのでなく、虚空を翔け巡り舞い下りて来ればいいのではないかと気になります。
そこで私なりの解釈を紹介します。
岩船は豪華大型船です。入り組んだ湾の中にある住吉の浜には直接着岸できません。
そのため、住吉の浜の遠く沖合にまずは停泊して、今でいうタグボートのような小さな、それでいて馬力がある曳舟が、天の岩船号を岸に寄せる、そう考えると自然です。
このタグボート役を担ったのが後シテの秋津島根(日本土着)の龍神です。早笛で登場して名乗ると、「宝を寄する波の鼓。拍子を揃えて、えいやえい、えいさらえいさ」の謡に合わせて威勢よく曳く様子が描かれます。しかも、龍神には八大龍王が加勢してついには御船を住吉の岸に着けるのですから、豪華です。その様を龍神の俊敏な動きを豪快にお見せするところが演者にとっての最大の技芸の見せ場となります。
八大龍王は難陀、跋難陀、娑伽羅・・・と難しい名前の付いた、中国の八龍王のことですが、後シテはその八大龍王を従えて大活躍する日本の龍王です。中国の龍王は素晴らしいけれど、日本の、純国産の龍王もすごいぞ、とのPRにも思えます。
喜多流の謡本には、ワキ「此の君、賢王にましますにより」と、この国が賢い帝によりよく治められている、だから、神が隣国(高麗、唐土)の宝を集めて帝に捧げるのだというように書かれています。
この国の誇り、偉大さを表現するこの曲は、かなりの日本贔屓の自信過剰と思われます。
今の時代、ちょっとやり過ぎのようにも感じますが、ウラがないストレートな表現が脇能・祝言能のよさかもしれません。同じように神々の話でも切能になると、そこはまたウラがあり、能の戯曲には表と裏があることを知っておくことは大事かもしれません。
日本の龍神が八大龍王に加勢してもらうという設定、実際に龍が八匹も出てくると壮観なのでしょうが、そうはせず、後シテの龍神を代表にして、その様子を描くところが能らしい演出です。しかし例外として、宝生流の小書で『春日龍神』の龍神揃、『鞍馬天狗』の天狗揃など、故意に演者がたくさん舞台に上がる演出もあり、それはそれで豪華ですが、能『岩船』には、そのような小書はありません。
宝生、金春、金剛、喜多の四流は前場と後場のある複式能の構成を今に残していますが、観世流は敢えて前場の無い半能として祝言能に徹しています。
写真 後シテ 撮影 新宮夕海
能『岩船』は一時、喜多流で謡本が発売されていない時期がありました。今は一冊本が販売されて謡のお稽古も可能となりましたが、内容がシンプルで、必ずしも謡って面白い内容とは言えないからか、お稽古される方は少ないようです。
実は演能もそう多くなく、今回は、平成27年に友枝真也氏が自主公演で勤められて以来、4年ぶりでした。それまでも演能は4、5年に1回ぐらいです。
シンプルな内容ですが、こういう祝言能・脇能が存在することを知っていただくうえで、今回の自主公演の番組は意義があると思い、勤めました。いつものことですが、取組んでみるといろいろな発見があり、また工夫してみたいことも出てきて、演能とは実に能楽師にとって楽しい場、といえるのです。
写真 前シテ 石田 裕
今回、装束を唐風にと、心がけました。ワキが童子を見たときに「姿は唐人なるが、声は大和詞なり」と語ります。ご覧になった方が日本人ではない異国の人だと想像出来るように、と扮装を考え装束を選びました。
まず前シテの童子は通常は黒頭ですが、喝食鬘の御垂髪(おすべらかす)に替えました。
また水衣の上に側次(そばつぎ・陣羽織のような唐風袖なし)を羽織り、より唐人の童子のイメージが強くなるように演出しました。唐風の装束は唐帽子などいろいろありますが、粟谷家に唐風を演出するにもってこいの側次があるのは恵まれています。この格好、玄人筋から好評で、まずは安堵しています。
写真 前シテ 撮影 新宮夕海
後シテの龍神の装束は、全体に赤色系統、赤頭に大きな龍を戴き、櫂棹を持って登場します。櫂棹は普通、ただの白木の棒ですが、唐艪(からろ)と謡われていますので、少し唐風にしたいと思い、紅段(赤い布)で巻き異国的な感じを出しました。
写真 後シテ 撮影 新宮夕海
それにしても頭に載せる龍(木製)、昔は重さをなんとも思いませんでしたが、とても重く感じてしまいました。加齢が原因でしょうか・・・。キビキビした動きがだんだん身体から離れていくのが悲しく内心忸怩たる思いはしています。もっと身体を鍛えないといけないようです。
写真 後シテ 石田 裕
喜多流の謡本の前シテの出囃子に「真之一声」と記載されていますが、これは間違いです。「真之一声」は脇能の前シテの出を囃す荘厳な囃子事で、シテツレを伴って出るのが常です。金春流は今でもシテツレを伴って演じられているようですが、喜多流はシテ一人の設定ですので、ここは普通の「一声」で勤めました。
写真 喜多流『岩船』謡本より
また、中入り後のアイについて、番組の解説に、浦人(アイ)が住吉明神の由来や岩船のことを語ると書かれていましたが、野村万作先生から「和泉流は浦人ではなく、鱗(うろくず)の精です」とご注意を受けました。アイは「賢徳」の面をつけ末社の神の格好で登場し、立ちしゃべりをした後に三段の舞を舞います。
大蔵流のアイは浦人で、舞はなくしゃべりだけです。このように流儀によってアイの演出が違うことがあるようです。今後はより深く事前に調べ、間違えないようにしないといけないと思いました。
写真 後シテ 撮影 新宮夕海
『岩船』は「櫂棹の扱いに注意」がシテの心得で知ってはいましたが、それでも演じてわかったことがあります。申合せの時は袴ですので棹が自分の体そばに寄せる心得を簡単に出来るのですが、本番では幅広の半切袴を履きますから、棹が身体から遠くなり勝手が違います。長い棹の先が舞台上の人間に当たらないようにしなければいけない事を改めて知りました。
『岩船』はあまりにシンプルで、敬遠されるむきもありますが、演者として一度は演ってみてもいいか、と思いました。唐風の装束の工夫や、狂言(アイ)もいろいろあることを知り、櫂棹のことも勉強になりました。いつも演じて思いますが、どんな能も、それぞれに面白みがあるから今に残っているのだと、今回も再認識しました。
(令和元年6月 記)
『木賊』を演じて投稿日:2019-03-18

『木賊』を演じて
酔狂で描く一途な親心
粟谷 明生
(『木賊』撮影:新宮夕海)
能『木賊』は男親と子の再会をテーマにした物狂能です。能には親子再会物、特に母子再会の女物狂能は多くありますが、男親と子の再会物は珍しく、『弱法師』や『花月』、『歌占』などあるとはいえ、男親が老翁というのはこの『木賊』一曲だけです。

(『卒都婆小町』撮影:前島写真店)
以前喜多流では、『卒都婆小町』などの老女物と同じように、『木賊』は演者が還暦を過ぎなければ勤められない秘曲として扱われていましたが、近年、還暦前に披かれた方々のお陰で、この秘曲が神棚から降ろされ、能楽師にとってやや身近に感じられるようになり演出も見直されるようになりました。
その『木賊』を第102回粟谷能の会(平成31年3月3日)で披きましたが、身近になったとはいえ、難曲であることに違いないことを実感しました。
シテの老翁は生真面目で頑固、子を思う一途な父親で、『木賊』はその一途な親心がテーマです。しかも老人の物狂能で、行方知らずになった息子を思い、酒に酔っては狂う「酔狂」が特殊です。酔狂という言葉、酒を呑んで常軌を逸することと、好奇心から変わったことを好むことと二通りありますが、『木賊』で扱うのは前者の意味です。今ではあまり聞かなくなりましたが、酒をこよなく愛する高知県人は、「あいつは酔狂やきー」などと、今でもうわさ話をします。酒を呑むとしつこくなり、まわりの人が迷惑でも、本人はいたって真剣で、「まっこと、そーじゃきー」としつこく同じ話を繰り返します。「もう先ほど聞きましたよ」と返しても、「いやまっこと分かっておらんで言うてるがやきー」と、若い頃、高知の御弟子様との宴席で実際にそんな酔狂人とお付き合いさせられたことを思い出します。しかし酔狂な人は一本気、一途で頑固であるからこそ、高知には坂本龍馬などのすごい力を発揮する県民性があるのかもしれません。
かく言う私自身も酒好きで、ついつい飲み過ぎ失敗もしますから、人のことをとやかく言えませんが、身近で言えば、父・菊生も酔狂な部分を持ち合わせていた、と思っています。
芸論や子供の教育論などになると譲らず、私と言い争いになったこともありましたが、それもよき思い出となっています。
この「酔狂」が存分に描かれるのが、能『木賊』で、特に後半の、ワキの僧たちを家に招いてお酒を勧めるところから、ここが『木賊』の一番の見どころであり、演者にとっても最難関であることは間違いありません。ここがある故に、『木賊』は高位で難曲と言っても過言ではないでしょう。私は普段、あまり面を掛けて稽古をしませんが、『木賊』ばかりは尉の面を掛けなくてはなかなか気持ちが立ち上がってこないので「小牛尉」の面を掛けて稽古を重ねました。
というわけで、まずは「酔狂」の場面を書きたいのですが、その前に、この老翁と息子の関係や、この物語がどう展開していくかを見ておきたいと思います。
最初に、息子の松若(子方)を先頭に、師の僧たち(ワキ・ワキツレ)が登場します。信濃国、園原の伏屋の里で育った松若が親に内緒で出家したが、年月が過ぎ故郷の父親のことが気になり、一目対面したいと、故郷の伏屋の里を訪ねます。
そこに父・老翁(シテ)が従者(シテツレ)を連れて、木賊を担ぎ登場し、秋の伏屋の里の景色を謡います。能『木賊』は確かに後半の物狂いの場面は重苦しいですが、前半の僧たちと老翁が出会う場面はサラッとしたものですから、前後の場面の雰囲気は当然違わなくてはいけません。
今回、シテの一声(出囃子)があまりゆっくりと重くならず、軽めにサラサラと囃していただきたく、大鼓の亀井広忠氏に相談すると、「あまり重苦しいのはいかがなものでしょうか。従者の中に老人がいるだけ。老人のスピードに合わせるのではなく、サラリと打ちたいですよ」と言われたので、これ幸い、友枝昭世師の前場は軽くサラリと、の教えの通りに勤めることが出来ました。
やがて僧が老翁に、刈り持っている木賊のことや、坂上是則が詠んだ「園原や伏屋に生ふる帚木の ありとは見えて逢わぬ君かな」(新古今和歌集)の歌のことを尋ねます。老翁は帚木というものが遠くからは見えるが近づくと見えない、そのように歌人が知っていて詠んだのだろうと、僧たちを帚木のある場所に案内します。
この「園原や・・・」の歌は恋の歌で、そこに見えているのに、逢えない君と嘆く歌ですが、この歌こそ、能『木賊』の芯になっているのではないでしょうか。
「親の心、子知らず」、「子は親に薄情だ」と怒る父親の一方的な思い込みにリンクさせて構成・演出しているのだと思います。
この帚木、源氏物語でも『帚木』巻があり、遠くには見えるが近くに行くとすっと消えてしまう、そういう女性の象徴のように使われていますが、ここでも親子の情愛のもどかしさに効果的に使われています。帚木という木は、今は落雷にあって根っこしかないようですが、実際に園原村にあった大木で箒のような形をしていたようです。
伝書にも「帚木は、高く見上げる」と書かれていて、今回、実在した帚木の写真を見て、伝書の真実性に改めて感心してしまいました。
さて、この親子、どういう人物で、どうして子は自ら出家してしまったのか、演者として気になるところで、自分なりに推察をしました。
詞章では松若は「稚き人」と書かれていますが、出家したのは9~10歳ぐらいで、そして父に一目対面したいと故郷に訪ねて来たのはそれから10年後ぐらい。
出家して、師匠に一目父親と対面したいと言えるには、少なくとも5年~10年の歳月が必要だったのでは・・・となると、舞台に登場する松若は19、20歳ぐらいということになります。実際、子方はもっと小さい年齢の子が演じますが、それが能独特の演出であって、親子対面の場面で幼い子の方が涙を誘う、その効果を能はよく知っているから、と思います。
老翁の父親の立場と性格は、決して貧しくはない、むしろ名家の主人で、質素、謹厳実直、子供に厳しかったのではないでしょうか。木賊刈りはもちろん生業ではなく、己の山に生え過ぎた木賊を刈るためで、これを家づと(家へのみやげ)だと僧に答えるところからも、推察出来ます。
また、「木賊刈る園原山の木の間より 磨かれ出づる秋の夜の月」の歌を謡いながら、露に映る澄んだ月影も刈ってしまおう、「刈れや刈れや花草」と花をつける草も刈ってしまおう、無駄なものは全部刈ってしまおう、と妙な一徹主義、そして「磨くべきは真如の玉ぞかし」「磨けや磨け、身のために」などと、自身生きるべき道への強い信念があって、その強い思いが我が子の教育にも波及していたのではないでしょうか。
「自分の信じるものは間違いない」「私の言う通りにしていれば、幸せになる」「無駄なことはするな、余計なことは考えるな」などと、一方的に口うるさい頑固親父です。
息子の意見、言い分には聞く耳を持たない父親に対して、松若は黙って家を出るしかなかったのです。
父親は老翁という設定ですが、今とは違い、当時は40から50歳ぐらいで、すでに老い人で、子供が19、20歳なら、ちょうどよい年齢で計算が合うな、と想定して稽古し、舞台を勤めました。
ちょっと話はそれますが、この曲は最初『フセヤ』との曲名だったようです。世阿弥から金春禅竹に相伝された曲名を記した「能本三十五番目録」に『フセヤ』があることから、これが『木賊』の古名だと考えられているそうです。木賊刈りのことはこの曲の最初に出て来るだけ、「園原や伏屋に生ふる帚木・・・」の歌からも、これから起こる伏屋での老翁の物狂いからも、『伏屋』がタイトルでよさそうなものですが、曲名が『木賊』となったのは何故でしょうか。
あまり露骨な表現を嫌う能(申楽)の考え方があったのでしょうか、よくわかりませんが、後の人がどこかで曲名を変えたのは確かです。しかし一見、物語には関係ないように見える木賊刈りで、老翁の実直さや自らを磨こうという謹厳な人となりを描くあたり、戯曲の構成としてうまくできていると感心してしまいます。
話を能の物語に戻します。子供の行方が知れなくなって、父親が苦しんだことは想像に難くありません。老翁は僧たちを自宅に招き一夜接待する「旦過(たんが)」に誘います。僧を泊めて話を聞けば、何か息子の手掛かりがつかめるかも知れないとの思いがあったでしょう。老翁は、自分には子が一人あるが、往来の僧に誘われ、失って(行方不明になって)しまったと告白します。そして「心安く一夜を明かして」といって物着になり、前半は終わります。僧たちに「どうぞ心安く」などと言いながら、ここは、お前らの仲間が我が子をさらったのだという、憎しみといら立ちがあったのではないかと思います。
老翁が物着している間に、従者(シテツレ)が「老翁はおかしな振る舞いをするかもしれないから、気を付けて」と注意すると、すぐに子方の松若が「只今の老翁は父親です」と僧に明かします。僧は喜びますが、松若はなぜか「まだ再会させないでほしい」と僧に頼みます。父と分かりながら、すぐに名乗り出ない、子供の複雑な心境です。自分はまだ修行の身、家に帰るわけにはいかない、一目会えればいいという思いだったのでしょうか。
そうとも知らない老翁。物着をして現れた姿を見れば、常軌を逸しているとすぐにわかります。子供が昔着ていた赤い着物を羽織り、子供の小結烏帽子(こゆいえぼし)を頭に載せています。子供の着物は裄(ゆき)が短くつんつるてん、袖のなかに大人の着物の袖がよじれ押し込まれていて、今でいえば、小学生がかぶる帽子をかぶり、ランドセルを背負って出てきたような異様な姿です。そして酒を僧たちに勧めるのです。
私はこの時すでに、老翁は酒を少し呑んでいた、とみて演じました。僧たちに酒を準備しながら、ちょっとひとくち・・・。であるからこそ、あの常軌を逸した姿でも登場でき、もうここから酔狂の世界が始まっているのです。
物着について、江戸時代の伝書には「肩上げした水衣の袖を物着にて下ろす」とありますが、近年は掛素袍や子方長絹などを着用し、しかも子方の中啓を持つ演出が主流となりました。これは近年の先人たちのよい工夫だと思い真似をして、観世銕之丞先生(銕仙会)から貴重な子方長絹を拝借し、今回の公演の原動力となりました。「たいへん似合っていた」と好評を得て、氏には感謝しております。
酒を勧める老翁に、僧たちは仏の戒めにより飲酒はできないと断りますが、古い故事などを引き、「法の真水と思って飲みましょう」と誘います。やがて酔うほどに、子はどうして親の心がわからないのか、と恨みの涙を、漣々(れんれん)と流すのです。
そしてクセ(舞クセ)では「親は千里を行けども子を忘れぬぞ、子は千里を経れども親を思わぬ」と、くどき、「人の親の心は闇にはあらねども 子を思う道に惑いぬるかな」(藤原兼輔)は本当のことだと嘆き、子の昔の面影が忘れられない、我が子はこう舞ったぞ、手はこう指したぞ、と舞いながら我が子の父への薄情を嘆き悲しみます。そして遂に興奮して狂い、泣き崩れて「酔泣(えいなき)」となるのです。
まさに酔狂。これでもかこれでもかと、かなりくどい嘆きの表白です。それも父親の側の言い分ばかり、子はどんな気持ちで家を出たのかなどは考えません。ただただ親の悲しいつらい気持ち、一方通行の嘆きです。この曲の後半の詞章の大半は父親の言い分、きっと子の言い分もあるのでしょうが、そこには故意に光を当てない演出です。能『木賊』は父親の頑なで一方通行の愛、真面目過ぎて自分の思いをごり押しする愛を描こうとしたのではないでしょうか。こんな父親、今も身近にいそうです。リアリティがあり、現在にも十分通じる話です。決して古びない、それゆえに、能は時代が変わっても長く継承されているのだと思います。やはり作者・世阿弥はすごいと感心させられます。(『木賊』は世阿弥作の可能性が高い、世阿弥系統の作品といわれています。)
今回、舞クセで「子はこう舞ったぞ」と地謡を聞きながら舞うときに、父はこう舞っていたかもしれない、と不思議な感覚になりました。この仕舞所は基本の型の連続ではありますが、それをその通りに舞うのではなく工夫が必要となります。その工夫こそに演者の力量が測られる、と信じています。老翁の心情をよく理解し、演者自身の身体を通して真似たものがごく自然と現れる、そのような舞でなければならないと思っています。更に酒が入って舞っていることを忘れてはいけないのです。単に狂うだけでなく、ここは酔狂なのです。酒に酔って狂い、思いがどんどん強烈になり興奮度が高まるのだと思って演じました。
そして老翁が「子を思ふ」と謡い序の舞となります。笛、小鼓、大鼓の囃子方の音色と掛け声に合わせて、まさに能ならではの表現で、最大の見どころです。
ご覧になった方から、序の舞で舞いながら扇を使って泣くような所作が入っていたが、特別な演出なのかと聞かれましたが、『船弁慶』で静御前が序の舞を舞うときシオリ(泣く型)が入りますので、舞の中に現実味を帯びた所作が入るのは珍しいことではなく、今回も特別ということではありません。ただし、今回は子方の中啓が老翁の心を動かす一物であるのを重視、誇張したことは確かです。幽玄能のような夢で舞う序の舞ではこのような表現はないかもしれませんが、現在物では正々堂々と感情表現が可能となります。
老翁が我が子の扇を見ては泣き出すところ、今回、泣く前後の囃子方のスピードコントロールがよく、とても気持ちよく演じることができました。笛の松田弘之氏、小鼓の鵜沢洋太郎氏、大鼓の亀井広忠氏、囃子方の3人の方々に感謝しています。
そしていよいよクライマックス、悲しみの一連の動きを大ノリ地で謡い、物狂いとなった老翁は、親が狂うなら子は囃すべきではないか、いま一目、父の前に見えよ、と訴えかけます。
現在物は夢の世界ではないのでリアリティある芝居心が必要です。役者の力量がはっきり現れる難しい曲、恐い曲です。最終的には、舞台を見てくださった観客に、自然と涙腺がゆるむような感情が伝わらないと、演者落第だと思っています。
泣き悲しむ父の姿を見た松若は遂にたまらず、自ら名乗り、二人は目出度く再会します。その後二人は古里を仏道を広める寺とし、これが伏屋の物語、目出度し目出度し、と終わります。再会後の話はこのようにあっさりしています。
しかしこの短いフレーズのなかに、一途な老翁は松若のすべてを許したのだと想像できます。仏道に入った息子の気持ちを汲んだからこそ、古里を仏道を広める寺としたのでしょう。親子というのはこんなふうに和解できるのです。
『木賊』は大事に扱われ位が重い曲、還暦過ぎないとできない曲とされてきたことは、最初に述べました。私も今63歳、還暦を何年か過ぎました。お酒は昔から好きで楽しく陽気に飲むことが多いのですが、最近、気の合う仲間たちと呑み語り合うと、思わず涙がにじむことがあります。こんなことは若いときにはなかったことです。「酔泣」をしてしまうチョイ爺になったからこそわかることもある、なるほど、『木賊』は還暦過ぎないと・・・という意味がしみじみわかります。能を解るには時間がかかる、まさに実感です。
ワキは朋友・森常好氏が勤めてくれ、子方に大島伊織くんがちょうどよい年頃で、立派に勤めてくれました。そして地頭に我が師友枝昭世師、演能後に地謡を謡ってくれた従兄弟の能夫にも、そして貴重な面「木賊尉」と装束「子方長絹」を貸して下さいました観世銕之丞様、皆様に御礼と感謝の心で一杯です。
よい時期に披くことができた、と幸せな気持でこれを書きとどめました。
(平成31年3月 記)
『東岸居士』を勤めて投稿日:2018-11-16

『東岸居士』を勤めて
謡い舞い尽くし、そして・・・

粟谷 明生
先々代十五世宗家・喜多実先生は10代から20代までの若い能楽師に習得曲を何曲か設定されていました。宗家預かりの友枝昭世師から私の後輩の長島茂氏までの世代がその経験者です。
脇能は『高砂』や『養老』はなかなか許されず、最初は『賀茂』、修羅能(二番目物)は動きが激しい『箙』と、不思議と床几の型が難しいマイナーな曲の『知章』を選曲され、三番目物は『東北』、『半蔀』よりは、まずは『六浦』、『羽衣』を、時には脇能としての分類にもなる『龍田』、そして四番目物に『東岸居士』が入っていました。五番目物は『紅葉狩』が多かった、と記憶しています。
私の『東岸居士』の初演は昭和51年の青年喜多会で、21歳でした。
今回は、喜多流自主公演(平成30年10月28日)で42年ぶりの再演となりました。

東岸居士(シテ)は自然居士(じねんこじ)の弟子で、名は玄寿といい東山雲居寺の放下僧(ほうかそう)です。
舞台は、東国から来た旅人(ワキ)が京都の清水寺へ参る途中、白川の橋で、門前の者(アイ)に東岸居士に引き合わせてくれと頼み、東岸居士が登場します。ワキとの問答になり、ワキの所望により、シテは中の舞、曲舞そして鞨鼓を舞いながら、仏の教化をするというシンプルなお話です。演能時間は50分ほどの単式現在能で、シテが終始、謡い舞い尽くす作品構成で、とりたてて高位の内容が濃い作品ではありません。何も飾らない演者の芸を淡々と見ていただくもの、と解釈されて実先生は若者に理屈抜きの謡や舞の基本を学ばせたかった、と思います。
では若者が研修過程で行う基本通りを吉(よし)としても、大人になった、しかも還暦を超えた自分が若い時と同じような再演はいかがなものか、それでは恥ずかしいです。
曲目の内容を把握し、テーマはなにか? 居士とはいかなる者か? など作品に隠されているメッセージを解きあかしたくなりました。
再演は、一度勤めたからと安心するのではなく、初演の経験を活かし演者の成長が舞台に現れるようにならなくては、と思います。演者の曲に対する意識が膨らまないと、父の言う「大人の芸」の域には至らないでしょう。特にシンプルな現在物ほど大人の味わいが必要とされます。

では具体的にどのように考え演出したかというと、まず中之舞については、舞は本来五段寸法ですが、長くだれるのは良くないと思い、近年流行の三段寸法に短縮し、替の型にして『東岸居士』特有の数珠を担ぐ型は取り入れました。

鞨鼓はややリズムをずらし遊興的な打ち方にするのも一興かと思いましたが、父の「一クサリ十六粒を舞いながら打つ難しさを披露する、そこは外さない方が吉」との教えが頭をよぎり、子方時代に覚えさせられた通りに打ちました。

ここでの中之舞や鞨鼓は、居士が、聴衆に向けて説教し仏道へ勧誘しようという意図で舞うものですから、人をその気にさせる、楽しく興味をもたせるもの、軽やかに乗りよくが大事だと思います。
さて、烏帽子について、寿山が書き残した喜多健忘斎の伝書に
「此の能、橋元にて舞い、謡いて供養を勧めたる能なれば、初めより烏帽子着ける理有り。さりながら曲舞(くせまい)に烏帽子の取合せ、宜しからず、後者損也」とあるのが気になりました。
伝書は先人の習得した技芸を後世に伝承する文書です。我が家の伝書には、最後に「こうしたら徳する、これは損」と書かれていて、そこが面白く演能に興味が湧きます。ここにも「後者損也」とあります。東岸居士は半俗半僧で、特に位があるわけではない自由な仏教徒です。現に『自然居士』は、人買い人の嫌がらせにより、いやいや烏帽子を附けさせられますが、最初は被っていません。今回は再演でもあるので、敢えて、健忘斎の教えの通り、烏帽子なしで演じてみました。

さて、謡い舞い尽くしの『東岸居士』ではありますが、稽古して初同の詞章が気になりはじめました。
「東岸西岸の柳の髪は長く乱るるとも
南枝北枝の梅の花、開くる法(のり)の一條(ひとすじ)に
渡らん為の橋なれば、勧めに入りつつ、彼の岸に到り給へや」
この前半の二行は和漢朗詠集の慶滋保胤(よししげのやすたね)の次の句(元は漢文)を引いています。
「東岸西岸の柳 遅速同じからず
南枝北枝の梅 開落すでに異なり」
春は地形によって訪れ方が違う。東岸の柳は西岸の柳より芽吹くのが早く、同じ梅でも南側の梅が散るころ北側の梅が開くというように、花の開く時期が異なっている、との朗詠です。東岸居士の説教も、この朗詠を下敷きにし、自然の営みも人間の行いも、いろいろ違うところがある、法の道に入るにしても東岸からと西岸からとでは違うのだ、ということを含んで始まっていますが、「どんな梅の花も時がくれば自然と花開くように、自然と悟ることができます。そのための橋なのだから、どうぞ私の勧進に従って、涅槃の彼岸に到りましょう」と、甘言で誘います。
そして、序やサシ、クセで、末法の世に生を受け、出離の道(生死の道の迷界を離れて涅槃に入る道)に入るのも難しい云々と、さんざんに、罪深い人間の苦しみや無力を謡い上げます。(この辺りは、難しそうなことが書かれているので、最後に現代語訳を記載しました。)
やがて、鞨鼓を打ち出すと、「いずれも極楽の歌舞の菩薩の御法だ、音楽だ、お聞きなさい旅人よ。本当に面白い」、「南無三宝(おおそうだ!)、太鼓も鞨鼓も笛、篳篥、絃管共に極楽の菩薩の遊びと聞く」
と謡い上げ、そして最後は「どうして人は雪と氷とを区別するのだ。溶けてしまえば同じ水だ。多くの仏の教えも、すべての真理も一つ、萬法皆一如。万物の真相は一つだから、法門に入ろうよ!」と、たたみ掛けるようにメッセージを送って終曲します。

難しいことも甘い言葉で人々を気持ちよくし勧進する。この居士の思想と生き様が、稽古を重ねて行くうちに、なにか疑念を持つようになってしまったのです。
「萬法皆一如」
初同に隠された、東岸と西岸では違う、花も南と北では違う、という現実。ところが真実を裏返すように「所詮、同じ柳、同じ梅、皆同じだよ」と、ざっくばらんな言い方に「矛盾していない?」と疑問を感じ、眉唾者のノリの良さを感じてしまうのですが、もしかしたら作者の観阿弥と世阿弥はそれを逆手にとって戯曲したのかもしれない、などと自由勝手に想像して演じました。
東岸居士の「居士」は、もともとは在俗の仏教徒の称号ですが、今は男性の戒名の最後に「○○居士」などと使ったり、また謹厳居士のように、性格や素性などを表す意味にも使っています。東岸居士とは、東岸に出没する居士の意で端的に言うと束縛を嫌う自由な芸能仏教徒、と私は思っています。その自由な活動には僧籍が有功で、それを上手く活用していたのではないでしょうか。

東岸居士自身、もともと家も無いのだから出家とは言わない、髪も剃らず、墨染の衣も着ないと答えています。が、しかし袈裟は掛け数珠を離さず持っているのが居士の根拠です。飄々とした生き方には自由人の趣がありますが、その自由が大雑把で、いいかげん、怪しさを感じさせます。橋のほとりで、橋のための勧進といって説教し、舞を舞い鞨鼓を打って見せ、人々から勧進料いただきますが、果たしてそのお金はどう使われるのか・・・いささか怪しいところです。
この様な怪しい勧誘は現代にもありそうです。おいしい投資話につい契約してひどい目に合うとか、あやしい宗教の勧誘にはまって財産を貢いでしまうとか・・・、現在にも十分通じる内容です。

仏法を庶民に分かりやすく広めるための、巧妙な話術と余興の舞、今風に言えば、ラッパーのラップ感覚です。最近、あるお寺でのライブで、若く可愛いアイドル系の女の子が歌や踊りで仏の教えを紹介する映像を見て、私は思わずのけぞり、「おお、南無三宝」と『東岸居士』の謡を謡ってしまいました。
現代に残っている能は、今にも十分通じる内容を含んでいるのです。そうでなければ、能は現在まで生き残っていないともいえるでしょう。

今回の『東岸居士』も萬法皆一如と言うけれど、本当にそうなの。東岸と西岸の柳はやはり違うんじゃないの? 南枝と北枝では開き方が違うでしょう・・・、善と悪はやっぱり同じにはならないよ、現実はそうではない、ということも秘かに提示しているように私には見えました。
『卒都婆小町』のレポートでも書きましたが、「悟りの道に入ろうよ」と言いながら、小町さんは本当に悟りの境地になったのかな、どう思います? というような戯曲です。
『東岸居士』の最後は「萬法皆一如」と謡い、型の動きは両手で大きな円を描き、撥と撥を重ねて合わせ、「わかりましたね」と念を押すように、よかった、目出度し目出度し、と締めますが、私は本当に「萬法皆一如?」と曖昧な気持を込めて舞おさめました。

深読みし過ぎかもしれませんが、能は深く読めば読むほど、いろいろな表情を見せてくれます。懐が深いのです。再演することで、今回もまた裏側を覗けたように思えて、やっぱり能は面白い、と再認識しました。
そして能は、観るより以上に演る方が面白い芸能!と改めて感じました。
添付資料 現代語訳 訳・長谷川 郁
東岸居士現代語訳はこちら(PDF)
写真 『東岸居士』シテ 粟谷明生 撮影 石田 裕
写真 二枚目 撮影 あびこ喜久三
(2018年11月 記)
『桜川』を演じて 桜尽くしで描く母の狂乱投稿日:2018-05-27

『桜川』を演じて 桜尽くしで描く母の狂乱

『桜川』を演じて
桜尽くしで描く母の狂乱
典型的な狂女物の構成に美しい詞章を散りばめた能『桜川』を、喜多流自主公演(平成30年5月27日)で勤めました。演じ終え『桜川』は「とても難しい曲である」が、62歳の私の正直な感想です。
生き別れた我が子を求めて彷徨う狂女物には、『桜川』のほかにも『三井寺』『百萬』『柏崎』『隅田川』など多くあります。特に春の桜のもとで狂乱する『桜川』と、秋の冴えた月下に狂う『三井寺』は対比されますが、演者の立場から比較すると、どちらかというと『三井寺』の方が高位で、『桜川』はそれほど高い扱いはされていないという印象です。『桜川』は謡や能の稽古順も早いほうです。それなのにどうして「難しい曲」なのか・・・、そのあたりを探ってみたいと思います。

『桜川』の稽古に入り、どうも気になったのが曖昧で大雑把な物語展開です。
能『桜川』は、母(シテ)が狂女になる経緯を説明する前場と、我が子を探す狂女となり謡い舞う後場の二部構成です。

まず前場の幼い桜子(子方)が母親の貧困を助けるために人商人(ワキツレ)に身を売る設定が腑に落ちません。昔は人商人が横行していて、身売りなどは珍しいことではなかったとはいえ、幼い子が自ら身を売る、という大胆な設定には無理があるように思えます。

そして善人とは思えない人商人を信じ、手紙と身代金を託し母に届けさせる設定、そして頼まれた人商人が律儀に届けてしまうのも、どうでしょう、不思議におかしく思われませんか。
更に、その手紙には、「これを機縁に母上様も御様を変えて下さい」と出家を促す、そんな大人びた幼い子が昔はいたのでしょうか。


後場では、磯部寺の住侶(ワキ)が桜子を伴い登場して、桜子と子弟の契約を交わした、と名乗りますが、どのような契約内容だったのか――。子方が僧姿ならば出家し師弟関係になったと考えられますが、稚児袴姿のため、その辺もはっきりしません。また「これにわたり候、御方は」と、住侶が幼い子を紹介する丁寧過ぎる言葉使いも、しっくり来ません。

ここで喜多流謡本に書かれている解説をご紹介します。
親子が再会する常陸の国、磯部には磯部稲荷神社があり、桜の名所で、近くには桜川が流れ、木花開耶姫(このはなさくやひめ)を祀っている。神社の文書に、五十戸(いそべ)神主祐行が鎌倉に上がったとき、関東管領の足利持氏に桜児物語の一部を献じたところ、持氏はこの物語を世阿弥に命じて謡曲に作らせた、とあります。
これによると世阿弥は、磯部寺を絡ませて春に絢爛と咲く桜と桜川、木花開耶姫信仰などのキーワードを結び付け、桜子と母の再会を入れた狂女物を作らなければならない状況にあった、と考えられます。もっともその伝説は、能『桜川』があるから、後から神社側でそのような伝説を作ったとの説もあり、どちらが本当かはわかりません。

ただ、この経緯を知ると、いろいろ腑に落ちない設定は、世阿弥の苦心作だということに行き着くのです。詞章に桜という言葉が46、花が53、これだけの桜花を散りばめた『桜川』。咲き散る桜だけをテーマに戯曲したかった世阿弥であったのかもしれません。もしそうならば、あまり些細なことにはこだわらず、能役者は桜に事寄せた春の狂女の芸の面白さを演じることに専念すれば、それでよいのでは、と未熟ながらも達観した境地になりました。
能は抽象的な芸であり、些細なことよりも、舞台人の歌舞を楽しんで見ていただくことが主と思われます。
ご覧になる方には、多少の矛盾を度外視し、不自然を気にせず問題にしない、おおらかな柔らかな発想と感情の上で観ていただくのがよいようです。能はそのようにして成立している芸能なのでしょう。
「理屈に合わないよ、そうおかしいんだよ。でもそれが能、能の面白さなんだ」と話された先人の言葉が、今ようやくわかる気がします。
では演者は、どう勤めたらいいのか。
母が我が子を探しに旅立ちしなければならなくなった場面、その事情を説明する前場は非常に短いですが、凝縮されています。理屈に合わない設定とはいえ、母親の驚き、嘆きを存分に劇的に演じなければ能役者としては落第です。後場の母の狂いに自然とつなげる謡がポイントのようです。

「あら心許なや(こころもとなや)」と文(ふみ)を開き慨嘆するところは、ただ平坦に謡っては到底伝わりません。「どういう事なの!」という驚愕と緊迫感が感じられる謡でなければいけないのです。
友枝師のお稽古では「前場はより、ドラマチックに!」とのご指導でした。
自分が思う以上に劇的に演じなければいけないことを、今回教えていただきました。

桜子(子方)は後場で住侶に連れられて登場しますが、全体的に宗教色はあまり強くなく念仏を唱える場面もありません。ただ無事親子再会を果たした後に最後のシメのように、母子共に出家し「仏果の縁と成りにけり」「二世安楽の縁深き」と、軽く仏縁で終曲しています。
磯部寺の依頼だからこそ、世阿弥は神仏への帰依を最後に入れたのでしょう。
世阿弥が本当に描きたかったものは、自分の子供を桜にみたて、名前も桜子、ご神木は桜、この地に流れる桜川、という「桜尽くしの縁」です。

母は3年かけて、宮崎の日向から常陸の国までやってきます。
常陸の国の神社からの依頼でなければ、こんなに長い道中の末の親子再会ではなく、もっと近場の、例えば京都や奈良でもよかったはず。それをわざわざ、常陸まで足を延ばさせたところに、神社からの依頼説に、私は賛同してしまうのです。

演者としては、この「桜尽しの縁」があるならば桜子に会えるかもしれないと、期待する母の心情をどう演じるか、が第一です。時は桜の節、しかし桜の花は無常にも散り始め、不安がよぎります。その憂いをどこまで伝えられるか。
一曲の見せ場「網ノ段」では、一時は子のことを忘れるほどに散る花と一体化して狂いますが、「花も桜も雪も波もみんな掬い集めたのに、これはみんな木々の花、真に私が尋ねるのは桜子。桜子が恋しい」と、急に子を思う母に立ち返り泣き伏すところを、型に頼るだけではなく、底力ある、説得力のある演技が上塗りされていないといけない、と思うのです。
『桜川』の後シテはここまで一度も座ることなく延々と立って演じます。狂女としての躁と鬱、桜と我が子への思いが交錯し変化しながらも謡い舞い続けるシテ役にとって気の抜けない時間が続きます。

稽古を始める前は、何だか取り留めがないと感じていた物語展開も、幾重にも連なる桜尽くしの母の狂いを、詞章の和歌なども深く知って演じてみると、オブラートに包まれたような、もやもやしたものが溶けていき、この能の面白さが少し分かってきたように思います。いや逆に、難しさ、に気づかされたのです。

今回の『桜川』は初演でした。先に述べたように、取り立てて位の高い能というわけでもないのに演能のチャンスはありませんでした。
十四世家元・喜多六平太先生は『桜川』や『三井寺』などの狂女物を得意としてよく演じられ、伯父の新太郎も父・菊生も、父の世代は六平太先生に憧れ、先生のお得意曲を好んで、真似て演られていたように思いますが、私にとって、これらの曲は、父たちほどに憧れの曲には入って来ませんでした。
年代によって、能役者によって、好みや流行といったものはあるようです。

それでも『桜川』を演じてみて、能の位は高くなくても侮れない曲、ということは確信しました。若い未熟な者が稽古して型だけをなぞり挑み済ますものではなく、むしろ、ある年齢になって、能役者自身が己に課す試練曲ではないだろうか、不思議とそれほどの奥行きある難曲なのだと、思っています。

この「難しさ」は観る側にも言えることで、ご来場の皆様が面白くご覧になられたならば、それは鑑賞力の高さに他ならないのです。能は演じる側にもご覧になる方にも、難しく厄介な舞台芸能です。しかし、求めていくと面白さが何倍にもなって返って来る、それが能だと。これが正直な感想です。

最後に『桜川』の面白いエピソードをご紹介します。
父が話してくれた祖父・益二郎の思い出話です。祖父が『桜川』で装束を拝借するとき、十四世宗家・六平太先生が出された水衣の色が尉(男の年寄り)向けの茶色でした。当然、浅黄色や花色が拝借出来ると思っていた祖父はガッカリだったようです。後日父が、茶色を出された訳を宗家にお聞きすると「道中、歩いているうちに汚れたんだよ」とのお返事だった、と。
笑えない、です。祖父は当時悔しく思い、こんな思いを我が子にはさせたくないと決意し、借金をしながらでも面、装束を集めるようになりました。
その心を受け継ぎ、長男の新太郎は主に面の収集に力を入れ、現在の粟谷家の装束や面があるのです。

今回の装束は、前シテは貧困な生活を送る母なので格子柄の厚板を着る選択もありましたが、やはりやや華やかな装束の方がよいと思い「紅無梶葉段模様唐織」を、後シテの腰巻は父たちが愛用した、今は少々生地が傷んでいる花色の縫箔に、水衣は浅黄色にしました。
面は「曲見」で、銘はなく、桜子の母、という感じの表情ではないのですが、とても評判の良い面なので、是非一度使いたく、敢えて『桜川』で使ってみました。案の定評判よく、面と装束の歴史に助けられた、とも思っています。
(平成30年6月 記)
写真
シテ 粟谷明生
ワキ 森 常好
子方 大島伊織
笛 藤田貴寛
小鼓 大倉源次郎
大鼓 亀井広忠
撮影 石田 裕
『卒都婆小町』を勤めて ひねくれ小町だから面白い投稿日:2018-03-07

『卒都婆小町』を勤めて
ひねくれ小町だから面白い
粟谷 明生

古は絶世の美女、歌に優れ、多くの男性に求愛され、華やかに生きた小野小町が、貧しく醜く、物乞いをするまでに落ちぶれ、百歳の姥になって老残を晒している。そんな小町を描く『卒都婆小町』を、「粟谷菊生十三回忌追善能・粟谷能の会」(平成30年3月4日、於:国立能楽堂)で勤めました。父が亡くなって12年、月日の流れがあまりにも早いと痛感します。
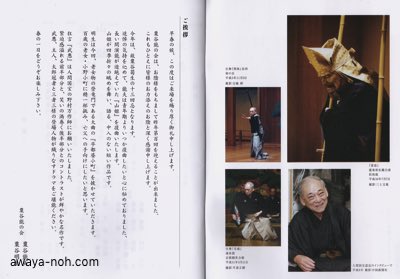
父が『卒都婆小町』を披いたのは68歳のときでした。老女物は60歳を過ぎないと手に負えないと言われる程の難曲ですが、いつかは挑んでみたいと思い続け、今回、未熟ながらも62歳にして、父の追善能で披くことができ、とても喜んでいます。
父が披く頃に、「この歳になると、老いた者が味わう諸々のことがわかってくるなあ」と話していたことを思い出します。私の披キは年齢的には父より早いですが、諸々の老いは恥ずかしながらもう既に感じ始めていて、そんな父の感慨が分かるようになってしまいました。今回、「父にお叱りを受けない『卒都婆小町』を勤めたい!」と臨みました。

今回、シテとして初めて老女物に取り組み、一番苦心したのは「老女の謡」です。
老女だから、と声量を下げて弱く小さな声では客席に届きません。かといって、大声で朗々と謡うわけにもいきません。静御前のような若い女の謡では駄目であり、弁慶のような強い男の謡とも違うのは当然です。特に前半の次第、サシコエ、道行の場面では笠をかぶっているので自分の声が耳に共鳴し過ぎて、どの程度声が響きどう届いているのかがなかなか分かりにくい状況を強いられます。しかもお囃子の掛け声と道具の音色が入ると、か細い弱い声ではかき消されてしまいます。
本番前に亀井広忠氏に観世銕之亟先生の老女の謡の教えを尋ねると「弱吟なれど強吟の息遣いで謡う、声を出すのではなく声は肉体の内面に負荷をかけた結果、洩れたもの、と心掛ける、と仰っていました」と教えてくれました。後日「次第、サシコエ、道行は呟くように文字を吐き捨てるように謡うんだとも仰っていました」と更に教えてくれました。
なるほど、と得心しながらもなかなか難しく、まだ体得出来ていない、のが正直なところです。私としては、役者自身の心技体の内芯を強く意識することで、柔らかな外面を持つ老婆が浮かび上がるのでは、と思って勤めました。

稽古しながら、小町の栄華と零落、あんなに美しかった人がこんなに落ちぶれて・・・、かわいそう、哀れ、と単にそれだけを描くために、観阿弥は『卒都婆小町』を戯曲したわけではないだろう、もっと何かがあるのでは、それは何なのかを掘り下げてみたくなりました。
道行が終わり阿倍野松原に着くと、小町は疲れて苦しいと、近くに横たわっている卒都婆に腰かけて休みます。すると、卒都婆は仏体色相のもの(仏の御姿とこの世を形作る五大、地水火風空を表したもの)、そんな大事なものを尻に敷くとは、けしからん、とワキの高野山の僧が咎めはじめます。ここからがシテとワキの論争、「卒都婆問答」となります。
(ここのやり取りは難しい宗教用語が多く分かりにくいので、石井倫子先生の現代語訳を参考にして、明生風に「お芝居風・卒都婆問答」を作ってみましたので、レポートの最後をご覧ください。)

ワキの咎めに対して、「卒都婆が仏体という謂れは?」「功徳というけれど、卒都婆の功徳って何?」と畳み込むように質問をし、私は「仏体と知っていたから近づいたのだ」「卒都婆も伏しているから私も休んで、何か悪い?」と屁理屈を並べ、ついには「悪も善」「煩悩も菩提」「仏も衆生も隔て無し」「愚痴の凡夫をこそ救ってくれるのが仏では?」と理屈をこね、論破する小町です。ついに、高野山の僧に「真に悟れる非人(乞食)なり」と頭を下げさせ三度礼をさせてしまいます。
この卒都婆問答は、観阿弥が高野山の真言密教と禅宗の理論的な戦いを小町にかぶせて面白く戯曲し、禅宗に軍配をあげています。
あれ、小野小町が生きた平安時代前期に禅宗がありましたでしょうか? もちろんまだ存在していません。小町にこのような問答をさせることには無理がありますが、敢えて、善悪不二、仏も衆生も隔て無し、すべては空である、という禅宗の宗教観を入れた観阿弥の戯曲・演出の才能のすごさが冴えます。
卒都婆問答で高野山の僧をやり込める小町は、老いても才気煥発、とても百歳の老婆には見えません。こんな元気な老婆に喝采する人もいるかもしれませんが、私は演じながらふと「イヤな老婆だな、こんな性格の老婆が近くにいたらイヤだろうなあ」と思ってしまいました。
博学ですが人を小馬鹿にしてしまう性格。ここでも僧を軽くあしらっています。自分の思うまま、自信に満ちて生きてきた傲慢で強い女、という人間像が詞章や動きから想像出来ます。
父が「こういうタイプが長生きするんだよ」と笑って話していたのを思い出します。

そして、老婆は遂に僧に頭を下げさせたうえ、駄目押しをするように、戯れ歌を謡います。
「極楽の内ならばこそ悪しからめ、外は何かは苦しかるべき」
(極楽の内ならば無礼をしてはならないが、外なのだから、卒都婆に腰かけて何の差しさわりがあろうか。)
と、極楽の外の意の「外は」と「卒都婆」をかけてダジャレにし、意気揚々と謡い上げます。
現代社会でも、お年寄りの中にはマイペースで、他人のことはどうでもいい、と振る舞われる方がいます。老々介護をしている人などは、こういう人が身近にいると、身に染みるのではないでしょうか。ですから能『卒都婆小町』は百歳まで生き抜いた小野小町の人生ドラマの一コマを描きながら、現代の高齢社会にも十分通じる作品になっています。決して陳腐なものではない、630年ぐらい前に、このような普遍的なものを作った観阿弥の戯曲力には感心させられます。
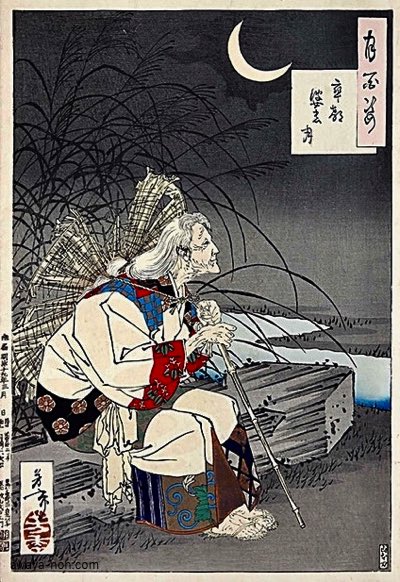
ところで、この「卒都婆(卒塔婆)」、どのようなものと想像されるでしょうか。
現在ならさしずめ、お墓の周りに立て掛けられている細長い板を思い浮かべるでしょう。しかし、能『卒都婆小町』の「卒塔婆」は人の身長を超えるほどの大きな木材の仏塔です。月岡芳年が描いた「卒塔婆の月」(東京都立図書館提供)に、老婆が尻に敷いているかなり大きな卒塔婆を見ることができ、参考になります。これが朽ちて横たわっているなら、そこに腰かけることもあり得ることで、容易に想像できます。
能ではその卒塔婆を、「鬘桶(かずらおけ)」と呼ばれる黒い円柱形の椅子を置くことで、演出します。歩き疲れた老女の小町がその卒塔婆に休もうというので、鬘桶に腰かける場面、これがシテにとって一つの難所です。被っていた笠を取り左手に持ち、右手で杖を突きながら鬘桶の前に行き腰かける。面の視野は狭く、後ろを振り向き確認できない状態で座ります。ここは父が以前コツを教えてくれていたので、それを思い出し、無事座れました。なにしろここでうまく座れないと大減点なので、気を抜けない箇所です。

卒都婆問答で論破された僧は、老婆がただ者ではないと思い、後世を弔うから名を明かせと尋ねます。すると「跡を弔ってくれるなら、恥ずかしいが名乗りましょう」と返答する老婆小町です。稽古していると先ほどまで小馬鹿にした相手に、弔ってくれるならばと、態度を急変させる節操のなさが気になりました。一体この老婆の信念はどこにあるのだろうか、やや不信感がつのります。それまでの成仏など眼中に無いと言わんばかりの物言いはなんであったのか・・・と。しかしこれも戯曲としての観阿弥の演出力、人間の弱さを見せたかったのだろう、と思って稽古を重ねました。
卒都婆問答はシテとワキの問答(掛け合い)でしたが、序のシテの名乗りからは、ワキの気持ちを地謡が代弁して、シテと地謡との掛け合いで舞台は進行します。古の栄華と今の境遇の悲惨さをシテは中央に下居して語り合います。

栄華と零落については、すでにシテの次第やサシコエで謡われていますが、ここではさらにリアルに今の落ちぶれた姿を語り尽くします。背負った袋には垢まみれの衣、破れ蓑、破れ笠、「路頭にさすらひ、往来(ゆきき)の人に物を乞う」乞食になった・・・と。栄華と零落を二度に渡り繰り返すのも、老いることの悲しさ、盛者必衰の理(ことわり)、人生の無常など、この曲に通底するテーマを作者は言いたかったのかもしれません。

そして地謡が「乞ひ得ぬ時は(誰も施しをしてくれない時は)悪心、また狂乱の心憑きて声変わりけしからず」と謡うと、突然「のう物賜べのう」(ねえ、何か頂戴よ、ねえ)と、僧の前に笠を裏返しに突き出し、なりふり構わず物乞いをする小町に変わります。そして遂に深草少将が小町に憑依し狂乱の体となり、後半へと続きます。

シテは物着で水衣を長絹にかえ、烏帽子を付け、深草少将が憑依した姿となります。ここが演者にとって、もう一つの難所です。男である演者が、取り憑かれた小町という老婆になりますが、同時に、取り憑いた深草少将という男の怨念をも、身体一つで表現しなければなりません。身は小町ながら少将に操られている心持ちで演じますが、その身体の使い方が難しいのです。
「私のところに百夜通ったら付き合ってあげるわ」という小町の揶揄い半分の言葉に、雨の日も風の日も雪深い日も、通い続け九十九日、あと一日というところで力尽きて死んでしまった深草少将。この無念ははかり知れません。その怨霊が、小町が悪心を持つたびに憑依し苦しめます。この作品の狙いは、少将を揶揄い死なせた悪事への報いなのか、はたまた、小町が悪心を持つたびに深草少将が鬼となり懲らしめにやって来る復讐劇とも、また逆に小町を守る守り神のように現れる、とも解釈出来、様々に想像出来ます。

一曲の最後、地謡が「怨念が憑き添ひて、かやうに物には狂はするぞや」と強く謡うと、一瞬静寂が訪れます。憑依が解けて少将が消え、格好は少将のままながらも元の老婆の小町に戻ったように演じなければ失格で、その気持ちと動きの切り替えの表現が難しく、しかし最大の見せ場となります。

これまで謡い囃していた舞台が静まり返り、空となる瞬間。深草少将が消え、これまでの物語がすべて消え、栄華も滅びも、恨みも喜びも、空となるほんのつかの間。やがて小鼓の掛け声の「ホー ホー」、そして静かに「ポン ポン」と打つ音が響くと、「これにつけても後の世を願うぞ誠なりける」(このような報いを受けるにつけても、後世を願うのが私のすることなのだ)と再び地謡が謡い出します。最後は「花を仏に手向けつつ、悟りの道に入ろうよ」と小町は手を合わせ祈り終曲します。この間の詞章はわずか4行、あまりに急転直下の終わり方です。
さて、ご覧になられた方はどう思われたでしょうか。
「小町さん、悟りの境地に入ろうとしたのね。よかったわ」
と思うのか、
「う?ん、小町さんは悟るのは難しいかもね」
と悲観してしまうか。

卒都婆問答で高野山の僧を論破する小町は宗教の教義をよく心得ているはずです。悟りの境地にならねばという気持ちの一方で、「でも本当に悟れるかしら」という不安な気持ちもあったかも。いやいやひねくれ小町のことだからそんなに急にお利巧さんになろうとはしないでしょう・・・などと二転三転します。その多面的な小町の裏の顔を覗かせるのが、作者・観阿弥のねらいだったかもしれません。私は、今でも答えが出せないでいます。
能はいろいろな見方があっていい。ご覧になる方が自由に想像してくださればいいのです。私もこのレポートを書きながら、小町の人柄、性格、人生に思いを馳せ、いろいろな見方ができることに気づかされました。現在物の能は、清純で美しく素直でソフトな能よりは、どこか角ばっていてひっかかりがあるものが魅力的です。
私は現在物の能に不思議と惹かれます。『卒都婆小町』の小町も嫌な性格の女だと思う一方で、そのひねくれ小町の複雑な心境が面白く、観阿弥の土臭く劇的、自由奔放な作品構成に惹かれ、遣り甲斐を感じます。能『卒都婆小町』はすべてが面白く、機会があればもう一度演りたいと思っています。

今回、面は「老女」を使いましたが、ただ優しいお顔の「老女」ではなく、私の演じたい小町は鼻っ柱の強いお婆さんでした。我が家の伝書にも「老女だが痩女が吉」と書かれています。もちろん「痩女」は死んだ女、霊になって登場する女にかける面で、現在物の『卒都婆小町』には不適なのかもしれませんが、どうしても「痩女」に近い「老女」が使いたくて、今回は、「老女」ながら痩女に近い表情のものを新たに能面師・石塚シゲミ氏に打っていただきました。今は落ちぶれ老いてはいるがそれなりに昔はきれいだったイメージ、口も達者な表情、と難しい注文をしましたが、自分では納得出来る面と認識し、感謝しています。
初めての老女物、いい時期にお披キが出来た、と思っています。老女物の型は一応決まっていますが、自由に創っていく余白の幅、遊び部分があります。これまで演能された諸先輩もこの余白、遊び部分を自由に創り、進化させてこられました。ただこの余白には基本的な技術が身についていない者が挑むとおかしなものが生まれる危険性もあります。
老女物は能楽師がこれまで積み重ねてきたものを糧に、自身で創り上げなければならないものと思っています。
小町はどういう人物なのか、指導者は教えてくれません。百歳の小町を自分自身で演出し演技しなければならないのです。シテ方能楽師は役者であり演出家です。そこが面白いところで、遣り甲斐もあります。自分で勉強し自分で創るもので、単に習うものではない。習ってもできるものではないのです。これまで培ってきたことを信じ、自分が感じるままに気負いなく自由に、そんな境地で老女物ができれば、と思っています。
今回は、ワキに朋友・森常好氏、囃子方は笛が松田弘之氏、小鼓が大倉源次郎氏、大鼓が亀井広忠氏、地頭にわが師・友枝昭世氏、粟谷能夫には副地頭を勤めてもらいました。
素晴らしい師と仲間たちが揃い、私を支えてくださったことに感謝します。
父の十三回忌追善能にこのような大曲、老女物を披くことができ、父へのよい手向けになりました。ご覧いただいた方々、支えてくれたスタッフ、すべての方々に感謝したいと思います。 (平成30年3月 記)
(補足資料/明生流訳「お芝居風・卒都婆問答」)
僧:「お婆さん、あなたが腰かけているのは仏体を形どった卒都婆ですよ。そこ、どきなさい!」
小町:「あら、仏体を形どっている、と仰っしゃいますが、もう文字も見えないから朽木と変わりないでしょ。」
僧「たとえ深山の朽木でも、花が咲く木はすぐにわかるものだ。まして仏を刻んだ卒都婆という木にしるしの無い訳がないだろう!」
小町:「私も賤しい埋れ木ですが、心の花は残っているよ。こんな私にも花があるんだから、私が座っている、という事は?、卒都婆に花を手向けている、という事なんだよ。
ところで、あなたが言う、卒都婆が仏体とは、どういうことかい?」
僧:「金剛薩?が人間に仏様の教えを示すために大日如来の誓いを形に表したものなんだよ!」
小町:「へえ?、どんな形なの?」
僧:「地水火風空、の五つ。万物の根本となる大事な要素なのだ!」
小町:「でもさ、人間も五大、五つの要素から出来ているから同じじゃないの?(笑い)」
僧:「形は同じでも心と功徳、功徳とは果報を得られるような善行のことですよ! それとは違うからね!」
小町:「じゃ?、卒都婆の功徳とは、なになのさ?」
僧:「一回卒都婆を見ただけで、永遠に畜生道、餓鬼道、地獄道の三つから逃れられるから有難いんだ!」
小町:「へぇ?、じゃあ、私だって言うよ。一念発起菩提心!!!
どうだい? 私だって一遍悟りを求める心を起こしたら、すごいよ。
たくさんの塔を作る事より、ずっと功徳があるはずだよ。卒都婆になんか負けやしないよ。」
僧:「じゃあ婆さん、菩提心があるなら、なぜ出家しないんだよ!」
小町:「してるわ、形の上ではなく、心でしているのよ。」
僧:「なに言ってんだよ、婆さん!
心が無いから、わからなくて卒都婆に腰掛けたんだろう?!」
小町:「違うわよ、仏体だと知っているから卒都婆に近づいたのよ。」
僧:「それならどうして拝まないで尻に敷くんだよ!」
小町:「どうせ倒れている卒都婆じゃないか。私も一緒に休んで、なにが悪いんだよ?」
僧:「それは順番が違う。まともなご縁の結び方になっていない!」
小町:「いいや、悪事がきっかけで出来たご縁だって同じことだよ。
だってあの極楽の提婆達多だって観音の慈悲で救われたし、愚か者の槃特も文殊の知恵と同じよ。
悪も善も同じで、煩悩だって菩提(悟った心)と同じ、菩提は菩提樹にたとえられるけれど、本当は植木のような物体ではないのよ。
澄んだ心は鏡と同じで台のようだと言うが、台に乗っかっているものではないんだよ。
すべてはね、空であり、実体はないんだよ!
そんな風に考えてみたら仏様も私達衆生も区別はないの。
あんたら順縁とか逆縁とか言うけどさ、元々は愚かな凡夫を救う方便だからね。逆縁だって救われるのよ、判ったかい?(笑い)」
写真
1 撮影 川辺絢哉
2 第101回 粟谷能の会当日番組より
7 添付資料 月岡芳年
14、15 撮影 石田 裕
その他 撮影 新宮夕海
能『蟻通』を勤めて ー 古い形を残した蟻通 ー投稿日:2017-11-07


能『蟻通』は古い形を今に伝えていて、能を観なれた方でも少し分かりにくい能であるかもしれません。実際、ご覧になられた方から「よく分からないうちに終わってしまいました」という感想をいくつか聞きました。そんな古風な能『蟻通』を喜多流自主公演(平成29年11月26日)で勤めました。
「古風な能」、「古風な感じ」「この能は分かりにくい」と言われる方に、私はこんな風に演能前にお話しさせていただきました。

蟻通神社の明神様(シテ)が、近頃和歌で人気の紀貫之(ワキ)が神社の前を通るようだ、ちょっと会って言葉をかけてみたい、一つ仕掛けてみようと待ち構えます。すると、貫之の馬が急に倒れ伏し、シテの仕掛けに見事にはまってしまいます。そして、神の心を鎮めるための歌のやりとりをして、その後、貫之は歌の徳や自身の業績を自慢げに語ります。和歌の力で馬が起き上がったと喜び、これもややご自慢で、今度はシテに祝詞をあげてほしいと要求します。シテは快く祝詞を上げますが、和歌自慢をする貫之に、そもそも神楽というのは日本のダンス(舞)や音楽の始まりですから、ほらよく見ておきなさいと、イロエを舞い、教えます。貫之は感心し、ともに舞歌を讃え、喜びを分かち合います。蟻通明神と貫之の、歌や舞をめぐる楽しいひと時、明神のいたずら心が描かれている、と思って観ていただけると、素直に面白く楽しめるのではないでしょうか、と。
能『蟻通』はワキ(紀貫之)からの視線で物語が展開していく演出になっています。
通常、ワキは登場して名乗り道行が終わると、ワキ座に座って、シテの舞を見たり語りを聞く役目ですが、『蟻通』は特異で、道行の後、馬が倒れる場面を動きある型で演じます。また、クセでは通常、シテが物語を語るのですが、『蟻通』では和歌の徳やワキ自身の和歌の業績までも語り、シテに聞かせる設定です。また通常は中入前に、ワキがシテにあなたは何者かと聞き、シテは○○の化身とほのめかして消えることが多いのですが、『蟻通』ではシテがワキに「如何なる人にて、わたり候ぞ」と聞いていて、これも特異です。クセの後半、馬が元気に起き上がる様子もワキが立ち上がり動いて見せるというように、いろいろな場面で、シテとワキの役割が逆転しています。

このようにワキが活躍する演出は現存する能では無い訳ではありませんが、稀少です。
私は稽古を重ねるにつれ、シテとして、なにか物足りなさを感じました。居グセなどは通常、地謡を聞きながらも、シテの思いを語り伝えるための心が入り、そこに微妙な心技の動きが生まれますが、『蟻通』では物語をただ聞くだけの受け身で、シテの気分は全く違います。

『蟻通』の作者は世阿弥と言われていますが、世阿弥の風が確立する前の古い作品ではないか、または演能記録があっても、それは好んで演じたのではないのでは、きっと世阿弥自身、演じて満足してはいなかっただろう、と稽古しながら勝手な想像をしてしまいました。そしてもしかすると、その物足りなさが、能の完成形ともいわれる複式夢幻能を創り出す要因になったのでは、と思い巡らしています。

では、その古風な能がなぜ今に伝えられているのでしょうか。
それはご覧になるお客様がご存じなのかもしれませんが、演者として感じたことは、演じる側の都合もあるのではないだろうか、能役者の成長の上で、ある年齢に到った者への練習課題曲(ドリル)というような意味合いがあるのでは、ということです。
若者では歯がたたない曲で、ある年齢になった人間が、この老人をどう解釈するか、どのような役割を持つ人間なのか、それをどう表現したらよいのかと探究しなければならない曲だと思えるのです。

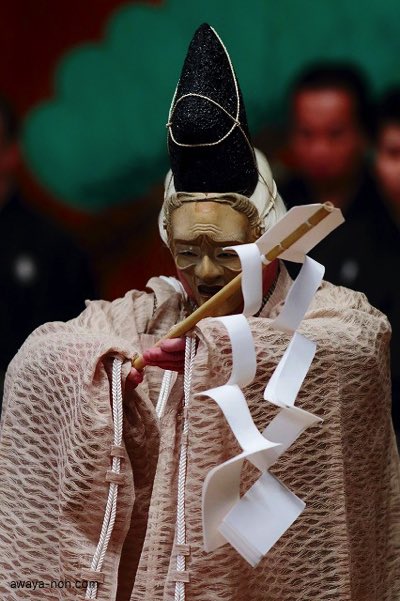

左手に傘を持ち右手に松明を振りながら登場するシテ宮人の佇まい。
「申楽談儀」に「能に、色どりにて風情に成ること、心得べし。蟻通など、松明振り、傘さして出づる肝要ここばかり也」とあります。この出で、宮人の風情を創り出し、雨が降る暗い神域を感じさせる謡い出しの「瀟湘の夜の雨、頻りに降って、煙寺の鐘の声も聞えず・・・」からのシテ謡が肝要で、口伝の謡です。雨が降っているとの状況描写から、蟻通神社が真っ暗で見えないのを嘆き、灯しの光も見えない、祝詞をあげる声も聞こえない、神職たちは何をしているのだ! 怠慢だ! と徐々に怒りがこみ上げてくる老いた宮人の声が客席に届くように謡わなくてはならず、私はここで既に蟻通の神が憑依していると解釈して演じました。

『蟻通』のシテが舞う「イロエ」は「舞」の基本となる非常に重要な動きです。
その動きは足拍子が入るものの、まず舞台を左回りに一巡し一区切りとし、さらに右回りして元に戻る、という二段構成のシンプルな舞です。初めてご覧になる方は、夢遊病者のような可笑しな動きと思われるかもしれません。
しかし、この一連の動きこそ、「我が日本国の最初の舞とはこうである!」と蟻通明神が宮人に乗り移って、申楽の能としての「舞」の原型を披露すると理解して演じました。

「イロエ」の動きに移る前に、シテは「神の岩戸の古の袖。思ひ出でられて」と謡いますが、これは天照大神の岩戸隠れの伝説の、天鈿女命(あまのうずめのみこと)が舞ったことが思い出される、と謡っていて、この時の舞が日本最初の舞といわれています。
申楽の能の舞は時代を経るに連れて複雑化していますが、はじめはシンプルな「イロエ」の2段構成からはじまり、それ以後の舞物の構成は、0段+5段の6段構成(喜多流)へと膨らんでいきます。ですから「イロエ」は舞の根本、ルーツです。そこを理解した上で、単純な動きであっても能役者は意識し力を注がないといけないのだと勉強しました。
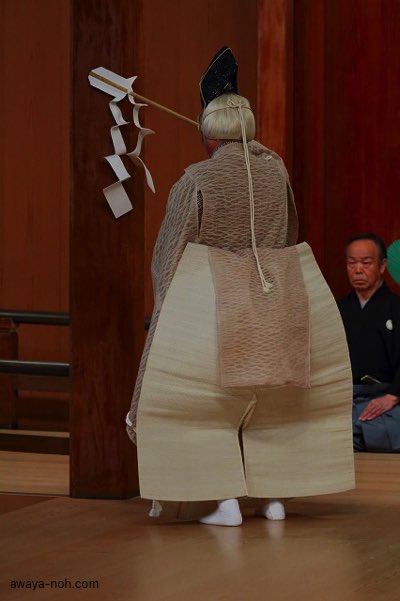

『蟻通』を勤める前は、ワキの貫之ばかり活躍して、シテとしては遣り甲斐のない曲かななどと思っていましたが、取り組み始めると、いろいろ面白い発見があり楽しくなります。
大切な謡いどころである最初のシテ謡「瀟湘の夜の雨・・・」は、静かに抑揚をつけてなどの教えはあっても、具体的に誰かに習って教えていただくというものではありません。もちろん過去に演じられたものなどを参考にできるのですが、『蟻通』のように喜多流であまり出ない曲の場合は特に、自分自身で「創る作業」が必要となります。ある年齢を過ぎたら、師に習うだけでなく、自分自身がどう能を創るかを考え、どう謡うかを創っていかなければならない??と知ることだと、今回特に実感しました。
実は次に勤める『卒都婆小町』にも通じることで、これは『蟻通』を勤めたお陰での、神のご褒美かな、と感じています。何でも真摯に取り組めば自らの演能の肥やしになります。
先代の観世銕之亟先生が「どんな能でもやればやるだけ面白くなる。でも終わるとすぐ次の曲が気になる、その繰り返しでいいんだよ」と言っておられたことが思い出されます。
そうなんだ、といま私も同感、この言葉が励みになります。
『蟻通』を面白く勤め、演能レポートも書き上げ、さあ今度は『卒都婆小町』(来年3月の粟谷能の会)と、今、気持ちはそこに向かっています。
写真提供 撮影 石田 裕
蟻通 シテ 粟谷明生 ワキ 殿田謙吉
(平成29年11月 記)
品川薪能にて(屋内で) 『船弁慶』を勤める投稿日:2017-10-07

品川薪能にて(屋内で)『船弁慶』を勤める
粟谷明生

(1)
品川区と十四世六平太記念財団(公益財団法人)の共催で、今回はじめて「品川薪能」が企画され、私が『船弁慶』を勤めることとなりました。(平成29年9月28日)
喜多流の本拠地、喜多能楽堂の最寄り駅は目黒ですが、住所は品川区上大崎です。ここ数年前より十四世六平太記念財団と品川区とのお付き合いも深まってまいりましたので、今後も、多くの区民の皆様に能に親しんでいただき、日本の古典文化を浸透させたいと思っております。
「薪能」は夜のしじまに幻想的に浮かび上がる能舞台のイメージで、初めてご覧になる方にも、長年能に親しんでおられる方にも興味をもって観ていただけるものです。「品川薪能」は区内にある「文庫の森」に特設能舞台を作り催す予定でした。野外にある能舞台を使うのと違って、特設能舞台は、その日のために敷舞台を組み合わせるところから始まるので、舞台作りがなかなか大変です。
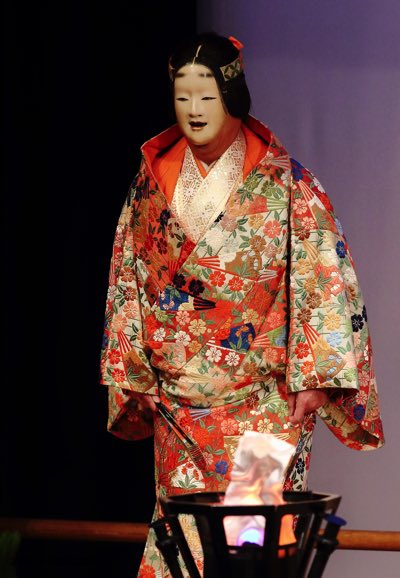
(2)
今回は、前日からの大雨と当日も雨が予想されたので、屋外ではなく屋内の「きゅりあん大ホール」での催しになりました。ご覧になった方からは「夜空の下での薪能を期待していたのに・・・」とのお声を聞きましたが、お天気ばかりはどうしようもなく、関係者一同、とても残念に思っております。来年は是非屋外での薪能となりますことを祈念しております。
「きゅりあん大ホール」での公演も「薪能」の様式にのっとり、火入れ式を行い、品川区長の濱野健様や六平太記念財団理事長の近衛忠大様、町会会長様に火入れにご参加いただき、屋内でも薪能の雰囲気作りをして、多くの皆様方にご鑑賞いただけた事を嬉しく思い感謝しております。

(3)
私の『船弁慶』は平家を滅ぼすに勲功があったはずの源義経が、兄・頼朝と不和になって西国に落ち延びようとする道中の話です。前場では愛妾・静御前(前シテ)との別れを描き、後場では義経や弁慶らを乗せて漕ぎ出す船に、平家の猛将・平知盛の怨霊(後シテ)が現れ襲い掛かりますが、最後、知盛の霊は義経との戦い、弁慶の祈祷に負け、波間に消えていきます。変化に富み、物語もわかりやすく、楽しく観ていただけたのではないでしょうか。


(4) (5)
今回は解説、『三番叟』、『船弁慶』、それに「火入れ式」と休憩を入れて、およそ2時間半が夜の能公演の適当な時間だと考え、『船弁慶』の上演時間を1時間5分ぐらいとしました。
特に夜の公演はダラダラと長くなるよりは、やや短くても十分楽しんでいただけるものにしようと、コンパクトな演出を心がけました。


(6) (7)
前場では、囃子事を短く、動きのない場面は省き、序之舞の段数も減らすことで、物語の展開がテンポよく進むように工夫しました。


(8) (9)
後場は、本来「早笛」という出囃子の後に後シテ(平知盛の霊)が本舞台にて「抑々これは桓武天皇九代の後胤・・・」と名乗りますが、今回は、囃子方に特別演出をお願いして、地謡の「一門の月卿雲霞の如く。波に浮みて見えたるぞや」の謡で後シテが橋掛りの三の松前に登場し「思ひも寄らぬ浦波の」と恨みを述べると、途端に早笛になり舞台に入る演出として、地謡の「声をしるべに出で舟の」で足音を立てない足拍子「波間之拍子」を踏み、最後は地謡に緩急を付けて勤めました。
コンパクトな演出とはいえ、全体としては、序、サシ、クセも省かず、詞章で省略したのは初同のみ、細部を工夫することで一曲を飽きずにご鑑賞いただけるようにいたしました。


(10) (11)
シテを演じる時、静御前と平知盛という前後で別人格を演じるところが難しいように思われますが、実はさほど気にせずに勤めているのが能役者の実態です。それよりも若いころは前シテの静御前をしっとりと、それでいて艶もあり、別れの辛さに耐える姿を表現することに苦心します。年を重ねると後シテの勇壮で活発な動きが難しくなりがちです。私も初演の時は前場の静御前が難しいと感じましたが、今は前シテよりも後シテの活発な動きが出来るか、と心配します。その一つに「流れ足」ができるかがあります。


(12) (13)
「流れ足」とは、曲の最後、弁慶らの祈りに負け、引く汐に揺られ流されと退散していくときの所作で、勇壮に戦っていた薙刀を捨て、太刀を背に両手を上げて、つま先で立って横に動く型です。ちょうどバレリーナのトウシューズでのつま先立ちと同じです。これは足の指の力が必要で、若いときにはいとも簡単にできたのですが、悲しいかな年齢とともにきつくなります。今回は、まだ何とかできるだろうと演じてみて、無事勤めることができましたが、終わって、あと何回出来るだろうか?と思いました。その意味でも、今回の『船弁慶』を無事に勤めることが出来たことを喜んでおります。


(14) (15)
私は最近、最後の幕に入るときに拘りを持って演じています。それは最後まで義経を見ながら後ろ向きに入幕すること。義経役のかわいい子方が活躍し、観客の目はそちらに釘付けになっているでしょうが、知盛としては、後ろ向きで義経を睨みつけることで、「このままでは済ませないぞ」という深い恨みを滲ませます。終曲の詞章は「跡白浪とぞなりにける」ですが、ただ何事もなかったように終わるのではなく、悪霊の執心と粘りを観客の心にも焼き付けたいのです。
実際、その後の義経は、平家一門の怨念のためか、舟は嵐によって元に戻され、西国行きを断念、陸奥の平泉への逃避行となります。それはまさに義経滅亡の旅、死出の旅です。知盛の霊を退散させ、勝った勝ったと能は終わりますが、その後の義経の運命は決して明るいものではない、と予感させるような、最後の知盛の粘りを舞台で演じたいのです。
能『船弁慶』は観世小次郎信光の作品です。信光は世阿弥の甥の音阿弥の七男ですから、世阿弥よりだいぶ後の世の人です。世阿弥が幽玄な能を完成したのに対し、劇的なエンターテイメント性の高い能を創り出しました。『船弁慶』のほかには『道成寺』、『安宅』、『紅葉狩』など人気曲があります。いずれも劇的でわかりやすく、登場人物も多くにぎやかに展開し、心躍るものです。
初めて能をご覧になった方は、ここを入口とし、世阿弥の幽玄な能や観阿弥の土臭く芝居的な能、あるいは美しい女人の能から武将、怪異な鬼の能に至るまで、能にはさまざまに変化に富んだものがありますから、それらに分け入って楽しんでいただきたいと思います。
また、今回はホールでの観能になりましたが、能楽堂にも足を運んで、その雰囲気を味わっていただきたく、もちろん「薪能」も機会があったら、と欲張りなお願いです。
今回の品川区との共催のように、能鑑賞の機会をできるだけ増やすべく、努力して参りたいと思っています。多くの皆様の能公演へのご来場をお待ちしています。
(平成29年10月 記)
写真 シテ 粟谷明生
撮影 (1)(3)(6)(7)(9)(10)(13)(14) 新宮夕海
(2)(4)(5)(8)(11)(12)(15) 石田 裕
『小督』という曲で シテ・仲国を描く投稿日:2017-09-07

『小督』という曲で
シテ・仲国を描く
粟谷 明生

『小督』は曲名にもなっている絶世の美女、小督の局がシテではなくシテツレとして配役され、シテは帝からの使者役、源仲国を演じます。
仲国は史実に従うと皇宮警察の部長といった役職の人で60歳近い老人! と「能楽手帖」(権藤芳一著)に書かれています。国立能楽堂からの出演依頼が来たときには、「直面物であまりお爺さんでは似合わないから、今ならばまだ間に合う大丈夫だろう」と快諾しましたが、もしかすると国立能楽堂の担当者は「粟谷明生は60歳ぐらい。『小督』を依頼するには丁度いいだろう」と考えたかもしれません。適齢期? 老人? とやや複雑な心境での稽古となりました。ここから9月15日国立能楽堂で勤めた『小督』についてレポートします。
能『小督』は平安時代後期の話。高倉帝の深い寵愛を受けていた小督の局は、平清盛の娘、徳子が中宮に立つと、平氏の権勢を恐れて宮中を去ります。
これを知った帝は日夜お嘆きになり、「小督が嵯峨野のあたりに身を隠している」「片折戸の家に住んでいるらしい」という噂を聞くと、仲国に小督を探させます。
折から八月十五夜。小督は琴の名手。名月に惹かれて琴を弾くだろう、仲国は帝から拝領した馬に乗り、琴の音を頼りに探しに出かけます。

仲国という人物像はどういうものであったか。高倉帝としてはある程度の年齢で信頼できる人間を使者としたかったでしょう。あまり若く美しい男性が小督のもとに行ったのでは、何か間違いでも、と心配です。仲国は若くなくしかも楽人で笛の名手、昔小督と合奏したこともあり、小督の琴の音色も知っている。「片折戸」に住むという庶民の暮らしも分かっている者ならば、きっと小督を探し当て誠実に使者の任を果たしてくれるという信頼が帝にはあったのでしょう。琴の音、秋の夜空、駿馬に乗って出かける美しい風景を、能は描いています。

能『小督』は美しい小督の人生を描くというよりは、あくまでもシテである仲国の心境や行動がメインになって展開していきます。
その場面展開を、序破急の構成で説明しますと、序は前場のごく短い場面です。ワキ(勅使)が仲国の私宅を訪ね、小督の局の行方を尋ねて参れとの帝の宣旨を伝えると、仲国は「今夜は八月十五夜、名月の夜だから、きっと琴を弾かれるだろう。小督の局の調べはよく聞き知っているから、安心してください」と引き受け、探しに出かけます。ここまでが序にあたります。
破は三段構成になっていて、一段目はがらりと場面を変え、小督の住む嵯峨野の隠れ家。小督は秋の夜、琴を弾きわびしい心境を謡い、侍女たちと語り合っています。
二段目は一声によるシテの登場から、名月の夜、仲国が嵯峨野に馬を馳せ巡らせ、法輪寺のあたりでかすかな琴の音を聞きつけ、その音を頼りに小督の局を探し当てる「駒の段」と、そして面会を果たし、帝の文を届け、小督も感涙し仲国に返事を伝え、酒宴となるところまでを描きます。
三段目は名残りを惜しむ男舞。
そして最後の急は、キリの仕舞を舞い、小督が見送るなか、仲国は帰っていき終曲するまでです。
中入り後、破の一段目で片折戸と柴垣の作り物が舞台上に運ばれます。片折戸の両脇に5つの柴垣が連なる、作り物としては大掛かりなものです。他の作り物のように、公演のたびに能楽師が作り運び込むのは難しいので、各能楽堂には、この一曲のための作り物が作り置きされています。今回も国立能楽堂の作り物を使わせていただきました。

この作り物は小督の家と嵯峨野の当たりの景色を想像させるに効果的なもので、鑑賞する手助けになっています。
作り物を、喜多流は舞台中央より脇座寄りに置きますが、宝生流は舞台中央、観世流や金春流は舞台中央より脇正面側に配置し、各流儀で違います。破の二段目、仲国が登場し駒の段を舞うときに、喜多流は舞台に入り舞うため、作り物をシテツレ側に置き、舞うスペースを広くしているのです。他流は駒の段を橋掛りで舞うため、作り物が舞台中央よりやや脇正面側でもよいわけです。作り物一つ置くだけでも、それぞれの流儀の主張があります。
今回、申合せで喜多流の基本を守りながら、作り物をどのあたりに置くのがよいか、出演者で意見を出し合ってみました。伝書に書かれたやり方では片折戸が正面から垂直になりよく見えないので、やや斜めにして、観客席から戸がよく見えるようにしてみました。能楽は「昔通り」を頑なに守っているように思われがちですが、決してそうではなく、今に合うやり方をいつも考えているのです。

駒の段のあと、宣旨の使いが来たと知っても、最初はなかなか取り合わない小督ですが、供女のとりなしでようやく対面することになります。仲国が小督の宅に入ることを許されると、片折戸と柴垣の作り物は舞台から運び出され、舞台は小督の宅となります。

さて、話をシテ登場の場面に戻しましょう。
破の二段目は、一声でシテが登場すると、「駒の段」(牡鹿鳴く此の山里と?想夫恋なるぞ嬉しき)となります。仲国が馬を走らせ、嵯峨野あたりから法輪寺を過ぎ、そして最後は想夫恋の琴の音が聞こえ小督の家を探し当てるところまでを「駒の段」と呼び、謡い舞う、聞かせどころ舞いどころとなります。シテは馬の手綱を両手で持ち、馬を一時止めては耳を傾け、琴の音を聴く型が続きます。それ自体は難しい舞というわけではありませんが、馬に乗って琴の音を聴いていると観客に思わせるのがなかなか難しいところです。しかも直面ですから顔に表情をつけることもできず、自然と役者の顔が面に見えるようになるには、稽古だけでは作れない時間が生む、という父の教えが思い出されます。

駒の段の最後、琴の音が聞こえてきて、まさしくそれは小督が弾く想夫恋と気づくところの謡、「峰の嵐か松風かそれかあらぬか。尋ぬる人の琴の音か、楽は何ぞと聞きたれば。夫を想ひて恋ふる名の想夫恋なるぞ嬉しき」は、なかなかの名調子、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、黒田節の二番と被っています。
「酒は飲め飲め飲むならば 日の本一のこの槍を 飲み取る程に飲むならば これぞまことの黒田武士」は、おなじみの黒田節の一節ですが、二番は「峰の嵐か松風か 訪ぬる人の琴の音か 駒引き止め立ち寄れば 爪音高き想夫恋」です。もちろん黒田武士と源仲国の関連は毛頭ないのですが、ちょっと気になりましたのでご紹介しておきます。

小督の宅に入れてもらい、仲国は帝からの文を渡します。そこには小督への想いの言葉が書き連ねてあったでしょう。小督は喜び泣きながら返事をします。観世流は実際に返事を「お文(ふみ)」として手渡しますが、喜多流は「直(じき)の御返事賜り」と「文」ではなく、言葉でのお返事と解釈しています。もし清盛に知られることになっては困る言葉が形として残ってはいけない、仲国を信頼してのお返事、と解釈して演じました。

そして破の三段目、男舞となります。通常、男舞というと颯爽とした武士の舞ですが、ここは颯爽と、とはやや風情が違う舞になります。小督を探し当てることはできたが、今後どうなるかわからない。が、酒宴となれば舞は付き物、小督への慰めの気持も込めて仲国は舞います。明るく晴れやかな祝言の舞ではない、若者の颯爽としたものでもない、そこを意識し、落ち着いて、やや速度を緩めて舞うのが心得です。囃子方にもゆっくり囃していただき気持よく舞うことが出来ました。
後シテの装束は、着付は鬱金色の厚板に淡い浅黄色の大口袴、そして花色の長絹にしました。替装束で、やや位の高い風情となる狩衣・指貫の選択もありますが、仲国が皇宮警察の部長さんとなれば、太刀を差しているので、従来通り、大口袴と長絹にしました。

小督については、平家物語で後日談があります。
高倉帝はその後小督の局を秘かに内裏に迎え、親王(範子親王)も生まれます。しかし、すぐに清盛の知るところとなり、小督は帝から引き離され尼にさせられてしまいます。それを悲しみ高倉帝は間もなく亡くなられます。小督という美しい人には悲しい人生の結末が待っていたのです。
平家物語は清盛の非道さを際立たせ、ゆえに滅びに向かうという、その物語の流れの中に、高倉帝と小督の悲劇をドラマチックに描いていて、その描写が史実かというと定かではありません。しかし小督という女性は実在し、尼となって生きたということは事実のようです。
能『小督』は小督という女性の人生を直接描いたものではなく、その後の小督がどうなったかも記していませんが、そのような数奇な運命をたどった人なのだということを心に止めて鑑賞すると、また違う深味も出てくるのではないでしょうか。
シテ方にとってよい能を作るにはシテとツレとの配役のバランスが大事です。
例えばシテがいくら立派でもツレが未熟だとよい能になりませんし、逆でももちろん然りです。
両者には充実した謡と型の力量が求められます。私が『小督』を披いたのは平成2年4月、厳島神社桃花祭の神能のときで、34歳でした。私が30代でしたので、ツレは当然私より若い20代の粟谷浩之君と友枝雄人君でした。この時はまだ能としての作品を深く考えず勤めていたなあ、と反省しています。もちろん、能楽師は将来のために、若いうちにいろいろな曲に挑んでいなければいけないのですが、本当に曲の深さがわかるのはやはり似合った年齢での再演なのかもしれません。老女物は一生に一度きりということもあるでしょうが、それ以外は早めに挑み、それを深めるのが肝要です。

私が『小督』を披いて30年近くが過ぎ、今回の演能は、私(シテ)が61歳、ツレ(小督)が佐々木多門氏45歳、供女の大島輝久氏が41歳でした。もちろん年齢だけでなく、芸力が大きく左右しますが、丁度良い配役、それぞれが役柄に似合った謡を謡い込め、ツレだけでなく、三役も、そして関わってくださった方々すべてが、「大人の舞台作り」にご協力いただいたことに感謝しています。ただ、ご覧になった方から「粟谷さん、お若い、とても60歳の老人には見えませんでした」というお声を聞き、「いや60歳ぐらいの老人に見えなくてはいけないのだが・・・」と素直に喜べない複雑な心境となったことも事実で、「もう少しお爺さんになってまた、もう一度勤めないといけないのかな・・・」などと感じた『小督』となりました。
(平成29年9月 記)
写真提供 石田 裕
写真 小督 シテ粟谷明生
『忠度』の執心 ー 桜に事寄せて描く ー投稿日:2017-07-07

『忠度』の執心
–桜に事寄せて描く–

(新宮夕海)
私の能『忠度』の初演は平成7年3月5日(粟谷能の会)でした。それから22年、今回、平成29年6月25日、喜多流自主公演において再演しました。
狂言にも忠度を扱った『薩摩守』という曲目があります。出家僧が茶屋の代金を払わないで出ようとするので、亭主が咎めますが、もちろん僧は無一文。あわれに思った亭主は、この先、渡しで困るだろう、そのときは船頭が秀句(しゃれ、軽口)が好きだから、船賃を請求されたら「薩摩守!」と言い、「その心は?」と問われたら「平家の公達、忠度」と言えばいいと教えます。良いことを聞いたと勇んで船に乗る僧ですが、「その心は?」のあとの「薩摩守」を忘れて「青海苔の引き干し」と答えてしまい、船頭に叱られて退散するというお話しです。このしゃれは言うまでもなく、忠度にただ乗り(無賃乗車)を掛けたものであり、青海苔は忠度のうろ覚えで咄嗟に出た言葉です。こういうしゃれや掛詞を、昔の人は好み、和歌や能にも多用されています。
私も高校生のころ、『忠度』の舞囃子を舞うことがあり、父に『忠度』について尋ねるとすぐ「薩摩守、ただのり!無賃乗車」と笑顔で返してくれた父の顔を思い出します。

(石田 裕)
能『忠度』は平忠度が自分の和歌が千載集に入ったが、名が載らず、「詠み人知らず」になったことへの不満、執心をテーマにしています。
千載集に入った歌は、「漣や志賀の都は荒れにしを 昔ながらの山桜かな」です。
文武二道に生きた忠度は、一ノ谷の戦いに出向くとき、この戦が自分の命の最後と覚悟を決め、和歌の重鎮・俊成卿に自らの和歌を託して出かけます。自分の命は尽きるとも、和歌と共に名を残したいという一縷の望み。しかしその後、忠度が朝敵ゆえ名前を載せるわけにはいかないと「詠み人知らず」になってしまいます。その無念で、忠度は妄執の世界を彷徨うこととなるのです。ここに焦点を当てたのが世阿弥です。
もし「漣や・・・」の歌に「平忠度」と名があったら、世阿弥は能『忠度』を創作しなかったかもしれません。名前が載らなかったことで逆に、こうして名前が残る、大いなる皮肉です。

(新宮夕海)
ところが、能『忠度』には千載集に入った「漣や・・・」の歌は一度も出てきません。
一曲に流れるのは、忠度の辞世の歌、「行き暮れて木の下かげを宿とせば 花や今宵のあるじならまし」ばかりです。
千載集に入ったが「詠み人知らず」になったというエピソードを物語の中心に据え、和歌への執心をテーマにしながら、辞世の歌にある桜の木に事寄せて美しく創り上げた世阿弥のセンス、その良さが光ります。
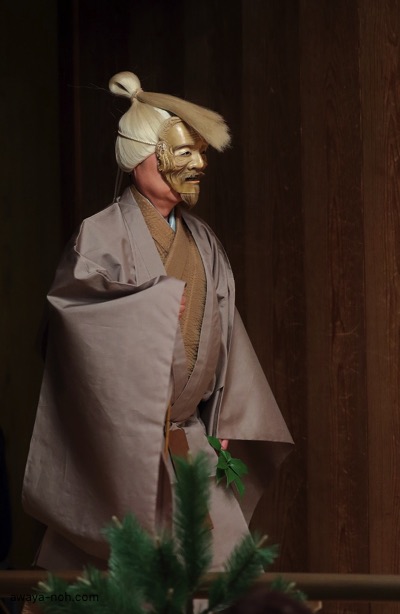
(石田 裕)
舞台は、俊成卿にゆかりのある旅僧(ワキ)が津の国須磨の浦にやって来るところから始まります。ワキは一本の桜の木を見つけ、そこに樵翁(前シテ・忠度の化身)が現れて、この桜はある人の跡のしるし、手向けにやって来ていると語ります。舞台上には桜の木があるわけではありませんが、ワキとシテの謡を聴きながら、正面席中央あたりに桜の若木があると想像してご覧になっていただきたいのです。簡素な舞台装置で観る人に想像していただく、これが能の演出方法です。

(石田 裕)
やがて日が暮れ、旅僧は一夜の宿を所望します。
シテ:「お宿ですね。参らせましょう。や、この花の蔭ほどの宿があるでしょうか」
ワキ:「花の宿というなら、誰を主と定めたらよいのでしょう」
このワキの質問に、シテは力強く「行き暮れて」と謡い「花や今宵の主ならまし」と詠じた人がこの木の下に眠っている、ここで仮寝をしたらいい、そしてこの主を弔ってほしいと言い、自分はその主であるとほのめかして姿を消します。老人の思いが次第に強く変わっていく様をどれだけ見せられるか、が演者の力量を測るところと思っています。

(新宮夕海)
後場は、桜の下に仮寝をする旅僧の夢に忠度の霊(後シテ)が現れ、和歌への妄執と一ノ谷の合戦での最期を語り、最後は「木陰を旅の宿とせば、花こそ主なりけれ」の地謡に合わせ、桜を見ながら袖をかついで一曲は終わります。
平家の武将をシテとしながら修羅能的な要素は少なく、花に添えた優美な作りは、なかなかない戯曲ですが、やり甲斐のある曲で、能楽師であれば憧れる一曲です。
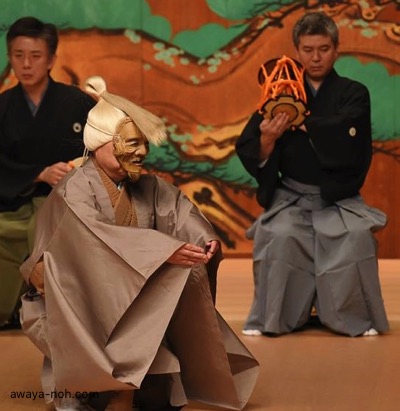
(新宮夕海)
能『忠度』は各流儀、多少の演出の違いはありますが、小書というものがありません。つまり、世阿弥の渾身の作で、非の打ち所がないということです。時間の都合でどこかを短縮するなどということが出来ない、手の入れようがない作品です。演者はこの優れた戯曲をいかに観客に届けるかに苦心しなければいけないようです。
『忠度』のシテ謡は前後共に一声です。前シテは「げに世を渡る習とて、かく憂き業にも懲りずまの・・・」と強吟の強い息ではじまり、途中からわずかにやわらかい和吟が入り、また「そもそもこの須磨の浦と申すは・・・」で再び強吟に、と強吟と和吟が入り混じっています。ここの謡い分けが難しく、忠度の文武両道に秀でたものの性格をにじみ出させているのかもしれません。あるときは強い武将らしさ、あるときは風雅な和歌を愛する優美さ、やさしさを謡で表現するのが能らしい演出と言えます。
後シテの一声には忠度の言いたいことすべてが込められていて、この曲の最も大事な謡いどころです。中でも「詠み人知らずと書かれしこそ、妄執の中の第一なれ」ここを最も強い気持ちを込め、強い意識で謡う、これが先人からの教えです。
強吟と和吟の入れ替わりは技法的にも難しく、強さが乱暴にならず、また和吟が浮わついてもダメで、その微妙な加減を音を外さずに謡い分けるコントロールが大事で、演者の力量が測られるところでもあります。
能『忠度』はとりわけ、修羅物の中でも謡が難しい部類に入る曲だということを、今叉再認識いたしました。



(新宮夕海)
後場の見どころの一つに、一ノ谷の合戦でのワンシーン、仕方話で繰り広げるところがあります。忠度と岡部六弥太、郎党たちとの壮絶な戦い。忠度は右手を切り落とされ、それでも六弥太を投げ飛ばし果敢に戦いますが、遂に観念し西方極楽浄土に向かい念仏を唱え首を討たれ最期を迎えます。六弥太は忠度の箙にある短冊をつけた矢を見つけ、相手が薩摩守忠度であることを知ります。この合戦シーンをあるときは忠度、あるときは六弥太等と、シテ一人二役を演じます。最初は忠度自身を演じ、「六弥太太刀を抜き持ち」から六弥太となり、「行き暮れて・・・」の歌を朗詠するところからまた忠度に戻ります。役柄とその心を入れ替えて演じます。
「よく、一人で両方ができますね」などと言われますが、演者達は若いころから舞囃子などで何回も稽古しているうちに、自然と体にしみ込み慣れてしまい、さほど手ごわい感じを持ちません。もちろんその慣れが危険性も含んでいるので、充分気をつけなくてはいけないのです。
今回の面はすべて粟谷家所蔵の面を使用しました。
前シテが「三光尉」(友閑作)で、後シテは「中郎将」と記載されている作者不明の「中将」です。忠度にはぴったりと思い、迷いなく最初から決めていました。
後シテの装束は「紅白段山道模様毘沙門亀甲輪宝熊笹」の厚板を着付に選びました。
これには拘りがありました。実は、昔伯父の粟谷新太郎が着ていたのを見て、いつか自分も着たいと憧れていました。先人たちの演じる曲や装束を見て、いつか自分も、と、憧れを持つことは能楽師にとってとても大事なことだと思いますし、また後輩たちからもそう思われるような能楽師を目指したい、と思っています。今回、一つの望みが叶いました。
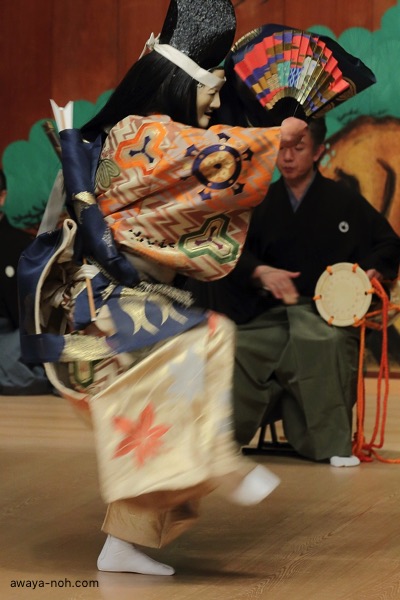
(石田 裕)
そして常は長絹を着ますが、今回は替えとして「単衣法被(ひとえはっぴ)」にしました。仕立ては長絹とほとんど同じですが、長絹が胸元と袖下に「露」を付けるのに対し、単衣法被は付けません。長絹の雅モードより、やや甲冑モードで勇ましさを出したいと思い試みてみました。
さて22年ぶりの『忠度』、当時を思い出しながら稽古をしました。私の師は友枝昭世師ですが、何曲か父が絡んで教えてくれたものがあります。『忠度』もその一つで、父の言葉が蘇ります。
たとえば、忠度が狐川より引き返し俊成卿の家に行き、百余首の歌を書いた巻物を託し、一首なりともとってほしいと嘆願するエピソードを語ったあとです。
「又、弓箭にたづさはりて。西海の波の上、と正面への一足シカケ、これは丁寧に大事にね。歌を詠んで楽しんでいたのに、こんな戦になってしまって、と強い憤りの気持ちを込めてシカケるんだよ」の父の言葉は印象深いです。歌への思いを振り払い、武士として戦場に赴く忠度の姿を描き出します。
そして「暫しと頼む須磨の浦。源氏の住所(すみどころ)。平家の為はよしなしと、知らざりけるぞ儚き、これ明生、分かるか?」に、きょとんとしていると、「須磨の浦は源氏の居場所で平家の居る所じゃないんだよ。この源氏は光源氏のことだからね。」
てっきり「源氏の住所」は源頼朝や義経の源家のことだと思っていた私には、衝撃が走りました。「須磨といえば光源氏!」とすぐに思い浮かばなければいけないのです。
須磨は源氏に縁のある土地、平家の土地ではない、と作る世阿弥の戯曲の上手さ。
前シテの一声でも、「わくらばに問う人有らば須磨の浦に藻汐垂れつつ侘ぶと答えよ」という、能『松風』にも使われている在原行平の歌を引いて須磨の浦の寂しさを謡い上げています。世阿弥は一ノ谷の合戦があった須磨の浦という土地柄に思いを馳せ、源氏物語や行平の歌をも重ね合わせ、和歌の名手・忠度の物語にふさわしい戯曲を創り出したのです。

(新宮夕海)
二十数年前は何も考えていなかった、何も分かっていなかったと、わが身を振り返ります。今ようやく世阿弥が創り出した世界、宿の主として人を包み込むような大きな花、辞世の歌を詠んだ短冊、人生のさまざまな出来事、うまい道具立てをぎっしり詰め込んだ『忠度』、戯曲の意図するところが少し分かるようになってきたと感じています。

(石田 裕)
だからといってそれが表現できるかというと難しく、手こずっています。
説得力ある伝わる謡を謡いたい、と心がけていますが、無念の思いには繊細なものと粗野でゴツゴツした部分もあるだろう、などと考えて稽古したり・・・。しかし考えずとも自然に忠度になれるのが本物、それは判っているのですが、まだまだ道は遠いと思いました。 (平成29年7月 記)
写真『忠度』シテ・粟谷明生
撮影 新宮夕海 石田 裕
『三輪』を勤めて ー 神々のちょっとエッチで面白い話 ー投稿日:2017-05-07


撮影 潮 康史
『三輪』を勤めて
–神々のちょっとエッチで面白い話–
広島蝋燭薪能(2017.5.15)にて『三輪』を勤めました。広島蝋燭薪能はこれまで、二年連続雨天のため屋内のアステールプラザ能舞台での演能でしたが、今回は三年ぶり快晴のもと、広島護国神社の特設能舞台にて催すことが出来ました。ご覧いただきました方々より、「少し寒くはありましたが、やはり屋外の方が雰囲気、空気感がよいですね」とのご感想をいただきました。

撮影 潮 康史
『三輪』は初番目物(脇能)にも四番目物としても扱える曲です。さほど難しい内容ではありませんが、三輪山の祭神、ご神体が男神でありながら、女姿で物語を進行させるところに、能独特の演出マジックがかけられているのではないでしょうか。
能『三輪』は一寸エッチな部分もある面白いお話で、能楽師にとってやり甲斐のある曲のひとつであると思います。

撮影 石田 裕
そのエッチな部分とは『三輪』のクセの部分にあります。いわゆる三輪の神婚説話のくだりです。
「されども此の人、夜は来れども昼見えず、或夜の睦言に御身、如何なる故に因り、かく年月を送る身の、昼をば何と烏羽玉の夜ならで通い給はぬはいと不審多きことなり」
この「此の人」とは男、三輪の男神です。男は里女のところに毎夜通いお楽しみになり、女もまんざらではなさそうで、夜だけじゃなくて昼にも来てよ、とおねだりします。男は昼は恥ずかしいから、だめ、と拒否しますが・・・。女は通ってくれる男の正体を知りたく、男に糸を付けてその住処を探そうとすると、その糸は杉の下へと垂れて・・・。
「糸、繰り返し行くほどに。この山本の神垣や、杉の下枝に止まりたり。こはそも浅ましや、契りし人の姿か」。そこで見てしまったものは、蛇でした。
「私のお相手は蛇?」とビックリするのは女だけではなく、お話の内容がよく理解出来ているならば、私たち観客もきっと驚いてしまうのではないでしょうか。

撮影 石田 裕
ただ、能の詞章には「蛇」という言葉はなく「羽束師の(はずかしの)」姿ほどの表現ですが、もとになる説話から蛇とわかる仕組みで、しかも、男の正体は三輪明神とも知らされるのです。
話は少し逸れますが、私は伊勢神宮の神、天照大神は女神だと思っています。が、江戸時代の喜多流は神が女であることを嫌い、天照大神を取り上げた『絵馬』を男神の演出としました。但し、今は「女体」の小書が付くと女神として演じることが許されています。喜多流の普通の『絵馬』は天照大神が女神だと思っている私には理解に苦しむ設定で、多分普通の演出の『絵馬』は今後勤めることはないでしょう。

撮影 潮 康史
さて神々が男であるか女であるか、また三輪は伊勢の元であるとの説も一旦置いておいて、ここからは能『三輪』をご鑑賞になる手引きとしてお読みいただきたいと思います。
男の神が里の女のところに通うことや、実は自分が蛇でもあることなど、また天照大神になりかわり、岩戸隠れの有様を紹介することも、すべてシテが女姿で演じます。この手法が、お話を理解しづらくしている一方で、逆に不思議な演出効果をあげ、いかにも能らしい演出の特徴となり、魅力となっていると思われます。

撮影 石田 裕
後シテの装束は確かに女姿ですが、金風折烏帽子を付け男の風情をにじませ、里女でもあり、通ってくる男神(三輪明神)であり、女神(天照大神)でもあって、観る人を靄(もや)がかかった神域へと誘っていきます。また、後シテの面は通常「小面」ですが、今回は試しに「増女」で演じてみました。一寸、エッチなお話に純粋で可愛い「小面」の表情よりは、大人びて神々らしい「増女」の方が似合うのではないだろうか、と考えて勤めてみました。

撮影 石田 裕
能『三輪』のもう一つの見せ場は神楽とその後に展開される天照大神岩戸隠れの場面です。天照大神が岩戸にお隠れになってしまったため、世の中は真っ暗闇となり、困った神々は相談して岩戸の前で歌い踊り、楽しげに騒げば、「なにやら外で面白そうな事がありそう」と天照大神が岩戸から顔を出すだろう、その時、力持ちの手力雄命(たぢからおのみこと)が岩戸を開けてしまえばいい、との作戦を立てます。作戦は見事に当たり、戸は無事開き、また日が差して世の中は明るくなり、神々の面が白く見えたので、「面白い!」となった、というわけです。この楽しげに踊るところを神楽で見せ、岩戸を開けるところは神楽の後の舞で見せますが、ここが一番の見どころです。

撮影 石田 裕
そして最後は「思えば伊勢と三輪の神、一体分身の御事、今更何と磐座(いわくら)や、その関の戸の世も明け・・・」と締めくくります。
私は「伊勢の女神も三輪の男神も仲良く御一体、夫婦仲良いんですよ」と観て下さる方々に思っていただければ、それでいいのでは、と思い勤めました。
ですから、三輪は男神でお伊勢さんは女神であってほしい、と思うのです。

撮影 潮 康史
今回の演能は18時開演で21時の終了を目指したため、『三輪』は一部を割愛させていただきました。通常100分ほどかかるところを70分にして演じました。
能は与えられた環境、状況に適応して演じ方を工夫すればよいと思います。
もちろん物語の展開に支障をきたしてはいけませんが、作品内容がわからなくならない程度なら、事情に合わせ、多少割愛してもお楽しみいただければよいと思っています。
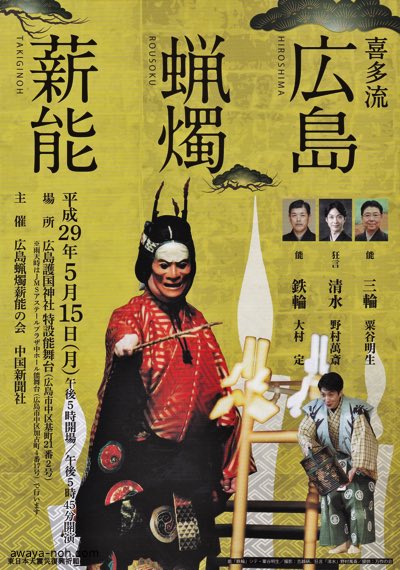

さて、今回小書無しの普通の『三輪』は二度目でしたが、前回も広島「花の会」(1994.9.10)で、どうも広島に縁のある曲のようです。しかし広島に限らず、いろいろな地域でご覧いただきたく活動の範囲を広げて、叉再演したいと思っています。(平成29年5月 記)
『石橋』一人獅子を披く投稿日:2017-03-07


(撮影 石田 裕)
『石橋』一人獅子を披く
粟谷 明生
中国が唐と呼ばれていた時代、所は霊場(仏教における霊地)、清涼山に千丈の深谷をまたぐ石橋がありました。橋の向こうは、文殊菩薩が住むという浄土。
しかしこの橋、幅は一丈にも満たない狭さ、苔むしてツルツル滑り、足を踏み外したら谷底にまっさかさま、危険極まりない橋です。そこへ文殊菩薩の眷属ともいわれる獅子が現れて、橋の上を軽々と飛び跳ね舞って見せる、それが能『石橋』です。
第百回目の粟谷能の会(平成29年3月5日)では、粟谷能夫の大曲『伯母捨』が企画され、2時間半ぐらいの長丁場が予想されたので、私の演能は短く、それでいて豪華絢爛で楽しんでいただけるものをと考え、まだ披いていなかった喜多流独自の巻き毛の一人獅子を半能で披くことになりました。
(撮影 石田 裕)
『石橋』は一時途絶えていましたが、江戸時代初期に喜多流がいち早く復曲して以来、広く親しまれ、現在は五流にさまざまな演出で引き継がれています。
喜多流は親獅子(シテ・白頭)と子獅子(ツレ・赤頭)が出る「連獅子」と赤い巻き毛の頭を付ける一人獅子の演出があります。
私の『石橋』の演能は子獅子を7回勤め、平成21年の秋の粟谷能の会で親獅子(シテ)を披き、今回、一人獅子を披きました。私のように子獅子から親獅子、最後に一人獅子を披く流れと、子獅子のあとに一人獅子を勤め、その後に親獅子を披く順序を吉とする考え方もあるようですが、今は、その時代に合わせて指導者と当事者で自由に選べる時代に変わりつつあるようです。
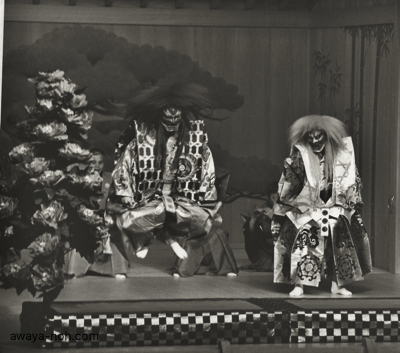
(撮影 三上文規)
私自身は今回一人獅子を披いて、子獅子のきびきびとした俊敏な動きをまず学び、次に荘重で威風堂々、どっとしりした親獅子の舞い方を経験した上で、巻き毛の赤頭の一人獅子の敏捷性とどっしりとした威厳ある動きの双方を意識し勤められるのではないかと感じました。
現在喜多流は、獅子全体を大事にし過ぎて、『道成寺』を披かない、経験させないと子獅子に挑めない現況ですが、それはどうだろうか、と疑問を感じています。次世代の子獅子の披きが遅くなっている要因となっているのは確かです。
私自身も子獅子の披きは『道成寺』の後で34歳でした。子獅子は軽やかできびきびした動き、親獅子を上回る激しい動き、一回転半を軽々とこなせる体のキレが必要です。獅子の披きが遅くなっている現況を再考し、若いうちに子獅子が披ける環境を作るべきで、その方が、喜多流の隆盛に繋がると思うのですが・・・。

(撮影 石田 裕)
話を舞台に戻します。
囃子方や地謡陣が着座すると、紅白の牡丹を華やかに飾った二台の一畳台を運び入れます。伝書には、二台をピッタリ合わせて前後に置くように書かれていますが、最近は二台をやや左右にずらして、舞台上に広がりを出すようにしています。私もそのような置き方にしました。さらに立体感を出すために二台を前後に少し離すこともありますが、これは難しく危険を伴います。
演能後、牡丹が邪魔してシテの動きが見えなかったとのお話を伺いました。
確かに現在の作物は牡丹の花房が密集しているため見づらいようです。ご覧になる方々に配慮し、もう少し間引いて、牡丹の花の間からもご覧いただけるように改善の余地があることを知りました。
(撮影 新宮夕海)
『石橋』の獅子の構成は、乱序の囃子が始まり、シテ・獅子の登場となり舞います。この乱序からはじまる演奏部分がより一層舞台に緊張感を漲らせます。
笛が高い調子で吹き上げ、大鼓、小鼓の叫び吠えるような荒々しい掛け声、太鼓も加わって激しい演奏となり、幽山深谷のすさまじさを表現します。途中、「露の拍子」といわれる、太鼓と小鼓だけで囃されるところは、露がポツンポツンと滴り落ちる静寂な段となり、そしてまた、笛が吹き出し大鼓が加わっての大合奏となり、シテは幕をあけ、すっと出て一度止まり、左右の足を上げ前へ乗り込みます。橋掛りを真っ直ぐ進み、一の松前にて牡丹を見込んで、三度飛んでクルッと回転して足拍子を踏むと、本舞台へスピードを増しながら進み、一畳台前まで進み、直ぐにシサリ下に居て面を伏せます。ここまでが細かくいうと乱序です。リズムがない文字通り乱れた囃子、それにのって、獅子が登場する場面で、囃子方の演奏の聞かせどころでもあります。楽しんで聞いていただき、幽山深谷を想像していただきたいところです。
(撮影 青木信二) 
(撮影 石田 裕)
その後がいよいよ獅子舞、リズムにあった囃子になり舞となります。今回は九段構成で勤めました。近年は八段ですることが多くなりましたが、正式は九段です。細かく獅子舞の構成を説明すると、左へ右へと顔を振り、牡丹に戯れ、香りをかぎ、橋を想像させる一畳台に上がっては喜び戯れるイメージとなります。時折、吠えるように面を後ろに反る所作をしますが、これは獅子が口をあんぐり開けている感じの表現ではないでしょうか。
(撮影 吉越 研)
獅子は一畳台の上に上がったり降りたり、激しい動きをしますが、以前野村万作先生が「獅子はライオン、ネコ科だろ。ダンダーンとけたたましい音をたてて台に乗るのはどうだろうか?」と、耳元で言われたことは忘れられません。なるほどもっともと納得した次第ですが、いざ自分が、となるとなかなか難しいものでした。音を吸収させ飛び跳ねる、至難の技です。

(撮影 新宮夕海)
今回、大曲『伯母捨』の地謡で2時間半ほど正座した後で、肉体的にはかなりきつかったのですが、限界ぎりぎり精一杯勤め、おめでたい百回公演を締めくくることが出来たことに正直安堵しています。
『石橋』の半能というのは、前場がなくとも、豪華絢爛の獅子舞で十分楽しめ、能として、独立して成立する内容だと思います。それでも、石橋というものがどういうものであるか、分かったうえで、この半能を観ていただくと、より深みが増すのではないかと思い、今回は番組に前場の詞章をすべて掲載しました。
半能で謡われるのは、ワキの「もと大江定基といわれた寂昭法師である、ほうぼうの仏跡を参拝して廻り、今清涼山にやってきた、ここに見えるのは石橋のようだ、向いは文殊の浄土、詳しく尋ねて、この橋を渡ろうと思う」という短い名乗りのみで、すぐに獅子登場です。
(撮影 新宮夕海)
しかし、前場の詞章には、ここがいかに秘境であるか、石橋がいかにすさまじい橋であり、また徳ある橋であるか、ここを渡れば文殊菩薩が住む浄土に到るけれども、相当の修行をした僧でもそう簡単に渡れるものではないといったことが余すところなく書かれています。

(撮影 石田 裕)
前場もある演出で行った、平成13年の秋の粟谷能の会(親獅子:粟谷能夫、子獅子:粟谷明生)で、父・粟谷菊生が地頭を勤め、クセなど、『石橋』の世界を謡い尽くしてくれたこと、忘れることができません。中入り前の地謡の最後「向ひは文殊の浄土にて、常に笙歌の花降りて・・・」と花降り妙なる音楽が聞こえてくるのは、奇特が現れるきざし、もう少し待ってごらんなさい、菩薩の来現も間もなくでしょうと謡い、中入り後、期待が高まるなかで、文殊菩薩が乗るという獅子が現れるのですから、それは奇跡であり、めでたさの窮まりで、絢爛な獅子舞が一層躍動して見えることでしょう。

(撮影 成田幸雄)
今回、一人獅子の赤い巻き毛を、佐々木多門氏に巻き直し作業をしていただきました。細かい手作業を丁寧にやっていただき感謝しています。
装束付けも、前場が無いため中入り後の慌ただしさはなく、ゆったり準備ができました。次世代の方々が巻き毛を実際に触れながら、そのうち自分が勤めるときは、いつか自分も、と憧れをもってくれたらと、出を待ちながら思った「一人獅子」のお披きでした。
(平成29年3月 記)
『伯母捨』で地謡を謡う投稿日:2017-03-07
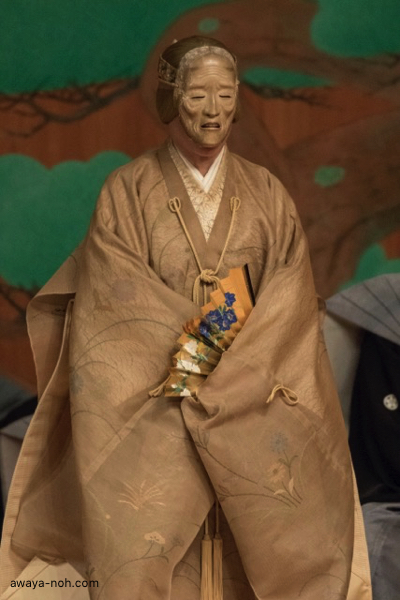

『伯母捨』で地謡を謡う
粟谷 明生
粟谷能の会の百回公演(平成29年3月5日)が無事終了しました。これもひとえに、観客の皆さま、舞台づくり関係者のみなさまのおかげと感謝申し上げます。粟谷能夫が大曲『伯母捨』を披き(私は地謡)、私が『石橋』一人獅子を披きました。百回への思いを込め、充実した時を過ごすことができ、今、ほっと一息ついたところです。

粟谷能の会は伯父・粟谷新太郎と父・粟谷菊生が昭和37年に立ち上げた会で、名称は粟谷会、粟谷兄弟能、粟谷能の会と変遷しましたが、以来、五十余年、年2回か1回の会を重ね、途中、伯父や父が亡くなった後は粟谷能夫と私が引き継ぎ、継続してきました。個人の会が珍しい時代に、主催者側の思いで、ある程度自由に執り行うことができる会を、伯父や父が起こしてくれたことは先進的で志があったことと思います。我々もその志を継ぎ、この会にどう曲目を選択し意義ある会にするかを、常々考えて臨んできました。
能夫は以前から老女物に取り組みたいという強い志がありました。「老女物をやらずに死ねるか」はお酒が入ると決まり文句でもありました。老女物の秘曲は『檜垣』、『伯母捨』、『関寺小町』で特に三老女物と呼ばれています。喜多流と金剛流は『伯母捨』ですが他の流儀は『姨捨』と表します。もちろん内容は変わりません。喜多流では『関寺小町』は江戸時代に事情があり止め曲になってしまい、『檜垣』と『伯母捨』が事実上、老女物の双璧となっています。
老女物は秘曲として神棚に挙げられ、あまり上演されることがない時代が続きましたが、この秘曲・名曲を埋もれさせてはならない、何とか世に戻したいとの思いで、父・粟谷菊生に演能依頼の話を持って行ったのは、実は能夫と私でした。そして喜多流として180年ぶりに『伯母捨』(シテ・粟谷菊生)が復曲したのです。平成6年10月の粟谷能の会のこと、もう23年も前になります。その後は大島久見氏、友枝昭世師が2回、高林白牛口二氏、香川靖嗣氏、内田安信氏が勤め、能夫は7人目となりました。私もそのうちの5回に地謡を勤めさせていただきました。一方の『檜垣』も、能夫と私で友枝昭世師に披いていただくなど仕掛けをしてきました。老女物の秘曲を神棚に飾るものではなく、多くの人に観て感じていただけるものにしたい、いつかは自分も勤めてみたいという思いでやってきました。
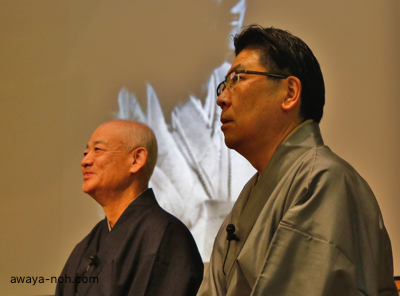
では、いつどのようにして披くか、個人の会にするか、などいろいろ悩みもありましたが、やはり長年育んできた粟谷能の会がふさわしいのではないか、しかも百回公演という節目を迎えるこの会がよい、と照準を合わせ、満を持しての能夫の『伯母捨』となったのです。『檜垣』にするか『伯母捨』にするかもだいぶ迷った時期もありましたが、結局は『伯母捨』になりました。
さて、能『伯母捨』は何を言いたいのでしょうか。
昔から各地に姨捨伝説がありますが、なかでも「わが心慰めかねつ更級や姨捨山に照る月を見て」(古今集・詠み人しらず)の歌に触発されて戯曲されたのは確かでしょう。近年は深沢七郎著「楢山節考」が広く知られ、その世界を想像する人も多いでしょうが、能が描くものは全く違います。山に捨てられる悲惨な物語は狂言方が語るアイ狂言に委ねられ、能自体にはそのようなリアルな悲しい物語は現れてきません。能『伯母捨』をご覧になる時は、一度「楢山節考」のイメージを払拭してからご覧になるとよいのではないでしょうか。
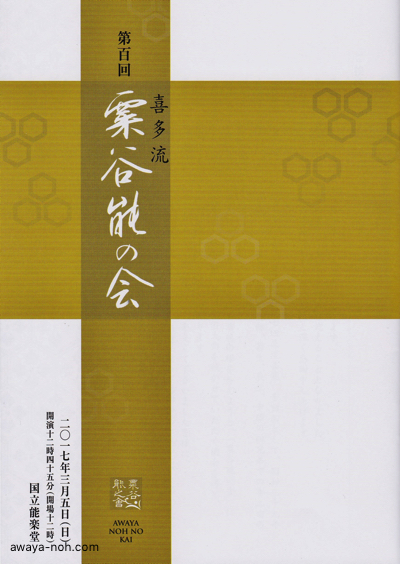
『伯母捨』は、中秋の名月のもとで、一人の老女が舞を舞うことが主題なのだろうか。人の世を脱し、月の光に同化し、浄化された明るく清らかな世界を見せたい、ただそれだけかもしれない・・・などと考えます。シテは年老いて山に捨てられた老女の霊です。にもかかわらず、そのことを悲しんだり、恨んだり、救いを求めたりしないのです。ワキも都の者(下掛りでは、陸奥の者で都を旅してきた者)で、僧ではないので、最初から救いをテーマにしていないことが分かります。「執心の闇を晴らさんと」や「思ひ出でたる妄執の心」と地謡が謡うところはありますが、そう深刻ではありません。美しい月の光を浴びて、この世の悲しみや恨みを突き抜けて浄化しているように見えます。
そのような作りでありながら、アイ語りに悲しい姨捨伝説の内容を語らせ、そっとその悲惨さを提示するのは能らしいところなのかもしれません。ただ普通、アイ語りは中入りしたシテが装束を替える時間に、物語と同じ内容を要約し補足説明することが多いのですが、『伯母捨』では、全く前場・後場に登場しない物語を語るところが特異です。
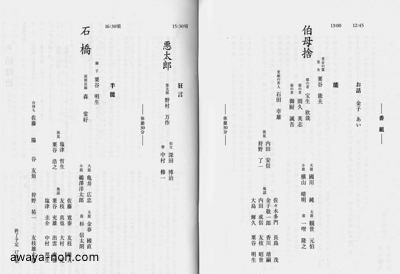
前場では、中秋の名月が近くなったある日、ワキが長い旅の末に姨捨山にやって来ると、里女(前シテ)が現れます。ワキが有名な姨捨の地を尋ねると、「わが心慰めかねつ・・・」の歌を詠んだ人の亡き跡ならと案内します。そして、月見の宴の慰めにまた参りましょうと約束し、自分はその姥の化身であることをほのめかして姿を消します。
初同(最初の地謡)の「今とても。慰めかねつ更級や。・・・」はゆったりとした調子で謡い出します。秘曲中の秘曲、これを掘り起こしたときはゆっくり荘重に謡うことを旨としました。車に例えると、制限速度40kmなら、そのようにただただ慎重にゆっくり謡うという感じです。しかし、この秘曲も8回目、私も地謡を5回経験すると、ただ重苦しくゆっくり謡うだけでよいのか、という思いにとらわれます。戯曲の内容を考え味わうなかで、少し謡の運びを速めたほうがよいのではないか、加重された謡から減量を意識した謡へと変化しなくては、と気づきました。
老女物といっても、前シテは杖にすがって出てくるわけではありません。老いの寂しさ、一人捨てられたつらさを突き抜けて、月と同一体となる老女は弱々しいのではなく、相当強くエネルギッシュなのです。リアルな老いを描くより、むしろ老いを超越した姿を描くのですから、それに似合う謡が必要です。秘曲を大事にするのは判りますが、あまりにもゆっくり重く慎重に謡うのが保守本流と決めつけこだわるのはどうだろうか、と感じました。これからは地謡も囃子も手慣れることで運び、適度なノリを付けることが大事だと思っています。

後場の地謡は特に曲(クセ)が硬質です。「さる程に。三光西に行く事は。衆生応じて西方に勧め入れんが為とかや」(日、月、星の三光が西に廻ることは、生きとし生けるものを西方浄土に導こうとするためだとか)からの謡は三光の功徳や大勢至菩薩が住む月の極楽世界を描き出します。クセで、「心引かるる方も有り」までの和吟が「蓮色々に咲き交る」から強吟になり、思いが強くなっていきますが、ここの父・菊生の謡が絶妙で、私も父の謡を思い出し、精一杯真似て謡い上げました。
そして、地謡はさらに続きます。「勢至菩薩の光はすべてあまねく照らすので無辺光ともいわれるが、しかし月はある時は満ちある時は欠け」と世の中の無常を語り、シテの「昔恋しき夜遊の袖」につなげ、序ノ舞となります。
序ノ舞は珍しく太鼓入りです。クセの後半から謡が強吟になり思いが強くなるのと呼応しているのでしょうか。シテもそれまで持っていた杖を捨て、中啓で舞い始めます。老女というより大勢至菩薩になったような風情です。面は「姥」で老婆ですが、杖を突いて足を引きずるような老婆ではなく、天空に遊ぶ、無重力状態で滑るような運び、エネルギーある運びが必要です。
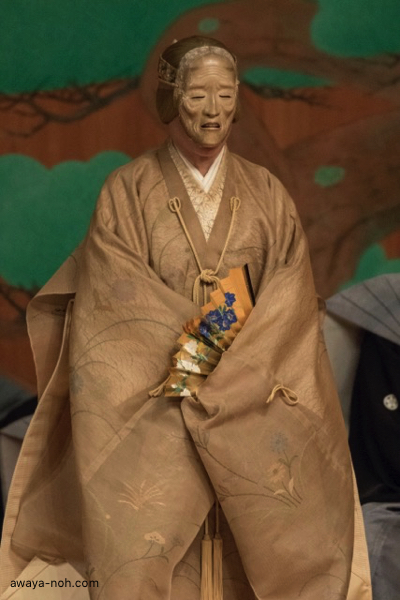
『伯母捨』は夢幻能です。老女をシテにした『卒都婆小町』や『鸚鵡小町』などは現在物でリアルな100歳の老女小町を描き出しますが、『伯母捨』は夢の中のできごと、夢かうつつかわからない、夢の中で遊び戯れる、まさに胡蝶の遊びのような趣なのです。
「思ひ出でたる妄執の心。・・・恋しきは昔。偲ばしきは閻浮の。秋よ友よと思い居れば・・・」と少しの執心をにじませますが、はや夜が明けて、シテの姿は消えていきます。
これで、普通ならシテが留め拍子を踏んで終曲し、シテ、ワキの順で橋掛りを通り消えていくのが常ですが、この秘曲『伯母捨』は特異です。「我も見えず」「旅人も帰る跡に」と地謡が謡い、ワキがシテの前を通り抜け、先に引き上げてしまいます。シテは舞台中央に座り込んで一人取り残されます。ワキは、消えてしまった亡霊のシテが見えずにそのまま引き上げるという演出です。
最後にシテが「独り捨てられて老女が」と謡い、地謡の「昔こそあらめ今も亦。姨捨山とぞなりにける。姨捨山となりにけり」と終曲します。老婆が本当に一人取り残され、姨捨山と一体化し、姨捨山の土になり自然に溶け込んでいくかのような風情です。他の曲にはない印象的な終曲で、人間の深いところを抉り出しているように感じます。
シテの「独り捨てられて・・・」以下の場面は、一般の能なら描かない部分です。現代の映像や舞台演出ならば、姨捨山の風景をスクリーンやステージ背景に映し「独り捨てられて・・・」以下をナレーションに語らせ、余韻を残した印象的な終わり方にするかもしれない・・・そんな想像をしてしまいます。
ワキが引き上げて、消えたはずのシテに敢えてセリフを言わせるのは、あまりにも前衛的です。シェイクスピアより100年も前の演劇で、これほどに前衛的なことが行われていたことが驚きであり、誇りでもあります。ただ、この感覚、観る側も相当前衛的でないと真意がわからないかもしれない、難しい・・・とも思うのです。
今回の後シテの白衣の装束は、白は白でも和の白で、やや茶の入った生成りに近い白です。これは観世銕之丞家から拝借したお装束で、能夫は長絹や白大口袴を白地にするか生成りにするか、と迷っていましたが、今回選んだ生成り色が、本当に姨捨山に同化する感じとなり、良い選択だったと思っています。
ここで改めて観世銕之丞氏へ厚くお礼を申し上げたいと思います。
粟谷能の会百回公演で、私はこの秘曲の地謡を謡い感じることが多くありました。次の『石橋』のことを考えると、体力的にきついだろうと思いましたが、日頃からご指導をいただいている友枝昭世師や私をこの道へと引きずり込んでくれた粟谷能夫への、その感謝の思い、そして最初にこの秘曲を手がけてくれた亡父・菊生への思いも込めて謡ったことに間違いはありません。
この大曲、地謡を謡わずに高みの見物気分でいたら、屹度作品の良さと難しさは判らなかったでしょう。もちろん今も判らないことだらけなのですが、ただ実際に舞台の中に入って謡うことで、作品により近く触れることができたことは、実感です。これからも多くの人が経験し、今後にその時代に合わせて伝えていってほしいとの思いを強くしました。
(平成29年3月 記)
写真
能『伯母捨』シテ・粟谷能夫 撮影 吉越 研
半能『石橋』シテ・粟谷明生 撮影 石田 裕
事前講座にて粟谷能夫と粟谷明生 撮影 石田 裕
第100回粟谷能の会当日番組表紙
当日番組
能『伯母捨』シテ・粟谷能夫 撮影 吉越 研
能『伯母捨』シテ・粟谷能夫 撮影 青木信二
『望月』という仇討ち物語投稿日:2017-02-07

『望月』という仇討ち物語
粟谷 明生

平成29年の私の演能は、喜多流特別公演『望月』(1月29日、於:喜多能楽堂)からスタートしました。
能『望月』はシテの小沢友房が主君・安田友春の妻(ツレ)と子(子方)と共に、仇討ちを果たす比較的単純でわかりやすい物語です。シテはほとんどセリフばかりのセリフ劇ですが、獅子舞があることから、重い習いとなっています。
また、仇討ちで重要な役割を演じる主君の子・花若役の子方にちょうどよい歳ごろの少年がいなければ成立しない曲でもあります。今回の特別公演では子方を大島伊織君が勤めてくれましたが、ちょうど子方適齢期です。ツレ役の父・大島輝久氏とともに、息もぴったりで立派に勤めてくれたことが、とても嬉しかったです。
『望月』の見せ場は仇討ちの場面に向けて、緊迫感溢れるクセ謡、そして子方の鞨鼓を付けた舞、シテの獅子舞と続きますが、実はシテ役としては、そこに至るまでの小沢刑部友房の心をいかに表現するかが大事で、課題です。能としての様式美を崩さず品位を保ちながらも、戯曲の面白さを伝えなくてはいけなく、あまり感情が入り過ぎては能の世界の結界を超えてしまい、かといってただセリフを謡うだけではお客様に面白く観ていただけないでしょう。シテは劇的、芝居的な要素と能らしさとのはざまで悩むところで、初演(平成12年3月、粟谷能の会)のときは声を張り上げるばかりで、友房の思いの深さを表現するにはやや単調になってしまったと、反省しました。

シテの友房は多くの負を背負っています。身分ある武士が、主人が討たれ、領地はなくなり、しかも、討たれた場に居合わさなかった無念。急いで戻りたくも、阻まれてそれも果たせなかった悔しさ。今は守山の宿・兜屋の亭主になり下がっているという境遇、それらを最初の名のりの謡で伝えなくてはいけません。
物語は、偶然にも亡き主君の奥様とご世継ぎが兜屋を訪れるところから展開していきます。再会の驚きと喜び、家来としての面目なさ、恥ずかしさが伝わる謡が必要となります。
さらには、そこにあろうことか、宿敵・望月秋長(ワキ)もやって来てしまい、あまりの偶然に驚愕する心、それらも抑えたセリフのなかにどう表現するか、これがシテ役者としてのこの曲の課題である、と思っています。

父・菊生は「腹芸(はらげい)でやれ」と言っていましたが、直球ではない、変化球を織り交ぜた謡い。その匙加減は難しいものですが、自分なりに織り交ぜることに気づいたことは今回の収穫です。
やがて、シテが主君の妻子に望月が来たことを伝えると、妻は、どのようにしてもいいから討つように、と強く頼みます。頼まれた友房にはよい策が浮かびませんが、思案の末、盲御前になって望月に近づこう、と計略を立てます。
盲御前は遊芸者であり、最終的には夜の伽もしなければならない者です。それを主君の奥様に提案するのですから、まさに苦渋の策です。しかし、盲御前ならばこそ望月の前に自然に対峙できるのです。この作戦に対して妻は毅然として受け入れ「嬉しやな、望みし事の叶ふぞと」と心強く謡います。仇討ちのためなら何でもやるという、相当な覚悟がここで見て取れます。
盲御前になりすました母と子は、敵の望月の前で出し物である、曽我物語(兄・一萬と弟・箱王)を聞かせることとなります。
「兄弟が五歳、三歳のとき、彼らの父は従兄弟の工藤祐経に討たれ、月日が経ち、七歳、五歳になったとき、幼けなき心にも父の敵を討つ、と思い始める」と地謡が謡い出します。

盲御前の定番の出し物とはいえ、安田の母子の境遇に重なる話です。地謡はさらに続きます。あるとき兄弟が持仏堂に入り、兄の一萬が不動明王に香を焚き花を供えると、弟の箱王が本尊をよくよく見て、「仏の名が宿敵の工藤、しかも剣と縄を持って自分たちを睨んでいるのが憎い」と走り寄り首を切り落とそうとするので、兄が「仏の名は不動、敵は工藤だ」と諭し、弟は刀を鞘に差し不動に向かい手を合わせ「どうぞ敵を討たせてください」と続き・・・。とその瞬間、子方の花若はしびれをきらし、「いざ討とう(今だ、あいつを殺せ!)」と叫んでしまいます。
この一連の場面は、演者達に全く動きはありませんが、力強い地謡の謡と強い掛け声と音色による囃子方の演奏に興奮させられるところで、聞かせどころです。
特に、クセの地謡には粟谷家伝承の特別な謡い方があります。それは通常より一段高い調子で謡うのが教えです。能が終わった後に、友枝昭世師が「菊生先生を思い出したよ。能夫ちゃんだから謡えるんだね」と仰っしゃったのが心に残ります。声量、キーの高さ、パッション、危機感をはらんだ謡い方。父・菊生の傍らで謡っていた能夫が顔を紅潮させ地頭を勤めてくれたお陰で、周りの地謡も張って謡ってくださった、と感謝しています。
「いざ討とう!」と子方が叫ぶとき、「討とうとは!」と脇差に手をかけて立とうとする望月の従者・アイ(山本則重)と緊張する望月・ワキ(殿田謙吉)に対して、「お騒ぎなさるな、うとうというのは八撥を打とうということだ」とシテのとっさの判断、この四人の一瞬の動き、ここから更に緊迫感あふれる場面へと展開されていきます。

そして、子方の鞨鼓を付けた八撥の舞に続き、シテの獅子舞となります。
獅子舞は喜多流では『望月』と『石橋』にあり、どちらも重い習いとなっています。
私は平成29年に、1月の特別公演で『望月』、3月に粟谷能の会で『石橋』と連続して勤めることとなりました。
両曲の獅子は実は全く違うものです。『望月』は武士が獅子頭を付けて獅子舞を舞うというお座敷芸であるのに対して、『石橋』の獅子は、獅子そのもの、霊獣的な雰囲気を醸し出さなくてはいけません。精神的にも違います。『望月』は獅子舞を舞いながら、相手を酒に酔わせ、敵のすきを窺い、仇討ちをいかに成功させるか、緊迫したなかでの芸であるのに対し、『石橋』は牡丹の咲き乱れるなかで、牡丹の香りをかぎ、狭い橋の上で軽快に飛び回るものです。今回は『望月』らしい獅子、を意識して勤めました。



『望月』の獅子の扮装は、赤頭に金扇を二枚重ね、間に舌にみたてた赤い袋のようなものを入れて獅子の口とし、覆面をして萌黄色厚板唐織の装束を被きます。この格好は現代もよくお正月に見られる獅子舞に似ています。獅子舞は息苦しい覆面をしますが、面を付けないので視界がよく、一畳台に乗ったり降りたりの危険もありません。舞の段数も少なく、『石橋』に比べるとプレッシャーはかなり少ないかもしれませんが、先に述べたような、緊迫した心理劇を意識し体現しなければならない難しさがあります。
獅子の胴体となる装束は厚板を坪折り(襟全体を内側に3つに折る)にし、被いて身を隠して出て、舞う時に装束から顔を出し両袖に手を通す早業を体得しなくてはいけませんが、実は装束の裏側にひもを通す仕掛けがあります。そのため、粟谷家では萌黄色立涌牡丹模様の唐織厚板を『望月』専用としています。演者は、望月が酔って眠ったことを舞いながら確認し、舞い納め、装束を被いたまま身を隠しながら、装束の内紐、赤頭、覆面と決められた順番に紐を解き、白鉢巻きの仇討ち姿となります。この段取り通りに作業することは『道成寺』の鐘の中の物着と同様です。



余談ですが、私が能にめざめ本気で取り組んだ曲『黒塚』で、後シテの腰巻にと選んだのが、この萌黄色の『望月』専用の装束でした。萌黄色と赤頭の赤が鬼女の装束として合うのではないかと思っての選択でした。見るとなんとも不似合いでお恥ずかしい組み合わせでしたが、あのとき能夫は「それはちょっとおかしいのでは」とか「望月専用だからだめ」などと言わず、黙って出してくれました。「自分で装束を選ぶ」ということの大切さを優先してくれたのです。今この萌黄色立涌牡丹模様の厚板唐織は、そんな装束選びの大切さを思い出させてくれる装束なのです。


初演の演能レポート「子方を通しての『望月』」では、子方が息子(粟谷尚生)だったこともあり、子方をどう育て、役作りをさせるかということに心を砕いてレポートしました。
今回は大島輝久氏が母役、ご子息の伊織君が子方で、親子共演、大島家の教育方針もあるだろうと、私からは特に何かを言うこともなく、信頼してお任せしていました。大島氏から、二人とも初演なので、型の多少の相談があったぐらいです。それでも申合せの前に一度本番さながらに稽古したいとの申し出がありました。本番さながら鞨鼓撥や刀を用意したほうがいい、最後に突き刺す笠も用意しようとしていると、すでに大島氏が準備してくださり、ここでもう内心安堵していました。ツレと子方のよく出来た連吟、親子で十分の稽古をされ本番に本領発揮されました。このことが私の『望月』の出来を盛り上げて下さったことは確かで、感謝しています。



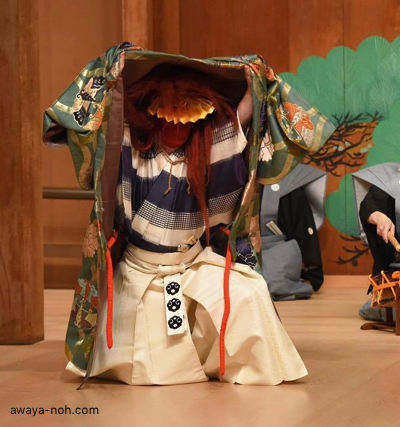
今回も以前同様、不自然と思われる役者達の位置関係を、お相手の皆様のご協力を得て改善して演じました。
望月が来たことを、母子にこっそり伝える場面に、シテと親子、ワキとアイ、この敵同士が隣に座るのが従来のやり方です。これは何とも不自然です。こんなに近くにいるのに「何、望月と申すか」と驚きを大きな声で謡うのは子方時代からの疑問でした。そこで今回も、ワキとアイが宿を借りることになった後に、お二人に、ワキ座の奥に横を向いて座っていただき、子方らから少しでも遠く離れている状態にしていただきました。
こうすることで、シテの「言語道断・・・」からの驚きと独白、母子に伝えて仇討ちの作戦を練ることにつながります。いくら能は舞台装置が少なく、観客の想像力に委ねるとはいえ、想像しやすいように、できるだけのことをするのが演者の使命です。些細なことのようですが、演者は己のことばかりではなく、観る側に立っての意識、そこを忘れてはいけない、そこを無視するとそのうち罰が当たると思っているのです。

獅子舞の終盤、気持ちよく酔いつぶれる望月を見届けたシテは、獅子舞の装束を脱ぎ捨て白鉢巻き姿になって、子方・花若に仇討ちは今だと促します。その瞬間、子方は太刀を抜きシテと共に望月に迫ります。他流では獅子舞の途中にワキは切戸口から姿を消すようですが、喜多流は、子方がワキの隣に置いてある笠を飛び越え背後に回り太刀を振り上げ、シテも望月に飛びかかり胸ぐらをつかむリアルな演出です。「おまえ達はだれだ?」の望月の慌てた言葉に、花若も友房もそれぞれ名のり、その後は、笠を望月と見立てて、太刀を振り下ろし、小刀で刺し通し、見事本懐をとげます。

『望月』という能はシテが小沢友房であるのに、タイトルは敵の名前です。他にもシテではない者の名前がタイトルになる能は『葵上』『満仲』『昭君』『蝉丸』『白楽天』などがありますが、ここが気になりました。

最後の地謡に「思う本望遂げぬれば・・・・彼の本領を望月の子孫に伝え、今の世にその名隠れの無き事も」と謡い、「弓矢の謂はれなるらん」と終わります。
この仇討ちは土地(本領)ほしさでやったわけではない、土地はすでに望月のものとのお沙汰が出ているのだから、望月亡きあとは子孫に伝えよう、ただ自分たちは「弓矢の謂れ:武勇の徳」のためにやったのだ、それが伝わればいいのだ、と結んでいます。
この能の曲名が『望月』とする意味は殺された者に華を待たせる、そんな想いからではないでしょうか。これは私が演じて思った単なる感想からの考えです。

平成12年の初演から今年は29年、17年の歳月が流れました。私の能は進化したのでしょうか。つくづく時の流れを感じながら、これからも能人生を歩んでいくのだと心に期した、年の初めとなりました。
(平成29年2月 記)
舞台撮影 新宮夕海
楽屋撮影 粟谷明生
『梅枝』の「楽」を見直す投稿日:2016-12-07

『梅枝』の「楽」を見直す
粟谷 明生

平成28年度・喜多流自主公演(12月18日)で『梅枝』を勤めました。
『梅枝』は『富士太鼓』の後日談です。
昔、天王寺に「浅間」、住吉に「富士」と呼ばれる二人の太鼓奏者がいて、二人は内裏の管弦の役で争います。結果、浅間が選ばれ、その後富士が殺害される事件が起こり物語は展開していきます。
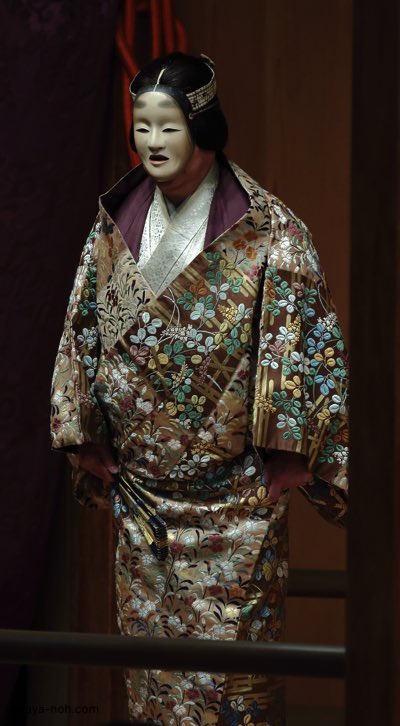
『富士太鼓』は富士の妻が我が子を連れて登場する現在物ですが、『梅枝』の富士の妻は亡霊ですので夢幻能となっています。ワキも『富士太鼓』では、単に富士が討たれた事実を知らせる役人で、救いなど無縁なのに対して、『梅枝』のワキは衆生を済度せんと諸国をめぐる僧の設定で、救済や成仏といった内容が盛り込まれた夢幻能らしい作品です。
『富士太鼓』では宮中から指名された浅間の方が評判も高く、帝も感心されたほどで、当然、浅間が役をもらったと説明します。ただ浅間は田舎者の富士が自分と対等に勝負を挑んできたこと、また役争いに負けたにもかかわらず、まだ「自分の方が上手い」と吹聴していたことに怒りを押えきれず、富士を殺害してしまいます。富士の身の程知らず、身分不相応の振る舞いが悲しい結末を招いてしまうのです。富士の妻は帰らぬ夫を心配し、娘と共に都にのぼり、富士が討たれたことを知らされると、狂乱し太鼓を敵として打ちます。最初は母の乱心をとがめる娘も、この太鼓があるおかげで父が死ぬことになったと同調し、母娘、「打てや打てやと攻鼓」とばかり激しく太鼓を打ち続けます。恨みや復讐心といったものが劇的に戯曲されています。

c
一方『梅枝』は、浅間は富士が役を賜ったことを憎々しく思い殺害したと短く語り、浅間が役を賜った事実も、富士の非も語られません。時が経ち、置かれた立場によって事実が曲げられてしまうのは、昔も今も変わらないようです。
物語は、諸国行脚の僧(ワキ)が雨宿りに里女(前シテ)の家を訪ねるところから始まります。里女は一度は断りますが一夜ならば、と僧を迎えいれます。すると庵の中には舞楽の太鼓と舞の衣装があり、不思議に思う僧に、女は事情を話し弔いを願います。そう語るうちに里女に富士の妻の霊が降りてくるような、里女なのか妻の霊なのか、境目がわからない不思議な感覚にさせるのが、お能らしい仕掛けではないでしょうか。
『梅枝』は『富士太鼓』のような復讐心をあらわにしたものではなく、いまだに富士への恋慕の妄執に悩まされている、救ってほしいと願う妻の懺悔物語になっています。時間の経過が恨みや復讐心を昇華しているのでしょうか。『富士太鼓』にある太鼓を打ち続ける激しい動きは姿を消し、『梅枝』という優美なタイトルのように、復讐心よりは恋慕の情を梅や鶯に事寄せて美しく描く感じがよく現れています。
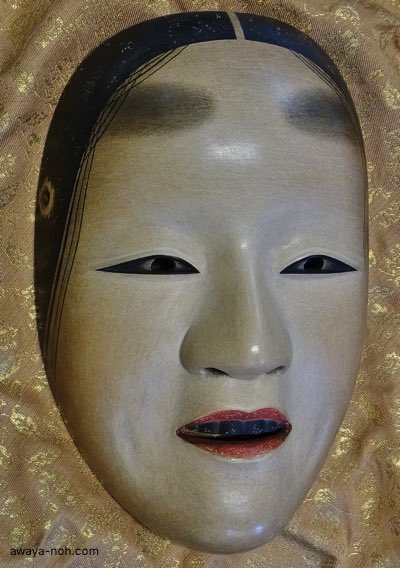
我が儘で野心家の楽人「富士」。その妻の、夫への恋慕を演者としてはどうするか、を考えてみました。
二曲の演出上で大きな違いは娘(子方)が登場するか否か、です。女の夫への深い愛情、その表現は、娘を伴う母親としてか、子を伴わず妻としての立場だけで表現するのかでは微妙に違うのではないでしょうか。そこで今回は妻としての女らしさをより強調させるため、従来の「曲見」や「深井」ではなく、少々老いを減らした「曲女」で勤めました。

また、「楽」の舞い方も、恨みや復讐心とは違う舞い方が必要で、子を伴わない妻の女心を表現するものでなければならず、ここが『梅枝』の最大の難所だと思います。
後シテは、ワキの僧が読経すると、舞楽の衣装(舞絹)をまとい頭には鳥兜をつけ男装した富士の妻の霊として現れます。
「憂かりし身の昔を懺悔に語り申さん」と始まるクセ、「残る執心を晴らして仏所に到るべし」と淡々と懺悔物語が続き、ロンギに入って懺悔の舞を奏でようと、夜半楽や青海波、花の越天楽、「歌へや歌へ、梅が枝」と気分が高揚し、遂に「楽」の舞となります。
「楽」の難しさは位どり、すなわちスピード感です。『梅枝』の「楽」は特殊でノリよく楽しい雰囲気になり過ぎてもいけませんし、かといって、ゆっくりベタッと重過ぎてもだめです。しっとりとしたなかにも「楽」の終わりの「面白や鶯の」のシテ謡に似合うスピード感、気持ちの高揚に沿うようなものに高めなくてはいけません。

喜多流の楽は5段構成ですが、最初に「掛り」という0段のようなものがあり、実際は6段構成です。撥を持って舞う演出もあり、『富士太鼓』の楽なら撥も似合いますが、『梅枝』は太鼓への恨みというよりは、妻の恋慕の執心に焦点を当てているので、伝書にもある通り、撥での舞姿は似合わないと思います。今回は先人たち同様に掛りの最後で撥を捨て、初(1)段目からは中啓で舞いました。
楽の前半は序ノ舞のようにゆったり、そして4段、5段になると「面白や鶯の」を引き出すような、ノリよく華やかな舞となります。『梅枝』は狂乱や復讐心よりは、お経のおかげで成仏できる、喜びの舞ですから、とにかく美しい舞姿が演者には必須だと思っています。

楽が終わって「面白や鶯の」のシテ謡。鶯の声に誘われて花の蔭にやって来たと謡い、「我も御法に引き誘はれて・・・」からは大ノリになり、狂乱の心を垣間見せ、「想夫恋の楽の鼓、現なの我が有様やな」と太鼓(作り物)をじっと見込みます。美しく舞いながらも、妻の心のうちには、そのような狂乱や激しさも隠し持っているのではないでしょうか。夫殺害事件から時が経っているとはいえ、執心を抱えていることには変わりないのです。
中入り前の「執心を助け給へ」やクセの「残る執心を晴らし」、ロンギの前の「執心を助け給へや」、ロンギの「妄執の雲霧」など、随所に執心という言葉が謡われ妻の複雑な心が感じさせられます。後シテの登場から楽へ、楽から終曲へと抑揚と一連の流れ。そして「思へば古を・・・」からは興奮がさめ、月を見、松風に音楽を感じ、静かにすっと姿を消す。『井筒』の終盤と同じ雰囲気で終わりたいです。

『梅枝』は祖父・粟谷益二郎の好演からしばらく演じられることがありませんでした。先代宗家・喜多実先生は参考曲とされていた数曲の一冊本をお作りになり、『梅枝』もそのうちの一曲として入りました。復曲にあたり、父・菊生に白羽の矢が当たり、一番手で昭和54年喜多例会で勤めています。その後は友枝昭世師をはじめ多くの人が取り組まれ、私も平成6年「妙花の会」が初演でした。最近では若い人も勤めるようになっています。昔この名曲がなぜ演じられなくなったのかは不明です。
私の初演では、夢幻能での楽をどう舞うか、が課題で、観世銕之丞家の教え「序ノ舞を舞うように丁寧にゆったり」を意識しました。友枝昭世師も従兄弟の能夫も楽にノリのよさだけではない序ノ舞風を入れることを試みていたので、私も同様に囃子方にもお願いし取り組みました。ところが、よい具合にいかず父に「楽が重すぎる!」と怒られてしまいました。私も少しやり過ぎだった、と反省し、今回はそのリベンジの気持ちを込めて勤めました。
今回は笛・松田弘之氏、小鼓・大倉源次郎氏、大鼓・亀井広忠氏と精鋭ぞろいで、私からは「楽の後の、面白や鶯の、に華やいだところがあるので、そこに上手くもって行けるような楽にしていただけたら嬉しいのですが・・・」と、その程度の話しかしませんでしたが、皆様、私の気持をよく理解してくださり、とても具合のよい楽となりました。ここに三人の皆様に感謝申し上げます。これで私自身も、初演のやり直しができたかなと、少し喜んでいます。

最後に、楽屋内の話を一つ。クセの場面で「夫ノ形見ヲ戴キの右手で頭をさす型」、「此ノ狩衣ヲで引分ヒラキの型」、「常ニハ打チシで巻きサシの型」とこの3つの型をすると死ぬ、と昔、父が話してくれました。この本意は、3つの型をすべてするとごちそうすぎて型が死ぬ、ということです。
「役者が死ぬということじゃないんだよ」と説明してくれた父。
実は、申合せのとき、この事を知りながらも3つの型をやってしまい、能夫に「3つはごちそうすぎ!」としっかり指摘されてしまいました。60歳を越えるとなかなか本当のことを言われなくなるこの世界。先人の教えと仲間の指摘を素敵だな、と思い知らされた『梅枝』の再演でした。
(平成28年12月 記)
(写真撮影)
新宮夕海 巻頭 6.8
石田 裕 2.3.5.6.8
成田幸雄 7
粟谷明生 4
厳島神社・神能で『猩々』を奉納投稿日:2016-04-07

厳島神社・神能で『猩々』を奉納

平成28年4月18日、厳島神社桃花祭御神事・神能で『猩々』を勤めました。『猩々』は能楽に携わる私にとって節目節目の曲となっています。
昭和38年(8歳)の初シテが『猩々』で、次に青年能楽師の目標とする『猩々乱』は昭和57年(27歳)に披かせていただきました。その後は平成4年(37歳)の「鳥取薪能」で『猩々』を勤め、今回は実に24年ぶりとなりました

『猩々乱』は体力を要する難易度の高い『猩々』の小書ですが、普通の『猩々』は演能時間も短く、特に難しい曲ではありません。催しの最後の祝言として、目出度く舞い納めるところに能役者の使命があるように思えます。
今回、敢えて『猩々』を選曲した理由は、自身の還暦を記念する気持ちの他に、来年お勤め下さる社中のお弟子様への模範能としたいというのが正直本音です。全身赤色の猩々緋を纏い恙なく勤める、28年度・神能の番組の最終曲を演じながら、自身の記念、そして次への継承、と思って無事勤め終えました。

では、『猩々』のあらずじをご紹介します。
中国が唐と呼ばれていた時代、金山(かねきんざん)の麓に高風(こうふう)という親孝行で評判の高い男がいました。彼はある夜、楊子の市で酒を売ると富貴の家となる不思議な夢を見ます。その夢のお告の通りにすると、次第に金持ちとなりました。すると高風のお店に酒を飲みに来る者が現れます。その男はいくら飲んでも顔色が一向に変わらないので、不思議に思い、ある日その名を尋ねると海中に住む猩々と明かして帰ってしまいました。
そこで高風はある月の美しい晩、潯陽の江(しんにょうのえ)のほとりに出て、酒壺を置いて、猩々が出てくるのを待つことにします。
と、ここまでの経緯はワキ(高風)の語りで紹介されます。
やがて猩々は下り端(さがりは)の特有のリズムで波間から浮かび出て登場します。そして高風と酒を酌み交わし舞を舞い、高風の素直な心を賞し、無尽蔵の酒壺を与えて消えてゆきました。

『猩々』の演出は、五流、さまざまなものがあります。喜多流では、通常の『猩々』で中之舞となるところを、「乱(みだれ)」という酒を呑んで舞うところを見せる特有の舞とする小書があり、そのものを題名にしている『猩々乱』や、「壷出(つぼだし)」という大きな酒壺を舞台正面先に置く演出もあります。
「乱」の舞は観世流の永遠の少年の妖精のごとき軽やかな動きに比べ、喜多流は腰を低くして壺から酒を汲んでは呑みを繰り返す、中腰状態が続く過酷な舞となります。強靱な足腰が必要となり、若き青年能楽師の身体作りに適した演出で、目標となっています。

使用する能面『猩々』はこの曲にしか使わず、真っ赤な顔色で笑みを浮かべているのは、気持ちよく酒を呑んだ表情をよく表しています。

今回、勤めて、『猩々』は還暦を超えた自分としては、決してやり甲斐のある曲ではありませんでしたが、人生の節目、興業の区切りに大人の能楽師が、祝言性を感じ身につけ勤めることで、「神への献上」という意味合いがあるのではないかと、能役者のルーツともなる精神の再確認が出来たことはとても有意義なことであったと感じます。厳島の女神、八百万の神に、そして私の周りにいる方々、すべてに感謝しています。 (平成28年4月 記)
写真 『猩々』シテ・粟谷明生
撮影 石田 裕
『融』を演じて 月の詩情に寄せた名曲投稿日:2016-03-06

『融』を演じて
月の詩情に寄せた名曲

昔、月には兎が住んでいる、と教えられました。今、子どもにそのように言う大人は少ないでしょうが、天上に浮かぶ月に何かが宿っているような、神秘な面影を見るのは、今も変わらないのではないでしょうか。
第99回粟谷能の会(平成28年3月6日)で『融』を再演しましたが、能『融』は冥界にいる源融左大臣の霊を月の都に住む者として描いています。「月」を融の霊に見立てながらも、人としての融の執心が月のように形を変えては見え隠れするのが面白いところです。前シテの一声の謡(最初の謡)は「月もはや」で、後シテの最後も「月もはや」で締め括られ、能『融』はまさに「月」がキーワード。形を変えることがあっても滅っすことのない「月」と、生者必滅の「人」を対比させ、世の無常を訴えています。仏教色を表に出さずに詩情豊かに戯曲した世阿弥の傑作だと思います。
舞台となる六条河原の院跡は、昔、左大臣源融が風雅贅沢をした屋敷跡です。融は皇位継承権を持ちながら、藤原基経に阻まれ天皇になれず、そのうっぷんを晴らすかのように、広大な邸宅に陸奥の景勝地、千賀の塩釜の風景を模作し、難波から海水を運ばせて塩を焼き、その光景を見て楽しむという、何とも贅沢三昧の生涯を送ります。しかし融の死後、その子、源昇(みなもとのぼる)が、この広大な敷地を宇多天皇に献上しますが、その後相続し管理する人もいなくなり廃墟となってしまいます。
前シテの汐汲み老人、実は融の霊の仮の姿ですが、彼の目に廃墟はどのように映ったのでしょうか。荒廃したことへの無念、時の流れを止められないことへの怒りと諦観があったのではないでしょうか。
では今回の舞台進行に合わせてご紹介します。
まず、東国から上京した僧(ワキ)が廃墟になった六条河原の院跡に着きます。ここで、番組には記載をしませんでしたが、ワキの森常好氏に「思い立の出」の小書を特別にお願いしました。「思い立の出」とは、囃子方と地謡が所定の位置に着き、揚げ幕が上がるとすぐに「思い立つ、心ぞしるべ雲を分け」と道行の謡を謡いながらの登場となるもので、『融』のみにある粋な演出です。
ワキが着きゼリフを謡いワキ座に着座すると、汐汲みの老人(前シテ)が田子桶を担ぎ登場し、常座(太鼓前)に出て立ち、一度揚げ幕の方(東の方角)を振り返ります。そして正面に向き直り「月もはや、出潮になりて塩釜の、浦寂まさる夕べかな」と謡います。
この一度振り返る型の意味するものはなにか。伝書には「東見る」としか記載されておらず、その真意は演者の思考にゆだねられます。私は「お、月は出たが、まだ低く暗いなあ」と解釈して勤めましたが、他流にはない喜多流独特の演出、どう考えるかが演者の試金石となるようにも思えます。

やがて老人は僧に素性を問われ汐汲みと答えますが、海辺でもないのに汐汲みと返す言葉に僧は不審を抱きます。老人は陸奥の千賀の塩釜を模した河原の院の者であるから潮汲みであるときっぱりと答え、融の大臣(おとど)が舟を寄せ遊舞をしたという籬が島を教えます。そして突如東の空を見上げ、「や、月こそ出でて候へ」と月が高く上がったことを言います。一声の「月もはや」に呼応するような謡で、時間が経過したことが知らされます。
現代の都会では月明かりなど意識することはないでしょうが、今でも明かりのない田舎などでは夜の月の明るさを感じます。シテが最初に登場した時はまだ月は低く薄暗く、気がつくと高く昇っていて辺り一面が明るくなった、その情景を演者は観客に伝わるように、また観客は想像してお互いに創り上げていく、能に想像力は不可欠です。
話が少し脱線しますが、続く詞章に、老人と僧が面前の景色を見ながら興に乗って次のように謡うところがあります。
シテ・只今の面前の景色を、遠き故人の心まで、お僧の御身に知らるるとは、もしも賈島(かとう:唐の詩人)が詞やらん、鳥は宿す池中の樹、
ワキ・僧は敲く(たたく)月下の門
シテ・推すも
ワキ・敲くも
詩人の賈島は「僧は敲く月下の門」の「敲く」を「推す」にするかを迷い、韓愈(かんゆ)の助言で「敲く」に決めました。ここから詩文を作る時に最適の字句や表現を求めて考え練り上げることを、「推す」と「敲く」で推敲となったといいます。こんな言葉がさりげなく入っているところも面白いところです。

話を戻します。その後、シテは僧に問われるまま、千賀の塩釜を都の内に写した謂れを語り始めます。栄華を極めた六条河原の院、今は荒れ果てて見る影もない、自分も老いの波が押し寄せると嘆く老人は昔が恋しく、あの時に戻りたいと大泣きします。華やかかりし頃にもう一度戻りたい。適わぬ願いを請う人間のはかなさ。30代では気がつかず、もし気がついたとしても演じきれない老いの波を、今60歳を過ぎ、自然と涙する自分に気づきます。

回想し涙する老人に僧も感涙し、そして名所を尋ねます。北の音羽山からはじまり、右廻りに「清閑寺」「今熊野」「稲荷山」と進み、「藤の森」から案内して「木幡山」「伏見」「竹田」「淀」「鳥羽」、最後は「小塩山」から「松尾」「嵐山」と360度パノラマ世界で紹介します。
この場所と方角は実際に京都にお住まいの方ならば、少し位置が違うと思われるかもしれません。私も謡いながら少し位置がおかしいのでは、と思ったりしましたが、伝書に「方角などにこだわらないのが能である云々」と記されていたのを読み、驚きと同時にすっと納得してしまった自分に実は驚いています。
感涙の涙にむせいだ後に、カラリと気分を変えての名所教え。『融』は深い執心がありながら、あまりじめじめしない作りとなっています。
前場の最後は、興に乗って長物語してしまった、自分は汐汲みだったと我に返り汐汲みする場面になり、見どころにもなっています。池水を海水に見立て汀に寄って舞台の外に田子桶を落とし汲み上げる型は、一瞬、観客をはっとさせます。左右の手に田子桶を持ちながら、正面先に勢いよく出て、舞台のへりぎりぎりのところでぴたりと止まる、至難の技です。
汐を汲んだ老人はすぐに消えてしまい中入となりますが、当然田子桶を担いだまま消えるべきところを、舞台中央に田子桶を落とし残します。このような演出もまた能らしく、ひとつの余韻を残すものと言えるでしょう。

『融』の後シテは、ありし日の融左大臣の霊として出現します。昔を偲び、すべての消滅を惜しみ月下で遊舞します。舞は「早舞(はやまい)」と呼ばれる盤渉調(ばんしきちょう)の高音の音色で、やや早めのスピードある舞です。颯爽としながらも寂寥感もある、二種混合の舞をどのように優雅に舞うか、今回の私の思考するところでした。強く凜々しく、時には激しく、融の遂げられなかった執心を舞い尽くすやり方もありますが、今回、融の複雑な寂寞たる心境も早舞で表現したく、「クツロギ」の小書を付け、その前後の印象を変えられたらと、お囃子方にご協力いただきました。


「クツロギ」とは文字通りお休みする意味です。舞の途中で橋掛りへ行き、三の松あたりにて、左廻りから右廻りと水の流れを想像させるように動き、最後は袖を返して止まりしばし休止します。
「クツロギ」の袖を巻く型までは昔を楽しく偲ぶ「陽」の雰囲気で舞い、夜空の月と池水に映る月影を眺めるうちに徐々に栄華時代を回想し、次第に時のうつろいと喪失感を「陰」な気持ちに変えて舞えたら、と緩急をつけてみました。
そして最後は型の多い地謡との掛け合いのキリの仕舞どころとなります。シテ謡の「例えば月の有る夜は、星の淡き(うすき)が如くなり」のように「月が出ている夜は、星は見えづらい」。なにかが出れば、なにかは引かなくてはいけない、謡う融の諦観がしみじみと感じられます。
融は冥界ではなく月の都から河原院に降りて、昔の雅を満喫していた頃を懐かしく偲び、遊舞しますが、夜が明ける前に、また月の都へと姿を消します。
決して時の流れは止めることは出来ません。

私の『融』の初演は平成4年、今から24年も前のことです。当時は『融』のテーマなど気にもせず、師の指導を仰ぎ舞台を勤めるだけでした。それでも演出の工夫に目覚めはじめた頃で、今では抵抗なく着用する後シテの黒垂(くろたれ)も、実は喜多流としてはじめて使用したのはこの時でした。
当時いろいろな陰口があったことはその後知る事となりますが、よりよい演出を、と意気込んでいた昔、融のように懐旧してしまいます。
「60歳なんてまだまだ、若造よ」と言われる能楽の世界ですが、私も還暦になり、それまで見えなかった能の世界が少し見えはじめ、聞こえなかったものも少し聞こえるようになりました。ようやく源融の生前への執心と懐旧が少しわかるようになりました。
最初、『融』が名曲である理由が正直はっきりしなかった私でしたが、稽古しながら、この曲が消滅する人(今は亡き人々)により伝承され、その時々の人々の手により工夫が加えられてきたことも知りました。稽古すればするほど、人生の深いところを描いていると共感するところが多く、やはり相当な名曲だと気づき熱が入ってきました。能に携わる者は、名曲は名曲であるがゆえにより一層の磨きをかけ、その光を観客に届けなくてはいけない、そう確信しました。
竹内まりやの「人生の扉」という歌に「信じられない速さで、時は過ぎ去る、と知ってしまった」があります。この歌詞が『融』と結びつくなどと思ってもいませんでしたが、今はしみじみとわかります。能はやはり、現代にちゃんと生きている!と感心しています。
(平成28年3月 記)
文責 粟谷明生
写真
粟谷能の会 『融』シテ 粟谷明生
撮影 石田 裕 森 英嗣(橋掛にて入幕の一枚)
『玉井』を勤めて 「神様の能」の面白さ投稿日:2016-01-10

『玉井』を勤めて
「神様の能」の面白さ
平成28年1月10日(日)喜多流自主公演で、能『玉井』を勤めました。
『玉井』は神話の海彦山彦兄弟伝説を題材にした作品です。
まずは簡単にあらすじをご紹介します。
兄から借りた釣り針を魚に取られた弟の山彦・火火出見尊(ホホデミノミコト)は、釣り針を探しに海底の都に行きます。そこで海の支配者・老竜王の娘、豊玉姫と結婚しますが、月日が経つと地上に戻りたくなり、豊玉姫に相談すると、父の竜王は取られた釣り針と海水を自在に操る二つの魔法の珠を尊に授け、大鰐(鮫)に乗せて地上に送り届けるのでした。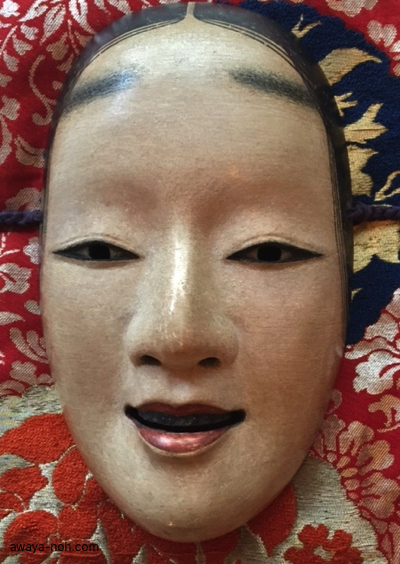

配役は、火火出見尊(古事記では火遠理命)はワキが勤め、前場の豊玉姫と玉依姫の姉妹を前シテと前シテツレが勤めます。後場の豊玉姫、玉依姫は後ツレとして、前場とは別人が天女の姿で登場し、後シテの海神・竜王は前シテの豊玉姫を勤めた者が演じます。つまり、ワキ以外は前場と後場をそれぞれ異なる演者が勤めることになります。この登場人物を多彩にした豪華な作風は、いかにも作者・観世小次郎信光らしいところです。
能には「神様の能」と「仏様の能」があり、とりわけ神様の能は奇抜でスケールが大きく、あるときは人が神であったり、逆に神が平気で下界に舞い降りてしまう大胆発想が面白く、作品を引き立てています。
例えば、火火出見尊は、天神七代地神四代の者であると堂々と名のるものの、神力を使える神の子なのか、そうではないのかが、はっきりしません。
尊が、目を細かく編んだ竹かご(目無筐=まなじかたま)に乗ると易々と海底に着いてしまうこと自体も、神の子であるから、?土翁(シオヅツオ:海水の神)のお爺さんが教えたのであって、その特別な力を発揮することが出来る時もあれば、そうでもない時もある、そういう発想がおかしくてたまりません。ご覧になる方も「普通ではない」「あり得ない」という思考をどこかに置き去りにして、ただただ素直なお気持ちでご覧になればよいのではないでしょうか。「神様の能」とは、そんな摩訶不思議な世界観を持っているように思えます。

さて、海底に着いた尊が桂の木陰で佇んでいると、水を汲もうと井戸に近づく女(豊玉姫)が尊を見つけてしまいます。
「あら恥ずかしや我が姿の、見えける事も我ながら、忘るる程の御気色、容(かたち)も殊に雅びやかなり。ただ人ならず見奉る。御名を名のりおはしませ」と、尊のイケメン容姿に完全に一目惚れしてしまい、大胆にも名前を尋ねます。
尊が名を名のり、釣り針を探しに来たことを明かして、「ここはどこ?」と尋ねると、豊玉姫は「釣り針は探してあげますから、さあさあ、龍宮に入りましょう?」と早速招き入れます。

この場面、どうも夜の繁華街での、一見綺麗そうなおねえさんの、あのあやしい勧誘シーンを想像してしまう私ですが、こここそが海洋民族が地上民族を招き入れてもよい、との意思表示であると思い意識して謡いました。
さて、三人が龍宮に入ると、以前は最初に舞台に据えられた作り物の「もちの木」と「井戸」は中入まで置いたままでしたが、場面が変わるのであれば、作り物は無い方が龍宮内に移動したと想像しやすいのではと思い、序にて引き下げる演出に替えてみました。能は古い形式も大事にしたいですが、ただ今は今なりの時代にあった演出と工夫を心がけたいと思っています。

竜宮で、尊は父母にも歓迎され晴れて豊玉姫と結ばれます。クセの謡に
「天より降る御神の外祖となりて豊姫も、ただならぬ姿、有明の・・・」とあり、「ただならぬ姿」はもちろんご懐妊を意味します。
詞章は登場人物の役柄や立場により丁寧に尊敬語を使うかどうか区別されていますが、豊玉姫も見惚れた当初は「いかに申し上げ候」と丁寧な言葉遣いだったものが、母となると「御心安く思し召せ!」と豹変します。この途端に強い口調に様変わりするところなど、現在にも通じていて、能は少し深読みするとちっとも古くさいものではないことを証してくれます。「女は弱し、されど母は強し」は昔のこと、今は「女は強し、されど母はもっと強し」です。

やがて、尊は豊玉姫の父、海の支配者・老竜王から釣り針と海水を自在に操る潮満汐干(しおみつしおひる)の二つの魔法の珠を授かり地上に戻ります。
能『玉井』でお伝えする「海彦山彦伝説」はここまでで、後場は天女(豊玉姫と玉依姫)の舞と竜王の舞事があり、尊を送り出し、竜王らも竜宮に帰って終わります。しかし私は、この伝説のその後の展開が気になりました。

能では、兄が怒ったときは二つの魔法の珠が役立つと、クセの中で謡われますが、その後の展開、竜王が「この釣り針は、おぼ針、すす針、貧針、うる針」と唱えながら後ろ手に渡し返すこと、兄が高いところに田を作ったらあなたは低いところに作り、兄が場所の交換を求めたら従い、もし兄があなたを恨んで攻めてきたら潮満玉(しおみつたま)で溺れさせ、助けを求めたら汐干玉(しおひるたま)で救いなさい、といった細かな内容は謡われません。
実際、古事記では、兄は田の交換を求め、遂に弟を襲いますが、魔法の珠の威力で兄は負け弟に従うこととなります。その際、兄方は顔に丹(に)を塗り俳優(わざおぎ)となって、その溺れたときの様子を演じ伝える役目を担い、敗者が勝者に芸能をもって仕えること、それが芸能者のはじまりと、日本書紀には書かれています。

能が負を背負った者を取り上げ、猿楽師が敗者の俳優(わざおぎ)を演じる。そんな仕組みが、このような太古伝説に息づいていて、そこに遡ることが出来たことは『玉井』を勤めるお陰と感謝し、大きな収穫、と正直喜んでいます。

『玉井』の後日談の最後、兄弟喧嘩のあとの話はまだまだ興味深く続きます。
尊の子を身ごもった豊玉姫は地上の尊を訪ね出産することを告げます。
海岸に産屋を建て始めますが、急に産気づき「今から出産しますが、私を見ないで」と言い産屋に入っていきます。神の子も所詮、人。「見ないで!」と言われたら見たくなるもの、中を覗いてしまいます。すると大きな鰐がのたうち回っているので尊はびっくり仰天、その場を逃げ出してしまいます。

尊が約束を破り出産を見たことに恥じらいと怒りで豊玉姫は生んだ子を置いたまま海の国へ帰ってしまいます。心配した海神の老竜王は、妹の玉依姫に子の養育を頼み、地上に送り込み育てさせます。生まれた子の名前は、天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(アマツヒコヒコナギサタケウガヤフキアエズノミコト)、とても長い名前に驚いてしまいますが、更に驚きは、この子が玉依姫、つまり叔母と結婚して4人の子をもうけ、そして4人目の子が神倭伊波礼比古命(カムヤマトイワレビコノミコト)、初代天皇・神武天皇となることです。常識を超える世界で、いろいろな男女の間柄を想像してしまいます。
能は演じ手も観手も想像が必須です。いろいろなことを想像することは大事ですが、妙なことまで想像すると、私は舞台で粗相をしそうな気がして、今回はお正月の初番であることを心がけて勤めました。
我が家の伝書に「この能はすべて、ひしけぬ様にかさを取る事専一也」とあります。「ひしけぬ」は「拉げる=押しつぶされて砕ける」の意で「かさ」は「嵩」です。『玉井』は全体的にどっしり、ゆったりと演じるのですが、逆に押さえ過ぎるのはいけない!と警告し、大きさや重みを大事に勤めることを第一に考えなさい、という伝言です。深い教えを知る事が出来たことも、大きな二つ目の収穫でした。

伝言を咀嚼し、守り大事にし、これからも私らしい能、私の個性を生かした演能を心がけたい。お正月の公演の場をいただき、今年も能と共に生きていこうと思いました。
(平成28年1月 記)
写真提供
能『玉井』シテ・粟谷明生 撮影・成田幸雄
能面 「増女」石塚シゲミ打 「悪尉」粟谷家蔵 撮影・粟谷明生
落人の悲哀 『安宅』(延年之舞)を勤めて投稿日:2015-10-07

落人の悲哀
『安宅』(延年之舞)を勤めて

昨日の粟谷能の会(平成27年10月11日)へお越しいただきました皆様、ご来場御礼申し上げます。
還暦記念と銘打ちました第98回粟谷能の会も無事盛会に終わることができて、今ほっと一安心。正直な気持です。
『安宅』の初演は43歳、お囃子方は笛・一噌隆之氏、小鼓・鵜澤洋太郎氏、大鼓・安福建雄氏。53歳の小書「延年之舞」披キでは、笛・松田弘之氏、小鼓・鵜澤洋太郎氏、大鼓・柿原弘和氏のお相手で勤めました。今回60歳の還暦記念の再演「延年之舞」は、笛・一噌隆之氏、小鼓・大倉源次郎氏、大鼓・亀井広忠氏でした。
富樫役のワキは親友・森常好(現 宝生常三)氏が三回ともお相手してくださいました。
『安宅』のような現在物は直面(ひためん)と呼ばれる能面をつけずに素顔で舞台を勤めます。能面は視界が狭く、肉体的にも楽ではありませんが、では直面ならば楽なのか、と問われると、顔自体を能面のように意識しなくてはいけないところが難しく厄介だと思っています。
『安宅』のシテ・武蔵坊弁慶は青年の若い顔では物足りず、かといって年を経た顔ならば事が足りるのか、というとそうでもないようです。
シテ方の能役者にとって直面で勝負出来る賞味期限はそうは長くはない、そう思っています。ですから期限内にできるだけ挑戦しておこう!と考えたのが今年の私の演能テーマとなり、春59歳で『正尊』、秋は60歳成り立てで『安宅』「延年之舞」でと企画、選曲しました。
『安宅』のような現在物は能役者にとって、能の様式美に心技体すべてをゆだねるやり方と、役を演じる芝居心に重点を置くやり方もあると思います。
私も初演では様式美にすっかりお任せするやり方となってしまいましたが、53歳の再演ではどうにかして弁慶という役を演じる、自分なりに芝居になるギリギリの境界線内側まで手を伸ばしたいと思い挑みました。しかしなかなか行けるようで行けない壁を意識させられました。いつの日か、もうこれ以上やったら能ではなくなる、という壁手前までで演じてみたい、それが60歳までに経験出来たら・・・、と考えていました。
能の様式美を蔑ろにせず、調和を取りながらも能の世界の外回りギリギリでの演能、それが私の現在能への美意識といっても過言ではありません。昨日の『安宅』がその域に達したのかどうかは、まだ自分自身答えが出ていない状況ですが、そう意識してのこと、と書き残しておきます。

例えば声。義経へ剛力に変装を依頼する謡や、主君を打擲する非常識なふるまいを詫びる謡。もちろん勧進帳も同様ですが、詞章によって変わる、声の強弱、高低、温冷、明暗、詰め開きなどを頭で考え、それが身体を通して出せるかが大事であり、そこへの意識を忘れてはいけないことを、60歳になってようやく、理屈だけではなく身体でわかりはじめたのです。まあ、なんとも遅過ぎ、と自己反省をしています。

そして曲の理解度を深めること。
演者の年齢により理解度は変わります。また変えなくてはいけないと思っています。
初演43歳と同じように演じていては進歩がありません。
いつも新しい発見がなくては気が済まない性格でもあるので、何かないかな?と探しています。

今回は野村四郎先生のご著書『狂言の家に生まれた能役者』の「安宅について」を参考にさせていただき、喜多流では無かった型を取り入れました。
関所での非礼を詫び、ところの名酒を持参してきた富樫の酌を受ける弁慶ですが、安宅の関はこれから落ちて行く道のりのまだまだはじめ、序の口です。このような困難な道がたくさん待っているかと思うと、弁慶は酒など酌み交わせないのです。富樫を信じていないのです。ですから、呑んだふりして相手が見ていない隙に酒を捨てる型を試みました。中啓(扇)を広げ、酌をうけた型をした後、「面白や山水に」と謡いながら広げた中啓を裏返しにし、「こんな酒呑めるか!」の意思表示です。
古典の伝統芸能は先人の教えを正しく継承することだと思いますが、ただ真似ていれば、それが正しいという考えには同調出来ません。古典を今に生かす、そのためには能にあることならば、流儀の壁など取り払い、よりよい舞台を観客にお見せする、それが芸能者のいろはのいだと信じて止まないのです。
粟谷能の会では「演能の最後の拍手は囃子方が退場するまでご遠慮ください」とお願いしています。『安宅』をご覧になり、最後、あ〜明生さんよかったわ、はい、頑張りましたね、の拍手は正直要りません。
落人のなった義経一行、これからの彼らの人生と悲哀が、終曲し最後幕に入るときの後ろ姿に出せるかどうかが本当の勝負どころだと思うのです。ですから、そこでもし拍手がおきたらもう完全に私の能は不合格ということになるのです。
図々しく「拍手はご遠慮ください」など記載しなくても、「どうしても拍手なんてできないよ」と言わせる能役者になりたい、今思っています。(2015年10月 記)
『安宅』については次の演能レポートもご覧ください。「能の表現と芝居の境界線」(1999年3月) 「延年の舞について」(2009年3月)
写真
1,跳ぶ型 3,金剛杖にて 撮影 石田 裕
2,勧進帳を読む、 4、盃の酒を捨てる型 前島写真店 成田幸雄
三流立合い『松風』の 一番手を勤める投稿日:2015-10-07

三流立合い『松風』の
一番手を勤める
粟谷 明生

国立能楽堂主催・定例公演『松風』は「演出の様々な形」をテーマに、10月から三ヶ月に渡り、三流の「立合い」の催しとなりました。10月喜多流(粟谷明生)、11月観世流(観世銕之丞)、12月に宝生流(武田孝史)で、三流それぞれ小書の特別演出となります。喜多流は「身留(みどめ)」、観世流は「戯之舞」、宝生流は「灘返・見留」です。
立合いの一番手として、私は10月16日(金)に「身留」にて勤めさせていただきました。
喜多流の小書は他に「戯之舞」と「見留(みとめ)」があります。「戯之舞」は先代喜多実先生が先代観世元正宗家より頂戴したものですが、残念なことに、あまり演じられることなく今日に至っています。今回の「身留」もあまりやり甲斐のある演出とはいえず、ほとんど演じられることはありませんでした。再演となると、どうしても派手な「見留」を選んでしまい、私も、10年前の粟谷能の会では「見留」で勤め、父の『松風』もほとんどが「見留」でした。

「身留」は破之舞の最後に、舞台大小前にて、松に向かい一足つめる(松に近づく)型で、能役者の松への思いを身体で表現する小書です。「見留」の場合は橋掛りの一の松にて、遠くに見える松を、左手に中啓を持ち替え眺める型となり、粋な格好に皆、憧れを持っています。それに比べ、「身留」はなにもせず身体の扱いだけで表現するので難しく、正直あまりやりたくない損な小書だと思っています。しかし喜多流にしかない、というのが企画者には面白いのでしょう、「身留で」で依頼されてしまいました。

今回は、大小前で松に向かっても正面席からは作物の松が重なって見えて効果が薄いと考え、松への思いがよく見えるようにと常座にて行いました。通常、小書「見留」になると「関路の鳥も声々に」で、ツレと共に謡の中で幕に入ってしまい、ワキが一人残り「松風ばかりや残るらん」と留拍子を踏んで終曲となりますが、「身留」でもこの形で入ることにしました。
それは、上掛りが「今朝見れば、松風ばかりや残るらん、松風ばかりや残るらん」と返しの謡があるのに対して、喜多流は「松風ばかりや残るらん」と一回で謡い切り、しかも高音で謡い留めるからです。二度謡う演出と一度しか謡わない喜多流の演出では自ら違い、その特徴を最大限に活かすのも立合いならばこそと、敢えて「身留」でも走り込むように姿を消すやり方を選びました。二人の海女乙女が潔く、スーッと消え去ることで、僧の夢のできごととの印象を強くさせ、効果的でなないでしょうか。
伝書は大事ですが、それは過去演じたものの記録です。伝書にはこの時はこのようにした、あの時は別のやり方のあり、と書いてあります。ヒントにはなりますが、書いてある通りでなければ間違いである、とは言えないと思っています。その場に一番似合うやり方、観客にもっともよい状態を提供するのが、本当に能役者のあり方だと信じています。

面に関しては、今回は立合いなので、最初は自分好みの「宝増」を使うつもりでしたが、喜多流らしく「小面」がよいのでは、とのご意見なども聞こえて来て、いろいろ悩み、最終的には山中家より小面系の「小姫」を拝借いたしました。伝書にはシテもツレも「小面」と記載されていますが、私はシテの松風と妹の村雨が同じような顔、表情では、その性格の違いがはっきりしないと思いました。敢えて違う面によって、恋慕の心が強い姉と、少し冷静でいられる村雨、そのように見えるようにと、意識して選びました。
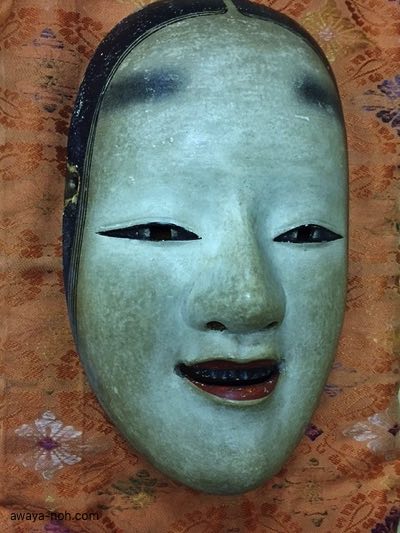

立合いは三流の特別演出(小書)の違いから、演出の仕方がいろいろあることを見ていただくことも重要ですが、それぞれの演者が『松風』という作品をどのように描き出すのかを観ていただくことにあると思います。これは流儀や小書きの違いだけでなく、粟谷明生の『松風』、観世銕之丞の『松風』、武田孝史の『松風』、三人三様の『松風』を観てほしいと企画されたのです。小書きや表の選択についてはすでに書きましたので、ほかにどのようなことを念頭において勤めたかを述べてみたいと思います。

第一場面はワキ(旅僧)の登場から「汐路かなや」で留拍子を踏むところまでです。旅僧が須磨の浦の由緒ありげな一本の松を見つけ、所のものに尋ねると、在原行平の愛した海女乙女の松風(シテ)、村雨(ツレ)の旧跡であると教えられます。旅僧が松を弔うと、幽霊の松風と村雨が静かに現れ、身の境遇を嘆きながら汐汲みを見せます。シテとツレの登場は「真之一声」という荘厳な出囃子によります。「真之一声」は脇能での登場に使われるもので、神の登場を思わせる荘重な趣向、脇能以外では、喜多流ではこの『松風』にしかありません。その荘厳な響きにあわせて、二人の幽霊が旅僧の夢の中に現れ、連吟となります。ここは「真之一声」の重々しさにあわせ、つらい汐汲み労働をさせられているという暗く苦しむ姉妹を演出します。この第一場面の最後、「汐路かなや」で一旦終わるような構成で、大鼓と小鼓の囃子方も一旦床几から降ります。ここまでが田楽の名手・喜阿弥作の『汐汲』で、次からが第二場面となり、観阿弥の『松風村雨』へ、さらに世阿弥が改修して現在の『松風』へと練り上げられています。
第二場面は、海女に一夜の宿を借りた旅僧が磯辺の松を弔った話をすると、海女は行平との恋物語を始めます。ここは、囃子方が床机からおり、シーンと静まり返った音のない世界で、静かにワキとの問答、シテ・ツレのクドキと続き、身の上の心境や変化を謡だけで表現します。少ない動きの中に細やかな心の揺れを表現するところで、ただ座っていればいいのとは違います。クセの「あわれ古を・・・」からは行平の形見の烏帽子と長絹を手にして追憶の涙に沈みます。形見を眺めては泣き、悲しさのあまり放り投げてはまた抱きしめ、また眺め泣き崩れる、ここも少ない動きで最大限の表現をしなければならず、難儀なところです。謡も強弱、明暗、緩急、詰め開き、張りと、あらゆる表現方法を駆使してその情景、心情を描き出していきます。
第三場面は物着(舞台上で装束を替える)から終曲まで。行平の形見を身に着けた松風は物狂いとなり、松を雪平を思い寄り添うほどですが、村雨に制止され諭され、次第に冷静になります。「立別れ」と行平の歌から中之舞、その後に破之舞が入ります。破之舞は短いながら松風の心を表現する強い舞です。この第三場面は変化があり、楽しくご覧いただけるところではないでしょうか。やがて海女乙女は妄執の苦しみを述べ、旅僧に回向を乞い消えていきます。すると夜が明け、旅僧は目を覚まし、すべて一夜の夢であったと終わります。

父・菊生は「演者は艶(イロ)が命」と口癖のように言います。『松風』の艶とは、宮中の高貴な方の艶とは違うものでしょう。海女乙女の素朴で純粋な、それでいて情熱的に思う女性の艶をいかに出せるかも課題でした。果たして「艶」のある女性になれたでしょうか。
今回、三流立合いの場に立たされると、いろいろなことが見えてきました。もちろん観世銕之丞氏や武田孝史氏がライバルとして見えてきます。負けてたまるか、という気持ちは腹の底にはあります。ただ、それにはどうしたらよいか、に目をむけることができたことが、今回の大きな収穫だったと思います。
面の選択、小書の見直し、観客へ届く謡い方はできたか。そして「長かったけれど良かったわ」ではなく、「あっという間に終わったわ」と思っていただければ勝算があると踏んでいました。今回、演能時間は1時間50分ぐらいでした。時間のかかる大曲をだれない進行で、観客の心を惹きつける、60歳になったからできることだと思いますが、それが私の『松風』への美意識なのです。あっという間に終わったわ、もう少しやってほしかったわ、と能楽堂を出られる方々から声が漏れた時、私は私自身に勝てたことになるのですが、さてどうだったのでしょう。
思えば、観世銕之丞氏と武田孝史氏とはほぼ同じ年齢。若い頃から親しくさせていただき、一緒に舞台に立ち切磋琢磨したこともある間柄です。お互いに60歳前後して、このような立合いができることは光栄であり、感無量のなにものでもないこと、ここに書き留めておきたいと思います。(2015年10月 記)
『松風』については次の演能レポートもご覧ください。 「シテツレの役割」(2002年10月) 「恋慕と狂乱」(2005年10月)
写真提供
国立能楽堂 (撮影:青木信二)
前島写真店 (撮影:成田幸雄)
『杜若』を勤めて 杜若の精と伊勢物語投稿日:2015-09-07

『杜若』を勤めて
杜若の精と伊勢物語

秋田県の大仙市にある唐松能舞台で、先日(平成27年8月30日)、三度目の『杜若』を20年ぶりに勤めました。唐松能舞台は大曲と秋田の中間よりやや大曲寄りの、JR奥羽本線羽後境駅から徒歩で10分ぐらいのところ、まほろば唐松中世の館にあります。秋田の大曲と聞くと、増田、十文字、横手、角館とともに、父・菊生が指導に通った地、十文字から増田への雪道を橇(そり)で行った話などが思い出されます。今では新幹線ができ便利になりましたが、昔はその地にたどり着くまで大変だったようです。
唐松能舞台は京都西本願寺の北能舞台を模して造られたもので、秋田県では唯一の舞台です。昔ながらの観能の形が楽しめるようにと、屋外の舞台になっています。今世紀初め、この舞台が建造された当初から、この時期に、粟谷能夫が大仙市から興業を依頼され、今回は私の『杜若』と、半能『鍾馗』を能夫が勤める番組となりました。開演前に一時小雨が落ちることもあり、お天気が心配されましたが、開演時には雨もやみ、夏の終わりを感じさせる爽やかな風を感じての演能となりました。

能『杜若』は旅僧(ワキ)が三河の国八橋の沢辺で、咲き乱れる杜若を眺めているところに、里女(シテ)が現れ、業平の詠んだ「唐衣着つつなれにし、妻しあれば、遙々来ぬる、旅をしぞ思ふ」の古歌を教え、旅僧を我が庵に招き入れます。
この歌はご存知「伊勢物語」第九段に出てくる歌です。「むかし、男ありけり。その男、身を要なきものに思ひなして、京にはあらじ、あづまの方に住むべき国求めにとて、行きけり」と始まる「東下り」の段で、「かきつばたという5文字を句の上にすえてよめ」と言われて詠んだ歌です。伊勢物語には「男」を誰と特定していませんが、「唐衣・・・」の歌は古今和歌集では在原業平作となっているので、業平の歌であることは明らかです。
伊勢物語にはその前の三段から六段にかけて、男(業平)と二条の后・高子(藤原長良の娘)の禁断の恋の話が語られ、后となった高子にはなかなか近づくこともできない男の姿が描かれています。
能の舞台に戻りましょう。

旅僧を庵に招き入れると、やがて女は、高子の后の衣を身につけ、業平の透額(すきびたい)の冠を戴き、雅な姿で現れ、実は自分は杜若の精であると名乗ります。そして業平は歌舞の菩薩の化現であるから、業平の歌の恵みによって、非情草木に至るまで、皆が成仏出来ると語り、舞い、姿を消して終曲します。
シテは物着で、杜若の精でありながら、高子の后のようであり、業平のようでもあって、まるで両性具有のような姿となり、しかも業平は歌舞の菩薩でもあるというのですから、観ている側も演じる者も、焦点を絞れず正直戸惑ってしまうのではないでしょうか。
私自身も初演では、舞っていてどこか明確性を欠くように思いながら、答えが出ずに、ずるずると終わってしまった記憶がありますが、今、それが能の本質的な部分でもあるように思えて来ました。敢えて二重三重の姿にし、伊勢物語の情趣を厚く描きだしたところに、能『杜若』の魅力、面白さがあるように思えます。
父・菊生は、「『杜若』は、あまり深刻にならず、ただただ綺麗に気品と品格、そしてところどころに女性の優しさを盛り込めるといい」と話していましたので、そのように意識して勤めてみたつもりですが、その域まで達せたのか、まだ自分ではわからないでいます。

今回は、時間の都合上、少し短縮版にしてほしいと、主催者側からの要請がありました。短縮するにはどうするか。他流でもいろいろな小書で工夫されています。それらも参考にし、今回は観世流の小書「恋之舞」のような演出にしてみようと考えました。
この小書は序、サシ、クセを省き、地次第の「遥々来ぬる唐衣・・・着つつや舞を奏づらん」から直ぐに「花前に蝶舞ふ、紛々たる雪、柳上に鶯飛ぶ片々たる金」につなげ、序之舞を主軸とする演出です。
「恋之舞」は十五世・観世元章の創作小書です。先代・観世銕之亟先生は「在原業平に恋をしてしまう花の精は、儚さ純情さがストレートに出ていて、通常の『杜若』よりやり易い」と言われたようです。友枝昭世師からは「花の精よりも、業平と二条の后との関係に焦点を置いているように思える」と教えていただきました。
確かに、小書「恋之舞」は文字通り、業平と二条の后の「恋」に焦点を絞っているように見えます。クセを見ると、伊勢物語はどのような物語かを語る詞章が続きます。十五段から始まって初段、七段、八段の歌も引き、「ひとたびは栄え、ひとたびは衰ふる理(ことわり)」という当時の世相に敏感な無常観も入れられています。この能で伊勢物語の全体を味わってもらいたいという作者の意図があったのかもしれません。当時の観客には伊勢物語は人気で、各段の歌などが頭に入っていて、このクセを面白く聞いたことでしょう。

焦点が絞りにくかったのもこのあたりにあったかもしれません。今回、業平と二条の后の恋に焦点をしぼり、やり易くなったことは確かです。能を短縮版にするとき、演劇的に省く根拠がなければいけない、そう思います。今回敢えて短縮版を勤めることで、根拠らしきものが見出せて、勉強になった、と思っています。短縮版を演じたからこそ、通常の『杜若』の魅力も再認識出来ました。

能『杜若』の主題、焦点はどこにあるのか? と自問自答したことがありましたが、今は、一点ではない、と答えるしかありません。伊勢物語絵巻の魅力を伝えたいようであり、能らしく草木の精としての杜若の花の美しさも見せたい。業平と高子の恋も大事であり、業平が歌舞の菩薩でその功徳で草木国土悉皆成仏、すべてが救われるという宗教性も絡めてしまうほど、ここが一番のポイントなのかもしれません。これらすべてを万華鏡のようにぐるぐる回して様々な模様でご覧いただけるのが『杜若』という能の魅力、味わいなのかもしれません。観る角度によりいろいろに変化する、つかみどころがない面白さ、それこそが能本来の面白さの一面でもある、と思えるようになりました。

料理で例えれば、通常の『杜若』がフルコース、短縮版「恋之舞」はそのメーン料理の魚か肉料理を省いて、少し軽目のコース料理といったところでしょうか。趣味の写真で
考えると、通常の『杜若』は花弁のひとひらから茎、根までを撮り、短縮版は花弁の中心部、業平と高子の恋を、あまり説明的にならず、杜若に近づいてアップして撮る、そんな感じではないでしょうか。
『杜若』は世阿弥作とも、また金春禅竹作ともいわれていますが、もともとはそれ以前のものではないかという気がします。ワキの名乗りから始まって、能の形式は整えられていますが、世阿弥や禅竹作なら舞台上で物着をさせずに中入りという形態をとったのではないでしょうか。それをしないところに演者としては古風な趣を感じてしまいます。

今回の演出で、初冠に「日陰の糸」を垂らし、あやめの花を挿して飾りとしました。
「日陰の糸」は喜多流にはありませんが、他流ではよく見られる形態です。とても雅な感じに見えるので、最近は敢えて付けるようにしています。

我が家の喜多寿山の伝書に「初冠の心第一也」と最後に書かれています。これは、女性の面をつけ、女性の装束を着ながらも、初冠、つまり男に、それは業平であることを忘れてはいけない、という教えであると演じる寸前に気がつき、今勤め終えてようやく理解出来た、というのが正直なところです。

喜多流の小書としては「働」と「合掌留(がっしょうどめ)」があります。
当初、「働」で演ってみようと計画していました。「働」は序之舞が終わり、シテ謡「昔男の名を留めし」を謡った後に囃子方のアシラヒが入る演出です。シテは舞台を一周するだけのもので、余韻を楽しむ風情ですが、序之舞のあとの謡は、やや声を張り上げ謡うのが鉄則です。その高揚を少し冷ます、シテ役者に冷静になる時間を与えるような意味合いがあると理解しています。そして「花橘の」と再び張り上げて謡うことで、演技の熱を上げたり下げたりさせる、それが「働」という高度な演出だと思っています。
実は、今回の「働」は、太鼓の金春国和氏と相談して、序之舞もやや長めにし、小書「恋之舞」を真似て、橋掛りでも舞うように試みたい、美しく群生する杜若を見て、そして自分の姿を映し見るような所作も入れるから、よろしく、とお願いしていましたが、昨年突然亡くなられてしまい、残念で堪りません。今回はご子息、国直氏が代演されることとなり、凝った演出は出来ませんでしたが、それでも「働」を試み、序之舞の寸法は変えずに、橋掛りに行く型は取り入れて替えの演出としました。

そして、最後は大小前にて合掌して留める小書「合掌留」を、番組には記載していませんでしたが加えました。故金春国和氏への追悼の気持ちを込めて、の替え演出です。
「合掌留」は残り留めという、謡が終わっても囃子方が延びて囃す演出があるようですが、伝書に「打延し候(残り留)事、これ無きこと也」と書かれていたので、今回は延ばさず勤めました。合掌は、本来舞台正面先におられる神様に向かって拝むものですが、今回は国和氏のご冥福を祈って手を合わせ、舞い終えました。
(平成27年9月 記)
写真 能『杜若』働 シテ 粟谷明生
撮影 石田 裕
無断転写禁止
『正尊』について 演能機会が少ない『正尊』に取り組む投稿日:2015-03-07
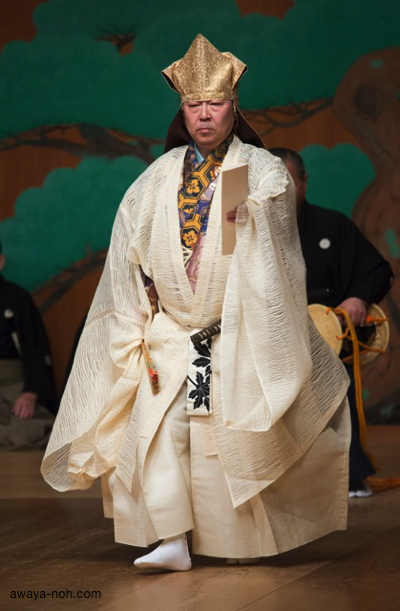
演能機会が少ない『正尊』に取り組む
粟谷 明生
正尊 後シテ粟谷明生 撮影 青木信二
【序にかえて 平成27年は『正尊』59歳『安宅』60歳】
平成27年の私の粟谷能の会は、春は弁慶相手に『正尊』(3月1日)を、秋はその弁慶役の『安宅』を「延年之舞」の小書で勤めようと、かねてより計画していました。この2曲はともに、直面物、現在能、義経物(弁慶物)という共通項があります。さらにいえば、どちらも登場人物が多い曲であり、「読み物」という難しい謡があり、聞かせどころがあります。『正尊』の「起請文」、『安宅』の「勧進帳」がそれで、能の三大読み物に数えられています。もう一つの読み物は『木曽』の「願書」ですが、喜多流にはないので、事実上当流ではこの2つが「読み物」となります。共通項の多いこの2曲を、還暦を迎えるこの年に集中し深めておきたいと考えました。
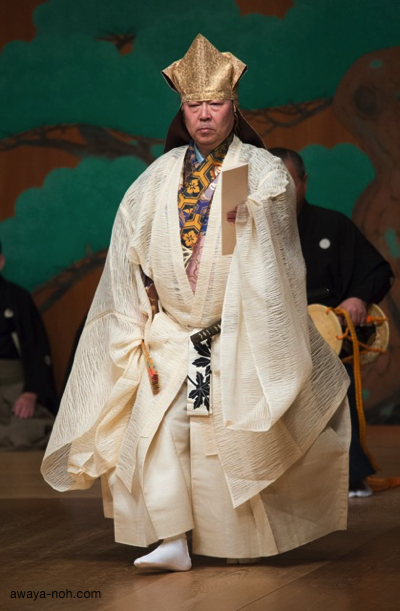
(写真)正尊前シテ 撮影 青木信二
【直面(ひためん)】
直面物(面を付けない曲)は余り若すぎてもその人物の風格が出ず、かといって、歳をとりすぎてしまうと観客は想像しづらくなり、体力が衰えた老体では真の力強さは表現できないと思っています。父・菊生は「自分の顔が巧まずしてその役に見えるときがいつか来る」と言っていましたが、味わいある直面物を勤めるには、旬となる時期がありそうです。今自分がその時期に来ているかは分かりませんが、『安宅』を45歳で初挑戦し、50歳で積み重ね、今年の60歳で3回目、このあたりが私にとっての賞味期限ではないか、と正直思っています。『正尊』は今回が初めてですが、もともと演能の機会が非常に少ない曲、今勤めておかなければ、との思いが強くありました。
【正尊の演能記録】
近年の喜多流で『正尊』を勤めた方は、昭和42年に宗家・十六世喜多六平太氏、昭和57年に故友枝喜久夫氏、平成8年に父・故粟谷菊生、そして平成17年に香川靖嗣氏(「二人会」)、平成25年に金子匡一氏がおられます。宗家が勤められたとき、私は子方(静御前)を、友枝先生のときはシテツレ(江田源三)を勤めています。父・菊生のときは、残念ながらその会で『隅田川』のシテを勤めていたので、同じ舞台には立てませんでしたが、そのときの父の舞台は目に焼きついています。香川氏のときは地謡で舞台を拝見しています。金子氏は松山での公演でしたので拝見していません。

(写真)静御前(子方・友枝大風)に酌をうける正尊(シテ・粟谷明生)撮影 吉越 研
【大人数の能役者を必要とする正尊】
『正尊』は人数物で、静御前を勤められる子方がいなければなりませんし、端正できりりとした義経役、豪快で芝居心もありシテと括抗する弁慶役(ワキ)、そして義経方と正尊方の郎党にそれぞれ数人ずつの若者が必要です。もちろん全体を盛り上げる地謡陣も必要で、それだけの陣容を整えられるかが問題です。数年前に『正尊』をと考え始めたとき、今ならそれができる、と思い決めました。今回、子方を友枝大風君、義経を佐々木多門氏、弁慶を朋友・森常好氏が勤めてくださいました。郎党も若手が勢ぞろいしてくれ、地謡陣も地頭を大村定氏に同世代でまとめてお勤めいただき、熱気あふれる舞台になりました。実は舞台に若手が出払っているため、楽屋は人数が少なく、初番の『三輪』の地頭の友枝昭世師、副地頭の香川靖嗣氏をはじめとした重鎮のみなさま方が、正尊の郎党や中入の私の装束の着付けを手伝ってくださり、まさに若手から重鎮、ワキ方、囃子方が一丸となって出来上がった『正尊』でした。このような結束力こそ演者側にとって大事なエネルギーであり意識であって、それが実現できたことを心底喜んでいます。
喜多流として、『正尊』のような曲は少なくとも10年に一度は舞台に載せ、継承していかなければならないと思います。私の子方や郎党、地謡の経験が宝となっているように、若者が、今回の舞台で経験を積んで、次へのステップにしてくれればよいと願ってもいます。
【あらずじ】
能『正尊』は、頼朝に、不和になっている義経を討つように命令される土佐坊正尊の話です。都に入った正尊は、義経の前に連れ出され、上洛の真意をただされると、熊野参詣のためと言い張り、起請文(神仏に誓って書く文書)まで書いて読み上げ、その場を逃れます。しかし、すぐに戦闘の準備をしていることが知られ、義経らに攻められ、最後、正尊は生け捕りにされて終曲します。
【正尊の役まわり】
正尊は頼朝の命令に背けず義経を討ちに来て、最後は生け捕りにされる、非常に損な役回りです。稽古をしていて、土佐坊正尊(「吾妻鏡」「義経記」では土佐坊昌俊)がどのような人物であったのかが気になってきました。
「能の平家物語」(秦恒平著)に「土佐坊という人物は魅力も乏しく、肌触りのざらついた面白くもない男で、・・・<中略>・・・「あはれ」という美的要素のしずくもない男に造形されていて、際立って弁慶や義経が良くみえる仕掛けを担っている」とあります。
単なる、弁慶や義経の引き立て役なのでしょうか。金剛流のように、シテを武蔵坊弁慶として、起請文も弁慶が読み上げる設定ならば、秦氏のご意見も理解できますが、喜多流や観世流など、正尊をシテとし、弁慶をワキとする設定ではどうでしょうか。敢えて敗者である正尊に焦点をあてることにより、その悲劇の深さがより強く伝わると、作者・観世弥次郎長俊は戯曲したのではないでしょうか。私はシテを勤めるとなると、その役柄に興味がわき、次第に好意を持ってしまいます。たとえそれが草木の精であろうと、義経や弁慶であろうと同じ。勝者であろうと敗者であろうと・・・です。そして、能は負を背負った者をテーマとすることが多く、『正尊』も然りなのではないでしょうか。
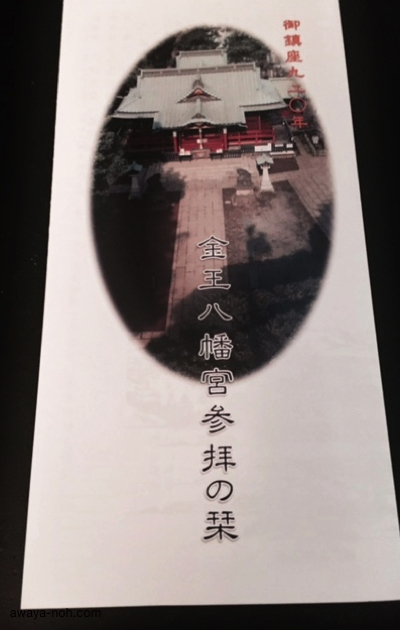
(写真)金王八幡宮の栞
【土佐坊正尊の人物像】
そこで、土佐坊正尊という男がどのような人生を過ごし、どのような最期を迎えたのか、そのあたりを深く知って稽古に励みたいと思いました。
正尊の生年は不明で、何歳ぐらいに没したかもよくわかっていないようです。『平治物語』に登場する金王丸を正尊とする説も確証あるものではないのですが、金王丸ゆかりの渋谷金王八幡宮公式ホームページでは、金王丸は永治元年(1141年)8月15日生まれとあり、これを正尊と結びつければ、そのくらいの生年と考えられます。彼は17歳のとき、源義朝に従い保元の乱で大功をあげその名を轟かせますが、続く、平治の乱で義朝が敗れると、渋谷で剃髪し土佐坊昌俊と称し、義朝の霊を弔います。1160年に義朝が斬られているので、金王丸は20歳ごろ剃髪し土佐坊と名乗ったことになります。
数年後、頼朝は金王丸のいる八幡宮に参籠し平家追討の祈願をして挙兵します。石橋山の合戦(1180年)のころ、正尊は40歳ぐらいでしょうか。壇の浦の戦い(1185年)で平家を滅亡させた後、頼朝は義経に謀反の疑いをかけます。頼朝にとって、平家をあっという間に倒した猛将・義経はまさに鬼神のような存在、要注意人物となったのでしょう。反旗を翻すかもしれないと危険を感じた頼朝は義経征伐を決断し、その密命を正尊に下します。正尊はこれを断れず、同年10月、百騎ばかりを率いて義経の館に討ち入りますが、このとき正尊は45歳ぐらいでしょうか。私は今回、そのぐらいの年齢だろうと考えて勤めました。

(写真)弁慶に無理矢理連行される土佐坊正尊 撮影 吉越 研
【頼朝の義経追討の命令、最初はだれに…】
一説には、義経追討を畠山氏や和田氏が辞退し、誰も名乗りを上げなかったため、土佐坊が自ら進み出たとも言われていますが、定かではありません。今回『正尊』を勤めるにあたって、私は志願ではなく、頼朝から、もしかしたら梶原景時の策略かもしれませんが、「指名されてしまった」と想定して演じました。義経を討ちたいわけではない、頼朝の命令に逆らうことはできない。選ばれたのだから、もう死を覚悟しなければならないという貧乏くじを引いてしまった立場です。頼朝も最初から正尊が義経を討ってくれると期待したわけではないように思えます。反旗を翻したという口実作りの、いわば捨て駒にされたにすぎない、しかもそのことを正尊は充分に承知していたはずです。それでも敢えて捨て駒にならなければならない、そういう男の悲劇がこの曲の狙いだと思いました。
このときの正尊の心境を言い得ているのが、初同(最初の地謡)の「否にはあらず稲舟の。・・・・なるともよしや露の身の。消えて名のみを残さばや。」です。「否」とは言えずに都に上ってきたが、もはや露となる身、生きて鎌倉に戻ることは出来ないだろう。それならばこの身は消えても名を残したいものだ・・・という、悲しい覚悟です。
このようなことは決して昔話ではありません、現在にもあることです。社長のために捨て駒になって罪を負い罰を受けて牢獄の中で過ごす部下や身代わりとなる秘書、通じるものを感じます。能は単に昔の悲劇を古い陳腐なものとして描くのではなく、現在にも充分通じる内容として継続している、すごい芸能であると思うのです。能が本当の古典であることをまさに実証している一面だと確信しています。

(写真)橋掛に勢揃いする正尊と郎党
【潔い正尊】
能『正尊』の最後は生け捕りにされるところで終わりますが、実際の正尊は鞍馬山に逃げ、僧兵に捕まって義経の前に引き出されます。義経は正尊の主命を重んじる忠誠心を賞し、命が惜しいならば鎌倉へ返してやろうと恩情をかけますが、これに従わず、後の世まで「褒めぬ人こそなかりけれ」と言われ、斬首されます。この潔さ。判官びいきの世の中にあって、義経側から見たら悪役であるはずの正尊を敢えてシテにするのは、それなりの意味があるのです。実は喜多流でも昔はシテを弁慶にし、正尊をワキにする演出があったようですが、喜多健忘斉の伝書には「これはよろしからず」と書かれています。『正尊』は敗者である正尊をシテにしてこそ、描けるものがあるはずです。それは私も同感で、土佐坊の哀れと忠誠心、潔さ、男の悲劇がうまく演じられればと稽古に励みました。

(写真)後場 斬り組全景 撮影 成田幸雄
【猿楽の能・最後の戯曲者、観世弥次郎長俊】
能『正尊』は前述したように、観世弥次郎長俊の作品です。長俊は観世小次郎信光の嫡子。観阿弥、世阿弥、禅竹と能は幽玄の世界に入っていきましたが、その流れが変わり、信光の時代は『船弁慶』や『紅葉狩』、『道成寺』に見られるように、一般の人も理解できる、わかりやすく娯楽性の高いショー的な構成の能になっていきました。長俊も信光を受け継ぎ、登場人物も多くエンターテインメント性の高い作品を作り出しました。しかし、ここまで来ると、傾く世界、歌舞伎に近いものになるので、このあたりで、能として幽玄へと揺り戻しがあってもよさそうでしたが、歴史はそうはなりませんでした。その後、新作能も作られたでしょうが、古典として今の世に残るまでにはなっていません。つまり、長俊は最後の戯曲家であり、彼の作品は幽玄物と対極にあって劇的、芝居的な曲であり、猿楽の能はここで息を止めてしまった、と感じます。この能を演じる者は芝居心をいかに発揮するか、しかも能という様式の中で、芝居との境界線ぎりぎりのところまで迫り、いかに表現するかが大きな課題です。今回はこのことを意識し、ワキ方の森氏や、郎党役の若者に協力を仰ぎました。

(写真)橋掛にて弁慶と正尊 撮影 成田幸雄
【試み・ワキへの依頼・1】
たとえば最初の場面、土佐坊正尊が都にのぼってきたが、これは義経を討たんがために違いない、正尊を召し連れて参れと義経に命令され、武蔵坊弁慶が正尊の宿を訪ねるところです。ワキ方下掛宝生流の詞章では「いかにこの家の内へ案内申し候。判官殿よりの御使い武蔵が参じて候、正尊はこの屋の内にわたり候か」となりシテは「武蔵殿とはあら珍しや」と受けるようになっていますが、喜多流は「誰にてわたり候ぞ」で詞章が違います。喜多流は最初誰が訪ねてきたか知らずに、正尊が出て行き武蔵坊と気づくと、「これはまずい、やっかいな武蔵坊だ」と早くも緊張が走る流れになっています。そこで、ワキの森氏に武蔵坊と名乗らないでほしいとお願いしました。思いもよらず、弁慶が訪ねて来た、ということは、自分が頼朝の密命で討ちに来たことがすでに知られている、そう直感した正尊の緊張感を大事にしたいのです。その後は、武蔵坊に問いただされ、正尊は熊野参詣のために来た、道中、病気となってご機嫌伺いが遅くなった、もう少し待ってくれと言いわけをしますが、有無をいわさず、連行されてしまいます。このやり取りの間、私は終始、頭を下げたままにしました。父も先人たちも、何回か頭を上げられています。確かに下げっぱなしは苦しいのですが、ここは顔を見せたくない、という正尊の腹の内を演じたいところです。

(写真)起請文を読み上げる正尊 撮影 吉越 研
【起請文について】
そして、前場での最大の山場は何といっても起請文の読み上げです。特に重く大事に扱っているためか、謡本に細かな節使いや音の上中下や拍子のとり方の記載はありません。習わなくては謡えないようになっていて、正式に伝授された者だけが謡本に朱書きをして習得し、後世に伝承することになっています。今回は、祖父・粟谷益二郎が書き残した伝書を参考にし、囃子方の横山晴明先生、佃良勝氏から地拍子の割付を頂戴し、また父が勤めたときの音源なども聞き習得しました。父が読み物は「最初はたっぷり謡うが段々乗ってきて早く、乗りよく謡う。懇切丁寧に同じスピードで謡ってはいけない」と言っていたことも念頭に浮かべながら謡いました。序破急をつけ、後半に躍動感を持たせ正尊の心意気をも見せる謡い方です。前後の地謡陣にも謡い方のスピードなど私の希望を述べさせていただき納得し協力していただきました。
義経らは正尊が偽りの起請文を書いたと承知しながら、あまりの文筆の見事さにひとまず酒宴を設け、静も舞を舞いもてなします。子方の友枝大風君もさっそうと舞ってくれ、この能の唯一の舞事を盛り上げてくれました。そして中入の型となります。橋掛り一の松あたりまで進んで「・・・各々退出申しけり」の地謡を聞き終え、囃子が終わったところで、一旦止まり、静止します。今までの時間とこれからの意気込みを見せる無言の型です。そしてズカズカと幕まで走り去る型。みなさんやられていることですが、伝書にはとくに記載はありません。ここは、起請文まで書いてようやく逃れてきた、もう猶予がない、今夜には決起しなければならないと、腹の中で覚悟を決めたという心持ちでしょう。止まった後、うしろを振り向く型もありますが、私は敢えて観客に顔を見せないほうが、能らしいと思い、振り向かず走り去る型にしました。

(写真)正尊郎党と江田・熊井との斬り合い[右より大島輝久・塩津圭介・友枝真也] 撮影 吉越 研
【能にもチャンバラあり】
中入後の、義経の郎党と正尊の郎党が乱闘となる、いわゆる「斬り組」の場面、能にチャンバラまで入ってしまい、まさに歌舞伎との境界線ぎりぎりの作劇場面です。しかしここはやはり能の様式的表現手法を駆使して戦闘場面を創出する、それで一つの見どころとなっています。竹光を使いながらも迫力満点。最後は、前に宙返りする者、仏倒れ(後ろ向きにまっすぐ倒れる)する者、前倒れする者、若者が能らしく演じてくれました。実はこの「斬り組」についても伝書に特に記載がありません。橋掛りの長さや立衆の人数によっても違い、毎回の舞台で違っています。若者が過去のものを見て、よいものを参考にして、自分たちらしく演じてくれたことを喜んでいます。もちろん稽古や申合せで私の意見も言いましたが、おおむね彼らが考えてくれました。



(写真)大太刀抜く正尊三体 撮影 上より 成田幸雄 吉越 研 青木信二
【試み・シテの太刀抜く型】
さて味方が次から次へと斬り伏せられていくところを、橋掛りの三の松からじっと眺める正尊。観世流はシテが薙刀を持っているのに対して、喜多流は大太刀です。薙刀を握りしめる形は劣勢に驚く気持ちを表現しやすいのですが、大太刀を腰に当てている姿で微妙な心理をどのように表現したらよいか最後まで悩み苦心しました。今回は、もう最期、自分の出番が来たか仕方が無い、という追い詰められた無念の思いを、大太刀を頭上に持ち上げ、ゆっくりと少々大袈裟な所作で表現出来ればと試演しました。本来ならば馬から降りる型をしてから太刀を抜くのが理にかなっているのでしょうが、ここも伝書には特に記載はなかったので、演者の演出に委ねられると解釈して、最初に大太刀を抜く型をしました。
能は型を大事にしますが、型でがんじがらめになっているように見えて、実はある部分ではまだまだ自由に動けるところ、遊び、幅があり、それが演者には救いになっています。それを知るまでに少々時間がかかってしまいましたが・・・。

(写真)弁慶が取り押さえる場面
【試み・ワキへの依頼・2】
そして正尊と弁慶の一騎打ちとなる場面。ワキの森氏に、もう一つ協力していただいたところがあります。弁慶は正尊を軽々と投げ飛ばしますが、その後、弁慶は大小前に戻るのが常です。これでは正尊はすぐに逃げることも出来そうで、違和感を覚えました。そこで森氏に正尊が逃げぬように押さえつけている型をしてほしいとお願いしました。義経の郎党、江田源三と熊井太郎が両脇から生け捕りにする場面まで弁慶が力を振り絞り取り押さえている、そのように見えたほうが自然ではないでしょうか。この場面、観世流では縄を使って縛る形にしますが、喜多流は縄を使わずに二人が胸倉を掴み、両脇から羽交い絞めにして捕らえる形です。どちらがリアリティあるでしょうか。いろいろな演出があって面白いところです。

(写真)江田と熊井に取り押さえられる正尊 撮影 青木信二
能『正尊』は両腕をとられた正尊と江田と熊井の三人が、橋掛りを幕を目掛けて走り込み、それを見送る義経の留め拍子で終曲します。何ともあっけない、空虚な感じが残ります。その後味の悪さ、妙な余韻に「何なの?」と、ご覧になられた方々が何か空しさを感じてくださればよい、と思って勤めました。確かに、土佐坊正尊は捕らえられ斬首される悲劇的な結末です。しかし勝った義経の運命はどうだったのでしょうか。平家物語では「土佐坊被斬(きられ)」のすぐ後に「判官都落」の項を配し、義経追討の院宣が下り、義経を討つために北条四郎時政が都入りしたこと、義経一行は吉野から奈良、そして北陸、陸奥へと逃避行となる運命を記します。締めくくりは「朝(あした)にかわり夕(ゆうべ)に変ずる、世の中の不定こそ哀れなれ」です。そんな余韻をどこかに残す義経の留拍子。これから義経はどうなるのか、めでたしめでたしではない陰の思いを、観客の心に残そうとも考えたのではないでしょうか。長俊の作品はドタバタ劇のように見えて、それでは終わらない、実は人間の行く末を見つめ、心情の深さも秘めているのです。

(写真)白水衣の前シテ 粟谷明生 撮影 青木信二
【装束について】
今回の装束は、前シテは紅無厚板、白大口袴に白縷大水衣、金茶系の角帽子(すみぼうし)を沙門の形につけ、観世流に近い格好を選択しました。喜多流の伝書には特に水衣の色の指定はないのですが、父も黒の水衣で、黒を着る人が多く、やや強いイメージとなります。観世流は白い水衣ですが、これは病人で、自分の運命をひがんでいるような弱々しい風情、頼朝に指名され仕方なく義経を討とうとする悲劇の男を描くのに似合うのではないかと、白を選択しました。秋の粟谷能の会で『安宅』を勤め、そのときのシテ・弁慶では強いイメージで黒を着るつもりですので、その対比も意識しました。

(写真)袈裟頭巾の後シテ粟谷明生と姉和平次光景役・友枝雄人
後シテは金茶地半切に白法被、父・菊生と同じ袈裟頭巾で勤めました。伝書には「長範頭巾」と記載されていますが、これは盗賊熊坂長範のイメージが強いので、正尊の風格を考えると不似合いです。近年は、僧兵のイメージで「袈裟頭巾」を使うことが普通になり、私もその選択としました。

(写真)御影堂にある金王丸木像
【最後に御礼の挨拶】
今回の演能に先立ち、東京都渋谷にある「金王八幡宮」の「金王丸社・御影堂」に参拝してきました。金王丸が正尊と同一人物かは確たるものではありませんが、能『朝長』で、前シテ・青墓の長者が「武具したる、四五人入り給う、義朝御親子、鎌田、金王丸とやらん」と謡い、能楽師の我々には親しみが持てる人物です。金王丸が15歳のころ、義朝に従って朝長の最期に立ち会ったのか、その子が40代半ばとなり、義朝の子、頼朝の命に従ってこのような悲劇となったのか・・・そのようなことを思い、願掛けの意味もあって参拝しました。その甲斐あってかどうか、能『正尊』はワキの弁慶役を引き受けてくれた朋友・森氏をはじめ、子方、立衆の若手、地謡、囃子方、みなさんと一致団結して創り上げることが出来たと感じています。こういう曲作りをしたいという私の思いをみなさんに共有していただき、とても風通しがよい快さを味わっています。人が多く出るということは装束や小道具だけでも相当数用意しなければなりません。森氏に装束や刀など多く拝借させていただきましたこと、ここにお礼申し上げます。恵まれた条件がそろったときにようやくできる『正尊』、これが今このとき、粟谷能の会で実現できたこと、この上ない喜びで、関係各位に深く感謝申し上げます。また会場に足を運びご覧いただいた皆様にも感謝の気持で一杯です。
追加
秋の粟谷能の会は10月11日(日)です。亡父の命日に還暦を記念して『安宅』を勤めますので、どうぞご来場いただきたく、お待ち申し上げております。
(平成27年3月 記)
写真無断転写禁止
写真についてのお問い合わせ
粟谷明生事務所
akio@awaya-noh.com
『六浦』を勤めて投稿日:2014-11-23

演能レポート 『六浦』を勤めて
平淡ななかの閑雅な風情

京浜急行逗子線に六浦駅がありますが、これは「むつうら」で、能『六浦』は「むつら」と読みます。舞台となる称名寺は六浦駅の近くではなく、金沢文庫駅から歩いて行ける距離で、大きな池に橋がかかる浄土庭園を持つ、景色のよい大きなお寺です。能『六浦』を喜多流自主公演(平成26年11月23日)で勤めました。
能『六浦』の季節は秋。都の僧が相模国(今は武蔵国とも)に下り、六浦の称名寺に立ち寄ると、あたり一面錦秋の景色であるのに、一樹だけ紅葉しない楓を見つけます。不審に思っていると、女性が現れ、昔鎌倉の中納言為相卿(ためすけきょう)が、紅葉した楓に感激して歌を詠んだため、楓は感激恐縮して以後紅葉しなくなった所以を語り、実は楓の精であることをあかし消え失せます。夜、旅僧が読経しているとふたたび女は楓の精の姿で現れ、僧に仏徳を感謝し、四季彩る草木の美しさを語り、夜遊の舞を見せ、夜の明ける前に消え失せます。

僧に救済を求めるでもなく、ただ報恩のための舞台展開は、純正の鬘物の定型ではありますが、やや削り過ぎと思えるほどシンプルな内容となっています。為相卿は、藤原定家の孫で歌道冷泉家の祖となる方で、詠まれた歌は「いかにしてこの一本に時雨けん、山にさきだつ庭のもみじ葉」です。山々がまだ紅葉していないときに、この一樹だけが紅葉色深く類無き美しさだったため、それを愛でて詠まれたものです。

能には草木の精を主人公にした曲が数多くあります。昔から日本人は草木に精霊が宿ると信じ、草木を愛で信仰してきたのでしょう。今は理解しにくい設定も自然に受け容れられていたものと思われます。春は桜の『西行桜』、秋は柳の『遊行柳』、両曲とも面は「石王尉」をかけ老人の姿となります。一方、伊勢物語に絡めた杜若の精を描く『杜若』は、若く美しい女性の設定で、『芭蕉』の精はやや地味な扱いとして中年の女性で演出されていて、双方両極端の位置にあると思います。では喜多流の『六浦』の置かれた立場はどこでしょうか?


近年は、面は前後とも「小面」、装束は前場が紅入唐織、後場は萌黄色長絹に緋色大口袴が多いため、『六浦』はやや華麗な『杜若』に近いと思われます。
六平太芸談に、十二世能静が幕府表方の舞台で『六浦』を勤めた時、わざわざ波に扇面を流した模様の緋色絵大口袴を作らせ、黄色地に紅葉を散らした長絹を用いて、綺麗な装束に見物一同驚いた、との記録があります。『六浦』という曲が、余分なものを削りに削ったシンプルな物語で、華やかさに欠け寂寞たる淡泊な能のため、華麗な装束で気を引こうと、演者の考案であったと思われます。私も真似て、粟谷家にある緋色に絵柄のある紋大口袴を使用してと、当初は思っていましたが、我が家の伝書の「後、長絹色大口、但し、緋は用いるべからず」の一文が目に飛び込んで来ました。そこで今回は敢えて緋色を使わない演能を心がけました。

今回の自主公演は、初番が『小督』でシテ連が「小面」を二面使用し、三番目の『黒塚』の前シテの面は「曲見」という周りの環境を考慮して、『六浦』の前シテの面は「浅井」をかけて紅無唐織を着て、後シテは「増女」に替え萌黄色長絹に鬱金色大口袴という、やや華やかさを押さえた格好にしました。紅入りの演出の狙いは紅葉していた時の楓の精を再現する気持ちですが、紅色を控えることで、以後紅葉しなくなった楓の精の気持ちで演じることが出来るのではないか、というのが、私の狙いでした。もっともお囃子方の皆様に「喜多流の平素の姿とは異なりますが、いつも通りの位でお願いします」と申し上げると、「他流は紅無ですから別に問題ありません。喜多流だけです、小面は・・・」とのお応えが戻ってきて、ほっとしました。

さて、昭和版の謡本の曲趣には次のように書かれています。
「一首の歌を題材として草木の精を舞わせる趣向であるから、内容もすこぶる単純であるが、優雅清麗の風情は三番目能の小品として、綿々たる恋情を述べるのではなく、四季折々の草木のおのずからに時を得る叙景的詞句も、平淡の内に滋味がある。功成り名遂げて身退く、という理念も人間的な処世の情とは異なる」とあります。「優雅清麗の風情は三番目能の小品として」のくだり、そのよさはわかります。しかし、最後の「人間的な処世の情とは異なる」の一文が気になりました。人間が世間で暮らしてゆく有様、気持ち、とは別物で演じなければいけない、という意味でしょうか?

シテ謡に、なぜ一樹だけが紅葉しないのか、楓の気持ちを述べる詞章があります。
「功成り、名遂げて身退くは、これ天の道なりと言う、古き詞(ことば)を深く信じ、今に紅葉を止めつつ、ただ常磐木の如くなり」。手柄をあげ、名声も得たならば、位から身は退く、これが天の定めで、この言葉を信じて楓も紅葉を止め、その後は一年中緑葉を保っているというのです。楓の精でありながら極めて人間的な詞です。草木の精を擬人化して人間と同様に心を持たせ、世の無常を語らせようとする能の演出で、人間的な設定をしておきながら、一方で人間的な処世の情とは異なる、という考えが、稽古していてどうもうまくかみ合わない、というのが演者としての本音です。
どのように考えたらよいのだろうか、と演じ終えた今も答えが出せないでいます。

『六浦』という曲は、とくに見せ場があるわけでもなく、強い心の訴えがあるわけでもありません。淡々と平淡です。しかし、この淡々と平淡を観ていただき、そこからなにかを感じていただく、そういう曲なのかもしれません。演る者も観る者も、見識を高く持ちながらも、それに満足せず、頼らない、もっともっと上の位に上がれる者が、草木の心がわかり、この曲の深い味わいを感じられるのかもしれません。
『六浦』を面白く見ていただくためには、まずは演者自身の心技体が高位に達しなくてはいけないのは勿論ですが、功も成らず、名も遂げていない我が身が、遂には身退く、という観念、理念で舞うことは、少々早かったようにも思えます。舞も謡も特にむずかしいところはなく、ある意味とても簡単に勤められる『六浦』ですが、実は形を受け継げば済むという能ではなく、能の本質を見極めることがとても大事で、そこがむずかしい曲であると知らされた、というのが演者としても感想です。
(平成26年11月 記)
文責 粟谷明生
写真 能『六浦』シテ・粟谷明生 撮影 前島写真店 成田幸雄
面 「浅井」「増女」粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
『清経』を演じて ー形見というキーワードー投稿日:2014-10-12

『清経』を演じて
形見というキーワード
能『清経』は平家物語や源平盛衰記をもとにして世阿弥が戯曲したものです。とはいえ、平家物語で清経について綴られているのは入水したことを述べる数行のみです。このわずかな叙述に心を留め、清経の震える心に分け入り、若くして入水しなければならなかった貴公子とその妻の情愛を香り高く創り上げたところに、世阿弥の能への思いが伝わります。都落ちの時、清経は19歳、妻は20歳ぐらい、若い夫婦です。まだ成熟していない清経の人間の繊細さ、弱さを能『清経』は表現しているといえるでしょう。
『清経』は中入りのない一場物ですが、前半は現在能形式、後半は夢幻能的な修羅物となっています。前半は粟津三郎(ワキ)が清経の妻(ツレ)を訪ね、清経の形見の鬢の髪を届け、清経が柳ヶ浦で船から身を投げたことを報告します。妻は、清経が遁世でもない、討たれたのでもない、病気でもない、自ら命を絶ったことに戸惑い、必ずこの世で逢おうと約束したのにと怨みます。後半は「夢になりとも見え給え」とまどろむ妻の夢枕に清経の霊(シテ)が現れ、夢幻能のような趣向になります。
この『清経』を第96回粟谷能の会(平成26年10月12日)で「音取」の小書付きで勤めました。「音取」は笛方の秘事で、シテの出に特殊な笛のアシラヒが入ります。演者は笛の音に引かれ、「どこから聞こえてくるのだろうか?」と探し求める心持ちで運びます。
私の小書への挑戦は研究公演以来二回目で、共に一噌仙幸先生のお相手で光栄に思っています。この小書は観世流、金春流では「恋之音取」、喜多流、宝生流では「音取」と呼ばれていますが、我が家の伝書に「恋の音取」と記載されていて驚きました。それでも、「音取」で通している今の喜多流なので、私も「音取」としておきます。
昔は音取の譜を聴き取ることが難しいからか、先人たちは敬遠されることが多かったようです。現に父は一度森田流の吉岡望氏をお相手に勤めていますが、とても苦労して、二度とやりたくないとこぼしていたのを覚えています。近年は録音再生が簡単に出来るようになり、笛の譜を聞き取るのはさほど難しいことではなくなってきました。とは思いながらも、やはり何度も音を聞いての稽古が必要なことは言うまでもありません。
伝書には、「音取」の演出が能『清経』本来のものであったような記載がありますが、昨今は笛方の秘事を過大視し、経済的に窮屈なものとなり、頻繁に行われることはなくなりました。良いことなのか、そうでないのか、私には判断がつきにくいところです。
笛方は地謡の「夢になりとも見え給へと」の謡の内に、本来の笛座から本舞台に進み入り、「枕や恋を知らすらん」と妻が眠りにつくと、幕の方に向き、静かにひとり譜を吹き始めます。清経の霊はその音色に引かれ、妻の夢の中にその姿をほのかに現していきます。清経が愛した笛、その音が聞こえると動き、止むと静止、この繰り返しが音取の型です。型附は、吹き出しで半幕、床几にて姿を見せ、一度幕を下ろし、次の吹き出しで三の松まで出て正面に向き、停止。また吹き出しで二の松あたりまで譜に合わせ運び停止。また一の松まで動き、正面を向くと、「恋の手」という特殊な譜となり、右向き聞き入る型、左向き聞き入る型、となります。最後は橋掛りより本舞台に入り、笛の音がやむと「うたた寝に恋しき人を見てしより、夢ちょうものは頼み初めてき」と小町の歌を歌い上げ、「いかに古人(いにしえびと)」と妻に呼びかけます。「音取」は静寂な舞台空間の中で、笛一管とシテの運び(歩行)のコラボが見どころ、ということになります。
このようにして夢の中に会えた二人ですが、妻は清経が自ら命を絶ったことへの怨み、夫はせっかく贈った形見を妻が送り返してきた怨みを言い合うことになります。この二人のやり取りは聞かせどころなのですが、妻のなぜ自分を置いて自殺してしまったのかという怨みはよくわかるにしても、清経の「なぜ形見を返してきたのか」という怨み節は少ししつこいように感じます。
そこで『清経』のテーマ、キーワードはなんだろうかと考えたとき、この執拗にこだわる「形見」に思い至りました。形見を返してきたことについては「源平盛衰記」に記述があります。それによると、形見は清経の生前に贈られていますが、能では彼の死後に返したと脚色されていいます。シテ謡に「再び贈る黒髪の厭かずは留むべき形見ぞかし」とあり、ここが気になります。「再び」とは生前と死後の二回形見を送っていること、それなのに両方とも返すのかと怨み節になる・・・と解釈出来ないでしょうか。もっとも他流の詞章では、「再び贈る」のところは「さしも送りし」となっていて、「再び」の言葉はないので、それほどこだわったものではないかもしれません。
さらに「源平盛衰記」を見ていくと、清経がひとり都落ちしたのは、妻の父母の猛反対があったからとあります。妻は同行したくとも出来ず、二人は泣く泣く引き裂かれた格好のようです。清経は悲しみ、西国への道中、鬢の髪を形見として妻へ送り、また連絡すると約束します。ところが、その後三年の間便りをしなかったため、遂に妻は心変わりしたと恨み、清経のもとへ鬢の髪と「見る度に心づくしの髪なれば、宇佐にぞ返す元の社へ」(見る度に心を痛める髪なので、つらさに宇佐の神の社へお返しします)と一首の歌を添えて送り返します。清経はこれを柳ヶ浦にて受け取り悲観したようです。入水の決意を固める一つの要因になったかもしれません。
妻の父母の猛反対とはどういうことでしょう。清経は平重盛の三男、清盛の孫にあたります。妻は清盛殺害を企てた藤原成親卿の娘でした。妻の家では平家を大事に思うはずもなく、平家一門からは心底気を許されていない、そんな両家の環境も影響したのではないでしょうか。私はそのように推察しています。
家と家の事情はあったでしょうが、清経の霊は愛する妻への想いをより深く演出したい気持ちで夢枕に現れたはずです。ところがさっそくの怨み節。シテとツレの問答は若い夫婦の口喧嘩で、これはいつの世にも通じます。現代風にアレンジしてみましょう。
男「いつでも自分のことを思い出してほしいから形見のプレゼントをしたんだよ」
女「プレゼントは見れば見るほどあなたのことを思い出して心が乱れるから、そんなものは返すわ」
男「私のことをまだ好きならば手元に留めておくのが普通じゃないか!」
女「なに言ってんのよ、女の気持ちがわかってないわね。見ると思いが乱れちゃうのが嫌なのよ!」
男「わざわざ贈ってあげたのに・・・」
女「なによ。ずっと一緒に、という約束を破っちゃって。しかも自殺なんて!!」
男「お互いに恨み恨まれるのもプレゼントのせいだね」
女「そうよ。形見のプレゼントとは、とてもつらいものよ」。
こんな会話を想像しながら、このくだりを演じました。
しかし口喧嘩というものも、途中でつらくなるのが常です。やがて清経は「このうえは怨みを晴れ給へ。西海四海の物語申し候はん」と都落ちから入水までの有様を語り始めます。
途中、宇佐八幡に参詣しようと、神馬、金銀、種々の捧げ物をしつらえていると、ご神詠が聞こえてくる・・・。
「世の中のうさには神も無きものを、何祈るらん、こころ尽くしに」
(世の中の憂さ、平家がこのような状況になっては、宇佐の神も何もできないものなのですよ。それなのに何を祈るのですか。・・・・)
神も仏も我らをお見捨てになったのかと一門の者は皆肩を落とし、それは哀れな有様であった。清経も一門の行く末に絶望し、いたずらに憂き世に永らえるよりは、いっそ身を投げて果てようと秘かに決意したと語ります。平家物語にある宇佐八幡のご神詠の話をここに持ってきて、清経が自死に追い込まれて行く様をみごとに描き出しています。
ついに清経は「船の舳板に立ち上がり、腰より横笛抜き出し、音も澄みやかに吹き鳴らし・・・・西に傾く月を見れば、いざや我も連れんと、南無阿弥陀仏弥陀仏迎へさせ給へと、唯一声を最期にて、船よりかっぱと落ち汐の底の水屑と沈み行く憂き身の果てぞ悲しき」と、実に美しい詞章で最期を見せ、修羅道の苦患へと続けます。美しい詞章と美しい型の連続、囃子方もそれに呼応して舞台を盛り上げてくれます。『清経』は修羅物ではありますが、勇ましい武勲談があるわけではなく、心の葛藤の表現としての「カケリ」もないのが珍しいところです。武将でありながらどこか心が柔弱で、入水という戦わずして命を絶ってしまう、その公家的な若き武将・清経の最期を、舞を中心にして見せるのが能『清経』です。最後「仏果を得しこそ有難けれ」で留めるとあたりは静寂に包まれます。夢の世界はその静寂のなかに余韻を残しながら消えていきます。もっとも能らしく、平家の貴公子の品のよさ、亡びる者への美学と救済が存分に描かれていると思います。私もそこを意識して勤めています。
装束は、前回の研究公演同様、粟谷家所蔵の「紅白段模様唐織厚板」を使用しました。これは佐々木装束店が「桃山時代のものかもしれません」と高く評価してくださるほどの名品です。滅多に身に着けることのできない装束で勤めることができ幸せでした。
今回、笛は一噌仙幸先生、ワキは宝生閑先生と、お二人の人間国宝の先生方にご出演していただき、身に余る光栄で、貴重な時間を過ごすことができました。これらのことが観ていただく方に少しでもうまく伝えることが出来れば、と勤め終えた今も感じています。
(平成26年10月 記)
『求塚』の地謡を謡う その2 ー地謡全員の気迫がつくり出すものー投稿日:2014-06-07
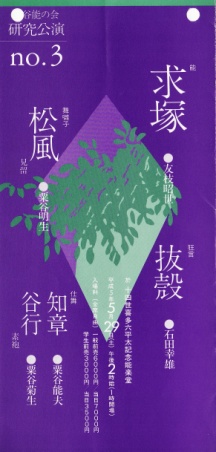
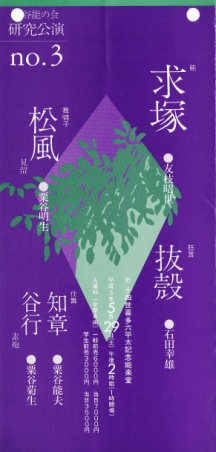
先日の第8回日経能楽鑑賞会『求塚』(シテ・友枝昭世師)(平成26年6月5日)で地謡を謡ってきました。『求塚』というと、「地謡の充実」をテーマとして、友枝昭世師にシテをお願いし、我々が地謡(地頭・粟谷能夫)を謡った粟谷能の会研究公演を思い出します。平成5年5月のことでした。あの研究公演では自分たちが立ち上げた会であるのに、なぜシテをやらないのか?という声も上がりましたが、我々はあえて地謡にまわり、地謡の勉強をしようと考えました。「能は謡が7割」と、父菊生は謡の大切さを強調していました。いくらよいシテがいても、地謡陣が情けないと、その舞台は台無しになってしまう、と。私たちも地謡の大切さをひしひしと感じ、父たちの次の世代である私たち、そしてさらに私たちの次の世代の地謡の担い手をつくっていくという志がありました。あの試みにご協力いただいたワキ・宝生閑師、囃子方は一噌仙幸師、柿原崇志師、亡くなられた北村治師、皆様のご指導とご協力は今でも忘れられず、感謝しています。
あの研究公演がよい経験となり、その後、父が平成10年・大槻自主公演でシテを勤めた『求塚』でも、平成15年の友枝昭世の会『求塚』にても、その成果が発揮されたように思います。
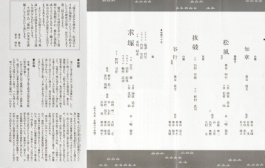
そして「地謡の充実」を折に触れ確認しようと、このテーマで、研究公演特別版を企画してきました。平成17年の『木賊』、平成22年の『檜垣』、いずれも友枝師にシテをお願いして、我々が地謡を勤めてきました。
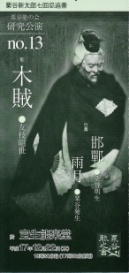

今回の日経能楽鑑賞会『求塚』も、シテが友枝師、地頭が粟谷能夫、私も地謡に加わり、研究公演と同じような配役となりました。地謡の充実とひとことで言いますが、それは地頭を先頭にして、地謡全員が真剣に、気迫をもって謡わなければ実現しないものです。
地謡は通常8人で謡うもので、地頭と呼ばれるリーダーが主となり、他の者が地頭の意向を感じて合わせて謡います。
地頭は一曲のテーマを考え、演じる者の動きや思いなどを考慮して、リズムやメロディーの流れを創り出す大事な責任を負っています。その責務は重くプレッシャーとなるものです。そして、他の地謡全員の力量が必要です。力量がなく上辺だけの謡い方で、地頭に寄りかかるような、責任を負わないような態度での謡は、地頭にはとても重荷になり、十分に力が発揮できません。地謡は地頭が優れていなければ成り立たないのは当然ですが、他の者が地頭を援助する気持ちに溢れていると、地頭は安心でき、心強くなって力を発揮できます。ひいては、地謡全体が充実し、よい舞台に繋がるのです。

今回の『求塚』も、地謡をしっかり謡おうと意気込んで臨んだのは言うまでもありません。順調に舞台が進行していました。そして、最後の場面、「暗闇となりぬれば・・・」のときのことです。囃子方の間の取り方がいつもより大きくなったため、地謡もうっと息を飲みました。それはほんの一瞬のことです。地頭もやや戸惑いがあったのでしょう、違う言葉を発しそうになりました。そのときです。残り7人の地謡が力強く、気迫を持って謡い出し、最後の一番よい場面を傷つけることなく、スムーズに運ぶことがきました。

地謡を謡っていると、思わず言葉を間違えそうになったり、言葉が出てこなかったりすることは正直あります。しかし、それがあからさまにお客様に感づかれてしまってはプロとして失格です。正確に間違わずに謡うということは当然ですが、間違いやアクシデントは演劇では付き物で、それをどのように粗相なく判らないようにうまく処理するか、これも大事なプロの技だといえるでしょう。
その策はいくつかあるでしょうが、私は今回の舞台で、もっとも有効な手法は「地謡全員が一致団結して気迫をもって謡う!」ということに確信を持ちました。このもっともオーソドックスな取り組み方をまっとうしていれば、大凡のことは防げるのではないでしょうか。地謡の各自が精一杯、声をふりしぼり、力を出し切るほど声を出す。それがアクシデントに動ぜずうまく対応出来る唯一の策、そう確信しました。
地頭と地謡のメンバーとの関係は、一般には地頭が責任者で他の者を引っ張り、皆は地頭に従って謡う、というように思われるでしょう。間違いではないですが、私の理想型は地謡の一人ひとりがみなぎる気迫を出し切って地頭を支える、というスタイルであると思います。両者は主従の関係だけでなく、横一列にならんだ仲間であって、リーダーを引き立て協力関係にある、と謡う者が意識する、そう信じることが大事だと思います。
地謡のどこのポジションで謡おうが、全員がプロ意識で気迫をもって、邪魔にならない程度を踏まえて大きな声で謡うことです。
昔よく能夫に「明生君お得意のサイコロステーキ論がまたお出ましだね」と苦笑されましたが、まさにそうです。大きなビーフステーキはナイフとフォークを扱い自分の食べやすい形に切り口に入れます。ダイナミックでよいでしょう。
しかし一方で、サイコロステーキのように最初から口に運びやすいサイズに切られているのは、食べやすく、それぞれのお肉のおいしい個所の味覚を楽しめるようになっていると思います。
つまり地謡のそれぞれのポジションの者とサイコロステーキは同じようなもの。自分の置かれたテイストを自らが引き出すこと、もちろん一番おいしいところは地頭肉にお譲りするのですが・・・、自分を美味しく食べて貰おうとする前向きな意識が大事なのです。
全員が一致団結というと、一枚岩のように最初から纏まった堅い物をイメージしてしまいますが、細分された個々の力の結集の方がより効果を上げ易い、というのが粟谷明生特有の持論なのです。先日の『求塚』は、全員がそれぞれの味わいを出し、協力し合い、その結果よい地謡が謡えた、私はそう感じて、持論のよい手本となる舞台だったと思っています。もっとも後日、どこかの批評家がダメ出しの感想を書かれるかもしれませんが、これは私の私なりの持論と感想であることを付け加えておきます。
今、頑張って地頭を勤めている粟谷能夫、いや能夫だけではありません、地頭という責任ある立場の者を、もっともっと強くフォローしよう! 前列も一体となって! と声を上げてくれ、そう叫びたいのです。
ふり返れば、地謡の充実をテーマにした研究公演から20余年の時が流れました。あの時の私たちの志、その成果がようやく現れて来たと感じ、なんだか嬉しい気持ちになっています。これからも心を引き締め、情熱をもって精一杯謡っていきたい、そんな気持ちを新たにした、思い出に残る日経能楽鑑賞会『求塚』となりました。
デジブック『求塚』シテ・粟谷明生
http://www.digibook.net/d/27d4a533819fa45d3b9de0c65cb86306/?viewerMode=fullWindow&isAlreadyLimitAlert=true
番組資料 粟谷明生蔵
写真 『求塚』シテ・粟谷明生 撮影 石田 裕
文責 粟谷明生
『道成寺』再び投稿日:2014-03-07

『道成寺』再び
粟谷 明生
平成26年3月2日(日)第95回粟谷能の会(於:国立能楽堂)にて『道成寺』を28年ぶりに(初演・昭和61年3月2日)再演しました。
能『道成寺』は「安珍清姫伝説」で焼失した道成寺の鐘の後日談「鐘供養伝説」を元に観世小次郎信光が能劇化したものといわれています。信光は安珍を登場させず、清姫もまた名前を明らかにせず、白拍子として設定し、鐘への執念をテーマにしています。
まず今回使用した面と装束についてご紹介します。
喜多流は本来、前シテの面は「曲見」、装束は「黒地丸尽縫箔」を腰巻にして「紅無鶴菱模様」の唐織を坪折(壺折)にするのが決まりです。しかし近年、若者が初演で年増女の「曲見」を使いこなすのはむずかしい、との配慮から「増女」に替えて勤める方が増え、私の披きも「増女」でした。装束は父の希望で「紅入蝶柄模様」の唐織でした。今回もやはり面は「増女」系で唐織も紅入りを考え、前シテの面は世にも不思議な女、妖しげな艶を出すために、梅若玄祥先生より、梅若家の名物面「逆髪」の写し、「白露」臥牛氏郷打を拝借し、唐織は『道成寺』に相応しい貴重な色入唐織「赤地鱗地紋花笠に獨楽糸(こまいと)」を観世銕之丞先生から拝借しました。両先生には感謝の気持ちで一杯です。

では舞台進行に合わせて演能を振り返ります。
『道成寺』といえば鐘ですが、この鐘の吊り方が上掛り(観世流、宝生流)と下掛り(金春流、金剛流、喜多流)では大いに違います。上掛りはあらかじめ狂言方の後見が鐘を吊り、その後に能が始まりますが、喜多流など下掛りは能の進行の中で、演技として鐘を吊ります。ワキ(道成寺住僧)が従僧を連れて登場して名のり、その後にアイ(能力)に鐘を吊るように告げ、ここではじめて狂言方が鐘を運び吊ります。吊り終わると、能力は道成寺で鐘供養が行われ、その間は女人禁制であることを、周りに「ふれ」伝えます。

そして前シテの出(登場)となります。通常の習之次第(ならいのしだい=出囃子)はシテが姿を現すまでに時間がかかります。今回は習之次第のはじまりに吹く、笛のヒシギ(甲高い音色)が鳴り響くと同時に幕上げとして、直ぐにシテが姿を現す替えの演出にしました。これは鐘への恨み、怒りを必死になって抑え我慢していた女が、鐘供養があるという知らせを聞いた途端に、鐘への恨みのスイッチが入り、自分ではどうすることも出来ない、制御が効かない行動になってしまう、その表れとして見ていただきたいとの思いでした。鐘への怨念に燃える魂は、女を白拍子姿に化し、鐘の吊られた地へと足を運ばせるのです。つまりアイのふれは、おとなしく恨みを抑えていた魂に火を付けしまったのです。

国立能楽堂の長い橋掛りは、鐘を目掛けての道中を演じるには格好です。今回は「作りし罪も消えぬべき・・・」の次第を一の松あたりにて謡い、名のり、道成寺への道行すべてを橋掛りにて行い、道成寺に着いた場所も一の松あたりとしました。その後、女人禁制だから供養の場には入れぬと断るアイに、白拍子はお構いなしに入り込みます。そのしたたかさを、謡いながら本舞台に入ることで見せ、アイに近づき「面白い舞だから、ね。いいでしょ?」と女の魅力を発揮し口説きます。

初演では「拝ませてたまわり候へ」の謡がうまく謡えず、父に「あんな謡じゃ、耕介(故・野村万之丞)がなんとも思わないよ」と叱られました。当時、白拍子は芸能を司る者として巫女的な待遇を受けることもあったといわれていますから、神事も行う芸能者ならば、鐘供養の場に入れてもよいかと応対する能力には、それなりの弁解理由になったかもしれません。が、しかしここは能力も男、不思議な女性の色仕掛けに負けてしまったと解釈した方が、人間らしく面白いと思われます。


能力のはからいで、シテは女人禁制の鐘供養の場に入れてもらい舞を舞うことになります。舞人の象徴である烏帽子をつけ身支度をして、いよいよ舞となります。はじめは遠くからぼんやり鐘を眺めている白拍子ですが、見るうちに興奮し走り込んで「あれにまします宮人の烏帽子をしばし借りにきて」と謡い掛け「乱拍子(らんびょうし)」の舞となります。

この白拍子の舞を模した乱拍子は、シテと小鼓の二人だけによる特殊な舞で、シテ方は小鼓方の流儀に合わせて舞(型=動き)を合わせます。初演では幸流の亀井俊一氏のお相手で勤めましたが、今回は大倉流宗家・大倉源次郎氏にお相手をお願いしました。足の動き(型)は単純な運動の繰り返しですが、小鼓の呼吸に合わせ、立つ姿勢を乱さず足の動きだけで演じるもので、そう簡単ではありません。身体の堅さをとり、ほんのりと女らしい柔らかみを感じさせるスムーズな身のこなし、初演は満足出来るものではなかったので、今回はどうにか自分の理想に近づきたいと挑みました。

幸流は掛け声と打つ音、その間(ま)を大事にし、自然と時間が長めになります。一方、大倉流、幸_流、観世流などは掛け声を長く引く間に合わせて足を動かすので、掛け声が終われば次の動きとなり、乱拍子の時間は幸流より短くなります。今回、ご覧いただいた方から「乱拍子が短く感じられた」とのご感想をいただきました。これは本来8段であるものを6段にしたこともありますが、小鼓の流儀の違いも大きな要因だと言えます。



「乱拍子」の舞は単純な動きですが、これを演者はなにと考え演じるのか? なにを真似て、なにを思うのか、そこの再認識が再演の課題でもありました。
道成寺の階段を蛇のように這い上がる心持ちを足遣いで表現するとも、足拍子を踏む乱拍子という踊りのステップのようなもの、とも考えられます。私はその両方を思いながらも、もうひとつ、女の道成寺という地、そして鐘への思いを内に抑えようとしながらも、どうしても外へ発散せずにはいられなくなるストレス、それがついには爆発してしまう、心の中の冷静と興奮の交錯でもあるように思えて演じました。



もちろん、どのように解釈されるかはご覧になる方のご自由です。単純な乱拍子の動きだからこそ、いろいろなことが想像出来るのかもしれません。
「乱拍子」の最後は「寺とは名付けたり」のシテ謡から大鼓も打ち出し、白拍子の思いは遂に炸裂し、速い舞「急之舞」に急変します。
この速い舞もまた、揺るぎの無い下半身としなやかな上半身の動きが必須で、剛柔のバランスをうまくとりながら、身体を乱すことなく俊敏な足さばきの中にも「女」を感じさせなくてはいけない、と父の言葉がまた思い浮かびます。静と動、速さこそ異なりますが、身体の扱いは乱拍子に共通するものがあります。

舞が終わり「春の夕べを、来て見れば」「入相の鐘に花や散るらん」と、シテと地謡は熱唱し舞台はクライマックスを迎えます。鐘入りは、この曲最大の見せ場であり難所です。何度もリハーサルが出来ることではないので、一発勝負となります。喜多流は烏帽子を後ろに払い落とし、片手を上げて鐘を目掛け、後ろ姿を見せたまま、鐘の真ん中で二つ足拍子を踏み飛び上がります。これが鐘後見の綱を放し鐘を落とすタイミングと合い、シテは頭を打ちながら姿を消すことになります。うまく綺麗に消えるほど相当強く打ちますが、まさに今回は数日傷みがあるほどでしたので、鐘入りは上手くいったということです。鐘入りはシテよりは、いかによいタイミングで鐘を落とすか、鐘後見の責任が大きく、今回、鐘後見の大役を受けて下さった中村邦生氏に感謝しています。

初演の難関として鐘の中での着替えがあります。面を外し、唐織紐を解いて脱ぎ、般若を付ける。狭く暗い中での作業は不自由です。今回は垂れ髪を付ける新工夫に挑みました。下稽古ではなかなか綺麗にならず苦心しましたが、試行錯誤と仲間からのアドバイスもあり、なんとか形にはなったと思っています。ご感想はいろいろありました。例えば、般若の面は下から上へのベクトル、口も上に、角も上に、鬘の毛も上に向けて掴み上げます。それに対して垂れ髪は下への力が加わるので、上への力が半減されるような不思議な感じを受けました、と。このご感想はもっともで大いに学ばせていただきましたが、私の狙いはそのバランスを故意に崩すことです。怒るだけではない女の悲しみをどことなく感じてしまうようなものをお見せ出来たらという思いもありました。
世阿弥の言う「してみて、よきにつくべし、ぜずば善悪定めがたし」の精神が私は好きです。まずは試みてみよう、ということでした。今後あの垂れ髪使用がどのように扱われるか、流行るか廃るか、それはこれから人々が証明してくれることでしょう。



「あれ見よ蛇体は、現れたり」と謡われると後シテは姿を見せますが、後シテの面は喜多流では「般若」をつけます。蛇のようになってしまった女の恐ろしさを「蛇(じゃ)」という面で表現するのが順当と言えますが、敢えて「般若」を使用するところに、そうならざるを得なかった女の悲しさがより強調されるのではないでしょうか。


蛇体の女は大勢の僧に祈られ己のつく息でその身を焼くほどとなり退散し、遂に日高川に飛んで消えます。近年、最後は幕の中に飛び入り幕を下ろして姿を見せない演出が普通となりましたが、我が家の伝書にはそれは替え演出であり、本来は橋掛りにて飛び臥し、その後立って入幕すると記載されています。このやり方は、死んだとは謡わない、もしかするとまた心のスイッチが入り現れるかもしれない、そのような悲しさ、終わりのない女の怒りと恨みをより一層引き立たせる演出と思い試みてみました。


能・狂言の世界では、大きな曲に挑み演ずることによって、能役者の成長の証を示す慣習があります。その中でも『道成寺』は筆頭です。若き日の初演の「披き」は、能楽師として一人前になれるかどうかの卒業試験と言われる方もいらっしゃいますが、私は入学試験の意識であると考えています。では再演が卒業試験かというと・・・。人、生滅の間は成長途上の身でありますから、卒業ではなく、昇進のためのレベルアップ試験と思います。
昔も今も能楽師は『道成寺』を披いて、はじめて一人前とみなされますが、残念ながら披きはやはり無事に勤める、その域を超えることは出来ないのです。『道成寺』という戯曲の大きなテーマを若さあふれる者が一回目で演じきることには少々無理があります。今回58歳の再演にあたり、初演では出来なかったことへの再チャレンジ精神で臨みました。それは緩みがちな私の精神と肉体に負荷をかける絶好の機会となり緊張の日々でした。またNHKの公開録画が決まったことは更に追い打ちをかけ、技術向上はもとより、健康管理など、能役者としての、初心に戻る好機となりました。
「稽古をしっかり積めさえすればそれでいい、余計なことは考えるな」そう教えられた時代がありました。確かに間違いではありませんが、それがすべてではないように思えます。能を演じるには、まず自分の思う役作りを考え、それに似合う面と装束を選び、その面と装束を生かすための稽古を積む、そうあるべきではないでしょうか。
『道成寺』についていろいろと考えていくうちに、ふと見えて来たキーワードは「妖気」です。「美」と「妖」の交錯、相克です。「美」の静、と「妖」の動が、常にこの不思議な白拍子の女の魂を動かしているのではないか、と。
蛇体となるまでの女の執心、執念、拘り、その怒りの対象は昔恋した熊野参詣の僧でも、目の前で祈る僧でもありません。男を隠した鐘そのものと、鐘があるその土地、このふたつへの恨みです。「鐘がいけないのよ」「鐘さえなければ」という逆恨みともいえる鐘への恨み。怒り爆発ギリギリの精神状態の危険な女をどう再演出来るかが、私のテーマとなりました。



作者の観世小次郎信光はお囃子事が達者な能役者だったようで、『道成寺』は信光らしい囃子方のパフォーマンスが遺憾なく発揮されています。大鼓の一調、小鼓の乱拍子、初めから終わりまで随所におもしろ尽くしが散りばめられて、観る者を飽きさせることがない、おもしろ演出満載の『道成寺』です。
披きは、このおもしろ尽くしのお任せコースに乗ればいいのでしょうが、再演はこのコースをどのように扱うかが問われ、それこそが再演の意義であろうと思いました。
フィギュアスケートは技術点と芸術点で審査されます。能役者とアスリートを同様にしてはお叱りを受けるかもしれませんが、技術点の満点を目指すのが初演の披きだとすると、再演では技術点の満点は当然、芸術点に重きをおいて、両者の高得点でよい舞台を作るもの、そう信じています。
今、自分自身、点数はわかりませんが、ある満足感、達成感に浸っています。
それは、初心にもどり、『道成寺』が大勢の仲間の協力で出来上がるものであることを再確認し、仲間への感謝の気持ちがこみ上げてきたこと、公開録画という高いハードルの設定にどうにか応えられたこと、すべて自分のためになったという充実感などです。舞台を創ってくれた囃子方、ワキ方、狂言方、喜多流の地謡、後見、楽屋働きの仲間たち、観てくださった方々、『道成寺』にかかわったすべての人たちに感謝しています。
●能『道成寺』のあらすじ
紀州(和歌山県)の道成寺で釣鐘再興のための鐘供養が執り行われることになりました。女人禁制を申し付けられた能力(アイ)ですが、白拍子(前シテ)の所望を受け入れ境内に入れてしまいます。最初、白拍子は供養の舞を静かに舞い始めますが、次第に興奮し激しく舞いながら、人々が眠ている隙を見て釣鐘を落とし、その中に飛び込み姿を消します。
能力から鐘が落ちた報告を受けた住僧(ワキ)は、かつてこの寺で起きた事件について従僧に語ります。
昔、真砂(まなご)の庄司の娘は、自分の家を定宿としていた山伏
に恋をした。ある年、娘は山伏に同行を求め迫るが、山伏は驚き道
成寺に逃げ込み、住職と相談し鐘の中に隠れた。山伏に恋する娘は
日高川まで追いかけて来たが、水かさが上がって渡れない。しかし
恋に破れた女の激しい恨みは遂に蛇となり、やすやすと日高川を渡
り、道成寺に来ると鐘の落ちているのを不審に思い、鐘の中に山伏
がいると分かると焼き殺してしまった、と。
その時の娘の執心が今回の禍の元と判断した住僧は鐘に祈り、吊り上げると、中から蛇体(後シテ)となった白拍子が姿を現し、住僧達に立ち向かいます。が、しかし終に祈り伏せられ、日高川の深淵へと姿を消すのでした。
●能『道成寺』の元となった「道成寺縁起」
延長六年(929)、真砂庄司娘・清姫は奥州から熊野詣に来た修行僧・
安珍に一目惚れします。清姫の片思いに困った安珍は、熊野からの
帰りに再び立ち寄ることを約束しますが、立ち寄らず、約束は守り
ませんでした。待ちわびる清姫の思いはついに安珍を探し追い求め
ることとなります。清姫の怨念を恐れた安珍は、舟で日高川を渡り
道成寺に助けを求めると、寺の僧は安珍を鐘の中に隠しました。安
珍を追う清姫はついに大蛇となって日高川を渡り、道成寺にたどり
着きます。そして安珍が隠れている鐘に巻きつくと、その怒りの炎
で鐘を焼き、中にいた安珍を焼き殺してしまいました。
写真 能『道成寺』シテ 粟谷明生 撮影 石田 裕
文責 粟谷明生
『道成寺』 談議 2014年3月 於 和食 いふう投稿日:2014-03-07

『道成寺』 談議 2014年3月 於 和食 いふう
ご協力 脇方 森 常好氏 小鼓方 大倉源次郎氏 大鼓方 亀井広忠氏
司会進行 粟谷 明生
粟谷 先日の粟谷能の会では皆様にお世話になりました。今日はその慰労会と反省会と言うことで、粟谷能の会ホームページにもお話したことを記載したいと思いますので、録音をお許し下さい。私は『道成寺』は二回目ですが、皆様は何回お勤めですか?

亀井 私はちょうど50回目の記念です、本当に忘れられない『道成寺』でした。
大倉 僕は133回目。常ちゃんは100回ぐらい?
森 そんなにたくさんやっていないよ。
大倉 でも年4回としても、30年経っているよ。
森 30年で120回!
大倉 ほら。
森 いやあ、100回もやっていないよ。でもやっているかな。去年も4回やったし・・・。
大倉 僕はペースダウンしても年3回はあるから、常ちゃんの100回以上は確かですよ。

粟谷 皆様、多いですね。
亀井 大小はいつも隣同士でしょう。私は源次郎先生のお相手が多く、今回も安心して勤めさせていただきました。なにか受け止めてくださる感があります。源次郎先生の場合は「ついてこい」というところがありながらも、「広(ひろ=広忠)がそう打つなら、お前についていくよ」というような、両方の気を出してくださるからとてもやりやすいのです。すいません生意気言いまして。
粟谷 いいコンビなのね。ではまず特別な習次第(替之習次第)についてお話していただきます。今回は笛のヒィヤーヒーのヒシギと同時に幕上げをしてシテの姿を見せる替えの演出としました、広忠君にお聞きしますが、「打つ心持ちが二通りあって、どっちでやりますか?」と言われましたね。
亀井 申合せの後に、明生さんが「習のヨセの手」の前はもうちょっと間がほしいと仰いましたので、本番はワンクッションの間を大きく作りました。「女体から蛇体」への変化の心持ちで・・・。
粟谷 その変化の葛藤みたいな意識はわかりますね。
亀井 シテが姿を出さられた時は蛇体で、また幕が下り一度止まられる時には女体に戻っている、そんな感じですかね。笛がヒシギを吹いた時は蛇体ですから、ヒシギと同時に幕を上げられた方がいいですよ、とお話しました。
粟谷 ヒシギと同時に姿を見せるのが効果的、ということだね。
亀井 そうですね、女の葛藤する気持ちと平常でいようと思う心、その二つがあると・・・。
粟谷 私も同感だね。
亀井 ですから幕の上げ下げの呼吸が大事だと思います。
粟谷 本番は上げる時は、ふわっとやや早めにして、下ろす時はゆっくり、にしました。
亀井 替之習次第は、こちらはいきなりハイテンションとなってシテの出の場面となりますが、あのように短い時間で雰囲気を創り出すのは結構難しいです。今回、お相手が源次郎先生でしたから安心してスムーズに出来たと思っています。
粟谷 私の替の演出の解釈は、能力(野村萬斎氏)が周りに「鐘の供養があるよ」とふれた瞬間に、その知らせ、つまり音や声でもいいのですが、それが鐘に恨みを持つ女に聞こえてしまうのね、するとその魂の怒りスイッチがオンしてしまう。「鐘! 何でまた吊るの!」と怒りがこみ上げて来る、と同時に執念の姿が表れるところを観客にお見せしたい、そう思って演じました。
亀井 なるほど。替之習次第は、たとえば『三輪』の「白式」「神遊」の後に『道成寺』とか、または『檜垣』『卒都婆小町』プラス『道成寺』という番組があった場合、習之次第が続きますね。その時は「老女物」の方は正規な習之次第として、『道成寺』は替之習次第があってもいいのではないか、と父に相談して「ではお前やれ、俺はやらないけれど」と言われて、最近流儀の公認となりました。
粟谷 あれ? 忠雄先生がお勤めになられたのではないの?
亀井 いえ、父ではありません。
粟谷 大槻能楽堂特別自主公演の時、忠雄先生がやられたと思っていましたが・・・
亀井 替之習次第を試みたのは私(笑) ですから阿吽の対談を読んで「あれ、父がやったことになっている」と思いましたが、「まあいいや」と思っていました。(笑)
粟谷 ああ、それはたいへん失礼しました。忠雄先生にお詫びしなければ・・・。兎に角、替之習次第は、囃子方、つまり大鼓、小鼓そして笛の方々の技術的なものがあってのこと、それは当然ですが、それだけではない奏し演じる想像力がないと面白くいかない、と思いますよ。
亀井 演じる心を囃して成り立たせたい、という欲求はありますが、それはお客様なり、まわりの方々の判断となりますね、正直、なかなか自分では決められないものです。
粟谷 源ちゃんとは替之習次第と乱拍子と、今回いろいろな挑戦にお付き合いいただきまして、本当に有難うございました。国立能楽堂30周年記念の金剛永謹氏の『道成寺』を拝見した時に、金剛流の古式の習之次第が面白くてね。
大倉 そうでしょう。(笑)
粟谷 あれを真似しようかな・・・、と浮気虫が騒ぎましたが(笑) 今回の替之習次第、源ちゃんは、どのような感想を持たれましたか? 替えの習之次第はやりにくい?
大倉 いやいや、そんなことはないですよ。あれはあれで、今お二人が言われた通り、同じ気持ちで勤めましたよ。
森 僕としてはすぐにシテが登場するのはいいね、あまり丁寧に、というか慎重過ぎて時間をかけすぎるのは、どうかと思うよ。
粟谷 今回の私の演出は喜多流としては新たな試みもありまして、「替之習次第」は能夫が一度(平成18年粟谷能の会)で試みていますが、名のり、道行、アイとの問答を橋掛りで行うというのは、今回が初めてでした。アイ(萬斎氏)との問答を橋掛と本舞台とで距離感を出して、アイの境内女人禁制との忠告を無視し厚かましく境内に入ってくる、なんとなくふてぶてしい女を演じてみたかったのです。
亀井 物着に入る前のアイのお言葉が申合せと本番が違いましたね。
粟谷 あ!それは私の責任ですね。シテの「ひらに拝ませ給わり候へ」のあと、本番当日に萬斎君から「和泉流の科白でいいですか? それとも最近の喜多流相手のお言葉にしますか?」と聞かれた時、喜多流にはその後の受ける言葉がないので、「どうぞご自由に、和泉流本来のやりかたでいいですよ」と返答しましたが、それをお囃子方にお伝えしなければいけなかったですね。
亀井 そうですね。道具をとる大事なタイミングのところですから。源次郎先生と私、息を殺しながら気配を感じられないように、手を出しお互いそっと道具をとるのが心得なので・・・、やはりあれは教えていただきたかったです。萬斎さんとしては明生さんが伝えてくれるだろうと思っていたのかもしれませんね。
粟谷 わかりました。そこは喜多流には関係ないから、ではいけないね。シテがそこまで責任を負い配慮しお伝えしないといけなかったですね、教えてくれて有難う、勉強になるなあ。
亀井 言葉を抜く時は、あらかじめ言っていただければ、いかようにも対応はしますので。鐘入りに迄に繋がる大事なスタートですから。
粟谷 広忠君、物着で立つのが少し遅れてしまい、ごめん。
亀井 あれ?と思いましたよ。(笑)
大倉 物着でアクシデント、例えば、烏帽子の紐が切れたりしたら、僕らに口伝があるんですよ。笛がアシラヒを吹き続けている限り、大小(大鼓と小鼓)はアシラヒをし続ける、というセオリーが大倉流にはあります。つまり笛が吹くのをやめるということはシテが立った、という合図です。私たちはシテの居る場所が見えません、立つかどうかは、見えない。ですから笛を頼りにしています。先日は幸ちゃんがシテの立つのを確認しないで吹くのを止めたでしょう。ですから私は道具を下ろすしかなかったんですよ。ですから、あの場面、笛が大と小の関係をもう少し配慮してくれていたら・・・とも思いますね。約束事、ルールというのは塊の繋がりとも言えるんですよ。
亀井 大小の「置キ」の手で笛がまだ吹いていれば、続行した、ということです。
粟谷 なるほど、でも私が約束の二つ目の「置キ」で立たなかったのが一番いけないね。さて乱拍子ですが、どう短かったでしょ?
森 あれくらいでいいよ。
亀井 そうですね、あのぐらいの長さが丁度いい感じですね。少し短い感じもしますが、内容的には充分に気が張ったよい乱拍子だったと思いますよ。私、一番間近でお二人のを拝見していましたから。(笑)
粟谷 今回は大倉流との乱拍子、喜多流はとかく幸流のお相手が多く、特にお披きは幸流が・・・という時代の流れがありましてね。幸流以外は皆、掛け声を長く引きますね。源ちゃんお互い乱拍子がうまくいってよかったね。(笑)
大倉 下申合せと申合の時、右と左が判らなくなって間違えてごめん、当日心配でね。
森 僕が見ていても右足と左足の動きが同じだから、あれは間違え易い、と思ったよ。
粟谷 初演が幸流でしたから大倉流に慣れるのに少々時間がかかりましたよ、でも一度経験すると、掛け声を引く方がどうも私は好きですね。幸流の短い掛け声もいいのですが、どうしても時間がかかり過ぎて・・・正式に八段ですと30分以上もかかるから。
亀井 源次郎先生、声の返し方、ちょうどいい感じでしたよ。
大倉 返し方も、あまり裏に返さない、できるだけ表声で、と取り組んだの。

粟谷 最初、表声と裏声の違いが分からなくてね。下申合で経験して判ったよ。今回は表声が主となったので、それに合わせて足の運びを考えました。喜多流の先人たちは掛け声の最後に合わせ足を動かしていましたが、能夫から声が聞こえても足が動いていないのは不自然でしょう、洋太郎君とやった時はすぐに動かしたよ、というアドバイスがあってね。最初はその通りにしていたのですが、仲間から同時に動かせば動かすほど逆に動きが目立たなくなって効果が薄い、それよりインパクトがあった方が効果的とアドバイスされて、敢えて少しづつずれるように変えてやりましたよ。(笑)
亀井 観世流も、ヤォッーっの掛け声でパッと足を出しますね。
粟谷 やはり小鼓の掛け声にシテが直ぐに反応する、これが基本じゃないかな。下申合せのときに、掛け声の裏声をあまり出さない、元々の大倉流のやり方を徹底的にやりましょう!と注文して源ちゃんとも確認、応えてくれてよかった、助かりました。やっていると幸流の8段がものすごく長いように感じましたね。この間のは20分ぐらいでしょ?
森 ちょうどいいよ。
粟谷 お披きのときは8段が正式ですがから時間がかかるのは仕方が無い、としても、見ている方にはお披きであるから、とかそうではない、というのは本来関係ないので・・・、でも喜多流と幸流よりももっと長いのも他流ではありそうですね。
亀井 観世流は「赤頭」の小書が付くと、まともに7段半をしてその後に「鱗返し」というプラス3段から5段増えるすごいのがありますよ。(笑)
粟谷 それ飽きない? 飽きないというか、だれない?
大倉 やるのしんどいのよ。
亀井 お客様が育ったらいいかもしれないですけれどね、今はちょっとね(笑)入れ替わりの時期だから。
粟谷 入れ替わりの時期か?
亀井 粟谷能の会でも菊生先生や新太郎先生がバリバリのときの観客はもうだいぶいらっしゃらないわけですから。昔のままをただ守ってやる、といのもなんだか不思議な気もしますよ。
粟谷 入れ替えなきゃいけない時期なのね。「昔の形式通り」を鵜呑みにするとシーラカンス化するよ。もっともいつまでたっても昔と同じ、という標本みたいなものも必要なのかもしれませんが・・・、私には似合わないなあ。(笑)
大倉 もちろん乱拍子というのは、当事者二人の緊張感は大事ですが、観る方がなんでこんなことをしているのだろう?というのがあれば、それ以上の説明は必要ないと思いますよ。
粟谷 そうですね
大倉 道成寺の石段上る、と言うのもあり、その他いろいろな考えを言う人がいてもいい、観る側が、何をしているのだろう?と自分なりの答えを見つければいい。だから国立能楽堂満席なら600通りの答えがあってもいいじゃないですか。
粟谷 そうね、私はね、どうぞご自由にお考えください、でいいのですが、それだけではなく、こんな見方もありますよ、という手引き、お助けアドバイスをするの事は今の時代には必要だと思います。少しサービス過剰かもしれませんがね
大倉 この人はこう言っていた、あの人はこんなことを言っていた、僕ならこんな風に思うというようにして・・・。あの乱拍子の時間というものは、それなりの対応があれば充実した時間に変わる、と言うことでしょうね。
粟谷 今回、大倉流にお願いしてやってよかった。大倉流で20分ほどで、「もうちょっと見たかったな、もうちょっとやってほしかったよ」と思われるぐらいが丁度いいのですよ、。
大倉 それはそう。
粟谷 乱拍子は究極な様式美の表現だと思います。鐘への執着心の抑制と爆発の繰り返しで、静の気持ちから動の女の激しい思い。当然、若い女と年増では違いがあるよね? 常ちゃんはたくさんの経験がおありで、お判りだと思いますが。(笑)
森 え! でも判るよ(笑)だがら面もなに使うか、と変わってくるんじゃないの。
粟谷 今回は若い女の気持ちで勤めましたが、伝書には「曲見」となっていますから年増女の気持ちで演らないといけないのでしょうが・・・年増はむずかしい。(笑)
森 おばちゃんはむずかしい?(笑)
粟谷 最近の喜多流は「増女」で演る方が多くなりましたよ。NHKのインタビューで、「本来は曲見です」と言ったら、その演能写真を見せてくださいと言われ、探しに探したら大村定氏の初演が曲見でされていたので、拝借しました、放送の時、ご覧下さい。
大倉 金剛流の古式というのは若い女ですよ。
粟谷 喜多流は「曲見」に「紅無唐織」が本来。
大倉 観世流は「近江女」ですから、もしかしたら若いというのは新しい演出なのかもね。
粟谷 今回拝借した唐織は観世銕之丞氏から、面は梅若玄祥先生からの拝借物です。どうでしたか?
森 上等なものを着ているなあ、と思ったし、前シテの面は喜多流では見たことないのが出てきたなと思ったよ。
粟谷 面は梅若玄祥先生に、「逆髪」はお恐れ多いので、その写し「白露」を拝借させていただきたいとお願いした訳、私には似合わなかった、という声もあったみたいですが・・・。
森 僕は似合っていた、と思ったよ。
亀井 私、青山銕仙会の虫干には小学校の頃からお手伝いに伺っていて、先代の銕之亟先生(静夫)にいろいろなことを教えて頂きました。虫干しも、たたんでしまうまでやらせていただきましたから、装束に直に触れています。あの赤地鱗模様の唐織のすごさは判りますよ。
粟谷 江戸時代のもので、近くで見るとあまり派手には見えないが。
森 鱗が飛び出て来るように見えたよ。
粟谷 あれは故銕之亟先生の出版された「ようこそ能の世界へ」で知って、NHKの放送ということもあって拝借出来たらいいなあ、と思ってね。

亀井 私、あれをたたんだことがありますので、あのよさがわかります、重くないんですよね。
粟谷 本当に暁べえ、(観世暁夫=現・観世銕之丞)のお陰ですよ。父たちの西町とのご縁、父が寿夫先生や静夫先生、榮夫先生と親しくさせて頂いたそのお陰だと感謝しています。
亀井 ただし、あれは小さいですよね。
粟谷 そう小さいの。だから、観世銕之丞さんから「お貸しするのはいいのですが、小さいと思います、少し袖を出しましたがそれでも小さいと思いますので事前に着てご自分でご判断ください」と言われたよ。
森 暁べえは着れないだろうね。(笑)
粟谷 だから身体を装束に合わせたよ、腕少し曲げながら着たからね(笑)今回の鐘入りうまく綺麗に消えたでしょ? 相当に頭を打ちましたからね、まだ頭痛いよ(笑)
森 綺麗に消えたよ、相当頭強打したと思ったもの。
粟谷 鐘の中での物着は二人のアイのやりとりの間にやることは完了しちゃいます。だから今回は脇の語りは中でしっかり聞かせもらいましたよ。
森 あっ君のフェイスブックのお友達さんが、脇の語りを褒めてくれて嬉しかったよ。

粟谷 NHKが入ったから、常ちゃん倍返しで頑張ったんじゃないの?(笑)
森 そう、10倍返しで頑張った。(笑)
粟谷 お互い58歳、私も相当な頑張り方をしましたよ(笑)
森 そうね、俺も若くないから、品よくやろう、みたいなものもあったよ。
粟谷 後シテの垂れ髪は喜多流でははじめての試みでした。あれは梅若万三郎氏がやられていたのが気になって挑んでみました。賛否両様は当然ありますが、あれは今回の私の主義主張で、なに言われても構わない、やりたかったからね。蛇よりも女に重きを置いて演じたかった、その表現のひとつなの。
亀井 喜多流は「つかみ出し」をやります? 観世銕之丞(暁夫)先生が辰巳満次郎さんの会で満次郎さんが『葵上』をなさるとき、「つかみ出し」というのは『道成寺』にあるのですかと聞かれたんですが、「あれは女なのですから。そのままの方がよいのではないでしょうか。つかみ出ししちゃうと」とお話されていました。
粟谷 なるほど、狩野了一君が「般若の面のベクトルは上を向いていて、目は上に、口も上に、鼻も、角も上に向かい、鬘のつかみ出しでも上へのエネルギーですよね、全部上に行くところに垂れ髪の下へのベクトルがあるのは不思議に思いましたよ、まあ私自分自身は面白いなあ、と思ったんですが、と話してくれてね。
亀井 なるほど

粟谷 そう了一君の言われる通りなんですよ、でも私の狙いはそのアンバランスなところで女をアピールさせたかったのね。能夫は「つかみ出し」が好きではなくて、あまりつかみ出しをしませんね。これは銕仙会の影響かもしれないね。究極、本鬘ではな馬須(ばす)鬘で『道成寺』やりましたからね。
亀井 それは大槻文蔵氏が最初にやられたと思います。
粟谷 初耳。
亀井 青山に半書生みたいにして育ててもらったから、それこそ虫干しのことも面のこともそうだけれど、だから六郎先生でも、どうぞ広忠さん、持ってご覧なさいと、持たせていただいたり。それはもう静夫先生や暁夫先生のおかげです。面や装束を小学校のときから触らせていただいていたから。これから受ける影響は計り知れない。「逆髪」の写し「白露」あれも神秘的でよかったですよ。
粟谷 そう広忠君に言われると嬉しいよ。似合わないという御意見があっても、とにかく一度付けてみたかった訳よ。「して見てよきにつくべし、せずば善悪定めがたし」世阿弥の言葉通りだよ。


森 僕もいいと思ったけど。「祈り」のシテ柱での「柱巻き」のところさ、今までの喜多流ではあまり印象に残っていないんだが、今回は結構インパクトあったよ。なにかべっとり感、巻きついているっていう感じが出てたよ。あれがよかったよ。58歳の粘着感。ねばねばねばねば(笑)。
粟谷 喜んでいいの?(笑)。常ちゃん、シテ柱のところで鐘を見たあと下向いたら、脇の3人もう並んでいなかったじゃない。
森 あれ、そう?並んでいなかった? 申し訳ない。
粟谷 乱拍子というと幸流という風潮ですが、喜多流と大倉流との関係はどうなの?
大倉 実はね喜多七太夫は大倉六蔵がお相手をしたんですよ。江戸時代の本当の初期はずっと大倉流だったんですよ。
亀井 そうですよ。喜多七太夫のときは葛野九郎兵衛ですよ。
大倉 明治維新以後、14世喜多六平太先生、喜多実先生の時代になり幸祥光先生、幸円次郎先生のお力もあって、流れがそちらにいったんですね。大倉流はその間に観世流とのお相手が増えました。
粟谷 その時代時代に力を持っている方、偉い人の影響力は後の人間にいろいろな影響を与えますね。それが本筋であればいいが、そうでなくてもそうだと思ってしまうことがありますね。
大倉 歴史をよくよく調べると、これが正しいと思ったものが全然違ったりしてますから、歴史を学ぶことは大事にしなければいけないんですよ。
粟谷 喜多流はこのようにします、我が家はこうです、と言ってみても、調べてみると、あれ?ということありますからね。今回の最後幕に飛び込まなかったでしょ?
森 そうだね。
粟谷 あれ私のアイデアではなく本来の型付け通りにしたまでですから、古い型付け読んだら書いてあったのを取り上げただけのことですから
亀井 そういうこと沢山ありますよね。
大倉 置鼓から開発された乱拍子はもともと長く声を引くものでしたが、幸流さんがおそらく『道成寺』を作られた時に短い掛け声を新たに考案されて。僕もやるチャンスがあったらやりたいな、と思うけれど。まあ、さすがにそれはできないし。今回はどこまで大倉流の先祖帰りができるか!が、鍵でしたね。
粟谷 しっかり先祖帰りしたんじゃないですか。
大倉 だいぶしたでしょう(笑)。
粟谷 それは、よかったよ。
大倉 自分なりにこういう風にやっていたんだろうなという感覚は。たまたま金剛永謹氏とで今回下掛りが2回連続で、こんなの珍しいんですよ。
粟谷 今回は金剛さんよりは少しグレードアップされたのではないですか、グレードアップという言い方は悪いね、更に磨きがかかったと言うか・・・・。
大倉 そうそう。永謹氏とのときは、まだこっちも試行錯誤でしたからね。
粟谷 大倉流の本来の裏声をあまり使わないという新たな源ちゃんの取り組みに、ちょっと協力も出来たよね?
大倉 もちろん
粟谷 どうも長々と有難うございました。最後にこれは皆様にお礼ね。今ここに同席されていない、一噌幸弘さんにも、あとの二次会で会える野村萬斎さんにも、そして喜多流の皆様にもご協力いただいたことに本当に感謝しています。私が選びお願いした良いお仲間と『道成寺』が無事に出来て、それがNHK「古典芸能への招待」の公開録画となり放送も正式が決まり、最後に反省会までご協力いただいて有難うございました。このメンバーで来年の東北・仙台の仮称「萩能」でまたいろいろな新しい試みをして、能を広めていきたいので、ご協力よろしくお願い申し上げます。
『錦木』を演じて 悲恋物語の真相とは投稿日:2013-11-07


喜多流自主公演(11月24日、於・喜多能楽堂)で能『錦木』を勤めました。
最初に、この能のあらすじを記しておきましょう。
旅僧(ワキ)が錦木を持った男(前シテ)と細布を持つ女(前ツレ)と出会うと、男は僧に思う女の家の門に錦木を立てる風習を語ります。思う女が取り入れないため三年もの間、立て続け遂に命絶えたことを語り、その男の祀られている錦塚に僧を案内し、男と女は塚の中へと消えます。
(中入り)
男女のために読経する僧の前に、男(後シテ)と女(後ツレ)の亡霊が現われ、弔いを喜び懺悔物語を見せます。適わぬ恋でしたが読経のお陰で今宵一夜、女と盃を交わすことが出来て喜び、舞を舞う男の霊。
が、しかし夜明けと共に僧の夢は醒め、幻の男女はまた幽冥へと消え失せるのです。
前場は能因法師の詠んだ「錦木は立てながらこそ朽ちにけれ、けふの細布胸合わじとや」の和歌を中心に悲恋物語を語り、後場は機織りの模様や三年通いの有様を展開し、生前の恨みと死後に適えられた法悦の境地を男の舞で表現します。

世阿弥作『錦木』は男の女への恋慕執心を描く曲ですが、似た曲に『通小町』があります。百夜通いの九十九夜で果てる深草少将(『通小町』)に対して三年、九百九十九夜まで通う『錦木』の男の執心、『錦木』のほうが想う気持ちは上回るのですが、残念ながらその上演回数はあまり多くありません。その理由ははっきりしませんが、演じ手としての私の感触では、まず1時間半を越える上演時間と、演能者の適齢期が広くないことが上げられます。だれもが演者になれるかというと、なかなか難しいものがあるのです。力量と似合いの年令や容姿など、様々なものが揃わないと説得力に欠けるからではないかと思われます。力量面では、楽屋内の技芸評価の登龍門的な扱いの意識があることも否みません。能で男女の恋物語を展開する時に、どのように男の苦悩を表現出来るかがカギになり、それらが図られる曲と言えるでしょう。従って、あまり若年では表現できず、かといって、あまり老年でも似合いません。

それは前場のシテ・里男が直面で登場するからです。直面は、自らの生身の顔を役柄の「面」として舞台に出ますが、その風貌、容貌が観る側の曲に対する想像とイメージが重なればよいのですが、重ならない場合は難しいです。背中が丸まり頭髪も薄くなり、足どりも不安な高齢者では不似合いです。また逆に、どんなに容姿が端正な若者であっても、男の遂げられぬ恋を謡と舞で表現するには、果たしてどうだろうか、それには時間が足りません。
それほどまでに演者の適齢が表面化してくる厄介な曲だということです。私も58歳という年齢で勤め終え、この歳だから曲の理解度を高められたとは思いながらも、容姿的には少し遅かったようにも思えてなりませんし、まだまだ本当の男心が判っていないのかもしれないと、反省もしています。ただ58歳なりの『錦木』が演じられたのではないだろうかという満足も正直感じているところです。
さて稽古に入り疑問点が出てきました。なぜ女は男を受けいれなかったのだろうか。三年までも通ってくる誠意ある男性を。そして、そもそもこの女の素性、正体とはなんだろうか、まずここから解明することを始めました。
能には男女の恋物語を作品としたものが数多くありますが、親の介入で破談になる話には『求塚』『船橋』があります。いずれも、謡本の詞章だけでは真相が判らなかったのですが、『錦木』もまた同様でした。能は謡本の詞章だけでは作品の深いところを探れないかもしれません。時には間語りや出典、原典となる物語なども知る必要があります。
シテ方の能楽師はまず謡を覚え、次に型をはめていきます。それらを覚えると舞台に立ち稽古に入ります。稽古の最初に思ったこと、それは「一緒に謡っている前ツレがだれなのか?」でした。当初は気になりつつも、自分の動きだけで手一杯でしたが、連日の稽古をするうちに明らかにしたくなってきました。
前シテは後シテと同様、錦木を立て続けた男です。前場に同行する前ツレは中入り前に「夫婦は塚に入りにけり」と謡うので夫婦であることは説明されています。が、しかし三年通い続けた男は結局思いを遂げずに死んでいるはず、妻が一緒にいるはずがないではないかと、矛盾を感じてしまいます。この疑問は錦木悲恋伝説を読むことで解決出来ましたので、ここで簡単ではありますが、ご紹介いたします。
昔、錦木(にしきぎ:今の鹿角市十和田錦木)の地域は、都から来た役人、狭名大夫(さなのきみ)が統治していました。狭名8代目になる狭名大海(さなのおおみ)には政子姫(まさこひめ)というとても美しい娘がいて細布を織るのが上手でした。一方そのころ、近くの草木(くさぎ)というところに錦木(にしきぎ)を売ることを仕事にしている若者が住んでいました。錦木は、「仲人木(なこうどき)」とも呼ばれ縁組に使うもので、当時は男性が好きな女性の家の前に錦木を置き、その錦木を女性が拾って家の中に入れた場合は、結婚を許すという意味、との決まりがありました。
ある日、若者は市日のときに政子姫を見て、その美しさに惹かれ恋心を抱きます。翌日から毎日毎日、一日も休まず、政子姫の家の門の前に錦木を立てました。しかしながら、錦木は一度も家の中に入れられることはなく、家の前に立てられたままでした。そのたびに若者は草木へ戻る帰り道のそばの小川で、涙を流して泣きました。その川は、のちに涙川と言われるようになったということです。

一方、政子姫は、家の門の前に毎日立てられる錦木を見て、機織りする手を止め、こっそり若者の姿を見るようになっていました。そして、いつの間にか、政子姫も若者を好きになっていたのです。しかし、身分の違いなどで親は取り入れることに同意しませんでした。つまり、女、政子自身は錦木を売る農家の青年を拒否していた訳ではないのです。前場の夫婦は亡霊たちの化身ですから、ふたりが一緒に登場するにはそれなりの意味づけがあるということです。

前ツレは、能では政子と紹介されていませんが、細布を片手にかけて登場します。何故、女は白い布を、それも鳥の羽の付いた織物、細布を持っているのでしょうか。
錦木物語にはもう一つ重大な、結婚の約束ができなかった訳が書かれています。
当時、五の宮岳(ごのみやだけ)の頂上に巣を作っている大鷲が里に飛んできては子供をさらっていました。あるとき、若い夫婦の小さい子供が大鷲にさらわれて村人がとても悲しんでいると、ある一人の旅の僧が「鳥の羽根を混ぜた織物を織って子供に着せてやれば、大鷲は子供をさらっていかなくなる。」と教えてくれました。布に鳥の羽根を混ぜて織ることは非常に難しく、よほど機織りがうまくなければできないものでした。そのため、機織りの上手な政子は周りから機織りを依頼されていたのです。政子は、子供をさらわれた親の悲しみを自分のことのように思い、3年3月を観音様に願かけしながら布を織っていたのでした。その願かけのために、政子は若者と結婚する約束ができなかったのです。若者は、そういう理由も知らず、毎日せっせと3年もの間、錦木を政子の家の前に立てていました。そしてあと一束で千束になるという日、若者はすっかり衰弱し、門の前の降り積もった雪の中に倒れて死んだのです。政子は非常に悲しみ、それから2、3日後に、若者の後を追うように死んでしまいました。政子の父親は、2人をとても不憫に思い、千束の錦木と一緒に、一つの墓に夫婦として埋葬しました。その墓が後に錦木塚と呼ばれるようになったのです。
このように書かれ、なぜ女は男を拒んだのか? なぜ前ツレの女が鳥の羽の付いた細布を持っているのか? という私のなぞは解かれました。
能『錦木』の物語の大半は、男の女への恋慕の苦悩を描いています。
しかし、この曲は心底何を言いたいのだろうか・・・。我々は何を感じればいいのでしょうか。
『錦木』はふんだんに語られる生前の懺悔とその怨みが強く押し出される演出になっていますが、実は死後に結ばれた瞬時の喜びを伝えたいのではないでしょうか。
男にとって、死後であっても愛する人への抱擁、情交、その一夜の喜びは無上なのです。そしてその歓喜はそれまでの苦悩を盛りだくさんに見せることで、逆にひかり輝きます。能はその喜びを「舞」という手法で表現します。

喜多流の『錦木』の「舞」はあまり荒く激しくならないように舞う、という教えがあります。我が家の伝書にこのことについて興味引く面白い記述がありますのでご紹介します。
「この曲、舞の謡い吟和らかなる故、兎角(とかく)静かになる也、宜しからず。
随分早立ちたるを用ふ。舞の前より俄に早く成ることを嫌ふ也。 中略
早立ちにても、にがみ無きは悪し、いかにも、にがみたるが宜し」
とあります。
「謡う音色が柔らかいから静かになりがちになるが、そうではない。気が立つ、心弾ませるような心持ちを持つこと。しかし、いきなり気が立ち弾むようでは荒くなるので良くない、疾き舞であっても落ち着きがなくてはいけない、落ち着きながらも強く疾き心で舞え」
と、細かく演者の心持ちが記載されています。
若者の歓喜をただ荒く激しいだけで終わらせてはいけない、円熟の舞を加味することでより観る者に想像力を膨らませることが出来る、ということなのでしょう。確かにそう納得して勤めるようにしましたが、正直白状すると、実は私の心は裏腹に、農家の若者であろうとなかろうと若者の情熱、恋慕は兎角激しく、時には少々乱暴であっていい、それこそが若さの象徴だから、強さに拘れ、疾きに拘れと、囁くのです。それはあたかも、だれかが私の心に囁くように響いてきました。

私が演じたかった男の霊の舞は、900回を越えて通いくたびれた頃の男の舞ではなく、心躍らせながら通いはじめた頃の男の舞なのです。今これを書きながらふり返ると、男を昔の自分に照らして舞っていたようにも思えます。あの呟く声は・・・、ふとあの錦木を運んだ若者の霊が58歳に取り憑いてくれたのかもしれない、などと・・・、こんな不思議な気持ちで演能を終えたのは、はじめてのことでした。
能の舞は5段(6ブロック)で舞うのが常ですが、今回、あえて3段(4ブロック)に縮めることによって、楽しく気持ちよいひとときが、瞬時にあっという間に消えてしまうというように演じました。そのつかの間の喜びと余韻を味わっていただけたら、この作品は、屹度作者も喜んでくれると思っています。
(平成25年11月 記)
写真協力 巻頭 前島写真店 その他 撮影 石田 裕
シテ・粟谷明生 シテ連・内田成信 ワキ・森 常好
文責 粟谷明生
『葛城』について 小書「古式の神楽」を再考する投稿日:2013-10-07

『葛城』について
小書「古式の神楽」を再考する
粟谷 明生

『葛城』というとすぐに思い浮かぶのは、私が平成6年、粟谷能の会で勤めた小書「古式の神楽」のことです。『葛城』の小書「神楽」には、後シテ(葛城明神)が舞う「序之舞」を単に「神楽」に変える「普通の神楽」と、特別な序が入る「古式の神楽」があります。この「古式の神楽」は、昭和31年に先代宗家・喜多実先生が演じられてから途絶えていました。従兄弟、粟谷能夫から『葛城』に「古式の神楽」があることを聞かされ、その掘り起こし作業をしたいと思いました。平成6年、38歳の時でした。この3年前に能夫と「研究公演」を立ち上げ、様々な試みを研究し、よりよい演能をしようと、既成伝承を見直し、埋もれている演出を再考し演じる、それが私のライフワークとなりました。特に小書には積極的に取り組み、能を様々な角度から見つめ深めるには小書は打って付けの目標ターゲットとなりました。

「古式の神楽」はしばらく演能が絶えていたことや、囃子方が限定されていること、伝書が限られた者にしか残っていないこともあって、掘り起こしにはいろいろ難儀しましたが、そのとき背中を押してくださったのが金春惣右衛門先生でした。先生のご助言もあり、囃子方のご協力もいただき「古式の神楽」に取り組むことができました。そのときは伝書通り、「特殊な序」に「神楽」を三段舞い、幣(榊)を捨て、三段目の後半からはゆっくりとした「序之舞」をまたじっくりと三段舞うという形でした。これはとても時間がかかり、やや冗漫な印象を与える演出になってしまいました。
そこで今回、第94回粟谷能の会(平成25年10月13日)では、この「古式の神楽」に少し手を加え短縮し、観ていて飽きない神楽にしたい、と心掛けて再演しました。まだまだ再考の余地は残っていますが、前回に比べて、少し目標値を上げることが出来たのではないかと、自分なりには満足しています。
今回ご一緒いただいた、笛・杉信太朗氏、小鼓・横山幸彦氏、大鼓・亀井広忠氏、太鼓・金春国和氏の皆様には、ここに深く感謝お礼を申し上げます。
神楽の縮小方法については後ほど述べるとして、『葛城』という曲を勤めるにあたって私の感想などをご紹介します。

『葛城』は、古今和歌集から引いた「しもと結う葛城山に降る雪は間なく時なく思ほゆるかな」を象徴的に、間なく時なく降る真っ白な雪景色と、そこで出会う山伏達(ワキとワキツレ)と里女(前シテ)の温かい交流の場(前場)から描かれます。「しもと」とは細い枝のことで、これを薪として暖をとるものです。舞台となる葛城山は古くは修験霊場であって、金剛山をはじめとする連山を指し、雄大な自然が息づき、神々が宿る神仙でもあります。そこを訪れた山伏一行は突然の大雪に見舞われます。あたり一面の白色の世界は、前シテの白色の装束、笠としもとに付いた雪で表しています。突如として現れた女は苦渋している山伏達を自分の庵へと誘います。寒さを凌ぐために、火をくべて暖をとり休ませると、女は自らの苦悩を明かし、実は葛城明神の化身であることも明かします。化身は役の行者(えんのぎょうじゃ)に葛城山と吉野山を結ぶ岩橋を架ける工事を命じられたが、顔が醜いことを苦にして夜しか作業をしなかったので、ついに役の行者に怒られ蔦葛で呪縛され苦しんでいると語り、救済を求めて姿を消します。後場は葛城の女神が蔦葛の這いまとった小忌衣をひるがえして、ここを高天原とみなして、神楽、大和舞を舞い、夜明けと共に岩戸に姿を消す、という神の苦悩を描いた物語です。

顔容の醜さを恥じて昼は姿を現さない女神。しかも身は蔦葛で縛られ苦しみを受けている。そのような神様であることを後シテの姿を観て想像することは正直むずかしいです。実際に縛られた形相ではなく、また醜い顔の面を付けているわけではありません。むしろとても綺麗で魅力的な表情の「増女(ぞうおんな)」を付けて登場します。私は稽古を重ねる毎に、女神の苦悩理由が、どうもはっきりせず気になって仕方がありませんでした。女神が役の行者から罰を受けること、山伏の法力を頼みとすることなど、私のこれまで生きて来た生活や宗教観には当てはまらない環境設定です。さてどのようにこの能と向き合い勤めたらよいのか・・・と、少々悩み考えました。
ある尊敬する師には「能は不真面目ではいけないが、ある程度いい加減なもの。偏見を持たず、取り敢えずボッとやっておけばよい。桜の花も全体を霞として見るので花弁の一ひら一ひらを見るものではないでしょう」とご指導いただき、なるほどと得心もいたしました。その通り、と思うのですが、どうも一ひらが気になって仕方が無いのが私の性分なのです。少し細かなお話をします。
人は、いや女性は特に、自分の顔容、容色、容姿に対して引き目を持っているように思えます。太っていないのに、痩せたい、痩せなきゃ、と言います。
可愛い眉毛を、こんなに生えて嫌と切ってしまいます。私から見て少しも悪くないのに欠点ではないのに嫌がるのです。それは単に、己が自分勝手に抱くコンプレックスではないでしょうか。能が葛城の神を女神に仕立てあげたのは、神も同じように劣等感があるのだから人間が持つのは当たり前、それでいいの、よくそこら辺を考えてみては? というのが作者の意図であり狙いではあるように思えてなりません。私は危険な目に遭い、なにかに縋りたくなった時、思わず「神様!」とお願いしてしまいますが、『葛城』の神は、そのような神ではなく、もっと人間に近い存在のようにも思われます。いや、実は両者とも同じなのかもしれません。しかし故意に違う一面を見せる手法を展開したのが『葛城』ではないでしょうか。神を人間味あふれる話として身近に感じられる、不思議な曲というのが私の感想です。
能は見て美しいと感じるだけでよい一面もあるでしょう。それは間違いではありません。ただそれだけではないものをどこか深層部に持ち合わせていて、それが能の魅力の真髄であるとも言えます。シテ方の演者は、老若男女、神や鬼にも、そして時には死者にも化けます。そして、その心を借りて曲のテーマと取り組みメッセージを伝えるのが役目ですが、常に「人に観ていただく」という感覚、意識を忘れてはいけないと思います。太古の芸能は神への奉納が主であったでしょうが、申楽の能の創設者、観阿弥、世阿弥以降の戯曲家たちは観客を強く意識し始めます。観客への技芸、能は永年このことを忘れずに継続してきました。
葛城山の神(一言主神)は本来男神ですが、能『葛城』では葛城明神を女神としています。女神とするのは金峰山縁起にも見えますが、醜いとコンプレックスを感じるところや、簡単に呪縛されるという弱々しさの演出は、女神に設定した方が想像し易いからでしょう。想像しやすいためなら、なんとでもする。それぐらい大胆なやり方をする能、それが魅力で、そのいい加減さの面白さが、ようやく少し判るようになって来ました。それもこれも『葛城』を再演したお陰で、それこそ神の力なのかもしれません。
さて、また小書について、感想などを織り交ぜて記載します。ここからは専門的になることをご了承下さい。

今回、装束の選択については、一面の雪化粧をイメージして、白を基調にしました。里女(前シテ)は腰巻に白練を坪折(つぼおり)にして着るか白水衣にするか両用ありますが、前回が坪折でしたので、今回は白水衣にしました。
後シテの葛城明神は醜いといいながら、あくまでも女神です。美しさが欠けてはいけません。喜多流では本来、緋色の大口袴が決まりですが、今回は前回同様あえて萌黄大口袴に、通常は長絹(ちょうけん)を白地楽器模様の舞衣にしました。頭の天冠には赤色の蔦葛を付け、面は前後を通して「増女」を使用し、美しさを前面に出すことを心掛けてみました。
では、「神楽」を掘り下げます。原初の神々の物語には「神楽」が似合います。
我が家の伝書には「それ神楽の始は、昔、日神天の磐戸に引籠もり給う時、諸神集会して神事有り」と天照大神が籠もった天之岩戸の前に神々が集まり神事をして慰めたときの、天鈿女命(あまのうずめのみこと)の踊りから音楽が始まったとあります。まずは神々が手拍子をはじめ、ばらばらだった手拍手がひとつのリズムにまとまり、そこに掛け声や口笛が吹き込まれ、そのうち足拍子も入り、身近なものを叩き始める、そしてメロディーが出来上がり音楽となります。このようなリズムにあう原始音楽は単純でありながらも、なんとなく身体に躍動感を持たせてくれるリズムの音です。これが神遊と言われ「神楽」の起こりとなり、能の「神楽」へ導入されるようになったのではないでしょうか。私はそのように推測します。
『葛城』に小書「神楽」が付くと、後シテの舞が「序之舞」から「神楽」に変わります。通常の「序之舞」は女体の葛城明神がしっとりと静かに山伏に舞を見せる演出ですが、「神楽」は神事的、儀式的な宗教性が重視されて、尚かつリズムは小鼓が八拍子の一拍ずつを等間隔に連打することにより、非常に乗りのよい音楽となり、より呪術的な雰囲気を感じさせてくれます。この単純なリズムは、また、単純であるからこそ誰にでも音に慣れ、馴染み、次第に乗ってきて楽しくなる、「神楽」はそんな音楽なのです。

さて、さらに細かく「神楽」の構成を説明します。
(0)序+掛、(1)初段、(2)二段、(3)三段、(4)四段、(5)五段の六段構成です。(0)から(2)までが神楽のリズム、(3)から(5)までは普通の舞となります。つまり「神楽」と言われながらも実際は半分が神楽で残りは舞となり、『葛城』ではこの部分が序之舞の位となります。それは『葛城』が元来序之舞の曲であるからです。ただ、すべてを神楽で舞う「総神楽」(喜多流では五段神楽という。『巻絹』のみ)というものもあります。
神楽から普通の舞に変わる変わり目は幣を捨て中啓(扇)に持ち替える時です。それが変化の合図です。乗りの良いリズムの「神楽」で憑依を意識し、普通の舞に変わったときに、私はその憑依を和らげる意識で舞っています。今回の『葛城』では幣の代わりに榊を使いました。
では、「古式の神楽」はどこが「普通の神楽」と違うのか?
囃子方が限定されることはすでに述べました。笛・森田流、小鼓・幸流、大鼓・葛野流、太鼓・金春流と明記され限定されています。「古式の神楽」が滅多に演じられることがない理由はここにあります。文化11年に演じられたものなど、数少ない演能記録をこのレポートの最後に資料として付けましたのでご覧ください。

「神楽」の構成については、(0)の掛の序が変わるのが大きな特徴です。
「普通の神楽」では軽快なリズムに乗りながら八拍子の二拍目に足拍子を3度踏んで楽しげな様に演じますが、「古式の神楽」では序之舞の序のようにリズムに乗らず慎重に儀式的な足拍子に変わります。しかも3回とも踏む個所が変わり難易度も上がります。そして榊や幣を持っての神への祈りも下居して丁寧に拝み、御神事、儀礼的な雰囲気が漂います。雪が降る景色であったり、厳粛な儀式を想像させる太鼓の特殊な手配りはより手が混んでいて一層荘厳さを演出します。

先に述べたように、平成6年に勤めに「古式の神楽」は時間がかかり過ぎたとの反省から、今回は時間を短縮しながらも神楽のエキスを失わない「古式神楽」を創作したいと試みました。
その新案は(0)序+掛、(1)初段、(2)二段、の(2)を省略、後半の序之舞部分も(3)三段、(4)四段、(5)五段の三ブロックの、(4)をまるまる省略することで、引き締まり感を出しました。
儀式の序はゆったりとはじまり、掛からリズムがやや乗ってきて、初段から憑依的な部分も持たせ、榊を捨てる時にはクライマックス、最頂点となます。
その後、少し落ち着き中啓に持ち直すとやや軽めの中之舞の位となり、オロシと呼ばれる特別な譜になるところでリズムが絞まりゆったりとした舞の位にしました。そしてまた次第にリズムを上げて来てほどよい乗りをと試行してみました。

『葛城』はしっとりとした情趣がありながら、ただ美しいだけではなく、やや陰の部分があり、それでいて、原初の神物語の神秘性と軽やかさが挨まった曲です。この曲をより面白く魅せるには小書「神楽」は最適です。今回、その「神楽」を「古式の神楽」で、しかも再考・創作できたことは喜びでもありました。
今回の試み、まだまだ改善の余地があります。これからもっと頻繁に演じられるようになり、名称も例えば「古式」などではなく「大和神楽」とでも変えて、変化しながら後世に残ればよい、と願っています。
(平成25年10月 記)
「古式の神楽」の演能記録
文化11年に二回勤められた記録があります。
●『葛城』「神楽」、文化11年3月27日、松平越前守殿へ一橋大納言様御立寄りの節、三番目に勤む。
シテ 喜多十太夫
ワキ 進藤権右衛門
笛 森田庄兵衛光淳
小鼓 幸小左衛門
大鼓 葛野市郎兵衛
太鼓 金春惣右衛門国義
以上、金春國義伝書より
●文化11年甲戌9月21日御本丸表、日光遷宮相済為御祝儀御表能。
ここでは、ワキが宝生新之丞に代わっていますが、その他の申楽師は同じ者が勤めています。注意書きに「神姿恥ずかしや、までスラスラと、よしや吉野の山葛、より地頭・野村理兵衛シッカリ謡う」と書かれていて、「此の序、昔は家元ばかり、弟子に伝えず相勤め候」と権威主義が垣間見られて面白いです。
●昭和31年10月28日喜多別会にて。
シテ 喜多実
ワキ 松本謙三
笛 藤田大五郎
小鼓 幸 祥光
大鼓 亀井俊雄
太鼓 柿本豊次
笛は森田流と限定されたはずですが、一噌流・藤田大五郎氏がお勤めなのが興味を引き面白いです。古いしきたりにひとつの新風がおこったように感じられます。
●平成6年、粟谷能の会にて
シテ・粟谷明生、ワキ・殿田謙吉、笛・中谷 明、小鼓・亀井俊一、
大鼓・亀井広忠、太鼓・金春惣右衛門、地頭・香川靖嗣。
●平成25年、粟谷能の会にて。
シテ・粟谷明生、ワキ・殿田謙吉、笛・杉信太朗、小鼓・横山幸彦、
大鼓・亀井広忠、太鼓・金春国和、地頭・長島 茂。
以上
写真1、5、 撮影 前島写真店 成田幸雄
写真2、3、4、7、8 撮影 石田 裕
写真6、9、 撮影 青木信二
写真記載の無断転用禁止
『夕顔』を勤めて 儚く逝った夕顔の執心投稿日:2013-08-07

『夕顔』を勤めて
儚く逝った夕顔の執心

秋田県大仙市の唐松能舞台(平成25年8月25日)で『夕顔』「山の端之出」を勤めました。屋外の舞台、猛暑の夏もあとわずかと感じさせるさわやかな風が吹く中での演能でした。
能で源氏物語の「夕顔の女」を題材にした曲は『夕顔』と『半蔀』の二曲があります。『夕顔』は『半蔀』に比べるとあまり頻繁には演じられず、観世、喜多、金剛の三流にしかありません。『半蔀』の作者は内藤左衛門。出生不明の夕顔という女性を白い夕顔の花に重ね合わせ、花のイメージを強調した演出となっています。蔀戸に夕顔の花や実が飾られた藁屋(作り物)の中から、後シテ夕顔の精が蔀戸を押し開いて出てくる場面はとても華やかです。さらに「立花」の小書がつくと、生け花が舞台中央先に置かれ、より豪華な演出となり、観ていて美しさがストーレートに伝わってきます。

一方、『夕顔』は作り物もなく前場の曲(クセ)は居曲(いぐせ)という動きがないもので、後シテも序の舞と短いキリの仕舞所があるだけの地味な演出です。薄幸な「夕顔の女」の霊が成仏を頼みにこの世の僧の前に現れ、法華経の功徳で救われ成仏するという単純な構成で、短く儚い人生を嘆く夕顔という人物に焦点を当てた宗教色濃い作品です。世阿弥作と言われています。
見せ場も乏しく、舞うところも少なく、いろいろ舞いたい、動きたい私としては、やや物足りなさを感じないでもないというのが正直なところです。しかしだからこそ、一層演じる側の力量もまた観客の観る力も必要となる曲と言え、能の究極はこのような簡素な形で、完成度を高めているのかもしれません。
であれば、まことに能は難解な芸能と言えるでしょう。
『夕顔』はその意味でも味わい深い、能らしい能で、シテを演じる者の意識としてレベルアップする先に『芭蕉』という曲が見えてくるように思えます。
これらの「能の味わい」を感じるには作品への理解と想像力が不可欠で、舞台上の動きを観るだけでは力及ばないつくりになっています。謡われる詞章から
観客側が作品の背景を思い浮かべ想像する、このような鑑賞法が「能を味わう」ということなのかもしれません。
演者の力量も観る側の力も問われる『夕顔』、さてどのように勤めたらよいかと考え、まずは「夕顔の女」とはどんな女性なのかを頭に入れるところから始めました。『半蔀』の時はさほど気にせずに勤められたものが、今回は夕顔の女そのものが気になりました。「夕顔の女」の生き様、源氏との関係などを知ることが自分の演能に何らかの力を与えてくれるだろう、と考えました。
「夕顔の女」は源氏物語の帚木の巻の「雨夜の品定め」で頭の中将が控えめな女と語った女です。正妻の手前、中将は夕顔の女を身近に置くことをさけ五条辺りの荒ら屋に住まわせます。そして夕顔の女との間には玉蔓という女子をもうけています。そのような状況でありながらも光源氏(当時17歳)は大胆に行動します。乳母の見舞いに行く途中に、ふとしたことで夕顔の女(19歳)と出会います。供の惟光に垣根に咲く夕顔の花を折って持って来るようにと頼むと、童が香を焚きしめた扇を差し出し「これに置きて参らせよ」と言います。扇には「心あてにそれかとぞ見る白露の、光そへたる夕顔の花」という歌が書かれていました。どうもあのお方は源氏の君のようにお見受けしますが・・・というような、ちょっとしゃれた詠いぶりです。やがて源氏も「寄りてこそ、それかとも見めたそがれに、ほのぼの見つる花の夕顔」と、寄ってみてこそ分かるでしょうと返し、つき合いが始まります。上流階級で名誉も資産もあるイケメン青年の源氏が、中流階級の可愛い女性との逢瀬は女の身の回りの環境、珍しい風景などすべてが目新しく、殊の外楽しかったことでしょう。
能『半蔀』はこの初めての出会いの喜び、一番美しい思い出に焦点を当て、「寄りてこそそれかとも・・・」(詞章では「寄りてこそ」が「折りてこそ」に)の歌を引きながら、最後は夕顔の花の精でもあるかのように夢の中に消えていく演出です。
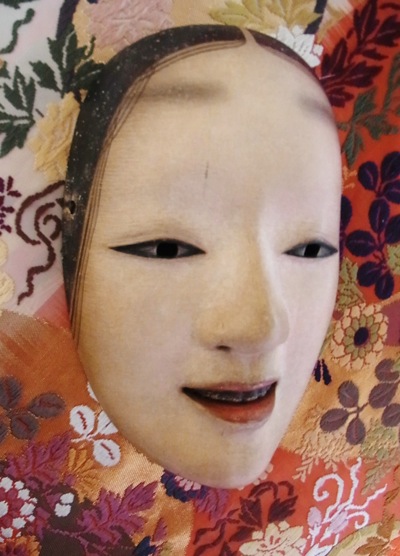
さて、度重なる荒ら屋での逢瀬、ふと気分を変えたくなる。そんな男女の心境間柄は古今変わらぬもの。源氏は思い立ってある場所を選びます。それが不幸を招きます。
8月15日の夜、源氏は廃墟となった源融の大臣の邸宅跡・河原の院に、虫の知らせなのか、気の乗らない夕顔を連れ出し一夜を過ごします。夜半二人の枕元に女の物の怪が現れ、驚いた源氏は供の者を呼びますが、だれも来ません。ふと夕顔を見るともう息途絶えています。物の怪の正体は、作者は明かしていませんが、おそらく六条御息所の生霊でしょう。葵上にも取り憑くほどの御息所の執心、嫉妬心は、彼女自身もう自分で自分を押さえられないまでになっていたのです。夕顔を失った後の源氏のうろたえぶり、悲しみ、打ち沈む姿は「源氏物語」にあますところなく描かれています。秘された逢瀬、夕顔の死も、源氏との関係も秘されなければなりません。供の惟光が夕顔の亡骸(なきがら)を上蓆に包んで車に乗せ、東山まで運び、源氏や右近(夕顔の乳母)ら、わずかな人たちで荼毘に伏します。薄命の夕顔は御息所を恨んで死んだのでしょうか。それともこのような運命を恨んだのでしょうか。最後までお互いの素性を明かさないままでした。夕顔は娘「玉蔓」を残しての突然の早世です。源氏への執心だけでなく、現世への執心も残ったことでしょう。ここに焦点を当てたのが能『夕顔』で、夕顔の霊はただひたすら僧に救済を願うのです。
通常の舞台進行は、ワキが名乗り、道行を終え着き台詞を謡うと、アシラヒ出となり前シテは一の松前にて「山の端の心も知らで行く月は、上の空にて影や絶えなん」と謡います。
「山の端の・・・」の歌は、河原の院に着いたとき、源氏に「昔の人はこんな風に恋のために惑い歩いたのだろうか。私は初めての経験なのでわからないが、あなたは経験がありますか」と聞かれて、夕顔が答えて詠んだ歌です。山の端=源氏の心も知らないで、ついて行く月=自分、夕顔は、(そのうち捨てられ)、上の空で消えていくのではないだろうか、といった意味で、夕顔の不安で心細い気持ちが詠われています。これがシテの最初の出で謡われるのは、能『夕顔』の全体を暗示しているように思われます。この歌は『半蔀』にも出てきますが、これほど強調したものではありません。
曲(クセ)も河原の院の暗く荒れ果てて恐ろしげな様子を切々と謡い、シテは居曲で片膝を立てて座り、内面の心のゆらぎを地謡が表現する手法で、けだし能の演出の特徴です。さらに「あたりを見れば烏羽玉の闇」「泡沫(うたかた)人は息消えて」「帰らぬ水の泡とのみ散り果てし夕顔」と、地謡は夕顔の儚く逝った運命を淋しく謡い上げます。
その夜、僧が法華経を読経し弔うと、夕顔の女の霊が生前の姿で現れます。
「優婆塞が行ふ道をしるべにて、来ん世も深き契り絶えすな」(優婆塞=俗体の仏道修行者。源氏が夕顔の隣家に住む行者の勤行の声を聞いて、夕顔を思って詠んだ歌)を僧と共に謡い、源氏と契りを結んだ時を追憶して舞い、法華経の功徳で解脱できたと喜んで、僧の回向に感謝し雲に紛れて消え失せます。
途中、「女は五障の罪深きに・・・」と女性であることが罪深いということや、「変成男子の願いのままに解脱の衣の・・・」と、法華経によって男子に変成して女性も成仏できるという、当時の宗教観も描かれています。現代なら、男女差別だ、承服できないといわれそうですが、能が創られた室町時代はこのような考え方があり、こう謡うことも自然だったのでしょう。このように、後半は宗教色の濃いものになっています。

今回は小書「山の端之出」で勤めました。この小書は、前シテの出の演出が変わります。ワキの道行の後すぐに、幕の中で姿を見せずに「山の端の・・・」を謡い、ワキはそれを聞いて「不思議やな・・・」と応じ、その後にシテの出となります。通常は普通の一声となりますが、今回は「巫山の雲は忽ちに、陽臺の下に消え易く・・・」と謡いながら一の松前まで出たかったため、今回に限った特殊な一声を打っていただき幕内より謡い出しました。この曲を象徴する「山の端の・・・」の歌をより印象づけ、シテの心細い境遇を際立たせる効果があればと思い試演してみました。

大仙市まほろば唐松能舞台は青空が見え、緑が美しく、そして心地よい風も流れる、屋外の舞台です。そんなロケーションであるため、演出を少し変えてみるのも一興かと考えました。『夕顔』の小書には、「山の端之出」のほかに、序の舞の最後の寸法が短くなる「合掌留」がありますが、囃子方の伝承には「合掌留」は「山の端之出」とセットになるように記されているようです。

今回、屋外の演能で天候や時間的な制約もあり、序の舞を短縮する必要もあったので、舞の寸法が短くなる「合掌留」は好都合でした。前場ではシテの下げ歌と上げ歌を省略し、間語りも短くし、後場では序の舞の短縮などして、60分で演能することが出来ました。また本来座りっ放しの居曲も、上羽の後より立ち、「闇の現の人も無く」と面遣いしながら正面先に出、「いかにせんとか思い川、泡沫人は息消えて」と下に心を付け、「帰らぬ水の泡とのみ」と少し引き下がり、「散り果てし夕顔の、花は再び咲かめやと」と左へまわり、「夢に来たりて申すとて」と脇に出る型をしてみました。
実はこれは私の新発想と思っていましたが、演能後に伝書を読み返すと、替の型として記載されていて、驚きと安堵という不思議な気持ちになりました。
新発想と喜んでいながら、実はそうではない。このようなことが昔から繰り返されている、伝統や伝承の意義など深く考えさせられました。

終盤、解脱を喜んだ後、「明け渡る横雲の迷いも無しや」では、通常、幕の方角の東をカザシ見る型となりますが、屋外で実際の大自然の青空に浮かぶ横雲を見ることができたため、方向を青空の雲を見る型に変えて、地謡の「明けぐれの空かけて雲の紛れに失せにけり」と謡の中で入幕してみました。
演能にあたり、以上のようにいろいろ考えましたが、『夕顔』を勤めるには、結局、あまり考え過ぎずに無心になるのが一番、これが正論だと思います。余計なことは考えずに・・・なのですが、どうしてもいろいろなことをしたがる自分が耳元で囁くのです。昔の型通り真似することばかりが正しい伝承ではないだろう? 昔から伝わる型も伝承も申楽発祥の当時はすべて新しいもののてんこ盛りだったはずだろう? と。

これからの私の演能は、もちろん演じる側の仲間の同意があってのことですが、常に新たな演出を工夫し再考し、より良いものを創り出していく、そうしたいと思っています。そして後世に書き残す作業も必要であると感じています。この思いが善か悪かは時が経って判断されればよいと思います。書き残し、演じる、このことは目新しいことでも新発想でもありません。申楽創始者の世阿弥や元雅、禅竹、信光たち申楽師は戯曲家を兼ねていて、創り、演じ、興行し、書き残してきたのです。このことこそが、今日の能が出来る所以です。自分もこれを真似たい、今、そう信じて止まないのです。
ただ古いものをそのまま真似るだけで満足していたら、創始者たちはうす笑いを浮かべ、きっと模写族に対してなにか、ひとことふたこと言うでしょう。
屋外の開放的な舞台で、今回もまた共演者のご協力と観て下さった方々のお力とに感謝しています。10月の粟谷能の会では『葛城』神楽を勤めますが、もう新たな演出が浮かび上がって来ています。
(平成25年 8月記)
写真提供
能『夕顔』シテ 粟谷明生 撮影 石田裕
宝増と唐織 撮影 粟谷明生
『紅葉狩』について投稿日:2013-04-07

「紅葉狩」について
宮島、厳島神社桃花祭神能(平成25年4月18日)にて『紅葉狩』を勤めました。
快晴とはいえ、塚の作り物も飛ばされそうなぐらいの強風が吹いたため、鬘帯は乱れ、舞っていて中啓(扇)を落とすのではと心配するほどでしたが、どうにか難なく勤めることが出来ました。

能『紅葉狩』は一畳台の上に山を想像させる塚に紅葉枝が挿された作り物が本舞台の大小前に置かれます。ここは山々の木々が紅葉し、ひとときの時雨にて錦秋も一入美しさを増す信濃国(長野県)、戸隠山です。作り物を見ながら、こう想像していただくところから能ははじまります。

やがて、妖艶な上臈・遊女(前シテ)が供の女たち(シテツレ)を引き連れて登場します。
時雨がにわかに降って来たことと、秋の美しい景色を謡いながら女達は木陰に雨宿りして休みます。そこへ鹿狩りに来た平維茂一行が通りかかり、女の身元を下女に尋ねますが、
「ただ身分の高いお方がお忍びで酒宴をされている」と名は明かしません。維茂は馬から下りて道を変えて通り過ぎようとしますが、遊女の一人(前シテ)が維茂の心遣いに感心して袂に縋り引き留めます。酒宴に誘い饗応する遊女に、維茂はその濃艶で豊麗な女の魅力に惹かれ、薦めに応じ酒を交わし美女の舞に酔いしれ、遂に不覚にも眠ってしまいます。
女達はそれを見ると鬼の本性を現し、「夢を見て寝ていろ」と言い捨て山中に消えます。
(中入)
寝ている維茂の前に八幡八幡宮(やわたはちまんぐう)の末社の神が神剣を持って現れ、鬼神退治するように維茂に神勅を伝えると、維茂は目を覚まし神剣を持ち身支度します。すると、稲妻が光り、雷鳴が轟き、先ほどの美女が化生の姿となって襲いかかりますが、維茂は応戦して烈しい格闘の末、見事鬼の首を斬り退治します。
能の構成は神・男・女・狂・鬼の五番立。最後の鬼の能は切能と呼ばれ鬼畜物の作品が多く、武将の鬼退治の曲目はこの『紅葉狩』の他に『大江山』『土蜘蛛』『羅生門』などがあります。山伏が霊を祈り伏せるものには『黒塚』『野守』、ちょっとニュアンスが異なりますが、弁慶の祈りで知盛の霊を追い払う『船弁慶』なども切能です。切能は一日の最後に演じられ『大江山』『土蜘蛛』『羅生門』『黒塚』などは悪者が退治され追い払われる曲ですが、実はもともとそこに住み着いていた原住民が、あとから来た侵攻者に追い出され殺されるという不条理な内容です。シテ方は敗者を演じるので、つい理不尽に敗者となる側の味方をしたくなります。これは私だけかもしれませんが。

しかし、この『紅葉狩』の鬼女には同情が湧きません。律儀にも敢えて邪魔をしないようにと、通り過ぎようとする維茂に誘いをかけるのは、最初からのもくろみがあってのことです。尚かつ酒を呑ませて眠らせておいて・・・、というのはずるい卑怯な悪な行為です。現代でも、しこたま飲まされ寝ている間にお財布の中身を取られるというのがありますが、なにか通じるものがあります。
『紅葉狩』は鬼の懲悪をテーマにしたもので、鬼に情状酌量の余地はなく、勧善懲悪の珍しい作品です。
芝居や映画で、怒った女が口をきかずに男に襲いかかるシーンがありますが、あれは怖いです。『紅葉狩』の後シテ化生の者の鬼女もシテ謡はなく、なにも言わずに襲いかかるところにこの鬼の凄まじさ、醜さを演出している様に思います。

『紅葉狩』は上臈(前シテ)が舞う舞に特徴があります。最初は静かでゆっくりな舞、喜多流は序之舞ではじまりますが、ゆったりとしたリズムの序之舞から、途中急にスピードが速くなり、美しい上臈が恐ろしい鬼の形相に替わるのを表現しています。急之舞と呼ばれるこの舞が囃すスピードがもっとも速いとされていて、喜多流では『道成寺』と『絵馬』の小書「女体」が付いた時の力神の舞、そしてこの『紅葉狩』にしかありません。

『紅葉狩』の急之舞の特徴は、ゆっくりな速度の序之舞から途中急転換して早くなる、その変化が急なため余計に後半の舞が早く感じられるように工夫されています。通常、舞の足拍子は音を立てますが、ここでは、維茂の眠りを覚まさないために、音を立てずに踏んだように腰を屈めます。顔は面をキビキビと動かして異常な精神状態を見せるように舞います。ここが演者の舞の力量が発揮されるところです。
世阿弥が幽玄の世界と称し、シテが一人静かに過去を回想して舞を舞う世界を確立しましたが、その反動なのか、『紅葉狩』の作者、信光は大衆に気軽に楽しんでもらえる風流能の創作に挑み、人気曲を生み出しています。大きな作り物を活用し、大勢の登場人物に各役に似合う配役をし、舞台進行を判りやすくするのが特徴です。
『紅葉狩』でも、例えば、塚(山)の作り物を一畳台の端において空いた場所でも演技する、袂に縋る型、ワキと組む型、役者同士が触れるなど、当時としても奇抜なアイデアが満載された新しい演目だったと思います。後シテの面装束は本来、面「シカミ」で装束は法被、半切袴という鬼神スタイルですが、近年は裳着胴姿(もぎどうすがた=重ね着しない)に面「般若」という鬼女をイメージしたもので対応しています。今回も般若でしましたが、維茂と強風と対戦相手が多く、気を遣いました。
さて、最後に父にどのように演じたらよいかを聞いた時のことをご紹介します。
「『紅葉狩』のシテをやることになったが、どんな気持ちで勤めたらいいのか?」と父に聞くと、即答で「BAR・もみじのママ・カエデチャンになった気分でやれ!」でした。
また、今回、小鼓を打って下さった横山晴明先生からは「『紅葉狩』のシテの色気は、銀座の高級クラブのNO.1のようなお気持ちでなさったら・・・」ともご指導を受けました。

このような言葉が私の想像力をかき立て、演能自体を面白くさせてくれます。こんな風に思うのは私だけかもしれませんが、こういうアドバイスが好きな私なので、今度は自分がそのように興味が湧くような面白い言葉を見つけられれば・・・、と思っています。
三日間の奉納の最後に自然の力、強風、雑音などいろいろなことを受けながらも、それに対応して舞うことが出来たこと、健康でいられること、母を含めて家族も安泰でいられること、厳島の女神様には感謝しています。来年はたぶん『弱法師』を勤めることになるでしょうが、元気に舞台を踏み、これからも奉納が出来る自分でいたいと、帰り際に神にまた祈り、島を離れました。
(平成25年4月 記)
写真 紅葉狩 シテ 粟谷明生 撮影 石田 裕
文責 粟谷明生
『俊成忠度』について 歌をめぐる物語投稿日:2013-03-07

『俊成忠度』について
歌をめぐる物語

(1)
平成25年3月3日粟谷能の会で『俊成忠度』を勤めました。
高校生の時に父に「『忠度』はどんな曲?」と聞いたことがありました。舞囃子で『忠度』を舞うことになり「どのような心持ちで?」と偉そうに聞いたのでしょう。返って来た言葉は「薩摩の守。ただ乗り!・・・無賃乗車」でした。一瞬白け、年齢不相応な質問しやがってと思ったのだろう、と思い、それで会話をやめたことがありました。もちろん「薩摩の守!」は、笑いながらでしたが。
能には平忠度を取り上げた曲が二曲あります。世阿弥作の『忠度』と内藤河内守(細川家の武士)作の『俊成忠度』です。前者がシテ方能楽師にとって二、三度は演じたい憧れの名曲なのに対して、後者は少年期の稽古能としての扱いで、上演時間も『忠度』が1時間30?40分かかるのに対して、『俊成忠度』は40分程度で終わる小品です。『俊成忠度』は一日の興行として、他の曲との時間的なこと、位のバランスなどを配慮した時に選曲されることが多く、今回も私が一日に二番勤めることになった経緯で選曲されました。
このようなことがあり、『俊成忠度』はとかく軽く扱われ、私自身も深く考察することなく来てしまいました。今回、『俊成忠度』を勤めるにあたって、この小品をどのように演じたらよいのかを考えました。能楽学会でのゲスト講師として、この曲を取り上げることもあって、いろいろ勉強しなくてはいけなくなり、それが演能に役立ちました。同時に、小品でも作品の内容をよく把握すると、いろいろなことがわかって面白いものだと思いました。型だけをなぞり、真似だけでは越えられないものが見えてきます。
平忠度(1144年?1184年)は平忠盛の六男、清盛の腹違いの末弟で、母親は歌人として有名だった藤原為忠の娘。母を早くに亡くした忠度は熊野の豪族に預けられ、武勇を身につけながらも母の血筋を受け継ぎ歌人としても活躍し、文武両道を極めた優れた武将として名を残しています。
忠度の歌と言えば、「行き暮れて木(こ)の下かげを宿とせば、花や今宵の主ならまし」(旅をするうちに日が暮れてしまいそうだ。桜の木陰を宿とすれば、花が今宵の主ということになるなあ)が有名ですが、これは辞世の句です。千載集に撰ばれたのは「漣(さざなみ)や志賀の都は荒れにしを、昔ながらの山桜かな」(志賀の古い都、今はもうすっかり荒れてしまったが、長等山の山桜だけは、昔ながらに美しく咲いている)です。
この歌にまつわる物語と都落ちの悲劇を、それぞれの趣向で戯曲したのが能『忠度』と『俊成忠度』といえるでしょう。

(2)
平家物語には「忠度都落」(七巻)、「忠度最期」(九巻)に忠度のことが記されています。「忠度都落」には、寿永2年(1183)に木曽義仲軍に攻められた平家一門が都落ちし、忠度も同行しますが、途中で都に引き返し、和歌の師である藤原俊成卿(藤原定家の父)の邸宅を訪ねたことが語られ、能『忠度』では「狐川より引き返し俊成の家に行き歌の望みを嘆きしに」と謡われています。
忠度が自分の詠んだ百首あまりを巻物にしたため、勅撰和歌集に入るにふさわしい歌があれば、たとえ一首でもよいから入れてほしいと嘆願すると、俊成卿はこころよくこれを承知したので、忠度は喜び「前途程遠し思いを雁山(がんさん)の夕べの雲に馳す」 と詠いながら西へ落ちて行ったと言われ、『俊成忠度』シテ謡の最初がこれです。
俊成卿は後に「千載集」編纂に当たり、約束通り忠度の歌から「故郷の花」という題で詠まれた「漣や志賀の都は荒れにしを、昔ながらの山桜かな」を選びますが、忠度が朝敵(天皇に反逆する者)となったため、名前を明かさず「読み人知らず」としました。この後日談も「忠度都落」に記されています。
平家物語「忠度最期」には最期の場面が語られます。忠度は一の谷の戦いで源氏方との合戦で奮戦しますが、右腕を切り落とされ41歳にて源氏方の武将・岡部六弥太忠澄に討たれます。この場面は『忠度』では紹介されていますが、『俊成忠度』ではまったく触れられていません。忠澄は箙(えびら=矢を入れる道具)に「行き暮れて木の下かげを宿とせば、花や今宵の主ならまし」と書かれた短冊を見つけ、忠度と書かれていたので、猛将を討ち取ったと大いに喜んだことが平家物語に書かれています。

(3)
能『俊成忠度』や『忠度』はこの「読み人知らず」と書かれたことへの執心で忠度が霊となって現れ、これは共通していますが、『忠度』が「行き暮れて・・・」の歌をテーマとし、都落ちの軍語りを加えるのに対して、『俊成忠度』は、俊成卿に「すばらしい歌でも、朝敵の名前を載せる訳にはいかない、読み人知らずとなってもこの歌は後世に残る、それが歌人の誉ではないか」と諭されると、すぐに納得してしまい、歌の功徳の賛美でまとめてしまいます。忠度の執心や忠度自身よりも和歌の功徳を賛美するのが作者の狙いのように思われます。
ここで、藤原俊成について少々触れておきましょう。
藤原俊成はたくさんの子供に恵まれましたが、その内のひとりにあの有名な藤原定家がいます。この親子、共に長生きで、俊成は91歳、定家も83歳までと、当時としてはかなり驚異的な寿命です。歌人は長生きと聞いたことがありますが、それを証明してくれています。
その俊成卿に後白河法皇より勅撰和歌集の編纂の勅命が下り「千載集」に取り組んだのが、寿永二年(1183年)70歳の時です。勅命が発せられてから文治四年(1188年)に奏覧と記録がありますので、5年の月日を費やしたことになります。
藤原俊成は仁安二年(1167年)に俊成と名乗り、安元二年(1176年)に63歳で出家し釈阿となります。忠度が俊成卿を訪ねたのは寿永二年ですので、勅命が下りたことは知っていたと思われます。
能『俊成忠度』では、岡部六弥太忠澄が忠度を討った後に、俊成卿のところに辞世の句の書かれた短冊を持参したように戯曲されていますが、どうもこれは作者のフィクションで史実ではないようです。
能『忠度』の霊は俊成卿が亡くなったあとに、息子の定家卿に読み人知らずを撤回してもらうようにと所縁の者に頼みますが、『俊成忠度』の方は、俊成卿本人に直接会いに出て来ます。これはいつの出来ごとなのか調べてもわかりませんでした。能は戯曲ですから、あまり史実に拘り過ぎない方が作品は面白くなるのかもしれません。

(4)
さて、前置きが長くなりましたが、舞台進行に沿って演能レポートします。
舞台は最初にシテツレの俊成が角帽子を沙門にして被り、掛絡を付けて高僧姿で登場します。我が家の伝書には「扇ばかりにて、数珠持たず」と記載されていますが、この「数珠持たず」が気になり、俊成についていろいろ調べました。「千載集」編纂の勅命を受けた時期なども調べ、出家していないのであれば、今回、狩衣の公家姿に変えてもと思いましたが、歴史的にはその時は既に出家していることがわかりました。すると「数珠持たず」は余計に解せません。私の推測ですが、昔の演者が演能中に矢についた短冊を落とす過ちをしたため、以後数珠を持たない方がよいと判断され、伝書の「数珠持たず」の記載になったと思われます。

(5)
その後で、ワキの岡部六弥太忠澄が登場し、忠度の尻籠に残された短冊を持参します。俊成卿が短冊を手に取り、忠度の辞世の句「行き暮れて・・・」を静かに詠み、初同の「いたわしや忠度は・・・」と続きます。そして、シテ忠度の霊が登場して、前述の「前途程遠し思いを雁山の夕べ・・・」と謡います。忠度は「読み人知らず」になったことへの執心を述べ、俊成卿になだめ諭されると、あっさりと歌物語に移っていきます。二の同(二番目の地謡)から、サシ、クセ、そしてキリの後半とすべてが和歌の賛美です。「千載集」云々よりも、和歌というものの宣伝マンとして、忠度はあの世から俊成の前に現れ、聴衆相手に和歌賛美を訴えたのだと思い、和歌ガイドとして舞い、謡えばよいと思い勤めました。ただ、前半の忠度自身の執心と和歌賛美の後半、カケリとキリの仕舞どころとの繋がりの部分の演じ方をうまく工夫しないといけないと思いました。

(6)
では、このカケリは何を表しているのか。「あら名残惜しの夜すがらやな」と謡い、カケリの型に入るので、ずっと夜でいてほしい、との思いなのでしょうか。それとも、カケリの後、忠度の気色が変わり「あれご覧ぜよ修羅王の梵天に攻め上るを帝釈出で合い修羅王をもとの下界へ追っ下す」と帝釈と修羅王の鬩ぎ合いとなるので、その導入と見るべきなのでしょうか。答えが出ないまま演じてしまいましたが、そこはご覧になる方のご自由で・・・と、逃れることにします。
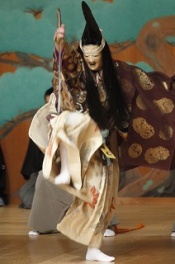
(7)
最後に修羅王と帝釈の戦いをもってくるあたりは、この作者・内藤河内守(『半蔀』の作者でもある)のすごいところです。
普通、修羅王というと興福寺の阿修羅を思い出しますが、日本に伝わる阿修羅像は興福寺も三十三間堂のも、神を守る側で、天界を守る帝釈天と変わりません。がしかし、『俊成忠度』では修羅王が帝釈天と敵対しているのが気になりました。
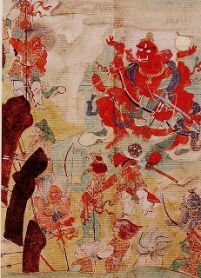
(8)
両者の戦いはインドの古い神話にある、阿修羅(アスラ)が須弥山の下の大海の神の時に、天上の神帝釈天(インドラ)と凄まじい戦いをしたことから始まります。阿修羅と帝釈は古代インドでは最初は仲間でしたが、霊薬をめぐって争い、阿修羅は敗れ、魔族となります。そして日本では密教として阿修羅は復活し、天界の守り神となりますが、面白いことに、北野天満宮にある北野天神縁起絵巻では阿修羅は赤い肌をした鬼神姿で、六道絵中の修羅道で帝釈天の軍勢と戦うところが描かれています。日本の阿修羅は二面性を持って入国しているということです。
最初この事態がわからず、興福寺の阿修羅みたいな美少年の守り神がなぜ帝釈に立ち向かわなければいけないのかがわかりませんでしたが、これで納得しました。

(9)
やがて「ややあって漣や・・・」とシテ謡から、テーマの歌が謡われます。この歌の功徳によって修羅道の責め苦から免れ、春の夜は白々と明け、修羅も帝釈も忠度の霊も消えて終曲します。
歌に対する執心や歌への賛美、こういうものが大きなテーマになるのは、時代背景があってのことかもしれません。歌は日本の文化の源であり、重要視されてきた歴史があります。今では、なぜそれほどまでに歌に執着するのかと不思議に思うかもしれませんが、文学や芸能に携わる人間なら、その心、通じるところがあるのではないでしょうか。
歌人はその生涯を閉じても、すぐれた歌は後世まで読み継がれ、消えることはありません。そして歌人の名前も残ります。忠度は「漣や・・・」の歌を読み人知らずと書かれたお陰で、その名も後世に残せたのかもしれません。平成の今の世にも語り継がれていることを、忠度はきっと想像だにしなかったことでしょう。
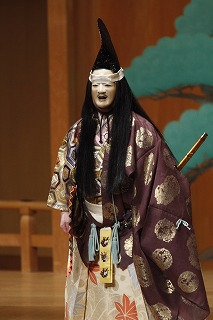
(10)
能も同じかと思いましたが、名人と言われた能楽師の役者名は残せても、その舞台は決して戻って来ません。ビデオで撮っておけば残せるだろうと言われそうですが、生の舞台の息吹までは残すことができないのです。そこが、能の道と和歌の道は同じようで大いに違うところです。
「能は花火のようなもの。華やかに見えたかと思うと、あっという間に消えてしまい、同じものはもう二度と見られない」は父の言葉です。

(11)
演劇は舞台そのものを生で見て、そこでなにかを感じることに重きをおきます。生の舞台を映像で伝えるのは至難の技でしょう。能は有名な和歌を多用して作られていますが、演じることと歌とはやはり大きな違いがあります。演じる舞台は花火のように消えて儚いですが、その儚さを素直に感じるところが面白いのです。
今回の演能で忠度や俊成卿、そして帝釈と阿修羅の関係などを調べることが出来て勉強させられました。小品の『俊成忠度』が大きなプレゼントをくれたとお礼を言いたいというのが、演能後の正直な感想です
。
写真協力
青木信二 2,4,5,6
石田 裕 1,3,7,9,10,11
北野天神縁起絵巻阿修羅の絵 アシュラブック 北進一著より記載
文責 粟谷明生 (平成25年3月 記)
『船弁慶』について 新時代を切り拓いた信光の工夫投稿日:2013-03-07

『船弁慶』について
新時代を切り拓いた信光の工夫

(1)
平成25年3月3日の粟谷能の会では『俊成忠度』に続き『船弁慶』と一日に二番を勤めました。
能『船弁慶』は、源義経が平家を滅ぼした後、兄・頼朝の怒りを被り、西国へ落ちのびる途中の話です。愛妾の静御前との別離、そして平知盛の亡霊との戦いをうまく絡み合わせた判りやすく、しかも随所に巧みな演出が施された、作者、観世小次郎信光の才能が充分に発揮された作品です。はじめて能をご覧になる方には気軽に楽しめる作品ですので、特にお薦めの曲です。
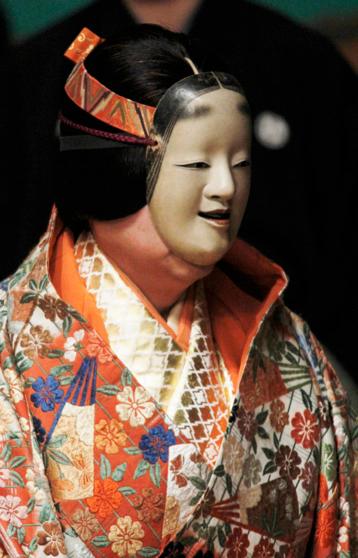
(2)
シテ方にとってこの曲のむずかしさは、前場・静御前(前シテ)と後場・知盛(後シテ)という異性の別人格を一人で演じわけるところです。若い時は、後場の知盛は力強く出来ても前場の静御前が具合が悪く、歳が嵩むと、前場の女物は良くなるが後場のパワーが落ちるということになりがちです。双方の力量のバランスがうまく取れて、よい『船弁慶』になるのです。

(3)
私が『船弁慶』を勤めるのは今回で5度目です。披きは昭和58年(28歳)の粟谷能の会で、当時、後シテはどうにか出来るにしても、前シテの静御前は正直手に負えない、と自信なく勤めたことを覚えています。
案の定、演能後に「今はまだ大人の女を演じるのは無理、仕方が無い。ただ将来のために今演っておく、それでいい」と先輩に言われた言葉がずっしり重く、記憶しています。
実はこの時、無断で父愛用の小面「堰(せき)」を使用し、後で父と伯父に怒られたことがありました。「堰」を使えばどうにか静御前になれるかもしれない、少しは大人っぽく見えるだろうともくろんだのですが、結果は私の予想、期待は見事に外れ、技量がないものがいくら良い面を付けてもだめであることを証明してしまいました。今でもあの不似合いの写真を見ると、恥ずかしくなります。その後は使用が許されなくなり、父が亡くなってから2年後に『三輪』神遊で使いましたが、その時は面がやや照って(上向き)しまい、どうも相性がよくないような気がして、その後は正直遠ざけていました。

(4)
今回再度使用してみようと思ったのは、最初に嫌われた曲が『船弁慶』だったので、もう大丈夫なのか試したいという私の挑戦が本音でもありました。ご覧になられた方の、ご感想をお聞きしたいものです。

(5)
内緒話ですが、実は父が愛用していた時の「堰」は彩色が浮いたり、削られ剥げていたりして相当傷んでいました。菊生が亡くなってから修理に出し今は綺麗なお顔になりました。能夫は修理して、「菊生叔父の魂は消えたはず。もう使っても安心して、大丈夫だから」と慰めてくれましたが、いざ鏡の間で付けようとした時、どこかで「イヤよ」と呟きが聞こえたような気がして、あれは錯覚だったのでしょうか、気になっています。

(6)
前シテの静御前は義経の愛妾で白拍子です。可憐で清純な静御前もいいでしょうが、義経を子方にする演出の意図には、シテの「艶」を引き立たせる工夫がなされていると思われます。能の「艶」とは、しなりをつけたり、わざと弱々しく声を出すような直接的な演技ではなく、能役者の身体から発散する内的な力です。舞う姿は身体的には強い芯がありながらも、どこかしなやかな、やわらかな手足の動き、そして面遣い、謡う声の芯は強く、見所の隅々まで聞こえながらも、うるさくなくしっとりとした女の声に聞こえなければいけません。硬質の中の柔和、相反する双方を兼備してこそ生まれるものでしょう。それを獲得するには能役者としての経験が必要で、当然時間がかかります。小手先だけの真似ではなく、男役者が女に見えた、それが良い能だと思います。

(7)
父が、『船弁慶』の前シテで大事なところのひとつは、旅立つ義経を遠くから見送り、泣きながら静烏帽子を左手で取り捨てる、この片手ですっと烏帽子の紐を解き、可愛く捨てる、ここだよと言っていました。一見簡単に見える動作ですが、烏帽子の紐が汗で固くなり解けにくくなったり、予め緩めに結ぶと烏帽子が落ちたり傾いたりするアクシデントが起きるので、実はなかなかむずかしい型なのです。そういう厄介なところで女のやさしさが出せれば本物、そんな能役者を目指したいと思ってきました。そして落ちる烏帽子が、捨てられた静自身を象徴するかのように見えれば、これはもう能役者としては一人前のすばらしい演者ということになるのでしょう。

(8)
前半最後のクライマックス、中入り前の型は、右に小さく小回りして正面を向いて半ヒラキと手付けにありますが、右への小回りは仰々しく、寂しさを表すには不似合いです。今回は泣きながら立ち、直ぐに去るように後ろ向きに変えました。能の基本をいじるのはいけませんが、ある年齢になり、力量がついたら、型付だけで納得しないで、感情を重視した型も取り入れるのが、健康な能だと思います。もちろんある年齢と力量を備えたればこそ、と重ねておきますが。

(9)
後場は弁慶の船出への指示から乗船となり、はじめは穏やかな海上も、急に天候が暴風雨となる有様を船頭(アイ)が囃子方の「波頭(なみがしら)」という奏法に合わせて演じます。この場面は、いかにも船が嵐にあっているところを想像させてくれます。そしていよいよ西海の海に沈んだ平家の公達を代表して、平知盛の怨霊が薙刀を持って浮かび上がり登場し、義経目掛けて激しい型の連続となります。

(10)
この後シテの波間から浮かび出る登場の場面で、番組には小書を付けませんでしたが、実際は小書「波間之拍子(なみまのひょうし)」と「真之伝(しんのでん)」の見どころを取り入れた演出にしました。「波間之拍子」とは地謡の「声をしるべに出舟の」のところで音を立てない足拍子を踏むものです。「真之伝」はシテが半幕の中で「思いも寄らぬ浦波の」の謡で幕が下り姿を消して、その後地謡が最初ゆっくり「声を」、段々と早く「しるべに」、もっとも早く「出舟の」と謡い、早笛になってシテが舞台に登場するものです。「波間之拍子」と「真之伝」は一緒に演じることは出来ませんが、今回は地謡「一門の月卿雲霞の如く」にてシテは三の松まで出て姿を見せ、シテ謡の「思いも寄らぬ浦波の」と謡うといきなり早笛になり、一旦後ろ向きに入幕して姿を消し、また幕を上げて舞台に入り「声をしるべに出舟の」にて波間之拍子を踏むという、二つの小書のいいとこどりを試みてみました。

(11)
『船弁慶』は薙刀を使用する曲です。薙刀を扱う曲は他に『熊坂』『巴』がありますが、『熊坂』は熊坂長範という盗賊の頭を大きな薙刀を荒々しく扱うことで表現します。『船弁慶』も荒々しくではありますが、どこかに霊魂の位の高さ、上品さが必要です。そして平家一門の怨念が薙刀に込められているように見えれば、能役者としては嬉しいです。以前は巧みな薙刀扱いの技術さえお見せすれば、それでよしと考えていました。がしかし、今回、薙刀の動きとシテの動きが一体でありながらも、時には薙刀が生き物のようにうごめいて見えて、それが怨念の象徴のように感じられれば、と演じてみました。

(12)
能役者は敗者を演じることが多々あります、私は演じていてつい、世の中を裏側から見るような感覚を持ってしまいます。『船弁慶』の終曲は「跡白波とぞなりにける」と、知盛は弁慶の祈祷に負けて渦潮の海中に沈んでいきますが、私は「判官よ。お前の思うようにはさせない・・・」と、怨念、恨みを残しながら消えたいと思い、最後は後ろ向きにあとずさりして入幕しました。弁慶の祈祷、義経の武術により平家の怨霊を払うことが出来た義経一行ですが、嵐がおさまり、さて義経の到着したところはどこだったでしょうか。平家が亡んだ西国の西海を目指したはずが適わず元に戻されてしまいます。『船弁慶』での義経と知盛の勝負、舞台では義経の勝利に見えるかもしれませんが、嵐で吹き戻された義経一行が怨霊に勝ったとはとうてい思えないのです。これは知盛を演じた私だからこそ感じることなのかもしれません。
『船弁慶』の前シテ静御前と後シテ平知盛を演じ終えて、全く違う二人でありながら、両者に共有するものが見えて来ました。それは両者が義経から未練という負の影響を受けた者同士ということです。同行を許されず捨てられ女と、「見るべきものは見た」と負け惜しみを吐きながらも死に追いやられ生を断ち切られた男、どちらも未練があったことでしょう。信光は負けた者を描きたかったのではないか、これも演じ終えての私の感想です。

(13)
今回、子方の友枝大風君が義経を凛々しく勤めてくれました。そのお陰で私の演能が一段と引き締まり、よくなったと自負しています。義経役を子方にした観世小次郎信光の狙いは、いくつか考えられます。大人のラブロマンスを双方の大人が演じる曲に『千寿』がありますが、正直、生な露骨な印象を受けます。信光はそれを避けるために義経を子方にしたと考えられますが、私はそれだけではないような気がします。それは当時若年であった観世大夫をどうにかして引き立て盛り上げるための策として、信光は敢えて観世大夫を子方に抜擢する作風に仕上げたのではないでしょうか。古今問わず、観客の視線はいたいけな子どもに向きます。そして賞賛します。そこを外さず狙ったのではないかというのが私の仮説です。観世小次郎信光の生年の記録は残っていませんが、文明4年(1472年)頃ではないかと言われてきました。ただ近年、表章先生の調査で、信光の生年が宝徳2年(1450年)であるとの研究成果が発表されました。それに伴い、信光がサポートしていたのは6世観世大夫の元広だろうと考えられます。残念ながら『船弁慶』がいつ作られたかは不明ですので、このとき大夫が何歳だったかはわかりませんが、若年の元広を、どうにか盛り立てようとの意図があったかもしれない・・・と、あくまでも私の確証のない推測ですが。
小さな子どもが舞台で頑張っている姿は、心打たれます。今回も「大風君、立派でしたね。ファンになっちゃいました」との声を聞くと、信光は若いかわいい観世大夫の人気取りを目論んでいた、とそう思えてならないのです。
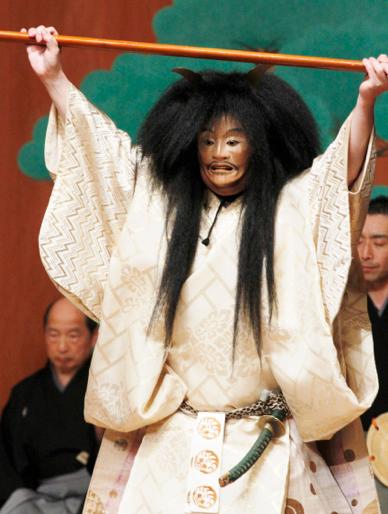
(14)
『船弁慶』は、曲名にもなっている弁慶役をワキが担当し、舞台進行役として重要な役目を担います。弁慶も義経の子方も、船頭のアイも、囃子方も、皆、大きな役割を持ち、各役者の力量や囃子方の力で面白さを出すことは、それまでにはなかった信光の工夫です。
今回、当日、宝生閑氏が体調不良のため、宝生欣哉氏がワキを代演して下さいました。欣哉氏は午前中にお父様の代演で観世流『盛久』を勤め、粟谷能の会に来られて本役の『隅田川』と『船弁慶』を代演するという三番もお勤めになりお疲れだったと思いますが、熱演して下さったのは能役者として見事で、個人的にも感謝しています。深田博治氏の船頭も囃子方も皆様熱演して下さいました。皆様のお力をお借りして無事舞台が勤められたことに満足と感謝の気持ちで一杯です。

(15)
観阿弥から始まった申楽は、世阿弥が完成させたシテ一人を中心とした夢幻能で完成度を高めました。それ以後は元雅や金春禅竹などが世阿弥の意図を継承しますが、時代の流れが音阿弥贔屓の将軍・足利教義になると変わります。音阿弥の七男の信光は世阿弥とは異なる演劇的な技巧を駆使し、それぞれの登場人物に役割を持たせ、劇的な葛藤を盛り込んだ作品を作りました。このような派手なショー的な風流な作品の誕生は、世阿弥や禅竹などの幽玄重視のやや難解な芸風から脱却せざるを得ない周りの状況があったと思います。それはパトロン頼りの仕組みから新しい観客層への芸の提供であったでしょう。信光の息子・長俊で戯曲を作る猿楽師は途絶えます。以後はそれまで作られた曲目を繰り返し演じる形となり現在に到りますが、そうさせたのは、激しさを増す戦乱の世の大きなうねりの中にあったからかもしれません。伝統芸能、古典と言われるものは、その時代時代に似合うものをいつも捜し求め生き残って来たことは確かで、歴史が証明しています。私たちも新しい時代にあった能を模索していかなければなりません。

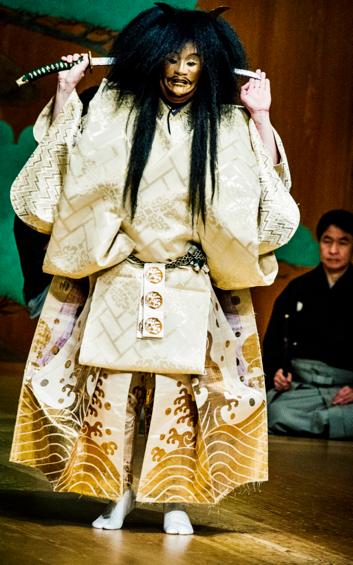
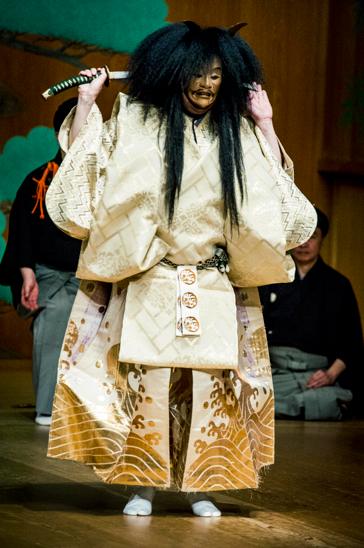
(16,17,18)
私見ですが近年、演能時間が少し長過ぎると思うことがあります。能には長くても良い場合と、そうでない時があると思います。一番だけのゆとりある公演と三番立てを同じように扱い企画しては観客無視だと批難されても仕方が無いでしょう。演能のスタイルも、いろいろなパターンがあり、観客はそこを自由に選ぶことができる、それが「現代の能」であって、そのようにしていかないと能は生き残れないのではないでしょうか。
今回の粟谷能の会では、三番立の番組を企画するにあたり、いろいろな方からご意見を頂戴して、出来る限り観客の立場でよいものをと改善しました。『俊成忠度』が40分、『隅田川』が1時間20分、狂言『舟ふな』で15分、『船弁慶』を1時間15分の短縮型で構成しました。短縮型にしても充分楽しめる、遜色ないものにすることを課題にして、演出の工夫に取り組んだのです。そして二度の休憩で1時間を確保しました。一部の観客や楽屋内からも、なんでこんなに休憩時間を取るのか、との声も聞こえてきましたが、終演後、多くの観客の皆様から時間配分が良かったと好評をいただいたことは、私たちの判断が間違いでなかったと自信に繋がりました。
これからの能は、様々な状況に応じて、時には演能時間の短縮化を考え公演すべきという場合もあるでしょう。今後もより観客の立場に立って演能時間、休憩時間などを配慮して構成したいと考えています。「従来の通り」という甘い言葉に胡座をかいていては新規の能楽ファンは増えないでしょう。今はまず減少している観客を取り戻し、その中から長時間の演能を好むファンが生まれればよいのです。
今回ややマイナーな作者、観世小次郎信光に焦点を当てて、そのたぐいまれな才能と新時代を切り拓く努力を垣間見ることができ、大いに励まされました。そして、そんな新たな発見があったことで、楽しい演能となりました。
(平成25年3月 記)
写真撮影
1,10,11,13,16,17,18 森英嗣
2,4,5,6,7,9,14,15,石田 裕
3,8,12, 前島写真店 成田幸雄
文責 粟谷明生
『求塚』を演じて ー三人の苦悩を思うー投稿日:2012-10-07

『求塚』を演じて ー三人の苦悩を思うー
粟谷 明生

一人の女が複数の男達に求愛され、返答に困って難題を課し果たした男を選ぼうとする物語はあまたあります。男達が難題を解決できずに退散してしまうのが竹取物語「かぐや姫」。
万葉集や大和物語をもとに作られた能『求塚』も一人の美しい女に二人の男が求愛するところは同じですが、男達が難題を解決したために起こった悲劇を描いています。愛された女はどちらとも選び得ず、川に身を投げ、愛した男たちも刺し違えて絶命し、そして皆、地獄に落ち苦しむ話です。一見純愛物のように思われる内容ですが、稽古していて、個人の好いた、好かれただけではない暗い背景、作品の奥深いところに三者三様の人間模様が見えてきました。作者は観阿弥か世阿弥かはっきりしませんが、近年世阿弥作との意見が有力とは研究者たちの判断です。
父の七回忌追善の粟谷能の会(平成24年10月14日)で、この奥深い作品『求塚』を披くことが出来たことは、感慨深いものがあります。
では、この能の奥深さ、背景とは何でしょうか…。一人の女と二人の男の素性や事情はどのようなものなのか、そこから探していきたいと思います。
美しい女の名前は菟名日処女(うないおとめ)。二人の男、小竹田男(ささだおのこ)は摂津の国の者、血沼益荒男(ちぬのますらお)は和泉の国の者。両者の菟名日処女への思いは愛とか恋とかだけでない、二人は単なる恋敵だけではない、もっと根深いものがあるのです。
それは土地の権力争いまでも絡む政治的な駆け引きがあった、と私は仮説を立て想像を膨らませ舞台に挑みました。

菟名日処女は、かぐや姫と違い裕福な豪族の家庭に生まれ育った可愛いひとり娘で、彼女を手中にすることは、即ち領土や経済まですべての利となる、そのため地元からは小竹田男、他国からは血沼益荒男が選ばれて、彼らは一族だけではない、国を背負っての使者の役であり、その使命を果たすために必死な覚悟と意気込みがあったのでしょう。それがもくろみと反して大事な女を自殺させてしまい取り返しのつかない事態になってしまいました。男たちは共に故郷に帰れなくなり、互いにその責任を相手に押しつけ啀み合い殺し合ったのだと思います。それは単に愛する人をなくした悲しみなどではない。火に燃える鶴ケ城を見て泣きながら刺し違えた純心な白虎隊の精神とは明らかに違うのです。憎み合い戦い抜いた挙げ句の相打ちです。


喜多流の伝書には「刺し違えて空しくなれば」の場面で、刺し違える型についての記載はありません。しかし先人たちは、「刺し」で少し前のめりになり「空しく」でのけぞるように後ずさる型をなさいました。これは十四世喜多六平太先生の考案ではないか、というのが楽屋内の話です。
この型は男同士の殺し合いの壮絶さを強調する、演者には難度の高い型です。今まで、引き分けひらき(前後一歩の移動)で処理していたものを、友枝昭世師のご指導もあって四歩前に出て、四歩あとずさりの大きな動きに変えて試みました。ご覧になられた方がどのように感じられたのか、お聞きしたいところです。

それにしても菟名日処女はどんな女だったのか、演じる前にいろいろ想像してみました。美しく可愛いことに間違いないと思うのですが、内面的にはどうなのか。いざ決断となると自分では判断能力が足りなく、優柔不断な一面を持つ女ではないか、と。もっとも女がひとりで判断出来る時代ではなかったと言われればそれまでですが。自己主張など考えられない、ただただ可愛い御姫様のような姿が連想されます。シテの詞章にはありませんが、鴛鴦を射止めた男の方を選べ、と指示したのは両親で、この指示も私の想像の根拠の一つになりました。

さて、舞台進行に合わせて話を進めましょう。
前場のシテとツレの出(登場)は一声ですが、本来は全員本舞台にて立ち並びで謡うように伝書に書かれています。近年、先人たちはこれは景色が悪いと避けられ、橋掛りにて謡うように変わりました。今回も同様に、ツレ二人を先頭に、シテが後から出てお互い向き合い橋掛りにての連吟としました。
国立能楽堂のように長い橋掛りはシテとツレの距離が遠く離れてしまうため、声が聴き取りづらく音が揃いにくくなるので役者泣かせです。特にツレが若年の場合、鬘をつけて耳を塞がれ、謡い声も面で籠もってしまうので聞きづらくなります。そこで今回は一声謡の後、サシコエの前に本舞台に移動する演出にしました。後日、ビデオやレコーダーで再確認すると謡も揃い、景色も悪くなかったので、それ相当の効果はあったと安堵しています。

春とはいえ未だ残雪のある生田川辺りの景色を謡う前場の前半場面はとにかく明るく、華やかに謡わなくてはいけません。『求塚』という曲の位の高さで、とかくゆっくり、丁寧に謡い、そして囃されていた時代がありましたが、これは作者の意図に反します。若菜を摘む場面は、後の暗い恋の告白と、明暗で対比させるために仕組まれたものです。その意図を外しては意味を失い演じ手失格と思います。

喜多流はシテの装束も面もよいものを選び、ツレはレベルが落ちるもので済ます、という風習、楽屋思考があります。私もそのようにすることもありますが、今回の『求塚』では、若菜摘みの女の一集団が皆同じように見える景色でありたい、と思い装束選びと着附の仕方を考えました。ツレの装束の付け方はいろいろあります。唐織を熨斗目付け(のしめつけ)にするか、肩脱付け(かたぬぎつけ)にするか、または腰巻水衣という選択肢もあります。今回はシテが孤立して妙に目立つのは嫌い、三人同じように見えるように、全員唐織の熨斗目付けの着流し姿にしました。

それでも能役者のスケベ心でしょうか、シテ一人だけが不思議となぜか際立つ、なにか感じさせるものが出せないかと、シテの面を「増女」に変えてみました。伝書にはシテ、ツレ共に「小面」と書かれていますが、三代喜多宗家宗能の「増女にても…」との資料が私の背中を押してくれました。
「増女」には「泣増」やその他いろいろな面が我が家にはありますが、「宝増(たからぞう)」の艶が似合っていると選びました。

演能後、「ワキの言葉の後にすぐにツレが謡い出したのが気になったが、あれは意図的なのか」とのご質問を受けました。
能では、問われた人が問うた者に答える、これが普通で当たり前ですが、『求塚』ではワキがシテに向かい「この辺が生田ですか?」と質問すると、ツレが「ここが生田と知らないなんて…」と謡い、シテの受け答えを遮るような構成となっています。これは珍しい特異な演出です。この特異を演者は効果的に見せる必要があります。そこでツレ役の息子・尚生と佐藤陽には敢えてワキの謡が終わると同時にかぶせるように突っ込んで謡うようにと指示しました。二人ともよく私の気持ちを理解して謡ってくれたことに感謝しています。

間語り 野村万蔵氏
さて後場になる前に、間語り(あいがたり)についてご紹介しておきましょう。
以前の演能レポート『求塚』(「友枝昭世の会『求塚』の地謡を勤めて?間語りから見えた男達?」参照)にも書きましたが、ここでも、シテ方は間語りをよく理解して作品を演じなければいけないと自戒をこめて言いたいと思います。
間語りはときに、シテ方の詞章にはないことも補って、物語をくわしく語ることがあります。
『求塚』の間語りは山本東次郎家の、血沼益荒男が死後も小竹田男に苦しめられているので旅人に刀を貸してくれと頼むと消えて、その後、血の付いた刀が残っていた、という長い語りがあり、私には鮮烈に印象に残っていて、作品の面白さを増し理解しやすくさせてくれると感じていました。本来、和泉流にはこの部分の語りはありませんでしたが、野村萬先生が観世寿夫先生の『求塚』のアイを勤められたときに、従来の語りではシテ方の語りと内容が重なるので横道萬里雄氏に新しく語りを創作して下さいるように依頼なさったとお聞きしました。少々長い語りになるので、今回アイをして下さった野村万蔵氏には大変ご負担をお掛けしましたが、この語りを聞くと作品の内容が一段と判り易くなると思い、今回やっていただけて感謝しています。

『求塚』はもともと宝生流と喜多流にあり、金剛流、観世流、そして近年金春流も復曲して現在五流にあります。
喜多流の演出の特徴は後場のシテの出にあります。「おお曠野人稀なり、我が古墳ならでまた何者ぞ」と太鼓の入る出端で謡い出す他流に比べ、喜多流のみ静かな習一声で「古の小竹田男の音に泣きし、菟名日処女のおき塚は、これ」と謡ったあとに「おお曠野人稀なり…」と続きます。この「古の…」と細々と痩女の位で引廻し(ひきまわし)で覆われた塚の作り物の中からの謡が難所です。どのくらいの声量でなら謡を届かすことが出来るか、ここが勝負になります。何を言っているのか聞こえないのも、また逆にうるさくなっても成立しません。ここは『景清』の「松門の謡」に共通するところです。「謡い声を固く凝縮しろ」と父の言葉が思い出されます。さて今回はどうであったでしょうか。

後シテの面は「痩女(やせおんな)」です。窶れ果てた顔立ちで、『砧』『定家』『求塚』に使います。『砧』の芦屋夫人は最後回向により成仏出来ますが、『定家』の式子内親王も『求塚』の菟名日処女も成仏できず、式子内親王はまた定家葛の匍う墓へ、菟名日処女も暗闇の火宅の栖へと帰ってゆきます。そこにしか戻れないのでしょうか。救われない終幕にいったい何を感じさせたいのか、作者の意図を見出したいのですが、答えはいくつもあるようにも、いや答えなどないかもしれない、それが能である、と思ったりもしています。能はやはりむずかしい、決して簡単なものではないようです。

「痩女」を使用する時は、その窶れた表情に合わせて、必死で前に歩もうとするも力のない重い足どりとなる特殊な運びをしますが、これを「切る足」と呼び、これも喜多流ならではの演出です。

さて、演じ終えて、私に何が残ったのか。
それは三人が皆、それぞれに思い、それぞれの行動をとったが、結果はよい方向には向かず残念なこととなった、三人が三人とも苦悩のなかにいるという苦い思いです。この苦悩、無念さは今の私にも思い当たり共感するところがあります。いろいろ手段を凝らし手に入れようとしても適わない、遮り邪魔だてするものがあって事をうまく運ばせてくれない、そんな風に悲観する時もあります。
小竹田男や血沼益荒男の気持ちがなんとなく判り哀れに思えてくるのは、自分に照らしているからかもしれません。

私は小竹田男や血沼益荒男を演じた訳ではありません。愛された菟名日処女を演じたのに、愛し、そして手中に納めたいと思う男たちの気持ちが充分過ぎるほど判りました。もっともこの程度の感想では、まだまだ『求塚』を演ったとは言えないよ、と父がどこかで笑っているような気もしています。
(平成24年10月 記)
写真提供
森英嗣
最後の2枚 青木信二
写真無断転載禁止
『百萬』について 舞い尽くしの芸投稿日:2012-05-07

『百萬』について
舞い尽くしの芸
粟谷明生

『百萬』を喜多流自主公演(平成24年4月22日)で勤めました。過去に稽古能で一度勤めたことがありますが、公式の場としては、はじめてでした。
まず『百萬』のあらすじをご紹介します。
奈良の西大寺のあたりで幼い子ども(子方)を拾った僧(ワキ)は、その子を連れて京都嵯峨の清涼寺を訪れます。門前の男(アイ)に子どもに何か面白いものを見せたいと尋ねると、「百萬」という女物狂いが面白く音頭を取り躍ると勧めるので、それを呼び出します。
門前の男が下手な念仏を唱え踊り出すと百万(シテ)が現れ、「あら悪の(わるの:下手な)大念仏の節や」と自ら念仏の音頭をとり歌い舞いはじめ、仏前に向かい我が子との再会を祈ります。それを見た幼い子どもは自分の母親であると僧に明かし、僧はそれとなく百萬に事情を聞き問いただします。百萬は子に生き別れたことを嘆いているので、僧は信心によって子どもと再会出来ると諭します。僧の言葉に慰められた百萬はふたたび奈良から京の都までの道中のことを舞って見せ奉納しますが、多くの群衆の中に我が子を捜し出せないことを悲しみ、遂に仏に手を合わせ狂乱してしまいます。僧は百萬が幼い子どもの母親である事を確信し引き合わせると、百萬はもっと早く名乗ってほしかったと恨みはしますが、仏の徳により再会出来たことを喜び、我が子を連れて奈良の都に帰って行きました。
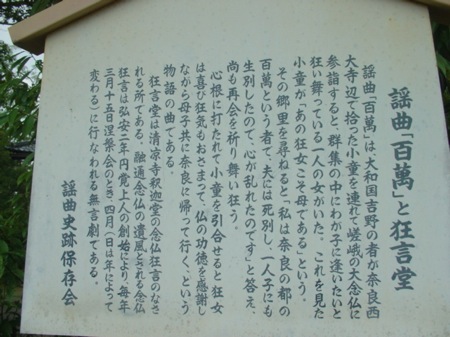
母子再会のお目出度い曲目と言えば『桜川』『三井寺』『柏崎』と『百萬』、喜多流にだけある『飛鳥川(あすかがわ)』などがあります。
これら狂女物の全般に言えることは、子を捜し求める形式をとりながらも実は親子再会が主要ではないということです。
『桜川』は桜を取り上げ春の景色を、『三井寺』は秋の月景色を琵琶湖や園城寺の夜景なども組み入れながら紹介します。『柏崎』は善光寺信仰と亡夫への恋慕などを主題としています。これら代表的な三曲では、愛子との再会は戯曲を組み立てる上での味付け程度で、主要部分は別にあります。
能は、このように主題のためならば、なんでも取り付けてしまう大胆な手法を取り入れ、それが却って能ならではの味わいになっているかと思います。
『桜川』『三井寺』『柏崎』の三曲は、中入りのある複式形式です。前場では愛子を失う経緯や状況説明の場面を設け、中入り後に子を捜す旅模様の道行から話が展開する方法がとられていますが、それは我が子の探索に焦点を当てているかのように思わせる見せかけであると言っていいでしょう。

一方、『百萬』と『飛鳥川』は中入りもなく道行もありません。特に『飛鳥川』は我が子を訊ねる母親の気持ちが稀薄で、逆に愛子の友若の方が母を捜し求めている異色な作品です。主題は母子再会よりも初夏の田植えの模様を描く方に重点が置かれ、友若との再会はまさに取って付けたような付録的な扱いです。
『百萬』も『飛鳥川』同様の構成で、親子再会のドラマは付録的に処理されていますが、二曲の違いは、『百萬』のほうが随所に行方がわからなくなった我が子のことを語り、母親の子に対する愛情が溢れているということです。
私は『百萬』という曲が、なにを見せたく、なにを訴えたいのか、を考えました。そして出した答えは「年増の女芸人の舞ぶりを見せつける」、これに極まると思います。
歌舞伎役者が芝居の物語の云々よりも踊りを披露することを第一とするに似た、能役者の舞っぷりを見せつける作品だと思い勤めました。
百萬という女は実在した曲舞の名手であったという伝承があります。また、奈良の西照寺には百萬供養塔があり、百萬について記載されたものがありましたので、ここでご紹介します。
「百萬とは女性の名で春日大社の巫女で一男児があった。ある日、西大寺の念仏会に親子で詣でたが、あまりの混雑に我が子十萬を見失った。その後、百萬は狂女となって必死に十萬を探し求め歩き、京都嵯峨の清涼寺の念仏会で遂に我が子に巡り会い、奈良に戻り親子仲睦まじく暮らし、やがて十萬は唐招提寺の道浄上人になったとも、清涼寺の十遍上人になったともいわれる」と。

神道の巫女が仏教の念仏会でという設定は神仏混合とはいえ、現代の感覚では、しっくり来ないところもありますが、そのようなことはさておき、『百萬』は女芸能者たる百萬という母親のいろいろな舞を見せるのが作者の狙いなのです。その工夫として狂女物に太鼓まで入れるのですから、これは大胆なやりかたで、百万の舞ぶりをいかに賑やかに囃すかという意図がありありと伺われます。
『百萬』には舞いどころが羅列されています。念仏の段、車の段、笹の段、二段曲(にだんぐせ)の舞、二度のイロエと、舞う場面がふんだんに盛り込まれています。この羅列された各種部分をシテの能役者がいかに綺麗にしっとりと、時には激しく舞うかが、この能の善し悪しの決め手となります。綺麗にきっちりと舞ってこそ、鑑賞者は各種の舞の起伏を自分なりの世界で感じ想像してご覧になれるのです。

清涼寺・釈迦堂門前の者(アイ狂言)の下手な念仏がはじまると、百万は笹を持ちいきなり登場します。シテは一途な思いの狂気の様を表す笹を片手に持ち、最初から立烏帽子を被り長絹姿という舞人の扮装です。通常、曲の後半や途中で物着(ものぎ=着替え)をしてこの姿になり、舞人に変身することが多いですが、百万は最初から舞姿で登場します。このことからもいかに舞を見せることに重点がおかれているかが判ります。

自ら念仏を唱え出す百万。「力車に七車・・・」「重くとも引けやえいさらえいさ」と車の段と呼ばれる部分、実はなぜ車が出てくるのか知りませんでした。百萬はもともと車の上で舞っていた芸人のようで、そのため車の段と呼ばれています。ここのシテの心持ちは上機嫌で、調子も張り上げ、ほどよい乗りで謡い舞う躁の意識で、との教えがあります。
しかし狂女というのは、躁と鬱が交互にやってくる特徴があります。次の笹之段と呼ばれる「げにや世々ごとの親子の道に・・・」がまさにそうで、一転して鬱な部分の舞となります。謡い方も陰気に暗く謡います。しかし私はこの笹之段があまりに陰気になりすぎるのは吉としません。
ただひたすらの鬱ではない、不安定な感情とでもいいましょうか、陰気だけではない、少し躁が見え隠れするような笹之段を舞いたいと思い、地頭(粟谷能夫)にお願いしてシテと地謡の感情の起伏が感じとれるようなものにしたいと演じてみました。観ていただいた方々のご感想はいかがでしたでしょうか?

笹之段を舞い終えると、母親百萬は愛子に会いたいと「南無や大聖釈迦牟尼仏、我が子に逢わせてたび給え」と仏前で祈ります。
それを見た子(子方)は僧(ワキ)にこれこそ自分の母であると告げます。しかし、そのあとの対応が現代劇になれている我々にはしっくりきません。
私は子方時代に「自分が、母親だと僧に教えているのに、何故ワキの僧は目の前にいる母親に子どものことを教えないのか」、また「何故母親も近くに居るのに知らん顔をするのだろうか」と、子ども心に疑問に感じていました。
しかし、親子再会が副次的なことで、終始女芸人の舞い姿を見せるのが主題ですから、ここで二人が名乗り合ってしまっては、事はここでおしまいになってしまいます。僧が確信出来るまで、子と再会させない手法をとり、女芸人の舞をふんだんに披露させる。ここが理詰めで物語の進行重視という現代劇とは異なる能らしい演出です。
ワキとの問答で百萬の心境は次第に興奮して語られていきます。
そしていよいよ曲舞が始まりますが、その前にプロローグのようなイロエがあります。
『百萬』には二つのイロエがありますが、最初のイロエはさしたる意味を持たない舞台を一周するだけの舞です。これはいわば舞を舞う前の能役者の準備運動のようなものと思ってくだされば良いと思います。このようなことを堂々とやってしまう、これも能の面白さのひとつです。

イロエの後、序、サシ謡と続き、本命の二段曲の舞となります。「奈良坂や、この手柏の二面」と奈良から京都への旅道中を舞い聞かせます。見せ場の型どころが続き、演者の力量が判るところです。我が子を捜し歩く百萬の気持ちを謡い舞いますが、次第に興奮状態となり気分は高揚していきます。
この『百萬』の二段曲は少年期や青年期に舞囃子でよく稽古させられました。
若い時に覚えた動きは年を経ても忘れません。父が若い時に謡い込んでおけ、舞込んでおけ、と教えてくれたことがひしひしと胸にせまります。私も未熟ながらも積み上げて来たもので舞えたことを喜んでいます。そして今回はじめて、百萬という母親になりきって舞っている自分を、遠くからまた別な目で見ながら舞っている自分を発見出来て不思議な気がしました、「離見の見」とはお恐れ多いことですが、なんとなくそのような体験が出来たことがとても面白く貴重に感じた能でした。
そして、「あら我が子」「恋しや」で二度目のイロエとなり、子を捜す型を囃子に乗り表現します。「これほど多き人の中に、などや我が子の無きやらん、あら我が子恋しや」と捜しても捜しても我が子に会えない百萬は遂に狂気も最高頂に達します。
この感情を表現するには舞という動きだけではむずかしくなります。興奮し高揚した気持ちは謡で表現するしかないのです。その謡い方は、音の高低や早い遅いの違いだけではなく、陰と陽、そして減り張り、出る息と引く息、これらすべてを駆使してようやく表現出来るものです。そこが能役者の力量を計れるところで、演者にとっての腕の見せ所ともなります。
私を含めて喜多流の若者が挑んだ『百萬』は、この大事な謡を疎かにしがちなため、最後の盛り上がりが足らず何か薄っぺらな心打たない舞台印象を与えて来ました。私も56歳となり、正直あれで合格か?と言われれば、まだまだ上があるのですが、なにかそれなりの手応えが感じられた、それが嬉しい、これが本音です。

終盤は、ようやく我が子を目の前にする母の百萬ですが、すぐには素直になれない性格のようです。「もっと早く名乗ってくれたら・・・」と愚痴って立ち去ろうとしますが、やはり母親です。気を取り直して我が子をやわらかく抱き、すべて清涼寺のご本尊のお陰と讃え、親子二人で奈良に帰ります。
これらの舞や動きをスムーズに女らしく、母親らしく見せてこそ大人の『百萬』を演じたと言えるのだと思います。
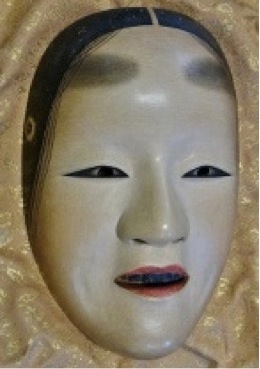
今回使用した面については、百萬は年増の女芸人ですが、あまり生活感のある表情の面では演じたくない、ちょっと艶がある、綺麗な表情の面が使いたいと思い、伯父・新太郎が愛用していた「曲女(しゃくめ)」を選んでみました。「深井」よりも若くみえる面はどこかエロチックな表情で、いつかつけてみたいと思っていた曲見の特殊版で、我が家の名品です。お客さまにも、また楽屋内にも反響がよく、私としては大満足しています。

今回子方を勤めてくれた金子天晟君は小4になりました。月日の経つのは早いもので、ついこの間、『鞍馬天狗』の花見をしていたのに、あっという間に成長されて驚いています。
今回、後見にお祖父様の金子匡一氏、地謡には父親の金子敬一郎氏と三代で、私の『百万』に協力していただき、伝統芸能を守る家、守る人々に、妙に感心してしまいました。
将来の能楽界を展望すると、親子三代という環境にとてもあたたかな気持ちになれて、なんだか本当に百万の母親になったような嬉しい気分になりました。
(平成24年5月 記)
能『百万』舞台
シテ 粟谷明生 小鼓 曽和正博 大鼓 大倉慶之助 撮影 石田 裕
清涼寺、釈迦堂、百萬供養塔、面「曲女」
撮影 粟谷明生
百萬と清涼寺合成写真
作成 川畑博哉
『景清』を演じて-芸能者としての景清を親子で勤める-投稿日:2012-03-04

『景清』を演じて
――芸能者としての景清を親子で勤める――
粟谷明生

『景清』と言えば粟谷菊生、菊生の『景清』と言われるほど父は数多く勤め、十八番と賞賛されてきました。そのためか、私は父の存命中はなかなか『景清』を演じる気になれずにいました。亡くなってから、いつかは勤めなければ、と思っていましたが、いざ番組を組む段階になると、どうも父の顔が浮かんで来て、比較されるのも嫌で避けて来たのが、正直な本音です。
今年は父の七回忌の年です。それまでにはと思い、息子・尚生もこの道を目指し成長しはじめてきたので、ツレ役を配役して、親子で粟谷能の会(平成24年3月4日)で披らくことを決めました。それが出来たことは嬉しい限りです。屹度、一番喜んでいるのは、あちらにいる父かもしれません。
景清は藤原秀郷の子孫の伊勢藤原氏であったので伊藤景清とも、また平景清とも言われていたようですが、はっきりしません。上総介忠清の七男で、勇猛であったため悪の字を付けて通称・悪七兵衛景清と呼ばれていたようです。
平家方の侍大将として常に戦の陣頭に立つ勇者のように思っていましたが、勝ち戦の数が少ないこともあって、戦の雲行きが怪しくなるとすぐに退散するので、逃げ景清と陰口をたたかれていたようにも伝えられています。しかし、能『景清』はそのような弱いところは一切見せずに、落ちぶれても豪の者として描き、昔華やかに戦った時代を戦語りで見せます。

平(または伊藤)景清が能に登場するのは、『景清』と稀にしか演じられない『大仏供養』の二曲です。東大寺の転害門で頼朝暗殺を企て失敗する『大仏供養』は、若者でも演じられますが、『景清』は若年や未熟者では許されない高位な曲として、喜多流では扱っています。喜多流では「盲目」と「老人」というハンディを背負う曲を大事にして、若者や未熟な者には許さない風習が今もあります。
私も56歳になり、いつまでも避けていてはいけない、そろそろ手がけなくては、という思いもあり勤めました。
喜多流の景清像は老いても武骨魂の消えない、意地っ張りな盲目ぶりを強調します。
専用面「景清」には、顎髭が有る無しの二種類がありますが、喜多流は老武者の往時の面影を偲ばせるため、髭のある面を好んで使います。装束も着流し姿で乞食となった落魄ぶりを主張する流儀もありますが、喜多流は仰々しく、敢えて白色の大口袴を穿くのが決まりです。
さて、今回『景清』を勤めるにあたって、景清とはどのような人物なのか、どのように演じたらよいのかを考えました。
まず人の憐れみで暮らす語り芸能者像、次に零落しても武士気質を捨てることが出来ない性格、最後に一人娘の父親である事実、この三つ巴に「老い」と「盲目」のハンディを加えた非常に複雑な構成になっていて、そこが『景清』の面白さでもあると思います。

では舞台進行に合わせてその複雑構成のベールをはがすべく、演者がどのように取り組んだかを少しずつ明かしていきます。まずその前に、簡単に物語をご紹介します。
悪七兵衛景清は日向の国に流され零落しても武士気質を残し、人の憐れみを受けて乞食同然の暮らしを芸能者として生きています。そこへ鎌倉から遙々、娘の人丸が訪れ再会となります。束の間の幸せを楽しむ二人ですが、景清は娘に故郷に帰り、自分の亡き跡を弔ってくれ、と決断し見送ります。一緒に居たい気持ちを抑え、将来の娘のことを考えた父・景清を思うと自然と涙腺が緩みます。
さて舞台進行です。
舞台には引廻しに覆われた藁屋が置かれ、ツレ(人丸)とワキツレ(男)が次第で登場し鎌倉から宮崎までの道中を謡います。
二人が脇座に着座すると、藁屋の中から「松門の謡」と呼ばれる謡が聞こえてきます。「松門、独り閉じて、年月を送り、自ら清光を見ざれば、時の移るをも、わきまえず。・・・」、ここの細かな節扱いは謡本には明確に記載されておらず、先人からの伝承、口伝です。口伝というのは不思議なもので、例えば一人の伝承者から二人が習うと、そこに二つの伝承が生まれてしまいます。どちらかが正しい、良いということではなく、演者がそれぞれの感性で聴き取るので、「松門の謡」であれば二つの謡い方が生まれてしまう、これはどうしても起こる伝承の定めなのかもしれません。
私は父のを規範として真似ていますが、稽古に入って一つの疑問が起こりました。
先ほどの複雑な景清のどの部分を強調し、どのような境遇で謡ったらよいのか、と。
残念ながらそこは父から伝授されていませんでしたが、「松門の謡」の底流に流れる人間景清に内在するもの、それが気になりました。

私は、「松門の謡」は、平家語りをする乞食芸能者の心持ちを全面に出して謡えればと思うようになりました。そのヒントとなったのは、角帽子の着用です。
景清は角帽子を付けますが、角帽子とは本来出家を意味する被り物です。
「なぜ出家していない景清が角帽子を被るのか?」
この疑問が発想の発端です。
「とても世を背くとならば墨にこそ、染むべき袖のあさましや窶(やつ)れ果てたる有様を・・・」(世を捨てた自分であるから、出家入道の姿をしているはずであるのに、墨染の衣も着ていない。俗体のままで零落している有様を・・・)と謡われるように、景清は出家していません。
であるのに何故、角帽子を付けるのか?
そこで調べてみると、盲目の方も検校(けんぎょう)や勾当(こうとう)のような位のある方には特別に被り物が許されていた時代がありました。実際、検校や勾当が角帽子を着用していた訳ではありませんが、それに似たものをかぶっていたため、昔の猿楽師の工夫で角帽子を選んだのではないかと推察します。
つまり角帽子は、盲目で日向の勾当と呼ばれた、平家を語る芸能者の象徴なのです。
そこをクローズアップするのが「松門の謡」と「語り」ではないかと思い勤めました。老いた語り芸能者であっても、ひとたびスイッチが入れば、声は高々と朗々と語りはじめ、悦に入って大声を張り上げてしまう、そのような一面もあるのが景清ではないでしょうか。

「松門の謡」は昔から「鎧の節糸が古くなってぶつぶつと切れたように謡え」と言われています。これには納得出来ますが、「決して聞かせどころではない・・・聞こえても聞こえなくてもそんなことはどうでもいい。シテの腹の中に応えがあればいい」となると、少々乱暴な教えだと反論したくなります。
胸の内の思いだから声は小さく聞こえなくてもいい、というのは舞台に上がる者の言い分けではないでしょうか。
能は歌劇です。謡の詞章は言霊として観客に的確に伝えられてこそ、観客はそこから想像を膨らますことが出来るのです。聞こえなくてもいい、は想像しなくてもよい、ということになります。「松門の謡」は呂の音を主にして、観客に的確に伝えられなければ失格です。胸の内の思いを、声をひそめたり、半分の声で、という発想は間違いだと思います。
西洋の音楽のピアニッシモ(とても弱く)や更に弱いピアニッシッシモ(とてもとても弱く)も、弱くとも芯は堅く、屹度演奏会の会場の遠く奥までしっかりと聞こえるのではないでしょうか。
「松門の謡」も見所の奥まで伝わるものでなければいけないはずです。

もう一つの景清の芸能者の本領を発揮する場が、屋島の合戦模様を語る「語り」です。
はじめ冷静に語りはじめる景清ですが、次第に興奮してきて、声も荒げていきます。
不自由な足下でありながら、遂には立ち上がり、娘のために、というよりは、もう自然と動いてしまう、そのような興奮状態で三保谷四郎との錣引きの有様を見せます。
景清のもっとも華やかで脚光を浴びたあの時、もっとも自慢したいあの場面です。
強く謡う地謡陣の謡い声に後押しされながら、太刀を振り、錣を取る型が続きます。
景清が謡の能でありながら、唯一身体全身で動きを見せるところはこの段だけです。ここにも演者には細かな伝承がいくつかあります。
杖をつかなければ動けない者が、思わず杖無しで動いてしまう、その演技には細かな裏打ちされた教えがあります。

例えば、右手に持っている太刀を見る場合は、右を見ずに、わざと左に顔をそらします。掴んだ錣が切れた途端に、足の動きは順でなく、すべて逆の動きをします。
左へ動く型は常は左足から動かすのがルールですが、わざと逆足の右足から出て不自由さを見せます。逆の動作は自然ではないので動きにくく、稽古を重ね慣れるしかありません。そして先人の舞台をよく見て身体で覚えるしかないのです。いろいろな先人の方々や父のを参考にして勤めましたが、今ふり返ると上手く出来たところもあれば、やり直したいと思うところもあります。

昔語りを終えると、父景清は娘にもう帰れと促します。
最後の別れの場面です。『景清』については、父からたくさんの事を教えてもらいましたが、中でも最後の人丸を抱いて見送るところ「さらばよ止まる」とツレの背中を押して別れる型は、地謡の「さらばよ止まる、行くぞとの・・・」と父・菊生の左手がツレを勤める私の背中を強く押したあの感触を今でも忘れません。
強い、のですが、しかしそのタッチは柔らかでした。
「背中を押したら、すっと一の松まで行って、ふり返って、最後はシオリをしながら謡に合わせて幕に入れ」が、父の最初の教えでしたので、今回もそのように息子にやってもらうことにしました。
能の伝書には細かなことは記載されていません。このような場面の動きは演者の感覚、意識に委ねられ自由です。
さて、この「すっと一の松まで」がむずかしいのです。運ぶ(歩む)速度が速過ぎては荒く雑に見え、遅くては景清が「もう行け!」と押した効果が上がらず、涙に繋がりません。さて、どのように息子に教えたらよいのだろうか。

自分を振り返ると、「遅いよ」「速過ぎだよ」とご注意を受けたことはありませんでした。きっと上手くこなしていたのだろうと、自惚れていたのですが・・・。よく考えると、私は父の押す力を受け、それに委せて運んで(歩んで)いただけ、と気付きました。
私がほどよい力で息子の背中を押してあげればよいことなのです。

最終場面の最後、明生景清がどのように尚生人丸の背中を押すかが見どころですと、ご案内させて頂きましたが、今回は少々力が入り過ぎて叩き過ぎたようです。
後日「押し過ぎだよ」と尚生人丸に言われてしまい、面目ない明生景清でした。
まだまだほどよく押せない力不足を反省しています。
今回の『景清』は息子・尚生との初共演で、しかも親子の役でしたので、二人で稽古を重ねられたことも嬉しいことでした。「尚生は、まだまだ」と辛口の批評も仕方無いと思いますが、年齢と経験を計算すると十二分に勤めてくれたと、私は評価しています。
父の『景清』の披キ(昭和45年 第10回粟谷兄弟能)は40代後半のことでした。その後、昭和49年、55年と続き、生涯で28回の『景清』を勤め、『景清』は菊生の十八番でした。私はそのうちの9回にツレを勤めました。晩年の菊生の『景清』をご覧になられた方は多いと思いますが、昭和の舞台を観ておられる方は、もうそう多くはいらっしゃらないかもしれません。

私が規範としているのは昭和の、父が5,60代のころの『景清』です。溌剌として老いと盲目を真似る父の芸に憧れていました。
晩年「なんだか最近演る『景清』は自分の素のまんまでやれちゃうが…。それがいいんだかどうだか…」と、こぼしていたのを知るのは、たぶん私だけでしょう。
そのような裏側まで知った上で、意識して真似しない部分もありましたが、基本は父の『景清』の真似、これは紛れもない事です。
先日、「10年後に、また親子共演を観たいものです」とご覧になられた方が仰しゃられたので、「いや親子で9回はやりたいから、3,4年後にまた再演しますよ」と答えてしまいました。本当にそうなれば、そうしたいと思っています。
(平成24年3月 記)
写真提供 粟谷明生 撮影 青木信二
『天鼓』について 日本人によって創られた唐土の空想物語?投稿日:2011-10-09

『天鼓』について
― 日本人によって創られた唐土の空想物語 ―
粟谷明生

br />
『天鼓』の初演は平成6年・粟谷能の会研究公演でした。
今回の粟谷能の会の『天鼓』(平成23年10月9日 於:国立能楽堂)は17年ぶりの再演ということになりました。
現行の喜多流の『天鼓』では「楽(がく=唐物の舞)」は太鼓なしが決まりです。
「楽は黄鐘調(おうしきちょう)盤渉調(ばんしきちょう)いずれも大小楽(だいしょうがく=笛と大鼓と小鼓で囃す楽)にて勤める」と喜多流では伝承されています。
これを、研究公演のときには「研究」という意味合いもあり、盤渉の太鼓入りで試演してみました。当時39歳でした。いま思うとよくもまあ冒険が出来たものだ、と自分ながら驚きますが、それは友枝昭世師や父菊生をはじめ流内や三役を含めた皆様のご理解とご協力の賜物であったと、今も感謝の気持ちで一杯です。本当に恵まれた環境にいたのだと思います。
今回、『天鼓』を再演するにあたり、まず考えたことは、この「楽」のことです。
前回同様、太鼓入りの盤渉で勤めました。

(撮影・森英嗣)
『天鼓』は太鼓が主題の曲ですので、黄鐘調でも盤渉調でも太鼓入りの楽であるのが相応しいと思います。
わざわざ太鼓を入れないで囃す根拠が理解出来ません。
喜多流の後シテは出端(では=出囃子)で登場するため『天鼓』には太鼓奏者が必須です。
現在太鼓方の能役者は、1時間40分ほどかかる『天鼓』の、ほんの10分程度の出端のためだけに舞台を勤めます。その他の時間はただただ座っているだけの環境です。
これがなんとも勿体ない気がします。せめて盤渉の時ぐらいは太鼓が入るルールに代わると良いと思っていましたが、研究公演での反響はすこぶるよく、近頃は太鼓入り盤渉が珍しくなく頻繁に演じられるようになりました。一石を投じてよかったと、嬉しく思っています。

(撮影・前島写真)
そのような経緯で、楽は太鼓の入る盤渉で勤めましたが、今回は更に「楽」の型(動き)に太鼓への思い入れが入った舞にしたいと工夫しました。
通常「楽」は本舞台でしか舞いませんが、途中で橋掛りに行く替えの型を試演しました。舞の寸法は変えずに、橋掛りを漏水と見立て、キリの仕舞どころで謡われる「水に戯れ、波を穿ち、袖を返すや」を楽の中で表現出来たらよいのでは・・・、との思いです。
本舞台から三の松辺りまで、クツロギ(替の舞)に似た動きで、水に戯れる心持ちを左や右に小廻りで表現して、左袖を巻く型で愛用した鼓を遠くから眺めます。そして徐々に太鼓に近づく心持ちで一の松まで移動し、また小回りして太鼓に向かって歓喜の足拍子を踏む新工夫の型です。

(撮影・前島写真)
天鼓少年と鼓との繋がりを、楽という形式化された舞の中で表現したい、少年自身が楽しくてたまらない、そしてより舞台が華やかに見えるように演出したいと仕組んだつもりですが、いかがでしたでしょうか。
今回は「楽」のほかに、あと二つのことを心掛けて勤めました。
異国(唐土)の物語であることが判りやすい舞台にすることと、前場のシテの登場を呼び出し形式にすることです。
能『天鼓』は中国のお話ですので、当然能役者の扮装は中国風が相応しいはずです。
本来、異国(唐土)の物語であることを判りやすくするのは能役者の仕事であって、その作業はごく当たり前のことと思われるでしょうが、現場はそうはなっていないのが事実です。
現行の喜多流の装束附は、日本を題材にした曲目と同じ格好で演じられています。
前シテの老人の格好は、日本の神を題材にした脇能の『養老』と同じです。これでは観る側にいくら中国の話であると説明しても想像し難いでしょう。舞台全体が中国であると思える工夫があって然るべきだと思います。
そこで今回はシテだけでなくワキもアイにも中国人らしい装束を着けていただきました。
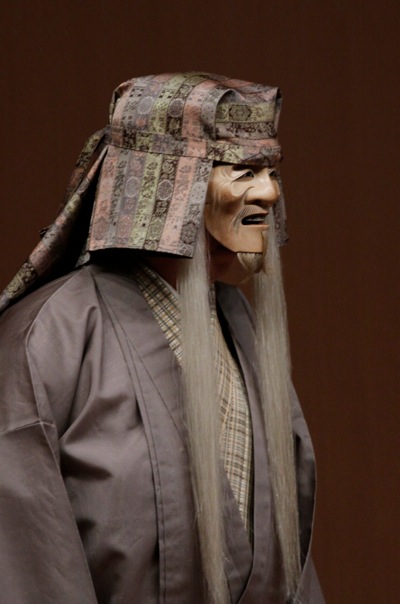
(撮影・石田裕)
前シテは「尉髪(じょうがみ)」に面「小牛尉(こうしじょう」を付けるのが普通です。
「尉髪」は髷の格好ですので、非常に日本人的なものを感じます。そこで髷を隠すために、「唐帽子(とうぼうし)」と呼ばれる頭巾を被りました。唐帽子はいかにも中国風な風情になります。しかも白い毛を両鬢に垂らすといっそう老人らしさが増します。
現在、喜多流では「唐帽子」をあまり使いませんが、先代宗家・喜多実先生は『張良』に使用されたことがありました。残念ながら我が家では「唐帽子」がないので、今回は観世銕之丞氏にお願いして拝借しました。
「唐帽子」は面の眉毛あたりまで頭巾で覆われるため、眉間に彫られた皺が隠れてしまい面の表情が変わって見えるのが難点です。このことは観世流の方々に事前にご注意を受けていたのですが、いざ「唐帽子」を付けてみると、本当に顔の表情に締まりが無くなり、やや笑い顔に見えてしまい後悔しました。
次回はもっと強い表情の、例えば石王尉など、または口髭がある面を使用してみては、と考えています。演能後、ご覧になった面打師のお客様数人にお聞きすると「別に問題はなく、充分成立していた」と、お声をかけていただきましたので、安心はしているのですが、私としては、次回は更なる工夫をと目論んでいます。
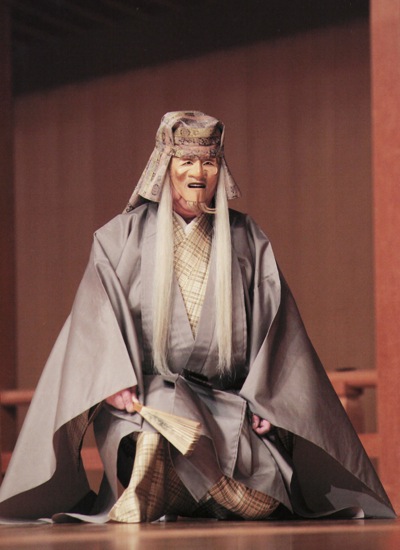
(撮影・吉越研)
話は少し脱線しますが、実は『天鼓』の物語は中国の歴史上にはありません。鼓が置かれた阿房殿、雲龍閣も史実として後漢の時代には存在していないようです。
中国では「雷」のことを天鼓とも呼び、晴天に雷鳴がして大石が落花し、その石を天鼓と名付けた、ともあります。
もっとも日本の仏教にも天鼓はあり、手で打たなくても自然と鳴り出す鼓のことを言うようで、須弥山の頂上、三十三天と呼ばれる帝釈天のいる善法堂にその鼓はあり、打たなくても自然に妙音を出す珍しい鼓とされています。また法華経には「天鼓は帝釈宮にあって阿修羅(悪神・悪の心)が攻め入る時、賊来ると警鐘を鳴らす」と書かれ、法華経巻六には「諸天が、天上界で音楽を奏でる時に使う」とも書かれています。
おそらく、能『天鼓』は日本の猿楽師が中国隕石物語と日本仏教の天鼓とを組み合わせて想像して作曲したものではないでしょうか。舞台を唐土にして日本人が創作した空想物語だと私は睨んでいますが、いつか専門家のお話を伺いたいと思っています。
話を戻します。もう一つの工夫は前シテの一声を省き「呼び出し」形式にしたことです。
普通、前シテの老人・王伯は「露の世に、猶老いの身のいつまでか、また此の秋に残るらん」の一声で登場し、「伝え聞く孔子は鯉魚に別れて・・・、白居易は子を先立てて・・・」のサシコエ、下げ歌・上げ歌が続き、愛児を失った身の悲しさを嘆く謡が綿々と謡われます。
この部分を割愛して、ワキの勅使の名乗りの後、すぐに「いかに此の家の内に王伯のわたり候か」と尋ねる形にしました。これは観世流の小書「弄鼓之舞(ろうこのまい)」の演出方法でもあります。この最初のシテの謡は、なかなか詞章も節もよく、愛児を失った老人の諦めや失墜の感情が彷彿とする聞かせどころですが、物語をより的確に現在物らしく演出するには逆効果です。
現代の能はよりコンパクトにより凝縮された形が求められています。時間を短縮してテーマを絞り込み、絞り込むほど能らしさが表現されるのです。冗長は現代には似合いません。

(撮影・石田裕)
削除、割愛、省略という言葉は楽をする、サボるという悪いイメージが湧くかもしれません。
しかし実はそうではなく、老父の悲しみを長々と語らなくても「そも何と申したる勅使にてござ候ぞ」のシテの応答の一句にすべてが見えてくれようであれば良いのです。
愛児を失った老父の悲しみと諦めを、一瞬にして観客に伝える。短い言葉を謡の力で観客に自由に想像させる、時間をかけるより能役者にとってはこちらの方が難易度は高いのです。
今回、敢えてその高いレベルに挑みました。見所の奥まで老父の感情が籠められた謡い声が聞こえる、しかしその声に精気は感じられない、まるで残りの人生を諦観しているかのように・・・弱者の声、そのように聞こえる謡が出来たら・・・と思いました。
楽屋話めいて恐縮ですが、このような事を行うのは能役者として当然、当たり前のことなのでしょうが、それを蔑ろにしてきた自分を恥ながらも、変えたい、と思ったことに間違いはありません。ただ謡本通りに謡っているだけでは到底出来ない演出に挑戦することで、自分の弱点、課題も見えて来ました。

(撮影・石田裕)
今回『天鼓』を勤めるにあたって、この曲がなにを言いたいのか? 何を観衆に伝えたいのだろうか? 稽古すればするほどわからなくなり考えされられました。
愛児を殺される能に『藤戸』と『天鼓』があります。
『藤戸』の母は、我が子を海に沈めた佐々木盛綱に対して殺意を持ち刺し違える覚悟がありますが、『天鼓』の父は違います。
我が子を殺されながら不思議と怨念が見えません。
老父にとって愛児の死はなんなのでしょうか?
諦めに近い喪失感で満ちています。
一度は拒む参内も、愛児の愛用した鼓をせめて見たい一心で、我が子のためにと勅使に従います。宮殿に入るとその広大な内裏に圧倒され驚き、また参内を拒みますが、我が子のためと思いなおします。
老父は鳴らないかもしれない、
もし鳴らなかったら殺されるだろう、
それでも我が子の愛した形見の鼓を手に取ることが出来れば・・・
と思う親心なのでしょう。
そして鼓を打つと、鼓は鳴り響き、それはあたかも我が子の声に聞こえ老父は安心します。皇帝だけではない、老父自身が驚き、ここで老父は愛児と再開出来たのです。
親子の情、文章では判っていても17年前は何も判っていなかった、と今白状します。
本当に身体で能が判るようになったのは、やはり父を亡くして時間が経ってからのことです。亡父が、よく「そのうちわかるよ」と言っていたことが思い出されます。

(撮影・石田裕)
一方、後シテの天鼓少年は、勅に従わぬ自分が悪く、当然の報いとして地獄に落ち苦しんでいますが、皇帝の弔いに今は浮かばれたと喜び感謝します。そして舞の所望に勅命と喜んで舞う少年の亡霊。
命を奪われながら、なぜここまで従順なのだろうか?
ここも稽古していて不思議でした。
なぜ老人も天鼓少年にも怨みがないのだろうか・・・・。
さてはこれは作曲した猿楽師の芸能者という立場からではないか、と推察します。
体制派を褒め称えるのは芸能者の宿命です。
彼らの応援なくして生活が成り立たないことを芸能者は充分承知の上で、そこで生きていくしかないのです。
恨み辛みの感情などは控えめに演出し、皇帝の情の深さを讃えるのです。
この能を観る権力者はご満悦でしょう。

(撮影・前島写真)
しかし、ただ一点だけ芸能者の意地が書き込まれているのが稽古して判りました。
それは、皇帝が少年から鼓を無理矢理奪い取り、権力をかさに横暴を奮うが、鼓はだれが打っても鳴らない、この鳴らない現象です。
唯一、鼓は帝に従わないのです。ここに芸能者の隠された心意気を感じます。
権力なんて無理強いしても所詮限度があるのだ、と言わんばかりです。低頭して服従して、でも心根は崩さない、そんなところの見え隠れを捜して能を勤めることが面白くてたまりません。
『天鼓』は前場も後場もテーマが盛りだくさんです。愛児を失った親の悲しみは、この曲の大事なところだと思いますし、さまざまな工夫も述べてきました。
しかし最後は、老人の忘れられない愛児の天鼓少年が天真爛漫に夜遊の舞を見せる、ここに重きをおくことこそが、老人の一番の喜びではないだろうか、そう思って勤めました。
(平成23年10月 記)
写真提供 粟谷能の会 『天鼓』 シテ 粟谷明生
(資料:天鼓あらすじ 粟谷明生作)
中国が後漢と言われた時代のこと。
王伯(おうはく)の妻・王母(おうぼ)は、天から降ってきた鼓が胎内に宿る夢を見て男の子を授かった。夢に因んで名前を天鼓と名付けると、天から本物の鼓が落ちてきて天鼓少年が打つと妙なる音が出て人々を感嘆させた。
噂を聞いた帝は、その音色を聞きたく少年・天鼓から鼓を召し上げようとしたが、少年は従わず鼓を持ち山中に隠れてしまった。しかし少年は捕らえられ鼓は奪われ、少年は漏水の江(黄河支流洛川・洛水)に沈められた。
鼓は内裏に置かれ打たれたが鳴らない。帝は少年の父親ならば鳴らすことが出来るだろうと、勅使を王伯の私宅に向かわせる。
このことをワキ(勅使)が名乗りで語り、ここから舞台展開がはじまる。
勅使に呼び出された天鼓少年の父王伯は老いた姿で我が子を亡くした失墜の体で現れ、鼓を鳴らすという勅命は口実で、実は罪人の父親も殺すのが目的であろうと答え、参内を固辞するが、どうせ死ぬならば、せめて我が子の形見の鼓を見て打ってからと決心し、勅使に連れられ宮殿に向かう。
壮大な宮殿の建物に驚く老父は、勅命により雲龍閣に上がり鼓を打つ。すると不思議に鼓は鳴り響き、その美しい音色を聞いて、帝は親子の恩愛に感銘し涙する。
老父は宝を与えられ帰宅を許される。
<中入り>
帝は天鼓を弔う為に漏水の江にて管弦講を催し法事を行う。
すると、弔いの音楽にひかれて少年天鼓が亡霊の姿で現れ、弔いに感謝し、鼓を打ち、舞楽を舞い夜明けと共に消えて行く。
『昭君』を勤めて 不条理な演出の見直しを投稿日:2011-06-26

『昭君』を勤めて
ー不条理な演出の見直しをー
粟谷明生

曲名になっている王昭君は、中国四大美人のひとりです。
漢の皇帝は胡国(匈奴 現・モンゴル)との和睦の条件として、胡国の韓耶将(かんやしょう)のもとへ宮女をひとり差し出すことを了承します。
その宮女の選出がふるっています。絵描きの画によって、三千人いる宮女の中から一番劣れる容色の者を、皇帝が選び出し決めることにしたのです。美貌に自信のない宮女達は絵描き師に賄賂を渡し、美しく描いてもらいましたが、美貌に自信があった王昭君は賄賂を渡さなかったので絵描き師はわざと醜女に描きました。そのため帝は醜女と思われる昭君を選んでしまいます。
さて胡国へ旅立つ日、昭君が帝に拝謁すると、その美しさに帝は驚き悔やみます。しかし君子に私の言葉なし(私心なし)と諦め、韓耶将の元へ送るのでした。後日、帝は似せ絵を描いた絵描き師をすべて処刑したと言われています。
能の『昭君』はしかし、その美人の昭君が主役ではありません。愛娘を遠い異国の僻地に嫁がせる境遇になった老父母の悲しみの心境を描いています。美人の昭君役を幼い子方に演じさせるやり方はいかにも能らしい演出です。
今回は金子天晟君(小学校3年生)が勤めてくれました。

物語は里人(ワキ=大日方寛)が昭君を弔うために、昭君の父母の私宅に出向く由を述べる名乗りからはじまります。続いて昭君の父・白桃(はくどう)(前シテ=粟谷明生)と母・王母(おうぼ)(ツレ=内田成信)の老人夫婦が一声で登場します。愛娘の昭君が胡国に嫁つぐ所以や、胡国への旅行の様子を涙ながらに語ります。

一声から初同前までのシテとツレの連吟は詞章が多く長い時間がかかります。ここはどうしてもだれ気味になり退屈してしまうところです。ここを情景が想像出来るような、説得力のある謡がいかに謡えるか、能役者の力量が試されるところです。今回は内容に沿って謡に緩急を付け、動きも少し加えましたが、ご覧頂いた皆様は如何に思われたでしょうか。
実は今回、謡と装束で、中国の老父らしさを彷彿とさせたい、と考えました。装束については後で述べますが、謡については中国人の会話を聞いていて一つの発見がありました。それは口調の強さです。気持ちが昂ぶり、相手を必死に説得させようとするときの発音の強さ。語気は日本人のものとは大いに違います。

今回、試しに強い口調の発音で、ゴツゴツとした固い感じで謡うように試みました。ヒントとなったのは『昭君』の三個所の秘伝、口伝の謡です。
前シテ「この柳も枯れ候…」の「枯れ」、そして「鏡に映して影を見ん」の「見ん」、後シテでは「韓耶将が幽霊なり」の「なり」です。いずれも強い気持ちを、調子の張りで表現します。「なり」は「鬼節(おにぶし)」と呼ばれ、最も甲高い鋭い声を張り上げて夷の大将の威勢をみせる特別な節です。
これらは謡本に特別な謡い方である記載はなく、私たちは先人からの口伝で伝承しています。私は前シテの二個所の強い気持ちを込めた謡が老父の性格を裏づけています。この老父に老いの柔和な感じは不似合いです。気の強い性格の老人を演じ切るように心掛けました。それが出来たかどうかは別として、この取り組み方に間違いはないと自信はあります。面も性格の強さに合った、特に強めの野卑な表情の三光尉を選びました。

老人夫婦はしきりと柳の木陰を清め、自らの心を慰めています。この柳は娘の昭君が胡国に送られるとき、自分が死んだらこの柳も枯れるでしょうと言って植えた形見の木。最近枯れはじめたので老父は悲しんでいます。
この柳は物語の重要な役割を担っています。しかし、現行の喜多流の『昭君』では柳の木はありません。シテもワキもあたかも柳が有るかのように会話しますが、実際に柳は舞台に存在しないので、能をご覧になる方は、本舞台正面先に柳の木があると想像しなければなりません。
能は想像の世界と言われていますが、度が過ぎます。他流では、このような不親切な現行の演出を見直して、柳の作物を置いたり、柳に鏡を付けるなどの新演出を工夫し、判り易くしています。
例えば、『羽衣』や『松風』は正面先に「松」の作物を出し、三保の松原や須磨の浦の一木の松(ひときのまつ)の情景をシンプルな一本の松で想像させます。効果は抜群です。『昭君』も当然「柳」があるべきですが、ありません。
何故このようになったのでしょうか。私は能役者側の行き過ぎた合理主義が原因だと推察します。猿楽の能が江戸幕府の式楽となり、観る側が大名など謡の詞章がすでに頭に入って内容を予め理解している場合、自ら松を思い描き楽しみたいのかもしれません。
その様な高尚な相手に、わざわざ柳を出す説明的な演出を能役者は故意に避けたのかもしれません。想像にお任せする、という極めて高度な演出を選んだのではないでしょうか。
それが近代まで続いて来たのが悲劇です。今は通用しません。
現代はより判り易い演出が求められていて「柳の木」は当然出るべき小道具だと思います。
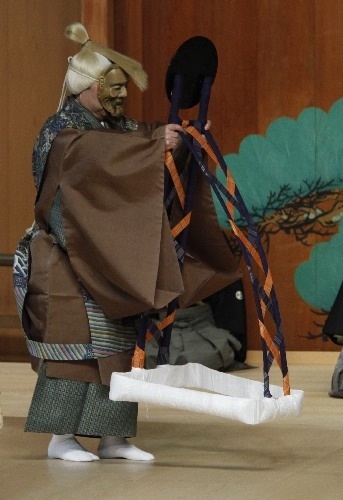
老人夫婦が柳の木陰を清め終えると、里人が昭君の弔いのためと訪ねて来ます。老父は弔いの来訪を感謝しますが、心の底では娘の死を認めてはいません。なかなか納得出来ないでいるのです。
東日本大震災で「妻は、父母は、我が子は、まだ見つかりません。しかし…死んだとは思いたくない。納得出来ない…」と嘆かれる被災された方々を思い出します。同じなのです。
ですから、恋しく想う人の姿が鏡に映るという故事を聞くと居ても立ってもいられなくなり、ついに老父は鏡を荒く持ち出し、柳の下に置き鏡に娘の姿を望み号泣するのです。ここの怒りにも似た激しい動きを、老人らしさを忘れずに演じるのが能役者にとって難しいところです。荒くなり過ぎると若さとなり、荒さを怖れると勢いがなくなる、このバランスを保っての演技こそ能らしいところなのです。
最近、能舞台で気になることがあります。
それは中国の話でも、その姿・格好が日本人役とまったく同じであることです。これも、江戸期の能役者の合理主義の影響で、一概に悪いと断定はしませんが、やはり中国は唐っぽく、日本人は日本らしい扮装で想像しやすい環境を創るべきです。

今回、前シテとツレは水衣の上に側次(そばつぎ)を着て、少しでも舞台が中国っぽくなればと試みました。後シテの出立ちは、従来、法被(はっぴ)半切袴(はんぎりはかま)ですが、我が家の伝書に「法被を二つ重ね着し、上の法被を襷に取るも有り」と面白い記載があり、粟谷能夫は以前この扮装で勤めています。
私は、古代武官の礼服で、鎧のイメージも湧く裲襠(りょうとう:打掛け)を着ることで、より胡国の蛮族の大将らしさを出したいと思いました。(裲襠は山中家から拝借しました。)また、「もとゆい更にたまらねば、眞葛(さねかずら)にて結び下げ」の詞章から、伝書の「赤頭を鬘帯にて飾り出るも有り」も試み、赤頭に鬘帯を元結のように結び装飾しました。これは赤頭の後ろ側のため、目立つほどではありませんでしたが、常とは違う異なる雰囲気に気付かれた方は、異国人らしさがお判りになったのではないでしょうか。

これらの工夫は、似合うと賛同のご意見もあれば、首をかしげる方もいらっしゃるかもしれません。ご感想は様々であって良いと思います。
しかし、私は周りや楽屋内の苦笑を怖れて何も挑まないで勤めるよりも、作品を生かすためにいろいろな試みをする能役者を目指します。

今回、頭の毛の色についても、赤頭にするか、黒頭にするかで悩みました。
『昭君』にはどちらが良いのか、どれが似合うのか。
後シテの韓耶将は死霊です。鬼のように見えますが鬼ではありません。
赤頭は畜類系の鬼のイメージが強くなりがちなので、より人間っぽい黒頭がよい、とはじめは思いました。実際、観世流では黒頭が主流のように変わって来ました。しかし、故観世銕之亟(静夫)先生の「赤頭は紅毛人(こうもうじん)のイメージ」、このお言葉が私の赤頭の選択を後押ししました。赤頭について、鬼という一辺倒の発想ではなく、紅毛人、異民族の象徴のようなイメージまでもっていく大きな発想に感服です。もう即座に赤頭と決めました。
また頭の上に載せる冠も同じです。「唐冠(とうかんむり)」は漢民族の象徴のような冠です。胡国の遊牧民族の大将・韓耶将に唐冠は似合わないと否定していました。
しかし「敢えて唐冠を付けることで漢と胡国の和睦を意味するのでは?」と説明を受けると、これもまた納得してしまう私です。従来通り唐冠を着用する根拠が発見出来ました。

面は喜多流の本面といわれる「小ベシミ(こべしみ)」を付けました。面の裏に能静の目利きが記されている歴史ある古面で、前から一度付けたいと思っていた名品です。ただ残念なことに、過去に真っ二つに割れた形跡があり、大胆な修復の跡がある危険な状態の面です。
しかし慎重に気を配り使用して、何事も無く、この面を経験出来たことは、私にとってたいへん貴重な経験で喜びでした。
『昭君』の中入りは早装束(はやしょうぞく)です。前場と後場の間に間狂言がないので(注・大蔵流山本家にはシテの所望によりアイが出る場合もある)、前シテは中入りしたら、ワキの退場、子方の登場という短い時間に着替えなければなりません。予め装束に仕掛けを施し、付ける者も着せられ者にも手際のよさ、要領のよさが求められます。
今回は、着附をして下さった狩野了一氏、佐々木多門氏、そして後見の内田安信氏の手際よいご協力のお陰と感謝しています。あっという間に短時間で着替えられたのは、念入りな事前の仕掛けのお陰ですが、そのために演者は出番の前に一度装束を着なければならず、体力的に消耗し疲労するのは目に見えています。
しかしそこは我慢で、より綺麗な着附で出たいという気持ちが優先されます。仕込み作業のたいへんさを痛感しながらも、効果を優先したいのです。

この能は、本来は前シテがそのまま舞台に居残り、韓耶将役は別人が勤めるのが自然です。現行の演出では、柳の木を鏡に映せば昭君が鏡に現れると聞くと老父は鏡を持ち出し映らぬ鏡に向かって泣き伏し、そのまま中入りして早替りし、後シテの韓耶将役を演じます。これはシテ一人に演出を集約する江戸期の手法の名残でしょうが理屈に合いません。また、一曲の最後は、昭君の美しさを讃える部分ですから、当然子方の昭君に脚光があたり昭君が舞うのが筋で当たり前ですが、現行は韓耶将が昭君の代わりに舞うというちぐはぐな演出になっています。

観世流の方々の中には、この従来のまずい演出を見直し、理にかなった本来あるべき姿に戻す作業をなさっている方があります。古典を現代に合った演出にして、また本来あるべき形が良ければそこに戻すことは、現代能役者の仕事であり使命だと思います。
喜多流も積極的な対応をすべき時期が来ていると思うのですが、しかし反面、喜多流自主公演だからこそ、不備でも現行のスタイルが見られることを期待する観客もおられる、それも現実です。
今回は不条理でも従来通りの型付けで勤めましたが、柳の作物を出し、韓耶将は別人が勤め、終曲の昭君の舞は子方が舞うという、ごくあたりまえの新演出の発掘作業が早く起こればよいと願っています。
(平成23年6月26日 喜多流自主公演にて)
写真提供 撮影 石田裕
1,後シテ 粟谷明生
2,子方 金子天晟 小鼓 曽和正博
3,橋掛にて 左 シテ 粟谷明生 右 ツレ 内田成信
4,前シテ 粟谷明生
5,前シテ 掃く型 粟谷明生
6,鏡を持ち出す型 粟谷明生
7,ツレと
8,赤頭に鬘帯 楽屋にて 撮影 粟谷明生
9,後シテ 橋掛にて
10.後シテ 鏡台の前にて
11,後シテ 飛び安座
12,後シテ
『翁』付『養老』を勤めて ー前シテの面「小牛尉」へのこだわりー投稿日:2011-04-16

『翁』付『養老』を勤めて
ー前シテの面「小牛尉」へのこだわりー
粟谷 明生

平成23年(4月16日)厳島神社桃花祭・神能で『翁』を勤めました。
神能は正式な『翁』からはじまる5番立番組で、『翁』のシテは脇能も勤めます。
脇能は『高砂』『弓八幡』『養老』の三曲を毎年順番に奉納する決まりになっています。

(写真2)
前年(平成22年)の脇能は『弓八幡』でしたので、今年は『養老』でした。
私の『翁』付『養老』は平成11年以来、実に12年ぶり。12年前の事を思い出しながらも、また東北の被災された方々へ神のお恵みがありますようにと、「天下泰平、国土安穏」と気持ちを込めてご祈祷の謡を謡い、勤めました。

(写真3)
喜多流の脇能の神舞物は五曲あり『高砂』『弓八幡』は本格、『養老』『志賀』は少し格下、『絵馬』は別格と区別するように謡本に書かれています。参考曲に『御裳濯』がありますが、現在絶えています。

(写真4)
笛方は神舞の位を、真(しん)と草(そう)に分け、本格は真の舞、格下は草の舞と扱っていますが、シテ方の動き(型)は変わりません。違いは、初段オロシの譜が男舞の譜に変わるだけです。もっとも最近では、シテ方の注文がなければ、草の場合でも真の扱いで吹いていると、森田流の杉市和氏は仰しゃいます。
『養老』は世阿弥作の脇能ですが、前場にクセがない簡略形式となっていることや、大口袴をはかずに着流し、面は三光尉というような装束附けや面の選択の影響でしょうか、『高砂』や『弓八幡』の本格2曲より格下扱いされています。
しかし私見ですが、『養老』の後シテは壮大な荒々しい山神の役ですので、本格と差別せずに、同等に扱って然るべきだと思います。
(写真5)
前シテは、身分の卑しい田夫野人であるため、老翁は位低い着流し姿となることに異論はありませんが、問題は、面がやや野卑な人相の「三光尉」と定められている伝承です。
神の化現でないため「小牛尉」を使用しない、と喜多流謡本に明記されていますが、これはどうでしょうか。私は同意出来ません。今の演出では、老翁は神の化現であると考えた方が自然だからです。前シテとシテツレ親子は来序で中入しますが、これは老翁たちが実は山の神であるが如くに観客に想像させますし、演者もそのような気持ちで演じています。

(写真6)
古くは、前シテとシテツレの親子はそのまま舞台に居残り、別の能役者が後シテの山の神だけを演じていたのではないか、という説もあります。例えば、現在喜多流の『昭君』ですが、古式では前シテと後シテを分ける演出があり、最近観世流の中にはその古い形式を再興しているところもあります。
それはともかく、現行の演出では、シテとシテツレが来序で中入りするので、老翁を神の化現として演じたくなるのは普通で、それならば面は「小牛尉」の方が適当となります。装束も従来の無地熨斗目よりは、格上げした小格子模様の熨斗目の方が似合います。
そこで今回は、『養老』も『高砂』や『弓八幡』と同じように品のある前シテにしたく、前回同様「小牛尉」を使用し、着附は小格子模様の熨斗目を着流しで勤めました。

(写真7)
伝書には、過去の経緯や心得が書かれていて貴重です。しかしそれを鵜呑みにするのはどうでしょうか、いささか危険であるようにも思えます。
今に生きる能、というものを常に意識して演じる能役者を目指したいと思います。
権威主義的、保守的な考えの方には、目障りだと思われるかもしれませんが、今に似合う、自分に似合う能を、それを受け入れてもらえるような環境作りをして創り上げていきたい。現在に似合う、今を生きる能役者でありたい。また後進たちにも、そうなってほしいと願いも込めて舞った、今年の『翁』付『養老』でした。
写真提供 粟谷明生 撮影 石田 裕
写真巻頭 『養老』前シテ 小牛尉をつけて
写真2 『翁』 翁の舞 地の拍子
写真3 『養老』後シテ 神舞の上羽の型
写真4 『養老』後シテ 神舞二段オロシの型
写真5 『養老』前場 左から ツレ佐藤 陽 太鼓 梶谷英樹 シテ 粟谷明生
小鼓 横山幸彦 笛 中村俊士 脇 高安勝久
写真6 『養老』前シテ 「影さえ見ゆる山の井の」の型
写真7 『養老』後シテ 仕舞所の型
(平成23年4月16日 厳島神社・御神能にて。 同年4月 記)
無断転写禁止
『一角仙人』について 将来を担う能楽師たちとの共演投稿日:2011-03-06

一角仙人について
― 将来を担う能楽師たちとの共演 ―
粟谷 明生

能『一角仙人』はインドの「マハーバーラタ・リシャシュリンガ(鹿角物語)」が原典で、中国や朝鮮を経由し日本に渡来したものですが、歌舞伎では『鳴神』となりました。
天竺婆羅奈(テンジクバラナ)国(インド中部・ガンジス川流域)の帝王の臣下(ワキ)が「この国に、鹿の胎内から生まれ、額に角が一本生えている一角仙人(シテ)がいる」と名乗るところから始まります。サラリと語られる異常な状況、若い時分はあまり何も考えずにいましたが、演能にあたり、また馬齢を重ねてくると「鹿の胎内に宿り出生したる故に…」は、なんとも猥雑な世界を連想してしまいます。
原典では「天竺波羅那国の仙人が、鹿の夫婦が交尾するのを見て、つい興奮して、うっかり草の上に精液を洩らしてしまい、その草を食べたメス鹿が、鹿と人の混血児を孕んでしまった」とあり、なんとなくご愛敬でほほえましくもありますが、私はどうしてもいやらしい人獣性交を想像してしまいます。つまりこの一角仙人は特別な修行を積んだ神聖な仙人ではないので、そこをどのように演じるかが鍵になると思いました。
額に角がある仙人(シテ)をどのように見せるか?
昔、喜多流ではシテの黒頭に角を取り付けていました。そのため父や伯父の写真を見ても面には角がありません。近年、粟谷家では数面ある真角(しんかく)のうち一面を、額に穴を空けて角を付け加え、『一角仙人』専用にしました。父も能夫氏も使用してきましたが、この角は長さが10センチ程度のため、黒頭の場合、角が隠れてよく見えないのが弱点でした。仙人の象徴が目立たないのでは効果がないので、角を強調したスタイルができないかと考えていました。
それで、今回初めてバス鬘を試みました。はじめは、やや不安でしたが、楽屋で装束と鬘、そして面を付けてみると、角の長さがほどよく見えて、奇怪な仙人の雰囲気が発揮されたのではと思っています。ご来場の皆様はどのように思われたか、お聞きしたいと思います。
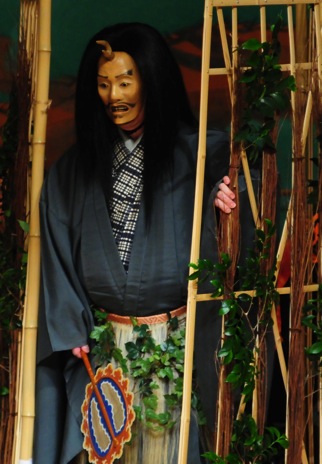
『一角仙人』は作物も登場人物も多く人手がいる曲目です。一畳台と岩に子方二人を隠して脇座に置きます。シテは萩屋の中に入り引廻を掛けて大小前に置かれます。この作業だけでも6名の働と2名の幕上げが必要です。ツレの旋陀夫人は臣下(ワキ)を引き連れ、輿舁(ワキツレ)2名を従えて登場しますが、この段階で舞台上には役者だけでも7名がいることになります。ほかに地謡、囃子方、後見と、なんとも大勢の人々が舞台の進行に携わっています。
今回、シテははじめての経験でしたが、今述べた、頭毛の他に、もうひとつ持ち物を工夫しました。通常はシテが唐団扇でツレは中啓を使用します。しかしシテが綺麗で優雅な唐団扇を持つのは似合わないと思いました。奇怪な仙人らしい厳ついデザインの物‥‥なにかそのようなものを持ちたいと思い、いつものように他流の方々に教えを乞いました。銕仙会の方から魔王団扇(まおううちわ)の存在を教えていただき、是非とも使用したいと、いつも御世話になっている観世銕之丞氏にお願いして拝借しました。
「それならばツレも唐団扇にした方がよい」と能夫氏のアドバイスもあり、ツレも中啓に替えて唐団扇を使うことにしました。
今回のツレに、私の教えている佐藤陽を、まだまだ未熟ですが、玄人は早く舞台に慣れ、本物に少しでも早く近づかなくてはいけないと思い、大抜擢いたしました。幸い粗相もなく真摯に勤めてくれたのがよかったと思っています。
この物語では、一角仙人が神通力で龍神を封じ込めたため、数年雨が降らないことから、これを何とかしようとして、帝が絶世の美女・旋陀夫人をつかわせ、その魅力で仙人の通力を失わせようという作戦を立てます。
『一角仙人』のメインは、夫人の魅力的な舞姿に仙人もいつしか誘い出され共に舞う、シテとツレの相舞です。仙人は誘い出され踊り出し、そのうち夫人に触りたくなる、触ろうとすると拒否される、そのような型どころもありますが、そこを坦々と演じるか、コミカルに演じるか、また艶っぽさを出して演じるか、演者の性格が出るところです。
私は一角仙人を勤めるにあたって、仙人が必死に誘惑に抵抗しているところが隠れないようにと、勤めました。
来るな! というのに来てしまう訪問者たちに、ではちょっと姿だけ、と現れ、酒は呑まない! と断るのに、お酌を受けないのも情けがないかな、と飲んでしまう。
見たこともない美しい女の舞に目を奪われ、しかしその自分に気が付き必死に平静を装い、己を取り戻そうとする、仙人の抵抗や揺れを見ていただきたいと思いました。
父は旋陀夫人が舞い出すとじっと追い続けて見ていましたが、私は、いやいやこんなことをしていてはと誘惑に負けまいとする一面も見せたいと思い、見続ける型をせずにいました。しかしそんな柔な決意を崩すのは、足拍子です。この相舞で、いつの間にか旋陀夫人のペースに乗せられてしまう仕掛けは足拍子にあると思います。
トントンと踏まれる音と、女の身体の動きに、完全に魅了され、仙人はもう自分自身を止められなくなり、夫人のお尻を追いかけて真似を始めます。
まずは、足拍子から、次第に見よう見まねで手も動かします。もう止まりません。ついつい夫人に触れようとします。なんとなく日常の人間界にもありそうなことを、この相舞から感じられるのは、私だけでしょうか?

父のツレをしたときに、シテが足拍子を踏んだら、「あらあら引っかかったわね。さあ付いていらっしゃい」という誘う気持ちで舞え、と教えられました。
今回、佐藤陽君にその事を伝えました。それが出来たかどうかは別として、ひとつの伝承が出来たことは事実です。
さて、この相舞の間中、子方は岩の中でじっと待っていなくてはいけません。
幼い龍神達(金子天晟君・友枝大風君)には辛抱の曲です。普通は、出番前ギリギリまで赤頭を付けずに岩の中にいますが、今回は、それぞれの父親の教育なのでしょうか、最初から赤頭をつけていましたので、辛抱と我慢の繰り返しが小さな龍神達を苦しめていたと思います。
そのようなストレスがあるからでしょうか。岩が割れ、鬱憤を発散するかの如く、二人のかわいい龍神達は、必死に教わった通りに動き回ってくれました。その健気な可愛い奮闘ぶりに、相手役の明生仙人も完全に負けてしまい、逃げだしました。

今回、ツレ佐藤陽、地謡の前列の一員として息子・粟谷尚生と、教え子たちと同じ舞台に立てたこと、そして彼らに舞台を勤めるうえでの指導が出来たことを喜んでいます。それでも、最後は子方達にお手柄を全部持っていかれた、明生仙人ですが・・・。
私ははじめ、この曲はシテの執心があるわけでもなく、遣り甲斐の少ない曲だな~と思っていましたが、勤め終えると、将来の能楽師たちと舞台を共に出来た喜びに満足し、それでいいと思う一方、そういうことを感じる年齢になってしまったか~と、やや複雑な心境になっています。
(平成23年3月6日 粟谷能の会にて 同年3月 記)
写真 1
一角仙人 シテ 粟谷明生 撮影 森英嗣
写真 2,3,4
一角仙人 シテ 粟谷明生 ツレ 佐藤 陽 子方 金子天晟 友枝大風 撮影 前島写真店
『鞍馬天狗』白頭を勤めて ー豪快天狗に秘める同性愛ー投稿日:2011-02-20

『鞍馬天狗』白頭を勤めて
―豪快天狗に秘める同性愛―
粟谷 明生
能の『鞍馬天狗』といえば、花見のお稚児さんを真っ先に想像します。
ときは春爛漫。鞍馬山には東谷と西谷に坊舎があり、東谷の僧が預かっている稚児たちを花見の宴へ連れだします。舞台では、橋掛りに沙那王(子方)を先頭に平家の稚児たち(「花見」と呼ばれている)が登場します。この「花見」は、幼い能楽師の初舞台となることが多く、幼い子どもたちの登場は舞台を一瞬に華やかにしてくれます。今回は子方に内田貴成君(11歳)、花見には金子天晟君(8歳)、友枝大風君(7歳)、野村真之介君(6歳、野村万蔵次男)、宝生尚哉君(6歳・初舞台、宝生欣哉次男)、そして粟谷僚太君(5歳)と喜多流と三役のお子様が舞台に満開の桜を咲かせてくれました。
義経は悲劇の英雄として国民的な人気があります。能でも義経(幼名:牛若丸=沙那王)が登場する曲は数々あり、牛若丸時代のものに、鞍馬山の天狗に兵法を教わる『鞍馬天狗』、京の五条橋で弁慶を家来にする『橋弁慶』、盗賊の熊坂長範を討つ『烏帽子折』があり、いずれも子方が勤めます。義経時代の曲は『八島』『船弁慶』『安宅』『正尊』『摂待』など、いずれも人気曲です。能の義経はなぜか子方が勤めることが多く、大人が義経を演じるのは『八島』と『摂待』の二曲だけです。
今回、式能で勤めた『鞍馬天狗』は義経のもっとも幼少のときの話で、平治の乱で敗れた父・義朝の死後、鞍馬山に預けられ、平家の子どもたちと生きる境遇になった源氏の御曹司・沙那王の憂鬱、そこに現れた大天狗との交流をみずみずしく描いています。
さあ、話を舞台に戻しましょう。
花見の宴席で、西谷の能力が稚児たちに舞を見せているところに、山伏(前シテ)が割り込んでどっかりと座り、華やいだ雰囲気はたちまち一変し、不穏な趣きとなります。しかし、東谷の僧侶は、諍いを避け、平家の稚児を連れて東谷に戻ってしまいます。こういう設定ですから、「花見」が舞台にいるのは10分程度で、あっという間に退場してしまいます。まさに桜の花がぱっと散るようで、観客の心に残るのでしょう。
さて残った山伏と源氏の御曹司・沙那王。この場面転換がみごとです。大勢の花見の場面から、焦点を二人に絞り、ここからが『鞍馬天狗』の本題となります。お互いに寂しい独り身を哀れみ合い、山伏は沙那王に鞍馬山の奥の山道を案内し、愛宕山、比良や横川、吉野初瀬の桜まで見せます。遂に自分はこの鞍馬山に住む大天狗であると明かし、沙那王に源氏の頭領となって奢る平家を倒すときが来たら加勢すると約束して消えてしまいます。後場では大天狗(後シテ)となって登場し、兵法の奥義や武術を伝えます。
今回『鞍馬天狗』を勤めるに当たり、牛若丸に兵法を伝授した鞍馬山の天狗の正体は何かが気になりました。
天狗は一般的には、山伏や僧侶などの姿をして、鼻高く羽団扇を持ち、山中を自由に飛行して、通力を有する架空の超人・怪人と思われています。私は一時、過酷な修行をした山岳信仰の修験者達が天狗と錯覚されてきたのではないかと思っていましたが、天狗は、“人はみな死後、六道と呼ばれる六つの世界のどこかに生まれ変わる”という仏教の輪廻思想を否定し、自らの意志で天狗道という魔界に創り住むということですから、天狗は死後の存在となるので、私の説は成立しないようです。ゆえに天狗は架空の存在として、とりわけ能ではそのように鑑賞されたらよいかと思います。
しかしこの天狗にも、コレステロール同様、悪玉と善玉があります。
悪玉天狗は仏教に敵対する『是界』の是界坊や『大会』『車僧』などの愛宕山太郎坊で、いずれも威勢を張って高慢さを見せますが、最後は仏力に負け退散するユーモラスな天狗です。
それに対し『鞍馬天狗』の僧正坊は仏教と融和しながらも、牛若丸に武術・兵法を教え、源氏再興に力を貸すと約束する善玉天狗です。もっとも平家方からすれば、善玉ではないのかもしれませ
んが…。ではなぜ、能『鞍馬天狗』は善玉天狗なのでしょうか。ヒントは鞍馬山魔王大僧正影向図にありました。大僧正坊は鞍馬寺の本尊、多聞天の夜の姿であり、しかも天狗たちの総帥として描かれています。つまり鞍馬寺の天台信仰は天狗道とうまく融和合体された珍しいケースのようです。

以前は『鞍馬天狗』という曲は、時の権力への反抗、反政府精神、鞍馬寺天台信仰が基盤であると解釈していました。確かに大天狗の豪快さ、威風堂々とした強さが必要で、奢る平家など、権力に対する反骨精神はあります。
しかし、父からも、友枝昭世師からも、『鞍馬天狗』のシテは強さの中に柔らかみが必要で、子方とのやりとりに強さだけではないものが必要と注意されて来ました。はじめは理解出来ませんでしたが、今回、地謡の詞章を読み返しようやくその意味が判るようになりました。
『鞍馬天狗』は大人と子どもの同性愛が底流にあるのです。
その根拠は地謡の「御物笑ひの種蒔くや言の葉しげき恋草の、老いをな隔てそ垣穂の梅、さてこそ花の情けなれ、花に三春の約あり。人に一夜を馴れ初めて、後いかならんうちつけに心空に楢柴の、馴れはまさらで恋の増さらん悔しさよ」です。
「あなたへの恋心は世の物笑いですが、老いた私を嫌わないでね、美しい梅のようなあなた。それこそが花の情けなのですよ。花は毎年春がめぐってくれば同じように咲くけれど、人は一夜を共に過ごしたとしてもその後どうなってしまうかはわからない。ふとしたことがきっかけで心惹かれて、すっかりあなたにぽーっとなってしまって、あなたとの仲は一向に進展しないのに、恋しい気持ちは増すばかり、あ??それがつらい。こんなことならあなたと親しくならなければよかったのに」。
牛若を可憐な梅の花に見立て、「花は春がくるたびに咲くものだけれど、あなたの気持ちはそうとは限らない。こんなに苦しい思いをするなら」と、まあなんとも女々しい恋する乙女モード全開の山伏の気持ちが謡われていて、すっかり沙那王に惚れ込んでいます。
私が思っていた、天狗は源氏再興を目論む源氏方の残党、鞍馬寺の天台信仰を普及させるための宗教PRソング、そのような主旨のものではないようです。
少年に惚れ込んでしまったオジサンの弱みで、代償に兵法の奥義を教え、支援することになるのです。
当時、僧侶の童子への男色の話はさまざまに伝えられ、ありえない話ではありません。
現代のノーマルな男女間の愛の考えでは、到底理解出来ないことかもしれませんが、時を昔に持っていけば想像は可能です。演者は、そこを意識して、強さの中にも柔らかみが必要になります。しかし露骨に見せないのが能のよいところで、そこはかとなく演じる力量が問われます。
それが出来たかは別として、そのように思いました。
今回は白頭の小書付きでした。後シテは頭が白い毛となり、鹿背杖をついてどっしりと現れ、位も上がります。喜多流で白い毛の頭を使用する曲は、『鞍馬天狗』のほかに、『是界』『小鍛冶』『殺生石』『氷室』『鵺』などがありますが、普通は白頭になると面が替わります。
『小鍛冶』は「小飛出」から「泥飛出」になり、『殺生石』は「野干」に、『氷室』は「悪尉ベシミ」になります。
ところが、天狗物の『鞍馬天狗』と『是界』は面が替わらず、頭が白い毛になっても、赤頭の時の「大ベシミ」を使用するように伝書に書かれています。「大ベシミ」は大きな彫りの深い目も鼻も口も大きく、口をぎゅっと結んで睨みを利かせた形相の面です。
私はどうも、今回の『鞍馬天狗』「白頭」にはこの「大ベシミ」がアンバランスのようで気になりました。理屈っぽいことは言わず、力感を持って舞えばよい、という先輩の声も判りますが、白い毛に似合う面をと思い「悪尉ベシミ」をかけることにしました。

我が家には、二通りの「悪尉ベシミ」があります。
一つは通称「猫ベシミ」といわれるやや戯けた形相のもの、もう一つは、いかにも頑固で強靱な老人の迫力を感じさせるものです。
今回は、後者の年を経たお爺さん山伏天狗で勤めました。
能の天狗の扮装は、二通りあります。
まず直面(ひためん)の場合は『安宅』の弁慶同様の山伏姿となり、頭に兜巾を載せ、水衣に鈴掛をかけ、腰に小太刀を差して、右手に中啓、左手には数珠を持ち登場します。
面をつける場合は、頭に大兜巾を載せ、狩衣を着て、右手に羽団扇を持ち飛行していることを表します。狩衣の上に鈴掛を附けたり、鈴掛の代わりとして縷水衣を重ね着する「大鈴掛」という特殊な替えもあります。また掛絡を被る僧侶姿もありますが、今回は山伏姿を強調する「大鈴掛」で勤めました。
最後に薙刀の扱いにもふれておきます。
能でシテが薙刀を扱う曲は、喜多流では『巴』『船弁慶』『熊坂』の三曲です。子方が扱うものは『正尊』の静御前と『鞍馬天狗』の沙那王ですが、『鞍馬天狗』は子方の小さな薙刀をシテが受け取って使用する珍しい曲です。
薙刀扱いは、『巴』の巴御前は柔らかく女性らしく、『熊坂』の熊坂長範は荒々しく豪快に、『船弁慶』の平知盛はその両方を取り入れるとよい、と父から教えられて来ました。
「『鞍馬天狗』の大天狗はね。牛若に剣術を指南する気持ちで、このように扱うんだよ! とやさしく教えるようにするんだ。子方用の小さな薙刀をうまく扱うところがミソ」と教えてくれました。実際演じると狩衣の大きな袖が邪魔で思うようにスムーズに扱えず苦労しましたが、どうにか菊生天狗に教えてもらったような明生天狗になったでしょうか…。今も私の頭に残る父の言葉です。
『鞍馬天狗』は初舞台を踏む「花見」から、子方の牛若丸(沙那王)、年を経てシテの大天狗まで、長い能楽師人生の節目にふれる曲です。今回この曲を勤めた喜び、流儀内だけではなく、将来の能楽を担う子どもたちと一緒に舞台に立てたことが、頼もしく嬉しくもありました。
花見や子方を自分が勤め、その子が勤め、やがて孫が勤めと、まさに能は継承されていると実感させられ、演能後、もう気分は晴れやかで、二・三日大満足の明生天狗でありました。
(平成23年2月20日式能を勤めて 平成23年2月 記)
今回の『鞍馬天狗』シテ・粟谷明生の舞台写真の権利は、能楽協会が所有しているため、ホームページへの写真の投稿は控えさせて頂きました。ご理解ご了承下さい。
写真
鞍馬寺山門 撮影 粟谷明生
面「悪尉ベシミ」粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
『鉢木』を勤めて 能の謡に芝居心を投稿日:2010-12-19

『鉢木』を勤めて
能の謡に芝居心を
粟谷明生

『鉢木』のシテ佐野源左衛門の年齢はどのくらいなのでしょう。「歳のほど四十ばかりなる男の…」と、後場のワキ北条時頼(前は旅僧)が家来に常世を捜し連れて来るよう命じることから、常世は当時40代ぐらいの武士だったと考えられます。但し人生五十年の時代の話ですので、今の年齢感覚では、40代は概ね70代位に相当するのではないでしょうか。
今回、喜多流自主公演(平成22年12月19日)で『鉢木』を勤めました。
私が今55歳ですから、深い情味を感じさせる常世を演じるには、少し早すぎた感もあります。たぶんご覧なられた方々の想像された常世は、もっと老いた、枯れた能役者常世であってほしいと思われたことでしょう。
私の常世像は、零落しても誇りを捨てない男気ある田舎武者です。真面目で忠誠心が強く、ただ少し頑固で気の利かない野暮なところもあるように思えます。
演じ手としては、そのあたりの雰囲気が演じられればいいのでしょう。
昔、拝見した先人たちの数々の『鉢木』の名舞台。肉体的には衰えがあっても、何とも言えない気骨溢れる田舎武士を目の当たりにしたように覚えています。
『鉢木』は通常の歌舞の能と違い、芝居的な要素が色濃い能です。前シテは『望月』と同様に台詞が多く、会話や独白を謡い分ける技法を持たないと、この芝居がかった能を楽しんでいただくことは出来ないと思います。演者が芝居心を持って勤めないといけないのです。しかし、紛らわしい多量の台詞を感情を込めて、背景が想像出来るように謡うのは難しいことです。芝居っぽくなり過ぎて能のテリトリーを越えてしまっても、また能という形式に甘んじて、ただ声を発している程度では能『鉢木』になりません。「下手未熟は慎め」との伝書の言葉が重く響いています。
では舞台進行に合わせて進めます。
常世の妻(シテツレ)が地謡前に下居すると、信濃から鎌倉に上る旅僧(前ワキ、実は最明寺北条時頼)が次第で登場します。信濃から軽井沢を経て佐野に到着する道行の謡が聞かせどころです。大雪のため一夜の宿を頼みますが、妻は主の帰宅まで返答出来ないと主を待ちます。

シテはなにもなく一の松前にて立ち、空を見上げて「あ?降ったる雪かな」と謡い出します。父は「フッ??タル」の「ッ」から「タ」の延ばし方で、雪の積もり具合を想像させるのだ、と言っていました。
続く「さぞ世にある人の酒飲うで面白からん」は観世流にはありませんが、武張った喜多流らしい詞章で、呑兵衛の私はこの句が好きです。
「今日の寒さをいかにせん」と両袖を合わせて、寒さに震える型をして舞台に入りますが、「寒さ」や「雪」の言葉から常世のひもじさを伝えたいところです。

家に戻ると妻が家の外で待っています。旅僧の依頼を伝えると、ワキが登場して問答となりますが、常世は終始ぶっきらぼうに対応し、家の中は見苦しく、夫婦二人で暮らすのも苦労しているからと、依頼を断ります。
ここの謡い方は、ワキのじっくりに対して、坦々とややサラリと謡うのがいいようです。断られた旅僧はまた雪の道を歩いて行きますが、それを見た常世の妻は、無碍に断る薄情を嘆き、宿を貸すことを薦めます。
このツレの謡が大事で、力量が試されるところです。雪の日に外で立って待っている貞淑さを、凜として綺麗な立ち姿で見せるのも、このツレの役目です。
今回、狩野了一氏が期待通りに好演して下さって感謝しています。
妻の説得に、常世は雪の中、旅僧を呼び止めに出かけます。
「のう、のう旅人お宿参らしょう、のう」との呼掛は『山姥』にも似ています。距離感を感じさせる謡い方は、最初に「ん」の字をつけて「ん?のう、ん?のう」と発音します。「あまりの大雪にて呼ばわる声も聞こえぬげに候」と間を置いて、気持ちを内へとり、独白のように謡います。決して単調な謡では表現出来ないところです。
旅僧に追いついて宿を貸し、粟飯を振る舞うと、いよいよ寒さのため秘蔵の鉢木で焚き火をする、「薪の段」となります。
梅、桜と枝を切り取る型は伝書には「刀にて」とあります。この刀は太刀ではなく、小柄(こづか)といわれる太刀の鞘の鯉口の部分に差し添えた小刀の柄のことです。当初は伝書通りにと思いましたが、生憎小柄付きの小太刀が無く、実際舞台では、小柄が小さく、何を手にしているのかがよく判らないという欠点もあり、扇での替えの型でやりました。

さて、暖をとった旅僧は常世に「主のご苗字は?」と聞きますが、はじめは名を明かそうとしません。しかしついに佐野源左衛門常世と明かします。
苗字の佐野姓は栃木県の佐野と考えられますが、常世の家は高崎市の佐野です。後日、加賀の梅田、越中の桜井、上野の松枝と点在した領地を拝領しますが、こんなに離れた三ヶ庄を貰っても困るのではないかと思います。ある説では、日本海側新潟県に佐野という地名があり、その近くに梅田、桜井、松枝があるので、そちらの話だとも言われています。しかし所詮後人の作成したフィクションですので、あまり追求することもないと思い、ここでやめておきます。
名を明かした常世は、一族に領地を横領され零落しているが、鎌倉に一大事あれば、千切れた具足を取って錆びた薙刀を持ち、痩せた馬に乗り、馳せ参じる、と熱く語り始めます。ここが山場で、シテの聞かせどころでもあります。はじめはゆっくりと、次第に速く、声を張り上げ、袖を脱いで型どころとなります。敵の中に一番に割って入り、命を捨てる覚悟があるが、このままでは餓えで死ぬかもしれないのがなんとも無念だと悔しがります。
一夜明けるとその興奮も醒め、旅僧は「鎌倉に来ることがあれば、訪ねて下さい、幕府に取り計らいましょう」と慰めて立ち去ります。
この別れの場面のロンギの謡は、泊まった旅僧と泊めた夫婦の心情を交互に謡い合う情緒的なところです。今回気になって心残りの場面があります。
ワキの「さらばよ常世」に対して、シテとシテツレが「またお入り」と答え、その後「自然鎌倉にお上りあらばお尋ねあれ、興がる法師なり…」とワキは歩き始めますが、ここは意味あいを考えると、「自然鎌倉にお上りあらばお尋ねあれ」と動かずにじっくりと常世を見つめていてほしく、「興がる法師なり」から動いていただきたいところです。しかし、なかなか大先輩(宝生閑氏)には申し上げにくいので、今回は遠慮しましたが、今後も気になるところとなっています。
前場の最後の見せ場、ワキが「ご沙汰捨てさせたもうなよ」と一足つめて右手を差し出すと、常世はなんとも言えぬ威風を感じ、思わず頭を垂れて、敬意を払います。実際に私は能役者・宝生閑先生の威風を感じ自然と頭が下がってしまいました。そして「共に名残や惜しむらん」と常世夫婦は旅僧を見送り中入りとなります。
中入りするとワキは前場の旅僧から後場の北条時頼に装束を替えて、家来を連れて登場します。場面はもう鎌倉です。
春になり全国の武家に鎌倉への招集がかかり、常世も約束通り痩せ馬に乗って駆けつけます。北条時頼は家来二階堂何某に軍勢の中から常世を捜し出すように命じます。

後シテは白大口袴に側次、白鉢巻きに薙刀を肩に背負い、颯爽と早笛で登場します。侍烏帽子に掛素袍の替えもあるようですが、自主公演でもあり、無難に常の通りにしました。
痩せ馬に乗り、「打てどもあふれども、先へは進まぬ足弱車、乗り力なければ、追いかけたり」と薙刀を馬に見立て、鞭で右腰を叩きながら舞台に入りますが、「乗り力なければ、追いかけたり」の詞章の意味合いからすると、馬に乗った型はおかしいのではないかという意見がありました。
確かにそうだと思いましたが、能には詞章と型がちぐはぐなところがあってもいいのではないか、馬から降りて馬を引きずりながらはせ参じる型では、見る方もつまらないだろうと思っていました。しかし、その後、観世流の野村四郎先生のご意見で、「あそこは鞭を捨てたところからが下馬を意味するので、鞭を当てながらの型はおかしくない」とのことでした。なるほどそれなら問題はないと納得し安心しました。ただ型を鵜呑みにするのではなく、詞章と合わない型なら疑問を持ち考える、それは大事な作業です。今回。それが解明できたのは演能後でしたが、疑問が晴れてよかったと思っています。

さて鎌倉につくと、従者(アイ)に御前に出るようにと呼び出されます。はじめは自分のことではないと断りますが、敵人と思われ首を切られるのも仕方がないと諦め、御前に出ると、いつぞや泊めた旅僧が最明寺北条時頼だったことを知り驚かされます。時頼は常世が言葉通り一番に鎌倉入りしたことを褒め、宿を貸し、鉢木を切り焚き火をしてくれた礼にと、梅、桜、松に因んで梅田、桜井、松枝(松井田)の三ヶ庄を褒美にとらせます。常世は気持ち晴れやかに華々しく上野国に帰ります。
『鉢木』は「水戸黄門」に似ています。
偉い方が身を隠して諸国を巡り、悪を退治し、正義が勝つ、毎回同じような物語なのに、日本人が飽きずに見るのは、どうもこういうものを好む民族のようです。
戦前はこのような忠誠、忠義物は時の政府に喜ばれたようですが、最近は『鉢木』の話をしてもわからない学生さんが多くなってきました。
忠義忠誠は悪くはありませんが、能役者として本音を言わせて頂ければ、単なる目出度し、目出度しのハッピーエンドの話は、能としての深みが正直あまり感じられず、少々物足りない面があります。
叶わぬ恋慕を扱う『野宮』の六条御息所、『松風』姉妹の松風と村雨、権力者から迫害を受けた先住民たちの叫びを描く『野守』の鬼神や『大江山』の酒呑童子、修羅道に苦しむ源平の武士たちなど、女物でも男物でも、鬼でも武者でも、そういうものには能の深さがあります。それは負けた者たちの心意気を演じるからでしょうか。
『鉢木』はそういう能とは本質的に違う能なのでしょう。常世という田舎武士の泥臭さと気骨、これを晴れやかにスカッと演じきることが肝要で、これが言うは易く、しかしなかなか難儀なものだと感じているところです。
(平成22年12月 記)
写真 『鉢木』 シテ 粟谷明生
撮影者 石田裕
撮影者 前島写真店 川辺絢哉
『檜垣』を謡い終えて ー研究公演で地謡の充実を目指し、老女物を再考するー投稿日:2010-12-02

『檜垣』を謡い終えて
?研究公演で地謡の充実を目指し、老女物を再考する?
粟谷明生
能のシテを勤めることはシテ方能楽師の名誉であり喜びで、いつもシテでありたいと思っています。しかしシテだけでは能は成立しませんし、シテが良ければよい能になるかというと、そうではありません。
本当によい能は、シテの演技もさることながら、周りの役者によって、より豊かになります。三役や後見、特に地謡陣の強力な援助態勢は必須で、シテ方は、よいシテ役者を目指す一方、よい地謡が謡える人材にならなければいけません。
粟谷能の会の研究公演は地謡の充実をはかるために、『求塚』や『木賊』など、友枝昭世師をシテにお招きして研鑽して来ましたが、今回(平成22年12月2日 於:国立能楽堂)も友枝師にシテをお願いして『檜垣』に挑戦しました。
敢えてシテをしないで地謡を謡う会を企画することは希有なことです。
「出来る限りシテを勤める機会を作れ…」と教えてくれた父ですが、「能の善し悪しは地謡で決まる。地謡が大事だから地謡を考えろ」も父の口癖でした。
優れたシテ方とは、作品を理解して地謡を謡えなければいけませんが、そのためにはどうしたらよいのでしょうか。
今まで考えて来ましたが、結論は、よい能を観て刺激を受け、その能の地謡を謡えるように志し、そしていつの日かシテが勤められるチャンスを待ち、チャンスが到来したら地謡の経験を生かし勤める。そしてまたシテの心持ちを活かし地謡を謡う。この円環のような繰り返しではないかと思います。
地謡を謡えるようになる事と、シテを勤めることは一対一体で、シテ方能役者の底力とはこの作業をしたか、しないかにかかっていると思います。
さて、『檜垣』は老女物と言われ、能楽師にとっては最高位の曲です。
喜多流の老女物は『卒都婆小町』と『鸚鵡小町』、それに三老女と呼ばれる『伯母捨』『檜垣』『関寺小町』があります。『関寺小町』は理由が有り止曲となっているので、実際には『伯母捨』『檜垣』が最高位と崇められています。
『伯母捨』は父粟谷菊生が平成6年10月粟谷能の会で180年ぶりに再演し、続いて大島久見氏、そして友枝昭世師が二度演られています。『檜垣』も昭和62年に友枝喜久夫氏が120年ぶりに演じ、以来、今回の友枝昭世氏が24年ぶりの再演となりました。
昭和初期まで喜多流の老女物は、大事にし過ぎて高い神棚の奥にしまい込まれていましたが、近年、老女物を手がける方々が多くなり、現場の我々も身近に感じるようになり手の届く曲までに下りてきました。
「喜多流の『伯母捨』や『檜垣』はどうなの?」と尋ねられて、昔は「観たことないので知りません」としか返事が出来なかったのは、なんとも恥ずかしかったことでしょう。
『檜垣』は比較的動く型が少ないので、謡に重きが置かれます。
前回の友枝喜久夫氏がシテの『檜垣』は、父が地頭で、NHKで録音し後日放送されたので、まずそのテープを聞いてみました。ところが父の声があまり聞こえて来ません。ややがっかりして、これは自分たちなりの謡を創り上げるしかないと思いました。
実は演能後、友枝昭世氏より「稽古は菊生先生の謡でやってきたから…」と言われ、「え、父の謡が聞こえますか? NHKテープでは父の謡がよく聞こえず、あの時は不調だったのかな、と思いましたが」と答えると、「ビデオを聞いてご覧。菊生先生らしい謡が聞こえてくるから」と。後日ビデオテープを拝借すると、なるほど父の張りのある声がよく聞こえて来ました。NHKの録音は、どうも地謡の音を平均化してしまうようです。しかし、その事実がわかったのは演能後のこと、時すでに遅かったのですが…。
では今回の『檜垣』で新たに取り入れたことを順を追って具体的に記していきます。
二の同(二つ目の同音)の「理を論ぜざる、いつを限る習ぞや」「老少といっぱ分別なし替わるを以て期とせり」の間に打切(うちきり)を入れて、この部分の主張をより強調するようにしました。
次第は通常、同じ和歌を二度繰り返し、その後に地取(ぢとり)となりますが、『檜垣』は「釣瓶の水に影落ちて袂を月や上るらん」と一句しか謡わないので、序に移行する間(ま)が空かないために、地取りを無しにしました。
老女物には約束事が沢山あり、特に囃子方には、それぞれの流儀の主張、特有の手組があります。クセの冒頭「釣瓶の掛け縄、繰り返し憂き古を・・・」も各流大小鼓の手組は違います。
今回は大鼓・高安流(国川純氏)、小鼓・大倉流(鵜澤洋太郎氏)の組み合わせでしたので、当初、後見をされた大倉流宗家の大倉源次郎氏から、高安流とは手組がうまく咬み合うから、出来れば大倉流本来の手組を打たせてほしいと要望されました。しかし私はどうしても前回(大鼓・柿原崇志氏)の時のように、大鼓の独調で謡に鋭く刻み込む大鼓特有の音色、あの緊張感を再現したく、小鼓方には申し訳なかったのですが、鵜澤洋太郎氏にお願いして、今回はクセの冒頭の手組を遠慮して戴きました。
具体的には「つ△ る△ 瓶の掛△ け縄、繰△ーり△ 返し憂△き」(△は大鼓の打つ所)と大鼓の国川純氏の打ち込む気迫と大鼓の音色、それに応えて地謡陣も負けじと気迫を込めて謡います。正に一調二機三声であり、その緊張感が、シテの写実的な動きを盛り上げると、信じています。
クセは動きが少なく、本来、上羽後は下居のまま動かない型附けですが、地謡としては動かない居クセより、シテの動きがあった方が張って謡えるのでテンションも上がります。今回は友枝氏に特別にお願いして、少し舞って頂くことにしました。
少し脱線しますが、私の謡の暗記法は、型と照らし合わせ覚える方法です。
型が無い場合は仕方がありませんので諦めますが、型があるのに詞章だけ丸覚えするのはどうも苦手です。そのため下申合前から、シテの友枝昭世氏にどのような動きをされるのかを細かくお聞きし、私なりの意見も述べさせて頂きました。
一曲の最後、いよいよ最終場面は残りトメ(謡が終わったあとに囃子方だけが、演奏するやり方)が普通ですが、今回は友枝昭世氏から敢えて、残りトメはせずに「罪を助けてたび給え」と地謡で謡い切ってほしい、との御要望で試みてみました。
以上がおおまかな改善点です。その他、細かなところがたくさんありますが、ここでは割愛させていただきます。
いろいろと自由に試み、身勝手が言えた研究公演でしたが、次回の大きなステップになったと自負しています。
演能後、「おシテのお姿は美しく魅了されました。ただ…、あのように微動だにしない強靱な足腰とご立派な姿勢から100歳に近いお婆さんを想像するのは…どうでしょうか?」と感想を述べられた方がいらっしゃいました。
それに対する私のお返事をこの演能レポートのまとめとして記載します。
父・菊生より以前の時代の老女物を勤められた方々は、老女物を大切にし過ぎる風潮があったからか、手が届かない曲、到底許されない曲と思い込んでおられたのではないでしょうか。
運良く勤める機会を得られた方々も、それ相当のお歳を経てのチャンス到来であって、その舞台は本当にお身体が老いていて・・・、とういうのが悲しい事実です。
それが効を奏したのか判りませんが、生な老いの動きは、観客にまさに老女物とはこのような無惨なものと写った、と推察します。
しかし、それが老女を演じる能、老女物とはそのようなものかというと、私は違うと思います。
老いた身体で老いを演じるのはリアル過ぎます。それでは能という虚構を演じる演劇ではなくなります。老女物だから背中が丸まってもいい、よたよたとあぶない足どりも許せる、聞こえないか細い声であっても、それが老女物だからいいというような考え方は間違っていると思います。
大声を出して、老いをまるっきり感じさせない無神経な所作は論外で、もちろん能は老いを演じる心がなくてはいけません。しかし、老女物であっても声は見所のすみまで聞こえ、能役者の姿勢はほどよく背筋が伸びて凜としたものでなければいけないと思います。
以上述べた全ての理想を兼ね備えていたのが、今回の友枝昭世師の『檜垣』であったのです。そのようにお答えしました。
最後に自戒を込めて能楽師の陥る落とし穴を書き留めます。
何故そのような老いのとらえ方になるのでしょうか?
私はこう思います。
若い時分の稽古能などは、みな初めての経験ですから、必ず位が重くなります。つまりゆっくりになります。丁寧に慎重に謡い、動くことで時間が掛かります。彼ら、いや私もそうでしたが、「軽い!」と怒鳴られるより「重い!」と叱られた方がまだマシだと考えるからです。
しかし馬鹿丁寧な謡や舞は曲本来の位では無いことがほとんどです。
適度な適正な位を習得することが大事なのですが、指導者も、早く進めたときは軽いときつく怒り、馬鹿丁寧の場合は、まあ大人になれば直るでしょうと妙な寛大さを示します。だからどうしても丁寧、慎重になって、必要以上に重くなってしまいます。この若い能楽師たちが陥る現象と、老女物に取り組む大人の能楽師の心境とたいして違わない、重なっていると思います。
今回の『檜垣』に向けて、6月から地謡の稽古を重ねて来ましたが、その時の録音を聞くと、最初はただゆっくり慎重だったものが、段々と位取りもやや軽やかに変わって来ました。繰り返すことによって、真の軽さが生まれることを体感出来ました。
喜多流のこれからの老女物への意識、課題は、もっともっと慣れることです。経験と慣れによって、ほどよいノリと位どりを習得しなくては玄人とは言えないでしょう。
老女物を大事にし過ぎるあまり、老いたから出来るという、年齢で演能の資格を計る考えを改めて、能に生きてきた経験と技術をもとに判断する、そのような意識が増えることを望みます。
研究公演で『檜垣』を24年ぶりに再演でき、この秘曲を次の世代に継承することができました。能という長い歴史の中で、今生きる能楽師として、一つの責任を果たしたと満足感と幸せを感じています。同時に地謡の充実をテーマにすることで、地謡に光を当て、老女物の地謡に真摯に取り組むことができたことを喜んでいます。
研究公演『檜垣』出演者
シテ 友枝昭世
ワキ 森 常好
アイ 山本東次郎
笛 一噌仙幸
小鼓 鵜澤洋太郎
大鼓 国川 純
後見 内田安信
後見 中村邦生
後見 友枝雄人
地頭 粟谷能夫
副地 出雲康雅
地謡 粟谷明生
地謡 長島 茂
地謡 狩野了一
地謡 金子敬一郎
地謡 内田成信
地謡 大島輝久
(平成22年12月 記)
『白是界』について 負ける天狗として再演出投稿日:2010-10-10

『白是界』について
?負ける天狗として再演出?
粟谷 明生

(1)
喜多流には曲名の頭に白や青などを付けて曲の位を上げることがあります。
白は『白是界』の他に、『白田村』『白翁』(白式とも)があり、珍しいものでは青を付ける『青野守』があります。いずれも曲の内容は変わらず、装束や面が常と変わり、謡も省略や緩急がついて面白さが増す特別演出となります。
能の天狗物は仏法の味方とそうでないものと、二つに分けられます。
仏法の味方となるのは『鞍馬天狗』一曲、源義経が沙那王と呼ばれた幼少時代に将来平家追討に助力を約束する天狗で、仏法の敵ではありません。
しかしその他の天狗物(『大会』『車僧』『是界』など)は仏敵として現れ、最後は仏力に祈伏され逃げ去るのが、お決まりの筋書きとなっています。
『是界』も然り、日本の神仏力の礼讃が主題で、天狗は悪役で書かれています。もっともそのような仏法の宣伝歌になっているのは、天台から作者への依頼であったのかもしれません。

(2)
今回、『白是界』(粟谷能の会・平成22年10月10日)を勤めるに当たって、先人たちが手がけられた演出を更に奥深く探求したいと思いました。
実は喜多流には『白是界』の正規な伝書は残っていません。現行の型付は、十四世喜多六平太宗家の考案で、それを継承した先人たちの書き留めたものがあるだけです。
現行の演出は、後シテが頭はもとより装束や羽団扇の持ち物の類いまで全てが白一色になり、大水晶数珠を片手に、よりどっしりとズカッー、ズカッーと大股で運び(歩行)、重量感を出し、天狗の存在感をより強調する特別演出です。それはそれで効果がありますが、反面謡われている内容とのギャップを感じる型がいくつかあり、稽古をしていくうちに、現行の『白是界』が作品の主旨(本意)から少し離れているように思えてきました。先人からお叱りを受けるかもしれませんが、私はどうしても、これまでの『白是界』は作品の主旨に従うというより、ただ面や装束類の色を替え、謡と囃子のノリを押さえることだけで済ませて来たように思えるのです。
謡われている内容とのギャップをどう埋めるか、『是界』という曲が何を言いたいのか? 特別に変化をつける『白是界』のねらいがどこにあるのか? それを見つけることが肝心だと思いました。
そこで、まず、そもそも天狗とはなにか? 是界坊はどうしたのか? 再度確認する作業からはじめ、自分なりの『白是界』を考案したいと思いました。
では舞台進行に合わせて今回替えたところをご紹介します。

(3)
通常、前場の是界坊(シテ)と太郎坊(シテツレ)の扮装は、『安宅』の弁慶(シテ)や『黒塚』の阿闍利(ワキ)と同じ直面(ひためん)の山伏姿です。
しかしこの扮装では、天狗という異界からの侵入者・悪(ワル)の印象が弱く、物足りません。
天狗というと、頭に兜巾を載せ、鈴掛姿に袈裟を付け背中に翼を付けて、団扇を持ち、一本刃の高下駄を履き、鼻は高く赤ら顔で、髪も大童姿、空を易々と飛ぶ山伏姿を想像します。これは中世以降の鼻高天狗と言われるものです。

(4)
『是界』の原典となる鎌倉時代の『是害坊絵巻』には、鼻が嘴のように尖っている「木ノ葉天狗」「烏天狗」といった、もっと以前の鳥類天狗が描かれています。今回はその嘴の形象を面「鷲鼻悪尉」にて表現しようと考えました。ツレは逆に鼻を意識させないながらも、異界の者を感じさせる「真角」を選びました。頭はシテが黒頭、ツレがバス頭を使用して、唐と日本の違いを出してみました。終わって写真を見ると、シテがバス頭の方がよかったかとも思えました。

(5)
『是界』と『白是界』の詞章の違いは、前場のシテの言葉の「案内申し候」を「案内申そう」、「是界坊にて候が」が「是界坊なるが」の二句が替わるだけです。
『白是界』では省略されることが多い前場のクセは、是界坊たち天狗が、不動明王の威力を怖れ、悪と知りつつ抜け出せない身を悲嘆する心情、戦わずして敗北が語られ、明らかに仏法礼讃の詞章です。
今回は、クセの省略だけでなく、不動明王賛美の序もサシもすべて割愛することにしました。天狗の弱音をはく個所を出来る限り除き、前場の是界坊たちの奮起がより前面に出るように、そして唐から日本に、愛宕山から比叡山にと、スピーディーな場面展開の面白さを観ていただきたく演出しました。

(6)
ここでちょっと、前場にしか登場しない太郎坊の話をさせていただきます。
「神国日本の仏界を攻めるには、まず比叡山だ! いざ一緒に比叡山に!」
と是界坊にけしかけた太郎坊ですが、その後の太郎坊の動向が気になります。
私も若い時分に、このツレを勤め、「何故、太郎坊は後半に登場して加勢しないのか? 太郎坊はどうしたのか?」と装束を脱ぎながら、疑問でした。
答えは、太郎坊が是界坊を裏切ったからとされています。
では何故、裏切ったのか? ここに面白い説がありますのでご紹介します。
『車僧』のシテは太郎坊です。太郎坊は車僧と禅問答で負け、天狗の姿となって行力競べをしますが、やはり遂に敗北し、合掌して逃げ去ります。
つまり太郎坊は一度天台の僧に懲らしめられ痛い目にあった経緯があります。
『是界』では、「蟷螂が斧とかや(カマキリが大きな車を止めようとする)、猿猴が月(猿が水に写った月を掬おうとする)に相同じ」と、所詮天台に勝つのはむずかいしいと、苦言を呈しています。
しかしそんな太郎坊ですが、是界坊は遙々唐から飛んで来た中国の天狗だから、まあお手並み拝見、一度挑んでみては? と考えた…。これが太郎坊の内心、立場と思われます。一緒に戦う気など毛頭なかったのです。だから後半に登場せず、加勢もしないわけです。
この度、息子の尚生に太郎坊を勤めさせました。
尚生はひととき舞台から離れていましたが、近年また舞台への意欲が伺えるようになったので、楽屋働きと同時に演能機会を与えることも、親であり指導者の勤めだと思い配役しました。
普通ならばツレは直面姿ですが、面をつけての初ツレ役はプレッシャーも強くあったと思います。実は息子の使用した「真角」ですが、喜多七太夫古能の花押が入った是閑打の名品です。本来ならば未熟な若者が使用するべき面ではありません。未熟者にはそれ相応の面を、これが然るべき姿です。ただ私のこだわりとして、粟谷能の会という場、そしてこれから粟谷家を背負っていくべき者には、可能であれば出来る限り本物に触れる大切さを知ってほしい、本物が似合う役者になってほしい、との願いがあります。
舞台前に緊張する息子と面に当て物をつけながら、是閑打、云々の話は敢えてしませんでした。終演後、話して聞かすと、「そんなすごいもの付けてよかったの?」と言うので、「能夫さんによく礼を言っておきなさい」と答えておきました。こんな楽屋裏の話ですが、これからの能役者の成長を見守っていただきたく、ここに記しました。私自身も同じように、周りの皆様からあたたかく見守られここまで来ました。それと同じことをしているだけなのです。
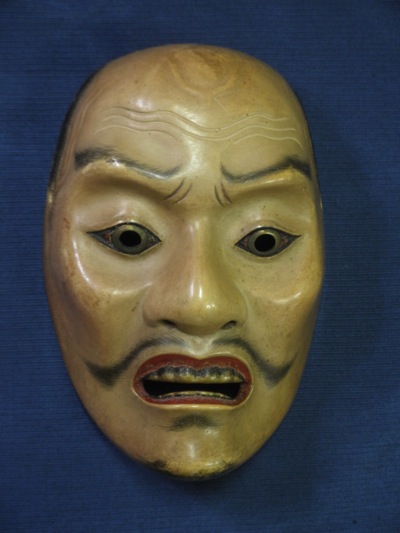
(7)
話を戻します。
『白是界』の後シテの面は、『是界』の「大ベシミ」から「悪尉ベシミ」に替わります。粟谷家には諸先輩方が愛用してきた「悪尉ベシミ」があります。
他人の言うことなど聞かない自己顕示欲の強い頑固な形相の、力強さが漲っている年老いた顔つきです。

(8)
当初、先人にならいこれを使う予定でしたが、稽古するうちにふと、「私が想像する『白是界』の天狗には似合わないのでは…」と思うようになりました。
もしかするとこの面の魔力が原因で演者や、そして観客までもが、『白是界』を見間違えているのではないか、と…。
『鞍馬天狗』ならば、いかにも強そうで福たけた表情が牛若丸を厳しく指導する姿に似合いますが、負ける『是界』の天狗にはどうも相応しくない、というのが私の判断です。
負ける天狗にはどこか愛嬌があって、間が抜けたようなユーモラスさが必要です。そこで別の「悪尉ベシミ」、通称「猫ベシミ」と呼ばれるものに替えることにしました。

(9)
終演後、「いささか、漫画チック」と評されましたが、それこそ私の狙いであって、実は内心ほくそ笑んでいるのです。
後シテの装束は白一色となり、小書「白頭」は鹿背杖をついて登場しますが、『白是界』は杖の代わりに左手に数珠を持ち、常に胸に当てています。
はじめ、この構えは不動明王を模しているもの、と解釈していましたが、友枝昭世師より、友枝喜久夫先生の書付けにある「左手常に胸に、これ如意の如し、肝要なり」との心得を教えていただき、私の『白是界』の発想の基となりました。如意とは「意のままに、なんでも自分が正しい、自分の思い通りに」と自己中心の信念で、その信仰心を、左手で数珠を強く握りしめ、胸(心)に当てる格好で表現します。『白是界』は、ほとんどこの構えで通すため、意外とバランスを崩しやすくなるのが、演じる時の注意点だと知りました。

(10)
今回の新工夫は後半に並びます。まず通常の舞働を『紅葉狩』や『船弁慶』などのワキへの威嚇と見える型に替え、静の僧正と、動の是界坊が対比してご覧いただければと考えました。結果はやはり従来通りの、是界坊と不動明王や諸々の神々との対決をシテの立ち回りだけで見せる型附の方が良かったように思えてきました。
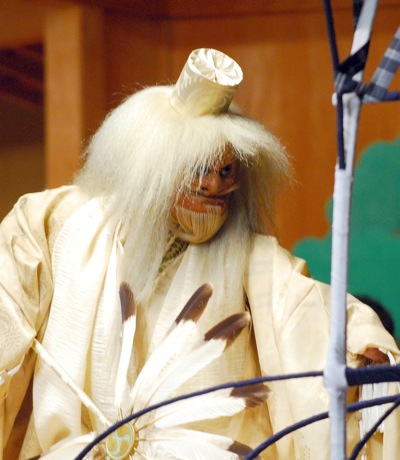
(11)
また、普通は「翼も地に落ち…」と組落の型で飛行から落ちた、と見せますが羽団扇は最後まで持ち続けます。今回は、羽団扇を捨てた方が、飛行能力が衰えた、と想像し易いと思い落とし捨ててみました。
また地謡も終始ただゆったりと重く強く謡っているだけでは天狗の慌てる滑稽さが見られず、逆に単調で飽きてしまいます。
そこで今回は「力も槻弓の八島の波の」から位を早め、慌てて逃げ去る光景に合う謡にしてもらいました。
そして『白是界』のクライマックス、是界坊はまた立ち戻り、遂に数珠を投げ捨ててしまいます。先人は皆、本舞台に入り、ワキの前に、「今回は帰ることにするが…」と偉そうにポイッと捨てるようにしています。これが心得と聞かされてきました。天台の僧に完全に負けていながらも、まだ相手を小馬鹿にして見下す風格が『白是界』には必要だと…。
しかし、それでは「飛行の翼も地に落ち、力も槻弓の八島の波の立ち去ると見えしが、また飛び来たり、さるにても、かほどに妙なる仏力、神力、今より後は来るまじと、云う声ばかり虚空に残り…」の敗北退散の詞章にそぐいません。
『是界』の作者は竹田法印宗盛という室町御所の医師ですが、書かれた戯曲は国粋主義の神国、仏国、天台宗の賛美で終始しています。
それが良いとか、悪いとかは別として、演者は書かれた台本を忠実に、充分に読み取って演じる、そう信じます。ですから、現実の負けを認めないような、是界坊のとらえ方には同意出来ず、そうはしたくないと思いました。

(12)
是界坊は負け天狗で悪役です。天台の賛美が根底になくてはいけないのです。
ですから、私は、本舞台まで戻らずに橋掛りから舞台へ数珠を投げ捨てました。虚空に上がった是界坊が、遥か下の地上にいる天台の僧侶に、悔しさを噛みしめながら敗北を認め、「クソ、この数珠、効かなかったか!」と未練なく投げ捨てるのです。
皆様は、どのように思われましたか?
ご感想を戴けたら嬉しいです。
この負ける中国の天狗の『是界』を中国の方々がご覧になったらどう思われるでしょうか。「中国の天狗はそんなに弱くない! これは違う! この作品良くない!」と聞こえて来そうです。尖閣諸島の問題を抱えている今、『是界』や『白楽天』は少々危険な作品のように思われます。しかし、これは演劇です、古典の能です。
中国や日本として見るのではなく、是界坊が説く、すべて己が正しく、間違いはすべて相手が悪い、このように考える人間の心そのものをテーマにしているのだと思います。
皆様の身のまわりにも、いらっしゃいませんか?
我が儘で、自分のことばかり、そのような人間の愚かな姿を、天狗という悪役に置き換え警告しているのが『是界』なのだ、そう思えるようになりました。
能役者は、戯曲に描かれているものを、現代に合った形で伝えることが第一です。羽団扇を捨て、謡に緩急を加え、敗北を認め、数珠を橋掛りから舞台に投げるなど、新工夫の『白是界』でしたが、それらは今までの喜多流にはありませんでした。
橋掛りから舞台に投げるとは、と遺憾に思う同胞の方もおられるかもしれません。しかし、演能後、金剛流に橋掛りから投げる型があることを知り、まったくのお門違いではないことに少し安堵しています。
以前、新しい試みに挑戦された友枝昭世師が「そんなの、喜多流にあるの?」と嫌味に問われ、「いや、能にはある」と答えられました。あの鮮烈な言葉は今でも私の心をとらえています。「能にはある」を信念として、新工夫の大切さをかみしめ、今回また『白是界』で能の面白さを再発見できました。
とはいうものの、まだまだ未熟な我が儘天狗の私です。
あまり独走しすぎてもいけないですが、消極的過ぎるのも効果はない、その兼ね合い、バランス感覚が極意、そう負ける天狗が教えてくれたようです。
(平成22年10月 記)
付録 「育王山、青龍寺、般若臺に至まで皆我が道に誘引せずということなし」と是界坊が自慢する「青龍寺」は、以前訪問したことがあるので、こちらからご覧いただけます。
写真資料
(1)イロエにて 下界を見下ろす型 撮影 前島写真店・駒井壮介
(2)数珠を握り邪法を唱える 撮影 前島写真店・駒井壮介
(3)前シテ・是界坊 粟谷明生 撮影 前島写真店・駒井壮介
(4)「是害絵巻」 写真引用
(5)「鷲鼻悪尉」粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
(6) シテ連・太郎坊 粟谷尚生 撮影 前島写真店・駒井壮介
(7)「真角」粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
(8)「悪尉ベシミ」粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
(9)「猫ベシミ」粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
(10)数珠を胸に当てる是界坊 撮影 前島写真店・駒井壮介
(11)飯室僧正を威嚇する是界坊 撮影 前島写真店・駒井壮介
(12)数珠を投げ捨てる 撮影 吉越 研
『綾鼓』を勤めて ー老いの恋心と女御の胸の内ー 投稿日:2010-09-05

『綾鼓』を勤めて
ー老いの恋心と女御の胸の内ー
粟谷 明生

「恋の重荷、昔綾の太鼓なり」と世阿弥の三道に記載があるように、現在、『恋重荷』は観世流と金春流に、そして『綾鼓』は宝生流・金剛流と喜多流にあります。
但し、喜多流の『綾鼓』は昭和27年、先代15世喜多実宗家と土岐善麿氏が創作した新作能です。そのため謡本も従来の見慣れた字体ではないので、玄人も素人弟子も一寸馴染めず抵抗感を覚えるのが正直なところです。
この曲の舞台の木之丸殿(きのまるどの)は『八島』でも謡われる、朝倉宮の皇居跡で現在は福岡県朝倉市にあります。斉明天皇(女帝)が百済の軍を援護するため大和からはるばる還幸された際の仮宮で、崩御後、御子の天智天皇が喪に服されるために殿舎を造られました。通常皇居は、厳選された木を切り、皮を剥ぎ時間をかけて干して念入りに建造しますが、木之丸殿は急いで造られた仮の宮のため、丸木の木材の皮を剥がずにそのままを使い木之丸殿と呼ばれるようになりました。

さて、事件はこの木之丸殿でおこります。
美しい女御(ツレ)の姿を見て恋に落ちた庭掃きの老人(前シテ)に、女御は池のほとりの桂の枝に鼓をかけて打って音が出たら姿を見せましょう、と約束します。喜んだ老人は必死に打ちますが、鼓は綾で張られていたので音がしません。思い諦めるように臣下に諭されますが、老人は初めから鳴らない鼓を打たされたことを知り憤怒悲嘆して池に身を投げます(中入り)。
老人の死を聞いて哀れを感じた女御は老人が飛び込んだ池の汀を眺めているうちに、波の音が鼓の音に聞こえ狂気の態となります。そこへ庭掃き老人の怨霊(後シテ)が現れて、「綾の鼓が鳴るものか、自分で打ってみろ」と女御を杖で責めます。女御は責苦に堪えられず、池の岸辺に倒れますが、怨霊は冷然とその姿を顧みながら、また池に沈み消えていきます。
能で失恋、邪恋をテーマにしたものは多々ありますが、老人の恋を扱う曲は『綾鼓』(『恋重荷』)が唯一です。しかも女御という宮中の適わぬ相手に恋心を抱いてしまう設定は、一般の想像を超える世界です。
私は今回の演能(平成22年9月5日「ひたち能と狂言」)にあたり、女御像について思いを巡らせてみました。
この女御が、鼓に綾が張られていたことを事前に知っていた場合と知らなかった場合では観る側の舞台への印象も変わるのではないか、謡本の解題にも、鼓に綾が張られたことを女御がいつ知ったかについて記載が不明瞭で、故意にぼかしているように思えます。

父は「女御がからかい半分で老人と接し、老人が本気にしてストーカーになる。女御はうるさくなって、ここはなんとか騙してしまおうと、企むわけだ…。老人をチャタレー夫人の森番に見立てるのが演能の隠し味だ」と『綾鼓』を勤める役者の演能心得を語っていました。
私は「近代能楽集」(三島由紀夫著)の影響でしょうか、どうもツレ(女御)を勤めた時に、卑賤の老爺が貴人に恋するなど身分不相応の異常行為、と不快感を露わにする気が強い女御を想像していました。
今回の演能に先立ち、周りの方とこの女御はどのような立場であったかを意見交換する場を持ちました。いろいろと意見は出ましたが、女御は老人の噂話を知りながらも直接諭せないので困り、鳴らない鼓を鳴らさせる、という一つの手段を思いつき、老人に諦めてもらおうとした、実は優しさに溢れる女御だったのではないか、とのご意見もありました。
いろいろな想像を巡らし、稽古を重ねるうちに、もしかすると女御は綾が張られていたことを知らなかったのではないか、と仮定して演じた方が面白い、と思うようになりました。老人が入水後、女御は臣下からはじめて事件の真相、綾が張られていたことを知らされる、宮中という特殊な環境であれば、本人の知らない間に、周りの者たちの取り計らいで事は進められてしまう…有り得ないこととは言えないと思うのです。
いずれにしても結果は老人を死に追いやり、逆恨みであろうとも女御は老人の死霊に責められます。女御が知っていた場合は、少しやりすぎたから当然の仕打ちだよ、となり、知らなかった場合は、女御への哀れみ、同情が湧いてくるように思えます。
『綾鼓』は新作能のため、基本の型附は喜多実先生の書付が残っています。
現在、この実先生の型附通りに勤める方もいらっしゃいますが、一方では新たに独自の工夫をし演出される方もおられます。私も、私なりの解釈で新工夫したいと思いましたので、舞台進行と共にご紹介します。
今回の『綾鼓』は、形式的な無駄を省き、より解りやすく鑑賞出来ることを、心掛けました。
通常、臣下(ワキ)の名乗りの後には、皇居の者(アイ)が呼び出され、アイが庭掃きの老人(シテ)を呼び出すという所作に重複があるので、直接ワキがシテを呼び出すようにしました。
老人が池のほとりの桂の枝に掛けられた鼓を見せられると、箒を捨てて鼓を打ちますが、従来は撥を使用せずに中啓(扇)にて代用していました。
中啓を撥の代わりとする演技は能らしい扱いですが、「ひたち能と狂言」の会では、はじめて能をご覧になる方も多いと聞いていましたので、より具体的に判りやすくご覧頂ければと思い、敢えて本物の撥を使ってみました。
また、鼓が鳴らずに落胆している老人に、ワキが直接告げるのが、現代の流行ですが、ここも敢えて判りやすさを誇張したく、アイが真相を告げ、撥を荒く奪い取ることで、邪険にされる老人の悲しい有様が強調されると、試みてみました。
後場のシテの登場は幕の内から「声ありて?」と謡い、常の出端(では)の寸法では老人が出現するまでに時間がかかり、間が抜けてしまうので寸法を短くして、シテの謡も橋掛りを歩みながら謡い出す、という今までにない新演出にしました。
今回特に気をつけたのが、綾の鼓への恨みです。老人は女御だけでなく鼓にも恨みがあるはずです。そこを最も強調した演技にしたい、と…。
実先生の書付には、女御へのアクションばかりが多く、鼓への恨みの型はあまりありません。
イロエ(立廻り)も従来のパターン通りの、「拍子を踏み、角に行き、左回りして常座で廻返し、ツレにシカケ開キながら膝付き、グワッシ返し、立ち右回り」と鼓への思い入れの型がなく、やや舞踊的に感じられます。
私はもっと鼓や女御への恨みを直接的に見せる、恐ろしさが溢れる動きにしたく、舞台に入ると、すぐに鼓を見つけ、次にジワジワと女御を探し当てると楚(しもと)を振り上げ、怒りは爆発寸前となる、威嚇の型にしました。
演者は勤める役柄の心境を深く理解して、それに沿った演出をすべきです。
新作能であれば余計、充分に考慮が許されてよいはずです。
今年54歳で、この庭掃き老人に扮するにあたって、老いの恋、老いのプライド、老いの嘆き、諸々の事を考え、以前勤めた老武者の『実盛』のことを思い出しました。
能役者はどうしても、まず外見的な肉体的な衰えを演じ切ろうとしますが、
やはり大事なものはその役の心の内です。老いとは、私にとってまだまだ未知なる世界ですが、少し解るような気分でもあります。
齋藤別当実盛も、庭掃き老人も、共通しているのは、その心根が若き日となにも変わっていない、ことです。
老いて異性への恋心がなくなる、というのは稀なことで、いつまで経ってもわくわくする気持ち、人間の普遍的な本能なのでしょうか。年齢には関係ない永久の感情のようです。
『綾鼓』の老人も庭掃きの労働が出来るくらいですから健康な体です。健康だからこそ、恋する気持ちが衰えないのかもしれません。
しかし事件はこの健康であるがゆえに起きます。老人であり、そのうえ身分の違いが大きく立ちはだかるのです。
女御が、私の解釈のように、事の真相を知らされていなかったとしたら、女御はやさしいお姫様像となり、観客の同情の余地も出てくるでしょう。
反対に死霊となった老人は、永遠に怒り恨み続けなければならない非道に落ち、観客はなんとも惨めな老人のその後のむごさを感じるでしょう。
それが面白いのかもしれませんが…。
死霊を演じながら、女御だけではなく、鳴らない鼓を、仕組んだ取り巻きや、身分の違いを生みだす社会を恨めばよかったのに…とも思いました。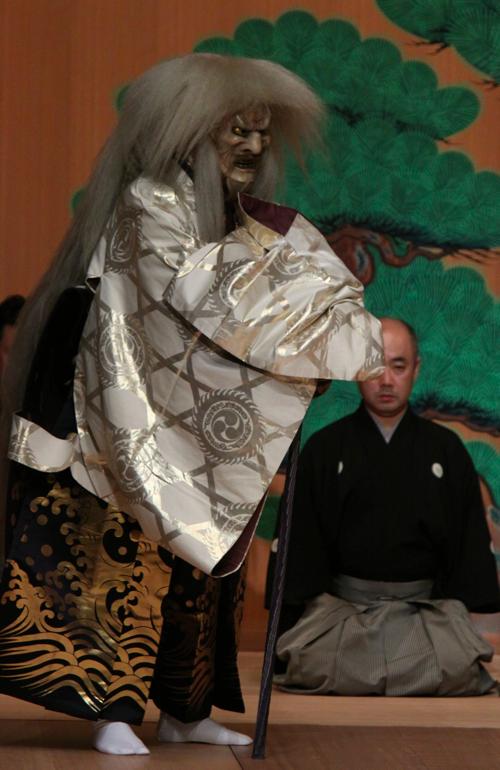
女御の立場を明瞭にしないで、最後まで救われない老人と女御を描く喜多流の『綾鼓』ですが、時代を越え、広く深く、多くのことを語りかけいるのかもしれません。それに応える楽しみもあります。
庭掃きの老人の執心が、私の老いを演じる意識と作品の本音を探ることに刺激を与えてくれたことは確かでした。
(平成22年9月 記)
写真 『綾鼓』 シテ 粟谷明生 撮影 石田 裕
写真 無断転写禁止
『巴』を勤めて投稿日:2010-07-25

演能レポート『巴』を勤めて
艶ある女武者を目指し

高知能楽鑑賞会(22年7月25日)粟谷菊生追悼の公演で、父が好きで得意でもあった『巴』を父への手向けとして勤めました。
能の世界で木曽義仲(源義仲)本人が主人公(シテ)として登場する曲はありませんが、その家来、巴御前(『巴』)や今井兼平(『兼平』)によって義仲は描かれています。特に『巴』は木曽義仲の家来でありながも愛妾としての姿、剛勇ながらも恋慕の心を持つ女性の忠誠心を描いた作品です。『巴』は二番目物・修羅物ですが、主人公(シテ)が女というのは異例で、この一番だけです。
修羅物は、主人公が戦死したゆかりの地に現れて討死の有様を見せ、修羅道の苦患からの救いを僧に頼む、というのがお決まりですが、『巴』は異色です。
また構成も普通と変わっていて、討死していない巴御前ですから、自分が非業の死をとげた土地に現れるのではなく、死後も愛してやまない主君義仲が祀られている社に現れます。修羅物でありながら、その想いは、共に死ねなかったことの執心、深い恋慕の情念が今も成仏の妨げになると苦しむところが特異です。
演者は物語の真意をよく理解して、派手な剛勇の女武者ぶりだけでなく、義仲を想って止まない恋慕の心根を演じ切らないと、あちらに居られる巴様から斬りつけられてしまうでしょう。
『巴』の物語は、木曽の山里に住む旅僧が都へ上る途中、近江国(滋賀県)琵琶湖湖畔の粟津が原に着くところから始まります。そこに一人の里女が現れ、社に参拝し涙を流して
いるので不審に思いわけを尋ねると、女は行教和尚も宇佐八幡へ詣でたとき、「何ごとのおわしますとは知らねども、忝なさに涙こぼるる」と詠まれたように、神社の前で涙を流すことは不思議ではないと答えます。女は社殿に神として祀られている木曽義仲公は、僧と同郷であるから霊を慰めてほしいと頼み、自らも義仲の家来、巴御前の亡霊であるとほのめかし消えてしまいます。〈中入〉
旅僧は、里人に、義仲の最期と巴御前のことを聞き、同国の縁と思い、一夜を明かし読経します。すると先の女が、長刀をもち甲冑姿で現れ、女武者の巴御前であると名のり、義仲の遺言により一緒に死ぬことが許されなかった無念さを、戦語りを交えて僧に見せます。
そして義仲からは生き延びて形見を木曽に届けるように命じられ、巴は泣きながら形見の品をもって一人木曽へと落ちのびたが、いまだに義仲への想いが成仏のさまたげになっているので、その執心を晴らしてほしいと回向を願って消え失せます。
私は今までに三度『巴』を勤めていますが、若い時分の『巴』を顧みると、確かに鮮やかな長刀さばきばかりに気をとられ、巴の女らしさを演じるには至っていなかったように思います。
以前、私がまだ20代の頃、ある女性に言われた言葉が、今も頭から離れないでいます。
「ご立派な『巴』は何度も拝見してきましたが、愛らしい、かわいい、イロっぽいと思わせてくれたことは一度もなかったわ。でも、あなたのお父様の『巴』は違った。あ~、女以上に女だわ! と感じさせてくれて・・・。でもそこまでしてくれないと能『巴』にはならない、そう思わない?」
いつもこの言葉を気に掛けているので、今回は私なりに巴御前の女らしさを意識して演じたいと思い、謡や型はもちろん、面や装束なども常と替えてみました。
能『巴』の使用面は、喜多流では「小面」が決まりですが、他流では「若女」「増女」「孫次郎」「十寸髪」など、いろいろ使われます。今回は父の追悼なので、父愛用の井関の「小面」を附けて、と思いましたが、敢えて父とは違う『巴』の世界をと、小面よりも少し大人っぽい私のお気に入りの「宝増」にしました。
私は幼少の頃は父から芸を教えられ、小学生から喜多実先生に入門、そして30歳にて師を友枝昭世師としましたが、青年時代に数曲、父から直接習った曲があります。その中でもっとも丁寧に細部まで教えてもらったのが『巴』でした。
ここからは父の教えなどもご紹介しながら、舞台進行に沿って私の舞台裏もレポートしていきたいと思います。
前場の里女(前シテ)は「アシラヒ出し」で登場します。囃子方の囃す「アシラヒ出し」はノリのないリズムです。シテは静かにどこからともなくふっと現れるような風情で運び(はこび=歩行)、舞台に登場します。一見何の変哲もない簡単な動きのように見えますが、ベタベタと単調に足を運んでは優美さに欠けますので、乗らないリズムながらも、演者自身の中に運びの流れを意識して、若干の序・破・急のスピード感を出すところに技の極意が秘められています。
義仲を祀る社前での僧(ワキ)との問答も、あまり重くなり過ぎると曲の位に合わなくなります。軽くサラリと謡いながらも、要所要所でしっかりと思い入れを言葉に載せる、言うのは簡単ですが、なかなか体得出来ないでいます。
中入り前「さる程に暮れてゆく日も山の端に、入相の鐘の音の、浦曲の波に響きつつ」と西の空を見上げ次第にうつむき、鐘の音を聞く型が唯一の型どころです。「観る者に鐘の音が聞こえるように」とは、シテと地謡への父のアドバイスでした。

後場は、唐織を壺織(坪折とも)にして武装した雰囲気を創りますが、今回は長絹を肩上げにする替の扮装にしました。これは、より武装の甲冑姿が想像しやすく、演者は壺織よりも軽く動きやすい利点があります。
しかし反面、中入りでの着附や物着での脱衣の手間などが面倒で、予めの仕込みが必要ですから、着せる者も演者も億劫なのが欠点です。
そして何よりも長絹姿は、演者の身体の構えが露わに見えてしまうので、体型が気になる人には難点となります。「体型がご立派過ぎて…熟女っぽく見えました」とのご感想をいただいて反省し、これからの食生活を考え直しています。

ここで脱線しますが、装束の着附について触れておきます。
能役者は胴着(真綿が入った下着)を着て身体をふっくらと見せる工夫をしています。
若い時分は、痩せてスマートですが、どうも装束を附けた姿は良くありません、貧弱に写ります。これはスポーツマンとも共通していることで、あまりに若過ぎては未だ身体が出来上がっていません。能楽師も同様で、30代を過ぎる頃から、自然と身体が出来てきます。特に腰回りがしっかりしてきますと、装束が身体にフィットしてきます。ですからガリガリの痩せが良い訳でもないのです。このように書くと肥満を正当化した言い訳のように聞こえるかもしれませんが、私の青年時代の写真をご覧頂ければお判り頂けると思います。

とは言いましても、過ぎたるは・・・なんとやらで、今の私の場合、ここはやはり体型、体形改善の努力が必要、と認識しています。
能でシテが長刀を使う曲は『橋弁慶』『船弁慶』『熊坂』の三曲がいずれも男物で、女物では『巴』一曲のみです。実は『平家物語』に巴御前が長刀を使用していた記載はないので、これはたぶん作者の着想でしょう。しかし巴といえば長刀、これが喜多流内での印象です。
「巴の長刀さばきは軽快に鮮やかに、しなりを入れることで女を表現する。逆に弁慶、知盛や熊坂はしなりを入れてはいけない」が父の教えです。
後場の型どころは多く、床几での型、長刀を駆使する仕舞所、義仲の形見となる小袖の扱い、物着にて水衣を着て笠と太刀を持つ最終場面。
すべてに父の言葉が浮かび上がって来ました。

特に終盤、長刀を捨て、白水衣を義仲の死骸とも形見とも思い取り上げて別れを告げ、形見を肌身離さず胸に抱き、「行けども悲しや行きやらぬ」と、なかなか立ち去れない心情で、死骸を振り返るあたりは、足、肩、面、それぞれの角度と向きにねじれをつけるんだよ、と直接演ってみせてくれた父の姿が浮かんできました。白水衣を羽織って浄衣の姿となり、最終の最高潮、笠を高々と上げて木曽の里を思いと、良い型が続きますが、「後ろ姿に哀愁が出ないとだめだ、後ろ姿だよ」「最後の留めは、笠と小太刀を捨てるも吉、また笠だけ捨て小太刀は義仲だと思って持ちかえる、どちらでもいいよ。意味さえ判ってやれば…」最も印象深い父の言葉です。

喜多流では、強く、強く、と教えられます。このシンプルな言葉、若い時分は強くを荒くと誤解しがちです。強いは、彊い、剛い、勁い、といろいろありますが、能ではつよい気持ちを基盤にして剛柔を表現します。やさしさ、女らしさ、哀れさも、強さでというと不審に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、強くとは思いを込める程度と理解していただければいいかもしれません。声は息を引いて発声し強さを出します。父の言う「芯は強く、まわりは柔らかく、マシュマロのように」が判りやすいかもしれません。しかし、言うは易く・・・、習得には時間がかかります。
今回の『巴』、自分なりには精一杯女らしさ、哀れさを意識したつもりですが、演りきれたか、というと反省点もいろいろあり、また演り直さなければ、というのが正直なところです。
もうすぐ55歳を迎え、自分を顧みると、若いときに哀れさや女らしさなど、演りきることなどは無理難題、出来るはずがないのです。このように書くとお叱りを受けるかもしれませんが、これは本音です。
若い時分は未熟です。出来ないのが当たり前、仕方がありません。ですから若気の至りで、自分なりにガムシャラに挑むしかないのです。哀れや悲しみ、女らしさを、間違ってもよい、勘違いしてでもよいから、演ってみる、その試みる気持ちが大事なのです。間違って演ることの無意味さを唱える大人がいるかもしれませんが、自ら身を以て体験し本物を探す、それしか本物には近づけない、今そう信じています。
「赤ん坊は一度熱いやかんに手を触れて熱さを知っておくといい。それを危険だからとさせないと、そのうちその子は溶鉱炉に手を入れるんだよ」とこれも父の面白い例え話。
一度立ち入らないと判らない、この年齢になってようやく判ったのです。
今50代半ばにして4回目の『巴』を勤め、どうしたら女らしさ、哀れさが、演じられるか、まだ悩んでいます。
父の追悼で父の『巴』を思い出しながら勤めた私の『巴』。
演じ終えて、いろいろご批判もあり、まだまだ先は遥か彼方ですが、自分なりの一歩が踏み込めた感触はあって、「いろいろなことをやって、それを能に還元すればいいの!」という父の声が今大きく聞こえて来ています。
今回いろいろなことを思い出させてくれたのは、巴御前のお陰か、それとも父がひょっとして近くにいたのか…。
父菊生追悼公演で父との会話を楽しませてもらったような気がしています。
写真3 『巴』シテ 粟谷明生 粟谷能の会 撮影 三上文規
写真4 『巴』シテ 粟谷明生 青年喜多会 撮影 あびこ喜久三
その他 『巴』シテ 粟谷明生 高知能楽鑑賞会 撮影 片岡鷹介
(平成22年8月 記)
『邯鄲』「置鼓・働」を「傘之出」と演じ分けて投稿日:2010-06-07
①.jpg)
『邯鄲』「置鼓・働」を「傘之出」と演じ分けて
①.jpg)
年が明けて、まだお正月気分の残る1月6日、はじめての国立能楽堂からの出演依頼で、平成22年度の公演の一番手として、しかも大好きな『邯鄲』を勤めることが出来たことはたいへん名誉なことで光栄でした。新年早々、この重大な役目が控えていると、日頃の健康管理にも気をつけ、舞台人としては健全で恵まれた新年の幕開けとなりました。
『邯鄲』の初演は平成元年に妙花の会、次は平成二十年と間があきまして「傘之出」の小書にて再演し、今回は三度目となり「置鼓(おきつづみ)」と「働(ハタラキ)」の小書付となりました。
「置鼓」は狂言方の小書とシテ方の小書の2通りがありますが、今回は狂言方の小書でした。アイ(女主人・野村萬斎氏)が枕を担いで登場する際に小鼓の独調と笛の音取が囃されます。これは本来、『翁』付(つき=翁の後に行う曲目)の時の演出ですが、今回、特別に『翁』が無くても行われたのは国立能楽堂の意向のようです。
さて、その舞台効果はどうであったでしょうか?
年の初め、一番手の能役者の登場ということで、『翁』付のような形式ばった雰囲気にしたのはお正月ムードにお似合いだったかもしれません。しかしそれが果たして能『邯鄲』の作品を活かす演出であったかというと、そうではないように思えました。このように思ったのは私だけではなく、実は楽屋内の反応も同様で、当事者の野村萬斎氏も演出効果に関しては「仰々しいですね。アイが官人ならばともかく、『邯鄲』の場合は女主人であるので、少々やりにくいですよ」と楽屋で話されていました。
「置鼓」に関して伝書を調べると、シテ方にも音取置鼓で演じることがあることを知りました。我が家の伝書には「替装束」と記載され、翁付や脇能としての演出に限り置鼓で登場し…と、通常とは諸々変わることが記されていました。
内容の一部をご紹介します。
まず脇能にて致す事、とあり、白大口に舞衣、唐団扇右腰に差し左手大水晶、右手払子を持ち、狂言口開後、笛音取吹き、小鼓独調となり出る、「抑もー(そもそも)これは」と名乗り、打切、「浮き世の旅」と次第を謡い、地取、また「浮き世の旅」と三ベン返となり、打切、「住み慣れし」と道行。
以下通常のものと異なるところが多々あります。ここでは省略させて頂きますが、これがシテ方の置鼓(替装束)です。あまり演能意欲が湧くものではないようですが、一度観てみたい気はします。
今回のシテ方の小書は「働=ハタラキ」です。
「月人男の舞なれば、*、雲の羽袖を重ねつつ、喜びの歌を」の*のところにイロエ(立ち回り)が入ります。
イロエ(立ち回り)とは囃子だけの演奏でシテが動くことを言います。舞台中央で拍子を踏み角に出て、左廻りにて大小前にて拍子乗り込み、段を取り、右回り大小前にて謡う…と伝書には記載され、イロエの心持ちや型の意味などの説明はされていません。
これをどのように解釈し想像を膨らませるかは、演者の仕事で想像と工夫が必要になります。私はこのように能が能役者の自由な解釈で出来る、その許容範囲が広い仕事であるから、こんなに面白く遣り甲斐をもってできるのだと挑めています。
②.jpg)
思いがけず王位に着いた廬生は50年の栄華を究め、さらに一千年の齢を望みます。
そこに人間の傲慢さが現れます。長寿を望み、絶大な権勢の保持と欲深さ、更に最高位を望み地上界だけではなく天空の月世界にまで昇り詰めようとする。そして月世界をも制しご満悦気分・・・、これをハタラキの抽象的な動きで表現出来れば…と思い勤めました。
今回、舞人(子方・内田貴成君)は舞い終えた後にすぐに消える演出にし、また同時に大臣達も地謡前に移動することを試演しました。通常は子方と大臣達は廬生の夢が醒める前に、あっという間に消えるように一挙に走り込みます。その良さは充分承知していますが・・・。その一方で、子方も大臣達(ワキツレ)もずっと脇正面側に座っているのでよく脇正面にお座りの方々から、大臣達が邪魔で見づらいとのご意見がありました。この対応として今回の試演が解決を見出したのでないかと思います。脇正面でご覧になられた方々のご意見をお聞かせ頂きたいと思います。
演能前に、ある観客の方から二年前の小書「傘之出」と普通の『邯鄲』とを見比べるのが楽しみです、と言われました。私は常々「傘之出」と通常の場合とをはっきり演じ分けるべきだと思っていました。「傘之出」は「望み叶えて帰りけり」と地謡が終わった後に女主人との問答があります。世の無常を悟った廬生の帰り際に、女主人が呼びかける「また、重ねて参り候へや~」という言葉の余韻にいろいろと想像を巡らせる趣のある演出です。通常は「望み叶えて帰りけり」と祝言の心で謡い、何事も一睡の夢と世の無常を悟った喜びに満ちて終わらせなくてはいけません。
能楽師としてどちらがお好みか、と問われれば、私は即座に「傘之出」の演出を挙げます。「本当に悟れたのかな?」という余韻を残し、盧生の人間描写が深くなるように思えるからです。しかし、通常演出にもそのよさはあり、それを引き出す事も演者の努めだと思います。今回は特に祝言の心で終曲する、その意識を大事にしたいと思い演じました。
能は演者が初演の時と何度も勤めている場合では、観客の目に映るものも違ってくるのだろうと思います。初演では、ういういしさなどが舞台のよさの糧になり、またベテランの手慣れた余裕のある舞台は観ていて安心感があって、こちらもまた良いもので、どちらが良いとは決められないものです。
今回の私も3回目ということで、今までの経験を活かし、余裕を持って勤めることが出来たことは事実です。
国立能楽堂の一番手、お正月気分もあり、盧生が悟れてよかった、めでたし、めでたし! と祝言の心で終わる演出がお正月には似合っていたと思います。何回か勤めることで、その時、その場所にふさわしい能を演出し工夫して勤める、そのことが出来る環境に感謝しています。新春にふさわしい能として、お客様に喜んでいただけたならうれしい限りです。
(平成22年1月 記)
(『邯鄲』を勤めて 小書「傘之出」の演出と展開―二年前の演能レポートも合わせてご覧いただければ幸甚です。『邯鄲』について、「傘之出」について、くわしく記述しています。読み物⇒演能レポートから検索してください。)
写真
『邯鄲』シテ 粟谷明生 国立定例公演 国立能楽堂 撮影 青木信二
能面 「邯鄲男」 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
『定家』を勤めて ー虚構の世界にみる真実ー投稿日:2010-03-07
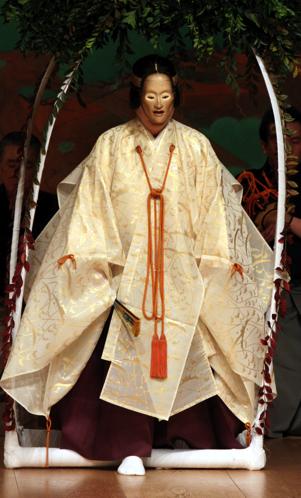

『定家』を勤めて
虚構の世界にみる真実
粟谷明生
粟谷能の会(平成22年3月7日)で『定家』を披らかせていただきました。54歳の披きは流儀としては幾分早く、このような恵まれた流儀の環境に感謝しています。
『定家』で思い出すのは、子どもの頃に「藤原定家と式子内親王は生きた時代が違うから二人の恋などは架空の話。でも能ではその嘘を承知でやればいいの」と話してくれた父の言葉です。もう40年以上前のこと。余談ながら父はこの曲を勤めずに他界しています。
能『定家』の物語が史実に基づいているかどうか曖昧だった時期もありましたが、冷泉家の「明月記」(定家の日記)が世に公開され、治承5年に藤原定家20歳、式子33歳の記載があったことから、13歳の年齢差が判りました。式子は53歳で亡くなり、定家は長生きで83歳の長寿を全うしたことも確定しました。しかし、能で語られるような二人の関係はなかった、というのが今の時代の定説です。父の「生きた時代が違う」という言葉は正しいとはいえませんが、たとえ二人の間に恋する関係がなくても、能には定家が式子内親王に恋慕して止まない心境が描かれているのであって、「能役者は嘘を承知で謡本通りに演ればいい」という父の言葉に間違いはなく、今でもあの時の事が頭から離れないのです。
『定家』の曲名は当初『定家葛』でした。しかし時が経ち「葛」の一文字が削られると、植物・定家葛よりも藤原定家という人物像が演者にも、また観る側にも強くクローズアップされるようになりました。
今回『定家』をご覧になられたご感想に、目に見えないながらも定家の存在感を感じた、というよりも、葛の印象が強く残った…と述べられた人の方が多かったのは意外でした。
私としては「定家の執心、葛となって、この御墓に匍い纏いて…」と稽古で何度も謡っていくうちに、定家の執心を葛という植物に置き換え、植物にとって切り離せない雨を、式子内親王の精魂に重ねるように仕組んだ作者の着想は奇抜で、面白さに改めて感心させられました。
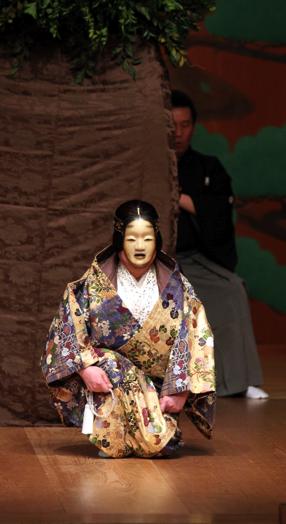
似たような曲に『西行桜』や『遊行柳』がありますが、「桜」や「柳」の文字を取って『西行』や『遊行』としては想像するものが変わってしまいます。植物の桜や柳に魂があり、神のように扱って、桜の精、柳の精を設定する能の演出は能独特の表現で、その曖昧さが面白さを増していると思われます。
『西行桜』や『遊行柳』はワキ役が西行法師や遊行上人という人物で実際に登場しますが、『定家』では、藤原定家を故意に登場させずに存在感を暗示させています。
あくまでも私見ですが、舞台上に定家を登場させないのであれば、今の『定家』の曲名を元の『定家葛』に戻した方が内容に似合っていると思うのですが…皆様はどう思われますか?
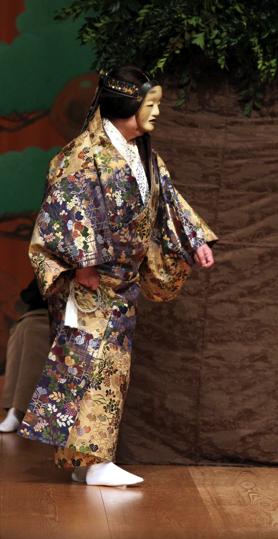
そのようなこともあり、今回は作り物の塚に付ける定家葛に拘ってみました。
まず葉の色と大きさです。定家葛は常緑樹であるため緑色の葉を付ける演者が多いのですが、私の知る冬の定家葛は、鮮やかな真紅ではないまでも紅葉しています。先人達の中にも作り物に赤い葉を使用した例もありましたが、葉の形や大きさがとても定家葛とは思えないもので、非常に違和感を覚えていました。そこで今回は、新たに葛の造花を作ることにしました。

<
br />写真 『定家』シテ十六世喜多六平太長世 撮影 あびこ喜久三
葉の大きさは本物の定家葛の葉と同じにし、緑色の葉と紅葉した葉を取り混ぜて構成してもらうよう、フラワーデザイナーの小島真佐江氏に依頼しました。引廻を付けた前場では常緑の葉を匍わせ、引廻を下ろすと上部は緑色、下部に下がるにつれ徐々に紅葉していくようなグラデーションをきかせてみました。また従来のように定家葛を作り物の柱にグルグルと巻き付けるのをやめ、匍う感じを出すために、付け方も糸で止めるやり方にしました。ただし当日、細かく多めに糸付けしなかったため、匍う感じが今ひとつ際だたなかったのは心残りで残念でした。
抽象化されている能の作り物ですが、あまりに実物とかけ離れていているものは観る側の想像に支障をきたします。と言っても演能後に映像で見て、舞台装置として考えた時には、もう少し葉が大きい方が舞台効果が上がったかもしれないと悔やんでいます。ご覧になられた方は如何に思われたでしょうか?
喜多流の『定家』は高位の重い習物として扱うため、他流が前シテに若い女性の面「増女」などを使いますが、喜多流は「曲見」を付け中年女性で演じます。また後シテは他流が「増女」や「泥眼」を選ばれていますが、喜多流では悲壮感の強い「痩女」を決まりとしています。
「曲見」は式子内親王の亡霊を中年の女性とすることで曲の位を高める効果がある反面、演者にとっては落ち着いた中年女性の雰囲気を身の構えと謡い方で演じる必要があり、難易度が上がり苦心するところです。

伝書には「若輩の者この能を致すならば小面にて色ある唐織着て苦しからず」と但し書きがありますが、私はこれまで「小面」の『定家』を見たことがありません。この但し書きは宗家などが若くしてどうしても演らなくてはいけない状況での補足であって、一般的には若き者が勤める曲ではない、という、むしろ戒めの言葉だと理解しています。
後シテの「痩女」は、頬の肉が落ち、目元もこけて目は虚ろ、苦悩し疲れ果てている表情で、式子内親王の苦悩を最大限に発揮します。喜多流では「痩女」を付けるとき、特殊な「切る足(一歩一歩細切れのように動く歩行)」を組み合わせる習慣があります。そのため楽屋内では、余計に老女物に準じる意識が高まっているようです。この「切る足」は足の扱いのさじ加減が難しく秘伝とされています。先人たちはかなり過剰に一足一足を躓くかのように演られていましたが、若い時分に拝見して「なにもあそこまで、よたよたのお婆さんにならなくてもいいのに…」と、生意気ながら思ったものです。

近年、友枝昭世師はそれまでの過剰気味の運びにメスを入れられ、単なる老いの動きだけではないものにと、改善されました。必死に自由に動きたいが、肉体はやせ細り体力も衰えてしまってどうにもならないもどかしさ、その不自由さ、アンバランスな心と身体、その葛藤を内に秘めた歩行こそが「痩女」の足遣いではないかと私は解釈しています。
実は、稽古当初は出来る限り普通の運びにと挑みましたが、不思議に「痩女」の表情が思い浮かぶと、それは出来ませんでした。これも面の力のなす技なのかもしれません。
これは私の身勝手な好みとしてお聞き頂きたいのですが、「痩女」の面は、どんなに痩せこけた表情でも貧相であってはいけない、と思っています。「昔はさぞお綺麗だったでしょうね…」という面影が残っていてほしいのです。『定家』はもちろん、『砧』にしても『求塚』にしても、シテの女性は生前美しく、それなりの身分ある方々です。いくら妄執にかられ苦悩しているとはいえ、あまりに汚ならしいお顔はご遠慮したいです。痩せ衰えながらも美しさや憂いがどこかに感じられる「痩女」、そのような面を探し求めて、今回は山中家の「痩女」を拝借しました。
「痩女」でのエピソードが一つあります。以前太鼓の観世元信先生が喜多流の『砧』を打たれた時、わざわざシテ方の楽屋にいらして「後シテの面を拝見させて下さい」とご覧になり「なるほど…。むずかしいね」とつぶやかれました。
この「むずかしいね」が当時は太鼓の出端の位作りのことだと思っていましたが、今思うに、曲そのもののむずかしさを言われていたのではないか、と思い直しています。
『砧』も『定家』も同様、「痩女」だけに限ったことではありませんが、面を付ける演者は面が何を語りかけようとしているのか、を見極めることが大事です。面の持つ力を役者の身体に浸透させ覚えさせ、どのように表現するか、そこが極みだと思います。能を観る方々には能役者のその力量に着眼して観てほしいものです。演者はよい面を付けることが第一ですが、そこで安心することなく、面の力を引き出す技を磨かなくていけない、これが『定家』を勤めての大きな収穫だったように思われます。

能の善し悪しは地謡で決まる、と言っても過言ではありません。
特に『定家』や『小原御幸』などはシテもさることながら地謡の出来不出来が演能の善し悪しを大きく左右します。
楽屋内の話で恐縮ですが、大曲・稀曲を大事にするあまりに、ただゆっくりと、慎重に謡えば成立するというのは誤りです。謡本にゆっくり、しっとりと、じっくり、と書いてあるからと鵜呑みにしてただ鈍重にノリ無く謡っては本物とは言えません。「なんでもノリがある、ノリが大事なんだよ」とは父の口癖でした。「丁寧に謡うのはいいが、頭に馬鹿の二文字がついては価値がないんだよ」と付け加えたのも父です。
ではどうすれば馬鹿が付かない丁寧な良い加減を体得出来るのか、いつも自問自答していますが、結局は良い意味での慣れだと思います。
大曲・稀曲は頻繁に謡うことが少ないので、どうしても慎重に、控えめにと位取りしてしまう傾向があります。しかし大曲・稀曲であろうとも手慣れていけば、ほどよい本当のノリというものが判り体得出来きてきます。そこを知ることが第一だと考えています。
今回の地謡は私より年下の仲間に集まっていただいたため、『定家』を謡うことは重荷だったと思います。しかし父の考えや、私のとり組み方を是非この機会に理解してもらい、臆することなく慣れることで、本当のノリと、引く息の強い訴えかけある謡を目指してもらいたいと希望しました。勿論、慣れ過ぎはいけませんが、経験不足の若者たちにより多く経験してもらうことで、『定家』を遠くて高い神棚にある曲から、もっと間近に引き寄せてもらいたいのです。当日、皆真摯に必死に謡ってくれ、居クセの足の痛さも感じない程で、私の望んだことはほぼ成し遂げてくれたと喜んでいます。もし私の定家がある評価を受けたならば、それは三役も含め、地謡力に助けられたから、と私は声を大にして言いたいのです。これからの彼らに大いに期待が持てると確信しています。
稽古しはじめて不思議に思ったことがあります。
それは何故、式子内親王が僧の弔いにより折角定家の呪縛の定家葛から逃れられるようになったのに、また身動きがとれない苦しい元の塚に戻るのか? ということです。「一味の御法の雨の滴、皆潤いて」とあるように薬草喩品(やくそおゆほん)の読経は時雨の滴のように葛の束縛力を解く効き目を発揮し、式子内親王は自由になって開放されたのです。それなのに何故?
稽古を重ねていくと、自分なりの答えが見えてきました。
それは、読経や雨の効力には時間の制限があるのだろうということ。
そして、式子内親王は成仏するより定家葛にまとわれていたかったのかもしれない、仕方なく塚に埋もれるのではなく、納得して自ら塚に戻ったのではないか・・・と。
実際の年齢は、定家が式子内親王より歳下ですが、式子内親王は53歳で亡くなり、定家は83歳まで生き延びています。
式子内親王の死後、定家は式子内親王の父親みたいな存在に変わっていったのでないか…というのが私の推測・仮説です。
定家自身死ぬまでは、式子の墓は私がお守りすると誓っていたでしょう。しかし自分の死後はどうなるのだろうか、と不安にかられます。そしてその想いは遂に、死後は式子内親王の守り神になろう、たとえ草木になったとしても墓をお守りするのだ…と、こんな想像を巡らせてしまいます。

しかし式子内親王にとってはそういう親心みたいなものが煩わしいのです。愛情とは判っていながらも、時として鬱陶しい…、親を煩わしく思う子ども心のようなものがあったのではないでしょうか。
ですから、二人の関係は肉体的なものではなく、親子愛のような純粋な、それも歌の世界という特殊な環境だけで繋がったものを感じるのです。
式子内親王の激しい恋の歌は実体験から詠まれたものではなく、情熱的な恋への憧れであっただろう、という論説もあります。現実とは別に虚構の世界で遊び戯れていたのかもしれないのです。
勿論、このように考えながら当日舞台を勤めたわけではないのですが、心の片隅にそんな空想を思い巡らせていたことは事実です。
作者の金春禅竹もおそらく、優れた歌の詠み手だった二人に思いを馳せたのではないでしょうか。美しくも激しい歌を詠む式子内親王の父は、あの源平争乱の時代をくぐり抜けた後白河法皇であり、兄は平家打倒の宣旨を出し、後に敗死した以仁王であるという事実。式子は否応なしに歴史の渦に飲み込まれ、翻弄されて薄幸な人生を終えたのです。高貴で美しく才能ある悲劇の皇女・式子内親王と、身分の差はありながら、当時の歌壇で第一人者となった定家の間に、和歌を通しての純粋な恋の話を創造することは、能作家・禅竹の野心であり、夢だったのではないでしょうか。二人の恋は真実ではなく、あくまでも虚構の世界のものだったとしても、互いの歌を認め合い、尊敬しあうという真実はあったかもしれません。禅竹は歌に生き、歌という芸術に殉じたともいえる二人の真実、二人の共通項を見つめていたのかもしれないのです。

いろいろと想像は膨らみます。しかし、「互いの苦しみ離れやらず、共に邪淫の妄執を弔って下さい」という謡の詞章から何を想像するかは、やはり観る方のご自由なのです。すべてご覧になる方にお任せする、それが能の魅力だと、今、再認識しています。
結局、父の言葉通り、演者は舞歌の基礎力と応用力を駆使して、虚構の世界を胸をはって演じればいい、ここに落ち着くようです。
この結論に至ったことと式子が塚に戻ってしまう行動、この二つ、どこか似ている感触を得たのは、演能が終わって数日経ってのこと、ふっと気持ちがほどけたときに感じたのです。
(平成22年3月 記)
『定家』出演者
ワキ 宝生欣哉
アイ 石田幸雄
笛 一噌幸弘(一噌仙幸代役)
小鼓 鵜澤洋太郎
大鼓 国川 純
地頭 長島 茂
副地 狩野了一
地謡 金子敬一郎 内田成信
佐々木多門 粟谷浩之 大島輝久 佐藤 陽
粟谷能の会『定家』シテ 粟谷明生舞台写真 撮影 石田 裕
面「曲見」粟谷家蔵 面「痩女」山中家蔵 撮影 粟谷明生
『土蜘蛛』を再演して投稿日:2010-02-17
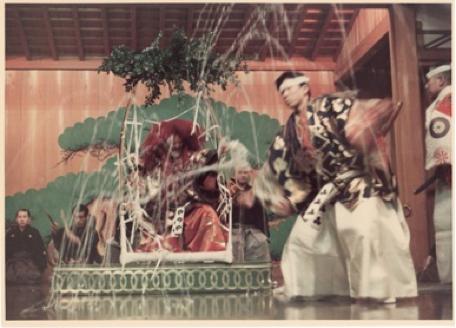
『土蜘蛛』を再演して
栃木県宇都宮市で文化庁「地域芸術振興プラン推進事業」として、喜多流の能『土蜘蛛』が市文化会館小ホールで催され(平成22年2月17日)、前シテを粟谷能夫が後シテを私が勤めました。
『土蜘蛛』は演能出来るまでの舞台裏の仕込み作業に時間がかかる曲です。
塚の作り物を作り、柱に巣を巻きつけ、大きな一畳台の運搬もありで、地方公演ではどうしても敬遠されがちです。出演者も多く、シテの他にツレが頼光、胡蝶、太刀持と3名、ワキもツレを数名出しますので大人数となります。そして投げる巣糸そのものの購入にもコストがかかるので、いろいろ物入りで、経済的に余裕がないと上演出来ない曲、というのが舞台裏の事情です。
私が最初に『土蜘蛛』に携わったのはツレの胡蝶役を勤めた時、まだ13歳(昭和43年、シテ・粟谷新太郎)でした。当時は若年のため面の使用が許されず直面で勤めました。それから3年後、16歳の時にシテの初演となりました。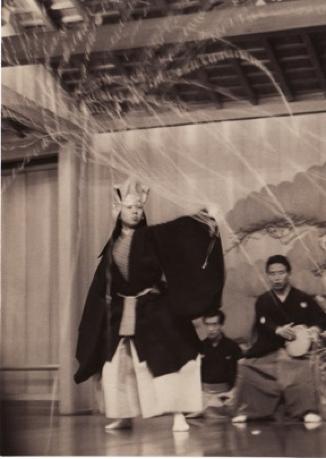
その時は、頼光に粟谷能夫、胡蝶には弟の知生、太刀持に父の愛弟子・丸山邦夫氏という粟谷関係者で配役し、ワキも私と同じ年の森常好氏がやられ、お父様の森茂好先生がツレをなさいました。
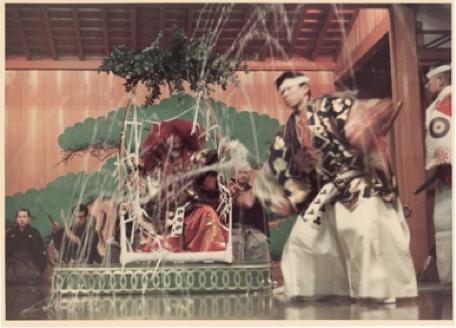
間狂言は野村耕介氏(故野村万之丞氏)でした。当時、出来るだけ若い人でやろう、と粟谷兄弟能の伯父や父たちの考えで出来た企画だったことを覚えています。
その後、頼光や胡蝶は何度も勤めてきましたが、今回のシテは38年ぶりとなり、当時の巣糸を投げた感覚を思い出すのに時間がかかりました。

『土蜘蛛』の物語は、病床の源頼光のところに胡蝶が薬を持って見舞いに来ます。気が弱っている頼光に胡蝶は慰めの言葉をかけ退出しますが、病室にはいつのまにか僧(前シテ)が近づいてきています。不審に思った頼光は名を尋ねますが、僧は蜘蛛の巣糸を投げかけ蜘蛛の本性を現して頼光に襲いかかります。しかし頼光が太刀で蜘蛛を斬りつけるとそのまま姿を消してしまいました。物騒ぎを聞き駆けつけた独武者(ワキ)はことの子細を聞くと、蜘蛛の血のあとを追い退治に出かけます。血は葛城山の古塚にと続いていて、塚を崩すと中から土蜘蛛の精魂(後シテ)が姿を現します。巣糸を繰り出して武者に抵抗しますが、遂に斬られ退治されてしまいます。
という単純な鬼退治の物語です。
鬼退治の能は『大江山』や『羅生門』などがありますが、『土蜘蛛』は実際に蜘蛛の巣糸を投げて見せるショー的なところが観ていても楽しく面白い能です。特に子どもさんを対象にした催しや、中学高校生などの学生能などでは人気が高く、たくさん観せてあげたいのですが、諸々の経費の事情で、なかなか上演しにくくなっているのは残念なことです。

『土蜘蛛』を勤める時、どうしても蜘蛛の巣糸がきれいに投げられるかが気になります。私も演じる寸前まで心配でしたが、綺麗な投巣のショー的な要素だけで終わってしまうと、単なるドタバタ劇能となり、本当の能とは言えません。能としての面白さは、演者の技巧もさることながら、土蜘蛛族という先住民の被害者の恨みをどのように演じられるかにかかっています。
大和朝廷から侵攻、侵略された土着民の悲哀がどこかに表現されなくては、この能は面白くないと思います。今回、私は後シテだけを勤めましたが、常の「シカミ」の面ではなく、敢えて伝書に書いてある替の面「長霊ベシミ」を試してみました。先日の『青野守』(能楽座日立公演:2月11日)で使った「黒ベシミ」でもよいかと思いましたが、能『熊坂』の専用面「長霊ベシミ」のほうがどこか間が抜けて滑稽な人相をしていて、なんとも憎めない敗北者のイメージにピッタリだと思ったからです。
ご覧になられた方々のご感想をお聞きしたいものです。

若い時は、どうしても投巣の時に焦ってしまい、うまく投げられないでハプニングも起きます。しかし本来は落ち着いた威勢の中に土蜘蛛族の精魂の復讐心を演じることが大事で、千筋の糸を吐きかけ独武者たちを苦しめながらも、勢いが次第に弱って最後は退治されてしまう、その無念さをも演じなければ土蜘蛛を勤めたとは言えないと思っています。
退治される鬼たちの悲劇は、我々芸能者にも通じるものがあると感じます。
侵攻する朝廷側について演じる猿楽師。その能役者は朝廷側が退治する鬼という敗北者を演じなければならない境遇にあるのです。何故か土蜘蛛の精魂を演じていてこの先住民に同情したくなるのは、不思議なことではないのかもしれない、勤めていて、そのように思いました。
(平成22年2月 記)
(写真資料)
『土蜘蛛』後シテを楽屋裏にて シテ粟谷明生 撮影 森 常好
16歳の前シテ 粟谷明生 撮影 あびこ喜久三
16歳の後シテ 粟谷明生 ワキ 森 常好 撮影 あびこ喜久三
楽屋鏡の間にて
シテ 粟谷明生 頼光 粟谷能夫 胡蝶 粟谷知生
撮影 あびこ喜久三
後シテ粟谷明生 後見 粟谷菊生 撮影 あびこ喜久三
面 「長霊ベシミ」 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
写真無断転載禁止
『石橋』親獅子を披いて投稿日:2009-10-11

『石橋』親獅子を披いて
粟谷明生

粟谷能の会(平成21年10月11日)にて『通小町』を勤めた後に半能『石橋』連獅子のシテを披きました。今までにツレ(子獅子)を7回勤め、最後は平成13年10月の粟谷能の会でした。あれから8年が経ち、この度、念願の親獅子を披くことが出来ました。ツレは従兄弟の粟谷浩之君で、こちらもツレの披きでした。
第86回粟谷能の会はちょうど亡父菊生の正命日に当たり、丸三年の月日が経ちました。洵に月日の流れの早さに驚いています。
私は、残念ながら父の子獅子は観ていませんが、親獅子は何度も観ています。
いつかあのように力強く舞いたい、と憧れていました。
父の親獅子は子獅子と変わらないほど軽快で俊敏に動き飛び廻る躍動感溢れるものでした。高齢なのによくあの様に激しく動けるものだと身体的な強靱さに驚き、感心させられたものです。
以前、囃子科協議会で『石橋』連獅子があり、親獅子を粟谷菊生、子獅子に友枝昭世氏という豪華配役がありました。その時もどちらが親で、どちらが子なのか判らないほど二人の勢いは凄まじく、兎に角、身体のキレの利かせ方が上手で、走り回り飛び回って他流の方々もいる楽屋を驚かせていました。「菊ちゃん、お若いね、よく動けるね」と他流の方から声を掛けられると、にやっと笑っていた父の顔が忘れられません。私は、親獅子というものはあのように素早く軽快に動くものだと思っていました。
ところが平成4年、私が友枝昭世氏(シテ)との連獅子を終えた後に、父が友枝氏にすっと近づき「昭世ちゃん、やはり白(親)はあのぐらいゆったりと、頭の振り方も、ゆったりとした方が親らしいね。我々のは、ちょっと動き過ぎていたね」と笑って話していたのを聞いてしまいました。確かにそうです…。私もそれから、ゆったりとしなければ親の貫禄は出ない、と思うようになりました。シテ(親)はツレ(子)よりどっしりとゆったりと、やや遅れめに動き、子の軽快さ俊敏さを引き立てる、それこそ親の役目なのでしょう。
私は数回の子獅子の経験から、いざ幕を上げて出て行くシテの後ろ姿が目に焼き付いています。シテの「おまーく」の力強い掛け声で揚げ幕が勢いよくサッと上がり、橋掛りへ出て行く後ろ姿、それを子は見て真似るのです。
父の出は、スーッと本舞台に吸い込まれるように滑らかに出ていく風でした。友枝昭世師のは、目の前にある重厚な固まりがズカー、ズカーと一歩一歩地響きを起こすが如くに、進むように見ました。どちらもすばらしく憧れます。それでも父には悪いのですが、今の私は地響きが好みです。
連獅子のシテは子を引き立たせることが役目で最優先といいますが、唯一シテの本領発揮の見せ場もあります。それは幕が上がってすぐの場面です。シテが進み出て三の松で一度ピタッと止まり、乗り込む拍子を踏むと次第に囃子のノリも進み、シテは徐々に加速して二の松から急進し一の松で身を乗り出し踏ん張って止まります。牡丹に向かいまるでライオンが「グア??」と叫ぶ様に面を大きく切る、ここの型が決めどころです。そして左右に三度、牡丹に戯れるように乗り込み拍子を踏みます。獅子の気分は最高潮に達し、喜びを表し、右回りに一回転飛びして右足を宙高く上げて一旦止まり、拍子を踏みツレに合図します。ここが最大の見せ場となります。

ここが決められるかどうかが、シテの善し悪しの判断基準になります。ドンと強く足拍子を踏み、子獅子に「さあついておいで、という気持ちでやるんだ!」とは父の言葉です。そして親の役目はここで決まり、あとは子獅子の世界だ! とも言っていました。さて、私がそのように出来たかどうかは別として、そのような意識をして勤めたことに間違いありません。
今回、ツレとの数回の稽古で浩之君には、私が父や友枝師から教えていただいたことを、私の言葉で伝えたいと思いました。常に牡丹に戯れる気持ちを忘れないこと、牡丹の匂いを嗅いでじゃれる獅子という動物である意識、それらを忘れないこと、胸を張り、首筋をきちっと決め、腰で舞うなどと言いながらも、実は自分に言い聞かせていたのです。

今回親獅子というものを経験して、昔のようにシテが自由な気分で動き回るのは荒々しさがあって良いかもしれませんが、現代はどっしりと力量感に溢れた親獅子というイメージで、このように変わっていくのだろうと感じました。
なんでも昔がよかったと丸呑みにする前に、本来どうあるべきかを再度調べる、それを忘れていけないと改めて思っています。

楽屋裏話になりますが、昔はこうだったと、まかり通っていることがよく調べてみると、意外と伝承の読み落としや読み違い、勘違いだったということもあるのです。間違いや勘違いが悪いというのではなく、何でも疑ってかかるのも行き過ぎかもしれませんが、能の本質、本物に気付く努力をしてこそ正統な伝承と言えるのではないでしょうか。
古典や伝統・伝承という言葉に頼り、甘えるのだけはしたくない、と思っている昨今です。
(平成21年10月 記)
写真 『石橋』 連獅子 シテ 粟谷明生 ツレ 粟谷浩之 粟谷能の会
撮影 石田 裕
『通小町』を勤めてー演出の工夫の重要性ー投稿日:2009-10-11

『通小町』を勤めて―演出の工夫の重要性―
粟谷明生
粟谷能の会(平成21年10月11日)で『通小町』を勤めました。
『通小町』は八瀬の里の僧が毎日木の実や薪を持って来る女の素性を尋ねると、市原野に住む姥で弔ってほしいと言い残して消えます。僧は姥が小野小町の幽霊と察し弔うと、薄の中から小町の亡霊が現れ僧に授戒を願います。すると深草少将の怨霊も現れ、小町の成仏を妨げようとします。僧は深草少将に懺悔のために百夜通い(ももよがよい)を見せるように説くと、少将は雨の闇路を小町のもとに通い無念にも九十九夜目に本望をとげられずに果てたことを語り狂おしく見せます。そして飲酒戒の戒め、佛の教えを悟った途端に多くの罪業が消滅して、少将も小町も一緒に成仏出来たと喜び消えていく、という物語です。
この曲は観阿弥作と言われ、通常の様式とは違った特異な構成です。シテ(深草少将の霊)は後場にしか登場せず、その代わりにシテツレ(小野小町の霊)が前場と後場に登場し、舞台進行役を勤めます。このツレ役はシテと同格・同等といわれる大役ですが、私はあまり意識過剰になり、シテのようになってはいけないと考えます。あくまでもツレはツレの立場、その許容範囲を超えずに勤めるのがツレの心得だと思います。
ツレは絶世の美人、小野小町ですから演者は立ち姿を良くし、謡も張りのある高音の声で、ちょっとツンとした冷たい感じの美人小町になれば、これが私の理想です。このツレ役、我々は指名されると嬉しい反面、その責任の重さを感じます。なんと言ってもツレとしての位をつくるのが難しく、これは何度も経験することでしか習得出来ません。
喜多流は観世流、宝生流と違い、前場の木の実尽くしの段の前にサシ謡(かたじけなき御譬なれども・・・)があります。ここの節扱いは難しく聞かせどころです。昔、父に「上がる音が違う、もっとやさしく張って謡え」と注意されたことを思い出します。今回、長島茂氏に私のツレの考え方を伝え、この大役をお願いしました。それに応えて勤めて下さったことに感謝しています。
前ツレは「市原野辺に住む姥…」と謡本にあるように小町の化身で老女です。しかし現行の演出は、前場も後場も若い女の扮装(紅有唐織・小面)のため詞章と姿が咬み合わなく、この似合わぬ扮装は演者からも観客からも、おかしいのでは…と言われています。
そのため近頃は前場のツレの装束や面を替えるのが流行っています。姥なら本来、鬘は白髪、面は「姥」ですが、中入で鬘を替えるだけの時間が無いので、今回、姥姿は諦め、鬘を替えずに装束を紅無唐織(いろなしからおり)にして面は「深井」にしました。後場は若き日の小町として再登場するので、中入で紅入唐織(いろいりからおり)に着替えます。短時間での着替えは忙しいので、あらかじめ装束に仕掛けをして、着付ける者も付けられ者も無駄を省き手際良く物事を運ぶことに集中します。
後場は普通、一声(いっせい=出囃子)にて、ツレは本舞台常座に入り、シテは橋掛り一の松辺りに立ち、無地熨斗目を頭から被り、被衣(かずき=姿が見えないことを表す能の約束事)の格好で問答となります。これは長時間屈んだままの姿勢なので息がしにくく謡いづらいもので、しかも無地熨斗目を持つ手が次第に痺れてきて肉体的にも非常に辛い演出です。「初演は被衣で…」という流儀の決まりがありますが、私は二度目ということで許して戴いて、被衣ではなく揚げ幕の内側に床几に腰掛けての問答としました。
幕の内側で謡う場合は、演者の声がしっかりと会場の隅々まで聞こえなくてはいけません。しかし、どうしても面を付け、揚げ幕の内側に居ると聞こえづらいようです。特に国立能楽堂のように長い橋掛りでは声の届きが悪く、演者は大きな声を意識しますが、ただ単に聞こえればと馬鹿でかい声では成立しません。地獄の暗闇からの亡者の叫びに聞こえれば良いのですが…。地下から呪いの声が聞こえるようで怖ろしい、と観客に思っていただけたら演者としては成功です。私も声の大きさには自信がありますが、どうも思ったほど充分に聞こえなかったようなご意見もあり、もっと大きな声を出す必要があるのかと、反省し勉強になりました。

演出の工夫に装束選びもあります。
普通は水衣に大口袴の出立ですが、替装束として狩衣・指貫(さしぬき)もあり、指貫の姿は少将の霊という優美な姿となります。初演は指貫で勤め、実は今回もそのようにと思っていましたが、同じ日に『葛城』で緋色指貫を使うことになり、指貫が続くのは好ましくないので、私は大口袴にしました。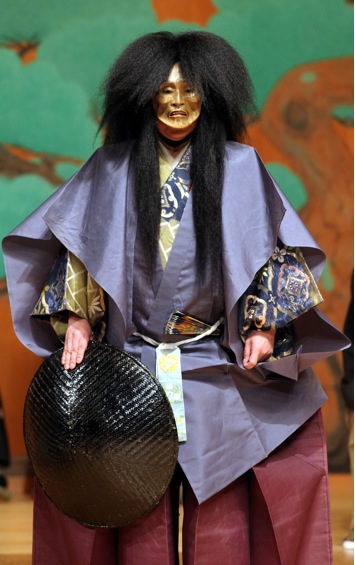
指貫と大口袴の違いは単に格好が違うだけではなく演じ方も変わります。指貫は雅な風でやや柔らかな動きでも似合いますが、大口袴は鋭さや強さが必要となります。今回は大口袴で力強い少将をと心掛けましたが、如何でしたでしょうか。皆様のご意見をお聞きしたいです。
さて、少将が雨夜、小町のもとに通う道中をカケリ(立廻り)で演じます。笠を両手に持ち頭を隠して静かに目付柱まで行き、一旦遠くを見上げると、また屈んで左廻りをして大小前にて廻りながら、笠を落とします。
何故落とすのでしょうか?
風が強く吹いたとも、雨に濡れた手が滑ったとも、いろいろ観る側の想像にお任せするところです。少将は暗闇の中、手探りに笠を捜し見つけ取ると「あ?ら暗(くら)の夜や」と低い調子でありながらも、まだ諦めない強い気持ちを込めて謡います。このような調子も、経験を積まなければ出てこないものです。
今回、特別に小鼓の大倉源次郎氏にお願いして、カケリの手組に干流しと乙流しを打ってもらいました。チ・チ・チ・・・・と干(かん)の小さな高い音色からはじまり、笠を落とす寸前にポ・ポ・ポ・・・と乙(おつ)の低い透き通る音に替わり、笠を落とした途端に通常の手組に戻ります。小鼓の音色の変化で雨夜の百夜通いを聞かせますが、その音色が、雨の音とも、また忍び歩く足音ともと想像して演じましたが、演能後、大倉氏は少将の心音を打つ気持ちで打ったと言われました。ひとつの音色もいろいろな聴き方、捉え方がある、能はそれぞれ個人の自由に想像して観賞するものなのです。
このような演出は他流の雨夜之伝にはありますが、喜多流としては今までに取り入れたことはありません。「喜多流にないものを…」と苦言を呈する方もいらっしゃるやもしれませんが、しかし私はこれからの時代、能楽演者はより良い舞台を提供するために、いろいろなものを受け入れ試みるのがよいと思っています。それが良いものならば必ず残り、似合わぬ物は自然と消えていくでしょう。それでいいと思うのです。消えるだろう、似合わぬだろうと頭から決めつけるのではなく、最善の工夫を凝らすところに価値があるのではないでしょうか。勿論、いろいろな試みを取り入れるには能楽師として技術的なものを会得した上でという条件付は当然の事ですが…。
能には理屈や詞章に合わないことがたくさんありますが、総てを理詰めにする必要はないでしょう。しかし、現代に似合う演出を可能な限り捜し出す作業も能役者の忘れてはいけない大事な仕事です。演者側の都合ばかりを優先するのではなく、ご覧になられる方が舞台で起きていることが、スムーズに判りやすく想像出来る、そのような舞台環境作りを志したいのです。
今回も能役者の工夫ということで、いろいろ試してみた『通小町』でしたが、
鬘を取り替えることが難しいからと諦めた姥姿も、鬘の上に白い毛を乗せる仮髪を用いる方法がすでに試みられていることを後日知り、驚かされ感心してしまいました。
あ?何でそこに気が付かなかったのかと、自分に悔しい思いもしましたが、そのように考え、挑まれている方がいらっしゃるかと思うと、心強く嬉しくもまた励みにもなります。次回『通小町』を演るときは、是非それを導入したいと思います。
能をようやく考えて舞えるようになり、今能が面白くてたまりません。
「考えて舞っているようじゃ本物ではない…」という父の嘆きの声が聞こえて来そうですが、考えないで舞える、そのような高位になるには、充分に考え、考え抜いて、というもがき苦しむような時期があってもいいのでは、そんな状態を通過しなければ訪れてこないのでは…そう自分に言い聞かせています。屹度父も判ってくれるのではないでしょうか。(平成21年10月 記)
写真 粟谷能の会 平成20年10月
シテ 粟谷明生 ツレ 長島 茂 小鼓 大倉源次郎 大鼓 亀井広忠
撮影 石田 裕
『鵜飼』についてー闇と光の間からー投稿日:2009-08-31
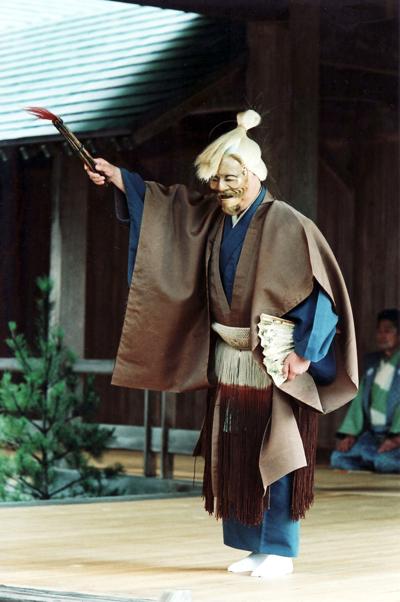
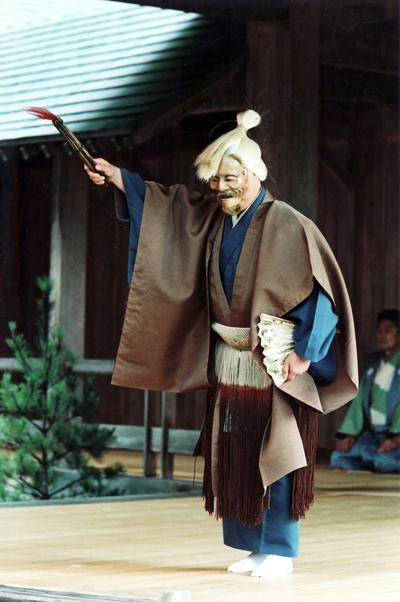
秋田大仙市の「まほろば能」(平成21年8月31日)にて『鵜飼』を勤めました。
『鵜飼』の物語は、安房国(千葉県)清澄の僧(ワキ)が従僧(ワキツレ)を連れて甲斐国(山梨県)へ行脚の途中、石和川(現・笛吹川)に着くところから始まります。
僧達は土地の者に宿を頼みますが、旅人に宿を貸すことが出来ない土地の決まりがある、と断られ、川沿いの御堂に泊まることにします。
夜も更けると、鵜使いの老人が現れ、鵜を休ませています。僧は高齢での鵜使いの仕事は身体にきつく、殺生の生業は佛の教えに反すると他の職を薦めますが、老人は若いときからやっているので、今更変えることは無理だと言い返します。
従僧は老人が、以前自分に宿を貸した鵜使いであったことを思い出すと、老人はその者は殺生禁断のこの川で鵜飼をしていたのが見つかり、簀巻きにされ、殺されたと語り、実は自分はその亡霊であると明かし、僧に回向を願います。
僧が回向を約束すると、老人は鵜使いの有様を見せて、名残惜しげに闇に消えて行きます。
(中入)
僧たちが土地の者に鵜使い簀巻きの話を聞き、供養のため法華経を川辺の石に一字ずつ書いて川に沈めていると、閻魔王が現れ、生前殺生をした鵜使いは無間地獄に行くべきだが、僧に宿を貸したことと、法華経の回向があった利益により、鵜舟に乗せて極楽へ送ると告げ法華経を賛美して消えて行きます。
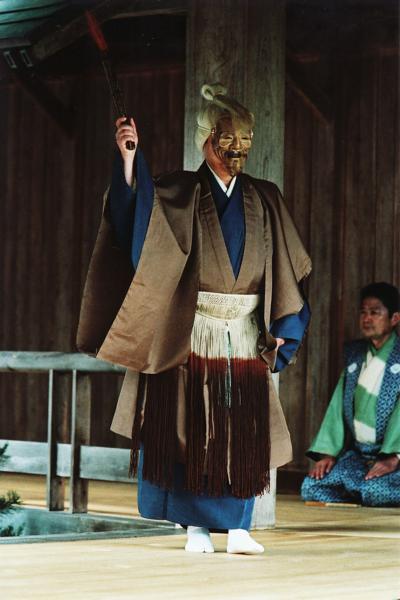
私は「鵜之段」(「湿る松明振り立てて・・・」から中入までの仕舞どころ)を舞うときにいつも不審に思っていることがありました。私の想像する鵜飼漁と仕舞の動きに、似合わぬちぐはぐさを感じていたからです。
そこで今回演能にあたり石和川の鵜飼について調べてみました。
すると、石和地域の鵜飼漁は徒歩鵜(かちう)と呼ばれる鵜匠が川の浅瀬に入るやりかたであることを知りました。
鵜飼というと、鵜舟に篝火を灯し、鵜匠と舵取りの二人が乗り、鵜匠が数羽の鵜を操る長良川の鵜飼いを想像していましたが、石和地域ではそうではないようです。
「鵜之段」は、右手に松明を持ち左手は中啓にて鵜の動きや鵜使いの様を見せるむずかしい型所です。その動きは、まさにひとりで鵜を操る様子を見せます。
この型を考えれば能『鵜飼』も徒歩鵜と考え何も支障はないのですが、ここに一つ問題があります。『鵜飼』で謡われる「鵜舟」という詞章が引っかかりました。
「鵜舟に灯す篝火の・・・」「櫂も波間に鵜舟漕ぐ」「鵜舟の篝 影消えて・・」と鵜使いが舟に乗っていることを示す謡が随所にあるのです。
私は能『鵜飼』の鵜使いは、やはり一人で行う徒歩鵜をしていたと思いたいのですが、どうしてもこの謡が気になります。
『鵜飼』は榎並左衛門五郎の作に世阿弥が改作したと言われています。作者たちが徒歩鵜を知っていたかは謎ですが、あの鵜之段の動きはまさに徒歩鵜だろうと思います。
ではなぜ鵜使いは鵜舟に乗って登場するのでしょうか?
徒歩鵜をするにしても、現場までは舟を使っていた、とも考えられますが、まったく回答が出来ないでいます。しかし判らなくても出来てしまうのが、能の世界。それらしく謡い、型をきちっと真似れば作品は出来上がります。
今、このことを自分の中で解明出来ないまま能を勤めたストレスがあるのですが、能にはまたそのような矛盾点もあっていいのかもしれない、などと納得してもいるのです・・・。
何かご意見などがあれば、お教えいただきたいと思います。
次に前シテの語りの解釈について気になることがありました。
喜多流の謡本には、次の通り記されています。
「今、仰せられ候、岩落と申すところは、上下三里が間は堅き殺生禁断のところなり、鵜使い多し。夜な夜な忍び上って鵜を使ふ。何者なれば堅き殺生禁断の処にて鵜を使ふらん。憎し彼を見あらわし。後代の例に罧(ふしづけ:簀巻きにして水の中に沈める刑)にせんと狙ふをば夢にも知らず。またある夜忍び上って鵜を使ふ。狙う人々ばっと寄り。一殺多生の理に任せ。彼を殺せと言い合へり、その時左右の手を合わせ。かかる殺生禁断のところとも知らず候。・・・」
これを訳すと、「石和川の岩落ちという所は禁漁区域であるのに、鵜使いが多く密漁が絶えない。そこで石和の土地の者達は相談して、一人の鵜使いを掴まえ見せしめに殺し密漁を防ごうとした。ある夜、土地の者達が見張っているとも知らず鵜使いが現れ密漁をはじめたので全員で掴まえた。鵜使いは禁漁の場所とは知らなかった、もうしません、と助命歎願したが、土地の者達はだれも鵜使いの言うことを聞かず、遂に罧にして鵜使いを殺した」となります。
以前、観世座で配布された「鵜飼をめぐって・義江彰夫」に石和川の鵜飼について興味深いことが書かれていました。
義江氏は、石和という土地が、もともと伊勢神宮の御厨(みくり:荘園)であったことに注目しています。
石和地域は北条殿並びに、甲斐源氏が代々伊勢神宮の御厨として統治してきました。
諸国各地にある伊勢神宮の御厨では、魚介類が年貢の中心とされていたので、石和の御厨も同様に魚を献上していました。そのために特権を持った石和御厨の鵜使いが存在し、献上以外での漁を殺生禁断の名のもとに厳重に禁止していた、とあります。
このように考えると、岩落あたりは殺生禁断の場所ではあるが、一部特権階級の鵜使い集団がいるので、「鵜使い多し」ということなのでしょう。
では、夜になると忍んで鵜を使うのはどこの誰なのか?
また憎いと思い彼を狙った人々の素性は?と気になります。
義江氏の説明から考えると、殺された鵜飼いは石和村の特権を持たない一般の鵜使いか、または他の土地から来る外来の鵜使い、ということになるのでしょうが、二三年前に往来の僧を泊めたという詞章から外来の鵜使いというのは可能性が薄いように思えます。
私は罧というあまりに残酷な罰を、見せしめだからといって、同じ村の一般の鵜使いに行うのだろうか?とも思いましたが、逆にそこに悪行をした末の恐ろしさが書かれているのかもしれないと思います。

今回私は、石和川の一般の鵜使いの老人として演じました。
ですから、知らなかった、もうしません、との弁明の謡にも、裏があるように思えて、
真実知らなかった、というクドキ謡では信憑性がない、口からでまかせのような鵜使いのしたたかさも演じられたらと思い、そのような気持ちで謡いました。
判っているがやめられない、現代にも通じる人間の弱さ、今世間を騒がしている麻薬中毒患者たちの事件が、それを証明しています。そこには中世と現代の共通性があり、それを描いてきたことが、能を長年面白く感じさせ、継承させてきた所以だと確信しています。
では、憎いと思って彼を狙った者はだれか、普通は上記の訳のように「土地の者達が相談して」となりますが、実際は、利権を持っている者がその利権を脅かす行動に怒り、それを伊勢大神宮の名前を借りて戒める行動だと私は解釈しています。
それにしても、一殺多生の理、一人を見せしめとして殺し、今後、規則を破る者を防ぐ策としての考えは、現代の警察庁が芸能人をターゲットにして、日本の薬物汚染を一掃しようとするのに似ています。昔も今もなんら変わらないことを、能は取り上げているのです。
『阿漕』『烏頭』『鵜飼』の三曲を三卑賤といい、いずれも殺生の業を営む漁夫、猟師の苦悩がテーマとなっていますが、『阿漕』や『烏頭』は後シテが生前の姿の亡霊となり回向成仏を願い地獄の悲痛さを訴えるのに対して、『鵜飼』の後シテは閻魔王と別の人格となり、短い後場は終始、法華経の賛美でまとめるという珍しい構成です。
『阿漕』『烏頭』が密漁をすると苦しい地獄の責めに会うという殺生撲滅キャンペーン曲なのに対して、『鵜飼』は禁を犯しても法華経を信じれば救われるという救済キャンペーンの宗教歌になっています。
『鵜飼』の前場は、いけないと禁止されていても、それを破る性分、そしてその業の面白さにはまってしまう人間的なところを演じますが、後場は一変して閻魔という異次元の鬼になって、法華経を賛美、演じるので、演者としては少々やりにくさを感じる、というのが正直な感想です。ではその対応は?と聞かれれば、それは、教えの通り、淡々と力強く、どっしりとしたイメージで動き謡う、それに留まる、それが本音なのです。

『鵜飼』は「暗闇」と「月」という二つの言葉がキーポイントでもあります。
暗闇という迷い多き衆生の世界と真如の月と言われる明るく正しい世界。
暗闇を松明で照らし、鵜を使い魚を捜す鵜使いが、漁の面白さに取り付かれた様を舞う「鵜之段」の終わりに、月の光が漁の妨げになると嫌う鵜使いの心が地謡によって謡われます。
「不思議やな篝火の燃えても影の暗くなるは、思い出でたり、月になり行く悲しさよ」と。
月が出ることで篝火が利かなくなり漁がやりにくい、と鵜使い(前シテ)は嘆きながら、やがて篝火の消えるように闇路へ、闇の世界へと帰っていくのです。
昔は、型の動きや、決まりどころばかりに気を取られていた自分、この曲の面白さを教えてくれたのが闇の暗さというよりは、「月なのだ」ということを今回知りました。
「暗闇」と「月」、この対比された言葉を追うことで、『鵜飼』が描く世界の謎解きが一つできたような気がしています。
(平成21年9月 記)
写真 鵜飼 シテ 粟谷明生 撮影 石田裕
無断転用禁止
『雲雀山』についてー現在物のドラマ性を追求ー投稿日:2009-06-28

演能レポート『雲雀山』について―現在物のドラマ性を追求―
喜多流自主公演(平成21年6月28日)にて『雲雀山』を勤めました。
当麻曼荼羅で有名な中将姫が登場する能は『当麻』と『雲雀山』の二曲です。
『当麻』は中将姫が弥陀の来迎を祈念し、弥陀称名の教えの尊さを唱う宗教色濃い曲ですが、『雲雀山』は幼い中将姫を危機から救い、秘かに養育する乳母のけなげな奉仕や忠義心を描いた曲です。
最初に簡単に『雲雀山』のあらすじと舞台進行をご紹介します。
横佩右大臣豊成公(ワキ)は身内の讒言を信じ、我が子中将姫(子方)を、雲雀山で殺すようにと、家臣(ワキツレ)に告げます。家臣は命に従い姫を雲雀山まで連れて来ますが、あまりに可哀想なので殺すことが出来ず、庵を作り姫をかくまいます。同行した中将姫の乳母(シテ)は、四季折々の花を摘んでは、人里に出て花を売って姫を養っていました。
前場は、ある日、家臣が乳母を呼び出すところから始まり、物狂能特有の短い導入部分により、山奥に住む主従の環境を描きます。
後場は横佩右大臣が狩りに雲雀山へやってきて、遊猟の情景、短いアイの鷹を放す場面が入り、その後、後シテが束ねた花を肩にして登場します。花売りの場面と身上話のクセ、続いて姫を思う心持ちでの舞(中の舞)、短いキリが終わって、シテが雲雀山に帰ろうとすると、ワキが呼び止め、局面は一変して劇的な親子再会となります。最後はでめでたしめでたしと祝言の心で終わります。
中将姫が捨てられ生活した所は、奈良県宇陀市の日張山・青蓮寺(せいれんじ)と和歌山県有田市の雲雀山得生寺(うんじゃくさんとくしょうじ)の両説ありますが、ワキの道行、狩猟の名所、交野の地から考えると前者のように思えます。

徳友寺の中将姫の墓
青蓮寺には、姫を助けた家臣、松井嘉藤太晴時とその妻の静野の墓がありますが、能『雲雀山』では個人名は明らかにされません。それはより観る者に想像を膨らます効果を狙った能作者、世阿弥の手法ではないでしょうか。
乳母は花売りまでして姫を養育し再帰を願いますが、その一途な献身的な思いは実の母親に勝るとも劣らぬやさしい慈悲心です。
喜多流謡本の曲趣には「シテは狂女ではなく、普通の狂女物に比べると類を異にするようであるが、幼君を守りつつ山から里に出て花を売る中年の女性という点から一種遊狂の風格を備えたものとして、カケリ、中の舞があり、狂女能に扱われる」と解説しています。この「シテは狂女ではなく」の文言は誤解を招きます。
現代、狂女というと一般的に気がおかしくなった状態、言葉は悪いですが、気が狂った精神異常者のように思われがちですが、能はそうではありません。
一途な思いや気持ちの集中を「狂い」と言います。ですから姫への一途な思いの狂女として勤めました。
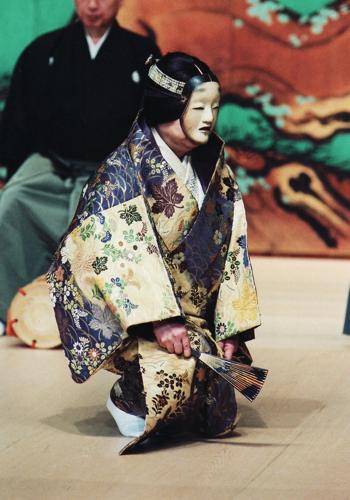
雲雀山 前
今回シテを勤めるにあたって気をつけたことは、いかに乳母の風格を出せるか、です。姫を思う中年女性をどのようにしたらうまく演れるかです。乳母は君主豊成の命に逆らって姫をかくまい養う、気丈な女性ですが、姫を慈しむやさしい女性でもあります。やさしく、やわらかに、やんわりと、三つの「や」の柔和な身のこなしを意識しました。

雲雀山 後
最後の豊成との対面では、はじめは姫がすでに亡くなったと偽りますが、豊成の前非を悔いた真心に打たれ、豊成を信じ、庵の場所を教えます。このワキとの問答がひとつの山場、作品の面白さに点数をつけるとしたら大事なポイントとなります。どんなにそれまでをうまく見せても、このやり取りの謡が白熱したものにならないと観る者の心は動きません。謡の間のとりかた、声の張り具合、音の高低差など、対峙する能役者同士の謡の緊迫感が、父子再会というお涙頂戴ドラマには不可欠です。思わず涙腺を緩ませる、そう仕掛ける巧み技が演者に求められています。
今回ワキを、人間国宝の宝生閑氏がお相手してくださいました。雲雀山に帰ろうとする乳母に「おーい乳母待て」とかけるワキの声で、一瞬空気が止まり、緊張した場面転換となります。シテもそれにじっくりと応えて、温厚ながらも気丈な乳母として勤めたつもりですが、ご覧頂いた方々には如何思われたでしょうか。
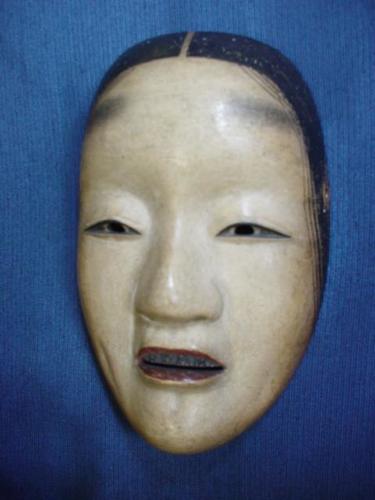
曲見の面 作者不明 粟谷家蔵
今回の面は、粟谷能夫が新太郎愛用の「曲女(しゃくめ)」もあると薦めてくれましたが、以前から一度使いたいと希望していた、銘はないものの粟谷家秘蔵の「曲見(しゃくみ)」にしました。これは近くで見るとたいしたことのない面に見えますが、舞台に上がると、中年の憂いと強さを秘めながらも、何とも位高いお顔に見える不思議な面です。『雲雀山』は夏の季節の曲目ですが、装束は梶葉模様の無紅唐織にしました。秋のイメージですが、やや脱色した感のある色あいが山仕事や花売りをする乳母に似合うと思い選びました。

写真 唐織
最近、能の稽古をして気がつくことがあり、私の経験談としてお読み下さい。
喜多流の稽古は、謡は一度先生が謡い手本を示し、習う者は復唱します。そして次回まで覚えてくることとなり、必死の暗記が待ち受けています。そこに何が謡われているか、物語を理解し諳んじればいいのでしょうが、若い時分はもう鵜呑み状態で、ただただ音を身体に叩き込み覚えます。もっともそれが舞台に立ったとき一番役立つ稽古法であるのですが…。
また舞も、まずは仕舞、そして舞囃子とレベルを上げて稽古し、ツレ役の稽古なども加わり、ようやく能のシテの稽古となります。能の稽古に入るまでに、幾度となく仕舞や舞囃子の稽古が繰り返され、積み重ねを大事とします。
型を正確に覚え、基本姿勢や上手な型のこなし、技の体得は必須で、これを習得しなければ話になりません。
しかし所詮仕舞や舞囃子は能の一部分であって、充分稽古したからといっても能の物語を理解出来るわけではありません。
能を目指す者の陥りやすい危険な盲点は、覚えた、舞えるようになったと、そこどまりになることです。それで出来上がったと錯覚する、それでは作品とは出会えません。
自戒を込めて言えば、私も以前は例えば『雲雀山』なら舞囃子が済むと、その部分はもうそれで仕上がった、それでよし、とより深い読み込みはしませんでした。これではいけないのです。
例えば、今回もクセの仕舞所で「面影残すかほよ鳥の…」とサシ廻しヒラキシオリの型があり、鳥の鳴く声が中将姫の嘆き悲しむ声にも聞こえ、それが哀れに思える心持ちで動きます。以前なら、ここどまりです。
ではこの「かほよ鳥」、さてどんな鳥なのでしょう。
問われても以前ならば、「型をきちんと表現すれば、あとは観る側が理解して下さるから、そちらにお任せすればよい」という先人の弁をそのまま、代弁してすませていました。
しかし、それでいいのだろうか、演者が、実は判らずに…とはあまりに情けないではありませんか。総て、とは言わないまでも、自分の知らないでいることをできるだけ判明させ、舞い謡いたい、そう思うようになりました。
以下、少し調べたことを書きますが、もちろん観客の皆様はご存知であると思います。ここは未熟な能楽師の調べたこととお笑い下さりながら、お読みいただければと思います。
喜多流の謡本では、ひらがなで「かほよ鳥(かおよどり)」と記載されています。「かほよ」は能『杜若』に「顔佳花とも申すとかや」ともあるように、顔佳花は美しい花の意で能『杜若』では燕子花(カキツバタ)をさします。
「かほよ鳥」は顔佳鳥とも書き、辞書には「顔鳥(かおどり)」と同じ意、カホと鳴くのでカッコウのこと、また美しい春の鳥、かおよどり、とあります。
演者としては、ただ漠然と美しい鳥、と思うよりも具体的に郭公と知ることで、その鳴き声を想像することが出来ます。演者が知ったからといって、観る側にそれとはっきり違いが判るかどうかの確証は持てませんが、演者の身体から発散されるものが、演者が知っているのと知らぬのとでは何か違いが出るのではないでしょうか。郭公の声が姫の泣き声と重なると具体的に知ることで、乳母の心の悲しみの演技に幅、真実みが生まれる、私はそう信じたいのです。

雲雀山 後
つぎに霞網です。「霞の網にかかり、目路もなき谷影の」と地謡が謡いますが、恥ずかしながら、私はこの霞網自体を知らずにいました。霞網とは細い糸で縫った細かな網を垂直に高く張り小鳥を無差別に捕らえる狩猟法です。その網にかかった小鳥がまさに中将姫に見え、悲しみ哀れむ乳母の心がより深く理解出来ました。
このようにして、より理解が進み、演じる心に余裕が出来ることで、能のドラマを演じる心持ちが生まれる、そう信じています。
まことに気づくのが遅く恥ずかしい限りですが、これからは若い時に稽古して自分で勝手に出来上がっていると錯覚している部分にも改めて目を向け、能がなにを言いたいのかを知りたいと思います。
また、舞台進行のことで、一つ気になったことがありました。
それはシテが太刀持に対して「あら花好かずの人々や花好かぬ人ぞをかしき」(「花が嫌いな人なんておかしいわ」)と小馬鹿にして花を売ることを諦め、次の序の謡となり、場面が変わるところですが、ここがしっくり来ませんでした。
そこで他流を調べると「それなら花を買いましょう。で、あなたの事を話して下さいよ」と太刀持の言葉があり、それに応えてシテがそれでは…とはじまります。こちらのほうが自然で判り安いのですが、喜多流は敢えて、そこを削除しています。となると、そのような心持ちで演じなくてはなりません。花を好かない、やさしさや余裕のない人なんて相手にしないわと、太刀持に言いながらも自分自身に言い聞かせるように相手を無視して語り始める、ある種の狂いとしての演出が喜多流には隠されているのかもしれません。
『雲雀山』は現在物です。現在物はただ型附通りに動いているだけでは観ていて面白くないはずです。演者の芝居心が必須です。
能という枠のぎりぎり境界線内側で、『雲雀山』ならば、乳母の心境をよく理解し、観客が判りやすく想像し易い状態にもっていく、それが演者が忘れてはいけない責務です。
能役者はともすると型を埋める、型をこなすことで安心してしまいがちですが、そこに留まらず、演劇的に中身を埋めなくてはいけない。舞台人としての埋め方、そこを考える必要があるのでしょう。
10代20代を振り返ると、ただ間違えないよう、正確に、格好良く、それしか念頭にありませんでした。あのときは自分なりに一途に、それこそ狂いのように集中して取り組んできた、と自信はありますが、今50代に入ると随分曖昧にやってきたものだと恥ずかしさも覚えます。
能、能楽師はある時を経て熟成されてこそ、その味わいが彷彿される、これが結論です。
今、演じ終えて、『雲雀山』は若年ではなかなか手強い現在物で、悲しいかな中年になり経験を積まないと判らないことが多々あることを知りました。
私がこの子方を勤めたのは昭和37年に故喜多実先生と喜多長世氏のシテで二回(7歳)、そして39年お素人の井手玲子氏のと、合わせて3回です。

雲雀山 子方 粟谷明生
少年にとって、初めから最後まであの藁屋の中に座らされ、ほとんど扉が開かない閉鎖された空間はまさに中将姫や小鳥の心境で、辛抱と我慢のなにものでもありません。
今回はその辛い役を内田貴成君がよく我慢して演ってくださって感謝しています。きっと将来、彼が『雲雀山』のシテを勤める時に、自分の経験を生かしてくれることでしょう。

雲雀山 後
勤め終えて楽屋に戻り、先輩能楽師の方から「あきくんも『雲雀山』をやるようになりましたね」と言葉をかけていただきました。
その言葉の響きが、大空高く楽しそうに飛ぶヒバリの声のように聞こえました。この鳴き声は演じる者だけに聞こえる歓喜の調べなのかもしれません。
(平成21年7月 記)
写真
雲雀山 シテ 粟谷明生 撮影 石田 裕
面 曲見 装束 唐織 徳友寺 撮影 粟谷明生
雲雀山 子方 粟谷明生 撮影 あびこ喜久三
『白田村』について 能の曖昧さと時流に似合う演出投稿日:2009-04-16

『白田村』について
能の曖昧さと時流に似合う演出
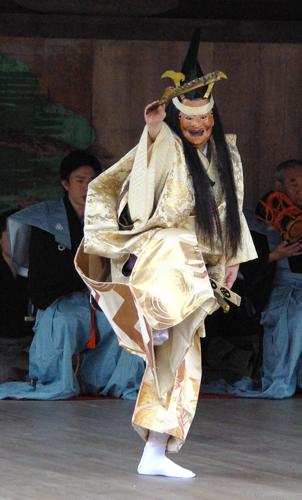
毎年恒例の厳島神社・御神能(平成21年4月16日)で『白田村』を勤めました。
演能前に観客の方から「『田村』と『白田村』はどこが違いますか?」「『白田村』の謡本がありませんでしたが…」とのご質問を受けました。『白田村』は『田村』の小書のひとつで『白田村』と『田村』は同じ曲です、とお答えしましたが、この質問はよく聞かれます。
『白田村』の歴史を調べると、演じられるようになったのは意外と新しく、現在行われているような形にまとまったのは、ごく近来のことだとわかってきました。
九世喜多古能健忘斎の伝書には『田村』の小書は「祝言之翔」のみとなっており、『白田村』の文字は見あたりません。十世喜多寿山が書き残したものに「田村に白水衣を着るもあり、宮子の心なり、古能公披成る候也…」とありますが、これは前シテの心持ちを記したもので、『白田村』そのものではないようです。
大正十三年の中型謡本に『白田村』とは別に「白式」の記載があります。前シテ白水衣、着附金地或いは白地紅入縫箔、後シテ法被白、「思えば嘉例なりけり」の後カケリ、「さるほどに・・・」の文句抜けて「如何に鬼神」。カケリは常と異なる…、とあることから、この白式が『白田村』のモデルになったと考えられます。
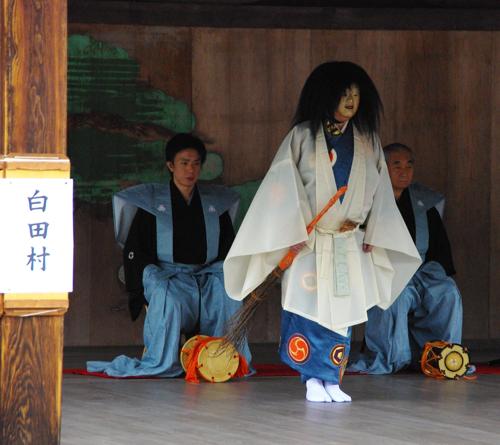
ではいつから『白田村』の記載があるのでしょうか?
六平太芸談に「『白田村』に似合う天神の面がない…」とあることから、『白田村』は十四世喜多六平太の時期にはすでに存在していたようです。ただ現在行われている型であるかは不明です。現在演じられている後シテの演出に新たな工夫を施し公式化したのは十五世喜多実先生のご考案であろう、というのが大方の楽屋内での認識で、その実先生も幾通りもの型をやられており、それぞれに伝承されているのが実態です。
この曲名を変えて小書とする手法は他流にはなく、喜多流独自の工夫のようです。
喜多流の成立は江戸時代初期、他の四座(観世・宝生・金春・金剛)に組み入れられ、五流に認可されたのは徳川秀忠公のお陰と言われています。流祖が舞った『羽衣』が豊臣秀吉公の目に留まったのをきっかけに、徳川秀忠公の庇護を受けるようになったのは注目を浴びる斬新な型や目新しい舞台演出の賜物かもしれません。弱小流儀の、それも後から出てきた喜多流には、それだけのバイタリティーが必要であったと思います。先人たちの他流と互角に張り合うための工夫、そして観客の目を引く演出、それらを生み出すものの一つとして、江戸時代末期か明治初期に、曲名に色をつける特殊なやり方をしたと思われます。他に、同じように白をつけた『白是界』、そして青をつけての『青野守』がありますが、どちらも流儀成立当時、または古くからあるものではありません。喜多流が時代の流れの中で育んできた精神によって生み出された特殊演出なのです。喜多流にはこのように、時流に合う演出を求める気風が備わっているのだと思います。それは成立以来の宿命であり、伝統であるとも言えます。現在、職分会で公認されている色つきのものは、『白田村』『白是界』『青野守』の三曲で、これは「喜多流正史」(高林吟二著)にその記載があります。
では今回の『白田村』を演じた感想を交え、舞台進行とその演出をご紹介します。

前シテは地主権現に仕える宮守として登場し、春の清水寺の景色と縁起を語ります。
シテ謡にある「もとより和光同塵の…」の言葉通り、仏が神として現れる本地垂迹の考えを踏まえて、面を喝食(かっしき)にして、喝食鬘の姿で清水寺や田村堂の仏的なものに重きをおいても、また面を慈童(じどう)や童子(どうじ)にし黒頭を被り地主権現の宮守、神の使い、または神の子と神道的なイメージを出しても演じられます。
どちらにするか? それは演者の自由で、その選択の余地があるのが能楽師にとって楽しみの一つでもあります。今回は面を童子にして「白式」に記載されている白水衣にしました。行叡居士が延鎮法師と出会った時に白い衣を着ていたという故事もその裏付けになり、仏と神の一体感が出せればと思いました。そして試しに今回は全部白地で…と希望しましたが、生憎厳島神社から出された装束に白地着附がなかったので、仕方なく他の物で代用しました。型や謡は通常の『田村』と変わりはありません。但し、通常クセの仕舞は扇を閉じて舞いますが、『白田村』では開いたままで舞うのが異なるところです。
後場は千手観音の威徳で鈴鹿山の鬼神を退治した戦物語となります。小書「祝言之翔」があるように、『田村』は修羅物の地獄の責め苦を見せるのではなく、田村麻呂の威風を見せる祝言性に溢れた曲ですので、演者としては他の修羅物とは別格の品位と豪快さを見せなくてはいけません。『白田村』では後場に工夫がなされていますので、装束や型などについてお話します。
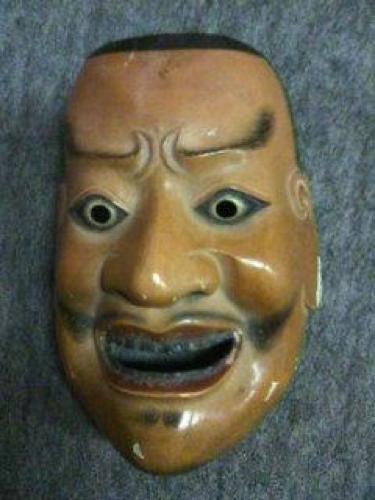
後シテ(坂上田村麻呂の霊)の装束は常と異なり、厚板・半切・狩衣(衣紋)などすべてを白色として太刀を付けます。面は平太から天神に代わります。頭部には梨打烏帽子・白鉢巻に鍬形を付ける珍しい組み合わせとなり、鍬形は兜の象徴となります。『船弁慶』の後シテ・平知盛の霊や、『羅生門』のワキ・渡辺綱などが黒頭と組み合わせて使いますが、黒垂との組み合わせは『白田村』だけです。常は太刀を腰に付けますが、宝剣にする場合もあり、肩に背負う方もいらっしゃいました。今回は厳島神社に似合う剣が無かったので太刀でしましたが、坂上田村麻呂が中国からの渡来系の人物であること、時代が平安初期というイメージを膨らませると、次回は古風な感じの宝剣を背負いたいと思います。

『白田村』の後場は謡に緩急がつきます。全体的には位高く、重くどっしりと謡い、カケリもややしっかりと囃されます。そしてカケリの後がもっともシマリ、「ふりさけ見れば」からの地謡は特に重厚感を持って謡います。そしてシテ謡の「あれを見よ、不思議やな」から気持ちがかかり、速度も早くなって、型は橋掛りでの動きとなります。三の松までクツロギ「大悲の弓には知恵の矢をはめて一度放せば…」から一の松まで勢いよく素早く動き、千手観音が千本の矢を放つ様を靡き扇で見せて、一の松前にて飛び跳ね、鬼神を退治する型をして、最後は下に居て千手観音に礼をして位は急にシマリます。このあたりの型が何通りもあり、今回は父の型と友枝昭世師からの型とを混合して勤めてみました。

ここで梨打烏帽子の着用で気になることがありました。
梨打烏帽子には右折、つまり役者自身から見て右側に折り曲げて倒すのと、左折、左側に倒すものの二通りがあります。上皇が着用する際に右折を用いるので、諸臣は左折を用いるという説、また『源平盛衰記』に、源八幡太郎義家が左折の烏帽子を用いた為、源氏の大将は左折を用い、他の物は右折を用いた記述もあります。
現在、喜多流では普通の『田村』は勝修羅の枠組みで梨打烏帽子を左折にしています。
他流も同じようですが、但し宝生流では梨打烏帽子は常に右折とのことです。
さて、『田村』は本来どうしたらよいのでしょうか?
先代実先生は一時、梨打烏帽子を折らずに真っ直ぐに立てて着けられたことがありました。確かに烏帽子の正装は立烏帽子ですのでそれも一考か、ならばいっそのこと立烏帽子を付けてみては…とも思いましたが、どうも力強さに欠けるようで不似合いです。

最近は実先生の立てるやりかたを真似る傾向がありますが、梨打烏帽子自体の本来の用途から考えると、私はやはり折らなければ理屈に合わないと思います。
これは推測ですが、能が発祥した室町時代から江戸時代の申楽の役者たちは、固定化していく能装束以外に、小物などは身の回りのもの、持ち運びしやすいものを新たにどんどん取り入れていたのではないか、と思います。ですから現在の梨打烏帽子も室町時代の申楽の役者にとって身近な持ち運びしやすいもの、という発想から生まれたかもしれません。
私も以前は、梨打烏帽子が武人の象徴、兜であると思っていました。確かにそう教えられ、そのようにも解釈出来ますが、鍬形こそが兜の象徴と言われれば納得せざるを得ません。梨打烏帽子は俗称・兜下といわれるように、兜の下に折り曲げて着用する柔らかな烏帽子のことですから、梨打烏帽子を兜と解釈するにはやはり無理がありますが、それでも見る側の想像でいかようにもなり得るのではないでしょうか。烏帽子一つとっても、いろいろな見方があり、面白いです。それが能なのでしょう。このように能の世界には、曖昧さを重宝に受け容れる面もあります。能には少々馬鹿げている演出もありますが、しかし逆に言えば、それだからこそ能であり、それが能の持つよさなのかもしれません。

能は現代にも生きています。現代になっても、能楽師の工夫と新たな発想で変化するのを待っているようにも思えます。従来通りでも吉、色々と発想するのもまた吉、そのように許容範囲の広い太っ腹なのが能のようです。今回は新たな発想が出ずに無難に左折れで勤めましたが、いつかよい工夫がないものかと思っています。
さて、もう一つ稽古していて気になることがありました。
坂上田村麻呂というと、征夷大将軍、征夷と言えば、蝦夷退治、現在の東北地方への侵攻と平定ですが、能『田村』に蝦夷の文字は、「東夷を平らげ悪魔を鎮め」の一言だけ、伊勢の鈴鹿山の鬼神退治の話にすり変わっています。鈴鹿山に朝廷に対して抵抗勢力があったことは史実でしょうが、坂上田村麻呂が鈴鹿山の鬼神を退治した史実はありません。
ではなぜこうなってしまったのでしょうか?
それも答えは、能だから、と言えるでしょう。
能は過分に曖昧さを武器として戯曲化されています。それは戯曲化した者達の時代のニーズに合わせること、申楽の役者の立場も関係していたかもしれません。
『田村』を成立させるときに、敢えて蝦夷退治の話題に触れなかったのは、作者やまたその後の申楽の役者たちの、自分や周りへの配慮だったと考えられます。
なんでも答えをはっきりさせたくなる、出ないと気持ちが悪い性格の私ですが、能『田村』の鈴鹿山鬼神退治については、このような能の曖昧さを大事にし、あまり言及すべきでないと判断しました。
物語を重視することは能を演じるときには大事なことです。
しかし、能の持つ曖昧さを考えると、能は舞台に上がっている能役者から発散される存在感が大事、その一言に尽きると思います。特に祝言性の高い曲は理屈ではない、最もシンプルな技を駆使して観客にアピールする、そこから焦点を外しては能らしくない能になってしまうのかも…と今回演じて感じました。
能は虚構と真実が拮抗しあうところから成り立つと故観世銕之亟先生はいわれました。
それぞれの役がそれぞれの役になりおおせて、且つその裏に役者の真実や美学が乱反射して豊かな表現となる・・・・いい言葉です。
乱反射の中にも、いろいろな光のさしかたがあることを武人田村麻呂が教えてくれました。
(平成21年4月 記)
追加
平成21年3月1日より5月31日まで清水寺の田村堂が特別開扉されます。
是非、この貴重な機会に田村堂の内部をご覧下さい。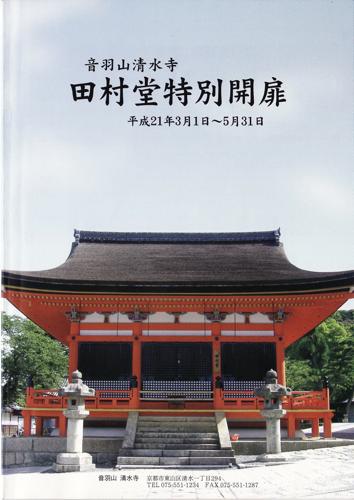
清水寺田村堂
音羽山清水寺田村堂特別開扉パンフレットより
写真
『白田村』シテ 粟谷明生 撮影 吉村真樹子
面 「天神」 厳島神社蔵 撮影 粟谷明生
囃子方 大鼓 亀井広忠 小鼓 横山晴明
『安宅』延年之舞ー延年之舞の疑問点を解明 投稿日:2009-04-01

『安宅』延年之舞(平成21年3月)を勤め、演能レポート『安宅』を更新して月日が経ちました。演能後「延年之舞」についてもう少し調べたいと思い、お弟子様の宮地啓二氏に資料集めを依頼したところ、寛永寺・土谷慈得氏のご協力により、日光山・輪王寺や平泉の毛越寺からの資料を入手することが出来ました。そこでその資料をもとに未だ解明出来ずに気がかりだったいくつかの疑問点を調べ、解明したことを、ここに演能レポートの補足として書き記すことにしました。なにぶん「延年」自体が今は途絶えてしまったこともあり、資料も少ないので正確さに欠ける部分もまた私の推測もあることをご承知の上、お読み下さい。
また、ご意見や参考資料などがございましたら、お知らせいただきたくお待ちしています。
さて、その疑問点とは?
能『安宅・延年之舞』の弁慶が舞う男舞の中で踏む音をたてない「抜く足拍子」がありますが、この動作の根拠、意味合いがはっきりしません。
また我が家の伝書に書かれていた「イトクリ、ブモヨシ、サンソウ」のカタカナ記載もどのようなものなのか、気になっていました。
まず、「抜く足拍子」を解明する前に、「延年之舞」の「延年」とはなにかを知る必要があります。
「延年」は正確な起源は不明ですが、平安時代中頃より寺院にて法会の後に僧徒が余興として観者に見せた歌舞です。延年の字の如く、観者を楽しませてはその長寿を祈る芸能でした。その内容は、問答や乱舞など様々のジャンルから集まり成立したもののようで、その歌舞の舞の部分を特に「延年之舞」と呼んだようです。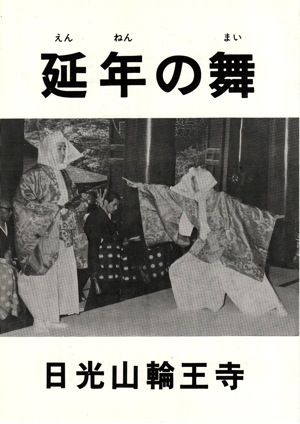
(日光山輪王寺のパンフレット表紙より)
平成の今、寺院で「延年之舞」と称されるものがあるのは、平泉の毛越寺と日光山の輪王寺の二寺だけです。毛越寺は正月二十日、二十日夜祭として常行堂で、輪王寺は毎年五月十七日午前八時から大本堂、三仏堂にて見られます。
能『安宅』の「延年之舞」が、室町時代にどのような経緯で創られたのかは、知る術はありませんが、現在、毛越寺や輪王寺で行われている「延年之舞」が時代の流れや系統により幾分変化していることを差し引いても、現存していることは、能『安宅』の「延年之舞」を調べる上で、ひとつの貴重なヒントになることは確かです。
平安時代から室町時代まで、寺院では延年を願う舞が流行したようで、はじめは下級僧侶や稚児らによる余興程度のものが、次第に演じ手は、芸に熟達した僧達が中心になり、遂には、延年を専門的に演じる僧が現れ、それらを「遊僧」「狂僧」と呼びました。
「歌舞伎十八番」戸板康二著には、「延年」は若い稚児のソプラノと成人した僧のバスとの掛け合いで進行したと書かれています。
『安宅』の謡に「もとより弁慶は山塔の遊僧…」と謡われているように、叡山と弁慶、遊僧そして延年之舞と関連していくと、『安宅』に小書「延年之舞」が付随したのはごく自然の成り行きなのかもしれません。
能の作者は室町時代の人です。その創作背景には、その時代の政治、生活環境、宗教観があり、それらを基盤として様々な過去を思い浮かべ戯曲したことでしょう。「延年之舞」は室町時代までは盛んに行われていたので、それを取り入れることは容易だったはずです。しかし室町時代以降は「延年之舞」は徐々に衰退していき、江戸時代にはほとんど行われなくなりました。
そのため現在の我々は、特に延年之舞を舞う能楽師にとっては、「延年之舞」が想像しがたい遠い存在になりました。能楽師の私が能『安宅・延年之舞』を勤めるにあたって想像するものは、平安時代に誕生した「延年」とはたぶん異なり、また現存の延年之舞とも違います。
もっとも、そんなことはおかまいなし、能楽師は師の言われた通り、型通りを忠実に真似て舞えばいい、との指導もあるでしょうが、どうもこのあたりをはっきりさせたいのが、私の性分でして、どうにも抑えられないのです。
実はこの延年之舞を衰退させた原因の一つに、江戸時代の支配者層である武家階級が、能を手厚く保護したことが挙げられていることを知り、能楽師の私としては、何とも複雑な気持ちでいます。
「延年之舞」は古記によれば江戸時代初期以前までは「開口」「延年」「大衆舞」の三部から成り立ち、能でいう「延年之舞」は「延年」ではなく「大衆舞」ではないかと言われています。「延年之舞」は能の原型である猿楽との関連が深かったらしく、互いに影響を与えあったらしいのですが、その後、能が延年之舞にとって変わったことは間違いないようです。
(毛越寺の延年之舞 平泉・毛越寺判より「老女」)
さて、喜多流独自の延年之舞での抜く足拍子ですが、左手に持つ中啓を腰に当て、右手の数珠の持ち様は、毛越寺の老女の舞の腰を屈めた姿が似ています。老女は左手に中啓、右に鈴を持ち、舞は翁の三番叟の鈴の段を彷彿させます。腰を屈め、鈴を鳴らす動作は、田畑への種まきを表しています。能の型も種まきや田植えの真似であるようにも思えます。抜く足拍子は滑稽さを味わいとしていた一面もありますが、しかし一方でもっと格式ある芸能であったと唱える方もおられます。能楽師が弁慶役を演ずるにあたって、抜く足拍子は何かの真似もさることながら、演じる心の内側には窮地に立たされた弁慶がどのように義経一行を逃がすか思案する時間稼ぎとも、またはふと昔手慣れた動きが自然に顕れてしまったとも、との思いになりました。
いずれにしても、あの不可解な、音を鳴らさない足拍子の意味は、滑稽なしぐさ、余興的な要素であることと、正式な儀式的な動きという双方を演者は想像して舞うのが肝要なのでは…、というのが私の結論です。
(『安宅』延年之舞 足拍子 シテ 粟谷明生 撮影 石田裕)
次に「イトクリ、ブモヨシ、サンソウ」について、粟谷家蔵書の堀池家の伝書に『安宅』「瀧流之掛(たきながしのかかり)」について、次の通りの記載があります。
「落ちて巌に響くこそ」と下を巻差し開き、「鳴るは瀧の水」と小鼓頭にて流し打ち、この時右の方へ下を見廻し乍ら廻り大鼓前にて直ぐ右へさし、破掛男舞、この時は脇へ酌なし、「鳴るは瀧の水も」一遍。延年之舞は比叡山にて僧の舞うものなり。イトクリ、ブモヨシ、サンソウ 斯様の名ある舞の由。これは小鼓ばかりにて翁の様にタタホ ホホと打ち返す囃子入りも有り。衣の袖を雪かと思ふて、払えば月の陰 ササトツトト、と声をかくる。
これは私が「瀧流之掛」で勤めるにあたって参考にした書き付けです。
演能当初はこのカタカナで書かれた「イトクリ、ブモヨシ、サンソウ」が何を意味するのか解らずにいましたが、今回の資料の日光山・輪王寺(平成9年第64号)の「日光山の延年之舞」菅原信海氏著にその謎を解く記載がありましたのでご紹介します。
延年之舞は、僧家で大法会の後に行う遊宴歌舞の総称、例えば興福寺の延年については「興福寺延年舞式」によると、その順序は寄楽(よせがく)振鉾(えんぶ)弁大衆、舞催(ぶもよおし)、僉議(せんぎ)、披露、開口、射払、間駈 掛駈、連事(つらね)絲綸(いとより)遊僧(ゆそう)風流 相乱(あいらん)拍子・・・・云々、とあり、あのカタカナは延年舞式のひとつでありました。
昔の「延年之舞」は寺によりその進行、歌や舞、曲目などが異なり、各寺院の特徴を出していたかもしれません。伝書に比叡山とありますが、上記の興福寺の舞式の記載と同じようなカタカナが羅列されていたのは驚きであり、面白い発見でした。
今回伝書のイトクリはイトヨリ、ブモヨシはブモヨオシ、サンソウはユソウ、と記述の違いであることが判明しました。しかしそれらがどのような動きで、どのような歌、歌詞であったかは残念ながら資料もなく、たぶん解らずじまいになりそうです。いろいろ調べ、事が明らかになることもあれば、闇の中のままということもあります。
今回の「瀧流之掛」の記載に、このような間違いがあることや、また瀧流之掛のあとの「平調返し」の記載にも問題があると指摘し、この伝書を貶す方もいらっしゃいますが、しかしだから信用出来ない、役に立たない伝書と決めつけるのはいかがなものでしょうか。懐が狭いように思われませんか?
私は伝書とは清廉潔白、正しいことだらけ、ではないものもあると踏まえて読むようにしています。先人たちのいろいろなやり方や工夫がふんだんに書かれている伝書ですが、その内容は今やられているものと異なることもあります。
それらを読み比べる作業、これもまた面白く、いろいろと新たな発見があります。いろいろな型を知り、その記載された型で勤めたい気持ちになりますが、同時に鵜呑みは危険であるということも心得ていなければいけません。伝書とは、よく心して深く今に照らして読むべし、なのです。
伝書は書き付けともいい、その当時の人が自分や一門、後世の人のために、次回に演じる時に役立てば、と書き留めたいわばメモです。そのメモに少しの書き間違いがあったから、それがインチキで役立たずと決めつけてしまうのは、いささか勿体ない気がします。
伝書を読むことの出来る今の者の心得としては、その書き付けの中にあるものから創造する力を養うことです。そしてそれをふんだんに体現すること。
能役者はとりくむ曲に纏わるいろいろな情報の収集と常にそれを体現する技を磨いていることが必要です。
能楽師としてのすべてのスキルを持ち合わせ、尚更に書き付けのメモを読む、これらのことをして、観ていただく、この作業を演者は忘れてはいけないと今回も再確認出来ました。演能が終わるとどうしても、次の曲への作業にとりかかり、それまでの曲を振り向かない私ですが、今回演能後に色々な方のお力添えをいただき、改めてまた追加として演能レポートに執り掛かれたことは、やりっ放し性分の私に、初心忘るべからず! を教えてくれたようです。これももしかすると寛永寺さん、輪王寺や毛越寺のお力かな、とも思いましたが、やはり能楽師ならば、ここは武蔵坊のお陰としておくことにいたします。
(平成21年4月 記)
『安宅』 延年之舞について投稿日:2009-03-07
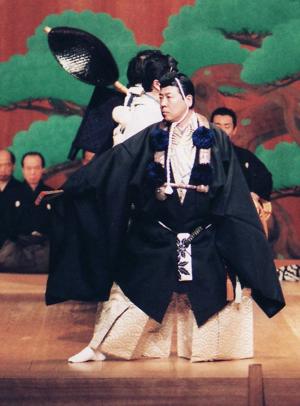
『安宅』―― 延年之舞について ―――
粟谷明生

粟谷能の会(平成21年3月1日)で『安宅』を十年ぶりに「延年之舞」の小書を付けて再演しました。
延年之舞とは、延暦寺や興福寺などの大きい寺で大法会の後の余興として、僧侶や稚児が舞ったもので、鎌倉時代には盛んに舞われていました。能の「延年之舞」は常の男舞に特殊な囃子方の手組「延年の手」が入り、それに合わせ喜多流ではシテが特殊な足踏みをする小書です。
この小書はシテ方の五流にあり、各流とも独自の扱い方をしています。
森田光春著「能楽覚え書帖」には「延年の型は、扇を左に取り右袖捲いて飛び上がる延暦寺の型(観世)、ハネ扇して左斜めに少し飛び上がる興福寺の型(金剛)がある」と記載されています。
喜多流の中興の祖、喜多健忘斎は「延年之舞」について、「三段目、数珠扇取リ替エ右廻リ袖ヲ巻処ニテ身入、数珠持チナガラ右手ウツムケ前ヘ突出シ、左手ヲ後ヘ廻シ、アオムケ腰ヘ付ケ左足ヨリ一クサリ拍子踏、マタ左手ウツムケ前へ突出シ・・・・拍子踏ミ夫ヨリ常ノ舞ニナル」と記していますが、現行のように掛け声と共に跳び上がる記載はありません。
いつ、どのような理由で今のような「延年之舞」になったのか、私は疑問を抱くようになりました。
先代・十五世喜多実宗家は掛け声をかけて跳んでいらしたと先輩方のお話ですので、十四世喜多六平太宗家または十二世宗家あたりの発案ではないか、と私は推察します。
現在の喜多流の「延年之舞」は、伝書にある特殊な足拍子を踏むものに、跳ぶ型を加えた形となっているので、「能楽覚え書帖」による系統で分ければ、延暦寺型を取り入れたことになりそうです。
ではこの跳ぶ意味、また特殊な拍子はなにを表しているのか、私は疑問を抱くようになりました。
山中玲子氏はご自身の著「『安宅』の小書・延年之舞の成立経緯」で、観世流も以前は足踏み拍子だけの演出を観世元章あたりの新工夫で跳ぶ型を導入したのでは・・・と記されています。徳田隣忠著「隣忠集」には、跳ぶ動作は「延年之舞ハ法会ニ児等ノ舞コト也。
其舞ニ両手ヲ肩ヘ打掛、両ヘ飛事アリ」と記されていますが、跳ぶ理由は記載されていません。

観世流が三回跳ぶところを、喜多流は一回だけで、「エイ!」と掛け声と共に高く跳びますが、実はそのことよりもその後の独特な抜き足のような足踏みの拍子を大事にしているのが喜多流の特徴なのです。
笛の譜と囃子方の掛け声に合わせて、五つ拍子、四つ拍子、三つ拍子と順番に踏みます。型は片手を腰に当て、もう一方の手で大地を抑えるような動きとなりますが、これも伝書には何を表しているのかは記載されていません。
いろいろ説はありますが、跳ぶことと関連して、やはり『翁』の三番叟の影響は大きいと思います。揉みの段や鈴の段の型を踏襲して、足踏みは大地を整地する心、手の動きは鈴の段の種まきの風情を真似ている、この説が今、最有力ではないかと思います。『安宅』の延年之舞は寺院の行事でありながら、翁の神事にも通じる、この両者の重なり具合が延年之舞を余計に興味深く面白くさせているのかもしれません。もっとも、延年をする衆徒が法会の間の場を取り持つ動きの一つとして、滑稽な動きを見せ観衆や聴衆の人目を引いたということも捨てがたい説ではあります。
演能後、弟子の宮地啓二氏に資料集めを依頼したところ、寛永寺・土谷慈得氏のご協力により、日光山・輪王寺や平泉・毛越寺からの資料を入手することができました。現在、寺院で「延年之舞」が舞われるのは、この二寺だけです。その資料によると、喜多流の「抜く足拍子」は毛越寺の老女の舞の腰を屈めた姿に似ています。腰を屈め、鈴を鳴らす動作は、田畑への種まきを表しているようです。(くわしくは、演能レポートの追加編「延年之舞の疑問点を解明」をご覧ください。)
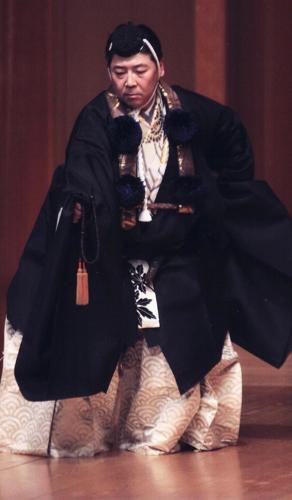
このようなことは演能後に分かってきたことですが、実は舞台で弁慶を演じているときの私の心の内側は、型の意味合いよりは、窮地に立たされた弁慶がどのように義経一行を逃すか思案する時間稼ぎ、または、三塔(比叡山)の遊僧として昔手慣れた動きがふと自然に顕れてしまった、といった解釈になっていたのが正直なところです。
『安宅』「延年之舞」を勤めるにあたってもう一つ気になったことがありました。それは「延年之舞」自体が、囃子方との約束事を重視した囃子の面白さだけに焦点を当て、物語の展開という本筋から少々はずれた演出になっているのではないかということで、私にはそう思えて仕方ありませんでした。
招かざる関守の前で舞を舞うことになった弁慶。しかし一刻も早くこの場から退出したい心持ちのはずです。ところが、延年之舞は「延年掛(えんねんかかり)」となり、通常より一クサリ長く伸びて、仰々しいシテの達拝が導入されます。囃子方の強くゆったりとした掛け声は神聖感が漂い悪くはありませんが、どうもこの達拝が不似合いです。早くどうにかして退出したい弁慶の心持ちを最大限に活かし、観客の心にも強くアピールする、『安宅』という物語に似合った演出はないものか、と考えました。そのとき、山中氏の『安宅』が創られた当初は破掛り(はがかり)で行われていたという記載が目にとまり、私の背中を押してくれました。そして、我が家の堀池家の伝書に「瀧流之掛(たきながしのかかり)」は破掛りと記されているのを見つけました。~「鳴るは瀧の水」と謡い直ぐにサシ・男舞・破掛~とあります。これが私の演じたい気持ちに似合うと思い、今回の試演となりました。

お囃子方(笛・松田弘之 小鼓・鵜澤洋太郎 大鼓・柿原弘和)のご協力を得て、堀池家の書き付けを配り、それを頼りに全員で新たな演出を考え試演しました。
安宅の関を通り、一安心していた処に、酒を持参して乗り込んでくる関守、しかし無碍に断ることも出来ない弁慶の心。兎に角、ひとまず飲んで座を持ち、一行をうまく早く奥州へ逃がす気持ちを観客に伝える、そのためにはどうしたらよいか?と囃子方に説明しました。そこで「落ちて巌に響くこそ」の「響く」で笛のヒシギに合わせてシテは足拍子を踏み、瀧を見上げ、落ちる水を見回しながら、「鳴るは瀧の水」と謡い、しぶしぶと舞に入る段取りにしました。瀧の水音は小鼓の乙流し(ポンポンと同じ拍子で打つ)の連打で表現し、弁慶の気持ちが乗らない心は大鼓の中々打ち出さない技法で表現してみることにしました。
ご感想などがあれば、忌憚なくお聞かせいただきたいと思っています。
今回のこの新しい演出、「目先の目新しいことばかりして・・・・従来通りに伝承を守るのが第一・・・」とのご批判もあるかもしれません。が、しかし、これは物語重視の思考の上でのことです。能役者・粟谷明生が能の台本を読み込み何を表現するか、何を伝え得るか、そこが大事でそれを蔑ろにする能役者人生は送りたくないのです。能役者の個性が舞台に表れてこそ、その演者の能になる。それがよい能となるかどうかの決め手、そう信じたいのです。書き付けを元にその先を読み込み演出に工夫をする、舞台を勤める演者たちの大事な作業であると思います。今回、この作業を囃子方の面々と共に真摯に楽しくできたこと、その充実感を、今堪能しています。
小書「延年之舞」には、狂言方の小書「貝立(かいだて)」が付き物です。
「貝立」は、アイ(強力)が関の様子を報告した後に、再度橋掛りに立って「ズーワイ、ズーワイ」とほら貝を吹いて出立を知らせる小書です。今回は野村萬斎氏がアイを勤めてくれましたが、申合後に「どんな感じで吹いたらいいでしょうか。シテの謡い方によって貝の吹き方が違ってきます」と言われました。どういうことかというと、「さあらば御立ちあろうずるにて候(さあ、出発しましょう)」と、弁慶が義経に告げる、その謡う心持ちによって、「ズーワイ」の吹き方も違う、というのです。勢いよく「さあ、行こう!」という明るい陽の謡い方なら、陽の吹き方になり、「大変だけれど、身を引き締めて参りましょう」という暗い陰の謡い方なら、陰の吹き方にと、吹き方はシテの謡い方に合わせるということです。私が後者の陰のやり方で謡う、と伝えると、萬斎氏は「ではそのように吹きましょう」と快く対応してくれました。
このようにちょっとしたこまかな言葉のニュアンスまでも配慮して舞台をつくる、当然のことなのですが、こうしたことがよい舞台作りには不可欠な作業だと改めて思い、当日はより新鮮な気持ちで舞台へ出られました。『安宅』の最後の場面では、シテが強力に笈をもって先に行けと合図し、それをうけてアイは笈を素早く肩にかけ、さーっと走り込みます。私の思い通りの、素早いながらも綺麗な型として萬斎氏が勤めて下さったことに、私は感謝しています。
今回のレポートは「延年之舞」の小書を中心にまとめました。このように書いてくると、延年之舞ばかりを考えていたように思われそうですが、決してそうではありません。
重ねて言いますが、小書の「延年之舞」は重い位の習です。もちろん大事にしなくてはいけませんが、『安宅』という能を演じるとき最も忘れてはいけないことは、物語の展開の面白さをきちっと伝えることです。現在物と呼ばれる曲は、お芝居にならずに能の手法の内側ギリギリで、いかに表現できるかにかかっています。私は幽玄物と現在物とを意識して演じ分けています。
『安宅』では、シテや子方と立衆全員から関を突破する意気込みが感じられなくては、観ていて面白くありません。そのためには各役者がそれぞれ謡い方に緻密な緩急をつけ、ひとつひとつの所作も冷静と興奮というような動と静が繰り広げられ、心の陰陽が彷彿されるように心掛け、観客の心を引きつけなくてはいけないと思います。それをしないと観客の心は醒めてしまうでしょう。能は伝統的な様式美によって表現されるものです。しかし、その言葉に甘え過ぎる危険が能役者には付きまとうようです。私は現在物に取り組む時、常にその危険な落とし穴を意識していたいと思っています。
たとえば、強力に身をやつした義経が疑われた後、郎党が一気に立ち上がり、刀に手をかけ一触即発、弁慶が郎党を押しとどめ、シテ方とワキ方の「押し合い」となる場面があります。ここでいつも気になることがありました。それは富樫に迫るとき、七人~九人の演者がまるで満員電車に乗っているかのように身体をすりつけ窮屈なさまを舞台中央で展開します。あの三間四方のなかで、肩と肩、体が触れ合うことで緊迫感が出せる一面もありますが、一方でもう少しそれぞれの役者が離れていても富樫への闘志が表現出来るのでないか、その方がお能らしいのでは・・・。全員が型として押されれば下がる、下がれば押し返すという動きができないものか、と提唱しました。前の人にぶつかりながら下がる、後ろの人に押されながら出るという身体同士の触れ合う感覚ではない、離れていても様式を整えた型としての動きです。それでいて、全員がまっすぐに富樫を見据え、一歩も引き下がらないという気持ちで・・・・。芝居心を持つ能役者の動きを能の様式美として観ていただく、能の表現ギリギリのところで演じ力強さも出せれば、それが私の理想です。
シテだけではなく、郎党たち(シテツレ)、富樫と太刀持ち(ワキ方・狂言方)、すべてがこの『安宅』という物語、能を創り出すための意識を上げる、今回、それの手応えが私には感じられて嬉しく思っています。
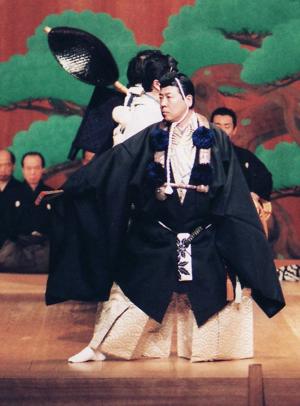
謡については、最初の道行の謡と、弁慶の勧進帳を読む謡が、聞かせどころです。
道行の謡は特に力強くノリよく謡いたいところです。ダラダラ謡っていては緊迫感が生まれません。ある能楽評論家が「落ちていく義経一行の姿と喜多流の力強い謡とは似合わない」と評したそうですが、私はそうは思いません。なぜなら、落人だからといって弱々しく謡っては、またいつか再興を、と志す武士団の強い気運がでないからです。もちろん強い声と乱暴な大声を取り違えてはいけませんが、私が子方時代に聞いた諸先輩の道行は物凄い迫力で子供ながらにぞくぞく興奮するものでした。私はその時の記憶をもとに今回の立衆にも同じように強さをもって、と強調し協力してもらいました。
弁慶の勧進帳の読み上げは、節扱いも拍子のあたりも難しく囃子方との呼吸で謡う特殊な謡で最大の聞かせどころです。囃子方との呼吸は、ただ拍子に合わせて謡うだけではなく、ここでもやはり、『安宅』という物語を意識しての演じ方が必要です。富樫に勧進帳を読めと言われて、そのようなものはもともとないわけです。空白の巻物を取り出して、本当に困って、しぶしぶ、しかしそれらしくどのように読むか、苦心の心持ちが聞かせどころです。最初はしぶしぶ読んでいるものが、そのうちだんだん流暢になって言葉が溢れてくるようなスピード感、ノリのよさが大事です。最後は「天も響けと、読み上げたり」と高らかに宣言するのですから、本当に見所の奥まで響き渡るほどの大音声で謡わなければ説得力に欠けます。囃子の拍子あたりだけに満足しない、謡本の詞章を読み上げることに意識を高めてこそ、本当の勧進帳が成立すると思うようになりました。それを観客は楽しみにしているということを、遅まきながら最近判るようになったのです。

能『安宅』では、安宅の関を通ったのは、弁慶一党の信仰の力、仏の力で通ったのだという描き方です。歌舞伎の『勧進帳』は、富樫が義経一行だと分かりながら、武士の情で通したという描き方になっていますが、これとは全く違います。能の富樫の心の中ではそれまで何人もの山伏を殺していて、仏罰が落ちるのではないかといった恐怖心があったと思います。それは富樫本人だけではなく家族や親族、何代にもわたるのでは、との怖れです。だからもし、この一行が本当の山伏なら、殺してしまってはたいへんなことになる。弁慶たちは富樫にそういう恐れを持たせ、安宅の関を突破しなければならないのです。子方のとき、なぜまた富樫が戻って来るのか、なぜ弁慶は招き入れるのかと不思議に思っていましたが、富樫が本当の山伏だと思ったからこそ、これまでの非礼をわびる意味で酒を持参してやってくるのであり、弁慶らはそれを平然と招き入れなければならない。史実とは違うのかもしれませんが、能はそのように描き、その緊迫感を能役者に求めていると私は解釈しています。
『安宅』は現在能、夢幻能とは違います。三番目物のようなしっとりした能の世界とは全く違うこのような現在能が、芝居としての面白さを持ちながら、能の枠組みを超えず、能として多くの人に支持され、今も人気曲として伝わっています。
今回も能の幅広さ、懐の深さを感じ、これからも多様な能に挑戦し続け、様々な試みも手がけていきたいと思いました。
能楽師人生も様々です。私は私なりの道を歩んでいく覚悟はありますが、正直なところ不安もあります。このような演出でよいのか、もっと違う考え方があるかもしれない・・・などと。先輩はじめ多くの人に忌憚のないご意見をいただき、それを自分のなかで咀嚼して次の演能にも活かしていきたい。今回のように、囃子方や狂言方、ワキ方、郎党を勤めてくれた喜多流の若い人たち、みんなと創り上げていくことの面白さ、素晴らしさを満喫しながら更なる能の世界の追及をしていきたい、そう思っています。
生意気かもしれません、考え過ぎるなとも言われそうですが、「い~や、それでいいんだ!」という弁慶の声が、私には聞えてならないのです。
(平成21年3月 記)
写真
1・2・3・4 撮影・吉越 研
5・6・7 撮影・あびこ喜久三
シテ 粟谷明生
ワキ 森 常好
強力 野村萬斎
立衆 狩野了一・内田成信・佐々木多門・大島輝久・塩津圭介・佐藤寛泰・友枝雄人
『張良』を勤めて ー中国の題材に相応しい演出ー投稿日:2008-12-21
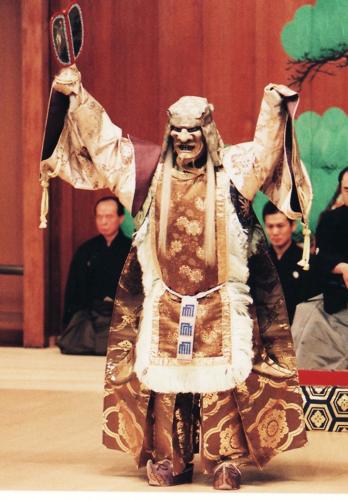

平成20年12月の喜多流自主公演で『張良』を勤めました。
『張良』は漢の高祖(劉邦)に仕えた若き日の張良が黄石公(こうせきこう)の試練に耐え、兵法の秘伝を伝授される話です。この張良の忠義心は鞍馬山の大天狗が牛若丸に兵法を伝える『鞍馬天狗』の一場面にも謡われています。老人の黄石公は若者の張良に何度も沓を拾わせ、その忠義心を試しますが、その模様を作品化したのが観世小次郎信光(音阿弥の第七子)作の『張良』です。
信光は『船弁慶』『紅葉狩』『龍虎』『羅生門』など、それまでにはなかったワキが活躍する劇的で動きのある能を数多く創りました。信光は大鼓の上手でもあったようで、『船弁慶』の間狂言の波頭(なみがしら=荒れる海を表現する手組)を創案し、音楽的に新たな工夫を残した能役者です。喜多流には生憎ありませんが、『胡蝶』や『吉野天人』なども創り、また晩年には老木の柳をテーマにした『遊行柳』も創りと、その幅広い作風は観阿弥や世阿弥そして金春禅竹とはまた別な新たな能の世界を作り出し、その作品が今日でも上演され続けているということは、その優秀さを立証していると思います。
ではまず、『張良』のあらすじをご紹介します。
張良はある夜、老人が沓を落としたので履かせると、五日目にまたここに来れば兵法の奥義を伝授すると言われる夢をみます。夢のこととは思いながらも、五日後に出向くと老人はすでに待っていて遅参に怒り、さらに五日後に来いと言い捨てて消え失せます。
そして五日後、今度は早暁に出向くと、老人はまだ到着しておらず、そこへ黄石公と名乗る老人が馬に乗って現れて、履いていた沓を川へ落とし、再度、張良の心を試します。
張良は沓を拾おうと川に飛び込みますが、激流に阻まれなかなか取れないでいると、龍神が現れ沓を取り上げてしまいます。しかし張良は剣を抜いて龍神を威嚇し沓を取り返し、川よりはい上がって黄石公に沓を履かせます。黄石公は喜び、張良に兵巻物を与え兵法を伝授します。龍神は実は黄石公の分身で、これからは張良の守護神となると約束して川へ消え、また黄石公も高い山へと消えて行きます。
以上があらすじです。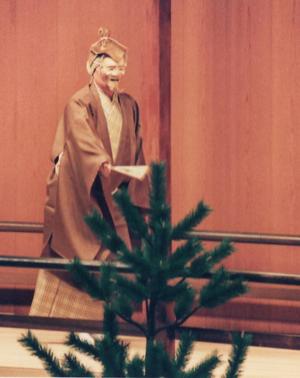
能は史実と異なることがたびたびあります。
この『張良』の場合も同様で、ワキの名乗りで「漢の高祖に仕える・・」と語りますが、実は兵法を伝授された時点では、まだ張良は劉邦には出会っていません。
ここで張良なる人物を大まかにご紹介します。
張良は戦国時代(紀元前475年?221年)の韓の宰相たる名門の出身で、この韓は秦により滅ぼされますが、その時のことが張良の秦に対する復讐心と祖国再興への思いを強くさせます。旅行好きの秦の始皇帝が陽武(ようぶ)に来たとき、張良は暗殺を試みますが、幸か不幸かこれは失敗に終わります。これ以後、逃亡生活を送り、下邳(かひ)での沓の話はこの時のことです。やがて劉邦と出会い自分が仕えるに足る人物と見込み、配下となります。項羽と劉邦で有名な「鴻門の会」では、劉邦の危機を張良の冷静な計らいで乗り越え、最後は項羽を烏合にて自害へと追い込むのも張良の策略だといわれています。漢帝国建国に尽力した張良ですが、実は生来虚弱多病で身体も小柄であったというのは意外でした。
さて話を能に戻します。
歴史がどうあれ、舞台鑑賞の観点からすると、逃亡生活中で風来坊の青年張良より、劉邦に仕える、身分ある、位ある者の忠義心の方が映りはよく、そのように設定したのは信光の工夫だと思われます。
能『張良』は、この張良役をワキが勤め、特にワキの重い習とされ大事に扱われています。今回私が『張良』を勤めることになり、ワキをどなたにと考えた時に、出来ればまだ披らかれていない若い方のチャンスになればと思い、宝生欣哉氏にご相談して、大日方寛氏にお願いすることとなりました。
ワキが重い位になるのは、ワキの型どころが多いことによります。特に重要な型所は川に落ちた沓を取ろうとする場面で、見せ場になっています。一畳台に飛び上がると、直ぐに川に飛び込む心持ちで飛び降り、急流に流されながらも沓を取ろうとする有様を、特有の流れ足と身体の反り返りと回転で演じます。これはなかなか特異な動きで、ワキの唐冠に捲かれた赤い色鉢巻きが床につくくらいに反り返れ、というのが心得と聞いています。
この見どころ、実は私はその場に居ても面を掛けているので残念ながらよく見えません。後日、大日方さんのその俊敏な流れ足とスピード感溢れる動き、若き勇士の威風ぶりを、映像を通してですが、見ることが出来ました。
この若さ、俊敏さを際だたせるために、シテを動きの少ない老人という対照的な設定にする、このことを作者は意図的に考えたのではと思います。
今回『張良』を演じるにあたり、シテ方にはあまり手柄もなく、特にどうのということはないので、稽古をしていても少々消化不良、物足りなさを感じてしまうのが正直なところです。しかしシテを勤めるからには、シテの心得を外さないで勤めるべきで、それは、ただただ黄石公のどっしりとした貫禄とスケールの大きさを演じきる、この一言に尽きると思います。ご覧になられて、さしたる動きが無く、簡単で楽であると思われるかもしれませんが、自然にどっしりとした貫禄を表現することこそ、能役者の表現力の一つだと思われます。そのために、それなりの技術的な作業が行われているのですが、私としてはそこを見ていただきたい、というのが本音なのです。
貫禄、というもの、これが若年では出来そうで出来ない不思議なものなのです。それが少しわかる年齢になった、ということは自分も既に若者ではないというお墨付きを頂いたような、嬉しいような悲しいような、複雑な私の気持ちです。
今回、私としては、この曲でなければという演出にこだわって、喜多流独自の沓を履く演出はもとより、装束も中国風にと気を遣ってみました。
我が家の伝書に「後シテ鼻瘤悪尉、長範頭巾ノ内ニ垂、狩衣半切・・・沓ハク静成ル早笛橋掛立つ」とあります。
能で沓を履く、しかも歩いて登場することは大変珍しく、これは喜多流のみの演出です。
沓を使用しての演能の歴史は、私の知る限りでは、20年近く前に、京都在住の職分・高林白牛口二氏が沓を購入され、福王茂十郎氏の会の『張良』にて沓を履いて演能されたのが最初です。それ以前は宗家や職分家に履ける沓がなかったためか、従来通り足袋での演能でした。もっとも江戸時代、明治、大正時代の記録を捜した訳ではありませんが、伝書には「沓ハク」とあるので、昔はたぶん履いていたと思われます。当時それを観た観客はもとより、その場に居合わせた能楽師達もみな、屹度その奇抜な演出に目を見張ったことだと推察します。ごく最近では従兄弟の能夫が高林家の沓を拝借して粟谷能の会にて『張良』を勤め、また『大会』でも同じ沓を履いて勤めています。
この沓の形は、現在禅宗のお寺などでは出頭沓と呼ばれているものに近い形です。
沓を履いて運び(歩行)をすると、沓底が固いフェルトで出来ているため、いつものように足裏で舞台を感じる事が出来ず、特に一畳台への乗り降りは危険が伴い、注意が必要です。やりにくい面も多々ありましたが、流儀にしかない稀な演出であり、今回は観客の目を引く演出として、敢えて挑戦してみました。
これは53歳の私の感想ですが、沓を履くという慣れないことは、あまり高齢になってからは危険が伴うので、履かない方がいいのではないか、履くとしたら何度も履いて慣れるようになしなければ、とここに記しておきます。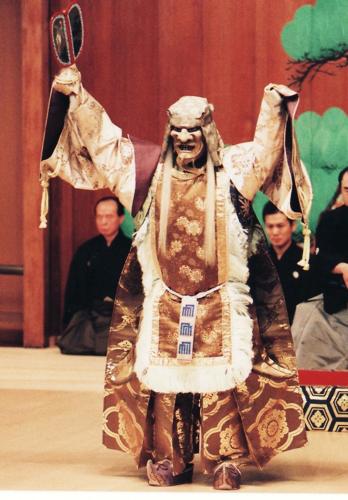
そして、中国風の装束選びは観世銕之丞氏のご協力を得て、前シテには尉髪の上に淵明頭巾をつけ、後シテは長範頭巾に替えて唐帽子に白垂とし、狩衣の上から裲襠(りょうとう=中国風のチョッキのようなもの)を着ることにしました。これによって中国らしい、異国風な情緒を出してみました。
前シテの装束は通常、神能の『養老』や『烏頭』の前シテの尉と変わりません。日本人と中国人が全く同じ格好である、そこに違和感を持ちました。お狂言方も中国物にはそれに似合った装束を着用しているのですから、シテ方がその工夫をしないでいるというのは、少しサービス精神に欠けている、というか無頓着過ぎるように思いはじめました。
中国が舞台の話を、日本人と同じ装束でこなしてきた歴史には訳があります。
昔、猿楽師が旅役者として少ない装束で、何の曲にでも対応出来るようにと装束を選び、持ち運びを工夫してきました。しかしそれは過去の話であって、現代それに甘えているのはどうも、私としては性分に合わないのです。
過去の歴史や資料は大事にしたいと思いますが、今の時代は、もっと観客の立場に立って考え、異国物にはそれなりの、想像しやすい環境作りが必須だと思います。私はその一つとして装束選びは重要なポイントであり、演じる立場がいつも心掛けなければいけない事だと思っています。
淵明頭巾の着用は喜多流では初めての試みでした。淵明頭巾という名前も知らない、付け方も判らない状態でしたので、観世流・銕仙会の方々に教えていただきました。
装束付けは狩野了一氏と佐々木多門氏、その他の方々にもいろいろとご意見やお知恵を拝借しながらの出来映えとなりましたが、私の我が儘を皆様が助けて下さって、いろいろとご苦労をお掛けしたこと、ここで皆様にお礼を申し上げます。
面についても触れておきます。
伝書に面は「鼻瘤悪尉」と記載れていますが、「上手ニテハ悪尉ベシミ掛ケルモ」とありましたので、今回は思い切って我が家の「大悪尉」を使いました。面の収集に力を注いだ故粟谷新太郎伯父が、この面が手に入ったことを喜び、面をかけたまま寝ていてそれを見た伯母がびっくり仰天した、という曰く付きの「大悪尉」です。迫力ある黄石公に似合っていたと思っています。
次に、沓の演出について記載しておきます。
伝書には、シテが沓を脱いで蹴り落とす、とありますが、今回は敢えて後見に投げていただくことにしました。高林家の沓は頑丈で重いため、シテ自らが蹴った場合近くに落ちる可能性が高いのです。ワキは沓が落ちると、すぐに沓を拾いに激流の中に飛び込み、流れ足や反り返りなど激しい動きのある型どころになりますが、もし沓が舞台の中央辺りに落ちると、動く範囲が狭くなり思う存分に型を演じることができません。
中央やまた別な所に落ちた時のために替えの型はありますが、大日方氏は初演でもあり、そういうわずらわしい思いをさせたくなく、存分に動いてほしいと考えました。後見の方には、沓が舞台から落ちてもかまわないので、出来る限り遠くに投げてくださいとお願いしました。
今回は本当に舞台から落ちてしまいましたが、その場合、龍神が沓を持って登場する方法(替えの型)と、今回のように、早笛と同時に後見が所定の位置に沓を置き、当初の通り、それを龍神が拾うというやり方があります。いずれにしても、落ちたときの用心に沓は3つ用意してあります。
私が聞き慣れた教えは、龍神が抱え持ち出る方法ですが、実は伝書には、その記載はありませんでした。むしろ早笛で堂々と後見が持って出ること、と書かれていました。
私はいざという時、二つのやり方のどちらを選択するかを考えました。そして、龍神が沓を持って出る替えの型よりも、伝書に書かれた方を採用しました。
それはワキ(張良)もシテツレ(龍神)も、沓の落ちどころで、わずらわされることなく、稽古してきた型で存分に演じてほしい、そういう場を設定するのが大夫としてのシテの役割ではないかと思ったからです。沓の処理については賛否両論ありますが、今回は、私はそのような意図で演出しました。
『張良』はワキの重い習いです。重い習いだから特別というわけではありませんが、ワキの型や龍神の型をシテがよく解釈し、深く理解し共に創り上げていかなければならないと思います。ワキの難しい動きをよく理解して、それに合わせるように謡う、ワキの溌剌とした若々しい動きに対してシテはどっしりと構えるなど、今回はとくにワキやツレを意識して勤めました。ワキの大日方さんが、流れ足、反り返り、謡と、難しい型どころ、謡どころを、青年張良らしくさわやかに力強く勤め、よいお披キになりました。私もシテとして微力ながらも力を貸すことができてよかったと思っています。
沓の演出、装束のことなど、一曲を創り上げるためにすみずみまで細かい配慮をする、今回のことは、シテが大夫としてするべきことの勉強であったような気がしています。
(平成20年12月 記)
写真
(1)『張良』後
シテ 粟谷明生
ワキ 大日方寛
龍神 内田成信
小鼓 成田達志
太鼓 助川 治
後見 金子敬一郎
(2)前シテ 粟谷明生
(3)沓 近影
(4)後シテ 粟谷明生
(5)淵明頭巾を付ける 左内田安信氏と狩野了一氏
(6)大悪尉 粟谷蔵
(1)(2)(4)あびこ喜久三 撮影
(3)(6) 粟谷明生 撮影
(5) 佐藤 陽 撮影
『絵馬』を勤めてー天照大神の威光ー投稿日:2008-10-12

『絵馬』を勤めて
――天照大神の威光――

第84回粟谷能の会・故粟谷菊生三回忌追善能(平成20年10月12日・国立能楽堂)で『絵馬』女体を勤めました。
『絵馬』は寺社の縁起や神を扱った脇能と呼ばれるジャンルに入ります。
前場は落ち着いた雰囲気で老夫婦の絵馬の掛け馬の話、後場は古代の天の岩戸神話の繰り広げる雄大なスケールの明るい作品で、派手やかなショー的要素の強い神能です。
『絵馬』のシテは天照大神です。天照とは、天に照り輝く太陽、を意味し、一般的には太陽神の女神を想像するのではないでしょうか。
しかし喜多流の小書の付かない『絵馬』では天照大神が男体の神として扱われています。
小書が有る無しで、前場に変化はありませんが、後場は大幅に役柄が変わります。
小書無しでは、シテの面は「東江(とうごう)」または「三日月(みかづき)」を使用し、荒々しい男の神体をスピード感溢れる神舞で表現します。シテが男体であるため、二人のツレを天女として登場させ、珍しい神楽の相舞となります。
しかしこれを岩戸の前で神々が喜んだ天鈿女命(あまのうずめのみこと)の舞であると想像するには少々無理があり、また岩戸隠れ自体を表していると想像するにも難しく、良い演出とは言えないでしょう。
そのため流儀で普通の『絵馬』はあまり上演されていませんが、何故か父や叔父の辰三、最近では従兄弟の充雄と粟谷家の人が、この普通の『絵馬』を多く手がけているのは、なんとも不思議なことです。
昔、父が囃子科協議会にて普通の『絵馬』を勤めた時に「東江」の面をつけながら「どうしてこうなるのかな?」とこぼしていたこと、私もそばにいて「変だね」と相槌したことを思い出します。
今、私の知る限りでは、天照大神には女神説と男神説の両説があり、喜多流は男尊思想から男神説を取り入れた歴史があるようにも聞いていますが、確証がある訳ではありません。
シテ方五流を比較すると、観世流と金剛流は女神、宝生流と喜多流は男神として演じます。金春流には『絵馬』が無く、これは江戸時代、幕府に未登録であったためと思われますが、五流で一番古い歴史を持つ流儀がこの曲を手がけないのは残念な気がします。

「女体」の小書が付くと後シテは女神の姿となり、頭上に日輪を戴き、白狩衣に緋大口袴を穿いて、両手で中啓を笏(しゃく)のように見立てて持つ独特の構えで現れます。
天鈿女命(女ツレ)を先頭に、手力雄命(たぢからのおのみこと・男ツレ)を従えて厳かにゆったり現れる様は「女体」ならではの光景で、後半の見どころのはじまりです。
「女体」になると曲の位が上がり重い習となり、若年の者は勤められなくなります。
「神遊」や「女体」など小書が付くと位が上がる曲は、若い能楽師にとっては「いつか舞いたい!」と憧れる曲、小書で、私も実現出来たことに満足して喜んでいます。
今回、追善公演でおめでたい『絵馬』「女体」を勤めることは、いささか不似合とお思いの方もおられたと思いますが、今回の選曲は父が亡くなる前から決定していたことであり、またこの大曲を私が勤めてこそ、父も喜び、よい手向けになると思い、精一杯勤めることにしました。
ではまず『絵馬』のあらすじです。
大炊の帝(淳仁天皇)に仕える勅使、公能は伊勢大神宮へ参向する途上、老夫婦が連れ立って斎宮へ絵馬をかけにくるのに出会います。
由来を尋ねると、昔は馬の毛によって翌年の天候を占う習慣があったが、今は絵馬を掛けて明年の天候を占う、と答えます。
尉は白の絵馬を掛けて日照を、姥は黒の絵馬を掛けて雨を占うと、掛け絵馬について争うが、結局万民快楽の世にしようと二人は二つ掛けることにします。そして老夫婦は公能に自分たちは伊勢の二神、天照大神と月読尊(つきよみのみこと)であると告げ消えてしまいます。
中入
やがて天照大神が天鈿女命と手力雄命を従えて現れ、天照大神は自身神舞を舞い、岩戸隠れの様子も再現して見せます。
前場は五穀豊穣万民快楽の泰平を祝い、後場は天の岩戸の神話を描いていきます。
『絵馬』は脇能ですが、その構成は『高砂』『弓八幡』などの通常の脇能とは大幅に異なります。
ワキは五段次第で登場し、シテは真之一声から下歌、上歌は通常の脇能形式ですが、序・サシ、クセ・ロンギという脇能の構成を持たず、クセの途中で中入りするなど特異で、しかも地謡の和吟での斉唱は非常に珍しいものです。
そのため、強吟で謡うシテとツレは和吟で謡う地謡へのスムーズな橋渡しが必要で、ここにシテとツレの謡い方の心得があります。

「女体」の後場では、シテが「小面」をかけて神舞を舞い、天鈿女命が神楽を、途中から手力雄命の急之舞と、舞尽くしの舞台展開となります。
囃子方にとっても、技術力はさることながら、体力も必要な非常にタフな小書であるため、裏話をすると、囃子方からはやや敬遠されがちな小書なのです。
しかし、優れた囃子方が揃っての「女体」は見ていて圧巻、また自分自身舞ってみると、お囃子の音色が身体にビンビン響いてきて、わくわくしてしまいます。
「女体」はシテが神舞(五段)を舞い、力神(手力雄命)も急之舞(神舞の後半)を舞うため、同じ早い舞が続いてしまい、代わり映えのしない印象を受けます。
他流では、そこのところ、シテがゆったりと中之舞を舞い、それぞれの役柄に似合った舞の特徴が出てよい効果を生みだしています。
そこでお囃子方(笛・一噌幸弘氏 小鼓・大倉源次郎氏 大鼓・亀井広忠氏 太鼓・助川治氏)に「女神と力神の違いが出るように囃してほしい、神舞を『高砂』のようではなく、少しゆったりと囃してほしい」とお願いしました。
今回は手力雄命(力神)が特別に面「大天神」をつけること、流儀の面と装束のことなども説明すると、助川氏は観世流太鼓方としての「女体」の心得を話して下さり、全員すぐに納得同意して下さいました。
当日、出番前の亀井広忠氏に「魚町の面を見ておいて」と言うと、「うお?、なるほど判りました」と答えられました。彼なりに神舞・急之舞の世界を思い描いて囃してくれたと思っています。また他の囃子方もご自身の描く「女体」の世界を想像されていたようで、その結果、適度な具合のよい神舞と急之舞になったと、私は囃子方に感謝しています。
今回、私自身「天照大神の神舞(シテの神舞)をどのように舞うか?」を考えました。
「演者は細かな事は考えずに、真っ直ぐに舞っていればいいんだ」と、先人のお声が聞こえてきそうですが、どうも、はっきりさせたがる私の性分で、いろいろと考えてみました。
神舞は弟の素盞鳴尊(すさのおのみこと)が高天原(たかまがはら)へ侵攻してくることへの怒りであると説明する方もあれば、小面を掛けて素早い舞を見事に華麗に舞う芸力を見せる、そうすれば自然と神に見えると唱える方もあり、また総神としての威厳が見せられればいい・・・、と色々様々です。
私は女神の威光、それは太陽そのものであり、広大な高天原にまぶしいばかりに輝く太陽光線のイメージではないだろうか・・・、天照大神の光臨、早い中にもゆったりとした包容力のある女性のやさしい身体の動きが見せたい・・・、いくら早くても乱暴な印象が残るのだけは避けたいと思い舞いました。
さて、皆様がどのようにご覧になられたかが、気になるところです。

今回、謡の詞章で気になるところが二つありました。一つはツレの謡です。
喜多流では、シテの「尉が絵馬を掛けて民を喜ばせばやと思い候」の言葉に対して、ツレは「さように謂われを宣はば、こなたも更に劣るまじ」と終わらせ、続いてシテが「力をも入れずして天地を動かし、目に見ぬ鬼神の猛き心を和らぐる」と謡います。そしてまたツレが「歌は八雲を先として、天ぎる雪のなべて降る、これらはいかで嫌ふべき」と続きます。
観世流はこの姥の尉に対しての反論をすべてツレの言葉として謡います。
それが当然だと思うのですが、どのような訳なのか、喜多流は尉が姥の反論まで謡ってしまう奇妙な演出です。
この老夫婦の言い争いを、自分の生活に置き換えてみると、確かに相手の意見を自らが喋ることもあるので判らないでもないですが、能の舞台という観客に状況を伝える場に於いて、この作りは少々不明瞭、不備だと思います。
今回観世流のように、ツレに反論の部分を全部謡ってもらおうかと思いましたが、披きでもあるので、新しい冒険は控えました。もっとも従来通りで正しいという意見があれば、お教え戴きたいと思っています。
次に後場の出端に謡われる「雲は萬里に収まりて、月読の明神御影の、尊容を照らし、出で給う」の詞章です。天照大神の弟、月読命があたかも登場するかのように謡いますが、実際月読命は登場しません。
これは前場の前シテと前ツレの老夫婦が、実は天照大神と月読命の伊勢の二柱だと告げているために作られた詞章なのかもしれませんが、「女体」でご覧になられる方には、これもまた不思議な光景と似合わぬ詞章だと思いました。
これはこじつけのような私見ですが、天照大神が月読命と両性を備えているとも考えられます・・・。これも同様にご説明して下さる方がいらしたらお教え戴きたいです。
今回は新聞(毎日・産経・日経、記載順)にも報じられましたように、豊橋・魚町能楽保存会のご協力を得て貴重な面の数々を拝借しての演能となりました。
我が家にも『絵馬』に使う面は用意出来ますが、古代の神話を桃山時代や江戸初期に創作された名品の面を借りて演能してみたいとの思いが叶い貴重な経験が出来ました。
前シテは出目友閑の小尉、少し面長な顔立ちですが、能夫は「尉髪の髷がのると丁度よく見える」と話していました。前ツレの姥は、先代金剛流宗家金剛巌氏が足利時代と目利きをされた面でした。しかしこれは生憎、面紐を通すあたりに問題が見つかり、急遽使用を諦めることになりました。万が一のときは、と予め用意しておいた我が家の姥を代用しましたが残念でした。
面は後生大事にお蔵に入れっぱなしでは、木も魂も死んでしまいます。
時には外気に触れ、人間の手に触れ、能楽師が使用してこそ、魂は目覚め生き返ると思います。今回の姥のように使えなくなってしまったり、修理をしなくてはいけない面は全国の神社や寺、または個人の家にもまだまだたくさんあると思われますが、手入れして、舞台にあがってこそ、面もそれを打った面打師も喜ぶのではないでしょうか。
至急、修理や保管の見直しなどの対応を急がなければ、取り返しの付かない事態になるのではと危惧しています。
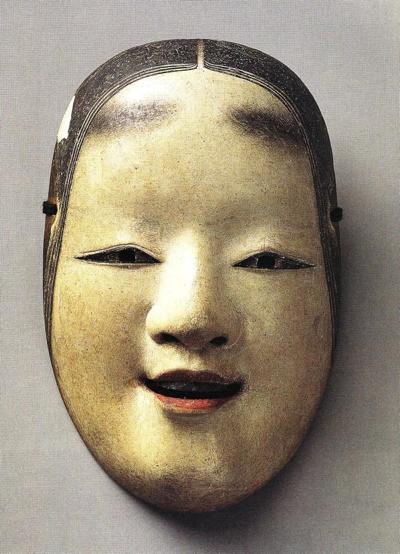
後場の面は、シテ天照大神に井関河内作「小面」、天鈿女命に名品、出目是閑作「増女」、そして手力雄命には作者不明ですが、桃山時代の作と言われている「大天神」を使用しました。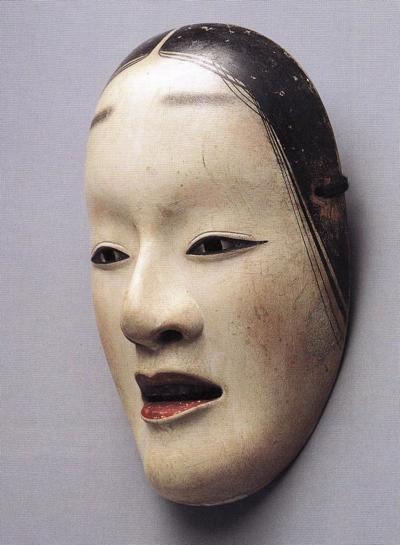
中でも「増女」のすばらしさは楽屋での話題となりました。
実は私も「増女」を掛けて舞いたかったのですが、披きでしたので流儀の決まり「小面」で勤めました。こんなことを書くと河内「小面」に怒られ拗ねられそうですが、勿論この面も天下一の名品です。
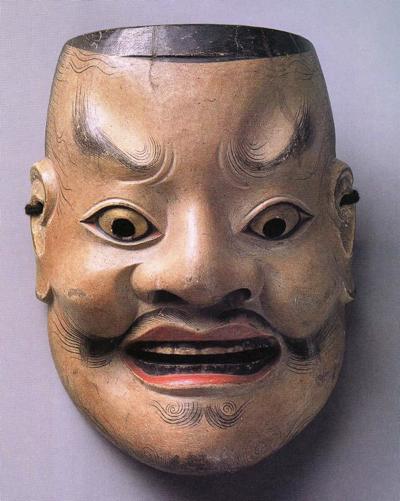
ツレの面は本来「三日月」ですが、浩之君の芸風には「大天神」が似合っていると思い、また、使えるチャンスがあまりない面なので拝見したく、思い切って使用しました。楽屋内の評判はなかなかのもので、効果があったとの意見をいただき一安心しています。
私は能面や能装束が古いものならばなんでも良いとは考えません。新しいものであっても良いものもあります。大事なことは古くても、新しくても、そのものに訴える力があるかどうかです。見る者の心に伝わるものがあれば、それでいい、それが本物だと思います。
私は常に本物に触れていたいと心掛けています。
では本物はどのようにしたら見極める事が出来るか、それは感性が第一でしょうが、時間をかけての経験と、好奇心をもって見ていれば、見極める力は自然とついてくるのではないでしょうか。
今回、魚町保存会の方々のご支援で、よい経験をさせていただきました。魚町保存会に感謝申し上げます。
この貴重な経験を大事にして、次の能へとまた志を新たにして行きたいと思います。
(平成20年10月 記)
写真
1 後シテ 粟谷明生
撮影 吉越スタジオ
2 橋掛にて 左より手力雄命 粟谷浩之 シテ 粟谷明生 天鈿女命 内田成信
撮影 吉越スタジオ
3 後場 左より手力雄命 粟谷浩之 シテ 粟谷明生 天鈿女命 内田成信
撮影 岩田アキラ
4 前シテ 粟谷明生 前ツレ 大島輝久
撮影 岩田アキラ
5 小面 井関河内作
撮影 粟谷明生
6 増女 出目是閑作
撮影 粟谷明生
7 大天神 作者不明
撮影 粟谷明生
『采女』小波之伝の新演出投稿日:2008-09-05
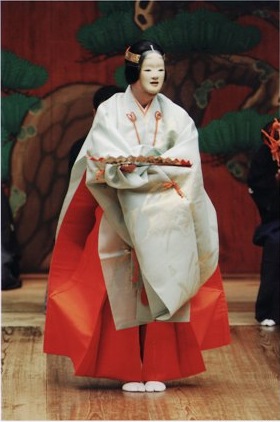
『采女』小波之伝の新演出
大槻自主公演にて
粟谷明生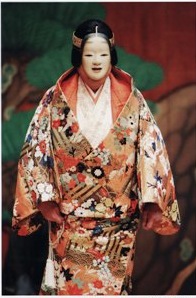
『采女』のレポートを書くにあたって、まず初めに、私に大槻自主公演(平成20年9月5日)での演能の機会を与えて下さいました大槻文蔵氏に深く感謝の意を申し上げたいと思います。
父(故・粟谷菊生)は大槻自主公演発足時より、喜多流を代表して、この会に客演したことをとても喜び、誇りにしていました。
異流公演となった『隅田川』(シテ・大槻文蔵氏、地謡・喜多流・地頭 粟谷菊生)の終演後、父が「よい思い出になるな」と笑顔で話していたのが、ついこの間のように思い出されます。父亡きあと、私にお声をかけていただきましたこと、父同様、私も大変光栄に嬉しく思っています。
ここで裏話をしますと、今回大槻文蔵氏からの出演依頼の曲は『邯鄲』でした。
しかし、『邯鄲』は、今年の春の粟谷能の会に予定されていましたので、演能意欲やチケットの売れ行きなどを考え、『采女』小波之伝では、とお返事しました。
すると「夜の公演で開始時間が遅いので、『采女』は長過ぎませんか」とのご意見でしたので、一時間程度で終わる小書「小波之伝」のご説明をさせていただき、ご了承いただいたという経緯がありました。
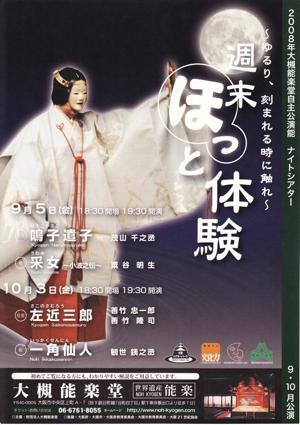
でははじめに、普通の能『采女』はどのような場面展開かをご紹介します。
前場は春日大社の縁起物語が多くを占めています。
一人の女(前シテ)が登場し、春日大社を建てた際、藤原氏が木を植えると春日明神が喜んだので、それ以後、参詣者は木を植える風習が流行った由来を語り、「盛りなる藤咲きて」と藤原家を賛美します。
前場の後半にようやく、采女という女性の仕事の役割の紹介や采女の入水の物語を語り、実はその釆女の霊と名乗ります。(中入)
後場は釆女の霊が女人でも成仏出来た喜びを中心に、法華経の賛美、クセでは安積山の故事の話、また藤原家の治める御世の祝言などが入り、作品の内容は豊富で、演能時間は二時間近くにもなります。このあまりにも長い演能時間とやや冗漫な作風のためか、我々能楽師は一度は勤めてみても再演となると、つい敬遠しがちになっています。
先代十五世喜多実宗家は晩年『采女』を再演される時、体力面で長時間の演能はきついと判断され、この主題満載の構成を短縮した小書を創案されました。
これが、当初『佐々浪之伝』と命名し、二回目以降『小波之伝』とされた小書です。
小書作成には土岐善麿氏が御相談役を引き受けられ、詞章部分は土岐氏の意見が反映されています。
しかし、残念ながらテーマの絞り込みの曖昧さなどを指摘する向きもあり、この小書はあまり評価されませんでした。
私は小書「小波之伝」を、能『采女』にこめられた主題を外さずに、しかも、喜多流能楽師が敬遠しないで、もっと身近に勤められるものにしたいと考え、粟谷能の会・研究公演(平成9年)において新演出を試み、その後、粟谷能の会(平成15年)に再度演出を変えて勤めました。今回、過去の二回の経験をふまえ、さらに工夫を重ね、テーマを一つに絞り込んで、コンパクトでありながら能として充分楽しめる曲作りを目指しました。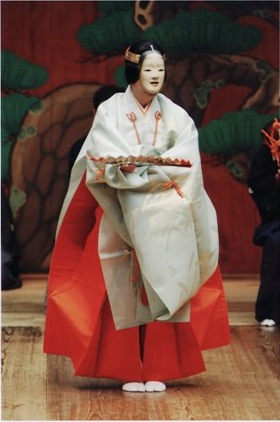
では、今回の改訂版「小波之伝」について、テーマと短縮された物語の展開をご紹介しながらレポートします。
采女とは、古代天皇の身の回りの世話に従事した女官です。彼女たちは地方豪族の容姿端麗な娘たちで、能『采女』は一人の若い采女を主人公としたものです。
小書「小波之伝」は、通常の『采女』の春日大社の縁起や藤原家を賛美した部分を削除し、采女の女が現世の苦患を超えて仏果得脱して清逸な境地を得ながらも、さらに昇華を望む物語として再考しました。
采女の女は入水し、地謡は「君を怨みし儚さは」と謡いますが、それは現世でのこと。
来世までも怨みや悲しみを引きずるのではなく、むしろ、死後の浄土の世界を美しく繰り広げるものです。そのため仏教賛美の色合いが少々濃くなりました。
女人も成仏出来ると説く法華経の教えは、女性はまず龍女となり次に男性へと変わって成仏するという考え方で、現代の女性にはご不満で腑に落ちない部分もあると思います。
しかし男女を問わず、人間の輪廻転生、生まれ変わる、という東洋人特有の願望を基盤にして一曲の組み立て方をしてみては、そこに焦点を当てるのはどうだろうと、改訂しました。
では舞台進行とともに改訂したところと私の意見をご紹介します。
都の僧(ワキと従僧ワキツレ二人)が奈良春日大社に着き参詣しているところに、ひとりの女が数珠を持ち、アシライ出にて本舞台に立ち「吾妹子が寝くたれ髪を猿澤の池の玉藻と見るぞ、悲しき」と和歌を詠みます。
僧が女に猿澤の池を尋ねると女は池へと案内し、采女の女が身を投げたこと、その謂われなどを語り、僧に供養を頼み、実は自分がその霊だと明かして池に消え、中入りとなります。
僧は里人にも采女の入水の話を聞き、夜の読経を池のほとりではじめます。
すると采女の女がありし日の姿で池の底より一声にて現れ、橋掛りの一の松辺りに立ち、読経の礼と成仏の喜びを僧に述べます。そして僧と釆女が「悉皆成仏は疑いない」とお互い確認しあうと、地謡はこの小書のテーマとなる「ましてや人間に於いてをや、龍女が如く我もはや、変成男子なり、采女とな思ひ給ひそ。而も所は補陀落の、南の岸に到りたり。これぞ南方無垢世界、生まれんことも頼もしや」を謡います。
恥ずかしながら、私はあの世とか浄土とは、何もしなくてもよく、楽に幸せに暮らせるところ、と想像していました。しかしどうもそう簡単で気楽なところではなさそうです。
仏教も、その教義はいろいろ様々でしょうが、ここでは能『釆女』の取り上げている法華経を主に考えますと、また男女差別のこととなり恐縮ですが、西方浄土は男性が、南方世界は女性が来世に行くところと区分けされていて、補陀洛は南方の観世音菩薩の修行の場です。
私は菩薩になれればそれなりに幸せでいられると思っていましたが、さらにその上の世界、如来の境地まで修行しなければ最高位にはなれないことを知りました。菩薩は涅槃に到るための修行の段階なのです。僧に幾重にも回向を頼むのはそのためかもしれない・・・・。
そう考えると、舞台上では池の底から現れる采女であっても、実は補陀落浄土という天上界の高いところから降りてくるイメージが思い浮かび、そのように、と勤めました。
話を舞台進行に戻します。
その後は、本来あるべき春日明神の賛美や、采女の安積山の歌物語などを省き、序之舞へと続けました。
「生まれんことも頼もしや」と僧へ合掌した後に、詞章を観世流の小書「美奈保之伝」のように「取分き」を「さるにても」に替え「さるにても忘れめや、曲水の宴のありし時、御土器(かわらけ)たびたび廻り、有明の月更けて、山杜鵑誘い顔なるに、叡慮を受けて遊楽の」に移行し、采女が帝に仕えていた時代の雅な情趣を少し添えました。
大胆な削除であっても、『釆女』という曲がもつ雰囲気、香気といったものを、残しておきたいと思い、ここは敢えて削除出来る個所であっても省くことをやめました。
昔、お酌をしながら眺めた、有明の月、山杜鵑の声も聞こえ、と遊楽ははじまるのです。
そして時間短縮でこの小書を面白くさせるもうひとつのカギ、それが序之舞の構成です。
今回の改訂では、序之舞の導入部分とその構成に心を砕きました。
前回は序之舞に凝りすぎて時間もかかり過ぎた反省があったため、その辺も考慮して、
あまり鈍重ならず、しかもしっとりして優美に、主人公が次第に昇華していく様を表現出来ればと考えました。
(ここからは楽屋内の細かい話となりますので、ご興味が無い方は、次の面の話へと読み飛ばして戴いて構いません。)
序之舞への導入は、通常、拍子不合(ひょうしにあわず)のリズムに合わないノリで和歌が詠われ、途中から笛が吹き出します。
例えば、『半蔀』ならば、地謡が「折りてこそ」と謡う途中から笛が吹き始め、序之舞が
はじまり、舞が終わるとまた繰り返すようにシテは「折りてこそ、それかとも見め、黄昏に」と和歌の全部を詠むのが定型です。
前回は「生まれんことも頼もしや」の後に先代宗家がなさった「吾妹子が・・」をいれて序之舞としましたが、今回は、普通ではない特別な対応をお囃子方(笛 杉市和、小鼓 成田達志、大鼓 白坂保行)にお願いし、この異例なことを了承していただきました。
地謡の「誘い顔なるに、叡慮を受けて遊楽の」という拍子に合った謡の直後に笛が吹き出し序之舞に入るという新形式です。序之舞の構成は掛・初段・二段と短い三段構成としました。初段オロシでゆっくりと池を見込む型が入り、次第に補陀洛世界へと昇華していく境地へと気持ちも高揚し、ノリも次第に早まり最高潮となります。
二段目は短く、橋掛り(一の松)へと移動し、舞の留めは『松風』見留の破之舞を真似て、譜は呂に落とし、「猿澤の池の面」と謡います。
それ以後本舞台には敢えて戻らず、僧から遠ざかりながらも、池の底へ戻りながら回向を願う型としました。
では今回使用した面についてご紹介します。
シテの面は喜多流では小面が決まりですが、私は前回粟谷能の会と同様に「宝増」を使用しました。この面は岡山の林原美術館にある「宝増」の写しですが、小面と増女の中間、かわいいと大人びた表情の双方の幽艶さがあり、私は気に入っています。
実は、前回は九世観世銕之丞氏にお願いして銕仙会所蔵の宝増を拝借しました。
そのとき、銕仙会の笠井賢一氏より、「あの面、君にとてもよく似合っていたよ」と言われ、それが忘れられないでいました。
父が愛用面とした「堰」の小面も先代喜多実先生から「菊生、いい面だね、おまえには勿体ないくらいだ」と言われたことがはじまりです。
面との出会い、面への信頼は能楽師の演能に大きな心の支えとなります。
以前から我が家にも「宝増」があれば、と思っていましたが、近年その願いが叶いました。今回この「宝増」が小波之伝や、私に力を発揮してくれたのでは、と私は信じています。
以上が今回の演能レポートですが、総括して振り返ると、
改訂小波之伝は、補陀落浄土という無垢世界に生まれ変わった喜びを優艶に美しく表現することが主題となったということです。
今回三度目の挑戦で、ようやく『采女』小波之伝の新芽が出はじめた感があります。
将来、どなたかにシテを勤めていただき、私は地謡にまわり別な視線、観点で舞台を創り上げたいと思っています。
最後になりましたが、この小書演出にご理解をいただきご指導と地謡を謡って下さいました、我が師友枝昭世師に深く感謝申し上げます。
また改作にご協力いただきました方々、「小波之伝」出演者の皆様、鳥居明雄氏、木澤景氏、横山晴明氏の方々にも厚く御礼申し上げます。
(平成20年9月 記)
写真 『釆女・小波之伝』
シテ 粟谷明生
撮影 森口ミツル
興行を請け負う立場になって投稿日:2008-08-01

興行を請け負う立場になって
―薪能で能の世界へどうぞ―
粟谷明生
午後2時の外気温は35度、猛暑日の夜、豊橋の吉田城本丸跡広場にて吉田城薪能(平成20年8月2日)が行なわれ、能『船弁慶』を勤めました。
今回の演能レポートは、能公演の依頼を受ける能楽師の立場を舞台裏からご紹介したいと思います。
今回主催する三河三座は能楽など古典芸能を地元三河地方に普及しようと発足されたNPO法人のボランティア団体です。その三河三座より薪能公演の依頼があったのは一年前でした。豊橋近郊のはじめて能をご覧になる方はもちろん、何度かご覧になられている方々にも、もっと能を身近に感じ楽しんでいただければ、そのお手伝いをしたいと思いご依頼を承諾しました。

能の催しの善し悪しは企画する側の取り組み方次第で決まり、面白くも平凡にも、またつまらない企画にもなります。
応援して下さる団体の経済力や宣伝力が興行に大きな影響を及ぼしますが、大事なのは実際現場で請け負う人がどのような考えに基づいて番組構成をして結果を出すかです。
能の興行の請負人には能楽団体の事務関係者や代表責任者もいれば、私のように能楽師自ら個人で受ける場合もあります。
今回、吉田城薪能の公演は三河三座から私個人に依頼がきましたので、私は私なりの薪能への考え方を反映したいと思い、企画に意見を言わせて頂きました。
“薪能”と聞くと「夏の夜の清々しい屋外で、雅で幽玄な世界の舞と謡」
などと想像されると思います。
確かにそのような好条件での薪能もありますが、それは非常に稀なことで、内幕は、まずほとんどが悪条件の下で能楽師も裏方現場スタッフも舞台を勤め、働いています。
演者は、蒸し暑い中、装束を着附け、出番前に既に大汗をかいています。
優美な篝火の炎の煙は、風向きによっては演者には煙たく謡に支障をきたします。
また舞台照明は虫などを舞台に集め、演者の妨げになることもあります。
また屋外での音声は音響技術を駆使しなくては観客には聞こえません。
吉田城薪能もこのような悪条件が容易に予測できました。
しかしどんなに暑くても、折角ご来場して下さる方々に「来てよかった!」「今度は能楽堂で観てみようかな」と思っていだだきたい、どのようにしたら、観客が満足して下さるか、を考えました。最近は様々なアイデアやプランがありますが、私は次のように考え企画演出しました。
まず第一に出演者の顔ぶれを揃えることにしました。
よい顔ぶれは当然、観客動員数を増やします。豊橋という地で、喜多流という小さな流儀の、しかも私のようなマイナーな個人が請け負う場合、当代の人気者能楽師の出演は力になり効果覿面です。今回は狂言師として、またテレビや映画でもご活躍の野村萬斎氏に狂言を、笛は幅広い音楽活動をしてご自身のバンドのCDも発売されている一噌幸弘氏に出演依頼して、能だけではない観客も取り込んでの公演にしようと思いました。
第二は曲目の選択です。能公演では出演者と同時に、能そのものに満足していただくことが重要で、曲の選択もカギを握っています。物語が判り易く、舞台進行の流れが良い曲が最適と考え、私は『船弁慶』を選びました。
今回、薪能の公演時間は二時間で、能の演能時間は一時間以内という制約がありました。
はじめは『船弁慶』は演能時間が長いので無理かと諦めかけていました。
しかし、一時間以内で、どうにか遜色のない見応えのある『船弁慶』短縮版を公演出来ないものかと思い、新演出を試みました。
はじめて能をご覧になる方、今までに一、二度しかご覧になられたことがない方々には、役者の動きが無い部分は退屈に感じられるだろう、出来る限り動きを中心にした舞台進行のよい流れに重きをおき、演出しようと考えました。

ここでちょっと『船弁慶』の曲について楽屋話をします。
『船弁慶』はシテ方の小書だけでなく、ワキ方や狂言方の小書も付くと長時間に及びます。
過去に霞会(脇方・故松本謙三氏の主催の会)でシテ・故粟谷新太郎で『船弁慶』真之伝・浪間之拍子・船中之語・早装束・舟歌の小書揃いで二時間二十分もかかった記録が残っています。もっともこれは特別で、通常最近の自主公演や例会では、一部を割愛して一時間半ぐらいにして演じています。
一番立ならば二時間を超えての番組も許されますが、三番立ての留(とめ)にあまり長時間の番組構成はバランス的にあまり誉められたことではありません。長時間の『船弁慶』を催す場合は、初番や真ん中の曲目を短めの曲や軽い曲にするという方法をとっています。
話しを薪能に戻しましょう。
では屋外の能、というものはどのように演じたらよいか。
私の経験上、屋外の演能は屋内の能楽堂や劇場とは違います。
屋外は、時折吹く風を感じ空気も清々しく気持ち良いものですが、反面、開放感が強すぎるためか、屋内で感じる演者と観客の密な緊張感は生まれ難いものです。
演じ手が精一杯舞台を勤めても、なんとなく物足りなさ、空振りしたような空虚さを感じることがあります。それは屋外と屋内の違いもありますが、それだけではなく、屋外に対応する能役者の取り組み方にも原因があります。
楽屋内の話しですが、能は屋外と屋内で同じように演じても、残念ながら同じ効果が出ません。そのことを能楽師が把握しておかなくてはいけません。
観客の皆様はさほどその違いがお判りならないかもしれまんが、楽屋裏ではこの微妙な違いを感じ、苦心し工夫をこらして演じている能楽師もいるのです。

もっとも、今のような屋内で屋根が付いた能舞台という奇妙な構造の劇場で演じるようになったのは近年のことで、能発生から江戸期の頃は、屋外中心の活動、興行であった訳ですから、昔の能役者は常に屋外用の演技をしていたことになります。
ですから私の意見は、今の演能ではどのようにしたらよいか、今に拘ってのことです。
私は、初心者向けで、屋外のしかも時間制限がある特殊な条件下の能は、短く判りやすい作品を選び、卓越した技の持ち主が観客にその思いが直に伝わるような設定を心掛けるべきと思います。
今回当日になって、音響映像担当者から一つのアイデアが提案されました。
舞台裏のお城に映像を映そうというのです。潮が巻いたり、波の音をたてたり、白色や赤色、青色の映像です。私は一瞬返事に困り、失礼かと思いましたが、すぐにお断りいたしました。
演劇には映像や音、煙など、いろいろな最新設備や技術を使った新演出があり、それを楽しみにしている方々もおられるかもしれません。それはそれでいいと思います。
しかし私は、能とは、観る者の想像力に委ねるところが最も大事なところだと思っています。観客の想像力を奪って、それをサービスだと考えるのは勘違いです。いくら時間を短くしても観能の基本からは外れたくないと思いました。
私が携わる能は演者たちの演じるエネルギーをより観客に伝わるようにと心掛け、それを最優先にしたい、それを邪魔するものはいらないのです。
粟谷明生に頼むと、最新型の演出は出来ない、奇抜な演出は期待出来ないと評判が立っても構わない。逆に、粟谷明生だから絶対に煙りが出たり不似合いな照明はない、と言われるほうがよいのです。
今回は二時間の演能時間の枠の中に、野村萬斎さんと私の舞台あいさつ、火入れの儀、舞囃子、狂言そして残った時間で能という流れになりました。演者たちは暑さを我慢し、エネルギーを集中して勤めてくれました。私も前シテ・静御前、後シテ平知盛と早代わり、両者の違った個性が引き立つよう懸命に勤めました。
地元の定盛友紀君の子方・義経の登場も新聞に取り上げられるほど興味を引くもので、ご来場の皆様には楽しんでいただけたのではないでしょうか。
時間の制約もありましたが、工夫を施せば短時間でも『船弁慶』を楽しんで頂ける、かえって制約があるからこそ、よい結果を出せたと思っています。
「あっ!もう終わってしまったの!もうちょっと見ていたかった!」と観客を唸らせられればと思っていましたが、後日、ご来場頂きました方から、「能や狂言の世界が身近に感じられた」「退屈するかと思っていましたが、充分楽しめた」というご感想をいただき、実は一番喜んでいるのは私なのかもしれません。
そして、スタッフの方々は舞台作り・会場整理からはじまり、すべてのことを献身的にやってくださいました。心より感謝申し上げます。
能を愛好する民間の人たちが、能の舞台公演に骨を折ってくださる、この様な試みを試行錯誤してやっていけたら、そして、こういうことを通して全国的に能が広がっていけばいいな、それも喜多流の能が広がっていけばよいな、と思いました。
(平成20年8月 記)
写真 撮影 新村 猛
写真1 ご挨拶 粟谷明生
写真2 能『船弁慶』前シテ 粟谷明生
写真3 能『船弁慶』後シテ 粟谷明生
友枝昭世の会『求塚』の地謡を勤めて ー 間語りから見えた男達の思い ー投稿日:2008-05-24
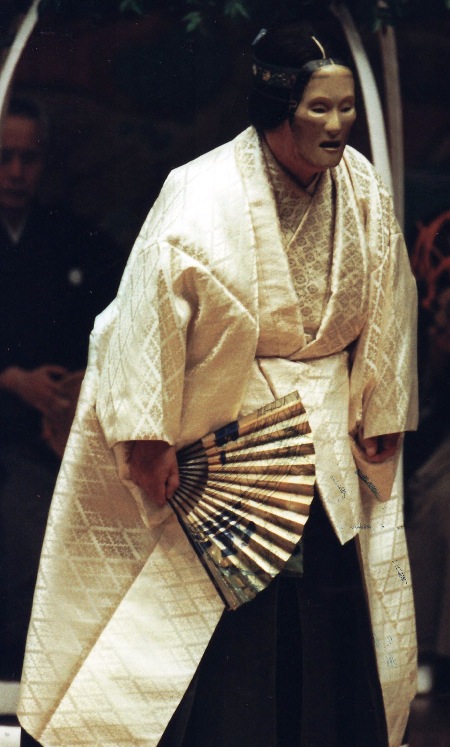
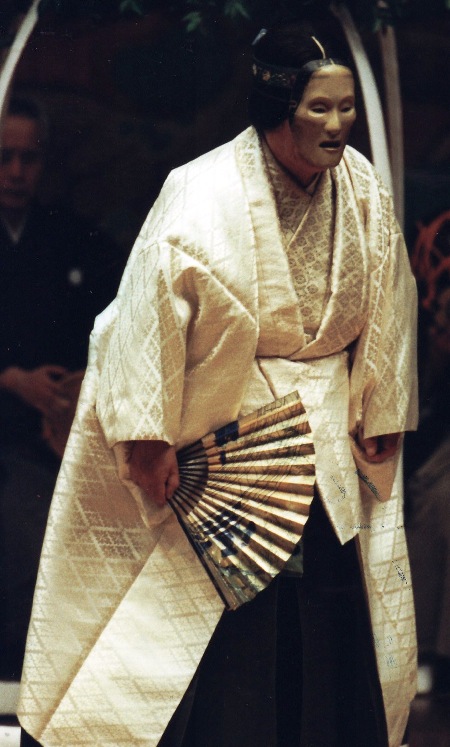
『求塚』は地謡がよくなくては成立しない!
と言われています。
「優れた演能には地謡がシテの演技を支える上で最も大切なの、
その充実を課題としたい」
と『求塚』を選曲し、友枝昭世氏にシテをお願いして地頭を粟谷能夫、私も微力ながらその隣で謡う会を試みたのは、粟谷能の会・第三回研究公演(平成5年5月)でした。
あれからもう15年が経ちました。
今回、友枝昭世の会の『求塚』(平成20年5月)で地謡を勤め終え、新たな発見がありましたのでここに書き留めます。
装束のこと、ツレのこと、いろいろな発見がありましたが、今回、一番気になったのは間語りです。地謡座で間語りをつぶさに聞いて、私のこれまでのいくつかの疑問が解けてきました。
間語りは、研究公演では野村万作氏、今回は山本東次郎氏がなさいました。
『求塚』の間語りは通常は菟名日処女(うないおとめ)が生田川に身を投げ、それを知った二人の男、小竹田男(ささだおのこ)と血沼益荒男(ちぬのますらお)が塚の前で刺し違え果てるところで終わります。
しかし近年はその後も語るのが普通の形式となって、かなり長い間語りとなります。
その後の語りの概要を先日の山本東次郎氏の語りを元にご紹介します。
「刺し違えた男の親達は嘆き、菟名日処女の塚の両隣に塚を作 り葬りました。
このとき小竹田男の親は刀を一緒に葬りました。あるとき旅人が求塚の前を通ると、ひとりの男が現れ、刀を貸してくれと頼むので、旅人は刀を貸すと、男は喜び消えていきます。
しばらくすると血まみれになった先ほどの男が現れ礼を言うと、また消えてしまいます。夜が明け男の塚を見ると血のついた刀が置いてありました」
このように終わります。
能の作品を読み込むとき、シテ方の私は流儀の謡本だけに頼りすぎる傾向がありました。
狂言方の間語りには本筋が述べられているので、曲の主軸をしっかり捉えるためには、間語りも把握しておいたほうがよいようです。
手元に研究公演の野村万作氏と今回の山本東次郎氏の資料があります。
双方を比べ、私のわからなかった謎解きをしながら、また後日に山本東次郎先生に伺ったお話を添えて、『求塚』の訴えたいものを探し出したいと思います。
まず喜多流の謡本では解読出来ないところ、私が気になったところをいくつか挙げ、その答えを間語りの中から見つけ、あらすじの裏打ちをしたいと思います。
謎1;二人の男はどこの人か?
山本家の間語りは小竹田男が摂津国、血沼益荒男は和泉国の者との紹介から始まります。
謎2;鴛鴦を撃って決着する提案は、菟名日処女が考えたことか?
喜多流の謡本には女の考えで鴛鴦を射止めた方に靡くとありますが、間語りでは女が両親に相談し親の指示であったと語ります。
謎3;菟名日処女の死骸を取り上げたのは誰か?
喜多流の謡本はまったく触れませんが、間語りでは、女の両親が嘆き取り上げ葬ります。
謎4;女はなぜ入水自殺をしてしまったのか?
間語りでは、恋路の判断のために鴛鴦を殺してしまった罪悪感と語りますが、私はそれ以上の何かがあったと思えてなりません。
謎5;女の入水で、なぜ二人の男が刺し違えなければいけないのか?
間語りでは、女が死んでは仕方がないと、両者落胆して命を落としますが、
これも謎4と同様、裏があるように思えます。
謎6;血沼益荒男の塚に刀が埋葬されなかった理由は?
和泉流の語りには、血沼益荒男の親は愚かなため刀を入れなかった、とあります。
以上のことから私の推察を書いてみたいと思います。
二人の男が一人の女に同時に恋をして、女は判断に耐えられず自殺する、実らぬ恋に男達も嘆き後を追い、命を落とす。
一見単純なラブロマンス・純愛物の作りに見えますが、実は裏側に大きな大人の力が働き、男女それぞれの運命を変えてしまったのではないでしょうか。
シテが「同じ日の同じ時に、わりなき思いの玉章を送る」と謡い、間語りでも二つの恋文が書き方までまったく同じと苦笑するかのように聞こえたところがあります。
同じ日、同じ時、同じ文面、何もかもが同じというのはどう考えてもおかしい、絶対裏があるはずと、疑いたくなります。
たとえ恋文にひな形らしきものがあったとしても、そこに個人の感情が溢れていないのは周りが作為したとしか思えません。この恋文も悲劇の隠し味になっていると思います。
では、この「裏」とは何でしょう?
それはこの恋が個人的な思いだけではない、家や村という組織をあげての女の獲得であり、そこに両者の駆け引きがあったと思われます。
仮説を立てると、菟名日処女には特別な力があって、たとえば霊力のようなものです。
それ欲しさに地元の小竹田男と隣国の血沼益荒男に任命が下だり、両者は女を手に入れるための道具となった・・・。
万が一、女を相手に取られたらば、家だけではすまない、村や地域という組織の存亡にもかかわる一大事となる。ですから男たちは是が非でも女と契りを結ぼうと必死になるのです。
個人的な「あの娘がかわいくて・・・」のような感情だけではない、男達に背負わされた重い責務があったのではないかと想像してしまいます。
しかし男達やその背後の努力も空しく、もくろみとは裏腹に結果は大事な女の死、という最悪な事態となります。そして、女の死は男達にとっても終わりを告げます。家に戻りこの結果をどのように報告、説明すればいいのか、そんな重圧が二人にのしかかります。
「もう家には戻れない」「行き先がない、死ぬしかない」と二人の男は追い詰められ、刺し違えて死ぬ、という哀れな結末となるのです。
これを、恋しい女に死なれ後を追う美談として、オブラートで包み覆っているのが、能『求塚』ではないでしょうか。
そして、菟名日処女と同国の小竹田男の両親は塚に刀を葬ります。�の血沼益荒男の塚には刀の埋葬がなかったのは、和泉流では「親が愚かのため」と露骨に語りますが、山本家の語りではそのような話は入りません。本当に親が愚かであったのでしょうか?
私は隣国の者がそう易々とその土地に入り得ない交通事情、部族のしきたりなどもあって弔えない状況、様々なものが遮って邪魔をしたのではないかと推察します。
それは小竹田男の男と血沼益荒男の名前からも想像出来ます。血沼益荒男は荒くれ者の感じで、侵入者のイメージです。
侵入者の血沼益荒男にとって、地獄に堕ちても、地元の小竹田男から永遠の責め苦をうけることになります。なんとも救いがたい恐ろしい世界です。
益荒男は一時、刀を貸してもらい反逆に出ますが、彼らは輪廻の如く地獄に堕ち続け、侵入者血沼益荒男は責め続けられるのです。そこに救いがまったくないのが男の私としては寂しくもあり、気になるところです。
そして『求塚』の最大のテーマ「そんなことまで私の科なのでしょうか」と女は旅僧に救いを求め回向を頼みます。
能の稽古をうけシテを経験し、実際の舞台で作品に触れると、一人の女が政治的に使われたことの哀れさが肌に伝わってくるようです。どうにかして救ってあげたい気持ちになります。
曲の最後に、地獄の有様を見せて暗闇となると、菟名日処女は火宅の栖を尋ね、求めて、塚の草の陰に消えます。
静かに『求塚』は終曲しますが、成仏できた、とは謡いません。
なんとも悲しい話ですが、私はこの悲劇を三役も含め役者全員が力を振り絞って演じ囃すことで、菟名日処女をひとときでも成仏させるのだ、と念じ謡いたいのです。
最後の「火炎も消えて」は強く謡い、次の「暗闇となりぬれば」で気持ちを変え、調子も変化させたい、むずかしい謡どころです。
友枝氏は
「昔はキリの謡の調子が高くて。張りすぎ、つっちゃってね。?暗闇となりぬれば?はもう転調せずにはいられない程で、自然と転調してしまう、それで演っていたんだよ。しかし、今それがいいかと言うとちょっと疑問だね?。あそこまで張るのがいいとは思えないからね?」
と話されました。
ここの謡い方については私の今後の課題となっています。
後シテの装束について、伝書には次のようにあります。
「後痩女・箔・腰巻・腰帯の上に水衣肩上げ」
「色大口袴・白練坪折ニテモ」
先人たちは水衣・色大口袴が多く、父も伯父の写真も水衣・大口袴ばかりです。
しかし、近年は色大口・白練坪折が主流と変わりました。
今、喪服は黒色ですが、日本はずいぶん長い間白色が主流でした。
昔は喪服といわず浄衣(じょうえ)と言い、清潔な着物を着せて死者を送ろうとし、純白こそ一番死者を送るのにふさわしい色だと考えていました。
『求塚』や『砧』など浄衣の姿を意識すれば、箔も白練も白色の着用が適当です。
今回も前回も、友枝氏はすべて白色を選択されたことは理に適っていて私は大いに賛成するところです。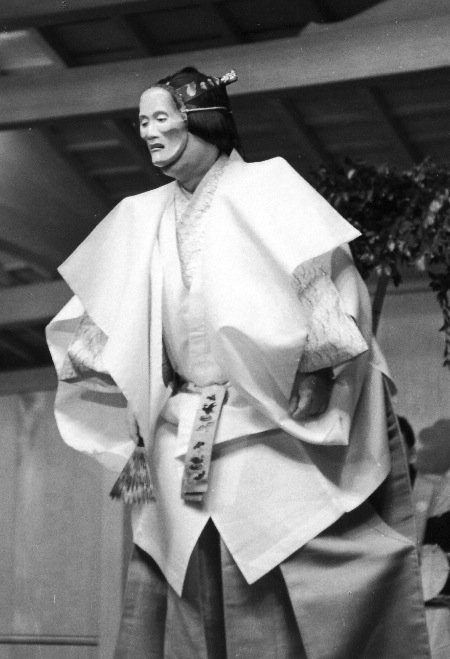
引廻が下ろされ、後シテが現れた姿を見たときは、死者と言うよ
りも美しく輝きを発散する、凛とした女性、あの世からのメッセンジャーのように私の目には映りました。
救いのない『求塚』ですが、浄衣の姿で描き、地謡も役者もすべてが全力で弔う舞台になったのではないかと思っています。
痩女物の代表曲は春の『求塚』、秋は『砧』です。
壮絶な死を扱うのは『求塚』です。
私は『求塚』はまだ披いていないので、『求塚』への熱い恋心が覚めないうちに是非とも早く勤めたいものです。
今回の語りについて、後日、山本東次郎氏にお話を伺いましたのでご紹介します。
明生 「先日の『求塚』の語りは面白かったですが、あれは新たに横道萬里雄氏が創られたものですか?」
東次郎「いえ、違います。大蔵の分家、八右衛門家にあるものを当家が伝承しています。以前、寿夫先生が『求塚』を演られるときに、全部語る間を御存知で御所望されたので、やるはずでした。残念ながら寿夫先生が亡くなられましてそれは果たせずにいました。
その後、静夫先生(故観世銕之亟)のときに私が勤めました。
ですから、新作ではありません」
明生 「血沼益荒男の刀について、親が愚かだから一緒に埋めなかったとか、長年の怨み思い知れ!みたいなことを血沼益荒男が言うのは語られましたか?」
東次郎「いいえ、それはないです」
明生 「和泉流だけですね。この間語りを山本家では、東次郎先生しかやれないというのは本当ですか?」
東次郎「みんな長いから、やりたがらないだけですよ(笑い)。実は先代まではやっていなかったのですよ。私は今の時代ならばもういいかな、と思いやっております」
明生 「どうしてやらなかったのでしょうか?」
東次郎「たぶん、生々しくドギツイ語りが能に合わないと控えたと思います」
明生 「なるほど・・・。お聞きしてそんな風には感じませんでした。私は適度な壮絶感が気に入りました。お忙しいところすいません、有難うございました。」
下記に2つの公演の配役を記します。
(研究公演の配役)
シテ 友枝昭世
ツレ 内田安信・塩津哲生
ワキ 宝生 閑
アイ 野村万作
笛 一噌仙幸
小鼓 北村 治
大鼓 柿原崇志
地頭 粟谷能夫
副地頭 出雲康雅
(友枝昭世の会の配役)
シテ 友枝昭世
ツレ 内田成信・大島輝久
ワキ 宝生 閑
アイ 山本東次郎
笛 一噌仙幸
小鼓 鵜澤洋太郎
大鼓 柿原崇志
地頭 香川靖嗣
副地頭 粟谷能夫
写真
カラー 『求塚』シテ 粟谷菊生
大槻自主公演 撮影 濱口工房
モノクロ 『求塚』シテ 粟谷菊生
喜多別会 撮影 宮地啓二
『三輪』における小書「神遊」の効果投稿日:2007-10-14
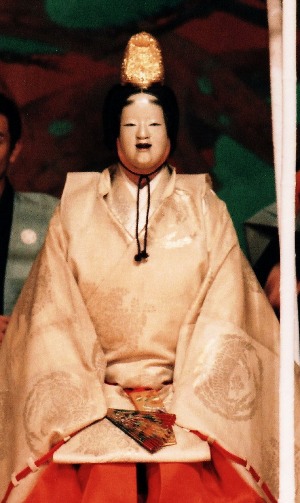
『三輪』における小書「神遊」の効果
女姿の男神
粟谷明生
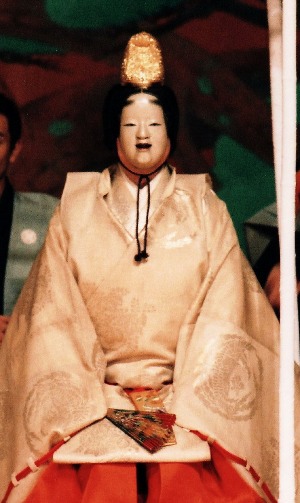
第82回粟谷能の会 粟谷菊生一周忌追善(平成19年10月14日・於 国立能楽堂)にて『三輪』「神遊」(かみあそび)を披きました。
「神遊」は青年時代から先人たちの舞台を楽屋裏や地謡座から拝見しながら、「いずれ自分もあのような装束で、あのように舞えれば」と憧れた小書です。
『道成寺』を披いてから許される、という流儀内の暗黙の了解事項があるくらい位が高い小書でもあります。
今回の番組を決めたのは二年前、父に地頭を謡ってもらいと考えていましたが、まさかその父の追善でこの大曲を勤めることになろうとは思ってもいませんでした。
能楽師の憧れであるこの大曲を勤められたことを、きっと父は喜んでくれていると思っています。
『三輪』はよく演じられる秋の代表曲です。
私の初演は平成六年(三十九歳)とやや遅いですが、稽古は若いときからでも受けられ、青年の会の番組にもよく載ります。
我々喜多流では先輩方の地謡を謡い、また仕舞や舞囃子の稽古を積みながら理屈抜きの反復による稽古方法で習得してきました。「老いても間違えないでいられるには、若い時分に謡や舞を身体に染みこませておくこと」、父が話していたことが、いま52歳になり舞台への恐怖感を少し覚えるようになって実感しているところです。
しかし単に、体に染みこませ、覚えただけで作品の真意を見据えることを蔑ろにしてはいけない、『三輪』神遊の主旨は何か、また「神遊」とは何か、単に囃子の秘事の解明だけではなく、曲の深層部、真意などを探りたいと思っていました。
今回の演能ではいまの自分の状況を客観視でき、今後の方針も考えるよい機会となりました。
単純にみえて実はかなり混雑したこの物語を理解するために、まず、私なりの解釈であらすじを追ってみたいと思います。
奈良、三輪山麓に庵を結ぶ玄賓という高僧(ワキ)のもとに、三輪の里に住む中年の女(前シテ)が毎日樒と水を供えにやってきます。
女はただ徒に年月日を送った身を嘆き、罪の救いを求めて庵へ通います。
秋の日、いつものように救済を願う女は僧に衣を所望します。
観世流は「夜寒になり候へば」の詞章の通り、寒さから衣を所望するようですが、喜多流は「わらわに御衣を一衣賜り候へ」としか告げないため、私は衣を拝領して弟子になると解釈して演じます。
前シテの女は実は三輪明神の化身ですが、これで神が仏に帰依するという意味あいになり、現代人の我々には一寸しっくりこない複雑な関係で展開されます。
衣をもらった女は帰り際に住み家を尋ねられると、「三輪山の杉の立っている門を訪ねよ」と言って姿を消し中入となります。
里人(アイ)が三輪山に参詣すると御神杉に玄賓の衣が掛かっているのを見つけ僧に知らせます。玄賓は杉に掛かっている衣に金色の文字で記された御神詠を読み上げると、御神杉の陰から三輪明神(後シテ)の「神にも願いがある、人に逢うことは嬉しいこと」と声が聞こえ、シテは烏帽子と狩衣を纏い女姿で現れます。
明神は「神も人間同様に罪を背負っている」と嘆くと、僧は「神は人間を救う為に人間と同じ立場になっているだけですよ」と慰め諭します。すると明神は神代の昔物語として、神婚説話や天の岩戸の神隠れ伝説の神楽を再現して見せ、伊勢の神と三輪の神は本来一つであるが、仏が衆生の為にと仮に別々の姿で現れていると告げると、夜も明けはじめ僧の見ていた夢はそこで醒めます。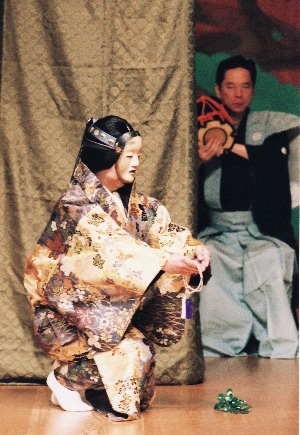
『三輪』は三輪明神が男神であるにも関わらず女神として現れます。クセでは古来より三輪山に鎮座する別の祭神、蛇神の神婚説話を取り入れ里の女になりすまし、また天の岩戸の伝説のくだりでは天照大神にも代わります。
単に三輪神社の祭神は大国主命(おおくにぬしのみこと)、別名、大己貴神(おおなむちのかみ)という設定だけではない、様々なものが混じりあっています。
この複雑な神の役をどのように演じればいいのか。そんな素朴な疑問を抱いてしまいました。女姿ですから艶やかに、天照大神ならば堂々として、などといろいろ考えますが結局、一能役者の習得した謡と型の美に落ち着くのではないでしょうか。
天照大神また蛇神云々と言っても、型として清麗なもの、神楽を厳かに華麗に舞うことを第一とするしかないようです。
また先人たちもそのように取り組んでこられたのでは、と思いました。
能『三輪』は四番目ものですが、脇能的な要素も多い曲です。宗教的なメッセージを多分に持ちながらも、芸能を観て楽しんでいただくという娯楽的要素が強い能と言えます。
ですから演者は脇能を勤めるときと同様に宗教的な意識は持たず、淡々と落ち度なく、神舞や神楽を舞えればよいのだと、と勤めました。
(神遊について)
次に、今回取り組んだ重い習「神遊」という小書について触れてみます。
この小書は我が家の健忘斎の言葉を書きとどめた寿山の伝書には記載がありません。
つまり九代目古能健忘斎が文政十二年頃に逝去し、十代目寿山盈親は天保二年に没していますので、たぶんそれ以後の演出であると推察されます。我が家の小書伝書には記載されていますので、たぶん十一代古能の子、七大夫長景(嘉永四年没)から十二代能静(明治二年没)までの間に出来たものではないかと推察されますが、確かではありません。
『三輪』には各流独自の重い習の小書があります。観世流では宗家の「誓納」、片山家ご自慢の「白式神神楽」、金剛流では「神道」が演能され、金春流は近年金春信高氏が「三光」を作られています。喜多流の小書は「神遊」と呼ばれ、宝生流のみ小書を持ちませんが、作品の主旨を外したくない意図が強く残った結果かもしれません。
では、喜多流の「神遊」はどのようにして命名されたのでしょうか。
そもそも神遊とは、天照大神の岩戸隠れによりこの世が暗闇となり、それを嘆いた神々が相談し岩戸の前で舞い歌い魂を呼び入れたことをいいます。その鎮魂の奏法全体を表現しようとするのが喜多流の「神遊」です。ですから神々の戯れや歓喜する様すべてを表したいため、巫女的要素を入れず、また天鈿女命(あまのうずめのみこと)の舞であると考えられる御幣や榊などを敢えて持たずに、扇(中啓)で舞い通します。
『三輪』は小書が付くと吉田神道の影響からか、囃子事に関する秘事口伝が加わります。流儀の「神遊」でも、前場はワキ方に音取(笛の独奏)や置鼓(小鼓の独奏)が囃され、シテ方は習次第(ならいのしだい)に三編返(さんべんがえし=次第、地取、次第と繰り返す)と脇能的で儀式的な演出に替わります。
これは得てして楽屋内の約束事に縛られすぎて作品の本位から外れることになりがちです。囃子方の腕自慢とも思われますが、一説には習次第を打つための手馴れとも言われています。今回芸術的な趣向とかけ離れるのを避け、ワキの宝生欣哉氏と御相談して脇方の習の音取や置鼓はやめて、自らも三編返を行なわずに勤めました。
習次第と呼ばれる特殊な次第は、喜多流では老女物の『卒都婆小町』『檜垣』と『道成寺』そして『三輪』「神遊」にのみ囃されます。老女物二曲は老いの位を特に際立たせる演出といえますが、『道成寺』と『三輪』も勿論、位を上げることに変わりはありませんが、両曲に共通する「蛇体」の執心の強調とも神聖視とも捉えられると言われています。観客にはシテの重々しい登場が、あの正体はなんだろうと興味をそそるような雰囲気を持たせます。
昔、観世銕之亟先生(八世静雪)が、「『三輪』の次第は、三輪山への距離感ね。いまのように簡単に楽には行けないんだよ。だって三輪の山本道も無しって謡うだろ? サラサラ出てきたんじゃダメだよ」と仰ってました。いつか自分が演じるときには、と心がけてきた言葉です。幕の内から橋掛り、そして常座まで運ぶこの歩みに思いをこめ、勿論、謡い出しまでの寸法調整や位の確保を熟知していなければ囃子方とうまく咬み合わなくなりますが、そこに単に囃子にあわせるだけではない、役者の思いが感じ取れるようでなければいけないのです。これが至難の業です。
蛇足ですが、『三輪』神遊は『道成寺』を勤めた者に許されると書きましたが、この二曲を同日の番組にするのはあまり良くないといわれています。それは『三輪』での神婚伝説で蛇が出現し、『道成寺』でまた蛇体が登場するので、重なることを嫌う能楽界の慣習から「悪し」と記されています。
実際の舞台では両曲共に習次第になるのを囃子方が嫌うことから来ていると言われています。
装束は通常の長絹が狩衣に変わり、鬘は喝食鬘で結います。この格好では鬘帯を使用しないため、王朝趣味が取り除かれ太古のイメージが膨らみます。三輪明神は男神ですが、女姿に男の烏帽子と狩衣を着るという不思議な取り合わせが魅力的です。
喜多流では小書が付くと位が上がるので装束も同様に袷(あわせ)狩衣になるのが本来です。先人たちは『三輪』神遊、『絵馬』女体、『融』遊曲、曲水之舞などで袷を着ておられ、父もまたそうしていました。しかし伯父新太郎が晩年体力面を配慮して、白地の単衣狩衣で勤めた舞台がありましたが、その姿が美しく印象深く残っています。袷ではがっちりした固い感じになり、単衣独特の織りは華麗で柔らかな優しいラインになります。
いつか自分が演るときは是非単衣でと思っていましたが、幸い近年、袷では位や強さが強調され過ぎて小面に似合わないと敬遠されて単衣の着用が普通になってきたので、今回はその例に従い単衣を着ました。
面については、前場の曲見は常と変わらず、後場は父が生涯愛用した「堰」の小面を使いました。
喜多流は後場では小面が決まりですが、天照大神というスケールの大きな神を、かわいい、愛らしい表情の小面では成立しにくいので、他のものをとも思いましたが、初演であり父の一周忌でもあるので、父が大事にしていた「堰」をつけて手向けようと思いました。
「堰」は父のもの、これからもそっとしておいてあげよう、との思いもありましたが、能夫の「使ってみて今度は明生君の魂を吹き込んでみたら・・・」という言葉に押され使うことにしました。
今回、折角の面が少し照りぎみ(上向き)だったことは悔いが残る反省点でした。作り物の中での作業は懇ろに打ち合わせたつもりでしたが、面のつけ方やウケに関してももう少し配慮したい、烏帽子の紐も少々長すぎたなど反省すべきところは二度と同じことのないようにと、心がけていきたいと思っています。
後場の作り物の中から謡う「ちはやふる・・・」の謡がむずかしいところです。
引廻しがはられた作り物の中で謡うため、声が籠もりがちで聞こえづらくなるので大きな声が必要です。
では大きければいいのかというと、そうではなく、高音で透き通るように張りながらも芯がしっかりしているように謡うのが心得ですがだれもが苦心するところです。
ワキは呼び止められると振り返り、シテとの掛け合いとなります。
地謡の「女姿と三輪の神」で引廻しが下ろされると床几にかけたシテが現れます。仕舞所となるクセの前半はじっくり動かずに床几に掛けたままで、進行を地謡に任せ上羽前の「さすが別れの悲しさに」からシテは作り物から出て舞い始めます。作り物に左袖を掛けたり、留めに足拍子を踏み、「語るにつけて恥ずかしや」と面を隠す型など、「神遊」特有の型となります。そしていよいよロンギから神楽となります。
「神遊」の面白さは神楽の構成にあります。
序は六つと通常より増え、足拍子も常と替わり複雑になります。何故このようになるのか根拠は明らかではありません。
通常の神楽は神楽の部分と神舞(時には中の舞や序の舞)が一体となって構成されていますが、「神遊」は神楽と後半の舞とを分けています。後の神舞を破之舞に替え、短い二段構成とします。神楽が終わると「天の岩戸を引き立てて」のシテ謡になり「人の面、白々と見ゆる」で破之舞となります。
破之舞ははじめを舞台で舞い、途中から橋掛りに行き、二の松で左袖を頭上に担いで岩戸隠れを表す『翁』と同様の型をして、すぐに橋掛りから舞台に戻りはじめます。はじめはゆっくり、徐々に勢いを増して日がさす有様を見せ、本舞台に入ると袖をはねて『翁』の左袖を巻く型となり、神々の歓喜を表して「妙なるはじめの物語」と一段落します。
神楽の譜は笛方の流儀により異なります。一噌流が常の神楽の譜と変わらないのに対して、森田流は「神遊」特有の譜があり、したがって森田流でなくては「神遊」の面白さは半減します。
森田流は序のあとに、ラア、ラア、ラア、ラア、ラア、ラアと長い反復の吹き返しから始まり、二段目に十のユリや七つユリなどの、見ている者も陶酔するような特殊な譜となり雰囲気を盛り上げます。
楽屋内の話ですが、一時森田流寺井政数家では、大小鼓・太鼓と手組が揃わず具合が悪く、いつか改善出来ないものかと思っていました。我が家の伝書は、現在森田流のまとめ役をなさっている杉市和氏の譜と同様なので、この度中谷明氏のご了解を得て、槻宅聡氏には杉家の譜で吹いていただきました。
これで長年のかけ違いが改善されました。
今回、小書「神遊」を調べ、独特な譜や重い習を学び、クセの神婚説話のくだりも改めて読み直し、幼くてはわからない艶やかな内側の部分も知りました。若い時分は門前の小僧習わぬ経を読むように、ただ闇雲に意味もわからず丸暗記するだけでしたが、そこで止まっていた自分に気付き、「神遊」に憧れ始めた時からのことも思い出しました。
演能レポートを書いて十年以上が経ちましたが、演能にあたり資料を調べ、稽古を重ねていくと、次第にその曲の持つ魅力を知り、その作品に引きつけられます。
『野宮』や『井筒』などはもとより、はじめは気乗りのしなかった『千寿』や『盛久』でさえ勤めるとその魅力に惹かれていきます。
これは正直能楽師でしか味わえない喜びです。
『三輪』は魅力ある曲で、且つ憧れる曲ですが、稽古を積めば積むほど、その深さや味わいを知れば知るほど、不思議と演じにくさを覚えました。
禅竹の『野宮』や世阿弥の『井筒』、元雅の『隅田川』、『歌占』など人間の苦悩に焦点を当てたものは、繰り返しの稽古でその演じ方の深みや幅広さを感じ面白さを知りますが、『三輪』はそのようには感じられませんでした。
どうしてなのか?
勝手な私見ですが、「神遊」は破之舞で『翁』の型があるように、『翁』と共通する祭事の儀礼的要素がふんだんに込められ、それが人間の感情的なものを拒んでいるように思えます。女神のような気高さと色模様を含む神話の豊かさ、流麗な型と躍動感あるリズムに酔うこの曲の良さは充分判りながらも、いま一つ踏み越えられないものがあるとしたら、それは人間を扱うものとそうでないものの違いではないでしょうか、それがいまの私の感想です。
『翁』や『高砂』、『絵馬』も同様、祭事としては手応えがある位高い曲です。しかし、私の心に活力や遣り甲斐を持たせてくれるお能は、人間の苦悩や喜びをテーマにしたものなのです。
ですからこれを書きながら心はもう次回の『邯鄲』傘之出に移り初めています。もしかして、もっと年を経て人間の苦悩や喜びを突き抜けて憂き世を達観するほどになればまた違った感想になるのかもしれませんが、今の私がその年々の能を見つめるとき、そんな思いにとらわれているのも事実です。そう思わせてくれたのは『三輪』の神力かもしれません。
(平成19年10月 記)
写真
『三輪』 シテ 粟谷明生 粟谷能の会 撮影 石田 裕
シテ 粟谷菊生(モノクロ)撮影 清水 一
『盛久』と観世音信仰投稿日:2007-07-22

『盛久』と観世音信仰
ワキと共に創り上げる舞台
粟谷 明生

喜多流自主公演(平成19年7月22日)にて『盛久』を勤めました。
『盛久』は若過ぎても、また逆にあまり老体でも不似合いです。流儀ではやや重く扱っているためか若手能楽師が青年能などで勤めることはまずありません。演者の適齢期は40代後半から50代のようで、今回私はその時期に演能出来、良い機会となったと思っています。
『盛久』はシテ謡が多く謡っても謡っても終わらず、謡・言葉の多さが演者にとってプレッシャーの一つとなっています。喜多流では、若い時に能『盛久』の稽古を受けることが少なく、先輩方が演じられるのをつぶさに見て勉強するという環境もないので、楽屋内では遠い曲、やりにくい曲としてやや敬遠されているのが実状です。
まず簡単に、あらすじを記しておきます。
平家の侍、主馬判官盛久は捕らわれ鎌倉に護送されます。前場は京都から鎌倉までの道行を名文で綴り、鎌倉で幽閉された盛久は流転の身を嘆き、死を願います。処刑される前に観音経を読み上げ、仮寝した盛久は夢を見て観音の告げを受けます。
いよいよ処刑の時が来ると刑場の由比ヶ浜へと移ります。太刀取が太刀を振り上げると経巻から発する光に目がくらみ太刀を落としてしまい、太刀は二つに折れます。
後場は、このことを聞いた頼朝が盛久を呼び自分の見た夢と盛久の夢が同じであることを確かめます。
夢の一致に奇特を思った頼朝は盛久を助命し盃を与え、舞の達人と呼ばれた盛久の舞を所望します。
盛久は頼朝を寿ぎ、我が身の喜びも添えて舞を舞いますが、舞い終えると急ぎ御前を退出して帰京します。
この場面展開が多い曲を他の演劇のように幕間(まくあい)を作らず、主にシテ(平盛久)とワキ(土屋某)の二人の謡や動きと地謡で話を進めます。
また、後場の頼朝邸では頼朝の存在なしで、これもシテとワキが創り上げていきます。
作者は『歌占』『隅田川』『弱法師』などの名作を手がけた観世十郎元雅です。世阿弥が「子ながらも類なき達人」と讃えたほどの人物です。
主人公の心の動きを、この場面展開や歌舞によって巧みに描きながらも、背後に大きなテーマを感じさせる曲作りは元雅らしいと思います。
この能はワキ役が大事で、シテとワキの息のあった舞台運びが必須です。元雅により巧みに作られたこの曲はワキに恵まれなければ成立しません。
今回、その重要な役を旧友の森常好氏にお願いし、『盛久』を演じる上で大きな助け・力となりました。
ワキ役は年齢に関係なく舞台では超越しているものです。
しかし例外もあり、私は『満仲』のワキやこの『盛久』のワキなどは、シテの年齢を考慮して配役すべき曲だと思います。シテ側の気持ちとして、あまりに年上の先輩では遠慮が生まれ、若年ではシテ同様土屋某には成りきれないでしょう。
森氏とは演能前より意見交換をして、立つ位置や謡の詞章などの確認や打ち合わせをしました。
通常、喜多流自主公演の申合はシテ方だけで行います。
しかし位が重い曲や稀曲などの特別な曲は三役の方々にお集まりいただきます。
昔ならば『盛久』ぐらいでは三役をお呼びすることはなかったと思いますが、近年は事前の打ち合わせ、申合の重要性を尊重してか、シテの希望で三役を呼べるようになりました。
『盛久』は細かな打ち合わせなくして曲の充実は計れないと思います。
成果が出たかどうかは別として、事前の打ち合わせにより、双方が気持ちよく出来たことは事実です。

それでは舞台経過を追って今回のレポートをします。
シテの出(登場)は我が家の伝書には「輿に乗り出る」と記載されていますが、輿に乗る場面が多いと、舞台景色上少々うるさく感じるのではと懸念して取りやめました。
幕が上がり橋掛りをシテ、ワキ、ワキツレ太刀取、ワキツレ輿舁の順に出て、シテは笛座前で床几に腰掛けます。ワキは一旦後見座でクツロギますが、シテが床几にかけるのを見計らって常座で名乗ります。
観世流や金春流の『盛久』は京都清水寺で捕まる設定のため、ワキの名乗りはなくシテは橋掛りを歩みながら「いかに土屋殿に??」と呼びながら始まります。
この奇抜な始まり方は元雅らしいところです。
喜多流は丹後の国、成相寺(なりあいじ)で捕えられ京都に護送されたと改変しているので、残念ながらこの面白い演出は出来ません。
成相寺は天橋立の近辺の山頂にあり、私も一度行きましたが、急坂を登りとても辺鄙なところです。
よくこんなところまで逃げたものだ、よくここで捕えることが出来たと感心しました。
ワキの名乗りに「よき案内者をもって易々と生け捕り、云々」とあります。
今でいう内部告発でしょうか、簡単に捕まえたと語るあたりが頼朝側の名乗りらしいところです。
喜多流の演出は成相寺から一旦京都に護送される設定ですので、道中囚人の心持ち、捕らわれた体で勤めます。
ワキの名乗りを聞き、シテは床几にかけたまま「いかに土屋殿」と呼び掛け、清水寺の方角に輿を向けてほしいと頼みます。
シテは正面先に下居して「南無大慈悲の観世音」と謡い、いよいよ鎌倉までの道行となります。
この街道下りはシテと地謡のかけ合いで進みますが、謡愛好家には謡い甲斐のある名文が続くところです。
シテの「いつかまた清水寺の花盛り」に地謡が「帰る春なき名残かな」と受け、もう桜も見られないと死を暗示し、刑地に赴く寂しさの心で謡います。
この道行、本来喜多流はシテやワキなど全員が動かずじっとして長い街道を下っていく様子を表現しますが、この演出が今の時代にご覧になる方々がお判りになるか、少し不安に思い、今回は「熱田の浦の夕汐」の段で一度、一の松まで移動して、大井川や富士山、三保の浦を橋掛りで眺め、舞台に戻ると鎌倉に着くという動きを入れてみました。
これは他流にある演出ですが、喜多流としては今回はじめての試みです。
これが可か不可か、楽屋内にも観客の方にも賛否両論あると思います。
しかし、試すことが可能な演者がその危険を恐れずに一度ぐらい挑んでみてもいいのではないかと、いつもの好奇心から試してみました。
みなさまのご意見をお聞きしたいと思っています。
鎌倉に着いた盛久は、この曲のもっとも難しい謡いどころ「夢中に道あって・・・」の独白となります。過去を顧み、生きて人前に面をさらす自分を嘆き、それならば来世での往生を願い、死を覚悟します。
ここの謡は大きな声だけでは成り立たず、しかし蚊の泣くような声ではこの深い思いは観客に伝わりません。
深く込められた気持ちを見所の隅々まではっきりと独り言として伝える、演者の技量の見せ所です。
このあたりが若者には適わないところで位が高いのかもしれません。
土屋を呼び出し死期を知ると、観音経の読誦を祈願して読み上げます。観音経、これがこの曲のキーワードでもあります。
今回経文の謡い方に工夫を凝らしてみました。
経文は四字または五字で区切り謡うという約束事があります。
今回の観音経は五字で区切ります。
若い時に経文の区切り方を知らずに「生老病死苦 以漸悉令滅」を死と苦の間で息継ぎして「苦以漸」と謡い、「五字で区切るんだ」と叱られたことを思い出します。
盛久が土屋に経文を聞かせるところは、「或遭王難苦」(ある王の怒りにふれて苦難にあい)、「臨刑欲寿終」(刑に臨んで寿命が終わろうとしている)、「念彼観音力」(観音の力を信じて念ずれば)、「刀尋段々壊」(刀もいくつかに折れ、ばらばらに壊れるだろう)と、5字で区切って謡います。これはその後、現実の刑場でその通りのことが起こる重要な偈文ですが、ここの謡をよりお経らしく謡えないものかと考えました。
謡は平坦にだらだら謡っていると「お経じゃあるまいし! 謡を謡え!」と父の注意が飛んだことを思い出しますが、ここは逆に、謡らしくなく、お経らしく謡ってみよう・・・と。
以前、野村四郎氏が、「寿夫先生が『通盛』の弘誓深如海歴却(ぐぜいじんにょかいりゃっこう)をお経のように謡われた」と仰っていました。これがヒントになりました。悪い謡の代表を雨垂れ謡と言ったり、お経謡と戒められますが、今回はまさにそのように謡ってみたわけです。
由比ケ浜の刑場での刑の執行場面、ワキツレ太刀取が盛久を切ろうとすると、観音経で唱えられているように刀がばらばらに折れてしまいます。
この太刀の落としどころは流儀により様々で、喜多流はシテの左前方ですが、ここにうまく落としてもらわないとシテは困ります。
今回は太刀取役の舘田善博氏がとてもいいところに落として演りやすく助かりました。
いよいよ後場、盛久が頼朝の御前に出る場面になります。
シテは後見座で袈裟を外し直垂をまといます。
囚人ですが、頼朝に謁見するというので、鎌倉方が用意してくれた晴れ着に着替えます。
以前、父が『盛久』を勤めた時の写真を見ると、シテもワキも同じ黒い直垂を着ていました。
両者の装束が同じである方が自然なのかもしれませんが、私はシテとワキの区別をしたく変えたいと思いました。
森氏は「当然、ワキは黒を使うよ。処刑人は黒でしょう」との意見、それではシテ側を替えるしかないと思いましたが、生憎粟谷家にあるのは黒色のみです。
困っていると、森氏から「白地の直垂があるから貸してあげるよ」といわれたので、さっそく見せてもらい、柄も問題なし、寸法もピッタリ、少し派手かとも思いましたが、盛久の平家らしさが出るのではないかと思い拝借させていただきました。
これも旧友との緻密な話し合いがもたらしたご褒美だと思っています。
さて元雅は『盛久』で何をいいたかったのか。
平家の侍、盛久という人物の死を目前にした諦観でしょうか。もちろんそれもあるでしょうが、私は観世音信仰と舞台には顔を出さない頼朝の存在を意識しているように思えます。
宗教と政治、宗派と幕府の二点が気になります。
元雅の生きた時代は、末法思想にあって、人々は観世音信仰に没頭して、現世や来世への救いを求めた時代でした。
『盛久』には全篇を通して観世音信仰が満ちています。
京都に着いて、千手観音をご本尊とする清水寺に輿を向けてと頼んで自ら拝む場面、鎌倉に着いてからは「あっぱれ疾く斬られ候はばや」と一人ごとを言い、念仏すれば来世で救われると日夜観音経を読誦する場面、少し居眠りして観世音の尊い霊夢をこうむり、頼朝が同じ夢を見たことから命を助けられるという物語展開、全てに観世音信仰が語られます。
そして頼朝もまた観世音の信仰のもと、罪人を許す、慈悲ある人として描かれています。宗教と体制側への贔屓があったのでしょう。
盛久という人物は、平家物語では長門本にのみ登場し、主馬判官盛国の末子として描かれていますが、実在した人物かどうかは疑わしいところです。
主馬判官という役職も、馬署の役人というほどのもので、それほど重要な地位とも思われません。
盛久の人物像がこのようにはっきりしないことから、演者は、盛久という人物を演じにくい一面もあります。
しかし、元雅の関心は盛久その人にあるというより、観世音信仰があれば二世(現世と来世)で救われるという信仰のありがたさであったのではないでしょうか。観音信仰の宣伝歌、それを描くために、実在したかどうか分からない盛久という人物を借りて、劇的な物語を作り上げた気がしてなりません。
観世音信仰という難しい信仰の言葉を散りばめながら、それでいて、盛久という刑死を目前にした切羽詰った人物の心の襞を描き、観客をあきさせず、一つのドラマチィックな物語にして見せつける、シテも物語や謡に運ばれて演者自身の姿で勤め演じ切る、そのような戯曲を元雅は求めていたのかもしれない、と思います。
『隅田川』や『弱法師』、『歌占』を勤めたときと同じように、今回もまた元雅の、父よりも祖父・観阿弥に似た作風、現在能という形で人の心と信仰心を感じさせる戯曲作りの才能と成功をしみじみと感じました。
(平成19年8月 記)
写真 『盛久』シテ 粟谷明生 撮影 あびこ喜久三
『満仲』の地謡を勤めて投稿日:2007-06-24

『満仲』の地謡を勤めて
粟谷明生
平成19年6月24日の喜多流自主公演の初番は『満仲』でした。
配役は、シテ・友枝昭世、ツレ・中村邦生、美女丸・狩野祐一、幸寿・友枝雄太郎、ワキ・宝生閑、笛・一噌仙幸、小鼓・大倉源次郎、大鼓・亀井忠雄、地頭は粟谷能夫で私は副地頭を勤めました。
『満仲』 シテ・粟谷菊生 美女丸・佐々木多門 幸寿 谷大輔
撮影・あびこ喜久三
自主公演で『満仲』が選曲されたのは一昨年のこと。何度か選曲委員が友枝昭世氏に『満仲』は?と打診をしましたが、友枝氏はなかなか承知されず、粟谷菊生が生きている内に、菊生の地謡で、という口説き文句に遂に了承された経緯があります。
当初の構想はシテ友枝昭世、ツレ粟谷能夫、地謡粟谷菊生、出雲康雅、粟谷明生の予定でした。これは内輪話ですが、実は最初ツレは明生でという、シテのご注文でありました。しかしこの多田満仲役は二人の子ども役の年齢を考慮すると、満仲と仲光の年齢差があり過ぎるのは・・・、と申し上げて、僭越ではありましたが敢えて辞退させていただきました。
しかし真意は、父が自分の十八番を、人情味あふれる現在物として、どのように謡うのかを、共に現場で謡いながら教わりたいとの一心でした。
そのような辞退の理由も説明させていただき、友枝昭世氏も納得して下さって、当初の構成となりました。しかし、不幸にも父逝去によりこの計画は実行出来ず、今年に入り再度番組編成をやり直すこととなりました。
『満仲』は旬のもの、年齢が近い二人の子方に恵まれなければこの能は実現できません。二人の子方があってこそできる能で、見守る大人としてはこの子たちが当日まで元気で風邪などひいたりしないかと、心配でたまらないのです。万が一のときに代役はいないので、子方のご両親、とくにお母さま方は相当神経を使われたことだと思います。このたび無事よく勤めてくれた子どもたちにも、お母さまにも「どうもお疲れ様、有難う。」と私は感謝とねぎらいの気持ちで一杯です。
私の『満仲』はシテ喜多実、ツレ粟谷菊生(昭和43年4月28日 喜多別会 喜多能楽堂)のときの幸寿役の1回だけですが、これが長い子方時代の最後の舞台となりました。
実先生じきじきのお稽古で「切られたら、すぐに横になって。でも頭は舞台につけてはいけないよ!」 このご注意は未だに頭に残っています。死んだら首は落ちるから舞台につけたほうがいいのにと、子ども心に、12歳なりに感じたことを覚えています。たぶん実先生は頭を舞台につけると演技が生っぽくなるのを嫌われたのではないかと思います。
頭を舞台につけないようにと身体を硬直させて、そして動かないように我慢する子方の身体から発散される緊張感が、舞台に横になり寝るという特殊な動作をも、能の型として表現するのがねらいであった、と私は思っています。

『満仲』 シテ・喜多実 美女丸・下村 幸寿・粟谷明生
撮影 あびこ喜久三
あの頃、私は声変わりで高い声が出ず苦しんでいました。美女丸役の下村君はきれいで透き通るような美声で、子ども心にもなんとも羨ましく、ねたましく思ったものです。
友枝昭世氏が「菊生先生がいらっしゃる間に一度は」と決められたのには、父の『満仲』演能回数3回ということが大きなウエイトをしめているかもしれません。『満仲』を3回も勤めている能楽師は珍しいでしょう。「うちの父は3人も幼い命を奪っていますから」と私は楽屋で冗談話をしていたのですが・・・。
父の『満仲』演能記録をここにご紹介させていただきます。
第一回 披き
昭和47年6月24日 喜多例会 梅若学院にて
シテ 粟谷菊生 ツレ 内田信義
美女丸 高林呻二 幸寿 粟谷知生 ワキ 村瀬登茂三
笛 中谷 明 小鼓 鵜澤 寿 大鼓 渡辺榮嗣
地頭 福岡周斉
第二回
昭和54年3月4日 粟谷兄弟能 喜多能楽堂
シテ 粟谷菊生 ツレ 粟谷幸雄
美女丸 井上雄人 幸寿 井上真也 ワキ 宝生弥一
笛 寺井政数 小鼓 幸義太郎 大鼓 柿原崇志
地頭 不明
第三回
昭和60年12月20日 国立公演 国立能楽堂
シテ 粟谷菊生 ツレ 友枝昭世
美女丸 佐々木多門 幸寿 谷 大輔 ワキ 宝生 閑
笛 寺井啓之 小鼓 幸義太郎 大鼓 安福建雄
地謡
(前列左から)
粟谷明生、粟谷能夫、谷大作、中村邦生
塩津哲生、地頭・粟谷新太郎、香川靖嗣、佐々木宗生
時代の移り変わりがこの記録で読み取れます。
能『満仲』の舞台進行は、幸寿斬首までの前半と、それ以後の後半とに分けられます。学問に身が入らない子・美女丸に腹を立て、手討にしようとする主君・満仲を制し、ならば誅せよと命じられる仲光。主君の命とはいえ、主君の御子を殺すわけにはいかない。悩む仲光に、実の子・幸寿が、父が主君に仕えるなら、自分は美女丸に仕えている、忠義なら我を身代わりに誅せよと、けなげな言葉をかけます。逡巡しながらも、仲光は幸寿を切り、自らは暇を申し出ます。そこへワキ恵心僧都が現れ、満仲にこの顛末や仲光の苦しみを語り、美女丸への許しを請います。

シテとしては、幸寿を切る場面はもちろん難しい見せ場ではありますが、後半の満仲と美女丸の再会、祝宴での舞などがもっとも難しいところだと思います。
感情過多では能でなくなり、感情稀薄では感動の薄いつまらない能となってしまいます。

『満仲』 シテ・喜多実 ツレ・粟谷菊生 撮影・あびこ喜久三
我が子を殺してまでも守ろうとする忠義心、この感覚は、現代の我々にはなかなか素直に受け入れにくい話と思われます。私もつい封建的な忠義物語となると、まずは忠臣蔵を思い出し江戸時代の武士の慣習を頭に思い浮かべてしまいますが、多田満仲は平安時代の人ですから、その歴史の古さ長さを思い、この手の悲しい痛ましい話は昔からある出来事なのだ、人の世とは・・・と考えさせられてしまいます。
こんなお涙頂戴ものは能の本質とかけ離れている、忠義だての物語など古臭くて現代にはしっくりこない、このようなご意見もわからないではありません。しかし能『満仲』は人間の根本的な悲しみや苦痛、忠義心、責任のとりかたなど、現在の我々の社会にも充分通じるように人情話として脚色され、観客の心にあますところなく訴える力を備えていると確信し、私の好きな曲の一つになっています。
『満仲』という現在物の能は、現代社会と密接につながり確かに存在しています。命の尊さと一門、一家を守り抜く努力と苦悩、この曲が伝えるメッセージが普遍のものだからでしょう。『満仲』はそのような香りをふんだんに放つ曲だと思います。
私もそのうち機会に恵まれれば是非演りたい曲ですが、『満仲』という曲は、『野宮』と同じに、だれでも近寄れる曲ではなく、曲が演者を選ぶところがあるように思います。似合わぬ者が挑むと、途端にばっさり切られるような力も備えているのでは、と思っています。さて自分はどうだろうか? 試してみたいのですが・・・。
今回の友枝昭世氏の『満仲』は父が生きていたら、謡い終えて切戸口をくぐり、囃子方に挨拶しながら、シテに向かって「昭世ちゃん!」と言って、いつもの右手でオーケーサインをだして・・・と思いました。屹度父はどこかで見ていたと思います。
父の『満仲』は父のもの、友枝昭世氏の『満仲』もまた友枝氏の新工夫がなされていました。伝書の行間から読み取る芝居心、現代に生きる能楽師として決しておろそかにしてはいけない大事な術です。例えば、子方への対応、太刀の持ち方や、男舞での工夫、掛の段を伸ばしすぐに舞わないなどの、適切な処置が随所に冴えていました。とくに直面というむずかしさ。悲しみの表情を見せずに、無表情でありながら、しっかりと心に響く役者の底力、見習わなくてはいけないと肝に銘じました。
私は『満仲』を終え楽屋にもどったときに、ふと悲しくなりました。
仲光は「我が子の幸寿があるならば、美女御前と相舞させ」と謡いますが、
私は「我が父がここにいるならば、菊生と共に地謡を謡い」とかぶって仕方がありませんでした。
そして昭和60年、私が30歳の時、地謡にいながら涙が出て仕方がなかったこと、いまも目を閉じれば鮮明に蘇ります。それはシテが我が子幸寿を切る場面ではなく、最後の橋掛りで美女丸を見送るところです。「仲光、遙かの脇輿に参り、この度の御不審なほざりならず、構えて学問おわしませと、お暇申して留まりければ」と謡いながら感動しました。自分の子が犠牲になっているのだから、ちゃんと学問してくださいよ、仲光の切ない胸の内がズーンと響いてきます。
今から5,6年前、父に「おやじさんの十八番の『満仲』をそのうち演りたいが?」というと「子方が揃えばすぐにでもやれよ、おれが教えてあげるよ、いまはコツだけまず教えておくよ!」と、次のように教えてくれました。
この話はこの秋、父の一周忌に合わせて出版予定の「父・粟谷菊生から聞いた話」(仮題)に記載され重複しますが、ここでもご紹介させていただきます。
菊生:いいか、「或いはお主」で美女を見て、「子はお惜し」と幸寿を見る、「弓手にあるは我が子ぞと」と太刀を幸寿に当てるようにして持つ、そしてすっと右回りで後を向いて、ちょっと止まる、逡巡するんだな、そして鯉口を切って、そしてちょっと躊躇したように見せて、あとは一気に太刀を抜いて真っ直ぐに幸寿に近づき切り、拍子、太刀を遠くへ捨て近寄る美女を左袖で留めて見せないよう、そして美女をゆっくり連れてくつろぐ。
いいかい、鯉口を切る、ここだよ。
それからこれも覚えておけ、橋掛りで美女丸に構えて学問と、扇遣いを二回する、その二回目は強くな!強くだよ、しっかり勉強しろよ!お坊ちゃま!と心では美女の頭をたたくつもりでな。」
このあと父の話はまだまだ続きました。
「静夫ちゃん(故観世銕之亟氏)が『仲光』(観世流では『満仲』をこう呼ぶ。)を演るからというので、僕のビデオを貸してあげたんだ。そうしたら、いいね菊ちゃん、と褒めてくれてね。そのうち四郎ちゃん(野村四郎氏)が『仲光』演るので静夫ちゃんに相談したんだ。そうしたら、これを見て、と僕のビデオを渡したんだ。無断でビデオの貸し借りはどうかと思うけれど、一級の能楽師同士の貸し借りは大いに結構じゃないか、これは僕の自慢だよ」。
この時の光景もまた、鮮明に思い出されて仕方がありません。
今回、『満仲』が父を思い出すもっとも大きな曲の一つであるということを認識させられました。そして、この悲しい曲を謡いながら、父がいつも言っていた言葉、「能はなんでも最後は祝言の心で」もまた思い出しています。
(平成19年6月 記)
平成19年11月 追加レポート
末子・美女丸の出家の真相
能『満仲』では美女丸(子方)が父・満仲(シテツレ)に出家するように言われますが、武芸に励んで、学問や仏道に心を入れません。父は怒り家臣の藤原仲光(シテ)に美女丸を手討にするように命じますが、家臣が主君の子を討つことなど出来ず、仲光は仕方なく我が子・幸寿丸を身代わりにしてしまいます。
何故、美女丸が出家を拒んだのか、どうして学問に励まなかったのかが私は気になりました。
先日、写真探訪で「満仲ゆかりの地」の謡蹟めぐりの際、多田神社に参拝に行くと、多田神社略記にいくつかの参考資料がありましたので、それを元に私の疑問を考えてみたいと思います。
先ず初めに満仲のことを知る必要があります。
多田の庄に住む多田満仲は人皇五十六代清和天皇の御曽孫で二十四歳の時に源姓を賜っています。満仲には5人の男子がいます。長男・満正は満仲三十八歳の時に生まれますが、何故か源家の系図には記されていません。想像ですが、たぶん早世したのではないでしょうか。
続いて四十一歳の時に、能『大江山』『羅生門』や『土蜘蛛』などに登場する摂津源氏の祖頼光が誕生します。系図では頼光が長男となっています。その後、大和源氏の祖、頼親、河内源氏の祖、頼信、そして頼平が生まれ、最後5人目に美女丸が生まれ、後に出家し源賢と名乗ります。
満仲は晩婚だったのか、それとも系図にはない満正以前に子どもがいたかは判かりませんが、ここにあげた5人の子どもは当時としてはかなり遅い誕生と思われます。
満仲は59歳の時、心機一転、出家を帝に奏請しますが許されません。そこで満仲はその思いを美女丸に託し、自分の替わりに出家させます。この時美女丸がいくつかは判明していませんが、ここから悲劇が始まります。
ではなぜ美女丸が選ばれたのか? その起因がいくつか考えられます。
1. 美女丸がまだ若かったため。
2.生来の武門の血を引きその性格も活発で荒かったので、一門の安泰を考えてのこと。
3.文武両道を旨とした満仲は、一門繁栄のため武門は4名の子に、文化面は美女丸に託し、文武両面を把握することで勢力拡大を考えてのこと。当時の中山寺(美女丸を最初に預けた寺)の繁栄を思うとそれも考えられる。
4.自分の出家が許されない状況を嘆き、まったくの父親の我が儘で子へ強制した。
など、いろいろと考えられます。
いずれにしても父親の考えを強制させられた子の悲劇、それが幸寿丸や仲光の悲劇と繋がります。そして『満仲』という能が描いた悲劇はシテ仲光だけでなく、生き残った美女丸にも及んだことを知りました。
満仲という武将が、たとえ武芸達者で信仰篤き者であろうと、その勇者の陰に、ある横暴がひっそりと隠されているのが能『満仲』なのです。
二人の子方に恵まれた時、いつか『満仲』を演りたいと私は願望しています。
『翁』付『弓八幡』を勤めて投稿日:2007-04-16

『翁』付『弓八幡』を勤めて
――― 翁と繋がる弓八幡のクセ ―――
粟谷明生

平成19年4月16日、厳島神社御神能で4年ぶりに『翁』付脇能『弓八幡』を勤めました。披キの『翁』は同じ御神能で平成7年(39歳)ですから、丁度12年前、そのときの脇能も『弓八幡』でした。
現在、御神能は初日と三日目を喜多流の出雲家と粟谷家が、二日目は観世流大江家が受け持って、この伝統を継承しています。近年、喜多流の翁大夫は執事の出雲康雅氏が隔年に、その間を粟谷能夫と私が交代で勤め、すでに14、5年が経っています。
初日の番組は『翁』付の五番立が基本で、脇能は『高砂』『弓八幡』『養老』の三曲のうちの一曲が、二番目物も勝修羅の三曲『田村』『八島』『箙』のうちの一曲がそれぞれ順番に組まれ、毎年演じられています。
『翁』は「能にして能にあらず」といわれ普通の能とは異なり別格です。発生は平安時代や鎌倉初期といわれ、中世室町時代初期に出来上がった能に比べ、演出や構成に特異性が見られます。室町時代後期に吉田神道の影響を受けましたが、その形はほぼ現在まで大きな変化はなく伝えられています。
私が厳島神社で『翁』を勤める喜びのひとつに、屋外しかも海の上という特殊な場所で舞えることがあります。晴雨に関わらず翁烏帽子に装束を纏い日光や風、大地の香り、そしてここでしか味わえない潮の織りなすいろいろな現象を肌で感じながら勤める『翁』は貴重なひとときです。屋内の能楽堂では得られない自然の中で舞える喜びを満喫し、無事奉納が終わると能楽師として、さあこれからまた一年がはじまる、とけじめも付き意欲も湧いてきます。
さて観客の皆様は『翁』をどのようにご覧になっているのでしょうか。
もちろん、どのようにご覧になろうと自由ですが、『翁』は演劇を観賞するというよりも、神への儀式を芸術的に表現している芸能の鑑賞、と思っていただければと思います。
翁大夫は「天下泰平、国土安穏」とご祈祷を謡い、演じるというよりも神事に奉仕する気持ちで勤めます。しかしこの言葉に甘えて芸能者の精神まで神棚に上げてしまってはいけないと思います。
生意気な私見ですが、『翁』を勤める能楽師は能にあらずといわれる『翁』であっても、その大夫役者でなくては味わえない魅力を発揮し、大夫の個性を感じさせなくてはいけないと思います。芸能者として磨き上げられた択一した動きや謡の技が始終見え隠れしていなくては、信仰思想と遊離している現在の『翁』を奏す意味がないのでは、と最近思うようになりました。
昔、厳粛な行事の始まりには必ず『翁』が出され、江戸時代に江戸幕府の式楽とされてからは『翁』は完全冷凍保存されたように形式が整い、伝えられてきました。しかし近年、冷凍庫から取り出した『翁』は少しずつ溶け始めているように思えます。
元の冷凍保存されたままの形でよいのか、見せ物的要素を繰り広げご覧いただくか、それは今、現代人がどのような『翁』を求め、演者がどのように提供していくかで、いかようにも変化していくでしょう。
能楽師にとって『翁』は位が高く大曲です。しかし『翁』を数回勤めて、何故これが大曲であるのか、と疑問を抱くようになりました。
軽視はしませんが、喜多流の『翁』では、大夫が勤める時間は出入りの儀式を含めても僅か30分程度で実質舞うのは15分ほどです。いろいろ秘事はありますが所詮短時間で済みます。
私は『翁』を勤めるための秘事云々を学習していくうちに、神事を芸能化した『翁』を済ませた後に脇能を勤める、後シテでは神体となって颯爽と舞う、そのために2時間半を超す演能時間、支度から最後の三役への挨拶が終わるまでの時間を入れれば、有に5時間を超すこの長丁場の『翁』付脇能を勤めてこそ『翁』という曲や翁大夫云々を語れるものであると思うようになりました。
近年『翁』のみの興業は多くなりました。しかしそれは『翁』が持っている本来のものとは似て非なりで、まさに見せ物化してきています。見せ物が悪いとはいいません。芸能をいろいろな方に観ていただく一つの方法として私は歓迎しますし協力もします。
いま私がいいたいことは現場にいる能楽師がショーはショーとして勤め、楽をしてもいいですが、もう一方で『翁』付脇能という辛い本来の形もあるということを忘れないこと、と思うのです。これは私が演じる立場であるからこそ言える感想なのです。身近で手頃で楽な『翁』と同時に長くきつい『翁』付脇能を勤めることで、自分自身に何か見えてくるものがある、今回の『翁』付『弓八幡』はそれを強く感じさせてくれました。
今回『翁』の演能レポートは、私が下掛の能役者として白式尉の部分のみ記します。
一部他流と異なることや黒式尉に伴う記載がないことなど、予めご承知おきいただきご高覧いただければと思います。
では当日の進行を追ってレポートしていきます。
『翁』の構成は大きく白式尉と黒式尉の二つに分けられます。
前半の白式尉の舞の前には露払いの千歳の舞があり、上掛はシテ方が勤めますが、下掛では狂言方が勤めます。千歳は颯爽と力強く舞い、大夫は千歳の舞の途中に舞台上で白式尉の面をつけ、ご祈祷とどっしりとした位のある翁の舞を天地人と三個所の拍子で神に祈り捧げます。
後半の黒式尉の舞は、揉みの段と鈴の段に分けられ、どちらも狂言方の三番三(和泉流は三番叟)が舞いますので、下掛の『翁』は大半を狂言方が担っていると言っても過言ではありません。
つまり喜多流の『翁』でシテ方が受け持ち舞っている時間が15分程度となるのはこのためで、三番三を勤める役者に比べその疲労度は格段の違いです。それでもシテ方が『翁』を大事にしているのは、秘事云々もさることながら、脇能も勤めなければいけない長(おさ)の立場、その責務からです。

070415_1646~0001
江戸時代公儀の伝えでは「三日前より別火を喰い、殊に潔斎すべし」と、『翁』を勤める前の心得が記されています。我が家の伝書にも「翁大夫を勤める者の演能心得、前日、昼午の刻に沐浴、別火して精進潔斎して舞台に臨む」と記載してあります。これらは今の時代、生活環境のこともあって、現実問題としてその通りに行うのは難しい状況です。私は『翁』を勤める精神性を軽んじるつもりはありませんが、時代に合ったやりかたで、大夫がそれなりに真摯に対応していけばいいと思います。
今回は前日に宮島に入り、個室に宿泊し、朝5時に起床して身を清め、朝食は『弓八幡』で初ツレを勤める弟子の佐藤陽君ととり、気持ちを引き締めて舞台に臨みました。形は大切です、しかし形だけでなくそこに込められる気持ちの充実はもっとも大切にすべきことではないでしょうか。
翁大夫の装束は伝書には厚板色無、俗名「浮糸」と書かれていますが、ここ厳島では紅無柳模様の厚板がお決まりで紫指貫、狩衣となり腰帯は緞子となります。他流には金襴模様の狩衣を使われることがあるようですが、当流は使わないようにと伝書に注意書きがあります。
『翁』には翁飾りと呼ばれる祭壇が置かれます。翁飾りは上段中央に白式尉と黒式尉の二面、そして鈴を入れた面箱を置き、左に大夫の翁烏帽子、右に中啓が置かれ一時的に飾られます。下段に厳島では煎り子(煮干し)と洗米、横に土器が置かれ、御神酒が置かれます。本来、翁飾りは鏡の間に置かれますが、厳島では場所が狭いため楽屋に設置されています。装束を着けた大夫は最後に翁烏帽子を付け中啓を取り、翁飾りの前に着座し礼をして最初に後見から御神酒をいただきます。次に千歳、三番三と、まず役の者がいただき、その後に侍烏帽子に素袍上下を着した囃子方、狂言後見、地謡が同様に順番に御神酒を頂きます。御神酒を頂いたお囃子方はすぐにお調べをはじめ、千歳は面箱を戴いていよいよ出となります。(注意・お調べや御神酒の頂きかたは場所により異なることがあります。)残念ながら、これらを観客がご覧になることは出来ません。また女人禁制ですので、女性は楽屋入りも許されません。

070415_1657~0001
揚げ幕の内側では橋掛りの中央に役者が並び待機しています。橋掛中央部に立つことは『翁』だけに許された特権です。千歳が面箱を高々とかかげ、大夫の「おまーく」の掛け声で翁渡りが始まります。
幕が上がり、千歳に続いて大夫はどっしりと一歩一歩位をもって運びはじめます。
この位取りはなんでもないように見えますが、演者としては、ここがなかなか難しいのです。父はここの位取りは、歳を重ねれば自然と出来る、若い大夫はあそこにどうしても風格が出ない、と教えてくれました。確かに自分の披きのビデオを見ると、なるほど軽いと痛感しますが、今回もまだまだ、どっしりとまではいかなかったと反省しています。
他流の『翁』には初日之式、二日目之式、三日目之式、四日目之式とありますが、喜多流に伝えられているのは四日目之式と云われています。流儀の主張は、御神事であり見せ物ではないので毎回同じで構わない、と喜多六平太芸談に記載されています。
大夫は舞台正中から正面先まで進み、座礼します。
伝書には「偉い方は南に向いて座るから、北を向いて礼をする、北斗へ向かう心」と意味ありげな事が記載されています。北斗へ向かう心、これをどのように解釈するか、そこが味噌です。私は貴人や神社関係者に対しての礼ではなく、空を見上げ神に「これからご祈祷と舞を捧げます」とご挨拶の気持ちを込めて深々と礼をしています。

070416_0722~0001
座礼が終わり、大夫が地謡座近くに座ると千歳は面箱を大夫の前に置き、面箱から翁の面を取り出します。これを手際よく出来るのも千歳の技量の一つです。千歳が脇座に移動するのを合図に、橋掛りに着座していた囃子方から一同順に舞台に入ります。地謡は『翁』に限り囃子方の後(後座)に着座します。これは『翁』が平安末期か鎌倉時代初期に作られた名残だといわれています。囃子方が着座すると笛はすぐアシライを吹きはじめ、その間に小鼓三人は素袍上下の上を脱ぎ道具を取って連調となります。今は番組に小鼓三名の名前があり、その真ん中が頭取と呼ばれ主導権を持ち、その左右に脇鼓(見所から見て、右が手先、左が胴脇)が並び囃します。なんでも古い時代は一番初めに道具を持った者が頭取になったとも言われていますが、今はそのような事はありません。
三丁の小鼓の打つ手組を聞いて、大夫の「どうどうたらりたらりら、たらりあがり、ららり、どう」と意味不明な謡となります。
我が家の伝書には詳細に意味が書かれていますが、これは音だけでも充分楽しめますし、また呪文と思えば、それはそれで意味不明でもかまわないと思います。『翁』は詞章より、ノリ、躍動感あるリズムが命と思い勤めています。
千歳の舞は露払いです。この役は『翁』の中で唯一若やいだ役です。千歳の「所千代までおわしませ」の謡で大夫は舞台上で堂々と観客の前で面を付けますが、『翁』ならではの演出です。
昔、足利義満公の前で、観阿弥が敢えて若い息子 藤若(世阿弥)にこの大夫役を勤めさせたのは、舞台の一番はじめに美少年の世阿弥の素顔を見せ印象づけ、そして舞台で面を付け変身する舞台効果を充分知り尽くしてのことだったのでしょう。
面を付けた大夫は三番三と大小前で向き合い、三番三は揉みの段に備えて後見座にくつろぎ、大夫は正面に向きご祈祷となります。
「ちわやふる」「千年の鶴も萬歳楽と謡うたり、また萬代の池の亀は甲に三極を備えたり、天下泰平国土安穏 今日のご祈祷なり、ありはらや、なじょの翁ども」
このご祈祷の謡は、朗々とはっきりと張って、なお奥深い広がりが感じられれば最高位の良い謡、と評されるでしょう。私も屋内ではそのようにと意識していますが、ここ厳島では意図的に少し変えています。
ここで『翁』を勤めるには全身全霊で神に届くが如く、大声で張って謡うものだと思います。当然役者の年齢によりその声は違います。30代の張る声量や声質は40、50、60代のものよりもいたらないところが多々あるでしょう。若さ故は百も承知です。60代や70代の年を経れば、自然と落ち着いてきて、それでいて張りのあるものが出来上がるのは当然です。役者には自然と年を重ねることで体得出来ることもあるでしょうが、ここ厳島での『翁』はそのような言葉に甘えずに、老若関係なくその場を受け持つ役者が精一杯大きな声で唱えることに意味があり、そのような謡い方が必須だと思います。それが屋外の『翁』を勤める時の心構えだと信じています。
能楽師は例えば、厳島というロケーションであれば、その場をどのように思い考え、謡い方を探り見い出すか、その作業を怠っては八百万の神々がお怒りになるのでは、と私は怖れています。

070416_0721~0001
ご祈祷が済むと翁の舞となります。
喜多流は中啓を持つ右手をかかげ目付柱まで行き、そこで少し屈んで天の拍子を踏みます。次に脇柱近くに移動して地の拍子を同じように踏みます。
踏み終わると位が少し早まり、翁独特の型、左袖を頭部に翳し中啓で面を徐々に隠して天の磐戸隠れを現します。袖を返したり巻いたりして、そして最後に舞の終わりは人の拍子を踏み、萬歳楽・萬歳楽と大夫と地謡の掛け合いの謡で最後に礼をして大夫の舞は終わります。大夫は元の座に戻り面を外し、面に礼をして面箱にしまい、また正面先まで出て座礼をして幕へと帰ります。
これを翁帰りといい、高安流ワキ方は装束を着て幕の内で脇能のワキ役者が大夫を出迎え、受けるのが決まりです。
さて大夫が幕に入ると、大鼓は床几に掛けて揉みの段となり、三番三の出番となりますが、それらを大夫は脇能(今回は『弓八幡』)の前シテの装束を着けながら聞くことになります。
我が家の伝書に「太子伝の翁、云々」と記載があり、これが喜多流の『翁』の基盤となっていますので、その一部をここにご紹介します。
又其ノ後人皇三十三代推古天皇ノ御時、諸国疫癘多ク様々ノ天災有リ。其ノ時聖徳太子摂政シ給フ故、神仏ニ御祈願有シ時、天ヨリ面降リ下ル。太子是レヲ御覧ジテ、是レ翁ノ神楽ノ面也。天是レヲ下シ給フハ、此ノ神楽ヲ奏シテ災ヲ退クベシトノ御託也トテ、翁ノ神楽再興有リ其ノ時、庭上ノ御池ヨリ亀浮カミ出ル。甲ニ文有リ。「トフトフタラリタラリラタラリアラリララリトウチリヤタラリタラリラタラリアラリララリトウ」太子此ノ文ヲ考ヘ、諸鳥ノ囀ヲ以テ調子ヲ調ヘ、神楽ヲ作リ給フ。今ノ翁ココニ始ル。太子伝ニ曰ク、撥調ヲ改テ手調ト為ス。此ノ時ヨリ今ノ世ノ笛始リ、臺拍子ヲ改テ小鼓ト為シ、太鼓ヲ改テ大鼓ニ成ル。「千年ノ鶴ハ萬歳楽ト謡フタリ」トハ諸鳥ノ囀ニ依テ調子ヲ調ヘタル儀也。「萬代ノ池ノ亀ハ甲ニ三曲ヲ備ヘタリ」トハ則チ此ノ文ニ依ル也。此ノ時ノ神楽ハ五人立チニテ翁ハ聖徳太子自ラ舞謡フ。而シテ此ノ神楽ヲ秦河勝ニ伝ヘタフ。
河勝ガ子孫、大和国竹田ニ住ミ、世々御祈祷有ル時毎ニ勅ヲ蒙リテ此ノ神楽ヲ奏ス。世ヲ経テ後、竹田家故有リテ断絶シ、翁ノ神楽ハ神祇官 卜部家ニテ奏ス。又其ノ後、兵乱ニ依テ、卜部家翁ノ神楽断絶ス。足利義満公ノ時、武威盛ンニシテ武家ニ諸禮ヲ定メラレ、住吉神功皇后御凱陣ノ吉例ニ依テ、翁ヲ武家ノ式楽ニ定メラル。此ノ時翁ノ神楽「堂上」ニ絶ヘテ古実ノ伝ノミ 卜部家ニ残ル。今ノ世、吉田家ヨリ翁ノ古実ノ相伝有ル事此ノ故也 云々
ここからは秘事が多くなりますので、中断させていただきますが、室町時代後期に吉田神道と繋がりを持ち、どのようになったのかが詳細に書かれています。
要約すると、往古に金春家と吉田家が争論して故実は吉田より伝えられたが、舞様は金春より伝えられた、よって観世大夫、宝生大夫、金剛大夫は吉田家より故実を相伝して、金春大夫と当流は太子伝故、吉田伝は受けない、とあります。
喜多流はもっとも新しい流儀ですが、『翁』だけは金春と姻戚関係になったこともあるので、古いやり方が継承されているというわけです。
この伝書には、『翁』が災いを退くために天からのご託宣として降りてきたこと、「とうとうたらり・・・」の詞章、囃子の位置づけなどが生き生きと描かれています。しかも、その精神はここまでレポートしてきた現在の『翁』のなかに生きて伝えられていることがわかり興味尽きないものです。聖徳太子自らが舞い謡ったという記載も面白いではありませんか。
また、先に述べたご祈祷の謡、喜多流の謡本には「千年の鶴も・・・・・甲に三極を備えたり」とありますが、これは三曲の誤りで、このような間違いを今頃になって気づくのは少々勉強不足でお恥ずかしいのですが、これも伝書を読めたからこそ、とつくづくと伝書の大切さと面白さを感じました。
『弓八幡』について

『翁』が一通り終わると、脇能の『弓八幡』となります。
『弓八幡』は脇能の中でも渋い曲で演者にとっては、さほど遣り甲斐のある曲ではありません。世阿弥も「すぐなる體は『弓八幡』なり、曲もなく真直なる能、當御代の初めに書きたる能なれば秘事もなし」と世子申楽談儀に書いているように、特別演出する小書もなく特別な型所があるわけでもないので、『高砂』に比べると面白みは少々下がるように思います。
『弓八幡』のような簡素な曲は演者が見せるというより『翁』と同じように真摯に、ただただきっちりと正統に脇能らしく謡い、脇能らしい力漲る構えや運びに心がければいいと思います。観客はその中から泰平の御世を祝う心を想像されればよろしいかと思います。
今回初ツレを経験したのは昨年より我が家で勉強している佐藤陽君で、東北大学で勉学中にこの道に入りたくなり、今能楽師を目指している者です。
喜多能楽堂改修工事も無事終わり、4月には本舞台も使用出来るようになったので、佐藤君と本舞台で二、三度稽古しましたが、やはり厳島の能舞台は橋掛りの位置が喜多能楽堂とは違い特殊なので、前日に場当たりをして舞台に慣れておくことにしました。その成果があり、見当違いや間違いもなく無事勤めてくれたことは嬉しいことでした。これからの益々の精進を期待しています。
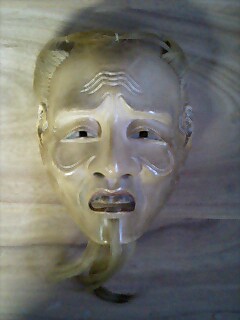
070416_1652~0001
『弓八幡』を再演するにあたって再度伝書を見ましたが、やはり「常の通り」とあるだけです。但、桑弓をワキに渡すところは通常初同で渡すとされていますが、意味合いからも「今日ご参詣を待ち申し、これを君に捧げ物と申し上げ候」とワキとの問答の時に渡した方がよいので、前回同様そのようにしました。
『弓八幡』の主題はこのワキとの問答にあると思います。弓矢をもって戦勝を祝うのではなく、弓を袋に入れて武をおさめるという平和主義者世阿弥の思想がここにあります。
スポンサーである武人足利氏を褒め称えながらも、帝を尊重する曲作りには世阿弥の芸能者魂がこのすぐなる能から伺えます。

『弓八幡』脇の五段次第、道行、シテの眞之一声、下げ歌、上げ歌、問答、初同となり、続いて序、サシ、クセ、ロンギ、中入となり舞があってキリの仕舞所と、典型的な脇能の構成で進行していきます。
サシから居クセまでは神功皇宮が三韓を従えさすために九州で祭壇を飾り祈ったこと、そして敵を滅ぼし応神天皇を生んだこと、その神が八幡山について石清水八幡宮となった故事を語ります。そしてこのクセの詞章が神楽発祥や『翁』に通じ、寿山が記載する伝書に同様に書かれていたのを知り興味が湧きました。
居クセが終わり、前シテの尉は自ら高良神(かわらのしん)であると名乗り消え失せ、中入となります。後場は高良の神躰として現れ、御世を寿ぎ泰平の御世を祝い舞を舞います。
では下記に『弓八幡』のクセと通じる『翁』の伝書の一部をご紹介します。
『翁』と『弓八幡』のは繋がりをご覧下さい。
人皇十五代神功皇后、三韓退治ノ時、九州筑前国博多郡ニテ諸軍勢ヲ集メ大酒ヲ給フ時、烏帽狩衣着シタル人、出来シテ、神功皇后ニ申サシ難所ノ瀬渡ヲ御渡リ給フ間、供奉申スベシトテ、則チ大酒シ給フ。此ノ時 神楽在リ武持神楽舞給フ。是レ武内神、高良ノ明神也。老人ハ「興玉神」「住吉大明神」也。千歳振、「高良明神」。翁ハ「八幡太神」。神功皇后懐妊ニシテ舞給フ故ナリ。
三番叟「住吉大明神」、此ノ時榊ノ枝ニ金ノ鈴ヲ附テ持チ給フト云フ。又一説ニモチノ枝ニテ舞給フトモ云フ。是レ鈴ヲ振ル始メ也。此ノ以前ハ竹ノ枝ヲ用ヰル也。今ノ世ニモ、三番叟ニ錫杖ヲ用ヰル事有ト云フ。竹ノ杖ヲ象リタルナルベシ。神功皇后三韓御退治ノ吉例ニ依テ武家祝儀ニ必ズ翁ヲ用フル也。其ノ時翁三人成ル故、武家ノ祝儀ニハ三人ニ立ニ限ル也。云々
『翁』は随所に秘事、秘技があり、芸事上いろいろな約束事を秘密に伝承しながら現代に伝えられています。今回、伝書を注意深く読み、面白い発見がたくさんありました。喜多流の『翁』の基礎となっている「太子伝の翁」の話や、『弓八幡』のクセが『翁』に密接につながっていること、こういう発見があると『翁』や脇能が自分の中で大きく広がって一つの宇宙をつくり上げてくれるようで、私の役者魂が躍ります。
伝書の記載事項が秘事であることは能楽師の一般常識です。もちろん秘すべしは悪くありません。公開しないことで浸食されず守りぬくことは大事でしょうが、今回敢えて、限度と節度を考慮しながら公開を決断しました。けしからんとお叱りを受けるかもしれません。しかし私は能の真髄を演者も観客も、ともに見極め共有することは必要だと思います。そのために資料公開がすこしでもお役に立つのであれば、それは悪とは呼ばれない、そう信じています。
伝承とは正しく伝え承ることです。
御神能後、体調を崩し私自身初めての入院を経験して、人間、万が一ということを身近に感じました。
書きとどめる作業、それがネット上であれ書きとどめたことで、私の役者魂が形をなして存在するかと思うと、花火のようにぱっと消えてしまう演劇活動に携わっている人間としては、たまらなく面白く、つい執筆に力が入ってしまうのです。
演能レポートを書きはじめて10年を超えましたが、これからも自分自身の能を見つめるために書きつづけていきたいと思っています。
今回の「『翁』と脇能」の演能レポートは、私事ですが健康であることの有り難さ、自然の中での体験のすばらしさ、伝書という先人たちの功績によって演能する意欲がさらに膨らんだことなど、たくさんの経験を書きとどめることができました。そして書くことでその思いを更に強くし、それだけでも充分価値あることだったと思っています。
(平成19年4月 記)
写真
能『翁』『弓八幡』 シテ 粟谷明生 撮影 石田 裕
面 翁 小牛尉 厳島神社蔵 撮影 粟谷明生
厳島神社能舞台楽屋 撮影 粟谷明生
『蝉丸』について投稿日:2007-03-01

『蝉丸』について
粟谷明生
愛知県豊田市にある豊田能楽堂3月能公演で『蝉丸』シテ粟谷能夫・ツレ粟谷明生を勤めました。実はこの企画は三年前に一度ご依頼をいただき、そのときは、当方の諸事情によりお断りしたのですが、再度、是非お二人でとのご要請をいただき今回お受けすることになりました。交渉は2年前でしたので、地頭は父粟谷菊生、副地頭に友枝昭世氏という豪華メンバーでの地謡を考えていましたが、昨年父が亡くなり我々の思い通りの形で実現出来なくなったことはとても残念に思えてなりません。
能『蝉丸』は、主人公のシテが延喜帝第三皇子逆髪であり、蝉丸はその弟で盲目の青年という設定です。能にはこのように曲名にある人物が主役でない場合がいくつかあります。例えば、喜多流では『満仲』、シテは藤原仲光ですが、曲名は仲光の主人多田満仲です。同じく、『葵上』のシテは六条御息所、『小督』のシテは源仲国、『張良』のシテは黄石公、『望月』のシテは小沢友房です。
能『蝉丸』は流離された身体に障害を持つ不遇な姉と弟の皇子の苦難の悲劇です。
申楽談義に「逆髪の能」とあるので世阿弥作と言われていますが、謡の詞章のすばらしさのためか、江戸時代は『砧』『小原御幸』『蝉丸』の三曲を能としては演能せず、謡だけで楽しむ曲にしてしまいました。これらの作品は能役者の謡の力が試される曲といえるでしょう。動きの型よりも謡の力を重視した曲ですので、謡のうまさが必須です。
うまさとは、技術的には音程が正確でしかも発声は綺麗で聞きとりやすいこと、そして観客へ訴える力、つまり謡の意味を伝えようという意識と説得力が加味されていなければいけません。これらを体得しはじめて蝉丸の役が降りてくるのだ、と先輩から教えられてきました。
戦前から戦時中は、二人が皇子という理由で不敬になると上演が禁止されていましたが、現在はそのようなことはありません。この重く悲しい世界、能だからこそ表現出来る世界ではないでしょうか。
私はツレの蝉丸を平成5年(第4回粟谷能の会研究公演・シテ 粟谷能夫)にはじめて勤め、その後、広島花の会では中村邦生氏にツレをお願いしてシテを勤めました。
今回は能夫との再演で、一回目のツレとシテの経験をもとに自分なりにレベルアップした役作りを心がけてみました。
盲目の青年皇子をどのように演じるか?
謡での表現はもちろんのこと、盲目の動き、殊に面遣いを意識して、私なりの工夫を凝らしてみましたが・・・・。
さて、それがどれほどのものであったかは、ご来場頂いた方々にご判断いただければと思います。
この曲では、ツレ蝉丸がワキと次第で登場してから最後の逆髪を見送るまで終始舞台にいます。ワキの藤原清貫は前場で退場し、シテも後場にしか登場しないので、この曲を支えているのはツレ役といっても決して過言ではないと思います。それだけにこのツレ役は重要で大事に位重く扱われています。
舞台進行は、盲目の皇子蝉丸がワキの清貫一行に連れられ都から逢坂山までの道中を謡い逢坂山に到着すると、勅命により出家させられ、この山に捨てられることになります。
ワキの道行が済むとツレは地謡前に移動して座り、おもむろに静かにしかし張った声で「いかに清貫」と清貫に呼びかけます。前半の作品の出来不出来を示唆するほどの一句です。盲目の青年は周囲の雰囲気を察知し「さて我をばこの山に捨て置くべきか?」と清貫に問いかけます。清貫も勅命で同行してきたことを嘆き、こころの動揺を隠すことが出来ないでいますが、蝉丸は自らの過去の行いが悪かったのであろう、きっと来世の為にとの父親の慈悲であるから恨むことはないと、逆に清貫を慰めます。このあたり、蝉丸の凜とした人物像を謡や座っている姿で表現しなければいけないところです。ここを上手く演じられると、次の落胆の場面とのギャップが大きくなり、観ている人の蝉丸への哀れみの気持ちも増す、というからくりでもあるのです。蝉丸役者の前半の仕事はここに集約されるので、ここをどう演じ切れるかが、私の課題の一つでもありました。
「御髪を下ろし・・・」と清貫に告げられ物着になります。狩衣を脱ぎ、髪を取り、角帽子をつけますが、これら物着の作業が後見二人によって舞台上でスムーズに行われると、それ自体にまた悲しみが込められるという演出です。いかに綺麗に的確に処置出来るかが後見の腕の見せ所といえます。今回は中村邦生氏と友枝雄人氏が手際よくやって下さったことに感謝しています。

物着が済むと「此は何と言いたることやらん」と先ほどよりもやや気弱な心持ちで、しかし強い意志で謡うのが教えです。実際に簑は着ませんが、蝉丸は簑を着て笠と杖を持たされ、清貫一行は都に帰ってしまいます。逢坂山にただ一人残された蝉丸は、杖にすがり琵琶を抱いて泣くばかりです。通常は舞台中央で下に伏してシオリをして泣く型となりますが、私は前回の時に「盲目にシオリ無し」と注意を受けたことがあったので、敢えてシオリをしませんでした。何でも医学的に・・・涙腺がどうのこうの・・・と説明を受けた覚えがありますが、演技的にも確かに手で涙を押さえる型より、何もせずに面遣いだけで深い悲しみを表現出来れば、その方がより強い表現になるのではないでしょうか。
アイ(博雅三位)は初同が終わると登場し、捨てられた蝉丸を見つけ藁屋へと案内します。このアイの名乗りや、ツレへの問答、ふれの言葉は多く時間がかかります。もう少し整理されてもいいように感じますが、これは蝉丸役者だけの感想でしょうか。
「源平盛衰記」では蝉丸が博雅三位に琵琶の秘曲をここで伝授したようですが、能ではそこは触れないでいます。
アイが退場すると漸くシテの登場となります。
一声で髪が逆立つ異体な姿で現れ、都から逢坂山までの放浪をカケリや道行の仕舞で演じます。
逆立つ髪と言っても能では、鬘の両鬢を垂らしたり、時には黒頭を付けることで髪の異常さを表現します。
道行が終わり、ツレの「世の中はとにもかくにもなりぬべし、宮も藁屋も果てしなければ」の謡の聞かせどころとなります。シテ逆髪は弟の声を聞きつけ、ここに姉と弟の再会場面となります。シテとツレの掛け合いは、徐々にお互いの謡の声や音の高さ、速度、張りなどを駆使し高揚させて絶頂に持っていき、地謡の「共に御名を木綿附の」にと繋げます。うまく繋がると、この再会の場面、自然と涙腺が緩むところです。

今回の演能にあたり、シテからの要望もありお互いに相談して、喜多流としては新たな演出を試みてみました。再会したあと通常は、蝉丸は藁屋の中に居続けますが、今回はツレが序で藁屋から出る演出にして、姉と弟の距離感を密なるものとしました。苦境にあるクセ謡の上羽「たまたま言訪ふものとては」を現行ではシテ謡ですが、意味あいから本来は蝉丸の言葉であるのでツレが謡うことに変え、また中啓を遣い琵琶を弾く型も取り入れ、謡だけの世界に少し視覚的な要素も入れてみました。

そして終盤、ロンギになり、シテとツレの最後の別れの場面、クライマックスとなります。
ここもまた能役者の力量が試される所です。
演者は単に作品の持つ力に頼りきるのではなく、謡と型の演技力で観客自身が感動のスイッチを自然と押してしまうほどのものを提供しなければいけないでしょう。
絶望感あふれる蝉丸の謡、それが判りながらどうしようもなく去らなければならない姉の逆髪。
お互いの謡の力と微かな動き、あとは観客の想像力にお任せしますが、そこまでの舞台作りをしてこそ一人前の能役者と呼べるのではないでしょうか。またそこまで求めているのが能『蝉丸』であり、世阿弥の思いだと思います。果たして私たちがそこまで出来たのかは気になるところですが、能夫と二人真摯に精一杯勤め、志があったことは確かです。
去る姉に弟は杖を突きながら、足弱く追いかけ見送ります。
「そこは右耳で聞く、そしてちょっと面遣いをするんだよ、それが出来るかどうかなんだ、そこが勝負だよ!」が父の言葉です。
これからも演能のたびに父の言葉を思い出し、父の顔が浮かぶことでしょう。父から教えられたもの、父が大事にしてきた先達の能、脈々と続く粟谷の能を伝承し、そして、粟谷明生の能というものを確立していきたいと生意気にも思っています。そうでなければと、能『蝉丸』の蝉丸が教えてくれたように思えてなりませんでした。
(平成19年3月 記)
写真提供 石田 裕
『千寿』について投稿日:2006-11-26
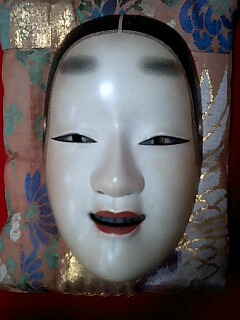
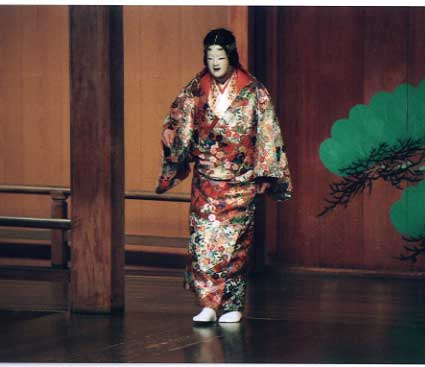
喜多流自主公演(平成18年11月公演)で『千寿』を勤めました。
『千寿』は最近では頻繁に演じられるようになりましたが、以前は楽屋内でいう遠い曲(あまり上演されない曲)でした。理由ははっきりしませんが、例えば『船弁慶』などは義経と静御前の恋事を一方が子方で演じることで、生々しくならないように、いやらしさを隠していますが、『千寿』は重衡を両シテのように重く扱い、大人が直面で演じるため、どうしても表現が露骨になってしまう衒いがあります。先々代十四世喜多六平太先生や先代喜多実先生はその当たりがお好みに合わなかったのでは、と私は推察しますが真相はわかりません。
実は私もこの曲が好みかと聞かれたら、ちょっと答えにくいです。
しかし能役者とは不思議なもので、好きではないと言いながらも取り組んでいくうちにその曲の良さを見つけてしまうものです。私もはじめは気乗りがしないで稽古に入りましたが、次第にその面白さ、よさが判るようになりました。
曲名の『千寿』ですが、他流では『千手』と表記します。本来は千寿の母親が「千手観音」に我が子の誕生を祈念し、その願いが叶い「千手」と命名したもので、吾妻鏡をはじめほとんどの文献で「千手」と記載されています。「千手」が正しい表記と思われますが、千手のふるさと磐田市や千寿保存会などのチラシにはあえて「千寿」と記し、そう呼んでいるようです。これも私の憶測ですが、本名は「千手」で白拍子の源氏名を「千寿」としていたのではないかと思うのですが、どなたか真実をご存じならばお教えいただきたいです。
能『千寿』は、一ノ谷の戦で生け捕られ鎌倉まで護送される平重衡と、頼朝の命令で遣わされた千寿との束の間の悲恋物話です。舞台で、シテの千寿、ツレの重衡、ワキの狩野宗茂の三人が三様に的確に役を演じ分け力を発揮するところに、この曲のおもしろさと魅力があると思います。余談ですが狩野宗茂は曾我兄弟の仇として有名な工藤祐経の従兄弟と資料にありました。
ではこれからは舞台の進行に従いレポートします。
舞台は囃子も何もなく、ツレ重衡が静かに出て脇座にて床几にかかります。鎌倉の館に拘束され処刑を待つ身という状況設定です。まず狩野宗茂(ワキ)が名乗り、頼朝が重衡に対し丁重な扱いをしていることを語ります。その扱いは武人として、平家の御曹司として相当に手厚いものであり「昨日もお湯をひかせ」と囚人に風呂を用意するほどです。更に頼朝お好みの美女十人衆のナンバーワン千寿をお世話係に付けるほどですから、その扱いは相当に上等な待遇であったことが判ります。
頼朝の命令により千寿は連日重衡のお世話をしていますが、雨の日に琵琶を奏して慰めようとするところからがシテの登場となります。
通常、『千寿』の次第は常座で謡いワキとの問答が終わると、一時後見座にクツロギ下居して、重衡の独白となる大事な謡い所を聞きながら待ちます。ここは素声(しらこえ)の節扱いがあり、わざと調子をずらすように謡いますが、「我はいつとなく敵陣に・・・」から謡本では三行も素声を謡うのは滅多にありません。異例です。うまく調子を取らないといい素声にならず重衡役者の力の見せ所ともいえるむずかしいところです。この大事な場面で正面にお尻を向け下居している舞台景色は綺麗なものではありません。以前からどうにかここを改善出来ないかと思っていたところ、我が家の伝書に橋掛で謡うこともある云々と記されていましたので、今回試しに取り組んでみました。楽屋内の反響としては橋掛が館の外、舞台が館の内という状況がより明確化されてよい演出であったと好評でした。
重衡は捕らわれの身でありながら頼朝に出家を願い出ます。平家の御曹司らしい我が儘ぶりが出ているところで、それまで丁重に庇護してきた頼朝ですが、さすがに許可出来ないと断ってきます。重衡の装束で気になるのは何故袈裟をつけるか、という問題です。出家していない重衡ですから本来袈裟はおかしいと思うのですが、喜多流では袈裟を掛けています。このあたりも御曹司の我が儘ぶりで袈裟ぐらい掛けさせろという解釈なのか、他流では袈裟なしの演出もあるといいます。
はじめは重衡に面会を断られる千寿ですが、頼朝の仰せである旨を狩野に伝えると重衡との面会となります。ワキが「只こなたへと請ずれば」と招きいれると、シテは「そのとき千寿立ち寄りて」と橋掛からするりと歩み寄り舞台に入り、「妻戸をきりりと押開く、御簾の追い風匂い来る」と戸を開ける型をして館の中に入ります。若い千寿が都人重衡の香の香りに反応する一瞬に演者は心して演じています。見落としやすいところですが、ここが大事な見せ場です。生前父は私の地謡を謡うはずでした。ここの謡い方について「どうも皆、ここをゆったり、ゆっくり謡っているが、僕はさらりと謡うよ。若い女が経験したことのないものを感じる一瞬だよ、都人のいい匂いをね。だからさらっと、風が吹くように謡いたいんだ」と言っていたことを思い出しました。
千寿は出家の願いを自分も頼朝に進言したが叶わなかったことを語り、心ふさぐ重衡を盃と琵琶で慰めようとします。菅原道真の現世安穏を祈る朗詠、死語の引摂を願う具平親王の句などが詠われ、はじめは心を閉じていた重衡も次第に心を開き、酒宴となります、ここからがシテの芸尽くしの舞となります。
謡曲では謡の聞かせどころはいろいろありますが、囃子方も一時囃子アシラヒを中断するほどの大事なところはいくつかありますが、喜多流ではつぎの三個所が有名です。
『江口』の「秋の水漲り落ちて」、『砧』の「宮漏高く」、そして『千寿』の「羅綺の重衣たる、情け無きことを機婦に妬む」の三つです。気持ちを込めて美しく張って透明感を持って謡います。役者にとって聞かせどころ、勝負のところです。
さて芸尽くしのクセ舞ですが二段クセとなります。舞の型は道行の詞章に合わせながら基礎的な型の連続で、それほど特徴がある面白いものではありませんが、だからこそ舞そのものの美しさ、役者そのものの力が必要で、それがしっかりと表現出来ないとこの能は成立しないでしょう。
他流では中之舞としているところもありますが、喜多流はしっとりとした感じを出すために序の舞です。今回は初番が『敦盛』で三段の舞を舞うので、同じ型が続かないように配慮して私は替の型で更に「つまみ扇」の型を取り入れて勤めました。
酒を酌み交わし琵琶を奏でてひとときの時間が過ぎると、そこは二人だけの一夜となり、その一時もやがて過ぎていきます。源平盛衰記ではその夜のことをプラトニックに書かれていますが、私は大人の愛の確認があったと、『千寿』を勤めました。
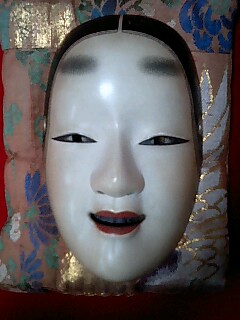
061126_1627~0001
千寿が重衡のもとに行かされたのは22歳。
年齢からも喜多流の小面を使用するのが順当ですが、艶、美女を前面に出して演じてみたい思いから、粟谷家蔵の孫次郎系統の面「柳孫」を使用してみました。華やかで、ちょっと大人の雰囲気がある面ですが、実は未だ使用したことがなかったので、いつか使いたいという役者心でもありました。

二人にとって貴重な時間が過ぎ、勅命によりまた都に戻ることになる重衡を千寿は泣きながら見送ります、最後の場面「はや着衣に引き離るる、袖と袖との露涙」と二人は舞台中央で交差しますが、ここをあまり近づきすぎると露骨になり舞台にイヤミがでてしまいます。少し距離をとりながらも二人の役者の心、息が上手く通じて、ぎりぎりのところで離れていければいいと思います。
ところで『千寿』のツレ重衡はシテと並列するほどの重要な役です。
『千寿』の演能心得として、謡はツレが一番重く、シテはその次ぎ一段高く張って謡うこととの教えです。
重衡を勤める者は、はじめから最後近くまで脇座で床几にかけたままです。私は未経験ですが、体験者はこの長丁場を腰掛けている辛さに苦しみます。膝や腰の苦痛は経験者しか判らないでしょう。今回狩野了一氏にお願いしましたが、重衡らしい良いツレを的確に演じてくれて私の舞台を盛り上げてくれました。
この重衡が床几に腰掛けている姿を拘束されている意味と先輩のある方は説明されます。申合で、重衡が心をひらき酒宴に加わり朗詠を聞くときと、琵琶を弾くときに床几から降りてみてはと思いツレに指示したところ、これは拘束されている意味だから不適とのご注意を受けました。重衡の床几についての考えは、それだけに断定してしまうのはいかがなものでしょうか。違う角度からの見方もあっていいのでは、確かに捕らわれ拘束の有様の表現ではありますが、それだけに留まらないものもあると思います。拘束されていると同時に、能『千寿』での重衡の役柄の位の高さを表していると思います。
当日は自主公演という流儀の催しでもあり、また狩野了一氏にご迷惑がかかるといけないと思い、今回は見送り普段通りにという師からのアドバイスに従いましたが、私としては少し気持ち悪さを残しました。
新しい試みが効果的か、また似合わぬ悪いものなのかは別として、能役者として常に心がけていなくてはいけないことがあると思います。それは常に能を演劇的に前向きに考え、演じる姿勢を崩さないこと、それが私のモットーです。
先日、ある方から「能はそれまでの体験が能(脳)力となって体力を越える」とのお言葉を賜りました。表現の枠組みを狭めたり、新風を吹かせないために、先を見つめる若き能楽師にプレッシャーを与えるようなやり方があっては流儀は繁栄しないのです。
能は決められた型や口伝など約束事もたくさんありますが、その理由については伝書に書かれてはいません。その真意は師や関係者から教わる中で、演者が思いを膨らます部分があることが重要です。情報はより広く、たくさんあるのがよく、それが正しいか間違いかは別として、考えて選択する作業ぐらいのことは、今の時代の能役者としての必須条件だと思うのですが。
千寿は重衡に名残があったのか若くして亡くなります。私は従来の重衡の型に新風を起こせなかったことに、名残があります。父が亡くなって初めての能、父への名残と共に、名残というキーワードで繋がる『千寿』でした。
(平成18年12月末 記)
能 「千寿」シテ 粟谷明生 撮影 あびこ喜久三
面「柳孫」粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
『江口』は普賢菩薩の心投稿日:2006-10-08


写真「『江口』後シテ 粟谷明生 撮影 石田裕
『江口』は普賢菩薩の心
粟谷明生
第80回の粟谷能の会(平成18年10月8日)は、祖父、粟谷益二郎五十回忌追善の催しとして、子である菊生、辰三、幸雄が仕舞を舞い、孫の能夫と私がそれぞれ大曲の『道成寺』と『江口』に挑み、一門全員が力を合わせ執り行うものでした。
父菊生は会の番組の挨拶に、孫たち(能夫と私)が大曲を追善として勤めること、自分は仕舞と『江口』の地頭として舞台に立つこと、「八十五歳に近くなって父の五十回忌追善能に参画出来るということは感無量、無上の喜びであります」と、晴れがましさと嬉しさをつづっていました。
その父が『江口』の申合せの前日に脳出血で倒れ、未明に入院、当日は病院のベッドの上で生死をさまようことになろうとは・・・・。
役者はどんな状況であろうと舞台を最優先しなければいけません。父の容態が気にならないわけがないのですが、この状況下で『江口』を勤めなければいけない私のことを察して下さったのか、ワキの森常好氏や囃子方の皆様(一噌仙幸氏、大倉源次郎氏、亀井広忠氏)、ツレも地謡も皆、心を一つにして父のいない舞台を盛り上げてくださる、それぞれの役者魂、舞台人魂を痛いほど感じました。そしてそれは舞台上の人だけでなく、観てくださる方々からも伝わってきて、まさに見所が一体になったような不思議な緊張感、胸打つものがありました。あの舞台を支えてくださった皆様にも、ここで厚く感謝、御礼申し上げたいと思います。
ここからは、いつもの演能レポートに入りたいと思います。
能『江口』の舞台となる、江口とは難波江(現在の大阪湾)の入口の意味で、昔、瀬戸の海を渡って来た人はこの江口で船を乗り換え、川舟で淀川を遡って目的地に行くという、水上交通の重要な地として華やかで賑わいを見せていました。鎌倉時代までは繁栄し、その後、次第に華やかさは消えていったようです。
現在、大阪市淀川区南江口には寂光寺があり、ここは境内に贈答歌を交し合った遊女・妙と西行法師の供養塔があることから、江口の君堂とも呼ばれています。以前、写真探訪(これは未公開)で訪れましが、静かな場所にあり、当時の賑やかな面影はまったく感じられませんでした。

写真 「寂光寺」 撮影 粟谷明生
『江口』は西行と江口の遊女との和歌贈答説話と性空上人が室の遊女を生身の普賢菩薩と拝したという二つの説話から構想されたものです。西行との贈答歌は新古今和歌集に載ったことで有名になりましたが、そこには遊女は妙と記載されています。一説には贈答歌はどちらも西行の歌ではないかとするものもありますが、能ではシテは遊女妙ではなく、江口の君とだけ謡われています。
いずれにしても、普通は僧が教える立場であるものを、僧が遊女に法を教えられるという逆転の発想が面白いです。女性は穢れたもので、女人成仏できないとされた当時の世相にあって、女性が僧に物申すという逆転場面は能の世界ではときにあります。『柏崎』では物狂いの母(シテ)が善光寺の女人禁制に対して「仏がそうおっしゃるのか」と住僧に抗議し、『卒都婆小町』のシテ・小町が卒都婆問答で僧を言い負かすなど、いくつかあげることができます。この逆転の発想が当時の観客にもおもしろく受け止められていたのではないでしょうか。
『江口』を演じるにあたって気になったことがいくつかありました。
まず遊女とはどのようなものなのか。私はすぐに映画「陽暉楼」のような遊郭にいる女性たちを想像していましたが、『江口』で描かれる女性たちはどうも少し違うようです。
『江口』を理解するには、世阿弥が描いた当時の遊女像で物事を考えないとわかりにくいかもしれません。故綱野善彦氏は以前、橋の会のパンフレットに遊女について、こう書かれています。
「近代、近世の遊郭の遊女のあり方から中世以前の遊女をおしはかってしまうのは大きな間違いである。世阿弥が昔を思い浮かべて描いた遊女は13世紀から14世紀のスタイルで今とはそのスタイルが違う。近世的、近代的な売春婦として単純に考えてはいけない。
つまり、遊女とは古くは一種の巫女、その職として芸能をする者であり、芸能者は神仏になることもあり、それが宮中との繋がりにもなったとも考えられる」と、あります。この状況下から、江口の君のような発想が生まれるのは不思議ではなく、歌舞音曲を業としながら集団生活をするひとたちと見るべきなのでしょう。
次に気になったのが普賢菩薩になる設定です。菩薩は仏陀になる前の悟りを求める者です。普賢菩薩は釈迦如来の脇侍で、智恵を司る文殊菩薩とともに、慈悲を司るものとして配されています。文殊菩薩が獅子に乗っているのに対して、普賢菩薩は白象に乗っています。私は今まで、菩薩は神仏そのものであると誤解していました。確かに神仏に近い存在ではありますが、まだ悟りまでは達していない、悟ろうとする修業の身です。
遊女が菩薩になるという、遊女を穢れた者とするのではなく、芸能をするものとして、芸能の価値を認めることで、神仏に近い存在とする考え方や設定は世阿弥の時代ならではの構想かもしれません。とりわけ普賢は美しいお顔なので女性の象徴のように思っていましたが、実は男性であるということなども判ってくると私の頭の中はまたこんがらがってしまい、あまり性別のことを持ち出しても意味ないとは思うのですが、まだ悟られていない身分であること、男性であることなどが、男性の能楽師たる私がこの曲に臨むにあたって取りかかりやすくなった要因のひとつということは事実でした。
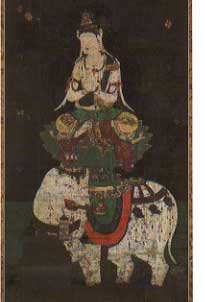
写真 国宝普賢菩薩像 東京国立博物館蔵 ポストカードより
次にもう一つ気になったことは、演者として前場を里女や江口の君の幽霊という設定でなく、普賢菩薩そのものの心持ちで勤められないだろうか、ということでした。これは私の単なる思いつき、ひらめきなのですが、そのように演じたい、と稽古しながら思い始めました。
そこへ、幸流小鼓方の横山晴明氏から森田光風氏の「平調返の試問に答ふ」というお手紙を拝見させていただく機会に巡り会い、私のひらめきが満更大間違いでないことがわかり自信がついたのです。
お手紙の一部をここに引用させていただきます。
「西行法師と江口の遊女との歌問答の故事を前提として転倒迷妄の窮境(きゅうきょう)から、三途八難の悪趣に堕ちた遊女も、愛執の境涯を脱すれば忽ちに実相無漏の大海に棹さして普賢菩薩と現じ、白雲に乗って西方極楽浄土に往生すると云う一種の人生観を説いた幽玄極致の能であります。遊女が普賢菩薩であるといふ事は、説話で名高い撰集抄や十訓抄から材を求めたものであります。是に依って江口の仕手の本体を遊女―江口の君と観察してはなりません。即ち普賢菩薩であります。・・・・・・云々」
この最後シテの本体を遊女・江口の君と観察してはならない、すなわち普賢菩薩なのだという言葉に力を得て、私は前シテの登場から終始、普賢菩薩という気持ちで演じられたのです。もちろん詞章を変えたり、変わるわけではありませんが、あくまでも普賢菩薩の心で、という精神性だけのことですが、私は能役者こそこの精神性を大事に演じなければつまらない舞台、空虚な舞台になってしまうと思っています。
森田流の伝書には、さらにおもしろいことが書かれています。能の骨子は五行によって成立され、五行とはすなわち、木、火、土、金、水、季節では春、夏、土用、秋、冬の五季、方位では東、南、中央、西、北の五方、色彩では青、赤、黄、白、黒の五色、調子では雙調、黄鐘(おうしき)、一越(いちこし)、平調(ひょうじょう)、盤渉(ばんしき)の五調子、音では角、徴、宮、商、羽の五音です。『江口』の小書「平調返」では、五行の四番目、平調と同列の金、秋、西、白、商が関係してきます。『江口』は「秋」の曲で、「白」象が、「白」妙の「白」雲に打ち乗って、「西」の空に行き給うと、一貫して五行の理にそって統一されていることが面白く、演じる手助けとなりました。これらは「能劇逍遥」横道萬里雄著(筑摩書房)にも記載されていますので、詳細はこちらをご覧下さい。
ここからは曲の最初から細かい演出について記していきます。
前シテの出は、常は「のうのう」とワキに呼び掛けながら幕から出ますが、普賢菩薩の心でと思い、現世の旅僧に悟らせるために、和歌を口ずさんでいるそばに、すっと姿を現す、そう思えるような演出として、ワキのサシ声の謡で静かに橋掛りに登場しているようにしました。西行法師の歌ばかりでは真意はわからない、「仮の宿りに心留むな」の歌も忘れてはいけないと諭すあたりの心は普賢菩薩の陰りが伺えられるようなものです。
後場は舟を橋掛りに出して遊女三人が並びます。シテを中央に、左右のツレを従兄弟の充雄と浩之に勤めてもらい、粟谷家一門全員が舞台に立てて、粟谷益二郎も粟谷菊生もきっと喜んでくれたことと思っています。ツレとの連吟「秋の水、漲り落ちて去る舟の」は、囃子方が道具を一時置くほどの謡の聞かせどころです。ここをどのように謡えたのかが気になるところではありました。
通常、ツレは序で地謡座前に移動して最後まで残っていますが、今回はシテが普賢菩薩になり白象に乗って西の空に帰るときにツレの遊女が舞台に残っているのは、景色が悪いと思ったので切戸口から退場してもらいました。舞台には旅僧たちだけが残るほうが『江口』の終曲としてはいいはずです。
今回は「干之掛」と「彩色」(イロエ)の小書付でした。「干之掛」は五クサリの序のあとに高い干の音から特殊な譜を吹く序之舞の特別演出です。一噌仙幸氏は『江口』という曲を吹いて下さいます。序之舞だけに留まらない能『江口』の全体の世界を吹いて下さる希少な笛方で、私の演能の大きな支えになっています。今回は初段オロシでは一噌流独自の「普賢の手」という特殊な譜も入れていただき、舞いながら序之舞の世界を堪能出来たことは大きな喜びでした。また後で「彩色」も入ることで常の三段を二段に縮小するという試みにも応えていただき感謝しています。
「彩色」は「序之舞」との繋がりを軽んじていけないと思います。『江口』の「彩色」は特に主張があるといいます。常はシテ謡で「波の立居も何故ぞ、仮なる宿に」と一息に続けて謡うところを「波の立居も何故ぞ」で一端切り、「彩色」の型が入ります。「波の立居も何故ぞ」と衆生への問いかけがあり、その仏の答えとして「仮なる宿に」とまた謡う、これが彩色の仕組みです。森田流の伝書には「彩色」があるものが本説である意が記されています。つまり彩色(イロエ舞)は遊女が徐々に菩薩に変化し始めるきっかけということのようです。詞章では「これまでなりや帰るとて即ち普賢菩薩と現れ」で一瞬のうちに普賢菩薩になりますが、その前兆のようなもの、それが彩色という位の高さを演出だと考えられます。
今回の「彩色」は舞台を静かに一巡するものながら、そこに変化の意識が込められるもので、破之舞のように、序之舞と同等、もしかするとより大事に扱われている二之舞と同じと思って勤めました。もっとも喜多流本来の彩色は働系統の途中に段をとる形式的ものです。型は大小前へ左回り正面乗り込み、右回り大小前、左右とありますが、これはあまり笛の精神性とは似合いません。近年友枝昭世氏がイロエ系の段なしの余韻を大事にする型を試みましたが、私もそれを真似て勤めました。
終曲は「有難くこそ覚ゆれ」で幕に入るのが吉・徳ですが、今回は次の『道成寺』の最後が脇留です、同じ型が続くのは避けなければいけないので、敢えて橋掛りの三の松で留めて終曲としました。
面については、本来、喜多流は小面が決まりですが、『江口』のシテは遊女であり普賢菩薩にもなる程の高位の女性です。単に可愛らしいだけの小面では『江口』にはそぐわないです。観世流では増女を使用する時もあるようですから、小面のかわいらしさだけの表情には限界があるでしょう。
江口の君に似合う小面、凄いエネルギーを発散する力強い小面。残念ながらそのような小面は我が家にはありません。ならば小面の縛りを越えて、いっそ増女を使用しては、とも考えましたが、今回は披きでもあり、また流儀の主張である小面を使用する所以「なぞとき」もしてみたいと悩んでいましたら、その私の悩みを解決してくださるものと出会うことが出来ました。それは観世流・浅見家の名品の小面です。浅見真州氏とは日頃いろいろお話をさせていただいている間柄でもあり、また亡き父と真州氏とのお付き合いのお陰でもあり、今回貴重な小面を拝借させていただくことができましたことは、真に役者冥利に尽きます。この小面は絶品で私の『江口』演能の根幹となって力を与えてくれました、ここに浅見真州氏に感謝申し上げます。
父が倒れた日は嵐のように大雨の降る日でした。二、三日後の、粟谷能の会の当日(8日)は一昨日からの雨があがり、さわやかな秋晴れの日となりました。もう少し頑張って、この会が終わるまではという我々の祈る思いが通じたのか、あるいはさわやかな陽気のせいか父の状態も小康状態を保ち、何とか命をつないでくれました。会が終わって3日後、11日に力尽き帰らぬ人となりました。
父や新太郎伯父は、祖父益二郎が亡くなった後、一周忌追善能、三回忌追善能・・・と、祖父の追善供養といっては大曲に挑み、充実した会を催して、粟谷能の会を盛り立ててきました。私たちもそういう機会に思いのある曲を勤めさせてもらい、成長してきたように思います。「追善ですからこういうことをやらせてくださいと実先生(家元)に申し上げ、大きい会を催すお許しをいただくのよ。追善という名前を借りて、お客様にもたくさん来ていただいてね」と言っていた父のいたずらっぽい顔が思い出されます。
五十回忌といえば、追善供養も最後、死者が完全に神になるというおめでたいときでもあります。これが終わり、次は父の一周忌から始まるのかと思うと、輪廻を感じ不思議な気持ちになりました。「五十回忌で追善能もおしまい。種切れになるね。じゃあ、僕の一周忌からまた始めたらいいよ」と言いそうな父の顔が浮かび、なにか、粟谷能の会のために、ちゃんと計算して逝ったような気にさえさせられるのです。
父の死と遺志を思うと、父や新太郎伯父が取り組んできたように、能夫と私が先頭きって、それぞれの思いのある課題の曲、大曲に挑み、一門の者が一致団結して、粟谷能の会を継承し、盛り立てていかなければ、と心底思っています。
役者は常に光源体であるべき、どんなときでも輝いていなければいけないと思っています。父は確かに光源体であって、いつも輝いていました。もっと謡ってもらいたかった。駄洒落や面白話ももっと聞きたかった。今私は、一つの光が消え、闇があたりを満たしているように感じます。しかし、蛍が明るい昼間より暗闇の方が美しく見えるように、暗闇だからこそ光源体は光を放ち、闇があればこそ、その光り輝きが冴えるのだと、いま自分に言い聞かせています。
父のいない舞台で『江口』を勤め、こういう闇の世界だったからこそ、見えてきたものもある、と感じました。またそのように見てくださった方もおられ、随分と勇気づけられました。どんな状況でも、役者は舞台に立つ宿命をもっている、たとえ闇のなかでも役者は光輝いていなければならない、それがもし輝かなくとも、光る作業はしなければいけない、そう感じ教えられた披きの『江口』でした。
(平成18年10月 記)
『黒塚』の白頭について投稿日:2006-09-02

『黒塚』の白頭について
粟谷明生
「ひたち能と狂言の会」(平成18年9月2日)で『黒塚』を「白頭」の小書で勤めました。
『黒塚』は私がこの道を一生の仕事と心に決めるきっかけとなった曲です。
今までに粟谷能の会で2回、国立学生能で1回、粟谷能の会福岡公演では、前シテを父の代演で勤めました。後シテを「白頭」で勤めたことはなく、今回初めての体験となりました。
喜多流の謡本の曲趣には「この貧しい女性は鬼女の化身であるが、初めは邪念も害意も示さず、月光のもとに生死輪廻を嘆くが、中入になり閨の内を覗くなというところから、鬼気のたちまち迫り来るものを感じさせる」とあります。
しかし、私は正直このような気持ちでは演じたくないと思っています。「閨の内を覗くなというところ」あたりは、まだ鬼になっていない、少なくとも前シテの段階では鬼ではないと考えて演じています。
安達ヶ原の女は元来の鬼ではありません、中年女性の独り身の寂しさが大きな背景になっています。昔覚えた都の流行歌を口ずさみながら、ひとり糸を繰りながらどうにかして生きていかなければならない惨苦を謡います。そして次第に窮地へと追い詰められていき、人肉を食らうという冒してはならない罪を冒した浅ましい鬼女の姿となるのです。(安達ケ原の女の身の上については、陸奥の安達ケ原に伝わる鬼婆の伝説によってうかがい知ることができます。演能レポート「『黒塚』の鬼女をどう表現するか」参照。)
禁じられた事は、一度破ると、もう後戻り出来ません。歯止めが利かなくなった人間の弱さが見え隠れして、人間とはなんであろうか、と自問自答したくなります。
いつかはやめよう! もうしないと思いながらも、また繰り返してしまう人間の性。
女は今度こそは、と修験者の山伏祐慶の仏の救いにすがろうとします。
やり直したい、それを手助けしてくれそうな山伏だからこそ、寒さを凌ぐために暖をとってあげよう、と親切心で夜の山に薪を取りに出かけます。
そこには、女のいじらしい反省と償いの気持ちがあります。
しかし、女はつい余計な一言を漏らしてしまいます。
「閨はみないで欲しい」と。
山伏はそんなことはしない、「言語道断」と言葉をはねのけ約束を守りますが、付添人の能力(アイ)にはそれが通用しません。その掟は破られます。
中入前に山伏に再度念を押して、山に出かける女は、橋掛で上を見上げ、裾をとり、ずかずかと切る足で運び幕に入りますが、私はそこで女が鬼になり、「さあ、いい獲物が来たぞ」とは思いたくなく、そうは演じていないつもりです。
夜の山道という危険をも恐れず、ただただ暖をとってあげようとして薪を拾いに行く、けなげな感じを出したいのです。そう解釈したいのです。
もっとも演者がどう言おうと、どう見るかは鑑賞者の自由ですが。
女が鬼に変わるのは、能力が掟を破り、閨の内を覗いたときと考えています。
私は楽屋で着替えながら、アイが閨の内をみて、「ぎゃあ、かなしや、かなしや」と叫ぶときに、「見たな」と鬼へと気持ちを変身させています。
面をつけるのが丁度そのときになるのが一番と、そのように私は思っています。これは楽屋の裏話のひとこまです。
今回、後シテの鬼女の扮装を白頭に般若、鬱金地立枠模様の厚板唐織を肩脱ぎで勤めました。
鬼女の姿も髪には、鬘掴みだし、黒頭、赤頭、白頭と4種あり、装束は紅有でも紅無でもよく、付け方も腰巻裳着胴(もぎどう)、着流肩脱ぎとバリエーションは豊富です。
(以前の演能レポート「黒塚」で過去の出で立ちを写真でご覧下さい。)
どれを選ぶかは演者の自由であり、演出に委ねられています。今回選択した「白頭」になると、面は「般若」、柴の持ち方(後に説明)も抱き柴となり、ただ恐ろしい鬼畜というより、鬼にならざるを得なかった女の悲しい定め、それを背負った女がより表現されるように思います。
以前から白頭で気になることがありました。それは白い毛と般若の面の彩色、つまり毛書きや顔色とのバランスがどうもぴったりしないこと。所持している白頭と般若の面、この二つを仕方なく合わせているからなのか、そんなことも考えていないからなのか、疑問を感じていました。
白頭なら、それに似合う般若がないだろうか。我が家にはない「白般若」みたいなものを付けたいと考えていました。
今回、面打師・石原良子氏の愛弟子たちの面の展示会「幻」で見つけた、やや白色の強い般若が白頭に似合うのではと思い、石原氏に相談し、打たれた土屋宏夫氏のご許可をいただき拝借し勤めました。
後の出は、女が怒り、逃げる山伏を、山から駆け下りて追いかける様を表現します。出囃子は「早笛」と「出端」の二通りがありますが、今回私は早笛で出ることにして、観世流の小書「急進之出」で演じました。
手掛ですぐに幕をあけ、三の松までするっと出て、逃げる山伏を捜している型をして、見つけると一端シサリ、幕に戻ります。この時一度幕を下ろすときもあれば、そのままもあるようですが、この度は下げずに太鼓の刻みで素早くまっしぐらに山伏目掛けて走り出し、「いかに旅人」と謡いかけました。
私としては、あの安達ヶ原の女が後半鬼女になるには、鬘の「掴みだし」か「黒頭」が似合う、早笛よりはむずかしいですが出端で登場する方が効果的だと思っています。しかし、毎回、同じ演出では観客にもあきられる、役者自身の鮮度も落ちる、興業主としての演出を考えたとき、今回のような選択となりました。
また、後シテの出のとき、山伏のために拾い集めてきた薪の持ち方も小書がない場合、ある場合で違いがあります。
通常は「負い芝(おいしば)」といい、薪を肩にかけます。
小書の時は「抱き芝(だきしば)」といって薪に自ら着ていた装束を巻きつけ左手に抱くように持って出ます。抱き芝のほうが女の薪にたいする思いみたいなものが表れているのではないでしょうか。私は抱き芝がいい演出だと思います。
「祈り」も演出を替えてみました。初段のあと、『道成寺』の鱗落しといわれるところで、通常打たない金春流の替え手を打ってもらい、そこで一度止まり、じっくり振り返り山伏を睨みます。そしてなかなか捨てられなかった薪ですが、遂に心の糸は切れて折角の薪を放り投げる型を入れました。もうここからあとは人食い鬼女そのものということでしょうか。
今回いろいろな注文に快くお相手していただいた囃子方(槻宅 聡・観世新九郎・亀井広忠・大川典良 敬称略)の皆様に深く感謝しています。
ひたち公演は私の責任で引き受けた興業です。受けたからには成功させたい。
曲目の選曲も私の考えで、粟谷能夫も『花月』を快く承知してくれました。
能楽師は自分の未経験の曲、それも中々出来ない曲をここぞとばかり取り出して演じたいものです。しかし、お客様に「ああ、楽しめた」と素直に喜んでいただいてこそ、公演の成功となると思い、選曲しました。そしてそれぞれが工夫を凝らして演じてみました。
今回試みた『花月』の弓矢を持っている謂われを説明する言葉の挿入や、『黒塚』の「急進之出」のようなものは喜多流にはありません。「ないのになぜ演る」と先人たちからのお説教の声や喜多流愛好家からの質問が聞こえてきそうですが、喜多流自主公演ならば、規律も守る必要がりますが、私的な会や地方公演で、よりサービスする演出もあっていいと思います。
昔、『道成寺』を替装束でなさった方がいらして、同輩から「あの替装束は喜多流にあるのか」と皮肉っぽく聞かれたそうです。すると、その方は「ない、しかし能にはある」と答えられたとか。私はこの言葉に能役者の精神のすべてが含まれていると思い気に入っています。流儀の決まりを蔑ろにするつもりはありませんが、その殻を後生大事に守ることだけが芸能の本質とは思えないのです。
「しかし能にはある」は、これからの私の演能活動の根幹となる言葉、そう信じて邁進したいと心新たにしています。
(平成18年9月記)
『井筒』について 女能の名曲の魅力投稿日:2006-08-27

『井筒』について 女能の名曲の魅力
粟谷明生
秋田県大仙市のまほろば唐松能舞台での定期能公演(平成18年8月27日)で『井筒』を勤めました。
『井筒』は三番目物といわれ鬘物の代表曲で、女能の名曲です。
能楽師ならば三番目物には憧れがあり、「いつか自分も勤めたい」と夢みているのではないでしょうか。
私は天の邪鬼なのか、ずっと二番目物や四番目物の現在物の方に心が向いていて、複式夢幻能といわれるものに興味を示さないでいましたが、40歳を過ぎるあたりから、能の真髄といわれる三番目物の魅力・味わいの深さを知り、いまはその世界に引き込まれ、虜となっています。
三番目物には、「本三番目物」といわれる最高位の曲がいくつかあります。
登場人物も高貴な女性で、緋色大口袴をはき、高位之序の序之舞を舞います。
喜多流では本三番目物を勤める順序は、『半蔀』や『東北』の入門編をまず習得し、『夕顔』『楊貴妃』『野宮』『江口』『定家』と徐々にレベルを上げていきます。
残念ながら『井筒』は鬘物の代表曲でありながら、「本三番目物」ではありません。理由は後シテの扮装が緋色大口袴を着けずに腰巻姿であること、そして序の舞が完全な高位之序でないからです。専門的になりますが、高位之序特有の序之舞の掛(かかり)の最後の拍子を踏みません。たぶん「本三番目物」に遠慮して、故意に踏まないのではないでしょうか。
『井筒』は世阿弥が「直(すぐ)なる能、上花なり」と申楽談義に自賛したほどの傑作で位の高い曲です。演者側としては本三番目物でなくてもそれに匹敵するように、同等に大事に扱っていますが、一度『野宮』を経験してしまうと、その層の違いは歴然と判る、というのが正直な私の感想です。
私は『半蔀』と『東北』は青年喜多会で、以後は『野宮』『楊貴妃』と勤め、18年10月の粟谷能の会では『江口』が予定されています。?本来『井筒』は『野宮』より前に披いておくべき曲ですが、『井筒』を大事に意識し過ぎたため、演能機会を逃してしまいました。今回、粟谷能夫の配慮で「まほろば公演」で、ぽっかりと穴があいていた私の演能記録に穴埋めが出来たことを感謝しています。
能楽師は、成長に合わせ順を追って大曲を適材適所に習得していく、判っていながらも、この教えの大切さを再認識させられました。
まほろば公演で『井筒』を選曲した理由には、実はもう一つあります。
正面に置かれる一叢の薄を付けた『井筒』の作物。
この風情がまほろばの自然の中でうまく季節感とからみ、秋の名曲が秋田の田園という特殊な屋外ロケーションで演じられれば、興業的に成功するはずという、私の計算でもありました。もしかすると、もうそこまで秋が来て、あたり一面に薄が見られるかもしれないという期待感もありました。興業主や演者は演じる環境設定に気を配るべきと、その必要性を説いてきたのは先人たちです。その教えを守りたいと、今回の演出を考えました。?当日は快晴に恵まれ、といって蒸し暑くてどうしようもないという程ではなく、お客様は日差しをよけながら扇子であおいでおられましたが、時折吹く風が演じていても心地よく、野外能の気持ちよさを演者と観客が一体となって感じられたのでは、と思っています。
『井筒』と『野宮』は形式が似ているため、よく比べられます。
演者側からすると、後者は六条御息所という高貴な大人の女性の複雑な女心を演じるので、若者には到底手に負えるものではありません。前者ならば純粋さを前面に強調したらどうにか若者でも勤められるかもしれない、という可能性に縋って(すがって)のことなのでしょうか、通常は『井筒』から取り組みます。
『野宮』には能役者の人生と演能の経験を通した心と技術の二つが不可欠ですが、
『井筒』には、乱暴な言い方ですが、一通り型付通りに動き、謡うことで、少々役者の力不足があっても作品をある意味成立させてしまう不思議な力があります。『井筒』という曲は、井筒の女(有常の娘)の業平に対するひたむきな愛、堪え忍び、ひたすら待つ女の純粋な愛を、余分なものをすべて削ぎ落とし、女性の心の襞という核心部分だけで訴えるという極めてシンプルで完成度の高い作品に仕上がっています。完成度が高いからこそ、若くても、少々未熟であっても、型付通り上辺をなぞることで、どうにか出来てしまうのです。何故私が『井筒』から遠ざかってしまったのか、それはその不思議な力に頼り過ぎては演(や)りたくない、という生意気な思いが自分自身の中にあり、その思いが固く固まりになりすぎたからなのです。
繰り返しになりますが、能役者は子ども時代から順を追って能の大きさを肌で感じ、その覚悟と喜びを体験していくものです。順序は乱れないに越したことはありません。
優れた能は演者が真摯に挑めば、いつでも必ず何かを返してくれる、そう信じて今回も勤めてみると、いろいろな発見がありました。
『井筒』のあらすじは、旅僧が在原寺を訪ね、在原業平とその妻になった紀有常の娘の跡を弔っていると一人の女性が現れ、古塚に花と水を手向けます。僧の不審にこたえて女は伊勢物語の歌などを引いて、二人の恋物語を語り、遂に女は実はその女だと名乗り、井戸の陰に姿を隠します。(中入)
夜も更けて僧の仮寝の夢に、業平の形見を身につけた先刻の女が現れ、業平を偲ぶ舞を見せ、やがて寺の鐘の声に夜も明け、僧の夢も覚める、というものです。
『井筒』のシテの面は喜多流では通常「小面」ですが、今回は「宝増」を選択しました。かわいらしい女だけでは井筒の女を表現できないからです。このことについては、東京文化財研究所の高桑いづみ氏が能楽観世座のパンフレットに「生いにけらしな、老いにけるぞや」「深井が見せる井筒の世界」と興味を引く文章を載せておられましたので、一部を引用して話を進めます。
高桑氏は室町後期から江戸初期に書かれた伝書には鬘物の前シテには「深井」をかける演出が一般的であったといいます。桃山時代には下掛が「小面」をかけるようになり、それが『井筒』の「おいにけらしな、おいにけるぞや」の「おい」を「老い」とするか「生い」に当てるかに関連してくると説明しています。下掛が「生い」と表記する背景として「小面」のイメージが大きくはたらいたのだろう、と説かれ、「老い」を当てるならば、時間の喪失感など若い女では似合わないので「深井」のような面の選択となったのだといいます。?
観世流には十世大夫重成が江戸初期の面打ち師「河内」に「若女」の面を打たせるまで、若い女性の面がなかったということで、「河内」以降も観世流では「深井」にこだわりをもっていたというのです。つまり『井筒』という作品に漂う「待つ女」の錯綜した内面は若い姿では表せないと感じていただろう、と書かれています。貴重な興味がわくお話です。
故観世寿夫氏は後シテの「老いにけるぞや」の謡い方に拘りを持たれていて、そこが銕仙会の大事な教えになっているといいます。内緒にしておかなくてはいけないのかもしれませんが、いかにも大乗の拍子に合うだけのような謡では駄目で、「老い」の「お」の字の発声に演者のストレスや焦れが必要である、リズムをはずす限界ぎりぎりまでの「ため」が大事だとおっしゃっていた、と聞いています。
はじめは、おっしゃる意味が理解出来ませんでしたが、今ようやく、それが井筒の女の「待つことの焦れ」の表現だと思い至ります。待つことの精神的な辛さ、そして年を重ねるという時間の喪失感、その二重苦の時間の流れこそが、井筒の女のテーマなのです。
父は『井筒』について、「昔、この国に、住む人のありけるが」で始まる曲(クセ)は幼い男の子と女の子が隣同士で住んでいて、次第に恋が芽生え、将来を誓うというふたりのかわいい思い出話だから軽くサラリと謡うものだ、その代わり「風吹けば沖つ白波龍田山、夜半には君が一人行くらん」のサシ謡、あそこは大事だから丁寧に謡うのだ。夫婦になり、夫が高安の女のところにいくことを知りながらも、妻は道中の無事を祈って見送る。ここがなんとも言えない『井筒』の裏側の、いいところだと言います。
そうなると、やはり青二才では歯が立たない曲ということになります。
夫と愛し合った時間、苦しんだ時間、一人の女性の喜びも悲しみもすべて含み込んで
ただ静かに舞う、シンプルだが、その中に人間の一生の深さを表現する、それが能の持つ力ではないか、と寿夫氏は語られていたといいます。
話を戻して、装束について触れておきます。
今回、後シテに流儀にはない、日陰の糸を付けてみました。
初冠に赤色(浅黄や白色もあるようです)の飾りの紐を左右に4本ずつ垂らし、笄(こうがい)に心葉(しんよう、またはこころば)を飾るものです。観世流は小書が付くと、宝生流は『杜若』沢辺之舞のときに使用すると聞いています。
後シテは、腰巻姿に長絹を着て、初冠に追懸という能特有の出立ちで、これが私の大好きなスタイルです。そして日陰の糸をつけることで、より雅な業平像を表したかったのです。地方の屋外の公演ということもあり、普段出来ないことにも挑戦したいという欲ばり根性を、観客へのサービスという言葉に移し替えて、我が儘を通してしまいました。反応は、「喜多流らしくない」や「華やかで結構」と賛否両論、いろいろなご感想があって然るべきだと思っています。
長絹は本来観世流では総柄模様がお決まりで、特に業平菱模様などが好まれていたようですが、観世寿夫氏は、あえて総柄ではなく男物の大紋模様の長絹を選ばれ舞われました。女が業平の形見を付けて舞うのですから、男模様が当然といえば、当然なのですが、そこに拘りを見出し従来の手法にとらわれない観世寿夫氏の芸術性の高い意識こそ、世阿弥の再来といわれる所以なのでしょう。今では大紋が主流と変わってきたといいます。
後シテの一声「あだなりと名にこそ立てれ」は男博士(おばかせ)と呼ばれ、男の気持ちでかかって謡うのが口伝です。「かように詠みしも」からは井筒の女にもどり、官能的なものも含まれてきます。
「形見の直衣、身に触れて」は後半の名場面のひとつ。謡もむずかしいところ、囃子の手組に合わせながら、左右の袖が業平に見えてきて、身体にそっと大事にしまい込むように胸にあてます。ここは、いろいろなやり方があるところですが、伝書には「懐かしや、昔男に移り舞」とシオリをするように書かれています。しかし私は昔を懐かしんで、めそめそ泣くのではなく、夢の世界でまた業平と一緒になれる喜びと回想の舞のはじまり、これから男と女が演者の身体を通して移り舞をはじまる、そこを表現したく、正面にじわっと一足つめる型に替えました。
能ならば、能だからこそ可能な手法ではないでしょうか。もっとも効果のほどは自分では判りませんので、ご覧になられた方に善し悪しをご判断いただきたいと思います。
また、後シテの扮装で太刀を佩く時と、佩かない時があり、太刀を佩くと一段と業平の形見のイメージが膨らみます。小書「段之序」が付くと太刀を佩くのが決まりです。今回小書ではありませんが、太刀を佩いてみたいと申し出たら、能夫が終盤のクライマックスの「業平の面影」と井戸をのぞき込む大事な型のときに、「太刀が井戸にあたるよ」と忠告してくれました。ここは見栄えより演技重視、太刀の着用は見送りました。
太刀には二番目物などの源平用の反りがある太刀と、業平や西王母など公家や仙女などの佩く装飾品に近い真之太刀があります。
最近喜多流では、『井筒』『杜若』『西王母』など飾太刀として使用する場合、真之太刀をそのまま使いますが、反りのある普通の源平武士用の太刀で代用する場合は柄の部分に鬘帯を付けてきました。これは装飾の意味で巻き付けていると認識していましたが、どうも誤解のようでした。真之太刀を使用するときは鬘帯を付ける必要がない、というのは誤りで、「禁中では、太刀が抜けないようにわざと紐で留めている、その意味での鬘帯の使用です」と観世流の方から教わりました。
これは勉強になりました。
能の最後には通常シテや脇留では脇が留拍子を踏み終曲します。
この留拍子を踏む方がいいか、踏まないで済ますか、とシテ方とワキ方が意見を交わしているのを拝聴したことがあります。
シテ方は、なにもなく静かに余韻を残して終わらせたいので、敢えて終わったという動作はしたくないから踏まない、しかし脇方は留拍子があるからこそ、旅僧の夢がさめるのであって、「私の夢を覚ましてくれなきゃ」と、踏むことを重視されます。
『井筒』の最後は芭蕉葉がばっと音を立てるように、旅僧の夢は破られ、夜明けと共に井筒の女の姿は消えていきます。
留拍子一つでも、踏むと式楽的な終曲処理となり、踏まなければ演劇的な舞台効果をねらったものになる、と思われますが、話の最後に「どちらでもいいじゃないの、要するにうまくやればいいの」と父の一言。まさに芭蕉葉が落ちるように、この言葉を聞きました。当日は、あの言葉が頭をよぎり、踏んで終曲してみました。
『井筒』は男の能役者が紀有常の娘という女に扮し、その女が業平の形見、初冠や男長絹を着け業平になろうとする、男装した井筒の女は井戸の中にその面影を見て永遠の一瞬を悟る。男の役者が女に扮し、そんな女の哀れを男の肉体の動きで表現する、このような作り方をしているのが能です。その典型が『井筒』だと演じて確信出来ました。
『井筒』を演じるにあたって幽玄、この言葉が気になりました。
幽玄とは、男が女になること、つまり女が表現出来ないことを表現すること。上品で清楚でしかも色気のある立ち居、振る舞いを言う、と私は教えられてきました。
能の成立過程や骨格、真髄というものを最優先すれば、自然と女流能楽師という存在には限界があり、存在そのものに問題があるように思えます。今、女流能楽師と言われている方には、男の能楽師よりその技術や精神において遙かに越えている方もいらっしゃいます、その昔女性が芸能者として能を演じていた時期がないわけでもありません。しかし女能(幽玄能)を突き詰めていけば、その根幹が何であるかが、問われます。女性がそれを演じるとき、能が本来の持っているものとは異質なものになってしまうのではないでしょうか。能が成立して600年余、男の芸能として追及され育まれてきたものは何であったか。男女平等や皇室典範改正云々とは違う時限で、能という伝統芸能のあり方、能の根幹である大事な能の精神を再認識するようにと、『井筒』の女が私に訴えかけているように思えてなりませんでした。
(平成18年9月 記)
『青野守』 青をめぐる演出考投稿日:2006-03-05

『青野守』 青をめぐる演出考
粟谷 明生

近年の『青野守』はおそらく二百年ぶりの演能ではないでしょうか。
春の粟谷能の会(平成18年3月5日)で珍しい『青野守』を勤めました。
喜多流には他流にない、従来の曲名に色名を付けて演出を変えることがあります。たとえば『白是界』『白田村』『白翁』などです。『是界』には小書「白頭」がありますが、『白是界』になると位はより重くなり面や装束が変わって風格あるものになります。『田村』にも小書「祝言之翔」がありますが、『白田村』では面が「天神」となり装束も常とは変わって謡に緩急も加わり、より強さを強調した演出となります。『翁』には『白翁』があり、装束一式が白色になり、揚げ幕まで従来の幕を白色に変える演出となります。昭和29年1月9日、十四世喜多六平太氏は文化勲章受章祝賀能でこれを演能され、また、先代十五世喜多実先生が国立能楽堂舞台披きにて演能されたことが思い出されます。
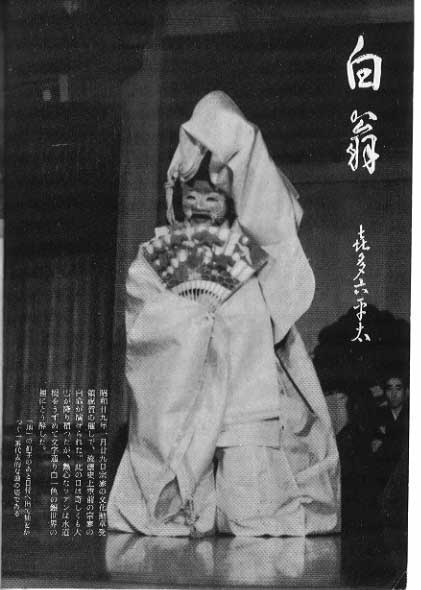
これらはいずれも詞章を変えずに、謡の位や面・装束などを変えることで曲の位を上げています。『青野守』も同様に『野守』と詞章は変わりませんが、演じる精神性が違うと、私は思っています。
『青野守』については、我が家の伝書のひとつに喜多流の中興の祖といわれる江戸後期(徳川家治時代)の九世喜多七大夫古能健忘斎の教えを十世十大夫盈親寿山が書き留めたものがあり、そこに記載されています。実は昨年(2005年)、大阪で高林白牛口二氏が二百年ぶりに『青野守』を勤められました。私がお聞きしたところでは、我が家にあるものと同じ伝書をもとに掘り起こされたようです。これで途絶えていた『青野守』が陽の目をみることができました。私も同じ伝書を持つ身として、是非一度勤めてみたいと思い、今回粟谷能の会で私なりの初の試みとなりました。
私の『野守』の演能は、披きが厳島神社御神能で次は粟谷能の会での『野守・居留』と今まで二回でした。この経験をもとに三度目ということ、新たな演出を試せる年齢や環境が整ったのではないかと思い、私的な会である場で少し自由に勤めたいと考えました。
ここにその伝書の一部をご紹介します。
「野守の後を萌黄法被、萌黄半切にて致す事在り、是を俗に青鬼などと言う人あれどもさにあらず。野守は春の能なり、尤も切には地獄の所作あれども、まったく地獄の鬼にてはなし。春日野の陽精、また春神の心なり<中略>古能公披かれ候なり、世人知るべし」とあります。
後シテは萌黄法被、萌黄半切にする、春の能だということ、野守の鬼は地獄の鬼ではない、春日野の陽精、春神の心であるということが、私のイメージを大きくふくらませてくれました。先人にこんな風にしゃれた演出を考えた人がいたということも大いに刺激になりました。
若いときは後シテの扮装が法被、半切を着て赤頭に唐冠を戴き面は小ベシミで、『鵜飼』の後シテと全く同じ装束、地獄道や奈落という詞章からも『鵜飼』の閻魔大王と錯覚して勤めていました。地獄や浄玻璃の鏡という言葉から閻魔王と繋がるのは無理もないことですが、詞章を読み込んでいくと、『野守』の鬼神は鬼といわれながらも人に害を与えるような、また人間の悪霊のような存在ではないことが判ります。この鬼はもっと特異な存在として描かれている、そこが世阿弥らしいのです。「怖れ給はば帰らんと、鬼神な塚に入らんとすれば」と「あなたが怖いと思うならば自分は墓に戻るよ」といかめしい顔とは反対に素直な純朴な心の鬼神なのです。

では、鬼神とは何でしょうか。鬼神は「きじん」とも「きしん」とも発音して謡います。雑誌「観世・『野守をめぐって』」で京都大学教授の浜千代清氏は「きしん」の場合は超自然的な存在で神の方に重点がおかれ、「きじん」と濁ると変幻自在の鬼のほうになると説明されています。『野守』ではその両方の言い方をしているのが面白いところです。
太古の時代、人間は死ねば神か鬼になる、生前の行いがよければ神になれるが、そうでなければ鬼になるしかないという信仰があったようです。死ぬと鬼というのはいささか悲しいですが、その鬼にも救いの解釈はあります。それは「鬼もまた神なり」という解釈です。荒ぶる神であると考えれば死後にもまた光が見えるのではないでしょうか? この「鬼もまた神」という言葉でこの伝書がいっそう身近なものになりました。
私は後シテの鬼神は地霊や国つ神、また守り神ではないかと思っています。東西南北有頂天から地獄まで四方八方全宇宙を照らし映し山伏に見せる神に近い存在です。最後の「奈落の底にぞ入りにける」の詞章や閻魔に似た扮装から恐ろしい地獄の鬼を連想しがちですが、伝書にある通り陽精とか春神です。春日野に太古から住んでいた土着民族の魂や霊が守り神に変化したのだと考えられます。先住の土着の魂や霊神は体制側の天つ神に押しやられ、徐々に引き退きながら地下深く隠れるしかなかったのです。ベシミの形相となり反抗を余儀なくされながらもけっして戦いを挑まない無言の抵抗者です。口をむすんで「もう何も語らない」とストレスに満ちた憤怒の形相で征服者を睨んでいる、そのストレスを同じ境遇にある芸能者が演じる、それが能発生当時の真髄と言えるのではないでしょうか。
『青野守』は後シテを地獄の鬼というより春神や陽精という位に一段上げた演出で、いみじくも太古の時代の現世に生きる者以外は鬼か神かになるという信仰と、伝書にある「陽精や春神の心」とがうまく一致しているように思えてなりません。ご覧いただく方にも、この一段位の上がった演出を観ていただきたいと思いました。
装束については、後シテは伝書にある通り法被・半切を萌黄色にしました。着付けの厚板の色の指定がないので、厚板を萌黄色にして裳着胴(モギドウ)姿というのも一案としてあがりましたが、やはり法被・半切萌黄色の記載にこだわり、法被を肩上げして萌黄色厚板に萌黄半切という三つの配色のバランスを考えて総萌黄としました。草萌える春の能のイメージ、『青野守』の青のゆえんでもあります。
頭(かしら)は何も戴かずに白頭にして、面は従来の小ベシミを大ベシミ型の「黒ベシミ」にしました。『大江山』や『紅葉狩』、『土蜘蛛』のようなショー的な鬼退治の話ではないので、神のような、スケールも大きい鬼のイメージでアニミズムの雰囲気を醸し出せればと考えました。
ではここからは舞台進行を追いながら今回の演出を記載したいと思います。
最初にワキの出羽国、羽黒山の山伏が登場します。この山伏は修行を積んだ立派な修験者で、だからこそ、野守の鬼神はその法味にひかれて出てくるのです。山伏がこの曲の軸を担っていると思います。そこで今回はどうしてもと、宝生閑先生にご出演依頼しました。一日の番組を考えると『柏崎』と『青野守』という二番能であれば、普通は『柏崎』を宝生先生が勤められ『青野守』は同年代の森常好氏があたるのが順当です。しかし敢えて『青野守』という新しい試みに大ベテランのご助力をいただきたいと思い、我儘をお聞きいただきました。この能はワキの占める位置がいかに重要かはご覧になられた方ならお解りいただけると思います。この山伏が一曲の進行役の存在で前・後場通してシテに大きく関連している役なのです。
『青野守』の前場は通常とほとんど変わりません。他流には小書が付くと前シテ(野守の老人)の一声(いっせい)の後の、下歌(さげうた)、上歌(あげうた)を省く演出もありますが、私は「昔、仲麿が我が日の本を思いやり~~」の上歌が好きで省きたくありません。以前、宝生先生に「仲麿なんていってもピンとこないだろう?」と言われたことを思い出します。確かに当時は「誰ですか? 人麻呂? 仲麿?」とお恥ずかしい返事をしたことを覚えています。二年前、北京と西安の中国旅行をした折、西安の公園で阿部仲麻呂の記念碑を見つけ描きこまれた詩を読んだとき、遣唐使として中国の地を踏み悲願の日本帰国が出来なかった史実を知ると、「我が日の本を思いやり、天の原ふりさけみると詠めけん、三笠山の山陰の月かも」の謡がなんとなく身体の中にすっと入り込んでくるのです。
その後、前シテとワキの問答が始まり、野守の鏡に二つのいわれがあることや敏鷹(はしたか)の伝説が語られます。シテの語りの最後、「狩人ばっと寄りて」で、老人がすっと立ち正面先に出て水底を覗く型がありますが、ここの動きが老人ということをすっかり忘れて若さあふれる荒い動きとなると、以前注意された箇所です。近頃少し老人の動きとしての瞬発力とは何であるかが判ったように思えるのですが、果たして今回はそのように出来たのかはいささか自信がないところです。
この後の同音は「あるよと見えし」の強吟から「さてこそ敏鷹の」と和吟に変わる構成ですが、これは『鵺』『八島』にも共通していて、これが世阿弥の作風と聞いています。
続く同音では「敏鷹の野守の鏡得てしがな思い思わずよそながら見む」と新古今集の歌を取り上げ、帝を賛美しながら老人は老いの思い出の世語りに落涙します。このあたりは体制側へのお世辞のようで、演じていてしっくりこない部分でした。しかしこの場面だけでなく「ありがたや慈悲萬行の春の花」と春日野を賛え、決して帝の賛美を忘れない曲の構成は、世阿弥の芸能者としての置かれた立場が伺えるところです。
この話が終わると、山伏は「野守の鏡」を見たいと所望します。鬼の持つ鏡で、見れば恐ろしいことになるから、池の水鏡を見ろと言い捨てて、老人は姿を消し中入りとなります。
この場面、伝書に「中入り前に杖を捨てる型あり」とあり、私も今回試みました。杖を捨てることで老人の姿がすっと消え失せてしまう、そして杖だけが不思議に残る、という場面効果を狙ったもので、後シテへの期待感をもたせるいい型だと思います。
山伏は里人(アイ)に池の謂れを聞き、奇特を喜び塚に向かい祈りをあげます。すると塚から大地に響く歓喜の声があがり、鏡を持つ鬼神が塚の中から現れます。
通常の『野守』では引き回しを下ろさずにシテは後ろから出て塚の横に鏡を持って現われます。歴史資料を調べると江戸中期までは喜多流も他流も引き回しを下ろしていたようですが、後期になり下ろさぬ方がよいということになったようです。私の持っている伝書にも「下ろさぬが吉」と書かれています。しかし今回敢えて下ろす試みをしたのは、引き回しを下ろし鬼神が作り物の中から現われた方が土や守り神のイメージが塚と一体となって見えるのではないだろうかと思ったからです。下ろさずに横から現われる場合、小ベシミならどことなく愛嬌のある顔のため似合いますが、大ベシミのスケールの大きい形相では不似合ではと判断しました。
演者は面や装束を作品の主張を主体に考慮し選択すべきです。たとえ伝書に損だ大損だと記載されていたとしても、そこに工夫を凝らしよい効果を上げることが最優先されなくてはいけないと思います。それが伝書や謡本を深く読み込むことだと思っています。

ただ、この塚の中にいる演出にはひとつ問題があり、文献資料にも先人たちの苦労が書かれています。「怖れたまわば帰らんと、鬼神は塚に入らんとすれば」のシテの詞章は、常の塚からいったん出ている場合は、この言葉で戻る型となり問題ありませんが、この謡の中で塚にいること自体が道理に合わなくなるからです。この「塚に入らんとすれば」をどのように処理するかが苦心のところでした。昨年、高林白牛口二氏はワキの「怖ろしやうちひ耀く」の言葉の内に一度塚から出て演じられたようですが、私は塚の中にいて床几から降り下に居る型でこの問題を解決したいと考えました。
後場の象徴となる鏡については、本来喜多流では小さい鏡でその縁を持つ手法ですが、これでは面とのバランスがとれない、鏡もまたそれに似合ったスケールの大きさがなければいけないと考え、観世銕之丞家の特大の鏡を見本にさせていただき、今回新たに作りました。そのため今まで習得してきた所作では適わないところもあり、鏡を扱う所作の見直しという新たな稽古も加わりました。
鬼神が現われると山伏はひたすら祈り数珠を揉みます。もちろん鬼を退散させるためではなく、もっともっと見せてほしいと祈るわけですから、鬼神はそれに応え、祈られれば祈られるほど得意になり鏡を四方に照らし映し見せます。
私は鏡というものがものを映すだけではない、サーチライト、烽火のイメージで照らす意味合いもあると思って演じています。天地東南西北の四方全宇宙を映しだすと同時に照らし出すエネルギーも必要だと思うのです。
一般に位が重くなると、どうしても鈍重になりがちです。『白是界』のように「ベシミ悪尉」ならば納得出来ますが、今回は大ベシミです。鈍重過ぎては効果が半減してしまいます。そこで要所要所に起伏がほしいと思い、太鼓の観世元伯氏には「一金伽羅二制多迦…」から替え手を打っていただくために、「暇を得ず」の謡に緩急をつけ、強く締めて謡ってもらうように地謡にお願いしました。
最後に鏡を、観世流や宝生流が奈落まで持ち帰るのに対して喜多流はワキに手渡します。大事な神聖視された鏡を山伏に手渡すことの是非はあるでしょうが、演者としては最後の居留の型へのことを考えると手渡すことは都合がいいのです。前回の小書「居留」では中啓を持ちながら組み落としをしましたが、どうも中啓が似合わないのです。両手を大きく広げ半切袴の裾を持ち上げ飛び上がり安座して地下深く消える、この型には何も持たないほうが力感が出ていいのです。ならば思い切ってはじめから中啓を持たないで演じてみよう、とこれはかなりの冒険でありました。

この曲は「奈落の底にぞ入りにける」で終曲します。この「奈落」が気になります。この言葉がシテの存在を閻魔系統に錯覚させる元凶でもあるからです。奈落と謡うのは体制側に対する演者たち、いわゆる芸能者の立場の者のへりくだりだと私は思っています。所詮、役者分際は地獄に行きますとへつらっていると考えればどうでしょうか? 本当は土中とか地下とか水底という方がいいと思うのですが・・・。私は作品が訴えてくる深層部分に鬼の立場という逆側からのへりくだった描写があるところに、何か風刺的な面白さを感じます。
今回の新工夫した『青野守』は、『野守』という曲を深く掘り下げて研究することの材料となりました。能は調べればそれだけの答えが返って来ます。先輩や仲間に問いかけ尋ねると皆さん真摯に答えて下さいました。ここに感謝申し上げます。
春を間近にした穏やかな一日、萌えいずる草木、土の味わいを醸し出す青色の野守、これまでの『野守』の鬼とはひと味違う春の神をご覧いただけたでしょうか。私自身は春風に乗るような楽しい舞台でした。能楽師として、再考、再演出できた喜びを味わっています。
しかし『青野守』は一回の演能では完成度は高まりません。私も再演に再演を重ね、また他の能楽師の方にも演じていただき私では不足していたところを補っていただいて、そのことでより完成度の高い『青野守』が出来上がればよいと願っています。
(平成18年3月 記)
(喜多流宗家についての但し書き)
・九代喜多七太夫古能健忘斎・・・八代目十太夫親能の養子であったが、実は七代目部屋住み長義の子。
・十代目十太夫寿山盈親・・・九代目の養子だが実は八代目十太夫親能の嫡子。
写真撮影
『白翁』・『青野守』前 あびこ喜久三
『野守』居留 三上文規
『青野守』後1 あびこ喜久三
『青野守』後2 吉越 研
『木賊』について 親子の愛情と反発投稿日:2005-12-22

『木賊』について -親子の愛情と反発-
17年最後の締めくくりとして、粟谷能の会・研究公演(平成17年12月22日)にて、友枝昭世氏に『木賊』を舞っていただき私たち(地頭・粟谷能夫、副地頭粟谷明生、中村邦生、長島 茂、狩野了一、金子敬一郎、内田成信、粟谷充雄)は地謡を勤めました。普通はこのような大曲、殊に『木賊』のような老いをテーマにしたものは熟年の経験者、今ならさしずめ父菊生が地頭を勤めるのが当然ですが、能夫と私は地謡の重要性を責任ある立場で挑みたいと思い、研究公演を4年ぶりに再開しました。大先輩について謡うときにはありえない数回の地謡だけの稽古、その中での微細な節扱いの確認、声の張り方までの検討という作業は喜多流では珍しいものでした。
また私はこの曲を理解するために資料にも目を通すうちに、謡本の解題やその他の本の概要に書かれていることが作品の主旨と幾分違うのではと感じ、この曲を理解するには少し説明を加えたほうがいいのではないかと思いました。何か大事なものがどこかに隠れているように思えたからです。地謡に取り組む中で、私なりの読み込み・解釈が出来上がってきたのでここに個人的な見解として書き留めることにしました。
まずは老人(シテ)とその愛児(子方)松若の人物像を考えるところから始めたいと思います。
松若の父は老いた父親として登場します。従者を連れての木賊刈りの場面からも、それ相当の大家で、大地主のような、階級も上のクラスの人物だと思われます。木賊という植物は砥草(とくさ)の意で物を砥ぎ磨くのに用いられる常緑シダ植物で、今でも庭に観賞用として植えられる生命の強い草です。園原は木賊刈りの名所ですが、老人にとってのそれは生活のためではなく、気ままな暮らしの中での趣味的なものとして理解したほうがいいと思います。『鵜飼』や『烏頭』のシテのような切実な生業の労働とは異なります。
では突如消息を絶つ松若とはどのような人物であったでしょうか。
能では実際は大人であっても幼い少年を子方として採用し、おセンチな涙を誘う効果をもたらすことがあります。しかし、私は松若は資産家の跡継ぎという有望な将来を捨ててまで、あえて仏道を志すほどの人物だったと推測します。ですから、ある程度成長し自立心のある立派な息子のイメージです。父親はきっと仏門に入ることを許さないであろう、ならば無言で家を出るしかない、と覚悟を決めてしまうほど意志の強さを持った人物だと思います。一説に、松若は恋をして父親がその恋路を許さなかったので家を飛び出したのだとする、面白い説もありますが、私は恵まれた環境の中で日々送っていたがある日、一念発起して出家を志したと考える方がよいと思いますが・・・、そこは観客の皆様の自由です。
まずここがこの曲の主軸に大きく関連しているところです。老いた父はわが子が誘拐されたと主張し、子ども側からは自ら望んで出家したという、このねじれた構想が能『木賊』の根本であると理解しないとこの作品のよさはわからないのではないでしょうか。解説にある内容は「都の僧が弟子とした少年を伴って、その郷里である信濃の国、園原へ赴いたところ、たまたまトクサを刈る老人に会う。・・・・・愛児を連れ去られた父は愛慕と狂乱の舞を舞うのであった」(喜多流謡本)であり、「人に誘われて故郷信濃の国を出た松若が父に今一度会いたいと思い、都の僧に伴われて、信濃の国園原に下り、里人とともに木賊を刈る老翁に会った。・・・・・子を失った悲しさを物語り、わが子の常にもてあそんだ小歌曲舞などを謡い舞った」(『謡曲大観』佐成謙太郎著)で、あくまでも父親側からの心の動き、視点でとらえていて、松若側からの視点は隠されています。演者や観客はこの解説を元に舞台での展開を観賞することになりますが、この親子のねじれこそが重要で、それを踏まえての型と地謡が必要であると思いました。
では今回の舞台経過を振り返り書いてみます。
出家した松若は故郷信濃の国の父親の顔をもう一度見たいと思い、師である都の僧に相談します。ここにも息子の意志が働いています。師は松若を伴い郷里の伏せ屋の里に向かい到着します。そこへ木賊を肩に背負う老人と従者が現れます。シテとツレ三人が橋掛りに並び、一声で秋の園原山一帯の情景を謡い、続いて地謡が木賊を刈る風情を謡います。一曲にロンギが二度ある曲は『高砂』『弓八幡』など珍しくはありませんが、前場の前半に設定されているのは珍しいものです。このはじめのロンギの場面は卑しい身を嘆くかのような詞章もあり、このシテが身分の低い者と錯覚しがちですが、これは老人の卑下と考えるべきで、「人として心を磨かなければいけない、わが心のために心を磨く木賊を刈り取ろう」と木賊を刈る真似をする型所は前半の見どころ、聞かせどころです。この名場面を鎌で扱うときと中啓で処理する場合がありますが、今回、友枝氏は所作が難しいとされる鎌で演じられていました。
ロンギが済むと、僧は老人に「見申せば由ありげなる御事なるが其の身にも応ぜぬ業と見えて云々(わけありの姿ですが似合わぬ作業をしていますね)」と不審に問いかけます。老人は木賊がここの名草なので家裏(いえづと=おみやげ)にすると答えますが、この言葉から木賊刈りが老人の生業でないことがはっきりします。僧は老人に伏せ屋の里の箒木について問い「園原や伏せ屋に生ふる箒木のありとは見えて逢わぬ君かな」の和歌を引き出します。箒木は遠くからは見えるが近くに寄ると見えなくなる、それを実証しましょう、と老人は僧の手を引き案内します。この歌は恋の歌ですが、親子の心情にも当てはまり、この曲の根幹をなしていると思います。そして後半の曲舞、序の舞へとうまく絡む構成のうまさがひかります。
老人は旦過を立てているからと我が家へ僧を招きます。旦過とは旅僧を無償で泊めてもてなす習慣です。旦の字は元旦の旦、水平線より日が上がると僧は出発します。
僧は松若と共に泊まることになります。すると従者の一人が老人は時折おかしなことを言うかもしれないからその心積もりで相手してください、と注意を促し退場します。通常、主ツレといわれる従者は舞台にそのまま残りますが、今回は終曲場面にワキだけが残る形にしたいために退場することになりました。
このあと子方松若の重大な告白があります。師の僧にあの老人が自分の父だと告白しますが、僧のよろこびの言葉を聞きながらも、ひとまず名乗り出ることを固辞する応対をします。ここが『木賊』の最大の要、隠し味で松若と作品の主張が凝縮されているところです。
今までは、この思わせぶりな言葉の真意を無視し、能独特の演出であるとか、そうしなければメインの曲舞や老人の舞が見せられない、能ではこのようなパターンで場面展開の処理をするものだと聞かされ信じてきました。しかし今回この解釈ではあまりに不自然で説得力に欠ける、あの世阿弥であれば、きっと意図的なものがあるはずと考えました。松若ははじめ元気な親の顔さえ見られればそれでよい、名乗らなくてもいい、と思っていたのではないでしょうか。再会しても、どうにもならない後戻りできない現実があるのを充分知っていたに違いないのです。それでもせめて一度、遠くからでもいい元気な姿を見れば自分は納得出来るという気持ちがあったのではないでしょうか。
そうとは知らず老人は酒を持参し、僧をもてなします。飲酒は仏の戒めだと断る僧に老人を慰めようとする気持ちならば仏法の真清水だと思って飲め、と酒を薦める老人です。早くもなんとなく一癖ありそうな予感をあたえながら老人も飲みはじめ、酔狂の始まりとなります。わが子への追憶は曲(クセ)から序之舞へと展開します。このクセの部分の謡は普通に淡々と謡うだけでは成り立ちません。父は独特の謡い方でここを表現します。父の口癖は「おれの謡を浪花節というが、ナニワ節で結構、それが悪いか、といいたいね」そのニュアンスはわかるのですが、どのようにすれば酔狂ながらほろっとさせるクセが謡えるか、それも課題でした。演能後の宴席で「僕の浪花節?? 違うぞ、情感だよ!!」という父のフェイント的な答えに居合わせた者が思わず「あー、やられた!」と大笑い。その情感を込めて謡えたか、そこは観ていただいた方に是非お聞きしたいところです。
序の舞から酔いも思いも最高潮となり、親が物に狂うならば子供は囃すものだ、どうして今我が子はいないのかと嘆くところの大ノリ地の謡は最大の難所。このように劇的に展開する場面、酔狂の父を見続けた松若であるからこそ、ついにいたたまれなくなり自ら名乗り出てしまいます。
ここの場面を観世流のロンギの詞章が「何か包まん、これこそは、別れし御子松若よ」と僧が紹介するように謡うのに対して、喜多流や他流は「何か包まん我こそは」と松若自身が名乗る形となっています。こちらの方が説得力があり、リアリティーがあると思います。ですからここは、当然子方の心ですから軽い位で謡うことにしました。
では一体この曲は何がいいたいのでしょうか? もちろん父の子への愛の深さですが、通常の能の親子は母と幼子です。それをわざわざ男同士、それも父親を老人に設定したところに奥深い味わいが隠されています。結末に親子の再会があり祝言で終曲していますが、もちろんそこが芯ではありません。男親と子供の再会には『歌占』『弱法師』『花月』などもありますが、この『木賊』のように父親が老人となるのはこの一曲だけです。老女物に匹敵する男の老人物、しかも老人の狂いです。この曲は老人の頑な想いが主題ではないでしょうか。それを酔狂という表現方法で曲舞や序の舞へと展開するところに演者側の技の秘め事があり、大曲と言われる所以でもあります。が、今までは妙に重々しく考えるだけに落ち着いてしまっていたのではないかというのが私の素直な感想でした。
あまり若者は使わない「酔狂」という言葉。酒に酔い常軌を逸すること、また好奇心から変わった物事を好む意、と辞書にありますが、父は「酔狂なんて言葉、近頃の者にはわからんだろうなあ」といいます。この曲での酔狂とはただ酒癖が悪いというのではなく、思い込みの強さ、それを譲らない頑な心です。後半への繋ぎとなる物着も当初は僧を接待するために労働着から着替える程度の意味で肩上げした水衣の袖を下ろすだけというものでしたが、時代を経て愛児松若の愛用した装束を着て舞う形式となりました。喜多流にはこの曲専用の「おもちゃ尽くしの掛素襖」があります。父や先人たちは皆それを着用してきました。今回もその素襖を考えていましたが、寸法が大き過ぎるという問題が生じ諦めることになり、子方用の長絹の使用となりました。しかしこの曲に似合う長絹は流儀にはなかなかなく、最終的には大槻文蔵氏より拝借することとなりました。このような経緯でしたが、いくら父に現況を説明しても理解してくれず最後まで、「おもちゃ尽くしがいいのにねーー」を連呼するまさに「頑な」な有様でした。酔狂という言葉は確かにあまり実感しにくい言葉ですが、『木賊』を何度も謡ううちに不思議と馴染み理解出来るようになりました。父には悪いのですが、まさに木賊のシテと父が重なりかぶるからです。父がヒントとなり、時にはそのものずばりという存在が、この作品を理解する助けとなりました。


今回、この大曲に取り組んでくださった友枝昭世氏の『木賊』への意気込みは並々ならぬもので、シテとしての技量、品位の充実は舞台への参加者を圧倒しました。子方、地謡にも綿密な要望を出し、装束の選択や、たとえば舞い扇は子方用の中啓を使いシテ用は腰に挿すとか、緊張の緩む物着時間をうまく処理する仕方、終曲の演出など従来の詰めの甘さを払拭するような演能が出来たことは喜ばしい限りです。そしてその担い手の一員となれたことが誇りであり、よい勉強になったと感じています。
親の老いと子の成長、この自然摂理は同時進行しながらも、次第に相反し遊離するように見えます。あるとき子は自分の人生を求めて親から離れていきます。親は頑なに子供の行動を見ようせず、子を愛しながらもそれを勝手な行動として認めない。子は子で親を愛しながらも頑なに己の規範でしか物事を見ない親に反発し離れていく。現代にも通じます。所詮時間が過ぎれば、子は親の立場になり、その子は自分がしてきたことと同じようにまた行動する、その繰り返しなのですが・・・。観阿弥の作風を伝承しながらも独自の幽玄の世界を確立した世阿弥。その子、元雅は父と異なる作風を切り拓き、次男元能は出家の道を選びます。観阿弥、世阿弥、その子供たちにも同じような親子関係がありました。『木賊』の能はそんな普遍の親子関係を教えてくれているみたいです。箒木の和歌は、『木賊』の中では恋の歌ではなく、近くでは実感しない親子の心情、生き様を歌ったように私には聞こえたのです。
写真
『木賊』シテ友枝昭世 撮影 神田佳明
小結烏帽子 撮影 粟谷明生
装束 おもちゃ尽掛素襖 撮影 粟谷明生
『項羽』を演じて投稿日:2005-10-23

『項羽』を演じて
学生に中国の歴代の国名を尋ねたら、いとも簡単に童謡の「もしもし亀よ」にのせて「殷、周、秦、漢、三国、晋」とすらすらと答えはじめたのには驚いてしまいました。今回、喜多流自主公演能(平成17年10月23日)で『項羽』を勤めるにあたって、学生たちとの会話のひとこまです。
謡の世界で中国の古い話となると喜多流では『枕慈童』ではないでしょうか。魏の文帝の臣下が周の時代の穆王に仕えた七百余歳の少年の形相の慈童に出会う話です。
周の次が秦の時代で、兵馬傭で有名な秦の始皇帝の築いた秦王朝です。そして、次に漢の時代に入りますが、その前に劉邦と項羽の両雄が争う戦国の漢楚時代があります。秦末の紀元前200年ごろのことです。能『項羽』は、劉邦(後の高祖)との戦いに敗れた楚国の勇将、項羽の最期に焦点を当てています。
能では劉邦を高祖と謡いますが、劉邦の名前の方が一般には聞きなれているように思えます。やはり司馬遼太郎の著書「項羽と劉邦」の影響が大きいのかもしれません。この二人、同じ位の年齢かと思っていましたが、項羽が三十一歳で亡くなるとき、劉邦はすでに五十代であったということです。ちなみに虞氏は十代の後半でしょうか? 項羽が歳下でありながら、それまでは連戦連勝したわけですから、如何に猛将であったかが容易に想像出来ます。

この能は、烏江(うごう=揚子江上流)の野で家路につく草刈たちが川を渡ろうと船を待っているところに老人の漕ぐ船が現われるところから始まります。草刈たちはいつものようにただで乗ろうとしますが、老人が船賃を請求するので、草刈は諦めかけます。老人は船賃はいらないと乗船を勧め、やがて岸に着くと、また船賃を請求します。約束が違うと草刈は憤慨しますが、老人は草刈の持つ草花を船賃がわりに欲しいと言い、赤い花を一輪もらって、美人草の謂れを語ります。この花は項羽の愛妃虞氏を葬った塚から生えたために美人草といい、項羽は漢の高祖に七十回以上も連戦連勝したが味方の裏切りから四面楚歌となり、この烏江の戦いで自害した、実は自分は項羽の幽霊であると名乗り、あとを弔ってほしいと頼み姿を消します。草刈たちが功徳すると、草刈の夢に項羽が鉾を持ち、愛妃虞氏を伴って現れ、四面楚歌の中、虞氏の哀切な最後と項羽の奮戦模様を再現し消えていきます。

美人草は漢名「虞美人草」、ポピーの名称が一般的です。花色は紅、桃、白、絞りなどがありますが、伝書にはわざわざ赤色を使用するようにと記載されています。私は美人草から「ひなげし」、そして「芥子」につながり、アヘン、モルヒネへと禁断の世界を想像してしまいましたが、ひなげしには麻薬成分は含まれていないということで、この間違った認識は捨てることにしました。
この能は唯一、鉾を使用します。扱い方は長刀と同じですが、横から切り払う長刀と違い、鉾は槍の原形で突く型が特徴となります。

能や狂言では中国系統の曲には、装束にも工夫がなされることがあります。
例えば観世流の『三笑』『天鼓』など、狂言なら『唐人相撲』と、それぞれ似合った装束で登場します。尉髪に違いを出している流儀もあります。私は今回演じるにあたり、『八島』の義経の化身の前シテの尉と『項羽』の前シテの恰好が全く同じというのが気になり、工夫が出来ないものかと思案していました。
すると能夫が「我が家に一風変わった側次(そばつぎ=チョッキのようなもの)がある、『項羽』の前シテに似合うと思う」とアドバイスしてくれたので、今回は着付け方も工夫し着用してみました。仲間内ではなかなかの評判でしたが、観客の方がどのように思われたのかが、気になります。あれが普通だと観てくださるなら、違和感がなかったということで成功だと思うのですが・・・。

ツレの装束も本来は唐織着流しの上に側次を羽織るだけ、何も持たずに登場しますが、愛妃虞美人が『西王母』の侍女と同じスタイルというのでは、虞氏の位が表現出来ないと思い、舞衣に腰巻姿そして頭には冠をつけ鬢を垂らし、唐団扇を持たせて、より虞妃の存在を前面に出し、妃らしさを強調しようと演出してみました。面も前の舞台が『住吉詣』で小面が続きますので、あえて、虞氏は若く小面でもよいはずですが、艶を重視して宝増女を使うことにしました。

後シテの面は本来「東江(とうごう)」で、伝書に未熟なる者は使用しないようにと注意書きがあります。東江は喜多の専用面と言われていますが、その人相はお世辞にも凛々しいとはいえなく、私は嫌いなので、今回は「怪士(あやかし)」を使うことにしました。
後は舞台正面先に一畳台を置きます。これは虞氏が飛び降りるときの高楼にも、揚子江との境界にも考えられますが、この台は四方に何も立てずに置くため、何処から何処までが一畳台なのかが判らず、演者にとっては非常に危険を伴う型どころとなり、注意が必要なことが演じてみてはじめて判りました。一畳台で舞う『邯鄲』では視界に四本柱があり、目安になって結界も出来、そのため気持ち大胆に動けるように思います。正先に同じように出す『小鍛冶』も注連縄しか張られませんが、台の隅々まで動き回るわけではないのでそれほど苦ではありません。
今回『項羽』ではじめて経験して意外と一畳台での所作が怖いことが判りました。きっと二・三十代ぐらいの若さなら平気で一回転や飛び回りが出来たんでしょうが、型をするたびに内心「えーい!」と掛け声を掛けていたのは、すこし悲しい、情けない思いが込み上げてきました。面を着けて何度も稽古していれば・・・と、演じながら思いましたが後の祭りです。これからはこのようなことがないようにと反省しています。
前シテは烏江の船人となって登場しますが、これは項羽が烏江の岸に辿り着いた時、川を渡り逃げるようにと船を用意してくれた船頭に、同士を沢山殺させてしまった責任は自分にある、それをおめおめとは逃げ帰れない、ここで自決すると言って名馬騅を授け戦地に戻ってしまうことの因果関係からではないだろうかと思っています。項羽は戦いに明け暮れて31歳の生涯を閉じます。天命だからと自らに言い聞かせ自決した死骸には恩賞が掛けられていたので、呂馬童をはじめ、みな争って死骸を奪い取ったと言います。悲劇のヒーロー、項羽の生涯や性格を調べていくと、私には木曽義仲がオーバーラップしてきます。
勝者があっという間に敗者になる。しかしそれにはそれなりの理由があります。武力に優れていても、我が侭で人を信用しない性格は、強さと結集力を持つ反面、事態が急変したときには、その体制はもろく崩れていくようです。四面楚歌になる状況は、味方の裏切り、策略への注意不足などから生み出されたものです。人を信じなくなった権力者や独裁者の最後はいつの時代も変わらず惨めなものです。今現在も身の回りを見れば首肯けることが多いのではないでしょうか?
能の多くは、このような悲劇のヒーロー、ヒロインを主人公にしています。そして舞台化することでその影の部分に光を当て主人公を生き返らせる、という作者の思いを強く感じます。成功者、勝者の能『劉邦』など面白いはずがないと考えたのだと思います。それでも時の権力者から『劉邦』を主人公とする能の創作を強制されたらどうしたでしょうか……?
たぶん世阿弥なら祝言能『劉邦』を拵えて「楽」でも舞わせてお茶を濁していたのではないでしょうか……これは私の勝手な想像です。「何故こうなってしまったのか?自分が悪いわけではない」権力者の最後の言葉に数多見られます。項羽も然りです。権力者・独裁者の盲点・死角とは、本人が闇の死の世界に行かない限り、自らの死因や現世での不備を究明できないということです。世阿弥が日本だけではなく異国人の猛将も書けたのは、芸能者の立場から主人である権力者に向かって、万国共通のテーマ「権力者の落とし穴」を訴えかけたかった、そこにメスを入れたかったからではないか…と、これも私の想像です。
(平成17年11月記)
写真
能『項羽』 シテ 粟谷明生 ツレ 粟谷浩之 撮影 安彦喜久三
装束 側次、 面 怪士 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
『松風「見留」』の恋慕と狂乱投稿日:2005-10-09

『松風』の恋慕と狂乱
第七十八回粟谷能の会(平成17年10月9日)で私は『松風』を選曲しました。『松風』は二十代から幾度となくツレを勤め、シテとしてはちょうど十年前の研究公演(平成7年)で披いて以来で、粟谷能の会での再演の必要性を感じていました。再演ということで、初演のときにはできなかったことをいかに取り組むかが課題となりました。
まず考えたのが面の選択です。喜多流は本来、シテもツレも小面を使用します。小面にもいろいろあり、皆同じお顔をしているわけではないのですが、かわいい清楚な感じの妹の村雨に対して、少し大人っぽい姉の松風を演じるにはそれなりのお顔が必要です。行平への執心を引きずる姉と、過去を悔やんで償って罰を受けている妹では、面にも違いが出てきて当然ではないでしょうか。今回、敢えて流儀の主張とは違う選択をし、姉と妹の違いを出してみたいと思いました。
実は前回の研究公演でもシテは眉の銘のある万媚(まんぴ)系、ツレは小面としましたが、その成果はあまり発揮されなかったので、今回はよりいっそう姉を浮かび上がらせたい気持ちで、宝増女を使用しました。観世流は一般的に、若女を使用するようですが、銕仙会系統では寿夫先生のお好みを継承してか、増女を使用するのが通例のように聞いています。
面が替われば、それに伴い烏帽子も替わっていいのではと思いました。かわいい小面には金風折烏帽子が子どもっぽく相性がいいですが、増女にはどうだろうか疑問です。ぴんと切立っている黒い小立烏帽子は大人を演出してくれるのではないかと思い選択しました。先代実先生は小書「戯之舞」で小面に小立烏帽子を使用されています。
再演でもう一つ考えたのが小書演出です。当初は「戯之舞」という小書で演じようと考え、資料集めも始めましたが、囃子方を勤めてくださる小鼓の大倉源次郎さんや大鼓の亀井広忠さんの「戯之舞より、見留の方が魅力的!」の助言もあって、「見留」にしました。
喜多流には「見留(みとめ)」「身留(みどめ)」と紛らわしい二つの小書があります。「見留」は破之舞の留めに橋掛りに行き、扇をカザシ松を見る型となり、「身留」は大小前にてじっくり身体を正対させ松を見て留めます。一般的なのは「見留」のほうです。
『松風』は長丁場の曲です。今回は1時間50分でしたが、シテは中入りがない、この長丁場の曲を終始、気を抜くことなく緊張を持続させ、しかも観客に飽きさせず舞台に集中させる体力も気力も必要な、まさに大曲です。
そこでこの長丁場を、シテは三つの段落に分けて演じます。
第一の段落はワキ(旅僧)の名乗りから塩屋に入るまでの汐汲みの情景描写、第二はワキとの問答から行平の形見への思いの段まで、第三は形見を纏い恋慕の思いに狂喜して中之舞、破之舞を舞い、終曲します。
三つの段落に分かれているのは、この『松風』という曲の成り立ちからもうかがえます。『松風』は亀阿弥作『汐汲』がもとになっているといわれています。亀阿弥は田楽のころ、能がまだ確立する前の人ですから、月の光に照らされて、汐を汲む女の物真似芸を、それなりの見せ場を入れて創作したのだと思います。『松風』の第一段落の最後、「汐路かなや」で留め拍子を踏むところからも、あの場面までが『汐汲』に当たり、そこで終曲していたことがわかります。
その後、観阿弥が汐汲みする二人の乙女に行平という男をのせて『松風村雨』という戯曲に作り変え、世阿弥がさらに、そこから村雨を取り除いて『松風』とし、松風に焦点を当てたものと考えられます。
ここで、『松風』の第一の段落から見ていきます。
ワキの旅僧が摂津の国須磨に来て、松風、村雨の旧跡、磯辺の松を弔い、日の暮れそうなので宿を求めることにします。
真之一声の荘重な出囃子にて二人の海女が登場しますが、ここからが旅僧の夢の世界となり、真之一声は夢への架け橋となります。その導入部分に真之一声を持ってきたのは作者観阿弥や世阿弥の思い切った手法であり、うまい工夫です。
真之一声とは一般に脇能の前シテ・ツレが登場するときの囃子ごとをいいます。脇能の神霊の登場にふさわしく、荘重で品よく、しかも力強さが特徴です。脇能以外で真之一声でシテ・ツレが登場するのは喜多流ではこの一曲、『松風』だけです。脇能の荘重さとも少し違う、重苦しい雰囲気は二人の海女の賎の業、汐汲みというきつい重労働と、苦悩の深さをよく表現しています。
脇能以外にはほとんど使われないこの真之一声を観阿弥や世阿弥がなぜここにもってきたのか、その意図を探るなかで、作者がこの曲をどう改作し造形しようとしたかが感じ取れ、後の伏線になっていることが意識されてきます。
二人の海女(シテ・ツレ)が登場すると、橋掛りで向かい合い連吟となります。離れた二人の演者が声を揃えて謡うことはもとより難儀ですが、真之一声のため、ゆっくり重々しくと、いきなり難しいところから始まります。ここは騒がしくなってはいけませんが、去勢されたような軟弱な声では駄目で、「汐汲車、わづかなる、浮世に廻る儚さよ」が観客に適切に伝わらなくてはいけないと思います。
『松風』では、この出だしだけでなく、シテ・ツレの連吟や掛け合いが多く、お互いの波長を合わせなければ、舞台は台無しになってしまいます。私はツレを多く経験してきて、『松風』のツレは特に、シテと拮抗するぐらいの力がないといけないと感じてきました。そこで、ツレの大島輝久さんには、これまで私が習い覚えたツレの心得をできる限り伝えたいと思いました。特にこの真之一声の「汐汲み車・・・」は、しっかりと芯の強い謡で、お互いの謡がビリビリと響きあうように謡おうと話しました。それがどのように聞こえたかは当日ご来場の方にお聞きしたいと思っています。囃子方の小鼓、大鼓、そして笛の一噌幸弘さんも、謡を盛り上げてくださり、よいアンサンブルができたと感謝しています。
第一の段落は、その後、須磨の景色を謡いながら次第にロンギへと進んで行きます。ロンギの最後に「月は一つ、影は二つ」とありますが、水桶を二つ汐汲車に置く時もある観世流と、一つ置くだけの喜多流では読み取り方が異なります。喜多流では空にある月が一つ、その影は車に乗せられた水桶に写るものと、もう一つは海面に写るものと解釈しています。ここを男は一人、女は二人と読み取る方もおられるようで、水桶が二つで出ていればそのように解釈できるでしょうが、喜多流の場合は素直に月の風景描写に留めているのではないかと思います。
三つに分けた第一の段落は、男と女の恋物語に入る前の静かな情景描写です。私はこの場面では、月=空高くある白く小さな寒々とした月、夜の海・潮騒=寂しく、恐ろしさを感じるほどの浪の音、海女乙女=最下層の女性、汐汲み=最下層の海女の賎の業、地獄に堕ちた二人に課せられた重労働 といったことを意識して、それらが表現できればと勤めました。しかし、それはあくまでも重苦しく、執心の罪を背負った二人の海女乙女の次からの物語をどこかで暗示させるものでなければならないと思います。
中盤は、ロンギの後、塩屋での旅僧との問答から始まります。囃子方が床机からおり、シーンと静まり返った音のない舞台で、しっとりとしたワキとの問答。第一の段落とは明らかに趣が変わり、場面の転換がなされています。
『松風』は在原行平という男が姉と妹という二人に愛を与えたために起こる話です。身分を越えた最下層の女たちが、中納言の職にある色男の伽の指名を受けた喜びと衝撃はその後の姉妹の心に重くのしかかります。身分の違いもさることながら、男一人に二人の女性、それも姉妹という複雑な関係がこの戯曲の面白さでもあると思います。待つことを諦め、執心の罪を悟っているかのような冷静さを持つ妹の村雨、周りの環境に感化されやすい情熱的な姉。恋慕のあまり追憶に浸り、まだ待とうとする姉の松風。この二人の性格の違いがこの戯曲を最後までひっぱっていきます。
塩屋に一夜の宿を乞う旅の僧に、姉から言われたとはいえ、きっぱりと断る妹の村雨。その後、旅人が出家の身であると知ると、心が変わり宿を許す姉の松風。そこには、旅の僧なら自分たちを弔ってくれるかもしれない、常に救いを求めている松風の気持ちが隠されています。
案の定、ワキの僧は「わくらはに問う人あらば・・・」と行平の歌を持ち出し、松風・村雨の旧跡を弔ってきたことを告げ、二人の涙を誘います。
そして二人は名を名乗ることになり、自分たちの境涯を嘆くクドキへと導かれていきます。
クドキの最後には、「三年が過ぎ、行平様は都に帰られた、そしてそれから少し経ってお亡くなりなったらしい。ああ恋しい」と松風は待つ女の悲しさを切々と訴えます。シテが最も力を尽さなくてはいけないところです。
史実を知ると夢がさめつまらなくなりますが、行平は実際75歳ぐらいまで生きています。能では都に帰った後まもなく亡くなったことになっていて、そうでなければ、「あーら恋しや、さるにても」の謡に続きません。死者になった行平だからこそ、同じ死者である自分がもしかしたらまた会えるかもしれないと、松風は思い、ひたすら待っているのです。執心の罪を負いながら、まだ「待つわ」「会いたいわ」と一途な松風だからこそ「あーら恋しや」と謡い、その昂ぶりが狂気とも追憶とも取れる舞へとつながるのではないでしょうか。
そして行平の形見を抱いて、恋慕の情をつのらせる松風。ここはよい型どころで、先人たちはもっとも女らしいしぐさで型を見せてきました。自分もと思うのですが、なかなか上手くいかない至難の型所です。
今回、『松風』を演じて、一番難しかったのは、この塩屋のワキとの問答から形見の長絹を抱くまでの中盤です。松風の恋慕の情の訴えかけ、物着以降の狂乱へとつなげるための大切な場面です。ここが演じ切れたか、いささか不安でもあるところです。
終段は物着の後、磯辺の松を行平と思い、近寄ろうとする松風に、村雨が「あさましや」と鋭く制止する場面から話はエスカレートしていきます。ここにも理性的な村雨と恋慕の情がまさり、物狂いとなる松風との違いがくっきりと現れます。『松風』という曲はともすると松風ばかりを考えてしまいますが、この妹役のツレは大変重く影響力がある位の高い役です。私は理性が働く村雨役を経験してこそ、姉の一途な想いが理性をも撥ね退けるほどのエネルギーに変えられるのだと思っています。しかし、言い争う姉妹も最後には同じ思いに沈んでいくようにも見え、人間の感情の面白さ、深さを感じます。
そして、「立ち別かれ」の地謡でイロエ掛の中之舞となります。形見の長絹、烏帽子を身に纏った松風は恋慕の舞を舞います。続く破之舞は『野宮』と同じ二の舞として舞われます。短いながらも主張のある舞です。ここに松風自身の思いが凝縮されていて最も大切な舞とされています。最初に検討していた小書「戯之舞」は、この中之舞と破之舞を合体させるような演出ですので、私の破之舞を際立たせたい思いとは少し違ってくるようで、今回の断念の一因でもありました。破之舞の最後、シテは袖を被いて作り物の松の周りを廻り行平との契りを表し、橋掛りにて扇をかざし、行平にも見える松を思い留めます。
舞ううちに夜が明け始め二人は何処ともなく消えて行きますが、小書「見留」では脇留(わきどめ・ワキが常座で留めて終わる)になるため、シテ・ツレは「夢も跡なく夜も明けて」までに幕に入ります。父は「故金剛右京氏のそれは風が吹くようにすーっと走り込んですばらしかった」と口癖のようにいいますが、正直国立能楽堂のあの長い橋掛りを綺麗に、短い謡の詞章の中で幕に入り込むのは至難の技です。曲が終わるまでにシテ・ツレが舞台から掻き消える演出は、いま目の前にあったものは夢・幻だったと思わせてよいのですが、やりようが問題になります。勢いよく、すたこら逃げるように見えては一曲が台なしになってしまうからです。ここは地謡も囃子も含めて再考の余地があるように思えました。
今回は小書「見留」で演じましたが、当初は「戯之舞」を考えておりました。「戯之舞」は観世流から戴いた小書ですが、その経緯が明瞭でなく、実先生の初演以来途絶えてしまっているので資料集めも難しい状況でした。私が調べた「喜多流の戯之舞」の経緯について、驚くべき発見がありましたので、ここに書きとめておきたいと思います。
先代の15世宗家喜多実先生は昭和44年4月6日の12代喜多六平太能静百年祭能を水道橋能楽堂(今の宝生能楽堂)で初演され、その際、当時の雑誌「喜多」の座談会に「戯之舞」について述べられています。ここに引用させていただきます。
実先生:「戯之舞」は元来おやじさん(14世喜多六平太)が先々代の観世清廉さんに「求塚」と交換してもらう約束していたものだ、ずいぶんこっちはわりの悪い取引だけれども、それがやはり反対があったらしいね。それで取りやめになって、去年元正さんのところに行って僕が頼んで承知してもらった。もっともそのとき「鸚鵡小町」の型付けを戴いておりますと元正さんの話だったよ、そのことは僕知らなかったよ。あっちには「鸚鵡小町」ないのだね、観世は。梅若だけにあるとかいうので、観世にはないので「鸚鵡小町」の型付をあげたらしい。左近さんのときらしいね。その話おやじさんにしたら、忘れちゃったというのだ。で、まあ「戯之舞」は随分長い間懸案になったまま中止になっていたのだ。だから今度もらって。
このように記載されています。私は今まで「戯之舞」と『求塚』の交換が成立していたと思っていましたが、事実はこのように不成立で、その代わり『鸚鵡小町』を譲っていたのは驚きでした。「戯之舞」を戴いて、『鸚鵡小町』を差し上げる不均等さは私には理解に苦しみますが、割の悪いトレードを敢えて行われたことの裏に、なにかが隠れているようにも思えて仕方がありません。しかしもう藪の中で、追求することは控えたいと思っています。粟谷能の会での『松風』を「戯之舞」にと思ったことが、思わぬ面白い発見へとつながりました。
『松風』は最初に述べたように、十年前の研究公演に続く再演でした。一度勤めると、初演のときの新鮮さ、意気込み、情熱といったものが薄れ、何となくできると錯覚してしまいがちです。安堵し危機感をなくしてしまうのは役者にとって怖るべき悪魔の誘惑だと感じました。
世阿弥は慣れを嫌っていました。いつも新鮮な気持ちで舞台に取り組まなくてはと説いています。慣れで同じ舞台を繰り返しているだけではつまらないものになるでしょう。先人、先輩方で何度再演しても、いや再演するごとに新鮮でよい舞台を創り上げている方もおられ、感心させられます。
同じ曲を何度勤めることになっても、常に新しい気持ちで、チャレンジ精神を持ってやっていきたいと改めて思いました。小書への挑戦、面への選択もしかり、粟谷能夫と「我々はさきがけ隊でありたいね」と話しています。新しく切り拓くことには障害もあり、批判もあるでしょうが、さきがけ隊として、できる環境の中で、最善の努力と最善のチャレンジをこれからもしていきたいと考えています。
今年の粟谷能の会は新太郎追善能と銘打って行いました。能夫の『実盛』も私の『松風』も思い出してみると、新太郎が大好きで何度も勤めた能でした。いまそれらを勤められる環境にあることを感謝しています。
(平成17年10月 記)
観世座の『小原御幸』投稿日:2005-07-21

観世座の『小原御幸』
法皇の重要性
粟谷明生

観世座で喜多流の『小原御幸』(シテ・友枝昭世氏)(平成17年7月21日)が公演された。観世座は観世清和氏が監修し、旧橋の会のスタッフが運営に携わっている。その観世座に喜多流が出演することに違和感を持つ方もおられるだろうが、優れた能楽師ならば広い視野で多様な演能があってよいのではないだろうか。もっともはめを外しては論外だが、能そのもののあり方や美を探求しようとする前向きな姿勢に私は賛同したい。
今回の配役はシテ・友枝昭世、法皇・梅若六郎、脇・宝生閑、内侍・狩野了一、大納言・友枝雄人に地頭は粟谷菊生。お囃子方は笛・一噌仙幸、小鼓・北村治、大鼓・亀井忠雄(以上敬称略)という豪華な顔ぶれであった。出演者は異流共演とNHKの公開録画という二重のプレッシャーがあったが、さすが名うての方々でそれぞれが持ち前の芸を惜しみなく披露し、私も地謡に連なり貴重な充実感を味わうことができたことを喜んでいる。
よい舞台・引き締まった舞台とは、優れた作品と優れた役者が必須だ。能も同様、シテ一人がいくら優れていても、その周りが劣っていてはその作品はもとより、時にはシテの技量さえも落としてしまう危険がある。三役をはじめツレ・地謡までが選ばれた一流の演者でなければ良いものは成立しない。当たり前のことだが、役者が揃うということは大変なことなのである。今回は役者が揃った感で申し分ないと思っている。特に法皇に梅若六郎氏を迎えたことで、ツレや地謡にまでよい波及効果があり、適度な緊張感が生まれた。地頭の父菊生も、いつもより気負って謡っているのが前に座りながら感じられた。流儀という枠をはずし、演者同士が力を出し技を競い合う、いわゆる「立会い能」といわれるものが効を奏し、結果、能がいかにすばらしい芸能であるかを証明する一番になったと、能に携わる者として誇りを感じている。
梅若六郎氏の謡は単に美声というだけではない。存在そのもののエネルギーはもとより、芝居・劇の領域の要素を含んだ謡に説得力あり、同業者として羨ましい限りだ。判りやすく言えば、5%の声量で100%を越える力のある謡になるということ、そこが私には魅力でならない。この謡にふれると喜多流の者はもっと謡に注意をはらわなくてはと反省させられてしまう。
後白河法皇が似合う能楽師は少ない。以前中尊寺白山神社で「銕之亟の会」があり、故観世銕之亟氏が父菊生を法皇にと依頼されたが、その理由が「あんな悪いやつはいない、あの悪役をこなせるのは菊ちゃんしかいない」であった。選ばれた父は、いいものやらどうやら……と、苦笑いをしていたが、正直私はあの時の父はそれほど似合っていると思えなかった。その後、広島で能楽座があり、父がシテ、観世榮夫氏が法皇をやられたが、これは衝撃的だった。
以前、演能レポートにも書いたが、これはもう拝見していて、法皇その人が憎々しく思えてくる。強い謡で強烈な自己表現がなされ、とてもお似合だった。これを超える人はいないだろうと絶賛したが、今回の梅若六郎氏はそれに拮抗していた。ごつごつした感じとは別な、ぬるぬるとした様な、貫禄とスケールの大きさを感じさせる後白河だった。これはもう、好きか嫌いかという個人の趣向ということになるので、これ以上は書かないでおくが、いずれも9月17日の14:50からNHKでテレビ放映されるので、是非このあたりも注意してご覧いただければと思う。
能『小原御幸』(観世流は『大原御幸』)は平家物語の灌頂(かんじょう)の巻を基に詞章もそのまま取り入れられている謡の名曲である。灌頂とは本来は頭に水を灌ぐ密教の儀式であるが、中世芸能伝授の際、奥義秘伝を授けることを灌頂といって、平家琵琶の伝授から生じたものである。平家物語では最終段の女院(にょおいん・建礼門院)の鎮魂を書きこんだ最後の巻の題となっている。
『小原御幸』は謡の曲で、シテの動きはまったくないと言っていいくらい少ない。最後に重い習の語りがあり壇ノ浦の合戦の有様を謡う。地謡は前場、後場と通して、それぞれの段を謡い分けなければならず、特にロンギの段、曲の段、最後の「今ぞ知る」に続く段は難しく、それぞれ心にしみる謡いどころだ。通常、語りの後のシテの「今ぞ知る」に続く地謡の「御裳濯川の流れには、波の底にも都ありとはと」の段が頂点となるが、今回は語りの前にある「まず一門西海の波に浮き沈み」から始まる地謡の曲(クセ)の部分にピークをもっていった感がある。平家一門の都落ちから西国での戦い、地獄道の体験談を騒がしくならず、品よくシテの心に突き刺すように謡うのが地謡の使命、役割だと私は思っている。ここをうまく劇的に謡い観客に女院の人物像を強くイメージさせることが出来ると、続くシテの語りが浮き立つのだ。
当日観世座より配布されたパンフレットに「エロスと救済」と題して水原紫苑氏が、平家物語では建礼門院が自ら六道の有様を語るのに対して、能の方は法皇が問う形になっていると解説している。
平家物語を読むと、女院は文治元年5月1日京都長楽寺にて剃髪して、お布施がないため先帝の御直衣を納めている。この御直衣は今でも見ることができて、幼い安徳帝のお姿を容易に想像させてくれる。そして女院は9月に寂光院に入るが、能『正尊』のシテ・土佐坊昌俊が義経に文治元年九月と空起請文を書き留めた、まさにその時である。それから一年後の夏、女院が静かに余生を過ごしているところへ、後白河法皇は御幸し、女院自らが六道の沙汰を語ることになる。
能『小原御幸』は法皇が一方的に女院から六道の輪廻の述懐を聞く形としている。歓迎したくない者の訪問を受け入れなければならない弱者の立場の悲劇がこの能のテーマになっているのではないだろうか。法皇は「どうだったのだ? 詳しく聞かせてくれないか?」といやらしく、すでに仏道に帰依している女院の心にずかずかと入り込む。己の立場を利用し興味本位に惨劇の思い出を引きずり出そうと問いかけるところに法皇の非情さの魅力があり、逆に女院の哀れさも法皇があることにより、より鮮明に浮かび上がる仕組みになっている。だからこそ、この法皇の役が『小原御幸』という作品の出来をも左右する最も重要な役と考えられるのだ。
能はしばしば史実通りではなく、作者の工夫がなされていることがある。例えば『八島』でも戦況の進み具合が違っていたり、このシテ(女院)の語りも同様で、必ずしも史実通りではない。
語りの「そのときの有様申すにつけて恨めしや・・・・。」は、壇ノ浦の合戦で戦況が不利になったので、ひとまず筑紫に帰ろうとみんなで相談し、薩摩の方がよいという緒方の案になったのだが、緒方は寝返り、潮も急に変わり薩摩へ落ちることが出来なく・・・・と読み取れる。しかし実際、緒方三郎はもっと以前、清経が入水する前に平家を見限っていて、この詞章は史実通りではない。謡曲の詞章を鵜呑みにすると史実を誤解するという危険があるが、しかし謡曲というものは、あえて歴史通りに創作しない作者の工夫があり、それが作品を純化させている、そこに芸能の面白さがあるようだ。鎌倉幕府ご用達の吾妻鑑が平安から鎌倉へと移行する歴史資料としては現在筆頭とされているが、それでさえすべてが真実かというと疑問もある、これはもう藪の中だ。
能楽の演者は謡本に書かれている詞章を第一として、そこからいろいろなものを読み取り創造して舞台を勤める、その作業があるからこそ能楽師という仕事は面白いので、この作業なしで、無神経に謡い型付け通りに動いていれば、きっとつまらなくなって、飽きっぽい私はもうとうに職業を代えていたかもしれない。様々な参考資料、関連するものをヒントに、作品の読み込み作業を私は重視したい。となれば後白河はやはり能の世界では悪役であってほしい。御幸して女院の話を聞いて、慰安のやさしい言葉を発して帰っては劇としての面白みはなく、凄みも出ず陳腐な作品になってしまうのだ。
『小原御幸』は登場人物が多く、法皇をはじめ、ツレの阿波の内待は藤原信西の娘、大納言の局は重衡の妻であり、シテを含めこの四人は花帽子を着用する。この花帽子は頭を布で覆う出家を表現するもので、この暑い7月にこの役を勤めることは皆避けたく、苦痛そのもの、まさに炎熱地獄なのだ。今回の放映をご覧になられる時にどうかこのことを頭の隅っこに置いておいて頂きたい。特に二人のツレは長い時間座っていて、耐えに耐え作品を作り上げている、それが地謡座から痛いほど感じとれたのだ。皆の必死な勤めが良い舞台を創ったと重ねてここで言いたいのである。
能『小原御幸』は後白河法皇はもとより、これら法皇とゆかりのある人びとが揃い、それぞれの生き様がからみあうドラマ。史実とは一味違う形で作者が創り上げた傑作だ。
蛇足だが、今回、地謡で不思議な体験をした。タイムスリップして平家絵巻物語の中に入り込んで浮遊しているような妙な感覚、一瞬なのだが味わった。正直、これを書きたくて筆をとったようなものだが、暑さで頭をやられたかと言われたくないので、ここで筆を、いやキーを叩くのを止めることにする。(平成17年7月 記)
『花月』について投稿日:2005-04-16

今年の厳島神社御神能(平成17年4月16日)で『花月』を、平成3年の御神能以来14年ぶりに勤めました。今回は『花月』地謡への奉納参加者をつのり、23名という多数の参加をいただきました。前列10名、後列13名、最後に出られた3名の方が後座に座るという異例の事態となり、東京国立博物館蔵の「能狂言絵巻」を思い出すような光景となりました。

父が地頭を勤めるのに、こんなに多くては地謡が揃うかどうか心配でしたが、その不安も何のその、意外によく揃ったのには驚きました。父にどのようにすると揃うのか聞くと、低い調子で謡うと皆が自分勝手に謡い出す、すると収拾がつかなくなる、最初からかなり高めの音で謡うのだ、すると皆揃えようとしてうまくいく、と教えてくれました。

能『花月』の面は「喝喰」をかけます。「喝喰」は喝喰行者に似せて作った美青年の顔で銀杏型の毛描きが描かれているのが特徴です。今回使用した厳島神社蔵の「喝喰」はお世辞にも美青年とは言えない面で、少し失望してしまいました。神社には傑作な「喝喰」があるのですが、奉納ではなかなかそのような逸品は出てこないのが御神能の近況です。
昔は楽屋を見渡すと、どれもこれも目を見張る面や装束が並び、それらに触れていると江戸時代にタイムスリップしたような感じで、貴重な体験をしました。管理する神社側の立場では、名品や逸品は大事にお蔵から出さずに保管し、いざという時だけ使うとの配慮になるのは仕方のないことですが、役者はどんな舞台でも最高の状態を望みますから、正直今回の「喝喰」は至極残念な思いが残りました。
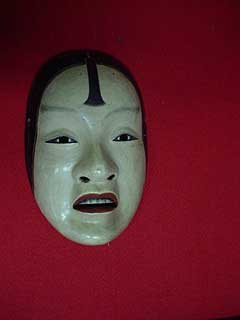
喝喰とは本来禅家で大衆読経のあと大衆に食事を大声で知らせる役僧でしたが、のちに稚児ともいわれる有髪の少年達が勤めるようになり、そして時代が経つにつれ、芸能者の徒となり堕落していったと言われています。室町時代、能の創作期頃には多分寺院に関わることよりも、もっぱら道の者となり芸尽しの芸能者レベルでの生活にひたっていたのではと推察出来ます。
喜多流の『花月』の謡本の曲趣には、「喝喰物として芸能尽しに興趣の中心がある。<中略>深刻とか悲痛とかいう内容のものではなく、一脈の洒脱味が軽快明瞭な印象を与える。少年をシテとする可憐な遊狂の一曲」とあります。
ここに書かれている通り、この曲は親子対面劇が主軸ではなく、芸能者、花月の芸尽しの曲といえます。しかし、この曲が創作された当時の時代背景を考えると、主題は別に戯曲のなかにひっそりと潜んでいるように思えるのです。それは堕落した喝喰芸能者達への改心でもあり仏道修行への功徳ではないかと思います。今、私も含めて現代人が何とも感じない終曲部分の謡の詞章に「あれなるお僧に連れ参らせて仏道の修行に出づるぞ嬉しかりける」とありますが、どうもそこにメッセージは集約されているのではと、今回演じ終えレポートをまとめながら思えるようになりました。
ではここから、『花月』の舞台進行に合わせて今回の舞台をまとめてみます。

春、桜の満開な清水寺に旅僧(ワキ)、実は花月の父左衛門は清水寺門前の者(アイ)に曲舞の上手な花月の芸を所望します。すると喝喰姿の花月は弓矢を持って登場し、自分が何故「花月」と呼ばれるかを語りはじめます。花月の「月」は四季常住のもので、真如の意味だから皆判るだろう…。では花「くわ」は何だろうか…。春ならば花、夏は瓜、秋は菓、冬は火と皆同じ「くわ」の字だから季節に合わせて使えばいいのさ…、しかし因果の果と考えれば悟りを開く最後の文字としてふさわしいだろうと、いかにも自然居士の弟子らしい一癖ありそうな説教者ぶりです。
花月は門前の者に小歌を歌おうと誘われ、仲良く小歌を歌います。観世流の詞章には「春の遊び友達と仲違いしないようにと思って、お仲間入りにやってきたよ」という言葉が入りますが、喜多流にはそれがなく小歌を謡う導入部分が唐突で説明不足の感です。小歌とは室町時代の俗謡で、ここでは男性の同性愛を歌っています。同じテーマを持つ『松虫』などに比べ『花月』はシテがアイの肩に手をかけるなど演出表現がストレートです。大蔵流の中にはシテの腰に手を廻す型もあり、こうなるとかなり露骨でシテ方としては動きにくくなるので、この型は遠慮させてもらっています。小歌は和泉、大蔵二流ともアイが扇で顔を隠し「昔から今までも絶えないものは恋というくせ者、身にはさらさら覚えもないのに、いつの間にやら恋が心に忍び入り、恋しい思いで寝られない」と謡いながら舞台を半周します。
歌通り二人は仲の良い様子を見せていますが、急に花月はよそよそしく、何かを察したのか咄嗟にアイを振り払います。この払う所作を「もうこのへんにしておこうよ」とも「誰かの目が気になる」とも解釈出来ます。アイは払われ飛ばされると、目付柱近くで一旦伏し、ふと上を見上げ、「いや! これに目がある、いやいや目ではない。目かと思えば鴬じゃ」と鴬の目と桜のつぼみの芽とを掛けていいます。つい最近、朝早く鴬のきれいな鳴き声で目を覚ましたことがあります。丁度、満開の桜、その何処かの枝に鴬は止まってしきりに鳴いているようです。どこにいるのだろうと捜す自分の姿、それがこのアイの所作に似ているのに気づき、苦笑してしまいました。

型付には動きが書かれていますが、その心持ちまでは書かれていません。役者の想像を型に注入し精神性を生み出すのだ、とは最近教えられた大事な教えだと思います。アイを放す所作一つとってもいろいろな考え方があり、それが演者の楽しみであり、能という戯曲は断定を許さない余白部分があるからこそ面白いのだと思います。ここに登場する鴬も、単に鳥類とも、また無粋な清水寺の見物人とも考えられ、面白いのです。このアイとの一連の動きを型の真似だけで終わらせては、なんとも味気ない、つまらない作品になります。特にここは狂言役者の粋な器量が重要で、能は優秀な能役者がお互い力を出し合ってこそ世界に誇れる演劇となるのだと痛感します。
アイは鴬を矢で射殺せと花月へ進言し、花月は弓は花を踏み散らす狼藉者の小鳥を射るものだ、外さず射れば中國の弓の名人養由にも劣らないと豪語し、私の好きな軽快な弓の段となります。弓を引きいざ矢を放そうとしますが、仏の戒めの殺生戒を破ることは出来ないと信仰心が表れ弓を捨てます。通常は実際に弓を捨てますが、今回はアイがシテ謡の前にかがんで弓矢を拾い上げる景色が美しくないと思い、以前友枝昭世師が考案されたように、直にアイに手渡すことにしました。アイも殺生戒を破ってはと納得し、花月に清水寺の縁起を旅僧に語り舞うように勧め、クセの舞が始まります。そして、父との再会の場となります。
花月は再会した喜びに羯鼓を打ち、山めぐりの模様を表すキリの仕舞所となります。以前はこの戯曲の主張が何であるかなど一切無視し、ひたすらシカケ・開き・サシと順番だけを追ってそれらの型をきっちりと美しくとだけ考えていたのですが、深く詞章を読み込めば、軽やかに鼻歌まじりに長閑に謡っているキリ部分が、なんと残忍な有り様の描写ではないか、と恥ずかしながら最近知ったのです。

七歳の時、筑紫彦山に登りその時に天狗にさらわれ、それからはあちこちの山々に連れて行かれ、非常に悲しい思いをしたと嘆き羯鼓を舞いますが、つづく謡の内容は陰湿で暗いものです。
まず筑紫彦山、泣きながら四王寺、それから讃岐松山、雪の降り積む白峯、伯耆の大山鬼ケ城、この名前を聞くと天狗よりも怖いと、話しの内容は拉致、拘束、稚児趣味の同性愛とみな強制されるものです。暢気に春爛漫で謡い上げる内容ではないのです。天狗とはまさに悪僧であり、山から山へと連れて行かれたとは、何人ものお相手をさせられたことで、ホモセクシャルなお稚児趣味の世界であり、花月は悪僧達の遊び道具という犠牲者なのです。父と再会出来たのだから簓(ささら)はもういらないと投げ捨て、父と仏道修業に専念しようとこの曲は終わります。
キリの内容はこのようなものですが、舞台に立つとそこまで落ち込んで演じることが私には出来ませんでした。そこが『花月』という曲の持つ特性でもあり魅力なのでしょうか。かわいい少年や熟年の方がやられたとき、素直な芸風が、鑑賞する方にはよいのだと思います。しかし反面やはり創作当時の作風・息吹を度外視してはどうだろうか、とも思い悩むところです。今回、小品でありながら根深いものを見つけてしまったようで結論が出ませんでした。
ただ、ワキが最後に少年花月を連れて帰る場面で、花月をおいてさっさと幕に入り退場しては連れて帰るという表現が充分出ないように思えました。いやいや、出家なのだから、自分の子どもを連れて帰るというのが表面に出ては恥ずかしい、あれでいいという意見もあるでしょう。しかし私はここでどうしても親子共に退場することに意味を感じたいと考えました。今回はワキに一ノ松で止まって待っていていただき、終曲してから同幕で退場したい旨を申し上げて対応して頂きました。これで親子再会、親子共に仏道修行へと向かう決意みたいなものがはっきりとし、ほのぼのとした明るさも表現出来ると思います。
『花月』という小品、初めは小馬鹿にしていましたが、小馬鹿は自分であり、作品の読み込みを蔑ろにしてはいけないと花月が教えてくれたみたいです。読み込むことで面白さが増し、表現にもふくらみが出ることを、今回もまた思い知らされました。

花月がさらわれた筑紫彦山は昔「日子山」といい、嵯峨天皇が「彦山」と改め、その後霊元法皇の院宣で「英」の字を賜り「英彦山」と称せられたといいます。英彦山神社は社殿まで長い石段がつづき、途中に花月が腰掛けて休んだといわれる石があると「謡蹟めぐり・青木実著」には記載されています。機会があれば是非一度行って、花月を偲んでみたいと思います。
(平成17年4月 記)
写真
絵巻 「能の多人数合唱」 藤田隆則著より
能『花月』 地謡の人々 撮影 牛窓正勝
喝喰面 厳島神社蔵 撮影 粟谷明生
能『花月』シテ 粟谷明生 撮影 石田 裕
『鬼界島』を演じて投稿日:2004-11-01
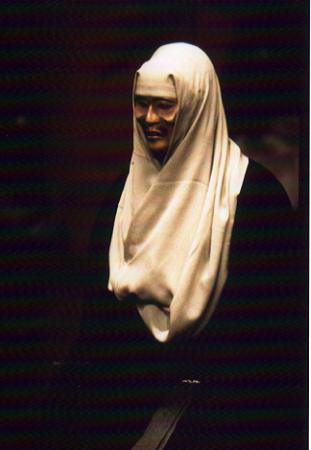
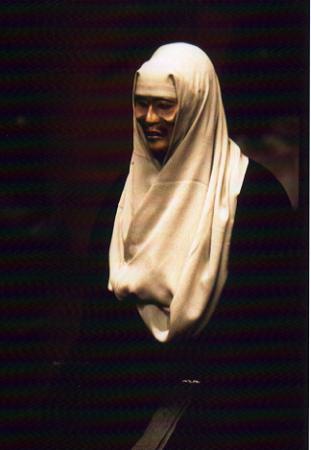
『鬼界島』という曲名は喜多流だけの呼び方で、他流は皆『俊寛』です。
我が家にある九世喜多七太夫古能(健忘斎)の伝書には『鬼界島』と『草紙洗小町』の二曲の記載がなく、『鬼界島』が正式に流儀として演じられるようになったのは明治時代以降と思われます。では喜多流の『鬼界島』の変遷はどのようになっていたのでしょうか?
最近私が入手した七太夫長義(=おさよし、七世喜多十太夫定能と八世十太夫親能との間にて八世を継承すべきところ、部屋住みにて早生した。健忘斎の父)の型付には、表紙に喜多流極伝能手附とはっきり記載され、目録には『卒都婆小町』『鸚鵡小町』『小原御幸』などと共に、『俊寛』が記載されています。記載されている他の曲目を読むと、今でも他流とは異なる喜多流独自の形式が書かれているので、『俊寛』という曲名の記載だけで喜多流の伝書ではないと判断し、伝書自体を否定することは出来ません。『俊寛』の項に記載されている内容そのものは、現在の観世流にかなり近い演出となっているので、これが、どのような経緯で現代の形に変遷したかは、はっきりしません。ただ江戸期の資料がないと思っていたものが、実は『俊寛』という曲名で存在していたことを発見出来て、今回『鬼界島』を演じるにあたって(平成16年11月28日 喜多会)、曲目の歴史・変遷から次第に喜多家の歴史へと興味は大きく膨らみ、演能のよい手がかりとなりました。
現在演じられている型附は、十四世喜多六平太先生の創案だと思われます。
曲名が『俊寛』から『鬼界島』へと変更されていますが、若年の十四世喜多六平太が一人で再興したかは、いささか疑問です。これは推察ですが、当時の後見人の梅津家や紀家などの人たちと相談して、流儀独自の構成を創案したのではないでしょうか。曲名の違いからはじまる他流との相異点は数々あります。まず主ツレは他流は康頼ですが、喜多流は成経が主ツレとなり、成経が赦免状をもらい読みます。そのためツレを勤める順序も先ず若輩者が康頼を勤め、その経験を経て成経を勤めることができるという修業過程です。私は今まで『鬼界島』のツレを15回勤めましたが、その内訳は7回が康頼、8回が成経でした。伯父の新太郎や父がこの曲が好きで十八番であったためか、15回のうち10回までがこの二人のどちらかがシテでした。
次なる大きな相違点はシテの登場がアシラ匕出となることです。他流にある「後の世をー」の一声は省かれて、橋掛の一ノ松に出て「玉兎昼眠る雲母の地ーー」と謡います。このため一つの問題が浮上してきました。大鼓と小鼓は、アシラ匕出しの後のシテ謡には、道具を置き囃さないのが決まりです。例えば『湯谷』『巴』『砧』『半蔀』など皆そうです。しかし『鬼界島』はお囃子方の手附に「続けて囃す(アシラ匕)」と伝えられているのです。これは、明治の復曲の時に、三役と詳細な相談がされていなかったため、他流での一声から地謡、そしてサシ謡としての「玉兎昼眠るー」と定型パターンをそのまま導入したためです。アシラ匕出しでのシテ謡は静かに囃さずに謡うところに良さがあります。今回はお役の亀井忠雄氏、亀井俊一氏にお願いし了承して頂き、囃さない演出としました。
さて俊寛を演じる時その人物像は諸流同一ではないようです。喜多流の俊寛像は片意地はって人に従わず反逆精神を失っていない孤高の人物として描かれています。私は今まで俊寛は齡を経た人だと思っていましたが、史実は36歳という若さであったことを知り驚きました。能では、なかなか若輩の者には演能が許されないためか、どうしてもそれまで勤めてこられた諸先輩の方々の俊寛像が重なりあって、勝手に老漢と思っていました。実際、能の世界では実際の年齢よりも、少し老いた感じとして扱っていますが、37歳という若さで有王という弟子に看取られ、島で一人で亡くなっている、なんとも悲しい結末です。
『鬼界島』のシテの面は「俊寛」という専用面です。表情は流儀により様々ですが、我が家の面は、細面で彫りが深く独特の表情で、父はアラブ人の顔に見えると言います。確かに面だけを見るとそのように見えますが、花帽子をつけるとまるで表情が違って見えるから不思議です。
今回、『鬼界島』を演じるにあたり、平家物語や源平盛衰記の資料などを見て、意外な事実が発見出来て、演じるにあたり興味がますます湧いてきました。
まずことの発端は内大臣と左近衛大将を兼ねていた藤原師長(左大臣頼長の第二子)が左大将を辞任することから始まります。この師長という人物は能『絃上』のシテツレとして登場する琵琶の名手で妙音院の大臣といわれていましたが、太政大臣になるにあたり左大将の任を辞すことになります。そのため後任をめぐるポスト争いで野望を持つ三人の権力争いとなります。
本来、後任の最有力は徳大寺大納言実定でありました。この人物は一昨年、私の手がけた新作能『月見』の主人公で、徳大寺がこれに大きく関与していたことも驚きでした。そのほか花山院中納言兼雅や新大納言藤原成親もその地位を狙うという三者三つ巴の権力争いになるはずでした。しかし結果は意外、右近衛大将だった小松殿重盛が左近衛大将に昇格し、右近衛大将には次男の中納言でしかない宗盛が昇格するという大抜擢で、三人の野望は断たれます。この平家の横暴に反感を抱く者が次第に増え、成親、西光等の平家討伐を目論む者は団結して密議の回数を重ねていきます。そこにはあのしたたかな後白河法皇も参加するようになり、後白河法皇の近習の俊寛僧都(そうず)も自らの鹿の谷の山荘を提供し「鹿の谷の詮議」となります。
現在の「鹿が谷(ししがたに)」は昔、「鹿の谷(ししのたに)」といわれています。古く四つ足はみな「しし」と言い、いのしし、かのしし。鹿(しか)も、しし、と発音していたので「しかのたに」ではなく「ししのたに」と呼びます。(資料 「鹿の谷事件」 梶原正昭著 より)
ここでは蛇足ですが、徳大寺については後の記述があります。徳大寺実定は一旦落胆しますが、家臣の勧めで直ぐに平家ゆかりの厳島神社に参詣し、後に清盛の推薦を得て、小松殿重盛が左大将を辞任した後に宗盛を越してちゃっかり左大将になっています。
平家打倒を詮議するために集まった者は、後白河法皇、浄憲法印、西光法師、藤原成親、平判官康頼、多田行綱、それに北面の武士など、そして山荘を提供した俊寛僧都です。俊寛僧都は今は焼失してしまった法勝寺の執行で、僧都とは僧正の一つ下の位です。この俊寛という人は平家物語では元来信心深くなく、傲慢な性格で策士のように語られています。密議は、恐れをなした多田行綱の密告で発覚し、直ちに西光や成親は捕らえられ殺害されていきます。康頼と俊寛、そして成親の子息成経は薩摩潟の沖、鬼界島に死一等の流罪となります。源平盛衰記でははじめ三人はばらばらに小島に流されたようですが、しばらくして硫黄島に三人一緒になったとあります。
能『鬼界島』はそれから一年後、清盛の娘、建礼門院徳子の安産祈願のための非常の大赦が行われ、鬼界島の流人も赦免されるというワキ(平家物語に「丹左衛門尉基康という者なり」とある)の名乗りの言葉からはじまります。
ワキの名乗りのあと、舞台は鬼界島と変わります。薩摩の沖にある鬼界島とは、現在のどの島かは諸説あります。ツレの次第で「神を硫黄(斎う)が島なれば」と謡うところから硫黄島が有力説と考えられますが、鬼界島という名称の島も存在します。どこであろうと絶海の孤島にはかわりがなく、硫黄島の場合はとくに空から降る火山の噴煙が硫黄のため田畑が出来ない状況で、その生活の悲惨さは目に浮かびます。流人となった三人は、きっと島民の濃く毛が密生した焼けた肌色や訛りのある言葉、少数の島民しかいない非常に不便なところに地獄を見たのではないでしょうか。彼らはそこで一年を過ごすことになります。
ツレ二人(成経、康頼)は鬼界島に三熊野九十九所を勧請して信仰に余念がありません。上歌(あげうた)に「真砂をとりて散米に」と神に祈ることを忘れませんが、それに比べ俊寛は元来の信仰心のなさから全く信仰を捨てたかのように振るまい、この対比が悲劇の結末を暗示するように場面設定されています。三人が流罪になってから赦免されるまでは、およそ一年の月日となりますが、ではその一年間をどのように過ごしていたのかが気になりました。
諸説あり、三人だけしか流されていない、いや少しの供の者はいたであろうとも、また三人は同居していた、いや各々別々に生活していたと様々です。能の描き方では、やはり三人だけが流され、成経と康頼は信仰心もあり近くに居住していて、俊寛はひとり気ままな性格のためか、別のところに勝手に自分の住み処を持っていたのではないかと思われます。生活の実態は、成経と康頼へは都から手紙や食料物資が届けられていました。それは門脇宰相教盛の娘が成経の妻である親族関係であったためです。しかし俊寛には家族からの手紙も物資も送られてこなかったようで、そこにも俊寛の悲しみと怒りがあったように思えるのです。赦免される成経の帰国は俊寛にとっては今後の食料物資の停止を意味し、田畑が出来ない土地に残された者には、それは完全に生きる望みを断たれたのも同然で、悲劇性は計り知れません。

今回の演能では喜多流では久しぶりに纜(ともづな)を出す演出としました。昔は纜を使用することが普通でしたが、最近は途絶えていました。纜があることで、ツレが纜を跨がなくてはいけない、クセの後半俊寛が赦免状を投げ捨てる大事な場面でアイが纜を舞台に設置しなくてはいけないなど、少々演技に差し障りがありますが、今回はアイの深田博治氏と相談して出来る限り問題が起きないようと改善策を練りました。結果舞台進行に支障なく、纜出しの演出が出来たことを喜んでいます。
能を習得するには、まずは基本形を経験して応用編に移る仕組みが正統です。であるならば、纜を使っての演技を踏まえた上で、使用しない型を駆使する段階へと進むことが大事だと感じました。マイナス面があるからと、初めから諦めて使用しないのではなく、マイナス面を出来る限り少なくする努力をして、そして次の段階に進むやり方でいきたいと思っています。現在流儀には纜がないので、今回も日頃お世話になっている銕仙会、観世銕之丞氏にご協力いただきました。ここに御礼申し上げます。
私の『鬼界島』はこれで二度目です。『鬼界島』は現在物で、劇的で舞踏的要素を全く持たない能です。舞の基本となる「シカケ」「開き」という型、定型の動きが一つもありません。能全曲の中で、もっとも演劇性が要求され、能楽師が、役者としての技量を試される特殊な能です。ともすると作品自体の劇的要素に頼りがちになり、その上に胡座をかいてしまいがちですが、それでは薄っぺらな芸にしか感じられず、到底この作品を表現したとはいえません。俊寛の拗ねた態度や一時の歓喜、そして忿怒と無念、絶望へとそれぞれの移り行く場面でいかに表現出来るかです。芝居ぎりぎりの演技を、生(なま)にならず、能の世界で許される範囲で踏みとどまり、どのように演じるか、『安宅』や『望月』同様、演者自身の演じる張りや役にどれだけ入れるかにかかっています。
『鬼界島』は明治時代の復曲のころの事情からか、型付等の伝書がなく、流儀本来の決まりがないというのは悲しくもありますが、反面演じる自由さもあるため、役者自身を試される、やり甲斐のある曲目だと思います。今回はまだまだ力不足を感じ反省していますが、纜での演技が出来たことが、よい経験となりました。次回へのステップとしたいと思っています。
この曲は『隅田川』同様全く救いがない悲劇の最高峰です。それだけに俊寛一人に焦点を絞り、俊寛そのものを演者自身がいかに手がけるかがポイントであり、それが演じるものへの限りないテーマなのかもしれません。NHKが録画した観世寿夫氏のビデオは『井筒』と『俊寛』でした。この舞踏と芝居の両極端の二曲で観世寿夫を表現しようとした、当時の担当ディレクターの意図と意気込みが、不思議にビデオを通して伝わってきました。その一つの極に挑めたことは幸せであり、一方で、人間の悲劇を徹底的に描いてきた能という芸能の抜き差しならぬ凄さに、身が引きしまる思いがしました。
(平成16年11月 記)
明治に発行された謡本『鬼界島』
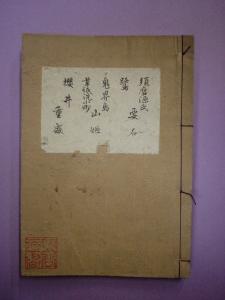
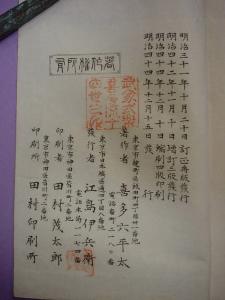
厳島神社にある卒都婆石、康頼が鬼界島から流した卒都婆はここに流れついたと言われている。

康頼燈篭

俊寛僧都山荘はこれから急坂を登ります。

俊寛僧都山荘跡

京都東山双林寺にある康頼の墓(右)。(左)噸阿法師(中)西行の墓。

面「俊寛」粟谷家蔵
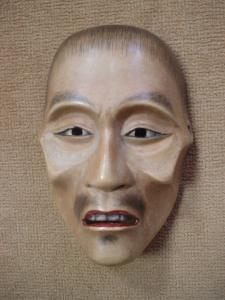
以上、撮影 粟谷明生
トップの写真 シテ 粟谷明生 撮影 東條睦
纜の演出 シテ 粟谷明生 ワキ 宝生欣哉 撮影 石田 裕
『砧』について 研究公演の新工夫の成果を再演投稿日:2004-10-10
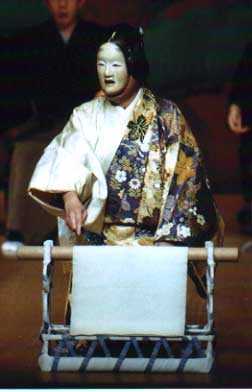

第76回の粟谷能の会(平成16年10月10日、国立能楽堂)にて『砧』を勤めました。
『砧』は6年前(平成10年2月)父の代演(練馬文化ホール能)が初演となり、その後、粟谷能の会研究公演(平成11年11月、シテ・粟谷能夫・ツレ粟谷明生)にて現行の演出の見直しを図りました。その成果に基づき、いつの日か能楽堂で再演したいと思っていましたが、今回その願いが叶いました。
最初に、演出を見直し、新工夫をした部分を簡単に説明したいと思います。
第一は、前場の初めにワキの名乗りとツレ夕霧へのことづてを入れたことです。
従来の喜多流の場合は、前場にワキが登場せず、ツレの「旅の衣の遥々と、芦屋の里に急がん」の次第で始まり、状況説明はツレの独白で済ませています。
それに対し上掛はワキが先ず名乗り、長年の在京となったが、故郷の妻の事が気になるので使いを出し、「この暮れには必ず帰る」とことづける場面があります。
夕霧も主人に「必ず」と念を押して九州芦屋に向かいます。これによって何某(主人)は無情な悪人ではなく、妻を思う心やさしい人として設定されます。
今回はツレ(内田成信氏)に観世流同様、ワキのあとについて出てもらい、常座後座に下居してワキの名乗りを聞き、呼び出され常座にてワキとの問答の形としました。ツレは何某を見送りながら、道行の謡となり、後は通常通りです。
従来の喜多流の演出では、ワキが下掛宝生流の場合、中入り後のワキの名乗りがないため、能『砧』全体を通して、どこにもワキの名乗りがない不自然なものになってしまいます。
喜多流の謡本だけを見ていると、ワキが中入り後に初めて登場し、そのときに名乗りを入れていますので問題はないのですが、能として見たときには、ワキ方や狂言方が担当する謡、語りとかみ合わないものが生じて全体のバランスが崩れ支障をきたしてしまいます。
では何故喜多流は現在の形式となったのでしょうか?
そのためにも、この作品の誕生の経緯を見ておく必要があります。
『砧』は世阿弥の晩年の作で、子息の元能に「このような能の味わいは、後の世には理解する人もいなくなってしまうだろう。そう思うとこの作品についてあれこれ書き残すのも気乗りがしない」と語っていて、元能の著、申楽談儀に記されています。
世阿弥の心配通り、その後の演能記録は音阿弥の二度の演能を限りに途絶えます。
慶長頃(戦国時代)には『蝉丸』『小原御幸』とともに、詞章のよさから座敷諷(ざしきうたい)として素謡専用曲となり、次第に能としての形体は曖昧なものになったと思われます。
そして江戸中期頃、幕府から各流に演能可能曲の申出が命ぜられました。
上掛の観世流、宝生流はその時に200何番かの中に『砧』を入れ復興し、次いで下掛の喜多流、金剛流も申し出ています。
金春流は『砧』の届け出をしなかったため、復帰は昭和も戦後になってからと、桜間金記氏は説明されます。
今日の喜多流の台本と演出が出来たのは、斬新な合理的演出を考案し他流と大差をつけ一線を引く、新流としての独自性を築きたいためだったかもしれません。
しかしこの合理主義の演出では、座敷諷ならまだよいとしても、能としてワキ方や狂言方と一緒に創り上げていくうえでは、矛盾に満ちたものにならざるを得なかったでしょう。
そして観客のみならず演者までも、この物語を誤解してしまう危険があります。
つまり、ワキの名乗りと状況説明がなくて一曲が始まると、どうしてもシテと夕霧という主従、都と鄙(ひな)、年増と若い侍女と二人の間のことのみに話が集中しすぎ、主人の「本当は帰りたいのだが、帰れない」という状況設定が希薄になってしまいます。
武智鉄二氏が「喜多流にある一種の合理主義は能楽の本質的リアリズムとは無関係だ」と言われたそうですが、現場にいる者として反論の余地はないと、痛感しています。
実際、喜多流の謡曲本を見ている喜多流愛好家は、どうしても中年女の若い夕霧に対する嫉妬が主題だと思い込み、同じ女の嫉妬を扱う『鉄輪』や『葵上』のような露骨で単純な復讐劇と誤解し、この曲の本質を見逃しがちです。
現に私が『砧』をお教えしたお弟子様のほとんどが、対夕霧の嫉妬復讐劇ですねと答えられていることからも、このことは実証されています。
演出の見直しの第2点は、シテと夕霧が砧を打つ砧の段「・・・・・ほろほろ、はらはらはらと 何れ砧の音やらん」の後、「いかに申し候」に続いて「只今都より御使い下り」を入れたことです。
従来は砧の段が終わると、間髪いれず「いかに申し候。殿はこの年の暮にも御下りあるまじく候」とツレの厳しい言葉が入ります。それでは余りに突飛すぎ、まるで夕霧が殿が今年帰らぬのを知っていて、わざと焦らして通告したように誤解を招く危険があります。
ここはワキ方、狂言方の科白にもあるように、やはりある時間の経過が必要で、また別に都から使いが来たという状況の言葉をシテ方も補わなくてはいけないと思います。
今回も研究公演同様、その状況の明確化と場面転換をはかるため、金剛流にあります、「只今都より‥‥」を付け加え、舞台進行の充実をはかりました。
妻はその知らせに、やはり夫は心変わりしたと誤解し病にかかり、絶命します。
なんとも悲しい最後です。誤解したまま空しくなるからこそ、後シテに繋がるわけですが・・・。
このように演出を見直し、台本を整える作業をしていくと、『砧』という曲は単なる復讐劇ではない、ましてやツレ夕霧への嫉妬劇でもないことが感じ取れてきます。
夫の芦屋の何某も妻のことを思い使いを出すくらいですから、善意に満ちた人です。
恨み復讐される対象ではないはずなのですが、残念ながら妻の思いとうまく噛み合わず、このずれが妻の心の恋慕、怨恨、哀傷といった様々の心模様に錯綜していきます。
その心の襞(ひだ)や屈折が作品の主題となっています。
『藤戸』の女が征服者佐々木盛綱に死を覚悟で殺意に溢れ訴える直線的なものとは意を異とします。
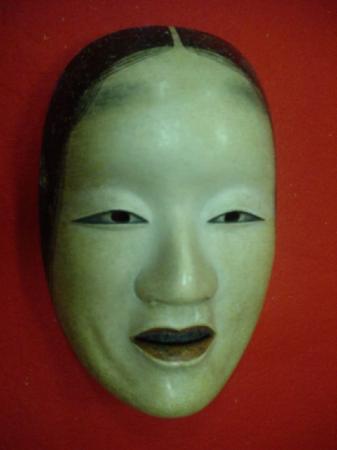
『砧』は一見ありふれた巷の出来事を素材にしながらも人間の奥深くある魂の呻きをテーマとして書かれています。故観世寿夫氏は「人の心の中の鬼、つまりー怨念ーといってもいい、人間が生きる上で苦しみ、悲しみといった、より人間的なものを鬼と据え、世阿弥自身の根源である鬼を得意とする大和申楽の規範に戻り新たに創作したのではないだろうか。それはいままで創り上げてきた『井筒』などの幽玄無上の夢幻能とは別の、自分が完成させた様式の破壊という新しい作品への凄まじいまでの創造意欲なのである」と述べられています。
私はこの文章に刺激され、作品に似合った演出が必要と思い始めました。
私の大好きな『砧』は中世という時を超越して、人間の心の弱みや恋慕の身勝手さを現代の我々にも鋭く抉るように訴えている、このことを蔑ろには出来ないと考えました。
前シテの面は通常、曲見か深井です。
伝書には小面とありますが、小面では色がありすぎ生々しくなり、孤独と不安、失意や時の喪失感などが表現しにくいです。
今回は粟谷家蔵の「若深井」を使用しました。
深井より少し若い感じの、憂いをおびた顔の面です。
装束は丁度、『砧』に合う、梶の葉模様の紅無唐織を仕立て直し使用することが出来ました。
シテはアシラ匕出で橋掛り三の松にてサシコエを謡います。
鴛鴦や魚の平目のように仲の良いものもやがて離れる宿命なのに、まして人間の情愛は当然だが、私たちのような疎遠な夫婦仲では…と、ここを冷えた切実な思いで謡えなければいけないのですが、なかなか難しく苦労するところです。
そして、シテは夕霧の訪問に、じわっと答えます。
「いかに夕霧」の一言にすべての思いが表現出来るようにと心得にある大事な謡です。
しっかりと内に込み上げてくる怒りを押さえながらも妻として年増女の強さがにじみ出なければいけません。
シテはツレの応答を待たずに、すかさず何故直ぐに連絡をしないのかと、叱りつけます。
その返答に夕霧は刺激的な言葉を返します。
「忙しくて連絡する時間がなかった、三年もの長い間都にいることになったが、それは自分の本意ではなかった」云々と。
この言葉はシテの気持ちを昂ぶらせ、人の言うことなど信頼出来ないと嘆かせます。
しかし今年には必ず帰るとの伝言に少し気持ちも晴れ、里人の砧打つ音に気がつきます。
蘇武の故事を語り自らも砧を打とうとする妻。
夕霧は賎しい者の業だが、妻の心が休まるならばと砧を拵えます。
その場所は妻の寝床と考えられます。それはかつて夫と共に過ごした場所でもあるのです。

前場はこのシテと夕霧との緊張感の中に、月の色、風の景色、影に置く霜、夜嵐、虫の音と、秋の風情を織りまぜ、シテの揺れ動く心情を、砧の音とともに謡い上げるところがみどころです。
夕霧については愛人だったとか諸説あるようです。シテは夕霧に対して「あんたお手がついたわね」というような気持ちで謡うのだと説明する先輩もおられ、その気持ちもわからないではないですが、それではあまりに許容範囲が狭過ぎると私は思います。
夕霧は芦屋何某の召使いです。当時の召使いとしての役割が、身の回りのお世話諸々となれば、そこには性的パートナーの面も含まれていたはずです。
『砧』の台本には夕霧が本妻の怒りを買うほどのライバル的な立場としては描かれていないと思います。
シテが夕霧に焼きもちを焼いて云々という事でこの戯曲が書かれたとは到底思えません。
少しの嫉妬はあるでしょうが、それは本筋ではないでしょう。
それではあまりに現代感覚過ぎます。
夕霧は妻公認の、かえって他でいたずらをしないためのお目付け役の女だと私は思います。
でなければ夕霧が側にいるのに、都の便りで主人の心変わりと思い込んで絶望して死んでいく件の辻褄が合いません。
夕霧もまた何某と同じで決して悪人ではないと思います。
ただこの夕霧は、妻の心を刺激し行動を起こさせるような微妙な言動を発します。
それ故に、ツレの夕霧は何某同様、この物語のもう一人の火付け人、キーパーソンとして重要な立場にいるのです。
その随所に面白いように妻が反応し癇癪を起こしたりするところに演じ方の難しさが隠されています。
砧の段に入って「宮漏高く立って風北にめぐる」と朗詠する謡がありますが、これを喜多流ではツレが独吟します。
囃子方も道具を下ろし、朗々と謡う聞かせ所ですが、ツレには難所です。
残念ながら、いままでこれは!という「宮漏高く……」は聞いたことがありません。
観世寿夫氏のパリ公演での『砧』の録音テープを聞く機会がありました。
観世流はここを地謡が謡いますが、その「宮漏……」のすばらしさには感動です。
地謡方のお名前を記載させていただきます。
地頭故観世銕之亟氏、山本順之氏、浅見真州氏、長山礼三郎氏、永島忠侈氏、浅井文義氏。連吟が見事に綺麗に揃い、透明感と緊張感がある逸品です。
この曲では「砧」がシテの心のありようを象徴しているように見えます。
後の地獄の責めでも砧を打ち続けなければならない因果応報。
それだけに、砧を打つ気持ち、作業がどのようなものなのかを詳細に演者が把握し表現できないと、おざなりの『砧』になり、手に負えない曲になると思いました。
この象徴ともいうべき「砧」の作り物について、我が家の伝書には記載がありません。
十四世喜多六平太先生が賎の者の作業するものを舞台に置くなどもってのほかと言われていた時期があると聞いています。
作り物は本来無いものでしたが、近年は曲そのものの象徴であり、出した方が演じ手も観客も判りやすいということから、十四世六平太先生もお考えが変わり、出されるようになり、今は出すのが当然になりました。
はじめは後場だけ出していた時期もあったようですが、最近は前場の物着の時に正面先に出し最後まで置いたままにしています。
そういう事情から、作り物を出した時の型付というのが喜多流には正直いってありません。
作り物を出すならば、それに似合った動きが必要で、今回、過去の資料などをもとにして工夫をこらす楽しみも味わうことができました。
砧を打つ型を二度にし、最初は「今の砧の声添えて、君がそなたに吹けや風」で少しヒステリックに打ち東の空を見送ります。二度目は「交じりて落つる露涙、ほろほろはらはらはら……」と意識も朦朧と憔悴寸前の態と、打ち方に変化をつけました。
ご覧になられた方はどのように感じられたでしょう。
感想をお聞きしたいと思っています。
後場は、妻の死を聞いた夫が帰国するところから始まります。
亡き妻に今一度再会したいがために梓の弓を引き、妻が砧を打った寝床で追善供養をします。
下掛宝生流の待謡は梓弓の弦を鳴らすことで、死後の妻と逢おうと願う男の気持ちが込められています。
喜多流の謡本では「かの跡弔うぞ有り難き」とありますが、これでは話は終わってしまい不適当です。
下掛宝生流のように「梓の弓の末はずに 言葉をかわす哀れさよ 言葉をかわす哀れさよ」となれば夫の妻への愛情が充分感じ取れます。

今回は後シテの出囃子を観世流の「梓之出」に近い演出でやりました。
我が家の伝書には、「この出端、鼓アズサ打つことあり、別の習い也」とありましたので、まったく喜多流に根拠のない事ではないので、御囃子方(一噌仙幸氏、大倉源次郎氏、亀井広忠氏、金春国和氏)のご協力のもと、流儀で初めて試みてみました。
アズサの音に引かれながら、シテは三の松にて一度止まり、砧の音を探します。
徐々に高鳴る砧の音とアズサの音に耳を傾けまた歩み始め、一ノ松にて「三瀬川沈み絶えにし……」と謡い「標梅花の光を……」で再び本舞台に入る演出です。
小鼓はアズサを打ち太鼓の音に執心が込められる、よい演出だと思います。
再度練り上げることで、より効果的な演出が考えられるのではないかと思っています。
後シテの面は「痩女」、装束は白練の坪折に大口姿です。
観世流の面は泥眼で鬼のような鋭い強さを表しますが喜多流の主張は痩女で、やつれて空しくなった女をひきずって寂々とした風情です。
そのため歩みも、「切る足」という独特の足遣いがあります。
炎熱の、または針の上を歩くが如く、また体力がなく痩せているからバランスが崩れているその様を表すとも、いろいろいわれていますが、先人達のそれを拝見してきてその手法が私の想い寄せる痩女の世界とは少し違う、隔たりを感じていました。
伝統とか、そのように聞いているからというだけではすまされない、技術的な問題があるように思えます。
現代は現代に似合った「切る足」であっていいと思い、今回はあまり極端な「切る足」は敢えてしませんでした。
これについては今後、流儀内での意見調整も必要だと思いますが、能という演劇が今という時間空間の上に昔を演じるのだということを理解したうえでことが運ぶといいと思っています。
キリの仕舞はじっくりとゆっくり演じるのが当流です。
しかし最後に怒りは押さえ切れずに勢いで夫に迫ります。
「夢ともせめてなど思い知らずや怨めしや」と。我慢の限界を越え、中啓を床に打ち、左手をさし出し夫に迫ります。
そして一方で、現世にいる夫であっても、今あなたと手を結び触れたい、でもそれも出来ないのかと悲しみます。ここは地謡も囃子方も激しく謡い囃すところで、シテもただメソメソするだけではない、荒くなってはいけませんが、強さ、激しさを込めなければなりません。ここもその度合いが難しいところです。
「思い知らずや怨めしや」が終わると、それが留めになってもおかしくないぐらいの一瞬の静寂、夫は法華経を読誦し、妻は成仏したと、この作品は終わります。後場での地獄の責め、死後も砧を打ち続けなければいけないという因果関係は、生前の恋慕の執念が死後の苦悩煩悩の地獄に落ちるという構図で、仏教思想を基盤にしてはいますが、『実盛』のような時宗の賛美のパターンとは異なり、そこが焦点ではないと思います。
法華読誦や成仏をクローズアップし過ぎてはこの作品が生きません。
世阿弥の時代背景を考え、作品構造上でのことと理解すればよいのです。
成仏とか宗教性とは別のところに、『砧』という作品の大事なメッセージがあると思います。
砧を打つ賎の業を主軸に、妻の夫への揺れ動く様々な感情の起伏。
一途に思うが故の怨みや激情。それはときに身勝手でありヒステリックでもあります。
女性だけでない、男性にもある、人類普遍の感情です。
現代風に身近な例をだすならメールのやり取りでもあります。
恋しい人にメールを送ったが返事が来ない。
どうしているのか?
私がこんなに思っているのに返事が来ない、あの人の冷たい態度はなんなのよと、怨み、怒り出します。相手はメールを見られない状況、見ても返信できない状態にあるかもしれない、しかしそんなことはお構いなしに送る方の感情は身勝手に増幅していくのです。

『砧』はそういった人間の普遍の感情の行き違い、心の葛藤を描いた集大成だと思います。
世阿弥は晩年、不遇の時を過ごしました。
体制の側にない芸能者のどうにもならない悲劇。
そこに耐え、あきらめながら、世阿弥はただひたすらよい作品の創造に執念を燃やし、そして仕上げた『砧』です。
生意気ですが「冷えた能」と世阿弥が自画自賛するのが、演じながら肌で感じられたような気がしたのです。
体の内部に熱い情念を持ちながらも、表面的には冷え冷えとした情感が漂うように演じなければいけない、演者にとって手ごわい能です。
私自身、人間にはどうしようもない事態がある、ということも少しわかってきた今、作品の曲目を深く読み込むことの重要性に気づき、演能レポートも書き始めました。
その作業の中で、私の演能形態に変化を与えた『砧』。
再演の喜びと初演の未熟さを恥ながらも、一つ一つの積み重ねの大事さが充分に身にしみる年となりました。
あまり思い詰めたり、物思いにふけることがない私が、いままだ『砧』の演能の余韻に浸り、演じ終えてしまった空しさを感じています。
そして世阿弥の残した「かようの能の味わい…」の「かよう」とはいったい何であったのだろうか、そのことがまだ心に残っているのです。
今回の演出の見直しを顧みて、昔なら演出を変えるなど、とても考えられない許されないことでだったと感慨を深くします。
今はよい時代となり、流儀では考え工夫する事が許される、さまざまな演出を試みることが出来きます。
本来出さなかった作り物は出すのが普通になり、切る足の所作も次第に変わってきています。
時代はよい方向に流れだしたと思います。
明治・大正の名人たちは魅力的で芸もすばらしかったでしょう、しかし現代の能も今を映しながら確実に進歩を遂げていると思います。
これからも作品の主張を見つめながら、一回一回の舞台を大事に真摯に勤めていきたい、そう思わせてくれた『砧』でした。
(平成16年10月 記)
能 『砧』前シテ 粟谷明生 撮影 あびこ喜久三
後シテ 粟谷明生
面 若深井 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
痩女 石原良子打 撮影 粟谷明生
唐織 梶葉模様紅無唐織 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
『半蔀』「立花供養」について投稿日:2004-09-11


横浜能楽堂特別公演(平成16年9月11日)で、『半蔀』を「立花供養」の小書で勤めました。私の『半蔀』は昭和59年、青年喜多会が初演で、これが三番目物に取り組む最初でした。先代宗家・故喜多実先生は若い世代の三番目物として『半蔀』『六浦』『東北』などを選曲され、それらは若者にとって大いに勉強になりました。私は未だ演じていませんが、類似曲に『夕顔』があります。『夕顔』は世阿弥作で構成的にもよく整理され、源氏物語の夕顔の巻を題材に、夕顔の上という人物像、可憐で儚い人生を歩んだ女を前面に出している曲のように思えます。
一方、『半蔀』は夕顔の上という人物像よりは、夕顔の花、夕顔の精に焦点が当たっているように見えます。作者は内藤左衛門、内藤河内守で守護代クラスの武士で細川高国という管領の家臣であったと、松岡心平氏は説明されています。あまり聞いたことがない人物ですが、『俊成忠度』の作者でもあると言われています。
今回の小書「立花供養」では、立花を花人、川瀬敏郎氏にお願いすることができました。私が川瀬氏の能舞台での立花を拝見したのは、昨年の橋の会・二日公演の二日目、シテ友枝昭世氏の時でした。ワキの言葉「中んづく泥を出でし蓮」のとおり、蓮の花が一輪すっと見事に長丁場立っている、その斬新さと無駄のない簡素化されたお花に驚かされました。シテは喜多流の友枝昭世氏、地謡は梅若六郎氏を地頭に観世流の方々、喜多流と観世流との異流共演の番組で、地謡の謡い方も勉強になりました。今でもあの日の演能と立花は忘れられず、私の脳裏に焼き付いています。衝撃的な一日でした。
今回の横浜能楽堂の催しは、実はあの橋の会の時に企画されており、すぐにも交渉に入りたかったのですが、川瀬氏が立花をやられて直ぐだったこともあり、少し難航しました。私としては、どうしても川瀬氏のお花で『半蔀』「立花供養」を勤めたい思いがあり、演出家の笠井賢一氏のご協力と、また横浜能楽堂のスタッフの方々のねばりある交渉があったからこそ実現できたと思っています。今、笠井氏をはじめ、横浜能楽堂の中村雅之氏や原田由布子さん、そして横浜能楽堂のご尽力、ご協力に本当に感謝しています。

近年、立花供養は草月や小原流でも行われていますが、本来は池坊に限られたもので、流儀の伝書にもそのように記されています。花の種類は季節により異なるようですが、今回のお花はススキが中央にすっくと立ち、桔梗や女郎花などの草花をあしらって秋の風情が漂うものでした。当日、川瀬氏が生けられている時に、我が家にある「立花供養」の伝書をお見せしたら、「ここに書かれているこんなに沢山の花を生けたら花だらけで、シテの姿が見えなくなってしまう」と仰っていました。お話しをしながら、その鋭い感性で生けられていく後ろ姿を拝見して、やはり当代の第一級の貫録だと感じ入ってしまいました。この度、川瀬氏とご一緒に舞台ができたことは、私にとって名誉なことだと喜んでいます。
今回の小書「立花供養」を勤めるに当たって自分の立場はどういうものか、すばらしい立花を前にして、演者である自分がどう演じられるかを考えました。通常は、夕顔の上という女性や夕顔という花の精をベールに包んで演じればそれなりになると思うのですが、あの立花があることによって、違った作用が舞台に現れてくると察したのです。川瀬氏が立花を持って幕から出てきた瞬間に、見所の人たちの目は一斉に立花に釘付けになります。正先に置かれてからも、その花の存在は大きく、舞台全体を支配しているといっても過言ではありません。その出来上がった舞台設定の中に、シテが出て行くとき、それは花と演者の融合なのか、拮抗なのか。あの美しい花にすべてを委ねて、その後ろで夕顔(シテ)はきれいに舞っていればいいのだろうか。それとももう一つ何かが必要なのだろうか。こんなことを考えながらも、かわいらしい夕顔の上と夕顔の花が、万華鏡のように観客の目に映ればそれで良いのかなとも思ったのです。
立花とは、僧が一夏(いちげ・90日間)の間、安居(あんご)し、つまり行脚せず修業するときに仏前に花(きり花)を供えますが、一夏安居が終わったときに、その花の供養をしようというものです。福王流の福王茂十郎氏にお話を伺ったところ、流儀ではワキが立花に一輪挿して「敬って申す」と謡うのが本来です、しかし最近は省略することが多くなりました、と仰っていました。また、小書「立花供養」では、福王流、下掛宝生流とも、中入後、アイとの問答の時に特別のワキの語りが入ることがあります。特に下掛宝生流では一子相伝として重く扱っているようです。今回は時間的な事情にもより、語りはなしとしました。
能の舞台進行では、ワキが立花供養をするのは前場の紫野・雲林院でのことで、後場の五条辺りは場所が変わるので、本来は、お花はシテの中入りと同時に後見が引くものとされています。お花を出すのも従来は後見が行っていました。今回のような瀟洒(しょうしゃ)な草花の場合は、後見が持って移動することは難しいので、川瀬氏が本幕から持って出て、正先に置き、そのまま据置の形としました。流儀の型としては、造花の夕顔を一輪、シテが左手に持って下居して立花に挿し、合掌してシテ謡となりますが、今回は敢えて挿す型は控えました。
シテは本三番目物としては珍しく、アシライ出で登場します。ワキが「敬って申す」と花に向かい読経をはじめると、シテは三ノ松まで進み出て、ワキ(僧)と立花を見る型となります。これは橋の会での友枝昭世師の創案の型です。再びアシライが始まると大小前に行き、立花に向かい下居して合掌し「手に取れば、たぶさに穢る立てながら三世の仏に花たてにけり」と謡います。『女郎花』では「折りつれば」と謡われる僧正遍昭の歌です。(花を折って供えれば手首によって穢れよう、咲いたまま過去、現在、未来の仏に奉る、の意)。そしてワキとの問答になります。立花の中に一輪、白い花夕顔がひとつ自分だけが楽しそうに微笑んでいるように見えるとのワキの言葉から、シテは自らが夕顔自身であると告げ、中入りとなります。
後場は、通常藁屋の作り物が常座に出されますが、今回は立花が据置のため、藁屋を橋掛の一ノ松辺りに置き、シテは作り物に入っての登場としました。
ワキが五条辺りに来て、寂れた小家を見つけると、中からシテの謡(一声)が聞こえてきます。そして地謡の「さらでも袖を潤すは廬山の雪の曙」でシテは姿を現します。
現在普通に舞われているクセの仕舞の型は伝書では座敷舞と書かれています。今回、正先に立花があるので、型はできる限り花に近づかないようにと心がけ、本来の、動きが少ない簡素化された型で勤めました。序之舞も、替の型で出来る限り花に近づかないようにし、三段のオロシ(序之舞の一部分)で袖を被き、とくと立花を見る型にしてみました。装束(長絹と箔)の質感や私の被き方に問題があったのか、三番目物らしくないというご意見や、あの立花にはあれぐらい派手な型が入っても良いのではとのご意見もあり賛否両論でした。
流儀ではシテの面は小面、後の装束は緋の大口袴に白の長絹が定番ですが、演じてみて、長絹はもう少し黄色味がかった時代を経たものの方が良かったかと、少し悔んでいます。

小書「立花供養」とは演者にとってどのようなものなのか、それが今回の勉強でした。花と演者の見事な融合とか、はたまた両者拮抗する反発力の美などと小生意気な思案をしていましたが、あの川瀬氏の存在感ある立花を目の当たりにしたとき、次第に遜色なく舞えればそれで良いかなと、消極的な自分が見えてしまいました。
花と演者が縦糸と横糸になって織り成していくような舞台をと、川瀬氏が話され、私自身もそのようなものを目指しましたが、存在感あるお花と向き合ってみると、立花が単なるオブジェではなく、みるみるその力を発散し始めるのに気づかされます。この不思議な感覚を舞台で感じることができるのは、正直、演者の私しかいないのではないかと有頂天になり、なにかマジックか催眠術にかかったような夢心地に浸りました。
日頃、演じるにあたってあれこれ考えようとしていますが、今回は曲の持つ主題や主張を云々するより、身体が感じたまま演じてしまったという反省が少しあります。いや、何を隠そう、それしかさせてもらえなかったという反省でもあります。それは、立花の持つ力もありますが、能『半蔀』が見事に簡素化され、夕顔の上の物悲しさ、源氏との恋、そして甘い思い出などを、ストレートに表現できないような仕組み、というより、そのように工夫されているからではないでしょうか。究極は、静かな回想の舞、序之舞をどのように舞えるかが勝負だというところに落ちると思うのです。そこに集中することがまずは第一かもしれません。しかしそれは演じ方、考え方としては一つの逃げかもしれない。
川瀬氏の立花を前に真の花を咲かすには、さらなる修業が必要だと痛感します。とは言え、横浜能楽堂特別公演という、大きな、立派な、華やかな、晴れ舞台に立てた贅沢な喜びに、まだまだ夢心地で浸っているというのが本音です。(平成16年9月 記)
写真
能『半蔀』前場 シテ 粟谷明生 撮影 神田佳明
立花 花人 川瀬敏郎 撮影 粟谷明生
小面 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
貴重な大槻自主公演投稿日:2004-06-26
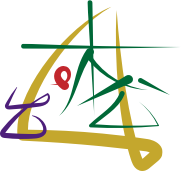
父、菊生の関西方面での最後のシテとなる大槻自主公演(主催観世流、大槻文蔵氏 平成16年6月26日)での客演公演、能『鬼界島』が無事盛会に終了しました。80歳を越えた高年齢や梗塞による障害、春の尻餅事件による腰痛の後遺症で、歯を食いしばっての父の力演でした。杖や床几の使用と特別な演出をし、ワキの宝生閑氏やアイの茂山千作氏と贅沢なお相手のお力添えを頂き、よい記念となる舞台となりました。
大槻自主公演の特色は演者を観世流一流に限定せず、広く他流の公演も催す画期的なものです。番組も計画的であり、毎回の斬新で優れた企画を私は高く評価しています。
父は喜多流の代表として、大槻文蔵氏よりシテを依頼されてから20年が経ちました。大阪という地は、決して喜多流の勢力が強いとは言えません。喜多流愛好家もさほど多くない状況下で大槻自主公演での喜多流の公演は貴重で、喜多流の能が観られる数少ない機会です。このようなお取りなしをして下さった文蔵先生には感謝の気持ちで一杯です。父は長年、大阪で指導に当たっていたこともありますが、それ以上に父と文蔵先生の親交の深さがその第一の理由であることは流儀の皆が周知しています。
この会では以前、能の前に観世流と喜多流の立合いの仕舞がありました。観世流は大槻文蔵先生、上田拓司氏、赤松禎英氏、喜多流は粟谷能夫、高林白牛口二氏、出雲康雅氏、そして私も競演の役を頂きおおいに勉強になり、良い刺激となりました。私がもっとも敬服することは、文蔵先生が観世流の内弟子さんに他流の能や仕舞の舞台を見せる機会を持ってきたことです。今このようなことを個人や団体で行っているのは少ないと思います。
昔、一時期故喜多実先生も他流の方々をお招きして、喜多流養成会なるものを起こし催しましたが、長くは続きませんでした。大槻自主公演の歴史の長さには頭が下がります。視野を広く学習させることは、流儀の良さ悪さが判り大切なことです。狭い思考になりがちな私たちの頭脳に大胆かつ新鮮な風を吹き込んでくれることと思います。今回、父の任は終えましたが、次に代わるものが生まれて、他流と交流する、このような喜多流の公演がなくならないことを私は切望しています。
幕に入り込むときの父の後ろ姿に、俊寛というよりは、役者粟谷菊生の舞台への必死な挑戦と達成を垣間見たように思いました。父の大槻公演での最後のシテの姿が俊寛にオーバーラップして私には残酷でもあり、悲しい場面として心に残りました。そして、父に教えられた言葉「芝居しては駄目、でも芝居心がなくては駄目」という名言が脳裏をかすめ、大槻自主公演で得た「他の舞台を良く見ること」の意識に立返ろうという思いも起こさせてくれたのです。
祝言の能『田村』について投稿日:2004-05-10


平成16年5月10日、広島薪能にて能『田村』を勤めました。『田村』は青年時代に稽古能でいたしましたが、公開のものでは今回が披きとなります。
先代宗家故喜多実先生は、青少年時代の稽古には厳格な一貫性をもって指導にあたり、我々直弟子はそれらを順次皆平等に平物(ひらもの=位が軽いもの)から稽古を受けて精進してきました。脇能ならばまず『賀茂』から始まり、『高砂』はなかなか許されませんでした。二番目物ならば、まず『経政』『知章』『箙』『田村』『敦盛』、次に『兼平』『巴』『八島』等が許されます。『清経』『通盛』は過去に記録がなく、勿論『実盛』『朝長』は論外です。『箙』『田村』『知章』『敦盛』などが選曲される理由は、前シテが直面の里男や『田村』のように少年であることが若いシテにとって取り組みやすいということではないでしょうか。特に『田村』の演能回数が多いのは、この曲が人間的な翳り悲しみとは無関係であり、心持ちより祝言性を基盤に脇能的な素直な稽古法で対応できることが大きな理由です。青年喜多会の過去の演能記録を見てもそれは歴然と判ります。
青少年時代、『田村』のキリの仕舞は『八島』と同様よく稽古させられたものです。少年時代は太刀を抜く能がかっこ良く憧れもあったので、『田村』を舞うときは「『田村』は刀を使わないんだなー」と子ども心にこの曲にもう一つ魅力を感じなかったことを思い出します。
キリの仕舞は「いかに鬼神もまさに聞くらん。千方(ちかた)といっし逆臣に仕へし鬼も…」と鈴鹿山の鬼神退治の話です。今昔物語には千方という頭領が鈴鹿山に立て籠もり、風鬼、火鬼、土鬼、隠形鬼と呼ぶ四人の手下を使って悪事をしていたので田村麻呂が退治したと記されています。白洲正子氏は山に住む異質の人種を「鬼」と呼んでいたと書かれています。私も鬼神、鬼の悪事とは先住民の抵抗であったと思います。能での「千方といっし」と謡われている世界と今昔物語では事実関係がすこし違っていますが、そこが能らしい演出なのかもしれません。
修行時代はとにかく「大きな声で…、張って謡え…」とひたすら身体で覚えさせられました。詞章がどうのこうのというのは問題外で、身体にたたき込んだものは意味も判らずとも詞章がすらすら出てくるので、これは究極の習得法だと今でも確信しています。しかし今、その指導法に感謝しながらも感じる事は、そこに停滞して満足していてはいかがなものか、それでは若き日となんら変わらず、なんとも情けないではないかということです。演能レポートを書きまとめるのは、そういう作業をすることで作品の見直しをし、もう一度身体に作品を浸透させるための手段だと思っています。
『田村』は勝修羅物と言われますが、実は修羅物ではなく祝言の能です。修羅物は修羅道という地獄に落ちた武将の妄執の責め苦を主題にしていますが、『田村』の詞章には「詞を交す夜声の読誦」と一言だけ仏教的な臭いがするものの、全体には祝言性に満ちています。修羅物と呼ぶのは江戸式楽の影響で、勝修羅三曲が特に武士に好まれたのは江戸期という時代背景によると思います。とりわけ初代征夷大将軍を扱う『田村』は征夷大将軍である徳川家には我が家の誉れを世にしらしめる恰好の曲だったのです。


前シテは通常、黒頭、水衣に着流し姿で面は童子(どうじ)です。面を喝喰(かっしき)にする時もありますが、そのときは喝喰鬘となります。この両者の面の違いは、演者が前シテを神道に関わる者と解釈するか仏教に影響を受けた者と受け取るかによります。地主権現の花守ならば神道系として「童子」が似合い、清水寺に関連づけると仏教色が濃くなり「喝喰」を選択したくなります。喝喰とは禅宗の寺に仕える半俗半僧の童子で食事などの世話をする少年を意味し、額に特別な髪型が描かれています。このたびは「童子」を選択し演じてみました。
後シテの装束は修羅物には頭に梨打烏帽子をつけるのが決まりです。梨打烏帽子は源平の区別で左か右に折ります。右に折るのが平家、左折(ひだりおり)が源氏です。昔、勝ったほうが左折で、負けが右だと誤解して装束をつけていた方がいらして、出る間際に折れ方が違うと言われ直していたことがありました。例えば『兼平』は戦では負けましたが、木曽義仲の家来ですから、源氏方、当然左折りです。ここで問題なのが『田村』です。当時はまだ源氏平家の区分けははっきりしていないので難しいところです。どちらに折るかと判断に困っていた時に「勝修羅だ、左折りにしておこう、そのほうが格好いいだろう」という意見が出てそのまま今に継承されているのが現状です。能夫氏が一度、折らずに真っすぐ立てて試みましたが、やは
りどちらかに折ったほうが落ちつき見栄えがよいというので、現在は左折りが主流です。
前場は春、桜の満開の京都清水寺地主権現に花守の少年が登場し、ワキの僧に清水寺縁起を語り僧に問われるままに名所案内をします。
現在地主神社の前には当時の桜はなく何代目かの地主の桜です。桜にも寿命があり、次第に枯れてしまうのだそうです。昔からある巨大な名物桜などを見ると永遠であるかのように錯覚していました。前シテは坂上田村麻呂の霊というよりも、神の使いとして大事な地主の桜を守る少年の花守として登場します。神聖な桜を折る者や花の下での宴から守るために花守が設定されているかと思うと、いつの世も衆生のあさましさを痛感します。以前、故観世銕之亟先生が夏の薪能で『田村』を舞われたとき、ワキ柱と目付柱に桜の造花を立てられたことがありました。先生が「こんなに暑い時に、いくら春の長閑さ、桜の満開を謡ってもお客様にはイメージが湧かないでしょう。薪能という機会だからこそ少しサービスをしてもいいのではないかな……」と仰っていたことを思い出しました。今回は桜の季節には遅れをとりましたが、春風を感じながらの『田村』は演じていても気持ちの良いものでした。
中入前の地謡に「地主権現のお前より、下るかと見えしが、下りはせで坂上の田村堂の軒漏るや月のむら戸を押し開けて内陣に入らせ」とあります。田村堂を想定して東方(揚げ幕の方)をカザシ見て、扉を開ける型をしながら中入りします。この田村堂の内陣は普通は拝観できませんが、先日テレビ番組でこの開山堂(田村堂)の内陣を見ることが出来ました。内部はお堂に向かい右側に田村麻呂の像、左側には高子妻室の像が安置されていました。能では田村麻呂が妻高子のために清水寺を建立したとは謡いませんが縁起物語ではそのようです(清水寺縁起しおり参照)。清水寺は修学旅行では欠かせない名所で誰でも一度は行かれていると思いますが、意外とその宗派は知られていません。唯識を唱えるこの寺は過去にいろいろな経緯がありましたが、奈良(南都)に対して京都(北)であるので北法相宗の本山となります。
後場は甲冑姿にて武将坂上田村麻呂が東夷を平定し、鈴鹿山の鬼神征伐の勝因は清水寺ご本尊千手観音の仏力であると讚えます。

勝修羅三曲では『箙』は「よく弔いて」と終曲し、『八島』は救済を求めない強い義経像を描いています。『田村』は喜多流には「祝言之翔(しゅうげんのかけり)」の小書や、また曲名の頭に白の字をつけた『白田村』があることからも、祝言性を強調した曲であるといえます。「祝言之翔」は面が「中将」となり、位が重く静かなゆったりとした翔になります。翔は翁の舞の片袖を捲く型が入り、戦況よりもめでたさを祝う特別な型となります。『白田村』は後の面が「天神」で鍬形を着し装束は白を基調として狩衣を衣紋に肩上して、型も橋掛りで行われ緩急が付く特殊な型となります。
今回、通常の『田村』を修羅物の枠から外し再考する、そのひとつの手段として、面や、出立ちにも特別な組合せを考えてみました。後の面については八帖花伝書や実鑑抄に「『田村』は祝言の修羅也、平太は祝言に掛けぬ面也。平太は坂東武者の顔也」と、「平太」は『箙』の梶原平太景季の専用面のように記載されています。「天神」では『白田村』に近づき過ぎてしまいます。今回は、我が家の伝書に「三日月」にもと記載されていましたので「三日月」とし、特別に鍬形を着けて試みました。装束は最後に記した通りです。父は装束を見ていると『白田村』のように緩急をつけて謡いたくなると笑っていました。能夫氏はこれぐらいの事をしないと曲が生かされないから、良い選択だったと賛同してくれました。今後も伝統や伝承を大事にしながらも、それを鵜呑みにしないで、自分なりの作品を立ち上げていく、作品を生かす演出や説得力のある舞台を勤めていきたいと、改めて気持ちを引き締めています。
ここに今回の後シテの出立ちを書き記します。
着付紅入厚板、白地狩衣(肩上)、紺地半切、太刀、面三日月、鍬形、梨討烏帽子、黒垂、勝修羅扇。
(平成16年5月 記)
能『田村』前シテ、後シテ 粟谷明生 撮影 石田裕
面 慈童、喝喰 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
清水寺の田村堂と音羽の滝 撮影 粟谷明生
(清水寺縁起しおり参照は下記)
清水寺の縁起

音羽山清水寺は、1200余年前、奈良時代の末、宝亀9年(778)の開創になります。
奈良子島寺の延鎮上人が「木津川の北流に清泉を求めてゆけ」との霊夢をうけ、幽邃の音羽山腹の滝のほとりにたどり着き、草庵をむすんで永年練行中の行叡居士より観世音菩薩の威神力を祈りこめた霊木を授けられ、千手観音像を彫作して居士の旧庵にまつったのが、当寺のおこりであります。
その翌々年、坂上田村麻呂公が、高子妻室の安産のためにと鹿を求めて上山し、清水の源をたずねて延鎮上人に会い、殺生の非を諭され、鹿を弔うて下山し、妻室に上人の説かれたところの清滝の霊験、観世音菩薩の功徳を語り、共に深く観世音に帰依して仏殿を寄進し、ご本尊に十一面千手観音を安置したのであります。
その後、延暦17年(798)上人は坂上公を助け、協力して更に地蔵菩薩と毘沙門天とを造像してご本尊の両脇士とし、本堂を広く造りかえました。

音羽の滝は、清水滾々と数千万年来、音羽の山中より湧出する清泉で、金色水とも延命水ともよばれ、ここより「清水寺」の名がおこりました。
古来、『源氏物語』『枕草子』にも記され、謠曲『田村』『盛久』らにも謠われ、浄瑠璃・歌舞伎『景清』に演じられ、広く篤い崇信を集めてきました。
寛永10年(1633)現在の規模に再建され、国宝の本堂、重要文化財の15建造物を中心とした堂塔伽藍の輪奐の美は、観世音の信仰とともに、観音霊場として多くの人々に渇仰されるところであります。
京都東山の中央・音羽山を背景にした絶佳の場所に位置し、京絡の町の南半を瞰下し、約13万平方メートルの寺域は春は桜、秋は紅葉と、四季の景観はすばらしく、観世音補陀洛楽土と仰がれております。
本尊の十一面千手観音菩薩は、霊験あらたかな観世音として著名で、西国三十三所観音霊場第十六番の札所として香華のたえることなく、全国屈指の名刹であります。
「松風や音羽の滝の清水をむすぶ心は涼しかるらん」
『八島』の修羅道について投稿日:2004-04-01


能『八島』は、喜多流では『八島』と書きますが観世流は『屋島』です。もっとも観世流も大成版以前は『八島』と書かれていたようですが、八の方が末広がりでめでたい感じがします。
私が『八島』の仕舞を勤めたのは今までに25回を数えます。それは若い時分、父が舞う機会があれば必ず『八島』と番組に記載したことに依ります。青少年時代は義経の修羅の苦患、妄執などは無縁で、ただ元気よく舞えばいいと思っており、指導法も強く強くと理屈抜き、身体を激しく動かすことに集中していました。子どもの頃は謡本を見ることなく、先生の謡われた通りの鸚鵡返しの稽古なので、シテ謡の「今日の修羅の敵は誰そ、何、能登守教経とや」を「今日の修羅の、かたき、わたそ(渡そう)、なにの とのかみ(何の、殿守)」と発音していました。音(おん)だけで覚えて起こる現象です。お恥ずかしい話ですが、それでも通用してきたので可笑しなものです。
ツレは6回勤め、その内3回が伯父故新太郎のシテでした。伯父は『八島』が好きだったようです。このツレは若者でなければ舞台映えしません。私も20歳に伯父のツレを初めて勤めてから、最後は37歳、父菊生のNHKテレビ放送の録画の時で、ぎりぎり間に合った感じです。以前は一声の「漁翁夜西巌に傍って宿す、暁湘水を汲んで楚竹を燃くも(老いた漁夫が夜に舟を西岸に寄せて宿り、明け方に湘江の水を汲んで楚竹を焚く)」の漢詩の意味など皆目判らず謡っていたのが実態で、今思い出しますと照臭い限りです。
私はこのツレが誰であるか気になりました。何者か判然としないこの役が物語を立体化させるとか、語りに立体感をもたらすための工夫だと言われる方もおられますが、どうも説得力に欠けます。演じる側としては、誰々と指定されたい気持ちが強く、大半の演者は義経の家来であると思っていて、とりわけ佐藤継信ではないだろうかという意見が多いのです。しかし佐藤継信ならば後場まで居残る喜多流の演出では弓流しの場に居合わせるのが理屈に合いません。高林白牛口二氏は、ツレは義経の霊の分身であると説明されます。義経の霊は漁翁一人として登場するのではなく、ツレの若い漁師にも乗り移って分身として登場するということです。これならばツレが後場まで残る喜多流の主張に合うはずと述べられました。私は今、この説が一番妥当ではないかと納得しています。

先代宗家喜多実先生は、シテの中入と同時にツレは後ろ(地謡側)を向くように指導されていましたが、これは見所に御尻を向け、しびれている足が丸見えで見栄えも悪く、現場はかなり抵抗感がありました。特にアイが「那須語(なすのかたり)」という那須与一が扇の的を射る話を演じる時には景色が悪く、野村萬斎(当時野村武司)さんの披きのときには、私(ツレ)は一旦立って笛座後方に移動し、後シテの一声の登場でまた地謡前に着座したと記憶しています。喜多流の場合、後場にツレが着座する必要性は弓流しの段にツレの謡があるからです。今回厳島神社の御神能という奉納の場でもあるので、試演として従来のやり方を見直し、ツレの友枝雄人氏には中入でシテと共に退場してもらい、後のツレ謡は地謡で謡うことにしました。また通常二同(にのどう=二つ目の同音)「鉢附の板より引きちぎって」のところでツレは立ち地謡前に移動しますが、今回は初同「さて慰みは浦の名の」にて移動して、シテとツレの舞台上での交差を避けてみましたが、効果ある演出と喜多流内部では好評でした。
『田村』『箙』『八島』の勝者の三番を勝修羅と言いますが、この区分けは江戸式楽以降の発想でいかにも武士好みです。作品内容を考えると『田村』は清水寺観世音菩薩の功徳を祝言能として描き修羅とはいえません。『箙』は梶原景季の勝修羅としての勇壮な能といえますが、『八島』の主題は修羅道(敗れても再生し戦い続け苦しむ世界のこと)に苦しむ武将義経の苦悩だと思うので、単に勝修羅と区分けすることに今は意味を見いだせないように思えます。この勝修羅といわれる三曲は青年期までに稽古し習得しておかなくてはいけない曲ですが、稽古順は『田村』『箙』、そのあとに『八島』となります。
能『八島』のシテは昭和59年(29歳)粟谷能の会で披き、今回(厳島神社・御神能 平成16年4月16日)は20年ぶり、「弓流」の小書での再演となりました。『八島』が世阿弥作であることは間違いないようです。作品構成は上手く整理され申楽談義にも「道盛、忠度、義常、三番修羅がかりにはよき能也」と載っています、『義常』は『八島』と言って問題なく、ワキの宿借りの問答は『松風』や『絃上』にも似て、シテもツレも言葉を間違え安く、気を遣うところです。

『八島』の前シテの面は本来「三光尉」ですが、今回御神能に用意された尉の面に「笑尉」がありましたので試しに使用してみました。表情は名前の如く、笑んだ顔のため修羅の苦患とは無縁な前シテとなってしまいますが、能楽師の好奇心で、一度はつけてみようという遊び心でつけてみました。結果は人物像に陰りが出ないのでいま一つだったように思えます。
塩屋に通された僧(ワキ)が八島の合戦の模様を尋ねると、老人(シテ)は「あらあら見及びたるところを語って聞かせ申し候べし」と語り始めます。この語りが聞かせどころで、あまり熱が入り力が外へ発散し過ぎては尉の語りには似合わず、抑制を意識し過ぎ内へ引きこもると臨場感の欠けた修羅場の語りではなくなり、面白味が半減します。丁度よい頃合いを体得することが演者の大事な修業過程の一つで、今回も苦労したところです。
老人は屋島の合戦の有り様をまず義経の装束描写と名乗りから始めます。ここは平家物語「継信最期」の原文に添って前半の見せ場の始まりです。語り終え我に返るように「今のように思い出されて候」と一旦落ち着くように謡いますが、能夫氏は、「菊生叔父や新太郎は、あそこは、最後まで強い口調で熱く謡っていたなあ」と話してくれました。能夫氏は一旦冷静に静まるからこそ、供の男(ツレ)が謡い出す戦況場面がまた生きてくるのではないかと言います。私も同感です。シテを挑発するかのような謡が、ツレの大事な仕事で、その触発にまたシテが語り始める、そのような繋がりの面白さなのです。
平家物語原文では、物語の進行は継信最期、那須与一扇の的、錣引き、弓流と進みますが、能では錣引きの後に継信最期の話となり、那須与一扇の的は狂言方が担当して、後場で弓流となります。子どもの頃より、能の世界で書かれた歴史に慣れ親しんできたため、誤って歴史を認識していたことを知りました。今回平家物語を読み直し、能の屋島の合戦が平家原本とどのように異なって戯曲化されているかを知り勉強になりました。

三保谷四郎と悪七兵衛景清の錣引き、ここも緩急と語る口調に気をつけなければいけないところです。やり過ぎては老人の枠から外れてしまい、内にこもり過ぎては気持ちが伝わりません。こういうところを偉大な先人たちはいとも簡単にやっておられたように思えます。見ていた時は自分も簡単に出来る気でいたのですが、いざ舞台に立つとなかなかうまくいきません。「鉢附の板より引きちぎって」で両手を放し両者が左右にどっと分かれる型がありますが、床几に腰掛けた少ない動きの中での型で難しいところです。この錣引きの模様は能『景清』の方が詳細にリアルに演じられています。『八島』では「これをご覧じて義経」でシテは床几から立ち、継信最期の話へと移ります。義経目掛けて能登殿が放った矢を、継信が身代わりになって受け、馬からどっと落ちます。平家方は教経の郎党、菊王丸が継信の弟忠信に討たれ、源平共に哀れに思い、互いに引き潮のように兵を引き、あとは磯の波や松風ばかりの音が寂しく聞こえるという地謡の謡で、シテはワキに静かに向かい下居します。小さな動きながらも激しい戦闘場面、ここが上手く繰り広げられなくてはと、演者が奮闘するところです。この後のロンギが唯一幽玄の世界となります。世阿弥はここを最も大事にしていたようで、最後の「よし、常の浮世の夢ばし覚め給ふなよ」は、義経と、よし、常の浮世の掛け詞でしっとりとした雰囲気を出し、悲劇の英雄義経の姿を垣間見せて中入します。
今回は小書「弓流」ですのでアイは「那須語」となります。語りの最後は「乳吸えやい、乳飲ませいやい」で終わります。この面白い表現、よくよく調べてみると、「よくやった、でかした与一、褒美に女性のところで甘えてくることを許すぞ」ということのようで、このいかにも武骨な武将らしい言葉の使われ方が私は好きです。
後シテの面は通常、平太(赤)ですが、小書の時は白平太になります。生憎厳島神社には白平太がなく、残念ながら常の平太(赤)にて勤めました。出立ちは厚板、半切、法被の肩脱ぎとなりますが、古来は厚板の上に法被と側次を重ねていました。以前『箙』の時も試してみましたが、なかなか重厚感ある扮装なので今回もまた付けてみました。
一声で「落下枝に帰らず、破鏡再び照らさず、然れども猶妄執の嗔恚とて…」と修羅道での苦悩、妄執を嘆きますが、不思議と救済を求めないのが、この曲の特徴です。おめでたい勝修羅といわれる所以でしょうが、根幹のテーマはやはり殺人者の懺悔、成仏への懇願ではないかと私は思っています。しかしそこを明らかにしないところに、この作品の妙な明るさと特別な味わいがあるようで、判官贔屓にはたまらないのかもしれません。私は今回演じて、何かふっきれない、すっきりしないもどかしさを感じました。勇壮なだけではない、義経自身の悔しさ、敗北者の悲劇がどうにか表現出来ないだろうかと試みましたが、手ごたえを感じるまでにはいかなかったことが反省点で、少し残念に思っています。

喜多流の弓流は、我が家の伝書には「囃子方、装束に変わりなし」、「舟を寄せ熊手にかけて、既に危うく見え給いしに」後に立ち、少し出て下居、「其の時熊手を切り払い」と切り払う型をするとあります。今回は下居せず元の座にシサリながら左手に弓(扇)を抱えたまま床几に腰かけました。弓流はこのもとの所に戻るのが難儀で技の見せ所です。「後見は床几にくれぐれも触れぬこと」と注意書きがされています。最後の仕舞どころに緩急がつき、橋掛りでの特殊な型が入り、「春の夜の闇より明けて、敵と見えしは群れ居る鴎」とまた舞台に入り、激しく面遣いして常座で廻り返しをして留拍子を踏み終曲します。
源義経という人は平家を滅ぼすためだけに生まれてきた人ではなかったでしょうか。義経が登場する能は『鞍馬天狗』『橋弁慶』『関原与一』『熊坂』『烏帽子折』『八島』『正尊』『安宅』『船弁慶』『摂待』などですが、シテが源義経(『関原与一』のシテは牛若丸)はこの『八島』だけです。負けず嫌いの源氏の御曹司は百戦錬磨の名将義経となりますが、壇ノ浦の合戦以降は、人生の歯車がかみ合わなくなります。政治家頼朝の策略に使い捨てのように使われ、奥州、藤原家を頼みに下向しますが、遂に衣川の戦いで自害して果てます。一の谷合戦の奇襲作戦、屋島の戦いの前に逆艪問題で梶原景時と対立し猪武者と言われても「勝ったるぞ、ここちよき」と尻込みを嫌う性格、壇ノ浦合戦では楫取、水夫(かこ)を射殺すルール違反の新戦法で勝利し、あくどさも見せつける義経。これらの出来事で修羅道に落ち、梵天に攻め上っては負け、攻め上っては負けという戦いの日々を暮らす義経の苦悩、これがこの曲の主題であり、そこが表現出来なくては意味がないと思っています。
大槻文蔵先生は、能は歴史の王道を歩いた人ではなく、そこからこぼれた人を描いている、平家物語は歴史を上から書いているが、それを下から描いているのが能だと仰っています。すばらしい言葉で心に残ります。
私はどうにかして義経の心の奥深いところにくすぶっている嗔恚(成仏を妨げる生前の怒りの心)と妄執の苦悩を表現できるような『八島』を勤めたいと、再挑戦を心に期しているのです。
(平成16年4月 記)
写真
『八島』 シテ 粟谷明生 撮影 石田 裕
面 笑尉 (厳島神社蔵) 撮影 粟谷明生
『野守』を舞って投稿日:2004-03-24

16年3月24日、囃子科協議会にて『野守』の舞囃子を勤めました。
「囃子科協議会に呼ばれたら一人前だ」と父がよく口にしていました。つい先日、観世流の野村四郎先生とお話した時も、やはり同じように仰っていたのを思い出します。昔は初めて囃子科協議会に出演依頼されたら後は祝杯をあげていたと聞いています。それほどシテ方には名誉なことなのです。
この会は、以前は年4回第三水曜日の夜の公演と決まっていましたが、最近は昼間の公演もあります。囃子科協議会は流儀の違う舞囃子が3,4番と狂言一番、そして一調があるときもありますが、最後に能が一番という番組です。出演依頼については、父のツレは別にして、初めて個人的に依頼を受けたのが平成8年、ちょうど40歳の時で『御裳濯』(みもすそ)の舞囃子でした。次に平成12年『女郎花』の舞囃子、今回は3回目となりました。
喜多流では『野守』の仕舞は位が高く難しいものとされていて、先代宗家喜多実先生は中、高校生の時分では手がけることをお許しになりませんでした。当時どうしてなのか疑問を抱いていましたが、その理由は能を勤めて判った次第です。
私の『野守』の披きは厳島神社の御神能でした。その時、小鼓の横山貴俊先生に後シテについてご注意を受けました。「キリ能でありながら、大嶺の雲を凌ぎからの小のりは『野守』独特のリズムがある、あれは土着民族のものです。それらしく謡い舞わないといけません」と。忘れらないお言葉でした。私としては気や力を抜いて勤めたわけでもないのにと当時は納得出来ず、深い意味が理解出来ませんでした。後に、軽快な動きが面の小ベシミや曲趣とうまくかみ合わなく映ったのではないかと、この曲はどっしりとした重みが必要であると知りましたが、その演技法を体得するにはそれからかなりの時間がかかりました。
その後粟谷能の会にて「居留」の小書で再演いたしましたが、とにかく『野守』は動きが激しいので、『鵺』同様あまり年を経てからの演能は敬遠しがちです。「居留」は最後に塚の前で飛び安座して奈落に落ちる様を表し、残り留めになります。『石橋』の留めと同じ型になります。この時の『野守』居留は当時、三役や他流の仲間たちと稽古し再考したものでした。これについては阿吽の稽古条々にもそのうち記載したいと思いますが、能を作り出す喜びを仲間と分かち合いながら楽しく過ごし、私にとって貴重な体験となったのです。
写真 『野守』居留 粟谷明生 撮影 三上文規

『鵺』に託した世阿弥の思い投稿日:2004-03-07

粟谷 明生
春の第75回 粟谷能の会(平成十六年三月七日、国立能楽堂にて)では、父菊生が『月宮殿』、能夫が『当麻』、そして私が『鵺』を勤めました。
今回のメインは『当麻』。長時間の演能が予想されたので、前後は短めの軽い曲にと選曲しました。当日『当麻』は二時間二十五分という喜多流史上、最長記録となりました。80歳を越えた父は『月宮殿』のシテを勤めて直ぐに、あの長丁場の『当麻』の地頭を勤めましたので、終演後、疲れないですかと聞くと、舞台のいい緊張感があったからと、さほど疲れないと、元気に答えたくれたのには驚きました。トメは私が20代に一度勤めた『鵺』を再考したいと選曲しました。

演能レポートとしては話が外れてしまいますが、この曲で思い出したことがありました。私たち能楽師は、若い時から謡を覚えます。意味など二の次、判らなくとも、とにかく繰り返し謡う、丸呑み状態で頭にたたき込んで身体に染み込ませます。能楽師のほとんどの方がそうだと思うのですが、地謡を覚えるとなると、まず地謡のところだけ覚え始めます。若い時は曲の内容よりも、音でひたすら間違えずにと丸暗記します。初同(しょどう=地謡が最初に謡う個所)はシテが登場してワキと問答の後にあるのが定型ですが、『鵺』は異例です。昔、前シテの一声の途中に短い地謡「こがれて堪へぬ、古を」の一句があるのを見落としてしまい、周りの地謡の人がいきなり扇を持ち、私の知らない謡を謡い始めたから、びっくり仰天しました。あとで「あそこに謡があるのを知らなかったな」と先輩に叱られましたが、「いや実は自分も昔、同じ間違いをしてね」と言われほっとした、そんな懐かしい思い出があります。
では、ここからは『鵺』について考えていきたいと思います。
まず最初に『鵺』のあらすじを簡単に記載します。三熊野詣の僧が、津の国蘆屋の里に着き、一夜の宿を求めますが、その里の禁制により宿をとれず、やむをえず川岸のお堂で一夜を過ごします。すると空舟(うつほぶね=丸木舟)に乗った人影も定かでない不思議な男が現れ、自分は近衛の院の時に源三位頼政の矢先にかかり命を失った鵺の亡魂だと名乗ります。僧の求めに答えて、その時の有様を物語った男は、空舟に乗ると見えて夜の闇の中に姿を消してゆきます。
その夜、鵺の読経をしている僧の前に、頭は猿、尾は蛇、足手は虎という恐ろしい姿の鵺が現れ回向を喜び、自分が討たれた時の有様を再現して見せます。そしてまた遥かな闇の中に消えてゆくという話です。
演じるに当たり、鵺とは一体何であろうか、が気になりました。
秦恒平著の「能と平家物語」には鵺は崇徳院の怨霊ではないかと書かれています。崇徳院は後白河と皇位継承の争い(保元の乱)で破れ四国の讃岐に流されます。流されてしばらくは野心もあったのですが、乱を起こした償いとして「五部大乗経」を写経し、京の寺に納経して欲しいと送ります。しかし後白河は折角改心した崇徳院の書いた膨大な写経を「呪いが込められている」と讃岐に送り返します。怒った崇徳院はそれから、風呂にも入らず、身に付く物のすべてを切らないと心に決め、髪、爪を伸ばし、ついには「我は日本国の大魔縁となる」と呪いを込めて憤死します。これが能『松山天狗』です。秦氏は、鵺はこの崇徳院ではないかと説き、後白河側に味方した頼政が、夜な夜な御殿に来ては帝を悩ます崇徳院の霊を射殺す図式と説明しています。

鵺はトラツグミという実在の鳥の異称、鳴く声がおぞましく不吉であることから、この曲の中では、頭は猿、尾は蛇、足手は虎という、異様な姿とされていますが、このような造形は、どこから来たのか。
馬場あき子著の「鬼の研究」では、中国の古い書物『山海経(せんがいきょう)』(紀元前2世紀頃)が紹介されており、そこには、角付きの獣皮をまとった山の神々が数多く登場し、その姿は例えば、「竜身鳥首」「人面蛇身」等と言うように、多くは二種類以上の鳥獣の部から身をなしていたといい、また、日本においても「日本書紀 応神紀」に角つきの鹿皮を着た人が現れた話の他、正身(むざね)を見せたがらぬ神が、獣皮を着て神域への来訪者を見に出る話なども常套のことであった、といいます。
能の鵺の姿は、これらの山の主神に類似しています。では、なぜ、山の主神の姿をとったのでしょうか。このような国つ神、山の神は王朝支配体制の確立のために次第に排除され殺されていきました。王朝支配体制は一方的な勝者となり、土着の民や神々はもの言うことを封じられ、自由を奪われたのです。馬場あき子氏は、「修羅と艶」のなかで、あるものは、苦渋に満ちた足取りの重い神、例えば悪尉の面をかける神となり、あるものは、忿懣を押し込めたように口をへし曲げて結ぶ小ベシミの面の鬼神や大ベシミをかける天狗にと能の題材になっていったと説明しています。

私は以前『大江山』を演じて感じたことを思い出しました。『大江山』の鬼神が、進攻する中央政権勢力から理不尽に追い出された、土着の反体制の神や人々の魂であると感じたように、鵺の正体も、同じような過去を持つもののように感じるのです。鵺も、佛法王法の障りとなるべく悪心外道の変化の姿となったと考えられないでしょうか。王朝支配体制の象徴である天皇に狙いを定めたことで、鵺の反逆者としてのイメージは鮮やかに浮かびあがります。
『鵺』という曲は、頼政と鵺という勝者と敗者を合わせ鏡のように描いた作品です。故観世銕之亟先生は「頼政自体が鵺のように生きてきた、そこが面白い」と言われています。では頼政自体が鵺のように生きてきたとはどういうことなのでしょう。ここで頼政の生き方を簡単にたどってみることにします。
頼政は、保元の乱では後白河側につき、名だたる源氏の武士が去っていく中、源氏方では源義朝と共に生き残ります。その後、源義朝と平清盛が争う平治の乱では、頼政は源氏でありながら清盛側につき、義朝は破れ平家の天下となりますが、源家の大将として一人生き延びます。保元・平治の乱の間、さしたる武勲も立てずに、源氏の頭領としてうまく身をかわし、一族を守ってきた頼政です。そんな頼政の一面を見ることが出来るのが、平家物語、鵺退治の段で、最初にその顛末を短く記しています。そして平家物語では頼政は実は二本の矢を用意しているのです。一本は鵺を退治するため、もう一本は仕損じたときに、鵺退治に頼政を推薦した左大臣の首をねらうためです。戦さで指名されるならいざしらず、得体の知れない化け物退治に推挙されたことを、頼政は不本意に思っていました。勅命のため断ることもできず、また仕損じれば恥辱と不名誉な烙印を押されるいやな任務です。そんな気乗りのしない化け物退治と自らの命を天秤にかけさせられる不本意に、指名した公家を射殺すつもりで矢を二本用意していたと書かれています。頼政にとって、鵺退治はどのように心に残ったのでしょう。頼政が名を上げ、鵺は空舟押し込められ流されという、両者の明暗をはっきり見せる能『鵺』の描写も、その裏側まで見れば、加害者でありながら被害者でもあった頼政像が見てとれます。後の頼政の生涯を見てもそれは表裏一体、勝者と敗者の関係は逆転劇へと進展します。ここでは勝者に見える頼政も、人生においては、思うように行かない鬱屈を抱えた敗者でもあったのです。平家物語の「鵺」の段でも最後は「よしなき謀反を起こして」(以仁王に謀反を勧めた橋合戦)滅びてしまったと締めくくっています。頼政自身が鵺のように反逆者として葬られる運命だったわけです。
『鵺』は世阿弥の晩年の作と言われています。『井筒』など美しい幽玄の世界を極め描いた世阿弥が佐渡に流され、六十代後半で都に戻って、この鬼の能を手がけたのには何か意味があるのではないでしょうか。なぜ幽玄の世界を築きあげた世阿弥が大和猿楽本来の鬼の能に戻ったのか。やはりここには中央勢力から押し出された世阿弥の鬱屈があったのではないかと思えます。佐渡に流された無念の思い、鵺という化生のものと頼政という人間を対比しながら自分自身を描いていたのかもしれません。
能『鵺』は前場、後場とも僧に回向を頼みに出現し、鵺退治の仕方話を繰り返します。前場は空舟に乗った鵺の亡魂が頼政に扮し、鵺を射殺しその姿を自らが見るところが見せ場となり、後場は闇の霊界より御殿に飛び覆い帝を悩ます鵺を演じ、頼政の放った一矢を境に演者は頼政と変わり、両者の明暗を演じ分けます。御剣の獅子王を賜り、宇治の左大臣頼長(保元の乱で崇徳側に付き殺された)の詠んだ「ほととぎす、名をも雲居に揚ぐるかな」の句に、「弓張月の入るにまかせて」(いや、たまたま偶然に当たっただけですよ)と月を眺め名を挙げた栄誉を喜ぶ頼政。しかし舞台は忽ち一転、演者は空舟に押し入れられた鵺となり淀川に流され、蘆屋の鵜殿の浦曲の浮き洲に流れ留まります。この一連の型はこの曲の難所で最大の見せ場となります。
観世鉄之丞さんに先代観世銕之亟先生が『鵺』の中入りについてお話しをされていたことを教えていただきました。「『鵺』の中入前を喜多さんみたいに演やりたいんだがねー」と仰しゃったそうです。喜多流では「いくへに聞くは鵺の声、恐ろしや凄まじや」と常座にて振り返りながらズカッと面を切り、棹を胸に引きつけ最後に棹を捨てて中入りします。観世銕之亟先生はこの型がお好みだったのでしょう。これは『鵺』に限る特殊な型で、鵺の叫び声を聞かす心持ちで凄みの利く型です。今回は残念ながら『当麻』に同じように常座で杖を捨てる型があり重なるため、私の方は橋掛りにて棹を両手にて強く引きつける替えの型にしました。これは空舟に乗せられて闇の世界に帰っていく鵺が、今一度僧に弔いを願う気持ちが込められ、また闇の世界に流される抵抗と未練の気持ちとして棹で舟を止めようとする所作です。家の伝書にも「止める心」と記されています。

前場と後場に繰り返し登場する仕方話ですが、私は、前場は抑制した力の表現、後半はそれが開放されていく力の表現とはっきりと区分けされていると思います。鵺と頼政を入り乱れ演じ、討つ側と討たれる側、この全く正反対のベクトルを持つ両者を演じていくうちに、いつしか両者は演者の中で重なり合っていきます。そしてもう一方で二役を演じている演者自身の存在に気づかされるのです。そのトライアングルのような繋がりは演じる者でしか味わえぬもう一つの『鵺』の面白みなのです。
前シテの一声の「悲しきかなや身は籠鳥、心を知れば盲木の浮木・・・」と、地謡の「こがれて堪へぬ、古を—」が大事な謡ですべての思いが込められていると思います 。全体を通して流れる鵺の鬱屈し屈折した無念の思いが、自らが放った矢で逆に射殺され、刺し殺されるという皮肉な構図の中で描かれるところにも面白さを感じます。
『鵺』は五番目ものですが、世阿弥や禅竹の後の時代の、『紅葉狩』や『船弁慶』などとは趣が違います。後の時代のものは、枯れた奥深い味わいより派手な動きや場面展開の妙味で観てもらおう、能を享楽的に面白くしようとする傾向が強くなりました。しかし世阿弥は五番目ものとはいえ、後の遊興性のものとは違い、幽玄の流れを引きずりながら鬼の能の再考をしたのではないでしょうか。そしてその作りは格別の上手さです。サシ、クセ、ロンギなどの構成は、『井筒』などと似て、他の五番目ものには見当たりません。『鵺』は単に、頼政に退治された鵺の仕方話をテンポよく体を動かしていればよいのではなく、老成した世阿弥の深い思いを汲み取って演じなければならないと思います。そうでなければ、鵺、いや世阿弥が泣くでしょう。
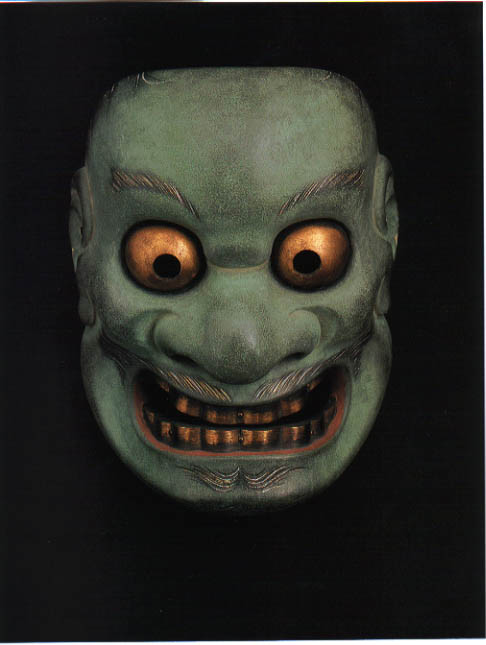
面・装束について、前シテは常の通り、面は家にある是閑の「真角」としました。後シテの装束は本来、赤頭に半切、法被(肩脱ぎ)ですが、今回は特別に狩衣の肩脱ぎという当流では初めての試みをしてみました。このやり方は近年梅若六郎氏が発案され、銕仙会でも『重衡』などで試みられています。当流では裳着胴(もぎどう)姿にて演じる時もありますが、肩脱ぎの方がより強さが表現出来、鵺という化生のものと頼政を重ねるイメージにしたいと狩衣を着ることにしました。狩衣は銕仙会から萌黄狩衣を拝借し、それに合わせ半切は粟谷家にある白地波模様を選びました。この装束の選択が決まると白頭の方が似合うのではと思い白頭を選択しました。観世流では小書「白頭」となると緩急などの違いがでますが、喜多流では頭が白色に変わるだけで、緩急は変わりません。
本来装束は面を決めてから用意するものですが、今回は逆で、装束を決めていくなかで面を選択する形になりました。後シテの面は珍しい「青飛出」と銘名された面です。本来「小飛出」ですが、古代的な少し鈍重なイメージの表情で白頭に似合うものと探し選択しました。彩色の青がきつい印象をうけ、結果は賛否両論でしたが、喜多流のあの曲ならあの面、あの家ならあの装束が出てくると、見る側から見透かされてはつまらない、また現場もそれに慣れてしまっていてはどうだろうか、時には奇抜なアイデアで演者や興業者側の遊び心を出しても悪くないのではないか。今回の善し悪しは別として、演出上一つの冒険ができたことに喜びを感じています。
私は、二十代に『鵺』を披きました。あのころは、型付通り基本を教えられるままに体を動かしそれで納得していました。二十数年を過ごし、人生の浮き沈みも少しは知り、今、作品の奥深いところまで読み込むことの重要性を感じています。失いつつある若きエネルギーに対抗できるものがあるとしたら、それは、挫折や悲しさ、人生を重ねてきた経験を糧に能に込められた奥深いもの、裏側をも探っていくエネルギーではないかと思うのです。

(平成十六年三月 記)
写真
鵺 養成会 前 後 撮影 あびこ喜久三
鵺 粟谷能の会 前 撮影 石田 裕
後 撮影 東條 睦
青飛出 撮影 粟谷明生
鵺塚 撮影 粟谷明生
『鳥追船』を謡い思うこと ー左近の尉の我慢ー投稿日:2003-12-01


喜多流『鳥追船』の謡本には曲趣として次のようなことが書かれています。
「劇能としての構成を目的としたものではなく、一種の遊狂気分が中心である…中略…前段は後段への準備的な場面に過ぎず、これをただ劇的に扱ったのでは、能楽の本質から逸脱したものとなる。興味の主題は、狂女能に類する船中の情景にある。一幅の田園秋景とみるべきであろう」とあります。さてこの説明、皆さまにはどのように思われますか? 私はあまり納得できぬ説明のように思えるのですが、いかがでしょうか。
『鳥追船』の作者は不明とも、また金剛作ともいわれていますが、確かではありません。この作品が生まれてくる土壌となるものは、たぶん鎌倉時代末期から室町時代の風習や時代背景に起こった様々な出来事、事件からと思います。それ以後、この作品は戦国時代の下克上の不安定な世相やまたそれを禁じた江戸時代やその後の時代を背景に演じられてきたわけですが、それぞれの時代でどのようにとらえられていたのか興味が湧きます。はたして上記のような秋景描写に留まった意識での舞台であったのか…。
私は『鳥追船』という作品が、上流階級の支配する立場からも、また支配される下流階級の民衆の者までも、素直に身近に感じる、ドラマチックな作品として見られていたのではないかと思っています。
もしそうであれば、演じる側は狂女能に類する船中の情景描写と田園秋景いう言葉だけでは片づけられない大事なものがあると考えねばいけないのではないでしょうか。訴訟のために都に上り、十年も帰らない夫、それを待つ妻と子(花若)、そして家人。鳥を追う秋景描写だけの意識では、あの世相での花若やその母、そして家人の耐えねばならぬ我慢を描いたドラマチックな作品は舞台に立ち上がってきません。特に前場では、演者が一人ひとりの人間としての生き様を背負って、それぞれの役に扮し、この物語の劇的な展開を演じなければ、見ている側も物足りなさを感じるのではないでしょうか。
演者が『鳥追船』という作品の中に描かれている人間模様をいかに表現出来るか、シテ・ワキ問わず、それが演者の大事な仕事であり、それがあるからこそ生涯の仕事として演能に張り合いを感じるのだと思います。舞台の演能は花火のように瞬間に輝いて消えていきます。書き物は後の代までも残り不変で、その内容は後の世の人に多大な影響を与えてくれるものですが、時としてそれらが正しいとばかり言えないこともあります。ここにあげた謡本の曲趣についても、信じる、信じない、認める認めないは受け手の自由ですが、問題はいかに演者が気をつけて対応するかであり、それが蔑ろにされては観客に失礼ではないかと思います。台本、謡本の深い読み込みこそ演者の使命だと肝に銘じたいものです。

十五年十二月の自主公演はシテ花若の母(日暮殿の妻)、粟谷能夫、ワキ左近の尉、殿田謙吉、ワキ日暮殿、宝生閑、子方花若、高林昌司で演じられ、私は地頭、粟谷菊生の隣で地謡を謡いました。
私はこの子方を故友枝喜久夫先生と伯父の故粟谷新太郎のお二人のお相手をさせて頂いた記録がありますが、今も記憶にあるのは伯父新太郎との時のことです。この時は自分の謡う個所を間違えたようで、たぶんおシテには大変なご迷惑をおかけしたのだろうと、思い出すと今も恥ずかしくなります。舞台というものは不思議でスムーズに進んだものより、少々怪我をしたものの方が脳裏に残ります。若いうちに沢山間違えておけ、という言葉が今また胸に響いています。
『鳥追船』は台詞劇で、内容もそれほど複雑ではありませんが、あらすじを喜多流の謡本の詞章だけで理解しようとすると少し無理があります。それは左近の尉(ワキ)や日暮殿(ワキ)の謡の詞章が大幅に欠落しているためで、左近の尉の花若の母に対しての申し立てに不明瞭さを感じます。喜多流の謡本の解読だけでは、作品の意図や登場人物の真意をつかむのは難しい状況です。
喜多流の謡本で、左近の尉(ワキ)のシテに対する詞章の文意は、次の通りです。左近の尉(ワキ)は花若の母(シテ)に当年は自分の田に鳥を追う者がいないので、お恐れ多いことだが花若殿に鳥追いを手伝ってもらいたいと言います。母は花若の代わりに自分が追うと言いますが、左近の尉はそれこそ思いもよらないこと、ただ自分の名を立てたいためだと言い、突然「所詮言葉多き者は品少なし」と怒りだし、家を出て行けと怒鳴ります。母は花若一人では幼く心もとないから、一緒に行くのだとさらに答え、左近の尉を納得させます。しかしこの流れでは、左近の尉の唐突な爆発の真意がわからず、理解に苦しみます。言葉の足りない詞章は説明不足で喜多流謡曲の愛好家を困惑させています。
下掛宝生流の謡本は、当流とはかなり違い左近の尉の気持ちが判るように、言葉多く詳しく書かれています。そのためワキ方は喜多流相手の時は、詞章のやりとりに工夫をこらし対応されていますが、これらの言葉を聞くことで事の起こりから、左近の尉の心情を読み取ることが出来ます。ここで下掛宝生流の舞台の展開をご紹介します。
左近の尉の鳥追いの催促に、自分がでかけるという母の言葉に対して、左近の尉の言い様はこうです。
「それこそ思いも寄らぬ事にて候、女性上臈の御身にて御追い候はん事、ただ左近の尉の名をたちょうずる為にてこそ候へ、まず上臈の御身にても、御心を静めてきこしめされ候へ、それ人の御留守とは、乃至一年、半年をこそ久しきと申し候が。すでにはや十か年に餘て、世に無き主を扶持し申したる左近の尉は、情けなく候よなう」と大声で叫びます。
ここにしばしの間があり、「いやいや言葉多き者は品少なしと申す事の候。所詮今日よりしては、某扶持し申すことはなるまじく候。この屋を明けていずかたへもおんにであろうずるにて候。ーーーー」と続きます。
留守を守るといえども十年は長すぎると家人の苦労を愚痴るのですが、語るうちに長年の張りつめた我慢はついに切れてしまいます。ここを喜多流では「所詮言葉多き者は品少なし」と唐突に言うため、まるで言葉多い母(シテ)は品が少ないと言っているように思えますが、ここは左近の尉が世間では、一般論としての言葉として自分に言い聞かせるようにして言っているのです。
これは能を鑑賞し、言葉をよく聞き取らないと理解できないところですが大事なところで、今回ようやく左近の尉の真意が解明できました。

父は『鳥追船』の謡について、後場の「げにや夢の世の何か例えにならざらん…」の段が、粋なところでここをうまく謡わなくてはと言い、益二郎(菊生の父)からは船の舳先がきゅっきゅっと変わる、そんな感じで謡うといいと聞いていると教えてくれました。謡い方を単に調子を落とすとか張るとか、ノリよく、じっくりなどと言われるより、このようにイメージが湧いてくるような教え方をしてもらうと、指導される者は想像し工夫して謡う必然性を感じ、興味をそそられ、それが面白さへと変わっていくのだと思います。
演じた能夫の言葉ですが、「狂女物の代表作に『三井寺』がある。狂女物の作風の特徴の一つに、一曲の終盤前まで凝縮されたテーマや物語が盛り上がっているのに、不思議とロンギという定型パターンに入ってくると途端に親子再会の祝言の場面となり、これですべての結末を片づけてしまう傾向がある。それが好きになれない」と、私も同感です。祝言で終えるという形式主義を否定はしませんが、演者としては、どうしても少しのストレスを感じながら終曲しているのではないかと思うのです。
しかし能夫は「この曲は最後までテーマが重く強く繋がっているように思えた」と、「たぶんそれはワキや子方の退場の仕方や地謡の謡い方によるものではなかっただろうか」と感想を述べ、父の地謡に対して「これほど陰影を感じさせてくれた地謡を聞いたのははじめてでした。『鳥追船』という作品を面白く謡って下さって有り難うございます」と感謝していましたが、その横で謡うことができた私も良い勉強になったと思います。
写真 カラー『鳥追船』前シテ 粟谷能夫 脇 殿田謙吉 子方 高林昌司
カラー 後シテ 粟谷能夫 子方 高林昌司
モノクロ 後シテ 粟谷新太郎 子方 粟谷明生
撮影協力 あびこ喜久三
(平成15年12月 記)
『楊貴妃』を演じて ー会者定離の響きー投稿日:2003-11-01
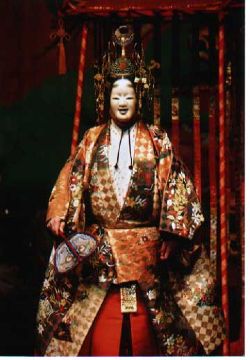
粟谷 明生
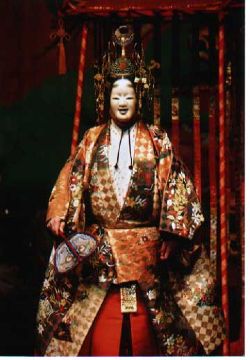
今年(十五年度)の喜多流自主公演では十一月に『楊貴妃』を勤めました。
『楊貴妃』は、『定家』『小原御幸』と並び、三婦人と呼ばれ、貴い女性を描く位の高い曲です。絶世の美女の波乱にとんだ生涯を、格調高い言葉で謳いあげた白楽天の「長恨歌」を題材にして、金春禅竹が創作したものとされています。観世栄夫氏は「禅竹は世阿弥の整った作品よりも一つ影がある、能の言葉としても暗い影、奥行きがあり、そこに惹かれる」と言われ、私自身も幽霊ではない死者という不思議な立場のシテを演じてみて、その心情の深みを感じとれたことが驚きでした。我が家の十代寿山公の伝書には「鈔云ク、一番ノ心持結構トモテナス事、楊貴妃二極リ多リ」と『楊貴妃』が女能の中で真の能であり、位の高い曲であることが書かれています。通常、能の演出は、死んだ人間(シテ)が現世に現れますが、『楊貴妃』は現世の人間(ワキ)が死者の国へ行くという逆の構造です。禅竹は世阿弥とは違った発想で、死者の内情、内面を生者の方が引き出す斬新な手法を『楊貴妃』に取り入れ成功しています。
・動きの少ない能・
『楊貴妃』の謡は長恨歌の原文を崩さずうまく導入された名文ですが、シテの型の動きは非常に少なく、謡の曲とも言えます。演能前に父や能夫が、「『楊貴妃』は謡の曲ということにつきる」と話していましたが、舞台を勤めながら「なるほどこのように謡うのか」と教えられました。しかし、動きの少ない曲は、どうしても観客は退屈してしまいます。こういう曲こそ、いかに観客の心をつかむかが大事だと思いますが、静止した時間の連続を飽きさせないようにするのは容易ではありません。それなりの工夫が必要ではないでしょうか。演者自身の舞台へのエネルギーのかけ方は当然のことながら、それ以外にも装束や面、作り物にもこだわりを持ち、できる限り退屈させないようにと考えました。
・装束の工夫・

装束は近年、他流では舞衣などを着用する時もあるようですが、室町後期の代表的な能伝書「八帖花伝書」には「女御・更衣・其の他公家・上臈の御風情信りたる能、いかにも気高く美しく華やかに、いろがさねに念をいれ、出立べし。まづ、上着ハ唐織を本とせり。<中略>楊貴妃、取分唐織本なり…」と、装束はやはり唐織であると書かれています。今回は、本家のお弟子様(宇都宮粟谷会の原田寛子氏)のご協力により、氏の所蔵される唐織を拝借させていただきました。萌黄と白の花筏市松段模様の唐織は歴史を感じさせるすばらしい逸品です。落ち着いた色合いながら、舞台に上がるとその華かさは輝きを増し浮かび上がるようだったと、ご覧になられた方の感想でした。時代を経た本物を着られることは、能楽師として無上の喜びであり、原田様に感謝しています。
・面の工夫・楊貴妃の生涯と容姿から・
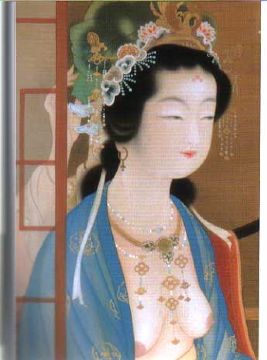
面は上掛りでは増女や若女を使いますが、喜多流は小面が本来とされています。しかし楊貴妃の生涯を思うと可憐な小面で演じるには少し抵抗を感じます。
楊貴妃は十七歳で玄宗皇帝の息、寿王の妃となりますが、翌年皇帝の武恵妃が薨(みまか)ってしまいます。九年の月日が経ち、或者が皇子の妃、揚氏の容色が殊に勝れていることを皇帝に説いたので、皇帝は皇子には韋昭訓の女を授け、皇帝の貴妃として迎え入れてしまいます。楊貴妃は前夫の父親と再婚するという極めて異例なこととなります。帝六十歳(六十一、六十二歳とも)、楊貴妃二十七歳のときです。歌舞に長じ穎悟(えいご)の貴妃は皇帝の寵愛を一心に受け、揚家一門を悉く要職につけますが、皇帝の政はこの時分より疎かになるようです。その後、安禄山之乱が起こり、皇帝の家臣によって楊貴妃は馬嵬が原で殺され、三十八歳の生涯を閉じる運命となります。皇帝との幸せな時間を失った喪失感の深さ、会者定離の無常観がこの曲の主題といえるのではないでしょうか。これらを考えると可憐な乙女の小面では少し辛いように思うのですが。
話はそれますが、楊貴妃はふっくらと豊満な肉体だったといわれています。茘枝(れいし、またライチー)が大好物は有名ですが、手羽先もまた好物だったようで、鳥のゼラチン質がふくよかな身体や、つるつるのお肌を維持するには最適らしく、それがまた皇帝のお好みでもあったようです。そういえば以前中国旅行で華清池に行ったとき、そこで見た楊貴妃の像も、上村松園の描いた楊貴妃もぽっちゃりとした豊満な姿です。

そのことと、皇帝と霓裳羽衣の曲を楽しんでいた時期を思えば、小面もしかりとは思うのですが、ロンギで謡う「我はまた何なかなかに三重の帯、廻り逢はんも知らぬ身に・・・」と、別れのつらさと恋慕の悲しい思いで帯が三重にも巻けるほどに痩せてしまった、ということですから喪失感の深さは並々ならぬものがあり、本来は増女の選択の方が似つかわしいとも思うのです。しかし、今回は自主公演という流儀の公式行事でもあるので、敢えて流儀の決まりを守り、我が家にある小面の中から少しでも艶を感じる面として「眉」の銘のついた小面を使ってみました。
・作り物の工夫・

作り物の宮は、普通四本柱に白帽子(しろぼうじ=さらし布)を巻くだけですが、先代の喜多実先生のころから、『楊貴妃』に限り赤帽子(ぼうじ)で巻くようになりました。今回は更に、赤帽子の上に紅段を螺旋状に巻きつけ柱の柄としてのイメージをより強調してみようと試みました。
小書「玉簾」は、宮の作り物の前方と左右に鬘帯を多数垂らし、帳や簾に見せ楊貴妃の姿をあらわにせず、また宮殿の豪華さを演出するものですが、今回は後面と左右に鬘帯を垂らしてみました。これは以前に故観世銕之亟先生がなされて、とても綺麗で舞台効果があったという能夫の助言からの試みです。この演出は引き回しを下ろしたときに、シテの姿が一段と栄えて見え、後方の囃子方との距離も置ける効果があります。作り物の宮は中国の蓬莱宮という未知の世界の宮殿という設定です。作り物は能楽界では簡素化された適応性の良さ、持ち運びの便利さが売りということはありますが、現況の舞台活動で日本と中国のものが同じでよいという気風は気になります。『大社』や『竹生島』に使用する宮と同じものが舞台に出てきては、観客は中国蓬莱宮を想像しにくいのではないでしょうか。私は中国らしさを少しでも出したいと思いました。従来の喜多流の引き回しの色は紫でしたが、近年萌黄や茶色のものも揃い、最近友枝家が緋色をお作りになりましたので、それを拝借することにしました。緋色を使うことで古代中国人の空想した仙界のイメージや華やかさが表現できたらと思いました。そして屋根にも蓬莱宮らしい工夫が施せないかと考え、今回特別に長絹の露(つゆ)を飾り結びにし、瓔珞をイメージして取り付けてみました。効果のほどは、いかがなものか、ご覧になられた方のご意見は様々のようです。
・シテ謡・
舞台の進行はまず、引き回しをかけた宮の作り物が大小前に据えられます。蓬莱宮と見立てられた作り物の中に、シテはじっと床几(鬘桶)に座って出を待ちます。ワキ(方士)の名乗り、楊貴妃の魂魄を訪ねる道行があり、ようやく蓬莱宮のある常世の国に着いたと説明します。アイに太真殿の場所を教わると脇座に着きます。ここまですでに三十分程の時間がかかります。
シテは作り物の中から「あら物凄の宮中やな。昔は驪山の春の園に共に眺めし花の色…」と謡います。ここはシテが最も気品をもって謡う聞かせどころですが、引き回しの中からの謡のため、か細い声では見所には届かず、馬鹿声をはりあげたのでは作品にふさわしくなく、難しく苦心する所です。
観世流、宝生流の上掛り(かみがかり)は「あら物凄の宮中やな」の謡はなく、「昔は驪山の春の園に・・・」から始まりますが、金春、金剛、喜多の三流の下掛り(しもがかり)は「あら物凄の宮中やな」と二回繰り返し謡い、「昔は驪山の・・・」と続けます。最近は観世流の方でも「いきなり、昔は驪山の・・・などとは謡えないね。あら物凄の・・・という導入があるほうが良いですよ」と言って謡われている方もいらっしゃるようです。
小鼓の大倉源次郎さんは故観世銕之亟先生から「あら物凄の宮中やな」の謡のイメージについて「例えば、敦煌あたりの一面砂ばかりの広大な大地に、一陣の風がシューッと吹く、すると砂がむくむくと立ち上がって形を成していく。それは宮殿であったり、楊貴妃の体になったりする。そんな雰囲気を想像して謡ってはどうだろうか」と聞かされたそうです。このような話を沢山聞いた源次郎さんは「面白い銕之亟先生の発想だなー、能って面白いなあ」と刺激され、「こういうことを教えて下さったからこそ、今鼓打ちやっているのかもしれないなー」と私に明かしてくれました。すばらしい人の深みのある言葉によって、人は衝撃を受け、志や発想が生まれてくるのだと思いました。私自身も諸先輩にいろいろな話をしていただいたことが大変役に立っています。今回の話も、歴史の奥底に埋もれた未知の世界の蓬莱宮のイメージやそこに佇む楊貴妃の面影が幻想的に、私の脳裡に浮かび上がってきたから不思議です。
謡は、声の音量や高低、息の使い方など技術的なことは言うまでもありませんが、しかしそこだけに留まっていては作品や役柄の訴えかけが充分に伝えられないように思います。この曲は何を言いたいのか、主題が何であるかを演じる者自身が理解し体現するという、次の段階の作業に携わらなくては作者や作品に申し訳ない気がします。イメージを演者の体の中に埋め込んで謡えるかどうかで、謡は違ったものになるといわれます。敦煌の砂嵐をイメージしてという先人の言葉は貴重であり、大きな手がかりになりました。自分の中にイメージを広げ、言葉に感情が入って、謡が体に染み込んでくるようにと精進しているのですが、なかなか道は遠いようです。
・ ささめごと・

ワキの方士は蓬莱宮に行った証に、楊貴妃と会って来たしるしのものを所望します。シテは釵(喜多流では冠)を手渡しますが、方士はこの釵ならばどこにでもある品物、これでは帝が信用なさらないでしょう、あなたと帝が人知れず話し合ったお言葉を聞かせて下さい、そうすれば帝も納得なさるでしょうと言います。
ここからが、父がこだわる謡のポイントです。つまり、二人だけしか知らないささめごとのくだりです。同音の「天に在らば願わくは、比翼の鳥とならん、地に在らば願わくは連理の枝とならんと誓いしことを、密かに伝えよや、ささめごとなれども今漏れ初むる涙かな」、ここは心を込めて謡うのだと。ここを乱暴に謡うと、父はかならず「二人は抱きあっているんだ、ベットインだよ。やさしく、静かに、内緒話だろー」と、私が『楊貴妃』というと思い出す言葉なのです。
・シオリ、泣く動作・

この曲は動きの少ない曲ではありますが、シオリという泣く動作の型が頻繁に出てきます。
シオリ(シオル)は喜多流ではシテは左手にて二回、ツレは右手にて一回、下から額に向けて手をすくい上げる単純な動作として行います。『楊貴妃』のシテはこのシオリを六、七回します。
単純な動作ですが、これを無意識な型の複写というだけ、型をなぞるだけで行うと、世界に誇る日本演劇の能としては、ちょっといただけないことになるでしょう。能の演技としてのシオルには、心の作業が必要だと言われます。演者自身の身体の中に悲しさ、ブルーな気持ちになる動作が起こり、すると自然と体が前に倒れ始め、面の受けを曇らせ悲しい表情となる、涙腺が緩んで涙がこぼれ、思わずその涙をそっとぬぐうという一連の動作なのです。これを形だけ真似た所作では本当の強い表現とはならない、父や能夫がしきりにこだわる注意点です。私自身も意識し注意を受けながらも、シオリの大事さを感じました。この単純な型を行うために、能役者は大汗かきながら歯を食い縛って身体を支え、必死にやわらかい手の動きで表現しているのです。ご覧になられている皆さまは、そんなこととはお判りにはならないかもしれませんが、こういう表現方法こそが能独特な世界であると、演者が身体を張って泣いているとご覧いただきたいと思います。
・舞う時期・
「八帖花伝書」には先程の続きに興味ある言葉が書かれています。「太夫三十のうち苦しからず。年よりたるシテはこれを斟酌(しんしゃく)すべし。その子細は年よりぬれば、つまはづれ、身入、身なり、姿かかりまで、若きときに違い、いやしき物なり…」とあります。若々しい肉体の持ち主でなければ楊貴妃の能は見られたものではない、年よりは姿がみっともなくて下品だから遠慮すべきであると、まあこういう意味で書かれています。(雑誌観世、研究十月往来142 小田幸子氏より引用)
華であったあのころを思い起こして霓裳羽衣の曲を舞う楊貴妃、若く美しい女性像を描くという意味ではこの条件もわからないではありません。しかし、役者の人間的な厚みを重要視する現代の能に照らし合わせてみると若く美しければいいという、三十歳以前の演能条件には少し違和感を覚えます。楊貴妃の素性はクセで語られています。「上界の諸仙たるが・・・仮に人界 に生れ来て」と謡われるように、能の中では仙女として描かれています。もともと天上界にいらしたが、縁あって人間界に下りて楊家に育てられた。死後も、蓬莱宮という天界の島に戻り昔を思い悲しく日々を送っている」と。この作品はシテは死んでいるので現在物とは言えず、また幽霊ではないので夢幻能ともいえない不思議なジャンルの曲です。執心に苦しみ、地獄の責め苦にあうといった酷さはなく、あくまでも上品で優雅な旧懐思慕と哀傷の世界です。
しかし一方で、『楊貴妃』を演じるとは、喪失感の深さ、会者定離の無常観を、役者がどれだけ魂を注ぎ謡い、少ない動きの中にも心を動かすという作業ができるかということでしょう。そうでなければ、この作品を生かすことはできないだろうと思います。
会者定離。この悲しい言葉の響きがなんとなく心に染みる年になった自分が、ある程度人生経験を積み、かといってそう年老いてもいないこの時期に、『楊貴妃』という美しくも哀しい曲を勤めることができたということは幸せなことだったと、今思うのです。
(平成十五年 十二月 記)
撮影者 能 「楊貴妃」神田佳明、あびこ喜久三
その他 粟谷明生 上村松園の楊貴妃画像は日経ポケットギャラリーより
『采女 佐々浪之伝』の新工夫投稿日:2003-10-12

粟谷 明生
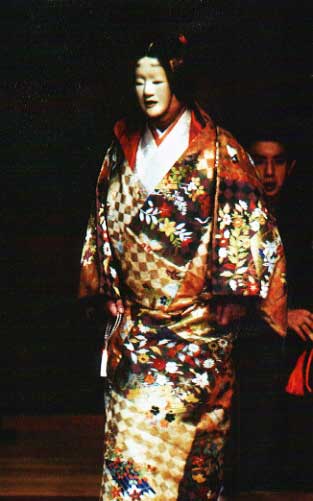 『采女?佐々浪之伝』といえば、六年前(平成九年)、粟谷能夫と私で主催する粟谷能の会研究公演でのスローガン、「新しい試み」に挑んだ思い入れのある曲です。
『采女?佐々浪之伝』といえば、六年前(平成九年)、粟谷能夫と私で主催する粟谷能の会研究公演でのスローガン、「新しい試み」に挑んだ思い入れのある曲です。
今回、秋の粟谷能の会(平成十五年十月十二日)では、もう一度、この『采女』を取り上げ、研究公演の成果と反省を踏まえ、一歩進めた、粟谷明生の『采女』を観ていただきたいと思い勤めました。
通常の『采女』の上演時間はおよそ二時間、長い作品です。粟谷能の会のように三番立の番組では、一曲にたっぷり二時間はかけにくい状況があります。
もちろん二時間なければ成り立たない曲であれば、番組構成を工夫し、その時間を確保することになりますが、現状の『采女』という作品ではどうでしょうか。
やや散漫な筋立ては、曲位として無駄な重さが感じられ、そのためか『采女』の上演回数は決っして多くなく、せっかくの優れた作品がどこかで損をしているように思えてなりません。
構成の散漫さを整理することで、『采女』のよさを十二分に引き出し、現代にも通じる能として再生、普及できないものか、これが私の挑戦であり、かなえられそうな夢だったのです。
では、『采女』の散漫さとはどこにあるのか。それは春日明神の縁起と猿沢の池に身を投げた采女の物語の二本立て構成にあるのではないでしょうか。『采女』は世阿弥作となっていますが、もともとは古作の『飛火』が原形で、それを世阿弥が改作したようです。
原形は、春日山の賛美が主体で、そこに後から采女の話をつけ加え作品化したものです。
しかしそのやり方は、当時はよかったのでしょうが、現代から照らしてみると、私には少し冗漫な作品として写ってしまうのです。
『采女』の小書は、昭和五十年、先代・喜多実先生が「小波之伝」(当初は「佐々浪之伝」)として、長時間の作品を凝縮するために創案されました。それを基に、私は先の研究公演で前場の春日明神の縁起や、後場の序、サシ、クセを省き、改訂版「佐々浪の伝」として試演してみました。
今回の小書再考にあたっては、演出家の笠井賢一氏にご協力をお願いしました。
新演出を作成するとき、演者ばかりでは思考に片寄りが生じ、つい演者のやりやすい方向に流れると感じてきました。
演劇、演能はあくまでも観客を対象としたもの、演者の自己満足、観客無視の舞台ではよくありません。
新たな事を起こす時こそ舞台全体を客観的に厳しい目で見ることのできる人が必要ではないかと思い、平素、研究公演などでお世話になり、ここ十年の私の舞台を気にかけてくださっている笠井氏に依頼いたしました。
まず新たな台本作りの検討からはじめました。研究公演での詞章を更に絞り込むことにし、前場は春日神社の由来、藤原氏の人々による神木の植樹の草木縁起を完全に削除し、後場は序、サシ、采女が安積山の歌を歌ったという采女の身にまつわるクセや、宮廷での酒宴の様の部分、そして「月に啼け・・・」の和歌に継ぐ御世を祝福する祝言を削除し、入水した采女の、現世の苦患を超えて仏果得脱の清逸の境地に焦点を当てたいと思いました。
春日山の植林から始まる春日縁起の段は興福寺、春日大社を讚える宗教賛美であり、藤原氏を讚える権力者賛美です。また「月に啼け・・・」以降は天下泰平、国土安穏という祝言性の強いもので、采女という女性には関連性が薄いと思います。これらをふまえて、今回の詞章を作成しました。
(どのように詞章が変わったか、粟谷能の会の当日に配付した資料を添付ファイルにてご覧ください。)
この能は、采女という女性の恨み悲しみではなく、得脱の晴れやかな境地を表現出来ればと考えました。采女は帝の寵愛を失ったと嘆き哀しみ、猿沢の池に身を投げますが、帝はそれをあわれと思い、「吾妹子が寝くたれ髪を猿沢の池の玉藻と見るぞ悲しき」(我が愛しい人との契りの後の寝乱れ髪が、今は猿沢の池の玉藻のように見えることの悲しさよ)と歌い弔ってくださったのです。帝の心も知らず恨んで恥ずかしい、浅はかだったと・・・、そこにはドロドロした恨み節はひとかけらもありません。采女はすでに変成男子、成仏し生まれ変わっているのです。
「佐々浪之伝」の主題は、入水した采女が現世の苦患を超えて、浄土を喜ぶ清らかな境地、法悦の余情と功徳、昇華した成仏得脱の境地です。詞章をきりつめて削った意図は、最小限の言葉によって能『采女』を表現する、能でなければ成しえない新たな『采女』の創作なのかもしれません。おそらく、これほどまでに言葉を削れば通常の芝居なら支障がでるはずです。最小限の凝縮された言葉や、言葉では語れない思いを序ノ舞という舞に感情移入し、舞歌という能の世界で濃密な時間と空間を織りなしてみたい・・・。
梅若六郎氏は能は基本的に無駄なものを削ぎ落としていく木彫芸術のようなものだが、それも程度問題で、削ぎ落とし過ぎると演者は理解していても観客には意味がつかめない事も起こる、程度が問題だ…と言われています。
この、程度が難しく、今回も絞りに絞った狭いテーマを扱いながらも、観る人の想像に任せる余白を大事に残し、面白く観ていただければ・・・、決して単なる仏法讃歌ではなくお説教曲でもない、新たな『采女』という作品を蘇らせたい、その一念だったのです。
ではここからは、実先生の「小波之伝」と、私の研究公演の「佐々浪之伝」とを引き比べながら、今回の『采女?佐々浪之伝』を見ていきたいと思います。
まず、実先生の「小波之伝」を簡単に紹介しておきます。昭和五十年六月、喜多実先生は土岐善麿氏の協力のもとに「佐々浪之伝」を創案され初演されました。配役はワキ・宝生弥一、笛・藤田大五郎、小鼓・幸円次郎、大鼓・安福春雄です。同じ年の九月二十六日の「能に親しむ会」が初公表となり、小書名もこのとき「小波之伝」と変えられました。以後はこの形が伝承され、友枝喜久夫氏、狩野丹秀氏、佐々木宗生氏などが勤められています。
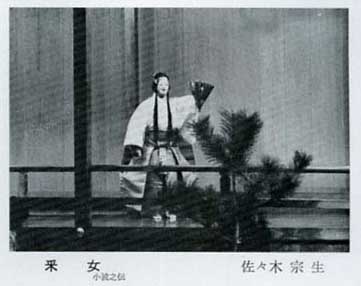
(雑誌『喜多』に、土岐善麿氏の『采女?小波之伝』の考察の手記があり、作成主旨がわかりますので、添付ファイルにてご紹介致します。)
ここでシテの出を見てみましょう。実先生の台本では、アシラヒ出で「照りもせず曇りも果てぬ春の夜のおぼろ月夜にしくものぞなき」という新古今集の大江千里の歌を謡い、すぐワキとの問答になります。続いて、語りが一部変更されていますが、初同以下は従来通りで、春日縁起も省略されていません。
私の研究公演でも、出は実先生と同じアシラヒ出で、大江千里の歌を謡い、その後植林の話を残しながらも「蔭頼みおわしませ、唯かりそめに植うるとも神木と思し召せ、あだにな思い給いそ」で止めて、以後の初同の春日縁起の謡は削除しました。
今回の「佐々浪之伝」では、植林の話も削除するため、シテの登場をどうするかが問題となりました。観世流の「美奈保之伝」では「のう、のう」とシテがワキに呼び掛け猿沢の池へ案内します。この「美奈保之伝」のやり方を踏襲することも考えたのですが、やはり喜多流らしさ、違いを出したほうがよいと考え、実先生のアシラヒ出を生かしながら「吾妹子が寝くたれ髪を猿沢の・・・」という帝の歌を謡うことにし、ワキとの問答につなげました。ワキの着きセリフの後に、「猿沢の池があるのでところの人に聞いてみよう」の詞を宝生欣哉氏に入れていただき、流れを整えました。
以前、観世流の片山慶次郎氏が雑誌『観世』の『采女』の記事の中で、「美奈保之伝」も呼びかけの言葉に工夫が必要では・・・例えば「吾妹子が寝くたれ髪を猿沢の・・・」と謡うアシラヒ出の可能性もあるのではと語っておられますが、これは今回の演出を選択する上での大きな自信ともなりました。
ただ問題もあり、「吾妹子が寝くたれ髪を猿沢の・・・」の謡が前場だけで三回もあり、少しくどい感じになります。そこで、シテの朗詠する形、シテの言葉で謡う形、地謡の小のりで謡う形と三種三様に彩りをつけての対応としました。
この曲のテーマともなる「吾妹子の・・・」の歌は史実は帝の歌ではなく、柿本人麻呂が詠んだ歌です。そのため実先生、土岐先生は「然れば天の帝の御歌に」を「然れば柿本の朝臣人麻呂」と変えられていますが、やはり帝が詠んだからこそ、采女は喜び物語が生きるのであって、柿本朝臣の歌では説得力に欠けます。能ではしばしば歴史にそぐわないことがありますが、能自体フィクションであり、物語の効果を考えれば、時には改変も許されるのではないかと思います。
後場は、実先生のは一声のあと、すぐに序、サシ、クセ、序ノ舞となり、序ノ舞は二段オロシから後見座にクツロギ物着となる斬新なアイデアです。
長絹を脱ぎ、蔓の両鬢を垂らし、裳着胴姿にて橋掛り一ノ松に出て入水、解脱のイメージを強めます。
小回りにて留め、シテ謡「猿沢の池の面」となり、「采女の戯れと思すなよ」と舞台に入り、最後は常座にて留め、終曲します。
研究公演では、序、サシ、クセを削除し、序ノ舞は物着をせず、替えの三段構成にして、掛(かかり)に「干之掛(かんのかかり)」、二段オロシに特別に老女物の譜を入れ、池への思い入れを型にしました。シテ謡「猿沢の池の面」からは終始橋掛りにての型に替えて勤めました。

今回後シテの出に関して、笠井氏より定型の常座でのシカケヒラキではないもの、「美奈保之伝」の被衣に替わるような演出はないだろうかと提案され、一声の留めを一ノ松にして、囃子方にお願いして特殊な手組を入れていただき、池水からの心情がこもる謡が謡えればと試みました。ここの「あら有難たの御弔いやな」の謡は笠井氏に、音、調子だけではない、有難いという感謝の念の訴えかけ、透明感のある謡を謡うことと、再三注意され、私には難所でしたが、これからの課題でもあることが再認識できたことは、有り難いことと思いました。
序ノ舞は、今回も序を「干之掛」にし、采女という女が昇華していく様とも、また我が家の伝書にある「采女一日曠れ也」のキーワードの如く、采女にとっての晴れやかな時を表現したいと思いました。
「一日曠れ」の絶頂感は官能的な高音から始まる干之掛の舞であればこそで、演者には一段と緊張をしいられる演出です。
二段オロシで中正面を池と想定して見渡し、池のほとりを浮遊する風情、妙なる調べを聞き、御光に照らされるかのように正先に出て、ふと合掌して祈る。静かで穏やかな特殊な舞の時間があってもよいのではないだろうかという、私なりの冒険でした。
「美奈保之伝」では水のイメージを重視して、拍子を踏まぬ、袖を返さぬが教えですが、私は采女が現世に現れて、補陀落の世界へ行けた法悦の舞を舞うことにしたかったのです。
凝縮されたひとときの舞、ただそれだけを念頭に描いてみました。ご覧になられたかたはどのように思われたでしょうか。
さて、このようにして作品を練り直し始めると、時代や人物の設定が気になります。
采女とはその歴史の中でどのような女であり、何を職務としたのか、采女という女がなぜ入水自殺をしなければならなかったか、それが知りたくなりました。
歴史的なことをあまり掘り下げてもどうかとも思うのですが、作品を見直し創作するには、この作業も大切ではないかと思い、私なりの采女像と事件背景をまとめてみました。
采女とは、その長い歴史の中で変化しています。古く七世紀?八世紀の古事記、日本書紀を編纂した古代貴族たちによると、采女とは専制的権力をふるった古代の天皇の侍女をさすようです。従って天皇の気分次第でどのような事も起こり得る、そこに悲話も生まれます。
例えば、五世紀の話。木工の名人・猪名部真根(いなべのまね)は木を削るのが上手で、石を台にして一日中木を削っていても、決して斧を石台にあてて刃をこぼすことはなかった。
あるとき、雄略天皇が「誤って刃をこぼすことはないか」と問うと、「ない」と自信満々に答えた。それを聞いた天皇はたちまち采女たちを呼び集めて、上着も下着も脱がせ、たふさぎ(猿股のようなもの)をはかせ相撲をとらせた。
いわゆる裸相撲です。そのため気が散って心を乱した猪名部真根は、斧を石台に当てて刃をこぼしてしまいます。
するとたちまち天皇は猪名部真根を殺してしまった…ということです。
残酷な話ですが、しかしここに出てくる采女の姿は猪名部真根に劣らず惨めです。
そこには女のはにかみも、こだわりも許されない。天皇の一言で否応もなく人々の前に肌をあらわにしなければならない悲惨な状況が実在したのです。
古代宮廷生活の一こま、軽く読み流せないエピソードです。これは門脇禎二著『采女?献上された豪族の娘たち』からの引用です。
采女は地方第一級の豪族の娘たちであり、郷里にいれば豪族の娘として大切にされ、生活も保証されていたはずの立場でした。
そのような娘が采女という立場に追い込まれざるを得なかったのは、豪族たちが天皇への忠誠の証として、娘を献上したからです。
采女は天皇と豪族との支配と隷属の関係から生まれた服従の証、美しい少女たちは人質だったのです。
天智天皇の時代にも歴史のひとこまに采女が登場します。中央政権は古代から中国の制度を取り入れたため、天皇には皇后のほかに、妃、夫人、嬪(ひん)がいて、その人数も決められていました。
采女は天皇のほか、これらの人々のお世話もしますが、身分的には決して高くはなかったようです。
天智天皇は皇后や妃、夫人との間に後継者に恵まれず、采女を召して子を生ませ後継者としました。それが大友皇子です。
以後、大友皇子は、天智天皇の弟の大海人皇子(後の天武天皇)の脅威となります。当初、大海人皇子は吉野へ逃避していますが、天智天皇が亡くなると、巻き返しを開始、采女を母とする大友皇子はにわかに形勢不利となり、その権力争いは壬申の乱へと拡大します。
瞬く間に大海人皇子は勝利し、大友皇子は最後には自殺という悲しい運命となります。
(能『国栖』はこの時の事件を背景に作られた作品です。
演能レポート『国栖』をご参照下さい。)悲しい運命ではありますが、この時代ぐらいまでは、采女という女性たちは、身分は低いながらも、天皇の寵愛を受ける機会があったということです。

以後、采女は地方豪族の娘たちであることに変わりないですが、生活や仕事、身分が厳しく規制されるようになり、天皇と恋愛できるような間柄はなくなっていきます。さらに時代が下って平安時代以降になると、采女の仕事は食膳係、裁縫係と限定され、天皇との関係は一層遠いものと変わっていったようです。
では能『采女』に登場する采女はどのような女だったのでしょうか。謡曲の詞章には「天の帝の御時」とあるように、故意に帝の名前の記述を避け、時代限定ができないようにしています。それでも、奈良・猿沢の池という地から、また『大和物語』に奈良の帝と記載されているため、平城京時代、つまり奈良時代の事件であったことは確かです。
平城京遷都は壬申の乱の40年ほど後、当時の采女は天皇と恋愛できる間柄ではなかったと思われます。采女のよき時代を想定してこのような物語が作られたのではないでしょうか。
そして采女は十四?十六歳ぐらいの生娘。帝に召され、純粋故の一途な思いが募ったのでしょう。
それに比べ帝は大勢の女性たちに囲まれ、采女の一途な思いなど気づかなかったかもしれない。
一度召してあげたのだから本望であろう、これで郷里の一族の地位は保証されるであろうぐらいの思いだったかもしれません。
帝と身分の低い生娘の間の契りには、支配する者と支配される者の価値観の違いもあり、それが悲劇の発端となったとも言えます。
しかし能『采女』はそのことによる恨み辛みを述べる怨念劇ではありません。帝の愛を失ったと悲観して入水した采女に「吾妹子が・・・」と歌を詠み哀れんでくれた帝の気持ち、ここに救いの始まりがあります。
法華経の祈りで女の身でありながら成仏できた喜びを美しい舞いでみせる、采女の悟りの境地と理解出来るのではないでしょうか。
序の舞が終わると、女は「猿沢の池の面」と謡い、「よく弔はせ給や」と、祈り続けることを願って池の底に消えていきます。
重ねて祈ることで、采女の魂の鎮魂を永遠の祈りに高めているように思えます。
采女はあくまでも美しくきれいに、人間味はなく、水と同化していく様にも見えます。
采女にとって、水や池は死に場所ではなく成仏の場所と変わっているのです。
采女が重ねて弔いを願い永遠を求めるように、私たちが携わる伝統芸能の世界も繰り返し反復することが神髄かもしれません。
しかしその反復の中にも、新しい試みや改良が必要です。
変えていく力を失うことは、能という伝統芸能のダイナミズムが失われ、抜け殻のようになってしまうのではないでしょうか。しかし伝統芸能の“変える力”というのは、根こそぎ変えるのでなく、伝統の持つよさ、匂い、臭さというものを残しながらのもののようです。
「名曲は伝承されつつ、その時々の工夫が加えられ、名曲であるが故に一層の磨きがかかってくる」これも梅若六郎氏のお言葉で、今回の作業をするにあたり大きな支えの力となりました。
演じ終え、この「佐々浪之伝」という小書を是非とも普及させたく、多くの方に体験していただきたいと思っています。

今回、囃子方を前回の研究公演のときと敢えて代え、笛は森田流(松田弘之氏)から一噌流(一噌幸弘氏)へ、小鼓は観世流(観世新九郎氏)から大倉流(大倉源次郎氏)へ、大鼓も高安流(佃 良勝氏)から葛野流(亀井広忠氏)にお願いしました。
それも多くの方々に体験していただきたいと思えばこそ。
みなさま私の試みを快く理解してくださり、協力してくださいました。深く感謝しています。
地頭を引き受けてくださった私の師・友枝昭世氏が「そこそこの作品になってきたね。序之舞を再考すれば・・・、今度自分もやってみようかな」と言ってくださいました。
この小書が多くの舞台で演じられることは嬉しい限りです。
コンパクトながら、能の世界を十二分に楽しめるそんな作品になるように、さらに改良を加えていきたい、あの池の采女が喜んでくれるような作品になればと思っています。
(平成十五年十月 記)
写真
佐々木宗生氏 「采女」あびこ写真
粟谷明生「采女」石田裕
頼政の男気投稿日:2003-09-20

粟谷能の会福岡公演(平成15年9月20日)『頼政』では、父の体調を配慮して、私が後シテを代演しました。
『頼政』は粟谷能の会(平成9年)の初演以来、能楽座静岡楕円堂公演(平成12年)でも急遽、父の代演をし、今回またと、何か因縁を感じます。頼政像が父の姿と重なるようで感慨深いものもあり、私なりに思うところを後半に重点をおいてまとめてみました。
『頼政』の後場は平家物語に基づいて作られています。治承四年の夏の頃、頼政は以仁王にご謀反を勧め、三井寺(園城寺)の援軍を頼みにしますが、平家方の知るところとなり、敢え無く、宇治平等院に御座を敷き平家を向かい討ちます。宇治川の橋合戦の様を語る床几に掛けての仕方話は、老将である頼政と、平家方の若武者、田原又太郎忠綱の二者を演じ分けるところに演者の力量が出て面白いところだと思います。特に忠綱の指揮による三百余騎が川を渡り攻め入る様子は、能『頼政』ならではの面白さ、見どころです。
床几での型には、それぞれ口伝が秘められていて充分な稽古が必要ですが、ともすると型の模写に留まってしまい、頼政という、老体であり法体そして軍体であるという、複雑な捻くれた人間像を見失う傾向があるので、演者はここを注意しなくてはいけないと思います。しかし言うは易く行うは難しで、私も完璧にはできません。
頼政は七十六歳(七十七歳とも)の老体ですが、目に金環がある専用面「頼政」を使用します。いかにも老武者らしくと三光尉をかけて「老い」を前面に出す『実盛』とは異なります。頼政の面には、老いて猶強い現世への執着、人間離れしながらも、何か生臭い執念のようなものを感じます。
修羅物を演じるとき、役者は命を懸けて戦っている様や、その戦慄を舞台に表現できなくてはいけないといわれます。『頼政』に触れるたびにこの言葉が思い出され、同時にシテを勤める時だけではなく、地謡を謡うときも、それが芸能の課題であると感じます。
能『頼政』を勤めるに当たり、源三位頼政という老武者がなぜ挙兵に及んだのか、どのような執心があったのかを、もう一度繙いてみることにしました。このことは、前回の静岡公演『頼政』でも書きましたので、参照していただきたいと思います(演能レポート「『頼政』の鬱屈と爆発」)。今回は、頼政と以仁王を結ぶ意外な人物がいたことを知り、興味深く感じましたので、簡単にふれてみたいと思います。
私は、平家物語の一段「月見」を能形式の作品にしたことがあります。月見の段は藤原(徳大寺)実定が福原に新都なるとき、旧都の月を恋い慕って、京のさわ子(太皇太后多子とも言う。近衛帝と二条帝の二代の妃となった実定の妹、また姉ともいわれている)宅を訪ね、月見をし、歌を詠み、互いに昔を偲ぶという短い話です。実は、この人々が頼政に関係があり、以仁王にもつながっているのです。
後白河法皇の第三子、以仁王は親王ではなく王という称号です。これは安徳帝を推す平家方による圧力があったのか…、高倉帝と徳子の間に安徳帝が生まれると、以仁王の帝位継承の目は完全に無くなりました。以仁王は父後白河法皇の指示か、また平家方に疎んじられていたためか、親王の号は最後まで許されず、元服も人目に着かぬ秘密の内に行わなければならなかった経緯があります。そしてその場所に選ばれたのが、さわ子宅でした。その後それが原因でさわ子は出家することとなりますが、そのさわ子宅の隣に屋敷を構えていたのが源頼政でした。さわ子の小侍従と頼政が歌を交していた事実もあり、遂には屋敷を交換したほどの関係であったようです。
平家方の横暴が激しくなるにつれ、荘園さえも没収された以仁王、安徳帝が帝位につくことになると、もはや武力行使しかないと思っていた矢先、頼政は以仁王に平家追討の令旨を出させ決断をさせます。以仁王の苦渋を見守ってきた誼も一つの要因であったかもしれません。一方、嫡男・仲綱は伊豆守を任命され着任していますが、当時、伊豆には流人頼朝がいます。そこで接触があったことは紛れもないことで、それらの報告は逐一、父頼政の耳に入っていたことでしょう。
以仁王との関係、宗盛の頼政一門への嫌がらせ、そして子息仲綱兄弟の決起催促、そこに、仲綱と宗盛の愛馬争いが事件の発端となり、旗揚げの口火となったことは確かで、今まで我慢に我慢を重ねてきた老将の感情を一気に挙兵へと爆発させたのだろうと思います。七十六、七歳、死に場所を失っていた頼政という老武者に、平家を裏切るという、これほどの決起をさせたのは、これら複数の原因はもとより、最後の一花咲かそうという男気があったからではないでしょうか。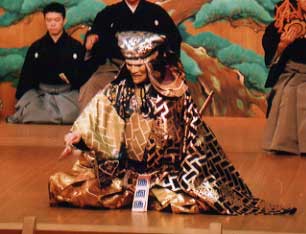
能『頼政』では、「木の下=このした」という愛馬に絡む話を中心に、頼政の決起のいきさつをアイが語ります。私はこのアイ語が好きで、後シテではこの語られたものを背負って登場しているつもりです。そして宇治川の橋合戦の仕方話へと繋がり、最後「兄弟の者も討たければ…」と息子達もすでに討ち死にしたと知るや、ここで敗戦を認め自害を決意します。子どもがいない戦はもう意味をなさなかったかもしれません。私は頼政の親としての心情を思い演じています。
『頼政』に関連した能に『鵺』があります。宮中を騒がす化生の物、鵺は頭は猿、尾は蛇、足手は虎の如くと謡にあるように、奇妙な化け物です。ここで頼政は宮中の弓の名手の警護武将として登場し、家来の猪早太(いのはやた)と二人で鵺退治をし名声をあげます。やはり頼政は宮中が似合っていたのではないでしょうか。宮中警備係筆頭であればよかったものを、似合わぬ場所に首を出したため、鵺のように退治されてしまいます。昔、観世銕之亟静雪先生に「頼政自体が鵺みたいに生きてきたんだよ、だからそこに繋がるものがあるんだ」と伺ったことを思い出します。『実盛』に「深山木の其の梢とは見えざりし、桜は花に現れたる」と頼政の歌がありますが、一花咲かす男気があったからこそ、歌人頼政の名声が今にあるのかもしれません。
今回、半能ではありますが、『頼政』を演じることで、この課題を作品にした世阿弥の老いての苦悩、苦労人世阿弥という人がひしひしと感じられるのです。次回の粟谷能の会ではこの『鵺』を演じます。頼政に因縁を感じつつ、『鵺』の中で、頼政像をもう一度見つめてみたいと思います。
(平成15年9月 記)
写真
面 頼政 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
能 頼政 シテ 粟谷明生 撮影 堤 恒子
『弱法師』俊徳丸の孤独と闇投稿日:2003-08-31
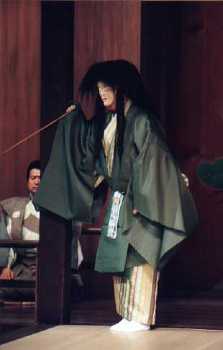
粟谷 明生
今年(平成15年8月31日)の秋田県協和町のまほろば能公演で『弱法師』舞入を勤めました。
『弱法師』は第二回粟谷能の会研究公演(平成四年六月)で初めて勤め、今回は十一年ぶりの二回目です。私はこの曲が大好きで、どうしても早く演じたいと思い、それがために、自分で演じる曲を決められる個人の会、粟谷能の会研究公演を発足したと言っても過言ではありません。
『弱法師』は若年では難しいという演者側の意識か、私がまだまだ未熟だったのでしょう、研究公演旗揚げの第一回では『弱法師』のお許しは出ず、まずは体を動かす曲を勤めてからでもいいだろうという父の言葉に従い『熊坂』を勤め、その翌年の二回目の研究公演で念願が果たせたという経緯がありました。『弱法師』を若年には披かせないという現場能楽師の意識は判ります。曲としての品位、悲境の身を嘆きながら、一面風流に心を保つことの重要性を思うとそういう結論になります。
しかし単に若年では叶わないと決めつけるのではなく、演じられそうな技量がある人間がいて、そこに精神性があれば、大人は積極的に場を与え、若い演者はそれに応えていくべきではないでしょうか。『弱法師』はそういう積極性を必要とする曲だと思います。大人になれば自然と淡々として出来る曲というものではないようです。不遜な言い方ですが、『弱法師』という曲に歯が立たない演者を見たとき、若い時分に演じていればこのようにはならないのでは・・・などと思うことがあります。
生意気だとお叱りを受けるかもしれませんが、私の正直な感想です。年を経ぬ者は演じてはならぬと頭から拒絶する方法論の犠牲者かもしれません。しかしそれは演者に責任があるのか、さてどちらに落ち度があるのでしょうか。
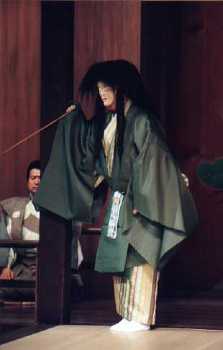
能『弱法師』は、父、高安左衛門通俊の後妻の讒言により、父に捨てられ、悲しみのあまりとも、流浪の果てにとでもいうか、やつれ盲目となり乞食として生きるしかなかった孤独な少年俊徳丸の悟りと諦念、そして法悦を描いています。初演の時はそういう精神性以前に、それまでに経験できなかった「盲目の杖」、その扱いの習得が私の念頭にありました。
喜多流の修業過程では、まず扇で舞うものから入り、次に扇以外のものの習得となります。扇以外に扱う道具としては、羯鼓の撥、長刀、杖などがあり、それぞれ難しいものとされています。段階としては、まず羯鼓での撥の扱いがあり、次に『熊坂』や『船弁慶』『巴』などで、長刀の使い方を覚えます。そして『藤戸』や『烏頭』などで使う「突く杖」、また『是界』『鞍馬天狗』『山姥』などで「鹿背杖(かせづえ)」という、T字型の持ち手がついている大型のものも習います。こういう扇以外のものを使うのはそれ相当の練習が必要で簡単に習得できるものではありません。それよりもう一段階上にあるのが「盲目の杖」だと思います。
「盲目の杖」と呼ばれるものは『望月』のツレ(母)や『蝉丸』のツレ(蝉丸)、『景清』にも使われますが、『望月』は構えをするだけ、『蝉丸』のツレも『景清』も終始杖を突くわけではないので、技を駆使する究極は何といっても『弱法師』の杖ということになります。
この「盲目の杖」は見た目には簡単に見えますが、実際やってみるとなかなかどうして難しいものです。面をかけて視界が狭められると、杖の先が見えず、すると手首の癖も出て、どうしても左右どちらかにずれて突いてしまい、身体の正面中央に綺麗に突けません。これは経験、稽古によって習得するしかなく、早めに手がける必要があります。このようなことも若いうちにという根拠になるのです。
では舞台進行に合わせて感想を述べたいと思います。
シテの一声からサシコエ、下げ歌、上げ歌とまずシテ謡の聞かせどころがあります。
私はサシコエの一部分が気になっています。「それ鴛鴦の衾の下には立ち去る思いを悲しみ、比目の枕の上には波を隔つる憂いあり・・・」という『砧』にもある一文は、夫婦の別れの酷さを謡っています。
世阿弥自筆本では、シテ俊徳丸にはシテツレとして俊徳丸の妻がいて、最初に一緒に登場します。ワキは天王寺の住職でワキツレとして従僧も出て、父の通俊はシテツレまたはワキツレという位置づけです。時正の日(彼岸の中日)は日想感を拝もうと大勢の人々が天王寺の境内に集まったようですから、その様子を表すには舞台に大勢の役者が上がっていることが必要だったのでしょう。
しかしこの演出は江戸時代にはすでに廃れ、現行のシテの俊徳丸、ワキの父・高安通俊、アイ通俊の供人の三人だけに絞り込んだ形と変わっています。天王寺の群衆のざわめきやにぎわいも必要でしょうが、作品のテーマは俊徳丸という悲惨な運命を背負った少年の達観した孤独感と超俗的な悟りの境地、しかし実はそれらへの葛藤であり焦れだと私は思い演じています。これらを際立たせるには、やはり俊徳丸は一人で出なくては成立しません。
「弱法師の奥さんを出すなんて言語道断、奥さんが弱法師の手を引いて登場しては強法師になってしまう」とは、白洲正子氏の弁です。

今回サシコエを削除して謡ってみようかとも思いましたが、後半の「今また人の讒言により、不孝の罪に沈む故、思ひの涙かき曇り、盲目とさへ成り果てて」を謡わなくては盲目の身となった経緯と嘆きが消えてしまいます。今後対処を考え、いつか新たな試みをしたいと考えています。
三の松から二の松、一の松と橋掛りを歩みながらの上げ歌は天王寺への道行きです。中国の高僧、一行がやはり讒言によって果羅の国に流されたが、九曜の神々が行く道を照らしてくれたと謡い、天王寺の石の鳥居のところまで来るもので最初の見せ場です。
型は常座に入るとシテ柱を石の鳥居と見立て、杖を舞台の縁に当てながらシテ柱を探り当て、カチと叩いて「石の鳥居、ここなれや」と謡います。いろいろな方々のこの場面を拝見してきましたが、やはり私は父のが心に残っています。探り当て、右足を引きながら、右手をグーッと上げて柱を確認する、その時顔は反対方向に向ける、ここが味噌で、いいところです。盲目の人は耳で見る、見たいところに顔を向けるのではなく耳を向けるのだ、が父の口癖です。

今回は時間の制約が有り、クリ、サシ、クセの釈尊入滅から聖徳太子の功績に及ぶ天王寺の縁起物語の部分を省きました。「金堂の御本尊な・・・」で始まるしっとりとした居曲(イグセ)、上羽の「萬代にすめる亀井の水までも・・・」より張って謡い、「皆成仏の姿なり」とシテが合掌する最後までは地謡の高揚感が聞かせどころです。序、サシ、曲の部分は世阿弥の作詞、作曲で独立した曲舞として別にあったものを十郎元雅が借用したといわれているようです。

今回は「舞入」の小書で勤めました。「舞入」は「東門に向かふ難波の西の海、入り日の影もまごをとか」の後に通常のイロエを中之舞に替える演出です。イロエは、昔見慣れていた難波の風景を思い次第に高ぶる俊徳丸の心理過程を、舞台を一巡するだけのさりげない動きで表しますが、「舞入」はここに中之舞を入れる演出です。杖を左手に持ち替え、右手に扇を持ち、杖を突きながらの舞です。左手は利き腕ではないので、扱いが思うようにいかず難しい技です。気をつけないと杖扱いがお留守になってしまうので充分な稽古が必要です。
「盲目の杖」の扱いは、他流では「心」の字に扱って突くと伝承されているようですが、喜多流は別で、特殊な、かいぐるように扱います。まず一つ突いてから一足出す、これが教えです。杖と足が同時になってはだめで、これに顔の動きを加えて盲目らしさを出します。この中之舞の位はノリのスピードをどのくらいにもっていくかがお囃子方の苦心どころです。単に、盲目だからとゆっくり囃せばいいというものではありません。心静かな日想観の様をみせるといはいえ、盲目の人間の暗く沈んだ気持ちの舞ではつまらないものになってしまいます。若い盲目の遊狂心の興奮とでもいうか、目は見えぬが心の中ではすべてが見えるのだという法悦の舞、ただベタベタと重ったるい舞ではテーマから外れるのではないか・・・、かといってやはりスピードが早過ぎては舞いづらい、適度なスピードが大事ということになり厄介なところです。
父菊生は十四世喜多六平太先生に俊徳丸にとっては天王寺は通い慣れた道だ、どこに何があるかは知り尽くしているから、のろのろせずに意外と速く歩むのだと教えられたとか。昔、父が勝新太郎の座頭市の真似をして説明してくれた、あれはとても面白かったといまでも思い出します。
そしてこの曲の一番の見せ場は、何といっても中之舞に続く仕舞どころのクルイです。時正の日は日想観といって、太陽が真西に沈むので、それを拝むことで、その先にある極楽浄土を想い願おうということです。そういう日であればこそ、俊徳丸もすべてのものが心眼で見えるぞと高揚感にとらわれるのです。「満目青山は・・・」で、左手を右の方から円を描くように大きく丸く動かし、「心にあり」と胸元に当て思いを込める、この一連の型に演者の精神誠意が込められ、すかさず「おう、見るぞとよ、見るぞとよ」と強く杖を突き、心眼の境地となります。そして東西南北の景色を眺め一瞬うかれたかと思うと、盲目の悲しさで行き交う人々にぶつかり、転び、人に笑われという現実にさらされます。ああ、やはり自分は悲しき盲人なのだと挫折し、「さらに、狂はじ」、もううかれたりはしないと落胆して座り込み絶望のうち心は閉じてしまいます。


最後はロンギの形式で、俊徳丸と通俊親子の対面の場面です。夜が更けていき、高揚のあとの挫折と落胆、そこに思いもかけぬ、父との再会。父と子は一つの舞台に居ながら、なかなか対面せず、焦らして焦らしてようやくの対面です。起承転結の結として見事に創り上げているといえますが、私にはどうしても、この結果が祝言ひと色には見えず、そこに元雅作らしさ、作品の深さを感じます。
元雅は世阿弥の嫡子ですが、時の将軍、足利義教が世阿弥の養子の音阿弥を寵愛し世阿弥や元雅を遠ざけたため、不遇の生涯を余儀なくされて、三十代前半の若さで没しています。そのためかどうか、『隅田川』『歌占』『盛久』に代表される元雅の作品は暗いテーマを扱い、最後に多少の光明を見せながらも(『隅田川』は最後まで救われない)、どこかに闇の部分を残して終わっています。『弱法師』も例外ではありません。
最後に父子再会を果たすとはいえ、通俊は息子だと気がついてからなかなか名乗らず、夜も更け、人がいなくなったころを見計らってようやく声をかけます。人目をはばかる通俊の態度に、俊徳丸の行く末は依然として暗黒の闇だと感じさせられます。高安の通俊は施行をするぐらいの人ですから身分も見識もある人でしょう。そういう人間が、この盲目の我が子をどのようにして面倒をみていくか逡巡する姿が想像できるのです。
安っぽい三文芝居なら、偉い人が現れて眼に手をかざしたら両の眼が開いた、これも日頃からの信心の賜物、めでたしめでたしということになるのでしょうが、元雅はそういう安易なハッピーエンドを嫌います。再会を“うれし”と喜びながらも、これからどうしたらよいかといった戸惑いを隠し切れない、現実とはこうではないか、もっとこのテーマを掘り下げてほしいという元雅らしいメッセージが伝わってくるのです。
最後は親子二人、手に手を取り合って戻るのではなく、少し距離を置いての退場としました。私は橋掛りを幕に向かって歩むとき、ゆっくりゆっくり、いまだに闇を背負っている思いで運びました。登場するときと同じくらいゆっくり、いや、登場するときは天王寺に光を求め信仰と希望に満ちているのですから、戻るときの方がもっと足取りは重いかもしれません。
俊徳丸は信仰の幻想と挫折を味わうのです。父に会ったが自分はこの先どうなるのかという暗い思い、父通俊にしても、讒言によって、この子をこんな酷いことにしてしまった、取り返しのつかないことをしてしまったという後悔と戸惑い、これらの負を二人がずーっと背負っていくのだという暗くて長い旅路が暗示されます。
元雅の、現実をしっかり見据えまっすぐに描き切る作風、どの作品もドラマチックで心がうねるような面白さがあります。元雅の作品に取り組むたびに、元雅という人がもう少し長く生きて、多くの作品を残してくれたら・・・と、遠く思いを馳せてしまいます。
(平成15年9月 記)
写真
弱法師 シテ 粟谷明生 研究公演 撮影 あびこ
弱法師 シテ 粟谷明生 まほろば 撮影 東條 睦
面 弱法師 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
四天王寺石の鳥居 撮影 粟谷明生
亀井堂 撮影 粟谷明生
『烏頭』 ー殺生の業についてー投稿日:2003-07-01


本州最北端の地、青森市で催される「外ケ浜薪能」にて『烏頭』(他流では『善知鳥』)を勤めました。外ケ浜(注・謡曲では外の浜)は謡曲『烏頭』の舞台として知られ、また版画家、棟方志功の出身地であります。棟方志功には能『善知鳥』を題材にした善知鳥版画巻があり、「善知鳥」(世阿弥元清原作、ブルース・ロジャース、メレディス・ウェザビー訳、棟方志功装幀、昭和22年旺文社発行)に掲載されています。今年は彼の生誕百年祭である為、今回の実行委員の方々が『烏頭』を選曲されました。
能『烏頭』は陸奥・外の浜でうとう鳥(ウミスズメ科の海鳥)を獲る猟師が、死後地獄の責めに苦しみ、僧に救いを求める物語です。
舞台は、越中の国(富山県)立山へ禅定(ぜんじょう=山中の霊場を廻る修業)した僧(ワキ)が目のあたりに地獄の光景を見て感慨し下山するところから始まります。そこに去年の春、外の浜で死んだ猟師の霊(シテ)が老人として現れ、禅定を終え陸奥へ向かう僧に、死別した妻子に麻衣の袖を届け、蓑笠を手向けてほしいと伝言します。立山といえば嶮しい霊山。今は立山黒部アルペンルートがあり、バス、ケーブルカー、ロープウェイを利用して簡単に立山から信濃大町まで横断できますが、その昔は、修験の山として信仰され、霊が集まる恐山、峻厳な秘境であり、立山に入ることは修行でありました。
私も学生時代に山に登った経験がありますが、残念ながら立山への登山は果たしていません。しかし室堂までは行ったことがあり、あのあたりの景色は今も覚えています。弥陀ケ平には「がきの田」といわれる、立山餓鬼道に堕ちた死者の霊が飢えを凌ぐために田植えをする田があって、この山に霊が集まるという立山信仰をあらわす不思議な場所でもあります。
後場の舞台は立山から遠く隔てた本州最北の外ケ浜となり、殺生を生業にする人間の罪という重いテーマを、前場、峻厳の地の立山と、後場、辺境の地の外ヶ浜を結んで描くところに、能『烏頭』の展開の面白さが感じられます。
今回は、初めてご覧になられる方もいらっしゃるのではないかと思い、物語が少しでも解りやすいようにと工夫を試みました。
一つは、日頃から気になっていた既存の簡略化されたアイの言葉の見直しです。横道萬里雄氏は著書「能劇そぞろ歩き」に『善知鳥』のアイの試案を書かれています。今回ご承諾を頂き、そのアイの言葉を野村万作氏のご協力を得て深田博治氏に勤めていただきました。通常、僧(ワキ)が外の浜在所の者(アイ)に猟師の家を訪ねると、「さん候、去年の春みまかりたる猟師の家は、あれに見えたる高もがりの内にて候。あれへ御出であって、心静かに御尋ね候へ」と非常に手短に、ややそっけなく答えます。それに対してワキは「ねんごろに御教へ祝着申して候」とたいそう仰々しく受けて謡いますが、私はここをかねてより不自然に感じていました。今回はご当地ソングでもあり、外ケ浜や主人公の猟師の説明などを丁寧に語ることにより、内容も一段とわかりやすくなり、ご覧になる方に身近に親しみを持っていただけるのではと思い試演してみました。
また「出し置き」の手法をとらないことにしました。出し置きとは、本来その場にいない人物を、最初から舞台に出しておくやり方です。『烏頭』の前場は立山が舞台ですから、外ケ浜の妻子がいるはずがないのですが、子方とツレは最初に登場してワキ座に座っています。初めて能をご覧になる方は、きっとここに戸惑いを感じると思うのです。「出し置き」は、能という中世の日本の演劇の特徴的な手法で面白いとは思いますが、敢えてわかりやすさに重点を置いて、中入り後、場面が外ケ浜に転回するところで、猟師の子どもと妻(子方とツレ)を登場させ、アイはワキに呼び出され幕から登場していただくことにしました。

面は前シテが小牛尉、尉としては品のよい顔で、喜多流では『高砂』や『弓八幡』などの脇能に使用しますが、なぜ身分の低い猟師の霊が小牛尉を使用するのか、品位の落ちる三光尉でよいと思うのですが、その理由ははっきりしません。研究の余地がありそうです。
前シテは呼掛で橋掛りにて留まり、片袖を脱ぎ取りワキに渡します。シテは本舞台へ入るぎりぎりのところで、ワキは決して橋掛りに入らずに受け渡しをするのが流儀の心得です。シテのいる橋掛りは霊界、ワキの立つ本舞台は現世とされています。その境で「立ち別れゆくその跡の」と二人の歩みが糸を引くように同じように離れて行くと良いと父は言いますが、これはワキとよくよくお稽古しなければ、そう上手くはゆかない難しいところです。
後シテは「痩男」の面に、羽蓑を腰につけ杖をつき猟師の霊として登場します。
『烏頭』のメッセージはシテ自らが謡う「何しに殺しけん」に集約されていると思います。人間が生きていくために、他の動物の命を奪わねばならぬという悲しい業。地球上のあらゆる生き物は弱肉強食のルールの上で成り立ち、人間も又例外ではありません。もし猟師の殺生が罪というならば、それは人間の背負った宿命的な罪と言うべきであり、道義的に許されない不条理であっても、これはもうどうしようもないものと目をつむるしかなく、理屈だけでは割り切れないことでしょう。生きるための生業ならば、致し方ないと思うのですが…。
『烏頭』『阿漕』『鵜飼』の三曲を三卑賎と呼び、いずれも殺生を生業にする猟師達の話ですが、『阿漕』『鵜飼』の猟師達が弔われ成仏していくのに対して、『烏頭』の猟師は、地獄に落ちて呵責の責めを負い続け、最後まで成仏せずに消えていきます。救われない何かがあり、それが『烏頭』の特徴ではないでしょうか。
では、救われない何かとは何か。答えは狩猟方法にあるように思います。幼い雛鳥を狩猟するところに問題点があるのではないでしょうか。度重なる殺生のうちに、いつの間にかそれ自体が快楽となり、罪の意識が薄れてしまった猟師。雛鳥と感じた瞬間、もう目の色を変えて散々に打ち尽くす姿は、正気を逸し、まるで何かに取りつかれたとも思えます。

猟師が鳥を打つ様を描く「カケリ」は「追打ち之カケリ」とも言われ、修羅道に堕ちた武者たちの苦悩や、狂女の心の狂いの様を表すカケリとは明らかに違います。型は正先に置かれた笠を巣に見立て、はじめは親鳥を狙い打ち、逃げられ空を見上げ悔しがります。二度目は橋掛りで「うとう」と親鳥の声をまねて謡い、それに答える雛鳥を見つけます。今度は散々に打ち殺し捕獲します。親鳥はそれを見て空から血の涙を流しながら泣き叫ぶという悲惨な場面となります。猟師は親鳥の血の涙が身にかかるのを嫌い、笠をかぶり蓑を着て身を守ります。現代でも人間が烏(からす)に襲われる事件がありますが、親烏は雛を守るために、巣に近づく者の頭めがけて襲いかかるといいます。襲われた人が帽子でもかぶっていたらよかったと言う言葉で、私は『烏頭』の笠と蓑というキーワードに繋がりました。前シテの猟師の霊の「蓑笠手向けてくれよと」と哀願する謡が、殊更強く切実な叫びとならなくては、と…。
稽古しているうちに、このカケリの動きが、親鳥を狙うものか、雛鳥を狙った狩猟なのかと、疑問を抱きはじめました。「うとう」と親鳥の鳴きまねをして、それに答える雛鳥を捕まえる猟法であれば、目的は雛鳥であるように思えます。あるいは雛鳥をおびき出して助けに飛んでくる親鳥諸共に打ち落としたいのかとも考えられます。我が師、友枝昭世氏ははじめの空を見上げる型は、雛鳥を打ちに行くと親鳥が猟師目掛けて襲いかかるので、親鳥への威嚇を表しているのではないかと言われます。でなければ一連のカケリの型の辻褄があわないと教えて下さいました。またある方は主眼は親鳥か雛鳥かではなく、猟という惨状の有様の表現ではないかと教えて下さいました。どちらであってもいい、観る方の想像にお任せすればという声が聞こえてきそうですが、どうも私は演者が自分の型、動きに説明ができないようでは問題ではないかと思う性分。師の教示でもやもやした疑問が晴れすっきり納得できました。
能『烏頭』は雛鳥の生命を絶つ罪の深さを、人間と鳥類の親子の情にからめて描いたところに主張があります。うとう鳥は親子の情愛が深い鳥だと言われています。「平沙に子を産みて落雁の儚や親は隠すと」も、外敵に見つからないように、親は懸命に巣を隠して子を守ろうとします。ところが、親鳥が「うとう」と鳴くと「やすかた」と答える習性があり、その親子の絆の深さがかえって命取りになっているわけです。そして、親子の別離は猟師の霊にも降りかかります。ひと目妻子に会いたいと外ケ浜までやって来る猟師の霊ですが、子供の髪を撫でようとしても、「横障の雲の隔てか」と阻まれてしまいます。まさに因果応報、罪の深さを鮮烈に描き出しています。
この救済なき罪にもがく猟師の心境。そこをどう表現するかが演者の力であり見どころです。後シテの「一見卒都婆永離三悪道、この文の如くんば・・・」と、経文を唱えれば助けてもらえるはずなのに、何故俺は救われないのか・・・という悲痛な謡を、単に朗々と謡ってはその苦しみが表現できるはずがなく、陰々滅々と気持ちを埋没して謡うだけなら容易いことですが、あの苦しみの訴えは通じないのではないか…。父は淡々と落ち着いて力強く謡う中に本当の強さが生まれ、それが聞いている人の想像力を掻き立てる、あまり前面に押し出すような謡ではいけないと教えてくれました。演じる心に余裕を持ち、下の下の身分の嘆き、実盛や頼政などの武将のような訴えかけの強さとも違う、低い身分にありながらもそこに強い張りと内圧のある叫びのような謡ができればと思うのですが、今回もつくづくその難しさを実感させられました。

私が『烏頭』の子方を初めて勤めたのは六歳の時、父菊生がシテでした。シテツレも二十三年前の昭和五十五年にやはり父菊生のシテで、奇遇にも青森喜多会の公演でした。私自身シテは、十年ほど前の妙花の会以来の二回目の演能です。
子方で思い出すことはたった一度の稽古で「ツレが立たせに来たら立ってシテの傍まで行きなさい、シテが触ろうとするから、触られないように長袴を踏まないようにもとに戻り、あとは最後まで座っていて、終わったら立って帰るんだよ」とこの程度の指示で、最初から舞台に出されたあのときの心境です。中入りが過ぎるうちに段々、いつシテの近く行くのだろうと不安になりながらも座っていました。シテが我が子の髪を撫でようと寄って来るところを、スッと後ずさりして逃げる動作は子ども心にも難しいと思い緊張しましたが、何よりもシテと向き合って、その面の顔をまともに見た瞬間、本当に恐ろしいと驚きました。これは髪を撫でてくれるのではない、殺しに来るから逃げるのだと思いました。それほどの恐怖を覚えたのです。もちろん、その場面はただ恐ろしいというものではありませんが、触りたいけれども触れない無念さで歩みよるその緊迫感が、子方の私には異常な恐ろしさと映ったのでした。
このシテツレは本来は年相応の者が勤めるべきものですが、流儀では若年でも勤めるチャンスがあります。シテが若年で勤める場合はどうしても、さらに若い者にということでこの役がまわってきますが、このツレを見事に演じた若年の舞台を見たことはありません。若い身体に「曲見」の面は似合わぬではないのですが、問題は「げにやもとよりも定めなき身の習いぞと」に始まるツレの謡を聞くと違和感を覚えます。若さでは表現出来ないツレの謡。父が言うように何回も何回も謡い、謡い込んでいくうちに、徐々にそれらしく謡えるようになるとはまさにその通りです。自分の過去を振り返れば恥ずかしい限りです。
終曲に、猟師は「助けて賜べや御僧」と嘆願しますが、救いはなく成仏は難しいようです。作者は、猟師に救済処置を施さず、永遠に地獄の責めを負わせることで、幼い命を奪うことの悪を教えているように思えます。最近の幼児殺害という悲惨な事件の数々。大人、子どもを問わず人間のもって生まれた残虐性と愚かさをこの作品は戒めているのではないか、現代にも通じる強いメッセージになっているように思えてなりません。人間が生きるかぎり『烏頭』は廃曲にはならず、永遠のテーマとして演じ続けられるでしょう。猟師の魂はあの恐ろしい地獄の有り様を表す立山の霊山に永遠に彷徨い続けていると、私は思っています。
(平成十五年七月 記)
小牛尉 痩男 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
烏頭 シテ 粟谷菊生 子方 粟谷明生 モノクロ 撮影 あびこ喜久三
烏頭 シテ 粟谷明生 カラー 撮影 石田 裕
能楽鑑賞教室の『黒塚』を演じて投稿日:2003-06-23

粟谷 明生
平成15年度の国立能楽堂主催の能楽鑑賞教室は喜多流の能『黒塚』、大蔵流の狂言『樋の酒』で催されました。6月23日(月)から27日(金)までの五日間、午前、午後の二部構成で十回公演、これを十人のシテ方が担当し勤めました。
能楽鑑賞教室は以前学生観賞能とも言われ、中高生など学生たちを中心に幅広く能、狂言に親しんでもらおうと催されるものです。シテ方は各流儀が交替で勤め、今年は喜多流の担当となりました。今年で20回を数えます。

歌舞伎役者や文楽など長期興行に慣れた方々は同じ曲目を繰り返し勤めることはさほど抵抗がないでしょうが、能楽師、特にシテ方は、一回一度きりの公演に身を置くことに自然と慣れているので、長期の公演はどうしても気の緩みが出てしまいます。その中で、いかに緊張感を持続させ、より良い舞台をつくるか、この五日間の興行をどのように過ごすかは、それぞれのシテ担当の能楽師、つまり太夫の責任に因るものと思います。
昔から興行が続く場合、例えば『翁』などの御神事のものは初日の式、二日目の式、と少しずつ演能形式を変え、演じる側の緊張を持続させ、観客にも飽きさせないような工夫が凝らされていたようです。伝書にも、続くとき、立ち会いのときには、それに似合った演じ方で演じ分ける心がけが必要と書いてあります。今回の興行はそのことを再認識する良い機会でした。
昔は家元から装束が出されれば、毎回同じ扮装、格好で登場することになります。幸い今は各々の演者が装束を調達するため、幾分個性が発揮され、一緒に舞台に出ている我々出演者の目も楽しませてくれますが、毎回同じ扮装、格好ですと、いささか興ざめしてしまいます。
今回、私は木曜日の午前を担当しました。前日までの演能形式に変化をつけようと考え、時間の短縮や、出囃子を変えることを試みました。地謡をはじめ、ワキ、アイ、囃子方すべての人の舞台慣れした空気を少し変えてみたいと思ったからで、必ず良い舞台効果を生むと確信していました。
前場は地次第「眞赭(まそう)の絲を繰り返し昔を今になさばや」のあと、シテの一声からクセまでを省いてロンギに続け、糸繰る労働歌「さてそも五条わたりにて夕顔の宿を尋ねしは」と糸繰る段に焦点を当てました。観世流には「長絲之伝」といい、枠枷輪を回し続ける小書がありますが、それにならってロンギの間、シテ謡を謡ながらも回し続けて糸繰りの動作をクローズアップしてみました。
黒塚の女をどのように勤めるか、どのように表すかは、演者の意識によりさまざまです。過去に人が人を食うという、犯してはならぬ罪障を背負った女が、今度こそは自らの過去を語り、懺悔したいと救済を求めている。夜陰の寒さに、通い慣れた山に薪を取りに出掛け救済者に暖をとらせようとする貞淑な女、私は決して前場で鬼女らしき所作は見せぬと思って演じています。中入りの橋掛りで一旦止まり、じっくり山を見上げ、裾を上げ、カッカッと大股で幕に入る型があります。ご覧になられた方から、「あのとき鬼女になったのですね」と言われましたが、私は、中年の女が真夜中、山へ薪を取りに向かうという強い意気込み、ある面尋常ではなくなる精神状態を表したいのです。庵で糸を繰る状態と山に出掛けようとする女の身体に異変がおきる、そこが表現出来なければと思うのですが。しかし能はあくまで、ご覧になる方の想像によるものです。鬼に変わったと思われればそれもまた良しなのですが、私としては鬼女になるのはその後と思って演じているので、演技の仕方に問題があったかもしれません。次回は型自体の修正も考え改善したいと思いました。山に向かった女の気持ちとは裏腹に約束は破られ、見られたくない閨の内を見られたその瞬間、彼女はまた鬼女となり、救いを求めようとした山伏をも食おうと襲いかかります。黒塚はこの怒りがテーマではないでしょうか。
今回後シテの装束は本鬘の掴み出しに般若をつけ、紅無腰巻の格好、登場の場面もそれまでやられていた早笛(はしり)を流儀本来の出端としました。これもまた工夫をこらし、怒りの鬼女は出端のはじめより幕から出て、三の松に止まり、逃亡する山伏達を見つけた途端、囃子が急速になるや、凄まじい形相で追いかけます。ここに鬼気迫る姿を表現したいと思いました。

鬼女は柴を持って登場しますが、持ち方に二通りあります。通常は負柴といい、肩に柴を背負うやり方、もう一つは抱き柴といい、左手に着物で包んだ柴を抱えながら登場する方法です。抱き柴は本来白頭で千鳥に(ジグザグに)橋掛りを歩むときの持ち方ですが、私はこの抱き柴に女の思いを感じます。あの人のためにと木々を集め自らの着物で束ね大事に抱えるその姿。それが救済者であろうはずのその人に祈られ退治されようとするのですから、女はついに抱き柴をほうり投げ、鬼女の本性を剥き出しにします。私はここに鬼女の精神の完全な断絶があると思って演じています。
祈りという型、動きは『葵上』『道成寺』『黒塚』の三曲が有名です。(稀曲『飛雲』もありますが、見た人はいません。)『葵上』はねちっこく、『道成寺』は激しく、『黒塚』は強くと教えられてきましたが、祈られる者は三曲とも女です。
強く激しくと動き、型ばかりが先走りしてとても女とは思えない後輩達の祈りをみると自分もかつてこうであったなと反省しますが、今祈りに、もがき苦しみ襲いかかる女の姿が見えないとやはり本物ではないと思い演じています。後半はキビキビした仕舞所があり、鬼女は祈り祈られ次第に弱り、夜あらしに紛れて消えていきます。
能楽鑑賞教室はそれぞれの演者が競い合い、見比べられる場。これにどう対処したらよいか、自分なりに考え、成果を示す良い機会となりました。日頃もそうですが、こういう機会こそ、それぞれの役者が切磋琢磨し、喜多流全体のグレードを高めていくものではと強く感じました。
(平成15年6月 記)
写真 前・後 石田裕
『梅枝』と『富士太鼓』の比較、そして「富士殺害事件の真相」投稿日:2003-05-01

『梅枝』と『富士太鼓』、この二曲には浅間、富士というふたりの楽人の名前が出てきます。富士に浅間、どちらも日本を代表する火山です。作品が作られた当時、二つの山はどのような噴火活動をしていたのでしょうか。能『富士太鼓』では、「信濃なる、浅間の嶽も燃ゆるといへば、富士の煙のかひや無からん」とあり、浅間山が富士山より激しく噴火していたと推察できます。富士や浅間の名前を使っての作者の工夫は大変興味あるものです。

さて『梅枝』は『富士太鼓』の後日談の能です。『富士太鼓』が4番目狂女物の現在物の分類に対して、『梅枝』はシテが富士の妻の幽霊として恋慕の情に苦しむ懺悔物語で、三番目物に近い夢幻能の作風となっています。これらの二つの作品は共通する一つの事件が引きがねとなって展開します。
花園天皇(萩原の院)の御代、内裏にて管絃が催されることになり、国々の役者に勅命が下ります。中でも太鼓の役は天王寺の浅間に勅命が下りますが、住吉の楽人、富士は自慢の腕前からか自ら望んで参内してしまいます。天皇は二人の太鼓を聞き比べ、富士も上手だがやはり浅間の方が上だと賛美したため、まわりの人々は以後、富士が上手と言わなくなりました。
もしここまでの話で殺害事件が起きたと聞かされたら、誰もが富士が自分の負けを恨み、ライバルの浅間を殺害したと思うでしょう。しかし事件の真相は浅間が富士を殺害するという思いもよらない展開となります。
『梅枝』のシテの語りに「浅間、富士とも内裏の管絃の役を争い、互いに都に上り、富士がこの役を賜ったのを浅間が安からずに思い、富士を討った」と語りますが、これは被害者、富士の妻側からの一方的な訴えで、富士が役を賜ったという事実はないのです。では実際はどうであったのか、気になるところです。
喜多流の『富士太鼓』のワキの名乗りには、浅間が富士を討った理由がはっきりせず、聞きなれた下掛宝生流の詞章でも謎は解けません。浅間が勅命という大義名分での参内だったのに対し、富士は所望されていない身でありながらの身勝手な図々しい参内です。この身分不相応の態度、そしてそのような相手と内裏で役を争わなくてはならなかった屈辱感、これらのことで殺意に及んだとなると、浅間という人物は随分短気で、乱暴な男と解釈せざるを得ません。天皇から認められた浅間なのです、勝者なのにと、私はどうも腑に落ちないのです。
先日喜多流自主公演(平成15年4月、シテ中村邦生氏)の『梅枝』で、大蔵吉次郎氏の間語(あいがたり)が、これらの謎を一掃してくれるものでありました。
大蔵流の語りには大事な一言が語られていました。それは浅間が召されたあとの富士の言動、「富士、散々にいいなしければ」の一言です。天皇からお呼びがかかった役者でもないのに図々しく参内し、その上負けの裁定を受けながらもなお、「浅間などたいした楽人ではない、本当は自分の方が上手なのだ、本当の勝者は私だ」などと吹聴する富士、さすがの浅間もこれを聞いては怒りが爆発し殺害に及んだと語ります。
ここに、天皇が浅間の勝ちと認めているにもかかわらず、事件を起こさざるを得なかった根拠がはっきりと語られています。
シテ方はともすると謡本の詞章からのみ作品を読み込んでしまいがちです。ワキやアイのお話や詞章をうかがうことで、取りこぼしたことなどを再発見することがあります。これらは作品全体を把握する上で大事なことです。今回の大蔵吉次郎氏の間語は私にとってこの曲の事件の全容を理解する有意義な一言でした。
『梅枝』は羯鼓台に舞衣を掛けるために支えの棒をとりつける特異な曲です。昔は中入りで舞衣を外すときに、支えの棒も一緒に取り外していましたが、昨今支えている棒はそのまま付けた状態で演じられています。先日もそうでしたが、私は舞衣がとられた後の羯鼓台の景色が気になります。演者側からみて右に一本張り出た棒が妙に気になって仕方がありません。羯鼓台は左右対称であってほしいので張り出す棒も左右均等にし、装飾を施すなど、見栄えもよく、舞台進行上、見劣りがしないやり方があるはず、新たな規格を考慮してもよいのではと思えるのです。次回には改善したい個所だと思っています。
『梅枝』を演じる難しさは、しっとりとした夢幻能の世界を作ることです。楽というやや明るくなりがちな舞を恋慕の思い深く静々と舞う、「『梅枝』の楽は序之舞を舞うように」が心得です。『梅枝』という曲名は「梅が枝にこそ、鴬は巣をくえ」と囃される越天楽より名付けられました。しっとりとした曲(クセ)からロンギへ、そして楽(がく)となって、終曲では夢幻能の代表曲、『井筒』の最後を思わせるような節と型、共通するものを持っています。
喜多流での『梅枝』上演の歴史は祖父益二郎の名演から始まります。伯父新太郎も祖父の名演で刺激されたのか、一時志しましたが、ついに演じることはありませんでした。その後、昭和54年当時の喜多例会にて父、粟谷菊生が久々に演じ、それ以来たびたび上演されるようになりました。
昔この名曲が何故封をされていたのかはここでは語りませんが、祖父、父の上演を機に『梅枝』が世に出たことは、たいへんすばらしいことだと思い、嬉しい限りです。『梅枝』と『富士太鼓』、共に名曲です。私自身は『梅枝』を平成6年、妙花の会にて、『富士太鼓』を平成13年、粟谷能の会にて勤めました。これらを演じてはじめて、それぞれの曲の持つすばらしさとテーマが私の心に残りました。
(平成15年5月 記)
写真は 梅枝 粟谷明生 撮影 三上文規
『翁付高砂』について投稿日:2003-04-16


平成15年の宮島厳島神社御神能で『翁付高砂』を勤めました。
御神能(ごじんのう)は毎年4月16日(初日)と18日(三日目)を喜多流、二日目は観世流が担い長い歴史を今に伝えています。初日の番組は翁付脇能に勝修羅物と定められ正式な五番立で演じられます。演目の組み合わせは『高砂』と『田村』、『弓八幡』と『八島』、『養老』には『箙』と決まっています。私が『翁』を披いたのは平成7年の『翁付弓八幡』で、その次は11年に『翁付養老』、今回『翁付高砂』を勤め、これで一循したことになり、達成感を味わっています。
近年、『翁』一曲のみの公演や『翁』だけを勤め脇能は別の能役者が勤める場合もありますが、やはり一人の太夫が翁と脇能の二番を勤めてこそ太夫を勤めたと実感できるのです。
『翁』について
『翁』は「能にして能にあらず」といわれるように、鎌倉時代以降今に伝わる猿楽の能以前に、寺社の行事や祭礼に奉仕する芸能として発生したもので、その形式を崩さず今に継承しています。そのため鑑賞本位の従来の能とは舞台芸術性が異なり、『翁』独自の構成、作法があるのが特徴です。上演時期は正月の初会や祝賀の会で演じられることが多く、そのため私は1月元旦の正月の節目と同様に、4月16日もまた正月に思えます。15日の桃花祭が大晦日、16日の初日を元旦として迎えるようで年の節目を感じるのです。
伝承では翁大夫は「勤める前日午の刻に沐浴し、食物の火を改め別火(べっか)致す事、服穢(ぶくえ)有る者に対面不致」とあり、楽屋は女人禁制がしかれます。とはいえ別火は現在の生活では不可能に近い習慣です。女人禁忌は女性の生理(月経や出産)による穢れを嫌ったもので、女性を不浄と見て聖所や宗教儀礼から締め出す習俗といわれ、私はあまり感心しません。かといって翁を勤める楽屋に女性が行き来しては長い歴史の流儀のしきたりからはずれるので楽屋入りはお断りしますが、女性の作った食事をし、心を落ち着け明日の演能を待つ、今の時代この程度の潔斎で良いように思っています。

『翁』を上演する時は、必ず、楽屋の鏡の間に「翁飾り」といわれる祭壇が作られます。上演前に最上段に白式と黒式の面と鈴を入れた面箱と翁烏帽子が飾られ、下段には洗米、塩、厳島神社は塩の代わりに炒子(いりこ)、盃がのせられ、お神酒が用意されて、『翁』独特の雰囲気となります。
シテは装束を着付け、最後に翁烏帽子を戴き中啓(ちゅうけい=扇の一種)を持ちます。準備が整うと翁飾りの前に下居し、面箱に向かって深々と礼をし、後見よりお神酒をいただいて出を待ちます。続いて出演者一同、まず三番叟、次に千歳から順に、囃子方、地謡方、後見とお神酒をいただき、洗米や炒子を口にして塩があるときはふり、心と身体を清めます。通常は、お神酒をいただく前に後見が切り火を行いますが、厳島神社では火に関しての細心の注意のためか、切り火はしないのが通例となっています。
『翁』の構成は上掛(かみがかり)と下掛(しもがかり)ではその配役が異なります。上掛は千歳(せんざい)の役をシテ方が勤め、別に面箱(めんばこ)を持ち運ぶ専門の役(この役名を面箱と言う)を狂言方が担います。これに対して下掛の喜多流では、千歳(狂言方)が面箱を兼ね、翁太夫(シテ方)、三番叟(狂言方・三番三は大蔵流の名称)がそれぞれ祝祷の歌舞を舞う形となっています。狂言方が千歳の披きを演じる際、下掛でなくてはならない所以はこの仕組みによるものです。
『翁』の様々な特異性の一つに、シテが舞台に出るときには役柄に入っていないことがあげられます。通常演者は楽屋で面を戴き役柄に入っていきます。『高砂』ならば、前場は「小牛尉」(こうしじょう)の面をかけ老人の役になり、後場は「邯鄲男」をつけ住吉の神の役になります。しかし『翁』だけは演者そのものとして舞台に登場し、舞台で面をつけ翁の役となる珍しい仕組みです。地謡や囃子方もその配置や扮装構成までも『翁』独自のものとなります。扮装は囃子方、地謡方、後見方、みな素袍上下に侍烏帽子を着用して最高の礼装にて勤めます。地謡は常の地謡座ではなく、囃子方の後方の後座に座り謡います。これは今のような地謡座がなかった舞台の名残だそうです。囃子は小鼓のみ三人の連調という珍しい形となります。小鼓方は奏者が正面見所に向い、幸流では中央を頭取(とうどり)、右隣を胴脇(どうわき)、左隣を手先(てさき)と称し、位も頭取、胴脇、手先の順となります。
小書きは他流にはいろいろあるようですが、喜多流では白式(装束や揚げ幕までが白一色になる特別演出)のみで、型自体は通常と変わらないので、『翁』の型は一通りのみとなります。
面箱を両手に掲げた千歳を先頭に、シテ、三番叟、囃子方、後見、地謡と、みな橋掛りから登場します。通常、橋掛りの真ん中は歩まないのが能役者の鉄則ですが、『翁』のみ特別に真ん中を歩むものとされています。千歳が目付け柱近くに下居すると、シテの翁太夫は舞台正面先に出て下居して深々と礼をします。一見正面席の方々にお辞儀をしているように思えるこの動作、実は上空の北極星を見上げ、そして舞台正面先に神のよりしろとされる我々の目には見えない「影向の松」(ようごうのまつ)に礼をしているのです。
シテが着座し面箱が置かれると出演者は所定の位置に着座し、まず笛の音取がはじまり、小鼓三調との演奏となります。シテの「どうどうたらりたらりら、たらりあがりららりどう」と呪文のような謡がはじまり、まず千歳が勇ましい千歳の舞を披露します。シテは千歳の舞の途中で白式の「翁」の面をつけ、舞台中央でご祈祷の謡を謡い翁の舞となります。翁の舞は右手に中啓を広げて高く掲げ、天(てん)、地(ち)、人(じん)と目付柱、脇柱、大小前にて特別の拍子を踏む舞で、最後に万歳楽(まんざいらく)と唱和して終わります。
シテは元の座に戻り面を外し、また正面先にて礼をし、翁帰り(おきながえり)といわれる特殊な退場をします。
通常シテが幕に入るときは後見が幕内でうける(礼をして演者を迎える)習慣ですが、『翁』にかぎり幕入りする大夫を次の脇能を勤める脇が装束姿で迎えます。
今迄出番のなかった大鼓はシテが幕に入ると床几にかけ、揉みの段を囃し、三番叟の出番となります。直面で大地を踏む揉みの段、続いて、千歳より鈴を手渡され「黒式尉」の面をつけて種まきをあらわす鈴の段となり、五穀豊饒を祝い舞います。農耕儀礼の芸能化といわれる『翁』の演能時間は一時間ですが、シテより多い時間、舞台の大半が狂言役者の躍動的な舞となるのも特徴の一つだと言えます。
『高砂』について
「高砂の松の春風吹きくれて、尾上の鐘も音すなり」、これは能『高砂』の真之一声といわれる出囃子でのシテとシテツレの連吟の謡です。
この謡の詞章から読み取れる場所、季節、時刻はと問われたらどうでしょう。答えは、季節は早春、場所は兵庫県高砂市、時刻は夕刻で、語意は「高砂の松に春風が吹き、日も暮れかかり、尾上にある寺の鐘も響いてくる」です。私はどうしてもこの謡に夕刻を意識しにくいのです。
厳島神社御神能は初日と二日目は翁付で始まる旧来の本式番組で朝9時より始まります。翁や脇能は、燦々とした朝日を浴び、すがすがしい気持ちで午前に演じるものと思い込んできました。能に限らず演劇は時間や場所を超越して演じるものとは承知しながらも、この真之一声での夕刻を謡う謡にどうしても少しの抵抗感を覚えてしまいます。奉納する役者は、屋外で朝日に照らされ爽快な気分で勤める、こんな厳島の習慣にすっかり慣れ親しんできたためです。
今回、能には詞章を越える役者の気分、心模様があるだろうと演じたのですが、演じるまではこれではいけないのではと答えがでませんでした。しかしなにはともあれ、演じてみて、翁と脇能は朝一番でなければと、確信しました。とりわけ厳島神社の御神能はこうでなければ・・・、詞章とは違ったこの感覚が抜けないのです。

『高砂』は本脇能ともいわれ、夫婦和合、寿命長遠、国土安穏を寿ぐ能で世阿弥作とされ、古名は相生といわれていました。
物語は、九州阿蘇の宮の神主友成が播磨の国高砂の浦に立ち寄ると老人夫婦が現れ、松のめでたさと相生(相老)の夫婦の情愛、和歌の徳をたたえるところから始まります。夫婦は実は高砂・住吉の松の神であると告げ住吉で待つと小舟で沖へ出てしまいます。神主友成が住吉に着くと住吉明神が出現して御代を祝福し、春浅い残雪の住吉の景色を描き軽快に颯爽と神舞を舞います。最後は「千秋楽は民を撫で、萬歳楽には命を延ぶ、相生の松風、颯々の声ぞ楽しむ、颯々の声ぞ楽しむ」の祝言の謡で留めとなります。
『高砂』の老人夫婦は今でいえばさしずめ別居結婚の形です。尉(実は住吉明神)は現在の大阪府の住吉に、妻の姥(高砂明神)は兵庫県の高砂に国を隔て住んでいます。互いに距離を置きながらも心は通い合っている、いや遠くに住んでいるからこそ新鮮で相生(相老)の夫婦となる、通い結婚のすばらしさでしょうか。なんとも進歩的なうらやましい神様達です。
脇能の前シテは尉ですが、この尉は喜多流に限らず老いを前面に押し出すようには演じません。謡も型も溌剌と力強さとスピードをもって神の化身を表現します。だらだらと謡うべたついた謡、よたよたとした老いの運びなどは脇能の世界には似合いません。クセの中の型どころに面白い言い伝えがあります。「掻けども落ち葉の尽きせぬは」と杉箒で左へ二つ、右へ一つ落ち葉を掻き寄せる型をしますが、これは幕府時代の大禮能の秘事の名残で、長久の久の字を逆さまに書いて演じたとされています。このような型や中入り前の「蜑の小舟に打ち乗りて」と小舟に乗る型などいずれも、力強く硬質に演じるように伝えられています。総じて脇能の尉は直線的で衒いがないのが第一、あくまでも荘重が心得との教えです。
少し能からは外れてしまいますが、中入りでアイとの問答の後に謡われる待謡。「高砂やこの浦舟に帆をあげて、月諸共に出で潮の、波の淡路の島影や、遠く鳴尾の沖過ぎて、はや住の江に着きにけり」は結婚式で謡われていますが、本来は新郎が新婦花嫁の着座を待つ時に迎え入れる心で待謡として謡われ、これからの二人の門出を祝したようです。このときは特別な作法があり、返し(同じ言葉を繰り返し謡う)の「この浦舟に帆をあげて」は二度目となるようで悪いというので謡わず、また「出で潮」の出るも縁起が悪いと「入り潮」や「満ち潮」に言葉を変えて謡うのが礼儀とされています。
話をもとにもどします。
後シテは初日に限り、七五三二一(しちごさんにいち)といわれる正式な寸法の出端で登場します。面は江戸時代の初期には「平太」や「怪士」を使用していたようで、最近でもたまに「三日月」をつけるのはこれらの名残のようだといわれています。現在は「邯鄲男」をつけるのが当たりまえのようになっていますが、本来この邯鄲男は名の通り『邯鄲』のシテ、苦悩する中国・蜀の国の青年廬生を表現して打ったものです。従兄弟の能夫はこのふくよかさを持つ「邯鄲男」を日本の神能に採用した当時の役者の芸術センスのよさに感服すると言い、私も同感です。
今回は御神能執事の出雲康雅氏にお願いして厳島神社所有の珍しい「神体(しんたい)」を出していただきました。以前よりいつかつけたいとの私の念願が叶い、よい記念となりました。「神体」はその名のとおり脇能、特に『高砂』に似合うのではと思い使用してみました。形は面長で目に金環があり、鼻がきりっと高く彩色はやや赤みがあり、一見西洋人かと思われる独特の顔です。近くで見ると凛々しさがあり、迫力を強く感じる面ですが、面長な形が私に合わないのか、私の技量不足でしょう、演じた結果、私としてはやはり「邯鄲男」に軍配が上がるように思えました。

『高砂』の小書きは各流様々にありますが、喜多流では真之舞、真之掛之舞、祝言之舞、真之留、颯々之留があります。真之舞は神舞の初段に達拝(たっぱい=立ちながら拝む動作の型)をします。真之掛之舞は掛(かかり)の段が延びて掛で達拝をします。これらは、舞のはじめは必ず達拝をするというきまりがありながら、『高砂』では「二月の雪、衣に落つ」と神舞の前に左袖を見る型があり達拝ができないので、どこかに達拝を入れようとする儀礼重視の工夫です。祝言之舞は二段目のオロシに左袖を卷く特別な型が入り、片手で中啓を持ち変える難儀な型があり上演機会は少ないです。真之留は終曲に通常二つの留拍子を三つ陽の拍子として踏むもので、颯々之留は「颯々の声ぞ楽しむ」と左右シトメをして留拍子となっています。何れも儀礼的要素が強く、芸術的な演出効果を狙った小書とは異なるものです。
後場の見どころはなんといっても颯爽としたスピードあるダイナミックな神舞です。この神舞をどのように舞えるかが能楽師にとっての課題です。非常に速いスピードある囃子の演奏に負けない舞の技術と共に風格をも兼ね備えることが必須です。私の経験から、まず脇能は『弓八幡』からはじめ、次に『養老』、最後に『高砂』を勤めるのがいいと思い、幸い私の場合は丁度その順番になったのは恵まれていました。
中学から高校時代、先代宗家喜多実先生に舞囃子のお稽古を受けたとき、まず『弓八幡』、そして『養老』、となかなか『高砂』の名前は出ませんでしたが、最近その理由がわかりました。舞囃子でさえ若造の『高砂』は似合わぬということだったのでしょう。そのためか時が経ちお許しがでた時の喜びは一入でした。演目には若く元気溌剌ですむものもあれば、それだけでは叶わぬものもあります。『高砂』はそのような曲なのです。能楽師は青年時代の修業を経て、徐々に神体らしい気品と力強さと爽やかさを兼ね備えることを目標とします。これは言うは易いのですが、どうしても時間がかかるものです。力強さが単なる粗鋼、荒々しい喧騒に止まってしまうだけではいけないという体験を経て、力強さと幽玄の調和の美を現出する、これが神能の真髄と思います。
今御神能の翁付脇能は執事出雲康雅氏が各年、その間を従兄弟の粟谷能夫と私で交代に勤めています。来年が出雲康雅氏、その次が粟谷能夫となり、私の出番は4年後ということになります。はるか先の4年後などと思っていても、時間がたつのは早そうです。今を大事により良い演能に精進しようと、この節目の今回の翁付でまた志を強く持てたことが良い経験となりました。
写真
翁 撮影 牛窓正勝
翁飾り(喜多能楽堂にて) 撮影 粟谷明生
高砂、前、後 撮影 石田 裕
(平成15年4月 記)
『鉄輪』の女の恨みと未練投稿日:2003-03-02

粟谷 明生
能『鉄輪』は頭に火を灯した蝋燭をいただく鉄輪(五徳)を載せ、怪奇な鬼の姿で形代を打ちすえる女の復讐を丑の刻詣と絡ませ、捨てられた女の男への呪いと恨みの物語です。春の粟谷能の会(平成15年3月2日)では、この『鉄輪』を勤めました。
舞台は最初にアイ(和泉流は神職、大蔵流は社人)が登場し、シテ(男に捨てられた都の女)の願いを貴船明神が叶えるとご託宣があったと口開(くちあけ)の形で始まります。そこへ前シテが笠を被り人目を忍び登場します。浮気な男と契りを結んだのは結局自分の心の到らなさの報いとは思うが、それではあまりに口惜しい、来世とはいわず今この世で罰が当たるように貴船神社に願をかけるのだと、丑の刻詣を決意します。
丑の刻詣とは時代により変様しているようですが、丑の刻(午前二時)に人目を忍んでに密かに参籠し祈願することで、特に人を呪う行為とされています。女にとって通い馴れた道とはいえ、暗闇の中を一人「糺す森」を抜け「御菩薩池」を通り、「市原野」、「鞍馬川」そして橋を渡り貴船神社に向かう片道二、三時間程の長い行程は念願成就のためとはいえ大変だったと思います。しかも七日間の参籠は、当時は衣食にも並々ならぬ不便があったでしょうから、それを押しての参籠には思い込みの凄さと恐ろしさを感じます。
アイは参拝しているシテを見つけると貴船明神のご神託を告げます。この問答の言葉は流儀により異なるため、シテはお相手のアイにより型、演技を変える必要があることを今回知りました。その問答をここにご紹介します。
和泉流はシテに向かい「丑の刻詣するのはそなたか。あなたの祈りを叶えるとのお告げがあった。先ず鉄輪の三つ足に火を灯し戴き、身には赤き丹を塗り、赤き衣を着て怒る心を御持ちあると、必ず望みは思いのままである」とまずお告げの内容を言い、それを聞いたシテは「いやいや私ではない、人違いでしょ」と言葉を返します。すると「いや確かにあなたのことだ、あー恐ろしいこと。こういう内に顔色が変わって恐ろしくなった。あー恐ろしい、恐ろしい」と退散します。これに対して大蔵流は「おい女の人よ、あなたの望みを叶えるとの明神のお告げですよ」と問い掛け、シテはすぐに「いやいや私ではない、人違いでしょ」と返します。すると「いや確かにあなただ。その訳は鉄輪の三つ足に火を灯し、顔には丹を塗り、身には赤き衣をまとい、怒る心を御持ちあれば、思う望みは叶えるとのことである、うわーこんな事を言っているうちに顔の気色が変わって恐ろしくなった、こんなところに長居は無用だ、急いで戻ろう。あー恐ろしい、恐ろしい」となります。問題はシテがどこで面を曇らせ顔色を変えはじめるかです。
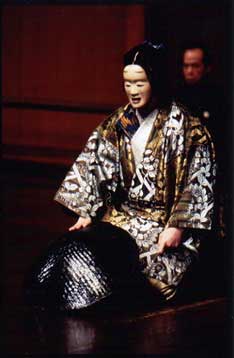
元来、喜多流は大蔵流と申合が出来ているので、「私ではない」と返事後、火を灯せ、丹を塗れ、赤き衣と聞くうちに、徐々に面を曇らせ形相を変えるやりかたが合うのです。和泉流がお相手の場合は、こちらが早めに対応をしないと兼ね合いが悪く、シテはこの違いをあらかじめしっかり把握して演技する必要があることを知りました。シテは「これは不思議の御告かな」から一変、地謡も次第に激しく囃子のテンポも速くなり前場の一番の山場となります。「恨みの鬼となって人に思い知らせん」と笠を投げ捨て、怒りは最高潮に達し中入りします。観世流はそれまでの籠められた怒りが我慢できず遂に爆発して走り込み(速足)の中入となりますが、流儀では走らずズカリズカリと力強い運びで怒りを表す教えです。走り込むエネルギー以上に演者の体から怒りや殺意が漲ってこなければならず、並大抵では出来なく能役者の技量が計られるところです。
ワキツレ(シテのもとの夫)はワキ(陰陽師・安倍晴明)に女(シテ・前妻)の呪いを調伏する祈祷を依頼します。舞台正面に一畳台と三重の高棚の作り物が置かれ、祭壇を表します。棚の四隅に五色の弊を立て、男の形代として侍烏帽子、女の形代として鬘が乗せられ、これらはそれぞれ男と新妻の象徴です。後シテの女は頭上に鉄輪を載せ赤地摺箔を着て鬼となって現れます。しつらえた祭壇の夫婦の形代に忍び寄り、捨てられた女の恨みを述べます。「あなたと夫婦の契りを結んだ時は、いつまでも変わらないと思っていたのに…。捨てられて恨めしく、でも恋しいとも思ってしまう、この苦しい思いを私にさせたあなた。もう命も今宵で終わり、お気の毒なことよ」と強い恨みの中に恋しさ、悲しさが同居している複雑な女心です。「命は今宵ぞ、痛はしや」の「痛はしや」を相手への憐れみとするか、それとも冷たく言い放つ心に扱うかで、その表現も変わってきます。
キリの仕舞所ではいよいよ祭壇に上がり、恨みが募って執心の鬼となったと迫り、まず後妻の形代の髪を手に絡ませ一撃のうちに打ち殺します。恨めしく憎いのは男であり、悪いのは男のはずですが、鬼となった女はまず同性の後妻のところに怒りをぶつけます。ここが女心の不思議なところです。後妻を殺し今度は「殊更恨めしき」と男の形代に目を向けます。私は地謡の「あだし男を取ってゆかんと、伏したる男の枕に立ち寄りみれば」の「取ってゆかん」の解釈が演ずるときのキーワードではないかと思います。「命をとる」と解釈するか、「連れ去ろう」と読み取るかでこの女の心持ちは決まります。「連れ去ろう」と解釈することで鬼にならねばならなかった悲しい女の性と激しい嫉妬心が浮かび上がるのだと私は思います。

後妻を容赦なく殺し、薄情な浮気男も殺したいほど憎いはずなのに、でももとの夫と思うと殺さずに連れ戻したいと思ういじらしい女心。願わくば夫の気持ちがまた私の方へと向いてくれればという哀願、未練を感じます。ところが、そんな頼みや願いは無残にも打ち砕かれます。男の形代には晴明の祈祷で三十番神の神々が守っていて鬼女を一歩も近づけさせません。安倍晴明の陰陽道と貴船明神のご神託による呪縛との争いとなります。
新妻はいとも簡単に殺され、男は神々が守っている、下京邊の男、つまり鉄輪の女のもとの夫は、新妻と自分の二人の命ごいをしたのではなく、自分だけ助けてくれるようにと祈祷を頼んでいたわけで、随分と身勝手な男として描かれています。
上田秋成作『雨月物語』の「吉備津の釜」は『鉄輪』の後日談のような話です。女に恨まれている男が、やはり陰陽師に祈祷を頼みます。四十二日間(女が亡くなってから四十九日間)、家の戸を閉めお札を貼っておとなしくしていれば大丈夫と言われ、男はその通りにしていますが、あと一日という日に、疲れが溜まってか、たいして眠ったつもりはなかったが戸を叩く音で起こされます。見ると外はもう明るいので、女の恨みからやっと逃れられたと喜び戸を開けてしまいます。しかしまだ外は暗かった、明るいと思えたのは満月の明かりだったのです。男は四十二日が過ぎたと錯覚して戸を開けてしまった。するとその瞬間、女が飛び込んで来て男を殺してしまうという劇的な結末です。

能『鉄輪』では、女は男に近づけず連れ去ることも殺すこともできません。結局安倍晴明の祈祷が貴船明神のご神託を阻止したことになります。しかし、最後に「時節を待つべしや、まずこのたびは帰るべし」と、今日のところはひとまず帰るが、またいつか来て必ず恨みを晴らすと消えてしまいます。男は、安倍晴明に祈祷を頼んだ後は舞台に出てきませんが、この結末を見て、ああ良かったと手放しで喜べるかどうか。世の男共にとっても肝が冷える、真底恐ろしい終わり方かもしれません。それにしても、呪い殺すと出てくるのは、死後、霊になってというのが能の通常のパターンですが、今この世に生きている間に恨みを晴らしたいと、直線的、直情的な恨みを描くところが能『鉄輪』の特徴です。幽玄な能とは全く趣向の違うこの能の直情的な感情、恨み、嫉妬を生々しくならずストレートに演じ、且つ能という枠内で表現する兼ね合いがこの曲の難しいところだと思います。
京都清水寺の森清範貫主に、何事もみな表と裏がある、その二つの真ん中には中庸があり、そこが大事であるというお話をうかがいました。能の表現法も同じような気がします。『鉄輪』では、女の嫉妬、恨みを直情的に表現するものであると断定するのも一つのやり方だと思います。また裏からの見方として、この女の本音はどこにあるのか、男への恨みは未練や恋しさの裏返しかもしれない、であるならばそこに主眼を置くような演じ方も可能でしょう。しかしそれらにはさまれた共有し得る主旨はと考えると、それはこの女の不憫さではないかと思い至るのです。それが中庸というものかなとも考えたりします。この曲を恨み呪い殺害と図式化することは間違いではありませんが、それだけではないメッセージがあるように思えるのです。

能役者が作品をどう表現するか、演者の身体が能の様式の中ぎりぎりで演じきる真実性の芝居、それは鬱屈した動きの型でもあり、内実を辛く謡うことで膨らんでこないといけないという教えを守らなくてはこの曲は演じきれないようです。型通りに動いていればよしというものではないとは充分理解しているつもりですが どんな作品でも曲の持つメッセージを深く読み込む作業を常に怠ってはいけないと、今回の『鉄輪』という曲が教えてくれたように思っています。
(平成15年3月 記)
能「鉄輪」 前、後 粟谷明生 撮影 東條睦
鉄輪の井 京都鉄輪神社 撮影 粟谷明生
面 泥眼、橋姫 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
不朽の名作『隅田川』投稿日:2003-02-01


能『隅田川』は、昭和三十年代、四十年代のころ、学生鑑賞会で頻繁に演じられていました。それというのは、当時の古文の教科書の古典芸能の項目で、能『隅田川』が取り上げられていたため、現場の先生がお能を学生に見せたいと考え、実際に見せていた時代だったからです。先代喜多実先生も、早くから学生に能を見せることを提唱され、率先して学生鑑賞会を開き、自ら多く演じられました。ちょうどそのころ子供であった私は、子方として駆り出され、実に『隅田川』子方の演能記録は六歳から十歳まで十五回を数えることになりました。
そのうち四回は普通の公演で残りの十一回は学生を対象にした学生鑑賞能でした。喜多能楽堂をはじめ、大勢の学生が鑑賞できるように、文京公会堂や厚生年金ホールなどさまざまな会場で行われたのです。十五回のうち六回が実先生のおシテでした。先生がいかに学生観賞会にお力を入れられていたか、それにも増して、先生は『隅田川』がお好きだったのではと、推察いたします。
子方で思い出すことは、私が「南無阿弥陀仏」と謡い作り物の塚から姿を見せると、必ず会場にざわめきが起こり、笑い声が聞こえてくることでした。『隅田川』という曲の最後、悲劇の絶頂となる場面で、なぜ観客の特に女学生たちは笑うのか、いぶかしくもあり、不満でもありました。母に「何でみんなは笑うの」と聞いたら、母は「あなたがかわいいからよ」などと答えていましたが、子供心に「馬鹿。あそこは笑うところじゃないよ」と思いながら舞台を勤めていたことを思い出します。今考えると、学生に最初に見せる曲としては『隅田川』は重い曲で、選曲を工夫する必要があったと思えます。
実先生が高齢になられると、次第に、当時の青年喜多会(後の果水会)の方々が代わりに勤めるようになり、その学生鑑賞会が『隅田川』の披きになった方もおられます。
私の披きは四十一歳のときの「粟谷能の会」で、子方は息子の尚生が勤めました。『隅田川』を披くに当たり、能夫に「何て言ったら、親父は許してくれるかな」と相談したら、もし駄目と言ったら「自分の子供が子方をするときにシテができないような役者では悲しいじゃないですか」と言うからと、ここまで用意していたのですが、いざ、父菊生に話してみると「『隅田川』かあー、いいねえ」の一言。この一言で終わったことが嬉しくもあり、あっけなかったことと懐かしく思い出されます。
そして、今回の日立能(平成十五年一月二十六日、於・日立シビックセンター)の『隅田川』が、私には二回目の演能ということになりました。
『隅田川』という曲は謡中心で、最初にわずかにカケリがありますが、舞と呼べるものはなく、非常に少ない動きの中でさまざまな感情を表現しなければなりません。舞う要素が少ないだけに、基本動作のシカケやヒラキ、型の模写だけでは到底叶わず、複雑で微妙な動きや謡に込められた芝居心といったものが問われます。かといって、生でリアルすぎる演技では能の能たる仕組みを逸脱し、粗末な作品に堕してしまいます。能の仕組みでの精一杯の芝居心、ここに演者の工夫が求められ、現在物『隅田川』の難しさがあるのだと思います。
我が家の伝書に「此能哀傷第一也、然れども能の哀傷は悲しきことにては無し、無常なること也」とあります。なるほど、これがスタートだな、すべてのものがこれに含まれていると感じます。『隅田川』は哀しく傷ましいお話ですが、それをただ辛く、生々しく表現するだけでは駄目で、役者の体の中でいろいろな感情や人生体験が濾過され、そこから突き抜けたもの、伝書では無常という言葉を使っていますが、そういうものが生まれてくるのだと感じさせられます。
『隅田川』はまた、狂女物の能と言われます。物狂能は面白尽くしの憑き物によるものと、思い故に自分を失ってしまうものとに分けられます。前者は世阿弥の作品にあり、憑き物によって舞い狂う表現が主流になり、後者は『隅田川』に代表される元雅の作品に見られるように、戯曲的筋道重視が特徴になっています。元雅は祖父・観阿弥の芝居的な要素と、父・世阿弥の幽玄な世界を見つめ、どちらかというと観阿弥の芝居的な要素を濃くしながらも、自らの作風を作っていったと思われます。
そして、世阿弥の物狂能がハッピーエンドの祝言性を重視したのに対して、元雅の、とりわけ『隅田川』はアンハッピーで救いはありません。この曲の終曲は子供の死を知って絶望する母の深い悲しみを描いています。元雅の手がけた曲は『弱法師』にしても『歌占』『盛久』でも、重苦しいテーマを扱い、最終的には少し安堵感を見せ、『隅田川』ほどではないにしても、最後は本当に幸せになったのかと問いたくなるような曲ばかりです。
この徹底的に描かれる闇の世界は、しかし絵空事ではなく、人間の本質や社会現象を的確にとらえています。人買いや人さらいなど、現在の私たちには無縁と思われるできごとも、昨年来の北朝鮮拉致問題を見てみれば、決して過去のものではないことを思い知らされます。いつの世でも、必要なところに強引に人を連れ去る行為は、悲しいかな存在しているようです。元雅という人は、当時の世相から、普遍性のあるできごとを鮮やかにすくい取り、その中に親子の別離や生と死という永遠不滅のテーマを提示し、不幸な結末が真実なのだ、舞台も不幸のまま終わっていいのだと一直線に描き切ってしまいます。この当たりが、元雅という天才のすばらしさで、かみしめればかみしめるほど味わいが深まります。

元雅は三十二、三歳の若さで客死していますが、彼がもう十五年、いや十年生きて、能の作品をものにしてくれていたら、能という歴史も違ったものになったかもしれないと言われるほどで、元雅という人の短い生命の中に、凝縮した輝きがあったように思えます。観阿弥や世阿弥とは違う魅力、すばらしさを、私自身も今回『隅田川』を演じながら強く感じることができました。
さて、ここからは『隅田川』の舞台の進行にそって話を進めてみます。まず舞台はワキ(渡し守)の名乗りから始まり、ワキツレ(旅商人)の登場となり、二人の問答によって、シテが女物狂として紹介されます。狂女が来るから船を出すのを待とうと状況設定をさせるのはワキツレであり、さらに船中で、向かいの岸で念仏の音が聞こえるが、あれは何ごとかと、ワキに物語をさせるのもワキツレです。シテとは一度も言葉をかわさず、何の関係もないこのワキツレの登場により、物語を展開する手法は、元雅の巧みな作風であると感じます。
ワキはといえば、最初は粗野な地元の渡し守ですが、船中で子供が死んだ経過を語る重要な役どころであり、シテが探していた子が、まさにその子であるとわかったときの嘆きによって、シテをいたわるやさしい渡し守に変身していく様を表現しなければならない大役です。
シテは物狂という、一つのことに思いつめる、つまり、人商人にさらわれた子供を探して都から東国の果てまでやってきたという、物思いを持って登場します。そのときの一声「人の親の心は闇にあらねども、子を思う道に迷うとは…」の謡が非常に難しいところです。『隅田川』という曲は位取りも高く、大変重い曲ですが、ただ重苦しく暗い表現だけでは駄目で、慕情を込めながら強い訴えかけがなければなりません。登場した段階では、まだ子供が死んだとは知らず、都から遠い東国まで旅するだけの希望も気力もあります。希望は持っているが、子供と別れ別れになっている今の境涯が悲しいという表現にならなければいけないはずです。

ただ重く暗く謡うと、先人たちは「駄目だね、子供の死を知っているような謡い方だ。隅田川の白頭かい、老女物じゃあるまいし」などと言われたようです。
シテは笠を着け狂い笹を持っての扮装ですが、この笠をかぶると、耳は鬘髪と笠の紐で塞がれ、自分の声が普段のように聞こえないのです。この悪条件のもと、謡いづらく、大事な第一声が余計にプレッシャーになり往生するところです。その後に続く、地謡の「松に音するならいあり」は、他流の調子を張ってさらりと謡うものとは違い、喜多流は独特の陰々滅々と謡うのが伝承であります。そのため、地謡の音の高さを誘い出すためにシテ謡が、とりわけ暗く低くなりやすいのです。
伝書に「初めより哀をみゆるもの嫌うなり」と注意書きがあり、演者の心得としては肝に銘じる大事であります。
シテが登場して船に乗るまで、ワキとの問答が前半の一つの山場です。在原業平の「名にし負はばいざ言問わん都鳥」という和歌を織り込んで粋な問答を繰り広げ、都の女の優雅さ、凛とした姿を見せてくれます。ここは美しく進め、遊興の趣があってよいところです。この辺から舞台に死相が出ているようでは作品の意図するものでなくなります。業平は妻を想って歌を詠み、この母親は子供のために詠うという、実にやり取りの面白い場面、その後の地謡、「我もまた、いざ言問わん都鳥」の段はぐんぐんとテンションを上げ華やかに謡い上げるところです。こういう華やかさを、この寂しい曲の前半に持ってくるところに元雅のうまさがあるように思えます。
シテの面は本来喜多流では「曲見」とされていますが、今回は、曲見よりはやや若い感じの「深井」を使いました。「深井」は「曲見」より表情に生活感が表れず、まだ仄かに艶が残る顔立ちだと思います。今回は「深井」で、都北白川の女を創造してみたいと選択しました。
渡し守の嫌がらせにも屈せず狂女は船に乗り込み舞台は一変、船中となります。なにやら向こうの岸から大念仏の声が聞こえてきます。大念仏とは大勢で念仏を唱えることをいい、おそらく平安後期の良忍(1072?1132)の説いた「融通念仏」の影響を受けているのでしょう。一人で念仏を唱えるよりは、多くの人が念仏し互いに融通し合って往生するという思想で、この阿弥陀信仰が以後の時宗へも影響を与えたのではないだろうか、室町時代の能の聴衆にも通じるものがあったのではないだろうかと私は思っています。
船中では、旅商人(ワキツレ)にうながされ、渡し守(ワキ)が梅若丸の最後を語ります。最初は人ごとに聞いていた母(シテ)が、都北白川と自分の里の名前が出た瞬間に聞き耳を立て、吸い込まれるように聞き入って、最後、その子が死んだとわかると愕然と力が抜け母の心の支えである希望の糸は絶たれます。川を渡る間に、子供は生きているという希望から、死んだという絶望へと場面転換が起こります。隅田川はあたかも生と死をわける川のようにとうとうと流れ、あちらの岸はまさに彼岸となります。
渡し守の語りが終わって、船が向こう岸に着いても茫然として立ち上がれない母(シテ)。死んだ子というのは本当に自分の子なのか。それは「いつのことか」「どこの者か」「父の名は」「稚児の年は」「稚児の名は」と聞きながら、確かに自分の子だと絶望の淵に落ちていく、そのワキとの問答の謡も難しいところです。母の昂ぶった気持ちを表現しなければならないけれども、あまりにリアルに生っぽくなってはいけない。劇的に演じることと生になることの境の難しさを痛感するところです。それをいかに表現するかが『隅田川』という曲全体のテーマであり、最初に述べた、能の仕組みの中での芝居心の葛藤となるのです。
女物狂の子供が、今まさに大念仏している子だと知ると、渡し守は母(シテ)をいたわり、そっと手を添えて、塚の前まで導いていきます。
役者の意識も前半の女物狂から後半は母そのものへと変化します。その変化は例えば足の運び方にも表れます。前半は普通の運び(摺り足)ですが、船中で愛児の死を知らされ、船を降りて塚まで導かれて行くときから、運びは老いの足(抜く足、切る足)といって、力のない、よろけるような運びに変わります。ここで舞台上での工夫を一つ。最後の場面で子供(子方)の姿が見え始めると一瞬普通の運びにしますが、また我が子が消えると老いの足に戻します。先人、先輩がここを上手に演じられていたのが、目に焼き付いているのです。いつか自分もあのようにやりたいと。でもこういうのはなかなか言葉で教えてもらうものではないようです。父がよくいう口癖、観て盗む、これしかないなと、はっきり解った一場面です。
塚を案内されクドキの謡を謡い、塚を掘り返せと渡し守に迫り泣き崩れる母。そして地謡がもっとも静かにしっとりと無常を謡う「残りても、かひあるべきは空しくて」の段、ここをシテは下居して静かに聞きます。現在物のこの能にあって、唯一幽玄的な雰囲気で演じる者が冷静に悲しみを感じ取れるところだと思います。
そして、念仏の段で弔いが始まりますが、実際に鉦鼓(しょうご)をチーン、チーンと打ち鳴らします。鳴らさない人もいますが、私は鉦鼓を一つの楽器として使うことで、その効果音がより一層の悲しみを表すのではと思っています。音のたて方も様々で、父は「南無阿弥陀仏」と繰り返し謡う中で「な・だ・あ・み・ぶ・つ」と当てて打ちますが、私は「なむあみだぶつん」を逆さまにして「ん・つ・ぶ・だ・み・あ・む・な」と当てて打てと教わっています。この打つ個所を微妙にずらすやり方は意味がないように思われるかもしれませんが、こういう込み入ったことに神経を使うことで、シテの感情が過度に高まらないように、生っぽくならないようにという、演技上の工夫であると聞かされています。
念仏の謡に子方の声が聞こえ始めると舞台はクライマックスになります。今回は六歳の友枝雄太郎君が小さいながらも最初から作り物に入って立派に勤めてくれました。梅若丸の年齢は十二歳ということになっていて、確かに人商人がさらっていくのには、労働力としての期待があったわけで、ある程度の年齢でなければならないでしょうが、能『隅田川』という舞台ではやはり小さい子の方が、その幼さゆえにより涙を誘い、効果的のようです。
塚の中にいて長い時間待つのは、ワキ座にじっと座っているよりは、中で何をしていてもいいので気楽ではありますが、それでも閉鎖的な空間は息苦しく、私も経験がありますが、あまり居心地のいいものではありません。そこを頑張って我慢し、一生懸命大きな声を出してくれた雄太郎君、将来が楽しみだと思いました。
子方を出す出さないについては、観客の方にもいろいろな思いがあるようです。申楽談議の第三段には、世阿弥と元雅が子方の演出の考え方の違いを語る有名な話があります。
「隅田河の能に、内にて、子もなくて、殊更面白かるべし。此能は、現はれたる子にてはなし。亡者也。ことさら其本意を便りにてすべし、と世子申されけるに、元雅は、えすまじき由を申さる。かやうのことは、して見てよきにつくべし。せずは善悪定がたし。」と。
世阿弥が子方は亡霊なのだから、本意を生かし、子を出さない方がよいと忠告したのに対して、元雅は「えすまじき」、「出さなくては演じられない」と強く反論しています。最後に父・世阿弥は「して見てよきにつくべし。せずは善悪定がたし」、「そうだ、演じてみてよい方を選べばいいね」と言ったということで、世阿弥の父親としての懐の広さが出ていて、この名文は現代にも通じる教育法ではないでしょうか。
子が出ない方がよいという意見は、塚から出た子方とシテが追いかけっこになるようで嫌だということらしいのですが、喜多流の型は、シテと子方が向き合って互いに手を上げ、子方はするりとシテの後ろに廻り込み塚に入るというもので、私には追いかけっことは思えないのです。多分他流のをご覧になってのご意見ではないでしょうか。私が子方のとき、シテの手の上げ下げに合わせるようにと言われ、実先生のお相手で特に重々しい立派な上げ方には子供心にゆっくり、ゆっくりやらなくてはと自分に言い聞かせていたのを覚えています。
ある作家の方が子方の起用について、塚の後ろからチラチラ出没して、子方特有のボーイソプラノで謡われては邪魔だ、と書かれていますが、そうでしょうか。ここに私が感銘を受けた観世銕之亟先生のご意見の一部をご紹介させていただきます。
「我が子の死を弔う念仏を唱和するなかに、子供の明るくて元気な声が突然混じり合った時に、鮮烈な生と死を感じさせることが出来るのです。(中略)子供の幻影を追い求めるところから夜明けとなり、広大な関東平野を流れる大河と母の世界でこの曲を終わらせるということが大事で、子方が出ないと情緒的に流れたままで終わってしまうことになります。子供の声、姿が失せてしまった後に広大な母なる大地の広がりと、ドラマの広がりとが合体して終わることで、この隅田川の曲がいかされるのではないでしょうか。」(銕仙421号)
私も元雅や銕之亟先生のように、子方を出した方がよいと考えます。出さなければ、演劇として『隅田川』という作品を観ることに、全く救いはなく、観客もそして演者もこの暗過ぎる気持ちをどのように処理していいのか、多分戸惑うことになるでしょう。子方の登場は観客や演じる私の心に何かしらのやすらぎ、安堵感を生じさせてくれます。また昔こんなお話があったのだ、と気持ちを落ち着かせてくれる要因にもなります。そしてなんといっても究極は、私自身、子方と共に作るこの場面が役者冥利に尽きる最高の見せ場であると思って疑わないからです。
そして終曲は、子の亡霊が朝日の光によりかき消され、立ちすくむシテの姿を描きます。もう二度と子供に会えない、これからどうして生きていったらいいのかという絶望の中の、広大な関東平野の無常な夜明けです。もう一方で、この塚から私は決して離れないという塚への愛着。この二面性を、じっくりと脇正面から正面へ空を見上げる型と、塚に手をかざしてじっと見込み、最後に正面を向いてシオリ(泣く型)だけで表現します。ここはまさに能ならではの表現だと思います。
燃え盛る憤怒と悲痛を少ない型で表現する難しさ、感情を露骨に出しては品がなく、型をこなすだけでは真実味に欠け、きれいごとの動きだけでは本物とはなり得ない。『隅田川』とは役者がいかに生きてきたか、どの程度できるか露呈してしまう、まさに踏み絵のような曲です。自分がこれまでに仕込んで蓄積したものを通して、いかに理解し表現したかを如実に語ってしまう曲なのです。
元雅という天才が生み出した永遠不朽の名作『隅田川』。今の時代でも古びない、現在に生きている我々にもその叫びがまっすぐに伝わってきます。世阿弥が確立した舞と歌の二曲で構成する能とは異質でありながら、異彩を放つ元雅の能。謡を中心として劇的感動的に展開する現在物のこの戯曲を、能として成り立たせるためには私もまだまだ課題がたくさんあるようです。だから一回や二回ではできない。披きのときよりは今回の方がはるかに手ごたえがありましたが、私はこれからもこの傑作を三回、四回、いや五回、六回・・・とやり続け、完成型に持っていきたいと思うのです。
(平成15年2月 記)
写真撮影「隅田川」東條睦
スタンプは木母寺
『絵馬』女体の力神を演じて投稿日:2003-01-03


平成15年の「新春・能狂言」・喜多流『絵馬』女体(シテ友枝昭世、地頭粟谷菊生)が、1月3日午前7時よりNHK教育テレビにて放送されます。
喜多流の本来の『絵馬』は、後シテ(天照大神)が男神として面・東江(とうごう)をつけて現れ、荒々しく神舞を舞った後、二人のシテツレの天女が神楽の相舞(あいまい)で、シテを岩戸の作り物から引き出す演出となりますが、「手力雄の明神引き開け…」という詞章と合わず、作品の構成としてやや問題が残る形です。それに比べ「女体」の小書がつくと、本来の天の岩戸隠れに沿った演出となり、シテは女姿で、女ツレ・天女=天鈿女命(あめのうずめのみこと)と男ツレ・力神(りきじん)=手力雄命(たぢからおのみこと)を従えての登場となり、舞台は豪華絢爛たる展開となります。
シテは女面(通常小面、今回は増女)をつけてスピードある神舞を舞います。狭い視野を強いられるなかで、修練した高度な技と役柄としての貫録、この二つを必要とし、流儀では重い習いとされています。
実はこの小書は囃子方泣かせで、シテの神舞五段に続いて天女の神楽、そして途中から力神の急之舞と変化に富んでいるため、これらを囃すには達者な顔ぶれが揃わなくては成立しません。観世流のシテがゆったりとした中之舞、天女の神楽、そして力神の急之舞となるのに対して、喜多流は初めから早い舞となり、神楽で少し緩んだかと思うと最後にまた急之舞でもっとも早い舞となり、奏す囃子方も技と体力を必要とするやり甲斐のある曲であることは確かです。今回も抜群のリズム感と音色鮮やかなお囃子方の面々、笛は一噌幸弘氏、小鼓は大倉源次郎氏、大鼓は亀井忠雄氏、これは前回、ご好評の中日名匠能と同じ方々で、太鼓はご都合により金春惣右衛門氏から助川治氏になりましたが、その演奏のすばらしさは聞き応え十分です。
力神は急之舞を舞うため『道成寺』を披いた者でなければ勤められない決まりがあり、私の力神の披きも『道成寺』演能後、平成7年の「粟谷能の会・大阪公演」(シテ粟谷能夫)においてでした。以後「大坂城薪能」(シテ粟谷菊生に代わり粟谷能夫)、「粟谷能の会・福岡公演」(シテ粟谷幸雄)、「中日名匠能」(シテ友枝昭世)にて勤めてきて、今回が5回目となりました。
力神を演じる難しさは、安座して、神舞、神楽の舞を待つ間の足のしびれの心配と、いきなり急に激しく舞うテンションの高さをどのようにするかのコンディション作りです。そしてなによりも力神としての力強い役柄が舞台に表現されないといけないのです。岩戸隠れの話では天照大神が岩戸に隠れると、神々が相談して外で面白く皆が楽しんでいれば、きっと天照大神も外を見たくなるだろう、そして岩戸を少し開けたその時、約束通り力持ちの手力雄命が岩戸を開ければ…と神々が相談し仕組まれた話です。この時の注意を誘う天鈿女命の舞が、お臍を出しながら色ある舞を舞い神々が喜んだという我が国最初のストリップであることは、古事記に書かれよく聞く話で、神楽の始めとされています。また御神楽とは別に里神楽の伝承などでは手力雄命は宴席で居眠りを始め天鈿女命に起こされるというものもあり、それらの引用から能『絵馬』の戯曲が出来上がったかもしれないと想像してしまいます。
力神の舞は、神楽の終わりに天鈿女命が御幣を振り上げ力神に合図を送りますが、それに応えて左手で天女を強くさし、面を切ります。このタイミングも難しく、天女との呼吸が合わなければこれからの舞が舞いにくくなります。私は安座している途中から徐々に面を曇らせ(下を向く)寝ている風情にも見せ、いざそのときが来ると強くしっかりと面を切る、これで強調されて見えると教えられてきました。天女は華麗に艶をもって、力神は力強くダイナミックに重量感をだしてが信条です。
今回、シテがはかれた赤地指貫は粟谷家蔵ですが、今までほとんど使用したことがありませんでした。友枝昭世氏がこの曲で起用したことにより、この装束まさに息を吹き返したかのようで、天照大神にぴったりと合いました。私もいつか『絵馬』女体を勤めるときは、是非使用したいと思っています。(平成14年12月 記)
写真 初演「絵馬・力神」 粟谷明生
『松風』のシテツレを演じて 投稿日:2002-10-17

粟谷明生
平成14年10月17日、広島県、宮島厳島神社能舞台の観月能にて『松風』(シテ=友枝昭世)のシテツレを勤めました。
厳島神社能舞台での演能は、毎年4月16日から始まる三日間の桃花祭御神能が恒例の行事として行われていますが、観月能は中秋の名月を背景に、ここ5年程前より友枝昭世氏により(主催=厳島観月能実行委員会、中国新聞社、友枝昭世の会、特別協賛=積水化学工業、住宅カンパニー)公演されています。

観月の名にふさわしく、日時は、天候、月の加減などを考慮して決められ、開演は夜6時半の満潮に合わせて始まり、特設の照明効果により舞台は美しく海の上に浮かび上がり独特の趣をかもし出しています。御神能の時は切戸口(きりどぐち)を使用するため、橋掛りの後方の壁板ははめたままとなり、舞台裏には仮設の通路が設置されますが、観月能では切戸口を使用しないため、橋掛りの背景には海が見え開放感を味わうことができます。
そのためすべての演者の出入りは本幕からという昔風の古い手法で演じられます。見所は回廊に椅子を並べ、また近年は特設桟敷席が作られるようになりましたが、見所からの美景とは反対に、演者側の感じる舞台状況は優美な世界とはかけ離れ、やりにくいものとなっています。
舞台を美しく照らす照明ですが、その光は、面をつける私達演者の目に入り視界を狭めてしまいます。周囲一面真っ暗に見えるため、演者は見当や方向を見失う危険にさらされます。また舞台の床板は平素吹きさらしの状態のため滑りが悪く、板は波打ち通常の運び(はこび=歩行)のようにはいかず、覚悟はしていましたが、舞台に立ってみるとかなりの戸惑いを感じました。しかしこれほどの過酷な条件下にあるにもかかわらず、私や観る人に少しもその不自由を感じさせずに舞う友枝昭世氏には、改めてその強靱な足腰、完熟の芸に圧倒、魅了され、敬服してしまいます。
私は今年47歳、そろそろ『松風』のシテツレをする機会も最後かもしれません。初めて父菊生のシテツレを20代で勤めてから幾度か勤め、7年前にシテを披き演じてみると、シテツレという立場がどうあるべきか、どのようにしたらよいかが、少しずつでもわかってきました。今回はそれらの経験をもとに勤めることを心掛けました。

本来シテとシテツレの登場は橋掛りで謡う真之一声(しんのいっせい=出囃子の名称)といわれるものですが、今回は特別に普通の一声(いっせい)で登場し、「潮汲み車わずかなる浮き世に迴る心かな」と謡い、続いて二の句といわれる「浪ここもとや、須磨の浦」というシテツレの謡につなげます。ここがシテツレ独吟の最初の謡いどころとなり、シテツレとしての位やその演者の技量の程度までが決まると言える大事な謡です。謡の位が重すぎてはシテツレとして失格、軽すぎて世界が広がらないのは問題外と言われ、演者としては悩むところです。舞台に出る間際、小鼓の横山貴俊氏にここの位について、「どの程度の位で謡うのがよいのか、たっぷり謡うべきでしょうか」などとお尋ねすると、「『松風』という曲は銀座のクラブナンバー1という気持ちです。少しやくざなんです」と答えられました。先日勤めた『野宮』の御息所の高貴な謡と比べると、なるほど『松風』の位の位置づけはそうかと思い、その言葉で『松風』に似合うシテツレの位取りが、電光石化閃いて、同時にその答えの面白さに妙な緊張が解け気持ちが楽になって、力まず謡え助かりました。
『松風』のシテツレはシテとの連吟が多く、その謡は重要です。シテツレとしての謡がシテに頼り寄り掛かるようなものでは、シテは疲労しストレスが溜まり良くありません。かといって、自分の勝手な調子を押し通す謡ではシテツレの立場をわきまえていないことになります。存在感がありながら出過ぎず、しっかりとシテを支える、これがシテツレの第一の心得と思います。言うは安く行うは難しですが。

私はかねがね、難しいシテツレの謡が三曲あると教えられてきました。ここがうまく謡えれば一人前、次の段階に進めるのだと思い強く意識して謡い、また聞いてもいます。その三曲とは、『葵上』の「四阿(あずまや)の母屋の妻戸に居たれども」と、『砧』の「宮漏高く立って風北にめぐり」、そして『松風』の「幾程なくて世を早う」です。『葵上』はシテの怒りを誘い出す謡、『砧』は囃子方もアシライを止めるほど、じっくりと独唱する聞かせどころ、『松風』は姉、松風の心を狂わす仕掛け人の謡です。それぞれ皆シテの心を奮い立たせ、導火線に点火する触発の謡と教えられてきました。とりわけ『松風』のそれは難しく、ツレとしての音の張りや高さを持ちながらも、決して調子をはずさず、しっかりと火をつけなくてはいけない難しい謡いどころです。ここが成立していないと、シテが次に進めないといっても過言ではないぐらいです。
シテ方能楽師にとってシテツレという役はシテ役への一つの関門です。『山姥』を舞うには、あの長時間座り続ける肉体的苦痛をシテツレ「遊君百魔山姥」という役を通して体験しておくべきで、『松風』を勤めるにはシテツレ「村雨」という役を通しての難しい謡やシテと連動した動きを習得しておく必要があります。シテツレの経験が少ないのに、一足飛びにシテにシフトしては、型としては成立しても訴えの弱い能、痩せた能になるのは当然です。今の喜多流の状況があまり威張れた状態ではないように思うのは私個人だけでしょうか。
能楽師はまず舞歌の稽古、つまり謡と舞の稽古から始まるといわれますが、一方子方の稽古のように能の舞台としての稽古も並行してはじまります。青年期になると子方からシテツレへと移り、徐々に役がつくようになります。役がつけば一生懸命稽古し、時には失敗をしながらも段階を少しずつあげ、これから何回も舞台に立てるようにと心掛け精進します。その結果、次第にシテを勤める機会に恵まれるのです。シテの立場にたつと、今までやり残してきた山積みの課題が見えてきて、それらに取り組むためひたすら稽古に打ち込むこととなります。この夢中で稽古一筋に取り組む時期が大切なのは言うまでもありません。そして次第に広範囲に目を向け、演能に役立つものはすべて吸収し稽古する心、単に芸達者になるというのではなく、自己の演技を自分で確立しうる人になるということ、つまり「能を知る」必要を感じ、皆それぞれ個人の次にやるべきことに向かい修練し、一人前の演者になるのだと聞かされています。父は言います。本当にお金のとれる舞台ができる能楽師になれ!と。それが一人前ということだと。

私はシテが充分にできる演者がまたシテツレという役柄に戻ってきたときに本当のシテツレが出来るのではと思うのです。世阿弥は却来(きゃくらい=高い境地に達した後、また下位の境地に立ち返ること)という言葉を使い、上三花(じょうさんか=曲や演者のレベルが最高位)から下三位(げさんみ=曲や演者のレベルが低い位)へ却来する、つまり最終の本物の芸とは最高位を経験したものが曲のレベルが低いものを演じたときでも、単に表面的なおもしろさに終わらせず、曲そのものの豊かな広がりを感じさせるということで、この本物へたどり着く過程で却来をすすめています。
私はこの却来の流れを自分の理想の規範においています。今、身近ではシテツレから徐々に始めるという、時間のかかる手法が少しないがしろにされ、手短かに易くシテを舞う機会が多くなっているように見えます。誤解しないでいただきたいのですが、私はこれからの人に早いうちにシテを勤めるのがいけないといっているのではありません。本物になるためには時間をかけた下積みのしっかりした芸も同じように必要であり、それがシテツレの勉強、稽古であると、まずシテツレの役が沢山つくように日頃の修練が大事だと言いたいのです。そうでなければ、よい能が出来ぬシテや、シテツレも出来ない中途半端な能楽師が氾濫するような気がするのです。本物の芸の華を咲かそうとする栽培方法をもう一度、今の大人たちが再考する必要があると、今思い始めています。
(平成14年10月記)
写真 能舞台裏
回廊より鳥居
特設桟敷席より橋懸り
橋懸りに立って
撮影 粟谷明生
『野宮』での心の作業投稿日:2002-10-13
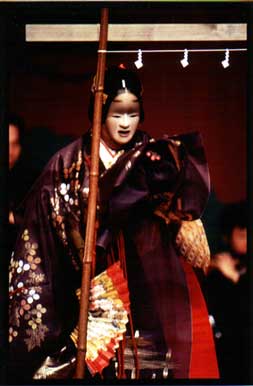

能楽師を志し、それを生業とするならば、一年に一番は心体ともに駆使するような大曲に挑み、つい緩む己自身にねじを巻くように鍛え上げる機会を自ら求めなければと思うようになりました。秋の粟谷能の会(平成十四年十月十三日)の『野宮』はまさにそういう試練の曲で、私にとっては大きな一番となったのです。
『野宮』は源氏物語を題材にし、もの寂しい晩秋の嵯峨野を舞台に、光源氏を愛した六条御息所の狂おしいまでの恋心と諦念を描いています。源氏物語「賢木の巻」や「葵の巻」を中心に、源氏と御息所の関係や背景をある程度理解したうえでないと、能『野宮』を観るのは苦しいはずです。これは観る方だけでなく、我々演ずる方にも言えることで『野宮』という曲の位の高さであるとも思われます。
そこで、『野宮』という曲に触れる前に源氏物語に目を通し、源氏と御息所の関係や人間像、二人の間で起こったできごとなどを自分なりに整理し稽古にかかりたいと思いました。この作業が、能『野宮』を演じるのに必要か不要か、演者はあまり考えすぎるとろくなものにはならないという声も聞きますが、自分自身舞台上での何かの助けになるのではと試みてみました。
御息所は十六歳で東宮妃(皇太子妃)になられますが、二十歳で東宮が突然亡くなられ未亡人となってしまいます。東宮妃としてのプライドが高く、一途な性格の持ち主だったようです。東宮妃として将来を約束されていた方が、いきなり東宮の死にみまわれ、いくら高貴の出とはいえ、経済的、社会的地位を失い没落していく寂しさを感じていたことは間違いありません。そこへ現れたのが光源氏です。七歳年下のプレイボーイ。年下とはいえ、経済力があり、恋の遊びにはたけています。年上の女性、藤壺との禁断の恋も経験ずみ、高貴で教養があり美貌の夫人に興味を持ったのも自然の成り行き。御息所の寂しい心にすっと入って虜にするのはそう難しいことではなかったのでしょう。御息所は簡単に源氏の誘惑に負け、恋に落ちていきます。源氏十七歳、御息所二十四歳のことでした。
これが御息所の間違いの始まり、不幸の始まりだったのです。手に入れた女性には興味がなくなるのがプレイボーイの常、次第に源氏の訪れは間遠になっていきます。御息所の幸せな期間は短く、悲しみの時間が長い、薄幸不運な生涯を生きた人というのが、御息所の大前提になっています。
御息所はプライド高く、教養があって美貌の持ち主、申し分ない女性ではありますが、このプライドの高さが一つの落とし穴になって、車争いをめぐる正妻への激しい嫉妬に結びついていきます。
夕顔や葵上に嫉妬を感じ始めたとき、御息所はこんな恋をしてはいけない、この恋は成就するものではないと察し、御代替わりで、娘が伊勢斎宮として選ばれた段階で自分も伊勢に行ってしまおうと、一度は決意しています。
そんな折、葵上との車争い事件が勃発します。ある日賀茂の斎院の御禊があり、その行列に源氏が出ると聞き、御息所も見物に出かけます。そこで後からきた葵上の車と出くわし、車置きの場所で争いになり、権力の衰えつつある御息所は無惨にも車を押しのけられてしまいます。御息所の車と承知の上での雑仕等の乱暴、この屈辱を受けたことが、御息所の敗北感と葵上に対する恨みへ増幅していきます。そして、葵上が妊娠していると知ると、生き霊となって葵上に取り憑きます。自分の意識ではもうどうにも制御できない、恐ろしいまでの恨みであり嫉妬です。そしてついに葵上を呪い殺してしまうのですが、そのとき源氏に自分の生き霊の姿を見られてしまい、これで源氏に自分の本性を知られてしまった、本当に嫌われてしまったと絶望します。手を洗っても髪を洗っても、葵上の物の怪を払う祈祷時に使われていた芥子の実の匂いがとれず、その絶望感は一層深いものとなっていきます。
ここで御息所は完全に伊勢に行くことを決心します。葵上亡き後、次の源氏の再婚相手は御息所ではないかと世間では噂されますが、そんなことはない、源氏の心が冷えきっていることを知っているのは御息所自身です。伊勢に行くことをもっと早く決断していればこんなに嫌な思いをしないですんだかもしれないと思いつつ、源氏を思う気持ちを断ち切れず、最後に大きな傷を負ってしまう御息所。『野宮』の謡「物見車の力もなき、身の程ぞ思ひ知られたる。よしや思えば・・・」に、その万感の思いが込められている気がします。
伊勢に行く前に皇女は精進潔斎のために、一時宮にこもります。その宮が嵯峨野にある野宮。御息所も娘につき添い、野宮に引きこもっています。そこに源氏の訪れです。源氏物語では、源氏は伊勢に行く御息所にご挨拶もしないのは礼儀知らずで無粋な男だと思われてはまずい、世間体を気にして出かけたように書かれています。愛情というよりは世間体。もう二度と逢うことはないだろうから、御息所の鎮魂のためにも一度は行かねばという気持ちだったのでしょう。それでも嵯峨野に入ってみると寂しい秋の風情です。もののあわれが加わると、一度心を動かした女性への愛しさが蘇ってきます。源氏は榊を神垣にはさんで御息所に歌を送ります。歌のやりとりの後、禁忌の野宮にずうずうしくも入っていく源氏、それを拒むことができない御息所。そして一夜の契りを結ぶことに。それが謡の詞章に繰り返し出てくる長月七日、あの日なのです。
御息所にとって、長月七日はどういう日だったのでしょうか。源氏との恋は終しまいにする、あれほど心に固く決めていたのに、なぜ受け入れてしまったのかという後悔の念であったか、それともあの日を自分にとって永遠の日にして大切にしまっておこうとしたのか。ここをどう解釈するかによって、前シテのイメージのふくらませ方が違ってきます。私は、長月七日を永遠のものにし、これにより救われないことになってもいいという強い情念ではなかったかという気がします。仏の世界から見て身の程知らない、これでは成仏できないと言われても仕方ない程の愛執、これが最後の「火宅留め」にもつながっていくと思うのです。
御息所はその後、娘が斎宮としての伊勢神宮奉仕が終わると、ともに都に戻りますが、間もなく重い病の身となってしまいます。源氏は今をときめく内大臣。死を悟って尼になった御息所を見舞うと、御息所は娘の将来を源氏に託します。幸薄い、短い生涯であったと思われます。
ざっと源氏物語を整理してみました。これが私が『野宮』を演じるために、原文や解説を読み込んでベースにしたものです。そして次は、演者が謡本という台本を通して何を読み込むか、能作者はこの能に何を言わせたいのか、能『野宮』をどのように表現し世界を創り上げるか。源氏物語原文の読み込みは、台本を読み解くための一つの手段と言えるでしょう。ちなみに『野宮』の作者は世阿弥と昔の喜多流の謡本に書かれていましたが、今は金春禅竹作が定説になっています。
『野宮』の構成は、前場で賢木の巻を基に晩秋の野宮に源氏への想いを語る御息所、後場は車争いの場面を再現して舞台には登場しない対葵上との世界を創り出し、源氏の来訪を回想しての序之舞、破之舞を舞い、再び車に乗って火宅を出たであろうかと終わります。
ここからは、私自身の能『野宮』を通して順を追って振り返っていきたいと思います。
まず、後見が小柴垣のついた鳥居の作り物を舞台正面の先の方に持って出ます。喜多流の作り物は正方形の台輪に鳥居を立て、台輪の左右の辺上に小柴垣を取りつけて、台輪の内を神域とし、外と区別していますが、観世流では台輪を使用しませんので小柴垣はその左右に張り出す形となります。喜多流の小柴垣のつけ方ですと、作り物に榊を置く型や足を踏み入れる型が、正面の限られた人にしか見えないので支障があることは承知しているのですが、今回は披きであるため、敢えてそれには触れず、従来の手法に従い勤めました。
面は本来「小面」となっていますが、これまで説明してきたような御息所像を思うと、小面では少々難があり、多少大人っぽい小面を選ぶとしても、やはりそこには限界があります。理知的で少しヒステリックなものが良いのではと、今回はお許しを得てやや柔らかい表情の「増」を使用いたしました。
前シテは次第の囃子で登場します。里女と謡本に書かれていますが、ここは確実に御息所の霊の意識です。ゆったりと囃す次第にゆっくりゆっくり執心を引きずりながらの登場ですが、ワキの「女性一人忽然と来り給ふ」の言葉通り、この女性は霊界から一瞬のうちに嵯峨野に舞い降りてくるという、この世のものでない不思議さと存在感を漂わせ、運びにもゆっくりとした想いと、忽然として現れるスピード感が同居しています。単に鈍重な物理的歩行にとどまらないが心得で、この次第のノリと運びの難しさではないでしょうか。
そして作品の主題となる次第の謡、ここの謡に緊張と不安がふくらみます。何度と稽古を重ねても、本番当日での状態でどのように声が出るかは本人も判らない未知なもの、曲の主題を謡う大事な瞬間であるから尚更そうなるのです。「花に慣れ来し野宮の・・・秋より後はいかならん」は、この野宮のあたりで、咲き乱れた花を眺めて楽しく過ごして来たが、秋が過ぎ花の散ってしまった後はどんなに淋しいことだろうというほどの意味で、秋を飽きに掛けて源氏に飽きられ捨てられたれ淋しい御息所の心情を謡います。ここをどのように表現出来るか。次第はシテが作品をいかに把握出来ているかを試されるところで、集中度の高さが要求され、演者には一番怖いところです。
忽然と現れた御息所の気位の高さはワキとの問答の中に隠されています。能の多くの場合、執心に悩む霊は、僧に成仏を願うため現れますが、御息所の場合は、長月七日は源氏との最後の契りを結んだ大切な日、宮を清め御神事をするのだから関係のない人は僧でもさしさわりがある、「とくとく帰り給へとよ」と強く訴えます。他にはみられない手法で御息所のプライドの高さが表されます。
私は前場で次の三ヶ所が好きで、いつも謡ながら興奮してしまうところがあります。それらは謡と型の融合するすばらしい見せ場と思っています。一つは初同の「うら枯れの、草葉に荒るる野の宮の・・・」と入り、「今も火焼屋のかすかなる、光はわが思い内にある、色や外に見えつらん、あらさびし宮所、あらさびしこの宮所」です。火焼屋から漏れる光が源氏にも見え、また自分の魂にも見えるのでしょうか。その光は遠くに消えていくかと思うと、不意に自らの胸にすーっと入りこみ、体をめぐり、女性そのものをほてらせます。目付柱先をじっくりと見、次第に正面に直し、とくと一足引いて左に廻るという簡素な型付けのなかにも、謡い込まれるものはエロチシズムにあふれています。「あらさびしこの宮所」とは、ほてる肉体を持つ己の悲しさ。寂しいのは嵯峨野のうら悲しい景色だけではない、己の心が、肉体が寂しいのだという心の叫びが非常に美しい詞章に織り込まれているとは父からの教えです。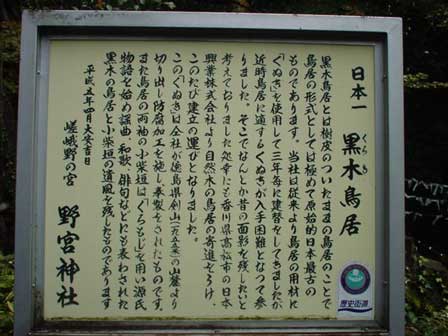
二つ目は、クセの上羽後です。『野宮』のクセは観世流では下居(したにいる)ですが、喜多流では床几にかけます。クセで「つらきものには・・・」と秋の景色を謡い始め、源氏との禁断の逢瀬があり、そして御息所と娘は桂川でのお祓いを受け伊勢へと旅立って行くことになったと語ります。作り物の鳥居は伊勢の鳥居にも、また鈴鹿川にも見え、「身は浮き草の寄る辺なき心の水に誘われて・・・」と、シテはおもむろに床几から立ち、自然に動き始める心持ちの型どころとなります。床几にかける意は、御息所の位の高さを表しているとも言われますが、私はこのふと立ち上がる風情が、なにかに取り憑かれたようにも、またどこかへ引き込まれてくようにもみえ、また見せるためではと思え、たまらなく好きなのです。「伊勢まで誰か思わんの・・・」とじっと遠くを見、距離感を出しながら歩みだす姿、両手を広げ娘の手を引こうとする御息所とも、また手を引かれる娘のようでもあるといわれ、「ためし無きものを親と子の、多気の都路に赴きし心こそ恨みなりけれ」とシオリ下居る型どころは、伊勢に下る御息所を描く絶頂だと感じています。
最後は中入り前の地謡の「黒木の鳥居の二柱に・・・」の謡です。シテは鳥居を見込み佇んでいるかと思うや、その姿は光のように消え魂だけが残る風情。この最後のところで、囃子方も地謡も気をかけ少しかかり気味に囃し謡う心得で良いところですが、また、もっとも難しいところだと思います。三番目物で中入り前がこのように強くかかるのも御息所の性格がなせる珍しい手法ではないでしょうか。
中入後のアイ語りは和泉流の野村与十郎さんが勤めてくださいました。本来の語りは車争いのことにはふれないのですが、近年野村家では、前場でふれない賀茂の車争いの話と、御息所が生き霊になった話を入れ、野宮に源氏が訪れた後、鈴鹿川の歌を詠み交わしたという話に続けています。車争いの段が入った事が、後の場面に続く橋渡しになり、わかりやすく良い語りであると思います。
後シテは車に乗った様子で登場し一声を静かに謡います。車争いの場面を語り、序之舞、破之舞と続きます。ここは情景描写であり、舞でありと、動いて表現できるので、前シテのように動きの少ない中に感情表現をしなければならない難しさと違って、取り組みやすさは感じます。
車争いの後、「身の程ぞ思い知られたる・・・」と舞台を二まわりしますが、これは妄執の闇から逃れられない輪廻の世界を表しているのでしょうか。「身はなお牛の小車の」で左手を高くつき上げ肩に乗せる場面は、牛の角がせり上がる真似であり、牛車を引く型と言われていますが、昔、後藤得三先生が「あの左手は光源氏、男性そのもので、あれが御息所の肩に重くのし掛かる。そこがわからなければ・・・」とおっしゃったことが甦ります。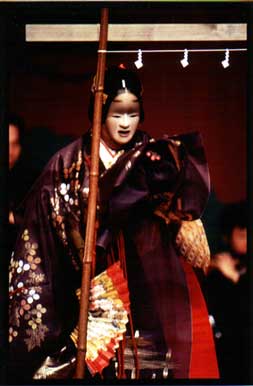
序之舞は「昔に帰る花の袖」「月にと返す気色かな」と謡い始まります。美貌も地位もあった東宮妃のころ、あるいは初めて源氏との逢瀬があったころ、そして野宮での最後のあの時を回想し、月夜に舞を舞おうという情趣でしょう。森田流の伝書には「序之舞とは謡では表現出来ない所作を舞に感情移入して一曲を盛り上げる」と、舞が楽劇の原点であると書かれています。このことは『野宮』など三番目物の序之舞のほとんどに通じ、役者がその役になるのではなく、つまり六条御息所としてではない別な世界、演者自身の思いを持ち舞うということなのです。あのゆったりとした時の流れと四つに組み、速く動きたくてたまらない自分を、じっと我慢させ苛める苦痛そのものが舞としての表現の真髄だということが、今回少しわかったような気がしました。
では破之舞とはどのようなものか。流儀には、太鼓ものでは『羽衣』、大小物ではこの『野宮』『松風』『二人祇王』の三曲しかありません。破之舞とは「本音の舞、二の舞ともいって、主人公の具象的な表現の本音である」と伝書にあります。「野の宮の夜すがら、なつかしや」という御息所の本音の心、その最後の夜がなつかしいという心の興奮や高ぶりを舞います。通常の舞は、歌舞音曲の形式にのっとって、ひたすら舞う抽象的な動きや型ですが、破之舞には心がある、本音の舞であるということです。この二つの舞の表現法を区別し意識することが大事な心得です。
喜多の九代古能(健忘斎)は「舞の後の破之舞は難しい。が、もっと難しいのがある。それは舞後のイロエや働き、余韻をあらわす、これが一番難しい」と。イロエや働きは、囃子方があまりにすばらしく囃したご褒美に、シテがもう少し舞い続けたいという気持ちから拍子を踏みだすと、自然とイロエや働き入りになるという約束事ですが、一つの舞を舞った後に本音の心を表す所作だといえます。いずれにせよ、舞後の舞が重要で、本音でここを掌握出来なくては駄目だということは確かなようです。
最後はこの曲に限っての火宅留めです。「火宅の門をや、出でぬらん、火宅の門」と謡う観世流、「火宅」で留める喜多流。御息所は火宅というこの世の苦しみの世界を出られるでしょうか、いやいやとてもでられない……。成仏できなくともよい、源氏とのあの日の思い出を大事に抱いていたいという強い意志があるように私には思えるのです。「火宅……」と留めた後の静まり返った舞台の緊張感の持続、これがこの曲の終演です。
今回の演能にあたり雑誌観世での野村四郎氏の対談『野宮』が私の演能に大きな力を与えて下さいました。「『野宮』は作品が役者を選んでくるように思います。下手すると作品の方が拒否反応を起こす。貴方にはまだ無理だよというような。」「人物像だけをぎゅっと絞り込んでいったからといって『野宮』にはならない、御息所になるわけではない」と語っておられます。これは心に残るメッセージで、私の心に衝撃が走り心引き締まる思いとなりました。たとえば『羽衣』なら天女になって舞おうという作業がある程度できるのですが、『野宮』ではそれができないと思い知らされるのです。また「ベースに季節感、秋深く木枯らしが吹きすさぶような世界、そして深い森をイメージし、御息所という高貴で複雑な女性の情念の世界や諸々の性格を、演者が身体の中に思い宿らせて演技という形にしていく」と、つまり心の中での作業が行われないと全く歯が立たない作品だとおっしゃっています。外面上の御息所を真似ても能『野宮』には成りえない、また最小限の動きで、最大限の描写をするところに能の最も大事な要素があり、『野宮』はまさにそうであるという野村四郎氏のお話は原文を読み込む作業など吹き飛ばすほどのものでした。
私にとって『野宮』という大曲は心と体を切り刻むような思い出の曲になりました。粟谷能の会の三番立ての真ん中を、父や能夫がゆずり押し出してくれる形で挑むことができた、そのうれしさと重圧をひしひしと感じています。 (平成十四年十月 記)
撮影、「野宮」東條氏
野宮神社
野宮神社鳥居
神社のまわりの小道
鳥居の説明
以上 撮影 粟谷明生
『竹生島』で脇能の妙を楽しむ投稿日:2002-09-07

琵琶湖の北端に浮かぶ小さな島、竹生島。能『竹生島』は荒神をシテとした脇能です。脇能は神能とも言われ、舞台となる神社仏閣を誉め讚え、神の霊験を寿ぐ内容のものがほとんどで、『竹生島』もその例にもれず、島の神社に祀られている弁財天、そして琵琶湖の水の精ともいうべき龍神の霊験を讚え、国土安穏を願うという、筋書きは単純明快なものです。シテ(漁翁、実は龍神)とシテツレ(女人、実は弁財天)が前場で登場すると、一声で「のどかに通ふ舟の道、憂き業となき心かな」と謡いますが、そこには特別な悲しみがあるわけでなく、ゆえに曲全体の主張に心を砕くより、謡そのものの美しさ、後場の弁財天の可憐な舞や龍神の活発な動きを楽しんでいただければよいのであって、そういう軽やかな能であると思います。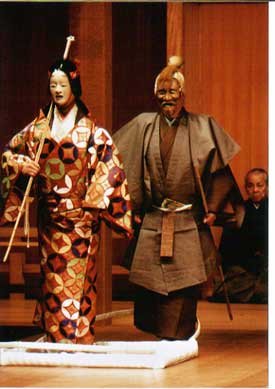
私はこの『竹生島』を9月の広島「花の会」(平成14年9月7日)で勤めました。後シテの龍神の舞働は短い動きながら、豪快で切れのよさが必要で、あまり年齢を重ねては体力的にきつく、かといって、前シテの漁翁の風格や少ない型の中に風情を出すにはあまり若くてもやりこなせず、若過ぎても老いても難しいこの曲を、年齢的にはちょうどよい今の時期に一度はやっておいた方がよいということで取り組みました。
『竹生島』の舞台は、ときは春、琵琶湖畔には桜の花が咲き乱れ、まさに春爛漫の風情。醍醐天皇の臣下(ワキ)が、竹生島に参詣しようと、近くに舟漕ぐ漁翁(シテ)を呼び止め、便船を願います。舟に乗ると左手には比良叡山の満開の桜。山からの風(峰おろし<ねおろし>)に吹かれ、散る花はあたかも白雪の趣です。「所は海の上、国は近江の江に近き、山々の春なれや、花はさながら白雪の。降るか残るか時知らぬ・・・」と、この情景を謡いあげる地謡がまさに聞かせどころです。謡を聴きながら、春の景色、自然の美しさを想像していただきたいところです。
私は7月に浴衣会(全国の菊生会、明生会の有志が集まって謡い舞う会)が長浜にあったこともあり、9月に『竹生島』を勤めることも意識して、竹生島詣でをしてきました。(そのときの様子は、このホームページの「写真探訪」でくわしく記しましたのでご覧ください)。
そのとき感じたのは、真野の入り江から老人が手で漕いで渡るのは大変だろうということ。琵琶湖は広大で湖というよりはまるで海のようです。真野から竹生島までは相当の距離で、フェリーでも35?45分かかるところを、老人がよく漕いで行けたなと、その大変さが実感できました。それでも昔の人は老人と言っても思ったより若く、漁で鍛えられていて腕っ節も強かったのかもしれません。あるいはシテの老人が龍の化身とあらば、難なく漕ぎ渡たれたのだと想像するのも楽しいものでした。
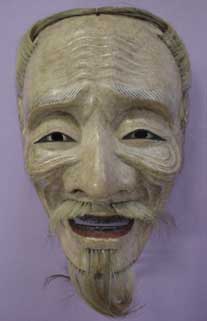
それから、型付に、舟に乗った後、左側を見回し桜を愛でる型がありますが、実際のフェリーでも左側に比良の叡山が見え、右側に長浜の地が見えと、型付の方向と実際の地形がそのままで面白く感じました。
能に描かれる場所を訪ねたからといって、能そのもののできがよくなるという保証はありませんが、それでも演じるうえでの心の余裕になり、遊び心をくすぐってくれるもののようです。これまでに叡山にも行き、琵琶湖、竹生島を訪ねた経験が能のイメージをふくらませるのに何らか役立っているという気はします。
それにしても、叡山からの峰おろしで桜吹雪になる様子を白雪にたとえる当たり、やはり名文と感心せずにはいられません。
さらに舟が進み竹生島に着こうというとき、「緑樹影沈んで、魚木に上る気色あり、月海上に浮かんでは、兎も波を走るか、面白の浦の気色や。」とあります。これも名文で、美しい自然の情景が目に浮かんできます。「緑樹影沈んで、魚木に上る気色あり」とは、緑樹の影が湖に映って暗くなっているから、その樹木の影の当たりに魚があたかも木に上るように群がっているという意味でしょう。司馬遼太郎氏の風塵抄に「孟子に“木ニ縁リテ魚ヲ求ム”と言う比喩があって、木に登って魚をとるようなものだというのだが、しかし孟子はよく知らなかったのか、木と魚はきわめて因縁がふかい」とあり、この言葉が思い出され気になりました。ここに書き留めておきます。
また「月海上に浮かんでは、兎も波を走るか」は、実際に兎が波の上を走るわけではありませんが、湖面に映る月、月といえば兎の連想で幻想的な描写になったのでしょう。先人は、ここを波の上を走る兎を追うようにして、数回、面を素早く切るのだと言いますが、兎というのは、さざ波が立った風情と思い、私は面を二、三回切る面遣いをしました。

後シテの面は「黒髭」です。粟谷の家には「黒髭」の面は2面あり、1面はやや小ぶりな一般的なもの、もう一面は全体に縦長で顎がL字型にせり出し、舌も長く出ているスケールの大きな面です。最近あまり「黒髭」をつける機会はないので、今回はあの大きな面をつけてみようと、後者を選びました。
わが家の伝書には「キリの舞様大飛出の扱い也」とあります。一般に龍神といえば「細かく」、俊敏に運ぶのが心得で、決して大股にならず、大まかな動きをしないが決まりですが、反面細かくやり過ぎるとやや位が低いものになる恐れがあります。「黒髭」の心ばかりでは脇能に成り難いということで、体の動きは細かく俊敏で冴えたものでも、心持ちはどっしりということでしょう。要するに、「黒髭」で「大飛出」の心持ちとは「細かく強く」といった心得だと思っています。
『竹生島』の見どころは、前場の謡と後場の天女の舞と龍神の舞働と述べました。後シテの舞働は豪快ではありますが、大変短いもので、やや手ごたえに欠けるからか、喜多流と金剛流には、弁財天をシテにして、短い舞のかわりに楽を舞う小書「女体」という特別演出があります。
喜多流の「女体」は、前場は従来通りでシテは漁翁、シテツレが女人ですが、後場のシテとシテツレが入れ替わり、シテが弁財天、ツレが龍神となります。この小書、井伊掃部頭(かもんのかみ)直弼のご所望で創られたようです。位が上がった人、龍神の動きが体力的にきつい人は、この小書で勤めることがあります。しかし、この演出ですと、女人が作り物の宮に入って、後場で弁財天となって宮から出てきて舞うという従来の演出ができません。地謡は「社壇の扉を押し開き、御殿に入らせ給ひければ・・・」と謡っているの に、女人は宮(御殿)に入らず、幕に消え、翁の方も「水中に入るかと・・・」と謡っているときに、舞台上の宮に入るというちぐはぐな演出になっています。この辺はやはり、お能好きな大名が、天女の楽をたっぷり楽しみたいと、あまり深く考えず、勝手に創ってしまったという感じがします。

その点、シテとシテツレを前場・後場ともそっくり入れ替える演出の金剛流の「女体」の方が理にかなっていると言えるかもしれません。
いずれにしても小書の「女体」では、後シテは弁財天で盤渉(ばんしき)の楽を舞います。弁財天の勢いのようなものを見せたいというのが趣旨であり、演じる側もそういうものをやりたいということでしょう。しかし逆に龍神はツレになり、やや位が低い感じになります。今回私は小書のつかない普通の演出で試みましたが、両者を見比べてみるのも面白いと思います。
ところで、広島「花の会」は今回が最後ということになりました。平成4年2月に、広島にゆかりのある若手能楽師が集まって・・・ということで、出雲康雅、粟谷能夫、大村定、中村邦生、そして私の5人でスタートし、後に長島茂が加わって今日まで続けて参りました。父が祖父・粟谷益二郎の地盤を引き継ぎ、広島喜多会として、家元をお呼びして会を催したのが始まりで、そろそろ若い人にバトンタッチしようというので、我々5人が始めたものでした。年に2回(ここ2年ほどは年1回)、2月と9月に3番ないし2番の番組編成で行ってきました。
最近は経済的に問題があり、ここでひとまず休会にしようということになりました。これはひとえに我々の責任でありますが、メンバー6人、広島にゆかりがあるとはいえ、今では全員東京に居を構え、その地に居づいて活動できなかったことが大きな原因になったように思います。
「花の会」では同じ曲目が重ならないようにと、スタートから今回まで違う曲の番組構成をするなど、さまざまに心を砕き頑張ってきたつもりです。それなりの成果も上り、よい経験ができたと感じています。広島の喜多会の方、関係各位には、深く感謝の意を表し、厚く御礼申し上げます。またいつか、形をかえて、広島の地に何らかの会を催すことができるよう、努力していきたいと思っております。
(平成14年9月 記)
| 写真 | 竹生島 前 | シテ 粟谷明生 | ||
| ツレ 金子敬一郎 | ||||
|
竹生島 後
|
シテ 粟谷明生 | いずれも撮影 石田 裕 | ||
|
面
|
前シテ 三光尉 | |||
| 後シテ 黒髭 | 撮影 粟谷明生 |
『橋弁慶』について投稿日:2002-08-04

小島誠様よりのご意見をいただいております。文末に掲載させていただきました。
粟谷 明生
牛若丸(後の源義経)と西塔の武蔵坊弁慶の出会いの場といえば京都の五条大橋。昔は「京の五条の橋の上・・・」と小学唱歌で歌われたほど、国民的によく知られたお話です。豪傑弁慶が牛若と主従を結ぶことによって、後の義経の力を確固としたものにし、源平合戦の功労を支え、最後は頼朝との不和により追われる身をかばう立て役者になったことは、多くの人の知るところです。それだけに、牛若と弁慶との出会いは劇的でなければならず、それが五条大橋の立ち会いに結晶しているといえます。
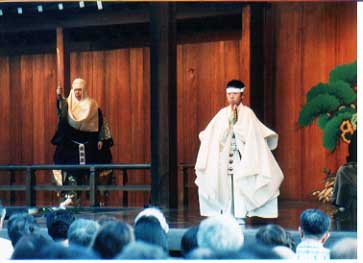
今年の夏(平成14年8月4日)、山口県、野田神社での山口薪能で『橋弁慶』のシテ・弁慶を勤めました。この『橋弁慶』こそ、牛若・弁慶の五条大橋(実は現在の松原橋)での出会いを描いた作品です。子方の牛若は、息子の尚生(たかお)が勤めました。尚生は今年小学校六年生、そろそろ子方卒業の年ごろで、今回の舞台がおそらくシテと子方という配役では最後の親子共演となるだろうと思われます。野田神社には、昭和11年、旧長州藩主の毛利家が明治維新70周年を記念して建築、奉納した大変立派な能楽堂があります。そこで思い出になる舞台を勤めることができたことに今感謝しています。真夏の大変暑い日でしたが、薪を舞台よりやや遠くに炊くなど配慮していただいたこともあり、薪能独特のやりにくさ、煙や灰により演者の謡で声がむせんだり、装束が汚れるなどがなく、気持ちよく勤められました。薪の火が近いと演者には大変暑く、飛んでくる火の粉は能楽堂には危険でさえあるのです。
さて、『橋弁慶』という曲に戻ります。牛若と弁慶との劇的な出会いの場となった五条大橋。しかし、小学唱歌で歌われるお話と、能『橋弁慶』の内容には、多少のねじれ逆転現象があります。つまり、小学唱歌の方は『義経記』によるものと思われ、千本刀を集めようと刀狩りをする荒僧・弁慶が、あと一本で千本というときに牛若に出会い、打ち負かされ、これほど強い相手ならばと家来になり、主従関係を結ぶというものですが、能『橋弁慶』は、千人辻斬りをしている悪逆無道の牛若を、五条大橋辺りで成敗してやろうと、弁慶が出かけていくという立場が違う話になっています。アイ狂言が牛若に斬られそうになって、怖い怖いと逃げ惑う場面は、観客のそれまで判官贔屓として描いていた牛若像とはまったく違い、少し戸惑う場面ですが、狂言方の演ずる気弱な都の者が普通の間(アイ)の科白ではなく、狂言調で通すところはなかなか面白く、『夜討曽我』の間、大籐内(おおとうない)に似て理屈抜きで楽しめるところです。
では本当の歴史はどうだったのか。まず牛若の経歴をたどってみます。平治の乱で父の義朝が敗北し、母・常磐御前は三人の子供を連れ大和国に逃れますが、平家方に捕らわれ、清盛の取り調べを受けます。常磐の美貌や周りの助命嘆願により牛若は幼少(生まれたばかり)であることから、命は助けられ、鞍馬寺の覚日阿闍梨に預けられることになります。常磐御前は平家の稚児に笑われないようにと、牛若の好みに任せて唐絹を山鳩色に染めさせ直垂袴など贈らせたとの記載もあり、七歳の春には、母に暇を乞い、具足、刀、笛などを餞別に得て鞍馬に登山しています。しかし牛若は平家の稚児達と一騒動を起こし、別当の押さえや常磐の諫めで一応おさまるもののさまざまな事件を起こし、とかく暴れん坊の問題児だったようです。
十一歳ごろ牛若は沙那王と呼ばれ、僧正ヶ谷に通って大天狗に兵法を学んだといわれています。この話は能『鞍馬天狗』にもなっていますが、天狗に象徴される強い力が、平家討伐のために牛若に力添えを約束するというものです。天狗とは実は源氏の残党ではないかといわれ、鞍馬山に源氏の御曹司がいるなら、彼を育て、源氏再興をと密談していたのではないでしょうか。幼い牛若に平家の横暴や義朝の非業の死、源氏再興の願いなどを話し、源氏の無念を晴らすのだと教育したものと思われます。現に牛若は天狗に会ってからは学問そっちのけ、剣術ばかりに打ち込んで、ますます暴れん坊に磨きをかけていきます。
天狗の教育が利いてか、牛若は十五歳になると、父の孝養のために千人辻斬りの願を立てます。非業の死をとげた父の無念を晴らすためといわれています。千人斬りの相手は恨みある平家方の武士だけではなく一般町民にも及んだようです。それにしても千人とは大変な願だったと思われます。
このように見ると、歴史的には能『橋弁慶』が描くように、牛若の千人斬りのほうが信憑性があるように思えてきました。この作品が出来た当時の人たちも、このことは当然のこととして知っていて能として創作されたのではないかと思われるのです。義経が主人公の『義経記』では、極悪非道、暴れん坊の肩書きが牛若には不似合いなので、悪として千本刀狩りをする弁慶像をこしらえたのではないでしょうか。判官贔屓の日本人の体質に合わせ、義経の伝説はときに美化されている節があります。
実際 美男子と思われていた義経はそれほどでもなかったようで、平家物語では背が低く小柄で出っ歯の醜男と書かれ、また性格も梶原景時が義経の奇襲戦法の卑劣さ、身勝手さを頼朝に注進するほどで、戦法的にも問題はあったようです。例えば、壇ノ浦の戦で舟戦では船子に向かい矢を放つなど、当時はタブーとされていたことを平気で命令し勝利する、そんな傲慢な性格は幼少時代より持っていたのではないでしょうか。
また、吉次と奥州へ向かう途中、今の蹴上(地名・けあげ)にて平家の武士の乗る馬のはねた水が首途に水を差したと怒り、九人を忽ち切り倒す事件も起こしています。そういう気性の義経であれば、十五歳の千人斬りの願も、まんざらうそとも思えず、うなずけます。
しかし能をご覧になる時は、実際の歴史がどうであったかなどは、さほど問題ではないかもしれません。世阿弥が美少年で活躍した時代を考え合わせれば、かわいい美少年が舞台に出て、立ち居ふるまいが美しく、豪壮な弁慶の薙刀さばきと、それに立ち向かう華麗な牛若の太刀さばきが見られれば拍手喝采で、舞台とはそれでいいのでしょう。子方というヒーローと大人の弁慶のからみの妙味、すがすがしさを見ていただければよいと思います。小品でもある『橋弁慶』、それはそれでよいのですが、息子と一緒に勤める機会に恵まれ、少し調べてみて、能で描かれている牛若の千人斬りが実は事実らしい、父の孝養のため、源の家の人間としての憂さ晴らしとしてあり得ただろうと自分なりに納得できたのが面白い発見でした。
私自身、子方(牛若)のときに後場の一声で、「さても牛若は、母の仰せの重ければ、明けなば寺へ登るべし。今宵ばかりの名残りぞと、川波添えてたちまちに、月の光を待つべしと」と謡うところは当然意味も解らず、大きな声で朗々と勤めてきましたが、今回、息子に謡を教えながら、これはどういう意味だろうかと疑問が出てきました。詞章を読む限りでは、母の仰せが何であるか、夜が明けたら何故寺へ登るのかなど、理解できず、この子方の唐突な謡の持つ意味や重要性に気が付きませんでした。
これは観世流にしかない小書「笛の巻」にふれなくては解決できません。「笛の巻」では、通常の前場と様相がガラリと変わり、前シテが常磐御前、ワキが羽田秋長となり、ワキが牛若の千人斬りを常磐御前に伝えます。常磐御前は牛若を呼び、涙を流して悲しみ、弘法大師伝来の笛を渡して牛若を諭します。牛若は母の仰せに従い、明日にも寺へ登って学問に励むと約束して、今宵ばかりは名残の月を眺めて来ると出かけます。しかし実際には五条で月を見ると言いながらも、謡では「通る人をぞ待ちにける」と、最後の相手を待ち望んでもいるようで、後場の弁慶との出会いにつながっていくわけです。これが重い母の仰せです。
小書がない喜多流では、ワキは登場せず、前場でまずシテ・弁慶が出て、名乗ります。「さても我宿願の子細有るにより」と語り、北野へ、一・七日(七日間)丑の時詣で、今夜より十禅寺に向かうと述べます。この弁慶の宿願とは何であろうか。能『橋弁慶』が『義経記』によらないものとすれば「千本刀狩り」の願とは考えにくい、では何であろうか。そして十禅寺に向かうのはなぜか。観世流は五条天神に向かうとなっているので、こちらならわかるのですが、十禅寺となると不明です。未だ解明できないままこのレポートにとりかかっています。どなたかのご指導を仰ぎたいと思っています。

また能では、二人は五条大橋で出会い、その場で主従関係を結ぶことになっていますが、『義経記』では、弁慶が五条大橋で一度負けて逃げ延び、翌日、清水坂で再会して、そのとき完全に打ちのめされて家来になります。能ではこの二回の戦闘場面を一場面に集約して表現します。「さしもの弁慶合はせかねて、橋桁を二、三 間退って(しさって)、膽(きも)を消したりけり」と、シテは橋掛りで膝を打ち、悔しがります。斬り込みが一段落し、その後にもう一度、「薙刀柄長く追っ取り延べて・・・」とかかっていく形になっていますが、これはもしかしたら、前段を五条大橋の場面、後段を清水坂の戦いと、二日間の戦闘を意識したものではと私は思います。
最後は、弁慶が降参して主従の関係を結び、牛若は弁慶を従え、「九條の御所へぞ参りける」で留めとなります。この九条の御所とは何を意味するのでしょう。九條の御所とは、常磐御前つまり母の住む御所を指しています。九條というのは常磐御前が義朝の妻になる前に、近衛天皇の皇后・九條院の女官をしていたことからはじまり、九條は常磐御前の代名詞のよう使われているのです。六条御息所が居所が変わっても、六条と言われたのと同じです。ですから、この曲の最後は、こんな豪壮の者を家来にして意気揚々と、母・常磐御前に報告に行ったことを暗示しています。しかし、暴れん坊の牛若を心配し、学問に専念してほしいと願った母・常磐は果たしてこの出来事を喜んだかどうか・・・。疑問です。
さて、弁慶を勤めるに当たって、面、装束をどうするか。型付には、前シテは直面、後シテは長霊ベシミ又は直面とあります。『橋弁慶』は現在物で前シテと後シテは同一人物、後が亡霊になるわけではないので、前が直面で後に面をつけるのはいかがなものかと思い、両方とも直面で勤めました。後の面「長霊ベシミ」を、兜についている顔当ての心持ちのように書き物にありますが、私はどうも不自然に感じしっくりしません。最近では、高林呻二氏が伝書通り後に長霊ベシミをかけて長範頭巾で勤められましたが、私は直面で勤めました。
伝書に、長霊ベシミ、長範頭巾とありますが、「面つけないときは衆徒頭巾の心なり」とあります。衆徒というのは叡山(比叡山)の僧兵のことで、衆徒頭巾は叡山の頭巾のこと、つまり袈裟頭巾です。今回は直面に袈裟頭巾の選択で勤めました。
もう一つ気になるところは前場の初同(地謡が最初に同吟するところ)です。「神変不思議奇特なる、化生の者に寄せ合はせ・・・」では、通常、シカケ・ヒラキの型付ですが、地謡が謡うところとはいえ、五条方面に行くと牛若という強い者がいて危険だから行かないでください、都が広いといってもこれほどの者はありませんという、太刀持ちの言葉に合わせてシテがシカケ、ヒラキをするのはそぐわないという意見もあり、私も今回は大袈裟なシカケ・ヒラキを控えてみました。
それにしても、勤めてみて弁慶という役を演じることの難しさを感じました。『橋弁慶』は小品ですが、そこにはどっしりとした弁慶像が浮かび上がらなくてはいけません。しかしあまり重々しくなり過ぎても、この能の妙味が損なわれます。淡々としてこの曲の弁慶らしさが出せればよいのですが、それはなかなか至難の技。ある年齢を重ねる必要があると思う一方で、あまり歳の弁慶が登場してはこれまたおかしく思えます。淡泊過ぎても、やり過ぎてもいけない良い加減とは? 弁慶らしく勇壮で重厚感がなければいけないが、お能の枠組からはみ出してもいけない・・・。『安宅』での弁慶でも感じた、能の世界ぎりぎり限界での演技、その難しさを、今回も充分感じました。最近耳に残る「人は一度味噌臭くなれ」の言葉が脳裏をかすめ、一度やれるだけやってみようと今回は非難を覚悟で臨んでみました。結果には多々あり、それだけ難しいことを再確認しています。
『橋弁慶』のシテは弁慶ですが、子方の牛若の役も重要で、シテに匹敵するほどの役どころです。尚生は六月の喜多流の自主公演で、シテ・粟谷能夫と『橋弁慶』に出る機会がありました。それで、能夫にせっかくのチャンスだから、親子で共演できる機会を持ったらということで、一年半前から話が進み、今回の舞台が実現しました。
子方の稽古は、子方の指導者が、理屈抜きにここではこのようにと型を教え込み、子方も繰り返し覚えていくもので、シテとは申合せ一回で舞台に臨むというのが通例です。そのため指導者が教えたことと、シテの型が違っていたりして、子方はかわいそうに面食らうこともあるのです。六月の自主公演のときは、能夫が「こういう曲は稽古のときから子方とやって、一緒に舞台を創っていくのがいい」と言い、何度も稽古をさせてもらいました。「一緒に創りながら覚えていく」、このような稽古ができたのがとてもよかったと思います。自主公演では私は地謡を謡い、子方の指導も私の役割だったので、シテとの稽古のときから参加して、まさに創りあげていく体験を三人でできたことを私は喜んでいます。
特にこの曲は、シテと子方の斬り込みが一番の見どころで、そこはやはり一人では稽古しにくいところです。相手が攻めてくるから受け、引けばこちらが攻めるという呼吸が大事ですから、相手あっての稽古が重要なのです。

斬り込みでは、互いの刀を触れず、合わせる寸前のところで止める勢いと気迫が大事と教わってきました。弁慶の薙刀も牛若の刀も竹光ですから、もし触れたら、そこには鈍い木材の音が聞こえ、金属のような鋭い音はしませんので、やはり触れずに表現する、これが第一の鉄則でしょう。能夫との稽古のときも、尚生は「ただ太刀を振るだけではなく、薙刀と当たるギリギリのところでしっかりと止められるように力を込めて」と注意を受けていました。細かい指導のおかげで、能夫のときも私のときも、子方として気迫のこもった斬り込みができたと思います。
尚生は子方の最後が近づいています。能夫と丁寧に稽古を重ねることができ、二度目の今回の舞台は暑い中ではありましたが、適度な緊張と余裕を持って無事勤めることができました。揚げ幕が降り、鏡の間で尚生と終演の挨拶をしたとき、私はこの子の役者としての一つのページがめくれ、今まさに一つの時代が変わろうとしていると感じ、少し寂しいような、また嬉しいような不思議な気持ちになりました。我が子を見ながら、共演の喜びと共に時間の過ぎ去る早さを痛感し、私にとっても尚生にとっても、良い思い出の舞台となったと、心に刻んでおきたいと思いました。
(平成14年8月 記)
橋弁慶 シテ 粟谷明生 撮影 野田神社
橋弁慶 シテ 粟谷能夫 撮影 あびこ
私も今回、みちのく明生会で橋弁慶を謡い、この能に対する興味が湧いてきたところでした。先生の演能レポートを読み、大変興味深く拝見したのですが、弁慶に関する点については私も少し考えたところがありましたので、以下、私なりに頭の整理を兼ねて書き出してみようと思います。あくまでも仮説ですので、史実誤認等ありましたらお許し下さい
まず、この能には、登場人物からすると当たり前ですが、実は一言も書かれていない主題として、打倒平氏という主題があると思います。牛若の母常盤御前は、平治の乱で義朝が殺された後も、平清盛の寵を受け、かつその側近と再婚したと言われています。従って、母常盤の美貌ゆえ命を救われたとはいえ、父義朝の仇である平家方から生活の保証を受けていた牛若は、自身の置かれた立場の矛盾に悩み、その発露として千人斬りという異常とも思える行為に駆り立てられた、と考えることができます。「義経記」と異なり、牛若が千人斬りをしているという状況は、より彼の苦悩を際立たせているのではないでしょうか。
一方、この能のシテである弁慶の装束が直面の場合「衆徒頭巾」であること、「宿願の仔細」があって「十禅寺」へ向かうことは、彼が天台宗、叡山の僧兵であることを象徴していると考えます。当時の叡山は、必ずしも常に平氏と敵対していたわけではないのですが、強力な院政を敷いた白河法皇ですら手を焼いた言われるほどの、一大反権力勢力だったわけです。平家物語巻一には、鹿ヶ谷の陰謀が発覚するなど、物語の全ての始まりである治承元年(1177)、叡山の天台座主である明雲僧正が法皇の不興を買い罷免されるという事件があったとき、宗徒が「十禅寺」へ集まり会議を開いた、とあります。
弁慶がいかなる目的で「十禅寺」へ向かったのか、「宿願の仔細」はどのような内容なのか、答えはここに隠されているような気がします。叡山と京を結ぶ線の中間の山科にある十禅寺は、いかにも衆徒が集まって鹿ケ谷のような打倒平氏の密談をしていそうな場所、というイメージを喚起させる単語として使われているものとも想像できます。作者はおそらく、登場人物に直接的に打倒平氏を語らせるのではなく、弁慶が反権力側の人間である象徴として「衆徒頭巾」「十禅寺」という記号を効果的に配しているのではないでしょうか。
こうして考えてくると、ロンギの部分で結ばれる主従の「契約」が、いかなる性質のものであったのかが良く理解できます。源氏の残党ではない衆徒弁慶と、まだあどけない牛若が、打倒平氏という共通の目的を持っていることを悟り、固い絆で結ばれるというストーリーは、平家物語に登場する「十禅寺」「衆徒頭巾」という記号を介してこそ、室町時代の観客に自然な形で受け入れられたのではないかと考えます。
小島 誠(2002.9.17記)
吉野山にくり広げられる『国栖』の世界投稿日:2002-05-01
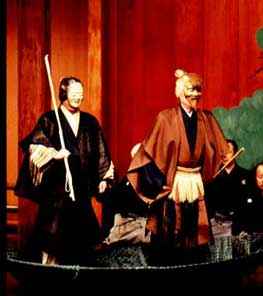
粟谷明生
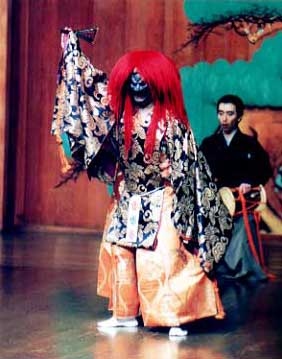
『国栖』は広大な吉野山を舞台にくり広げられる能です。国栖は奈良県吉野町にある地名。この吉野は熊野と並んで山岳信仰の修験道の発達した地である一方、国家権力への反逆者や政争の犠牲者が逃げ込んだ地域で、独自の世界を作り出していたようです。そのためここは敗北者の根拠地となり、そこに現れる蔵王権現は、その霊験が敗北者への味方になるとして、人々の信仰を集めていました。『国栖』に登場する浄見原天皇は天智天皇の弟、大海人皇子で後に天武天皇になる人です。弘文元年(六七二年)に起こった壬申の乱はあまりにも有名ですが、この大海人皇子と天智天皇の子、大友皇子との皇位継承をめぐる戦いです。この戦いでは大海人皇子が勝利し、以降比較的安定した世の中がつくられたようですが、『国栖』の舞台はその前の段階のお話です。
天智天皇は采女との間に生まれた大友皇子に皇位継承させようと画策し、それを察知して身の危険を感じた大海人皇子は剃髪して吉野に下り、壬申の乱で反撃に出るまでは、大友皇子の軍に攻め込まれたり、憂き目に会っています。『国栖』では浄見原天皇(大海人皇子、後の天武天皇)が吉野山に逃げ込んできたときに、尉と姥が機転をきかせて追手を追い払い、浄見原天皇を救うお話。後場では王を蔵すの名の通り、王を隠す霊験ありの蔵王権現が登場し、短く仕舞を舞って、後の天武天皇の御世を寿ぎます。
『国栖』という曲は、この広大で奥深い吉野山という地に思いを馳せ、当時さまざまに繰り広げられただろう、このような物語を味わっていただければよいのではと思います。私は喜多流自主公演(平成十四年四月)の『国栖』を、そんな気持ちで勤めました。
ここでちょっと一言。謡本では、浄見原天皇が皇位継承すべきところを「御伯父大友皇子に襲はれ給ひ」とあり、大友皇子が浄見原天皇の伯父にあたるように書いてありますが、史実は、おじ、甥の関係が全く逆。私はついこの間まで、この歪んだ謡本によって壬申の乱の歴史を誤って覚えていました。ときに謡本は歴史に忠実でない場合があるので注意が必要です。しかしそのこと自体が作品の主張に大きな障害を与えることがないのが不思議で、これが能という演劇のもつ特質かもしれません。
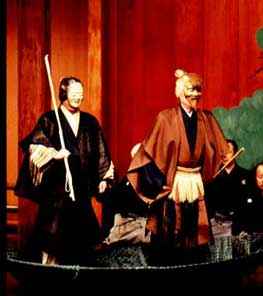
『国栖』は後場がツレの天女の舞とシテの短い仕舞ですから、やはり面白いのは前場です。そしてそのほとんどが台詞劇となっています。シテは囃子のアシライで出て、作り物の舟に乗り、唐突に「姥やたまえ」と謡います。ここの謡が曲をつくる難しいところです。紫雲が立つのは天子のご座所。遠い空に紫雲が立つのを見て、老人は奇瑞の起こる確信を持ち姥に言葉をかけます。紫雲を見るときの役者の位置、然るべき覚悟や思いを距離感を持って謡わなくてはいけないところです。強く強くと教えられていますが、生の強い声ではなく、老人の確信の強さが表面化しなくてはと思い、難しい限りです。
『国栖』は喜多流では古来の形を継承しているため、国栖という地方、田舎を思わす台詞が謡本に残っています。例えば「姥やたまえ」。子供の頃は何を言っているのか皆目検討もつかず、そのまま青年期を送ってしまいましたが、「姥や、見給え」が本来です。他には「まわこうよとて、おうじ姥は」は「いまはこうよとて」の意などがあります。観世流は明和の改正でかなり改訂変更しています。この改訂は国栖族の持つ民族性や方言らしきものを取り払ったため要領よく綺麗に整理され、私も理解するうえで大きな手助けとなりましたが、それだけに味わいが浅くなったきらいがあり、従来の古雅な方が良いように思えてきたから不思議です。
前場で唯一の型の見せ場は「鮎の段」です。短いながら技の利かせどころです。吉野川に放した鮎が素早く川を泳ぎ回り、君の再興を占うというものですが、老人でありながら急に活発に動く型で、短いだけにスケールは大きく、且つ凝縮して舞う、至難の技だと思います。
子方時代、この「鮎の段」を見て、焼かれてしかも食べられた魚がなぜ生き返るのか不思議に思っていました。今回の演能にあたり、ここはどうしても理解しておきたいところでした。これは焼いた鮎を川に放したとき、同じ形をした生きた魚が近づいて来て泳ぎまわったのを放した魚が生き返ったと錯覚したものであるらしいです。些細なことですが、天皇の吉凶を占う重要な場面、私としては理解しておかなければ動けないと思っていましたので、解決できてよかったです。
さて、最初に舞台に持ち込まれる舟の作り物。布地が張ってあり、出し入れは二人がかりでします。後に子方を隠すために重要なものですが、演者としてはこの舟への乗り入れが一苦労です。慎重にからだを運びますが、なかなか厄介です。ご老体が苦労なさっていた舞台を思い出しますが、今、この苦痛が判るというのは、少し早すぎるかもしれない、足腰の強化を心がけようと思いました。
老人夫婦は追手が来ることを告げられると、この舟に子方を隠します。私はこの子方を三回勤めましたが、それは暗く狭い舟の中での窮屈な時間でした。舟を開けたら子方が寝ていたとか、指で舞台の板の穴をほじっていたため、指が抜けなくなって大騒ぎとなったなど、エピソードにはことかきません。これらが嘘ではなく、本当のことであると証明できる子方経験者は何人もいると思います。
アイは追手として登場し、老人相手に威嚇しますが、この応対の台詞が一曲の聞かせどころであり、芝居心が必要とされるところです。シテは凛とした威厳、人を威圧する気迫と技巧、追手のアイは滑稽味を帯びた腰抜け侍の風情、両者相まって効果を出す腹芸といわれる世界でもあります。アイは和泉、大蔵の流儀により多少言葉やスタイルが異なります。喜多流には大蔵流の言葉がうまく合い、特に大蔵弥太郎氏や吉次郎氏は昔からこの曲にはいい味を出されていました。今回は吉次郎氏がお相手でやりやすかったことを喜んでいます。
中入り後は天女の舞となります。後ツレは前ツレと違う人間が演じるため、シテの中入りと入れ替わるように天女が登場します。シテは天女の舞の間に装束の着替えとなります。この天女の舞をこの曲に限り五節之舞といいます。シテの中入りに下り端(さがりは)二段、ツレの天女の舞に五段と、囃子方泣かせの繰り返しの連続、これには少しマンネリを感じてしまうのは私だけではないようで、観世流では楽で舞われることもありますが、ここはやはり下り端の吹き返しが順当のようです。五節之舞は日本書紀に「神女、五たび袖を返す」からの由来とあり、ツレは五回綺麗に袖を返すのが心得です。

続いて後シテ蔵王権現の登場となります。通常は地謡の内に無地熨斗目(むじのしめ 絹布の小袖、男性用の普段着)をカズキ、橋掛りに出ますが、今回は「不動」の面を使用することにしたので、幕の中にて「王を隠すや、吉野山」と謡い、「即ち姿を現して」と舞台に走り込む型としました。蔵王権現は悪魔降伏の憤怒の形相を示すもので、「大飛出」よりは、我が家にせっかく「不動」があるので、一度試してみようとの試みでした。父は「あのように早く動いては、不動と合わない」と注意してくれましたが、私としては、「不動」かけたさの一念、我がままを通してしまいました。ご覧になられた方のご感想を聞きたいと思っています。
子方時代に初冠をして舟に隠されたことを今でも鮮明に覚えている、この『国栖』、青年期に能夫のツレ、姥を経験して、今回となりました。月日の経つあまりの早さを感じつつ、「未来は、今何をしているかで決まるよ」といわれた先人の言葉が今、私の心をゆさぶり続けています。
(平成14年5月 記)
撮影 舞台写真 東條 睦
面 不動 粟谷明生
『殺生石』「女体」にカケリを入れる投稿日:2002-03-03


平成十四年、春の粟谷能の会(三月三日)で『殺生石』を小書「女体」で勤めました。この小書はもともと金剛流のもので、先代宗家喜多実先生が宗家就任記念として先代金剛巌氏よりお祝いとしていただき、その御礼として喜多流の『富士太鼓』「狂乱の楽」をお渡ししたいきさつがあります。以後この小書を両流で共有することになりました。
「女体」導入初期は、扮装のみ女の姿で、型は従来ある白頭の型にとどまる演出でしたが、平成九年に友枝昭世師が、前場の曲(クセ)を居グセから舞事にし、後場も激しく動き回りながらも艶やかな演技に創作して、新形式で演じられました。あの舞台は従来の、殺生石に封じ込められた狐の執心にとどまらず、美しい玉藻前の妖艶な肢体の内に激しく燃える怨念を見る思いがして、地謡を謡ながらも感動しました。この曲に込められている真意を新たに表現する可能性がある、いつか自分も「女体」で演じてみたいと、演能意欲が高まりました。
『殺生石』の舞台は那須野が原。そこに置かれている大きな石。その石は、人も鳥類畜類も近くに寄るものすべてを殺してしまう殺生石。それは昔、玉藻前が王法を滅ぼそうと鳥羽院の宮中に入り、帝を病にさせるが、安倍泰成の占いによって、玉藻前の仕業と明かされ、妖狐の正体を現して那須野の原に逃げ去る、しかし勅命による三浦介と上総介に射殺されてしまい、死後も執心とどまらず、殺生石となって害を及ぼしているというものです。
この殺生石に込められた魂はいかなるものか。後場で石を割り現れた後シテは、「野干(やかん・狐の意)の形はありながら、さも不思議な人体なり」と言われるように、正体は狐ですが、天竺(インド)にあっては斑足太子の塚の神、大唐では幽王の后、わが朝(日本)にては鳥羽院の玉藻前と転生してきたことをうかがわせる不思議な姿で、その魂は妖狐であり、魔性の女であり、石という生命体の石魂でもあるというものです。そこには幾重にも重ねられた暗く深くおそろしい闇の世界がうごめいている。そのような意識が「女体」に取り組む一つの基盤になり、演出にも、面や装束選びにも反映したと思います。
面は前シテが通常「増女」、玉藻前の容顔美麗に似合う美しい面ということで決まりとされています。しかし今回は、「石に近寄るな」と強い口調で言い放つほどの女ですから、それに似合う力強い執心が溢れ、異様な雰囲気が漂う面はないかと思い、岩崎久人氏打ちの創作面「玉藻其の四」を使わせていただきました。恐ろしい目、人相もきつく、髪をもふり乱しての特異な表情です。これは後シテ用に打たれたものでしすが、敢えて前シテでと試みてみました。
後シテは通常「小飛出」が決まりで、小書「白頭」では「野干」となりますが、いずれも鬼畜系です。小書「女体」ではそれら鬼畜系を除外します。今回私は、女という枠の人面ではあるが、女狐にも見え、またこの世にはない怪奇な力を持つような異次元の形相に思いを巡らせて、やはり岩崎氏の金泥「玉藻其の二」をかけることにしました。
装束は、「女体」の特徴である緋長袴を軸に、黒垂、舞衣のところを、近年流行の白頭に、私の考案で狩衣を衣紋に着けてみました。後で述べる「カケリ」の演出を意識したものです。
演出は、全体としては鮮烈な印象を受けた友枝師の型付を踏襲し、そこに後半、観世流で導入され始めた「カケリ」を入れて自分なりの創作を試みました。
前場の曲(クセ)では、友枝師が金剛流の型をもとに創作された通り、私も居グセではなく舞うことにしました。光を放って清涼殿を照らす玉藻の前の姿や、御幣を持ち占う安倍泰成など、当て振りな型を多く取り入れた舞です。ここは「その石に近寄るな」と制止する強い女、後シテの殺生石の魂につながるような強さを、舞という動きで表現したいところです。居グセよりはわかりやすくご覧いただけたのではないでしょうか。
石の作り物が割れて後シテが登場する場面は、他流には石の作り物を出さない演出もあるようですが、喜多流はほとんど作り物を使用し、玉藻前の霊(あるいは石魂)の念力で割れるイメージで、後見が両側から引いて割ります。今回は二つの石の間を少し開けて、玉藻前の姿を一瞬見せ、すかさずシテ自身で石を払って出る演出としてみました。このやり方には賛否両論あるでしょうが、シテの押し出す力があって割れるというのも一つの方法で、玉藻前の霊の強さが出るのではないかという思いでいたしました。
そして後半の「カケリ」を入れる演出、これは私の創作で行いました。カケリは修羅道の苦しみや物狂いの心を現す所作で緩急の激しいものですが、『烏頭』のように猟師が鳥を捕る場面にも用いられます。今回の「女体」では具体的には「草を分かって狩りけるに」の後、橋掛りを往復する所作を入れます。三の松に行くときは、玉藻前を追いかける二人の武士、三浦介と上総介の姿を、三の松から一の松に戻るときは、逃げ惑う玉藻前の様子をカケリで表現します。追う側と追われる側をひとつのカケリの中で同時に表現できないだろうか、難しい一つの実験でもありました。後シテの装束を緋長袴に狩衣としたのもその両方の姿を見せる狙いでした。追う両介が狩装束で馬にまたがり弓を引き、追われる玉藻前は、王朝に忍び込んでいた姿で、最後は、“玉藻前ここにあり”と果敢に挑み正体を現す型で留めるというものです。
しかしそのいさましさも空しく、玉藻前は統治者という力を誇る体制側の武士にあえなく射殺され、征服されてしまいます。『殺生石』ではこの玉藻前の死後の執心や恨み、女の情念をいかに表現するかではと思うのです。
殺生石に幾重にも込められた魂、玉藻前の執心、『殺生石』の闇の世界。それを演ずる舞台空間には、異様な空気が流れ、ただならぬ不気味な雰囲気が満ちてくるようでなければなりません。後の出端で、シテが「石に精あり。水に音あり、風は大虚に渡る」と謡う場面、太鼓の観世元伯氏に「とてつもなく変な臭いがして、異様な生ぬるい風が吹き起こるようなイメージの音色、掛け声で打てないだろうか」と話したところ、「それは難しいよ、できないよ」と即答されましたが、本番彼は何となく私の意を汲んで下さったのか、それは今までに体験したことのない、何か重苦しい出端であったように私には思え満足しています。
囃子方は他に大鼓は亀井広忠氏、小鼓の鵜澤洋太郎氏、そして笛は重鎮の一噌仙幸氏で、舞台の緊張感を盛り上げてくださいました。広忠氏は先代観世銕之亟静雪先生考案のカケリを最初に手がけており、若手ながら経験豊富。彼に相談して、追う側と追われる側の二段構成ながら、その段落を単に掛声とともに鮮明に区別するのではなく、舞台上での役者と囃子方が共有する独自の意思を基盤に、ある特殊の間で世界が切り替わるような狙いで練り直してもらいたいとお願いいたしました。手組の寸法にこだわらず、演じ手と囃子手の呼吸の見計らいで表現してみようということでした。舞台上では強い意気と緊張感が感じられ、舞いやすかったのですが、テーマにした追う、追われる様が表現できたか、今後の課題でもあるように感じました。
今回後場で予想外の事態が生じました。一畳台の前で、緋長袴を後ろに蹴り上げ、右足を台に乗せ膝をつく型で、膝が台から少し外れてしまいました。あのような事が起きた原因は何であったか。
今回、カケリを創作するにあたり、見ごたえあるものにするにはどうしたらよいかを考え、喜多流には本来無い、欄干に足をかける危険な動きなど稽古の過程で念入りに創りあげました。ところが、事の起きた場面はすでにある型を鵜呑みにして演じたところでした。創作者とは、何度も試み、危険箇所を入念にチェックし、動きを体にしみ込ませていくものです。それを、型だけをまねたレベルでの動きにとどめていた自分。そこに思わぬ落とし穴があったのだと思います。自分で創作した型と、型を真似ただけのものと両方あるときに、一方に気をとられ、もう一方に思わず落とし穴が生まれる。新たなものを創り出すとき、演者はその落とし穴を埋め尽くして演じなければならないものなのです。そして緋長袴の扱いの難しさ。早く動くときに袴の先が思うほどには動いてくれないこともわかりました。この教訓を今後の演能に生かしたいと思います。
「女体」は導入されて以来、金剛流の型付をベースにしながらも、さまざまな手が加えられてきました。後シテは緋長袴を採用することが多くなり、それまで喜多流に存在しなかった緋長袴を、各家で持つようにもなりました。しかし、まだ確固たる喜多流独自のものが確立されているわけではありません。友枝師の創作で方向は見え始めましたが、まだまだ工夫の余地はあるように思えます。手を加える事が許される曲だからこそ、今回のカケリのように自分なりの新しい試みが出来て面白く、心に残る体験ができたのだと思っています。
(平成十四年三月 記)
写真「殺生石」 粟谷明生 撮影 伊藤英孝
粟谷菊生と観世栄夫氏の『小原御幸』投稿日:2002-01-13

広島県廿日市市のさくらホール主催の能公演を能楽座で承り、ぜひ能らしいものをという要望でしたので『小原御幸』を新年早々の1月13日に公演いたしました。シテの建礼門院は父・粟谷菊生、法皇は観世栄夫氏という異流共演、私は地謡を勤めました。

父はこのところ、足に痛みがあるようで、幽玄な女物の演能はやめていました。父が若い女を演じるときは、面は必ず井関河内の小面が決まりで、この面は当家のものではありますが、誰も使わぬというルールが自然と生まれているぐらい、あの面に対しての父の愛着は絶大です。父の毎度の言葉、他の面を使おうとすると「浮気しちゃダメよ」と言われそうでね、というわけで60年来愛用してきたこの小面、実は3年ぐらい前に、もう女物はやらないだろうというので修理し、お蔵でお休みされていたのです。今回、父はこの小面に当て物(裏面に面のウケが良くなるようにつける添え物)をつけ、つくづくと眺め、「もう二度とつけることはないと思ったが、再会したなあ」とつぶやいて、感慨深げでした。
父は七十九歳、今年には八十歳になろうというのに、あの沢山の謡の文句を一つも間違えることなく勤めました。肉体そのものは若き建礼門院とは遠いはずですが、寂寥の中に凛とした風情と品格、まぎれもなく、そこに建礼門院が浮かび上がっている、寂光院『小原御幸』の世界がつくり上げられていると、父の役者としての偉大な力を感じてしまいました。
今回、観世栄夫氏が引き受けてくださった法皇役は、シテと対座する大変難しい役どころです。この役をこなせる能楽師は極めて少ないというこの言葉に異論をとなえる関係者はまずいないと思われるほど、この役のはまり役は限られた人なのです。前に先代観世銕之亟静雪先生が中尊寺白山神社で『小原御幸』をなさったとき、法皇は是非粟谷菊生さんで「後白河は菊ちゃんでなければだめ」とおっしゃられて、父が勤め異流共演となったことを思い出しますが、この法皇がはまり役になるかならないか、役者としての気持ちはなかなか微妙なものがあるのです。
それは法皇という人となりに関連します。つまり後白河法皇は建礼門院の舅に当たります。建礼門院は平清盛の娘・徳子ですが、後白河法皇の息子の高倉天皇の中宮になり、後に安徳天皇となる皇子をもうけます。しかし平家の栄華はつかの間。壇ノ浦の戦いで一門の者はほとんどが死に、子の安徳天皇も二位殿(清盛の妻)と共に海に沈みます。自らも続いて入水しますが、源氏の武士に助けられ都に連れ戻されてしまいます。その後は、一門の人々や安徳天皇を弔うために、尼となって大原寂光院に幽居します。後白河法皇はといえば平家と縁戚関係を結び、時の権力に取り入っておきながら、源氏が巻き返してくるや、平家追討の院宣を出し、平家を滅亡へと追い込んでいく、大変な策士です。孫となる安徳天皇を見殺しにすることさえ厭わなかった人です。
そんな後白河法皇が、建礼門院が侘び住まいする寂光院を訪ねるのですから、建礼門院の心中はいかばかりだったでしょう。しかも、建礼門院の姿を見るやいなや、壇ノ浦で生きながらにして見た六道(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上)の世界を語って聞かせよ、先帝・安徳天皇の最期を物語せよと迫る残忍さです。今は完全に弱者の立場である建礼門院は問われるままに、その有様を語りますが、静けさ、諦念の中にも、一瞬炎が燃え立ったのではないでしょうか。後白河法皇と建礼門院の間の緊張感、鬼気迫る場面です。ここを単に、幽居する嫁を慰めるために法皇がおしのびでやって来たと見るだけでは、『小原御幸』のすごさは理解できないわけです。
ですから、この後白河法皇という、策士であり、片や今様に凝って喉をつぶすほどの遊び人、聞かれたくない六道の様をほじくり出す神経の持ち主、この大変な悪役を演じるには、役者としてのスケールの大きさが必要です。それに直面という難しさもあります。ある貫禄をもった役者が法皇を演じるのでなければ、『小原御幸』は成り立たないのです。
今回の舞台について、父が「こんなにいい法皇はないなあ」と栄夫氏を讚えたところ、「悪役だからだろ」とかわしておられたそうですが、観世栄夫氏という法皇役者のすばらしさをつくづくと感じさせられました。七十九歳と七十四歳、朋友二人の意気のあった熱演を見ることができ、よい舞台になったと思いました。
大納言の局は若い大島輝久君、阿波の内侍は内田成信君が勤めました。二人とも異流共演という緊張の中で、よい謡を聞かせてくれました。特に内田君はこの役は二回目、初めてでは固くなるところを、二回目という余裕が見られ、かといって慣れず、異流の大先輩のお相手をするという緊張感でよい味を出してくれました。この役は花帽子をかぶり、ほとんど呼吸しにくい状態(これはシテも大納言も同じ)でずっと座り続けるつらい役ですが、立派によく勤められたと思います。彼の父・安信氏が昔はこの役のはまり役者で長い間やっておられましたので、ここにきっちりと継承されているなと感じました。
地謡は地頭が粟谷能夫、副地頭が出雲康雅氏で、私は能夫の隣、後列の端に座りました。父は私に『小原御幸』の地謡についてこんなことを教えてくれました。「観世流の地謡は、きれいな絵巻物のように美しく謡うが、喜多流のそれは、ただきれいというのではない、描かれているものがぐにゅぐにゅ動き始めるように謡うのだ」と。絵巻物の中にある炎が燃え立つように、劇的に謡ってこそ喜多流としての『小原御幸』が成り立つのでしょう。前半はしっとりした感じですが、後半の曲(クセ)の部分、後白河法皇に問われて六道の様を語る当たりはやや激した謡い方になります。そして最後、先帝の入水する様を語るシテの長い語りとクドキの後、地謡の「御裳濯川(みもすそがわ)の流れには、波の底にも都ありとはと・・・」は、ぐんとテンションが上り、音も甲高くなり大合唱となります。今回もこれまで肌で感じてきた父の謡い方を継承して、そのように謡おうと、地頭能夫を軸として皆懸命に謡いました。
『小原御幸』という曲は、一曲の中に舞が入らない珍しい曲です。室町時代には演能記録が見当たらず、初めは謡い物としてつくられたのではないかといわれています。舞がなくとも能が成立するということは、『小原御幸』全体が、強い訴えかけのある謡で占められているということです。謡が重要な『小原御幸』、これをいかに謡うか。私自身は中学・高校までは大曲のため、『小原御幸』の舞台には上がれませんでした。二十歳近くなり、伯父新太郎や友枝喜久夫先生の建礼門院を聴き、父の地頭の声を背中で聞き謡い、最近では研究公演で能夫が勤めたときに、初めて後列で地謡を謡わせてもらいました。『小原御幸』を数多く謡う機会があったこと、自分なりにさぐっておいたこと、謡い込んでこそ、建礼門院の悲しさや後白河法皇の怖さがわかってくるのです。名文に酔い、節使いに胸が高鳴り、心が張りつめてくる、こんなことを経験しながら、最近は謡の魔力に取り憑かれているみたいです。
終演し、やや放心状態、長い曲で謡い手も大変、役者もあの花帽子で苦しく大変だったとはいえ、父が元気で得意な謡を聴かせてくれ、しまい込んであったあの大好きな井関の小面をかけられて良かったと思うばかりでした。
面 河内堰 撮影 粟谷明生
(平成14年2月 記)
『女郎花』にみる男の一途投稿日:2001-11-25
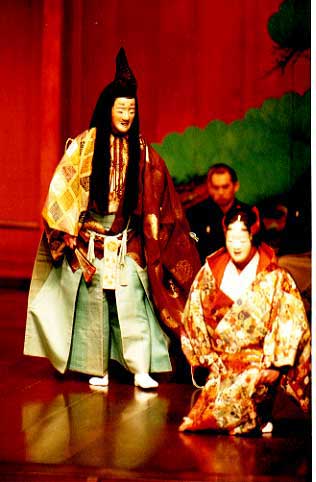
喜多流自主公演(平成13年11月25日)で『女郎花』を勤めました。女郎花で思い出すのは、中学生のころ漢字の読み方テストで女郎花が出たときに、得意になって「おみなめし」と書いて、しっかり×をもらったことです。「先生、お能ではおみなめしと読むのですが・・・」と言ったところ、 先生は「お能はそうかもしれないけれど、読み方はおみなえしですよ」と教えてくださったのですが、×には違いなく、がっかりしたことを覚えています。
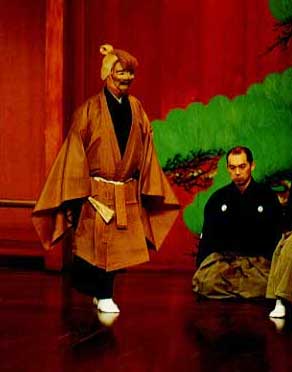
お能では「おみなめし」と読みますので、お間違いのないようにして下さい。
女郎花=おみなめしは、おみな=女、めし=召しで、女が身を投げる前に着ていた(召していた)衣を土中に埋めたところ、その衣が朽ちて花が咲き出たため、その花を女郎花と言うようになったということのようです。
女郎花は秋の七草の一つで、茎は細長く、その先がいくつかに分かれ、黄色い可憐な花をつけます。曲の中では、この女郎花、頼風が近寄ると「怨みたる気色」でくねり、離れると「もとの如し」でシャキッとします。男の私の感覚では、頼風が近づけば嬉しくて元気になり、離れると寂しくて萎れてしまうと思うのですが、本当の女心とは近寄るとすねる、この花のようでいいのと、女性から教えられました。「くねる」は風に吹かれてたわむのほか、すねる、怨むという意味がありますから、この女郎花の怨みの深さ、頼風にすねてみせる女のかわいらしさが見え、普通とは違う風情になるのでしょう。
能『女郎花』は、このような女郎花の花のイメージを一曲の中に通しながら、女郎花にまつわる古歌の論争、石清水八幡宮への信仰に、舞台の多くを費やし、そして中入り直前にようやく、男塚、女塚を紹介して、男と女の悲しい恋の結末へと物語を進めています。
それだけに、男と女が共に身を投げ、成仏できずに邪婬の責め苦があるといいながらも、さほど深刻にならず、この曲のありどころを不明瞭にしています。戯曲の組み立てそのものが手ぬるいといえるかもしれません。

後シテの装束を見ても、戦陣の物語ではないのですが、平家の公達のような格好をしています。喜多流は長絹の肩脱ぎ姿で、面は中将です。「肩脱ぎ」は舞を舞うときや修羅や邪婬に苦しめられている風情を表すときに使いますが、今回はもちろん後者の意味です。しかしこの美しい公達姿、邪婬の悪鬼が身を責めてというには、余りにもスマートです。観世流では単衣狩衣を着るぐらいですから、頼風という男、身分も高く上品なイメージなのでしょう。『通盛』も後場、夫婦で登場するのは似ていますが、シテは梨打烏帽子に太刀をつけての修羅の業に苦しむ公達武者の定型パターンがあって、その苦しむ様がそれなりに想像できますし、『船橋』も、二人の仲を反対する親が、橋の板間を外して橋を渡る男を殺し、女もまた急に消えた男を捜しながら共に川に落ちて死んでしまうという悲劇的な内容で、怨みは強く、かける面も怪士系の恐ろしい顔ですから、川に沈んだ苦しさを表現しやすいのですが、『女郎花』の二人の場合は、これら二曲に比べ、人格描写が曖昧で緩いように思え、地獄に落ちて苦しむ様を表現するのが難しいところです。
流儀の本には「情けは深けれど執拗ならず、哀切なれど酷烈ならず」と述べていますし、怨念や執心に焦点を当てるよりは、女郎花に寄せる美しい詩情を表せばよい、これもお能の趣きであるというようなことがよく言われます。しかし、もう少し人物像をくっきり描いてもよいのではないかというのが、稽古してみて、私が第一に感じたことでした。
そこで、この曲の男と女はどのような人物かを考えてみたいと思います。頼風は訴訟のために都に上り、都の女と契りを結びます。訴訟が終わって帰るとき、後で必ず迎えを差し向けるからと約束しますが、何の便りもありません。そこで女は八幡の男の家までやってきますが、家の者は、主人は山上していないと邪険な扱いです。女はさては男の心変わりか、裏切られたと感じ、このまま京にも戻れないと絶望し、放生川に身を投げてしまいます。讒言のみで怨みを助長し、あっけなく自殺してしまう胸狭き女で、六条御息所のような積極的な嫉妬の情とも違う弱き心ではないかともとれますが一方で、自らを空しくすることで、頼風の心の中に永遠に生き続けるのだという特異な強さを持っている女であるともとれます。
男の方はどうかというと、本妻がありながら、都の女と契るのは浮気男であるともとれますが、当時、本妻の他に通う女がいるのはごく普通のことで、身分の高い人であったと思われる頼風には、それほど非難されることではなかったはずです。都の女が誤解して自殺したと聞いて、泣く泣く死骸を土中に埋めて弔います。ここまでは普通ですが、そこから咲き出た女郎花がくねる姿を見て、女のあわれを思い、自らも身を投げるのですから、浮気男というよりは純粋で一途さを持った男のように私は思ってしまいます。本妻ではない女郎花の女に結構惚れてもいたのでしょう。女が身を投げた後も非常に嘆いて、この女が死んだのは、家族の讒言によると責任転嫁せず、自分のせいであると自らを責める誠実さも持ち合わせています。
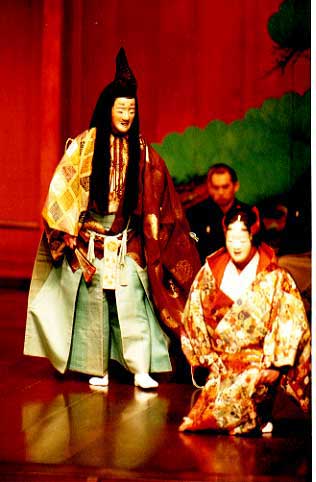
そして、頼風は、共に地獄に落ちて邪婬の悪鬼の責め苦を受ける覚悟で、身を投げます。この当たりは、女の一途と男の一途がかみ合わずに不幸な結末となったとも、昇華された純愛ともとれるのです。
このような人物像が見えてくると、このお能の居所も少し鮮明になってくるのではないでしょうか。しかし、舞台を一度見ただけでは、そこまで読み取れないところに、この戯曲の弱さがあるのだろうと思います。
そして、この男と女の物語があいまいに感じられるのは、前場の女郎花による歌争いや、石清水八幡宮の神が宿る霊地を大観する趣きに力が込められていることにもよると思われます。男塚、女塚の話を期待している人にとっては前半は中だるみし退屈なものかもしれません。しかし歌争いの中身を知って聞いてみると、前シテの尉の茶化し心が面白く感じられると思います。
ワキの僧が女郎花を手折ろうとすると、花守だと名乗るシテの尉が現れ、菅原の神木にも「折らで手向けよ」とあるとか、古き歌にも「折りつればたぶさに穢る(けがる)立てながら三世の仏に花奉る」と言って、手折ることを押し止めようとします。そうすると僧も負けていないで、僧正遍昭の歌の上の句「名に愛でて折れるばかりぞ女郎花」を引き、女郎花という名にひかれて折っただけだと反論します。シテの尉は、その下の句は「我落ちにきと人に語るな」とあるではないかと言って、女郎花を折ったために自分は落馬してしまった(深く忍んでいる女と契り、草の枕を並べてしまった)ことを語るなと言っている、だからその歌を引くのは出家の身としては誤りと反論し、この歌争いに勝利します。それでも最後には古歌の故事由来を知っているから、それに免じて一本折らせてやろうなどと言うのですから、この尉もなかなか茶化し心がある面白いおじいさんなわけです。歌争いの部分はそういう面白さを感じながら謡えというのが心得です。
歌争いの後には、石清水八幡宮を大観する場面が続きます。全体の物語からすると、中だるみの要素となる部分ですが、謡としてはとてもよいものがあって、落とすわけにはいかないところです。「鳩の峯越し来て見れば三千世界もよそならず・・・」の当たりは、男山の頂上に立ってあたかも三千世界が見えるかのように謡い上げ、謡愛好家には、ゾクゾクと体が震えると評判が良いところです。お能にはこのように、物語を追うだけでない醍醐味があるといえるでしょう。
そして中入り前にようやく頼風と女の物語に入っていきます。後場は曲(クセ)などの仕舞どころがあって、テンポよく進んでいきます。仕舞どころはよい型があるため、仕舞や舞囃子でよく舞われ、親しまれています。私自身も物語がわからない中学生のころから、何回も稽古し、舞台を勤めてきました。

曲も終盤。「あら閻浮、恋しや」と謡った後にカケリとなり「邪婬の悪鬼が身を責めて」と大ノリとなって盛り上がります。しかしここは『八島』や『田村』などの軍体もののそれとは違って「カケリがあまり激しくならないように」というのが諸先輩からの教えです。『女郎花』は花の情趣に寄せてあまり激烈にならないという全体の色合いがあるからだと思われますが、私は激烈にならないからといって、ただおとなしく舞えばよいというものではない、頼風の一途を表現するためにも、カケリはカケリらしく、やや激しさをもってキリリと引き結んだ演技があっていいのではないかと思います。戦物語の主人公とは違うとはいえ、地獄の責め苦にあえいでいる場面は度外視できません。
笛の森田流の伝書には、この部分「責めなり」とあります。責めの意識で吹けということでしょう。「あら閻浮、恋しや」と、昔の人間世界を思い出す表現もあるかもしれませんが、「邪婬の悪鬼は身を責めて」への導入部分としてのカケリともとれるのです。森田流の伝書にあるように、邪婬の責めや苦しみが表現されなければいけないのなら、それなりの強さが必要で「カケリは激しくならない」とするのは後シテの装束の優雅さにひかれた、形を優先させたものだと思うのです。やはりある強さが心に入っていないといけないのですが、実際には、それを表現する度合いが難しいように感じました。
カケリは荒くなくという通り一遍の教えを鵜呑みにするのではなく、今回私は少々荒くて良いのだ、そうせずにはいられないのだという思いで舞いました。伝承されていることを鵜呑にするだけでは何も生まれない、自分なりに、なぜそうするのかという考えを持って演じることが大事で、その考えに従って演じてみて、それがどうだったかを検証する姿勢が必要ではないでしょうか。
最後に、観世会の演能のしおりに、観世芳宏氏が『女郎花』について面白いことを書いておられましたので、ご紹介します。
「女の濃厚過ぎる愛情は、恨みにまで進展してしまうことがある。愛し愛される事は罪ではないが、男がいったん外にでれば色々なつき合いがある。それを理解しないで勝手に恨むから地獄行きとなるのである。巻き添えを食って地獄に落ちた男はやりきれない。」
『女郎花』は純愛ラブロマンス、当時の聴衆もこんなのないよというぐらいの過度の純愛が、また逆に面白かったのかもしれないと思いつつ、現代でも、およそ考えられない純愛物が、妙に受けることがあるかもしれないと感じながら、私は『女郎花』で男の一途さを演じたつもりですが、私自身の現実は、「男がいったん外にでれば色々なつき合いがある」という観世芳宏氏の一文に共感するところ大で、「ちょっとしたことで誤解しないでくれよ・・・」というのが本音かな・・・というところです。
(平成13年12月 記)
能 女郎花 前 粟谷明生 撮影 伊藤英孝
面 中将 満志作 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
能 女郎花 後 粟谷明生 撮影 伊藤英孝
女郎花とリンドウは新城の加藤佳子氏のお庭にて撮影 撮影 加藤佳子
刺激的な会となった「大槻文蔵の会」投稿日:2001-11-21

一曲を異なる流派で共演する「異流共演」、能や仕舞、舞囃子など、同種の内容で異なる流派が競演する「立合」、鼓一人、謡い手一人で演ずる「一調」、これらの珍しい内容を盛り込んだ会が実現しました。大槻能楽堂で催された第7回大槻文蔵の会(平成13年11月21日)です。我々演じ手にとっても刺激的な会になりました。
番組は、最初に舞囃子が二番、私の『猩々乱』から始まり、次がシテ観世暁夫氏(平成14年元旦より観世銕之亟を襲名)、ツレ片山清司氏の『三山』。これが喜多流と観世流の「立合」となります。そして一調「笠の段」(能『芦刈』の一部)を小鼓が曽和博朗氏、謡が粟谷菊生の、人間国宝同士の競演。狂言は茂山千作・千之丞氏の『昆布売』で、最後は能『隅田川』。これがシテ大槻文蔵氏、地謡が喜多流(地頭が粟谷菊生)による異流共演ということでした。
この会のしおりのご挨拶で、大槻文蔵氏はこの会が実現に至った思いを次のように書いておられます。
「一昨年七月能楽堂の公演で『通小町』がありその折、シテ粟谷菊生・ツレ観世栄夫・地謡観世銕之にて私も隣で謡わせて頂きました。流儀による主張の違いが、より盛り上がりとなり、常と違う緊迫感を生みいいもんだなあと思いつつ、地頭の銕之亟師のいつもと違うもっていき方になるほどと感じた事でした。そんなこともあって今回粟谷菊生師に是非とも地謡を謡って頂きたいとお願いして、実現の運びとなりました」
このような文蔵氏の思いと、そのご挨拶に続いて書いておられるように、大槻家と粟谷の家との祖父の代からの長きに渡る親しいつき合いがあったからこそ実現したのだと思います。特に、父菊生は二十年近く、大槻自主公演に参加し、何曲も能を舞わせていただいておりますから、仲間意識も強いのです。
私自身は今回、舞囃子の『猩々乱』、一調で思いがけなくも父の助吟をし、『隅田川』で地謡を勤めさせていただきました。めまぐるしい中にも、感じること、学ぶことが多くありました。
舞囃子『猩々乱』

『猩々乱』は『猩々』の中ノ舞を「乱」という特別演出にするもので、曲名そのものに乱と言う字が入るほど特殊なものです。「乱」は、猩々という人面で猿類の獣身、架空の怪物というよりは仙童ようなものですが、このお酒好きな猩々が海中より、酒に酔って現れ波上を乱れ舞うという、写実的でものまね舞踊化された舞です。「乱」の舞い方は流儀によって様々で、観世流はまさに妖精のような動きで、水を軽快に蹴る感じで舞いますが、喜多流は腰を落とし中腰のままゆっくりした動きで、アメンボのように足を大きく回しながら水の上をすべり舞うようにします。演じる方にはこれがきつく、大変な体力を必要とします。この違いを、各流儀で見比べてみるのはとても面白いと思います。
乱のように特別な型というのは、最初は目新しく面白く見ることができますが、六、七段も長く続くと、どうしてもだれて、飽きがきてしまいます。文蔵先生に「観世さんの乱はエレガントで妖精みたいで良いですね」とお話したところ「面白いけれど、あれも長いと飽きる」とおっしゃっておられたので、どの流儀でも特別な型というのは飽きる要素があるのだと発見でき面白く感じました。序ノ舞などシンプルで簡素化されたものとは対照的です。
今回は夜の公演で時間が限られているうえに番組も盛りだくさんだったことから、私の『猩々乱』は短い時間でその真髄を見ていただけるものにしようと考えました。それで乱の独特の型はすべて盛り込み、三段半の短い形にまとめてみました。
私にとって『猩々乱』は披きで一回、その後に囃子の会で一回、今回は久しぶりで三回目となります。披きのとき器械体操のような硬い動きで稽古していると、父に「どうも違う。猩々は酔っぱらっているんだぞ。もっと柔らかさ、ソフトなホワーッとした感じがないと。お前のは硬すぎる」と言われました。二回目の囃子の会のときも、やはり硬い直線的な動きに終始していたと思います。

若いときは体が動くに任せて直線的な硬い動きになりがちで、そこには若さあふれる運動美のようなものがあるのも確かですが、やはりお能の持つ優美さ、猩々の酒を酌んでは酔い、酔っては乱れという姿を表現するには、どこか柔らかな動きが必要だと感じ、今回はそこのところを心がけてみました。柔らかい動きというのは、鋭く速い動きよりはるかに体力がいるもので、面や装束をつけているときはその負担は大変なものです。その点、今回は舞囃子で、紋付袴姿、面もつけていませんから、身が軽く、やりやすかったということもあります。柔らかい動きをしてみて、父の言っていたことがこういうことだったのかと改めて理解できたことは一つの収穫でした。今回このような機会がなければ、私の乱は器械体操に止まっていたでしょうから、よい体験ができたと思っています。
私の舞囃子『猩々乱』の後は観世暁夫氏による舞囃子『三山』で、まさしく「立合」となりました。立合は昔から各流儀が己の芸で競い合うもので、出る以上は勝たなければ自らの食い扶持を減らされたり、失うほどの厳しいものでした。世阿弥も立合のときは、先の流儀の舞台を見て、急に演出方法を変えたり、色や形が重ならないように、装束を変更したりした様子を書き残しています。すぐに対応できるよう数種類の装束を持参するのが常で、それがうまくできないと失敗し、負けるので注意が必要とも書かれていて、非常に厳しい情況だったことがわかります。
立合といえば有名なのは、細川藩主が金春流の桜間家と喜多流の友枝家をかかえ、両家を競わせたことです。当時は、広島の浅野家なら粟谷というように、一藩主が一家をかかえるのが普通でしたが、細川氏は二家をかかえていたわけです。ですから両家は常に「立合」をさせられます。だからこそ両家からは素晴らしい役者が輩出し、今もその伝統が受け継がれているともいえるのです。
現在は「立合」といっても、具体的に勝った負けたの評価を下すものは何もありません。しかし私は、立合には「負けない」と思い舞台を勤めますし、演者自身も心の底では「勝った」とか「負けた、やられた、相手はすごい」と感じるものがあるはずと思っています。今回、文蔵先生が「面白いなあ、あの喜多流の乱もいいな」と盛んに言ってくださったので、先生の会で、それなりの責任が果たせたかなと、胸をなで下ろしているところです。
一調「笠の段」

一調とは小鼓、大鼓や太鼓が一人、謡い手が一人で勤めます。ここに笛が入った場合は一調一管といいますが、いずれにしても、それぞれのパートは一人で担当するものです。ところが大槻文蔵の会の一調は、父菊生の体調が不調のため私が助吟(じょぎん)をする変則的なものになりました。
このような突然の故障のときは、お相手の方に非礼を詫びるのが礼儀です。父も曽和先生に「すみません。体調が悪くなり声が出ませんので、明生に助吟をさせます」と申し上げ、私が助吟することになりました。
一調というのは、特別な手組で囃すのに対して、謡がそれに唱和するというもので、あくまでも囃子が主体となります。相手が常とは違う手組で打つ恐さ、一人ですから、絶句してしまえば成り立たない恐さがあります。それだけに恥をかきたくないと尻込みし、一調をやりたがらない人が多いのは確かです。その点、父はそのスリルが面白いとなにか楽しんで挑んでいるように見えるときがあります。囃子科協議会の調べでは、一調を勤めた回数が一番多いのが粟谷菊生ということですが、おそらくそれは間違いないところでしょう。
そして、父がこれまでの一調の中で助吟を許したのはわずか一回だけ。広島の会で、幸流小鼓の一調の中でも重い扱いの一調一声『玉葛』を勤めたときで、鼓が幸宜佳氏、助吟は粟谷能夫でした。
一調は、曽和先生いわく「慣れたらアカン」。慣れたら面白くない、一調は真剣勝負、ピリピリ神経を研ぎ澄ませてやらなければということなのです。申合をしても本番でその通りに打つとは限らない。父は「曽和さんはいつもそうなんだよ」と笑っていましたが、幸流の若手で、曽和先生のお弟子さんの成田達志さんは「あんな手組、初めて聴きました」とやや興奮気味でした。私はというと、「申合とは違うぞ」と思いながらも、曽和先生が巧みに打ち込まれてくる面白みを味わうことが出来ました。恐いながらも、小鼓との真剣勝負、一調「笠の段」を体験できたことが、一つの勉強になりました。
父は「一調をうまく謡えるようになるのは慣れ。父・益二郎の助吟をよくやらされたから。あれで場に慣れたんだよ」と言います。今回、父との助吟ができ、よい思い出ができました。
異流共演『隅田川』
今回の異流共演はシテが観世流、地謡が喜多流という大変珍しいものになりました。異流共演そのものが珍しいうえに、共演といえば、前シテと後シテとか、シテと重いシテツレということが多いので、今回のような共演は異例中の異例ということになります。
文蔵先生が「菊生さんに是非」と言ってくださり、曲目もこちらに任せるということだったので、父の得意曲である『隅田川』を提案し催す運びとなりました。
『隅田川』は詞章も両派それほど違っていないので、よい選択だったと思います。それでも、喜多流が念仏を五回唱えるところを観世流では三回しか謡わないなど微妙な違いがありますから、申合で調整しなければなりませんでした。シテのクドキの後「さりとては人々。此の土を覆して(かえして)今一度。この世の姿を母に見せさせ給えや」と謡うところは、喜多流では「さりとては人々」とシテが謡い、「この土を」から地謡が謡うことになっていますが、文蔵先生より「さりとてはから地謡で謡ってほしい」と言われ、「えーっ」と驚いた場面もありましたが、あとはさほど問題なく進めることができたと思います。
多少の違いがあっても、地謡が喜多流であれば、我々は喜多流らしく謡うことが肝要だと思うのです。文蔵先生の主張も「喜多流らしさを存分に発揮して謡ってほしい、それに乗せて観世流の主張で舞う」というもので、そこに現れる両派の緊張が演じ手には一番大切だと思います。ですから共演だからといって、相手にべったり合わせるのではなく、そこには両者拮抗した状態を創りあげることが必要になってくるわけです。
とはいえ異なる流儀が共演するには少なからず困難なことがあります。その困難を乗り越えて共演する意義はといえば、それは一つの流儀に閉じこもらず、新しい風を入れることで、新境地を開くことでしょうか。私自身、自分の中に閉じこもって行き詰まってくると他流の舞台を拝見したくなります。異流共演はただ外から見るだけでなく、その懐に入って、同じ舞台を共有することで強烈に感じ取れるものがあります。
今回も、都の女(シテ)が隅田川に着いて、遠くを見やりながら「あれに白き鳥の見えたるは。都にては見慣れぬ鳥なり。あれをば何と申し候ぞ」と謡われたとき、その謡や立ち姿、全体の雰囲気から、ああ、ここは東(あずま)の地なのだ、隅田川が見える、鴎が鳴く声が聞こえると、私には本当にその場の情景が立ち昇ってきたのです。今までそんな風に感じたことはありませんでした。役者の存在そのものがエネルギッシュで私に訴えかけてきて興奮しました。
そして、船に乗る前の動きも両派では異なります。喜多流は持っている笹で地面と思われる舞台をバチーン打ってから願うのですが、観世流は手をさしのべ願いを乞うた後に打つ、さし迫り方の表現も様々です。こういうことが発見できるのも面白いことです。観世流の舞台を観に行くことで、このような発見もできるかもしれませんが、舞台の中で、ほんの二、三メートルの近さで、自分が謡いながらその情景をみることのすごさ、こんな強烈な吸収の仕方は他にはないと思うのです。

また最後、子供の幻が塚の中に消えて、夜がほのぼのと明けてくる場面では、文蔵先生の限りなく強い塚への執着に対して、私は「東雲の空もほのぼのと、明け行けば跡絶えて」と塚から離れ明け行く広大な関東平野の夜明けの空を眺め、その情景の中にこの母親はどうなるのかという風情を感じさせて終わらせたいと思い謡っています。この当たりの事を、観世流の方を初め他の方々の感想もうかがい、お互いの感じ方をつき合わせることができました。よりよいものも多く吸収し、こういう異流共演が出来たことを私は喜んでいます。
今回は父が地頭を仰せつかりながら、本番で声が出なくなり、父を挟んで座った私と能夫で、父の分まで謡おう、観世さんにご迷惑はかけられない、異流共演の責任を全うしようと使命感を持って精一杯謡いました。異流共演は一種の立合、喜多流それも粟谷の地謡を力の限りシテにぶつけ、それでどうなのか答えを出してもらおうと必死でした。父の負を背負ったからこそ、私も能夫も大きな力を持て集中できたといえるかもしれません。
最後にもう一つ。子方の上田顕崇さんが、伸びのあるすばらしいボーイソプラノで立派な子方を演じられ感心しました。観世流では日ごろから子方には高い声で謡う稽古をされているようです。その成果が現れて子方らしくすばらしいと思ったのは私だけではないと思います。このことは、我々喜多流の子方の指導の仕方についてもう一度考え直すべきとの忠告に思えました。これから沢山の子方が育ちはじめますが、今まで通りの地声尊重ではいけないのです。あの舞台に座っていたお父さんたちがそれに早く気付いてくれればと思っています。
父菊生は他流の方々とも友人が多く、流派を越えてよいおつき合いをさせていただいています。私もこのよき伝統を受け継いで、一つの流儀や家に閉じこもることなく、他流の方々からも多くの刺激を受けて精進していきたいと思います。今回の会はその思いを新たにいたしました。
(平成13年12月 記)
写真 舞囃子、猩々乱 粟谷明生
写真 一調、笠の段 粟谷菊生、粟谷明生 曽和博朗
写真 能、隅田川 大槻文蔵 上田顕崇
写真提供 大槻文蔵
写真撮影者 浜口昭幸氏
『石橋』の連獅子を舞う投稿日:2001-10-14
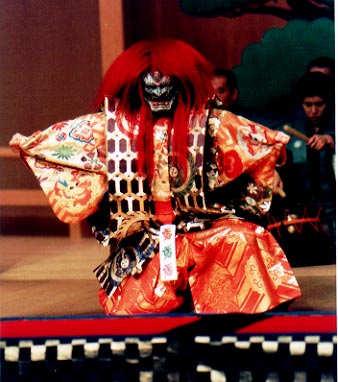
今年の秋の粟谷能の会(平成13年10月14日)では三番目の舞台『石橋』連獅子を、シテ親獅子・粟谷能夫、ツレ子獅子・粟谷明生で勤めました。
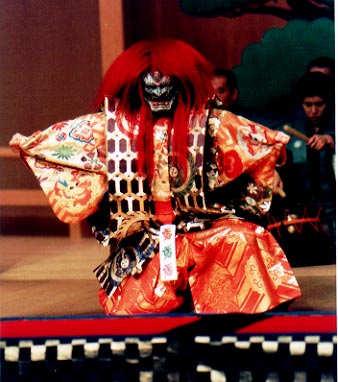
私が子獅子を勤めるのは、これで7回目となります。最初は、『道成寺』披きの後、34歳のときで、シテの親獅子は父・菊生でした。そのあとの3回は友枝昭世氏と、その後2回は能夫と勤めまして、今回が7回目となります。
父と勤めた披きのときは半能(前場を省略する)で、ワキの名のりの後、いきなり後場の獅子舞から演じるものでした。舞は、当時一般的に行われていた新しい型。これは、先代の喜多実先生が香川靖嗣氏に連獅子を披かせるときに一緒に舞われるために、やや型を少なくして創られたものです。それ以来その型で演じることが多くなり、私も新しい型で披きました。友枝昭世氏とは、東京駅の駅コンでの公演をはじめに笛の中谷明氏の明音会、青森能での公演の3回。この明音会(平成4年)のときから友枝昭世氏が従来の型に戻そうということで、以後は喜多流本来の型に戻り、実先生が考案された省略型は演じられなくなりました。
能夫とはすでに2回勤めています。昨年の秋田の協和町まほろば唐松能では、私の不注意で胃の中にアニサキスという虫が入ってしまい、大変体調が悪く、無事勤めましたが、自分自身不本意に思っていました。そのとき能夫が、私をいたわるように「今度、連獅子のやり直しをしよう」と言ってくれて、今回は私にとって、そのやり直しの気持ちの舞台ということだったのです。
これまで私が勤めてきた子獅子は、父と勤めた披きの舞台からすべて後場だけ演じる半能でした。今回は、前場もある正式な能で勤めるという、能夫の強い思いがあり、70回記念の粟谷能の会で実現することとなりました。今回は仙人が三人も登場する替えアイの特別演出を野村与十郎氏にお願いしました。中入り後、シテが装束の準備をしている間
に、三人の仙人が酒を酌み交わし、石橋のありさまや獅子の登場を予感させる語りの場面は、一人で語る通常のアイより楽しめるものと、シテが依頼したものです。
前場ではクセが謡の重い習とされています。力を込め大きなスケールでまさに唸るようにと父は言います。居グセのため、シテはじっと動かず、地謡が謡う、幅は一尺もなく、長さは三丈、谷をのぞめば千丈あまりという石橋のすさまじさ、そして、石橋の向こうにある文殊菩薩の住む浄土の美しさに耳を傾けながら、心の中にて共に謡うという、静の能です。観る方にとっては、いつ獅子が出てくるのか、待ち遠しい思いで、じりじりとしてくるところでしょう。中入りした後も、仙人が長閑に謡いながら出てきますから、ここでも焦れて焦れて、まだなのかと獅子の登場を待ちます。この焦れがあるからこそ、後場の獅子の舞の豪快な動きに心踊らせるのではないでしょうか。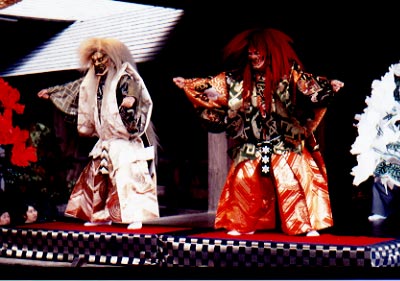
出の、激しい乱序の囃子で、半幕にて姿を見せる親獅子。幕が上がりどっしりとした運びで一の松にて石橋を見込み、さあ来いとばかり子獅子に合図を送ると、それを受けて子獅子は激しく軽やかに飛びはねシテについて舞台に入り、獅子舞の相舞となります。獅子とは文殊菩薩に仕える霊獣です。牡丹で飾られた2台の一畳台を所狭しと躍動し、飛び乗り飛び降り、息もつかせぬ動きで舞い遊びます。親獅子はゆっくり、ゆったりとしながらも力強い動き、子獅子は面も激しく振り、機敏に軽やかに子供のように飛びはね、すべてが敏捷に強く、そして子獅子らしくかわいらしさもあるというのが、父や先人たちからの心得として教えられてきました。前場と後場、鮮烈な静と動の対照。この対こそ能『石橋』の望ましい形であり真髄ではないでしょうか。
ツレの面は通常は子獅子口やシカミを使用します。私の披きのときは、銕仙会から「青鬼」という面を拝借しました。父は気持ちの悪い顔だと不満げでしたが、私は、青二才ならぬ、金泥に成長する前の段階として青い顔でもよいのではないかと思って、その恐ろしくパワフルな青鬼を使わせていただきました。拝借するときに観世暁夫氏は「我が家では青鬼は親獅子に使います」と仰っしゃられ、私自身も果たして赤頭に似合うか心配でしたが、つけてみるとよく似合い満足できました。後日『谷行』の鬼神役に梅若六郎氏が赤頭に青鬼をつけられたのを拝見し、おかしな選択ではなかったと安心したのを思い出します。
それ以後の公演は、粟谷家にある子獅子の面を使ってきました。この子獅子は残念ながらやや迫力に欠けるもので、私としては晴れの70回記念の粟谷能の会、能夫との『石橋』で、前回の不本意な舞台を一掃する気持ちも込めて勤めるとき、何か強い面をと思っていました。そんなとき、能夫より「実は良い獅子がある、ただ金泥なんだ。今回は披きではないからいいだろう…」と言われました。子獅子の顔は肉色(にくしき)といって、本来肌色で金泥は使わぬのが決まりなのです。親獅子は本家のお弟子所蔵の面を拝借し、久々の金泥獅子口の親子の再会となったわけです。
『石橋』は他流に比べ、喜多流では特に重い大曲とされています。それは獅子を重く大事に扱うということと共に、喜多流独特の赤い巻毛をつけた一人獅子が特別に重い扱いになっている所以だと思います。しかし、私は獅子に勿体をつけて、なかなか演じられない現状は不健全だとかねがね思っていました。連獅子のツレは20代の身体がきれる時期にやるべきです。ただ動きが活発なだけ、まるで運動会のようだ、能の演技とはいえないなどと言われても構わず、まず披きで一度猛烈に動くという体験をして、その経験を次につなげ、30代、40代と年齢を重ねながら、動きの妙味を覚えて円熟していき、子獅子を完成させていけばよいのです。そうしてゆくことで次の段階、目標の親獅子というものが見えくるのだと思います。そして、親獅子も同じように早め早めにと挑み、白い親獅子を作り上げていくべきと思うのです。そのためにも若い人たちに、早く挑んでほしいのです。私たちの諸先輩はみな、20代、24、25歳でお披きをしています。私が子獅子を披いたのが34歳ですから、これさえ遅いぐらいだったのです。
今回はとりわけ、二人で頑張って九段の舞(通常『石橋』は八段、『望月』は七段)でやろうと決め勤めました。激しい動きの子獅子を、歯切れよく舞いながらも、一回転半の飛び廻りに恐怖感を抱くようになりました。私も40代半ばを過ぎ、そろそろ自分の髪の毛に白いものも混じってまいりました。それにふさわしく次の目標、白獅子にシフトしていきたいと思います。
「早く来たれよ、若き獅子たち」と、思うこのごろです。
(平成13年10月 記)
石橋 披き 粟谷明生 撮影 あびこ写真
石橋 青森公演 友枝昭世 粟谷明生撮影 撮影 不明
石橋 まほろば公演 粟谷能夫 粟谷明生 撮影 東條 睦
面 獅子口 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
石橋 ツレ 粟谷明生 撮影 伊藤 英孝
『富士太鼓』の小書「狂乱之楽」を見直す投稿日:2001-10-14


秋の粟谷能の会(平成十三年十月十四日)で『富士太鼓』「狂乱之楽」を選びましたのは、息子、尚生が子方のできるうちに一度一緒に勤めておきたいという気持ちは言うまでもありませんが、それ以上に、能夫の「狂乱之楽」に対する熱き思いがあったからです。
以前に小書「狂乱之楽」を舞ったが、自分の思いを果たせなかった、それを私に託したい、今回の舞台でこれこそ「狂乱之楽」というものを創り出してほしいという強い働きかけがあったからこそで、私自身の演能意欲も一段とかき立てられました。
子方が出演する曲は子方の登場によって、ほのぼのとした雰囲気が生まれ、心休まるものです。
しかし反面、幼い動きや謡により演能の妨げになる危険も兼ね備えています。この『富士太鼓』も子方がよく演じてくれなければどうにもならないものです。
とりわけ最初のシテとの連吟が重要で、ここはシテと子方がよくはもり、音をきちんとそろえないと聞き苦しいものになり、『富士太鼓』という曲の扉が開きません。
子方は精一杯高い調子で大きな声を出して謡うことが肝要で、シテはその調子に添って、しかも味わいのある謡を、というのが心得です。
今回は尚生が一生懸命勤めてくれたお陰で私の演能がいかに助けられたかは、ご覧になられた方にはご承知いただけたと思います。
この曲に使用する面は中年の女性ということで「曲見」(しゃくみ)をかけることになっています。
我が家の伝書では、「深井」は上掛りの面也、下掛にては用いず、然れども、曲見にては楽の拍子に似合わず、依って「深井」とあります。
今回は粟谷家の「深井」よりもう少し若い「浅井」を選んでみました。
では今回の眼目である「狂乱之楽」とはどういうものか…。
これは、住吉の楽人・富士の妻が、宮中の管絃の催しに志願して都に上った夫が、天王寺の楽人・浅間に殺されたことを知り、狂乱して舞う楽の部分に特別演出を試みるものです。
「狂乱する」とは、能では、苦しみや悲しみで気が狂うほどに我を失ってさまよう様を表し、非常に高揚し激していくテンションの高い部分と、逆にボーッとして何も考えていないような部分との温度差が大きい状態を言うのだと聞かされています。
ここでは楽の途中で、シテが橋掛りに行き、クツログ型を入れ、舞の緩急も常とは違ったものにします。
「狂乱之楽」は、笛が森田流、小鼓が幸流、大鼓が葛野(かどの)流の三流がそろったときが本流であると能夫は教えてくれました。
笛が楽を吹き出すと、大小の鼓は、序の舞の序の部分の手配りで囃します。
この拍子に合わない、ある種ねじれのような手配りが心の高揚を表し、非常に面白い演出となります。この手配りがうまく重なり合うのが、幸流と葛野流という組み合わせなのです。能夫が「狂乱之楽」を試みたときは、大鼓が高安流であったため、この部分が実現出来ず悔いが残ったといいます。
そこで、今回はこの幸流 葛野流をそろえた「狂乱之楽」をと考えました。笛は敢えて私の信頼する一噌流の名手、一噌仙幸氏にお願い致しました。
一噌流は、先代の家元・実先生のときに申合ができ、藤田大五郎先生が「狂乱之楽」用に譜を作られており、遜色なくできるという思いがありました。
小鼓の幸流と大鼓の葛野流は若手で固めてと、小鼓は広島から横山幸彦氏をお呼びし、大鼓は若手のホープ亀井広忠氏にお願い致しました。
では、「狂乱之楽」をどう演出するかですが、伝書には、ただ「全体ニ静、橋掛ニクツロギ、太鼓ヲ見込ミ、後ハ位ススム」と書いてあるだけで、何の面白味も感じられません。
クツロギとは、言葉通り大昔ではゆっくりくつろいで、演者が幕の内に入りお茶を飲んだことさえあったようですが、今はもちろんそんなことはなく、クツロギという少し休止する型を入れて、思いを込めるという意味合いになります。
そこで、思いを込めるためにも、富士の妻の狂乱はどういうものかを考えなければなりません。妻は物着(舞台上で装束を替える)で、夫・富士の楽人の装束を身にまとい、鳥兜をかぶるだけで気持ちが高揚し、太鼓を敵(かたき)として打とうとします。それを娘が、あれは敵ではない、乱心ではないかと、母を制しますが、母は高ぶった声で、あの太鼓があるために夫は殺されたので、あの太鼓こそ夫を奪った敵と言って、一緒に太鼓を打って怨みを晴らそうと促します。娘も同感し、母娘は「打てや打てやと攻鼓」と太鼓を打ち続けるのです。
そうして打っていると、ふと、無念の死で成仏できずにいる富士の霊が現れ、妻のからだを借りて怨みを表白する移り舞となります。
ですから「狂乱之楽」の場面では、あるときは妻自身の狂乱であり、あるときは富士の霊の狂乱となるわけです。
最初、妻の気持ちが現れているところでは、ボーッとした感じで、ややゆっくりした動き、妻自らの葛藤した思いを表します。舞の途中から富士の霊の力が強くなると、怨みを前面に出したように激しく動き、またしばらくすると、自分自身に戻り、再び穏やかな動きになります。ときには、敵のはずの太鼓が亡き夫・富士のようにも見えてきて、なつかしく、ふと触れてみたいような衝動にかられるのではないでしょうか。
こんなややねじれた狂乱は、通常の型付では、なかなか表現できるものではありません。
今回は、妻と富士の怨みが入り乱れる様を表し、一方で妻が夫をいとおしむ所作も入れてみたいと考え、友枝昭世師や能夫とも相談して、太鼓に触れる新しい型を創作してみました。楽という抽象的な舞の中にやや写実的な、舞自体に意味を持たせるような、ドラマチックな演出があってもよいのではないかと思ったのです。
私はシテを演じていて、この富士の妻というのはとてもできた女性だと感じました。最初に夫の富士が管絃の催しに出るために都に上ると言ったとき、管絃に出られるのは直命が下った楽人だけである、富士はそれがないのだから行くべきでないと諭すなど、精神的にしっかりした方だという印象です。
そういう人でも狂乱してしまう、その辺を加味しながら演じなければと思いました。
このような「狂乱之楽」への思いを囃子方にもお伝えし、単に緩急をつけるにとどまらず、かけ声による演出効果も工夫していただき、妻自身の狂乱と富士の霊が取りついたときの狂乱の微妙な色合いをつけていただきました。
狂乱之楽が終わると、シテは「持ちたる撥をば剣と定め」と謡い舞った後に、怨みも少し晴れたのか、娘を伴って、郷里へと帰っていきます。この終盤の場面で、シテは「修羅の太鼓は打ち止みぬ・・・千秋楽を打たうよ」「泰平楽を打たうよ」と謡い、急に煩悩の雲が晴れ、明るいイメージになります。
お能はもともと祝祭的な芸能でもあったことから、こういう最後になる場合はありますが、ここでは、ただ泰平楽を謡うにとどまらず、あくまでもこの曲の主張となる、二人の親子の残像を演じ出さなくてはならないと思います。
最後に、夫の装束や鳥兜を脱ぎ捨て、最初にかぶっていた笠をかざして、「太鼓こそ思へば夫の形見なれど見置きてぞ帰りける」という地謡の謡で、シテは太鼓をじっと見込み、留拍子を踏みます。
そのとき、その後姿に、果たしてこの母娘の行く末は一体どうなるのだろうかというメッセージが見えないといけない、そうでなければ現在物『富士太鼓』が演じられたとはいえないだろう、などと考えて勤めました。
「狂乱之楽」という小書は、先代の実先生が先代宗家金剛厳氏との間で、この小書と金剛流の『殺生石』(女体)とを両派で共有すると約束され、現在この二流にしかないものです。
喜多流では『殺生石』(女体)は面白い小書として、頻繁に演能していますが、金剛流での「狂乱之楽」はあまり演じられていないようです。
伝書通り、「楽にクツロギが入る」だけでは面白味も無く、興味も湧かないのでしょう。
この小書が精彩を放つ演出法をみつけだし、必然性のある納得出来る小書きに再生しようと能夫も私も挑んだのです。
今回のように「狂乱之楽」の見直しができたのは、私自身が冒険のできる年齢であり、周りの温かい環境も含め、友枝昭世師や能夫のようなよき理解者がいたお陰と深く感謝しています。
能夫より託されたことができたかは不安もあり、改善の余地も多いと思います。
しかし、従来の伝承、伝書通りとその上に胡座をかき、曲、小書本来の持つ主張を見いださなくては、演者の怠慢と言われても返す言葉もありません。
これからも曲の主張を深く読みとり自分にしかできない演能の世界を創り上げていきたいと思っています。

思い起こせば四十年前、父・菊生が広島の粟谷益二郎七回忌追善能で「狂乱之楽」を勤めたときは、私が子方でした。
小鼓は横山幸彦氏のお父様の貴俊氏、大鼓が亀井広忠氏のお祖父様の俊雄先生、ちょうど今回のメンバーの一世代前の顔ぶれでした。役者があまりにもピッタリはまって驚くと共に、一つの舞台がここに伝承されたのではと感慨深いものがありました。
平成十三年十月
富士太鼓 粟谷明生、粟谷尚生 撮影 石田 裕
橋掛かり 撮影 あびこ
モノクロ 撮影 吉越 研
富士太鼓 粟谷菊生 粟谷明生 撮影 不明
『海人』の後場の存在価値投稿日:2001-06-23

粟谷 明生

喜多流に、私の年齢層が少ないこともあって、私は数多くの子方を勤めてきました。子方のときは、謡の言葉の意味などわかるはずもなく、ただ言われるままに鸚鵡返しに謡を覚え、自分の役割を忠実にこなしていたわけですが、それでも、舞台の一角にいて、先人たちの能をじっと見て、幼いながらも感じることはたくさんありました。
今回の研究公演(平成13年6月23日)で『海人』を勤めるに当たって、私自身が子方の房前の大臣としてシテを見つめていたときの子方の視点が曲づくりの出発点となりました。「メイロコンコントシテ、ワレヲトムロウオヒトナシ・・・・ゲニソレヨリハジウサアネン」と意味も解らず唱えていたときの子方の視点、シテの母親の感情、大臣淡海公と契りを結んだ海女少女(あまおとめ)像を考える前に、子方が母親をどう見ていたかを考慮してみたいと思ったのです。
子方はワキ、ワキ連を引き連れて登場すると、自らを房前の大臣と名乗り、亡くなったと聞かされている母の追善に讃州志度の浦に来たと述べます。そこへ一人の海女が現れ、ワキとの問答となり、海女が昔語りに大臣淡海公が志度の浦に下り、卑しき海女少女と契り、御子をもうけ、それが房前の大臣であると述べると、子方は「われこそ房前の大臣である、あら懐しい海女よ もっと詳しく語りなさい」と、母親と自分を結ぶ手がかりに喜び、自らを名乗って、自分は大臣の子と生まれ今は恵まれているが、気にかかることは「自分が生き残っても母を知らない」と涙します。母親が卑しい海女と知り、今は亡き母と側近から聞かせれているが、「いやもしかするとまだ生きているかもしれない」と願う一途な子の気持ち。シテはこれを受け止める側として十分な意識を持っていなくてはならないと、演技法が少しずつ見え始めてきました。
まず面に関してです。通常、後シテの面は「橋姫」か「泥眼」です。いずれも恐い顔で、とりわけ「橋姫」は『鉄輪』にも使われるように角はないが、怒り狂った鬼女なわけでたいへん恐ろしい顔つきですし、「泥眼」は眼光鋭く、嫉妬や怒りをたたえた『葵上』の六条御息所のイメージが相当強く、慈母の愛などを感じることは難しいものです。「龍女」という特殊な面もあるようですが、これも私の今のイメージには合いません。私が子方として、「どんなお母さんが出てくるのかな」と思いをふくらませているときに「橋姫」や「泥眼」では似合わず、子供心に「なんでこうなっちゃうのかな。こんな気持ち悪い顔がおかあさんじゃ、いやだよ」と思っていたものです。

そこで今回は、後シテの海女・母親像を考え直してみました。房前の大臣の供養により、龍女として成仏した海女。龍女ですから着付けは鱗模様の箔を、頭には女龍を戴きます。(喜多流には今まで女龍がなかったため、男龍に蔓帯をつけて牝であることを表していましたが、今回はやや細身の女龍を 大分の準職分、渡辺康喜氏に作って戴きました。)
からだ全体は龍を思わせますが、面はやはり、珠を取り戻すために海中に潜っていった若い海女少女の母の顔であり、悪魚と戦い死んでいくときの苦悩がにじみでてくる人間味ある顔でありたいと思いました。
淡海公と契りを結び、身籠り、房前の大臣を産んだすぐ後に、珠を取り戻してほしいといわれる少女、しかしこの少女はもう少女ではなく一児の母なのです、我が子の為なら命は露程も惜しくないと言いきれる無限の愛情を持つ母です。この子を世継ぎにするならと身分不相応の交換条件を提示したのは、賎の女では終わらない女の意地もあるかもしれませんが、我が子かわいさ,母親の情以外の何ものでもないわけです。海中深く、命がけの珠取りの行為、それは二度と戻れぬ死への旅路、その思いはどんなものだったでしょう‥‥。珠を目前にして、海上にわが子、父大臣も待っている、しかし自分の命と引き替えにしなければ珠を取り戻すことはできない、決死の覚悟をして手を合わせ、乳の下をかき切って珠を押し込めたときの、若き母親の苦悩が後シテの面に出てこなければ私は納得できないのです。龍女成仏はしていますが、成仏したことへの喜びだけではない表情が必要で、「泥眼」などが使われた経緯も、それゆえだと思うのですが。
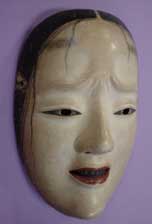
今回は、『玉葛』(平成13年2月)でかけた「玉葛女」を使ってみました。眉間に皺を寄せ苦悩を表す増寸髪系の面です。『玉葛』を演じるとき、小面では玉葛の苦悩が表現できないだろうと使ったのですが、玉葛にはもう少し美しいイメージがかもしだされないといけないようで、もっとこの「玉葛女」の面が生きる場面はないものかと思いあぐねていました。今回は試験的にかけてみましたが、観る人にはどのように映ったでしょうか。
そして、子方のときあっけない幕切れだと感じていた後半の演出にさまざまな工夫を凝らしてみました。よく『海人』は前場が勝負で後場は付け足しのようなもの、なくてもよいぐらいの言われ方をしますが、私はこれには異を唱えたいと思います。流儀内には、前場さえうまく謡い、舞えばよい『海人』になるという傾向、偏見があり、これは我々演者が知らず知らずに陥りやすい落とし穴です。作品の主旨を見失い、各部分の積み重ね、例えば『海人』の場合、一声を謡い、ワキとの問答常の如し、居クセアシライ常の如し、仕舞所玉の段、経を子方に渡し中入、後シテ舞囃子の通り最後にトメ拍子と、これでどうにか対応してしまおうと思ってしまうのです。私も以前は、能を演ずるとき、先輩より拝借した型付けをただ自分の謡本に写し、ここで立つ、右に回るそしてシカケヒラキ、あとは囃子型付け通りと、演能を軽く安易に考えていました。、また不思議にそれでもある程度はできてしまうところがあります。しかしこれでは、自分の一生の仕事たる能、情熱を傾ける能にならない、それより第一、観客にお見せする能にはならないと、今では思っています。

確かに前半は「玉取りの段」があり、子供のために、珠を取りに海中深く潜り、乳の下をかき切って珠を隠し、息も絶え絶えに、海上に浮かび出てくる仕方話は迫力があり圧巻です。ここに力を入れなければならないのは当然のことです。しかし、勇ましく海女の手柄話をし、子供は立派に大臣になったけれども、親になった早々、子供と死別させられて悲しいと消えていく前半だけでは、やはり優れた作品とはいえず、観る側に物足りなさ、ストレスがたまるでしょう。世阿弥もそう考え後半を付け加わえねばならなっかたはずです、その意味をくみ、私は私なりの工夫で『海人』を作りあげたかったのです。
能の構成が序破急という導入、展開、解決から成り立っているのに、急すなわち解決なくしてはおさまりが悪いです。能の最後は、余韻を残す幕切れであっても、切れ味が良い終わり方、これは演者の力量によるものですが、これが巧くできなければ作品全体の味わい、充実感が与えられるものではないと思うのです。
『海人』の後場は大変短いものですが、後場があって、充実してこそ、一曲として成立するのです。海女の霊が母として、龍女として、歓喜、報謝の舞を舞うところまで、充実感あふれる演出が必要です。立派になった子供に会えた喜び、前半に通い合った親子の情が後半も又くっきりと現れていなければいけないと思います。讃州志度寺縁起物語であるとだけで終わったのでは、作品の本筋からは外れてしまうのではないでしょうか。
そこで、後シテの登場の「出端」(大小太鼓で囃子、笛があしらう)では二段返(にだんがえし)という小書付の演出にしてみました。二段返は、出端を通常二段構成の寸法のものに打ち返す、つまり一段追加して三段にする演出です。この演出は、喜多流では昭和61年に粟谷新太郎が東京式能で金春惣右衛門氏、穂高光晴氏、柿原崇志氏、松田弘之氏で勤めた記録が最も新しくそれ以来となります。
この二段返しは素晴らしく、私の二段返しの構想に大きな力となりました。
二段返しを取り組むに当たり、金春惣右衛門先生や観世流の助川治氏にお教えをいただきました。金春先生にお尋ねしたら「観世寿夫さんとお相手した時は、シテは幕の中で床几に腰掛けていたね。本来は二段目で幕から出て、三の松まで出るんだよ、金春流の主張は上手が集まったときに、囃子方の技を見せるもの」と教えていただきました。助川氏からは「観世流は木魚をたたくような、管絃講の読経をイメージしてと元信先生から教えていただいています。ですから荘重に厳粛に打ち、クツロギはせぬが主張です」と教えていただきました。
このように観世流と金春流での二段返の考え方の違いが解ったのは大きな収穫でした。私は今回、金春先生の「三の松まで出る」を試み、観世流の仏教音楽を奏でるイメージを合わせて演出してみました。
また「出端」の前に、子方の言葉を受けて地謡が「いざ弔はん」と待謡がありますが、ここを今回はワキ方に謡ってもらいました。太鼓の観世元伯さんが、「この出端を打つときが難しい。お弔いの出端なのであまり騒がしく打ってもいけないと思うけれど、五流とも、その前に地謡が大合唱しているので抵抗がある」と言ってくれたのがヒントになり、ワキ方で謡ってもらうのはどうかと宝生閑氏に相談したところ、本来、ワキ方の謡本ではワキが謡うことになっているというので問題無しとすんなりとできました。
そして盤渉早舞(ばんしきはやまい)ですが、今回は「経懐中之舞(きょう、かいちゅう、の、まい)」の小書でいたしました。常は早舞の前に経巻を子方に渡すのですが、経懐中之舞は経巻を胸に懐中して早舞を舞います。大事な経巻を身体に温めその温もりを我が子に渡すとも、また経巻の力により舞い動ける母の霊、手放すときが我が子との別れのしるしともとれる、この演出。そしてクライマックス、舞の最後に子方に経巻を渡し「今この経の、徳用にて」と謡い、子方は高々と経巻を持ち上げる自然で説得力があるこの小書が私は好きです。
これらの演出を通して、後半を充実させ、『海人』という一曲を完結させていく、決して、多くの人が言うところの、前半だけが華ではない、後半の存在価値を見直したところに今回の研究公演の意味があったのではないかと思っています。
(平成13年6月 記)
写真撮影
カラー海人 石田裕氏
モノクロ海人 伊藤英孝氏
中啓 玉葛女 紋大口 粟谷明生
『経政』「烏手」を演じて投稿日:2001-03-01

3月の粟谷能の会は、粟谷新太郎三回忌追善能という事で、私は初番に『経政』「烏手」(からすで)を勤めました。
『経政』は、所演時間45分程の小品であるため、少年の初シテや素人弟子の初能に選ばれたり、曲目編成で重い曲が重なるときに、そのバランスをとるために配されたりすることがあり、今回もその例にもれず、能夫の大曲『三輪』、父菊生の『鞍馬天狗』「白頭」へと続くことから、初番は軽く、追善能にふさわしい曲ということで選びました。

『経政』は小品とはいいながら、詩情豊かで香り高い曲趣の中に、適度な緩急があり、舞っていても楽しく面白い作品です。修羅能ですが戦闘場面はなく、わずかに修羅の苦患を表現するのみで、全体としては琵琶の妙音に導かれながら、芸術魂をふるわすような趣向で、修羅能としては他にあまり類のない曲です。
平経政(観世流は経正)は、平清盛の弟、経盛の長男で、幼少のころより仁和寺の稚児として、鳥羽院第五皇子の覚性法親王と次の代の後白河院第四皇子の守覚法親王などに仕え、寵愛を受けていました。そのころより琵琶の名手と言われ、帝より琵琶の銘器青山(せいざん)を預け置かれるほどでした。それが都落ちの際、自らの運命を見定めた経政は、大切な琵琶を返上しに守覚法親王の許を訪ねます。そのときの様子は平家物語にくわしく語られていますが、親王と経政がかわす和歌や、仁和寺の僧・行慶(能ではワキ)とかわした和歌に、切々たる惜別の情があふれ、貴公子経政の人となりが感じさせられます。
能『経政』は平家物語とは場面をガラリと変え、物語は一の谷の合戦で果てた経政の霊を弔おうと、仁和寺で青山を出して管絃講(音楽による弔い)を催そうというところから始まります。
執り行うのは、和歌をかわして別れを惜しんだ僧・行慶。一般の能では一見の旅の僧が幽霊に出会い、回向を頼まれて弔うというものですが、ここではシテとワキが生前の親しい関係という形になっています。消え消えに、有るか無きかの様子で恥じ入りながら現れたシテ経政と、それを受け止めるワキ行慶。やがて夜更けて、花鳥風月、詩歌管絃を楽しんだころを懐かしみ、琵琶をかき鳴らして、夜遊の舞を披露します。突然、修羅の苦患に襲われますが、修羅道に落ちた自分の姿を人には見られたくない、恥ずかしいと言って「燈火を消し給え」と訴えます。最後は経政自ら燈火を吹き消し、修羅のまま消えていくのですから、成仏というより、暗闇の中に芸術を愛した自らの美意識 をひた隠しにする貴公子像を表現しているようです。
経政が琵琶の名手なら、弟の敦盛は笛の名手、父経盛も琵琶をよくし、経政の家はまさに音楽ファミリーでした。戦乱の時代の音楽家は美しくも悲劇的であったことは容易に想像できます。
能『経政』は、詩歌管絃に親しんでいた幼少のころの楽しさ、優雅さ、そして修羅の苦患を恥じらう繊細さを緩急つけて表現し、さわやかな小品として仕上げなければならないと思います。
『経政』は少年の演能によく選ばれると述べましたが、私自身も10代で初演して、近年2度ほど勤めました。今回勤めるに当たり、小書「烏手」というものに携わりたく取り組むことにしました。
「烏手」は喜多流と笛の森田流の間でしかない小書で、管絃講に惹かれ登場するシテが特に琵琶の音色に聞き入るという演出です。「烏手」は琵琶の演奏方法の一つだそうで、琵琶の音を笛に託すということです。もちろん笛の音が琵琶の音に聞こえるわけではありませんが、一曲の能の中で一管の音色の面白さを楽しむという稀な演出で笛方の重い習の演出方法だといえます。過去の記録では祖父粟谷益二郎が大正7年に演じているようです。
シテは琵琶の音(実際には笛の音色)を舞台にて下居て聞く型を演じ、独奏が終わると「あら面白の琵琶の音や」と心持ちを大事に謡います。シテは、管絃講の数ある楽器の中から、自分が親しんでいた、最も執心のある琵琶の音を聞き分け、右から聞こえてくるのか左からかと探っている風情の動きをします。
観世流は、この「あら面白の琵琶の音や」という詞章がなく、いきなり「風枯木を吹けば・・」と謡います。「あら面白の・・」の詞章がないことが、他の流派に笛の音を楽しむ「烏手」の小書がないゆえんなのでしょう。喜多流の「烏手」では「風枯木を・・」から「妄執の縁こそはかなけれ」までを省略し、笛の音に耳を傾ける型に思いを込め一つの見せ場としています。
能の世界では『絃上』や『蝉丸』など、琵琶の音を笛一管で奏で、そのイメージを表現するという手法があります。「烏手」「音取」のような小書では、笛がいかにその演出意図に合った演奏をするかがカギになり、同時にその吹き手の独奏自体を味わう事も大きな要素となります。
半年前、松田弘之さんが師である田中一次先生の「烏手」のテープを持ってこられ、「このように吹ければ…」といわれ、私に聞かせてくれました。その「烏手」は、すばらしく特にその音色に魅了され感動しました。松田さんとは、私の動きと吹き込むタイミングを繰り返し申合せしながらも、最後はお互いにあまり気にせず自己表現しあおうと決め舞台に臨みました。そして彼の力演で、「烏手」という今まであまり見向きもされなかった喜多流にしかないこの小書きが、あらたに息を吹き返したように思えたのは私だけではなかったと思います。
「烏手」になると常は「十六」と決まっている面を「中将」に替え、年齢も位も少し上がることになります。経政が一の谷の合戦で亡くなったのは二十歳か二十一歳ですから中将にすると死んだ時のお姿ということになるでしょう。しかし能『経政』に登場する経政は、仁和寺で詩歌管絃に親しんでいた平和で幸せな時期でのお話です。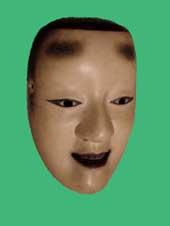
我が家の伝書にも「中将」と記されているのですが、私はどうしても曲の文意から「十六」からあまり離れたくない思いがあります。例えば梅若六郎家が所有されている、「十六中将」のような両者の中間にあるような面はないかと思っていましたところ、面打ち師石原良子氏とのお話の折り、「十六」と「中将」の間にあるという面を拝見し、今回は敢えて「中将」に拘らず拝借することにしました。
装束は伝書には白地厚板唐織、紫長絹それに萌黄大口袴と華やかなものに定められているようですが、残念ながら我が家ではなかなかそこまで揃いません。そこで観世暁夫さんにお願いし、銕仙会から拝借することができたことは嬉しく、暁夫さんには感謝しています。昨年銕仙会の夏の虫干の場に伺って装束を拝見させていただいたときに、紋大口袴がずらりと並んである中に紫と萌黄の紋大口袴が目にとまり、気に入ってしまいました。
是非『経政』「烏手」の時に拝借したいと、烏手や我が家の装束の内情などの話をして拝借させていただくことになりました。拝借に伺うときまで、萌黄色か紫色かで迷っていると、「うちの父はこの組合わせで清経の音取をいたしました」と、紫大口袴と白地の銕仙の花模様の厚板唐織、花色の長絹を見せてくださいました。もうその一言ですんなり決まりました。何しろ観世銕之亟先生と同じ扮装がつけられる事はこの上ない幸せですから。
今回も他流の人とお話をさせていただくことで、いろいろな面で得ることが多く、自分自身の意識を高めることにもなり、大変貴重な経験が出来たと思っています。喜多流の特徴を基盤にしながらも、決してその殻に閉じこもることなく、より広く、深い意識を持続したいと考えています。

『経政』の詞章の中に「情(こころ)声に発す、声文(あや)を成す事も」という言葉があります。喜多流の謡に関する伝書に、九代目七太夫・古能・健忘斉が書いた「悪魔払」という本があります。ここにも「情声に発す、声文に成す事」という一文があり、声に文があるように心がけて謡えと教えています。しかし未熟者がいたずらに文をつけると、文が嫌味に聞こえてよくないとも書かれています。「文を成す」という短い言葉の中の深い意味。この一文はいつも私自身の課題を指摘してくれるように思えるのです。
今回も、内向した中でどれほど外への訴え掛けが出来るか、その具合、程度の微妙と声そのものの質、張り、位と悩む中でこの言葉が浮かんできました。ただ謡らしき声を出し、節さえ正しく謡えば良いというにとどまらず、真実味のある演劇として、訴え掛けの強い謡を保つのはやはり難しいことです。自分の謡をもっとレベルアップしていきたいとあれこれ悩むときに、この言葉が脳裏をよぎります。
小品といわれるこの曲も、掘り出せば、まだまだ掘り尽くせないものがあります。それが古典としての存在する所以でしょう。
今回「烏手」を通して、いくらか掘り進んだとは思うものの、能の奥深さ、無尽蔵な宝の山は、掘れども掘れども、なかなかその正体を明かしてくれません。だからこそ掘り甲斐があるのだと思うのです。
(平成13年3月 記)
写真撮影 経政 東條 睦
石原良子打 創作面・仁和寺本堂 粟谷明生
一期一会の舞台となった『鞍馬天狗』白頭投稿日:2001-03-01

粟谷 明生 春の粟谷能の会(3月4日)のトメ(一日の最後の曲目)『鞍馬天狗』白頭は、父菊生が左足の不自由を押しながらも重厚な山伏、大天狗姿を見せてくれ、息子尚生も子方(沙那王)として、祖父の力演に元気に応じ、緊張感のあるよい舞台になったのでは…と思っています。
シテが菊生78歳、子方が尚生10歳、地頭が能夫51歳、後見の私が45歳、この4人が四角形のやぐらのようにガップリ組んでできたことが、私達のこの上ない喜びです。
子方は、幼稚園から小学1~2年生頃迄がまだ身体も小さく、舞台に立つと本当に幼気でかわいらしく、よい時期なのですが、反面身体の小ささの為か、喉はまだ完全に出来上がってなく、体力も充分とはいえないので、声の調子や張りにやや不足するところがあるのは仕方がありません。
尚生は小学4年生、子方として今が一番充実しているときです。大きな張りのある高い声でその充実期を通過することは貴重で不可欠なことですが、それは夏鳴く蝉の様にその命は短いものです。あと何年かで、子方独特の高い澄んだ声が出なくなるのは間違いなく、身体の成長と共に表舞台からは遠のく時期が来るのです。
父もまたこれから傘寿を迎えますが、今回ほどの底力ある演技がどのくらい続いてくれるか‥‥、そう考えると、今回の舞台はまさに一期一会、舞台役者の花を見るようで、感慨深いものがありました。
『鞍馬天狗』のシテと子方は親子より、祖父と孫の関係ぐらいの方が、案外冷静にことを運べるようです。後方の後見座から二人を見ていると、役としての距離をおきながらも決して遊離するでもなく、互いの間にしっかりとした緊張の糸を張っているようで、能『鞍馬天狗』を演じる空気が漂っていると感じました。ご覧頂いた皆様にも十分に楽しめる舞台になっていたものと確信しています。
同じ舞台にいて、父の長刀の使い方や謡の間の取り方などを目の当たりにすると、やはり貫禄があり勉強になります、私自身いつか真似して、盗んでみせると思う一方で、尚生も本物にふれ、舞台での各演者のエネルギーを心やからだに感じ取ってくれたのではと思いました。
父の舞台は、身体が楽々と自由に動いていた10年前と今では明らかにその動きに違いが生じていますが、足の痛み、梗塞による左側の不自由と動きがままならない部分を巧く舞台技術で補い、再びこの曲を舞うことがないのではという思いが込められ演じるところに、花咲くものであったのでしょう。孫との共演はもとより、将来の喜多流を担う大勢の「花見」(牛若丸を先頭に花見に行く平清盛の稚児たち)を従え、華やいだ気持ちの充実も後押しとなったことは間違いありません。
当日楽屋で、父は珍しく、花見の子供たちをみんな集めて、写真撮影をしていました。楽屋は小さい子供たちでにぎやか。「楽屋が子供たちでうるさいぐらいでないと、流儀は栄えない」と上機嫌で、大勢の子供たちに笑顔を振りまいている父の姿が印象的でした。
私の初舞台の花見の時は、近い年齢の子供がいなくて何人かの先輩の方々にご迷惑をお掛けしたようです。父がシテ、子方が能夫、花見は谷大作さん、佐藤喜雄さん(佐藤章雄氏の弟)が並んでくださいましたが、谷さんに後日談を聞くと「こんな大きなからだで花見に出されて本当は恥ずかしくていやだったんだよ」と苦笑されていました。どうも人数不足で無理矢理駆り出されていたようです。
当時、「大法輪」という雑誌に「子役」と題して、そのときの写真が掲載されましたが、良い記念として今でも残っています。そのときの花見の稚児が四十代半ばになり、その子供が今、子方を勤めて写真に納まっている、時の流れの早さを感じさせられます。
今回の申合せ(リハーサル)で、花見の子供達に長袴をはかせていると、ふと自分の花見の時のことが思い出されます。先輩たちが私の稽古時間に合わせて集まって一緒に稽古を受けてくれたこと、父が長袴姿の私に、こうやって出て行き、ここに座り、こうやって帰る、そして大事なことが一つ、絶対前の人の長袴を踏んではいけないよと教えてくれたことなど。今でもあの時の事は鮮明に思い出せるのです。 ですから、花見の子供達には当日の装束をつけて動きも実際にやらせてみる、本番の顔ぶれで共に舞台に立たせるなどして、本番に向けての緊張感や仲間意識を高めてやる必要があると感じます。これで、能舞台にあがるという特別な気持ちが子供達の心に刻み込まれるのではないか。こういうことが能楽師としての出発点であってほしいと思うのです。
舞台を勤め終わったあとも、父は舞台に立てた喜びが大きかったようです。夜、電話で尚生が父にその日の舞台のお礼と「もう一回、キクオチャマとやりたいなあー」と感想を言うと父が「これからもよろしくお願いします」と神妙に応じ、すかさず尚生が「こちらこそ」と答えたというので大笑いになったとか。こんなこともよい思い出になりそうです。(平成13年4月 記)
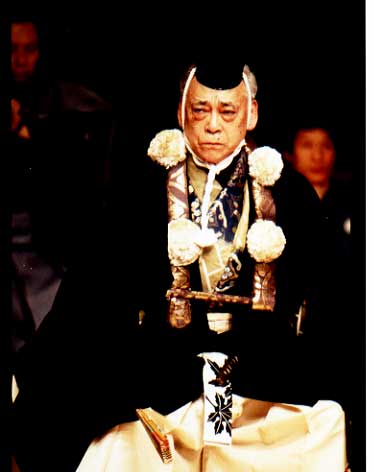 写真1
写真1
 写真2
写真2
 写真3
写真3
 写真4
写真4
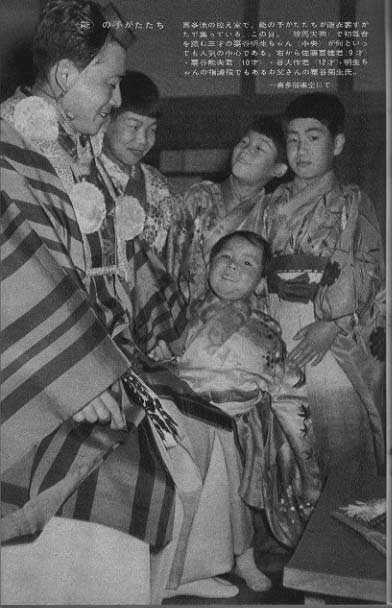 写真5
写真5
 写真6
写真6
写真説明
1.鞍馬天狗 前シテ 粟谷菊生 撮影 東條睦
2.鞍馬天狗 後子方 粟谷尚生 撮影 あびこ写真
3.鞍馬天狗 子方と花見 手前より 粟谷尚生 谷友矩 高林昌司 狩野祐一 友枝雄太郎 撮影 東條睦
4.鏡の間にて 左より 狩野祐一 友枝雄太郎 粟谷尚生 谷友矩 粟谷菊生 高林昌司 金子龍晟(今回出演せず)
5.「大法輪」 左より 粟谷菊生 谷大作 粟谷能夫 粟谷明生 佐藤喜雄
6.稽古 左より 粟谷菊生 粟谷明生 佐藤喜雄 佐藤章雄 粟谷能夫
『玉葛』の漠としたわかりにくさとは?投稿日:2001-02-01

玉葛の業因とは何だったのだろうか。回向を頼まれた僧(ワキ)が中入り後シテを待って謡う「たとひ業因重くとも、照らさざらめや日の光」という一文。はかなく逝った夕顔の忘れ形見であり、美しく、あまたの男たちに愛された玉葛が、なぜ業因に苦しめられなければならないのか。能『玉葛』を勤める(平成13年2月4日・広島「花の会」)に当たり、最初に感じたことは、この漠としたわかりにくさと、謡本だけ読んでいても作品の主旨はつかめないということでした。
『玉葛』に対する一般的な評価は、優雅さに欠けた平凡な曲であるとか、玉葛の苦悩が何であるかがわかりにくい、四番目能に入っているが、妄執や狂乱はそれほど強調されている訳でもなく、むしろ抒情的な曲である、といったものです。曲全体をみても、序の舞などの舞はなく、カケリ(動揺や苦悩を表す所作。緩急の変化がある)とキリの仕舞所があるだけで、後場の狂乱の部分もわずかに十五分くらいで終わるあっさりした作品となっています。
このキリの仕舞は、初心者用仕舞付に入っていて、ある種の乗りの良さのため身近で手軽な曲として扱われています。これが悪弊になっているというか、教える側も教わる側も曲趣を深くさぐることもなく、ただただ型のみの伝承に終わってしまう傾向にあると思います。そして私を含め能楽師達は「もう一つ面白味に欠ける、やり甲斐を感じない、玉葛の苦悩がはっきりしない…」とすすんで勤める者が少ないのが本当のところです。
しかし、今回演じる状況になり、そこに留まっていたのでは演じようもなく、また観る人に何も伝わらずじまいになるのは如何なものか、自分なりに納得して演じたい、そのためには作品の主旨を自分なりに掘り下げてみる必要があると感じ、謡本の向こうまで足を踏み入れることになりました。
『玉葛』は金春禅竹の作品です。彼の作品は『芭蕉』『定家』にみるように、芭蕉という植物に象徴される精神的なスケールの大きさ、式子内親王の恋の妄執の心の動きを定家葛になぞり緻密かつ大胆に描く発想の曲趣があります。『玉葛』も源氏物語をよく読み込んでいた禅竹が、その中から精神的な何かをすくいとって一曲に仕上げたのではないでしょうか。当時の観客は源氏物語をごく一般の教養として知っていたようですので、内容も十分理解して楽しんでいたはずです。
源氏物語の中で、玉葛に関する物語は「玉葛」から「真木柱」まで十帖にも渡り、作者・紫式部が力を入れて書き込んでいることがわかります。玉葛は頭中将と夕顔の間の子。母・夕顔は源氏との逢瀬で突然物の怪に襲われて急死します。母の行方がわからないまま、玉葛は乳母に育てられ、四歳で乳母の夫の赴任先、筑紫へと下ります。二十歳になり美しく成長した玉葛。大夫の監や多くの男性の求愛を受けますが、田舎に埋もれさせてはならじと決死の逃避行。無事都に着きますが頼る者もなく、卑しい人たちと暮らしながら、何一つ事態は好転しません。かくなる上は神仏にすがろうと母との再開を祈願する初瀬詣にでると、夕顔の侍女で、今は源氏の北の方・紫上に仕えている右近に出会います。右近の報告で、源氏は玉のように美しい夕顔の忘れ形見を引き取り、養父として大切に世話します。柏木、蛍兵部卿宮、髭黒大将など多くの男性たちからの求愛、それにも増して養父源氏からの恋慕に戸惑う玉葛。物語では最終的には髭黒の妻となり、子供ももうけ幸せな生涯を送ります。
玉葛の一生をたどってみれば、早くに母を亡くし、田舎に下ったつらさはあるものの、源氏に迎えられてからは一見幸せな生活ぶりです。「業因」とか、払えども払えどもついてくる「執心」「妄執の雲霧」とは無縁のように思えますが、禅竹は何をもって玉葛の執心と考えたのでしょう。
一つは玉葛の美し過ぎるための罪です。大夫の監、柏木、蛍兵部卿宮など、多くの男の心を悩ましたことへの罪。中世の仏教思想には、女は生まれながらにしてけがれたもので、男の心を乱れさせ苦悩を与えるのは業因の深い罪障となると考えられていました。その罪が成仏するのにさしさわりになるということです。美しさが罪つくりで、そのために妄執に悩まされ成仏できないなど、現代ではとても理解できない考え方で、玉葛という舞台を曖昧に終わらせてしまう一因でもあります。
そしてもう一つは源氏との関係における罪です。源氏にとって、夕顔は愛情が頂点に達したときに突然、死によって断ち切られた存在。その思い出は美しいままに結晶されています。その忘れ形見である玉葛は夕顔の面影を残し、愛しくてたまりません。源氏は養父としての立場を保とうとしますが、その思いはあふれ、ときに玉葛を困惑させるまでになってしまいます。
瀬戸内寂聴氏は『わたしの源氏物語』(集英社文庫)の中で、源氏が玉葛に添い寝する場面について「几帳の中に入り手を握っているのだから、その接近度は密接である・・・源氏の着ているものは直衣と指貫だっただろうから、それを脱ぐというのは、ぴったり女に寄りそいたいためで、あわよくば、そのまま、抱いてしまうつもりだった。ところが玉葛があんまりびっくりして身を硬くして辛そうに泣きだしたので、さすがにそれ以上のことは出来なくなってしまった。…(そして)出て行きぎわには、ゆめゆめ人に悟られないようにと注意したのは、いい気なものにもほどがある」と書いています。源氏の恋慕、それに困惑する玉葛。ここにも女の罪障があるというわけです。
私は今回、後場の一声でシテ(玉葛の霊)が謡う「恋いわたる身はそれならで玉葛いかなるすじをたどり来ぬらん」で、つくづく源氏との関係を意識させられました。この歌は「母を恋い慕って初瀬にやってきた。今は現し身にない私がどうしてここに来たのでしょう」というほどの意味で、玉葛の気持ちが表現されています。源氏物語ではこの歌とほとんど同じ歌を源氏が詠っています。つまり「それならで」が「それなれど」、「たどり来ぬらん」が「尋ね来つらん」と違うだけであとは全く同じ。「私は今も夕顔を恋い慕っているけれども、その娘である玉葛がどういう筋で私のところに尋ねてきたのだろう」という源氏の気持ちです。禅竹がこの歌を意識しているのは当然で、後場でいきなりこれをシテに謡わせるのは、やはり玉葛の苦悩の一番目にくるのは源氏との関係だと考えます。
私自身、玉葛の歌を謡いながらも、布石になっている源氏の歌を合わせ鏡のように体に感じずには、謡えませんでした。
しかし、玉葛の執心は、美しさや源氏との関係のみに集約されるものではないと思いま<す。時を経て髭黒の妻になり暮らしながらも、なぜ髭黒というそれほど愛してもいない男と一緒にならざるを得なかったか、待つだけの時代の女の悲しさを思ったり、または過去に心を悩まさせた男たちのことを思い浮かべたり、もちろん源氏の息づかいや語り口をも思い出し熱くなることもあったでしょう。現代の私たちでも共有する、幸せな結婚生活をしながら、時折、若き日の恋の遊びと痛手が思い出され、心にチクリと刺される感触、そういうさまざまな執心のようでもあります。全体にそれほど深刻なものではないにしても、二重、三重にも重なる執心、雲霧のように晴れない妄執が、玉葛を苦しめているとみることが出来るのではないでしょうか。 
今回の演能で、普通は前場も後場も小面というのが喜多流の手法ですが、後シテで我が家の「玉葛女」という、苦しみが漂う面を使ってみました。観世流では十寸髪(ますかみ)という、髪が乱れ眉間にへこみと皺のあるものを使うようです。
喜多流本来の小面を選択する意図は「喜多の女物は小面」という規定であったり、また持ち運びの簡素化に歪められながらも、やはり世にも稀な清純な美人を考えてのことでしょう。しかし私はやはり後シテの執心に苦しめられている玉葛を想像するに、小面のお顔では、それを表現するには似合わなく、あまりに難しい演出になると思います。苦悩し、屈折した表情があってこそ訴えかけが生まれると思いたいのです。
能『玉葛』では、玉葛の長い一生のうち、いつの時期を想定して登場するのだろうかと考えてみました。美しさに磨きがかかってくる十代の玉葛をイメージし、成人する女性以前の乙女のような段階ではないかという人もいます。私は稽古を重ねるに従い、源氏の影に悩んでいた二十一歳過ぎのころそのままの玉葛と、物語にはあまり書かれていない落ち着いた生活に入りながらも時々心の奥底に蘇るあの時を思う大人の玉葛なるものを思い巡らして演じました。
そして「居グセ」の部分。筑紫から早船を仕立てて逃亡する道行的な場面で、松浦潟、浮島、響の灘など原作を知らないとわかりにくい暗示的な文体でつづられています。ここを舞う型付が狩野家に伝わっており、今回はそれをお借りして舞ってみました。心の内をじっくりと地謡が謡う表現、またそれにつられてどうしても動きたくなる自分の体の反応が面白く感じられました。
シテの出(登場の仕方の出囃子)で、たまに前場も後場も同じ出になることがあります。玉葛も前場、後場で一声(いっせい)という出で舞台へ登場しますが、この出の気持ちを我が師、友枝昭世氏は「前場は棹を持ち、女舟人の風情だから、船の流れを意識し、いくぶんサラリと運び、後場は執心を持ちながらも、お経にひかれて出てくるので、やや重々しく運ぶと良い」と教えてくださいました。また当日お相手して頂いた小鼓の横山貴俊氏に、一声をどのように打ち分けられるのか、お聞きしましたら、「そう違いはないけれども、簡単にいえば、生きた人間と死んだ人間の違い、そう思って打っています」ということで、これもなかなか面白い見方だと思い、心に留めておくことにしました。
今回の広島の公演は、『芦刈』『玉葛』『海人』の三曲構成でした。私の後の『海人』の装束が腰巻・水衣で、私の『玉葛』と重なってしまうので、私の方の装束を常とは変えてみました。舞台上、一日の公演で装束や作り物が重なる番組構成は好ましくなく、通常は重ならないように調整するのですが、仕方がない場合は両者がゆずり合う習慣があります。
前シテは唐織着流しの肩脱ぎにしてみました。肩脱ぎは本来、後シテの狂乱姿のものですが、肩脱ぎには労働を表現するという意味もあります。今回は女舟人、棹を持ち舟を漕ぐという事で、そのようにしました。後シテは上衣は金の摺箔で、緋大口袴の裳着胴大口袴という形でいたしました。鬘は常は片方だけ垂らすのですが、大口袴とのバランスを考え両側の髪を垂らしました。今回は装束が常とは大きく違い、面も替えの玉葛女ということで、観る方には多少戸惑いがあったかもしれません。
演者としては伝書を基に、謡本や源氏物語を読み、演出に工夫を凝らし、いろいろ考えて勤めてみましたが、やはり『玉葛』は難しく、演じにくいと言わざるを得ませんでした。万物は決して一重ではない。玉葛の妄執も決して源氏のこと一色だけではなかったはずです。業因だとか妄執といいながら、劇的な葛藤というほどのものでなく、もしかしたら、夢の中で、あの頃の輝かしい時代にひととき浸っていたいという贅沢者の悩みであったかもしれないのです。実際、この曲の終わり方は「長き夢路は覚めにけり」(玉葛が迷いの夢から覚めたと見て、僧の夢も覚めた)というもので、成仏したとか救われたとかではありません。だから『玉葛』は単純な解釈では消化しきれない難しさがあるのです。
我々は修業過程で「気をかけて」とか「気持ちを張って」と教えられてきました。これは芸に心を込めてという意味らしく、とても重要で深い内容のある言葉ですが、ともすると、一手一足の誠意の込め方が足りないときに、叱咤激励として発せられる言葉に変化し、受け取る側もただ力を入れるに留まってしまいがちです。『玉葛』という曲は、この気合いとか気の張りといったものがおよそ似合わない曲のように感じます。強い妄執を演ずる時、我々はその思いを体の中に一端蓄積し、加工しそして発散しますが、玉葛の妄執はそれとはちょっと異質です。蓄積されたものを、故意に外へ訴えかけるのではなく、演者自身の体の中へ中へと取り込んで、幾重もの思いを熟成させていくもののように思えるのです。ですからこの『玉葛』は、人生経験を積んだ本当の大人がさりげなく演じたときに、すばらしい作品に開花するのかもしれません。
(平成13年2月 記)
撮影 「玉葛」前後 石田 裕
面 「玉葛女」 粟谷明生
『実盛』で老体の執心に取り組む投稿日:2000-12-07

『実盛』で老体の執心に取り組む
粟谷 明生

二十世紀最後の研究公演(平成十二年十一月二十五日)で、私はかねてからの夢、憧れの大曲『実盛』勤めました。『実盛』は老武者の執心を描く大曲です。前場は老人の独唱が大半を占め、後場は老体ではあるが型所が多く、その動きの中に老武者の心情を入れなければならないため、若い演者には手も足もでない難曲と言われていますが、私はこの名曲を是非四十代で演じたいと研究公演発足の頃より計画していました。
能の世界では、ある年齢にならないと老体ができないという消極的な考えが、さも本筋本流のように美化されているところがありますが、本来そういうものではなく、技量を持ち得た志のある演者ならば、若年であろうと許されるべきもので、演者は年齢に左右されることなく、常に前向きにそれぞれの高い目標を見据えることが肝心だと思うのです。でなければこの世界は閉鎖的であまりに悲しいではありませんか。今四十代で老体を経験しておくのは、それを演じるのにふさわしい年齢になったからといって、いきなりできるものではない、若い時に取り組む必要性を充分心得てのことです。そして何よりもよき指導者からの芸の伝承を逃すわけにはいかないという本筋の信念にほかなりません。今回四十代半ばの私の実盛がどうであったか、それにしてはへたじゃないか、といわれれば一言もないのですが、志がそこにあったことは、間違いないのです。
若い人が老体を演じるのが難しいと言われる要因は、老体のからだなり、動きに、なりきれないということがありますが、もっと本質的なことは、尉である実盛の霊としての謡が謡えるかということにあると思います。声の質や発声を、老体らしくする工夫は当然必要ですが、それ以上に、実盛という人物像をどのように理解し、謡の意味するところは何かを明確に把握し、自分の中で消化して、イメージすること、だからこう謡うのだという裏打ちされたものが必要です。それが言葉の強弱や張り、位に反映し、強い訴えかけになっていくのだと思います。
そこで私はまず「実盛の執心とは何だったのか」を考えてみました。「老武者とて人々にあなずられんも口惜しかるべし、鬢鬚(びんぴげ)を墨に染め、若やぎ討ち死にせん」と常々言っていて、それを実行に移した実盛。そこには、人生五十年時代に、七十三歳まで生きた男の、生き過ぎたという思い、どう死すべきか、人生の幕引への切ないまでの美学があったと思うのです。平家の衰退はわかっている、篠原の戦いが自分の死すべき場であろうと覚悟を決め、それならば若々しく、日本一の剛の者として果てたいと考えていたのでしょう。修羅の中に生きた老武者の死に場所は戦さの場こそがふさわしい。これが多くの戦さで人を殺してきた修羅の業でもあったのです。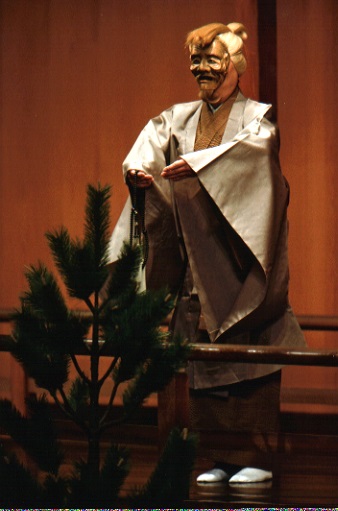
ところが実盛の思うように事は運ばない。二歳の頃、実盛が命を救っている敵の大将・木曽義仲、彼に討たれるならそれもよしと立ち向かう老武者の心意気を、家来の手塚の太郎光盛にはばまれてしまう無念。討たれた後、首を洗われ老体を暴かれてしまう無念。それによってあっぱれな武者として名を残すことになったことへの恥ずかしさ。これらが複雑に絡み合って、実盛の執心となって成仏できず、二百年もの間、幽霊となってこの世をさまようことになるのです。戦さの場でも名を名乗らず、二百年後、他阿弥上人の前に立ち、安楽国に生まれ変われると歓喜したときも、名を名乗らぬことに固執したところに、ひねくれ者・実盛の執心の深さが見てとれます。
さて、実盛を知るために、ここで少し、彼の生い立ちを見ておきたいと思います。斎藤別当実盛は越前の生まれ、藤原氏の藤と、藤原の斎宮の頭を勤めたことから斎をとり斎藤の名字をもらったようです。別当は荘園の管理をする職で、それほど高い位ではなく、下級武士ほどの身分だったと思われます。保元・平治の乱では源氏につき、義朝のもとで手柄を立てています。二十年を経て篠原の戦いでは平家につき、これは二股武士ではないかと文楽などで脚色されているようですが、当時の田舎の下級武士は、自らの領地を守るために、その時々の領主につくことはよくあることでした。ましてや源氏方で戦ったときから二十年の歳月が流れているとあれば、何らの問題はなかったはずですお能で取り上げられ、あっぱれな武将と讚えられると、高貴な人と勘違いされがちですが、実盛の場合はごく身近にいる下級武士で、偉いのは人物像であって位ではないことをわきまえて演じるべきだと感じました。

父菊生は謡が難しいものに『葵上』があるが、やはり一番難しいのは『実盛』だろう、その中でも前シテならば「笙歌遥かに聞こゆ孤雲の上、聖衆来迎す落日の前・・」と「深山木の、その梢とは見えざりし、桜は花に現はれたる、老い木をそれとご覧ぜよ」は、とりわけ難しいがいいところなんだと言います。
「笙歌遥かに聞こゆ孤雲の上」は能『石橋』で登場する大江定基、出家し寂昭法師となった人の臨終の和歌です。ここは浄土への距離感と透明感をもって遥かを見やりじっくりと謡うのが鍵のようです。
また、「深山木の…」は名を名乗れの問答の後に自らをほのめかして謡いますが、大鼓の亀井広忠氏が「本来道具を取り準備するところですが、とても動けない」と言われるごとく、訴えかけのある大事なところです。これは頼政の和歌ですが、執心を残している老体同士をここにはめ込んだ世阿弥らしい洒落た演出を感じさせられます。
そして物語も最後「老武者の悲しさは、戦には為疲れたり」。戦さ上手の実盛のはずが、老いて、戦さにも、人生にも疲れたと独白するところは、壮絶であり悲しくもあります。そして、篠原の土になることを願い、弔いを乞います。実盛の執心、心の揺れを常に意識しつつ気持ちを張りつめ謡っていくこと、この作業なしではこの作品は成り立たないように思えました。
世阿弥は、斎藤別当実盛没後二百年目にして、その亡霊が時宗の他阿弥上人の夢枕に立ち、言葉を交わし、十念を授けられたという噂話に魅かれ、これを戯曲にします。当時流行の時宗のPRにもなるのではないかと思いたったようで、江戸時代に曾根崎で心中事件が起こると、即座に心中ものを戯曲にしてしまう近松門左衛門のように、作り手の名手達は、いつの時代も、世の中に流布する話に敏感でパワフルに対応していたのではないでしょうか。

修羅物としては珍しく、狂言口開け(アイが最初に舞台状況を説明する)で始まり、シテの老人を幽霊として登場させ、後半は甲冑姿にて極楽世界を謡い、強い執心の表現としての大ノリのリズムにも多分に踊り念仏を意識させ、全体に宗教色を強く現わしています。実盛の執心に焦点を当て、静かにその心の内を語らせながらも、ただ静謐さに留まらず、後半の踊り念仏の場や戦さ語りで盛り上げ、一人の男を描いていく当たり、さすが世阿弥、物語作家としての面目躍如というところです。
四十代で『実盛』という老体を勤めて、今後五十代、六十代でのよりよい実盛への布石となったことは確かです。この曲が実盛という人物を通して、男の生涯はどうあるべきか、どう生き、どう幕を下ろすかという重いテーマを我々に投げかけているように思え、研究公演で取り上げ、深く掘り下げておく意義があったのではと思っています。
(平成十二年十二月記)
実盛写真
舞台写真撮影 石田 裕
首洗い池・実盛塚 粟谷明生
『葵上』の謡の奥深さ投稿日:2000-10-01
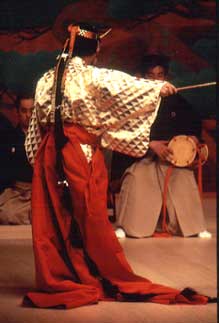
粟谷明生
シテ方の能楽師が一人前になったとお墨付きをいただく曲が『道成寺』です。
昔は『道成寺』を披くには、『紅葉狩』で「急の舞」、『黒塚』で「祈り」を、『葵上』では『道成寺』と同じ扮装の坪折姿に慣れ、謡の勉強をし、そして『道成寺』へと進むという修行過程があったようです。しかし最近は必ずしもこの順序は守られず、かくいう私も『道成寺』のあとに『葵上』を勤めた経験者です。
私は『葵上』はやはり『道成寺』の経験を基に勤めた方がよいと思っています。『葵上』は謡が難しい曲です。単なる節扱いだけではなく、『葵上』という曲をいかに謡えるかが重要なのです。だからこそ、この曲が『道成寺』を勤めた者の次なる大きなテーマになると考えた方が良いのではと私は感じています。
これからの喜多流を支えていく若い人々が、謡の技術アップのためにどうしても通らねばならぬ曲、又一般のお謡のお稽古をなさっている素人の方々でも一度は謡ってみたいと思う曲、『葵上』。そうでありながら、簡単に稽古や演能のお許しが出ない理由は、それほどまでに大事な曲だからなのです。聞いていてる人が六条御息所の生霊と想像出来る謡、それは難しく短期間で修得出来るものではありませんが、玄人も素人も乗り越えなくてならない課題で、これが上手に謡えるようになると「ああ、大人の謡になってきたね」「曲を謡えるようになりましたね」とようやく先輩や先生に認められるのです。
というわけで、『葵上』の最も大事なところ、それは前場のシテの謡であるといえます。シテ連(照日の前)の梓弓の音と呪文によって呼び寄せられたシテ(六条御息所の生霊)の第一声「三つの車に法の道、火宅の門をや出でぬらん」。ここからクドキまで、一部シテ連やワキ連が謡うところを除いてほとんどシテ一人が謡い続け、葵上(出し小袖/小袖が葵上を象徴するように舞台中央に置かれている)を打擲するところまで、一気に物語を進めていきます。
ここの謡、詞には御息所の思いのたけが込められ、節づかいは感情の起伏を巧みに表現しています。この大事な箇所を、ただ大きな声で朗々と謡いあげるだけでは曲にならず、曲に拘り過ぎて蚊の泣くような萎びた声では謡にならず、節を追うだけの幼稚さでは気持ちを表すことは出来ません。そして舞台に於いては必要以上のやる気満々、情熱いっぱいという熱演は、逆に観客や廻りの出演者をもしらけさせ空回りで失敗になるという性格を持った曲なのです。
喜多流で私の年代以上の人たちは皆、喜多実先生にお習いしていました。実先生は、
お稽古というと「さあ、仕舞を舞ってごらん」「能の稽古をしてあげる」と型重視で舞うことの嬉しさ楽しさを教えて下さいましたが、謡の方には余り時間をかけられませんでした。詞や節づかいが間違いなければ、それほど注意も受けず、謡のご注意で何回もダメ出しが出るなどの経験はありませんでした。しかし、歌舞二曲でできている能の中で、その構成は謡の占める割合が七割から八割、動き(舞など)は二、三割ぐらいと言われています。七割を占める謡をいかに謡えるかで、お能の出来不出来、その演者のよし悪しが決まるといっても過言ではないのです。
『葵上』のシテ、御息所の謡は、張りのある柔和な落ち着きと、柔らかさの中にも強さがあり、強さの中に艶がある、‥‥こう謡いたいのです。そのためにも、御息所の人となり、心の動きを知らねばなりません。
六条御息所は、前の東宮妃、つまり皇太子妃であったわけで、東宮の早世によって後ろ盾を失ってしまいますが、高貴な身分の女性です。しかも教養豊かで理知的、源氏とかわす和歌やもてなし方にも典雅な気品が匂い立ち、源氏の心をとらえた女性でもあります。しかし一方で、源氏より七歳年上であることや、近頃の何の契りもない情況の心もとなさから、いつかは源氏が自分のもとから去っていくだろうと不安を抱え、若く美しい正妻・葵上に対する嫉妬は知らず知らずにつのるのです。それでも高貴な身の上、はしたない行動には出られず、じっと耐えています。
そんな六条御息所を打ちのめしたのは、賀茂の斎院の御禊(ごけい)の折、都大路を行列する斎院と光源氏らの姿を一目見ようと出立した六条御息所の車が、後から来た葵上の車に押しやられ、打ち払われた事件です。散々の恥ずかしめを受け、その上源氏の晴れ姿を見ることも出来ませんでした。これが深い恨みとなって、夜半ともなると理性の箍(たが)がはずれ、生霊となって葵上に取りつき苦しめることになります。その行為は自分では押しとどめることができませんが、恥ずかしく悲しくも感じているのです。
こんな六条御息所の心情は「夕顔の宿の破れ車、遣る方なきこそ悲しけれ」や「あら恥づかしや今とても、忍び車のわが姿」など、前場のシテや地の謡に切々と謡われています。「われ世にありし古は」からのクドキでは、自分が華やかにときめいていた時代を謡い、それにひきかえ、今の自分のみじめさも吐露します。そして「われ人のため辛ければ、必ず身にも報ふなり」と謡って、人に辛い思いをさせた者は、報いを受けるのだとばかり、六条御息所の気持ちは高ぶり、「今は打たではかなうまじ」と、ひと打ちするところまで追いつめられていきます。
この流れや心情をシテはしっかり受け止め謡っていくことが大事です。日ごろ理知的で高貴な人が、自分の感情を抑えきれずに、こうまで爆発してしまうのは何故か。それは賀茂の祭りという大衆の面前で散々に恥ずかしめを受けたことと、もう一つ、自分にはもう望めない葵上の懐妊が決定的な打撃となったのです。嫉妬する対象がただ若く美しい正妻というだけではない、全ては承知の上なのにどうしても気になる懐妊という事実であると私は解釈して演じています。
さて、『葵上』では、葵上(出し小袖)を打つときの打ち方もポイントの一つです。
林望さんは著書『林望が能を読む』(集英社文庫)において、「葵上を打擲した後も、それで六条御息所の心が晴れたのではない。それどころか、嫉妬に狂って、葵上を殴る自分の姿が、鏡に映ってはっと気が付く。ああ、なんて醜いおのれなのだろう。こうして、彼女は、ますます深く暗い絶望の淵に沈んで行きながら、破れ車に乗って消えて行くのである。」とし、「その面影もはづかしや。枕に立てる破れ車、うち乗せ隠れ行こうよ」というのは、恥ずかしい己の姿をさっと乗せて行こうというのであって、葵上を乗せてさらっていこうというのではないと指摘し、従来みなそのような解釈になっているのは怪しむべきだと述べています。
この指摘は、私もまったく同感ですが、このような誤解となるのは型付のためでもあろうと思われます。「その面影・・・・うち乗せ隠れ行こうよ」と大小前にて廻り返し(ぐるぐるまわる)をしながら着ている坪折を脱ぎ、葵上の出し小袖の所にフワッと取りついたかのようにして行き、拍子を踏んで消えていく型付。これではいかにも、葵上を自分の破れ車に乗せ、邪悪な霊界に連れ去ろうとしているように受け取られてもしかたない型です。この型が問題であって、林さんが言われるように、鏡に映った自分の醜い姿、嫉妬に狂った姿を恥ずかしく思い、さっと消え去るしかないという所作に型を変えるべきでしよう。実際、観世流にはこのような型があり、昨年(平成11年)10月に私が勤めました『葵上』ではそのような型にて試みました。
さらに、そのときの舞台は小書「長髢」(ながかもじ)で、緋の長袴をはき、長い髢をつけました。長袴は宮中の優美なイメージが出るので、六条御息所にふさわしく、観世流では小書「空の祈」で使っているようです。私はかねてからこれを着て演じたいと考えていました。緋色は激しい嫉妬や執心を表現するのに合っています。長袴や長髢は長いものを引きずりますから、執心を引きずっているイメージにも合います。緋の長袴は喜多流では『殺生石』の小書「女体」を金剛流から頂いた時に入って来まして、使用が可能となりました。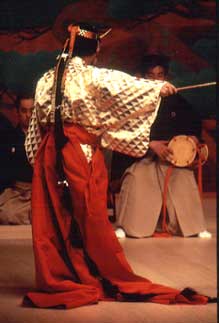
長袴の演出にしますと、袴を付けるためどうしても中入りしなければならず、従来の型ができにくく、工夫が必要とされます。鏡に映った自分の姿を見て恥ずかしく思い、さっと破れ車に乗って帰っていく型を生かすためには、坪折を脱ぎ葵上を見たら、すーっと橋掛かりに走りこんで中入りしてしまう、このほうが似つかわしいだろう思い、そのようにやりました。
また、喜多流には替えの型で、葵上の出し小袖に扇を投げ捨てる型もありますが、ここまでしますと、六条御息所像が全く違うものになってしまい感心しません。この型と常の型は誤解される型であり、演出のまずさが残っていると気になり改めたいと思っているものです。
私は父(粟谷菊生)から、この打つところが難しく、御息所になれるかなれないかの大事なところだと教えられてきました。「ここぞとばかり強く打つ者がいるが、そこは本当は打てないところ、打ってはいけないのだ」と父は言います。そして、六条御息所は皇太子の奥様になり子供もある高貴な方であることなど、御息所の立場とその場の状況を簡潔な言葉で説明し、だから打ち方はこうなるのだと言って、一振り見せてくれます。
この教え方はわかり安くとても説得力があって、私の心に深く刻まれています。
最初に説明があると、それでイメージをふくらませ、ではどんな打ち方になるのか集中して見ます。そうすると「えー、なるほど」となります。もうひとつのやり方は、逆に、打って見せてから、これはこういう意味だと教える方法ですが、どちらがわかりやすいかは様々です。一般には、こうやるんだと型を見せ、あとはそれを真似ろと、意味もなく教えられることが多いもので、このやり方が有効な場合もありますが、父の教え方は稽古論として参考になると思います。
もう一つ父から教わったのは、最後の「祈リ」の場面です。ワキの横川の小聖が数珠をジャラジャラと押しもんで、呪文を唱えると、シテは聞きたくないので橋掛りの幕際まで逃げていきます。父は「ここのワキの山伏はうるさい小犬だと思え。」と教えてくれます。小犬がキャンキャン、ワンワン言っている声は、最初は我慢していますが「あーっ、うるさい」とついに癇癪を起こして睨みつけてしまう、そんなイメージだと。『黒塚』の鬼の場合は、真に迫った戦いの場で、山伏、阿闍梨祐慶に襲いかかり、食べてしまわんばかりの迫力があるところですが、御息所のそれはもう少しソフトで、うるさい山伏の祈りを振り払おうとする程度のものと解釈すればよいということです。
確かに、最後は「悪気心を和らげ」「成仏得脱の身となり行くぞ有り難き」で終わっていて、悩まされ続けた嫉妬や執心から救われるのですから、悪鬼を強調し過ぎなくてよいわけです。こういう終わり方は、いかにもお能らしいところです。
(平成12年10月 記)
粟谷 明生
写真撮影 前 吉越研 後 東條睦
『班女』を演じて夢幻能へ投稿日:2000-10-01


能の世界を夢幻能と現在能という分け方をすることがあります。
(注=夢幻能という言葉は中世には存在せず、大正15年ラジオ放送にて佐成謙太郎氏が造語されたものです。「夢幻能」田代慶一郎著より)
夢幻能は死者が旅僧や旅人の夢の中に亡霊として姿を現し、在りし日の栄光や苦しみを謡い舞う表現手法で、最後は闇の世界に消えて行く死者側からのメッセージです。世阿弥が確立したといわれる夢幻能によって、能は人間の運命との葛藤を幻想的に描き人間の奥深くにある情念を普遍化して、能を永遠なものに高めたといっていいと思います。
現在能は文字通り生者を登場人物にし、そこで繰り広げられるドラマ、喜怒哀楽を表現する舞台で、この現在能も大きく三つに分けられます。まず言葉(台詞)のやりとりを中心にした『自然居士』『望月』『鉢木』など、次に自分の体験を語る「語り」を中心にすえた『小原御幸』『景清』など、そして言葉と舞いの両方を重視したもの、例えば恋人を慕い、母を想い舞い尽くす手法をとった作品、『班女』『花筐』『湯谷』などがあります。
秋の粟谷能の会(平成12年10月8日)ではこの現在能の『班女』を勤めました。
我家の伝書には『班女』「ただただ舞詰める也」と、舞い尽くす心得が記されていて、三番目の部類に入ることがうなずけます。
現在能を演じる時、私はちょっと複雑な心境になります。それは現在能では演者がどのように生き、どういう舞台を踏んできたか、その人の芸風がどのような物で、どういう素質があるかといったことが舞台にはっきりと現れるからです。もちろん、どんなお能でも現れますが、とりわけ現在能は、それらが如実に出るので恐い曲なのです。『班女』や『湯谷』はその代表的な曲といえるでしょう。夢幻能の方は、幽霊として生身の人間とは違うところで演じ、抽象化し、達観して演じられる部分があるので、演者自身がむきだしにならず、演者達の一つの救いや余裕になっているのは確かです。このようなことがあるからか、現在能である『班女』を「妙に濃艶で生っぽくて嫌いだ」と言う人もあり、私もこの気持ちはわからないでもありません。
一方、一世代前の先輩の方々の『班女』への思いは大きく上演回数も非常に多かったので、私も多くの方々の『班女』を拝見してきました。中でも友枝喜久夫先生、伯父新太郎と父菊生のは、それぞれ強烈な個性のある舞台で今も私の脳裏に焼き付いています。その演じ方は世阿弥のいう「恋慕専ら也」の如く、純粋に少将を慕うかわいらしい班女であったり、女の恥じらいを持ったやや大人の遊女であったりして、それぞれ自然とその役者の人となりが表現されてくるのですから不思議です。先輩達は人間性の出る現在能を競演し楽しんでいたようにも見えました。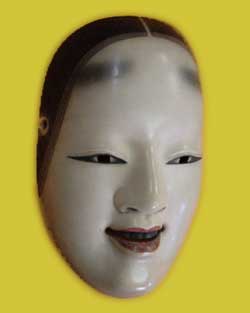
今回演じて難しかったことの一つは、シテ花子の出のところです。野上の宿の長(アイ=狂言方)が、花子という上臈は吉田の少将殿に酌をとり、愛のしるしとして互いの扇を交換して以来、扇を胸に少将のことばかり思い、他の客の酌をとらないと腹を立て、このような有様では宿から出ていってもらわなければならないと、花子を呼びたてます。そのとき花子は幕から出てきますが、うつろな様子で歩みもゆっくり、長の思うようにやってきてくれません。その様子に長は一層もどかしがりイライラをつのらせます。シテとしては、相手をジリジリさせる歩みが必要で、見ている方もじれったく思われるでしょうが、大事な演じどころなのです。稽古の時は運びが早過ぎると言われ、申し合わせ(リハーサル)ではやり過ぎと注意されました。その頃合いが微妙で、程の良さが必要で難しいところです。
野上の宿の長はアイが勤めますが、この部分、和泉流と大蔵流では演出が違います。和泉流はシテが橋掛りの三の松まで出たころで、シテの方を向き文句を並べますが、すぐに舞台に入ってしまい、じっと我慢して待っているという、気持ちを重視した演出です、大蔵流はシテの近くまで寄り、何をウジウジしているのだ、早くしろと矢継ぎ早にののしりの言葉をかけ、右から左からとまくし立てるしつこい演出です。和泉流の気持ち重視の演出はややさっぱりとして物足りなく、大蔵流の執拗なまでの演出も少々やり過ぎの気がして、中間ぐらいの程度のものがあるとよいと思うのですが…。このようなアイとのからみの中で、シテは相手を焦らすようで、実は心ここにあらずの放心状態、少将のことしか頭にないという風情を、運歩(はこび)一足一足で表現しなければならないのです。
次に、喜多流の『班女』の序之舞について考えてみます。他流では現在物の場合は中之舞を舞うのが常のようですが、喜多流は序之舞を舞うことがあります。「喜多流の『班女』や『船弁慶』の序之舞はおかしい」という方々がおられますが、これからの説明で序之舞を舞う意味がお判りいただけるのではないかと思います。
まず喜多流の中之舞と序之舞の区分けを整理してみましょう。
中之舞? (大小物) 『飛鳥川』『賀茂物狂』『草紙洗小町』『雲雀山』『湯谷』
※『松風』
(太鼓物) 『西王母』『猩々』
序之舞? (大小物) 『采女』『住吉詣』『東北』『半蔀』『井筒』『野宮』
『芭蕉』『檜垣』『夕顔』『楊貴妃』『江口』『定家』
※『千寿』『班女』『二人静』『船弁慶』『紅葉狩』『吉野静』
(太鼓物) 『雲林院』『小塩』『伯母捨』『葛城』『杜若』『西行桜』
『誓願寺』『羽衣』『遊行柳』『六浦』
喜多流でも、一般には大小物(笛、小鼓、大鼓の三人演奏)では中之舞が現在能、序之舞が夢幻能となりますが、何曲か(※印)異例のものがあります。太鼓物は登場人物が神や精であったりとこの世に現存する物ではないため、現在能としては扱いません。従って曲によって、中之舞、序之舞が決められているだけで、他流とも違いはありません。
大小物の※印『松風』は、狂女物は中之舞を舞うという決まりがあるため、夢幻能形式でありながら狂女物扱いとして中之舞となります。『千寿』『班女』『二人静』『船弁慶』『紅葉狩』はいずれも現在物ですが「遊女の序」を入れるため、敢えて序之舞としています。
今回の『班女』を例に違いを説明しますと、観世流の中之舞は、班女の恋というものを、その肌の暖かさ、体の感覚、臭いまでも全て生身で舞い表し見せようとするもので、喜多流の序之舞の方は昔の恋を回想する感覚で、一度熱き思いを醒ましつつも又思い出すことにより、より燃焼させた思いを見せるようなものではないでしょうか。
一般に序之舞は死者(霊体)が回想する場面などで舞うものと考えられていて、具体的には笛の吹く早さが「序之舞はゆっくり」「中之舞はサラリ」と違い、序之舞は「序を踏む」という型、つまり緩やかな拍子に乗らない導入部があり、それが吉田の少将への思いの集中であったり、もの思う花子自身の幾重にも連なる思いの凝縮や昇華であったり、遊女独特の舞いの足さばきでもあったりするわけですが、ここにサラリと舞に入らないという喜多流の主張があるように思われます。
では今回ここをどう演じるかです。『班女』という現在能の序之舞は、『定家』や『野宮』などの夢幻能の序之舞とは違うものと考えたい。それならば目に見える形で序之舞の演出を替えてみたいと、替えの型「摘み扇(つまみおうぎ)」を取り入れて演じることにしました。この型は夢幻能には似合わぬ型、動きで、花子の吉田の少将への想いを扇に焦点を合わせる洒落た演出です。「摘み扇」とは通常の持ち方とは違う握り方で、扇を親指・人差し指・中指の三本でつまみ、顔の前面に差し出し舞う型です。普通、扇は演者の手や体と一体になるように持つのが正しいのですが、「摘み扇」は演者自体は後方に、扇だけが前面に出て、そこに焦点が合たるような景色です。これで私の意識の中では夢幻能とはっきりと区切りがつけられ、喜多流としての『班女』の遊女の序之舞をお見せ出来たように思えました。
さて『班女』というお能の、悩ましくこってりとした情緒に重きを感じ演じていると、花子と少将が再会しハッピーエンドとなる結末が余りにもあっけなく、能舞台としての充実感が損なわれる気がしてきます。『班女』は、前漢武帝の寵妃が、帝に捨てられ「怨歌行」という詩を作ったという中国の故事に想を得、「扇」の持つ宿命、秋になれば捨てられる、「秋(飽き)の扇」の悲しいイメージと、反面扇は「逢う儀」と音が似ていてめでたいものとされ、再会の願いが込められていると、このような巧みな道具立てを揃えて、遊女のひたむきな恋を描くには申し分ない設定で、捨てられた女の寂しさ、狂おしいほどの恋慕の情、それらを思いを込めて深く謡い上げています。ここまではよいのですが、終わり方が余りにも淡泊で、掘り下げが浅いと指摘する人もいます。『班女』が秋の扇の悲しい想いをテーマにしながら、一転してハッピーエンドに終わるのは、日本での扇のめでたいイメージにそっているとする考えを否定はしませんが、私も終盤の進行には何か物足りなさ、わだかまりを感じます。
一般にお能では、特に複式夢幻能では、世の中のはかなさ、つらさ、切なさを考えずにはいられない結末で、余韻を楽しませてくれるものが多いものです。
三島由紀夫も『近代能楽集』の中で「班女」を現代劇にしていますが、この結末は、訪ねてきた吉雄(能では吉田の少将)を、狂女・花子は吉雄でないと拒絶し、自らを永遠に待つ女として閉じ込めてしまう、完全な悲劇にしています。ハッピーエンドでは三島文学にならなかったのでしょう。
現在能の典型である『湯谷』でさえ、宗盛の許しを得ますが、田舎の母親の命は定かでない不安があり、完全なハッピーエンドとはなっていません。それらを考えると、『班女』は安易に落ち着き過ぎています。「捨てられたのではと思う寂しさ、狂おしさ、しかしそれでも男への愛を誓う優しい女心、それも遊女という立場でありながら」などを心に思い演じ終え、この空虚に思える終幕を体感することで、私の中で次なる目標、それは未だ手つかずの本三番目物「夢幻能」への取り組みという夢が動き始めてきたようです。
(平成12年10月 記)
(写真)班女前 東條 撮影
班女後 安彦 撮影
面 万媚 明生 撮影
『黒塚』の鬼女をどう表現するか投稿日:2000-09-16


叔父・粟谷幸雄の「幸扇会」四十周年を記念する会(9月16日)で、『黒塚』を、私が前シテ、父が後シテで勤めました。
能は約束された型である動きや謡の調子、ノリそして面、装束など一見がんじがらめの規制に身動きできないようで実は、曲のありようを様々に解釈できる余裕、あそび、自由さがあり、この懐の大きさが能を現在まで継続させてきたと言っても過言ではないのです。演者は人技体の伝承と同時に、演じるという意識を常に持ちながら、能のあそびの部分の演出を追求すべきです。私が古典というやや古臭く感じるかもしれない能の世界の中に居ながら、一生の仕事として面白く取り組んでいけるのもこの自由さとシテが演者であり演出家でもあるという魅力のおかげなのです。
『黒塚』を演じるとき前シテの里女をどのように演じればよいか。「孤独で寂しい無力な女」という人間性を強調するか、それとも「身体の中の本性をいつ現すとも知れぬ鬼の心を隠し続けている女」とみるか。さてどのように意識すべきか、迷うところです。
『黒塚』は、陸奥の安達ケ原(福島県二本松市、安達太良山の東山麓一帯)に伝わる岩手(いわで)の鬼婆の伝説が基本になっていると言われています。この伝説は、京都の公卿屋敷の乳母・岩手が、姫の病を治すためには妊婦の生肝を飲ませればよいという易者の言葉を信じて、陸奥にこもり、宿を借りようとした若夫婦の妊婦の腹を切り裂いて肝をとり出したところ、その妊婦が実は生き別れとなっていた実の娘だとわかり、狂乱し、鬼と化してしまう、それ以来、岩手は宿を求める旅人を食らう「安達ケ原の鬼婆」となったという伝説です。これが平安前期の歌人・平兼盛の「みちのくの 安達が原の黒塚に 鬼こもれりと いふはまことか」と歌われ伝説ではないかということです。
JR東北本線の二本松駅から2キロほど、阿武隈川のほとりには岩手を葬ったといわれる黒塚があります。黒塚近くの天台宗観世寺の境内には、鬼女が住んでいたといわれる岩屋があって、縁起には閨(ねや・寝室)を覗くなという禁忌を破ったために鬼の正体がわかり、阿闍梨祐慶東光坊の法力で鬼婆が殺される話が伝えられています。
能『黒塚』は、岩手が鬼になった生々しい伝説の中身とはほとんど重ならない作りで、観世寺の縁起の内容に近いものになっています。敢えて凄惨な伝説にふれなかったことから察して、能の『黒塚』の女は、おどろおどろしい鬼というよりも、人間の罪障によって鬼にならざるを得なかった女が、その運命から逃れられず、寂しく一人暮らしをしていると見た方が良いような気がします。
以前、観世銕之亟先生に黒塚の女についてお尋ねしたところ、先生は能の『黒塚』(観世流は『安達原』)は「最初から鬼を考えるのではなく、あくまでも孤独で寂しい女の性(さが)や不安が最後に鬼にならざるを得なかったというストーリーのほうが良いし、あのロンギの糸繰り歌にも合っているね」、とおっしゃいました。「ロンギ」で糸車をまわしながら、源氏物語夕顔の巻を絡めた労働歌謡を謡う当たりは、都で裕福に幸せに暮らしていた人が、何か特別な事情で鄙の地に来て一人寂しく暮らすというあの岩手の物語りにも繋がるようでもありますが、代々語り嗣がれているその土地の労働歌の情緒を感じさせる意図とも捉えられます。
糸繰りは昔から女性の仕事で、女性の体の月のリズムと蚕の変態のリズムを同一視する説があると聞きます。
『黒塚』の女も糸車を廻しながら、月ごとにめぐる命と、輪廻する永遠の命を紡ぎ、寂しさに耐えているように見えます。そして孤独や悲しさ、罪障によって人は鬼に変わっていくのです。それは決して超能力を持った物の怪だからではなく、人の心が鬼と化すととらえるのでしょう。 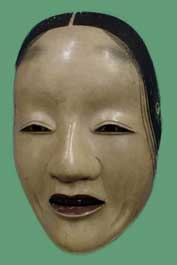
シテは引き回し(作り物を包んでいる幕)が下りると、その姿を静かに現し「げに侘人の習い程、悲しきものはよも有らじ。かかる憂き世に秋の来て、朝げの風は身にしめども、胸を休むる事も無く、昨日も空しく暮れぬれば、まどろむ夜半ぞ涙なる。あら定めなの生涯やな」と、寂しく謡います。
この曲の位を創る大事な謡い所です。
これを謡う女は、人を食わざるをえなかった環境、もうこのようにしか生きられない罪深い境涯に苦しみ、罪障に心が休まるときがなく、絶望し、静かに死を待ってるようでもあり、また、この境涯から救われたい、改心したいと宗教者(僧侶や修験者)をひたむきに待っているとも思えます。それが、鬼の正体をあばかれ、救われるどころか自らが拠り所にしていた法力で逆に退治されるという悲しい結末になってしまうのです。
お能ができた室町時代は、飢餓や戦さがあり、平穏無事の時代ではなく、死者を身近にみることが多かったようです。山中には屍が放置され、どくろが風雨にさらされている光景もそう珍しくなかったかもしれません。最も犯してはいけない、人が人の肉を食らうことがなされていたかもしれない、そういう時代背景で死や人間の生き方をとらえて、『黒塚』という作品が生まれてきたのではないでしょうか。
能では里女が住む庵を四角い木の枠の塚の作り物で表現しますが、そういう実体のあるものでなく、夢、幻とみる人もいます。安達原の原からは荒涼とした原に累々と続くどくろの群れ、黒塚の塚からはこんもり盛土された墓を想像することもできます。その時代の死者を思い、罪障深い人間の生を思うとき、ただすさまじき鬼の話だけではない、捉え方が大事な事と思えるのです。
私は『黒塚』の鬼女をこのように捉えて演じていますが、解釈の仕方によって、前場の里女の演出に違いが生じます。
中入り前、寒いので薪を焚いてあげようと言って、女が薪を取りに行こうとする場面。自分がいないときに「閨の中を見ないように」と念を押しながら、最後、橋掛りでじっくりと山を見上げる型をしてカッカッと大股の足運びで幕の中に入るところがあります。そこではすでに鬼になっているのだ、だから強い「切る足」で鬼のすさまじさを内包した足づかいをするのだという考え方をする人もいます。私は、その時点ではまだ鬼になっていないのではないか、強い足づかいは、薪を取りに山に入るのだから、着物の裾を上げて、力を込めて登っていく風情なのだと思います。
しかしここに悲しいかな鬼の本性が見えてしまうのだと解釈すれば、鬼の切る足でも成立するわけですが、私は鬼になる時点は、おそらく、閨の内が暴かれた瞬間(あるいは、その様を目の当たりにした瞬間)ではないか、従って、橋掛りから幕に入るまでは里女の心持ちのままで演ずる方がよいのではと考えています。
後半の鬼女の扮装の演出もいろいろあります。一般には赤頭で顰(しかみ)という鬼の形相をした面をつけ、法被半切の荒々しい装束で、柴をしょって(負柴)で登場します。これは鬼畜、怪物を前面に出した演出といえるでしょう。替装束の時は黒頭となります。
今回父は白頭で演じました。白頭は当然髪が白くなり、面は般若になります。般若の方が鬼畜というより女の恨みが角に現れ、女の業をより強く表現します。柴の持ち方も負柴ではなく抱柴です。自分が着ていた着物を柴に巻いて抱いて約束の証として出てくるのです。これも鬼畜というより、より人間的な、ある種、女のやさしさが出ているように思います。ですから、白頭という演出は、すさまじい鬼というよりは、鬼にならざるを得なかった人間、人間らしいやさしさを内に持った鬼を演ずるのに合っていると思います。
ところで、「閨の内を見るな」という禁忌を破る話は、日本だけでなく世界にもさまざまあります。見るなと言われれば言われるほど見たくなる人間の性、それによって劇的に迎える結末、それらが物語をドラマチックにしたてています。禁忌を破る場面はいつの場合もハラハラ、ドキドキさせられます。
能『黒塚』では、ここをアイ狂言が滑稽に、コミカルに見せてくれます。私が若い10代で、人間国宝の野村萬先生が万之丞と名乗っておられた頃、このアイをやられて、とてもあったかで人間的なものを感じたことを今でも鮮明に覚えています。その名演技に、地謡の前列で笑いを堪えられず思わず下を向いてしまったことを思い出します。「見るなと言われれば見たくなるのが倅のころからの癖」の語り口、閨の内に行こうとして咎められ言い訳をする言葉のあややタイミング、体の動かし方が絶品で、何ともいえぬ味わいです。
『黒塚』という曲は実は、私が能の魅力に目覚めた出逢いの曲です。初めて『黒塚』を演じた27歳のとき。それまで私は心が定まらず、お能に興味が持てずにいました。あの手この手と、私を能の方に引き寄せようとしていた能夫が、『黒塚』のときに一つの話をしてくれました。『「月もさし入る」っていうところ、普通は枠かせ輪(糸車)に手をかけ、常はただ右手で糸車を持つだけだが、まあ替えの型で月を見るように上を見る型をやる人もいるけれど、そこを観世寿夫という人は「月もさし入る」と言って右下の閨の内に射し込む月の光をじっと見たんだ。こんな発想喜多流にはないだろう。』と。
この言葉は衝撃でした。月といえば上、海といえば下を見ると決まっている、お能はそういう決まりごとを伝承していくだけで、創造性のないものだと思っていた私の心を大きく揺るがし、今までの私のお能のイメージを一掃させ、新たに能という演劇世界のイメージを脹らませてくれたのです。流儀内の決められたものとは違う世界がある、これは何て面白いのだろうと・・・・。
そして、能夫はそのとき、装束や面を自分自身で選べ、着たいものはすべて出すからと言ってくれました。自分の責任で演出し、デザインしろと言ってくれたわけです。
今、当時の写真を見ると、装束の色彩のバランスは悪く、よくあれを着て出たなと思うのですが、能夫はおかしいから替えろとは言わずに、選んだもののよし悪しより、自分で選び見立てる作業の方を優先してくれました。そして、粟谷の家にはいくつもの装束や面があり、自分はそれらを自由に選べる恵まれた環境にあることや、それを集めた祖父や叔父たちの蓄積をその時身にしみてわかったのです。今もあの時が私の演能の始まりだと思っています。
この能にこめられたものは何か、どう演出したらよいかを考えるようになりました。それが能を伝承する者の勤めでもあり、また生き甲斐になるのです。
『黒塚』は自ら創造的に役づくり、舞台づくりをしようとした最初の曲でした。少しずつではありますが、演ずるたびに積み上げられていくものが実感できるようになりました。様々なものを見聞きし、考え、研究し、取り込み作業をするなかで「げに侘人の習い程、悲しきものはよも有らじ」が見る人の心に届くように謡え、全体を通して黒塚の女の心が表現出来たらと、望みは果てしなく高いのです。
(平成12年9月 記)
写真
1 前シテ 粟谷明生 撮影 堤 恒子
2 前シテ 粟谷明生 撮影 三上文規
3 曲見 撮影 粟谷明生
4 後シテ 粟谷明生 撮影 三上文規
5 般若 撮影 粟谷明生
神となった光源氏 ー『須磨源氏』を演じて投稿日:2000-08-06


鎌倉芸術館が「能で見る源氏物語シリーズ」(全9回)と題して能楽公演を打っており、私はそのシリーズの5回目を依頼されて、8月6日『須磨源氏』を勤めました。『須磨源氏』という能は、光源氏が兜率天(とそつてん)という天上界から須磨の地に下向し、ひととき、在りし日の下界の地を楽しんで舞い、また天界に帰っていくという、比較的単純な物語で、能の基本の二曲(舞歌)に基づいて簡潔に作られた世阿弥作の小品です。演者としては、どこをどのように演じたらよいか苦心し、正直申しますと、やりがいのある曲とは言い難く、やりにくい厄介な曲の部類に入ると私は思います。
前場のクセなどは源氏物語の巻名を語呂合わせ的な詞章で綴っているあたり、能『源氏供養』にも類似しており、源氏の経歴を語るのみで、心のうちを謡いあげているものではありません。ですから奥深さがある能とは思えないのです。
しかし演じる以上何かを掴まなくてはなりません。それで私は気になる、光源氏、須磨、兜率天という言葉を軸に考えてみました。
『源氏物語』を本説にした能はたくさんありますが(現在残っているのは十数曲)、ほとんどが、源氏を取り巻く女性たちを主人公(シテ)にしたもので、光源氏自身が登場するものは『須磨源氏』と『住吉詣』のわずかに二曲。しかも『住吉詣』はシテが明石ノ上で源氏はツレですから、シテとして登場するのは『須磨源氏』のみということになります。数ある能の中でたった一曲しかシテとして現れない光源氏をどう表現するかが問題です。光源氏は『源氏物語』という物語の中の空想上の美男子です。同じ美男子でも、在中将業平の方は実在の人物としてそれなりのアプローチが可能と思われますが、源氏の方はつかみどころがありません。しかし、あまたの女性の心をとらえた美男子であることは間違いなく、平安時代から現在に至るまで『源氏物語』を愛読した人々のイメージの中の美男子像を裏切るわけにはいかないという難しい役どころです。
作者・世阿弥は、光源氏を登場させるのに、なぜ須磨の地を選んだのでしょうか。栄華を極めた地ではなく、都から自ら退いた辺境の地・須磨。
源氏二十六歳の春、右大臣家と左大臣家の政争の中、朧月夜との恋をきっかけに、自らの立場を自覚しての須磨への引退でした。須磨での侘びしい暮らしは、源氏に静かに物を想う清澄な時間を与え、その後の生き方を決める重要な転換期を作り出したといえるでしょう。すでに兜率天の神となり、天界に住む源氏が懐かしく舞い降りてくる地、そこは想い悩んだ青春の転換期の地・須磨以外にはないのです。住吉の神の導きによって過ごした明石では明石ノ上との恋があり、再び華やかな都に召還されるスタートの地となることから、須磨ほどの純粋性、透明性には欠けるのではないでしょうか。『明石源氏』では成り立ちません。
『須磨源氏』の詞章の中でわからなかったのが「兜率天」という言葉です。
サンスクリット語のトゥシタ(満足する)を漢字に当てた兜率陀が基になったといわれ、満足の心で満たされた境地を表すそうです。
辞書(広辞苑)を引くと「欲界六天の第四位。内外二院ある。内院は将来仏となるべき菩薩が最後の生を過し、現在は弥勒菩薩が住むとされる。外院は天人の住所」とあります。弥勒菩薩が住むというのですから、天上界でも位の高い仏が住むところと考えられます。
仏教の世界では地の下に地獄があり、地の上には天界があるとしています。その天界には1、2の地上に住む天、地居天(じごてん)と3?6の空中に住む天、空居天(くうごてん)があり、さらにその上には色界というもう一段位の高いところがあります。1?6に住む神々は、天(=天神)といわれながらもやることは人間と大差無く、道徳的にも不完全な神の存在であるそうです。より高所に住むものほど修行が進んでいますが、未だ愛欲なども持っているため、六欲天と呼ばれてるということです。(参考資料 定方晟 著 「須弥山と極楽」より)
私は、兜率天は神が住む空間であると同時に神の存在そのものでもあるように聞いています。能の光源氏は兜率天という空居天に住み、すでに神になっているように思います。早舞の後の舞台進行が『高砂』の住吉明神や『弓八幡』の高良の神のような脇能の作りに似ているのも一つの根拠になっています。ですから光源氏は気品のある美男子である以上に、神の存在としての神々しさが表現出来ればと思います。
このように考察してきて、今回は様々な新しいを試みをしてみました。
まず第一は面です。源氏は空想上の美男子、多くの人のイメージを崩さない面となると、意外に難しいものです。伝書では中将となっています。
中将には高貴な人々の亡霊系の面と、修羅道に落ちた平家の武人の二系統があります。『須磨源氏』ならば、この高貴な人がつける亡霊系を選べばよいということですが、なかなか『須磨源氏』に使えるような、きりっとした「中将」にはめぐり逢えません。
この「中将」という面は眉間にしわを寄せ、やや苦悩している表情なので、兜率天に住む神としての源氏には似あわないのではと、最初は思っていました。多少の憂いはあったとしても、神としての晴れやかさ、のびやかさ、大らかさがなくてはいけないのではと。そこで、「源氏」という専用面も思案しましたが、この面は「十六」の替えで、余りにも若過ぎて、人生の転換期を過した人の顔としては幼なすぎるため対象外としました。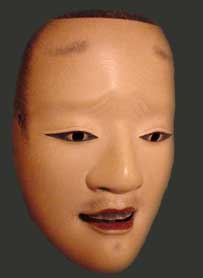
今回私の意向を聞いてくださって、岩崎久人氏が「二十五六」のイメージにて創作面を打ってくださいました。此の面は邯鄲男をベースに今若、中将、若男を掛け合わせたようなお顔で、眉間に皺が入っています。当初は「中将」の眉間の皺が気になっていましたが、六欲天の事を調べているうちに、彼らは未だ色界にいて天という神でありながらも、やることは人間とそう変わらず、道徳的にも未だ不完全で愛欲さえあるらしい、ならばかえってその負を表現するためにも皺は必要かもしれないと思えたのです。
光源氏というテーマが大き過ぎるため、必ずしも全てが私のイメージ通りとはいかないまでも、創作面にかける意義を再考する良いチャンスとなりました。
能誕生当初は皆、面は創作であったわけです。般若は般若坊が女の恨み、怒り、嫉妬を持つ顔を想像して打ち、三光尉は三光坊が老人の顔とは、と想像して打ったのです。源氏の面としてピッタリ当てはまるものがない今、『頼政』には頼政という面があるように、『須磨源氏』にも適切な創作面が作られていくのもよいのではないかと思っています。
創作するエネルギーのすばらしさ。室町桃山は日本の文化の絶頂期といわれ、面制作においても傑作が続出しました。現代の面打ち師にも、素晴らしい模写の世界と共に是非創作にもエネルギーを注いでいただき、そういう面打ち師の登場を期待したいと思います。 次に装束です。我家の伝書に、「?後ハ、初冠(ういかんむり)追掛(おいかけ)有ルモ宜シ無シハ取リ合ワズ、源氏武官ヲ兼ネタル左大将也?」とあります。
追掛ということは、武官の姿でありますから、巻纓(まきえい・纓は冠についた短冊型の垂で巻纓はそれが丸く巻かれた状態)の武官式でもよいということです。源氏は武官・文官の両方の位についた人物だったので、どちらでも良いと言っているようです。
私は今回、直衣(のうし)《普通は狩衣で喜多流には所有者無し》を着てみようと考えました。直衣は裾横に大きな襞がついていて全体にたっぷりとした、いかにも文官の形で、身分の高い人が着るものです。今回は観世暁夫氏にお願いし、白地に金の刺繍が施されている直衣を拝借しました。ということで文官式ですから、追掛は付けず初冠(ういかむり)に垂纓(すいえい)の形となりました。
そして新しい試みとして、冠鬘(かんむりかづら)をつけてみました。これは最近、暁夫氏が銕仙会にて能『雲林院』で試演されたもので、考案者は銕仙会の清水寛二氏です。
喜多流従来の面をつけて初冠をかぶるだけの姿ですと、演者の耳や髪という生な部分が見えてしまいます。今まではそれに慣らされてきましたが、私はこの格好を好むものではありません。
源氏は神となったのですから、出来る限り演者の素肌が出ない方がよいのではないでしょうか。今回冠鬘を拝借して、自分の髪と耳を隠し、鬘の髪を頭の上で結って、その上に冠をかぶるという本来の形でやりました。楽屋内では慣れないせいか「違和感がある」との話でもちきりでしたが、そのうち慣れるかもしれません。また今後は、黒垂や冠鬘の他にも、喝食鬘(本当の髪の毛を使った鬘)をつけるなど、兎に角生身の人間を出さない工夫はすべきであると思うのです。
私のイメージに近づけ、高貴な出立で登場した光源氏は、ただただ美しく舞うことが大命題で、ここをいかに舞えるかがシテの技量の見せ所、勝負どころです。
早舞は主に貴人が舞うものですから、颯爽と凛として、が心得です。
早舞には「クツロギ」という特別演出があり、今回私はこれを採り入れてみました。
「クツロギ」は舞の途中でしばし休息する意で、舞台より橋掛りへ行き、三の松でしばし佇んだままになります。そして徐々に高まる囃子の演奏と演者の想いの充実感によって又舞台に戻り、舞い始めるという演出です。この橋掛への行き来の時、リズムに合った笛を吹くのが常ですが、今回は往復ともリズムに乗らずアシライ笛にていたしました。これはなかなかやらないのですが、一噌隆之氏をはじめ囃子方全員にご協力願い、その場での一回勝負という、独特の緊張感の中で作りあげました。一つの舞台効果となったと思います。
私のクツロギでの心持ちは、橋掛りで佇みながら須磨の景色を眺め、青海波を舞っていた時分や青春期のあやまちを回想しながら、下界と天界の間の浮遊感を楽しむといったところです。神でありながらも人間的感情は残っているという色界の神の意識がそこにはあるように思えます。
謡では、「ロンギ」の最初「さてや源氏の旧跡の、分きていづくのほどやらん。詳しく教え給えや」を、ワキの森常好氏に特別にお願いして地謡の代わりに謡ってもらいました。ここの段はまさにワキがシテに問いかけるところですが、現在では地謡が代弁するように謡っています。阪大喜多会OBの藤田隆則氏の著書『能の多人数合唱(コロス)』によると、昔は地謡とワキが明瞭に分かれておらず、ワキが地謡も謡うのはごく自然なことのようでした。喜多流では地謡が謡うところを、地(観世流などはこう呼ぶ)といわず、「同音」というのは、このなごりからです。
今回試しに地謡の一部をワキの謡いに替えることにより、シテとワキのロンギらしいかけ合いが出来たらと考えました。この成果の賛否は判りませんが、地謡を謡った能夫氏によれば、シテとワキのロンギを黙って聞いていて、最後にいきなり「天に住み給えば・・」と張って謡うとなると、なかなか地謡全員のボルテージが上がっていかない。本来ワキが語りかけるところを敢えて地謡が代弁しながら徐々に高揚していき、最後の「雲隠れしてぞ失せにける」で大合唱となる現在の形式には、やはりそれなりの意味があるということでした。今の形の良さを再認識出来たことは、一つの収穫だったと思います。
お能には長く伝えられている形式があります。長い年月に洗われ確立されてきたものですが、形だけの継承で、なぜそれがよいのか実感できないことが多いものです。
今回のように、既存形式を代え新しい試みをすることで、なぜ伝承された形式がよいのかを発見できると思うのです。その意味で今回のさまざまな新しい試みは、次の演能へのステップとして生かされていくものと思います。
最後に、この曲を演じていて一番難しかったのは前シテの尉の謡でした。
世阿弥も『風姿花伝』で「老人の物まね、此道の奥義なり。・・・能をよき程極めたる為手(シテ)も、老いたる姿は得ぬ人多し」と言っているほど、老人を演ずることは難しく、能楽師にとっての大きな課題の一つです。『須磨源氏』においても、演者自身の声で謡って、自然に、前シテは尉に聞こえ、後シテは光源氏になるというのが理想です。私はまだ、自然と尉を演ずるまでに遠い道のりがあるようですが、いろいろ試行錯誤しながら体得しなくてはと思っています。
今回の『須磨源氏』は、待ちに待った粟谷明生指名の公演依頼でありました。
鎌倉芸術館の公演は、私のシテ方としての新たなデビューともいえます。嬉しくもあり、身が引き締まる思いです。これを機会にますます精進していきたいと考えています。
(平成12年8月 記)
船弁慶の義経はやはり子方投稿日:2000-07-28

粟谷 明生
7月の終わり(平成12年7月28日)に青森市の外ケ浜で薪能『船弁慶』を勤めました。薪能といっても最近は主催者や会場の都合で屋内で行うことが多くなりまして、今回も屋内の会場に薪が置かれる程度の演出でした。
『船弁慶』の子方(義経役)は20回勤めていますが、シテを演じるのは3回目です。今回は義経を子方でなく、ツレ(大人)で演じることになりました。
結果は、やはり義経は子方でなければということです。『船弁慶』は観世小次郎信光の作で、大衆的で見せ物的な華やかさ、おもしろさがふんだんに盛り込まれています。信光の作品は『安宅』『紅葉狩』『道成寺』などにみるように、どれもエンターテイメントに徹しているところがあります。観阿弥、世阿弥、金春禅竹などの幽玄美とは趣を異にし、おもしろ味のある作風であると思います。
舞台が始まり、まず最初にかわいい子方が側次(そばつぎ)や長絹に大口袴という扮装に梨打烏帽子や金風折烏帽子を付けて登場する、これだけで観客の視線は子方を先頭とする弁慶達に釘付けになるでしょう。子方にはこのような魅力があるのを計算に入れて信光は創作していると思います。
『安宅』も山伏姿の子方が先頭に立ち、シテの弁慶はじめ9人もの家来をつれての登場です。『紅葉狩』の場合は煌びやかな遊女達が次々と登場し、『道成寺』はあっと驚くような大きな釣鐘が大人数で舞台に運ばれてくるなど、信光らしい舞台の幕開きが印象的です。しかし何といってもかわいい子方の登場に勝るものはないでしょう。
義経を子方にするのは、舞台上でシテ(静御前や知盛)と脇(弁慶)の関係にもう一つ義経という大きな存在(大人の義経)を入れて、舞台の焦点が散漫になるのを避けるためと、シテをよりクローズアップさせるためだと思います。とりわけ曲名にもなっている脇の弁慶は、シテと繋がりを持ちながら型の動きが多く大活躍します。このような中で義経を子方にして全体のバランスを考えたのは信光の工夫のたまものと思うのです。
今回演じて感覚的にそのことが理解できました。例えば前シテ(静御前)が序の舞を舞いながら別れを惜しむ場面で、義経役に髭が生えた大人が座っていたのでは何か生々しい。かわいい子役の義経を見て泣くからこそ哀れが出て、説得力が生まれ判官贔屓の気持ちになるような気がします。能を初めて観る人や外国の方などは、義経が子方だというので驚かれるようですが、能舞台上では義経は大人ではだめで、子方でしかも小さい子供であればある程良く、これが能の世界での巧みなトリックなのです。
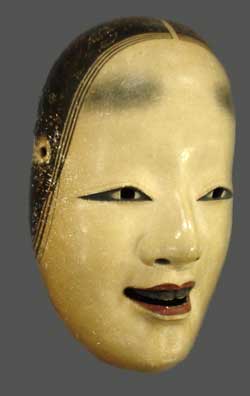
前シテが静御前で後シテが平知盛、この何の関係もない両者を、一人のシテが演じ分けるという大胆なことを、能ではやらせてしまい、能楽師はそれを平気でやってしまうおもしろさがあります。「前と後と役柄が違うのによくできますね」という質問を受けることがありますが、私はこう答えています。「船弁慶のお能のお稽古の前の段階で、先ずクセの仕舞、次に前場の舞囃子のお稽古、それが出来ると薙刀の持ち方から始まり後場の仕舞、後の舞囃子と進んで行き、面白いのはここで一段落して能の稽古となるまで時間があることです。しばらく時間が経ってさあ能の稽古となり最後に全部繋ぎ合わせ補充して出来上がる、つまり部分部分の修練から成立っているため、抵抗がないのです」と????。
一般の方は能『船弁慶』から始まると思われるから、難しく考えてしまうのかもしれません。ですから『天鼓』の様な前シテの老人と、後シテのその子供という役設定も全く気になりません。実際、部分から入り最後にお能を仕上げる教え方が良いのか悪いのか、わかりませんが、近年の喜多流はこのやり方を通してきました。
薙刀を使う能は、よく演じられるものとして『船弁慶』『熊坂』『橋弁慶』『巴』の四曲があります。『橋弁慶』の薙刀は悪僧武蔵坊弁慶が振り回す荒々しいものです。『熊坂』も盗賊の大将として同じように荒々しさが出れば良いでしょう。『巴』は女性が持つ珍しいケースで、薙刀さばきは美しく、華麗にしかも切れ味鋭く女性的な味わいが要求されます。
『船弁慶』知盛の場合は「桓武天皇九代の後胤」と仰々しく名のり出ますから、それなりの威厳があるものでなければならないと思います。薙刀はもともと僧兵や雑兵が、騎馬武者の馬の足を切って打ち倒すための武器で、平安時代武士同士が名乗り合って戦うときの武器ではありません。南北朝時代以後上級武士も愛用したらしいですが、敢えて知盛に薙刀を持たせたのは、華やかなショーを演出する一つの小道具になるように信光は考えたのではと思います。
知盛の薙刀のイメージを、父菊生は、義経主従に襲いかかる荒波を作り出すのだと言います。『船弁慶』の薙刀は『巴』のような華麗な切れ味のものでもなく、『橋弁慶』や『熊坂』のように荒々しさだけでもいけない、もっともダイナミックで、威圧的な薙刀扱いが出来なくてはと教えられてきました。この区別を上手に演じないと、「あれは知盛になっていないね」「巴御前でもあるまいし」などと言われるのです。
この薙刀を使う「後の仕舞」で思うことがあります。この仕舞、内弟子時代はなかなか実先生(先代宗家)のお許しがでないのです。ですからお許しが出たときは、何か自分の芸のランクが上がったようで、同時に自分自身が大人になった、大人の仲間入りができたように思えて嬉しくなり、大いに喜んだことを思い出します。
この仕舞を子供が舞ったのを見たことありますが、実先生がなかなか許可なさらなかったのが判りました。大人の身体になっていない坊やが舞うと、『船弁慶』の仕舞にならず、似合わず滑稽になってしまいます。そして不思議にその子自体の美しささえなくなって見えてくるのです。知盛という大きい像が、大人の標しとしての体毛の生え揃っていない幼い肉体を受け付けないように思えます。

子方の頃、後シテの演技の迫力に、本当に怖いと感じていました。今度は自分がシテとして知盛を演じるのですから、子方が怖いと思うほどの威厳のある薙刀さばきをし、迫力ある演技をしなければ子方に笑われてしまいます。後半のクライマックスにシテが薙刀を振り上げ、義経に襲いかかった後、子方に薙刀を払われよける型があり、上手くやらないと、本当に子方の首をはねてしまう危険な箇所があります。ここばかりは子方に怖い思いをさせてはいけません。
昔、この場面で心得た薙刀扱いをしないと、父が「うちの子を殺す気か」と演者に怒鳴り、「こうやるんだ」と真剣に教えていたことをよく覚えています。私も自分の子供がそんなことになったら、父のように注意出来るようにと思っています。この3月、父のお弟子さんが『船弁慶』をやられ、息子の尚生が子方を勤めたとき、「ここのよける型は菊生先生に口すっぱく言われていますからご心配なく、大丈夫です」と相手に先を越され、拍子抜けしてしまいました。
子方を勤めてきておもしろい話をひとつ。
子方は自分の台詞や前後の謡を耳から覚えます。謡本を見せられることはありません。それがどういう意味かわからないまま、しばしば違うイメージで勝手に覚えていくことがあります。
たとえば『船弁慶』では観世流の関根祥人さんも同じように間違えていたと笑い話になったことのある「このお船の陸地に着くべきようぞなき」というくだり。陸地と書いて「ロクジ」と読むのですが、子供は「六時」と覚えていて「大丈夫、今五時だから六時には着くよ」と思っていたという話や「いかに弁慶、静に酒を勧め候へ」を、自分は「静に」と言ったのに、弁慶はドタバタと荒々しく酒を進めているなと思った、などいろいろあります。
また「舟子ども・・」(舟子は舟を漕ぐ人々、どもは複数を表す)という言葉。それを聞いたらそろそろ立たなければという合図だったので、私はずっと「舟子供.舟子供」と覚えていて、どんな子供なのかな?、海の近くに住む子供かな?などと想像していました。まったく違う意味であったことがわかるのは大人になってからです。子方を経験してきた者同士で話すと、同じところを同じように勘違いしていることがわかり、おもしろいものです。

子供は謡を耳から覚える時期が必要です。理屈ではなく、感覚的にからだにしみ込ませる。しかし、ある時期からは謡本を全く見せないというのではなく、必要な場面では見せ読ませ、意味をわからせることがあってもいいように思います。また、自分が子方のとき、こんな風に勘違いをしていたということを話して聞かせるのもいいのではないでしょうか。
能の世界の子方は義経という名を背負って成長していくと言っても過言ではないと思います。初舞台の『鞍馬天狗』の花見から始まり子方の牛若丸へ、『船弁慶』『安宅』等の義経を勤め、斬り組みの型の勉強になる『橋弁慶』の牛若丸、そして最後は『烏帽子折』の牛若丸で子方を卒業する、このような修練過程になっています。
長く子方を勤めたから一層感じるのかもしれませんが、義経は「子方でなくては!」とつくづくと感じた舞台でした。長い伝統の中で必然になっていることが、今回も意味あることだと知らされました。
(平成12年8月 記)
(写真1 船弁慶 粟谷明生 平成4年三上文規 撮影)
(写真2 船弁慶 大矢克英 粟谷尚生)
野田神社の能舞台で歴史を感じつつ 『小鍛冶』を演じて投稿日:2000-07-28
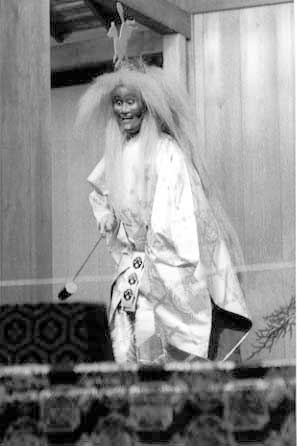

今年の夏(平成12年)は、7月28日に青森の外ケ浜薪能で『船弁慶』、8月4日に山口の野田神社で『小鍛冶』白頭、そして8月6日に鎌倉芸術館で『須磨源氏』を勤め、暑い夏に熱き演能が重なりました。
野田神社は山口市にある明治維新の宏業、毛利敬親公をまつる神社です。昭和11年旧長州藩主の毛利家が明治維新70周年を記念して建築奉納した能舞台で、大変立派な素晴らしい屋外の能舞台です。特に陽が落ちてからの薪能でのロケーションは舞台が浮かび上がるように見えて幻想的で、全国屈指の能舞台と言えるでしょう。もともとは神社旧参道横(現.野田学園運動場)に建立されていましたが、昭和43年、山口都市計画事業による市道の新設に伴い参道が分断され、運動場として野田学園に割譲されたため、一時能舞台は運動場の片隅にポツンと孤立した寂しい状態になっていたそうです。これではいけないということで、平成2年に神社内に移動し、それ以来毎年夏に山口薪能を催すようになりました。第一回は喜多流で始まり、粟谷新太郎、菊生が勤め、毎年順に他の流派にもお願いして継続してきました。今年は10年という記念すべき年に当たり能夫が『葵上』、私が『小鍛冶』白頭を上演することは、嬉しくもあり、また時代の流れを感じさせられるものでした。
この能舞台は地元の愛好家や能に好意的な宮司様のお力で保存状態が大変よく、本舞台も橋掛かりも板が平らで足の運びがスムーズにでき、演じていてとても気持ちのよい本物の能舞台でした。黒光りする柱や床、薄暗い舞台に浮かび上がる老松、すべてがとてもよい雰囲気で演者側から見ても感激します。
能楽堂の側に過去に奉納した能の記録があり、そこに祖父・粟谷益二郎の文字、先代喜多実先生や十四世六平太先生の名前が見えて、興味尽きないものでした。さらによく見ると、粟谷新三郎という名も見えます。新三郎というのは益二郎の祖父で、明治26年4月の御神能に『融』を演能したとあります。そしてその地謡に粟屋藤次郎という名が記されています。粟谷ではなく粟屋です。いったいこの人は誰だろう。「や」が違うから粟谷家とは無関係ではないか、いや、昔は粟屋と書いていた時期があるらしい、途中で粟谷となったとも聞かされている。地謡の粟屋氏は谷にしなかった何か訳があるのだろうか、もう少し調べてみたいところです。結論は出ませんが、能を我々の先祖が代々しっかり守ってきたのだという証しを見たようで誇りに思いました。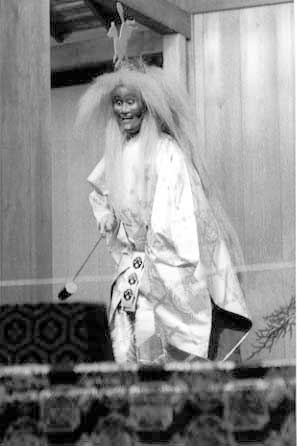
今回の野田神社での能は屋外での薪能。私の『小鍛治』白頭のときは、日が暮れる前だったため、火入れの儀式はその舞台の後となりました。能夫の『葵上』では、暗闇の中、薪がメラメラと燃えて、舞台を映し出し、ときには薪がバサッと崩れる音がして、ムードはいやおうなく盛り上がりました。ただ演じている方は、暑くて汗びっしょり、装束に煙はつく、湿気が多くあまり気持ちのよいものではありませんが、夏の風物詩として、観客のみなさんには喜んでいただけたのではないでしょうか。
さて、私が勤めた『小鍛治』白頭ですが、数ある名刀譚の一つで、名刀工・三条宗近(ワキ)が、帝の霊夢によって剣(つるぎ)を打たせる旨の命を受けたとき、稲荷明神(後シテ)が相槌(共に刀を打ってくれる名工)となって、見事にその任を果たした話です。
稲荷明神は狐の化身ですから、頭には狐の飾り物をつけ、白頭なので狐足という喜多流独特の足づかいをするのが特徴になっています。運びはすり足ではなく、踵をできるだけ床につけず、腰を一定の位置に決め爪先だけでピョンピョンと跳ぶような動きをします。まさに狐の動きを模したもので、非常に脚力が要求されます。後シテ・稲荷明神は普通は赤頭をつけ黄金色の狐を頂きますが、白頭は白い頭(かしら)に白い狐を頂きます。喜多流の小書きは白頭のみで、観世流にある黒頭の演出はありません。白頭(黒頭、赤頭)については研究コーナー『殺生石』のところで考察しましたが、「白頭」にすると、老体のイメージというよりは、劫を経て超越したものを表し、重々しい演出になるのが一般的です。しかし『小鍛治』の場合の白頭は狐の系統で狐足となり、重厚さというよりは狐のような俊敏な動きがテーマになります。伝書を見ますと「白頭の時、面は野干又は泥小飛出」とあります。一度「野干(やかん)」をつけてと思うのですが、やはり狐足の動きと合わないように思えてなかなかその気になれません。
ここで小鍛冶の面について『芸道読本』(高林吟二著)に十四世喜多六平太先生の面白い話がありますので紹介させていただきます。
「昔は小鍛冶の後は、何時でも野干だったそうだがね。どうも野干では白頭の狐足がうまくいかねえやネ、それでどうしたもんかと野干を床の間に掛けて工夫していたんだが、つい、うとうととした処へ『七太夫!七太夫!』と呼ぶ声がするのでハッと目が醒めた。そして床の間を見ると、確かに今まで野干を掛けていたのに、いつの間にか泥の小飛出になっているんだよ。ハハア!是で解った、さては今のは小狐の御告げかというわけさ。それから後、流儀の小鍛冶の白頭が泥の小飛出であんな風になったという事だぜ」
稲荷明神という神格化したものを表現するという意味では、面は金泥小飛出がふさわしく、装束は清楚、純粋、高位を表す白装束、そして白頭というのが似つかわしい、この演出はまちがいないところです。
この小鍛冶という曲は私の演能の節目にいつも関係しています。第1回目は昭和47年青年喜多会に入会した時、2回目は昭和56年粟谷能の会で舞えるようになった時、3回目は昭和57年我が母校(学習院)での学生能での演能、その後も二回程勤めていますが、思い返せば節目節目の記念すべき時にこの曲が当たっているように思われます。
さてここで、前半の仕舞いどころについて。日本武尊(やまとたけるのみこと)が使って武勲を立てた草薙の剣(くさなぎのつるぎ)【熱田神宮にて保存】の起こりや武勇伝を語る場面の仕舞には、速くかかって舞う場合としっかりとゆっくり舞う場合と二通りがあります。本来はゆっくり舞うのが常だったようで、先代喜多実先生はゆっくり力強くとよくいわれていました。技が冴える六平太先生が、キビキビした動作を入れ、速く舞ったことから、早い形もできたようです。六平太先生に習った方々は速い方で舞い、実先生の教えを受けた方々はゆっくり舞っているようです。このように流儀内でも指導者により多少やり方が異なるという事は昔からあったようです。父に聞いた苦労話ですが、両先生から教えていただいてた頃、六平太先生は右から、実先生は左から見るようにと、仰っしゃることが違うので、どちらの教えに従ったらよいか困ってしまい、本番両先生が見ておられる中、「えいしょうがない、真ん中を見よう」と中間をとったら、両方の先生に叱られたという話があります。
今私達は両方の型ができるように訓練されていますが、私自身は速くキビキビと演じる方が好きで、今回はそのようにやってみました。暑い炎天下の薪能であってみれば、観てくださる方々の為にも、さらりとしている方が合っていたのではないでしょうか。『小鍛冶』は短時間(約1時間)で終わる小品の一番ですが、分かり易い作品内容、激しい動きでの展開で、お能の魅力を身近に楽しんでいただけたのではないかと思っています。
(平成12年8月 記)
写真1、2 野田神社能楽堂
写真3 小鍛冶 白頭 粟谷明生 宮地啓二 撮影
写真4 泥小飛出
写真5 野干
『歌占』の難解さにひたる投稿日:2000-05-01
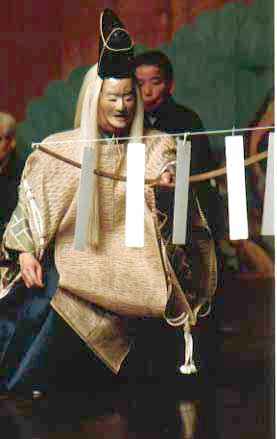
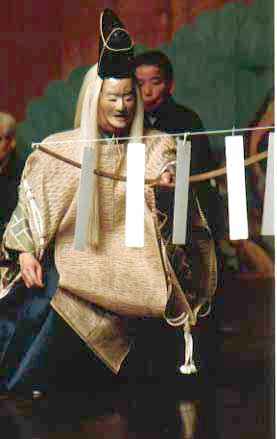
能が長い年月の風雪に耐え、今に伝えられているのは、能に関わる多くの人達の努力によって、ある様式美が確立されてきたからに他なりません。
しかし今、様式がしっかり決まっているがために、逆に演者はその中でただ、形さえ演じれば足りると考えがちです。今回(平成十二年五月自主公演)の『歌占』という曲は、その様式美に頼るだけでは、観る人が理解するのに限界があるのではと感じるものでした。難解な言葉の群、そこに込められた宗教観や死生観。当時の人はわかって楽しめたものも、現代人の日常生活や常識、教養からはかけ離れ、私自身も理解に苦しむ作品内容です。演ずる者が作品を深く知る、このあたりまえの事、これが『歌占』に取り組む始めとなりました。
『歌占』は歌による占い、地獄の曲舞、神懸かりの狂乱場面の三段構成で、そこに親子の邂逅をうまく入れて作られています。今回は個人的に全体のあらすじと、一番難解な「金土の初爻を尋ぬるに」以下の占いの段の現代語訳を作り当日配布しました。現代語訳を出すについては賛否両論あるでしょうが、あえて観る人の理解を助けることを優先しました。占いの段現代語訳 少年の引いた歌
占いの段で「金土の初爻を尋ぬるに」の「金土の初爻」は観世流では「今度の所労」という漢字が当てられ「今度の病気を占うと」ほどの意味ですが、喜多流の「金土」は“金剛に覆われた聖なる国”とか“須弥山の世界”の意で「初爻」は占いの初めを意味し、「西方金剛界におられる諸仏にお目通りを願って、占いの第一からいいますと」というような、巫の常套句ではないかと考えられます。
雄大な宇宙観のもとに占いを始めるという、武士好みの凝った言葉の選択には、喜多流の真髄が現れているようです。
そしてワキが引いた歌の下の句「西紅にそめいろの山」のそめいろは須弥山の別名「蘇迷廬」のことで、転じて「蘇命路」、命が蘇るとよみ解き、病は回復に向かうと占います。
須弥山は古代インドの世界観から登場し、仏教の宇宙観にでてくる世界の中心に立つ山。その雄大な宇宙観、世界観を述べながら、男(ワキ)の父親の病について占うという趣向です。須弥山について現代人は殆ど無知ですが、秀吉の時代、太閤の前にて家臣が須弥山という言葉を使って、歌の雄大さを競ったという逸話が残っており、*(須弥山の歌争い)このことからも、中世から江戸ぐらいまでの武士や知識人には須弥山などの教養は備わっていたもののようです。このように歌占いに込められている意味や深さがわかってくると、興味は尽きないものになります。
次の地獄の曲舞の段や神懸かりの段はこの曲の山場で、シテとしても大事な型の連続で、見せ所です。*(『歌占』にみる地獄の様)『歌占』の作者、観世十郎元雅は地獄の様を見せることで、人生や生き様、死を考えさせようとしたのではないでしょうか。男巫(シテ)は一度頓死し、三日後に蘇るという臨死体験をしているという設定ですから、地獄の有様の舞は正に真に迫ったものになったでしょう。
元雅は『隅田川』『盛久』『弱法師』など、死や生き様を題材にした作品が多く、父世阿弥とはいくらか趣きの違う世界を作り出しています。元雅にとって「一生とは」「死とは」が一つの大きなテーマだったに違いありません。
ここでシテ渡會の某について、渡會家といえば、伊勢の神職にある由緒正しき血筋のはずです。その一族の一人が、家族も捨て、神職もなげうって、遊芸(歌占い)を生業にして放浪の旅に出るというのは、言語道断のことで、神からのお叱りを受けるのは当然のことだったはずです。
にもかかわらず、渡會の某は、伊勢の神が唯一の神なのか、自分の人生はこれで良いのかと苦悶し、広く世界を見て考えたいと、放浪の旅に出たのではないでしょうか。そして旅の途中、神罰に当たり頓死して地獄を体験させられ、三日のうちに生き返って、再びこの世の生を与えられます。しかし私は、この段階での彼は未だ死の淵にいる、つまり自分のこれからの生き方を掴んでいないように思えるのです。
蘇生という大変な体験をしながらも、未だ伊勢への帰還をためらっているように見えます。それが我が子との邂逅によって、この子ともう一度伊勢で生きてみようと、心に決めたのではないでしょうか。
地獄の曲舞が主題の『歌占』に子供との邂逅を入れたのは、地獄の恐ろしさを見せつけられた観客に、心がふっとなごむ場面を作って精神のバランスをとるとともに、渡會の某の再会後の生き方を決定づける重要な仕掛けにするためだったのではないか–。父子邂逅の場は筋立ての為の単なる付け足しで、それ故『歌占』は主題がやや散漫になり失敗作ではという人がいます。
しかし、この場は、親子掛け合いでの舞台の盛り上がり、役者自身の真実性ある演技が必要とされ、舞台に立つ人も観客も興奮するような場面をつくらなければならないと、教えられてきました。私は自分で演じてこの場の重要性を肌で感じ、これが付け足しであろうはずがないと思いました。
元雅は無駄なものを一切削ぎ落とし、見事に一曲を構成していたのです。一見、無駄に見える親子邂逅も、実は渡會の某の心の動きに焦点を当てた時に不可欠で、作者が予め巧みに仕組んだものであったのです。
人生への惑いと悟り、現代人にとっても永遠のテーマがここに盛り込まれ、今観る人の心を突き刺していくようです。
今回『歌占』を深く理解しようとする中で、渡會の某という役を演じることから、彼の中に自分自身を投影し、己を表現するという事が意識できたのは、一つの嬉しい体験です。サシ謡以降の「一生は唯夢の如し、・・・」はまぎれもなく、今自分の心のうちにあるものです。この作品は壮大な宇宙論に思いを馳せながら、生き様や死をじっくり考える時が、自分にも間近に迫っていることを教えてくれているようでした。
2000/6/20 記
子方を通しての『望月』投稿日:2000-03-05

粟谷能の会粟谷新太郎一周忌追善(2000年3月5日)で『望月』を勤めました。
『望月』は、獅子舞をベースにした仇討ち物語で、能としては珍しく一句の拍子謡の歌唱部分がなく、会話の台詞しかありません。安宅同様、直面物(ひためんもの)の芝居的な要素が多い曲と言えます。『井筒』(いづつ)、『野宮』(ののみや)、『定家』(ていか)に代表されるような幽玄としての要素が乏しいことから、作品としてこれから生き残る価値が無い等という人もいますが、私は『望月』のように、物語が分かり易く、獅子舞という見せ場があり、特に子方が活躍するこの曲は観客が存分に楽しめるものと信じ、決して廃れるとは思いません。一日の観能の最後に何と無く気持ちがほっとする、このようなものもあっていいのです。
しかし、それには子方が立派に勤めることが必要とされますので、その役割は重要です。子供を子方から一人前の能楽師に育てること、これは親としての勤めでありますが、周りの環境の力もまた大きな支えとなります。子供の成長過程に於いて、今この小さな役者に何が必要かを考え、その年齢にふさわしい曲目を選曲してあげること、これは大事な事なのです。大人の勝手な演能スケジュールに振り回される事を良しとしたくありません。子方の修行過程をむやみに変えるような無謀な計画、それがもし成功したとしても、私は慎むべきではと考えます。周りが優しく暖かく見守ってあげなければ子供は上手く育たないでしょう。そして親は子供のふさわしい時期に、たとえその機会が無くても、共に勤めるだけの力をつけておくこと、それができない様では父親として能楽師として、悲しく恥ずかしいことであると教えられてきました。
私は三歳にて『鞍馬天狗』の花見(はなみ)で初舞台を踏んで以来、子方を百二十回勤め、多くの経験をさせてもらいました。それは確かに芸の肥やしになっていますが、一方曲全体の流れがわからず、自分の演ずる部分だけをこなすような事が多かったので、息子尚生には一つ一つの舞台を丁寧に勤めさせ、その中で何らかの感動を得ながら、能を演ずることは辛く苦しいが、反面こんなにも楽しく面白いものがあるのだと、感じてもらいたいと常々思っています。子供が演じることを楽しむようになったら、まずは大成功なのです。
私の『望月』の子方は八歳から十歳の間に六回勤めており、今回は自分の経験を基に息子に教える事としました。例えば最初の橋掛りにおけるツレとの連吟(連吟=二人以上で同時に謡う)。ここでの謡の音の高さが合わないと舞台の緊張は一瞬に解け、子方は登場したそうそう不安にかられ、声の張りは萎縮してしまいます。子方は子供の声の高さで体中を使っておもいきり大きな声で伸びやかに謡うのが身上ですから、ツレが位を保ちながらも上手に子方に合わせ誘導しなければならないのです。今回、ツレの長島茂さんには何度も念入りに、音あわせ に協力していただきました。その結果、子方が安心して大きな声が出せて良い成果をだしたと思っています。
今回舞台での見直しにつながったことですが、子供の頃より気になっていた事がありました。ワキ(望月秋長)が登場して、シテ(小沢友房)が子方(安田友春の子、花若)に望月が来たことを知らせます。それを聞き、子方が「何、望月と申すか」と勇む場面があります。従来の喜多流の演出では本舞台上に二つの部屋があるという設定で、ワキとアイ、ツレ(友春の妻)と子方という仇同士が直ぐ隣に座っているというなんともおかしな舞台風景になっています。私は子供の頃、こんなに直ぐ隣に望月がいて見えているのに、どうして急に驚いたように、「何、望月と申すか」と謡わなければならないのか、子供心にも腑に落ちなく違和感を覚えていました。そこで今回はワキとアイが宿を借り舞台に入った後はワキ座の奥に本舞台から外れて座って貰い、子方とワキのいるところとがはっきり分かれている形の演出にしました。そのほうが自然なはずです。
『望月』の子方にとって最も大変なのは羯鼓(かっこ)を打ちながら舞う場面です。笛に合わせて舞うのは難しく、重要な稽古のポイントですが、笛方と合わせるのは申合(もうしあわせ=リハーサル)一回だけです。最初は笛の部分を口で唱歌して稽古します。最近はテープがありますから、型ができあがりかけたら本番さながらにテープで練習することができますが、私の時は唱歌に合わせるだけでしたので、いざ申合という時にお稽古のように笛が聞こえてこないので、びっくりし困惑した思い出があります。それに本物の羯鼓は当日でなければ付けることができません。当日初めてこれが刀、これが羯鼓と見せられ、こう持つ、こう打つんだと教えられるのです。とにかく初演の時に面食らった色々なことは、今でも忘れられません。
今回息子には、稽古の時から羯鼓と同じくらいの大きさのものを腹に付けさせ、刀もおもちゃの刀を買ってきて、扱いの練習をさせました。最近の子供はチャンバラごっこをしないので、刀の抜き方、持ち方、例えば左手は鞘(さや)を腰につけ持ち、右手は鍔(つば)ぎりぎりを持つ、などということを知りません。大人の感覚で教えなくてもわかるだろうと思う事でも、子方は戸惑うことがあります。ですから、できる限りこのような障害は最初に取り除いておくことが、大事なことだと思うのです。これは私の体験からのものです。
『望月』の最大の見せ場は獅子舞。これがあるため重い習(ならい)とされていて、シテとしても力の入るところです。子方の時子供心に、この場面のシテは格好いいな、自分も将来やってみたいなと感じて見ていました。そして気持ちが熱くなってきたところで、いざ仇討ちの場面になります。観世銕之亟先生は『望月』は目が大事といっておられると聞きました。仇討ちに向かうワキを見据える目、特別な動きとしてではなく自然と身体の内側から出てくる動きとして利いてこないといけないのです。子供にはしっかりと場面設定を言い聞かせ舞台を理解させておき、本人が楽しんで舞うようになった時、それは自然と生まれてくるものなのです。
子方ができる時間は限られています。息子も、三,四年すれば子方卒業です。そういう子供との一番は大変貴重で、まさに一期一会。子供にも能の舞台に立って熱く感じるものがあるのですから、一曲一曲ステップアップしていけるように配慮していきたいと考えています。
最後に『望月』のもう一つの醍醐味、それはクセ(子方とツレが曾我兄弟の仇討ちの物語を謡うところ)の部分です。この地謡は前半のクライマックスで粟谷の独特な謡い方があります。謡本の下音(げおん)としるされている箇所を低く謡わず、一段高い調子で謡いあげるところに口伝があります。今これを上手に謡いこなすのは父粟谷菊生が一番です。自分が『望月』を勤めるときは絶対父に謡ってもらう、これが私の願いでした。今回菊生、能夫が地謡で朗々と謡い上げてくれて、息子と力を併せて『望月』の舞台を勤めたことは、私の良い思い出となりました。伯父新太郎への追善として、良い舞台を手向ける事ができたと思っています。
写真 東條 睦氏
『頼政』の鬱屈と爆発 小劇場にて投稿日:2000-02-26


SPAC能楽特別鑑賞講座(平成12年2月26日)の『頼政』では、父の体調が突如悪くなり私が急遽代演する事となりました。急な代演というのは、技術面(謡=言葉、型=動き)の心配もさることながら、曲に取り組む心の準備に時間がないため不安が付きまといます。あわただしく舞台に向かう中、繰り返し謡や型の確認をし、その短い時間で集中して、どう演ずるかを見つけださなくてはなりません。
しかし当日の観客は予定されていた演者を期待し、代演者では少なからず失望しています。その負の要素を背負って舞台に立つことは、どんなに心を込め精一杯勤めていてもやりづらいものがあります。
今回の『頼政』は静岡県舞台芸術公園内、楕円堂という小さな円形劇場で現代劇、小劇場用の空間で行われました。壁、柱も黒いうえに照明が暗く、ほとんど真っ暗な中、シテやワキにスポットライトが当たり、演者が浮かび上がるような演出でした。(通常能の世界ではスポット照明は使用しません。これは面の中に光が入ると演者の目が見えなくなる為です)。
もちろん橋掛りも四本柱(舞台を支えている笛柱、ワキ柱、シテ柱、目付柱の四本)もありません。最初この舞台を見て驚きましたが、それよりも増して、プロデユースをなさっている観世栄夫先生に「いったい、どこから舞台に出て、どのようにワキに呼びかけたらよいのですか」とお聞きすると、「ここは扉が沢山あるから、どこからでも好きなところを開けて出てよ」とのお返事で、尚仰天してしまいました。
常の寸法(普通の能舞台は三間四方)ではない変形の狭く暗い舞台は、面をつけて演ずる側にとって、全くいい条件とは言えず演じにくい難しい空間です。
しかし、観る人の意識や息づかいなどが、直に伝わってきて、舞台と客席が一体となる小劇場ならではの魅力はこういうことか、とわかる気がしました。全体の舞台効果について、地謡の人達から、いつもと違う空間の面白さがあった、能舞台でないところでそれなりに充分成立していたと聞き、表現方法にはいろいろな可能性があることを、再発見できました。
『頼政』を勤めるに当たって、初演に出来なかったことを思い出しました。後シテの頼政が宇治川の橋合戦の模様を再現する場面は、地謡が宇治川の急流を謡いあげる中、決められた型をしっかり演ずれば、よい見せ場となりますが、難しいのは、前シテの老人がワキの旅僧に名所教えをする前半部分です。
ワキの「名所旧跡を教え侯へ」に対して、シテは「卑しき宇治の里人なれば?」名所旧跡など知らないと、ひねくれた答え方をします。そのうち喜撰法師の庵はどこか、槇の島、小島が崎はどこかと次々と聞かれていくうち、平等院のことをなかなか聞いてくれないことに苛立ちはじめます。そしてついに自分の方から、宇治の名所といえば平等院ではないかといって案内し、頼政が自害した扇の芝の説明を始めます。この何でもないようなやりとりの中に、頼政の思い通りにいかなかった一生や、この世への執心が象徴的に表現されなくてはつまらないと思います。
頼政の辞世の句は「埋もれ木の、花咲くこともなかりしに、身のなる果ては、あわれなりけり」です。平治の乱では源氏でありながら、平清盛につき、源氏方の滅亡を見ながら、生き延びるという複雑な立場でした。それ故か武勲を積んでも思ったように認められずなかなか昇殿を許されない不遇、以仁王(もちひとおう)に謀反を勧め、諸国に散らばる源氏に平家追討の令旨(りょうじ=王、皇族の出す命令)を発しさせ、共に挙兵するが、直ぐに亡ぼされ、自らも平等院で自害する不運、これだけのことを見ても辞世の句の通りの生涯です。自分の人生へのやりきれなさ、もどかしさ、鬱屈した情念、それがこの世への激しい執心となって成仏出来ずにいます。そういう頼政を思うと前半の名所教えの苛立ちも解っていただけると思います。
「何故自分が一番聞いてほしい平等院を聞かないのか」という焦れ(じれ)を大袈裟にならず、しかし観る人にほんのりとわかるように表現できたらと思うのです。
そして七十五歳とも七十七歳ともいわれる老人が何故以仁王を唆し(そそのかし)挙兵したか。不遇の身をかこちながらこれまでじっと耐えてきたのですから、本来なら動かぬはずです。しかし事を起こしてしまったのは、息子仲綱が平宗盛に、はずかしめを受けたからです。宗盛は仲綱の愛馬「木の下(このした)」を所望しますが、仲綱は断ってしまいます。父頼政はこれを聞き仲綱をなだめ愛馬をさし出させますが、時既に遅く、わがまま宗盛は「木の下」の尾とたてがみを切り、尻に「仲綱」の焼き印を押して放ってきます。戻ってきた愛馬の哀れな姿が、頼政にはきっと自分自身にもまた源氏一統にも見えたのではないでしょうか、遂に自らの怒りの心に火をつけてしまいます。能ではこの馬の話しからを間(アイ)狂言が語ります。
私はここを聞くのが好きで、地謡の時先人の上手い語りに心ときめかせたものです。今これを後シテで演じる心の高ぶりや怒りの基盤にしています。それにしても子供の喧嘩に親がでるのは愚かということになりますが、親になってみるとこの気持ちがわからないでもなく、ちょっと考えてしまうところです。我慢を積んでいる人にとって、自分より身内や家名をけがされたことが発火点になることはよくあることで、頼政も武門の恥をそそがんと奮い立つわけです。しかしこの事件は引き金であって、謀反の原因のすべてでないことは明らかです。今までたまりにたまった頼政の感情の爆発なのです。
もとよりこの反乱、清盛に漏れ知られ、情勢はたちまち不利となり無念の最後となります。この数々の鬱積した不運を頼政という人間像につつみこんで演ずるのが、能『頼政』です。

『頼政』の面は[頼政]という専用面(その曲にのみ使用する)を使います。専用面があるものは他に『景清』『鬼界島』『山姥』『弱法師』『蝉丸』『一角仙人』『猩々』でこれらの曲を一面物といいます。その面でなければならない強い特徴があり、[頼政]は目に金属が工作されていて、この世の人ではない、修羅の巷での強い怨念を表した面といえます。ですから後シテ(頼政の霊)は老人といえども、老人らしくとは演じず、只ひたすら強く強くと演じるのが心得となっています。
修羅能でシテが老人であるのは『実盛』と『頼政』の二曲だけですが、実盛が六十数歳で写実的老体の演技を求められるのと対照に、頼政は七十七歳でありながら年齢を超越した強い執心を描いたところに作者世阿弥の思いがあるようです。成功者『頼朝』では、世阿弥も描かなかったでしょう。能の世界ではこの世に強い思いが残っている者を選んでいます。その選ばれた人々を演じ思いを伝えることが能楽師の喜びではないでしょうか。
2000/4/24 記
『殺生石』「白頭」のあり方について投稿日:2000-02-05


2000年2月5日の花の会で『殺生石』「白頭」を勤めました。能は人間の心の葛藤を極めて様式化した手法で表現する演劇形態だと思います。従って表現する心の対象は、明らかな面よりも闇の部分の方にその比重をおくことになってくるのは容易に想像できるし、実際そのような曲が多いのですが、中には物語としての面白さと同時に演出としての面白さを主としたものもあり、今回の『殺生石』は後者の部類に入ります。この様な曲は、あまり深刻にならず、軽妙な面白さを楽しんでいただけたらよいと思います。この度は『殺生石』の小書「白頭」について考えてみたいと思います。現在喜多流では白頭(しろがしら=通称 はくとう)を使用するものは次の三系統に分けられます。
(1)曲の本来の形として白頭を着用するもの
『龍虎』(後して)『石橋』(「連獅子」のシテ)『綾鼓』(後して)
(2)本来は使用しないが、替えとして着用し、型や位はさほど変わらないもの
『黒塚』『鵺』『山姥』
(3)本来は赤頭(あかがしら)であるものを、正式な小書として白頭に替えるもの
『鞍馬天狗』『是界』『氷室』『小鍛冶』『殺生石』など。
ここで問題になるのは、(3)小書演出による白頭についてです。 通常「白頭」になると曲の位(大事に扱う度合い)は上がり、謡も型もしっかりと重く(より大事に)なります。謡の運びに緩急がつき、型も小書独特の型が入り、装束や面も変わります。
さらに、この小書による「白頭」も二つの流れがあり、一つはベシミ系の『鞍馬天狗』『是界』『氷室』、もう一つは狐の系統『小鍛冶』『殺生石』です。
喜多流では、『小鍛冶』の「白頭」のみ用いる狐足と呼ぶ特別な抜き足の型があり、敏捷で小刻みな狐の動きを模したものですが、これは特別なもので、普通は「白頭」になると、よりどっしりと重量感をもたせ、より硬質な大きな力を表現しながら舞うのが心得とされています。
ではこの小書によって赤頭を白頭に替える理由はどのあたりにあるのか、そもそも「白頭」の白とはどのような意味を持つものなのか。
一般には、白い髪すなわち老い、というイメージがありますが、能の世界では少し違うようです。
喜多流の場合はその役の位が最高位に上がり、劫を経て超越した力の表現として象徴的に使われて いるように思います。
以下に、殺生石の演出上の相違点を表に纏めてみました
| 形式 | 頭(冠) | 面 | 着付け | 袴 |
|---|---|---|---|---|
| 常 | 赤頭(無) | 小飛出 | 法被 | 赤半切 |
| 白頭 | 白頭(無) | 野干 | 法被 | 紺半切 |
| 女体 | 黒垂(狐) | 泥眼 | 舞衣 | 緋長袴 |
| 今回 | 白頭(狐) | 創作面 玉藻 | 舞衣 | 白半切 |
本来喜多流は常の型と「白頭」の二形式だけでありましたが、先代15世喜多実先生の宗家就任記念として、先代金剛巌氏との間で、喜多流の『富士太鼓』「狂乱の楽」と、金剛流の『殺生石』「女体」とを互いに共有し合うことで合意し、喜多流に「女体」の形式が加わりました。
話が少し脇にそれますが、金剛流の「女体」は、前場の曲(クセ)の部分が喜多流の居曲(いぐせ=座ったまま動かない)と違い舞うこととなり、後は女姿となり活発に動き回る玉藻の前(実は妖狐)の有様が良く表現できていて、大変興味深いものです。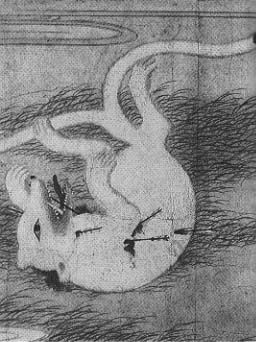
喜多流の先代宗家の初演の折りは、型は白頭の型のまま、つまり、後は一畳台の上だけで演じ、扮装のみ「女体」という演出にとどめられていました。しかし、近年にいたって「女体」をより分かり易く、動きのあるものへと変化させようとして、様々な試みがなされています。
将来私も「女体」を勤めたいと考えいますが、事前に本来の型としての小書による「白頭」を経験し、整理しながら次の段階への縁がとなればと、今回勤めた次第です。
伝書では、前、後場共、ほとんど動きらしい動きの記載はありません。その為面白味に欠けると評価は低く、身体が動かなくなったときの老人用小書であるなどと、演者仲間の内向きの話として囁かれています。確かに私も、その要素が無いとは言い難いと思います。
舞台を見ていた人々が少数の選ばれた人達であった時代、物語の筋も謡も十分理解できているし、ことさら動かなくてもわかっていただけるだろうという演者側の甘えがもたらした悪しき慣習によるものではないでしょうか。
限度を超えた演出演技のダイエット(謡や舞の省略・改変など)は、その能本来の形を破壊して、一曲の存在意義さえ無くしてしまう事になりはしないかと思います。
その様なわけで現在の我々能楽師の型付け鵜呑みの、踏襲のありかたも考え直す必要があるだろうと、演じながら常々感じています。
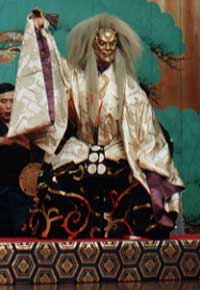
さて、殺生石の演出ですが、巨大な石の中に未だ閉じこめられている、絶世の美女に変化してきた妖狐。その執心は石のように硬く冷たく、今も周囲に悪をもたらしている。那須野原にて射殺されながら、その魂は当時のままに凝固されてあり続けているのだという内的要因を、なんとか観客にメッセージとして訴え続けなくてはと思いました。そこで今回は、鬼畜はなんでも男姿とする江戸式楽的な発想から離れ、幾分女体に近い型としての「白頭」ということで演じたわけです。
面も本来の野干(やかん、狐の意)では(左写真)、動物的な印象のみ強すぎる為、岩崎久人氏の創作面、玉藻(下写真)を拝借しました。女体に近づきながらも、中性で大きな石の中の妖狐の魂として演じるべく、装束すべて白に纏めてみました。それは次に勤める「女体」へと通じるものでもあります。
平成9年の友枝昭世氏による『殺生石』「女体」は、鬼畜の狐を超えた、時代を経て昇華した女性の魂の表現の領域に踏み込んだ、卓越した演出であり演技であったと感動した事を覚えてます。一番の能にも再認識することにより、新たな表現の可能性があることを実感しました。

能楽という限られた世界で生きている自分にとって、演じる曲についての発見や改良は喜びでもあり責務でもあります。難解な曲、わかりにくくなってしまった作品を見直し、その主旨をもう一度考えながら自分の能に活かしてゆく、この一連の作業は困難でもあり楽しいものでもあります。
この過程を経て一番の能があることをおわかり戴ければと思います。
『清経』の音取を演じて投稿日:1999-11-01


この度の研究公演(一九九九年十一月)に於ける『清経』では小書「音取」に取り組みました。そもそも「音取」とは何なのか。平家物語の中に、清経が「舟の屋形に立ち出て、横笛音取朗詠しあそばせけるが」と出てきます。この横笛音取とは、今様の朗詠を始める前に横笛で音を定めたことを言うらしいのですが「音取」の名称の由来はこのあたりかも知れません。「音取」ではシテ(清経)の登場から、小野小町の歌といわれる「うたた寝に恋しき人を見てしより夢てふものは頼みそめてき」と謡う所までの演出に違いがあります。
常のシテの登場は橋掛りより舞台まで地謡に合わせて出ますが、「音取」では橋掛かりの歩みを笛の音と呼吸を合わせ、思いを込めて運びます。まず笛が地謡の「夢になりとも見え給え」で舞台地前まで進み出、幕をうけ、音取の世界となります。シテは笛の断続的な特別の譜に合わせ、笛が止めばシテも静止する、聞こえれぱ又動く、というように、死後の世界より妻の思い寝の夢の中へ、自分が好んだ笛の音と共に歩むというものです。笛は流儀により多少吹く長さが異なり、その音色は不思議に同流の方でも微妙に違って、個性が充分発揮されるところです。
さて、シテはこの音取をどのようにつとめたらよいものか。難しい笛との呼吸の合わせ方を、先人は手向けの笛に引かれる心を十分に感じて歩むのだ、などと言われますが、稽古していて、どうも釈然としないものを感じます。それは私自身、笛が何の心を吹き、シテは笛の何に反応すれば良いのかということが、十分理解納得していなかったからだと思います。演技とは思いを伝えること。言葉や音が演者自身の肉体を通して何かを伝えようとする、その働きを常に意識、作動させなくてはいけないと思います。
そこでいろいろとある資料を見ていく中で、一つ気になるキーワードを見つけました。それは森田流の心得にある「音取ノ出様ハ妻乞ノ鹿ノ心……」です。鹿という動物は夫婦仲が良く、遠く離れていても、雄が雌に向かって鳴くと雌もそれに答えて鳴くそうで、これを鹿の遠鳴きといっているそうです。尺八の曲に、深山幽谷に呼び交わす雌雄の鹿の鳴く音をテーマとする、琴古流本曲『鹿の遠音』があります。尺八二管が雌雄の鹿のように奏で合うもので、官能的で大変面白いものです。
『清経』の音取はこの響き合いに似ています。つまり、笛の音は清経という男の心の叫びであり、それを受ける妻の心情であって、音取はそれを一管に託した演出であろうと思われます。この様に思うと、演ずる心のよりどころを一つ掴めたようで、とても歩み易くなりました。音取という演出では、笛の音を利かせながら、行き違ってしまった二人の気持ちを、夢の中に於いて引き出すようなものに焦点があるように思われます。二人は互いの恨みごとを言い合うことになりますが、夢幻での再会はやはり美しく演出されなければならないと思います。
次に、シテの面をどうするかです。常の通り中将ですが、それぞれ面の表情が違うので、どのように演ずるか迷うところです。中将の名称は在原業平の面影を打ったというので業平の在中将からつけられたといわれています。中将の面は在原業平、光源氏、源融や天皇などの高貴な人々の亡霊系のものと、修羅道に落ちた平家武人の系統のものと、大きく二系統に分けられます。
清経は左中将で修羅道で悩む平家武人の代表的な人物です。私は今回、家にある平家武人系統の面の中から、強く苦悩を感じるものを探しました。能に登場する平家の武人で修羅道に落ちた者はたくさんいます。忠度、通盛、経政、敦盛、彼らはみな合戦で勇敢に戦って殺され、亡び行く者の中に死の美学さえ感じさせる武者たちです。ところが清経は平家の将来を憂えて、戦わずして身を投げ修羅道に落ちたのです。戦わず心弱く死んでいった者の顔は、立派に戦った武者の顔とはどこか違うのではないか。かといって、自ら死を選ぶ者の顔は決して弱いのではなく、逆に一番強い苦悩がにじみ出ているものでなければならないだろうと考えての選択でした。
清経は平重盛の三男。重盛の一族は小松殿と呼ばれ、内省的な家風があったようです。源氏方から追われ、身内からも孤立し、そして神からも見放され、そのような中での清経の深い孤独感、苦しみ等、選んだ面を見ながら、清経二十一歳の若き苦悩を思いました。
装束は、喜多流では本来長絹姿で、肩を脱いで舞うのが一般的ですが、今回私は単衣法被肩上という甲冑姿を試みることにしました。この姿は音取の場面ではとてもりりしく、効果的な風情が出るのですが、曲(クセ)を舞う時には少々難があるように思われます。つまり舞人の装いではないからです。しかし今回は研究公演ということもあり、思い切って挑戦してみたく、この事により何かを感じとれるかもしれないと、敢えて甲冑姿にこだわってみました。どちらが良いか、私の気持ちは五分五分というところですが、観る方にはどのように映ったのでしょうか。
ところで、能、『清経』は、戦わずして身を投げるのでは武士の士気にかかわると、江戸時代、藩によっては演能が禁じられたところもあったようです。今でも宮島・厳島神社での御神能では、『清経』は舞台に乗せてはならない慣習になっています。江戸時代の流れをくむものでしょう。
しかし現代、『清経』は人気曲の一つで、よく演じられています。平和な時代がこういう武将の物語を受け入れられることとなったのでしょうが、人気なのは何よりも、詞章の美しさにあると思います。
平家物語では清経に関する叙述はわずか数行、それを世阿弥があれだけの名文でつづり、ひとつの物語として完成させているのです。謡い上げ、舞い上げる中で、亡び行くものに花を咲かせること、これが役者の仕事ではないかと思っています。
『絃上』について投稿日:1999-10-01

能『絃上』は喜多流ではこのように書き、「けんじょう」と読みます。この絃上とはそもそも琵琶の名器の名前ですが、いろいろと説があるようです。「玄象(げんじょう)」と書かれる観世流のものは、仁明天皇の御物で藤原貞敏が唐より持ち帰られた楽器らしく、「玄上」は村上天皇のお使いになった琵琶だったそうです(資料提供は宮内庁式部職楽部)。二つとも残念ながら戦争で消失してしまったそうで、現存していません。ですから喜多流の「絃上」はこのどちらにもあてはまらず、当て字のように思われます。
琵琶の種類は現在大きく楽琵琶と俗琵琶に分類されます。楽琵琶は雅楽の演奏に用いられ、俗琵琶としては、盲僧琵琶(荒神琵琶)、筑前琵琶、薩摩琵琶などがあります。平曲の伴奏に使われる平家琵琶は楽琵琶と盲僧琵琶を折衷したようなものになるようです能『絃上』の琵琶は楽琵琶です。楽琵琶は大きいため横に倒して弾きますが、俗琵琶は形が小さく縦にして構えるものもあるようで、両者は弾き方も異なります。
喜多流の『絃上』では琵琶は作り物として登場しますが、本来は前場の「絃上」に本物の琵琶を使用し、後場での「獅子丸」(これも琵琶の名器)は作り物を使うようにと伝書にあるようです。今回の『絃上』(平成11年9月16日 シテ高林白牛口二氏)は国立能楽堂の協力を得て、琵琶演奏家の田中之雄氏から楽琵琶を拝借することで、本来通りの舞台が実現しました。私もツレ藤原師長を勤めることで、あの重く大きい楽琵琶をこの手に直に触れることが出来幸運でした。
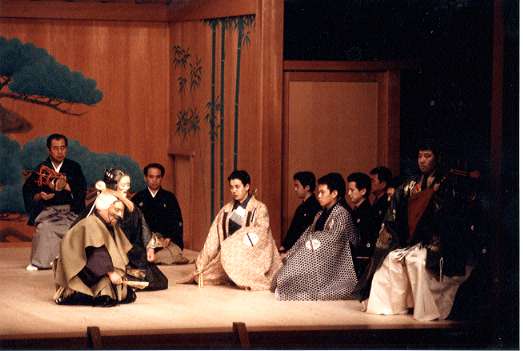
師長という役柄上、床几にかけ琵琶を持ちますが、やはり弾くときは床几から降りて下に居て弾いた方が落ち着くように思いました。あのずっしりとした重みのある琵琶を床几にかけて弾くのは少々景色が悪かったように思えますが、ずり落ちないように必死に抱きかかえたことは、良い思い出になりました。
琵琶を弾くために本物や作り物を用意するなど、前場は謡と型がよく合っていて、当てぶりな具体的な所作なども多い演出となってます。師長が塩屋を出ていこうとする場面でも「忍びて塩屋を出で給えば」と謡って、脇座にて後ろに向いて座り、出ていくことを見せるやりかたも分かり易くなっています。
一般にお能では、例えば『経政』や『蝉丸』で琵琶を扇にて表現するように、本物を使う、あるいは当て振りな表現をすることは少ないのですが、今回のように、伝書通り思いきって本物を使うのも面白いと感じました。
琵琶の道を極めんと入唐渡天を志す藤原師長を、思い止まらせるために老人夫婦として須磨の浦に現れ、琵琶と雨の音を調和させるすばらしい演奏を聴かせる村上天皇(シテ)は前場では素性を明かさず、宿を提供する老夫婦として師長に琵琶の演奏を所望します。

師長が琵琶を弾くくだり、「恋い侘びて泣く音に紛ふ浦波の 思う方より風や吹くらん」と謡い、琵琶を奏し始めると、にわかに雨が降り始め琵琶の音をかき消してしまいます。老人(村上天皇)は板屋根に苫を葺いて、甲高い雨の音を和らげる心づかいをみせます。この場面で森田流の笛は真の会釈(アシライ)笛を吹きます。最初の師長の謡いに合わせ双調の呂、地謡の上歌の琴の言葉に合わせ黄鐘の高音、雨という言葉に合わせ盤渉中の高音とそれぞれ三調をアシライで吹かれるのですが、琵琶,琴、雨を表現しとても良い演出で、今回、京都の杉市和さんは情感豊かに吹かれ、演者の私も思わず聴き入ってしまい、味わい深いものがありました。
雨に対する心づかいに、師長はこのふたりはただの老夫婦ではないことに気づかされますが、さて、しての村上天皇はどのような人物なのでしょうか。
平成八年の、演能に当たって調べた事を掘り起こしてみました。村上天皇は醍醐天皇を父として14番目の皇子として生まれたため、ほとんど皇位継承権は期待出来ず、政に関心を持つより、ただただ琵琶を弾き毎日優雅に遊ばれていたようでした。ところが、次々に兄弟が病により亡くなると、急遽皇位につくことになります。それまでは天皇と皇子は琴を弾く習慣となっていたようですが、この村上天皇の御代より琵琶を弾くことになるようです。この特異な生い立ちは能として登場するに十分の題材であったと思われます。
後半では龍神に持ってこさせたもう一つの名器「獅子丸」を師長に弾かせ、天皇自らも「絃上」を弾かれ、早舞を舞います。この演出の真意は、「師長、おごる事なかれ、唐に渡らずとも、ここに琵琶の名手がいるではないか」と語りかけるように天皇が師長に琵琶の秘技を伝授する様子を表現しているように思われます。

しかし、現状のままの早舞をご覧いただくだけで、観る人にこのことを理解していただくのは、やや辛く無理があるように感じます。
前場とのバランス(当て振り的なものが多い)を考えれば、例えば早舞の間、師長が伝授されている風情で琵琶を弾く型をするとか、また梅若六郎氏が一度なさった様に、実際に本物で弾いてしまうというのも効果的で、そのくらいのアクションがあっても良いのではと思います。ここのところ、書き物にある 「少ししっかりした位にて舞う也」、とあります。「しっかりした」の解釈にもよりますが、単に伝書の言葉止まりにならず、やはりそこには村上天皇という人物を表現するために、スケールの大きい、力強いダイナミックな舞を基盤に、色々と工夫を凝らすことが出来るのではと思います。次回には何か工夫してみたいと思っています。
また最後の舞台上の役者の動きの処理も、喜多流では師長が龍神に引かれてゆく動きですが、龍神がしてを先導してゆく風情を大事にするならば、他流のように師長が『須磨の帰洛ぞ有り難き』と最後に止め拍子を踏んで一曲を終えるのもよいのではと思います、またいつか機会があれば勤めてみたいものです。
1999/10月記
能『大江山』の酒呑童子について投稿日:1999-06-01
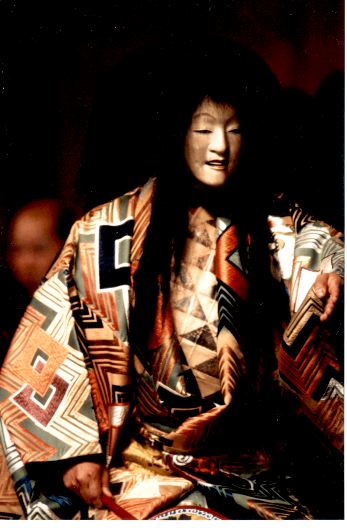
子供のころ、鬼退治の能は楽しみでワキが鬼を退治すると拍手喝采で楽しんでいましたが、近ごろはどうも楽しくない、いや晴れ晴れとしない、何か心に引っかかるものを感じるようになりました。それは退治される側を演ずるたびに徐々に大きくなっていったのです。こう感じるのは大人になって見飽きたからではなく、演じながら作品の主旨が少しずつ読み取れるようになったからかもしれません。今回(六月自主公演能)、『大江山』を演能するに当たり、まず酒呑童子とは何者か、能としての『大江山』は何をメッセージしているかを知らなくてはと思いました。 酒伝童子絵巻では、大きい顔をした酒呑童子が酒宴の珍しき肴として美女の白い太股を出し、それを頼光らがたじろがずに塩をつけて食べている場面や、頼光一行に首を切られる恐ろしい場面が描かれています。
また酒呑童子は大陸からの漂流者で、その大きい身体、赤い毛、緑に光った目、そして赤い顔で血を呑んでいたと恐れられていたが、実はその血は葡萄酒で漂流者はロシア人であったという説や、疫病を流行らせる疱瘡神(ほうそうしん)であるとか、兇賊、山賊のようなものである、村里から遠く離れた辺鄙な山中に住む賤民で、荒っぽい力仕事をして鬼のような怪力をもっていた人のことだという説などもあります。 どの説もそれぞれに面白いのですが、能『大江山』の酒呑童子としてはやや合わないように思われます。酒呑童子は本当に京に下って人を殺し、財宝を盗み女をさらったのだろうか。能の『大江山』では唯一、間狂言が洗濯女として血のついた衣を洗うところがありますが、それ以外はこわい場面は描かれていませんし、次の謡の言葉を拾ってみても恐ろしい悪人像は浮かんでこないのです。
1.我 桓武天皇にお請けをもうし 出家の人には手をささじと固く契約もうしたり
2.一夜に三十余丈の楠となって奇瑞(きずい)を見せし所に
3.霞に紛れ雲に乗り、・・・飛行の道に行脚して、或は彦山、伯耆の大山、白山立山富士の御嶽、上の空なる道に行き
4.此の大江山に篭り居て、隠れすまして在りしところに、今客僧達に見表され通力を失うばかりなり
5.さも童形の御身なれば 憐れみ給え
6.構えてよそに物語せさせ給ふな
7.情けなしとよ客僧達 偽りあらじといいつるに
酒呑童子は山伏達(頼光達が変装している)に敵意を見せず無抵抗に歓迎して(1)無邪気に身の上話をし、特殊な力(通力)をもつ存在であるが(23)、今は効き目がない(4)と悲しく語っています。恐ろしさや鬼畜性よりも通力をもちながら、争いを拒み、どこか弱いところがあるように感じさせられます。 父は『大江山』というと必ず「一稚児二山王だよ」といいます。第一に稚児、比叡山の神(山王)より大事にされるべきものだという意味で、自分は童子の格好をしているのだから「山伏達よ、どうか可愛がってくれ」(5)と依頼するところに焦点があるようです。本性は鬼のような異界のものであっても前場ではそれを見せず、綿綿たる訴えかけの言葉が重要で、能としてはここを大事に謡えという教えです。 酒呑童子の童子とは少年という意味ではなく、童形である永遠の青年、不老不死の特異な力が宿る者であります。最澄に比叡山を追われ各修験霊地を転々とするのが八〇六年ごろ、殺されたのが頼光二十五歳の時として九七三年と推定すると、童子の年齢は少なくとも百六十七歳の計算になってしまい、おかしく感じられるかもしれませんが、人間界以外では時間はゆっくり流れているようでさほど問題にならないようです。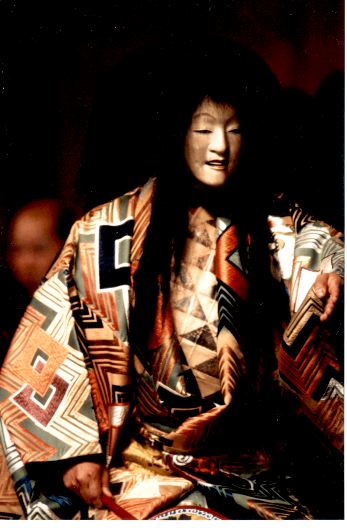
能としては童話性をもたせ、後の鬼神との対照の効果をねらうためにも、永遠の若さを象徴する神仙の化現として優雅で妖精的な神秘に満ちたものとして登場させたのでしょう。面は童子や慈童を使用しますが、今回は我が家にある余りに美しく透明感があるものより、霊性を濃くしたものの方が向いていると思い、岩崎久人氏の打たれた童子の面を使わせて頂きました。 『いざいざ酒を飲もうよ』の場面で、喜多流はシテがワキの酌を受けますが、たぶんこれはお伽草子による頼光達が自分達が飲むと勇気百倍、鬼神が飲むと忽ち通力が消えるという酒を持参したところからきたものだと思います。観世流では酒呑童子に子方の稚児二人がついて出る演出があり、ワキ・ワキ連等に酌をしますが、こうなると意味あいが異なります。私は酒呑童子がワキに酌をするくらいの方が童子の無抵抗さがでてよいのではと思うのですが、今回はワキに酌をする気持ちをもちながらも、従来の喜多流の型付け通りに行いました。 次にこの能のメッセージを知るために、神仙の化現とはいかなるものかを、もう少し掘り下げる必要があると思います。私は酒呑童子は最澄が比叡山延暦寺建立の前より住み着いていた地主神であったという説(金井清光氏・作品研究大江山)に興味が惹かれます。この場合の神は異界に住むものという意味で、異界とは人間界のコントロール不十分なところと考えられます。 異界の存在は、国家(京都朝廷)のような中央の権力者・統治者達にとっては邪魔であり、退治されるべきものだったのでしょう。権力者が領土拡大を謀るとき、それと敵対するものはすべて悪であり、統治できなくなった都の乱れは鬼神の仕業と見立てるのが妥当であったのです。そしてその対象となった最も目障りな存在とは、もともとそこに住んでいた多くの異界の地主神(地霊)であったわけで、彼らは差別・排除・征伐の打撃的措置を受けざるを得なかったのです。 酒呑童子も地主神であるならば、ときの権力者にとっては悪者でなければならず、退治されるべき存在です。しかし能『大江山』では、酒呑童子を単なる悪者ではなく、気の良い誠実な鬼として描き、むしろ偽りがあるのは寝込みを襲うなど退治する側にあることを見せ、征服する側にささやかな抵抗を示しているように思えます。 とはいえ、後場で実体は鬼神として退治征服されるものであると皆に知らしめる必要があったのは、見物者は体制側の人々であり、そうしなければおさまらなかったからで、中世の劇作成の手法だったのでしょう。童子を演ずる猿楽役者も酒呑童子と同じ階級に属する賤民で、征服者に調伏される運命にあり、それを自ら演じなければならない悲しさがあったと聞いていますが、それは中世の時代での事、今の能楽師は中世とは違う心持ちで、この能の訴えかけを考えてみる必要がありそうです。 最近の都心部における烏(からす)によるゴミ問題、計画性のない開発による自然破壊、ここにも征服者と被征服者の関係が見えるようです。私たち人間は、人間の都合で烏をもともとの住処から追いやっておきながら、都会に出没すると邪魔にし、その黒い姿を不気味がって、つい石でも投げて追い払おうとしてしまいます。でもこの烏、どこか能『大江山』の酒呑童子と似ているように思えてなりません。
(一九九九年六月)
『安宅』を演じてー 能の表現と芝居との境界線 ー投稿日:1999-03-01


平成十一年春の粟谷能の会で『安宅』を披かせていただきました。息子(尚生)と『隅田川』をはじめ『安宅』や『望月』を勤めることは私の夢でもあり、その夢の一つずつがかなっていくことは無上の喜びです。
今回『安宅』を演じるに当たっていくつか気になったことがありました。一つは四十三歳という自分の肉体が弁慶になり得るかです。歴史的にはおそらく都落ちしてゆく弁慶の歳は四十代前半ぐらい(義経は二十九歳)ですから、ちょうど今の私に合っているのでしょうが、能の舞台として考えると、この年齢は少し不安です。それは『安宅』のような直面ものには演じる役者が醸し出す味わい、風格というものが非常に大きなウエイトをしめるからです。
シテ方は面をつけることで、その役に入りますが、その面の力に助けられることが大きいのです。たとえば老人を演じるにしても、身体や声が少々若くても、尉の面をつければ、不思議にそれなりに見えてきます。面には偉大な力があります。しかし直面ではその力を借りることができません。身体から発する力をもとに風格を添え、自分の顔自体も面だという意識が必要になってきます。
役者は舞台でその生き方が滲んで見えてくるようでなくてはと解っているのですが、粟谷明生という人間の武蔵坊弁慶を安心して見ていただけるようになるには、まだまだ時間がかかることで、これはなかなか難しいことです。
能『安宅』は弁慶の思慮と沈着な行動がいかに主君の危機を免れさせたが主題です。構成は能本来の要素(謡と舞)と芝居(劇)的要素を取り混ぜた形になっています。その芝居的な部分をいかにこなすかが、大きな関門でした。
『安宅』は形式的には中入りのない一段でできていますが、都から安宅の湊までの道行と関所手前の作戦会議までの一場、関所におけるワキとの問答から、最後の勤行、勧進帳の読上、主君打擲と実力行使にて通過を成し遂げる見せ場の二場、関所通過後の休憩、関守の来訪、酒宴饗応と遊舞、一行の逃走の三場と、それぞれ場所を別にした三場構成となっています。能の定型の一場と三場の間に台詞を中心とした劇的な色彩の強い二場が入っているとみてよいでしょう。
私が苦心したのは第二場の言葉が多い部分、歌舞的要素の無いところでした。ワキとの問答、勧進帳を読み上げるくだり、ワキとの激しい型どころはややもすると、やりすぎのお芝居になってしまったり、また逆に演者の自己満足に留まり、何も観客に伝わらないことになりがちです。
謡本をただ読み上げるだけでなく、いかに劇としての真実味ある台詞を謡えるかが重要です。勧進帳の謡は難しい節扱いや拍子当たりだけに気を取られていたのでは駄目ですし、あまり感情が入りすぎるのも、また劇のレベルに達していないのも考えものです。ワキとの問答も台詞の中に運び、音の高低、張り押さえ、詰め開きを入れ、問答の緊張感を聞いてもらわなくてはいけません。
能の世界でできうる限りの表現をしながら、お芝居にならぬギリギリの境界線の内側で感情の起伏を観客に伝えることがカギとなります。境界線を越えてしまえば能ではなくなり、歌舞伎座や他の劇場で演ずるものと何ら変わらないものになってしまいます。勧進帳という名で歌舞伎のほうが一般に知られていますが、歌舞伎より前に生まれそのルーツとなった『安宅』。能本来のもっている味わいがあるはずですから、それを大事にして演じたいと思いました。
最後に、これは子方のころから不審に思っていたことですが、「一行はどうして通れたのだろうか」「なぜまた関守がやって来たのか」ということです。このことを自分なりに整理し、舞台作りに生かしたいと考えました。
私の考えている富樫像は山伏を容赦なく殺す冷徹で、単に役目に忠実な地方役人というものです。ワキとの問答の末、最後の呪詛の行に入り、「明王の照覧計りがとう、熊野権現の御罰と当たらん事」(不動明王がご覧になってどうお思いになるか、熊野権現の御罰は当然)と凄みますが、富樫はここで山伏を殺したことの恐ろしさを感じ「問答無益、一人も通し申さじ」と頑なだった態度を換え、勧進のために通るなら勧進帳があるはず、それを読むようにと軟化します。中世の宗教観で、山伏という修験僧をむやみに殺すことは神仏の罰が当たることだと感じ、目の前の山伏の迫力にも気圧されたのでしょう。勧進の責任者・俊乗坊重源の後ろにある仏や朝廷の存在も恐れたはずです。
一旦は通すことになりながら、強力が義経に似ていると呼び止められると、弁慶は「強力を止め笈に目をかけ給うは盗人ぞ」と逆にいいがかりをつけ、武力をもって富樫を圧倒し押し通ってしまいます。通れたのは決して富樫の情けなどではなかったと、私は思うのです。また、「最善は聊爾を申し」と非礼を詫び酒を持参するのも、当時の宗教心厚い中世社会では当然の風習であったでしょう。
今回は、このような解釈で演じたいと思い、ワキ、ツレの人たちに、富樫像や、通り抜けたのは山伏の武力や迫力であること、当時の宗教観などを説明し、協力をお願いしました。全員殺されるかもしれないが何としても通るぞという意志と緊張感を、最後まで立衆各自に貫いていてもらいたかったのです。
今自分を振り返ってみるに、諸先輩の『安宅』の子方を経験し、高校生で初めて立衆に参加して大人の仲間入りができ、最近では父菊生の主立衆を数回、そして今回シテをやらせていただいたことは大変幸せだったと思います。長い月日をかけ、いろいろな立場で演じながら、その時その時に思ったこと、感じたことが自分の中でたくさん沈殿していることに気づかされました。『安宅』はそれらの蓄積の大切さを感じさせられた一曲でした。一つの舞台の作成に今までの経験が生かされて良かったと思います。
(平成十一年三月)
『羽衣』の「霞留」演出で発見したこと投稿日:1998-10-01
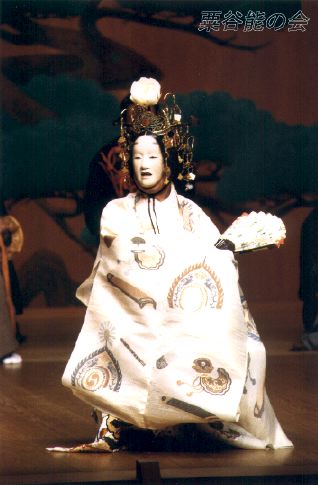
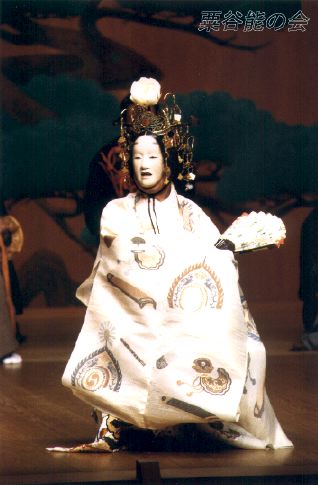
“>平成十年の「粟谷能の会」では、三月に父が.十月に私が『羽衣』を舞うことになりました。三月の『羽衣』は父の病の関係で『西行桜』を急遽変更したものです。一年に能の会で同じ演目が出るのは好ましいことではありませんが、私の方も、すでに三役の方にお願いしておりましたので、予定通り行なおうという事になりました.私は当初から「霞留」という小書(特別演出)でやってみようと思っていましたが、父が舞った数カ月後ですから、父の「舞込」と私の「霞留」の演出ではどういうところが違うのかを整理して、私なりの特徴を出してみたいと考えました。
霞留の特徴でまずわかりやすいのが、松の作り物が出ないということです。能では一般に天人が降り立つ目印となる松を象徴するように一本の松の作り物が置かれます。ところが霞留では橋掛りの一の松が作り物の代わりをして、羽衣は橋掛りの欄干に置かれ、羽衣を返してほしいという白龍とのやりとりは、天人が橋掛りに留まったまま(この部分は舞込も同じ)行われる演出です。これは天人と白龍との距離を保ち、空間的な広がりをつくる効果があると思われます。その後羽衣を返してもらうと、舞込では天人がすぐに衣を着てしまいますが、わが家の伝書の霞留では「乙女は衣を取り返し」という言葉が入るようになっていて、情景描写がていねいになされます。
白龍に所望されて舞う序の舞の笛の調子は、舞込では黄鐘なのに対して、霞留では盤渉という高い音色に変わります。また、舞込では序の舞の後に、興に乗じてあるいは名残惜しみの意味合いの破の舞という短い舞がありますが、霞留ではそれを省略し、序の舞の後、すぐにキリの仕舞所になり、地上の人間界に七つの宝を降らすという意味の扇をおとす型が入ります。
そして、舞込と霞留の一番の大きな違いといえるものは、退場の仕方だと思います。舞込では「霞にまぎれて 失せにけり」と地謡が高い調子で大合唱する中、シテ(天人)は白龍や三保の松原、愛鷹山、富士山をゆっくり見渡し、下界に未練があるような、もう少しとどまっていたいような風情を感じさせながらも、くるくると回転しながら月の世界に戻っていくように幕の内に入っていきます。一方、霞留では「残り留め」といって「霞にまぎれて」で地謡は言葉をやめ、「失せにけり」を謡わず、後は囃子方だけが演奏して余韻を楽しむような演出となっています。シテは愛鷹山を見たり、富士山を見たりと、ある程度は舞込に似た所作で舞っていますが、最後には月世界からのお達しがあった様子で、袖を翻し後を振り返りもせず、雲に乗っているかのような感じで、幕に向かってすーっと消えていきます。この辺の帰り方によって、天人の気持ちの違いが表現されるのではないでしょうか。
羽衣伝説は日本全国はもとより、世界的にも多くの地域で形を変え伝えられている伝説です。能の『羽衣』は「疑いは人間にあり、天に偽りなきものを」というセリフがあることからも、駿河の国の風土記を素材にしたものだと言われています。多くの羽衣伝説が天人と男が夫婦になり、地上に暮らして子供までもうける話になっているのに対して、能の『羽衣』の天人はその場で羽衣を返してもらい、下界の男と交わることはありません。白龍が羽衣を隠そうとしても、天人の前ではそれができず、天の崇高さを美しく表現しています。男と女の話ではなく形而上的で上品な物語にしたところが能らしいところで、『羽衣』が名曲として今も親しまれているゆえんではないでしょうか。

霞留は崇高さを際立たせる演出であるように思います。私は天人をかわいい乙女というよりは、もう少し高位で、神に近い存在として描きたいと思いました。天人というと思い浮かぶのが、宇治にある平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像の飛天光背に描かれている五十二体の雲中供養菩薩。楽器を奏でる天人、ちょっと太ったかわいい天人、そこに描かれている様々な天人像を思い起こしながら、霞留の演出による『羽衣』の天人像は阿弥陀如来のそばに居る、最も神に近い天人像ではないかと想像をめぐらせてみました。
このように、天人を崇高なものとしてとらえると、白龍との距離をとって対するところ、笛の高い調子、扇を施すところ、きっぱりとした退場の仕方など、霞留演出のいくつかの特徴に一貫性があることに気づかされます。
装束や面についても考えてみました。『羽衣』では長絹を着て小面をつけるのが喜多流の特徴で、父も緋の長絹、かわいい小面で舞いました。私は白い「舞衣」という装束に、面もあえて神聖さが出る「増」にしてみました。長絹はふわっと軽やかできれいな姿になりますが、「舞衣」はやや硬い感じでありながら、なまめかしい女性のラインが出ることが今回使ってみてわかりおもしろく感じました。白にこだわったのは、曲の中に「白衣黒衣の天人の・・・」という言葉がありますが、シテの天人はあくまでも「白衣の天人」で天上界に近いイメージにしたかったからです。
最後に一つ、今回解明できずに研究課題になったことがあります。普通、シテは頭の上に月日輪(丸い銀紙に半月をつけたようなもの)をつけますが、現在喜多流では小書がつくと「牡丹の花をいただく」ようにします。小書になるとなぜ牡丹なのか、天人と牡丹は関係があるのだろうか。私は今回牡丹をやめて、宗教的な意味合いも含んでいる白蓮華にしてみました。他流でも鳳凰や白蓮華にしているところがありますが、鳳凰の方は、「挿頭の花もしをしをと」という天人五衰(天人の五種の衰相)の一つ、花がしおれる描写がありますので、適当ではないと考えました。しかしこれはまだ研究の余地があると思っています。
今回「霞留」演出で、父と少し違った『羽衣』を求める中で、多くの発見があり、能の奥深さを改めて感じさせられました。
参考資料 雲中供養菩薩(平等院発行)
『柏崎』における重層性投稿日:1998-06-27

六月の研究公演で『柏崎』を取り上げました。息子の尚生に子方としてふさわしい内容を年齢に合わせてやらせてやるのが、この世界で生きる親の責務であるという想いもあって、今回は
子方が登場するもので、自分としても挑戦しておきたいものを選ぶことにしました。
『柏崎』では、訴訟のために鎌倉に滞在していた柏崎の某が風邪のために亡くなると、同行していた息子の花若御前が遁世してしまいます。妻はその知らせに嘆き悲しみますが、やがて我が子の安穏を祈る気持ちになります。しかし後半には、妻は悲しみのあまり物狂いになって登場します。妻であり母であるシテのこの早い心の動きを演者がどのように納得して演技できるかが問題です。能では、内面の心のエネルギーが抑えた動きの中から外に出ていくことを重要視します。従って内面の心の動きを理解して演じることは、動きの少ないものほど要求されるのです。シテの心を理解するには、シテの女性像をつかむことや『柏崎』の中のいくつかの疑問を解決する必要がありました。シテの女性像・母親像はどんなものでしょうか。息子の遁世を冷静に受け止める凛とした女性、宗教心が篤く教養の高かった女性、しかし我が子や夫を思う愛情豊かな女性でもあった・・・でしょう。
自分の息子を前に舞台稽古をしていると、この子はなぜ母親に会おうともせず出家してしまうのかという疑問がわいてきました。今の一般の常識では父親が亡くなったら、息子は急ぎ郷里に帰り、母を助け、父の代わりに城主として、その地を守っていくのが筋だろうと思うのですが、『柏崎』の息子は母に一度も会おうとしないで出家してしまいます。これはどういうことだろうか。このことを理解するには当時の宗教的な背景を知らなければなりません。
浄土思想に、出家は自分自身だけでなく、周りの人をも救うことになるという考え方があることを知りました。つまり自分が出家して厳しい修行をすれば、父親も極楽往生し、母の来世も約束される、家臣や柏崎の人たちも救われるという考え方です。これで子の出家の意味が理解できました。
しかしこれを解決しても「テーマは何か」という疑問が残りました。『柏崎』は一見、子別れ・再会の曲のように見せながら、メインは物狂いとなった妻が、夫への愛や恋慕と、極楽浄土や善光寺信仰への礼賛といった深い宗教性を込めて謡い舞っていくところではないだろうか。極楽のすばらしさをいうために、人間の悲しさを表し、その上で来世での再会を願うというのがテーマだったのではないか。
『柏崎』は古作(榎並左衛門五郎の作)を世阿弥が手を入れ完成させたものであるという説が有力です。左衛門五郎が作った段階では、善光寺を讃える当時の流行歌を題材にし、曲舞に仕立てた単純なものだったのでしょう。これでは戯曲として面白味や起承転結がないので、世阿弥が母子再会の話をつけ加え、形を整えたといわれています。子の説のとおり、子別れ・再会のテーマは付け足しで、曲舞のきらびやかとも言えるほど宗教的な言葉がちりばめられている部分がメインにふさわしいところだと感じさせられます。今では難しい言葉に聞こえるものも、当時の善光寺信仰に篤い人たちにとっては心地よい言葉の嵐だったのでしょう。
世阿弥の時代には興行的に成功させるために、宗教的なPRの意味合いが強い能もつくられていました。『柏崎』もその傾向をもった能といえるでしょう。ただ、信仰を讃えるにとどまらず、社会風刺的な彩りも加えています。たとえば、妻が善光寺の内陣に入ろうとしたとき、住僧に女人は入ってはならないと制止される場面で「仏がそう仰るのか」とすごみ、女性差別に切り込むところがありますが、庶民はそうだそうだと喝采したのではないでしょうか。
夫への恋慕の情も強く表現されています。夫の形見の長絹をまとい烏帽子をつけて、亡き夫は弓も歌も舞も上手で、立ち姿も美しかったと、一種ののろけともとれる謡い舞いぶりを見せ、曲舞の最後は夫との来世での再会の願いでくくられています。
一般の芝居では、特に落語がそうですが、最後のオチが重視されます。しかし、能ではときに最後の結びの部分(『柏崎』では子供との再会)はさほど重要ではなく、もちろん一つの見せ場には違いありませんが途中の舞や謡など、見せどころ聞かせどころを幾重にも作って楽しんでもらおうとする曲目があります。これは能の持っている特徴でしょう。私は『柏崎』もそういう種類の曲であり、重層性をもった能であると思うのです。ただ、最後に小さい子方が出ることによって、それまでの難しい宗教性などを一時忘れ、母子再会というハッピーエンドにわいて、安堵して帰っていただくという効果があるようで、世阿弥はそれをねらってたかもしれません。
これが、私なりに納得出来るものとして出した結論です。今回、自分の中にある疑問を解決することで、『柏崎』という作品を知り、その演技にも集中出来たように思います。
また現在『柏崎』の演出方法として「中の舞」を省略する形が一般的になっています。初期の能では、夫を思いだしてのろける件の後に舞がありました。扇を差し出し「鳴るは滝の水」と謡うのですから、その後は、当時の流行歌に合わせて謡え踊れとなるのが普通です。
『翁』や『安宅』でもこの言葉が来た後には舞が続いています。それが現在の『柏崎』には舞がなく、いきなり「それ一念称名の声・・・」と宗教的なことばが連なっていくのですから、世阿弥のころの人が観たら物足りないに違いありません。
それで今回、舞入りで演じてみたいとも考えましたが、『柏崎』自体が大曲であること、そして初めて取り組むことなので断念しました。しかし、次回演じる機会があったら、ぜひ舞入りを加え、世阿弥本に「ヲカシ(狂言)女物狂ガ来ルト云ウベシ」とあるように、間狂言等も入れて特別演出で演じてみたいと思っています。
「砧」を演じて─演出方法を考察する─投稿日:1998-02-01

父が正月一日に倒れ、一月三日の『月宮殿』、二月十二日の『砧』を私が代演することになりました。『砧』は大曲で、五十歳近くなってからでないと演じられないと思っていましたが、代演ということでやらせていただくことになりました。
『砧』を演じるにあたって、父からアドバイスも聞き、喜多流に伝わる伝書通りに臨んだのですが、演じなから、この演出方法では見ている人がわかりづらいのではと感じるところがありました。
まず気になったのが最初の場面です。喜多流の台本では、夕霧という女(ツレ)が登場して、芦屋の某(ワキ)の使いで、奥様のいる芦屋に向かうところである。某殿は訴訟のことがあって、三年あまり在京しているが、古里のことを心もとなく思われて使いにいけというので急ぎでやって来たという説明をしますが、他の流儀では、最初に芦屋の某自身が登場して、上京している事情を説明し、古里が心もとない、この年の暮れには必ず帰るから、そのことをよく心得て伝えるようにと夕霧に伝える場面から始まります。私は喜多流の台本ではあまりにもそっけなくて、夫(芦屋の某)の心情が理解されないのではないか、その後の妻の恋慕の情へとつながっていかないのではないかと思うのです。
世阿弥は『砧』について、「かやうの能の味はひは末の世に知る人あるまじ」と嘆いていると『申楽談儀』にあります。世阿弥がそれほどに深い味わいを込めてつくった曲ならば、単に帰らぬ夫への妻の恨みつらみの情念を際立たせて終わりといったものではないはずです。
夫は妻に愛情を持ちながらもどうしても帰れないという苦渋に満ちた立場にあり、妻の方も夫を思い、恋慕しつつ帰りを待っているという、お互いの愛情が底流にあることが感じられないといけないと思います。それがあるからこそ、孤閨をかこつ妻が、恨みつらみにさいなまされながらも、時には夫との思い出に浸り、帰って来てくれるならいつまでも添い遂げようというやさしい気持ちにもなり、最後には絶望の淵に落ちていくのです。こういう感情が織物の綾のように幾重にも交錯して深い味わいをかもし出していくのだと思います。
こう考えると、夫の愛情をどこかで表現しておきたいということになりますが、喜多流の台本では、最初に夕霧が帰れぬ事情を説明するだけで、そこには夫の妻への思いやりをほとんど感じることができません。夫の登場は、妻が絶望のあまり空しくなって(亡くなって)からです。夫は妻を弔うことはしますが、最初の伏線がないだけに、それは通り一ぺんの印象をぬぐえないのではないでしょうか。
世阿弥が「かやうの能の味はひ…」と述べるほどに、夫婦の愛情をベースに、それ故に地獄まで落ちるところを名文で謡い上げている『砧』。世阿弥自身が書いた曲のなかでとりわけ気にいっていた『砧』。しかし、世阿弥の危惧通り、しばらく演能されることはなく、江戸時代になってようやく復曲しています。その折に各流派が演出を考え、喜多流にも現在のような台本と演出方法が伝えられているわけです。今回私は『砧』を演じながら、この江戸時代の演出方法は、『砧』のテーマからしてやや説明不足ではないかと感じています。他流のように、最初に夫を登場させて気持ちを述べさせる場面が必要ではないでしょうか。
そして、『砧』では砧を打つことが重要なモチーフになっていますが、シテは妻がどんな気持ちで打っているかを感じながら演じなければならないと思います。蘇武の故事に自分の心境を重ね合わせて砧を打つことになったとはいえ、夫に柔らかい着物を着せてあげたいというやさしい心情があってのことでしょう。そこを伝えるには砧を強く打ってはならないのだと思います。世阿弥も「ほろほろ、はらはらと」と音楽的な響きで書き込んでいるところですから、柔らかく美しく響かせねばならないと思います。
夕霧が芦屋の某の妻に、殿は今年も帰れないと伝える場面の演出方法も気になります。その言葉を聞いて、妻は夫の心はやはり変わり果てていたのだと絶望し、病の床に沈み、やがて空しくなってしまうのですから、夕霧と砧を打ちながら、疑いと信頼との間を行きつ戻りつつしていた妻の心を切り裂く重要なひとことであり、時間的にも空間的にも場面転換があるべきところです。そこが、ただ夕霧が、今までと変わらぬその場で向きを直して伝えるだけの味気ない演出になっています。芦屋の某から使いが来るなどの説明描写は必要ないとしても、この大事な場面を鮮明に印象づけるために、動きと同時に言葉にも注意を払い、他の演出方法を検討してみたいと思っています。
私はこの頃、演出方法はこれでいいのかと考えることが多くなりました。以前は、謡の文句を覚え、上手に謡うこと、きれいに舞うことが関心の中心でしたが、この頃は、この能は何を言いたいかということを考えなければいけないし、そうでなければ深い味わいまで表現できないと感じるようになってきました。現在に生きる能を創造するものとして、伝統というワクの中の限界ギリギリのところまで、演出方法について考察し、ときには思い切って変えていく必要があるのだろうと思います。
今回、『砧』を喜多流のしきたりからすれば、年齢的に早く演じさせていただきました。演じてみたからこそ、ここに書いたようなことを感じることができ、次に演じるときはこうしてみたいという思いが広がってきたのです。大曲や老女ものは、ある年齢になってから初めて演じることを許されるという習慣は悪くはありませんが、早い時期に演じ、その後何回も試行錯誤しながらいい味に仕上げていくということも必要ではないでしょうか。思わぬ代演ということで『砧』という大曲に挑ませていただき、感じることが多く、意義あることだったと思っています。