「能の力強さ」
粟谷 明生
今年の自演会は一年ぶりに能が出せる。喜ばしいことだ。
曲目は『経政』に決まり、シテを勤める高山啓君は阪大喜多会の存亡の危機を乗り越える原動力となった人物でもあるから、通常より一年早い能の体験となるが、これもご褒美と思って、部員は一丸となって自演会に向けて頑張って稽古してくれるだろう。
能『経政』は小品だが、よくまとまっている曲である。
クセはしっとりした風情で特徴あるよい型がつづき、キリは修羅道に苦しむ有様を舞い、自ら灯火を吹き消して消えていく。
キリの仕舞は学生諸君のように若く力があり余っていると、つい荒くなりがちだ。これを若さゆえ仕方のないこと、と諦めてもいいが、本来の能の力強さを是非知ってもらいたいと思い、このことを邯鄲への寄稿とさせていただくことにする。
私は子どものころから稽古を受けると必ず、「強く!力強く!」「気合を入れて!」と注意を受けてきた。そのときは「はい!」とうなずきながらも、実はその真意を全くといっていいほど理解していなかった。
「強く」は、ともすると若いときは「荒く」とか「激しく」というイメージで捉え、錯覚しがちだが、決してそうではない。
「乱暴」「粗雑」とは無縁な、もっと内面的なものを言う。
つまり力強さは表面的なうわべの力ではないのだ。
では「強さ」とか「気合」とは一体何だろうか?
私は演者の身体の内側に溜める気の充満と発散の作業だと思う。それは内圧と外圧、動と静、みな相反する力関係から生じるものだ。
演じるという思いを凝縮して、それを秘めながら、その思いを表現するところにエネルギーが生み出される。
例えば、息には出る息と引く息があって、引く力を備えることで、より出る力が生まれる、と解釈している。
舞も同じで、動きの激しい曲目の場合はなおさらのこと、引き込む力がないと演者の生の部分が露骨に出て、動きに制動が利かない舞となってしまう。すると、「荒いよ」と注意が飛ぶのだ。それを克服するには自分の身体に、出て行く力と引き込む力の両方を持ち合わせること、それが肝心だ。
例えば、「身を焼く苦患恥ずかしや」と面を隠す型がある。左足を引き右手を顔の横に当てる型だが、それだけの動きではいけない。「あ?なんて己の姿は恥ずかしい、行慶僧都に顔を見せられない」と思いながらワキ座前まで勢いよく進み、すっと扇を顔に当て恥ずかしいと顔を隠す、その思いが内に強くあると美しい説得力のある型となる。
能の作品が持つ力に、頼り委ねるだけではなく、作品と役者の二つの力で力強く表現する。それが能の力強さ! 私自身も己にこう言い聞かせながら能を勤めるように心がけている。
観る側も、演者がそれらを備えているかどうかに注目して観ると、能の真髄が見え隠れして面白いかもしれない。
平成19年 6月 記

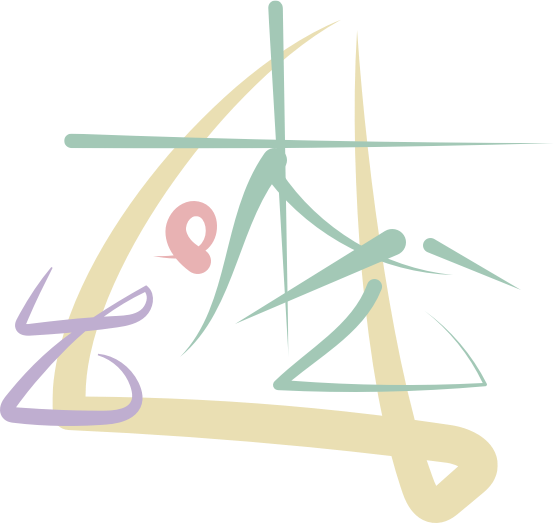

コメントは停止中です。