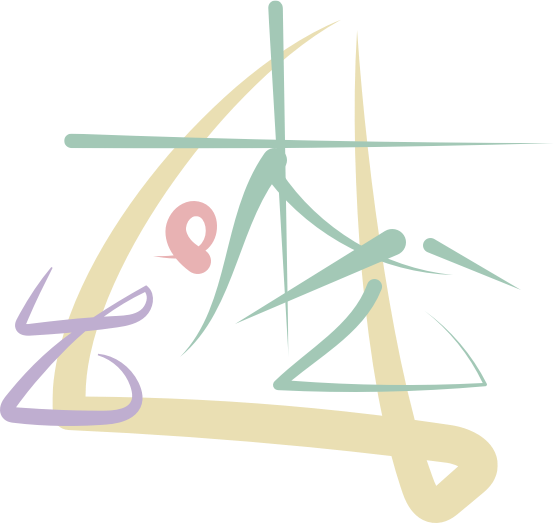『黒塚』の白頭について
粟谷明生
「ひたち能と狂言の会」(平成18年9月2日)で『黒塚』を「白頭」の小書で勤めました。
『黒塚』は私がこの道を一生の仕事と心に決めるきっかけとなった曲です。
今までに粟谷能の会で2回、国立学生能で1回、粟谷能の会福岡公演では、前シテを父の代演で勤めました。後シテを「白頭」で勤めたことはなく、今回初めての体験となりました。
喜多流の謡本の曲趣には「この貧しい女性は鬼女の化身であるが、初めは邪念も害意も示さず、月光のもとに生死輪廻を嘆くが、中入になり閨の内を覗くなというところから、鬼気のたちまち迫り来るものを感じさせる」とあります。
しかし、私は正直このような気持ちでは演じたくないと思っています。「閨の内を覗くなというところ」あたりは、まだ鬼になっていない、少なくとも前シテの段階では鬼ではないと考えて演じています。
安達ヶ原の女は元来の鬼ではありません、中年女性の独り身の寂しさが大きな背景になっています。昔覚えた都の流行歌を口ずさみながら、ひとり糸を繰りながらどうにかして生きていかなければならない惨苦を謡います。そして次第に窮地へと追い詰められていき、人肉を食らうという冒してはならない罪を冒した浅ましい鬼女の姿となるのです。(安達ケ原の女の身の上については、陸奥の安達ケ原に伝わる鬼婆の伝説によってうかがい知ることができます。演能レポート「『黒塚』の鬼女をどう表現するか」参照。)
禁じられた事は、一度破ると、もう後戻り出来ません。歯止めが利かなくなった人間の弱さが見え隠れして、人間とはなんであろうか、と自問自答したくなります。
いつかはやめよう! もうしないと思いながらも、また繰り返してしまう人間の性。
女は今度こそは、と修験者の山伏祐慶の仏の救いにすがろうとします。
やり直したい、それを手助けしてくれそうな山伏だからこそ、寒さを凌ぐために暖をとってあげよう、と親切心で夜の山に薪を取りに出かけます。
そこには、女のいじらしい反省と償いの気持ちがあります。
しかし、女はつい余計な一言を漏らしてしまいます。
「閨はみないで欲しい」と。
山伏はそんなことはしない、「言語道断」と言葉をはねのけ約束を守りますが、付添人の能力(アイ)にはそれが通用しません。その掟は破られます。
中入前に山伏に再度念を押して、山に出かける女は、橋掛で上を見上げ、裾をとり、ずかずかと切る足で運び幕に入りますが、私はそこで女が鬼になり、「さあ、いい獲物が来たぞ」とは思いたくなく、そうは演じていないつもりです。
夜の山道という危険をも恐れず、ただただ暖をとってあげようとして薪を拾いに行く、けなげな感じを出したいのです。そう解釈したいのです。
もっとも演者がどう言おうと、どう見るかは鑑賞者の自由ですが。
女が鬼に変わるのは、能力が掟を破り、閨の内を覗いたときと考えています。
私は楽屋で着替えながら、アイが閨の内をみて、「ぎゃあ、かなしや、かなしや」と叫ぶときに、「見たな」と鬼へと気持ちを変身させています。
面をつけるのが丁度そのときになるのが一番と、そのように私は思っています。これは楽屋の裏話のひとこまです。
今回、後シテの鬼女の扮装を白頭に般若、鬱金地立枠模様の厚板唐織を肩脱ぎで勤めました。
鬼女の姿も髪には、鬘掴みだし、黒頭、赤頭、白頭と4種あり、装束は紅有でも紅無でもよく、付け方も腰巻裳着胴(もぎどう)、着流肩脱ぎとバリエーションは豊富です。
(以前の演能レポート「黒塚」で過去の出で立ちを写真でご覧下さい。)
どれを選ぶかは演者の自由であり、演出に委ねられています。今回選択した「白頭」になると、面は「般若」、柴の持ち方(後に説明)も抱き柴となり、ただ恐ろしい鬼畜というより、鬼にならざるを得なかった女の悲しい定め、それを背負った女がより表現されるように思います。
以前から白頭で気になることがありました。それは白い毛と般若の面の彩色、つまり毛書きや顔色とのバランスがどうもぴったりしないこと。所持している白頭と般若の面、この二つを仕方なく合わせているからなのか、そんなことも考えていないからなのか、疑問を感じていました。
白頭なら、それに似合う般若がないだろうか。我が家にはない「白般若」みたいなものを付けたいと考えていました。
今回、面打師・石原良子氏の愛弟子たちの面の展示会「幻」で見つけた、やや白色の強い般若が白頭に似合うのではと思い、石原氏に相談し、打たれた土屋宏夫氏のご許可をいただき拝借し勤めました。
後の出は、女が怒り、逃げる山伏を、山から駆け下りて追いかける様を表現します。出囃子は「早笛」と「出端」の二通りがありますが、今回私は早笛で出ることにして、観世流の小書「急進之出」で演じました。
手掛ですぐに幕をあけ、三の松までするっと出て、逃げる山伏を捜している型をして、見つけると一端シサリ、幕に戻ります。この時一度幕を下ろすときもあれば、そのままもあるようですが、この度は下げずに太鼓の刻みで素早くまっしぐらに山伏目掛けて走り出し、「いかに旅人」と謡いかけました。
私としては、あの安達ヶ原の女が後半鬼女になるには、鬘の「掴みだし」か「黒頭」が似合う、早笛よりはむずかしいですが出端で登場する方が効果的だと思っています。しかし、毎回、同じ演出では観客にもあきられる、役者自身の鮮度も落ちる、興業主としての演出を考えたとき、今回のような選択となりました。
また、後シテの出のとき、山伏のために拾い集めてきた薪の持ち方も小書がない場合、ある場合で違いがあります。
通常は「負い芝(おいしば)」といい、薪を肩にかけます。
小書の時は「抱き芝(だきしば)」といって薪に自ら着ていた装束を巻きつけ左手に抱くように持って出ます。抱き芝のほうが女の薪にたいする思いみたいなものが表れているのではないでしょうか。私は抱き芝がいい演出だと思います。
「祈り」も演出を替えてみました。初段のあと、『道成寺』の鱗落しといわれるところで、通常打たない金春流の替え手を打ってもらい、そこで一度止まり、じっくり振り返り山伏を睨みます。そしてなかなか捨てられなかった薪ですが、遂に心の糸は切れて折角の薪を放り投げる型を入れました。もうここからあとは人食い鬼女そのものということでしょうか。
今回いろいろな注文に快くお相手していただいた囃子方(槻宅 聡・観世新九郎・亀井広忠・大川典良 敬称略)の皆様に深く感謝しています。
ひたち公演は私の責任で引き受けた興業です。受けたからには成功させたい。
曲目の選曲も私の考えで、粟谷能夫も『花月』を快く承知してくれました。
能楽師は自分の未経験の曲、それも中々出来ない曲をここぞとばかり取り出して演じたいものです。しかし、お客様に「ああ、楽しめた」と素直に喜んでいただいてこそ、公演の成功となると思い、選曲しました。そしてそれぞれが工夫を凝らして演じてみました。
今回試みた『花月』の弓矢を持っている謂われを説明する言葉の挿入や、『黒塚』の「急進之出」のようなものは喜多流にはありません。「ないのになぜ演る」と先人たちからのお説教の声や喜多流愛好家からの質問が聞こえてきそうですが、喜多流自主公演ならば、規律も守る必要がりますが、私的な会や地方公演で、よりサービスする演出もあっていいと思います。
昔、『道成寺』を替装束でなさった方がいらして、同輩から「あの替装束は喜多流にあるのか」と皮肉っぽく聞かれたそうです。すると、その方は「ない、しかし能にはある」と答えられたとか。私はこの言葉に能役者の精神のすべてが含まれていると思い気に入っています。流儀の決まりを蔑ろにするつもりはありませんが、その殻を後生大事に守ることだけが芸能の本質とは思えないのです。
「しかし能にはある」は、これからの私の演能活動の根幹となる言葉、そう信じて邁進したいと心新たにしています。
(平成18年9月記)