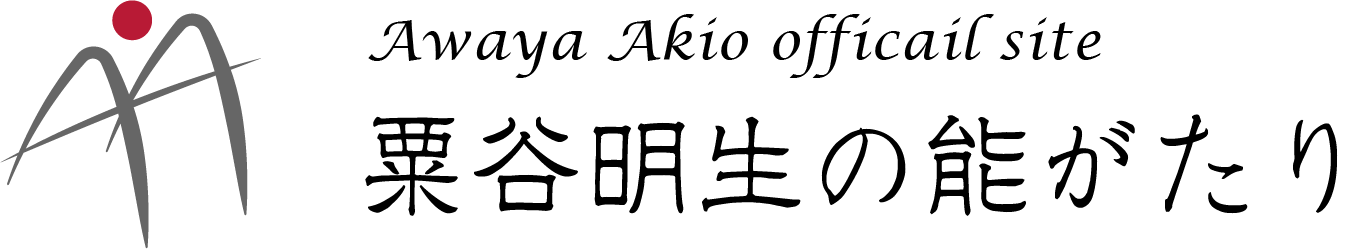粟谷菊生氏が語る、次男・菊生投稿日:2018-06-07
今回のちょっと一言は以前、国立能楽堂のパンフレットに記載された「西哲生の【聞書き】近代能楽私史◎巻之二十二、粟谷菊生氏が語る、次男・菊生」に少し手を入れまして、ご紹介することにいたします。(平成15年10月31日)
粟谷家と広島
私ども粟谷の家は、もともと和歌山の出身です。浅野家が紀伊から広島藩主として安芸へ移ったとき、ついて行ったようです。広島に粟谷家の墓地があり、その寺も原爆で焼かれてしまいましたが、墓には「茶屋新三郎」と曽祖父の名が書いてあったのを覚えています。なぜ粟谷姓に変わったのかはわかりませんが、もとは茶屋姓だったのです。粟谷家
父の益二郎は、本籍名では益次郎となっており、一人っ子でした。父は、子供たち全員に能をやらせるのは危うい、菊生は愛敬者だから養子にだしたほうがいいと親類から言われたそうですが、番組に粟谷の名前を沢山書きたかったのでしょうか、4人ともにこの道に進ませたのです。
私の名は、大正天皇の天長節の日に生まれたので、菊生と喜多実先生がつけて下さいました。ちょうど本日で満八十一歳となりました。兄は、祖父・新三郎、先代喜多六平太先生、父・益二郎の三人から一字ずつとって、六平太先生が新太郎とつけて下さいました。弟の辰三は辰年生まれの三番目で辰三、末弟の幸雄は時の総理大臣、浜口雄幸の雄幸を引っくり返して幸雄。子供の命名も、下に行くほど、雑になってきますね。
いま東京では私と辰三、それに、それぞれの子供たちと、兄新太郎の息子の能夫とでやっていますが、幸雄は福岡にいます。九州には喜多流の地盤があるのだからと、喜多実先生の命令で、幸雄が派遣されたのです。
兄弟仲のよいこと
子どものころの思い出と言われると、お膳が丸かったことを思い出します。食事の時、すき焼の鍋がお膳の真ん中に置かれる、家族の誰からも鍋までは等距離だったわけですね。兄は春菊の下にこっそり肉を隠すことがあり、私はそれを見つけては素早く奪い取る。こんな状況でしたから、すき焼の肉をよく煮えてから食べた経験は少なかったです(笑)。子どものころはよく兄弟喧嘩をしました。しかし長男の兄には、一家の中で権力をもっていた昔気質の祖母がついていましたから、兄に勝つには容易なことではありませんでした。次男は長男の三倍の努力を、弟子家は宗家の三倍の努力を、つまり私は九倍の努力をしなければならないのだ、と私なりの持論はこのころからはじまったとも言えるかもしれません。
粟谷の家は仲がいいとよく言われます。「その秘訣は」と皆さんから聞かれます。「本当に仲がいいはずなかろう」と言う人もあります。父は六十六歳で亡くなりましたが、私たちはまず兄をたてて粟谷家の団結を図りました。マネージメントは、次男の私がやっておりました。よそから粟谷へと頼まれた能は、兄へ持っていきます。
2人ともがスターを目ざせば、なかなかうまくはいきません。そこで、ずうっと兄をたててきたのです。五十歳を過ぎてからは、私の余生もいつまで続くかわからないのですから、粟谷家に能をと頼まれれば、兄ですか、私ですか、どちらをお名ざしですか、と伺うことにしました。今は、すべて甥の能夫と息子の明生にまかせていますが。
小袖曽我、右父・粟谷益二郎、左・正木亀三郎
父は明治三十五年に広島から上京し、先代六平太先生に師事しました。広島の饒津神社の神能で舞った父を六平太先生がご覧になり、スカウトされたのです。先生と父とのつながりは、単に師弟というだけではなかったようです。父は先生を親と思っていたのでしょう。父が『烏頭』の演能中に舞台で倒れ、亡くなったとき、六平太先生は父の棺の前で、「オイラもお前のように舞台で死にたい」と言われ、そして父に向かい、「バカな息子たちはオイラが引きうけた」とおっしゃって下さいました。
父は六平太先生のハードな稽古をうけて、理屈ではない、いわゆる職人芸の人でした。先生の能の地頭をよく勤めていました。美声で、豊麗な謡でした。喜多実先生が、父の地謡について、「『鷺』の初同、『枕慈童』の初同は、粟谷さんでなくては謡えない」と言っておられました。どちらも巧まない、すんなりと謡うものなのです。私も子供心に、それを参考にしようと思ったものです。そして、同じ『湯谷』のシテでも六平太先生のは妖艶であり、父のは可憐な『湯谷』であったと思います。私がいつも濃艶な「万媚」よりも可憐な「小面」を用いるのは父親ゆずりの好みでしょうか。父は容姿がととのっていて、淡々と舞う人でした。
全国を回り、作ってくれた地盤は、のちに兄や私が手分けして引き受けることになったのですが、回り切れないほどでした。父は若いころ、『桜川』の能を茶色の水衣で舞わされたといいます。六平太先生のお考えは、長い旅で、着る物もよごれたから、ということでしょうが。しかし、そのとき以来、父は自分で装束を作らねばと考えたようです。今日の粟谷家の装束は父の思いから始まり、そのお蔭で一応装束はそこそこ間に合うようになってきました。
家の面・装束
兄は装束を集めるのが好きで、また面の収集が道楽でした。新しい面を手に入れると、それをかけて、そのまま寝てしまったりするものですから、いつでしたか、知らずに外出から帰った姉がそれを見て仰天したことがありました。私は面・装束は作り集めません。弟の私が作り始めたら、やがて争いになると思ったからです。分家というものは、本家に頭を下げて面・装束を出して下さいと頼むのです。それをこちらで持ってしまうと必ず争いが生じます。現在は粟谷装束保存会があって、新調したり修繕したりしています。
私の師
私は初め父に習い、通いの内弟子として喜多実先生に師事しました。後に六平太学校に入りますが、実先生は、「一所懸命弟子をこしらえあげると、オヤジが持っていってしまう」と嘆いておられたものです。六平太学校の一番の先輩は故友枝喜久夫先輩、若いほうでは孫の喜多長世(現六平太)さん、故節世さん、そして私は先生のお稽古に間に合った最後の弟子といえましょう。兄も私も、友枝喜久夫先輩には謡をずいぶん教わりました。友枝さんと兄との仲は、他人には計りしれないものがありました。
十四世喜多六平太先生
先代六平太先生が鮮やかな能を舞っておられるときは、私はまだ子どもでした。先生は百歳近くまで生きておられた方ですから、舞台で舞われなくなってからが長いのです。先生はとくに小柄な方でしたから、座高の高い私は、ツレのお相手はあま
していません。先生のツレは、もっぱら友枝先生と兄でした。釣りのお好きな六平太先生のために、弟子たちの釣りの当番がありました。先生は、釣りに興味のない私を眠らせまいと色々と芸の話をして下さいました。私は『小鍛冶』の白頭を舞ったあとすぐ軍隊に入りましたが、先生は「菊坊が戦争に行くようでは日本は負ける」と言われました。実際そのとおりになりましたね。
六平太先生は、ご自身が舞えなくなってから、やってみたい型を私どもにやらせてご覧にりました。私の『山姥』について、お前のは山ウバでなくて山ジジイだと言われたことがあります。兄が『玉井』に、いい面を手に入れかけたときのことです。「面が違うよ」と言われ、「龍神だから黒髭でなければ」とおっしゃるのです。私が「先生、白頭でございますよ、黒髭ではおかしくはございませんか」と申し上げると、「昔、オツムは白くてもヒゲの黒い人はいたよ」と言われる。また『小督』では、小督局は二階から月を見ているのだからツレは床几にかけろなどと言われます。私が「当時、二階家はなかったと思いますが」と申し上げると、先生は「五重塔があるだろう」と、万事こんな調子でした。先生が難題ばかり言われるものですから、『雷電』ではありませんが、先生が「弘徽殿」におられると皆は「清涼殿」へと逃げてしまう有様でした。
先生は番組の作り方にも厳しく、呼掛けが三番ついたり、僧脇が三つついたりすると叱られました。そういえば、私が先生をやりこめたこともあります。『蟻通』『蝉丸』『融』が出たとき、「まことに申し訳ございません、三番とも、ついてしまいました」と私がお詫びに行きますと、先生は何がついたのかお気づきになりません。そこで申し上げました。「全部、虫がついております」と。
老女物を演じる
『卒都婆小町』を勤めたときは、まだ色気のある『湯谷』『松風』等をやりたかったのですが、甥の能夫から、ぜひと言われ決心しました。そこで、世の中のお婆さんを観察し始めたのです。新宿駅の階段で、ため息ついて休息している老女を見て、これを使おうと思い、幕を出て左へ歩み、柱に手をかけて休息する型をやりました。
『伯母捨』のときは、喜多流では百八十年も演じられていないのですから、何も判りません。それでまずは掘り起こしに没頭しました。演能までの二年間、実に様々な方々からあたたかい御支援をうけました。特に故観世銕之亟さん、そして栄夫さんは、装束のことにいたるまで親身になって力を貸して下さいました。野村萬さんが、「老女物は誰でもよく見えるから大丈夫だよ・・・・」と言って励ましてくれましたが、とにかくあの時は命がけとは言いたくありませんが、一所懸命でした。朧月という型を考えていたとき、ふと心に浮かんだのは、昔見た、橋岡久太郎氏の寂しく立ちつくす『姨捨』の一枚の写真だったのです。四拍子、ワキ、アイの皆さんにも本当に感謝していますよ。
次代へ伝える
六平太先生、実先生、後藤得三先生、友枝喜久夫先生、そして兄、という先人に私は恵まれました。先人に教えられたことを、私は友枝昭世さんたちの次の世代に伝えれば、芸は伝わってゆくと思います。口で言うだけでなく、舞台で一緒に謡い、一緒に舞う、それが伝えることだと信じています。だからこそ現場で、一日でも長く働いていたい、そう思う今日このごろです。
銕之亟さんを偲ぶ投稿日:2018-06-07
銕之亟さんを偲ぶ
粟谷菊生
榮夫さんが喜多にいられた頃、初めて能がヨーロッパ公演を行った時を機に、静夫(八世銕之亟)さんと親しくなって以来、ずーっと頼れる友達であった。?能楽座を立ちあげるときも、静夫さんから話があって加わった。
青年時代と変わる事なくいつも能のことを考え、話し合う人だった。
彼には能の一曲一曲について教わることが多かったし、彼も私の意見を求めに来た。そんなときはいつしか二人とも興奮してくるのを禁じ得ず、情熱的に話し合ったことは大切な思い出である。
亡くなる四年ほど前に、平泉の中尊寺で「大原御幸」を舞うことになったが、菊生さんに後白河法皇をやってもらいたい、という。私のようなごついのがやったら貴方の邪魔をする、といったら、「後白河法皇っていうのは大もので悪い奴なんだよ だから似合っている」という。「悪い奴なんだ」と何度も繰り返すその言い方がえらく気に入って承知してしまった。心に残る舞台だった。喜多流の初同のところを、喜多流と違ってシテとツレが三人で謡うところはとても綺麗だった。そのほか思い出す舞台はいろいろあるが、式能を目黒の喜多能楽堂でやったときに舞われた「采女」で、中入りのところで何ともなく後ずさったのが心に染みた。また能楽座の一九九九年の自主公演のときに、私のシテ、榮夫さんのツレ、銕之亟さんの地頭で「通小町」を演じた。本当によい地頭だった。これが能楽座自主公演の最後だったかもしれない。
神楽坂投稿日:2018-06-07
神楽坂
粟谷菊生
 最近子どもの頃住んでいた神楽坂に行く機会があった。坂を上がりながら左右の商店の変貌に驚き、「この路地の奥には◯◯という店があったんだ」などと同行の妻に説明しながら独り遠い昔の思い出に浸っていたが、そのうちに「あった!あった!」むかし懐かし、老舗の履物屋の「助六」が…。父益二郎がいつも下駄を買っていたあの「助六」。平素、白足袋で通していた父はウナギと言って裏が白ネルになっている鼻緒の下駄を愛用していた。さすが神楽坂、気の利いた鼻緒の男物の下駄がある。デパートや他所では見つからないという妻の言葉に、早速買ってしまった。因みに僕は銀座の阿波屋で草履を注文しているのだが、或るお弟子さんが僕にプレゼントして下さろうと阿波屋に行って「マムシでお願いします」と言ってしまったそうな。お店の人、吃驚仰天。
最近子どもの頃住んでいた神楽坂に行く機会があった。坂を上がりながら左右の商店の変貌に驚き、「この路地の奥には◯◯という店があったんだ」などと同行の妻に説明しながら独り遠い昔の思い出に浸っていたが、そのうちに「あった!あった!」むかし懐かし、老舗の履物屋の「助六」が…。父益二郎がいつも下駄を買っていたあの「助六」。平素、白足袋で通していた父はウナギと言って裏が白ネルになっている鼻緒の下駄を愛用していた。さすが神楽坂、気の利いた鼻緒の男物の下駄がある。デパートや他所では見つからないという妻の言葉に、早速買ってしまった。因みに僕は銀座の阿波屋で草履を注文しているのだが、或るお弟子さんが僕にプレゼントして下さろうと阿波屋に行って「マムシでお願いします」と言ってしまったそうな。お店の人、吃驚仰天。
脳梗塞や半年前の思わぬ転倒で足の弱った僕は底の滑らかな皮草履は滑りそうで履けなくなってしまっている。特別の時以外は不本意ながら底裏がゴムで凸凹になっている安っぽい草履を履いている。下駄もエスカレーターに乗る時、怖い目にあったことがあるので、折角買った下駄だが少々の雨だったら履き慣れたゴムの裏の草履にしてしまう。もう見栄も恰好も構っちゃあいられない。老醜と言う言葉があるが、加齢はやっぱり美から遠ざかるようだ。一心同体とは決して決して言わないが、長年連れ添った女房殿、僕の思いは手に取るように判るらしく、「老いの浪の、上にて舞はむ、足弱の、おぼつかなくも、こらえ、こらえて」と戯れ歌を詠んでくれた。
喜多流の自主公演は一昨年(平成十四年)十二月で引退し、大阪は今年(十六年)六月に『鬼界島』で幕引きとし、この秋十月に粟谷能の会も『景清』で舞い納めとした。僕の元気なうちに息子や甥に大曲を舞はせて、その地を謡いたいと謡を謡うことの大好きな僕は、今張り切っている。
長命の喜びにはウラがある。喜びのウラは哀しみで、深みも判る反面、淋しさも味わわされる。これは誰もが味わっていることで、別に僕だけではない…などと、ちょっとしんみりしているかと思うと、来年の仕事の依頼が次々に入り、手帳のスケジュール欄がどんどん埋まっていくのは、もう少し生かしておこうという神様の思し召しかな、と相変わらずの能天気でもある。
景清で 舞い納めとす 胸の内
めでたくもあり めでたくもなし
10月30日
『景清』 粟谷菊生 能楽座札幌公演 撮影 三上文規
今にも通じる父娘の情『景清』投稿日:2018-06-07
11月1日(土)に能楽座つくば公演で『景清』演じる。最近は数年前の脳梗塞による微かな障害や、八十歳を越えた僕の体力を気遣い、甥の能夫や息子の明生の配慮で出演の依頼がくるともっぱらこればかり演じることになってしまった。ある方が「あの人はあの曲しかやらないねー。なんていう役者がいてもいいの、それが本物なら」などとおっしゃって下さるから、「よしまたお見せしよう、勤めよう」と僕の舞台へのすけべ心が動き出す。

お能の世界というのは何か遠いところのものに一生懸命噛りついて守っているように思われるかもしれないが、そんなことはないと僕は思う。演っていると、能は僕の人生そのものだ。どんな曲でも僕は僕なりの解釈をしてしまう。もちろん見識者、学者が称えるような立派な解釈ではないが、例えば『山姥』。山姥とは何かと問われれば、「編み笠をかぶり街道筋に出る夜鷹」と答える。街頭で身を売るんだ。それが僕の山姥、「山また山、いづれの工(たくみ)か青巖の形を削りなせる・・・」と謡う山また山というのは男の数なんだ。男が巖となっているのだとか、僕なりの解釈が働いている。
今回の『景清』は僕の大好きな曲だ。ここには親子の情というものがあって、とても身近、遠い話なんかではない。昔、悪七兵衛と恐れられた景清も、日向の国宮崎に流されて年月をかこち、今や落ちぶれて盲目の身となっている。そこへ娘の人丸が訪ねてくる。しかしなかなか自分を景清とは明かさない。「今訪ねて来た子は自分の子なんだ。そうだ、思い起こせば昔、熱田の遊女と相馴れて、一人の子供をもったのだ」とひとり愚痴る。
昔、ここのところをちょっと色っぽく謡おうと苦労したが、最近は淡々と謡えるようになってきた。僕が景清で景清が僕なのだという気持ちで謡っている。
あるお弟子さんが、大きな声で「遊女と相馴れ!」とお謡いになるので、僕は「二人は抱き合っているんだぜ。女の子ができるんだ。そんな謡い方ではダメだ」と言って、何度も何度もやり直しをさせたことがある。そうしたらやがてよい感じで「相馴れ」が謡えるようになった。その方が亡くなられたときに、弔問に伺うと、奥様が「あのころ主人は朝から晩まで“相馴れ、相馴れ”でした。そのうちとてもよいように謡えるようになったんです。本当にどこかで相馴れたのではないかと心配しましたよ」などとおっしゃった。能は理屈ではない。人生そのもの。何度も謡っていくうちにその人になるのだと思う。そして最後、景清と娘は名乗り合い、別れていく。従者と立ち去る娘・人丸の肩に手をそっとかける場面は「匂いを嗅げ」と教えられてきた。愛しい娘だけれども別れていかなければならない。その万感の思いを込めるところだ。僕はこのとき、結婚式のバージンロードを思い浮かべる。教会のバージンロードに父親が娘の腕をとり歩いていく場面があるではないか。あれは残酷なシーンであると思う。娘を連れて歩き、いよいよ最後、娘を奪っていく憎っくき男に渡さなければならないのだから。
しかしあの場面で、世の父親というのは相手の男をにらみつける度胸はないようだ。必ず視線をはずしている。僕の弟子でバージンロードをすり足で運んで、娘に「いやだなあ……。先生、父に何とか言ってやってください」などと言われた男もいる。そこまでくると僕も致し方ないが、父親の心境というのも複雑なものなのだ。
それで僕は『景清』の最後、「さらばよ」という言葉を形見に別れ行くところは、バージンロードの父親のように、右に視線を落とす型をやっている。身近なことを何でもお能の参考にしてしまう、これが僕のやりかただ。
写真 景清 シテ 粟谷菊生 撮影 あびこ写真
白竜社、絵はがきより
能楽座パンフ「菊生さんを偲んで」投稿日:2018-06-07
梅若六郎
私にとって菊生師は、年齢は離れてはおりますが非常に身近にアドバイスをいただける良き先輩でした。特に謡についてはいつも適切な助言をいただき、私自身も菊生師の謡によって触発されることが多々ございました。今となってはそのお言葉の数々が懐かしく、そして心に強く残っております。
また、永年、能楽会の重鎮としてのご活躍はかけがえのない役割をお果たしになられたと思います。
この後も菊生師をはじめ、先輩方の教えを思い出しながら舞台を勤めていきたいと思っております。
大倉源次郎
昨年の粟谷能の申し合わせに、菊生先生の地謡で江口を勤めさせて頂けると意気込んで国立能楽堂の楽屋へ入った時、そこに先生はいらっしゃいませんでした。状況を伺い愕然としたことを昨日のように思い出します。
大阪で育った小生は、大阪菊生会と阪大喜多会の舞台が菊生先生との出会いの場で、力強く独特の浮き節を謡われる菊生先生の舞台と、酒席での先生のお話に純粋無垢な少年が影響を受けるのに時間は掛かりませんでした。
父を早くに亡くした小生に対して、同じ次男坊で気持ちを良く判って下さったのだと思いますが折に触れアドバイスを頂きました。心細く迷ってばかりいた小生を気遣って下さったことが嬉しくどれだけ勇気付けられたか知れません。
先生の若い頃は「人数が少ない喜多流は観世流の三人分働かなくてはダメだ。」と猛烈な忙しさで全国を飛び回っていらっしゃいました。阪大OBが纏められた喜寿のお祝いの冊子に、これからは二人分に減らして身体を大切にして下さいとお願いしました。こんなに早くお別れが来るのなら、一人分に減らして大切にして頂きたかったと叶わぬ思いを抱いています。
現代社会と能楽会、喜多流、そしてこの能楽座を見渡し様々に配慮されていた菊生先生が亡くなった今、大正、昭和、そして平成と戦中戦後を通しての労苦を越えて成されたことを思い直し、この豊かな時代に生まれ、遺された私たちは、これからの舞台づくりを少しでも良いものにすることで遺志を継がなければならないと思い居ります。
大槻文蔵
菊生先生には、大槻能楽堂自主公演に二十数年お舞い頂きました。数々の名場面に多くの方々が感動されました。私も色々の事を勉強させて頂き、今も深く残っています。しかし、一番思い出深いのは私が自分の会で“隅田川”を舞いましたのを地謡して頂いた事です。
「文ちゃんうまく謡ってやるからね。」
そこは異流しているというような事を、全く感じない自然体の舞台でありました。
子を尋ねる母の強さ、孤独感
念仏の輪がどんどん広がっていく有様
茫洋と明け行く関東平野
素晴らしい地を謡って頂きました。
「先生、もう一番“善知鳥”を謡って下さい」と、お約束していたのが出来なくなって残念です。
色々教えて頂いて有り難うございました。
片山九郎右衛門
まことに惜しい方を亡くしました。
残念です。
粟谷菊生さんは東京にお住居の、まして他流の方ですから、京都在住の私には、舞台上の御縁も、スケジュール的にもお出会いが殆どございませんでした。
しかし、〈喜多流に粟谷菊生さんあり〉とは、先頃没くなった観世榮夫さんや静夫さんから、よく伺っていました。粟谷さんのことを、真剣に、そして愉快に話していられるのを聞き、いい先輩なんだな、と思ったものです。
その後、追い追いに、東西合同養成会や仲間内のパーティなどで拝眉の機を得ましたが、折々のスピーチには何時も感心させられ、楽しみにしておりました。
八世銕之亟氏の亡き後、能楽座の代表も務めて下さり、私も折にふれ、大先輩と楽しく一杯やらせて頂くようになり、いろいろお話をする内に、次第にお人柄に魅かれて行きました。率直に申せば、私自身が年齢を重ねる程に、何と得難い、大切な方だ、と思うようになって参ったのです。
直接拝見できなかった貴方の「景清」の写真集を改めて手にし、感銘を受けております。この決然とした強さ、そしてツレの肩に置かれた手の、むっくりとした温かさ、やさしさ。〈自分が粟谷菊生さんに魅かれたのは、これやった〉。今、如実に感じております。
賜りました御厚誼、誠に有難うございました。
心より御礼申し上げます。
近藤乾之助
粟谷さんにお会いすると楽屋でも、道でも「よお……。乾ちゃん」まず、その言葉でした。最近、私におっしゃった言葉で、「我々の年では自分から動かないで、よく見て考えて行く。」そのような意味の言葉ではなかったかと。
菊生さんに初めてお会いしたのは昭和二十年代の初め、染井能楽堂での能楽協会の稽古会の折でした。
先輩の能で印象を受けた中のひとつ、景清で作り物から顔を出し、脇、ツレを見る時、背中、腰は作り物の中、そこに景清の生きて来た、過去の姿が見えたのです。
初めに述べました先輩の「よお……。」と云う声が忘れられません。
茂山千作
確か昨秋のことだったかと存じます。粟谷さんの舞台写真集の出版に際して、私に序文を書くようにとのお話がございました。勿論、積年の畏友・粟谷さんのこと、喜んでお引き受けいたし、昔を偲びつつ拙文を認めましてお送り申し上げたのですが、その後いくばくもなく粟谷さんの訃報に接しようとは……遠く京都におります身にとりましては余りに突然のことで、しばらくは信じ難く茫然自失の体で、やがて深い悲しみと喪失感がおしよせて参りました。
粟谷さんとはお兄様の新太郎さんともども、七十年に垂んとするお付き合いでございました。豪放闊達なお人柄で無類のお酒好き—–そんな処が互いに触れ合ったのでしょうか、舞台が終われば共に盃を重ね、酔えば談論風発……誠に芸の上ではよきライバル、舞台を離れれば無上の友—–最後まで「七五三チャン」と私の本名で呼んでいただいたのは粟谷さんお一人でした。
粟谷さん亡き今、ありし日がひたすら懐かしく、寂しさがひしひしと身に迫ります。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
茂山忠三郎
菊生さんとは六十年ほど前から毎年宮島の桃花祭の奉納の時にお会いしていました。
戦後、桃花祭は一日目と三日目は喜多流と決まっていますのでご一緒する時間は長いので楽屋ではよくお話をしました。
四国の金子五郎さんの催しでもよくご一緒し、松山にいる忠三郎門下の古川七郎と一緒に飲み歩いたこともありました。
また、毎年春の「菊生の会」、十二月には大阪大学の学生能には間狂言のいるときには私を必ず呼んでもらい、うかがっていました。能のあとには学生連中と一緒に飲んだこともあり、酒飲み友達でもありましたね。
いつも豪快に賑やかに飲んで楽しむお酒でした。粟谷さんは小さいことにはくよくよせず、お人柄も豪快なお方でした。舞台でも真面目な能を舞われる方でした。能を舞われるときと同じで優雅に堂々と「豪快な侍」という感じの方です。今はそういう方は少ないのではないでしょうか。
こういうように一年中ご一緒することが多く、また粟谷さんのお父さんの時から私の父と仲良くしていただきました。私が倖一なので、「倖ちゃん」と呼んでもらい、私は「菊生ちゃん」と呼ぶくらい親しい仲でした。
粟谷さんにはお兄さんの新太郎さんがおられて、私たちは次男同士、息の通じるところがありました。「どうも長男は得で次男は損をすることが多い」と愚痴をこぼすこともありました。
最近は段々と心やすかった人が先に逝かれるので寂しい限りです。粟谷さんとはお互いに体を大切にしようと約束していたばかりでした。
ご冥福をお祈りいたします。
追悼 菊生さんを偲ぶ
曾和博朗
在りし日の菊生氏の面影を思い浮かべ乍お相手の事等考へて居ります。
菊生さんは一九二二年のお生まれで、私は一九二五年で御座いますので三ツ上の兄貴になります。もっともっと活躍して頂き度いのに誠に残念です。
昭和二十三、四年頃、山陰でお能の会があり、喜多長世氏(元六平太氏)、粟谷新太郎氏、菊生さん達と夕食の席にてお酒をあびる程飲みました。亡くなる前の日までお酒を飲んで居られた由、わたしもこう在りたいとうらやましく思います。
舞台ではいろいろとお相手をさせて頂きました中で、私が無形文化財各個指定を受けた記念でNHKのテレビにて菊生先生のお謡で一調一声玉葛を打たせて頂きました。もとより何もかも御存知のお方ですから安心して思ふ存分勤めさせて頂きました。
二、三年前四国松山で景清があり、ひろちゃん(私)は元気だけれど、手をつかないと立てねんだよ、情けない、と菊生さんらしくない事を言はれました。其の後、能のシテは引退された由、昨年東京観世座にて鵜飼がありシテ友枝氏、地頭菊生氏にて勤めさせて頂き本当に良い地謡でした。これが最後のお相手となりました。
天国にてよく舞いよく謡い、そしてよく飲んでください。 合掌
菊チャンと呼んだ先輩
野村万作
十歳年上ですが、菊チャンと呼ばせていただいていました。
催し後の宴席などで、「菊生先生がいられたらば、さぞ楽しいだらうに。」と喜多流の後輩の人々の声を聞きます。あの世の方が、だんだん賑やかになり、実先生(菊チャンは壮年期、実先生の影の如き存在でした。)友さんと敬愛していた友枝喜久夫さん、勿論お兄さんの新チャン(粟谷新太郎さん)節世さんなどと、菊チャンは今の能界のあれこれを面白く話して、皆を笑わせているのではと想像させられます。
粟谷ご兄弟に誘われて、目黒での催しの後よく一緒に飲みました。先輩たちの喧々ごうごうの芸談の渦の中にいられたことは、誠に幸いで、懐かしく思い出します。
菊チャンは懐の深い人でした。年寄りから若手まで、流儀を超えて誰とでも親しく話し、人に影響を与える言葉の表現力を持っていられました。先輩たちが亡くなったとは言え、いつの間にか能界の頭目としての大きな存在となったのも、その芸は勿論ですが、人柄のしからしむるところでしょう。
新チャン健在の頃、「次男は長男の三倍の努力!」と同じ立場の私によく言っておられました。あれは菊チャン五十代の頃だったでしょうか。「二朗チャン(私のこと)は兄貴と仲良くて、僕は太良チャン(兄のこと)と仲がいい。面白いもんだね。」そんな言葉もよく聞きました。
揚幕から顔を出すようにして狂言もよく観ておられ、的確な感想をもらされる。相手の人に即して物を言える、会話の名手でございました。
「花月」のお相手をしたことがあります。シテが、間狂言の肩に手をおいて、共に歩む小唄の動きについて、「君についてゆくから、足数は細かくは決めないでやらう。」と言われ、大変気持よくできたことがあり、後々まで、そのことをよく言っておられました。
柔らかな心で人との調和を生み出す、芸、人生の達人は、敬愛する多くの人々に送られて、西の空に旅立たれたのでした。
菊チャン、長い間お導きいただき有難うございました。
粟谷先生の想いで
藤田六郎兵衛
名古屋に居りますので中々先生のお相手をさせて頂く機会はありません。しかし有り難い事に粟谷先生の代表曲とされる「景清」を四度、そして地頭をお勤めの時に数度お相手をさせて頂きました。
舞台の終わった後、あのニコッとされた迫力有るお顔で今日の日吉(ヒシギ)は良かった、あのアシライはこうだった、あそこに藤田流はアシライが有るんだね、または藤田流は吹かないの?と必ず一言声を掛けて戴きました。笛方としては何よりもアシライの事に気を掛けて戴け、ご注意戴ける事が大変有り難く、そして大変嬉しい事でした。
舞台が終わった後に、今日はお小言かな、笑顔かなとドキドキしつつも声を掛けて戴くのを楽しみにしていたのですが、もう先生はいらっしゃらない。寂しい事です。
菊生先生との半世紀
三島元太郎
一九五四年秋、東京駒込にあった染井能楽堂。毎日存分に太鼓を打てた環境は有り難い事この上なしでした。が、金春先生と仲良しの菊生先生が頻繁にご来宅。稽古場でもあったのですが常にお二人の存在は最初から師匠が二人。機会ある毎に的確なアドバイスを頂戴しました。
偉大な功績の一つは大阪大学での能の指導でしょう。学長になられた岡田実先生のご尽力もありますが、四〇年近く自演能を続け、育った人たちは凡そ二〇〇名に及ぶとか。一流人として社会に雄飛しつつも、声が掛かればすぐに応じて舞える人が何人もいます。学生時代に如何に充実した稽古がなされていたか、ずっとお手伝いをさせていただいた者のよく知る所です。ぴしっとした緊張の持続の中で、時にほっと心を和ませる巧みな指導法は鮮やかなものでした。またこれらの方々が後に能楽を支える客ともなってくれているのです。経済性を度外視した先見のご努力には心底敬服いたします。
昨年七月能楽座自主公演の後席で、話題は太鼓の撥捌きにも及び、最後にあの天下一品のにっこり笑顔で「元ちゃんあとをよろしくたのみますねえ」横で頷いておられた榮夫さん。爾来あの場面は脳裏を去らない。
ありがとうございました。 合掌
菊生先生さようなら
山本東次郎
太平洋戦争は能楽会にもさまざまな傷跡を残しました。貴重な面・装束・伝書類はもとより、多くの能楽堂が跡形もなく焼失してしまいました。終戦当時八歳だった私の記憶の中だけでも、その大半の舞台を踏んでおりますので、たいへんな数になります。戦後、都内に残った舞台はたった三つ、「多摩川」・「染井」・「杉並」。戦争のために失った時間を取り戻そうとするかのような各流、各派の先生方の気迫と情熱、それにはまず稽古場としてこのわずかな能舞台をいち早く確保すること、我が家の舞台を使われたのは喜多流と金春流で、喜多流は月・水・金の三日が稽古日でした。
菊生先生とはその頃からのお馴染みでした。私より十五歳年嵩の、いつも面白いことを言って笑わせてくださるお兄さんでしたが、少年・青年時代の十五歳差は一緒に遊んで頂ける仲間ではありません。しかしそれが三十歳と四十五歳ぐらいになると、なんとなく同世代的な意識が見えるらしく、様々なところで一緒のお仲間に入れて頂けるようになったと思います。
当初は「女性」への心理的な接し方やマナーについて語ってくださいました。また共に年を重ねていくに従って、「老」というものへの心構えや考え方を教えて頂きました。それらはいつも菊生先生の実体験に基づいた反省やら考察やらで、身を乗り出すように真剣な面もちでおっしゃるその内容は、いつも実にユーモア溢れる楽しいものでした。大阪の大学で稽古している女子大生が「センセーッ」と言ってすぐ手を繋いでくれるので「俺もまだまだモテるんだな」って思っていたら、「お足元が危ないから、お気を付けください」との一言に凄いショックを受けて、落ち込んでしまった等々。
物事は何でも良い面・悪い面の両面があるものですが、菊生先生は常に良い面を選び取り、明るく前向きに生きてこられたのでしょう。「女性」はともかく「老」楽しいものではありませんが、菊生先生に掛かると何でも楽しく思えてくる、いつもそんな風でした。
菊生先生は喜多流のみならず、能楽界全体の後輩たちの舞台をたいへん気に掛けてくださる方で、時には見所までお出になって、よくご覧になっていました。近頃は私の狂言さえも幕際でよくご覧くださって、いろいろ感想を述べて下さいました。何しろ小学生の時からずっと見て頂いているわけで、特に私の科白の言い回しについて過去からの成長の過程を見知っていらして、それをとても一生懸命分析して、よく頑張って来たと誉めてくださったりもしました。そんなことを率直におっしゃって下さる方は他にはおいでになりません。ほんとうに有り難く思ったものです。
持ち前の明るさと明晰な頭脳、誰にも愛されるお人柄で能楽界を縦横に席巻なさった菊生先生、心からの御冥福をお祈り申し上げます。
写真集と弔辞投稿日:2018-06-07
写真集と弔辞
粟谷菊生
 此の度 国文学の鳥居明雄教授と能の写真で皆様よく御存知の吉越研氏との編纂による僕の能の写真集が出ることになった。
此の度 国文学の鳥居明雄教授と能の写真で皆様よく御存知の吉越研氏との編纂による僕の能の写真集が出ることになった。
鳥居氏は彼の大学生時代から今日に至るまで僕の追っかけ的大ファンだったそうだが 一度もお目にかかったことは無かった。それが三年前の平成十五年四月 僕が宝生能楽堂での玉華会で「鬼界島」の能を勤めたとき ロビーではじめて妻に自己紹介をされ、それからの面識ということになる。このときの「菊生先生のこれまでの舞台を写真集に残しては…」との御提案が発端で以後 氏は大学での本業の傍(かたわ)ら まことに多大の御盡力を払はれこの二冊の写真集の上梓(じょうし)に至った。
写真集の話のもち上った前年の夏 偶々(たまたま)妻は それまで演能順に整理してあった写真を急に思い立って曲目別に整理したそうだ。あまりの膨大さに半分は捨てたとのことだが喜多流専属のあびこ氏撮影の写真帳の分も、後に曲目別のアルバムに移し入れ、その後再度、五番立てに準じて分別するなど何回か整理し直してくれてあった。
当初「景清」だけの写真集を企画されていた鳥居氏だったが はじめて来宅された折 アルバムを見て これは「景清」に限らないで いっそ演能曲全般に亘(わた)った写真集にするべきだという考えに変った。そのうち一冊にまとめるには余りに多過ぎるので検討の結果二転三転、最終的には「景清」を別に一冊にまとめることになった。昭和三十年代からの舞台写真を百数点に選別して しぼり込むには随分と手間と時間がかかったようではある。僕は「我、関せず」とばかり外野にいるつもりだったが、そのうち写真の場面が どういう謡の箇所かと聞かれる度(たび) それには説明したのだから 心ならずも些かの参画とはなった次第。
今年になって夏を迎える頃、本の刊行に当って「日頃御昵懇(ごじっこん)の方々から一言お言葉を頂けたら…」との出版社の宮田社長や鳥居氏の御意向で各氏に寄稿をお願いしたようだ。
各氏から寄せられた御文章を読ませて頂いて僕は感激した。御座なりでも儀礼的でもないお心のこもった、実に個性のあふれたそれぞれの素晴らしい文章に。これはこのまゝ弔辞にしてほしいと僕は思った。いや、死んでからでは僕が聞くことは出来ないわけで、生きているうちに こんな最高の手向けのお言葉を頂けるなんて何という幸せかと とても嬉しく思っている。
「写真集が出来上がったら、一番うれしく眺めるのは吃度、能から幕引きをした貴方よ」と 何も彼もお見通しのような女房殿。それ当っているかも。
写真 粟谷菊生 仕舞「鉄輪」 出雲康雅の会 18年2月 撮影 石田 裕
うれし恥ずかし『弱法師』投稿日:2018-06-07

息子の明生が、8月31日秋田県協和町の「まほろば唐松能舞台」で『弱法師.舞入』を舞うという。
『弱法師』は、十四世喜多六平太先生の当たり芸であり、父・益二郎の仕舞が絶品であった。僕はその両方をうまく取り入れ、座頭市(主演、勝新太郎)の味も少し加えて勤めている。特に最近はこの曲を舞うことが多くなった。
『弱法師』の舞台となる天王寺には、悲田院があって、乞食や病人が集まるところがあった。今でも、天王寺の付近には悲田院町という地名がある。簡単な病院があって、捨てられた人たちの面倒をみていたのだろう。そこは施しを与える人や受ける人が多く集まり、ずいぶん賑っていたようである。「踵(くびす)を継いで群集する」とあるから、前の人の踵を踏むくらい大勢の人が集まっていたわけである。この能ではシテ、ワキ、アイのほかには登場人物が出ないため、踵を踏むほどの賑いは舞台をみるだけでは感じにくいかもしれないが、謡の言葉の中から情景を想像していただきたいのである。中世は、寺社仏閣にはそのような乞食、身体の不自由な人が集まっていた、実際によくある光景だったと思われる。
盲目の俊徳丸も毎日天王寺にやってきて施しを受けていたと思われる。だから六平太先生は「とぼとぼと歩かないで、もっと運んでいいんだ」とおっしゃった。俊徳丸は盲目とはいえ、毎日この場所に来ているのだから通い慣れている。どこに何があり、道が悪く大きな石ころが転がっているなど全部わかっているのだ。どう歩けばよいかちゃんとわかっているから、あまりヨロヨロとする必要はないのだと。そういえばあの盲目の勝新の座頭市も動きは素早く、目が見える人間より感覚が鋭いではないかと納得する。
さて話は変わって、舞台の進行を見ていくと、父の通俊と子の俊徳丸の邂逅はどうなるのか。天王寺の同じ場にいながら親子はなかなか会えず、観る人はジリジリするだろう。最期に「夜も更け人も静まりぬ」というころになって、ようやく二人は名乗り合い、親子であることを確認する。それでも二人は終始、うれし恥ずかしの気持ちなのだ。「親ながら恥ずかしくて、あらぬかたに逃げければ」と地が謡うのに合わせ、シテは逃げ惑い、それを止めるようにしてワキの父・通俊が走り寄る。そして「明けぬ先にと誘い」と、俊徳丸を高安の里に連れて帰ることを促し、父も続いて行くと暗示させながら留めとなる。この最後のクライマックス、父子の逃げる、止める動きがきれいな絵になるようにしなければ『弱法師』ならない。「明けぬ先に」とは夜が明けてしまっては恥ずかしいとうれし恥ずかしの気持ちが満ちているのだ。
僕は謡が好きだから、よい謡があるとうれしくなる。『弱法師』にも名文句があるのがよい。「それ鴛鴦の衾の下には、立ち去る 思ひを悲しみ、比目の枕の上には、波を隔つる愁ひあり」。ところがこの名調子、うっかりすると『砧』になってしまうから気をつけなければ・・・。『弱法師』はこのあと「いはんや心あり顔なる」と 続くが、『砧』は「ましてや疎き妹背の中」となる。お能の名調子はときに複数の曲に使われることがあるから面白い。
人間国宝認定にあたって投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
人間国宝認定にあたって
粟谷菊生 此の度、人間国宝認定の栄誉を賜りました事まことに有り難く恐懼いたしております。 |
百八十年ぶりの『伯母捨』投稿日:2018-06-07
私が百八十年ぶりの『伯母捨』を勤めて、もう九年が過ぎた。七月には素人会ではあるが、素謡と舞囃子でこの曲を謡うことになり、今準備に入っている。
今回の菊ちゃんの一言は、あの『伯母捨』を思い出し、思うことを記したいと思う。 老女物といえば、当時、兄の新太郎が『鸚鵡小町』を舞い、僕が『卒都婆小町』を舞って、親父が果たせなかった老女物を兄弟で一番ずつ舞っていたのだから、あの世へのよい土産物もできたし、もうこれで老女物はよいと思っていたのだ。
老女物といえば、当時、兄の新太郎が『鸚鵡小町』を舞い、僕が『卒都婆小町』を舞って、親父が果たせなかった老女物を兄弟で一番ずつ舞っていたのだから、あの世へのよい土産物もできたし、もうこれで老女物はよいと思っていたのだ。
ところが能夫と明生に「『伯母捨』を舞ってほしい」と言われてしまった。『伯母捨』は喜多流では、百八十年前に井伊掃部頭(かもんのかみ・宮中の施設・掃除などをつかさどる役所の長官)の邸において上演され、そのときは太鼓が加わる出端であったという記録があるばかりで、その後舞われたことがなかった。僕の知る先輩たちは誰一人として舞ったことがないのである。『卒都婆小町』のように謡で親しまれているわけでもなく、喜多流ではほとんど廃曲のような曲だったから、これはえらいことになったと思った。
私は次男に生まれ、重い曲は長男がやるものと思っていたから、次男の自分が『伯母捨』を勤めるなどと夢にも思っていなかった。それが平成六年十月粟谷能の会で実現することとなったのである。私をやる気にさせたのは能夫と明生の説得上手、その技以外の何ものでもなかったと思う。
決意した翌日からおよそ二年間、僕は『伯母捨』の掘り起こしに没頭した。喜多流では百八十年間誰も勤めていない曲なので、他流の方からも素人の方からも、いろいろな方からお力添えいただいた。本当にありがたく感謝してしきれるものではないと思っている。
とりわけ銕仙会の観世静夫さん(故観世銕之亟さん)が力になってくれた。「菊ちゃん、一緒に見ようよ」と言って、銕仙会の楽屋に誘ってくれ、静夫さんが舞ったときのビデオをみせてくださった。そこで二時間、二人だけの部屋で、静夫さんは『伯母捨』を熱っぽく語った。「菊ちゃん、僕はここをこうやりたかったんだ」「ここはもっと違う型もあるよ」「月はあるときは満ち、あるときは陰るでしょ。それをたった一つの扇の上げ下ろしで表現するんだ」などと、段々お互い興奮し、盛り上がったのである。まことにありがたい二時間だった。
装束も銕仙会から拝借することになった。静夫さんの暖かい心づかいが身にしみたが、装束を借りるということは、すでに負けなのである。負けたのだから徹底的に下手に出て、どうぞ私に力をお貸しくださいという態度で教えを乞うのでなければならない。安易に「ビデオでもあったら貸してよ」などは失礼千万な言い方で、とんでもないことである。僕はそう思って教えを乞うてきた。
「朧月の型」を考えていたとき、橋岡久太郎先生の一枚の写真が思い出された。全身力を抜いてすっと立ち尽くされた姿、僕はこれだと思って、その型をいただいた。そこからいろいろなイメージが湧いてきたのである。
『伯母捨』は捨てられた身でありながら、恨み言を言うでもなく、「わが心なぐさめかねつ更科や伯母捨山に照る月をみて」と月に情趣が注がれ、月光に興じ、遊ぶ、品格のある曲のように解釈されやすい。しかし、僕は『伯母捨』という曲は、お能の品というものだけに逃げてはいけないと思っている。僕の『伯母捨』は月夜に座ってじわっとおもらしをしながらそのまま死んでしまう老女だよ、それでいいならと言ったことを覚えている。
『伯母捨』に挑むときに、動かぬところは微動だにせず、舞いかつ謡う、徹底的に老女になって舞うからな、だから、お能としての品格は閑ちゃん(宝生閑氏)がつくってくれ、太良ちゃん(野村萬氏)がアイで語ってくれ、囃子方も含めて、あなたたちが品格というものを供えてくれとお願いした。囃子方も、菊生という人間の芸をよく知っている人ばかりだったから、僕の老女に添ってくれ、すばらしいものをつくり出してくれたと感謝している。当時の配役をここに記しておこう。ワキは宝生閑、ワキツレが宝生欣哉、殿田謙吉、アイが野村萬(当時、野村万蔵) 地頭が友枝昭世。囃子方は笛が一噌仙幸、小鼓が横山貴俊、大鼓が亀井忠雄、太鼓は金春惣衛門であった。
百八十年前の『伯母捨』は太鼓が入る出端であったという。竹馬の友であり、天才的な太鼓打ち、金春惣衛門という男がいるのだから、今回も出端でやってみよう。それに絶妙な大小鼓、百八十年ぶりの囃子はすばらしい音色で能楽堂に響きわたった。
そして曲の最後。「恋しきは昔」と、月に興じ、月に遊び、夜もしらじらと明けてくると、老女を残して旅人は帰って行く。その帰っていくときの宝生閑と欣哉、謙吉のできがすばらしかった。三人がぴたっと息が合い、すこしの崩れも感じさせない。ワキとワキツレの後ろ姿を見ながら、老女が「一人捨てられた女が」と謡うところが哀しく難しい。そこをワキとワキツレがちょっとでも不揃いでシテの前を通ったのでは、この曲はおしまいなのである。シテの僕がいくら夢の世界だ、死の世界だと情感込めていても、それだけでは能は成り立たないのだ、役者が役者らしいことの最善の努力をして、囃子方が最高の音色や掛け声を奏でることがすべてだと思う。あとは観る人が想像してくれるのだ、と思っている。
『卒都婆小町』も一生懸命だったが、『伯母捨』は我を忘れるほど没頭した。僕にとって忘れられない曲となった。喜多流に見本となるものがなかったから、いわばすべての型が処女だった。演技しようなどという余裕もなかったから、一つ一つをきちんと確実にやろうと、そのことばかりだったようにも思う。しかし、それだけに僕の心の中はきれいだったかもしれない。
「まことの花」投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
「まことの花」
粟谷菊生
平成十年、今年の新年はめでたく元旦の祝酒で過ごしたと思ったら、軽い脳梗塞で入院。お屠蘇を祝ったのは元旦だけで、不本意にもお正月につゞく約一ヶ月を入院生活で過ごすことになった。
僕は、能『羽衣』の「いや疑いは人間にあり。天に偽りなきものを」という名文句を謡うとき、いつも清らかな天使像を思い描いていた。そして、その清らかな姿を体現したいとの思いを込めて、長年『羽衣』の能を舞いつゞけて来た。しかし、羽衣をまとう僕の天女よりも崇高な天使たちが、なんと天上ならぬ此の僕のベッドのまわりにいたではないか。何事も嫌な顔一つせずに世話をしてくれる彼女たち。日夜骨身を削って患者たちの面倒を見ている姿を見るにつけ、本当に頭の下がる思いであった。報い少なく、労多き此の天使たちのことを少しでも多くの人に話してきかせ、彼女たちの幸せを心から願わずにはいられない。
退院する時は、杖をつくことになるかも…と云われたが、二月一日に二本の自分の足で退院。その月の二十八日には周囲の心配を押し切って日立で能『景清』を、翌三月一日に東京の国立能楽堂で好きな『羽衣』の能を舞った。息子が「一度、面をつけて舞ってみては?」と心配してくれたが、「面をつけてみて愕然としたら、その愕然とした暗い気持ちを本番まで持ちつゞけて行かなければならない。それでは箪笥でも担いでしまうという火事場の糞力が出なくなってしまう。それより本番になって面をつけてみて愕然としたら、その時こそ、火事場の糞力で演るからいゝ。」と拒んだ。
ワキ、地謡、四拍子、みんなが病み上がりの僕を心配して盛り上げてくれるのを、ひしひしと感じ、辛いながらも喜びを噛みしめながら舞った『羽衣』だった。血圧が上がらぬよう、あまり気張らないで…と演能中、自分に云いきかせたり、内心、不安と挑戦との葛藤で今までにない異質の緊張を味はったが、再び舞台に立つことの出来た喜びは何にも増して大きい。観客には、それと判らなくても僕自身、些か障害の残った左大腿部の固い重さを克服して、これからは世阿弥の云う「まことの花」を咲かせられるよう努めたいと思う。
(因みに入院した一月三日の国立能楽堂定例公演の『月宮殿』と、二月十二日の練馬文化ホールの『砧』は明生が代演。)
阪大、東大で教える 「植林が大事」投稿日:2018-06-07
僕が謡や仕舞を教えるようになったのは十代の終わりのころだった。秋田や東京女子大などに教えに行けたのは、父が地盤を築いておいてくれたから。それを踏襲するだけでは、丹精して育ったものを刈り取るだけになる。僕の子や孫へと長く続けてもらうためにも、親父がやってくれたと同じように、僕も植林しなければならない。とりわけ学生を教えることは、将来の能愛好家をつくることになるから重要だ。若い学生のときに謡や能の楽しみを知ってしまうと、それはからだにしみ込んで、忙しい社会人になって一時離れることになっても、必ず戻ってきてくれるものなのだ。
僕も学生を教えられないものかと思っていたところ、女房の母親が知り合いの東大生を一人紹介してくれ、たぶん昭和25年頃に東大喜多会ができたと記憶している。東大病院外科の木元博士に喜多会の部長になってほしい旨をお願いしたところ、「将来のためと思って菊生さんが学生を教えたいというなら私立の方がいいのではありませんか。東大は一匹狼が多くて、キミの期待には応じられないかもしれない。私立は社会に出るとスクラムを組みますからね」と忠告してくださったが、当時、慶應や早稲田といった私大にはすでに謡曲部があって、僕の入る余地はなかった。僕は東大と阪大といういずれも国立大学に縁あって教えに行くことになったが、卒業後も結束が固く、OB、OGの会をつくり、息長くつき合いが続いている。
東大喜多会は最後は入部部員がいなくなり廃部となり残念であるが、阪大はこの5月4日(平成15年)にOB会の翁会総会を京都西本願寺の聞法会館で開き50名が集まって、私の傘寿のお祝いをしてくれた。
阪大に初めて教えに行ったのは昭和四十二年。僕が大阪で謡や仕舞を教えていたその頃中学生だった子のうち、二人が阪大に合格したことをきっかけにして謡曲部をつくろうということになった。当時は学生運動が盛んで大学は勉強どころではなかった。授業がないから謡の稽古をするといった具合で、生徒はかなり熱心で、阪大謡曲部の基礎を築いてくれたように思う。僕は月一回ぐらい教えに行っていただろうか。僕がいないときでも稽古ができるように、謡は、阪大の近くに住む、謡の上手な僕のお弟子さんにお願いし、型の方は僕が中学生のころから教えていて、阪大に入った前記の二人が仲間に教えるというように、一通りのレールを引いた。その後は新一年生が入ってくると二年上の部員(三年生)が教え、一学期に仕舞三曲を覚えさせる、これが阪大謡曲部の伝統になり、今に続いている。
阪大や東大の学生の中には独特の覚え方があるらしい。謡本をみると、アンダンテ、モデラート、四拍子などと書いてある。なるほどこんな風にして覚えるのかと妙に感心したことがある。半下げといって半音下がるところがあって、下げたら少しずつ上げていってもとに戻すのだが、こういうことを六十代ぐらいの人にいくら説明してもなかなか理解してもらえないが、学生は一回言うとすぐにわかってくれる。学生というのは乾いた土に水がしみ込むように飲み込みが早いから、教えていても実に気持ちがよい。しかしあまり理屈ばかりではダメで、特に一年生にはあまり説明しないで、感覚的に入ってもらうようにしている。大ノリの八拍子も慣れないと謡いにくいところだが、まずはからだで覚えてもらい、理屈は二年生になってから徐々に・・・としている。
からだで覚えるといっても、もう少し謡本の内容を読んできなさいよと注意したくなることもあるのだが・・・。阪大の話ではないが、ある会社で相当お偉いお弟子様が『融』で「木幡山伏見の竹田、淀鳥羽も見えたりや」と謡うところを、「木幡、山伏」と平気で謡ってしまう。「ここは木幡山、伏見の竹田ですよ」と僕が注意すると、「あっ、そうでしたか。山伏と思いました」などと。山伏など全く物語に関係ないお話なのに、もう少し謡本の内容を理解して謡っていただきたいと思う。
阪大では、年一回一週間の夏合宿も恒例の行事になっている。僕も毎年楽しみに出かけ、学生と同じ生活をする。合宿所は三食五千円ぐらいの予算だからかなり粗食だが、僕の食事が特別ということはない。あるとき天ぷらが出たのだが、あまり衣が硬くて唇を切って往生してしまった。蚊の襲撃にあったり、部屋に蛙が跳んできたりと合宿のエピソードには事欠かない。
学生が熱心に稽古している姿を見ているうちに、僕はこの子たちに何とか能を舞う経験をさせてあげたいと思うようになった。年一回、十二月の第一土曜日に行う自演能。これが恒例になって、もう三十回は越えている。初めのころの番組は『羽衣』『小袖曽我』『小鍛冶』と決まっていたが、そのうち『通小町』や『忠度』『花月』など、新しい曲も入れるようになった。お能を舞った後、学生は必ず泣いている。なぜ泣くのか。それはやり遂げた達成感とあっという間に終わってしまう花火のような舞台への名残惜しさではないだろうか。お能を舞った連中が、後に集まると、「オーッ、お前は『花月』やったのか、うちは『羽衣』や」と話がはずむ。一度お能を舞った人間は、必ず謡や舞、お能に戻ってくる。何か特別な魔力があるようだ。
自演会で僕に入ってくる謝礼は七万円。三十年以上前からこの額は変わっていない。最初のころの七万円というのは、学生にとっては大変な額だったことだろう。親御さんから出してもらったり、あるいは仕送りの中からなけなしのお金を集めて僕へ最大限のお礼をしてくれたのだと思う。ところが三十年以上たった今も同じ。これでは新幹線代と宿泊代で消えてしまう額だが、僕は植林、植林と思って、黙って受け取っている。
阪大では、僕の舞台があるときには必ず観に来てくれて、終演後、僕が着替えて楽屋口から出てくるまでは、楽屋口の前で整列して待っているという規則があるらしい。ある寒い日のこと、「粟谷先生は学生をよく育てていますね。早く行っておあげなさい。学生が寒いところに立ってずっと待っていますよ」と言ってくれる人があった。学生たちはみんなで話しながら、寒さに耐え、僕が出て来て車に乗って帰るのを見送る、というしきたりになっているのだ。
阪大の稽古の後は学生主催の会食があって、そのあと何人かを連れて二次会に行くのが恒例で、そこでみんなといろいろな話をすることを楽しみにしてきた。昔は部員が多かったから、学生の方で今回は誰と誰にするかと割り振りをしているようだった。半数は女の子を入れるという心憎い気配り。それで、豪華なところではないが、彼らが行ったことのないちょっと気のきいた店に連れていく。「菊生先生、おでんのおつゆお代わりしてもよろしいでしょうか」などという子がいたりして、同じものを食べて「同じ竃(かまど)の飯を食う」という言葉があるが「和」を作って行くように思う。
その頃の連中も、今ではみんな偉くなって社会で重要な役割を果たしている。そしてOB、OG会に参加して、いまだにつき合いが続いている人が多いのは大変嬉しい事だ。
「菊ちゃん、いつまで学生と遊んでいるんだ」と太良ちゃん(野村萬)に言われたことがあるが、僕は学生に教えることが好きだからいまだに教えている。教えているというより、学生の若いエネルギーにふれ、生きる力をいただいているようなものなのだ。
合宿の方は、暑い夏、一週間かんづめになるのはきついだろうとの明生の進言に、自分もそうかなと思っていたところ、たまたま肉離れを起こし、さすがの僕も観念して、平成十二年の夏から、息子の明生に行ってもらっている。明生は僕が病気をしたときに代役で教えに行ってくれたことがあったが、学生を教えることの楽しさを知ったらしい。学生の方も僕よりはもうちょっと自分たちに近い明生に親しみを持ってくれたようである。
しかしまだまだ阪大は全面的には明生に渡さないぞという心意気で今のところ頑張っている。とは言え、将来は勿論引き継いで貰いたいと思っていることも確かだ。情熱を注いで育ててきた学生たち。さまざまな思い出が頭をめぐる。これらの思い出は僕にとって大切な宝物だ。そして僕の植林した樹木はしっかり大地に根付き、枝をはり、次の世代に渡してあげられるようになってきていることを僕はとても喜んでいる。
(平成15年5月)
写真 モノクロ49年8月 淡路島阪大合宿
カラー50年8月 丹後網野阪大合宿
ハ・ハ・ガ・メ・ト投稿日:2018-06-07
ハ・ハ・ガ・メ・ト
粟谷菊生
 古人の歌に「しわがよる。ほ黒が出ける。頭がはげる。ひげ白くなる。手は振う。足はよろつく。歯は抜ける。耳は聞こえず。目はうとくなる。身に添は頭巾襟巻、杖、目鏡…云々」(仙崖の字句をそのまま引用)と続くのがあるが、自分が該当しないのは僅か三つでガックリ。鼻の下の大きな黒子は生まれたときからのもので、よく剃刀で切り(電動カミソリでも)血を流す。若かりし頃の多すぎて困った髪は周知のように情無い状態となり、頭巾ならぬハンティングを冬は防寒、夏は日除けに、風吹げば、ほうぼうの逆髪になるのを押さえるために四季愛用することになる始末。耳も確かに遠くなり、テレビの音量を矢鱈に上げ、妻の声もとみに大きくなり、物が見えない見えないと騒いで「眼鏡もかけずに見えないとは図々しい」と呆れられ、その眼鏡を探すのに、これ又多くの時間を費やす。生来、家庭に於いて、使ったものは決して元に戻さないという習性を持っているため常に何処に置いたか判らなくなるのだ。眼鏡がない、眼鏡が無いと探しまわっていると、「新聞の下になっているのでは?」とか、「洗面所では?」とか、時には探している物を「これでしょう?」と云ってヒョイと目の前に出してくれる魔法使いのお婆さんのような妻のいるおかげで男ヤモメでない僕は幸せ。一人で暮らしていたら一日二十四時間の内、三分の一の八時間は探し物に費やすことになるだろう。忘れ物のないようにと、「ハンカチ、歯(部分入れ歯)、がま口(札入れと小銭大れ)、眼鏡に時計」の頭をとって、紙に大きくハハガメトと書いてくれたのを口だけハハガメト、ハハガメトと呪文のように唱えるだけで、実際は身につけていない口先居士。一つずつしっかりチェックしているつもりなのだが、駅まで来て始めて持っていないことに気づいたり…。あゝ年はとりたくないものとかこつこと毎日。弟子の多くが(何故か女性)膝を痛め、困っておられるが、僕も脳梗塞から具合の悪くなった左足には苦労している。駅の階段を一段毎に足を揃えて下りている人の難儀さ、座りつづけると立てなくなってしまう始末の悪さも知り、他人の苦しみが今更ながら身をもってよく判った。昨年十月の『巴』と『花月』の能は、僕にとって一つの目標だった。この二曲を自分なりに工夫してクリヤー出来たことは、まことに有難いことだったが、十二月の囃子科協議会定式能に於ける『藤戸』は、痛み止めの薬を飲んで揮身の力を振り絞った必死の思いの舞台だった。そして正月三日にNHKで放映の『羽衣』は、『藤戸』の九日後の、足の具合のますます悪くなった時に収録された。僕の一番好きな此の能が、不本意にも思うような従来の運びが出来ず、これが全国に放映されるのかと思うと悔やまれてならない。足がこんなに不自由になってしまう前に何故、撮っておいて貰えなかったのか。愚痴は言いたくないが、まことに残念だ。この残念は、今年から未来永劫続くことになるのだろう。長生きをするというのは、こういうものなのだ、と残念無念を噛みしめ、目の前に餌をぶら下げながら、その餌に向かって一生懸命走る短距離ランナー、それしかない年齢となった。昨年の喜寿の誕生日は僕の意思で、近所の寿司屋でさゝやかに妻と自祝したが、三年後の傘寿は盛大に菊全会をやるぞ!と意気込んでいる。それまではボケてはいられない。八十近くなると、演じられる曲目は、だんだん限定されてくる。前方にかゝげる明るい光は、いっ消えるか判らぬが、その時まで毎回、完全燃焼して謡い、舞いましょう!!
古人の歌に「しわがよる。ほ黒が出ける。頭がはげる。ひげ白くなる。手は振う。足はよろつく。歯は抜ける。耳は聞こえず。目はうとくなる。身に添は頭巾襟巻、杖、目鏡…云々」(仙崖の字句をそのまま引用)と続くのがあるが、自分が該当しないのは僅か三つでガックリ。鼻の下の大きな黒子は生まれたときからのもので、よく剃刀で切り(電動カミソリでも)血を流す。若かりし頃の多すぎて困った髪は周知のように情無い状態となり、頭巾ならぬハンティングを冬は防寒、夏は日除けに、風吹げば、ほうぼうの逆髪になるのを押さえるために四季愛用することになる始末。耳も確かに遠くなり、テレビの音量を矢鱈に上げ、妻の声もとみに大きくなり、物が見えない見えないと騒いで「眼鏡もかけずに見えないとは図々しい」と呆れられ、その眼鏡を探すのに、これ又多くの時間を費やす。生来、家庭に於いて、使ったものは決して元に戻さないという習性を持っているため常に何処に置いたか判らなくなるのだ。眼鏡がない、眼鏡が無いと探しまわっていると、「新聞の下になっているのでは?」とか、「洗面所では?」とか、時には探している物を「これでしょう?」と云ってヒョイと目の前に出してくれる魔法使いのお婆さんのような妻のいるおかげで男ヤモメでない僕は幸せ。一人で暮らしていたら一日二十四時間の内、三分の一の八時間は探し物に費やすことになるだろう。忘れ物のないようにと、「ハンカチ、歯(部分入れ歯)、がま口(札入れと小銭大れ)、眼鏡に時計」の頭をとって、紙に大きくハハガメトと書いてくれたのを口だけハハガメト、ハハガメトと呪文のように唱えるだけで、実際は身につけていない口先居士。一つずつしっかりチェックしているつもりなのだが、駅まで来て始めて持っていないことに気づいたり…。あゝ年はとりたくないものとかこつこと毎日。弟子の多くが(何故か女性)膝を痛め、困っておられるが、僕も脳梗塞から具合の悪くなった左足には苦労している。駅の階段を一段毎に足を揃えて下りている人の難儀さ、座りつづけると立てなくなってしまう始末の悪さも知り、他人の苦しみが今更ながら身をもってよく判った。昨年十月の『巴』と『花月』の能は、僕にとって一つの目標だった。この二曲を自分なりに工夫してクリヤー出来たことは、まことに有難いことだったが、十二月の囃子科協議会定式能に於ける『藤戸』は、痛み止めの薬を飲んで揮身の力を振り絞った必死の思いの舞台だった。そして正月三日にNHKで放映の『羽衣』は、『藤戸』の九日後の、足の具合のますます悪くなった時に収録された。僕の一番好きな此の能が、不本意にも思うような従来の運びが出来ず、これが全国に放映されるのかと思うと悔やまれてならない。足がこんなに不自由になってしまう前に何故、撮っておいて貰えなかったのか。愚痴は言いたくないが、まことに残念だ。この残念は、今年から未来永劫続くことになるのだろう。長生きをするというのは、こういうものなのだ、と残念無念を噛みしめ、目の前に餌をぶら下げながら、その餌に向かって一生懸命走る短距離ランナー、それしかない年齢となった。昨年の喜寿の誕生日は僕の意思で、近所の寿司屋でさゝやかに妻と自祝したが、三年後の傘寿は盛大に菊全会をやるぞ!と意気込んでいる。それまではボケてはいられない。八十近くなると、演じられる曲目は、だんだん限定されてくる。前方にかゝげる明るい光は、いっ消えるか判らぬが、その時まで毎回、完全燃焼して謡い、舞いましょう!!
写真『藤戸』 栗谷菊生(平成3年)撮影:森口ミツル
吉右衛門に刺激された『鬼界島』投稿日:2018-06-07
『鬼界島』(他流は『俊寛』)を勤めると思い出すのが、強烈に印象に残っている先代中村吉右衛門(初代)さんの歌舞伎『俊寛』のラストシーン。共に流された成経、康頼は都に帰り俊寛一人が取り残される。クライマックスの最後は岩場を伝って岸壁を這い登り松の枝に手をかけ舟を見る。すると枝は折れて、からだは平衡感覚を失ってしまう。ここを猿之助(二代猿之助=猿翁)ならパッとこけて、ドングリ眼をむいて見栄を切るところだが、吉右衛門は違った。自分のからだがどうなろうと構うことはなくじっと舟を見ている。視線を舟から離すことがなかった。これだ。自分の乗れなかった舟を追うことで、残されたものの悲壮感が出ると僕は思った。歌舞伎はどちらかというと大袈裟な芝居になり、能とは違う表現方法をとるとかねがね思っていたが、あのときの吉右衛門の演技は、能に応用がきく気骨のあるものだった。吉右衛門は背中と足の裏で俊寛を表現している、あーすごい役者だと、彼の演技が頭を離れなかった。
僕の俊寛も、舟が去っていくまで、左手は舟を指し、視線は舟から離さないやり方をしている。舟の動きを追いながらかすかに面を動かし、心のひだを表現するのだ。
僕が大坂城薪能で『鬼界島』を勤めたとき、堂本正樹氏が「菊生さんの差し出した手の先に大きな海が見えた」と言ってくれた。役者にとって嬉しい言葉だ。
舟に乗って行こうとする二人の袂に取りついて、「せめては向かひの地までなりとも、情けに乗せて賜び給へ」と俊寛が言うところは僕の大好きな謡い所の一つ。そのとき、「情も知らぬ舟人が櫓櫂を持って」打擲しようとするので、またうろたえて右往左往する。この哀れな場面をことさら哀れっぽく謡うのではなく、間(ま)と節のちょっとしたなびきの具合で表現する、ここが何ともいえぬ面白さなのだ。
僕が使う面は喜多流にある「俊寛」という専用面だが、鼻が高く、彫りが深くて、アラブの人のような不思議な雰囲気がある面だ。舞台では花帽子で包んでいるから不思議さが伝わらないかもしれないが、とにかく他の俊寛の面とは違う趣があって僕は気に入っている。
『鬼界島』はもともと喜多流にはなかった曲。喜多流の明治本には見当たらず、型付などの伝書もない。六平太先生、実先生、後藤得三先生、親父もやっているが、それぞれに型をつくって演じたのだと思う。もともと型付けがないから自由に創作することができる。僕は中村吉右衛門の舞台に刺激され、自分なりに自由に演じてきた。それが幸い評判よく、『鬼界島』は菊生さんの当たり芸だと言われる。僕自身も好きな曲で、よく舞台にも出すようになった。
僕が父益二郎の『羽衣』が美しいと思い、その型を継承しようとしたように、僕の『鬼界島』によさを感じて真似ようとする人があれば、その型は伝承されていくのだろう。能は古いものを継承するだけでなく、いつの時代も創造と継承が織り込まれているように思われる。
兄を偲んで投稿日:2018-06-07
兄を偲んで
粟谷菊生
僕は実は五人兄弟の次男なのだ。兄、新太郎、僕につづいて輝代という妹が居たのだがこの妹は五歳の時、亡くなり、辰三、幸雄となる。従って僕と辰三の間は六年ぐらい空くので僕は小さい時から、いつも年の近い兄と二人で遊び、能に関わってきた。親父は『小袖曽我』、『放下僧』などを二人に演らせ、地方の演能にも連れて廻った。世間では僕が剰軽な男という定評になっているが、新太郎も郎も結構、面白いことを言う人だった。いつか酔っ払った時、こう言っていた。「世の中の美人は、みんな僕のものなんだ。ただ予算の都合で今のところ他人に預けてあるんだ」と。兄は倒れてから八年間も能が舞えなかったわけだが、どんなに辛かったろう。兄は文部大臣賞、紫綬褒章など後年矢継ぎ早やに受け、娚が空恐ろしい位だと喜んで洩らした事がある。僕が人間国宝になった時、病院の担当医が「おめでとうございます」と仰言って下さったのを「自分が貰ったのかと思った」と。これは冗談なのか本気なのか?兄は最後まで頭はしっかりしていたようだった。体が利かなくなって、頭だけはっきりしているというのも本人にとって幸せなことかどうか。最近老人問題がテレビでよくとり上げられるようになったが僕も人間の晩年、最期ということを、しきりに考えるときが多くなった。
キャディあがりのプロ投稿日:2018-06-07
ここしばらく更新ができず申し訳ございませんでした。昔まだビデオなどなかった時分、雑誌「喜多」に投稿したものを記載させてお許し頂きたいと思います。
京劇では二本の旗を立てると車に乗ったことになりますが、能にもたくさんの約束ごとがあるのはご承知のとおりです。例えばワキが一足出て手を合わせて開けば、ある地点からある地点まで旅したことになるとか、悲しみの表現にも、シテは左手で二度シオるが、ツレは右手で一度しかシオらないというような。昔は南を向いて坐っている貴人の前で演じられた能ですから、舞台は北向きに建っています。『弱法師』の「南はさこそという波の」というところで、シテが南を向けば、天子にお尻を向けることになるのがおそれ多いから、少しはずした型が生まれてきたわけですし、『邯鄲』の能では夢の中での型はすべて逆というのも、曲趣からの発想だとうなづけます。そんなふうに考えてみると、謡でも仕舞でも、もっとわかりやすくなって、興味が出てくるのではないでしょうか。
私はよく稽古中、お弟子さんの型をオーバーに真似てみせます。若い娘さんは「あらッ、ひどいわッ」とにらんだり、キャァキャァと笑いころげたりしますが、実をいうと、そんな真似でもしたら印象に残っておぼえやすいのではなかろうかという気持ちなのです。
うちの稽古場には、サラリーマン・OL・学生さんなど若い人が多勢来ていますが、私のねがいは、誰にでも一度は装束をつけて能を舞わせたいことです。そしてまた、お弟子さんに能を教えるのは私にとってもプラスになることなのです。
というのは、自分の舞い姿は自分では見られないのですから、お弟子さんに能を舞わせて、その姿から間接的にも自分の姿、自分の能を眺めたいのです。だから時々、見所の側面からお弟子さんの能をみつめ、自分を矯正する一つの手段にしています。六平太先生、実先生から受けついだものに、多少自分の工夫を加えた私の能が、果たしてお弟子さんの能にどんなふうに表現されているか。それは私にとって大きな期待でもあるし、こわさでもあります。
私たち能楽師は、ゴルフでいえばキャディあがりのプロといったところ。技の点ではたしかに素人のお弟子さんには真似のできないものがあるでしょうが、素人の能には、時によって私たちをはっとさせる美しさ、よさがあります。それは何だろうと考えてみると、私たちプロとちがって、ねらわないよさといったもの、小学生が立たされている時のような無心の気もちの現れではないでしょうか。
私など、とかく器用だといわれる半面、技に溺れやすい危険性もあると思っているので、そうした素人の能から、時には教えられるものを感じることがあります。
仕舞、囃子は、いわば能のデッサンです。もちろんデッサンがなくては能は舞えませんが、現代人としては、永久にデッサンばかりやっていたのでは、というていこの道に引きいれられないのではないかと思われます。デッサンができて、やがて一環した曲が舞える喜び、それをぜひ一人一人のお弟子さんに味わってもらいたいのです。そうでなかったら、せっかくの能が、やがて上流階級の人たち、少数の人々の楽しみになってしまうのではないか、それが私には心配なのです。
芸道一筋だった兄投稿日:2018-06-07
芸道一筋だった兄
粟谷辰三
兄、新太郎の死は、私にとってやはりショックでした。長年にわたって闘病生活を続けていたので、いつかはこの日が来るのではと覚悟はしていましたが、ついに舞台への復帰を果たせずさぞ無念だったことであろうと、察して余りあります。芸道一筋に精進してきた兄の死を悼んで断片的ですが、いくらか想い出を連ね、兄を偲ぶよすがにしたいと思います。父・益二郎亡き後、粟谷家を支えた長兄。新太郎と次兄・菊生の二人は、私とは年齢が離れていたので、兄というよりは兄親というべき存在でした。ある喜多流ファンから「新太郎は芸一筋、辰三は呑気一筋」とひやかされたと聞いておりますが恥ずかしながら思い当たるところがあります。私は兄の後見を数多く勤めましたが、色々な失敗をしました。『巴』では数珠を反対の手に持たせてしまったり、『竹生島』では床几を出し忘れたりしてその都度叱られました。しかしそこは兄弟ですから叱責も一過性で、帰途には二人食事をしながらもう笑い合っていたものでした。兄は能面蒐集に執心しており、面をつけたまま寝ていて、義姉をギョッとさせたこともありました。その大事な能面を二面、私にくれました。その一つである「邯鄲男」の面を喜多舞台で稽古に使っていたら、六平太先生(先代)に見とがめられて、「こんな立派な面を稽古に使ってはもったいない…」と叱られました。兄の能面にかけた執念と、それを一目で見抜かれた六平太先生の眼力に、改めて敬服したものでした。古い話になりますが、独身時代の私と四男・幸雄は中野の兄の家に住んでいました。あるとき次兄に「お前たちも家に生活費を入れなけれぱいけない」と注意され、以来、兄嫁さんになにがしかのお金を入れていました。長兄夫婦はそのお金を使わずに、いずれ私たちがお披きをするときのためにと貯金しているということを亡母から聞かされた時には思わず頭が下がりました。陰に日向に私を支支えてくれた兄が、もうこの世に居ないことは寂しい限りですが、私も能楽師の端くれですから、残る舞台人生に全力を注がなければいけないと、遅まきながら反省している今日この頃です。合掌
孫、尚生の初シテ『猩々』投稿日:2018-06-07
今年、平成十三年四月八日に明生の主催する明生会で孫の尚生が初シテとして『猩々』を勤めました。私の初シテの時に父、益二郎が作ってくれた装束を、その後みんなが着て今、また孫の尚生が着ている…まことに感慨深いものがあります。
 |
 |
 |
|||||||
|
菊生
|
明生
|
尚生
|
|||||||
橋掛かりを頭を揺らさずに下り端(さがりは)で出てくる尚生の腰の入った運びを見て、此の子の将来にひそかに安堵を感じた「孫可愛いや」のジージ(爺)ですが、爆発的に謡い舞っている尚生の姿に、私も地頭として全精力で応えてやれたのが何よりの喜びです。日頃、孫に「おじいちゃま」と呼ばせず、「キクオチャマ」と呼ばせている私が、この日ばかりは、孫の初シテで地頭を謡えた幸せに浸り、大いに爺馬鹿ぶりを発揮してしまいました。
芸術院賞受賞に因んで投稿日:2018-06-07
「芸術院賞受賞に因んで」
粟谷菊生
平成十一年度の日本芸術院賞受賞の内定は三月はじめに発表されましたが、授賞式は六月十九日に上野の日本芸術院で行われました。前日の十八日、野村萬さんの古希と初世披露を祝う会が国立能楽堂で催され、私は乱狂言、(ワキ、囃子、狂言の三役が能を演じるのが乱能というが、その逆)の『唐人相撲』で唐の皇帝の役を演じることになっていました。唐に渡った滅法強い力士を演じるのは観世暁夫さん。三日前の申し合せで、次々に唐人の力士が負けてしまうので最後に皇帝が玉座からおりて自分が相撲をとろうと取組む所作で、ちょっとジャンプをしたところ、脳梗塞で不調となっている左脚のふくらはぎがピシッと微かな音がしたと思ったら肉ばなれを起し、早速医者に行きましたが、これは取り敢えずアイスノンで冷やすだけで、あとは日日薬によるしか術はないということで当日は出演不能となってしまいました。申し合せの次の日が授賞式のリハーサルの日。痛い足を引きずりながら妻に付き添って貰って出掛けましたが此の時、既に皇太后様のお傍らには御近親の方々がお集まりで、三日後の授賞式は約五十年振りの両陛下の御臨席の無い授賞式(前回は貞門皇后崩御の際)となりました。当日は、いかにも慎み深く静かに進み出で、賞状を恭しく頂くという、いとも神妙な演技(?)で、まともに歩けない足をなんとか誤魔化しましたが、両陛下が御臨席遊ばしていらしたら、もっとピーンと張りのある空気となり、式の重み、格というものが違ったであろうと感じたのは私一人ではなかったと思います。ところで、恩賜賞受賞の河竹登志夫さんが授賞式の控室で、終始じっと腰かけている私の所に来て「今日、粟谷さんと会うので新ちやん(新太郎)から頂いたモンブランの万年筆を原稿や作品と一緒に展示室に置きました」と。その昔、新宿の飲み屋で兄と大いに飲んでいたお仲間だったとか。兄が文部大臣賞を受けた時、お祝を頂いたお返しに差し上げたのが此の万年筆だったそうで、思いがけない御縁に暫し若かりし頃の新宿の夜の灯を互いに懐しく思い起しました。人間の治癒能力は三週間……。おかげで肉ばなれも段々治ってきたようです。近頃多い野球選手の肉ばなれの話を聞くと、あながち年のせいばかりではないんだと妙に自己満足している菊生です。
景清を舞うにあたって投稿日:2018-06-07
能楽座パンプレットより
?今回は「景清」を舞われますが
粟谷 「景清」は非常に好きな曲です。先代の六平太先生の当たり芸だったし、特に先生の晩年は、「景清」を舞われることが多かったんですね。ですから私は若いころに型を全部覚えちゃってました。この曲の一番大事なところは、「松門ひとりで閉じて・・・」の謡だと思うんだけれど、その「松門」の謡を、喜多流は強くぼそぼそっと謡うんですよ。装束も他流は着流しで、面も優しい表情のものだけれど、喜多流は大口をはいて強い面をつけて、景清の心境を謡います。ヨワ吟があったりツヨ吟があったりしますが、竹を切って割ったように、ぼつぼつ切って謡えと教えられました。私が四十歳ぐらいで初めて舞った頃は、声がありすぎて非常に苦労するわけ。ところが最近は、今年七十四歳なんだけど、五、六年前からは、そんなことを一切考えないで、そのままの自然体でやっていれば、「景清」が舞えるような気がして、今は苦しみというより楽しみながら勤めさせていただいてます。
?喜多流の謡は狂言の平家節に繋がるような、強くばっと切って謡うというか、他の流儀にはないやり方ですね。
粟谷 そう、六平太先生はぼそぼそっと謡われた。それからうちの親父(故粟谷益二郎)の「松門・・・」の謡もとてもいいと思っているのね。若い頃には、「尾張の国熱田にて遊女相馴れ一人の子を持つ・・・」というところなんかは、ちょっと色っぽく謡おうとして節をつけて謡ったりしたけれど、最近は淡々と謡えるようになってきました。
?「女子なれば何の用に立つべきと思ひ、鎌倉亀が江が谷の長に預け置きしが・・・」というところに、武士の身勝手さとか、断固たる強い生き方が、ばんと出てくるように思うんですけど、以前、壽夫(故)さんの「景清」には、どこか公達のロマンの雰囲気を感じました。喜多流のは非常に男っぽく、女子だから何の役にも立たない、しょうがないから置いて来た、その子が遠く日向まで逢いに来てくれた、その娘に本当は縋りたいのだけれど敢えて帰してしまう、というところが、見事に浮き彫りにされる作品だと思います。
粟谷 最後にツレ(娘)が立ち去って行くところで、シテとツレはすれ違うんだけど、そこで「匂いを嗅げ」って言われて稽古しました。六平太先生が百歳ちかくまで長生きされたお陰で、お稽古に間に合ったわけで、本当によかったと思っています。そのほか友枝為城さん、敏樹さんがなさった「景清」は、六平太先生とはまるで違うんだが、これがまたじつにいい「景清」なんだ。「さてまた浦は荒磯に寄する波も聞こゆるは・・・」というときに立ち上がらないで、ちょっと面を傾けるだけですよ。そんな型をいっぺんやってみたいと思うけれど、よっぽど力のある者でないとできませんね。
?ワキと囃方との関係ではいかがですか
粟谷 作り物の中にじっとしていて、「里人の渡り候か」というところからワキの問答を聞くのが好きなんですよ。道行のところもね。私は余りにも六平太先生のが強烈で、どうしてもそこからとびだせないけれど、近年になって、生意気だけれど、こうした方がいいんじゃないか、ああしたほうがいいんじゃないかなっていうのをつけ加えてやっています。
?子供のころからずっと舞台をみてきて、自然に覚えたものをしっかり見につけ、その上でご自分の思いや工夫を加えていくというのは、凄いことだと思います。
鞍馬の花見投稿日:2018-06-07
「鞍馬の花見」
粟谷菊生
子供が初めて能の舞台に出るのは大抵、鞍馬天狗の「花見」としてです。鞍馬山の東谷という想定の橋懸りを子方の牛若丸を先頭に花見に行く平清盛の子供達。この稚児たちを我々は「花見」と呼んでいます。長袴をはいて舞台にゾロゾロと出てきて、ちょっとの間、座っているだけのものですが、これが初めての能への参画ということで後々まで深く脳裏に灼きつくのです。三歳ぐらいの子供が長袴をはいて出てくると舞台では豆粒みたいで、歌舞伎の子役の初舞台と同じように、それだけで可愛いものです。ワキが「花は明日にても御覧候へ。まづ此の所をば御立ちあらうずるにて候」と花見たちを帰すのですが、先代山本東次郎師の能力(アイ)が「もーし、苦しからぬことにて候」と一人ずつに顔をのぞき込んで言うのを、その大きな声に馴れていない花見の一人が吃驚して立止まってしまい、帰ろうとしないので、あわてて小さな声で「行ってもいいのですよ。歩いていくのですよ」とその子に言って、再び「も-し苦しからぬことにて候」と大声で一人ずつにくり返しました。又、花見の一人が舞台で動けなくなってしまってワキが抱っこして退場したという珍景もありました。喜多流は或る時期、男の子の出生率が非常に低くなった時がありました。これで後に演能の曲目を選ぶに当たって子方の要らないものを探さねばならない事となりました。親が『鞍馬天狗』のシテを演る時に子供が花見として初舞台を踏むというケースが多いのですが。今回春の粟谷能の会では私がそのシテを演じることになりましたが、「菊生先生の『鞍馬天狗』なら」と大勢の花見が出てくれることになり、孫の尚生も子方(沙那王)として出るし、老体は今から心はずませております。私の予知できない未来を握っている此の幼い子供たちに、前の時代から次の時代へと承け渡してゆく伝統というものを如実に見る思いがしますし、喜多流の将来にも明るいものを感じてまことに幸せです。
「上野東照宮新年謡初め」の思い出投稿日:2018-06-07
元旦は各流とも、その流儀の舞台に集まって「謡初め」という行事がありますが、近年までは正月二日に上野の東照宮にて三流合同の謡初めの行事がありました。毎年必ず勤める観世流と喜多流に、一年おきに交替で宝生流と金春流が加わり、三流でこれを勤める慣わしとなっておりました。
正月二日は稀に暖かい日もありますが、概して寒く、夜半からの寒気で冷え切った朝の参道の玉砂利の冷たさをそのまま、下から吹き上げてくる風は拝殿に素砲上下の紛出(いでたち)で列び坐す我々の襟元を刺し、手はかじかんでしまいます。私が子供の頃、先々代観世左近さんが神官の「謡いませ?!!」とのひと声に、間髪を入れず『高砂』の「四海波」を神殿に向かって平伏したまま朗々と謡い続けていらしたのが印象に残っております。続いて『老松』、それから宝生流か金春流の『東北』、最後に喜多流が『高砂』を、それぞれ舞囃子で舞います。そして神官が白い寿服(じゅふく)を観世さんから順に、膝まづいている太夫たちの素砲の肩に掛けてゆき、太夫たちは、それを着けて『弓矢立合』の曲を三流合同の地謡で、三流が同時に舞囃子で舞い納めると いう珍しいものでした。三流で同時に謡うのですから一応は簡単に申合せはするものの、流儀によって文句や発音が違うので、ここは一番大声を発する者の勝ちと、喜多流は馬鹿声を張り上げたものでした。吹きさらしの拝殿は、まことに寒いので、体の中から温めておくようにとの思し召しか、始まる前に御神酒を頂戴します。故亀井俊雄さんが、この御神酒を土器(かわらけ)で何杯もお代りしていらしたのを子供心に妙に憶えています。
いう珍しいものでした。三流で同時に謡うのですから一応は簡単に申合せはするものの、流儀によって文句や発音が違うので、ここは一番大声を発する者の勝ちと、喜多流は馬鹿声を張り上げたものでした。吹きさらしの拝殿は、まことに寒いので、体の中から温めておくようにとの思し召しか、始まる前に御神酒を頂戴します。故亀井俊雄さんが、この御神酒を土器(かわらけ)で何杯もお代りしていらしたのを子供心に妙に憶えています。
戦争が始まり途絶えていたこの行事を復興させたのは観世流の関根祥六さんですが、お弟子さんの地元の世話人の方が亡くなられてからは残念ながら行われなくなりました。
身も心も引き締まる冷たい新春の、清々しい空気の中で勤める上野東照宮での謡初め?
これは今となっては、懐かしい思い出の新年行事となりました。それはともかく、
新世紀も粟谷能の会をご支援、お引き立てのほど宜しくお願い申し上げます。
弓矢立合 写真右より 観世左近 宝生英雄 喜多実
撮影 あびこ喜久三
亀井俊雄氏 写真 撮影 吉越立雄
まづ此度は投稿日:2018-06-07
まづ此度は
粟谷菊生
 来年、二〇〇二年の十二月に喜多自主公演で、『猩々』の能を舞うことに決まりました。まわりから「未だ元気に舞っているじやないの」と云はれ、「十二月の出演者が欠員してしまいましたから『猩々』をお舞いになりませんか?」と云はれて、つい、その気になってしまったのです。僕にとって初めての能は、父益二郎の主宰していた喜扇会で舞った『猩々』でした。それで自主公演での最後を『猩々』で舞い納めるのもよかろうと、お受けしてしまいました。しかし最近、脚力の衰えをとみに自覚している菊生ゆゑ「御酒と聞く」…と竹の葉の酒を汲まぬ内から、ほろ酔い機嫌の猩々となっているやも知れず。今年四月の自主公演で『鉄輪』の能を勤めて、これが自主公演に於ける最後の演能と宣言してしまったにも拘わらず、何事ぞと訝られる方もおありでしょうが、そこは『鉄輪』の最後のことばを思い出して下さい。足弱車の廻り逢ふべき。時節を待つべしや。まづ此度は歸るべしと。というわけで「時節を待つ・・・」のは来年十二月。一年以上先の傘寿の『猩々』を目ざして今は頑張るしかありません。
来年、二〇〇二年の十二月に喜多自主公演で、『猩々』の能を舞うことに決まりました。まわりから「未だ元気に舞っているじやないの」と云はれ、「十二月の出演者が欠員してしまいましたから『猩々』をお舞いになりませんか?」と云はれて、つい、その気になってしまったのです。僕にとって初めての能は、父益二郎の主宰していた喜扇会で舞った『猩々』でした。それで自主公演での最後を『猩々』で舞い納めるのもよかろうと、お受けしてしまいました。しかし最近、脚力の衰えをとみに自覚している菊生ゆゑ「御酒と聞く」…と竹の葉の酒を汲まぬ内から、ほろ酔い機嫌の猩々となっているやも知れず。今年四月の自主公演で『鉄輪』の能を勤めて、これが自主公演に於ける最後の演能と宣言してしまったにも拘わらず、何事ぞと訝られる方もおありでしょうが、そこは『鉄輪』の最後のことばを思い出して下さい。足弱車の廻り逢ふべき。時節を待つべしや。まづ此度は歸るべしと。というわけで「時節を待つ・・・」のは来年十二月。一年以上先の傘寿の『猩々』を目ざして今は頑張るしかありません。
写真 粟谷菊生「鉄輪」撮影 東條 睦
大阪城薪能への寄稿投稿日:2018-06-07
以下は粟谷菊生が大阪城薪能に出演したときに書いたものです。
「巴」によせて 粟 谷 菊 生
ぼくたちにとって、能舞台というものは、三間四方に橋掛りのついた空間であり、長年、それに慣れて能を舞ってきたが、最近は能楽堂以外の場所で能が催されることもあって、たまには臨機応変に能を舞わなければならない場合もある。
何年か前、大阪城多目的ホールの七間四方の大舞台で能が催され、照明つきの船弁慶の能を舞った経験があったが、橋掛かりを行けども行けども舞台に行きつけないのには、度肝をぬかれた思い出があった。
綿入れの胴着の上に装束をつけるので、昔は夏には能の催しはなかったもので、装束をつけない袴能が催されたが、今日では冷房がはいるので、夏でもけっこう能の催しが多い。
野外で催す薪能も各地で盛んだが、陽の落ちかかるころの初番の暑さは格別で、さぞ暑かろうと思うけれども、三時ごろから日傘をさして開場を待って居られる見物の人々の姿を見ると、こちらも暑いなどといってはいられない。
今回舞う巴の能は、名人と言われた十四世喜多六平太先生も好まれ、私も大好きな曲で、これまで何回となく舞い、弟子たちにも数々舞わせてきたものだが、その体験を基にして考えると、この曲の見どころは、巴が床机に掛けての型どころ、立ち上がって長刀をふるう奮戦の場面、義仲との別れの場面など、いくつかを挙げることができるだろう。ぜひそれをとっくりと見ていただき、この曲によせるぼくの思いを知っていただきたいと思う。
最後に、巴が落ちて行くとき、流儀によっては装束を変えないこともあるが、喜多流では後見座にくつろぎ、白水衣壺折りに替え、形見の小太刀を衣に引きかくし、笠を傾けて落ちてゆく演出となるが、その姿には、いっそう哀れ深い思いがあると思う。
絵馬によせて 粟 谷 菊 生
今日の絵馬半能(中入(なかいり)後半の部だけの演能)になっております。
後(のち)ジテは天照大神なのですから、当然、女性の筈です。他流では増(ぞう)女の面をかけるのですが、喜多流では常の絵馬というと(つまり小書なし)東江(とうこう)という面をかけて、何故か、男体として扱われております。今回は小書きで「女体」となっているので私は愛用の小面をかけ、天女(天鈿女(あめのうずめの)命(みこと))と力神(手力雄(たぢからおの)命(みこと))を従えて出ます。昔、小書なしの絵馬を演じた時、男体としてツレの天女を二人随えて出て行ったので「後ジテは手力雄命かと思った」と仰云った方がいましたが当然でしょう。演じている私自身が非常に奇異に感じたのですから。何故喜多流では男体として扱われているのか、これには諸説あるようですが定かでは無いので、ここでは申し上げない事にします。
この曲は囃子方泣かせで、一曲全部演った場合には、大小(大鼓・小鼓)共にワキの出から打ち始め、道具を下に置くことのない、そして後(のち)の出からも打ちっぱなしなのです。シテが「急」の五段の神舞(他流では中の舞)、ツレの天女が神楽(かぐら)の前半を、力神が位の極めて早く力強い後半を舞い、その上、中入後の間(あい)狂言(きょうげん)も蓬莱の島の鬼の舞があり…と息のつく暇も無い大変な曲なのです。
今回はシテの五段の神舞は三段にさせていただきます。「天の岩戸に閉じ篭もって……常闇の夜のさていつまでか」と謡う地謡に、前面に扉がついて幕を引き廻した天の岩戸を模した作り物の中に入るのですが、初番の陽の未だ落ち切らぬ夏のさ中、装束をつけて、あの狭い引き廻しの幕の囲いの中に入るのは、さぞや暑かろうと今から覚悟してます。
シテ、ツレ、三者三様の舞が見どころでしょうか。ともあれ、日本人のルーツとも云うべき天照大神の天の岩戸の故事に據るこの〈絵馬〉を今日の薪能の幕開けに楽しんでいただければ幸です。
地謡について投稿日:2018-06-07
初めて能を見ようとする方や、能とはどんなものなのか、とお尋ねの方に説明するのは、「オペラのようなもの」というのが一番判りやすいようです。外国の方だけでなく日本人にも、そう言うと直ぐに納得していだけるのは、まことにおかしな話ではあります。つまり日本人も、日本のクラッシック芸能より西洋のクラッシック芸能の方が良く判っているということで、オペラは常識的な知識としてインプットされ、日本の能といったら皆目見当がつかないという人々が大半ということがオカシクもあり、日本人として、ちょっと悲しくもあり…というところでしょうか。 ところで今回お話しようとする地謡はオペラのコーラスに当たります。但し能の地謡には必ず地頭(じがしら)がおります。つまりコーラスリーダーですが、地頭の良し悪しで地謡が良くも悪くもなるのは当然です。そしてこの地謡が良いか悪いかでその時の能の良し悪しも決まります。地謡が良ければシテは演じ易く、囃子方も大いにノッテ、技を発揮しようという気にもなってくるのです。
ところで今回お話しようとする地謡はオペラのコーラスに当たります。但し能の地謡には必ず地頭(じがしら)がおります。つまりコーラスリーダーですが、地頭の良し悪しで地謡が良くも悪くもなるのは当然です。そしてこの地謡が良いか悪いかでその時の能の良し悪しも決まります。地謡が良ければシテは演じ易く、囃子方も大いにノッテ、技を発揮しようという気にもなってくるのです。
地謡は通常、8人が舞台に向かって右の地謡座というところに座ります。喜多流では後列の客席に近い方から数えて2人目が地頭の座る位置、流儀によっては笛座に近い方から数えて2人目が地頭の座る位置となっている場合もあります。
素謡(能一曲を謡だけで奏す)の時は喜多流は膝の上に扇を両手で持って謡いますが、能の時は各流通じて右手に持った扇を立てて謡います。この扇を立てて持つまでの作法は各流異なります。
地謡は情景や物語の運び、故事来歴等を謡うのですが、脇やシテの科白となる部分を謡うこともあります。
ここで又ちょっと面白いお話。宮島の桃花祭(毎年4月16日?18日)の時、厳島神社で御神能という奉能があります。初日と3日目のが喜多流、2日目が観世流の受け持ちで行われていますが、素人でも御榊料をお納めして能を舞ったり、地謡にも出ることが出来ます。4?5年前、我も我もと地謡に出る希望者が多く、前列と後列共に10人ずつ、気がついたら脇座のところ迄座ってしまっていて、脇が出ていったものの座る場所が無かったなどということや、地謡同士が舞台や楽屋で日頃着慣れない長裃の裾を踏み踏まれ、つんのめっては危うく転びそうになったりという事がありました、子供の頃から長年親しみを以てそう呼んで来た「宮島さん」の御神能ならではの珍景です。
(写真 地頭 粟谷菊生 撮影 宮地啓二)
わが安住の地投稿日:2018-06-07
わが安住の地
粟谷菊生
自分の意に副わぬ職に就き、満たされぬ思いの内に日々を過して「安住の地」という望みを未来にかけるか、又は手の届かぬ、はるか彼方の夢として生きている人も、世の中には少なからず居られると思うが、その点、私は何という幸せ者だろう。私は舞台の上に在る時、最も安住を感じられる時間と空間を持つことが出来るからだ。安らぎの場と云えば誰しも、先ずは家庭と思うだろう。無論、私も家にいる時はタガがはずれたように人一倍だらしのない為体で、注意力は散漫、やりっぱなし族のグータラ亭主をきめこんでいる。気の移り易い私はテレビを見ていても矢鱈にカチャカチャとチャンネルを変えて妻にイヤな顔をされたり、頭の中は雑念だらけ。しかし、ひとたび舞台に上がると何故かたくまずして、全集中力で、神経はその舞台に統一できてしまうのだ。新曲や稀曲に取り組むとき以外は、快い緊張感こそあれ、能という大きな傘の下で安住の地に居る心地に浸っていられる。能そのものに歿入し、全身全霊が集中していられる雑念の無い此の世界は、私にとって、何ものにも代え難い最も「安住の地」を感じる時であり、場所である。そしてまだ此処に自分を必要としてくれる舞台があるのだと思える悦び。いつかは頭も体もダメになって、この「安住の地」を去らねばならなくなる時が来るであろう。が、それは今は考えないでおこう。来し方を顧みて幸せな人生だったとつくづく思い、ただただ神に感謝だが、日本はまことに八百萬の神の国、四方八方に頭を下げて御礼を申し上げたい。「菊生の”日本は八百萬の神の国”発言」などと物議をかもすかも知れないが、日本人は生れ出づれば両親や祖母に抱かれて産土神に詣で、七五三になれば氏神様に手を引かれてお詣りし無事に育ってきたことを感謝し、これからも健やかであれと柏手を打つ。私の住む能の世界に至っては、イザナギ、イザナミノミコトから始まって、神を主人公として神社の縁起や神威を説き、国の繁栄と御代を寿ぐという曲目が多数あって、神とは切っても切れない仲。私は無宗教、無信心に徹している人間ではあるが、神社に詣でれば心を込めて感謝と、これからもお守り下さるよう諸々のお願いをする。それは自分の能の事、家族の事、その他、気にかかる人々の事等々。但しゆっくっり出来ない時は、ときどき「神様のことですからお判りでしょう?いつものとおりです」と端折ってしまうこともある。そうそう、最後にウチのヤマノカミにも感謝しておきましょう。心の底の底では、これでけっこう安住させていただいているのですから。
桜投稿日:2018-06-07
来年も 此の桜 また見れるかと
年々おもう 年齢(とし)となりけり
と僕の心を妻に詠まれてしまったが、この数年来、家の前の桜並木の花を見上げては、本当に、毎年、そう思うようになった。
昭和四十四年、見渡す限り何もないようなキャベツ畠の中に家を建て、風が吹くと関東ローム層の赤土が舞い上がり、一日に何回も掃除しなければならないと妻がボヤいていたが、その内どんどん家も増え、区が道を舗装して桜まで植えてくれて、短い距離ながら「桜通り」と名づけられてから、もう何年になったろう。
はじめは、ひょろっとしていた細い幹が一抱えもあるように太くなり、毎年見事な花を咲かせ、花の散った後は青葉を繁らせてくれる。染井吉野の並木の中、うちの前の一本だけが八重桜だ。或る年、台風で家の前の桜が我が家の方に傾いてしまった。区の担当と思われる所に電話したところ、早速来てくれたのは良いが、幹に縄をかけてトラックで引っ張った。ナント乱暴なこと! その桜は可愛そうにメリメリと音を立てて折れてしまった。そして、その後に何故か八重桜が植えられた。天に向かって上に伸びる枝々から幾重にも花びらを重ねた八重桜の花はポッタリと下に向いて咲いている。
妻は染井吉野の方が好きというが、僕はいつの間にか此の濃い桃色の八重桜に愛着を持つようになっている。何か艶なる色気を感じてしまうのだ。悪く言えば爛熟した年増の色気か? とは言っても女性に対する僕の好み、いまの言葉でいう、「タイプ」は必ずしもそうではない。念の為(ため)。
八重桜は遅れて咲くので、夜タクシーで帰る時「一本だけ花の咲いていない木の前で止めて下さい」とか、染井吉野が散ったあとは「一本だけ花の咲いている木の前で止めて下さい」…と。ほとんど毎夜アルコールの入っている老人は、舌のもつれを悟られまいと正しく発音するよう、無駄な抵抗かもしれないが、それでも懸命な努力を口の筋肉に課して、運転手さんにそう告げる。では花の咲いていない時季は?
「路面に30kmとペイントしてある上で止めて下さい」と、この時ばかりは、ちょっと英語など使ってみるのであります。満開の桜、花吹雪、八重桜、僕は心ゆくまで上ばかり見て楽しんでいるが、下ばかり見て、散った花びらを掃き集め、毎日のように大きな袋に入れてゴミの日に出さねばならない人の労苦は、嬉しがってばかりもいられないらしい。雨の日は散り敷いた花びらに滑りそうで老人は殊に御用心! それでもやっぱり桜はいいですなあ。日本人だとしみじみ思う。
大鼓について投稿日:2018-06-07
大鼓はオーツヅミともオーカワともいいます。大鼓は「皮を焙(ほう)じる」といって、大火鉢に備長の堅炭を真っ赤におこして皮を焙(あぶ)り、カンカンに乾燥させます。それを男の強い力で思いっ切り締め上げる・・・そういう手間が掛かるので他の囃子方よりも、ずっと早く楽屋入りせねばなりません。昔は素手で打った方もいて、その音色は捨てがたいものがありましたが、今は皆、指皮(ゆびかわ)をつけて打っています。
小鼓を打つ人の袴の縞は細く、大鼓の袴の縞の幅は太めで、両サイドの笛と太鼓は無地に近いようなごく細い縞を用いると言われておりましたが、今はそれは守られておりません。僕の若い頃には、川崎九淵先生、亀井俊雄先生、安福春雄先生、瀬尾乃武先生・・・と何れも名人と言える素晴らしい方々がいらっしゃっいましたが、今もこの分野の方々が先人たちの立派な芸を受け継いで活躍しているのは頼もしい限りです。 安福先生には、その頃若かった僕は大変可愛がって頂きました。よく飲みに誘ってくださいましたが、したたかに飲んでは、大事な衣装鞄を盗まれることしばしばで、なんとあのアラン・ドロンが「サムライ」という映画の中で安福先生の紋付を着て出ていたのです。紋所が「丸に洲濱」だったので直ぐ判りました。世の中が今のように豊かではなかったので泥棒は中のものを期待して盗ってゆくのでしょうが、宝石箱のような小箱は開けてみてさぞガッカリしたことでしょう。中に入っていたのは指輪ではなくて指皮だったのですから。盗まれた紋付が、どういう経路でそこまで行ったのかは判りませんが、安福先生はお背が高かったので、廻り廻ってドロンが着ることになっても寸法は合ったようです。風貌も、ちょっと欧米人的で、昭和二十九年、能の初めての海外公演となるベネチア国際演劇祭にご一緒に参加した時のベニスで撮った僕と二人のスナップ写真などは、先生を知らない今の人に見せると「この人は外人?」と訊かれる位です。体格の良いことではその時代、小鼓の幸圓次郎先生(幸清次郎氏の父上)は大兵肥満型でしたが、このお二方の大鼓、小鼓と笛の寺井政数先生との組み合わせによる修羅物の後場などのお囃子は聞いていて、ワクワクしたものでした。今は昔・・・と思い起こす懐かしい舞台シーンです。
安福先生には、その頃若かった僕は大変可愛がって頂きました。よく飲みに誘ってくださいましたが、したたかに飲んでは、大事な衣装鞄を盗まれることしばしばで、なんとあのアラン・ドロンが「サムライ」という映画の中で安福先生の紋付を着て出ていたのです。紋所が「丸に洲濱」だったので直ぐ判りました。世の中が今のように豊かではなかったので泥棒は中のものを期待して盗ってゆくのでしょうが、宝石箱のような小箱は開けてみてさぞガッカリしたことでしょう。中に入っていたのは指輪ではなくて指皮だったのですから。盗まれた紋付が、どういう経路でそこまで行ったのかは判りませんが、安福先生はお背が高かったので、廻り廻ってドロンが着ることになっても寸法は合ったようです。風貌も、ちょっと欧米人的で、昭和二十九年、能の初めての海外公演となるベネチア国際演劇祭にご一緒に参加した時のベニスで撮った僕と二人のスナップ写真などは、先生を知らない今の人に見せると「この人は外人?」と訊かれる位です。体格の良いことではその時代、小鼓の幸圓次郎先生(幸清次郎氏の父上)は大兵肥満型でしたが、このお二方の大鼓、小鼓と笛の寺井政数先生との組み合わせによる修羅物の後場などのお囃子は聞いていて、ワクワクしたものでした。今は昔・・・と思い起こす懐かしい舞台シーンです。
傘寿、目の前投稿日:2018-06-07
傘寿、目の前
粟谷菊生
 年をとるというのは大変なコトなんだ、高齢になって生きている人というのはエライんだ・・・とつくづく思うようになった。
年をとるというのは大変なコトなんだ、高齢になって生きている人というのはエライんだ・・・とつくづく思うようになった。
吉行あぐりさんのような方は稀有だと思う。九十九.九%の人は高齢になるに従い、何らかの故障が身体に出てくる。頭にも、肉体にも。一度つまずくと、多くの場合その支障を引きずって多かれ少なかれ苦痛と闘いながら生きて行かなければならない。
僕も四年前に自分の不注意と、まずい巡り合わせで脳梗塞になり、左脚に不自由を感じるようになった。言語に支障を来さなかったのは好運というか、神様のおはからいに感謝せねばならないが、脚のハンディを克服して舞台で舞うことは、その都度ギリギリ精一杯、渾身の闘志で立ち向かうしかない。いつも、これが最後だ、これが最後だ・・・と思ってしまう。自分の思うようにならない肉体をカバーするため、謡には、これまで以上の・・・もちろん、今までだって謡には常にベストを尽くしてきたつもりだし、又僕にとっても謡は大好きなので、おろそかに謡ったことは一度も無いが、・・・それでも謡の一言一句を、これまで以上に万感の思いを込めて、表現し得る最大限のものを出そうと、真底そう思って謡っている。
はてさて、こんなことを字に書いてしまっては、僕自身、なんだかふうっと拍子抜けしてしまう感じ。何故なら演じている時は、そんな客観的な思考などは、まるで無く、ただただ全身全霊、一丸となって、そのものになり切っているだけなのだから。ただ以前と違って観てくださっている方々に、肉体の支障を感じさせないようにしようと細心の配慮を必要とし神経をも使わねばならなくなっていることは事実だ。そこで加齢の悲嘆をしみじみ味わっているわけだが、生きとし生けるもの必ず終わりはあるので、老木のあとには若木が萌え出るのは理の当然。息子、孫、甥、そして流儀内の若手たちが、ぐんぐんのびてくるのを見るのは心強い。あと五年は生きてくれと息子と甥に言われている。新太郎の七回忌や益二郎の五十回忌の追善能をしたいからと。自分自身は明日死んでよいと思っているが、伝えておかねばならない事もまだまだあるのが、もう少し生きながらえさせて貰うよすがとなろうか。
妻には「死ぬのは、ちっとも怖くはないが貴女に逢えなくなるのが淋しいし、イヤだなあ!」と云った。こういう言葉を私の年代の者がぬけぬけと言えますか?言えないでしょう。日本の古き夫たちよ、もっと素直に心の内を妻に表現しなさい!でも、こう僕が言った時、我が女房殿は「その科白(せりふ)、どこで覚えていらしたの?」・・・そして何秒か間をおいて「それ何人に仰ったの?」・・・と。ギャフーン!
写真「頼政」粟谷菊生 撮影 三上文規
粟谷菊生は古今亭志ん生投稿日:2018-06-07
1年前ですが、ピープルNo.32 能・芸・人に粟谷菊生が石淵文栄氏にインタビューされていました。遅ればせながらご紹介します。
太鼓について投稿日:2018-06-07
このホームページの「囃子方の楽器」の最後は、お能で最後に登場する太鼓です。
太鼓方は観世流と金春流の二流がありますが、金春流宗家の金春惣右衛門氏と僕とは、竹馬の友であり、観世流宗家の観世元信氏とは1954年日本初の海外演能となる、ベネチア、ビエンナーレ国際演劇祭に御一緒に参加した仲で、この名人達者のお二人に育てられた人達が今、立派な舞台を勤めている事は心強い限りです。
さて、太鼓は一目瞭然、嵩(かさ)、目方、共に一番大きく、昔は弟子に持って貰える少数の人以外は、持ち運びがなかなか大変でした。今は車のついた旅行用の鞄を用いたり、自分の車で移動出来る便利な時代になりました。 戦争中(第二次世界大戦)、食物が欠乏し、お米を手に入れるのも容易ではなかった頃の面白い話を一つ。能楽師も御多分に洩れず、ひもじい思いをしておりましたが、お勤め料(出演料)が「お米で何斗(と)」(斗は一升の十倍)という時もありました。これは当時は有り難い話なのですが、食糧の配給制度下のことですから、正規のルート以外にお米が流れるのは御法度で、折角頂戴したお米も、無事持って帰ってこられるかどうかは、その時の運次第。厳しい検閲にひっかかって没収されてしまうのです。ところが不思議ことに、無事通過してお米をしっかり持ち帰る人が二人いました。一人は先々代家元の故喜多六平太先生と、もう一人は金春流太鼓の柿本豊次先生。六平太翁は長い靴下にお米を入れてご自分のふんどしにぶらさげてくるのです。想像しただけでも滑稽ですが、小さな身体の老人が少々おかしな歩き方をしていても疑われなかったのでしょう。一方、柿本先生の方は、太鼓の胴にお米をしこたま詰め込んでくるのですが、警官は太鼓が本来どの位の目方のものなのか、知る由もありません。平素、お荷物になって申し訳なく思っている太鼓が思はぬところで、ご主人様のお役に立って「太鼓の恩返し」というところでしょうか。
戦争中(第二次世界大戦)、食物が欠乏し、お米を手に入れるのも容易ではなかった頃の面白い話を一つ。能楽師も御多分に洩れず、ひもじい思いをしておりましたが、お勤め料(出演料)が「お米で何斗(と)」(斗は一升の十倍)という時もありました。これは当時は有り難い話なのですが、食糧の配給制度下のことですから、正規のルート以外にお米が流れるのは御法度で、折角頂戴したお米も、無事持って帰ってこられるかどうかは、その時の運次第。厳しい検閲にひっかかって没収されてしまうのです。ところが不思議ことに、無事通過してお米をしっかり持ち帰る人が二人いました。一人は先々代家元の故喜多六平太先生と、もう一人は金春流太鼓の柿本豊次先生。六平太翁は長い靴下にお米を入れてご自分のふんどしにぶらさげてくるのです。想像しただけでも滑稽ですが、小さな身体の老人が少々おかしな歩き方をしていても疑われなかったのでしょう。一方、柿本先生の方は、太鼓の胴にお米をしこたま詰め込んでくるのですが、警官は太鼓が本来どの位の目方のものなのか、知る由もありません。平素、お荷物になって申し訳なく思っている太鼓が思はぬところで、ご主人様のお役に立って「太鼓の恩返し」というところでしょうか。
ちなみに金春流と観世流では胴の大きさが違います。金春流の方が胴の高さが少し高いのです。従って締め方も違って、金春流は舞台の上でも締め直すことがあります。しかし今は観世、金春共に道具の画然とした使い分けは無くなっているようです。
(写真 柿本豊次氏「吉越立雄写真集 直線の美」より)
『芭蕉』によせて投稿日:2018-06-07
『芭蕉』によせて
粟谷菊生
 謡曲の文章というものは何れも美しく優れたものではあるが、『芭蕉』のそれはとりわけ胸を打つものの一つだと思う。ワキのサシコエ「既に夕陽、西に映り…」から始まる情景描写には寂寞たる山陰の迫り来る夕闇と冷気を自ら覚え、シテの次第の「芭蕉に落ちて松の声…」以降の詞章にはその味わい、美しさにふっと静かな感動を覚えるのは人生の晩年に在る身の殊更の感慨だろうか。
謡曲の文章というものは何れも美しく優れたものではあるが、『芭蕉』のそれはとりわけ胸を打つものの一つだと思う。ワキのサシコエ「既に夕陽、西に映り…」から始まる情景描写には寂寞たる山陰の迫り来る夕闇と冷気を自ら覚え、シテの次第の「芭蕉に落ちて松の声…」以降の詞章にはその味わい、美しさにふっと静かな感動を覚えるのは人生の晩年に在る身の殊更の感慨だろうか。
花も色も無い、微塵たりとも色っぽいものは入らぬこの三番目物の凄まじいまでの冷たさ、寂びた寒さの中にあるこれほどの優雅さは一体何なのだろう。
僕は『芭蕉』の能を舞ったことが一度も無い。良い曲だとお思いながら長いこと、いざ何を舞おうかという時は、きまって『羽衣』『班女』『湯谷』『松風』のような華やいだ色っぽい「可愛いい女」のものに、つい走ってしまう。自分はいつまでも若いような気になっている呆れた錯角を持ち続けていたのかもしれない。或いは『隅田川』『景清』『鬼界島』のようなものを、つい選んでしまうのだが温かい情味のあるものが好きなのは、これはもう僕の体質のなせるわざかも知れない。そして又それらのリクエストが断然多いのも確かだ。そのくせ、あまり演じられた事のない『羅生門』のような能の依頼がくれば、いやとは言わず引き受けてしまうし、うちの流儀では四、五十年途絶えていた『梅枝』のような曲を演ってみたりもするのだが…。
この齡になるまでには、やはり随分といろいろな曲目を沢山舞ってきている。にも拘わらず、この『芭蕉』は何故か自分がシテとして舞った事がなかったのだ。『芭蕉』の地頭を最初に勤めたのは昭和五十八年、兄、新太郎がシテの舞台だった。その時の『芭蕉』は気負いや衒いの全く無い、アクの抜けた、枯れ寂びた芭蕉の葉を見る思いのする、『芭蕉』の曲そのもので素晴らしかった。そしてこの度、平成十五年度春の粟谷能の会では兄の息子、能夫の『芭蕉』。何十年かの隔たりを思い、走り去る歳月の早さに今更ながら愕然とするが、こうして傘寿を過ぎて今また甥の地頭を勤められるのは幸せと言わねばなるまい。兄がこの曲を舞った齡に比べると能夫は、はるかに若い。彼は菊生叔父が地頭をしてくれるうちに…という計算であったかもしれない。結構、結構。何はともあれ、僕は謡が好きなのだから。
こういう謡い甲斐のあるものを謡えるのは、或る種の緊張感と充実感があり、張り合いもある。この長く静かな重い曲を精魂込めて謡いたいので僕は仕舞『山姥』を舞うことにした。
父子二代の『芭蕉』の地頭を勤めるのは、まことに感無量であるとともに、これが兄への供養にもなると思っている。
写真 粟谷菊生「通小町」 撮影 東條睦
阪大機関誌「邯鄲」への寄稿投稿日:2018-06-07
「ちょっと一言」の更新が停滞していて申し訳ございません。そこで阪大機関誌「邯鄲」への寄稿文を記載しますので、ご覧下さい。
「邯鄲36号」へ
18,9歳でストレートで入学し、阪大喜多会に入部した人々も、そろそろもう58、9か?還暦に近い方もいる筈。この中には現在、大阪菊生会のメンバーになって「昔とった杵柄」を発揮している方々もいる。 3月の大阪菊生会で舞囃子『松虫』を舞った阪大喜多会第一期生の福田全克君の舞台を見た明生は「おやじさんそっくりだった!!」と言っていた。勿論彼は器用でもあるのだが、如何に阪大の稽古は密度の濃いものであったか。集中力の塊のような状態の作れる若い時代に、良い稽古を受けると如何に好ましい結果を得ることが出来るか(尤も、こういう集中力があったればこそ阪大に入れたのかも)。何もない新しい土地に植林したのが今、漸々、緑の枝を繁らせ始めている。阪大喜多会の来し方をゆくりなく思い起こし、長い年月、自分のやってきたやり方は間違っていなかった。欲望なしに、いつの頃からか交通費を頂戴するだけで教え続けてきた、その実りの果実が今、自分の掌の中にそして良き報いの温もりがそこはかとなく胸の内にひろがっているような思いをしみじみ感じている。
4月に馬鹿げたことで脚のバランスをくずし転倒、尻餅をついたあと、頭を打つまいとしてコンクリートの地面に背中を強打し、寝返りも出来ない程の痛さに呻吟し続けたが、二ヶ月経っても、もとのようにはならず、阪大の稽古に行っても、これが理想の型だ、動きだとお手本を示して見せることが出来ないのが何とも残念、無念、腹立たしい限りだ。父益二郎は67歳で亡くなったので僕もその年齢で他界ということになるだろうと思っていたが、それから15年近く生きてしまった。妻に「生きて十三回忌をめだたく通過しましたね」などと言われるが、今や正真正銘の御老体と相成り、時々電車で席を譲られ、そのご親切に有り難きことと感激しながら、傍らから見てもそんなに老いとるのか……と淋しくもなる。かと思うと「八十過ぎて面をつけて舞台に立って、実際に舞っているシテ方はいない」と豪語してみたり……。完全な幕引きまでの狭間にあっての暫し揺れ動くアガキと言ったところか。
前号で「阪大喜多会は永遠であれ」と言ったが、孫の尚生が大きくなって、明生の教えた阪大生やOBを見て「パパにそっくり!!」と言ってくれるような時がくるといいなァ!と。こうなるともう好々爺の面持ちですね。 平成16年6月15日 粟谷菊生
小鼓について投稿日:2018-06-07
小鼓というものは黙って前に置いて持たせると、大抵左手で持って左の肩にもってゆくものです。テレビのコマーシャルで綺麗なお嬢さんが実際そうしているのがありましたが、正しくは左手で持った小鼓は右の肩の方に持ってゆき右肩に一寸かけて、右手を下から上に向かって打つのです。地球の引力に逆らって打つ打楽器は小鼓だけではないでしょうか。小鼓の皮は馬の皮で、特に馬の腹部の皮が最良とされています。そして調子皮といって、皮の振動を加減するために皮の裏に一糎角程の小さな鹿の皮を張ります。それで小鼓は馬鹿皮ということになります。親の代に皮を張って打ち込んで、本当に鳴るのは孫の代だといいます。二枚の皮の間には胴があります、この材質は何だろうか?
こう覚えてください。馬は、皮が小鼓に、肉は馬刺に、なります、ですから胴はさくら(桜)です。
夏の全国浴衣会投稿日:2018-06-07
夏の全国浴衣会
粟谷菊生
 毎夏、各地で行われる菊生会全国浴衣会も今年で第三十五回。初回は昭和四十三年、高野山の密巖院で私も四十五歳の男盛り。お弟子さん達も皆若かったが、今ではもう卒寿になられた方もいらっしゃるし、既に鬼籍に入られた方もおられる。しかしこの三十五年間浴衣会で大勢の社中が集まるのに一度の事故も無かったというのは奇跡のようなものかもしれない。全国から参集する会員は多いときは百名を越す。旅館の大広間を借り切っての二日間の謡会と三日目の観光。毎年七月の第一土、日、月曜と決めている。初日は現地に到着後午後一時から始まり、翌日は昔は朝六時から初めていたが、明生の勧めで最近は七時から、夕方五時半まで終日、謡と仕舞と、時には連調もある謡漬けの一日となる。明生もはじめは、なんで朝早く六時に開始するのかと不服だったが、いざ自分の社中を参加させてみると、やはりなるべく多くの方に謡ったり舞ったりして頂きたいと思うようになるのが人情で、必然的に朝七時開始というプログラムをいつのまにか自分で作ってしまっている。
毎夏、各地で行われる菊生会全国浴衣会も今年で第三十五回。初回は昭和四十三年、高野山の密巖院で私も四十五歳の男盛り。お弟子さん達も皆若かったが、今ではもう卒寿になられた方もいらっしゃるし、既に鬼籍に入られた方もおられる。しかしこの三十五年間浴衣会で大勢の社中が集まるのに一度の事故も無かったというのは奇跡のようなものかもしれない。全国から参集する会員は多いときは百名を越す。旅館の大広間を借り切っての二日間の謡会と三日目の観光。毎年七月の第一土、日、月曜と決めている。初日は現地に到着後午後一時から始まり、翌日は昔は朝六時から初めていたが、明生の勧めで最近は七時から、夕方五時半まで終日、謡と仕舞と、時には連調もある謡漬けの一日となる。明生もはじめは、なんで朝早く六時に開始するのかと不服だったが、いざ自分の社中を参加させてみると、やはりなるべく多くの方に謡ったり舞ったりして頂きたいと思うようになるのが人情で、必然的に朝七時開始というプログラムをいつのまにか自分で作ってしまっている。
昔、朝五時頃から起き出し各部屋を起こしてまわるという奇特な御仁もいらっしゃって、ご婦人方はお化粧、身繕いと男性より大変な筈だから、おちおちゆっくり寝てはいられないのだろうと推察する。
印刷された番組は一応、各自に配られてはいるのだが番組通りに進行しないのが、この浴衣会のコワーイところ。番組通りだと自分の出番はまだまだ先だと、ひそかに抜け出して自分の部屋でちょいっと御午睡、あるいはほんの少し外へお散歩に…などと出来るわけだが、そうはさせない。番組の順序には全く頓着なく突如掲示板に出ている順序を僕が変えるから油断も隙もあらばこそ。此の実に絶妙なアイデアにユニークな組立式移動掲示板を考案作成して下さったのは山口の吉田隆次氏のお弟子さんで、毎回、非常に重宝させて頂いているし、浴衣会の名物となっている。夜の宴会は、勿論壮観だが、各自の部屋に引き上げてからのお喋りもまた楽しみなのではないだろうか。
振り返ると、あんな所にも、こんな所にも、そして、あんな事もこんな事も…と思い出は盡きない。明生会と合併して行くようになって何年になるだろう。菊生会明生会両方の社中同志が交流し、東京と地方の方々との交流も深まる。
地方にこんな謡の名手がいらっしゃったのか…とか、あの方は随分と御上達なさったとか、新鮮な刺激や感動を覚えて下さることもあると思う。また、地方から東京に観能にいらしても能楽堂で知己に会えるのはなんとなく温いものが感じられるのではなかろうか。いずれ明生が引き継いでくれるだろうが、一年でも長くこの浴衣会が続くことを願っている。
写真 鬼界島(シテ粟谷菊生 平成12年 粟谷能の会)
さて行李(コーリ)よ!投稿日:2018-06-07
「今更さこそ、悔しかるらめ、さて懲りよ」まさに『鉄輪』の文句。人には散々「転ぶなよ転ぶなよ」とエラそうにご注意申し上げていた僕が、何と行李など持って転ぶとは。ええ何とも忌々しきことを。今更さこそ悔しいのなんのって。
余りにも愚かしき所業による報いのもたらした苦痛の大きさ。語るもお恥ずかしき事ながら、持たなくてもよい重い行李をタクシーのトランクから自分で運ぼうとして(因みに運転手さんは軽い方の衣装鞄を持って)喜多能楽堂の楽屋口の階段脇で行李を一先ず下に置こうとした途端、脚のバランスを崩し尻餅。頭を打たないようにと背中を着いたつもりが、したたかに背中を打って転倒。暫くは起き上がれぬままコンクリートの上に横になっていた。女房にやっと助け起こされ、何とか楽屋に入ったものの、あまりの痛さに内弟子部屋で四つん這いになったまま。とにかく病院へと。今まで何度も入院し現在も月に一度は検診に行っている済生会中央病院に連れて行かれ、レントゲン検査の結果は異常ないとのことで、医師は「安静に」と仰ったが舞台に戻り、痛さをこらえて、明生会の社中の『蝉丸』『道成寺』を気力で謡い、番外仕舞の『籠太鼓』を事件を知らぬ人々には全くそれと気付かせぬ舞を舞い納めてヤレヤレ。
然し四週間を待たず、高知の粟谷会で仕舞『海人』を舞い、広島薪能で明生の奉納の『田村』の地頭を勤め、山口に廻り稽古をつけ一旦帰京、一ヶ月振りの東京のお弟子さんの稽古を一日やって、次の日は大阪へ。なんで四十代と同じこんなハードスケジュールになってしまったのか…とぼやきながら、五月二十一日のユネスコによる第一回世界無形文化遺産の能の会の『景清』はこれ又死に物狂いの舞台となってしまった。
はじめの内はやさしく和吟の心で対応してくれていた妻も、僕が少しづつ回復してゆくにつれ、声も強吟へと変わってゆく。妻に言わせれば「やさしくしていると、いつまでもいい気になって甘ったれているから…」とのこと。「幼稚園の年少組のままでいいわけないでしょう?」と。妻の色分けは謂わば僕の回復度のバロメーター。
世の中には八十歳で、或いは九十何歳になっても鍬を振り畠を耕したり、米俵を担いだり、こんなに元気元気と毎日テレビに出てくる矍鑠(かくしゃく)たる老人たちを見ていると、つい自分もそんな気になってしまったのが運の尽き…。ナァンテ悪い事はみんな他人のせいにする僕だが、今回こそは、自分自身に「今更さこそ。悔しかるらめ。さて懲りよ、思い知れェ!」というところです。僕としましては充分過ぎるぐらい後悔してますよ。懲りました。懲りました。
能は笛で始まり笛で終わる投稿日:2018-06-07
能で使われる楽器は四拍子といって笛、小鼓、大鼓、太鼓の四種あり、笛はこの中で唯一の旋律楽器です。三月三日の雛祭りに飾られる五人囃子に扇子を持っている人形が一人居ますが、あれは謡を謡っていて、他の四人を見ると、それぞれの楽器がお判りになるでしょう。演能開始前に、鏡の間で先ず「お調べ」といって楽器の調整(チューニング)をいたしますが、笛から始まり、続いて小鼓、大鼓、太鼓の順となります。
揚げ幕を片幕にして橋掛りから舞台に入るのも笛方からです。笛方が後座に入る頃に地謡(コーラス)が切戸より登場し、笛方が笛座についた後に地謡の先頭から順に地謡座に座わります。
能は笛の吹き出しで始まり(時に例外の曲もありますが)最後も笛の音色で終わりとなります。そして退場は、まず笛方が立ってから地謡も立ち上がります。
囃子方、地謡方の人々が全て舞台より立ち去って、その曲の舞台は完全に終了したということになるのです。
地謡の前列右端は笛柱を挟んで笛と最短距離にあります。
私が少年だった頃、忘れもしない靖国神社の奉能の時でした。地謡の中で最年少だった私が、そこに座っていて一曲が終わったので立ち上がろうとすると、「坊や、笛より先に立つんじゃない!」とお笛の偉い先生に一喝されたことがありました。
武田信玄のようなお顔をした、島田巳久馬先生でしたが、ある時「江口」の地謡を謡った私に、その同じ先生から「坊や、いい謡を謡ったね」と誉められました。これは今でもはっきり覚えているほどで、とても嬉しかった。
叱るときは叱る、誉めるときは誉めて励ます。今はこういう事が世の中全般にわたって無くなってきたと思います。
島田先生から受けた此の二つのことばは、この年になっても心の中に深く残る忘れ難いものとなっています。
島田巳久馬
1889(明治22年)?1954(昭和29年)笛方一噌流 熊本生まれ
正木利三郎 十二世一噌又六郎に師事、1938(昭和13年)より宗家代理を勤めた
派手な大島投稿日:2018-06-07
派手な大島
粟谷菊生
 傘寿を越えて、はや一年。月日の経つのも早いが、この一年間の加速度的わが肉体の衰えには、我ながら愕然。「八十を越えてみたら思い知るぞ!」と或る先人はよく言っていたが、「はあ、そんなもんですかねえ」という感じで、聞く耳もなかば上の空だったが、自分が実際その年齢になってみると、つくづくその言葉が身にしみる。
傘寿を越えて、はや一年。月日の経つのも早いが、この一年間の加速度的わが肉体の衰えには、我ながら愕然。「八十を越えてみたら思い知るぞ!」と或る先人はよく言っていたが、「はあ、そんなもんですかねえ」という感じで、聞く耳もなかば上の空だったが、自分が実際その年齢になってみると、つくづくその言葉が身にしみる。
現在、八十を過ぎて舞台で能を勤める非常に数少ない能役者の中に入ってしまったが、私の知る限りでは、せいぜい三人位だろう。
八十歳過ぎて『道成寺』を舞った故桜間道雄氏には全く敬服。明治生まれの人たちは強かった。自分で鍛えようと思わなくても、今のように車の無かった環境では自然に鍛えられていたのではないだろうか。スキーの三浦雄一郎の父上は今も現役スキーヤーで、自己管理を理想的に全うしておられる。それを見ると、その強靱な意志に脱帽してしまう。僕は、「菊ちゃんが飲まなくなったらオシマイだ」と言われると、すぐ「そうだ、そうだ」と、そのお言葉を素直に有り難く受け入れて、相も変わらず飲んでしまっている、だらしのない男。
平成十六年も能六番程度は勤めることになっているが、曲目が限定されることは否めない。もう可愛い女にはなれなくなってしまったのが残念無念。しかし自由の利かない枠の中で如何によい舞台を観客に見ていただけるか、それしかないと、その都度歯を食いしばって頑張っているというのが現状だ。それに地頭を勤めさせて頂いていることも舞台に足を運ぶ喜びとはなっている。
顧みればここ十数年和服で通しているが、着物の目方も老体にはだんだん重荷になってくる。紬やお召しよりも大島の方が軽くてよい。というわけで最近ひとつ新調した。先代家元、実先生から頂戴している極上の大島は普段着のよそゆき用。何年か前に作ってはいるが僕はすぐに食べこぼしをするので代えをもう一枚…と今回は僕の好みで選んだところ「貴方は汚れの目立つことを考えないで、洋服でも着物でも明るいキレイな色をお選びになるのね」と言われてしまった。光線の具合で僕にはもう少し地味に見えたのだけれど。気の小さい?それともケチ?な僕は新調したてのばかり着ては勿体ないと思って古い方を着ようとしたら「これ少し派手だから年をとると着られなくなるでしょう。今のうちにどんどんお召しなって」と妻に言われ、一瞬?…と思わず黙したが「僕は八十過ぎているんですよ、もう充分老人ですよ!」今度は一瞬おいて女房、大爆笑。マチガイでもこんなこといわれると一寸嬉しくなっちゃったりして。その日はいそいそと稽古に出かけたという次第。
写真 『大江山』粟谷菊生 撮影 石田 裕
阪大喜多会誌「邯鄲」に寄稿 投稿日:2018-06-07
今回の菊ちゃんの一言は、阪大「邯鄲」への寄稿文を記載しました。
阪大喜多会誌『邯鄲』第35号に寄せて
粟谷菊生
阪大喜多会は1971年度卒の寺川知良君、下城圓君、福田全克君が草分けということになるのだが、阪大謡曲部の長でいらっしゃった出口庄佑先生も大変お力添え下さって、年々恒例となった阪大喜多流能を催す立派な会となっている。寺川、下城両君は父上たちが以前から僕のお弟子さんだったのだが、寺川君は中学生時代から稽古に来ていたので、彼とはもう40年以上のおつき合いとなるのではないだろうか。
今年5月に西本願寺会館で、大勢の翁会(阪大喜多会OB・OGの会)のメンバーたちと、現役の数名が加わって、僕の傘寿を祝ってくれた。卒業後、各方面に散らばっていたメンバーが、よくぞこの日、一堂に会して下さったと感激した。今では50代を超えている人もいて、多士済々、すっかり貫録がついているのに、話をしていると、学生時代のそれぞれの顔にダブって・・・・というより僕の中には昔の若い顔貌が、そのままによみがえって懐しい一ときを過ごした。が、はて、それでは相手には自分の顔はどう映っただろう。この過ぎ去って行った何十年という時の流れを共に、今この顔貌になっている己れの加齢に気づき、ちょっぴり溜息と哀惜をおぼえてしまったのも正直なところだ。
丁度僕が結婚した頃に始まった東大喜多会は、30年程前に途絶えてしまったのに反面、阪大は先輩の新入生や後輩たちへの面倒見の良さと相まって、何か温かい横のつながりとフレンドリーな雰囲気が、今まで綿々と長つづきしてくれている要因ではないかと思う。僕はそれをとても喜ばしいこと、有難いことだと思っている。
いつだったか、4月の入部勧誘のキャッチフレーズが「人間国宝に触れます!!」だったそうだが、こういう文句を考えつく学生さんってスバラシイですね。でもこんな老体に触るの面白いですかねェ。それより「人間国宝に触られちゃいます」なんてのにしたら?
女の子は入ってこなくなるでしょうね。
最近になって指導は息子の明生が引き継いでくれているが、このまま、ずっと続いて、皆さんのお子様たちが明生に、その又お子様たちが孫に習ってくれるようになって”阪大喜多会は永遠です!”と末長く伝承して行ってくれるといいなあ、と思うのは少し息が長過ぎる話?些か翁さびた話になってしまったかな。
父 益二郎のこと投稿日:2018-06-07
父 益二郎のこと
粟谷菊生
先頃、喜多宗家の装束問題が新聞紙上に載って、この芳しからぬニュースに我々流儀の者はなんで今頃また?と言う思いだが、これは宗家だけの個人的な問題で弟子家には全く関係のないこと。
我々弟子家は演能に不自由しない装束をそれぞれ持っているので何の痛痒(つうよう)も感じない。粟谷家では父益二郎が生前、収入の大半を装束や能面の購入に注ぎ込んでいたおかげで今、不自由なく舞台を勤められる装束を持ち合わせている。
しかしそのため父は実によく働いた。
父の時代は,今と違って一般の家庭では電話を設置してはいなかった。
今の人たちには考えられないことだろうが急を急ぐ場合は電報を打った。今では電報は祝電か弔電と、桜が咲いたとか散ったとか、入試や就職の合否の通知ぐらいになったのではなかろうか。
この電報で面白い話がある。その昔、地方の社中が予定の稽古に人員が集まらず、この度は稽古にお出で頂くのは遠慮したいと電報を下さった。
父の返信がフルッテいる。
「デン、ミヌ、ユク」。
これには先方の御社中
「イヤー、マイッタ、マイッタ。」と。
しかし人数は少なくても費用は皆が分担して益二郎先生には御出で頂こうということになった。強引な押し掛け教授というところだが六人の家族を養い装束や能面を買うためには孤軍奮闘的、働き続けねばならなかったのだろう。
昭和三十二年六月に第二回能楽渡欧団の一員としてパリに発った兄を、母スエ子と共に見送りに行っている羽田空港での父の写真がある。

舞台姿や職分、御社中の方々との集合写真はあっても、こういう家族的な写真は非常に珍しい。カンカン帽をかぶって。生後一年九ヶ月の明生を抱いているが、この約三ヶ月後に染井の能楽堂で『烏頭』の演能中に斃れ父は他界した。
僕は父に似ているとよく言われてきたので、僕も六十六歳であの世に行くことになるだろうと長年、勝手に思い込んできたが、その予測死亡年齢より十八年近くも生き延びてしまった。
ということは、もしも僕が冥土に行っていたら既に十七回忌を迎えていることになり、僕の遺影の前で皆がお線香をあげている図を想像したりすると、おデコに三角の白い紙でもはりつけてみようかなんて気になる。くだらない妄想はいよいよ頭の方がオメデタクなった証拠?
父の舞台については折にふれ話したり、書いたりしてきたが、『谷行』『弱法師』などの、あの切れと味のある舞は、他の追随を許さぬもので、僕はこれをそっくり頂戴して僕のものにしてしまいたいと思ってきた。
『湯谷』『羽衣』などそのふくよかな温かみのある美しい舞い姿は、豊麗な謡とともに今でも特に鮮明に心に残っている。
「石橋の間」投稿日:2018-06-07
「石橋の間」
粟谷菊生

昨年(平成十五年十二月十五日)芸術院会員の任命を受け、今年六月七日に新会員として、今年度の院賞受賞者の芸術院に於ける授賞式に参列。今年は芸術院創設六十年を迎えるにあたって、両陛下のご来臨を仰ぐこととなり、旧会員も多数参列した。式後、文部科学大臣主催の午餐会に夫婦同伴で招かれ、そのあと受賞者と新会員のみ、午後の宮中に於ける茶会にお招きいただいた。人間国宝、院賞受賞につづいて宮中へのお招きを受けたのは、今回が三度目。「石橋の間」で前田青邨画伯描く先々代家元、十四世喜多六平太先生の『石橋』の絵画を眺めるのも、従ってこれで三度目になる。
故六平太翁は明治七年七月七日生まれの戌年(いぬどし)で、僕は四廻り下の同じ干支なので互いに気心が通じるというか非常に可愛がっていただき、釣りのお供もよくさせられた。その折々に人生訓や芸談、能の心や演技の虎の巻的なことも話していただいたのは、今にして思えばまことに私は果報者であった。迫力ある此の有名な「石橋」の絵画の前に最初に立った時は、「オイオイ、キク坊! 何しに来た?」と言われているような気がしたが、二度三度と伺うようになった今、「先生、また参りましたよ」と心の中で言って、その絵画を見上げ「オー、また来たね」と石橋の六平太先生から言われているような気がする。
 この絵画が描かれるに当たって、こんな一幕があった。画伯と相対(あいたい)して話しておられた六平太先生が、先ずデッサンをして頂くには装束の下の腕の張り方、筋肉のあり方を見て頂きたいとその頃既にご老体であったにも拘わらず着物を脱ぎ捨て褌(ふんどし)一つになられて舞台で『石橋』の獅子の型をして御見せになった。「褌が汚れています」と慌ててご注意申し上げたが、そんなことは一向に頓着なく…。画伯はと見ればこちらも素知らぬお顔でデッサンの筆を運ばせていらっしゃる。高齢の裸体は常識的には正視には耐えられるものではなかったと思うが、両雄相対する姿に一種の感動すら覚えた。僕はその場に居合わせたこともあって此の絵画には格別の感慨がある。此の絵画の他に、宮中には青邨画伯描く六平太先生の「出を待つ」という絵画もあるが、『石橋』の絵画だけがある故に「石橋の間」と呼ばれている此処に立つ時、六平太先生に再会出来る懐かしさのようなものを、ひそかに感じてしまう。
この絵画が描かれるに当たって、こんな一幕があった。画伯と相対(あいたい)して話しておられた六平太先生が、先ずデッサンをして頂くには装束の下の腕の張り方、筋肉のあり方を見て頂きたいとその頃既にご老体であったにも拘わらず着物を脱ぎ捨て褌(ふんどし)一つになられて舞台で『石橋』の獅子の型をして御見せになった。「褌が汚れています」と慌ててご注意申し上げたが、そんなことは一向に頓着なく…。画伯はと見ればこちらも素知らぬお顔でデッサンの筆を運ばせていらっしゃる。高齢の裸体は常識的には正視には耐えられるものではなかったと思うが、両雄相対する姿に一種の感動すら覚えた。僕はその場に居合わせたこともあって此の絵画には格別の感慨がある。此の絵画の他に、宮中には青邨画伯描く六平太先生の「出を待つ」という絵画もあるが、『石橋』の絵画だけがある故に「石橋の間」と呼ばれている此処に立つ時、六平太先生に再会出来る懐かしさのようなものを、ひそかに感じてしまう。
白寿を全うした先生にあやかり何とかして一日も長く舞えたらいいなあ…と、若い時には考えられない芸への執着に我ながら驚き、先輩たちの晩年の心境が理解出来るようになった。という事は、今は亡き先輩たちのその晩年と自分が同じ年齢になっているということで愕然とする。惨めな幕引きだけはしたくないと常々心に決めながら、命ある限り舞いたいと思う心もあるにはあるんですなー、困ったことに。
写真 上 「出を待つ」下 「石橋」 前田青邨記念館所蔵品目録より複写