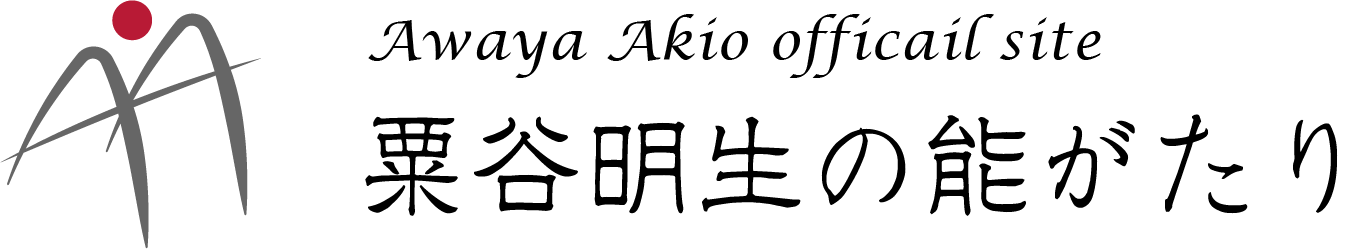兄新太郎を偲んで投稿日:2018-06-07
兄新太郎を偲んで
粟谷幸雄
四兄弟の末である私は、兄新太郎と長く生活を共にし、独立して福岡へ派遣された時も、その後も、何かと心配りや恩恵を受けてきた。その兄を亡くして、淋しさも一入である。戦後、戦地からの帰還を危倶された新太郎が、無事帰還して来た時、幼心にも良かったと喜んだ。国内の復興に伴い、能楽も次第に盛んになり、新太郎、菊生の兄達は、父益二郎を助けて、喜多流の公演を地方へも拡げ、流儀と粟谷家の発展を盛り上げていった。併し、父益二郎が六十六歳の若さで突然亡くなったあと、粟谷家の将来を心配した長兄の新太郎は菊生と共に、辰三や私の親代わりとなってくれて非常に力強かった。兄弟仲良く団結して、父益二郎の謡や能を継承してきたが新太郎に紫綬褒章、菊生は人間国宝の認定を受けた事は、粟谷家の光栄である。それは、父益二郎が受章したも同然であると思っている。互いに切瑳琢磨して、粟谷家を盛り立ててきた新太郎は晩年、菊生に一切を頼んだと聞く。幼い頃は恐いなと思ったこともあったが、やはり頼りになる兄達である。新太郎との演能の思い出に、宮島で『小袖曽我』を一緒に舞ったことがある。兄の迫力ある舞台に引っ張られて、流石に兄貴だなと思い、自分の未熟さを反省したものである。新太郎の演ずる能は何ともいえぬ魅力があり、橋掛りに向かう所作や、笹などの扱いが独特で趣があったと私は思う。新太郎の芸風は謡も型も淡々としているが、余韻があって『芭蕉』は特に印象深く感じた。新太郎は、面や小道具などの蒐集に心掛け、捜して来るのが得意で、手に入れた面などから、能のイメージを膨らませていた。新太郎の蒐集したものを重宝していられる喜多流の重鎮もおられる。又、お弟子のグループ作りがうまく、あちこちのお弟子を上手にまとめていたのは、新太郎の人徳であろう。来年は幸扇会を主催して四十周年を迎えるが、父益二郎の偉大さや、夫々の芸風を持つ兄達の魅力が、年を重ねていく程に分かってくる。その兄達に報いる気持ちで、少しでも近づくよう心に期している。粟谷家一門も、次代の活躍へ移行の時代にさしかかり、今後の喜多流の発展と共に、粟谷家一門の益々の繁栄を祈念し、努力を続ける覚悟である。
『砧』について投稿日:2018-06-07
『砧』について
研究公演の新工夫の成果を再演
粟谷 明生
 第七六回の粟谷能の会(平成十六年十月十日、国立能楽堂)にて『砧』を勤めました。『砧』は粟谷能の会研究公演(平成十一年、シテ・粟谷能夫・ツレ粟谷明生)にて現行の演出の見直しを図り、その成果に基づき、いつの日か再演したいと思っていて、今回その願いが叶いました。
第七六回の粟谷能の会(平成十六年十月十日、国立能楽堂)にて『砧』を勤めました。『砧』は粟谷能の会研究公演(平成十一年、シテ・粟谷能夫・ツレ粟谷明生)にて現行の演出の見直しを図り、その成果に基づき、いつの日か再演したいと思っていて、今回その願いが叶いました。
最初に、演出を見直し、新工夫をした部分を簡単に説明します。第一は、前場の初めにワキの名乗りとツレ夕霧へのことづてを入れたことです。従来の喜多流の場合は、前場にワキが登場せず、ツレの次第で始まり、状況説明はツレの独白で済ませています。喜多流の謡本では、ワキは中入り後に登場し名乗りますが、ワキが下掛宝生流の場合中入り後に名乗りがないため、能『砧』として、どこにもワキの名乗りがない不自然なものになってしまいます。それに対し上掛はワキが先ず名乗り、長年の在京となったが、故郷の妻の事が気になるので使いを出し、「この暮れには必ず帰る」とことづける場面があります。これによって何某(主人)は無情な悪人ではなく、妻を思う心やさしい人として設定されます。今回はツレ(内田成信氏)に観世流同様、ワキのあとについて出てもらう形としました。
では何故喜多流は現在の形式となったのか、『砧』という作品の変遷をたどってみます。『砧』は世阿弥の晩年の作で、子息の元能に「このような能の味わいは、後の世には理解する人もいなくなってしまうだろう。そう思うとこの作品についてあれこれ書き残すのも気乗りがしない」と語ったと、元能著、申楽談儀に記されています。世阿弥の心配通り、その後は音阿弥の二度の演能を限りに途絶えます。慶長頃(戦国時代)には『蝉丸』『小原御幸』とともに、詞章のよさから座敷諷(ざしきうたい)として素謡専用曲となり、江戸中期頃、幕府から各流に演能可能曲の申出が命ぜられ復興されます。今日の喜多流の台本と演出が出来たのは、その折、合理的な演出を考案し、新流としての独自性を築きたいためだったように思われます。
演出の見直しの第二点は、シテと夕霧が砧を打つ砧の段の後、「いかに申し候」に続いて「只今都より御使い下り」を入れたことです。従来は砧の段が終わると、間髪いれず「いかに申し候。殿はこの年の暮にも御下りあるまじく候」とツレの厳しい言葉が入ります。これでは余りに突飛すぎて、まるで夕霧は殿が今年帰らないのを知っていて、わざと焦らして通告したように誤解される危険があります。ここはワキ方、狂言方の科白にもあるように、やはりある時間の経過が必要で、また別に都から使いが来たという状況説明の言葉を補う必要があると考えました。
このように演出を見直し、台本を整える作業をしていくと、『砧』という曲は単なる復讐劇ではない、ましてや夕霧への嫉妬劇でもないことが判ります。夫と妻の思いが噛み合わず、このずれが妻の心の恋慕、怨恨、哀傷といった様々の心模様に錯綜していく。『砧』は一見ありふれた巷の出来事を素材にしながらも人間の心の襞(ひだ)や屈折、奥深くにある魂の呻きをテーマとして書かれているのです。
故観世寿夫氏は「人の心の中の鬼、つまりー怨念ーといってもいい、人間が生きる上で苦しみ、悲しみといった、より人間的なものを鬼と据え、世阿弥自身の根源である鬼を得意とする大和申楽の規範に戻り新たに創作したのではないだろうか。それはいままで創り上げてきた『井筒』などの幽玄無上の夢幻能とは別の、自分が完成させた様式の破壊という新しい作品への凄まじいまでの創造意欲なのである」と述べられています。私はこの文章に刺激され、作品に似合った演出を手がけることがいかに重要であるかを知りました。私の大好きな『砧』は中世という時を超越して、人間の心の弱みや恋慕の身勝手さを現代の我々にも鋭く抉るように訴えてきます。この名曲をあだやおろそかに演じては、作者の世阿弥に申し訳ない、寿夫氏が言われるのはまったくその通りと痛感します。
前シテの面は通常、曲見か深井です。伝書には小面とありますが、小面では色がありすぎ生々しくなり、孤独と不安、失意や時の喪失感などが表現しにくいです。今回は粟谷家蔵の「若深井」を使用しました。深井より少し若い感じの、憂いをおびた顔の面です。装束は『砧』に合う梶の葉模様の紅無唐織を仕立て直し使用しました。
シテはアシラ匕出で橋掛り三の松にてサシコエを謡います。「それ鴛鴦の衾の下には・・・」と、ここは切実な思いを冷えた謡でと心得がある、難しく苦労するところです。そして、シテは夕霧の訪問に、じわっと答えます。「いかに夕霧」の一言にすべての思いが込められるようにと、ここも心持ちのある大事な謡です。すかさずシテは何故直ぐに連絡をしないのかと叱りつけますが、夕霧は刺激的な言葉で返してきます。「忙しくて連絡する時間がなかった、三年の月日や都にいたことは自分の本意ではない」云々と。前場はこのシテと夕霧との緊張感の中に、月の色、風の気色、影に置く霜、夜嵐、虫の音と、秋の風情を織りまぜ、シテの揺れ動く心情を、砧の音とともに謡い上げるところがみどころです。
この曲では砧を打つ作業がシテの心のありようを反映しています。演者は常に「砧」と向かい合いながら演じ、砧を打つ気持ちや作業、それが妻の床で行われたことなどを、確と把握し表現しないと『砧』は手に負えない作品となります。この曲の象徴ともいうべき「砧」の作り物は、喜多流には本来なく、我が家の伝書にも記載がありません。しかしこの作り物を出さない演出は、物語を理解しにくくさせ、演者側も気持ちを込める対象がないため、演じにくいということがあります。最近は前場の物着の時に正面先に出し最後まで置いたままにしていますが、当然作り物を出した時の正式な型付はないのです。作り物を出すならば、それに似合った動きが必要で、今回いろいろな資料をもとに工夫をこらす楽しみも味わうことができました。砧を打つ型を二度にし、最初は「今の砧の声添えて・・・」で少しヒステリックに打ち、二度目は「交じりて落つる露涙、ほろほろはらはらはら……」と意識
も朦朧と憔悴寸前の態と、打ち方に変化をつけてみました。
後シテの出端は観世流の「梓之出」に近い演出としました。我が家の伝書に「この出端、鼓アズサ打つことあり、別の習い也」とあり、まったく喜多流に根拠のない事ではないので、御囃子方(一噌仙幸氏、大倉源次郎氏、亀井広忠氏、金春国和氏)のご協力のもと、流儀で初めて試みました。アズサの音に引かれながら、シテは三の松にて一度止まり、砧の音を探します。徐々に高鳴る砧の音とアズサの音に耳を傾けまた歩み始め、一ノ松にて「三瀬川沈み絶えにし……」と謡い「標梅花の光を……」で再び本舞台に入ります。小鼓はアズサを打ち太鼓の音に執心が込められる、よい演出効果だと思っています。
後シテの面は「痩女」、装束は白練の坪折に大口姿です。観世流は通常「泥眼」で鋭い強さを表しますが、喜多流の主張は「痩女」で、やつれて空しくなった女をひきずって寂々と登場します。そのため歩みも、「切る足」という独特の足遣いとなります。キリの仕舞はじっくりとゆっくり演じるのが当流の特徴です。しかし最後に堪えていた怒りは押さえ切れず、「夢ともせめてなど思い知らずや怨めしや」と、中啓を床に打ち、左手をさし出し夫に迫るとも、また、夫に触れたいとも思わせる型となり、それさえも出来ないと悲しみ泣きます。ここは地謡も囃子方も激しく謡い囃すところで、シテはただメソメソするだけではない、荒くなってはいけませんが、強さ、激しさが込められていなくてはいけない難しい大事な場面です。そして「・・・怨めしや」のあとの一瞬の静寂、夫は法華経を読誦し、妻は成仏することができた、とこの作品は終わります。
後場での地獄の責め、死後も砧を打ち続けなければいけないという因果関係は、生前の恋慕の執念が死後の苦悩煩悩の地獄に落ちるという構図で、仏教思想を基盤にしてはいますが、『実盛』のような時宗の賛美のパターンとは異なり、そこが焦点ではないはずです。法華読誦や成仏をクローズアップし過ぎてはこの作品が生きません。
成仏とか宗教性とは別のところに、『砧』という作品の大事なメッセージがあると思います。砧を打つ賎の業を主軸に、妻の夫への揺れ動く様々な感情の起伏。一途に思うが故の怨みや激情。『砧』はそういった人間の普遍の感情の行き違い、心の葛藤を描いた集大成だと思います。世阿弥は晩年、不遇の時を過ごしました。体制の側にない芸能者のどうにもならない悲劇。そこに耐え、あきらめながら、世阿弥はただひたすらよい作品の創造に執念を燃やし、そして仕上げた『砧』です。生意気ですが「冷えた能」と世阿弥が自画自賛するのが、演じて肌で感じられたような気がしました。演能が終わった今でも、世阿弥の残した「かようの能の味わい…」の「かよう」とはいったい何であったのだろうか、そのことが心に残っています。
今回の演出の見直しを顧みて、昔なら演出を変えるなど、とても考えられない許されないことだったと感慨を深くします。今はよい時代となり、流儀では考え工夫する事が許される、さまざまな演出を試みることが出来きます。本来出さなかった作り物は出すのが普通になり、切る足の所作も次第に変わってきています。時代はよい方向に流れだしたと思います。明治・大正の名人たちは魅力的で芸もすばらしかったでしょう、しかし現代の能も今を映しながら確実に進歩を遂げていると思います。これからも作品の主張を見つめながら、一回一回の舞台を大事に真摯に勤めていきたい、そう思わせてくれた『砧』でした。
*(「粟谷能の会」のホームページ演能レポートで内容補足&写真も掲載しています。ご覧いただければ幸甚です。)
『砧』 粟谷明生 粟谷能の会 撮影 石田 裕
能楽機関誌「DEN」2009年1?3月号より記載投稿日:2018-06-07

現在・過去・未来
粟谷明生 さん
●シテ方喜多流
粟谷菊生の継承と
そこからの飛翔
PROFILE
粟谷明生(あわや・あきお)
◆1955年(S30年)、東京生まれ。シテ方喜多流人間国宝、故・粟谷菊生の長男。父及び喜多実、友枝昭世に師事。59年『鞍馬天狗』花見にて初舞台。63年『猩々』にて初シテ。82年『猩々乱』以降、『道成寺』『石橋』連獅子、『翁』『安宅』『望月』『三輪』神遊等を披く。「粟谷能の会・研究公演」をはじめ、同世代にて「妙花の会」広島にゆかりのある能楽師を集め「花の会」などの立ち上げに努めた。
「粟谷能の会」を、従兄の粟谷能夫と主宰する粟谷明生さん。この会は昭和三十七年の十月に、能夫の父新太郎と明生の父菊生の兄弟で始めたもので、平成二十年で八十四回を数える。
人間国宝・芸術院会員でもあった喜多流の重鎮、粟谷菊生が亡くなって二年。「能?粟谷菊生舞台写真集」「景清?粟谷菊生の能舞台」と、明生さん自身が編纂された「粟谷菊生・能語り」も出版された。三回忌追善公演も済まされた現在の心境と、これからの展望を伺った。
●喜多実先生の教え
父の指導で三歳に初舞台を踏んだ明生さんは、小学生の頃から、先代喜多流宗家・喜多実に子方と仕舞の稽古を受けるようになる。
「少年期は同世代の仲間がいなかったこともあり稽古は一人、個人稽古でした。子方の稽古というのは、子方が関わる個所だけ教わります。
例えば『国栖』では“シテが最後に留拍子を踏んだら終わりだから、立ってシテの後に付いて帰りなさい”、とただそれだけ。途中で天女(ツレ)が登場し長い五節之舞を舞うなどとは知らされないから“あれ?僕はまだここに居ていいのかな?”と不安になるのです。この不安が逆に緊張感を生むからよい、という教えだと思いますが、当事者には、やや酷な感じもします。それで息子には自分の経験から、曲全体の流れや舞台進行を説明して稽古しました」
明生さんの最後の子方は『満仲』(観世流『仲光』)の幸寿丸、シテの仲光に斬られる役だった。「私の子方時代の終幕は斬られてオシマイ!」と笑って話す明生さん。子方は舞台上で横に倒れても頭を舞台に付けない、それが実先生の教えだったと語る。
「この間、久々に『満仲』がありまして、幸寿丸の頭が舞台に付いていたのを見て、実先生の言われたことの真意が判りました。
頭を舞台につけると楽なのですが、それでは子どもの身体にある緊張感が薄れ能の型ではなくなる、たぶんそう言われたかったのではないでしょうか。
太刀の扱いも同様で、太刀が長刀や他の太刀に絶対に触れてはいけないと教えられました。これも理由などは教えては下さらない。
しかし最近、カチャンカチャンと竹光のあたる音を聞くことがあって、なるほど、これでは太刀が凶器であるという力は伝わらないと判りました。実先生の教え方は理屈抜き、鵜呑みにするしかありませんでした。
しかし若い時分は鵜呑みが一番だと思います。納得出来ない、気になるということは、時を経て自分で考え答えを出せということでしょう。正直、正しく早く教えるほうがとも思いますが、やはり時間を掛けたものの強さでしょうか。あまり楽をしちゃいけないのかもしれませんね」
中学、高校に通う頃は喜多実学校で先輩と一緒に団体稽古を受けた明生さん。指導の骨格は型重視、厳しく身体の動きと精神を教えられたという。
「実先生の指導を受けた人たちは皆、型については充分鍛えられたと胸を張って言えます。稽古場では、腰を入れろ!肘をはれ!背筋を伸ばせ!フラフラするな!が先生の口癖でした。型をきちんとするというのは、実先生の元で習った者同士の共通の美意識で、その同じ根っ子が今の喜多流を支えていると思います」
その後、明生さんは友枝昭世を師と仰ぎ、直接教えを乞うてきた。もちろん、父・菊生が身近にいて指針になったのは言うまでもない。
●追善能『絵馬』女体と伝書
粟谷菊生三回忌追善公演(粟谷能の会)で、明生さんは『絵馬』を女体という小書で演能された。喜多流の本来の『絵馬』は、後シテの天照大神が男神として現れ、荒々しく神舞を舞うが、「女体」は、本来の天の岩戸隠れに沿った演出となり、シテは女姿で小面をつけてスピードある神舞を舞う。小面の狭い視界で、早い神舞を舞うには修練が必要とされ、「女体」は喜多流では重い習いとされている。
「先人の女体を拝見してきて、神舞が天照大神の怒りを彷彿とさせるものが多かったと思いますが、父の舞台や話からは、女性らしい優しさ柔らかさを基調にしていたように思います。ですから自分もそのような感じで勤めました。女体は実はお囃子方にとって体力的にも技術的にもご苦労な曲なのです。
でも、そこを力を合わせてやると素晴らしいものが出来上がります。今回もお囃子方の心意気を感じ、気持ちよく勤めることができました。女体に限らず、よい演能には三役の理解と協力がなければ出来ないと思います。シテはこのようにやりたい、こうしていただけないかと真摯にお願いして、そうすれば相手からも、このようなやり方があるよ、こうしたらと返事がきます。こういうやりとりがまた楽しいのです。
ですから私的な会では、出来る限り三役の交渉は自分自身でしています。己の舞台は己で決める、決められない場合もありますが、己で決められる粟谷能の会を特に大事にしています」
明生さんは一回一回の能を大切にしてきた。能は花火のようなもので、二度と同じ舞台は出来ない。だから、その一度に全力を投入する。どんなに素晴らしいものでも、舞台で演じられたものは残念だが消えてゆく。だからこそ、書き留めて残していきたい。同時に、今昔を問わず、書かれたものを読み起こす作業が大事だと考えている。
「私は伝書を元に師や諸先輩からの教えを自分用の型附として書き残していますが、伝書にはいろいろな事が書かれていて興味が湧きます。我が家には喜多家九代目七太夫古能健忘斉と十代目寿山の伝書があり、それらを読むと書く作業の重要性を感じます。
伝書を読むには、変体仮名の勉強も必要になりますが、読めるようになると実に面白いのです。特に後半に書かれている心得がとても為になり面白い。こうすると大損とか、こんな型があるが名人の業也とか、未熟者はこうしろとか。読み手が幅広く解釈出来るものが優れた伝書といえるのではないしょうか
●「謡はホットに、辛(から)くだよ」
喜多流は技が切れるといわれるが、型重視の稽古だったから、型が決まるのは伝統なのだろう。だが、なぜ謡の稽古があまりなかったのだろうと不思議に思う。“喜多さんは仕舞や舞囃子を見ているといいが、どうもお能になると・・・”と言われるのは謡の問題だったのではないかと、明生さんは謡の重要性に気づいていく。
四十歳近くなった頃、故観世銕之亟さんがご子息の暁夫(現銕之丞)さんと近藤乾之助さん、粟谷菊生、明生親子を誘い、ひっそり呑む会を設けてくれた。その時に銕之亟氏に“お父さんの謡を真似たら”と言われたという。
「四十近くなって、これはとにかく父の隣で謡うことが勉強だと気づきました。父は“謡を面と向かって習うなんてことはないんだ、玄人はそんなに甘くないよ、とにかく、上手の前や隣で謡って覚えるんだよ、芸は盗むんじゃない、盗むなんて悪い言葉を使っちゃだめ、黙っていただく”と言っていました。
父が六十歳半ば頃、丁度油の乗りきった地頭時代がやってきますが、その時から、私は父の前列で謡い、そして晩年に父の隣で謡えたことが肥やしになっています。先日、大倉会大阪公演で、一調一声『玉葛』を大倉源次郎さんとやらせていただきましたが、父ならこう謡うだろうな、こうだったな?と思い出しました」
「菊ちゃんの謡は浪花節的!」と言われると、菊生は「浪花節的で大いに結構だよ!」と言い返していたという。
明生さん自身も若い頃、父に向かって芸が臭くて浪花節的だと言って喧嘩になったこともあった。
「浪花節的、この言葉が誤解を招くのかもしれません。父の謡は情があり艶のあるものでした。父の口癖は“謡はホットに、辛く”、その言葉が今は頭から離れません。父の地頭に座る精神は、相手のために誠意を尽くし情で謡うということだったと思います。
舞台に立っている人のために、そして観客に喉が枯れても、体調が悪くなっても必死に謡う、そんな生き様でした。こんなお人好しの人はそうそう出現しないと思います。ですから義理人情に重きを置く浪花節的な人生だったのかもしれません。私が父を誇りに思えるのは、型も謡も出来た人だったからです。若い頃はそれに気づかなかったのですね」
青い鳥ではないが、結局一番身近に学ぶべき人がいたということかもしれない。謡を語る時、単にシテの謡だけを評価しても意味をなさないという。
「先代観世銕之亟先生が教えて下さいました。“シテが出来、地頭が出来、後見も出来て初めて一人前の能楽師だよ。それが出来なきゃ能楽師じゃないと思うが、どう?”私の指針となる言葉です。
能をご覧になる方はシテの謡いを云々されますが、地頭、地謡がきちっと謡えてが大前提です。声は鮮明に綺麗に、音も正確に、囃子方への対応も出来て、尚かつ演者の雰囲気に合わせて作品を創り上げる、大変な仕事です。今喜多流の現場で補充しなくてはいけないのは優秀な地頭と地謡です」
●演能レポートの軌跡
粟谷能の会のホームページ、粟谷明生のブログなど、その充実ぶりには目を見張るものがある。忙しい中どのようにして更新、投稿されるのだろう。
「ブログは書き込みが簡単なので楽屋内の情報を、粟谷能の会ホームページでは、演能レポートなどを書いています。現場の人間が書くことも良いのではと思いまして。書くことで発見があり、作品を改めて深く読み直す事も出来て、得をしながら楽しんで書いています。記録として残しておけば、五十年後には、この頃はこのように演じていたのか、この人がこんな事を考えていたのかと、こういう資料があってもいいかなと思います」
これが明生さんの普及の形。以前は、演能レポートは舞い終わってから書いていたが、最近では演じることが決まると、あらすじから書き始め、メモをとる。この作業を通して舞台展開が見えてきて、疑問が出てくる。それに対応しながら書き直し、演じ終えて最終的な演能レポートが完成するという。
「だから、本音は自分のためにやっているのです。でも、粟谷能の会を観終わった後で、レポートを読むのが楽しみだとメールを下さる方が多くいらっしゃいます。自分の観方と演者の思いがどう違うか見てみたいと。それが面白くてまた舞台を観に来て下さる方も、いらっしゃいます。私なりの観客増員方法ですよ。」
粟谷能の会では、自分たちがやりたいものを演じられるが、必ずしも観客の入りがいい曲目とは限らない。自らの研鑚の場であり、プロとしての技量を観ていただく演能の場でもある。これを両立させていかなくてはならない。何年か後には『卒都婆小町』を演じたい。父菊生も「歳を取ってから演るのではなく、相応の若いうちに一度演っておくとよい」と話していたという。
「その前に『景清』『定家』ですね。父の演じた『景清』が強烈です。父と比べられたら堪らないが、そろそろ手がけておく必要があるでしょうね」
ツレ(人丸)を勤めた経験と地謡で見てきた様々な景清像を基盤に、自分なりのものをと、父を受け継ぎ、父を超える日を夢見る粟谷明生さんだった。
注
「粟谷菊生能語り」編纂:粟谷明生(ぺりかん社)
「能 粟谷菊生舞台写真集」編:鳥居明雄・吉越研(ぺりかん社)
「景清 粟谷菊生の能舞台」(ぺりかん社)
(平成21年上半期粟谷明生演能予定)
3月1日 国立能楽堂13時始
『安宅』延年之舞 粟谷能の会
SS 席 \12000
S 席 \10000
A&B席 \7000
C&D席 \5000
学生料金 \3000
6月28日 喜多能楽堂12時始二番目
『雲雀山』 喜多流自主公演
当日券 \6000
我流『年来稽古条々』(28)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(28)
?研究公演以降・その6
『松風』について
粟谷 能夫
粟谷 明生
明生 今回は、第6回研究公演(平成7年11月25日)で取り上げた『松風』について話したいと思います。研究公演を立ち上げて五回が過ぎ、そろそろ大曲に挑もうということで、一日に能一番の番組にして、まず私が『松風』を勤めました。あの時は、父が仕舞『芭蕉』を、能夫さんが仕舞『熊坂』を長裃の小書でやられました。仕舞の小書については後日取り上げるとして、では本題の『松風』について。あのときの『松風』の地謡は豪華な顔ぶれでした。地頭が父(粟谷菊生)、副地頭が友枝(昭世)師、左端に能夫さん、右端が幸雄叔父と、まあ贅沢なことで有難かったです。でも申し訳ないのですが、非常に豪華過ぎて・・・船頭が多すぎたというか…。
能夫 相殺してしまうかもしれないね。(笑)
明生 原因は私でして…。皆様、私のことを心配されて謡われるものですから、譲り合う、というか…。地謡は、少し負を背負っている方が却ってよいことってありますから。
能夫 負と言っても地謡を謡えない人では困るが、喜多流は人数が少ないから、適度なバランスが必要だね。
明生 『松風』を今までに何回演られましたか?
能夫 僕の披きは昭和63年の粟谷能の会でだった。その後は、青森の公演で一度しているね。それっきりかな…。
明生 能夫さんのお披きでは私がツレを勤めましたね。それで私のほうは研究公演の十年後、平成17年の粟谷能の会で再演しましたが、二度目も父が地頭をしてくれまして。最近ようやく父の謡の味、というか、良さみたいなものが判るようになってきて、まあ遅ればせながら、有り難みを噛みしめているのですが…。父の謡は音量も調子も大きく、高く、自分の肉体疲労など考えずに、シテを盛り立てる、舞台を支える意識で謡っていたように思えます。特に『松風』はホットに謡うようにしていたと…。冷たい『松風』ではダメな気がしますが。
能夫 そうだね。ホットな感じだね。僕も『松風』を謡うとなるとなんだが、特有の意気込みというか、感性が湧いてくるよ。『松風』は詞章もいいしね。シテの謡も含めて、『松風』は『道成寺』に匹敵する、いやその上を行く曲だよ。だから『道成寺』の次の課題曲となるわけさ。
明生 『道成寺』が終わると、次は『松風』。『道成寺』も難しいですが、『松風』はもっと上。能役者ならば目指さなければいけない曲だよ、とよく言われていましたね。
確かに『道成寺』はいろいろ秘技があり、難易度は高いですが、鐘入りすれば、誰にも見られない、一息つける場があり、我に帰ることが出来ます。ところが、『松風』は汐汲みの段が終わり、やれやれ前半が終わったか、と思う間もなく、曲は後半に続行されていくわけで、長丁場の苦しさ、体力が必要ですね。
能夫 『松風』はとてもやり甲斐のある大曲だね。シテ(松風)とツレ(村雨)の力が拮抗していなくてはいけないし、中入りがないのも特殊であるし、憑依する面白さもある。能のいろいろな要素が入っていて難易度が高くなっている。夢幻能であるようで現在能のようなところもある。『道成寺』はある意味、運動能力を試される、体育会系の成果を期待されるが、『松風』はそれだけではない。だから『道成寺』に取り組むと同じような懸命な意識で稽古して、技術面と精神面の両方を磨かないと、処せない曲だね。『松風』には映えがある、それが難関だよ。
明生 ですから早いうちに一度経験しておく必要がありますね。どのくらいの負荷がかかるのかを身を以て知ることが第一で、ある年齢になったら自然と出来る、という領分のものとは違うことが判らないといけないと思いますよ。
能夫 明生君はいつもそう言っているね。
明生 力量に合った経験の積み重ね、が大事で…。『松風』は確かにシテとツレが拮抗する曲です。だからまずシテを勤める前にツレをきちんと経験していなくてはいけない。辛いシテツレの経験無しで、シテなど言語道断ですよ。だから、日頃の学習が大事で、『松風』のツレの指名を受けられるような状態、条件を備えていなければいけないですね。そこを満たして、はじめてシテという晴れ舞台に上がれる、能夫さんが言われる、競泳のスタート台に立てるわけですね。『松風』のツレ役は、謡は多く、足の痺れも心配で、逃げたくなる気持ちも判りますが、まあご指名がかかる喜びみたいなものもありますからね。
能夫 先輩に、「頼む、やってくれよ」と言われたときの嬉しさって、あるじゃない。
明生 嬉しさの反面、不安感もあってね。でもその経験を活かさないといけないですね。そしてシテを勤めると、次にツレを演るときに、「あっ! こう動けば、この程度に謡えば」という程度が判ってきます。それ以前は、ただ書付にある通り機械のように動き謡うだけでしたから、悪くはないが、良いわけがない。パターン化されて…。
能夫 昔は皆、パターンでやっていたよね。明生君の最初のツレのシテは菊叔父ちゃんかな?
明生 そうです。27歳の時、大事なところで謡を間違えて、恥かきました。楽屋で怒鳴られるなあと覚悟していたら、父の無念そうな顔、妙に静かに「しっかりして頂戴よ」と叱られたの、今でも覚えています。大反省です。そんなこともあり、能夫さんのお披きの『松風』のツレは改心して…(笑)。あのときは能夫さんに細かく、ツレの立場での心持ちまで教えてもらい、あれで能の面白さを知った、引き込まれた、といっても過言じゃない。それまでツレであのような細かい稽古は正直無かったですからね。パターンで覚えるだけでしたから…。それが33歳のときです。
能夫 『松風』というのはシテ・ツレが二人で一人みたいなところがあって一緒に創ろうとする気持ちが絶対必要でしょ。ツレが何も知らなかったら、こうやろうよ、こうやってよ、なぜなら、と説明してそれに応えてくれないと困る。運命共同体というか、一緒に仕事するわけだから。ただ昔の人たちは、そんなことはしなかったみたいで、自分のことだけで…。自分が良ければ相手も当然そうだ、と勝手に思っていたからね。まあそれで出来上がってしまう凄さもあるわけだが、僕はそういうのはいやだから。
明生 あのときの稽古のお陰で、いま役に立っています。ツレの在り方を教わり、その後、父の相手を二度、そして研究公演でシテを披いたわけですが、先ほど話したように十年後にもう一度シテを勤め、実はその間に友枝昭世師のツレを平成十四年、宮島厳島神社の観月能で勤めまして、このときはじめてまともなツレが出来たかな…と思っているのです。それまでは、どこかシテに寄りかかる気持ちが強かったのですが、あの時は拮抗出来た。そう実感したのが観月能でした。観月能にふさわしく、月がきれいな秋の夜、師の友枝さんからの指名でお役を勤め、父が地頭で能夫さんも地謡にいて、三役も揃い最高のロケーションでした。ただ書付通り、右向いて左向いてと幼稚でいたら、評価を下げたと思いますね。
能夫 『松風』はそういう風にツレが充実してはじめて成立するんだよ。姉の松風、妹の村雨、この姉妹の微妙な関係が出てこなきゃね。
明生 あの二人の姉妹の性格をどのように演じるか、このさじ加減がミソですね。
能夫 そう、それと先ほど話した、『松風』は長丁場で、中入りがなく二時間近い時間を舞台の上でさらされながら表現しなければいけない。
明生 中入りがあれば、楽屋で一息ついて変身して登場出来ますからね・・・。
能夫 中入りは、インタバルで何かチェンジして出て行ける。ところが『松風』は、己の体だけで己の世界を変えていかなければならない。肉体で攻めて凌いでいくような能だね。古作の能だから、能の原型というか、そういう特徴がある。戯曲の処理能力というか、曲を理解していないとできないね。覚悟してやらないと…、ただ『松風』をやりましただけのことになってしまい、それじゃ『松風』にならない。
明生 松風の恋慕をいかに表現するか。やはり型と謡というものが試されますね。謡の力で、恋で壊れている女を演じるわけですから。男の役者が女に扮して、その女が行平に憑依して男になる…。女性では表現出来ない世界を男が創造する、それが能ですね。女流能楽師の方々には、申し訳ないがそこには限界があると思いますよ。
能夫 そうだね。「げにや思い内にあれば、色ほかに現れさむらふぞや」、あそこは、単に上音で綺麗に謡えばそれでいい、というものではないよね。やはり、生々しい恋の能だから、型で処理するのではなく、何か心情が前に出たり、後ろに引っ込んだりしないとね。それが見えないと・・・。
明生 『松風』は熱い恋、『野宮』は何か冷たい愛…。
能夫 両者には、身分の違いもあるからね。六条御息所は高貴な人だもの。でもカッと燃えるところもあって…。
明生 御息所の燃えるのと、松風のお姉様の狂気とを演じ分けないといけませんよね。同じ手法では無理ですから。演ってみてわかりました。最近、思うのは、温かみのある謡や舞、ということ。父の『松風』は温かだったなあ、と。私も温かく演りたいなあ、と…。
能夫 温かさね、判るよ。『松風』は内に秘めてだけではない、ふと表に溢れ出てしまう感情、そういうものが起きないと、世界が立ち上がらない気がするね。
明生 『野宮』と『松風』はどちらも「破之舞」がありますが、これも質が違う気がします。破之舞は『羽衣』でも舞いますが、あれは最後の付録、サービスの舞です。それに対して『野宮』や『松風』の破之舞は序之舞よりも想いが強くストレスもある。両者の微妙な違いを舞い分ける心が大事だとわかったのは、やはり経験からですね。『松風』を勤めて、破之舞の重要性を知りました。『羽衣』だけでは破之舞は語れませんからね。
能夫 『松風』も『野宮』も破之舞が醍醐味だね。舞ってて楽しいもの。ところで「真之一声(しんのいっせい)」だけれど、あれ、おかしくない? 嫌じゃない?
明生 真之一声は脇能の出囃子ですよね。脇能以外ではこの『松風』だけですか? なるほど・・・、なぜ真之一声なんですかね。
能夫 根拠はないよね。『松風』という曲を大事に考えたからかな。でも鬱陶しいよ。似合わない。
明生 身分は低いし、神々が現れるわけではないし、神への祈りがないのに、空虚な感じがしますね。
能夫 汐汲みという作業をしている、いわば労働者に真(まこと)の一声だからね。考え直してもいいような気がするな。違和感あるよ。真之一声で厳かにやらなくても、リアルな今を謡ったほうがいいんじゃないのかな。
明生 今後考えてもいいかもしれませんね。私は、研究公演の披きは、普通に小書なしで、十年後の再演は小書「見留(みとめ)」で勤めましたが、喜多流の小書にはこの他に、身体の身を使う「身留(みどめ)」、それに「戯之舞(たわむれのまい)」がありますね。父は「見留」一辺倒で、すーっと幕に消えて入っていく景色の良さを一番に上げて、「見留」が一番、が口癖でした・・・。
能夫 『松風』は各流儀にたくさんの小書があるね。やり様もいろいろだね。
明生 「戯之舞」の面白い実先生のお話がありましたね。「戯之舞」は元来、十四世喜多六平太先生が、観世清廉氏と『求塚』と交換しようとされたが、喜多身内から反対があり取り止めになり、後に、昭和44年に実先生が観世元正氏に再度お願いに伺い頂戴した。そのお礼にと何か差し上げます、とおっしゃったら、『鸚鵡小町』の型付をいただいています、とのお返事だったとか。
まあ、経緯などどうでもいいのですが、私、次回はこの「戯之舞」でやってみたいと思っているのですが…。この「戯之舞」を再考し、「真之一声」についても考えてみたいですね。『松風』は体力がいる曲ですから、早めに計画しないといけないな。実先生のように15,6回も出来る立場とは違うので、還暦前にもう一度…。
能夫 ほんとうに体力がいるからね。やり様はいろいろあるけれど、型の連続だけではできないということは確か。技術力だけでは絶対に解決できない。内面の演技ということかな。そこに恋する女がいなければいけないからね。
明生 はい。シテが出来ればいいですが、地謡でも同じような気持ちで謡いたいと思います。地謡は、隣同士お互いの主張があり、ぶつかり合いがあって、そう出来れば上質な地謡が出来上がるわけですから。
能夫 隣同士、前列と後列でも、絶妙な呼吸を大事にしたいね。『松風』のシテをやることで、ツレがわかり、地謡がわかる、そういう相互性が大事だよね。
明生 みんなで創り上げていく。これがすごく刺激的。刺激し、感じていければ、次にシテを勤めるときに、自分はこうしたいという、なにかが生まれてきますから…。
能夫 そういうものが重層化したときにふくらみのある、温かさが出てくるのかもね。
明生 大事なもの、大曲をすればするほど、そういった底力がないと出来ないなと思いますね。それが今の素直な感想です。どうやって地頭を盛り上げ、シテを盛り上げ、囃子方も含めて、曲全体を創り上げていくか、大事な課題だな…。
能夫 そうやって全員がやらなければいけないんだよね。全員の曲への理解を深めていく。それができたとき、流儀全体のレベルが上がっていくんじゃないかな。
明生 そうですね。なんだか私の『松風』の話ばかりになってしまって…。では次回は能夫さんの『小原御幸』についてですね。
(つづく)
流儀と個投稿日:2018-06-07
流儀と個
粟谷能夫
 例えば『喜多会』と『粟谷能の会』とどちらが大事かと聞かれたらどう答えるだろうか。
例えば『喜多会』と『粟谷能の会』とどちらが大事かと聞かれたらどう答えるだろうか。
まずはその問いかけそのものに問題があるとは思うのだが、それはおいておこう。それは車の両輪であり、どちらもともに大事なのだという答えになるだろう。個と『喜多流』とどちらが大事かという問いに対しても同じ答えだ。個が充実した存在になることによって、『喜多流』として魅力ある演能ができ、充実した演能集団である『喜多会』によって個が磨かれ優れた存在になるのだ。
ただ、能はほかの演劇に比べれば、個の力量にゆだねられている部分が非常に大きい。普通の演劇であれば一つの舞台を成り立たせるために、ひと月とかふた月、稽古を全員が共にするのに対し、能は一回の申し合わせで本番を迎える。これを可能にするのが個の日々の修行、稽古なのだ。その意味では個がしっかりと磨かれなければ演能は成り立たないし、流儀も繁栄しないことになる。芸術性の高い個が多様に存在していることが流儀の力であり、魅力だろう。それがなければ家も流儀も色あせたものになる。
そしてもうひとつ、流儀の是とするところというものが、長い年月の間には必ず変化していることを見逃してはならない。世代が代われば当然違ってくるものだ。そうした中で、何を基準とするのか。それは能の本質を見据える事だろう。その視点で流儀の優れた所をはっきりと認識すると同時に、流儀の抱えている問題点も見えてくるはずだ。実際この何年かの間に流儀内部でいろいろな変化が起きて来た。指導ということでも大きな変化が起きて来ている。このことに対応して行くにはどうすればいいのか。
自分のことを振り返れば、親からの教えがあり、喜多実先生からの徹底した基礎教育によって自己形成が始まった。そして能を自覚的に見る年になって、他流の優れた個や能の集団の有り様を目の当たりにした。自分はこのままでいいのかという問いかけをもちながら修行をした。その頃は当然批判も受けた。しかし本当に自己を確立するためには、親の価値観や流儀の規範を一度は疑い見直すということを通過することが必要なのだ。それがなければ、その個はスケールの小さなものになってしまう。
能は個では出来ない。だからこそ広い視野と魅力を持った個が集まり、切硅琢磨することが能を豊かにするのだ。
写真 粟谷能夫「砧」撮影 東條 睦
^
面に想う投稿日:2018-06-07
面に想う
粟谷能夫
 私が初めて面を手に取ったのは子どものころ、お能ごっこのために父よりもらった稽古面でした。それをかけて廊下を走っていた記憶があります。そして子方として舞台に出るようになり、シテのかけていた、小面、曲見、怪士等と対面しました。殊に『船弁慶』の後シテの面はとても怖かったことを覚えています。十代後半頃になると演能用の装束出しを手伝うようになって、面、装束に触れる機会が増え、殊に面に強い関心を持つようになりました。
私が初めて面を手に取ったのは子どものころ、お能ごっこのために父よりもらった稽古面でした。それをかけて廊下を走っていた記憶があります。そして子方として舞台に出るようになり、シテのかけていた、小面、曲見、怪士等と対面しました。殊に『船弁慶』の後シテの面はとても怖かったことを覚えています。十代後半頃になると演能用の装束出しを手伝うようになって、面、装束に触れる機会が増え、殊に面に強い関心を持つようになりました。
粟谷家の面、装束は祖父益二郎が苦労して収集したものが大半ですが、父も面を中心に収集を続けていました。
父の話では、戦後すぐの頃には銀座あたりの骨董屋に面の出物があり、ずいぶんと集めたそうです。その後は道具屋に頼んで捜してもらっていましたが、ある時その道具屋が十面ほど置いていったことがあります。四、五面はとても良い面で、残りはあまり必要としないものでしたので、私はてっきり良い面だけを求め、残りの面は返すのかと思っていましたら、父はすべて求めました。あとでその話をしたら、こちらの勝手ばかりすると次がなくなるのだ、と。大人の世界を垣間見た思いがしました。父だけでは手に負えない時は、目の届く範囲の方々にお世話しておりました。新しい面が手に入ると必ずその面をかけて能を舞う事を楽しみにしていた父。この面なら、あの曲にふさわしいなどと、面から能を発想することを楽しんでいるようでした。祖父や父の努力のおかげで面が揃い、今私たちが能を舞う時、多少の面の選択も出来る程で感謝しております。
私自身も粟谷家蔵の面や新しく求めた面を手に取る機会が多く、面への目利きの基礎が養われました。家の面、装束の把握が出来てくると、あの面がかけたい、あの装束が着たいと思うようになって、目標の曲目が出来ていきました。しかしその曲目へ到達するには、まだまだやらなくてはいけない事が山積みになっていることも事実でした。
二十歳ごろまでは、私の演能の面、装束は父が選んでくれ、それで勤めましたが、その後は少しずつ自分の主張を通すようにしてきました。能はシテの考え方次第で、面、装束の選択の幅があるものですから、今は自分で責任を持ち決めております。
先日の『船弁慶』(平成十六年秋の粟谷能の会)の前シテでは、その前の番組『砧』のツレが小面をかけるので、小面の使用を避けました。小面にもいろいろな表情のものがあるのですが、やはり、前後は重ならない方がよいという判断で、私の方は孫次郎系統の面としました。
面は手に取って見て良いと思ったものが、必ず舞台で良いわけではなく、またその逆の事もあります。舞台で最初の感じは良いのに、舞台が進行しても表情を一つも変えない物もあり、ここにはシテの責任もありますが、まことに難しい生き物のようです。面はある意味完成品ではなく、シテの演技の余地を残しているものの方が良いと思います。
父と面を通して感じ合っていた共通認識を基本に、面の力を借りる時もありましょうが、面を遣いこなす芸力をつけていきたいと思っています。
『船弁慶』粟谷能夫 粟谷能の会 撮影 東條 睦
美醜一如 粟谷能夫投稿日:2018-06-07

あるところに長者が住んでいました。その長者の家の門口にある日美しい女性が現れ、その名を功徳天(幸福を呼ぶ神)といいました。長者は喜んで早速家の中に招き入れ、いつまでも留まるように願い出ます。すると、功徳天は「私には妹がおります。その妹と一緒なら」というので、長者がそれに応じると、やって来た妹は二目と見られぬ醜女でした。黒闇天(災害を呼ぶ神)といいます。
長者が「妹は困る、姉だけにしてほしい」と言ったところ、姉は「私と妹はいつも一緒に暮らしており、離れて生活する訳にはいかないのです」というので、困った長者は思案の末、結局二人を断ったというのです。
この説話は涅槃経に出てくる物語です。幸福と災害、或いは善と悪、この二つは別個の存在のように見えても切り離すことの出来ない一つのものであり、双方とも真実なのだと教え、姉妹を断った長者の思考は、いわば私たち人間の分別であり、分別はしばしば、真実を遠ざけ、ものの道理を不明にすると結んでいます。
お能でも同じような真実が描かれます。
『葵上』では、シテ六条御息所がワキ横川の聖の法力により「此の後またも来るまじ」と神妙に引き下がるのですが、「まず此度は帰るべし」と明らかに再来を予言する『鉄輪』のときよりも、一層重苦しい後味を感じます。六条御息所は深い教養に身を包んだ女性です。教養とか理性とかいうものは、人生の深刻な悩みの解決には大してプラスにはならぬばかりか、時にはマイナスに作用するもののようです。『道成寺』のシテのように髪を振り乱して日高川に飛び込むほどの行動を敢えてさせなかった彼女の誇りや理性が、いつまでも後悔と入り乱れて『野宮』のような陰鬱な苦しみを味あわせているのだとはいえないでしょうか。
これらに描かれる執心は一つのものにすべてをかける情熱というようなものに通じ、すべての女性が備えている本来は非常に美しい性質のものであると思います。その執心の対象が奪われさえしなければ、これらの悲劇も起こらなかったでしょう。
人間はだれでも、心のうちに美醜をあわせ持っています。理性で醜さを消そうとしても、たやすく消せるものではないようです。おきびのように鎮まっていた醜い感情が、あるとき燃え盛り、あたりを焼き尽くすこともあるのです。人間の悲しさ、人間の真実。これを能は余すことなく描いています。そこには物質的な幸福より心理的な幸福を求めている人間の心情があるのでしょう。
謡の覚え方と上達の秘訣投稿日:2018-06-07
謡は能という戯曲の詞章(文章)を声を出して歌い上げるものです。
私たちシテ方の能役者は詞章を暗記します。
それは会話文でも、想いを込めた胸の内の感情であっても、舞台進行に伴い
すべて声を謡の音に変えて発し、観客に伝えます。
地謡は、謡うためだけの専門分野です。
文楽の義太夫や歌舞伎の長唄などの謡い手は、本を見ますが、能では役者はもとより地謡も謡本を見ることはありません。ですから謡の詞章を覚えなければならないのです。
芝居の役者さん同様、台詞覚えも仕事の一つで、これが一苦労です。
若い時分、謡を覚えるのは、鵜呑み、丸暗記でした。
謡っている意味など理解していません。とにかく声を出して、音で覚えます。繰り返し声を出すことで、身体に叩き込むやり方です。
若い頃は頭脳も柔らかいのでしょう。不思議と意味も判らないのにどんどん覚えられました。今は違います。脳細胞が減ったためでしょうか。二倍は時間がかかります。
この若いときの丸暗記は悪いことではないと思いますが、しかし大人になり、そのまま変えないのは問題です。舞台芸術にはならないからです。
大人には、大人の覚え方が必要になってくると思います。
理屈がわかり、意味を知り、型(動き)を把握して、謡声でフォローして覚えるのです。
では、謡を習われている謡曲愛好家の皆様に、謡上達の方法をお教えしましょう。
それは舞台人同様、暗記することです。
謡を暗記し声を発すると、その謡の言葉が生き生きと響いてきます。
何故でしょうか?
下を向いて前屈みで、謡本を読んでいると声の通りが良くありません。
しかし暗記すると姿勢を真っ直ぐにして声を出すことができます。すると身体全体を使って共鳴させて声が出るのです。
嘘だとお思いなら、一度試してみて下さい。
それから、もうひとつ、
能をたくさん観ることです。
但し、舞台に目を向けて鑑賞して下さい。
折角能楽堂にいらして能をご覧になられても、膝の上においた謡本の詞章ばかり見ていては、謡を聞いているだけに過ぎず、それでは役者の動きが判りません。
舞台で能役者の動きに、注目して下さい。
そして、ここからが大事です。
謡うときは、その見た能の光景を思い出しながら謡ってみるのです。
『羽衣』を謡うには能『羽衣』をご覧になり、想像しながら謡います。
きっと上手に聞こえるはずです。是非試してみて下さい。
(平成23年1月 粟谷明生記)
人生五十年投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
人生五十年
粟谷菊生
昔、商店には錠のかかる銭箱があって、毎日の上りを入れておき、それが商売の資金として活用されてきたといわれる。
考えてみると、芸の道も同様だ。ぼくたちが若い頃から一生懸命稽古を続けてきた、その日銭の貯金があるおかげで、年をとった今日でも能が舞えるのかと思う。
その銭箱の中身には、自分の体験のほかに、先輩の芸に学んだ預金も、たくさんはいっている。なかには他流の芸に学んだものもあるが、その蓄積のおかげで、七十四歳の今日も能が舞えるのだろう。
ところが近ごろ、郵便貯金の利率が低くなってきた。百万円に対しての○・三%は、利息も甚だ僅かなものだから、昔の銭箱だけでは、なかなか間に合わなくなってきた。年をとってもなお、毎日稽古に励み、日銭が減らないように勤めなければならないのではないか。
昔は、十七歳で道成寺を披いたという人もあったけれど、それは「人生五十年」の時代のこと。金さん銀さんの居られる長寿時代の今日では、披きが高年齢になるのは、当然のことだろう。
先年、八十人ほどの弟子を集めて、宮島で浴衣会を催したことがあった。その謡い、舞う人々の中に、九十歳以上の人が四人もいたのには驚かされた。
考えてみると、古来稀なりの古稀が七十歳、不惑が四十歳とは、とんでもない話だ。今や百歳がざらにある世の中だから、百二十歳位が古稀にふさわしいのではないか。ぼくは七十四歳でも、未だに迷っているのだから、不惑は八十歳かな。
ところで、ぼくの考える人生五十年とは、自分の年から数えて、上の二十五年、下の二十五年の人たちといっしょに能を楽しみ、その影響を受け、あるいは下の人たちにそれを及ぼしながら、緻密な能を作り上げていくことかと思うが、悲しいことには、自分が年をとるにつれて、上の二十五年が、だんだん薄れていくのはさびしいことだ。最近、下の二十五年の人たちに、やさしく扱われるのに気づいてきたが、同情されるようになったらおしまいだ。適当なお邪魔虫になって頑張りたいと思う。
それにつけても、人間、口を動かすことが長寿の秘訣だという人があるが、年をとって会社を退職して、俳句や盆栽を楽しむのもいいが、昔から「おしゃべりにモーロクなし」の諺もある。口を動かす謡いに打ちこむのも、長寿の世の中にふさわしい健康法の秘訣かもしれない。せいぜい長生きして、謡の妙味を楽しんでいただきたいと思う。
型付と向かい合う投稿日:2018-06-07
型付と向かい合う
粟谷能夫
 型付けには奥深いものがある。おもに江戸時代から明治迄の先人がいろいろな経験の中から見つけ出した演出が記され、大変貴重なものである。動きや演出上の心得の後、最後には「—も宜し、—も有り、—は損なり」といったものが入り、その書き方には幅といったものが感じとれる。だから問題は、読み手が型付をどれだけ深く的確に読みとれるかということになる。型をなぞるだけでは駄目なのである。たとえば『烏頭』のカケリの場面、囃子の手組で大小の鼓が「ツタツタツタタ」と打ち、シテは「トントントン」と三つ拍子を踏み、大鼓が大きな掛け声で「イヤー」と頭(かしら)を打って「親は空にて血の涙」となる喜多流独特の型がある。型付けにはこの「トントントン」は近づく、歩み寄るという意味合いだと書いてあるが、今はただ結んで拍子を踏むだけになっている。しかし大事なのは子鳥を捕らえようと近寄るという意識で、ぐっと前に出る思いを込め、演ずることだろう。ただ「ドントントン」と拍子を踏むだけでは駄目なのだと思う。やっている型としては同じでもそういう思いが含有されているといないとでは表現が違ってくる。また『梅枝』の「夫の形見を戴き、この狩衣を着しつつ、常には打ちしこの太鼓の…」で、頭をさす。続いて衣を見る、そしてまた太鼓を巻ざし見ると三つの具象的な型が続くところがあるが、伝書には三つの型が続くと死ぬというような事が書いてある。『梅枝』は同じ題材を扱った『富士太鼓』とは違って、夢幻能の極致のような曲だから、生々しくなっては駄目だという教えだと思う。そこに注意しないと、一つ一つの型が生かされず、型そのものの味わいが死ぬという意味だろう。この教えを理解した上でなら、三つの型を続けても、演じようによっては十分成り立たせることが可能だと思う。知らないで演ずるのとでは自ずと違いが出てくるはずである。これを極端な例だが「三つの型を続けて演じると演じ手が死んでしまう」と解釈するようでは困ってしまうのである。このように、型付には基本の型の他にいろいろな情報が書き込まれている。そこから先人の心に深く分け入り、読み取っていく喜びは大きいものがある。自分が一つの曲に対してどこまで考え抜き、稽古を重ね、先輩達や他流の人達の舞台から多くを吸収するか、そういうことが積み上がっていくと、同じ型付が違うように読みとれることがある。日々発見があり、新たな発想をもたらしてくれる。時には型付通りということを越えて、自分に引き寄せて創造することがあってもいいとさえ思う。そういう意味では、その役者としての広がりがどこまであるかということが問われることになる。結局は日々の能に対する真剣な向かい方、その積み重ねが大切だということだと思う。
型付けには奥深いものがある。おもに江戸時代から明治迄の先人がいろいろな経験の中から見つけ出した演出が記され、大変貴重なものである。動きや演出上の心得の後、最後には「—も宜し、—も有り、—は損なり」といったものが入り、その書き方には幅といったものが感じとれる。だから問題は、読み手が型付をどれだけ深く的確に読みとれるかということになる。型をなぞるだけでは駄目なのである。たとえば『烏頭』のカケリの場面、囃子の手組で大小の鼓が「ツタツタツタタ」と打ち、シテは「トントントン」と三つ拍子を踏み、大鼓が大きな掛け声で「イヤー」と頭(かしら)を打って「親は空にて血の涙」となる喜多流独特の型がある。型付けにはこの「トントントン」は近づく、歩み寄るという意味合いだと書いてあるが、今はただ結んで拍子を踏むだけになっている。しかし大事なのは子鳥を捕らえようと近寄るという意識で、ぐっと前に出る思いを込め、演ずることだろう。ただ「ドントントン」と拍子を踏むだけでは駄目なのだと思う。やっている型としては同じでもそういう思いが含有されているといないとでは表現が違ってくる。また『梅枝』の「夫の形見を戴き、この狩衣を着しつつ、常には打ちしこの太鼓の…」で、頭をさす。続いて衣を見る、そしてまた太鼓を巻ざし見ると三つの具象的な型が続くところがあるが、伝書には三つの型が続くと死ぬというような事が書いてある。『梅枝』は同じ題材を扱った『富士太鼓』とは違って、夢幻能の極致のような曲だから、生々しくなっては駄目だという教えだと思う。そこに注意しないと、一つ一つの型が生かされず、型そのものの味わいが死ぬという意味だろう。この教えを理解した上でなら、三つの型を続けても、演じようによっては十分成り立たせることが可能だと思う。知らないで演ずるのとでは自ずと違いが出てくるはずである。これを極端な例だが「三つの型を続けて演じると演じ手が死んでしまう」と解釈するようでは困ってしまうのである。このように、型付には基本の型の他にいろいろな情報が書き込まれている。そこから先人の心に深く分け入り、読み取っていく喜びは大きいものがある。自分が一つの曲に対してどこまで考え抜き、稽古を重ね、先輩達や他流の人達の舞台から多くを吸収するか、そういうことが積み上がっていくと、同じ型付が違うように読みとれることがある。日々発見があり、新たな発想をもたらしてくれる。時には型付通りということを越えて、自分に引き寄せて創造することがあってもいいとさえ思う。そういう意味では、その役者としての広がりがどこまであるかということが問われることになる。結局は日々の能に対する真剣な向かい方、その積み重ねが大切だということだと思う。
写真 『鵺』シテ 粟谷能夫 撮影 あびこ喜久三
百拾五曲投稿日:2018-06-07
百拾五曲
粟谷菊生
 先代梅若六郎先生は、『輪蔵』のシテ一曲だけを残して全曲を舞われたと聞く。自分の能を振り返ってみると百拾五曲勤めている。しかし、その中で圧倒的に多いのは二番目物、四番目物、キリ能だ。好きなのに比較的少ないのが三番目物。友枝喜久夫先輩、兄新太郎の存命中は春秋会、果水会、鼎の会など演能の催しがしばしばあったが、三番目物は二人の先輩が優先的にお取りになってしまう。そのお蔭で人のやりたがらない曲、例えば『羅生門』などを勤めさせて頂くことにもなり、これは良い経験だったと思う。
先代梅若六郎先生は、『輪蔵』のシテ一曲だけを残して全曲を舞われたと聞く。自分の能を振り返ってみると百拾五曲勤めている。しかし、その中で圧倒的に多いのは二番目物、四番目物、キリ能だ。好きなのに比較的少ないのが三番目物。友枝喜久夫先輩、兄新太郎の存命中は春秋会、果水会、鼎の会など演能の催しがしばしばあったが、三番目物は二人の先輩が優先的にお取りになってしまう。そのお蔭で人のやりたがらない曲、例えば『羅生門』などを勤めさせて頂くことにもなり、これは良い経験だったと思う。
甥や息子たちから、また同じ曲を演(や)るのかとよく言われたけれど、その曲が好きなだけでなく、リクエストされるからだ。『景清』『鬼界島』『頼政』『藤戸』『隅田川』『羽衣』などはそのよい例だ。『羽衣』などは何回舞っているか判らない。頼まれれば嫌といえない性質(たち)でなんでもお引き受けしてしまうと言いながら、何回頼まれても演らなかったものが一つある。それは『翁』だ。自分が選ぶとつい、好きな曲ばかりになってしまうが、その最たるものが『羽衣』で『班女』も好き。勿論、『湯谷』『松風』も好きなのだが、二人の先輩亡きあと、自分の好みの地を謡って貰える後輩の成長を待っていたこともあって、三番目物の上演回数は意外に少ない。『富士太鼓』『天鼓』『融』『烏頭』『鉢木』など好きな曲の多い中で、NHKで放映された最後の能は、自分にとってはやはり『景清』と希望したが、諸般の事情で『大江山』になってしまった。
こうしてみると、まだまだ舞残している曲はあるけれど、喜多流に長い間、あまり演能されていなかった『梅枝』は僕が舞ってから後輩がよく演能曲目の中に入れるようになったし、喜多流で二百年位誰も舞っていなかった『伯母捨』を自分が久々に勤められた事で自分としては満足に思っている。因みに老女物を喜多流ではあまりに大事にしすぎて高齢になってからでないと勤めさせて貰えなかったが、老女物だから老人になってからでないと、というものではない。老女物は非常に体力が要る。故に壮年に一度体験しておいて、人生のいろいろな「おもい」を味わってから、後年、もう一度演じてみると、本当のよい結果が出るのではないかと思う。身体がキカナクなった時「本質が判る、本当の花が判る」というのも事実だ。
僕も舞い残した曲は、あの世に先に逝かれて僕の逝くのを首を長くして待ち構えておられる諸先輩方の囃子や地で舞わせて頂くことにしよう。
写真 『実盛』17年2月5日 出雲康雅の会 撮影 石田 裕
我流『年来稽古条々』(25)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(25)
??研究公演以降・その三
『求塚』で地謡の充実
明生 第三回の研究公演では、『求塚』を取り上げ、地謡の充実をテーマに取り組みました。友枝昭世師にシテをお願いし、我々は地謡を勤めたわけです。それがメインで、私は『松風』の舞囃子、能夫さんが『知章』の仕舞、父は『谷行』の素抱という珍しい小書の仕舞を舞ってくれて、石田幸雄さんに狂言『抜殻』という番組構成でした。平成五年五月、もう十六年前ですよ。あのころ地謡の充実を、と考え企画したわけですが…。


能夫 自分たちが主催する会で、シテをやらずに地謡を謡います! なんていう人は、それまでいなかったよね。
明生 一番でも多く舞いたいと思うからこそ、苦労して会を主催するわけですから、普通はありえない。地謡にまわって、シテをしないことは、一回舞うチャンスをつぶすことですからね。それを敢えて能夫さんはやろうとした。成果はどうあれ、地謡の充実を掲げることに意義があるとしたことに間違いはなかったと思いますが、自画自賛かな?
能夫 シテがどんなに舞台で頑張っても、地謡が充実していなければ、その作品は成立しない。シテと地謡をどうつなげていくか、そういうことが肝腎なんだ。
僕は、喜多流の能楽師はシテを勤めるのはもちろんだけれど、物着せから地謡、後見、すべてができる、オールマイティの人間であるべきと思っているんだ。シテを舞っているときでも、地謡や装束付けの苦労がわかり、対応できる人材でなければいけない。すべての面でオールマイティなのが能楽師だ、とずっと思っていたからね。シテを舞っていれば楽しいけれど、それだけではない、あらゆる経験をしたいと。それで、自分たちが主催する会だったら何から何まで自分たちで設営できるからね。それでこういう趣旨の会を研究公演でやりたいと提案したのさ。
明生 舞がない、謡だけで勝負する曲。能夫さんが『求塚』という大曲に挑もうと決められて、よい選曲でしたね。痩女物の春の代表曲で、そう頻繁に出る曲ではないし、友枝さんは初演でしたが、我々が謡いますから…と無理にお願いして。当時父は「一番でも多く舞ったほうがいいのに、お前らは何を考えているんだ」と、憤懣気味でしたが…。
能夫 それは菊生叔父とすると、「俺がいるじゃないか!」なんだろうね。(笑い)
明生 それで能夫さんがコンコンと説明してね。今は菊生叔父ちゃんがいらっしゃいますよ。だけどそのうち…いなくなるわけですから、次のことを考え、地謡がしっかり謡える人材を作っておかなければいけないんじゃないですか?・・・と。残念ですが、今そうなってしまいましたね。
能夫 それは仕方ないこと、自然なんだ、当たり前のことで、次のことが見えてこなければいけないでしょう。菊生叔父だって地謡の重要性はわかっていて、晩年はとくにそのことを主張していたからね。当時、菊生叔父は元気で地頭を頑張っていて、喜多流の能を支えてくれていたけれど、将来は我々にそれを託したい気持ちはあったと思うよ。
明生 謡が大事、と盛んに言っていましたね。
能夫 研究公演の『求塚』では、まわりが全部先輩だったよね。大鼓の柿原崇志さん、小鼓の北村治さん、笛は一噌仙幸さん、脇は宝生 閑さん。いろいろと経験をされてきた人の知恵や力を拝借して謡ったという感じだったね。僕らが新たなものを創るというよりは、伝統的というか・・・。
明生 経験者のお力を借りて学ぶという・・・。
能夫 そう、お力を借りながら、自分も何か表現したいなという気持ちはあったと思う。観世寿夫さんの『求塚』の連続写真があるけれど、そこで打たれているのは北村治さんだからね。そういう経験をされた方々と対峙して謡いたいと思ったよ。あのとき、治さんから「死ぬ気で謡え」って言われたよね。こっちは精一杯謡っているのに。でも甘かったのかもしれないね。囃子方の経験に対して僕らなりの主張したい謡い方と、舞台上でのキャッチボールはあったことは確かだね。そういう囃子方とのぶつかり合いが大切で、それがないといけないだろうね。
明生 あのとき、地謡の充実を掲げてやった体験が、このごろ舞台で少しですが活かせるようになったかな、と思っています。この間、『須磨源氏』(青年能)の地頭を勤めて…。『須磨源氏』はシテを勤めたことがありますから、自分なりの舞台展開が見えてくる、すると自然と謡い方も変わってきます。
能夫 そう違ってくるね。経験は大事だよね。
明生 位取り、乗り具合、音の高低など、ある程度自信を持って主張できるのです。そうすると、その能のドラマを支えているのは、シテだけではなくて地謡の底力だということが、だんだん肌で感じられてきます。地謡は作品全体を包み込むような力を持たないといけない・・・と。
以前はただ頭で考えていただけで、体感出来ていなかったかもしれないのです。もっとも地謡の前列で謡うだけでは深いところの体感は難しく、やはり後列や地頭で謡うと責任感も環境も全然違ってきますから。
能夫 そうだよね。本当に地謡の大切さがわかるよね。
明生 それも、ある時期に「地謡の充実」を意識したからこそ大切さがひしひし感じられるのだと思います。
その後、私は『求塚』を披いていないのですが、能夫さんは平成十二年の粟谷能の会で演られましたね。地謡を謡い込んで舞うのと、そうでない場合の違いはどうですか?
能夫 うーん、それはね。あのとき地頭をやらせてもらったからできたことがすごくある気がする。後シテの「飛魄飛び去る目の前に」とか「鴛鴦の鉄鳥となってくろがねの」のあたり、親父たちのやり方は、テクニック的にはテンション高くすごいけれど、あまりその情景が立ち上がってこなかったような気がしてね。もっともそれはそれで素晴らしさはあったと思うけれど、そこに描かれているリアリティが欠如しているように感じたんだ。それに対して、友枝昭世さんは最新型を見せてくれる人でしょう。実先生、友枝喜久夫さん、父新太郎、菊生叔父が演っていた『求塚』の像があるとすると、昭世さんはそういうものはわかっているが、だけど自分はこのようにしたい、と最新型を示してくれる。
明生 最新型ですね、今風に変える力というか、今まで見落としてきたものに光をあてる、そういうお能創りですね。
能夫 今まではこうだったけれど、自分はこうやりたいという主張がある。親父たちには無かったもの。ただテンション高くやりましょうみたいな。それで素晴らしい面もあるんだけれどね(笑い)。僕はそういうものと違うやり方をしたいなと思っていたんだ。
そのお能のなかにどういうことが描かれていて、だからこういう表現になるというのでなければならないと思う。右向けと言われたから右向くというのではなくて、どうして右を向くのかを意識する。たとえば「風の行方をご覧ぜよ」で、型付に目付柱の方を見ると書いてあるから、そこを見る、それだけでは伝わらないよ。リアリティが無いじゃない、芝居心がないでしょ。風の行方を見る、風がふーっと通っていく、それに合わせて顔を動かす、とやらなければ。謡にしても、抑揚とかテンションだけでなく、一つ一つの言葉の意味を感じ表現しなければ・・・、そういう親父たちとの落差をとても感じた。
研究公演では『求塚』に関して、こうしてくださいと友枝さんに言えるほどの立場でもなかったし、そこまで自分も掘り下げていなかったけれど、そういうことは感じたね。だから次に、自分が勤めるときは、そのときに感じた経験が生かされたと思うよ。
明生 このことは、能夫さんが憧れた観世寿夫さんが目指したこととも通じますね。
能夫 そうね。何もしていないけれどある意味格好よくやってしまう親父たちの芸風と、寿夫さんたちのようにある主張もって表現していくという、僕は両方を観てきたから。
明生 友枝昭世さんも両方を観てこられて、自分はこうやりたい!をはっきり主張なさる。私はそこからいろいろ学ばせてもらうことが多いです。
私はまだ『求塚』を勤めていませんが、実は平成十年の大槻自主公演で、父に、「明生、いざとなったら舞えるようにしておいておくれ」と言われて代演のための稽古を受けました。そのとき研究公演での経験が助けになりました。結局、父は無事に勤めて、幸雄叔父が地頭で、能夫さんが副地頭、私も隣で謡わせてもらいましたが、研究公演の経験があったから、自分なりに自信を持って謡えました。大槻公演の客演という場で観客はもちろんのこと関西の三役の方も、喜多流の『求塚』とはどんなものなのか、興味を持たれていたとひしひしと感じました。私たちの地謡はこう、と自信を持って謡えたと思います。謡の重要性を意識した研究公演の『求塚』の経験が活かされている。だからこれからもどんどん意識してやっていきたいですね。
話はずれますが、『望月』のシテを勤めたあと、能夫さんに謡をもっと意識しなければ、と注意されましたね。『望月』は、ほとんどが科白、言葉ですから、正直、謡への意識がありませんでした。以前、故観世銕之亟先生に「ノリ地は語るように、科白はノリを意識して」と教えていただいたこともありました…。
能夫 語りというと、語りの調子があるけれど、そこに留まると謡がひと色になるということなんだろうな。僕もそういう謡をと、意識しているよ。
明生 「勁き花」(八世観世銕之亟遺稿集)に、銕之亟先生が「集団としての個性とは、個としての能役者の現代に生きる自覚と舞台に立てる役者としての身体とが稽古によって一人一人に培われてこそ、素朴な手織りの確かな舞台が出来、そのときにこそ発揮されるもの…本当の集団とは個々間に強い抵抗が在りながら一つの目的を共有する…」とありましたが、本当に今そう思います。
能夫 そうだね。個の力だよ。謡を大事に、個の充実。僕らが地謡の充実を目指しはじめたとき、周りの人は何か回り道をしているように思っていたかもしれないが…。
明生 それは回り道でなくて、通過しなければいけない道なのではないでしょうか。
能夫 長期的な視野に立つことって大事でしょ。
明生 そうですね。そして、ただ謡だけ充実すれば完璧かというとこれも片手落ちでして…。やはりたくさん舞う機会を作ることも必要で、『須磨源氏』で経験したように、シテを経験したからこそ謡える世界って、ありますから。シテと地謡、双方バランスよくが一番で、それが本物への近道です。だから極端はいけないかもしれないけれど。
能夫 もちろん両面が必要だけれど、今、喜多流全体としてみたとき、謡の重要性への認識を高めることが大事だと思うよ。謡への意識が希薄でしょう? その指針みたいなものがないよね。
明生 タイムズの対談で、梅若玄祥さんが、地謡は大事です、しかしその育成となると…と危惧しておられましたが、謡の育成というのは能楽界全体の問題でもあるようですね。他流のことは判らないので別として、喜多流として、そろそろ指導・育成の方法論を再考しないといけないと思います。間違えずに拍子をはずさない、だけではなく、謡の内容を深く知り、節扱いももっと細かく知ること…。どうも 喜多流は武士的なニュアンスが強く、竹をスパッと割ったような謡、とやや曖昧な言葉に甘えているように思えてなりません。それは教える方も教わるほうにも…。
能夫 そうだね。たとえば『班女』だったら「翠帳紅閨に枕を並ぶる床の上・・・」をどう謡うか。愛し合っていたときのことを思い出しながら、今は失われた恋を謡うわけでしょう。それを、下音はこの音、節はこう扱って、だけでは謡えないでしょう。
明生 『千寿』で「琴を枕の短か夜のうたた寝、夢もほどなく・・・明け渡る空の…」、抱き合って一夜を過ごし、夜が明ければ別れなければならない、その状況をどう謡うか。そのためには、もちろん経験も大事(笑い)、それから千寿と重衡がどういう間柄で、どういう生き方をしたか、その背景が身体を通して謡えるようにならないと…。
能夫 千寿はもともと頼朝の愛人でしょ。捕虜になった重衡が都に送還されるとき、慰めのために遣わされるわけで、それが恋をしてしまうのだから、複雑だよね、そう簡単には謡えないよね。
明生 そのあたりは、謡本だけでなく、平家物語にも目を通す。深い事情や、意味を知っているのと、そうでないのでは、謡の聞こえ方に違いが出てくると思います。詞章の読みも、能全体に描かれたことの読みも深く深くですね。
能夫 そう。だから源氏物語も読まなければならないし、伊勢物語も読まなければいけないわけなんだろうね。それと、他流はどういう表現をしているかとか、もっと広く音楽や演劇の世界にも関心をもってもいいよね。
明生 そういうことを意識して、早いうちから蓄積して、もちろん謡の技法の徹底した学習も伴っていかないと…、将来、間に合わないかもしれませんからね。
能夫 志と経験と外への関心、こういうことが必要だね。
明生 そういう意味では、地謡の充実を掲げた研究公演は、若い私たちに志があったと自負出来ますね。
能夫 そうだね。
明生 その後、平成十七年に研究公演を復活して、『木賊』(シテ・友枝昭世)で地謡の充実に再度取り組みまして…。
能夫 そして来年の十二月に、同じ趣旨で『檜垣』を友枝昭世さんにお願いし研究公演で取り組むことになったね。
明生 我々は地謡の大事さを意識して、微力ながらも、そこを確認する作業はやり続けていきたいですから・・・。
能夫 微力ながらも実践して、みんなもそれを目指そうよというメッセージを込めてね。
明生 十六年前の『求塚』がその原点になったといえますね。
(つづく)
我流『年来稽古条々』子方時代(1)投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
我流『年来稽古条々』子方時代(1)
粟谷能夫
粟谷明生
創刊号で予告しましたように、我々の自己形成を振り返る、我々にとっての年来稽古がどういうものであり、何を学び、何が問題であったかを考えてみます。
能夫─ 僕は昭和三十二年に祖父益二郎が亡くなるまでは稽古は祖父にしてもらった。まだ中野の舞台が出来る前で、朝起きると布団を畳んでそれを片づけ、それに唐草の大風呂敷をかけて八畳二間ほどの所が稽古場になる。南側に縁側があってそれが橋懸代わり、ノレンが揚幕代わりになっていた。そこで祖父に向かい合って謡や仕舞の稽古をしてもらった。その部屋の昔の白い電気の笠を道成寺の鐘に見立てて遊んだ記憶がかすかにある。
明生─ 私はそのころは全く覚えてないです。祖父が亡くなったとき二歳ですから。
能夫─ 子方時代で僕が一番鮮烈に覚えているのは、やはり益二郎が舞台で亡くなった『烏頭』で子方を勤めていたことだ。前日申合わせがあって、行き帰りおじいちゃんと行動を共にしていて染井能楽道の帰りに中野の駅でうどんを食べた記憶がある。
当日の舞台で後シテの出で「陸奥の…」と一言謡って常座で倒れて、人々が右往左往していたことを覚えている。それからこれは後で人から聞かされたことと自分の記憶とが一緒になっているかも知れないが、もうこれで駄目なら最後だと、主治医の先生が心臓に直接モルヒネを注射していたのを記憶している。
明生─ 幸雄伯父から聞いた話ですが、祖父が倒れて地謡後列の親父や新太郎伯父が楽屋に入って行き、戻って来て、後見だった後藤栄夫(観世栄夫)さんが代わって舞う地謡で「親は空にて 血の涙を…」というところを、とても尋常ではない絶叫のような調子で謡うのを聞いて、ああ、もうこれは駄目なのだなあと思った、と聞いています。
能夫─ 僕の子方時代で一番鮮烈な記憶だ。子方時代は舞台の前になるとプレッシャーのためか熱を出してしまい、舞台上で責任感と高熱の引っ張り合いのなか、不思議な緊張感を体験しました。
教わる時は一対一で口移しで教わったが、高い声で一杯に謡わされた。これが何より大事だと思う。こういう教え方が今は出来なくなって来ている。
明生─ 私の子方時代の出演記録を調べると、他に子方がいなかったせいと、またその頃からいろいろな会が増えたせいもあると思うが、とにかく集中して忙しかったです。
教わるといってもせいぜいきっかけになるシテの言葉の一句前位からしか教えてもらえないし、曲の筋も教えてもらえない。だから例えば『国栖』の子方をやったとき、舟の中に入り隠れ、それから出て来たら後は帰るだけだと教えられていても、そのあとに長々と天女の舞があったりすると自分はもう帰っていなければいけなかったのではないかなどと思ったり、全く違う曲に出てしまったのではないかなどと悩んだりしたことがありました。だからある程度曲の筋を教えておいて欲しかったです。
能夫─ 教えられたシテの句が何時出てくるか何時出てくるか、と待ち構えることで、緊張が持続する仕掛けなんだろうけど、これからはそれだけでは充分ではないだろうな。
明生─ 息子が去年『隅田川』の子方を勤めたとき、子供から「どうして死んだ自分があそこで出て行くの?」と問いかけられた。今の子供達は昔のようにうぶではないから、ストーリーと役についてある程度教えておく必要があると思う。
私はいろいろな舞台で子方を勤めたが、その度に必ずどなたかが、遊んでいる自分をその日の舞台に立たせ、今日はこの所でこっちを見るんだよとか、止まる所はここだとか注意や確認がありました。これは今にして思えば、実に有り難いことで、今日になっても舞台に立つときは、前以て舞台のすべり具合や位置、方角などを見る習慣がつきました。
それと私の場合は子方が多くて、例えば「船弁慶」なんて度々やらされていると、アシラウ所なんかもなんとなく解ってくるので、今日は誰々だからここでアシラッた方が良いとか、今日は伯父だから見ないほうが良いのだとか、子供心にも相手とのかけひきみたいなものを小さいときから覚えたみたいです。
能夫─ 僕は祖父が亡くなって、実先生のところで子方のお稽古を受けるようになって、前以て親父に教わって憶えて行って稽古をうけるのに、どうした訳か最期の言葉を教えてもらってなかった。子供心にまだ何かありそうな気がして親父にもっとあるんじゃないかと聞いたが、無いと言われた。それが実先生の所に行って取りこぼしがあると知って、悔しくて泣いてしまった。その頃からだと思う、自分でやらなければいけないという自覚というか、自我が出来て来たのは。
(つづく)
地謡の熱き思い投稿日:2018-06-07
地謡の熱き思い
粟谷能夫
 能はシテ一人ではできない。シテの謡とワキや地謡の謡が躍動感をもって曲の世界を造形し、囃子がそれをくっきり浮かび上がらせる。人に感動を与える能は、そういう総合された力があってこそなのだ。このごろ地謡の重要さに思いをせずにはいられない。
能はシテ一人ではできない。シテの謡とワキや地謡の謡が躍動感をもって曲の世界を造形し、囃子がそれをくっきり浮かび上がらせる。人に感動を与える能は、そういう総合された力があってこそなのだ。このごろ地謡の重要さに思いをせずにはいられない。
今年三月の粟谷能の会に於ける私の『西行桜』に引きつけて考えてみたい。『西行桜』といえば、観世寿夫さんの晩年の舞台が鮮やかに思い起こされる。特に最後の『西行桜』は寿夫さんの熱といおうか、あたたかいオーラが見えてきた。寿夫さんの能はときに怜悧で冷たいと評されることもあったが、あのときの舞台はあたたかい能だと感じさせられた。それは寿夫さんの能世界が変わるときだったかもしれず、その前兆を見たような、不思議な感動であった。それを二十数年経て、今自分が舞おうとしている・・・。
『西行桜』は閑雅の中に桜の美しさを味わいたい歌人・西行と桜の木の精との心の交流とでもいったものを描いている。しかもその桜の精は美しい乙女ではなく、老翁であるところに、この曲の曲趣があって、春爛漫を愛でながらも薄墨桜のような渋さ、老いて散りゆくもののあわれさをにじませているように思われる。
この世界を創り出すのが地謡の謡。謡い出しで、世捨て人も山までも桜の花に誘い出されると謡い上げ、サシのシテとのかけ合いや、クセの地謡で「見渡せば、柳桜をこき交ぜて、都は春の錦、燦爛たり、千本の桜を植え置き・・・」からの桜の名所を経巡っての詠嘆。これらの謡で、地謡が世界を創ってくれるから、シテの「惜しむべし、惜しむべし、得がたきは時、逢ひがたきは友なるべし、春宵一刻値千金」という強い感懐が引き出され、「待て暫し」と春を惜しみ人生を惜しむ風情が浮き上がってくる。これはシテ一人ではどう頑張っても創り出せる世界ではない。
地謡は謡いながらシテを創っていく、全体を自分の中に呼び込んでいくという感覚、よい能だったと思える舞台にはそんな感覚がある。だから地謡は恐くもあり楽しくもあるのだ。シテのためにエネルギッシュに謡うのだという心意気、その世界をどう創るかという思いが地謡一人一人の中にないといけないと思う。
最近「前列病」という病気があると知らされた。ただ座っているだけで、地謡や能に積極的に参加しようとしない症状だ。前列は後列に比べれば責任感の度合いは少ないかもしれないが、一人一人が自覚を持ち地謡を支えていかなければいけない。私が地謡の前列にいた頃の大先輩たちは、どんな曲でも、大いに気張って謡われ、喜多流の謡とはこういうものだと強く体感させてくださった。
我々も次の世代も、この先達のよき伝統を受け継ぎ、地謡の熱き思いを謡っていかなければと思う。そのためにやるべきことは山積みされている。
写真「西行桜」 粟谷能夫 撮影 東條睦
続・面について投稿日:2018-06-07
続・面について
粟谷能夫
 父新太郎がいつも好んで掛けていた小面があります。先輩のお世話で手に入れたものですが、父が最初に集めた面で、我が家の小面の中でも一番年増の表情をしています。同じ小面と呼ばれる面でも表情や年齢に幅があり、この曲なら、この小面が相応しいとか、この小面なら演出の幅がここまで出来るなど演能意欲をかきたてられます。
父新太郎がいつも好んで掛けていた小面があります。先輩のお世話で手に入れたものですが、父が最初に集めた面で、我が家の小面の中でも一番年増の表情をしています。同じ小面と呼ばれる面でも表情や年齢に幅があり、この曲なら、この小面が相応しいとか、この小面なら演出の幅がここまで出来るなど演能意欲をかきたてられます。
私も当初あまりふくよかでない清楚な表情をした小面ばかりを使っていました。その大人びた印象に引かれたのだと思います。やがて自身の成長と共に様々な発想が生まれ、曲趣といおうか、その曲にふさわしい面を選択するようになりました。
時が経ち『野宮』を舞うことになりました。シテの深層心理の複雑さを考えると小面では成り立たないところがあるような気がして、たいそう悩んだ思いがあります。当時は喜多流の専用女面は小面を使う厳然たる流是があり、小面以外の選択肢は考えられませんでした。『野宮』に使えそうな小面を二、三面手にとり、結局、父が好んで使っていた小面といたしました。何か小面の創成期に近い古風な表情をしており、中に強靭な意志を含んでいるような力強い小面です。また一方でつややかさもあり、ひとことでは言い表せない深みのある面です。
能を舞う時には、どの面にしようか、装束は何にしようかと、まず第一に面の事が頭に浮かびます。観世寿夫先生は「面は安心して己の全部をゆだねられるものであってほしい、と同時に思い切って闘い合える相手でもなければならない」と書いておられます。この言葉は肝にめいじておかなければと思っています。
面と向かい合う機会が増えてゆくと面の裏の様子や刻印、面目利き極め書にも目が行くようになり、面打師の事にも興味を覚えるようになりました。
能面伝書によると、桃山時代から江戸時代になってくると、世阿弥が挙げた十人の能面作者は「十作」、室町末期までの六人の名人を「六作」と称するようになって、江戸期になると世襲能面打家が確立していったようです。
また九代目喜多健忘斎古能の著した「仮面譜」や「面目利書」を通して、能面の名称の起源、焼き印の形、彩色、かんな目の特徴などいろいろのことを学びました。健忘斎藤古能は多くの伝書を残してもいて喜多流にとっては中興の祖であります。広島の厳島神社所有の能面の中にも裏面に喜多古能の花押のある極め書があるものが多数あり、古能の面に対する造詣の深さを見て取れます。
家伝の面の焼き印や目利き極めに是閑、大和など多数の作者名を見出し、古面(新作面に対する)を持つことの豊かさをかみしめています。同時に、父の七回忌の今年、一面一面コツコツと集めてきた、祖父や父の仕事の大きさに、改めて思いをいたしているところです。
写真 『卒都婆小町』17年3月6日 粟谷能の会 撮影 東條 睦
小面 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
メイキングNHKテレビ 「芸能花舞台」 その1投稿日:2018-06-07
メイキングNHKテレビ 「芸能花舞台」 伝統の至芸 粟谷菊生
***その舞台裏話 ゲスト 山崎有一郎と粟谷明生が語る***
○前置き
この度、NHKの芸能花舞台・伝統の至芸で、没後三年となった粟谷菊生を取り上げていただきました。放映は平成21年10月22日(再放送:同10月25日)。
菊生の舞台映像とともに、葛西聖司アナウンサーのご案内で横浜能楽堂館長の山崎有一郎氏と私、粟谷明生が、菊生の芸風や思い出を語る内容です。
この制作に当たり、NHKのディレクター安里恭幸氏と数回の打ち合わせ、山崎氏とはご自宅にお邪魔してお話を聞かせて頂きました。いろいろな昔話や楽屋裏話が飛び出しましたが、残念ながら時間の都合で放映されたのはそのごく一部です。
そこで打ち合わせ中に出た面白い話、貴重な話をここに再現し、舞台裏をご覧いただきたいと思います。これを読まれて再度、ビデオなどで放送をご覧いただくと、面白さも倍増するのでは、と思います。
写真 録画当日 右より 葛西聖司 山崎有一郎 粟谷明生
○二人の師
?粟谷菊生さんは二人の師匠・名人十四世宗家喜多六平太先生と十五世宗家喜多実先生に習らわれましたね。お二人の芸風の違いはどんなものだったのですか。
菊生さんがお二人に習って苦労した話を、ご自身が語っているインタビュー映像を紹介したいので、よろしくお願い申し上げます。
山崎 喜多六平太先生の芸風は、ほわっとした情の人だね。実さんはカチッとした古武士的な強さを持って、知の人ですよ。古武士的なキリッとした感じというのは、僕は喜多流の流是でもあると思うよ。
六平太という人はものをあまり考えない人なんですね。考えないで体で舞っている人。考えなくて出来る人、ということね。だから観る方が勝手に解釈して可愛いとか、面白いとか思うんだ。あの人はそれを意図してはやっていないと思う。それでも観る方は何となく暖かいものを感じたりする。名人芸の域にいかないと、こういう風にはなかなかできないですよ。

写真
第一回能楽渡欧団、ローマ駅にて 喜多実先生と粟谷菊生(左)
実さんはそれに対してとても理知的、だからとてもわかりやすくて学生に人気があった。ふわっとした芸なんていうのは、僕らみたいに長く観ていればそういうものか、と思うけれど、若い学生が初めて観たら何のことかわからない、仕方ないでしょう。
そこへいくと実さんが、例えば『海人』で「さすが恩愛の故郷の方ぞ恋しき、あの波のあなたにぞ我が子やあるらん…」と、さっとサシの型をして右手で遠くを指す型をすると、そこに人がいるように見える、そうと分かる、そういう納得させるような型をするんですよ。それが当時の若者に非常に受けたのね。だから、実さんには学生のファンがとても多かった。他の能は何やっているか分からないけれど、実さんのはよく分かるってことでね。
観て分からないものにはファンはついて来ないからね。キリッとしまる古武士的なところも学生や若い人には非常に魅力的でね。実さんにはそういう意味で、若い愛好家を増やしたという功績があったのね。『羽衣』だとあの問答のところ、偽りは人間社会にあるというところね。
明生 まず先に天人(シテ)の舞楽を見せてもらわないと羽衣は返せない、という白龍(ワキ)に対して、天女が「いや疑いは人間にあり、天に偽りなきものを」というところですね。
山崎 ああいう理屈っぽいところになってくると、実さんの芸はキーッと光ってくるんだよ。六平太先生はここをほわほわとやってしまうけれど、実さんはどうしても羽衣を返さなければならないようなものをちゃんと作ってくるからね。こういうところがとても分かりやすくて、理屈っぽい学生には受けたの。実先生の芸というのは合理的だったと思う。そういうと実先生は嫌かもしれないけれど、結果的にそうなっていたと思う。
それで一つ話があるんですがね。実先生に学生がいっぱいついてくるのを見て、実先生より少し若かった先代梅若六郎氏が、どうして実さんは受けるのだろうか、自分もああいう風にしたいと、僕に話をしたことがあるんだよ。でも梅若六郎という人は、そのような資質の持ち主ではないからね…、実さんのようにはなれないんだよ。

写真 喜多実先生と粟谷菊生(左)残雪の東京にて
?六平太先生の『羽衣』はかわいいと言われますが、実先生のはどうでしたか?
また菊生先生のはどうでしょうか?
山崎 かわいいというのは六平太先生だよね。先生は身体がとても小さいから水衣や長絹を引きずってしまうんだ。それが何ともかわいらしいんだね。普通ならみっともないということなんだろうけれどね。もっと上にあげてやればいいのに、と当時は思ったもんですよ。

写真 『羽衣』シテ 十四世喜多六平太 大鼓 川崎九淵
明生 どうしてご自身や周りの方が装束に直しを入れなかったのでしょうかね?
父の話や、当時の写真からでも判りますが、長絹も長いままで、調整も敢えてしなかったようで、またそれでいい、という気風だったのかもしれませんね。父たちは、長絹とは引きずるものだ、それが素晴らしいと思っていた、と語っていましたからね。
山崎 僕も最初は、水衣や長絹は引きずるものだと思っていたね。だから、僕は何かに書いたことがあるのだけれど、短く着ている人のことを、あの人はつんつるてんだ、なんてね。
そうしたら、それは逆だったんだね。でも六平太先生の装束を引きずった姿をおかしいと思ったことは一ぺんもないものね。それが、何となくかわいいいんだよ。
実先生のはね、かわいいというところはあまりないよ。全部が理に走っているから、きっちりしていて、納得はするけれど、かわいいという感じはしない。美しいというのはあるけれどね。
菊生さんの『羽衣』はかわいいところがあるんだな。六平太風なんだよ。体は大きい割にとにかくかわいいんだ、菊生さんという人は。彼は六平太に心酔していたからね。
?具体的にどんなところが六平太風とか言えますか。
山崎 それはちょっと難しいけれどね。例えば、さっきの場面、ワキから衣を返してもらうところなんかね、六平太先生はかなり無造作でしたよ。菊生さんは割に慎重に受け取るね。そこはちょっと違うけれど、全体の雰囲気だね。
菊生さんだって、演じるうえでは実さんに聞いた話や稽古を受けたことが、ずいぶん参考になっていると思うけれど、芯に何があるかというと、やっぱり六平太風だったと思うね。
明生 父は自分で言っていますけれど、小学校から大学までの勉強を実先生から教わって、大学院の内容を六平太先生から教えてもらった、と。だから、そういう芸風になるのでしょうね。
山崎 彼はね、とにかく六平太に心酔していたことは事実だよ。僕らがよく聞いたのは、昔、菊生さんが六平太先生のお共で釣りに行った話ね。六平太先生は菊坊、菊坊とかわいがって、よく釣りのお共に連れて行ったのね。葉巻をくわえ釣りをしながら、いろいろな話をしたんだね。それが六平太さんの芸談なんだよ。菊生さんはあんなこと聞いた、こんなこと聞いたと、僕らが学生の頃いろいろ教えてくれましたよ。その話が菊生さんの血となり肉となったと思うね。
写真 左 粟谷菊生と十四世喜多六平太
?それで言うと先ほどの、「疑いは人間にあり」の場面のところなどは・・・。
明生 「疑いは人間あり、天に偽り無きものを」の場面で、「天に偽り無きものを」と言うとき、相手(ワキ・白龍)の方をゆっくり向きながらやさしく諭すように謡うと「偽りはないわよ」という風に見えるけれども、正面向いて謡うと「天に偽りはないのよ、そんなことも知らないの!」と、少し冷たい感じになります。二通りどちらでもいいのですが、僕はやさしく見るほうが好き、と父はいつも言っていました。型付にはどっちを向かなければいけない、というようなことは書かれていない訳でして…。どちらをやっても、先生にそれはいかんと怒られることはありません。そこは自由ですね。
山崎 その辺の話は放送にいいんじゃない? とてもいいと思うよ。
○菊生さんはサービス精神が旺盛だった
山崎 菊生さんは、能をかなり演劇的に解釈する人なんだよ。感情を入れようとするんだね。だけどやたらに感情を入れても能にならないから、ちょっと型を作るんだよ。おそらく型付にはないものだと思うよ。自分で感情を入れるから型ができちゃうんだ。だから、他の人よりあの人、型が多いと思うよ。自分でいろいろなことを考えて、ちょっと向いてみようとか、手を出してみようとか、そんな型付にはないことをやっている人なんだよ。明生さん、そんなことを本人言っていない?
明生 そういうところはあるかもしれませんね(笑)。
山崎 あるよね。確かにあるんだよ。そこらが面白い。あの人の魅力なんだよ。
明生 父に「『卒都婆小町』の橋掛りの柱に手を添える型、あれはどうして?」と聞くと、「駅の階段を上がったお婆さんがそうしていたからね。参考にしていただいちゃったよ」なんて言っていました。
山崎 へえ、そう。それで、ちょっとやり過ぎるときもあるんだよね。菊生さんの舞台がすんで、僕が菊ちゃんに近づいていくと、何か言おうとしているな?とすぐにわかるんだろうね。こちらが言う前に、「ちょっとやり過ぎまして…」なんて言うもんだから、僕らはもう何も言えなくなる。
そういう意味では菊生さんという人は本当に舞台を楽しんでいる人。舞台そのものが楽しい。自分が楽しむことによって、観るお客さんも楽しんでくれる、そういう考え方の旺盛な人だったよね。能楽師みんながそうだったら、能というものを本当に楽しくやっていたら、もっとお客さんも増えると思うんだよ…。その点でも、菊生さんというのは典型的な能役者だと思うよ。もったいないね、ああいう人がいないというのは・・・。
舞台に立つ人はみんなそうでなくてはいけないと思うよ。ところが能役者は見せてやるみたいな偉そうなところがあるんだよ。そうじゃなくて、何もかも迎合的になることはないけれど、お金を出して観に来てくれるお客さんに、少なくともその時を楽しませる、サービス精神がないといけないと思うんだよ。何も媚びることはないけれど、みんなが楽しく面白い舞台にしなければ…。型通りにやって、はいそれでお終いだったら面白くないよね。型付はあるけれど、ちょっとした工夫で大変面白く映ることがあるわけですからね。そのことに努力しているか、していないか、というのでは違いがある。僕は、そういう意味では菊生さんというのは最大のサービス家だったと思うよ。自分のためじゃないよ。お客さんのために本当にサービスしていたと思うね。
その点、お兄さんの新太郎さんという人は型通りきちんとやる人だったよ。それは粟谷家の長男だからね。粟谷家に伝わっていること、喜多流に伝わっていることを、ちゃんとやるということを非常に頑ななまでにやった人だと思う。粟谷の跡取りだからね。
菊生さんは、俺は次男だから少々はずれていたっていい、面白く見えたほうがいいんだからという考え方、お客のためにやるんだという考え方があったと思うね。
○『羽衣』をちゃんとやれるか
?番組では2000年の『羽衣』の映像を観ていただきます。
明生 天女の頭の上に載せる冠を天冠(てんがん)といいますが、そこに瓔珞という垂れ下がった飾りがあります。「天女役を勤める能役者はこの瓔珞が出来るだけブラブラと揺れないように! それには腰を安定させ、運びをスムーズにすれば瓔珞は振れないんだよ」と、父はいつも言っていました。しかし残念ながら、晩年の映像では微妙に動いていますので、きっと父としては不満だろうと思います…。どうしても高齢になると、体力が衰えてきて揺れてしまうのは仕方がないことですが…、私もその内にそうなるのでしょうね…。
『羽衣』は能楽師だったらいつでも舞える身近なポピュラーな能ですが、父は「『羽衣』をちゃんと舞える能楽師がいま何人いるだろうか?」と言っていました。

写真 十四世喜多六平太先生と釣棹を見る粟谷菊生
『羽衣』の舞台ははじめは三保の松原ですが、最後は天女がだんだん天、月の世界に舞い上がって帰っていきます。長絹は天女の翼だ、翼で浮遊して舞い上がっていくんだ…と。小書の「舞込」はその部分がより強調される演出です。長い橋掛りをうまく遣い、くるくると回転しながら上がっていく様子を見せます。
最後、「愛鷹山(あしたかやま)や富士の高嶺・・・」と地謡が謡うときには、かなり天高くなっているわけです。六平太先生はそこで、「つま先立ちして伸び上がれ、天上から下界を見下ろす気持ちで…」と仰っていたといいます。
私が「愛鷹山や富士を見るんだね」と父に言いましたら「バカ、富士山を見るんじゃないよ。どんどん小さくなっていく白龍を見るんだよ」と言われたことがあります。羽衣伝説の天女と白龍、神と人間のつながりを描いているんですね。単に愛鷹山や富士山を見て、とやっているようじゃ?だめ、つまらないだろ、こういう教えなんですね。
ですから、この二の松での型、父も私はもうこれ以上前にかかったら倒れてしまう、というほど限界ぎりぎりまで前のめりになって下界を見下ろす気持ちで演っています。この辺が見る人の想像をかき立てるところではないでしょうか。ワキの宝生閑先生も月世界、天界を見上げる風情で最後のワキ留めをなさっていますし…。
○謡における色気
?謡10年、舞3年と言われるようですが。
明生 これは特に菊生の言葉というのではなく、よく言われることなんですよ。
山崎 謡は能の第一条件ですからね。
明生 謡の方が難しくてということです。
?菊生先生は謡でどのあたりにこだわられておられたのでしょうか? 色気ということについてお聞かせ願いたいのですが…。
明生 色気と一言で言われても難しいのですが・・・。確かに、父はよく「色気のある謡を謡え、色気のある型を…」と言っていましたね。お酒が進むと、色気がエロケに変わっていきまして…(笑)。いまの謡にはエロケがない!と始終こぼしていましたよ。
先ほどの、謡10年、舞3年ということを補足すると、舞の方は3年もやれば形にはなるけれど、謡は3年では声は出るようになっても、相手役や周りを納得させる作品としての謡はできない、舞台の総てのお相手を納得させ、お客さまにもアピールできる本物の謡、それを習得するには最低10年はかかるということです。大きな声を出して、書かれた文字を読むだけではなく、詞章の表現を伝えるという、能役者の気持ちを込めていかに伝わる謡が謡えるかが大事でして…。
父は、「女をくどけるような謡、やさしくも説得力ある謡を謡え」と、しきりに言っていました。「ぶっきらぼうにくどいても女は落ちない…」、と。
ですから「菊生の謡は色気があるね?」とか、「かわいい女に化けちゃいますね」などと言われると、「そうだろう」とすごく喜んでいましたよ。

写真 鏡の間にて「羽衣」シテ粟谷菊生
鎮魂と祈りの芸能投稿日:2018-06-07
鎮魂と祈りの芸能
粟谷能夫
平成二十三年三月に起こった東日本大震災では多くの方が被災され、自然現象のとてつもない大きさを思い知らされました。東京に住む私にとりましても、余震の恐怖や、現場の凄さまじさを見るにつけて心身の強い緊張が中々取れず、心に余裕を取り戻すのに時間を要しました。
しかしながら、避難所で人々が協力し助け合い、手を取り合っている姿には励まされました。これは皆が同じ価値観の上に立っているもので、仏教や儒教の教えが心を一つにしているのだと思います。大昔から自然に畏敬の念を払い、共生してきた人々の無常観なのかもしれません。やはり、このような非常時に支えとなるのが心のありようで、日ごろからの文化教育の大切さを痛感いたしました。
能には天下泰平、五穀豊穣、子孫繁栄から始まり、人間の普遍的な情感を主題とし、仏教や儒教などの教えを取り入れた人間の心のドラマが多数有ります。鎮魂、祈り、復活の思いを込めた芸能であり、だからこそ、今、能の出番だと思います。
そして能は時代を取り入れ時代に対応しながら今日を迎えています。能の庇護者の好みの変化や戦乱など、困難を背景にして、むしろレパートリーを増やしてきました。困難な時代こそ文化や芸能は人々を救い、鼓舞してきたといえます。
戦後でいうならば、西洋化の著しい中、人々に日本文化の素晴らしさを示し、世界に誇れるものである事を知らしめるため、三島由紀夫は「近代能楽集」を発表しました。敗戦で打ちひしがれた日本人の魂を取り戻すかのように発表したものでしょう。
編集者の言葉によれば、「若い時より能に親しんでいた著者は、能楽の自由な空間と時間の処理方法に着目、・・・・・・古典文学の持つ永遠のテーマを近代能という形で作品化した大胆な試みは、ギリシャ古典劇にも通じるその普遍性を世界に発信した」のです。
日本には日本人の心情に根ざした芸能が数多く有り、人々の心を慰め、励ましてきました。困難な時代であればあるほど、鎮魂と祈りの芸能が必要です。私たちも芸能の持っている力を信じ、日々活動して参りたいと思います。
そして、舞台芸術は基本的には人と人との繋がりによって成り立っています。それは演者と観客ということでもあり、演者対演者ということでもあります。また、自然と人、神と人間との繋がりの中にも存在意義があります。避難所での人の繋がりや絆を見るにつけ、この基本に立ち返らなければと再確認したのです。

『鸚鵡小町』 シテ 粟谷能夫(平成23 年3月6日 粟谷能の会) 撮影:吉越 研
松風を終えて投稿日:2018-06-07
松風を終えて
粟谷明生
松風 この曲は道成寺より難曲であることを強く感じました。
道成寺の場合、静の乱拍子、動の急ノ舞、それからクライマックスの鐘入りと続き、中入りはシテ一人で鐘の中で装束を着替え、蛇体となり現れ、祈り祈られ最後は幕の中に走り飛び込む。まことに技の極みの連続でありますが、この鐘入りの作り物の中というのはある短い時間ではありますが、それまでの緊張が解け自分に帰り、しばしの休息がとれる逃げ場があるのです。
それに引き替え松風は、真の一声の二人の海人乙女の侘びしさを嘆く謡から始まり、月光の中での塩汲みの段、ワキとの問答からクドキ、舞台上での物着、そして恋慕の狂乱の舞、キリの仕舞どころ、と劇として一曲全体の心憎い程の巧みな構成の中で、演者の精神と体力の持続がいかに辛く、困難で、大事な事かを演じ終えてはじめてわかりました。
先達の、その辛く、難しい、苦労を少しも感じさせない舞台の凄さに改めて低頭するばかりです。
私は今まで数回、シテ連(村雨)をやらせて頂きましたが、その都度、シテ連としての重要性を痛感いたしました。
父菊生のシテ連は三回いたしました。私は父の松風はいつも小面の中から見える一センチ四方の世界で感じてきました。謡い方、歩む速度、間のとりかた等、ただシテの力に乗せられて動かされていたように思います。
演じている時は、ここはシテ連としても自己主張しよう、もっとはって謡おう、位をもった歩みをしよう等と、思って演じてはいるのですが、今考えてみると悟空がお釈迦様の手のひらで好き勝手に飛び回っていたようにしか思われてなりません。父をはじめ先輩の方々は、私の思いの外で大きな力を持って演じられていた事がシテを勤めてはじめてわかりました。
松風という曲に憧れを持ちはじめてから、印象に残る一つは、伯父新太郎の松風でした。松模様の古い紫長絹で舞っている姿に、いつか自分も──私のは寸法が小さいのではと思っていた松模様の長絹がどうにか着れて、鏡に映った自分の姿を見たとき「これで装束は良し」と思わず笑みを浮かべてしまいました。装束は決まり、いざ面となると、なかなか決まりませんでした。粟谷家には松風に使える小面は数面ありますが、その中の一面、井関の小面─これは父以外、誰も使用しないという暗黙の了解の小面なので、気に入っているのですが父の元気なうちは使わないと思っています。
実は昔一度この井関でもめた事があるのです。十五年前父の承諾なしに船弁慶に使用した時でした。私には何も文句を言わず伯父新太郎に「あれはおれの面だ、どうしてだした」と噛み着いたようです。私はその話は後日、伯父より聞かされましたが、父のこの小面に対する愛着心、執着心はわが子でも、触らせたくない、貸したくないという程の気持ちであることをその時はじめて知りました。
今回は、伯父所有の、媚と銘のある小面を使う事といたしました。この面は艶のあるお顔で、目がものをいうようなすばらしい面です。今、大変気に入っている面です。
そのうち、これは明生しか使わない、という演者に自分もなりたいと思ってますが、私の心の片隅にいる浮気虫が「井関の面をかけてやってみろ」といわれるのを待っているようでもあります。
これからも自分を鍛え、力のある、大きな存在感のある能役者になりたいと思っています。
『野宮』での心の作業投稿日:2018-06-07
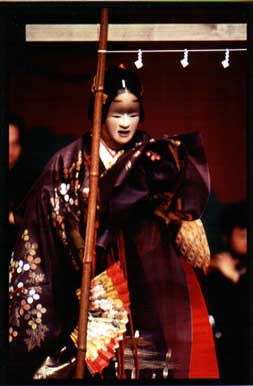
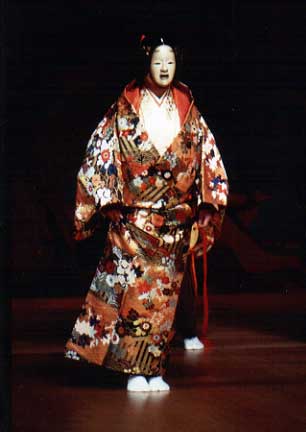
能楽師を志し、それを生業とするならば、一年に一番は心体ともに駆使するような大曲に挑み、つい緩む己自身にねじを巻くように鍛え上げる機会を自ら求めなければと思うようになりました。秋の粟谷能の会(平成十四年十月十三日)の『野宮』はまさにそういう試練の曲で、私にとっては大きな一番となったのです。 『野宮』は源氏物語を題材にし、もの寂しい晩秋の嵯峨野を舞台に、光源氏を愛した六条御息所の狂おしいまでの恋心と諦念を描いています。源氏物語「賢木の巻」や「葵の巻」を中心に、源氏と御息所の関係や背景をある程度理解したうえでないと、能『野宮』を観るのは苦しいはずです。これは観る方だけでなく、我々演ずる方にも言えることで『野宮』という曲の位の高さであるとも思われます。
そこで、『野宮』という曲に触れる前に源氏物語に目を通し、源氏と御息所の関係や人間像、二人の間で起こったできごとなどを自分なりに整理し稽古にかかりたいと思いました。この作業が、能『野宮』を演じるのに必要か不要か、演者はあまり考えすぎるとろくなものにはならないという声も聞きますが、自分自身舞台上での何かの助けになるのではと試みてみました。

御息所は十六歳で東宮妃(皇太子妃)になられますが、二十歳で東宮が突然亡くなられ未亡人となってしまいます。東宮妃としてのプライドが高く、一途な性格の持ち主だったようです。東宮妃として将来を約束されていた方が、いきなり東宮の死にみまわれ、いくら高貴の出とはいえ、経済的、社会的地位を失い没落していく寂しさを感じていたことは間違いありません。そこへ現れたのが光源氏です。七歳年下のプレイボーイ。年下とはいえ、経済力があり、恋の遊びにはたけています。年上の女性、藤壺との禁断の恋も経験ずみ、高貴で教養があり美貌の夫人に興味を持ったのも自然の成り行き。御息所の寂しい心にすっと入って虜にするのはそう難しいことではなかったのでしょう。御息所は簡単に源氏の誘惑に負け、恋に落ちていきます。源氏十七歳、御息所二十四歳のことでした。
これが御息所の間違いの始まり、不幸の始まりだったのです。手に入れた女性には興味がなくなるのがプレイボーイの常、次第に源氏の訪れは間遠になっていきます。御息所の幸せな期間は短く、悲しみの時間が長い、薄幸不運な生涯を生きた人というのが、御息所の大前提になっています。
御息所はプライド高く、教養があって美貌の持ち主、申し分ない女性ではありますが、このプライドの高さが一つの落とし穴になって、車争いをめぐる正妻への激しい嫉妬に結びついていきます。
夕顔や葵上に嫉妬を感じ始めたとき、御息所はこんな恋をしてはいけない、この恋は成就するものではないと察し、御代替わりで、娘が伊勢斎宮として選ばれた段階で自分も伊勢に行ってしまおうと、一度は決意しています。
そんな折、葵上との車争い事件が勃発します。ある日賀茂の斎院の御禊があり、その行列に源氏が出ると聞き、御息所も見物に出かけます。そこで後からきた葵上の車と出くわし、車置きの場所で争いになり、権力の衰えつつある御息所は無惨にも車を押しのけられてしまいます。御息所の車と承知の上での雑仕等の乱暴、この屈辱を受けたことが、御息所の敗北感と葵上に対する恨みへ増幅していきます。そして、葵上が妊娠していると知ると、生き霊となって葵上に取り憑きます。自分の意識ではもうどうにも制御できない、恐ろしいまでの恨みであり嫉妬です。そしてついに葵上を呪い殺してしまうのですが、そのとき源氏に自分の生き霊の姿を見られてしまい、これで源氏に自分の本性を知られてしまった、本当に嫌われてしまったと絶望します。手を洗っても髪を洗っても、葵上の物の怪を払う祈祷時に使われていた芥子の実の匂いがとれず、その絶望感は一層深いものとなっていきます。

ここで御息所は完全に伊勢に行くことを決心します。葵上亡き後、次の源氏の再婚相手は御息所ではないかと世間では噂されますが、そんなことはない、源氏の心が冷えきっていることを知っているのは御息所自身です。伊勢に行くことをもっと早く決断していればこんなに嫌な思いをしないですんだかもしれないと思いつつ、源氏を思う気持ちを断ち切れず、最後に大きな傷を負ってしまう御息所。『野宮』の謡「物見車の力もなき、身の程ぞ思ひ知られたる。よしや思えば・・・」に、その万感の思いが込められている気がします。
伊勢に行く前に皇女は精進潔斎のために、一時宮にこもります。その宮が嵯峨野にある野宮。御息所も娘につき添い、野宮に引きこもっています。そこに源氏の訪れです。源氏物語では、源氏は伊勢に行く御息所にご挨拶もしないのは礼儀知らずで無粋な男だと思われてはまずい、世間体を気にして出かけたように書かれています。愛情というよりは世間体。もう二度と逢うことはないだろうから、御息所の鎮魂のためにも一度は行かねばという気持ちだったのでしょう。それでも嵯峨野に入ってみると寂しい秋の風情です。もののあわれが加わると、一度心を動かした女性への愛しさが蘇ってきます。源氏は榊を神垣にはさんで御息所に歌を送ります。歌のやりとりの後、禁忌の野宮にずうずうしくも入っていく源氏、それを拒むことができない御息所。そして一夜の契りを結ぶことに。それが謡の詞章に繰り返し出てくる長月七日、あの日なのです。
御息所にとって、長月七日はどういう日だったのでしょうか。源氏との恋は終しまいにする、あれほど心に固く決めていたのに、なぜ受け入れてしまったのかという後悔の念であったか、それともあの日を自分にとって永遠の日にして大切にしまっておこうとしたのか。ここをどう解釈するかによって、前シテのイメージのふくらませ方が違ってきます。私は、長月七日を永遠のものにし、これにより救われないことになってもいいという強い情念ではなかったかという気がします。仏の世界から見て身の程知らない、これでは成仏できないと言われても仕方ない程の愛執、これが最後の「火宅留め」にもつながっていくと思うのです。
御息所はその後、娘が斎宮としての伊勢神宮奉仕が終わると、ともに都に戻りますが、間もなく重い病の身となってしまいます。源氏は今をときめく内大臣。死を悟って尼になった御息所を見舞うと、御息所は娘の将来を源氏に託します。幸薄い、短い生涯であったと思われます。
ざっと源氏物語を整理してみました。これが私が『野宮』を演じるために、原文や解説を読み込んでベースにしたものです。そして次は、演者が謡本という台本を通して何を読み込むか、能作者はこの能に何を言わせたいのか、能『野宮』をどのように表現し世界を創り上げるか。源氏物語原文の読み込みは、台本を読み解くための一つの手段と言えるでしょう。ちなみに『野宮』の作者は世阿弥と昔の喜多流の謡本に書かれていましたが、今は金春禅竹作が定説になっています。
『野宮』の構成は、前場で賢木の巻を基に晩秋の野宮に源氏への想いを語る御息所、後場は車争いの場面を再現して舞台には登場しない対葵上との世界を創り出し、源氏の来訪を回想しての序之舞、破之舞を舞い、再び車に乗って火宅を出たであろうかと終わります。
ここからは、私自身の能『野宮』を通して順を追って振り返っていきたいと思います。

まず、後見が小柴垣のついた鳥居の作り物を舞台正面の先の方に持って出ます。喜多流の作り物は正方形の台輪に鳥居を立て、台輪の左右の辺上に小柴垣を取りつけて、台輪の内を神域とし、外と区別していますが、観世流では台輪を使用しませんので小柴垣はその左右に張り出す形となります。喜多流の小柴垣のつけ方ですと、作り物に榊を置く型や足を踏み入れる型が、正面の限られた人にしか見えないので支障があることは承知しているのですが、今回は披きであるため、敢えてそれには触れず、従来の手法に従い勤めました。
面は本来「小面」となっていますが、これまで説明してきたような御息所像を思うと、小面では少々難があり、多少大人っぽい小面を選ぶとしても、やはりそこには限界があります。理知的で少しヒステリックなものが良いのではと、今回はお許しを得てやや柔らかい表情の「増」を使用いたしました。
前シテは次第の囃子で登場します。里女と謡本に書かれていますが、ここは確実に御息所の霊の意識です。ゆったりと囃す次第にゆっくりゆっくり執心を引きずりながらの登場ですが、ワキの「女性一人忽然と来り給ふ」の言葉通り、この女性は霊界から一瞬のうちに嵯峨野に舞い降りてくるという、この世のものでない不思議さと存在感を漂わせ、運びにもゆっくりとした想いと、忽然として現れるスピード感が同居しています。単に鈍重な物理的歩行にとどまらないが心得で、この次第のノリと運びの難しさではないでしょうか。
そして作品の主題となる次第の謡、ここの謡に緊張と不安がふくらみます。何度と稽古を重ねても、本番当日での状態でどのように声が出るかは本人も判らない未知なもの、曲の主題を謡う大事な瞬間であるから尚更そうなるのです。「花に慣れ来し野宮の・・・秋より後はいかならん」は、この野宮のあたりで、咲き乱れた花を眺めて楽しく過ごして来たが、秋が過ぎ花の散ってしまった後はどんなに淋しいことだろうというほどの意味で、秋を飽きに掛けて源氏に飽きられ捨てられたれ淋しい御息所の心情を謡います。ここをどのように表現出来るか。次第はシテが作品をいかに把握出来ているかを試されるところで、集中度の高さが要求され、演者には一番怖いところです。
忽然と現れた御息所の気位の高さはワキとの問答の中に隠されています。能の多くの場合、執心に悩む霊は、僧に成仏を願うため現れますが、御息所の場合は、長月七日は源氏との最後の契りを結んだ大切な日、宮を清め御神事をするのだから関係のない人は僧でもさしさわりがある、「とくとく帰り給へとよ」と強く訴えます。他にはみられない手法で御息所のプライドの高さが表されます。
私は前場で次の三ヶ所が好きで、いつも謡ながら興奮してしまうところがあります。それらは謡と型の融合するすばらしい見せ場と思っています。一つは初同の「うら枯れの、草葉に荒るる野の宮の・・・」と入り、「今も火焼屋のかすかなる、光はわが思い内にある、色や外に見えつらん、あらさびし宮所、あらさびしこの宮所」です。火焼屋から漏れる光が源氏にも見え、また自分の魂にも見えるのでしょうか。その光は遠くに消えていくかと思うと、不意に自らの胸にすーっと入りこみ、体をめぐり、女性そのものをほてらせます。目付柱先をじっくりと見、次第に正面に直し、とくと一足引いて左に廻るという簡素な型付けのなかにも、謡い込まれるものはエロチシズムにあふれています。「あらさびしこの宮所」とは、ほてる肉体を持つ己の悲しさ。寂しいのは嵯峨野のうら悲しい景色だけではない、己の心が、肉体が寂しいのだという心の叫びが非常に美しい詞章に織り込まれているとは父からの教えです。
二つ目は、クセの上羽後です。『野宮』のクセは観世流では下居(したにいる)ですが、喜多流では床几にかけます。クセで「つらきものには・・・」と秋の景色を謡い始め、源氏との禁断の逢瀬があり、そして御息所と娘は桂川でのお祓いを受け伊勢へと旅立って行くことになったと語ります。作り物の鳥居は伊勢の鳥居にも、また鈴鹿川にも見え、「身は浮き草の寄る辺なき心の水に誘われて・・・」と、シテはおもむろに床几から立ち、自然に動き始める心持ちの型どころとなります。床几にかける意は、御息所の位の高さを表しているとも言われますが、私はこのふと立ち上がる風情が、なにかに取り憑かれたようにも、またどこかへ引き込まれてくようにもみえ、また見せるためではと思え、たまらなく好きなのです。「伊勢まで誰か思わんの・・・」とじっと遠くを見、距離感を出しながら歩みだす姿、両手を広げ娘の手を引こうとする御息所とも、また手を引かれる娘のようでもあるといわれ、「ためし無きものを親と子の、多気の都路に赴きし心こそ恨みなりけれ」とシオリ下居る型どころは、伊勢に下る御息所を描く絶頂だと感じています。
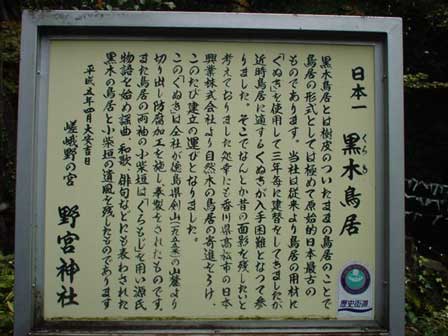
最後は中入り前の地謡の「黒木の鳥居の二柱に・・・」の謡です。シテは鳥居を見込み佇んでいるかと思うや、その姿は光のように消え魂だけが残る風情。この最後のところで、囃子方も地謡も気をかけ少しかかり気味に囃し謡う心得で良いところですが、また、もっとも難しいところだと思います。三番目物で中入り前がこのように強くかかるのも御息所の性格がなせる珍しい手法ではないでしょうか。
中入後のアイ語りは和泉流の野村与十郎さんが勤めてくださいました。本来の語りは車争いのことにはふれないのですが、近年野村家では、前場でふれない賀茂の車争いの話と、御息所が生き霊になった話を入れ、野宮に源氏が訪れた後、鈴鹿川の歌を詠み交わしたという話に続けています。車争いの段が入った事が、後の場面に続く橋渡しになり、わかりやすく良い語りであると思います。
後シテは車に乗った様子で登場し一声を静かに謡います。車争いの場面を語り、序之舞、破之舞と続きます。ここは情景描写であり、舞でありと、動いて表現できるので、前シテのように動きの少ない中に感情表現をしなければならない難しさと違って、取り組みやすさは感じます。
車争いの後、「身の程ぞ思い知られたる・・・」と舞台を二まわりしますが、これは妄執の闇から逃れられない輪廻の世界を表しているのでしょうか。「身はなお牛の小車の」で左手を高くつき上げ肩に乗せる場面は、牛の角がせり上がる真似であり、牛車を引く型と言われていますが、昔、後藤得三先生が「あの左手は光源氏、男性そのもので、あれが御息所の肩に重くのし掛かる。そこがわからなければ・・・」とおっしゃったことが甦ります。
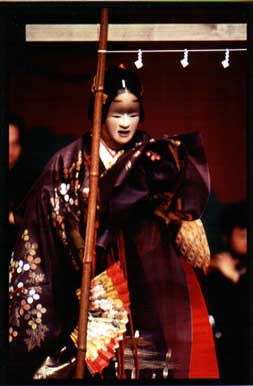
野宮後シテ序之舞は「昔に帰る花の袖」「月にと返す気色かな」と謡い始まります。美貌も地位もあった東宮妃のころ、あるいは初めて源氏との逢瀬があったころ、そして野宮での最後のあの時を回想し、月夜に舞を舞おうという情趣でしょう。森田流の伝書には「序之舞とは謡では表現出来ない所作を舞に感情移入して一曲を盛り上げる」と、舞が楽劇の原点であると書かれています。このことは『野宮』など三番目物の序之舞のほとんどに通じ、役者がその役になるのではなく、つまり六条御息所としてではない別な世界、演者自身の思いを持ち舞うということなのです。あのゆったりとした時の流れと四つに組み、速く動きたくてたまらない自分を、じっと我慢させ苛める苦痛そのものが舞としての表現の真髄だということが、今回少しわかったような気がしました。
では破之舞とはどのようなものか。流儀には、太鼓ものでは『羽衣』、大小物ではこの『野宮』『松風』『二人祇王』の三曲しかありません。破之舞とは「本音の舞、二の舞ともいって、主人公の具象的な表現の本音である」と伝書にあります。「野の宮の夜すがら、なつかしや」という御息所の本音の心、その最後の夜がなつかしいという心の興奮や高ぶりを舞います。通常の舞は、歌舞音曲の形式にのっとって、ひたすら舞う抽象的な動きや型ですが、破之舞には心がある、本音の舞であるということです。この二つの舞の表現法を区別し意識することが大事な心得です。
喜多の九代古能(健忘斎)は「舞の後の破之舞は難しい。が、もっと難しいのがある。それは舞後のイロエや働き、余韻をあらわす、これが一番難しい」と。イロエや働きは、囃子方があまりにすばらしく囃したご褒美に、シテがもう少し舞い続けたいという気持ちから拍子を踏みだすと、自然とイロエや働き入りになるという約束事ですが、一つの舞を舞った後に本音の心を表す所作だといえます。いずれにせよ、舞後の舞が重要で、本音でここを掌握出来なくては駄目だということは確かなようです。
最後はこの曲に限っての火宅留めです。「火宅の門をや、出でぬらん、火宅の門」と謡う観世流、「火宅」で留める喜多流。御息所は火宅というこの世の苦しみの世界を出られるでしょうか、いやいやとてもでられない……。成仏できなくともよい、源氏とのあの日の思い出を大事に抱いていたいという強い意志があるように私には思えるのです。「火宅……」と留めた後の静まり返った舞台の緊張感の持続、これがこの曲の終演です。
今回の演能にあたり雑誌観世での野村四郎氏の対談『野宮』が私の演能に大きな力を与えて下さいました。「『野宮』は作品が役者を選んでくるように思います。下手すると作品の方が拒否反応を起こす。貴方にはまだ無理だよというような。」「人物像だけをぎゅっと絞り込んでいったからといって『野宮』にはならない、御息所になるわけではない」と語っておられます。これは心に残るメッセージで、私の心に衝撃が走り心引き締まる思いとなりました。たとえば『羽衣』なら天女になって舞おうという作業がある程度できるのですが、『野宮』ではそれができないと思い知らされるのです。また「ベースに季節感、秋深く木枯らしが吹きすさぶような世界、そして深い森をイメージし、御息所という高貴で複雑な女性の情念の世界や諸々の性格を、演者が身体の中に思い宿らせて演技という形にしていく」と、つまり心の中での作業が行われないと全く歯が立たない作品だとおっしゃっています。外面上の御息所を真似ても能『野宮』には成りえない、また最小限の動きで、最大限の描写をするところに能の最も大事な要素があり、『野宮』はまさにそうであるという野村四郎氏のお話は原文を読み込む作業など吹き飛ばすほどのものでした。
私にとって『野宮』という大曲は心と体を切り刻むような思い出の曲になりました。粟谷能の会の三番立ての真ん中を、父や能夫がゆずり押し出してくれる形で挑むことができた、そのうれしさと重圧をひしひしと感じています。 (平成十四年十月 記)
撮影、「野宮」東條氏
野宮神社
野宮神社鳥居
神社のまわりの小道
鳥居の説明
以上 撮影 粟谷明生
花あるいのちと散りぎわ投稿日:2018-06-07
花あるいのちと散りぎわ
粟谷菊生
 テレビを観ていたら超美味しそうなフランス料理が出てきた。銀座のLOSIERというフランス料理のレストランだ。二、三ヶ月前から予約でいっぱいだそうだが、そこのシェフが引退するという。満員御礼、味も最高の今引退することにしたのは何故?
テレビを観ていたら超美味しそうなフランス料理が出てきた。銀座のLOSIERというフランス料理のレストランだ。二、三ヶ月前から予約でいっぱいだそうだが、そこのシェフが引退するという。満員御礼、味も最高の今引退することにしたのは何故?
僕は“三百六十日鮨男”と言われているくらい、“お鮨大好き人間”だが、ホテルに泊まると年甲斐もなく無性にステーキが食べたくなって、ワインならぬ常の如く好きなビールで独りビフテキを食べることがある。が、結婚披露宴で頂くディナーとたまにご招待を受けて頂く時以外は自分から仏蘭西料理を食べにわざわざ出掛けて行くことはない。
その日のテレビでの画面に出てくる静かでエレガントな雰囲気、上品なたたずまいの中でのテーブルに置かれている食器の美しさと見事な料理はさすが! しかし対照的にその陰で活気ある調理場の奮闘と迫力あるシェフの総指揮ぶりがいい。そのシェフが大繁昌の頂点にあって、しかも最高の味を提供できる技の頂点にあって今、引退の決意をした心境とはーー。彼は「今だからこそ引退するのだ」という。総指揮をするということは、やはり大変なことで肉体の衰えに自分自身が僅かにでも気づいた事が、引退のきっかけとなったようである。「自分と同じだと言いたいのでしょう?」と一緒にテレビを見ていた妻に言われたが、常に私の心の内を見抜いてしまうのが女房だ。そのシェフは引退して自分の時間が持てるようになったら世界中を旅行して各地の味を追及したいと夢を語っていたがーー。
花あるうちに退く美学が僕は好きだ。まだまだと言われて最後に無残な姿をさらけ出してしまいたくない。
若いときに読んだ「シラノ・ド・ベルジュラック」の最後の方。シラノが迫りくる死期を感じながら訪ねたロクサーヌ姫から「読んで」と言われて、昔、美男子ながら文才の無い友のために代筆して送り続けた、実はシラノ自身の心の内を込めて書いた恋文の一篇を、文字も読みえぬ暗さとなった夕闇の中で諳んじている如く読み続けている。
それを見てはじめて彼の心を知って驚くロクサーヌに瀕死のシラノが言う科白が「これが私の心飾気」(訳者の坪内逍遥は心意気を心飾気と書いてココロイキと読ませた)。この心飾気と書く文字が僕は大好きだ。
僕は去年、潔く心飾気で演能は引退したものの、さて仕舞はいつまで舞えるかと、うそ寒い怖れにおののきつつ今、散りぎわに向かっている菊爺なのだ。
写真 「柏崎 道行」粟谷菊生 撮影 安彦喜久三
メイキングNHKテレビ 「芸能花舞台」 その2投稿日:2018-06-07
メイキングNHKテレビ 「芸能花舞台」 その2
?明生さんの出版された「粟谷菊生・能語り」の中で、そんな謡を謡っているようじゃ女を口説けないぞと、よく注意されたというお話が出ていますね、これがいい話だなと思いまして…。

写真 読売新聞に掲載された「粟谷菊生・能語り」著 粟谷明生
明生 え! 今のこと…放送で言うの?
?それぐらいだったら。お人柄も出ますし。よいと思いますが…
明生 いやだな?。
山崎 でも菊生さんという人はそういうことをよく言った人なんだよ。
明生 軽妙洒脱というか。
山崎 そういう話はたくさん聞いているねえ。
○浮きの謡い方
?謡い方でいえば、たとえば、『羽衣』の最後、「かすかになりて、天つ御空の・・・」の謡い方を実先生が変えられたとか。
明生 昔の喜多流は浮き(謡の途中で音を浮かし少し高くすること)が早かったんですよ。
例えば『羽衣』の最後の場面「かすかになりて」を今は「なりい?」と一回のウキ(浮く音)、昔は「な?あり?い?」と「なあ」と「りい」を浮かしています。上がるところをできるだけ少なくしようとなさったのが実先生のお考え。昔はウキが二字前とか三字前から上げるものですから、音が上がってつってしまう傾向になります。謡い手は高い音まで上げなければいけないから当然苦しいわけです。でもその苦しさが聞いている人にはいいんだよ、と父は言うんですね。祖父の益二郎とか十四世六平太先生の時代はみんなそういう風にウキを早くしてやっていたのです。

写真 粟谷菊生
山崎 それを実先生が謡いやすくしたということでしょうね。
明生 そうですね。謡いやすいですよ。
山崎 シンプルにしているんですよ。昔の謡い方のほうが言ってみれば芸術的なんだよ。だけど、そんな謡い方ばかりでは普及しないから、なるべく謡いやすい簡単に謡える謡にするというのが実さん。こういう考え方は実さんの偉いところだね。だから実さんの時代に喜多流の流儀の人がだいぶ増えたんですよ。これは大事なことだと思うよ。
明生 そうですね、芸術性から普及に、それが実先生のやり方なのですね。
?そうすると、謡いやすくはなったけれど、ちょっとシンプルになり過ぎたというのがあるのでしょうか。
山崎 菊生さんの言葉で言うと、花(華)がなくなったということね。
明生 そうなのでしょうね。山崎先生のおっしゃるように、シンプルにさせるのは普及させるためだったのかもしれませんね。
特に大ノリ(謡い方のひとつ)は実先生のやり方ならば、わりと簡単に謡えるんですよ。普及するためにはいい手法なのかもしれませんね。
山崎 実先生の時代に流儀の人が増えた、これは大きいことなんですよ。謡本も新しくしたしね。そういう意味では実先生は中興の祖ですよ。それは実先生の功績だと思いますね。

写真 右 粟谷益二郎と菊生
明生 謡本を読み易い字体に変えたのは十四世喜多六平太先生です。実先生は昭和の改訂版に更に手を入れられましたが…。実は菊生の意識の中には六平太先生や実先生だけではなく、父親の益二郎の影響が結構多いのです。「僕は、おやじの謡い方を継承している」と自慢していましたからね。祖父の謡いは、今の謡い方とはちょっと違います。今聞くとクラッシックな感じを受けます。
友枝昭世さん以降の能楽師は全員実先生に習っているので、当然実先生風に謡います。
しかしそうは言っても昔の方々と一緒に謡うことはある訳でして…。ですから父と一緒に謡う時は、当然早いウキで合わせて謡いますよ。
山崎 益二郎さんという人は本当に謡のうまい人だったからね。昔は謡がうまい人が一杯いたんだよ。福岡周斎とか伊藤千六とかね。昔は謡がうまいというのが第一条件だったからね。今は舞のほうがどうとか、見える姿をどうとか言うけれどね、昔は謡ができなければ能役者になれなかったわけですよ。

写真 福岡周斎
写真 伊藤千六(後に伊藤裕康に改名)
?菊生先生は益二郎さんと六平太先生のを聞いていたので、そちらがいいということに?
山崎 そこが難しいやねえ。菊生さんは実さんに教わって実演者としてやってきた人。それでも六平太先生に心酔していたからね。
?菊生先生は謡の人と言われたのですか。
明生 そうですね…。でもそれは還暦過ぎてからではないかと?、その頃からピークを迎えたのではないでしょうかね。
能夫は「菊生叔父ちゃんの謡、そういうスタイルを完成させたね」と言っていますし…。
山崎 喜多流の謡というと、粟谷菊生型とか友枝喜久夫型とか言われてね、そういう連中が謡っているのが喜多流の謡になっていくんだね。そういう意味では菊生さんというのは喜多流でも大事な存在だったと思うよ。今はほとんどみなさん菊生さんの謡を謡っているんじゃない? なにしろ粟谷一門の人数が大いんだから。一番多くいたときは現役の能楽師が九人いたことがあったでしょ。ある時期なんか野球のチームができるぐらいだもの。喜多流の中でも粟谷勢力は相当なものだったよね。

写真 粟谷菊生
明生 はい、そうなれば嬉しいのですが、でも正直申しますと残念ながら菊生の謡を謡っているのは、ほんの少数なんですよ。
つまりそれほど難しい、ということなんでしょうかね。私は私なりに精一杯真似ているつもりなんですが、でも向こうにいる父から、そんなんじゃないよ、と聞こえてきそうでして…。
○地頭として活躍
?菊生さんはシテが舞えなくなってからもずっと地頭としてご活躍されましたよね。
地頭というのはお能の中では大切なものなのですか。
明生 それは大切ですよ。
山崎 今回の放送でこのことを強調しないといけないと思うよ。能の中では、シテと地頭が野球でいうバッテリーのようなものなんですよ。シテがピッチャーで舞い手、地頭がキャッチャーなんです。極端な言い方をすると、地頭がシテを舞わしていると言ってもいいんだ。だから本当の名人はみんな自分の地頭をもっていたよね。いいコンビみたいな人がいましたよ。粟谷益二郎が六平太の地頭というようにね。
明生 父の場合も友枝昭世さんの専属の地頭であったように思えますね。
山崎 それはどこでもそうなんです。名人上手にはね。たとえば金春流の櫻間弓川には本田秀雄とか、観世流なら観世左近には藤波順三郎とかね。近いところで言えば近藤乾三には高橋進とか、全部名人上手には名地頭がいたんですよ。
明生 うちの父は、「俺が舞うときにはどうするんだよ?」と愚痴ってましたよ(笑)。
山崎 そうね、菊生さんをうまく舞わせてあげられる地頭は難しいね。あなたも舞うときには一番舞いやすい地頭というのがあるでしょ。自分が主催する会なんかでは、自分の思うような地頭を選ぶべきだよ。これはもう、地頭を選ぶことによって能が違ってくるもの。ある場合は自分より上位の人になるかもしれない。でもそれはお互い肝胆相照らして、何でも意見が言えるような人でないとダメだよね。
野球のバッテリーだから、たとえば、舞の緩急にしたって動きの緩急にしたって、全部地頭が握っているんだからね。どうにもならないよ、舞うほうは。
明生 父は友枝昭世さんの演能のほとんどに関わっていましたから、友枝さんも父には絶対の信頼を寄せていましたし。「もう菊生先生に丸投げしておけば、ちゃんと僕を舞わせてくれるから安心なんだ。囃子方も僕が細かく言わなくても、菊生先生について行ってくれるから、もうそれでいい」とも仰っていましたからね。
山崎 そういう意味では、菊生さんが亡くなって一番打撃を受けているのは友枝さんだよね。
?それで、今回は友枝さんがシテで、菊生さんが地頭の『井筒』を映像として見ていただこうと思っています。序之舞の後のところでいいでしょうか。
明生 よいと思いますよ。よく録画されていて、父の声が十分聞きとれれば、という条件でね。父の謡の特徴は、音の高さを上手に調整するので、続けて謡う役者や地謡もとっては音がとりやすいのです。こんなこと言っても判らないですかね?
シテからも、謡いやすい舞いやすいというお褒めの言葉はよく聞こえてきましたよ。
父の謡は声量があり音域が広いので、音をどんどん上げていっても平気なんですよ。
『井筒』の「寺井に住める…」の「寺井」の節扱いも、今は一度しか上げない謡い方ですが、父のは三回も上がってきます、これは父だけですが。
まあ、このように我々が習ったものと違う謡い方であっても、リーダーの地頭には全員揃えてついて行く、合わせる、それが地謡の鉄則ですから、みなさん合わせますよ(笑)。
父が父の謡いたいように引っ張って行く…。みんな必死に大きな声で高い音を出して、そこで生まれる、臨場感と興奮、そこをねらっているんですね。
これがまた不思議なんですけれど、上手な地頭だとまわりも上手になった気になる、そう聞えるようになる、錯覚かもしれないのですが(笑)。
ところで、これはいつの録画ですか。

写真 粟谷菊生
?1996年のものです。
明生 みんなで大きな声で謡っているのですが、マイクのポジションもよかったのでしょうね、父の声が私にはびんびん響いてきますよ。視聴者にお判りになるかな?
山崎 これは得がたいね。やっぱり僕は長年喜多流を聞いているけれど、菊ちゃんの謡いはいいよ。
明生 ありがたいお言葉です。
山崎 地頭がいいってことはね、菊生さんは自分で舞っているからいいんだね。自分が舞っていない人の地頭はよくないんだよ。菊生さんは地頭で謡いながら自分でも舞っているよね。だからシテは舞いやすいんだ。
?あ、そういうことですね。自分が舞いやすいように謡えばいいわけですね。
山崎 そうです。だから地頭というのがすごく大事になるの。他の流儀で名地頭と言われている人でも、いつも地頭ばかりやっているけれど、どこかちぐはぐさを感じることがあるんだよ。それはその人が立ち方をやっていないからなんだ。だから立ち方ができる地頭じゃないとダメ。今やっていなくとも、かつてはやっていたという人でないとダメなんだね。
そういう点では、喜多流はほとんど地頭専門という人はいないね。みんな舞っているね。
明生 そうですね。喜多流ではほとんど地頭専門という人はいませんね。実先生がむしろ型を重視されましたから。全員舞えなければダメだという教育でしたから…。

写真 地頭 福岡周斎の地謡
右より 大島政允 福岡周斎 粟谷明生 谷大作 梅津忠弘 出雲康雅
山崎 僕らが子どもの時分にね、例えば謡のうまい福岡周斎という人がいたんだよ。だけどあの人は舞わないんだ。独吟はすばらしいけれど、地頭をやらすと、あいつの地頭では舞えないという人が出てきたんだ。なぜだろうなって、僕は当時学生だからよくわからなかったんだけどね。だんだん、ああそうかと分かってきた。実際に能を何番も舞っていなければダメなんだよね。
今の喜多流の地頭を見るとほとんど立ち方ができる人がやっているからいいと思うね。それはある時期から実さんがそういう風に仕向けていったんじゃない。だから今の喜多流はそういう意味ではいいんじゃないですか。
我流『年来稽古条々』(29)?研究公演以降・その七?『小原御幸』について投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(29)
?研究公演以降・その七?
『小原御幸』について
粟谷 能夫
粟谷 明生
明生 研究公演の第七回は平成八年(六月二十二日)、能夫さんの『小原御幸』でした。大曲に挑む、ということで、二年間懸けて、各自、能一番ずつ、私が『松風』(平成七年)を勤め、能夫さんが『小原御幸』でした。法皇役は香川靖嗣さんにお願いしました。今回は『小原御幸』を中心に話をしたいと思います。
能夫 平成八年、もう十五年も前になるんだね。
明生 曲を決めたのは二年前でしたから、平成六年のこと、父(粟谷菊生)にどのようにして『小原御幸』を許可してもらおうかと思案して…。きっと、「もっと身体を動かす曲をやった方がいいんじゃないか」と言われるのを予想して、その時は「謡を勉強したいので…」と答えるから、と言われたのを覚えています。
能夫 そうだね。『小原御幸』はほとんどが謡や語りで出来ている能だよ。もともと謡い物として作られたと言われるぐらいですから、シテの動きは極端に少ないね。謡や語りが、いかに説得力をもってできるか、それが課題だったね。人生の辛さも分かってくる、ある年齢を過ぎないとできない曲だ、と言われていたから、余計に早く手がけてみたかったわけね。『小原御幸』は喜多流では外の曲扱いだから、伝書も最後の方に記載されているだろう。
明生 そうですね。『小原御幸』は本人が希望しないとできない曲です。選択の理由はなんですか?
能夫 それはいろいろな先人の『小原御幸』を見て来て、憧れが生まれるじゃない。観世寿夫さんの『大原御幸』とか、父(粟谷新太郎)も友枝喜久夫先生も好きだったし、そういう目標みたいなものがあるよね。いい曲でもあるし、花帽子をつけてみたいとか、楚々たる雰囲気がいいなとか。
明生 最初のシテの謡「山里は物の寂しき事こそ…」は京から離れた大原の山里に寂しく暮らす建礼門院の境地を語り、場面作りをする大事な謡ですね。この謡で忘れられないのは、フラメンコのステージで先代の観世銕之亟先生の、ここの謡が流れてきたことですよ。それがもう透明感というか、寂しさの中にある気品というか、そんな雰囲気をひしひしと感じさせる謡で、あれは絶品でした。
能夫 僕も先代の銕之亟先生の『大原御幸』の後シテの語りを聞いたことがあるが、まさにリアリティだね。喜多流は藁屋にシテ一人が入って、ツレの阿波の内侍と大納言の局はその地謡前に座る演出だけれど、観世流は大きな大屋台にシテとツレの三人が入っているね。喜多流では地謡が謡う「折々に…」のところも、三人の連吟になる。
明生 そういう演出の違いはありますね…。
能夫 話は少しずれるが…。『小原御幸』の舞台は大原寂光
院だけれど、同じ大原にある三千院、あそこの仏像は正座しているんだよ。阿弥陀三尊坐像の脇士ね。普通、仏像というと立っているか胡坐をかいているか、半跏の姿でしょ。それが正座しているの、珍しいよね。正座は何か礼儀正しいというイメージだけれど、日本古来からのものではないといういい方もされてきたが。このお姿で、昔からの座り方であったことが判るよね。あのイメージで、シテもツレも下居するといいじゃないかな…、と思うよ。
明生 なるほど。能夫 後シテの謡も難しいんだな。後の出の橋掛りの一の松で止まって謡う、祈りのところなんかもいいところですが、難しいよ。
明生 「極重悪人無他方便、…一門の人々成等正覚」の祈りですね。短い前場ですぐに中入りとなり、後場は後白河法皇の登場です。シテは山に花摘みに出かけ帰ってくる。法皇が訪ねて来ているなどつゆ知らずに。
能夫 侘び住まいで空しい日々を暮らしながら、ただ先帝・安徳天皇のことばかりを思い静かに読経しているわけですよ。祈ることで救われようとする静かな境地なのにね。
明生 そこに後白河法皇の御幸の知らせが…。
能夫 これで心がざわめくわけだよ。後白河法皇は建礼門院の舅であり、安徳天皇の祖父にあたるけれど、平家を滅ぼすための宣旨を出すぐらいの策士でしょ。
明生 建礼門院は平清盛の娘・徳子ですからね。法皇は最初、平家と姻戚関係を結んで組みしながら、源氏が勢力を伸ばしてくると源氏につくぐらいの人間です。建礼門院としては身内でありながら仇のような複雑な心境ですよね。
能夫 心の中はどろどろしているよね。だから、内侍から法皇の御幸を告げられたときに、シテには躊躇があるんだ。会いたくないってね。でも法皇だから…、力関係からいっても帰すことはできない。
明生 心の動揺をどう謡うかですね。
能夫 そう、そこが難しいよ。謡と立ち居・振舞みたいなもので物語を進めていかなければならないのが『小原御幸』だよ。シカケ・ヒラキといった型で修業してきた人間にとっては、その表現法が使えないわけだから、謡うこと自体を考えなければいけないよね。建礼門院という高位で物静かな人物を八割がた声だけで表現する…。能には、そういう課題の曲が用意されているんだと痛感したよ。
明生 建礼門院にたたみかけるように、六道の有様を語れと言って平家滅亡の有様を語らせ、挙句の果てには安徳天皇が入水して亡くなる最期の有様まで語らせる法皇役、この悪役も中々ぴったりの人っていないですよね。観世銕之亟先生が法皇を父に依頼したことがありましたが、父の法皇も正直完璧かというと…、逆に法皇がピッタリはまり役だね、なんて言われたくないですね。(笑)
能夫 そうだね、ある種サドだからね。これでもかといたぶる感じ。銕之亟先生は黒ミサの世界だと言っておられた。
明生 だからこの法皇役って本当に難しい。悪役に徹し芝居が出来れば出来るほど『小原御幸』という能がしまるような気がします。父が広島で勤めた時に、亡くなった観世栄夫先生がやられましたが、あの時は似合ってると思いました。あ、栄夫先生に失礼かな。(笑)
能夫 すごく強く演じられていたね、覚えているよ。語りたくない女院に、「自分は六道の有様を見たいのだが…、普通は仏や菩薩の位でなければ見られない世界を、おまえは見て来たのだね?」と挑発して、うまく引き出すんだよ。
明生 あそこはぞくぞくする場面ですね。ロンギまではなんとなく静かで流れるように謡ってきたものが、一変する。台本がうまく仕掛けていますね。
能夫 本当に魔女裁判みたいだよ。国母だった人が、自分も平家とともに、安徳天皇とともに入水して果てようとしたのに、黒髪がからまって不本意ながら生き延びてしまう。そういう辛い思いをしている人に、その有様を再現させて語らせるんだから。
明生 残酷ですね。生涯の一番忌まわしい部分を語らなければならない。それも滅亡に追いやった張本人の前で…。
能夫 そう。そこですよ。子どもを失い、一門も全滅し、自分だけ生き残った。その思い。
明生 それはやはり能楽師人生のすべてをかけて謡うしかないですね。
能夫 自分の人生で体験したこと。一番つらいこと。死とどう向き合ってきたかといったこと、すべての集大成になる。だからあまり若くしてはできない曲なわけだよね。
明生 でも、一度やって経験しないとそれもわからない。
能夫 謡い、語るとき、自分の肉体をどうしたらいいのか。同情から始まって、シテという登場人物の心境になったとして、でも表現はこの肉体でしなければならないんだ。それは経験してみないとね。具体的に言うと、たとえば笠をかぶっただけでも自分の声が稽古のときとは違うと感じるでしょ。ましてや花帽子ですよ。結構聞こえないんだよ。
明生 私は俊寛でしか経験がないのですが、息苦しいですよね。なんとなく酸素不足で苦しい感じ…。
能夫 それをかぶって謡う。それはやはり経験してみないとわからない。だから、研究公演で演ってみて、ちゃんと出来たとは言えないが、語りというものの大切さを勉強した、という手応えは充分感じましたね。
明生 経験値を上げるということですよね。私はまだ『小原御幸』のシテは勤めていないですし、ツレも法皇も経験が無いのですが、地謡はたくさん経験して来ました。この研究公演では、後列で父の左隣で謡わせてもらいましたが。これは研究公演だからこそ出来たこと。それ以外は父の地頭の前列で謡ってきたわけで、あ、このように謡うのかと身体に染みこませてきたものを、あの時は後列で謡い、後列の舞台を支える力、責任感を肌で感じました。
能夫 そうなんだ。僕もこのシテを勤めたことで、今度、地謡を謡うときにとてもプラスになったね。
明生 シテの経験を経て地謡を謡うのと、無くて謡うのとでは雲泥の差です。だから、いずれ地頭や副地頭を謡う使命、宿命かな、そういう人は、出来るだけ多くシテを経験しておくべきだと思います。そして、そこで学んだことを生かして、他の人のために謡う、それが普通で、健康的で、そうでなければいけないと思います。能はシテだけ良ければいいという物ではなくて、地謡も、三役も全てがよくなければいけませんからね。
能夫 『小原御幸』は特にマスゲームみたいなもの。みんなの力量が上がって、みんなが揃っていないとできないよ。
明生 本当にそう思います。私もいつかシテを勤めて、この難しい謡と語りに挑戦したいと思います。能夫さんは研究公演以来、『小原御幸』は再演していませんね。
能夫 僕は、それ切り演っていないね。なかなか人手が必要だからね出にくい曲ではあるね。いい曲ですが…。今だから言えるのだが、謡の勉強をするなら『朝長』がいいよ。
明生 『小原御幸』と『朝長』の語りは共通項もあるけれど、質的にちょっと違う感じがしますが。
能夫 『朝長』はまた違う世界での、現場にいたリアリティを語るんだね。『小原御幸』の方がスケールの大きさ、物語の大きさという点では上をいくかな…そんな感じがする。平家滅亡の過程をすべて述べるでしょ。平家物語の最後、わざわざ灌頂巻をつくって、この物語を平家物語の締めくくりにしただけのことはあるわけで…。
明生 平家物語の集約されたものですね。一番辛い部分。愛別離苦、親との別れ、子どもとの別れ、人間の生き死にに関することを物語る。究極のお能のテーマです。そういう辛いものに対してじっと耐えている、そういう人間と拮抗するような謡ができないといけないわけですね。
能夫 そういうことだね。愛別離苦は過去の話ではなく、現代にもあることでしょ。今回の東日本大震災だって、親を亡くした人、子を亡くした人、家や財産、仕事を亡くした人がいて、辛い体験をされている。そういうときに能は何ができるのか、考えさせられた。
明生 自粛、自粛ムードのなかで、お能をやっていていいのかって。お能を見たって腹がふくれるわけではないし、そういう意味では不急不要の最たるものかもしれません。
能夫 でも、じゃあこういう芸能が全くなくなってもいいかというと、そうではないと思うよ。被災しても、日本人って素晴らしいと、外国のメディアが賞讃しているじゃない。略奪はないし、物資が来たときに、我先に奪い合うわけでなく、みんな整然と並んで受け取っている、と…。日本にはそういう文化があるんだよ。儒教や仏教、お能や芸能、文学、そういうものから育まれた精神というものがあると思う。だから、我々が今までやってきたことは、そういう文化を浸透させ、秩序を生んできたと思うな。
明生 直接の腹の足しにはならないけれど、そういうことはありますね。そして能は辛い経験をした人が救われていく話です。特に乱世にはこういう救いの芸能が必要だったのかも。それは現代にも通じると言えますね。
能夫 能は魂を鎮める芸能でもあるからね。つらい運命を引き受ける芸能、そういうものが今こそ必要だよ。そして今、日本中で何ができるかが問われているよね。それに震災で、みんな人との絆の大切さを感じたのではないかな。自分一人で生きています、村社会なんて関係ありません、みたいに開き直る人がいるけれど、でもやはりみんな関わりあって生きているよね。絶海の孤島なら一人で、と言えるかもしれないけれど、日本の国土にいる限り、それはあり得ない。電気一つにしても、自分で作り出しているわけではないし。何でもそうだよ。そういうことを知るよい機会になったと思いますよ。
明生 はい。電気だって、今まで無頓着に使っていましたからね。能のことは考えているつもりですが、電気のこと、原発のこと、何も考えていなかったなあ。自分たちの生活はこれでいいのかな、あらゆることを見直そうというムードになって来ましたね。
能夫 今、電気がないと何もできないけれど、これ高々百年ちょっとの話でしょ。江戸時代は電気なんてなかったのだから。
明生 能楽界もいろいろなことを見直すのにいい時期かもしれません。能も過去にはいろいろ困難な時期がありました。明治時代にはパトロンだった大名がいなくなって経済的に困窮したし、欧化政策で日本の古くからの芸能はスポイルされた。戦中は歌舞音曲はまかりならない、だったし、戦後はマッカーサーが来て、八度ないのは音楽ではないと言われたり…、能は数々の存亡の危機に立たされて来ました。
能夫 そこを先人たちが頑張って乗り切ってくれたわけです。我々もこの困難なときに、みんなで考え、見直していく、ほんとうにいい時期かもしれないね。
明生 興行のやり方、プロデュース力をつけるとか、若い能楽師への教育とか。改めて考える時期ですね。
能夫 子どもたちに日本の芸能、文化を、特に能をもっと知ってもらう努力が必要だね。惜しんではダメなんだよ。
明生 まだまだやることはたくさんありますね。 (つづく)


『小原御幸』 シテ 粟谷能夫( 撮影 あびこ喜久三)
我流『年来稽古条々』子方時代(2)投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
我流『年来稽古条々』子方時代(2)
粟谷能夫
粟谷明生
能夫─ 子方をやっていてシテの演技を鮮烈に憶えているという経験でいうと、実先生の『安宅』で、義経が留められて「腹立ちや、日高くは能登の国までさそうずると思いしに……」という言葉と、後で写真で見た姿が忘れられない。メインの場ではないかも知れないけれど、一人言のようでもあり、また相手に聞かせるという複雑さが伝わって来て、いいセリフだなと思ったし、自分もあんな風にやりたいなという指針になった。
明生─ すぐその後に金剛杖で打たれる所、稽古の時は実際に笠をつけないのでよく解らなかったんですが、本番では本当にボコボコ叩かれるので、両手でしっかり笠の紐を持っていなければいけないのだ、とか、「通れとこそ」の時も実先生のはとても力強く本当に突き飛ばすようだったので、すーと速やかに歩まないといけないとか、体験しながら憶えたことを思い出します。『富士太鼓』や『望月』ではお相手の方により、謡の早さや、音の高さなども子方の調子に合わせて謡われる方もあれば、シテやシテ連の本来の位通りで謡われる方もいらして、子供心にも色々あるんだなーと思いました。例えば、『富士太鼓』の「打てや打てやと攻め鼓」の所、ある時は子供らしく、さらりと打つ場合もあれば、また謡一杯粘るようにしっかり打たされる時もあり、このような経験は今の私に大きく役に立っていると思います。私はとにかく子方の回数が多くて、調べてみたら百十九番。小学四年生位から声変わりが始まり、子方らしい高い、澄んだ声が出なくなり、自分自身に徐々にいら立ちを感じ始め、ついには謡に劣等感を持つようになってしまい、自分なりに悩みました。生まれつきの良いつつ(喉)に恵まれない分、自分なりに工夫し声を創っていかなければならないと思い始めた最初ですね。
能夫─ 僕がめぐまれていたと思うのは、子供の頃から、実際に面装束にふれながら父に色々なことを教わった。また大事さも知った。やはり子供の頃から面を見ているものと大人になって見るのでは自ずから違いが出て来る。良い面というのも、手にとって見ただけでなく、実際舞台で生かされるのを見て知った。辰三さんが装束を出していて、それを手伝っていて厚板と唐織の違いも分からなくて、それが口惜しくて大いに勉強した。
明生─ 私の子方の卒業は十二歳の時で、実先生の『満仲』で幸寿丸でした。だから私の子方時代の幕切れは斬られて終わり。その時に忘れられないのは、美女丸をやる同じ年の素人の子なんですが、美声でね、声で悩んでいた自分にはすごく羨ましかったです。この声の問題はまたあとで話にでると思うけれども。
能夫─
僕は『烏帽子折』だったけど、いまでこそ『烏帽子折』で子方卒業というけど、当時は勿論そういう自覚はなかった。今にして思えば、実先生がそういう場を作ってくれたと思うけど、週二回位のペースで実によく稽古してくれた。そういう意味ではうまく育ててくれたし、育てられた。 明生─ とにかく子方時代は終わった後は必ずご褒美が頂けたし、褒められたし、これが結構気分よくて、そうして知らないうちに、次から次へと舞台に立たされるわけです。
子方を卒業したあとには、色々な難関が待っていました。なによりもまず謡本が読めないんです。それまでは先生が、見本として謡ってくださり、それを鸚鵡返しで憶えるという稽古でしたが、中学生になると突然、いついつまで憶えてくるように、と言われるのです。さあ謡本をあけても節付の意味がさっぱりわからない、今までに謡った箇所は解るのですが、初めての所はどのように謡うのか解らない、この謡本に全く歯が立たない状況には自分ながら愕然としました。
謡の仕組みはこのようで、この節の時はこのように謡う、などという事はなく、自分でどうにかしろという風潮ですから、親切な教わり方も子方と共に卒業させられた訳です。とにかくこの状況が急に襲ってくるんです。
能夫─ そう、子方時代何の苦もなく憶えられていたから自分では出来ると思っている。それが謡本を見ての稽古になると全く理論が解ってなかった。ともかく節付が読めない。
明生─ 中学一年生で太鼓を習い始めた頃、大ノリなら、まあ何とか謡えますが、小ノリとなるともう全然お手上げ、小鼓の稽古が始まると自分のさえ憶えていくのが大変なのに、先輩の、それも『柏崎』や『朝長』をいきなり地拍子に合わせて謡うわけですから、そりゃもう聞けたものではなかったでしょう。
能夫─ その時に思ったのは、節付を理論としても解し、地拍子も身につけ、文章も理解し憶え、その曲にふさわしい謡を謡えるようにならなくてはいけないと思った。
明生─ 私は謡で苦労したから余計思うのですが、我が流は謡に関しては野放し状態でした。子方から青年期への大事な時期、もっと指導者がしっかりした方向性を指示していく必要があると思います。
能夫─ 自分なりに謡と対峙したけれど、謡ということにぶつかったのは二十歳過ぎて青年喜多会で『玉葛』をやった時に、悲しい役の女性ということで多分に情緒的な、女々しい謡を謡った。それは違う、もっと身体の奥底から出す強い声で謡わなくてはいけないと言われた。
(つづく)
能の仕掛け投稿日:2018-06-07
能の仕掛け
粟谷能夫
 能は長い時間かけて今日のような様式をもつ芸能として作られて来ました。我々が教わってきたことは流儀の規範として大切なことですが、それが形だけの伝承では大事なものが抜け落ちてしまいます。伝承というものの根拠を理解し、また諸先輩の理解のしかたを学び、より良い表現に至ろうという努力を忘れるべきではないと思います。
能は長い時間かけて今日のような様式をもつ芸能として作られて来ました。我々が教わってきたことは流儀の規範として大切なことですが、それが形だけの伝承では大事なものが抜け落ちてしまいます。伝承というものの根拠を理解し、また諸先輩の理解のしかたを学び、より良い表現に至ろうという努力を忘れるべきではないと思います。
能の表現にとっての一番の基礎となる「構え」と「運び」そして「シカケ、ヒラキ」についてどれだけの人が自覚的なのでしょうか。
具体的に言うと「構え」というのは、前に行こうという力で、両腕を前に引き上げ、肩甲骨を返す(左右の肩甲骨を引き寄せる)ことで後ろに引き戻される力を身体の中に作り、さらに肘を内側へねじることによって外へ向かう力と対峙するのです。このことで前と後、内と外に引かれ合う緊張感が生じ、ねじれという負荷をかけることで、能役者の身体の強い存在感が表現可能になります。また腰を入れる(腰椎を緊張させ腰を引き上げる)というのも「構え」の力学的中心を腰に置くことで安定した動きを得、重力に対して反発する力を生み出す身体の技法なのです。ここには拮抗する上下の力のせめぎ合いがあり、腰を入れるより腰を返すと表現した方がわかりやすいかもしれません。
このように前後、左右、天地とあらゆる方向から引っ張り合うその中に強い存在感、緊張感のある「構え」が成り立ちます。このような力学的根拠なしに形だけを真似ても能の表現にはならないのです。「運び」というのは、この身体が、上下左右にゆれ動くこともなく前に進むことです。前後に引き合っている力の均衡が破れて、何足(なんぞく)か前進するのですから強い表現となり得るのです。
そして「シカケ」によって、前方それもあるときは宇宙の彼方という無限大の焦点に向かって凝縮した気力を集中させ、「ヒラキ」によって大きく解放してやります。こうした型の内実に無感覚で安易に「シカケ」をしたのでは器械体操のように両手を広げた「ヒラキ」になり、最後まで開ききってしまっては、役者の限界が見えてしまい、存在感、緊張感が失われてしまいます。負荷がかかっていれば開ききることはあり得ないのです。そしてその残り部分、余白や余韻を観客の想像力に委ねる、このことも表現の豊かさだと思うのです。
先代の観世銕之亟さんが「アクセルを踏みながらブレーキを踏む」とよくおっしゃっていましたが、負荷の掛け方を的確に表現された言葉だと思います。
これが能の「仕掛け」であり、単なる「シカケ、ヒラキ」という物理的な動きとは違います。三間四方という限られた空間で時空を越えて人間の深い情念を表現し、宇宙的な大きさを表現する芸能の本質的な方法であり、まさに仕掛けなのです。
写真 粟谷能夫「黒塚」 撮影 東條睦
我流『年来稽古条々』(20)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(20)
?青年期・その十四?
『翁』について(1)
粟谷 能夫
粟谷 明生
明生 これまで『猩々乱』から始まって、青年期に重要な披きについて話してきました。今回はその披きの流れからいって、青年期より上の年齢での披きになりますが、『翁』について話し合っておきたいと思います。私の披きは平成七年、宮島の厳島神社・御神能のときで、三十九歳でした。能夫さんは何歳のときですか。
能夫 僕も同じ御神能のときで、三十四歳だね。『翁』の披きは通常は四十歳前後ということじゃないかね。
明生 『翁』は能以前の段階で神事として執り行われ、今につながっているので、特別ですから軽くは扱えませんね。
能夫 各流儀とも、昔も今も大切に扱っているね。
明生 以前は流儀の長老か代表役者が勤めるという風潮で、若手では『翁』を披くことは難しかったような印象を受けていますが。もっとも最近はそのような制約を払拭しつつあるようにも思えます。現に一月の初会では今後順次に若手にも順番が廻ってくるようですから…。
能夫 一時、日本能楽会会員になるには『翁』を披いていなければ云々ということがあって…、それでそういう配慮をしよう、という風も起きたね。
明生 そういう縛りがあったためか、『翁』を披いていない人は自分の会で披かざるを得なかったということもありました。でも自分の会で多大な投資をしてまでする曲ではないというのが、私の本音です・・・。
能夫 そうね。でも今は日本能楽会会員になるためという条件は外れたんでしょ。
明生 なくなりましたね。女流能楽師の入会が関係しているでしょうか…。
能夫 それにしても、我々は厳島神社の御神能で勤める機会があるからありがたいね。
明生 本当にそうですね。厳島神社の御神能は、毎年四月十六日と十八日を喜多流が担当していますが、初日の翁付脇能を隔年に執事の出雲康雅氏が、その間を能夫さんと私で勤めていますから、このところ我々は四年に一回、『翁』を勤める機会に恵まれていますね。
能夫 父はこの御神能が好きで愛着があったな…。晩年にはまた来年これるかなとよく言っていたよ。四月というすがすがしい季節で、とても気持ちがいいよね。一年息災に過ごし、今年も無事ここにやって来ることができました。ありがとうございましたと、自然と神に感謝する気持ちになるよ。
明生 四月十六日が一年の始まりのような、厳かで新鮮な気持ちにさせられます。我々はここで『翁』を披いたと考えていますが、こういう野外の神事で行う能では正式な披きとはいえないという意見もあるようですが…。お相手の狂言が素人だったりすることもあるからかもしれませんけれど・・・。
能夫 確かに御神能は全体に素人の方が多くなさって、我々がお手伝いする格好だし、参拝者がゾロゾロ歩いていたりするわけで・・・、でもそんなことがちっとも気にならないじゃない。何しろ厳島神社というのは『翁』を勤めるにはいいロケーションですよ。やってみるとわかるんだな。四月、若葉がもう萌え出していて…。幕を開けて一足出ると、空気は澄んでいるし・・・。もう、こんなに大夫冥利に尽きるところはないですよ。
明生 燦々と輝く陽の光とか海の匂いとか・・・もう自然を感じますね。自然の力に圧倒されるんですよ。装束だって陽に照らされた色を見ると、極上の綺麗さでしょう。能夫さんがよく言っていますよね。自然の神々しさ、木々の生命力、そういうものに訴えかける気持ちもなければ駄目だって・・・。
能夫 そうだよ。『翁』では我々は神にならないといけないんだから。
明生 宮島はその気にさせられる絶好のロケーションですね。
能夫 もともと『翁』というのは五穀豊穣、天下泰平を祈る祝言性の強いもので、一般の能とは違うよね。
明生 「能にして能にあらず」ですから。古い芸能の形ですね。「とうとうたらり」とあの訳の判らぬ呪文めいた謡も然り、「天下泰平、国土安穏。今日の御祈祷なり」と謡い舞うわけですから、演劇性はなく、「祈り」のパフォーマンスですかね…。
能夫 昔は、『翁』には特別な意識があって、勤める前には精進潔斎をしていたわけでしょ。
明生 勤める前日に沐浴して身を清め、食事も「別火」にして作るとか、私、恥ずかしながらしたことはありませんが…。楽屋は今でも女人禁制になりますね。
能夫 前の日は自宅に帰らず、別世界にいるような意識だろうね。銕仙会の浅井文義さんが銕仙会の舞台に泊り込んで精進潔斎をされたと聞いているけれど…。なんでも親父さんの書き付けがあって、それには翁汁という小豆汁のようなシンプルなものを食べて禊をするとあるらしいよ。
明生 そうですか。貴重な体験ですね。
能夫 そうね。厳島神社の御神能では、楽屋に翁飾りの祭壇が作られ、演者はその前に並ぶでしょう。
明生、そう。普通はまず太夫にそして三番叟、千歳、そしてお囃子方へと、後見二人がお神酒と土器を持ってお酌に廻りますが、後見が動かず演者が交代で移動してお神酒を頂くのは御神能の特徴かもしれませんね。
能夫 翁は元はといえば御神事そのものだったわけよ。それを芸能にしたのは観阿弥といわれている。あの有名な今熊野で大和猿楽四座が催した能のときね。
明生 鬼夜叉(世阿弥の幼少の呼び名)が足利義満に見出されたときの、あの歴史的な催しですね。
能夫 そう。あのときは、義満の側近である南阿弥という人が企画して、猿楽というローカルなものを中央に持ってきて将軍に見てもらおうとしたんだ。そのとき観阿弥に『翁』をやらせた。当時は『翁』といえば、その座の長がやることになっていたわけだけど、結崎座として、長老ではなく、一座のスターであった観阿弥が勤めた。その観阿弥の芸を、もちろん眉目秀麗だった鬼夜叉への寵愛もあったけど、義満が気に入るところとなったわけ。『翁』を長老ではなくその一座のスターがやるというのは、異例なことだったんだ。
明生 そのとき、観阿弥・世阿弥は何歳でした?
能夫 観阿弥が四十二歳、世阿弥は当時は鬼夜叉だけど、十二歳だったかな?・・・。
明生 観阿弥が四十二歳か。私たちが『翁』を披いた時期と同じくらいですね。長老でなくトップスターが勤めるにしても、四十歳ぐらいというのは適当かな…。
能夫 長老がやるのは神事という位置づけだけれど、一座のトップスターがやるのは芸能という位置づけになる。だから観阿弥が神事を芸能にしたんだと聞いているよ。もちろん、昔ながらの神事をそのまま継承した流れも、明治時代ぐらいまではあったようだけれど…。神事を芸能にしたというのは、芸能者が厄を祓い福を呼び寄せるという役目を担うということで。芸能は瓦乞食の所業と言われながらも、必要とされ今日まであるのは、人々を代表して厄を引き受け、福を祈るというところにあるんじゃないかな。
明生 そもそも、我々がやっている芸能の根っこはそういうところもありますね。芸能の力は祝言の力というか・・・。五穀豊穣や天下泰平という祈りから始まって、人間の悲しみ、苦しみ、すべてそういう普遍的な負を背負って、それを提示し、その苦しみから救済するという役目だと思います。
能夫 そう、それが芸能の根源。我々が能役者としてやっている根拠なんだよ。
明生 『翁』は能の根本芸ということになりますね。それにしても、お能の歴史の始まりといってもいい、あの記念すべき今熊野の能で観阿弥が『翁』を勤めたとは・・・。『翁』という曲の見方が少し変わりましたね。
能夫 あれがなかったら、今の我々もなかったかもしれない。その後、世阿弥が数々の台本を書き、能を発展させていくことにつながっていくわけだから。
明生 そう考えると、『翁』を単に儀礼的にやるだけではいけないことになりますね。
能夫 祝言性なりを体に引き受けていないとね。
明生 五穀豊穣や平和を祈るという芸、その根本にあるものがどこかで生きていないといけませんね。舞台に出て翁の面をつけることによって、神となり、人々を代表して厄を引き受け、福をもたらすという意識かあ…。
能夫 翁という存在になって、エネルギーを持って演じないとね。芸能者が神に通じる何かを感じて演じなければいけないということだね。
明生 でも、『翁』は全部で一時間ほどでしょう。その中で三番叟(大蔵流では三番三)が三十分ぐらい占めますから、我々翁大夫(シテ方)が演じる時間はとても短い。出入りの時間を引くと正味十五分ぐらいのものでしょうか。型付だけを見れば、まあ簡単にできてしまい安易に考えてしまいがちです。これが我々能楽師の陥りやすいワナで、一番悪いところですね。
能夫 そうだよ。型だけではない、精神性が大事だよ。もっと『翁』の根源的なことを意識して、それを体に入れてやらないとね。
メイキングNHKテレビ 「芸能花舞台」 その3投稿日:2018-06-07
○一調一声が得意だった
?『井筒』のあとに、一調一声の『玉葛』を一部分ですが聴いていただこうと思うのですが…。小鼓が曽和博朗(ひろし)さんで謡が菊生さんです。
山崎 とても面白いと思いますよ。やっぱり菊生さんは舞う人なんだね。自分が舞っているからリズムがものすごくいいんですよ。謡い屋さんに謡わせるとああはいかないんですよ。菊生さんは謡いながら舞っているね。だからとても面白いよ。僕なんかが聴いていると、舞台が目に浮かんでくるよ。
明生 一調一声は囃子方が打つ手組に合わせて謡うわけです。拍子に合っているところも、合わないところも、囃子に合わせ音の幅や高低差でふくらみをつけて謡う、しかも、今山崎先生が仰ったように、聞いている人がその情景が思い浮かぶよう…というのは、なかなか至難の技なんですね。
山崎 今回の一調一声は小鼓と謡ですね。小鼓に合わせてシテも一人で、リズムにはずれないように謡わなくてはいけない。ところが今言われたように、拍子に合わないところが難しいんです。ここに気持ちを込めて謡わなければよい一調にはならないんですよ。拍子に合わないところは自由に謡うところだけれども、そこをいかに気持ちを込めて膨らませて謡うか、これが一調の謡い方のコツなんですね。だから意地悪く言えば、これを聴くことで、その人がわかっている人かどうかがわかるくらいなんですよ。
明生 曽和先生との一調一声をNHKで収録するとき裏話がありまして…。リハーサルのとき、曽和先生が「菊生さん、どうしますか? 一回やっときますか?」と聞かれ「そうだね」と言ってお二人は別の部屋に行かれて申合わせをしたんです。
それで父が戻って来たときに「どうだった?」と聞くと、「まあ普通、とんでもない手組はなかったよ」と答えてくれて…。さて本番が無事終わって父が楽屋に戻ってくると「やっぱり博ちゃんは本番で違う手を打ってきたよ」と言うのです。
「博ちゃんは、馴れが嫌いでね。だから最後のところで申合とは違う手を打ってきたよ。でもな明生、僕もそうくるだろうなと覚悟していたからね」と、今でもその時の父の顔、克明に覚えていますよ。
なんでも、この録画はまずは曽和先生が先に決まっていて、NHKが「謡い手はどなたに?」と曽和先生に聞かれたら、「粟谷さんでお願い」とのお返事だったとか。これはNHKから聞いた話ですが…。
山崎 それもいい話だよね。馴れちゃダメなんだよ。いつも真剣勝負だから、一調一声というのは。だから面白いんだよ。何度もリハーサルやっているのをそのまま聞いても面白くもなんともない、緊張感がないよ。お互いに真剣勝負でぶつかってやるから、こちらにも伝わって来るんだよ。
明生 『玉葛』の「あかぬやいつの寝乱れ髪、結ぼれゆく思ひかな」というところ、幸流の鼓は「流し」といって、最初にチ チ チ チ チと干高い音の連打で始まり、次第にポン ポン ポンと音色を変えて連打するところがあるんですね。ここを小鼓への配慮なく無神経に謡うとダメなんですね。相手が楽しんで打ちたい気持ちを汲んで、ゆったりと邪魔にならないように、打ちやすいように、そう謡うのがよろしいようです。
基本的には一調一声は一対一でするのですが、主人公、主役は小鼓なんですね。シテはそれを補うように、楽器奏者を盛り立てるように謡わなければならない、向こうが楽しく好きなように打てるようにしなければ、と父はよく言っていました。
だから、「あーかーぬ」というところは、向こうはたくさん打ちたいのだから、サラリと短く謡ってはダメで、そういうことを心得えておけよ、とよく言われましたね。
山崎 一調というのは囃子方のものなんですよ。囃子方が主人公なんだ。舞台の真ん中に座るのが囃子方。謡い手はそれに謡いかけるわけですよ。そのためには囃子方を生かさなければならないのね。そういうところが菊生さんはうまかった人なんですね。だからみんな、菊ちゃんに謡ってくれ、とオーダーが殺到したんでしょう。
明生 お囃子方の方では、父とか梅若六郎(現・玄祥)先生
だと心配しないですむ、好きなように打っても合わせてくれるといって歓迎されていましたね。僕みたいな新米は、お相手から「おい大丈夫か、こう打つからね、外すなよ」、なんて言われたりしてますからね(笑)。
山崎 そういうものなんだよ。あくまでも楽器が主だからね。だから能の地謡と一調一声の謡は全然別のものなのね。だから経験を積んでいないとダメなの。菊ちゃんのように海千山千の人でないと、囃子方は安心できない。だから菊ちゃんはよく囃子方に頼まれたんだね。
明生 囃子科協議会の調べによると、今まで一調一声の出番が一番多かったのは父だそうです。「菊ちゃん、なんでそんなに出ているの?」とは北村治さんのお言葉ですが。
結局、頼んでもみんな嫌がるのを、父は嫌がらなかったからでしょうね。私は嫌ですが…(笑)。
山崎 そりゃ嫌がるさ。それから囃子方の会というのはお素人さんが打つんだよね。それを打ちやすいように謡ってあげなくちゃならない。それには彼はとてもいいんだよ。
明生 プロの会でないときは苦労すると言ってましたね。お素人さんの中には謡に関係なく自由勝手に打つ方もおられるわけで…。それをハイハイとうまく無傷のように謡い終えて、「ああ、よかったですね。お上手、お上手、なんてお上手が言えるのは、僕と六郎さんぐらいだよ」と言っていましたよ。お弟子さんたちも失敗していてもわからないから、「先生、次回もまたやります!」となるんですって(笑)。
一調や一調一声はみんな敬遠しがちなのですが、父は相手がどう打ってくるか分からないスリリングな感じが好きと言って、頼まれれば必ず受けていましたから。
で、「一調を謡う時の心得とか、コツはどうしたらいいの?」と聞いたら、「経験と馴れ」ですって。
○好きな曲『鬼界島』
?最後に菊生先生のお能を、名演と言われている舞台を見ていただこうと思いまして、
明生 菊生と言えば『景清』でしょう? 『景清』『弱法師』などが父のお得意十八番でしたよ。これに関わる話ならばいくらでもありますよ、裏話がね。
?すいません。『景清』と『弱法師』は放送に支障ある言葉がありまして、違う曲でお願いします。それで『鬼界島』を取り上げてみたいのです。先生がお好きでしかも工夫されたところがあるということで。2000年の舞台映像がありますので、これでお願いします。
『鬼界島』は伝書に残っていない、というようなことが、明生さんのホームページに記載されていたのですが、先人のみなさん、そして菊生さんそれぞれのご工夫されていることがあるようでしたらお聞かせいただきたいのですが・・・。
明生 九世・喜多健忘斎の伝書には『鬼界島』と『草紙洗小町』の二曲についての記載はありません。それ以前の伝書にはありますよ。でも『俊寛』となっていて観世流に近い型みたいです。『隅田川』も『角田川』と書いてあったり。それらを全部整理したのが健忘斎なのでしょう。この我が家の伝書は私が知る限りでは、高林家と我が家の二家にしか残っていないと思います。家元のところにも以前はあったようですが戦争で焼けてしまった、と父は申しておりました。ですから貴重な伝書です。もちろんこれは祖父益二郎が手に入れて書家に写させたものですが…。昔の弟子は修行した後に、先生から写しのお許しをいただいたそうで…その写しなんです。
そこに、今言った二曲がないのはどうしたわけなのか、幕府から何か言われたのか、他流からの何かの影響があったのか、それはもう全然分かりません。
たぶんその後、時代を経て、十四世喜多六平太先生が流儀を再興され、この曲をなさって、現代やっている原型を創られたのではないだろうか、と言われています。それを実先生も継承されてと。といっても、実先生はあまり『鬼界島』をお好きではなかったので、あまりおやりにならなかったですし、弟子の稽古でもあまり細かなことは仰らなかったみたいですね。『鬼界島』は友枝喜久夫先生や新太郎伯父、父などが、六平太先生はこうやっていたという教えでやられていました。今は我々がそれを受け継いでいます。
?『鬼界島』はあまり多くは上演されていなかったのですか、それを六平太先生がやるようになってやるようになった?
明生 昔のことは判りません。ただ他の流儀と比べるとあまり多くは上演されていなかったかもしれませんね。でも父たちの時代は結構多くやっていました。やはり名人の先生の舞台を見て憧れて、いつか自分もあのように!と皆様やりたがったのではないですか。
六平太先生が『羽衣』が好きとなると直弟子たちも『羽衣』をやりたがる。先生が『井筒』をあまりやらないと、みんなもあまり・・・というようにね。
?菊生先生は『鬼界島』お好きだった?
明生 好きでしたね。父は非常に好んで『鬼界島』をやっています。上演回数もすごく多いですよ。
?伝書に記載されていないので、ある程度自由にできたのですか?
菊生先生の工夫みたいなところもあったと聞いていますが。
明生 六平太先生からの教えに自分なりの工夫を重ねていったと思います。
『鬼界島』はシカケ・ヒラキ、サシ・ヒラキとか、左右して上羽して拍子をポンと踏んで・・・というような舞の型はありません。『小原御幸』もそうですが、謡が中心の曲ですので型らしき型はないのです。だからこそ役者の創造性が能そのものに反映され、それが充分許される特異な曲目と言えます。
山崎 この曲は能としての型がないので、あれが能かなと思うほど、非常に不思議な曲で、むしろとても演劇的。能というのは型というものがあって、個人が出せないカテゴリーがあるわけね。この曲のように型がないものは、能であるという核をもって演劇にならないように作る、これに難しさと面白さがあるんですよ。『鬼界島』のような演劇的なものはヘタをすると芝居になってしまうんです。芝居のセリフが謡になっているという違いはあるけれど、芝居になりやすい。だからこういう曲はやらないよという人も多いんだ。こんなの能じゃないと言う人もいるし。だけど、こういうものを能的にやるのも面白いという人もいる。
?菊生先生はその考え方だったんですね。
明生 そうですね。
山崎 菊生さんという人は、こういう能らしくないものを、能のカテゴリーの中にちゃんとやろうというところがあったのね。あの人、割合無造作な人ではあるけれど、非常に緻密にものを考える人なんだよ。一見素朴そうに見えて、何も考えないのかなと思うと、そうじゃなくて、非常に緻密に考えるんだね。僕は長年付き合ってきたから、そこがよくわかるんだね。非常に細かいですよ。
明生 父は、六平太先生の型をベースにして、歌舞伎の初代吉右衛門さんの「俊寛」がよかったから、それを取り入れて、自分なりのものを作った、と言っていました。
最後の場面、迎えの船が成経と康頼(ツレ)を乗せて出て行き、俊寛だけ島に取り残されるシーン。この映像では両手を上げていますが、以前は片手でした・・・、とにかく、手をあげて船の行方をずっと見つめているシーンです。そのあと正面向いて少し下を見て右足一足をぐっとなんとも言えない力で後ろに引き下がり終曲となるのですが、その一連の一型で一人残された絶望感を表現するのです。そこを、吉右衛門さんの芝居を見て、右手をずっと上げてどんぐりまなこで船の行方を見つめているところ、そこが気にいって、それをいただいたんだと言っていました。最後には片手でなく両手をあげて、あーあーとか、お?い、という嘆きの絶叫を無声で表現する、そう私は解釈していますね。
山崎 ずっと手を差しのべて船を追う、それだけで表現ね。船が遠くにいってしまった悲哀、一人取り残された悲壮感を、じっくり見せてくれる。能なんだね。ところがこれが芝居になると、歌舞伎なんか、船が遠くに離れて行くと俊寛は岩によじ登り、それがまわり舞台になって動いていって、船が小さくなっていく・・・そこまでリアルにやるの!と思うほどリアルなんだよ。能は、ただ船が静かに帰っていって、俊寛は手を差し出すだけ。これだけで孤島に一人残された悲哀が舞台全体に広がっていき、観るものの涙を誘うよね。お能はよくできているよね。
明生 それから、ツレの成経と康頼が二人で「痛はしの御事や、我等都に上りなば、よきやうに申し直しつつ、やがて帰洛は有るべし、御心強く待ち給へ」と謡うところがあります。「あ?、かわいそうに。私たちが都に帰ったらとりなしてやりますから、心を強くして待っていて」と慰めるわけですね。ここをしんみりと、かわいそうという同情の気持ちを込めて謡いましたら、父が「お前らはそんなにしんみり謡うんじゃない。だいたいお前らは僕のこと、俊寛のことなんかそんなに心配していないんだよ。さらっと謡ってくれ。そうするとその後の僕の、“帰洛を待てよとの”の謡が利くから」と言うんです。
お前らが「痛はしの」なんてしんみり謡うと全然引き立たないじゃないか、と怒られたことがあります。ツレはツレらしくサラッと、内心はそんなこと思っていないけれど一応言っておくよ、ぐらいの気持ちで謡う心得ですね。そうするとシテはやりやすい、という事なのですね。
山崎 それはいい話だよ。
?それは腑に落ちる芸談ですね。なるほどなるほど。これは鑑賞のポイントにしていいですね。
山崎 こんな風に菊生さんは工夫しているんだよ。菊生さんは『鬼界島』が好きだったし、事実よかったよね。明生くん、喜多流としては今、『鬼界島』はあまり出ない曲なの?
明生 いいえ、出ています。喜多自主公演でもここ何年かで数回は出ていますし。
何となく能役者の力量が試される曲目ですね。
?それはなぜ?
明生 いくらシカケ・ヒラキだけを上手くやって舞っても、演じる心みたいなものを取得していないと本物ではないのです。能は一見なにも演者がしていないように見えるかもしれませんが、表現力が大事でそこで勝負しなければならない世界です。いろいろな曲や役を経験することもそれを得るための過程なのです。
『鬼界島』は立派に舞をこなすだけでは手も足も出ない曲です。まず謡が上手でないとダメですね。本当に説得力ある謡、涙が出てくるような謡ですが、それが発声できないといけないのです。私の型付には細かなことなどはあまり書いてありません。そういう意味では若年や未熟者には手に負えない曲と言えて、まあ四十代後半ぐらいになって、ようやくそろそろ演ってみたら?と言われる曲なのです。
山崎 このシテはかなり難しいと思うよ。菊生さんは好きだったらしいが、何回やっている? 僕も何回も観ているもの。
明生 そうですね。地方の公演も含めると、正確な数字はちょっと判りませんで、すいません。地方公演では、というよりどこでもそうでしょうが、日本人ならばこの曲は結構受けますね。わかりやすいし、お涙頂戴というの日本人好きなのです。
山崎 情が深い内容だしね。
明生 それから、シテの面は「俊寛」という専用面ですが、父はいつもアラブ人のような彫りの深い面を使用していました。決して品があるとはいえない独特な顔です。
俊寛僧都といえばいくら島流しになっているとはいえ、それなりの位のある人のはずですから、この顔でいいのかなと思うのですが、父はいつもそれを気に入って使用していました。
父は頭に花帽子をかぶるんですよ。位が高い僧ですから普通は沙門帽子なのですが、父は絶対花帽子。我々はこの花帽子に慣れてしまったせいか、これを見ると喜多流の俊寛だなという気がするのですが・・・。あの花帽子はシテにとっては呼吸がしにくい、苦しい被りものなのですが…かならず花帽子。父も年をとってからはきつかったと思うんですけどね。
山崎 花帽子は喜多流だけかな?
明生 ウーン、どうでしょうか。判りません、六平太先生のお好みなのかな?。
山崎 僕は沙門でいいと思うけどねえ。
?花帽子にするのは何か?
明生 知りません。六平太先生がつけていたのを憧れて、かな?
みなさん花帽子、花帽子って仰いますよ。
伝書にないわけですから判りません。ただ喜多流でも沙門でなさる人もいますし…。
山崎 沙門が多いですよ。
明生 その面の話ですが…。彫りが深くてギスギスした感じのお顔をしているんですが、花帽子をかぶるとそれが大分隠れてしまい、独特のお顔になるのです。それが気に入っていたんですね。
?そういう、ご自分がなさった『鬼界島』について、菊生さんのメモとか覚書、型付みたいなものはあるんですか?
明生 ないですよ。父は書きません、ですから私が書くように、反抗精神ですね(笑)。
○創造と継承と
?それにしても、九世・健忘斎の伝書には興味ありますね。それを見せてもらえますか?
我々一般の人間は、そういう能楽の演出ブック、演出帳というのは興味があります。
能楽師の方はこういうものをご覧になって演技を伝えていらっしゃるのかなと思うのですが、一般にはそれがなかなかわからないものですから。これを一度見せて、その中に『鬼界島』が書かれていなかったということを示したいのですが・・・。
山崎 あんまり見せたくないやねえ。
明生 それはサービスしますよ、いいですよ。
山崎 一種の型付だよね。
明生 父はなんでも健忘斎の伝書があるからいいんだといって、ほとんど書き留めたりせずに、それを頼りにしてやっていました。自分の工夫は口で語るばかりで・・・。友枝先生のところにはこの伝書がありませんが、友枝喜久夫先生はご自身がやられたことを細かく書いておられて、それが次の世代の友枝昭世氏がご参考にされているようです。
観世流の銕仙会ならば、華雪先生が几帳面に細かく書き残されたものがバイブルみたいになっていて、それを現代の方々が読まれているようですよ。だから銕仙会の人はその華雪メモが重宝だとお聞きしていますが。
山崎 昔の喜多流は、名人・六平太が何かやろうと思っても、自分のところには型付がないわけです。それで九州から来た友枝に「これやったことあるか」「やりました」「そうか、ではやってみろ」と言ってやらせて、それを見て、全部作ったという話がある。
家元なのに『石橋』をやっていなかったんだな、六平太という人は。ところが素人の弟子で偉い人がたくさんいたから、今度お前の家で『石橋』やらせてあげるからと言って、それを写して、今その型が家元のところに残っているという話だけどね。本当かウソかわからないけれど。それぐらい型付がなかったんだよ。
明生 関東大震災と第二次世界大戦で二回焼けていますから。六平太先生が二回も焼けちゃしょうがないよ、と言っていたという話があります。
喜多流は外様大名が庇護してくれていましたからね。福岡の黒田 熊本の細川、秋田の佐竹、安芸の浅野、そういう遠いところの大名のところに伝書が残っているわけです。
震災の後、落ち着いたころにそういう遠方の弟子に伝書を持ってこさせて写したようですが、それも戦争で焼けてしまったんですね。
?九世の伝書は喜多流で残っているもので古いほうですか。
明生 九世というのは喜多健忘斎といって、喜多流の中興の祖と言われている人です。
江戸時代後期の人ですけどね。このころは観世大夫も宝生大夫も若かったので、健忘斎が能楽界を牛耳っていて、とにかく優秀な方だったということですね。面の目利きでもあったようです。健忘斎以前の伝書もあるにはあるのですが、現代にマッチしないというか、あまりや役に立たないものが多いのです。
健忘斎の伝書は曲目ごとに文章が連なっていて、この時はこうすると書いてありますが、最後に、こういうことをすると大損なりとか、これは未熟者はやらぬことなりとか、この型は吉とか、そんな書き方をしています。健忘斎がどういうことを言おうとしたか、その行間を読むことが大事で、またそれが楽しいのです。
父はもっぱらこの健忘斎の伝書をベースにしていましたが、そこに必ず菊生流を加えるんですね。だから創造と継承ということをよく言っていました。伝統芸能は継承が大事、それは当然ですが、決められたことをそのままやるのではなく、自分で考え、工夫して、創造して行くことが大事ということですね。こういう役者魂が大事なんだということを、父はいつも言っていました。
なにか新しいことを私たちがすると、「今青い鳥をさがしているんだね、そう捜すことが大事、青い鳥が本当は身近な我が家や当流にあるということを、他人が教えてもだめなの、自分で捜して、自分が納得しないとだめなんだよ…」と。
?山崎先生も最後にひとことお願いします。
山崎 僕はこうみえても喜多流を習っていたんだよ。僕の先生は高林吟二さんでね。
で、菊ちゃんと僕は九歳違いだけどね。僕が高校のときに一緒に遊んでいるんだよ。家が近くだったから。有ちゃん、有ちゃんと、よく僕のところに来てくれてね。長いつき合いだったからね。菊ちゃんは「私は次男だから」ということをよく言っていたね。次男だから長男を立てて出過ぎたことはしない、だけど次男としてやるべきことはいろいろあって、ちゃんとやったんだ。喜多流や粟谷の家を支えるということね。次男としての苦労もした、その半面、次男だから割に自由に創造できる面もあったのね。非常に楽しそうに能をやっていたよね。
?山崎先生の方が菊生先生より年上なんですよね。

写真 左 粟谷明生と山崎有一郎 録画後
p>山崎 そう。今年僕は96歳ですよ。もう能楽界で私より年上の人は誰もいなくなったね。
六平太先生や実先生、古い人の能を観ている人がだんだんいなくなってきたね。
飯田橋3丁目にあった舞台なんか知らないでしょ。僕が最初に稽古に行ったのはそこだったんだよ。僕が初めてそこに行ったのは5つか6つの頃のことだよ。11月の終わり、雪がちらちら降っているときだった。その舞台のそばに木田建設事務所というのがあって、それは僕の親父の知り合いの事務所なんだ。僕の弟が生まれるときで、僕と妹がその木田の事務所に預けられることになって、飯田橋で人力車に乗ったんだ。「木田」といったのに、「喜多」と間違えて、喜多の舞台に連れて行かれてしまったんだよ。入ると右側が応接間のようになっていて、六平太先生と奥様がおられてね。僕がお二人にご挨拶をするとどういうわけか入れてもらってね。それで晩になって、八時、九時になる。「坊ちゃん、お腹すいたね」「はい」と言ったら鍋焼きうどんが出てきたんだよ。奥さんたちも困ったと思うよね。布団も敷いてくれてね。翌日になって親父が飛んできて六平太先生にぺこぺこ頭を下げているんだ。何でお辞儀をしているんだろうと僕は思ったけれど、それは喜多と木田の間違いだったんだね。この話、僕はほうぼうで書いているけれどね。六平太先生との最初の出会いですよ。そのあと、稽古に行くようになったんだね。
その時分は喜多さんには伊藤千六、福岡周斎とか、高林吟二とかそうそうたるメンバーがいましたよ。あとで喜多流の幹部になるような人たちもね。そういうことを知っている人はもういなくなっちゃったんじゃないかな。
?そういう話をまた今度いろいろ聞かせてください。今日はありがとうございました。
喜多流の謡について 声と謡 投稿日:2018-06-07
ランチタイムに「今日はちょっと静かなお店でゆったり雰囲気を楽しみながら昼食でも…」などと、私に似合わぬ行動をすると事件は起きる。
「えっ何?」と、びっくりするほど大声で話すお客さんに遭遇した。
隣合わせではないのに、まるですぐ隣に居るかのように話の内容もはっきり聞こえる、その馬鹿デカイ声。
柄にも無くわざわざ静かなお店を選ぶと、この様か…と首をうなだれた。
「仕方がない、運が悪かった」と自分自身に言い聞かせるが、なかなか諦められない私、まだまだ未熟だ。
デカ声の張本人は自分の声がお店でどのような影響を及ぼしているのかなどお構いなし、ひたすら喋りまくる。
その相手は頷いているだけ、屹度うるさいな?と思っているかもしれないが、言わないでいる。私も言えないだろう。
悪いことは続くもので、コーヒーをあまり飲まない私が、珍しくコーヒーを飲もうと、ひょっとマクドナルドに入った。
すると、またまた大きな声が聞こえて来た。
よく通る声で、とても大きく響く声だが、先ほどのオジサンの声とは違う、かわいいものだった。
声を出しているのは女の子、歳の頃は小学生の高学年ぐらいだろうか…。
「この女の子に謡を謡わせたら、きっといいかも…」などと感心してしまった。
しかしその賛美も束の間、その声は止むことを知らず、次第にどんどん大きくなり限界を越えていった。女の子は遂には、お店中を走り回り、声は店内に響き渡った。
女の子の動きは普通でなく、その挙動を見ればだれも注意は出来ない、そんな状況だった。女の子は自分の声をうまく制御出来ないのだろう。脳からの指令がうまく繋がらないようだ。うまく繋がれば太い喉と良い声でよい謡が謡えるのだが‥‥、残念だ。
先ほどのオジサンも、もしかしたら脳からの指令が外れているのかもしれない。
声は制御力というコントロールを失うと雑音になり、人に害を与えるものに変わる。
能の謡も同様、「どのように謡うか?」と脳に尋ねる必要がある。
どのような吟なのか、強吟か和吟か。リズムは小ノリか大ノリか、それとも拍子に合わずなのか、と。
吟とリズムを確認して、声量と声の高さ、謡のスピード、陰か陽か? 息づかいはどのように配分するか? など、いろいろなことを考え、脳が身体に指令し、鼻から空気を吸い込み腹に溜め、徐々に喉を通して口から空気を出して声となる。
能は舞歌二曲から成るが、歌の占める割合は舞よりはるかに大きい。
だから、謡声は大事、考え抜かれた洗練されたものでなければいけないと私は思う。
どのように声を出したら、舞台から客席に伝わるか、観客に心地よく聞こえるか。
心地よいという言葉は適切でないかもしれないが、能に心地よく浸ってもらうための謡だ。
シテ方能楽師というプロならば、そのスキルは獲得しなければいけない。
しかし、若手(喜多流)の謡を聞いているとどうも謡を蔑ろにしているように思える。
それは間違いである。
だれも間違いであることは判っているのかもしれないが、しかし本人も指導者もそれには触れないようにしているのが現状だ。
私は能楽師(喜多流)も正規にボイストレーニングをした方がよいと考えている。
自分がしていないのにおこがましいが、しなくて苦労したから、これからの人にはもっと効率よく正しく習ってほしいと思う。
私は流儀の若手能楽師の何人かに先生を紹介するから、と呼びかけたが、反応は寂しいものだった。
内弟子の佐藤陽と息子・尚生の二人が習いたいと申し出たので、私は先生を紹介し、やるか、やらないかは本人達に委せた。現在もトレーニングを続けているところを見ると彼らはトレーニングの必要性を認めているのだろう。トレーニングしたから直ぐに見違えるようによい声になるということにはならない、とトレーナーからも言われているが、昔に比べて、声に張りが出てきたことは確かで、トレーニングしない人より数段進歩していると思うのだが、私の欲目だろうか。
シテ方の能役者は、まず謡のレベルを上げることが第一だと思う。
これには時間がかかるが、時間をかければかけるほど熟成した謡が生まれると思いたい。
リアリティがあり説得力もあって、心地よく聞こえる、そんな謡が私の理想だ。
今、私を含めて喜多流の能楽師は能という様式美のプロテクターに頼り過ぎているきらいがあるのではないだろうか。
流儀の若手も中年能楽師も一度プロテクターを外して、謡というシンプルな、実はとても複雑なものを再考する時期が来ているのではないかと思う。
それが私の思う本物の能楽師に近づく、時間はかかるが近道のように思えてならない。
もっともっと謡に、声というものに意識を持たなければいけないと、あの昼下がり、オジサンと女の子が大声で私に注意してくれたのかもしれない
間遠になりて投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
間遠になりて
粟谷新太郎
四月の中頃、院長先生より「粟谷さん人間国宝おめでとう」と声をかけられ、これはえらいことになったと当惑し、よくよく聞いてみると弟菊生の人間国宝認定の報と解り、あの世にいる父、益二郎に電話をしてよろこびを分かちあいたい気分になりました。この慶事は我が家の誉れであり、これまでの演能活動の積み重ねのたまものと心得、なお一層の前進を願っております。三月には認定記念の粟谷能の会が、東京、大阪、福岡にて催される由、大変心強く思います。
「阿吽」No.2我流『年来稽古条々』でも取り上げておりましたが、父益二郎の最後の舞台『烏頭』についてお話ししたいと思います。囃子科協議会が駒込の染井能楽堂で催されていた時(この染井能楽堂の舞台は今年、横浜能楽堂として復原された由)、ぜひ父に『烏頭』をということで、演ることになってんです。子方には能夫が出ていました。私は地頭をしていましてね、前シテが橋掛へ出て来た時、実は、ゾーッとしたんですよ。いかにも淋しげに現れてきたんです。あとから思えば、死に直面していたのだと思いますね。ワキに片袖を渡し、立分かれて行くところは、父の生涯の舞台の中でも絶品の一つじゃないでしょうか。後シテで舞台に入り、常座で「陸奥の外の浜なる呼子鳥」と、謡うか謡わないうちに、前に膝をつくように倒れたんです。最後の力を引き絞って運んで来、精一杯に謡ったんでしょうね。それで、地に座っていた栄夫君(観世?当時後藤)が直ぐ立ってあとを舞いました。栄夫君は妙な因縁があるんですよ。前年に岡山で倒れたときも彼が後を舞いました。『黒塚』だったんですが、後のイノリで倒れましてね。
一体に、父は何をやっても情感をもってすることがありませんでした。淡々と演るんですよ。まあ、昔の人は理屈で考えて舞うわけじゃなく、教わったとおり、からだで覚えているとおりに舞った結果として、たまたまいろんな事が表現されているんでしょう。現在では一曲を徹底して稽古をするようなことも難しくなっているようですが。謡にしましても、六平太の名地頭として活躍し、『粟谷の謡』と云われるようになりました。此の謡をみんなで継承して行かなくてはならないと思っています。『謡』がちゃんと謡えないと仕事になりませんから。
私は「烏頭」を被いたのは三十歳ぐらいの頃でしたが、何しろこの曲は先生(十四世六平太)の十八番極め付けだったもんですから、とても私には演る気がしませんでしたね。そこへもって来て父のこともありましたからね、よけい演るチャンスがなかったんです。「烏頭」というのは、本当にいい能です。殊に後の一人称で、いろいろに演り分けるところに妙味があります。先生は、呟くように謡えといわれました。無論、後のカケリ前後が型所には違いありませんが、前段の、あの短時間、動きの少ない型を十分気をこめて演ずる舞台は難しいものです。色々な意味もありますが、私には襟を正すような、コワイ能だと思います。
父は四人の息子を皆能楽師として育て、面、装束を集め、地盤を築くという大仕事をしてくれました、私も面蒐集を心掛けてまいりました。良い面で佳い能を舞いたいという思いからです。昨日も、古道具屋から能面が売りに出た夢を見ました。これが正夢ならばと能夫に話をしたところです。皆々様の前より失礼いたして久しくなりましたが、毎日、能のことを思い、見はてぬ夢の中で過ごしております。いま暫くの雲隠れを、お許し下さいませ。
(聞書・能夫)
『芭蕉』と向かいあって投稿日:2018-06-07
『芭蕉』と向かいあって
粟谷能夫
 能役者として、これまで辿ってきた道筋、歴史といったもので勝負するしかない、そうでなければ全く歯が立たない曲があることを『芭蕉』(平成十五年三月二日、粟谷能の会)という大曲に取り組む中でつくづくと思い知ることが出来ました。前号「阿吽」巻頭の菊生叔父の文章の中で『芭蕉』の地頭として舞台を支えるという、熱い応援を受けて私自身大きな一歩を踏み出すことが出来ました。
能役者として、これまで辿ってきた道筋、歴史といったもので勝負するしかない、そうでなければ全く歯が立たない曲があることを『芭蕉』(平成十五年三月二日、粟谷能の会)という大曲に取り組む中でつくづくと思い知ることが出来ました。前号「阿吽」巻頭の菊生叔父の文章の中で『芭蕉』の地頭として舞台を支えるという、熱い応援を受けて私自身大きな一歩を踏み出すことが出来ました。
私の人生の中で『芭蕉』の記憶を辿ってみると、まず父の舞台が蘇ります。言葉では表現できない能の極致のようなものでした。外見は豪放磊落にみえて、実は繊細でこわれやすい父の内面が、『芭蕉』の曲をとおして佳く出ていたと思います。
次に、観世寿夫さんが地頭をされていた、観世静夫さんの舞台です。それは思いの外に情緒的な舞台でした。『芭蕉』は、どちらかといえば無機的な曲と思っていた私には、新鮮な驚きであり、初めはよく理解できませんでした。しかし、静夫さんの能は寿夫さんの抽象度の高い謡と対峙しながらも良い味を出している。その人の人間性や体質、思いを出して、その人の能を創り上げていいのだ、能というものは、それほどまでに幅広く懐が深いのだと、その時に強く感じさせられました。
そして次に思い出されるのは、寿夫さんの「芭蕉と禅竹」という文章です。
「能では、多くのめんにおいて、表面的に人間的な表現を否定してしまって、しかもそうした抑圧をつきぬけて訴えかける、より深い時点において人間を表現するという技法が用いられていますが、この曲なども、一見して非人間的な主題と見られやすいが、その奥底には人間が強く描き出されていると思うのです。しかし一歩まちがうとまったく劇でなくなってしまう、その辺のところに、この曲のむずかしさがあるのではないでしょうか。私ははじめにあげた『安宅』や『船弁慶』と比較して、この『芭蕉』や『定家』といった曲のほうが、より本質的な意味で演劇であると考えると同時に、現代に能がつながり得る価値を持っていると思うのです。」
今回『芭蕉』という大曲に取り組むうえで、この文章から大きな勇気を頂きました。夢幻能の極致ともいえるこの能に何を巧むことができるだろうか。能役者として、これまで辿ってきた道すじ、様々な出会いを糧に、自分自身の思いと人間性で、自らの自叙伝を書くつもりで創り上げていくものだと思うのです。
写真 芭蕉 (シテ粟谷能夫 平成15年 粟谷能の会)
父や祖父の仕事に連なって投稿日:2018-06-07
父や祖父の仕事に連なって
粟谷能夫
 平成十七年は父新太郎の七回忌の年にあたり、追善の能を三月と十月に東京、五月に福岡にて催しました。皆様のお力添えをいただき無事済ますことができましたことを感謝いたしております。
平成十七年は父新太郎の七回忌の年にあたり、追善の能を三月と十月に東京、五月に福岡にて催しました。皆様のお力添えをいただき無事済ますことができましたことを感謝いたしております。
また秋には七回忌追善の粟谷会大会を催しましたところ、各地より父の薫陶を受けた方々が大勢ご参加くださいました。父への思いのうえに、地域を代表しての出演とあって熱気あふれる会にしていただきました。出演者の舞台での精華を見ていますと父のした仕事の偉大さに感心するばかりで、自分の未熟さを痛感させられました。全力で弟子と対峙している父の姿が浮かび上がってくる思いがしました。
そして一方で、父は面・装束を集めるという仕事もしてくれました。この二つの仕事のおかげで、今、私たちは能に集中することが出来るのだと感謝しております。
父は能を舞うのが趣味のような人でしたが、病気をするまではお酒を飲むことを楽しみとしておりました。自宅稽古が済むとよく外出し二時間ほどで戻って来るのです。母に聞くと新宿のバーへ行くのだといいます。当時の私ではちょっと理解が出来ませんでしたが、きっと美しい人がいたのだなーと思います。父のストレス解消術だったのです。
晩年は能関係の骨董品、主に掛け軸、書画、彫り物、陶器などを求めて、中野の舞台に飾って楽しんでおりました。
父の収集したものの中で家宝となっているものがあります。それは喜多流九代目喜多健忘斎古能筆「月宮殿」の初同の一句を掛け軸としたものです。地方の旧家よりいただいたものです。古能公は多くの伝書を残し喜多流にとっては中興の祖であります。私も古能公の伝書を根拠に演能をいたしておりますが、伝書を読み込んでいくといろいろ発想や直感をもらい、目の前が急に明るくなるようなことがあります。父も掛け軸を見るたびに、気持ちを新たにしていたことでしょう。

本年(平成十八年)は祖父益二郎の五十回忌にあたります。祖父は十二歳のとき、広島より上京し十四世喜多六平太先生の内弟子となりました。粟谷の能の始まりです。独立後は東京に居を構え、各地へ稽古に出て多くの地盤を残してくれました。面装束の収集は自前の面装束にて能が舞いたいという強い意志からでした。父の話によると、不都合な装束にて能を舞わなくてはいけなかった無念さがきっかけになったようです。もちろん四人の息子たちのためでもあったのです。私は子方の謡の稽古を祖父から受けていたのですが、具体的な記憶はあまり残っていません。ただし祖父が亡くなった時(『烏頭』の演能中、私は子方でした)や申し合わせの日のことは鮮明に覚えています。
私自身も祖父や父の仕事にならって、演能や稽古はもちろんのこと、面装束の収集も続けております。収集以上に修理・修繕・維持・管理も大事と思い心がけております。
本年は祖父の五十回忌追善の会を計画しております。菊生叔父を先頭に充実した一年を送りたいと願っております。
写真 「実盛」粟谷能夫 撮影 東條睦
掛軸 撮影 粟谷明生
我流『年来稽古条々』(26)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(26)
?研究公演以降その四?
『蝉丸』で見直す力を
粟谷 能夫
粟谷 明生
明生 第四回・研究公演で取り上げた『蝉丸』について話していきましょう。第四回の公演は平成五年十一月二十七日でした。第三回の『求塚』が五月ですから、その年は研究公演を年二回やりましたね。
能夫 すごく頑張っていたよね。
明生 『蝉丸』は二人で同じ曲に挑もうということでした。
能夫 共有しようということだね。
明生 一曲の場合、片方がシテで片方が地謡ということになると、地謡は舞台に出ないことになるから、両方が一緒に出られるものにしたいということで『蝉丸』が選ばれました。シテの逆髪を能夫さんが勤め、私がツレの蝉丸を勤めることにしましたね。ツレ蝉丸は曲名に名前があがるほど、大切な役で重く扱われています。だからシテもツレもほとんど同等の意識で演じることができますから。
能夫 僕が年上だからシテをやったというぐらいで、どちらがシテになってもいいぐらいの曲ですよ。シテとツレがほとんど同等で拮抗してよい舞台を創らなければならない曲なんだ。だから明生君も燃えていたよね。
明生 そうですね。大事に勤めたいという気持ちでした。
能夫 僕も『蝉丸』のシテは初めてだったので、同じように大事に勤めたいという気持ちがあったよね。過去のものを観て来て、自分がするときにはこういうふうにしたいということがいろいろあったから。
明生 それで、変えたことがありましたね。
能夫 今までは「花の都を立ち出て・・・」という道行の段が終わると、シテは大小前に座ってしまい、そこでツレの「第一第二の絃は・・・」という謡を聞くわけ。弟の蝉丸のすぐそばにいて声を聞いているのに、わざわざ立ち上がって遠くの常座に行き、弟との問答が始まる。それでは、姉と弟の再会が舞台進行上、おかしいでしょう。
明生 健忘斎の伝書にはどう書いてあるのですか。
能夫 その通りに書いてある。だから父も菊生叔父もみんなそのように演ってきたんだ。だけど観世流は、橋掛りにいて蝉丸の声を聞くという演出なんだよ。「花の都」の段を橋掛りで聞いて、それでだんだん距離が詰まってきて、弟の蝉丸との再会になる、このほうが自然でしょ。それで、研究公演では僕は「花の都・・・」から蝉丸が「世の中はとにもかくにも・・・」を謡い始めるまで、橋掛りの一の松に佇むことにしたんだ。
明生 そこは何とか変えられてよかったですね。でも、能夫さんはもっと変えたいことがあった。全部で四つありました。一つは今のこと、シテが大小前に座るのではなく橋掛りにいることですね。二つめは、クセの上羽の謡「たまたま言訪ふものとては」を喜多流の謡本ではシテが謡うことになっていますが、意味合いからツレが謡う方がよいということ。三つ目は蝉丸が藁屋を出るタイミング、これを早めにしたいと言われましたね。
能夫 だって再会したのだからね。藁屋の中に入りっぱなしというのは不自然でしょう。理不尽なことがいっぱいあるよね。
明生 それと四番目はツレが琵琶を弾く場面で、型として中啓を使って、琵琶を弾く風情を見せる、ということもやりたかった。いろいろやりたいことはありましたが、能夫さんは研究公演ではこの中の一つだねといいました。
能夫 そうね。『蝉丸』は初めて挑む曲でもあったし、研究公演だからといっても、どうしても変えたいというところ一つだけにして、その後につなげていこうという思いだったね。

明生 だから、研究公演では思っていることの四分の一しかできなかったわけです。でも、伝書や謡本に書かれていることや、流儀の先輩たちが演られてきたことでも、ここは理不尽だということがあれば見直していかなければ、という、そういう志しがスタートしたのだと思います。
能夫 研究公演の『蝉丸』は、見直す力が必要ということを意識し始め、それを実行に移した初めての曲であり、場であったと言っていいと思うね。
明生 その後、確か彦根での能で、友枝昭世氏がシテで能夫さんがツレ、という機会がありましたね。
能夫 そこでもっと改革しようとしたんだ。研究公演でできなかったことや、その他諸々とね…。
明生 友枝氏との相談も進んでいたのですが、友枝さんが病気になられ、出来なくなってしまったのですね。
能夫 それで急遽、菊生叔父がシテを代役することになってしまって…。菊生叔父に根本的に改革しましょう、なんて言えないし、またそのような時間もなかったので、あのときは今まで通りでやることになった。菊生叔父には言えないよな。それはそれでいいのだよ。(笑)
明生 そこでは近代型にしようとした試みはできなかった、ということですね。それから時が経ち、平成十九年に愛知県豊田市の豊田能楽堂の三月公演で能夫さんと二人で『蝉丸』という企画のお話がありまして…。能夫さんがシテで私がツレで。そのときは今度こそと、研究公演で考えていた四つのことを全部やりましたね。ツレが藁屋から出るところも序のところにして、いろいろと・・・。
能夫 ツレが藁屋から出て、お互いが身近にいるという状況を創らないとね…。再会なんだからね。
明生 研究公演から十四年もの月日が経ってしまいましたね。でもこの間に様々な試みをしてきて、よかったなと思いますよ。いろいろ苦言を呈する方もおられますが、あのときはスムーズにクレームもなく・・・。まあ、言う人をお
呼びしていなかったこともありますが…。(笑)
能夫 普通は流儀のやり方を変えるというのは大変な抵抗があるんだよ。観世寿夫さん、あれほどの人だって大変だったんだから。昭和三十六年に寿夫さんが『昭君』で新しい試みをしようとしたとき。先代の銕之亟さんがシテで、寿夫さんが地頭だった。ところが雅雪さん(寿夫さんの父)から待った!、が入ってできなかった。寿夫さんは涙を飲んで諦めたという話がある。これはもう伝説になっているぐらい有名な話だよ。それぐらい流儀の型や決まりごとを変えるのは大変なことなんだよ。
明生 それは私たちが父親にダメ出しされるのと、同じですね。
能夫 その改革ができたのが、昭和四十八年だよ。
明生 十二年後か。やっぱり改革には十年以上の歳月がかかるということなのですね。
能夫 それでも最初にどこかでカッと爪を立てるとか、そうしないと物事は変わらないということだよね。
明生 そう、どこかで爪を立てないとですね。能役者は、演出的にも演劇的にも考えて、型付を検討し、不備なところがあれば改善しようとするのが健全ですよ。ただ目先だけを変えればいいというのではないと思いますが、そういう見直す努力をする、ということが大事だと思います。
現在、当たり前にやっていることも、歴史的に見れば、高々数十年ぐらいのあいだでのこと、そこで固まってきたことかもしれないのです。だからもっと昔のことを調べていくと違うやり方をしているということもあります。
能夫 だから、親や先輩がやっていることを金科玉条のようにして真似するだけではない、見直す力が必要ということですよ。
明生 以前に能夫さんが話してくれたことがありましたね。だいぶ昔のことですが、友枝さんが新工夫をされたときに、ある人が「あれは喜多流にあるのか?」と尋ねられたら、友枝さんは「喜多流にはないかもしれないが、能にはある」と答えたと・・・。
能夫 格好いいじゃない。能にはある! これからはもっと能という大きな枠の中でやっていこうよ。
明生 そんなこともあって友枝さんは私たちがこういうふうに変えてみたいと相談すると受け止めてくれますよね
能夫 友枝さんは見直すこと、新しいこと、改革すること、そういうことを許容する懐の広さがあるよね。こうやりたいと僕らがいうと、それはいいけれど、こういう問題があるよと、細かな指摘もしてくれたり、そういう意図ならば全面的にやってみろ、と言ってくれたりね。そして僕らがやったことを見て、どうだったということも言ってくれる。ご自身も声高には言わないけれど、ちゃんと改革というか冒険をやっておられるよね。先日の『江口』だって、普通はワキのサシコエが終わるときに、シテが呼びかけるのを、、そこにアシライ笛を入れて、心象風景を共有しているところに、遊女・江口(シテ)がふっと現れるようにされました。新工夫ですよ。
明生 私も、友枝師に『江口』の稽古を受けたとき、「のう、のう」とただ呼びかけで出るのではなく、ワキが西行の歌を詠じはじめると、シテが三の松あたりにすっと現れ、歌をそっと聞いている、その風情を観客に見せるというのは、どうですか、と申し上げたら、それいいじゃない、と言って下さいまして。『半蔀』の「立花」のときも、川瀬敏郎さのお花が舞台の中央前方に出ているわけですから、「いつもの位置取りや型をすこし替えていいですか?」とお聞きすると、「今日はお花が半分主役だからね。そうした方がいいよ」というように心に響く、やる気が出る言葉で返して下さいますから。

能夫 そういうことだよね。『半蔀』といえば、寿夫先生の印象に残る言葉があるよ。潗の会で浅井(文義)君が稽古しているときのこと。先生が「ワキが夕顔の花をイメージしたときに、シテはふっとワキのイメージの中に入っていく」そう言われたんだ。僕がワキが謡っているときになぜシテがアシライのように出てくるのか?と質問したときの答えだった。ワキの作っている世界にシテが入っていくということで、ただお囃子の手組だけの対応では絶対できないということなんだ。
明生 私たちはただアシライ笛に合わせて、コイ合いくつ、としか考えていませんでしたからね。ワキがどのような対応で動いているかなどと、正直以前はあまり考えていませんでしたよ。
能夫 そうでしょう。舞台というのは役者と役者のかかわりで創っていくものでしょ。アシライ笛だってそのためにあるんだよね。アシライがあるからそれに合わせて出るのではなく、むしろ舞台全体を創るためにアシライがある。考え方が逆転しているわけ。そういうことを、あの時代、僕は二十代後半だったから全然わからなかったけれど。
でもその話を聞いたことが僕にとっては画期的なことだったね。
明生 そういういい話を次の世代へどうつなげるかですね。私自身もそう見ていないし、今、寿夫さんの素晴らしさを知る人が少なくなっていますからね。
能夫 それからね、『葛城』についても思い出があるよ。寿夫先生に今度は何をするのと聞かれて、『葛城』と答えたら、『葛城』は面白いよ、普通の世界じゃない、神様の世界を描いているあたりが面白い、音曲的にもこんなに面白いものはないというようなことを言われたんだ。そのころ僕は、『葛城』という曲に対し明確なイメージをもてなくて迷っていたが、先生の一言により道がばっとひらけて、やる気がわいてきましたよ。
明生 『三輪』とか『葛城』は不思議な能ですよね。人間的でもあり神的でもあり、両方備えている…。
能夫 それを寿夫さんは指摘されたんだな。そういう意識で能を創っているんだ。寿夫さんの能の成り立ち、美しさ、それはそういうところの意識の違いにあるんだと感じた。「じゃあ、頑張ってやります」なんて僕も言ってね。ずいぶん励まされました。この二つのことは、寿夫さんと直接言葉を交わして影響を受けたこと、忘れられないね。ああいうすごい方と命を共にしたというか、同じ時間を呼吸できたということは嬉しいことですよ。
明生 能夫さんは寿夫さんのお能の見方に影響を受けて、自分のやっている能を見直そうと・・・。もちろん単純に右回りしていたのを左回りにしてみるかということでなく、この能にこれが必然だということをよく考えてですね。
能夫 右回りのことで一つ思い出したよ。中入りは普通、右回りして常座で正面を向いて「失せにけり」とかになるでしょ。右回りというのは、正面から中正面、脇正面まで、全部の観客の視線に演者の身をさらすわけですよ。そこになにかキュッと凝縮したものが必要だよね。それを静夫先生(先代・観世銕之亟先生)は「凝固」とか「凝結」という言葉で説明された。凝固だと石になってしまうから、違うかな。「凝結」だね。「失せにけり」だから生身の人間はそこにはいない感じで凝結している、でも内燃機関は静かに燃えているみたいな・・・ね。
明生 中入り前の右回りも、そう言われると意識が違ってきますね。
能夫 そうでしょ。そう考えると、お能って本当に面白い。こんなふうに何気なくやっていることも見直す力が絶対必要だということですよ。流儀とかでなくて、曲に対して、能に対してどうなんだということをやっていかないとね。
明生 お能って本当に面白い、と素直に理解出来るのは、もしかすると演じている者だけかな…なんて、こんな事をいうと観客の方々に叱られるかな。とにかく、友枝さんがおっしゃった、「流儀にはなくても能にある!」ですよね。能を生かすには?ということを追求していかなければいけませんね。
というわけで、研究公演の『蝉丸』は我々が能を見直す最初の曲になったということですね。以来、いろいろ見直しをやってきました。そして今度の研究公演、平成二十二年十二月に『檜垣』を計画したのも、その心意気ですよね。シテを友枝昭世氏にお願いして、我々が地謡を謡います。是非期待していただきたいと思います。
(つづく)
我流『年来稽古条々』( 30 )?研究公演以降・その八?『景清』 『砧』について投稿日:2018-06-07
植林投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
植林
粟谷菊生
ふり返ってみると、どこの社中にも、必ず一人や二人は能狂い、謡気ちがいといった能好きの人がいるものだ。
その人たちは必ずといっていいほど、子供のころとか、学生時代に、仕舞や謡の稽古をした人たちで、それが年をとった今日に続いてきていることが多い。
私の社中でも、今は故人になられたけれど、毎年、能を舞われた、日立の副社長のあと、動燃の理事長であられた清成廸さんにしても、学生時代に清成さんに将来を托して、骨身を惜しまず謡を教えてくれた人があってこそのおかげで、それが最後に実ったところで、私の会で能を二十四番も舞っていただき、私は大いに恩恵を蒙ったものであった。
であるから、私も若い人たちに植林をと思って、将来の喜多流発展のために、早くから東大喜多会、阪大喜多会を作って教えてきたが、阪大は毎年、学生の自演能が催されて、それが二十五回を終え、この十二月で二十六回になる。
ある人に「菊ちゃんはいつまで学生と遊んでいるのだ」といわれたけど、昔、観世寿夫さんが「炎天の砂浜に水を撒けば、あっという間に吸い込んでしまうような、覚えのいい人に教えたい」といわれたそうだが、水を撒いても、ほうぼうに水たまりができたり、中にはボウフラがわくしまつ。吸い込みの早い、覚えのいい学生たちと共に、ある時間を過ごし、夏は合宿に参加して、学生の見つけてきた宿に泊まり、彼らと同じ物を食べて、共に過ごす何日間は、今では私の回春剤となり、若やぎの秘訣となっているのがうれしい。
学生たちも既に立派な医者になっているが、昔、その一人の福田君が「先生、白内障になったら手術してあげますよ」といい、泌尿器科の寺川君が「小便の出が悪くなったら通してあげます」とか、あるいは福本君が「先生、ぼけたら、ぼくの家の病院でめんどうみますよ」とかいってくれたけれど、ぼくは七十四歳の今日でも、まだ三人のお世話にならずに過ごせているのを幸せと思い、自慢にも思っている。
若い頃から植林の仕事に励み、逆に、若い人たちの情熱をいただいて、今日の私があることを、たいへんうれしいと思う。
我流『年来稽古条々』(15)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(15)
青年期・その九
『道成寺』本番、そして
粟谷 能夫
粟谷 明生
明生 『道成寺』について、もう一回、本番以降のことを話し合ってみたいと思います。まず装束と面ですが、近年通常は紅無鶴菱模様唐織で、面は「増女」ですね。
能夫 僕はそう。実先生の鶴菱唐織を拝借して、面は本来「曲見」だけれど、披きでは使いこなせないから、どうしても「増女」になるね。「増女」だと少しアンバランスになる気がするけれど・・・。金春流は「若曲見」とか「白曲見」を使っているね。僕は「泣増(なきぞう)」、これは父が僕の披きのために買ってくれたものなんだ。
明生 私も「増女」でしたが、装束は紅入蝶柄模様の唐織でした。父がこれを着ろと言ったのが印象に残っていますが、これは何か意味があったのですか。
能夫 深い意味はないと思うよ。菊生叔父が実先生に「鶴菱でなければいけないでしょうか」とお伺いを立てていたのを覚えている。実先生が「そんなことはないよ」と言ってくださったから、家にある少ない選択肢の中から蝶模様が選ばれたというわけだよ。
明生 そうですか、披きで紅入の着用は珍しいですね。その後は皆、鶴菱模様ですから。
能夫 そう決めてかかるのも変だと思うよ。本当だったらシテが自分の主張で決めるべきもので、いろいろな選択肢があった方がいいと思うけれど。そういうこともあって菊生叔父は実先生に聞いたんじゃないかな。
明生 装束もそうですが、演技においても、今みたいに自分でどの様にしようなどとは考えませんでしたね。
能夫 まあ考えないこともないけれど、自分でこう解釈してこうしたいなどということが許される状況ではなかったでしょ。実先生もいらして、もうみんな先輩たちがいるから、勝手なことはできないよ。
明生 そうですね。ただ粗相なく、つつがなくやろうということでした。『道成寺』というのはすごく資金がかかります。それを親が負担し、一門の人たちが支えてやらせてくれるわけです。だから披きではすごく親や一門の人たちの応援に感謝しましたよ。舞台に出ていく前に、新太郎伯父に「しっかりやれ」とか「ちゃんと戻ってこい」と言われるわけです。それが一番心に残っています。だから芸術性がどうとか言う前に、粗相しないで、親や一門の人たちに恥をかかせないで、とにかく無事にということがありますよね。
能夫 まあ、つつがなくだよね。
明生 そう。粗相したら恥ですよ。父や伯父たちは遠方からもお客様を呼んでいるわけでしょ。それで失敗でした、不勉強でしたではすまない。
能夫 本当にそう。まず基本は失敗なくきちんとやること。それを通過することで次のステップに行くということだよね。自分の価値を自分で見極め、その後の点数を上げていくのは自分自身だということを自覚する曲だと思うね。
でも、つつがなくと言ったって、もちろん『道成寺』自体はそんなにおとなしい曲ではないからね。乱拍子があって、初めは鎮静していたものが、急の舞で爆発して鐘入りする。その辺の心の変化というか、対応の仕方というのは今までにないものだから。尋常なエネルギーではない、それは演じると強く感じるね。
明生 理屈だけでは絶対にできない。
能夫 そうなんだよ。乱拍子は地謡でも見ているし、いろいろなところで見ていてイメージはできている。ところが見るのとやるのとでは大違い、そういうことを発見するね。見ているときは割に単純な作業だと思うけれど、実際にやってみると、もう勘弁してよといいたくなるほどつらいし、バランスがうまくとれなかったりする。鼓との戦い、せめぎ合いも感じた。そして急激に爆発するというのが難しいね。徐々にスピードアップするならいいけど、急激に爆発するからね。そういう意味でも『道成寺』というのはすごくおもしろい題材だと思うよ。
明生 そして何といっても興奮するのが鐘入りですね。
能夫 鐘入りも流儀によっていろいろなやり方があるでしょ。以前、NHKで各流儀の違いをやったことがあるね。喜多流は目付けから鐘の下に行き、縁に片手をかけて飛び込む、観世流は鐘の下で正面を向いて、両手で縁をさわって飛び上がる感じだね。
明生 動きとしては角で鐘に向かい、左廻りしながら烏帽子を白洲に払い落とすように取って鐘を見る。私、ここまでは冷静でいられたのですが、その後はあまりはっきり覚えていません。ハッと気がつくと、鐘の中に落ちていた。
能夫 何度も稽古しているから、体は自然と動いているけれど、僕もあまり記憶がないね。終わって扇を見みると壊れていたんだ。びっくりしたね。とにかく鐘入りは孤独な戦い。実先生は、片膝ついて落ちるとおっしゃていたけれど、そうはいかないね。
明生 実際はそんなお行儀よいものではなくて、仰向けにされた蛙のような状態ですからね。そしてハッと気がついて思い出すわけです。安心している場合じゃないぞ。鐘の中での手順を手際よくやらなければと。足でも手でもいいから鐘を回せと言われたことを思い出すのです。
能夫 うちの流儀は、落とした後に再度、鐘を少し上げ、鐘を正面に向ける作業をさせるね。シテが中で失神していませんよ、ちゃんと生きていますよという証し、合図にもなる。それから僕は、習之次第というもののおもしろさも感じたね。ちょっと誘ってくるような出でしょう。
明生 幕離れでノリがグンと進んできますね。その後少し沈滞し落ち着く出で・・・。
能夫 出るときに、執心とか思いが含有されていなければいけない、その思いが幕離れの具合に現れていると思う。
明生 幕から出た後に大小鼓がコイ合、三地を打つという習之次第は、流儀では『三輪、神遊』や『卒都婆小町』『檜垣』にありますが、普通は『道成寺』で初めて体験します。幕上げの後、通常は大小鼓はノル打ち方を続けますが、習之次第では一旦沈まる特別な手組み、あの落ち着く感じが初経験になりますね。
能夫 そうなんだ。『道成寺』というのはすべてが新しく、すべてが楽しくてしようがないね。『道成寺』に携わっている時間はみんなそうだと思うけれど。いい時間だったんだな、『道成寺』に向かっているころというのは。いろいろなことを経験して、一人の人間ができ上がっていくような感じがある。稽古に向かう態度、プレッシャーに対して真剣に取り組む気構え、他の曲に向かうときとは全く違うものが確かにあったと思う・・・。
終わったときは本当にくたびれたと感じた。しゃがみ込んでしまったよ。その夜の宴席では何も食べられなかった。あんなに消耗したことはなかったね。初めての経験でした。宴会のときにはみなさんにありがとうと言ったけど、僕はまるで抜け殻みたいだった・・・。
明生 終演後、私のときも大宴会でした。二次会もあって、他流の友人も来てくれて。無事終わったという解放感にひたりました。だからパーと飲む。
能夫 パーとね。
明生 その後はしばらく放心状態でした。二、三日して、父に友枝さんにお世話になったのだからご挨拶をしなさいと言われて、昭世さんをお招きして、能夫さんと私の三人の席を設けましたね。話題はあそこがまずかった、こうしたらよかったという反省よりも、無事に勤めて良かったということでした。これからが大事だとも言われました。『道成寺』に向けたと同じぐらいのエネルギーで、これからも励めよの言葉が印象に残っています。
能夫 『道成寺』というのは結果が出るわけじゃなくて、通過点だということだよ。それからどう枝分かれするかは、それぞれであって、『道成寺』で何をつかむか、まるでリトマス試験紙のように試されるんだ。ある時期、これだけのことを逃げ隠れなくやったという実感はある。実際、一番稽古するのが『道成寺』だからね。これは大事なことですよ。
明生 若さの限界に挑んだということですね。挑んだ分だけ手ごたえがあったと、後で感じられます。だから日々が大切だと。
能夫 いつのときも地道にやっておかないといけないということだね。
明生 『道成寺』が終わってから、能夫さんに「『道成寺』と同じくらい稽古するのが『松風』だからね」って言われました。それで『松風』をやるとき、同じくらいの時間をかけて、それだけのことがある曲だと実感しました。
能夫 自分で演じてみてそう思ったからね。『道成寺』の体験はそれらの曲への布石といえるだろうね。
(つづく)
粟谷菊生を偲ぶ その一投稿日:2018-06-07
鼎談
粟谷菊生を偲ぶ その一
粟谷 能夫
粟谷 明生
笠井 賢一
 明生 今号は粟谷菊生の追悼号ということですから、「我流年来稽古条々」は次号にかけて、阿吽発起人の笠井さんにも加わっていただき、菊生を偲ぶ鼎談義としたいと思います。
明生 今号は粟谷菊生の追悼号ということですから、「我流年来稽古条々」は次号にかけて、阿吽発起人の笠井さんにも加わっていただき、菊生を偲ぶ鼎談義としたいと思います。
笠井 菊生さんという方は、年齢を重ねるほどに独自の持ち味を発揮されましたね。この阿吽の最後の文章「写真集と弔辞」(22号)も粋じゃないですか。写真集に寄せられた各氏の文章を読んで感激し、これをそのまま弔辞にしてほしいと思った、生きているうちに手向けの言葉をいただけるなんて、何と幸せかという語り口ね。飄逸というか、何ともいえないユーモアがあって。自分で追悼のことまで言ってね。
能夫 すべて自分でやって、さいならって逝った感じ。
笠井 まさにそう。功なり名遂げたというか・・・。
能夫 倒れる二日前に、NHKで『頼政』の番囃子を元気で録音したんだからね。
明生 録音の経緯は、NHKの方から、菊生先生の謡を記録として録音しておきたいという電話がありまして。
笠井 最初は放送予定なしだったの。
明生 そうです。私が「故人を偲ぶ」といういざというとき用のものでしょうとちょっとふざけて言いましたら電話口で笑っていらした。曲や配役はすべてお任せします、一番お気に入りで、ということでしたので父に相談しました。父は『頼政』だなと即答して、ワキは閑ちゃん(宝生閑氏)、アイもあるから太良ちゃん(野村萬氏)、笛は仙ちゃん(一噌仙幸氏)、とどんどん配役を決めていきました。父と親しかった方が顔をそろえて下さり無事録音は終了しました。その二日後に倒れて、一週間ほどで亡くなるのです。ですから。放送は本当に「故人を偲ぶ」になってしまいました。
能夫 だから全部段取りして逝ったようなものだね。写真集を出すのもそうでしょ。最初、僕たちが勧めたときは嫌だといっていたんだよね。
明生 父は写真集などで俺の能のすべてが表現出来るわけないだろう、と記録として残してほしい私たちの思いには少し抵抗していました。パッと、花火のようにそのとき輝けばいいの、という・・・、まさに生き様がそうでしたが。ですから、あの写真集を発刊された鳥居明雄さんには本当に感謝しています。鳥居さんは、私が出したいのです、先生は許可して下さればいいのです、売る必要もないし何もすることはありません、と父を説得なさって。結局、出来上がって一番喜んでいるのは本人じゃないのって、母が言っていました。
笠井 結局、菊生さんはおいくつでしたか。
明生 八十三歳。十月三十一日が誕生日ですから、もう少し頑張ってくれたら八十四歳になるところでした。欲を言えば、倒れるのをあと四日遅くして、粟谷能の会が終わってからなら・・・。でも何とか会の日を生きてくれたから、よかったです。頑張ってくれたのだと思います。
能夫 粟谷能の会は益二郎五十回忌追善能ですからね、頑張ってくださいよと言って、本人もその気だったよ。
笠井 プログラムにも菊生さんの思いが書かれているね。それを読むとちょっとたまらないな。
能夫 たまらないですよ。
明生 約束破りですよ。でも人間、完璧はないですから。
笠井 舞台には立てなかったけれど、五十回忌追善能への意気込みがああいう形で残っているのはいいことで、何ともいえず魅力ですよ。益二郎さんは『烏頭』の舞台で倒れ、菊生さんもそのようにありたいという舞台人魂みたいなものがあったわけでしょ。五、六日入院したけど、まさにその通りの燃焼し尽くした舞台人生でした。そして葬儀のときにあの笑顔(遺影)でしょ。あれを見たらみんなああいう風に生きたいと思いますよ。
能夫 菊生叔父は何回も入院して修羅場を潜り抜けているでしょ。その度に復活して元気な姿を見せてくれていたから、誰もがこんなに早く逝くとは思っていなかった・・・。でも叔父ちゃんらしいね。走って走って、バタッと倒れて。その前に全部やることやって・・・。
笠井 理想的だよ。男の本懐だよ。
明生 葬儀も多くの人のお骨折りをいただいて、日本能楽会と粟谷家の合同葬儀にしていただき、多くの人がご弔問に来てくださって、ありがたいことでした。普通は合同葬なんてありえないことですから。
能夫 現役の日本能楽会長だったから。そうでなければありえない。お手伝いの人も菊生さんのためにと自然と集まったね。人柄だよ、徳だよって、野村四郎さんも言われてたよ。
明生 父は人が好きで、にぎやかなことが好きだったから、喜んでくれたと思いますよ。
笠井 僕が初めて菊生さんの能を観たのは、広島での反核と平和のための能の会で、『黒塚』でした。もう二十数年前のことです。それは観世流とか他の流儀にないものでした。ズカッとした大きさ、スケール感があった。こざかしさがなくて、ああいう表現というのはすごいなと思った。その後別の曲もいろいろ観て行くと『班女』などはあのかわいさでしょ。そして晩年になるほどに、謡の味わいが深まって、粟谷能の会や喜多流の地謡を支えたというのは、ものすごい業績だと思いますよ。
能夫 それはそう。僕たちはずっと菊叔父ちゃんに寄りかかっていたもの。若い頃、僕は寿夫イズムだったから、新太郎や菊生の謡い方は嫌だなと反発しながら、それでも隣に座らせてもらって、それはそれで一つの喜びでした。本当に僕なんか、自分なりの「こうあるべし」でやってきたつもりだったけど、お釈迦様の掌で孫悟空が飛び回っているようなものだったんだね。それでも、最初から父や菊生叔父に右習いだったら、今のような関係にはならなかっただろうし。ぶつかり合いながらいいものができてきたのではないかと、勝手に思っていますよ。
明生 反発していても、知らず知らずに教わり洗脳されているのでしょうね。最近、はっと、あっ、これ父だと思うことがありますから。
能夫 ある年齢になって、素人会などで地方に連れて行ってもらうでしょ。それで一緒に謡ったり飲み会に出たりするうちに、叔父ちゃんはこう謡っているというのが徐々に、ジワジワと僕らの体に入ってくるんだよね。
明生 そうですね。地方で全然知らないお弟子さんが近寄って来て握手させられて、「今日のは粟谷の節ですな」などと言われると、次の会では「粟谷の節というのはね・・・」などとしゃべっている自分がいたりするわけですよ(笑い)。
能夫 そういうことで鍛えられたというかね。とにかく菊生叔父の隣で地謡を謡うのは楽しかった・・・。
笠井 菊生さんという人は地謡を楽しんだ人だったね。これはすごく大事なことですよ。それは寿夫さんもそうだったし、先代銕之亟さんもそうでした。能で一番大切なことだから。
明生 父はそういう思いで謡っていたと思います。晩年は謡での評価が多くなって喜んでいましたが、たまに能を舞っていた身体が利いたときのことも評価してほしいよ、とこぼしていましたが。これは内緒にしておいた方が・・・。父は能に好き嫌いはありませんでしたが、中でも現在物が大好きで、特に『安宅』、『満仲』はお得意で何度も勤め、大曲『正尊』も披いています、人が演らない曲も嫌がらずに勤め、俺の能はこれだ!というスタイルと自負があったように思います。益二郎は六平太先生の名地頭とばかり言われてきましたが、父は親父の能はすばらしかったんだ、『羽衣』の最後、スーッと消えていくところなどきれいなんだよと、何度も話していました。そして自分も、『弱法師』などは身体が冴えて杖扱いも巧みなときは取り上げないで、動けなくなったら地謡のことばかり、と愚痴っぽく私には漏らしたこともありました。
 笠井 菊生さんの舞台人としての評価は、もちろん謡だけでなく、舞っているところの評価もしかるべきものがあると思う。でも、僕は体が動くときの芸というのは何ほどのものかと思うんだ。京舞の先代井上八千代さんは四十代後半で人間国宝になった破格の人です。その頃の『長刀八島』の映像が残っていて、それは技が切れて実によく動いていますが、今見てそれほど感動しない。それより、七十代、八十代の体が動かなくなったときの八千代さんの方がずっと存在感があり深い表現力があっていいんですよ。つまり、四十代で技が冴えた人が七十代、八十代、年を経て動けなくなったときにもたらす豊かさというのは何にも代えがたいものがあるんですよ。菊生さんという人はそういう芸の人だったと思います。それにプラスして謡の感性がある人だったということですよ。
笠井 菊生さんの舞台人としての評価は、もちろん謡だけでなく、舞っているところの評価もしかるべきものがあると思う。でも、僕は体が動くときの芸というのは何ほどのものかと思うんだ。京舞の先代井上八千代さんは四十代後半で人間国宝になった破格の人です。その頃の『長刀八島』の映像が残っていて、それは技が切れて実によく動いていますが、今見てそれほど感動しない。それより、七十代、八十代の体が動かなくなったときの八千代さんの方がずっと存在感があり深い表現力があっていいんですよ。つまり、四十代で技が冴えた人が七十代、八十代、年を経て動けなくなったときにもたらす豊かさというのは何にも代えがたいものがあるんですよ。菊生さんという人はそういう芸の人だったと思います。それにプラスして謡の感性がある人だったということですよ。
能夫 それはいえるね。僕は十年、二十年、三十年と地謡で菊生叔父の隣に座って、いただいてきたものがあるから、それをこれから発揮しないといけないと思っている。菊生叔父の死は、単に一人の爺いがいなくなったということではなく、粟谷能の会としても、喜多流としても、地謡を謡える貴重な戦力を失ったということですよ。そういう認識をして、これから残されたものが頑張らないとね。
明生 本当に、これは流儀の活動としては、とても打撃をうけ痛いことですよ。益二郎が亡くなったとき、新太郎と菊生が追善能をやって、粟谷兄弟能を作り、我々にもレールを敷いてくれました。今度は、その保護者がいなくなって、本当に我々が中心になってしっかりやらなければ、もう一度スイッチを自分たちで入れ直せよ、と言われているとすごく感じています。
笠井 そういう意味では下地はできてきたし、そうやっていくことが供養になるということでしょう。(次号へつづく)
能『定家』の物語投稿日:2018-06-07
能『定家』の物語
神無月十日の頃のことです。未だ都に上ったことのない、北国育ちの僧が、一度は都を見てみたいと思い立ち、京の都へとやって参りました。
都はといえば、冬枯れの木々にも名残の紅葉がところどころに残り、鮮やかに彩られており、折しも冬になるかならぬかの時雨の頃です。空模様が怪しくなり、上京(かみぎょう)という処に着いたころ、ついに雨が降り出してしまい、僧とその従者は、ちょうど近くにあった建物で雨をしのぐことにしました。
しばらく雨宿りをしていると、どこからともなく手に数珠を持った女が現れました。
(女)「もうし、お坊様、どうしてこの建物にいらっしゃるのですか」
(僧)「時雨が降ってきたので、雨宿りをしているのです。そうお聞きになったということは、この建物はなにか特別な所なのでしょうか?」
(女)「ここは『時雨の亭』という名の由緒あるところです。そのことをご存知だったわけではないのですね?」
(僧)なるほど、あらためて建物に掲げられた額を見ますと『時雨の亭』と書かれていますね。」
(女)「それは昔、藤原定家という貴族が建てたものです。洛中といわれていますが、昔から寂しいところで、今の時季…時雨の頃にはとても趣深い場所で、定家の卿は、ここに居を構えて、毎年歌を詠んでいました。ちょうどこの時季に、あなたさまのようなお坊様がここを立ち寄られたのも、何かのご縁でしょう。今は亡き定家卿の菩提を弔って下さい。」
僧は、この話に興味を惹かれ、『時雨の亭』について、定家の卿という人について、さらに詳しく話をしてもらいました。
(女)「定家の卿はここで様々な歌を詠われました。ですから『時雨の亭』という名の由来は、定家卿のどの歌であるかはわかりません。ただ有名な〈偽りの なき世なりけり 神無月 誰がまことより 時雨初めけん〉という歌の詞書きに〈私の家にて〉とありますから、もしかするとこの歌に由来するのかもしれません。」
僧は、とてもいい歌だと思いました。
この世には、嘘偽りは多くありますが、時雨の時季になれば時雨が降る、これに偽りはなく。作者はすでに亡き人ではあるものの、定家卿がここで風雅を楽しんだ昔と同じように時雨は降っているのでしょう。
そうしてみると、人というものは本当にはかないものです。ですが、この儚い世でこうして誰かと出会うというのは、〈一樹の蔭、一河の流れ〉というように前世からの因縁があるのでしょう。そう思うと僧は、この浅からぬ縁に心惹かれるものを感じました。時雨の亭の周りは今や荒れ放題で人の訪れもないのでしょう、時雨が去ったあとの夕暮れが、さらに寂しさを増しています。
女はさらに、今日は供養するために行くところがある、と言って僧を案内しました。
連れてこられた場所には、蔦葛が這い纏っている石塔があり、どうやら年月の経ったお墓のようです。
(僧)「ずいぶんと古いお墓ですね、これはいったいどなたが眠っているのですか?」
(女)「これは、式子内親王のお墓です。ここに這っている草は定家葛です。」
どうやら先ほどの『時雨の亭』を建てたという定家と関係のある場所のようです。
(女)「式子内親王という人は、もともと賀茂の斎院を務められた方です。しばらくして、その任を退かれると、藤原の定家の卿と秘めた恋をし、契りを結ばれたのです。しかし、その後、内親王は亡くなられ、定家の卿は思いの深さゆえに執心が葛となり、お墓に這いまとっているのです。そのため、内親王も定家の卿も、成仏ができず苦しんでいます。どうか、お坊様、お経を読んで弔ってください。」
僧は、その申し出を受けることにして女の話をさらに聞きました。
(女)定家と内親王は世間に秘めた恋でした。それもそのはず、内親王は後白河法皇の姫であり、定家は歌を詠む貴族にすぎません。ふたりの身分には大きな差がありましたから、世に認められるはずもないものです。
〈玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば 忍ぶることの弱りもぞする〉と内親王が詠まれたように、絶え忍ばねばならぬ恋の辛さに、ふたりの心はやがて弱ってゆきました。いつしかその秘めた仲も人の知ることとなり、離れ離れにならざるを得なかったのです。
内親王はなんと、悲しい女性でしょう。
辛い恋などしない、とお就きになった斎院の位であったのに、神はその思いを聞いて下さらなかったのでしょうか。定家の卿との恋があらわになってしまったのは、本当に悲しいことでした。
隠そうとしても、ふたりが恋仲であるという噂は、世間に広まってしまい、それを恐れるが故に、まるで太陽が雲に隠されるように、定家の卿の通い路も絶えてしまい、互いが苦しい思いをしたのです。
定家の卿が〈君葛城の峰の雲〉と詠んだのは、手の届かぬ存在のたとえなのでしょう。この思いこそが執心を生み、定家葛となり、お墓から離れることなく、乱れた髪のように這いまとい、思い焦がれるかのように赤く紅葉するのかもしれません。
女はここまで話すと、僧に、どうかこの妄執を断ち切ってほしいと願い、姿を消しました。自分こそが式子内親王であると、云い残して……。
この出来事を不可思議に思った僧は、近くに住んでいる都のものにこのあたりの話を聞くことにいたしました。
(都の者)「今はむかし、後鳥羽上皇の時代のこと、式子内親王という方が賀茂の斎院になりました。しばらくして、その位を下りられ、この近くの歓喜寺というところにお住まいになりました。そのとき、〈恋せじと御手洗川にせし御祓 神や受けずもなりにけるかな〉とお詠みになったのでございます。男性と恋をしないという心が込められております。
しかしながら、定家の卿が内親王に恋慕し、忍びつつこちらへ通われたのです。
その恋は秘めたものでしたが、やがて世間の知られるところとなり、定家の卿は通うのを憚られるようになりました。
その後、内親王はこの世を去り、お墓はこの場所に築かれました。
年月が経ち、定家の卿が亡くなられますと、内親王のお墓には蔦葛が覆い隠すほどに這い纏うようになったのでございます。近くのものたちがそれを取り除きますが、不思議なことに一夜のうちにまた元通りになってしまうのです。
みなは気味悪がって、このことをとある位の高い人に相談いたしますと、その御方は夢でみたことをお話になりました。〈式子内親王のお墓に這い纏う蔦葛は、取り除くのではない。それは定家の卿の執心であり、もしこの後、それを取り除くようなことをすれば、祟りを起こす〉と告げたれたそうでございます。
その後は、誰もその墓を触るものはなく、ただ、あの植物を《定家葛》といい、この建物を『時雨の亭』というと伝えられているのです。」
都の者の話は、僧が不思議な女から聞いたものと同じでした。
(僧)「なるほど、先ほど、あの『時雨の亭』に立ち寄ると、どこからともなく女性が現れてそのような話をした。不思議なことに、その女性は、自分は式子内親王だといい、姿が見えなくなってしまった…」
(都の者)「なんということでしょう、お坊様は不思議な体験をなさいました。それは間違いなく、式子内親王が妄執にとらわれた亡霊の姿となって、あなたさまに助けを求めたのございましょう。どうか、お坊様、ここでありがたい読経をなさって、おふたりの執心をお弔いになってください」
僧は、その言葉に、先ほどの女は式子内親王の亡霊であると確信し、弔いをしよう、と約束しました。
荒れ野の原は、日が沈むと、なおいっそう恐ろしさが増します。
月の光があたりを照らすと、時雨の名残の露が哀しく光っています。
僧は、人の世の儚さを思い、読経をはじめました。
すると、僧へ語りかけてくる声が聞こえて来ました。
これは、式子内親王に違いありません。
(内親王)「夢なのでしょうか、月影の闇の路を、あなたの弔いの声を頼りにやってまいりました。思い出します、定家の卿もこうして、私の住まいへと闇に紛れて忍びつつ通ってきたものです。しかしそのような通い合った心もやがて、紅葉が散り散りになるように、薄れてしまいました。人の心は無常なものです。私の住まいもまた、無常なもので、このような荒れ野になってしまいました。しかしそれだけならばまだしも、私の墓は定家の妄執の葛が這い、私は成仏もできず苦しいのです。」

(僧)「なんとお痛わしいことだ。
『仏平等説 如一味雨、随衆生性 所受不同』」
(内親王)「私はこうして苦しい姿でいるけれども、今のお経は私の心に響いてまいります。なんと有難いことでしょう。今のは法華経の薬草喩品ですね?」
(僧)「そうです、この教えによって救われない草木はありません、定家の執心によって苦しめる葛を払いのけ、どうか成仏なさいませ。」
仏の慈悲は雨のように万物に与えられ、『草木国土 悉皆成仏』という言葉の通り、すべての衆生は成仏がかなうのでしょう。
やがて纏わりついていた葛と涙とが、ほろほろと落ち、解け広がり、そこに内親王の姿が現れました。苦しみからやっと逃れられた内親王は、よろよろとした弱い足取りながらも、お礼に、と、
(内親王)「昔、宮中で華やかに過ごした有様を舞でお目にかけましょう」
そう云って懐かしむように、舞いました。
しかし舞終えると、今度は恥ずかしそうに、顔を伏せ涙を流し…
(内親王)「昔は私も、〈月の顔、桂の眉〉といわれるように美しかったものですが、この世から消えたのち、悲しくも定家葛に纏われ、醜いゆえに夜しか姿を現さぬ葛城の女神のようになってしまいました。私も女神にならって、夢の覚めないうちに、姿を隠しましょう。」
そう言うと、内親王の姿は墓の影へと消えて行きました。
見れば、またもとの通りに定家葛が墓に這い纏ってゆきます。
ありがたいお経によって、内親王は成仏がかなったのでしょうか?
あとには、時雨の露に濡れた寂しい荒れ野が残るばかりでした…。
(終わり)
現代語訳 伊奈山明子・粟谷明生
挿絵 宮島 咲
面のウケについて 「小ベシミ(こべしみ)」を例にして投稿日:2018-06-07
面のウケについて
「小ベシミ(こべしみ)」を例にして

口をへの字に結び、怒りを押さえ、物を言うのを堪えているような赤ら顔の表情の「小ベシミ」は『鵜飼』『野守』『昭君』『鍾馗』などの後シテに使用されます。
面の表情は上向きでもなく、俯き過ぎにもならない中庸の位置を「よいウケ」と言います。私たちシテ方の能楽師は面の裏側に当て物という小さなクッションを付けて受け具合を調整し、一旦決めたらその角度を動かさないように一定にし、首を据えて舞台を勤めます。
面は上に向けると緩んだ表情に、下に向け過ぎると暗い表情になりますが、適度な中庸な受けがなんとも言えぬ物言う表情になるのが不思議です。
面によって受けの幅が広いものと狭いものがあります。
「小ベシミ」は狭い場合が多く、受けの判断がしづらい面です。
下顎が出たら面は生きませんし、また引きすぎても、これまただめで、判断がむずかしいのです。
「大ベシミ」は「小ベシミ」よりスケールが上回りますが、この面の受けは「小ベシミ」より広いように思えます。
何故でしょう?
彫りの深さも関係していると思いますが、もしかすると大ベシミの表情に隠されている滑稽な部分、どこか間が抜けた感じの表情が関係しているかもしれません。
「小ベシミ」に滑稽さや間の抜けたものは微塵も感じません。だから、受けがむずかしいのかもしれません。
この受け具合は付ける人間では見られないので、他人に見て判断してもらいます。
周りの能楽師は、受けを横から目を見て判断している人がいますが、これは正確さに欠けます。私は正面から口のラインで受けを決めています。
「明生、ウケ見て」と言われた時は責任を感じながらも、私の眼力を評価されてのことと思うと、嬉しいものです。
出会い投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
出会い
粟谷能夫
この阿吽のなかで『我流年来稽古条々』を連載していて自分たちの修行時代を振り返って見るということをしているのですが、その中で自分自身の未熟さを痛感することも多いのですが、一方では、若いころに素晴らしい出会いがあったから、能という仕事に生涯をかけていられるのだと、今更ながらに思います。
私たちの世代は明治に育った錚々たる名人の最後の舞台と、戦後、能の価値を意識的に問い直して出発した観世寿夫さんの舞台を見ることが出来ました。そうした舞台から大いに触発されて頑張ろうと思ったものでした。
多分十代の後半の頃、友枝喜久夫先生の『葵上』のツレの役が付いて、大抜擢だったんだろうと思うのですが、その舞台のあと、恒例の我が家での忘年会で父と菊生叔父と喜久夫先生とが飲んでいて、私が呼ばれ喜久夫先生に「能夫、今度謡を教えてやるからな」と言われました。自分にはおっしゃられる意味合いが充分に理解出来ていなかったのですが、いまにして思えば、節が間違っていないというだけのことで『葵上』という作品のツレの謡になっていなかった、そのことをおっしゃられたのだと思います。基本の技術の上に立ったうえで、作品の内容に即した表現に出会っていなかったということです。
そういう自己の芸を確立していこうという時期に、多くの名人や、とりわけ寿夫さんの舞台を見たことで、型をなぞるだけでない、作品に出会った表現をするという方向性をもてたように思えます。
どの世代の若者もそれぞれの時代の制約のなかで、精一杯生きて学んで稽古しているのでしょうが、自分たちがそうした先輩たちから学び、身につけて来たものと比べ、いまの若い人たちはこと技術においても、志しにおいても衰弱しているように思えてなりません。
明日の自分を見ていないのです。今しか見てない。時間を切り売りして、なんとか今の辻褄をあわせて、それでしのいでいる。自分のやる曲にはオタクになっているけれど、その根底に人の舞台を見てそれに憧れ触発される、といった志しが感じられないのです。規範を追うことで汲々としていては自前の表現に到達しようもない。
私の思う佳い能は、自分が獲得した技術や曲への取り組みかたが、周りの皆に理解され支えられ一体となって表現されたものです。そうした方向に向かった習練がなされていないのではないか。
私の祖父たちの世代の名人は血の出るような稽古を積んで、それもただ、ダメだ、ダメだと言われ、よくいわれて手が高いとか低いとかそんななかでの稽古をして来たから、舞台に立って、シカケ、ヒラキをすれば、自ずから『船弁慶』の能になり、『湯谷』の能になった。しかし我々の世代は勿論、今の若い世代もそんな稽古はしてないし、出来ないのにもかかわらず、シカケ、ヒラキ、といった型を組み合わせたら能になると思っている。それではいつまでたっても作品とは出会えない。もっと自分の視点、美意識といったものを日々積みあげていかなければ駄目だと思う。
私はいつか自分がこの曲を手がけるんだという思いで能を見て来たし、その舞台から受けた刺激の積み重ねで今迄やって来ました。
譬えで言えば、二人のコックがいて、一人はその道が好きで命懸けでコックをめざし、もう一人はほかにやることがなくて、たまたま家がその仕事をしているからという理由でコックになった。一人は勉強もするし、ほかのコックの仕事も熱心に見て良いところを取ろうとする。もう一人はそこそこに型どうりの仕事をして日々を送る。この二人はどちらもコックを職業としているからともにプロだということになる。その出す料理は違うに決まっているのに、世間では同じプロということになる。どちらのコックになるかは本人次第だが、その道で生きるかぎりどちらを選ぶかははっきりしているはずだ。
『烏頭』ー殺生の業についてー投稿日:2018-06-07
『烏頭』ー殺生の業についてー
粟谷 明生
 本州最北端の地、青森市で催される「外ケ浜薪能」にて『烏頭』(他流では『善知鳥』)を勤めました。外ケ浜(注・謡曲では外の浜)は『烏頭』の舞台として知られ、また版画家・棟方志功の出身地であります。棟方志功には能『烏頭』を題材にした「善知鳥版画巻」があり、今年は彼の生誕百年祭である為、今回の実行委員の方々が『烏頭』を選曲されました。
本州最北端の地、青森市で催される「外ケ浜薪能」にて『烏頭』(他流では『善知鳥』)を勤めました。外ケ浜(注・謡曲では外の浜)は『烏頭』の舞台として知られ、また版画家・棟方志功の出身地であります。棟方志功には能『烏頭』を題材にした「善知鳥版画巻」があり、今年は彼の生誕百年祭である為、今回の実行委員の方々が『烏頭』を選曲されました。
能『烏頭』は陸奥・外の浜でうとう鳥(ウミスズメ科の海鳥)を獲る猟師が、死後地獄の責めに苦しみ、僧に救いを求める物語です。
舞台は、越中の国(富山県)立山へ禅定(ぜんじょう=山中の霊場を廻る修業)した僧(ワキ)が目のあたりに地獄の光景を見て感慨し下山するところから始まります。そこに、去年の春、外の浜で死んだ猟師の霊(シテ)が老人として現れ、禅定を終え陸奥へ向かう僧に、死別した妻子に麻衣の袖を届け、蓑笠を手向けてほしいと伝言します。立山といえば嶮しい霊山。今は立山黒部アルペンルートがあり、室堂あたりまでは容易に入ることができますが、その昔は、修験の山として信仰され、霊が集まる恐山、峻厳な秘境であり、立山に入ることが修行とされていました。殺生を生業にする人間の罪という重いテーマを、前場、峻厳の地の立山と、後場、本州最北の地の外ケ浜とを結んで描くところに、能『烏頭』の展開の面白さが感じられます。
今回は、初めてご覧になる方も大勢いらっしゃると思い、少し解りやすいように手を加えてみました。
一つは、既存の簡略化されたアイの言葉の見直しです。横道萬里雄氏は著書「能劇そぞろ歩き」に『善知鳥』のアイの試案を書かれています。今回ご承諾を頂き、そのアイの言葉を野村万作氏のご協力を得て深田博治氏に勤めていただきました。通常、僧(ワキ)が外の浜在所の者(アイ)に猟師の家を訪ねると、「さん候、去年の春みまかりたる猟師の家は、あれに見えたる高もがりの内にて候。あれへ御出であって、心静かに御尋ね候へ」と非常に手短に、ややそっけなく答えます。それに対してワキは「ねんごろに御教へ祝着申して候」とたいそう仰々しく受けて謡いますが、私はここを不自然に感じていました。今回はご当地ソングでもあり、外ケ浜や主人公の猟師の説明などを丁寧に語ることにより、内容もわかりやすく、身近に親しみを感じていただけるのではと思い試演してみました。
また「出し置き」の手法をとらないことにしました。出し置きとは、本来その場にいない人物を、最初から舞台に出しておくやり方です。『烏頭』の前場は立山が舞台ですから、外ケ浜の妻子がいるはずがないのですが、子方とツレは最初に登場してワキ座に座っています。初めて能をご覧になる方は、戸惑いを感じるところだと思います。「出し置き」は、能という中世の日本の演劇の特徴的な手法で面白いとは思いますが、敢えてわかりやすさに重点を置いて、中入り後、場面が外ケ浜に転回するところで、子どもと妻(子方とツレ)を登場させ、アイはワキに呼び出され幕から登場していただくことにしました。
面は前シテが小牛尉、尉としては品のよい顔で、喜多流では『高砂』や『弓八幡』などの脇能に使用しますが、なぜ身分の低い猟師の霊が小牛尉を使用するのか、品位の落ちる三光尉でよいと思うのですが、その理由がはっきりしません。研究の余地がありそうです。
前シテは呼掛で橋掛りにて留まり、片袖を脱ぎ取りワキに渡します。シテは本舞台へ入るぎりぎりのところで、ワキは決して橋掛りに入らずに受け渡しをするのが心得です。シテのいる橋掛りは霊界、ワキの立つ本舞台は現世とされています。その境で「立ち別れゆくその跡の」と二人の離れ行く歩みが糸を引くように同じようになると良いといわれています。ワキとよくよく稽古しないかぎり、なかなか難しいところですが、一つの見せ場です。
『烏頭』のメッセージはシテ自らが謡う「何しに殺しけん」に集約されていると思います。人間が生きていくために、他の動物の命を奪わねばならぬ悲しい業。地球上のあらゆる生き物は弱肉強食のルールの上で成り立ち、人間もまた例外ではないのです。もし猟師の殺生が罪というなら、それは人間の背負った宿命的な罪というべきでしょう。
生きるための生業なら致し方ないと思う殺生ですが、『烏頭』の猟師は地獄に落ちて呵責の責めを負い続けています。能では『烏頭』『阿漕』『鵜飼』の三曲を三卑賎と呼び、いずれも殺生を生業にする猟師達の話ですが、『阿漕』と『鵜飼』の猟師達が弔われ成仏していくのに対して、『烏頭』は最後まで成仏出来ずに消えていきます。救われない何かがあり、それが『烏頭』の特徴ともいえます。
では、救われない何かとは何か。答えは狩猟方法にあるのではないでしょうか。幼い雛鳥を狩猟する悪業を重ねていくうちに、殺生自体が快楽になってしまった猟師。目の色を変えて雛鳥を散々に打つ姿は、正気の沙汰とは思えず、まるで何かに取りつかれているように見えます。
猟師が鳥を打つ様を描く「カケリ」は「追打之カケリ」とも言われ、修羅道に堕ちた武者たちの苦悩や、狂女の心の狂いの様を表すカケリとは明らかに違います。この型は正先に置かれた笠を巣に見立て、はじめは親鳥を狙い打ち、逃げられると空を見上げ悔しがります。二度目は橋掛りで「うとう」と親鳥の声をまねて謡い、それに答える雛鳥を見つけ、散々に打ち殺し捕獲します。親鳥はそれを見て空から血の涙を流し、泣き叫ぶという悲惨な場面です。
生まれたばかりの雛鳥の生命を絶つという罪の深さ、それを人間と鳥類の親子の情にからめて描いたところに、『烏頭』の主張があります。うとう鳥は親子の情愛が深い鳥と言われています。「平沙に子を産みて落雁の儚や親は隠すと」も、外敵に見つからないように、親は懸命に巣を隠して子を守ろうとします。ところが、親鳥が「うとう」と鳴くと「やすかた」と答える習性があり、その親子の絆の深さがかえって命取りになっているわけです。そして親子の別離は猟師の霊にも降りかかります。ひと目妻子に会いたいと外ケ浜までやって来る猟師の霊ですが、子供の髪を撫でようとしても、「横障の雲の隔てか」と阻まれてしまいます。まさに因果応報、罪の深さを鮮烈に描き出しています。
救済なき罪にもがく猟師の心境。そこをどう表現するかが演者の力。後シテの「一見卒都婆永離三悪道、この文の如くんば・・・」と経文を唱えれば助けてもらえるはずなのに、何故俺は救われないのか・・・という悲痛な謡を、単に朗々と謡ってはその苦しみが表現できるはずがなく、陰々滅々と気持ちを埋没して謡うだけでは、あの苦しみの訴えは通じないのではないか…。父は淡々と落ち着いて力強く謡う中に本当の強さが生まれ、それが聞いている人の想像力を掻き立てる、あまり前面に押し出すような謡ではいけないと教えています。演じる心に余裕をつくり、下の下の身分の嘆き、実盛や頼政などの武将のような訴えかけの強さとも違う、低い身分にありながらもそこに強い張りと内圧のある叫びのような謡ができればと思うのですが、今回もつくづくその難しさを実感させられました。
私が『烏頭』の子方を初めて勤めたのは六歳の時、父菊生がシテの時です。シテツレは二十三年前の昭和五十五年に父菊生のシテで、これも青森公演でした。私自身シテは、十年ほど前の妙花の会以来の二回目の演能となります。
子方で思い出すことはたった一度の稽古で「ツレが立たせに来たら立ってシテの傍まで行きなさい、シテが触ろうとするから、触られないように長袴を踏まないようにもとに戻り、あとは最後まで座っていて、終わったら立って帰るんだよ」とこの程度の指示で、最初から舞台に出させられたあのときの心境です。中入りが過ぎるうちに段々、いつシテの近くに行くのだろうと不安がつのりました。シテが我が子の髪を撫でようと寄って来るところを、スッと後ずさりして逃げる動作は子ども心にも難しいと思い緊張しましたが、何よりもシテと向き合って、その面の顔をまともに見た瞬間、本当に恐ろしいと驚きました。これは髪を撫でてくれるのではない、殺しに来るから逃げるのだと思いました。それほどの恐怖を覚えたのです。もちろん、その場面はただ恐ろしいというものではありませんが、触りたいけれども触れない無念さで歩みよるその緊迫感が、子方の私には異常な恐ろしさと映ったのでした。
恐ろしい形相のシテ、永遠に子に触れることのできないシテ。何故作者はシテの猟師に救済処置を施さなかったか、成仏させず永遠に地獄の責めを負わせることにしたのか。それは幼い命を奪うことがいかに悪であるかという大事な教えであるように思えます。最近の幼児殺害という悲惨な事件の数々。大人、子どもを問わず人間のもって生まれた残虐性と愚かさをこの作品は戒めているのではないか、現代にも通じる強いメッセージになっているように思えてなりません。人間が生きるかぎり『烏頭』は、永遠のテーマとして舞台で演じ続けられるでしょう。猟師の魂はあの恐ろしい地獄の有り様を表す立山の霊山に永遠に彷徨い続けていると、私は思っています。
(平成十五年七月 記)
写真 「烏頭」 シテ 粟谷明生 平成15年7月 外ケ浜薪能 撮影 石田 裕
鼎談投稿日:2018-06-07
鼎談
粟谷 能夫
粟谷 明生
笠井 賢一
明生 前号に引き続き、菊生を偲んで、三人で語り合っていきたいと思います。祖父益二郎には女の子が一人いましたが早世してしまい、四人の息子全員を能楽師にしました。菊生はその次男です。父から聞いた話ですが、茂山千作(当時千五郎)氏に、「粟谷さんとこはご兄弟うまくいってますな、お宅のようになるには、うちはどないしたらよろしいか?」と聞かれたと。父はその秘訣を話したらそく、何年後に「七五三(しめ)ちゃんにお宅の通りやって間違いおまへんな」と言われたと、話してくれました。
笠井 その秘訣というのはどういうこと?
明生 次男は長男を立て、三男は次男を立てる。次男は長男の三倍の努力、三男はその倍の努力と・・・。兄貴をたて、マネージメントは全部次男坊。そして装束、舞台を持たない!っと。そして必ず、昔のたばこでスリーエーという銘柄の模様を例に出しては、益二郎が亡くなって粟谷の力が弱くなったときに、頂点が二つも三つもあっては力が分散するからよくない、弟は一歩下がって兄をもり立てる、頂点は一つの方が強い、これが秘訣!と、まあ、私によく諭すように話していました。
能夫 だから菊生叔父は、面も装束も舞台も本当に持たなかったね。すべて本家を立てるということで・・・。

明生 それでも五十歳を過ぎてからは、舞台上のことではは、自分もそろそろ自己主張したい時期にきたからと、スリーエーの一点になろうと・・・。演能の依頼があったら、それまでは聞かなかった、「新太郎へですか?」「菊生へですか?」を聞くからと宣言したようです。もちろん長男を立てる姿勢は崩さずにいました。私は能夫さんとは従兄弟ですが、浩之君も充雄君もみな、そのように教育を受けていますから、私は本家を立てますし、浩之君も充雄君も私たちを立ててくれて今のところ皆うまくいっています。能夫さんは「明生君、次はこれを舞っておくといいよ」と大曲やその時期にしておくべき曲目を積極的に薦めてくれますし、全く問題ない状態です。
もっとも、能夫さんは子供のころ、菊生が長男だと思っていたのですよね。(笑)
能夫 そうなんだよ。だって、我が家にズカズカ入ってきて、てきぱきとものを決めていくから、長男だと思っていたよ。親父がおばあちゃんの面倒みているのに、どうして菊生叔父の方が威張っているんだろうってね・・・。(笑)
菊生叔父は対外的な窓口の立場をうまくこなしていたし、顔も広くて、何か主導者的なものを強く感じさせられましたね。
明生 多方面に交流関係が広かったですから・・・。新太郎伯父はやはり本家で、粟谷家の中心にどっしりと構えている感じで、菊生は次男として活発に外周りを・・・、いつも家にいませんでしたから、外周り専門?
笠井 次男だから長男を立てる。だから舞台も何も持たない。その代わり、自分は自分の世界で遊び、独特の世界をもつようになった、芸にも反映させていったという解釈もできます。次男気質ということもあるし、本来持っている人なつっこい気質もあったと思う。お酒を愛し、人との語らいを愛し、自由奔放な生き方をした人ですよ。
能夫 それはよくわかりますね。
明生 それだからこそ、魅力的な菊生の能を創りだせたということになるのでしょうが・・・。
笠井 ところで、能夫さんは寿夫イズムにかぶれて、新太郎さんとぶつかったという話は聞いているけれど、明生さんは菊生さんとはどうだったの。
明生 私は一回、父と取っ組み合いの喧嘩をしたことがあります。父は、父親と息子というのは、一度はそういう喧嘩をしなければ駄目だ、といっていましたが・・・。
笠井 どういうことで喧嘩を? 芸のこと?
明生 芸のことで言い合うことはありましたが、その一度の取っ組み合いの喧嘩はたわいもないことですよ。私が「能楽師なんてやる気ない」と反発して・・・。おやじも誰も謡の指導をしないのに、どうして出来るんだよ!ってね。
笠井 爆発したの。たわいなくないよ。能楽師として一大事だ。それはいつごろのこと?
明生 高校一年生ぐらいですかね。シテ方の親子というのはなかなかうまく教え、教えられるという関係を作るのがむずかしいと思いますね・・・
能夫 僕も親父とはよくぶつかったけど、それでも家には面はあるし装束はある、舞台もあるから、そういう座というようなところで育っているわけ。だから反発していても親父の姿が見えるし、常に能の環境のなかにいるわけですよ。だから、子供のころからずっと能は好きでした。でも明生君は親の姿を日常的に見ていないから、あれだけ子方をやっても、中学、高校ぐらいになって、気持ちが少し離れるのは無理もなかったかもしれないね。
笠井 確かに。銕仙会の三兄弟、寿夫、榮夫、静夫さんたちは、華雪おじいちゃんがいらして、子供用の装束を作ってくれてお能ごっこをして遊んでいたのだから、それは自然と好きになりますよ。
明生 今は華雪先生や能夫さんのような環境を持っている方が特別で、私のような環境の方のほうが多いのではないでしょうか。いや、私が特別ですかね。
笠井 それは、今後の能楽界の課題でしょうね。
明生 それで、父はそういう喧嘩をすると、父親は息子に殴られることで子が思いの外成長していることを実感する、子は子で、子どもの時に描いていた父親像より案外弱くなっていることを知ってしまう。それがいい、世界が変わるから、と言っていました。
笠井 一度、父親を否定しない限り、親を越えられないのだと思いますよ。
能夫 僕は実先生の指導を受けながら、先生や父、伯父の謡い方に違和感を覚えるようになって・・・。そこで寿夫さんや銕仙会の人たちにふれて、地謡の重要性というかシテと対峙する姿勢、そんな衝撃波を受けたわけ。舞っていればいい、謡いは二の次という風潮では通用しない、と外を見て感じたわけですよ。まあその後だいぶ経ちまして、親父たちの謡、益二郎の謡いみたいなものを、見直すようにもなるんですが。そうそう、うちの親父は僕の育成係を菊生叔父に任せたんですよ。
笠井 能夫さんは寿夫さんに真っ赤っかにかぶれていたから、親父さんたちも危機感を持ったのだろうね。
能夫 そう。だから喜多流本流に戻す方便として、菊生叔父に委託したのだと思いますよ。そんな風に親に反発しながらも、あるとき、父の謡や能のよさを知る、親も懸命にやってきたことを知り、自分にもこのDNAが流れていることに気づかされる。それで今度は本当の意味で、親に出会うのだと思う。
明生 そう、一回否定して、そしてまた「出会う」。
能夫 それで親の大きさ、ありがたさがわかるのですよ。
明生 まさに今、それを感じています。父たちも外の刺激をずいぶん受けていますよ。能夫さんが寿夫さんの影響を受けたように、父も観世三兄弟の影響を受けている、そう申していましたし、父はベネチアの国際演劇祭に行ったでしょ。
笠井 ああ、昭和二十九年の第一回能楽渡欧団ね。
明生 観世三兄弟もご一緒だったようで、この公演の話となると決まって父が話すことがありました。どこかの公演で靴を履いたまま現地の外人スタッフが舞台を掃いているので、団長(喜多実先生)が「だれか舞台を拭いてこい!」と仰った、もう始まる寸前だったが、直ぐに雑巾掛けをしたのが榮ちゃん(観世榮夫)と僕だよ。紋付をたすきがけして袴をたくし上げて中腰で、すーっと橋掛を拭いていたら、既に会場入りしていた観客から拍手が湧いたよ、拭いたのは榮ちゃんと僕で、揚げ幕の内から雑巾を絞って手渡ししていたのは、観世の御曹司で・・・。すいません、これは脱線してしまいました。まあ、そこでいろいろ刺激を受けたということです。その後も亡くなるまで親しくおつき合いさせていただきましたね。父の広い交流で、私はそのジュニア世代と、親しくお付き合いさせていただいています。能夫さんは他流では浅井文義さんとか櫻間金記さんとかお仲間がいらっしゃるが、私は父を通して、例えば武田喜永さんのご子息孝史さんや金井章さんの雄資さんとか観世銕之丞さん、故観世清顕さん皆ジュニア仲間というか・・・。もっともすべて森 常好さんや金春国和さんや耕ちゃん(故野村万之丞)を通してでしたが。他流の人と話すといろいろ刺激を受けますね。
笠井 そういう意味では親父さんたちが、外とのいいつながりをつくってくれたわけだね。それで能夫さんは菊生さんから指導を受け、謡を学んでいった・・・。
能夫 鍛えられたというかね。あるときから、菊生叔父から隣で謡ってくれというオーダーが出るようになった。
笠井 四十代ぐらいのこと?
能夫 そうねえ、十五年ぐらい前かな。二十年ぐらい前から一緒に謡ってはいるけど。
明生 父は晩年、大事な曲をやるときは、能夫を左に置いて、前には明生がいればいいと言ってくれました。それだけ言われるということは嬉しいし、励みになりました。晩年の菊生は地謡の評価が高かったという話が前号でも出ましたが、その確かな一ページが開かれたのは、京都での友枝昭世さんの『朝長』小書「懺法」のときだと私は思います。十五年ぐらい前かな。『朝長』という曲は、喜多流では地謡の位取りがきっちりとは決まっていない状況です。六平太先生の時の緩急と、実先生が違い。そして父の謡も、謡う度に違うというものだったので、「どのように謡うのかを決めてほしい、そうでなければ前列は謡えない」と口論になった。そうしたら友枝さんが、「まあまあアッ君、そういういい加減なところのよさが菊生先生のいいところなんだ。僕はその謡についていくから大丈夫、心配ない!」って、この一言でことは終わったのですが。私たち前列もそれに合わせられる力量をつければいいのか、と学んだわけです。
笠井 臨機応変というか・・・ね。
明生 それは父が謡う、という認識と、地頭という重さを教えられた一番だったと、私は思っています。地頭が力を尽くし、それにあわせて、地謡が全員一緒になって作りあげる、そういう意識になったことを覚えています。
能夫 確かに、喜多流をあげて行こうやというね。
明生 京都での喜多流の公演は、敵陣にて勤めるようなものですからね。ましてや小書「懺法」でしたから。
能夫 喜多流では初演かな? 重い小書だからね。
明生 その後、父は地頭として、能夫さんや私の舞台を支えてくれました。父は半分は能夫さんの父親でもあったように思えますよ。特に新太郎伯父が倒れてからは新太郎の代わりに能夫さんの親代わりというか、粟谷能の会の責任者というか、そういう気持ちがすごくあって、能夫さんを盛り立てていこうと・・・ね。
能夫 僕を育ててくれました。
明生 能夫さんのためにというのは、阿吽の『芭蕉』について書いていますが、それにはわけがあるわけで・・・。僕に『野宮』を舞わせ、『卒都婆小町』、『伯母捨』を薦めたのは能夫だから、その感謝の気持ちというのが本音です。『野宮』を決めたときは・・・。能夫さんが「何故叔父ちゃん演らないの? やったらいいじゃないですか」と言ったら、僕の思うような地謡をまだ謡ってくれないからできない・・・って。まあ、それぐらい『野宮』を大事に思っていたようでして。
能夫 能楽師にとって『野宮』ができるということは誉れですから。その人の人生を背負って舞台に立たなければならない曲ですし。能楽師の成長の証の曲でもありますから。
笠井 生き死にや、痛みの深さ、喪失感の深さ、それを表現しなければならない、すごい曲ですからね。
明生 能夫さんが『野宮』を、その二年後に『卒都婆小町』を、またその二年後に『伯母捨』をと薦めてくれたわけです。
能夫 明生君も一緒に話をしたね。
笠井 それはすごい。お二人が、菊生さんの六十代、七十代のプロデュースをしたわけだね。
明生 それで、父は能夫の言うことを聞いていれば間違いないと、我々の意見を聞いてくれていろいろなことに取り組んでくれたのです。高齢になるとどうしても我が儘になりますから、自分で自分をプロデュースするのがだんだん難しく、また億劫になりがちですから、まわりにそれをしてくれる誰かがいないといけないと思います。能夫さんは「菊生伯父の晩節を汚さないように、、僕らがフォローしますから」って父に常に言っていましたね。
能夫 それはすごく頑張りましたよ。
明生 能を舞わないことを決断したときは、私のところに周りから、いろいろご注意もありました。何でやめさせるのか、って。
能夫 まだ舞えるじゃないかって。確かにありました。
明生 「お父様はまだできると言っています」って。
笠井 言っているのかもしれないな。
明生 能夫と明生が結託して舞わせてくれないんだ、と冗談で言ってたみたいです。まあ、父は怪人二十面相だから、二面性がありまして。でも、能夫さんの「晩節を汚さない」、この一言に尽きますよ。結局納得してたんですよ。
能夫 ウフフ、そうね。
笠井 その結果、いい意味で功なり名を遂げられた。人間国宝にもなり芸術院会員にもなり、ほとんどすべての名誉をいただいた。それでいて変に孤立することもなかったし、変に権威ぶらなかったしね。
能夫 「大好きな菊生さん」と萬さんが言ってくれるぐらいで、人柄、人徳ですかね。人情味もあった。一つの時代が終わったという感じがすごくします。いい時代だった。
明生 反発もしましたけれど、支えてもらっていたんだなって。親が亡くならないと、わからないことってたくさんありますね。
能夫 本当にそう。それで成長するの。
明生 それにしても、父は私がこの年になるまでよく頑張ってくれたと思います。もうお前も抵抗力ができただろう、自分たちでやっていけるだろう?って・・・。
能夫 我々にいろいろなことを伝えてくれてね。まあ勝手に、そこのけそこのけで生きてきた人かもしれないけど、その中に真実があったというか、家族に対する愛も、粟谷家に対する愛も、能に対する愛も、人一倍あった人だったよね。そんな気がする・・・。
明生 そうですね。
(終わり)
写真 粟谷菊生 近影 平成18年8月2日 読売新聞取材時 撮影 亀田邦平
能舞台と天地人投稿日:2018-06-07
能楽師・粟谷明生が演じる立場から能を解説する「解能新書」
その2は舞の構造を説明します。
能の舞は左回りからはじまります。
舞人は舞台に「天」・「地」・「人」を頭に描き舞います。(図1参照)

図1
本舞台の目付柱あたりを「天」、ワキ柱近くを「地」、大小前と呼ばれる小鼓座と大鼓座の間を「人」としています。
舞人は舞(お囃子に囃される舞)のはじめ(掛かり)に、まず「天」に行き、次に「地」へ移動し、「人」に戻るという左回りをして、三角形を描きます。
これは翁の舞に基づいています。
翁のシテは「天」「地」それぞれで拍子を踏み、その後、面を隠す型や左袖を巻く型をして、最後に「人」に戻り「人の拍子」を踏み舞納めます。決して「地」から「天」へと逆回りすることはありません。
仕舞も「人」よりはじまり、「天」から「地」へと左回りに移動して「人」に戻る、この一連の動きを、上羽(あげは:クセの後半以降にある、1?2句、上音で始まる、シテやワキなどの役の謡)までに行うのが基本形です。もちろん例外もあります。
中の舞、序の舞など、お囃子方に囃される舞や、クセなどの仕舞を、注意深くご覧になると、みな最初に左回りしているのがお判りになると思います。
スカイツリーと空の月投稿日:2018-06-07
スカイツリーと空の月
粟谷 能夫
今年五月に東京スカイツリーが開場となりました。隅田川の業平橋のほとりです。業平といえば「伊勢物語」。業平東下りの段(九段)に隅田川が描かれています。
「昔、おとこありけり。そのおとこ、身を要なき物に思ひなして、京にはあらじ、あずまの方に住むべき国求め・・・」
と、東下りの冒頭です。やがて隅田川に至り、
名にし負はば いざ事とはむ都鳥
我が思ふ人はありやなしや
と詠むと、「舟こぞりて泣きにけり」とあります。
能『隅田川』はこの和歌を元に構想されたものです。子を捜し都より東の地、隅田川までやってきた物狂いの女(シテ)は、この歌をひき、「ありやなしや」と問う心は業平も自分も同じと訴えます。このようなよい場面を織り込みながらも、救いの無い母と子のドラマを生み出しました。しかしここには、母親の子に対する深い慈しみの心や、温かいまなざしが投影されております。
私の子どもの頃は東京といえども高層ビルも無く、高い所へ上るといえば、電波塔ぐらいでした。東京タワーができるまでは、各放送局が電波塔を持っていたのです。私も赤坂プリンスホテル辺りにあった電波塔に連れて行ってもらったことがあります。大変高くて少し怖かったことを覚えています。
東京タワー開場の折には、母に連れられて妹と共に展望台までエレベーターで上り、下りは歩いて階段を下りた記憶があります。その折、日付入りのメダルを買ってもらい嬉しかったこともよい思い出です。
また今年は金環日食や金星の太陽面通過等、天体ショーがあり、皆専用メガネ等で空を見上げる様子をテレビ等で見ました。私の頃は小学校の校庭で下敷き越しに観察をした記憶があり、随分と進歩したものだと感じています。
能にも空を見上げる事があまたあります。例えば月を見る場合、役者は自身思い描く月を想像しながら上を見ます。暖かい大きな月なのか、遠くに見える小さく寒々しい月なのかと。しかし観客は月を見ている役者の姿を見ることで、月を見ているなと想像し、自分なりの月を考えます。
その曲に適うような月を伝えられるのかと、思うことがあります。扇のかざし方、面の傾け方、あらゆる所作に神経を集中します。そこに謡が加わる事で情景が浮かび上がり、なんとかまとまるのだと思っています。
スカイツリーを眺め、空を見上げて、能のふかぶかとした趣きに想いをいたしているところです。
写真 シテ:粟谷能夫 撮影:吉越研
畳の目一つ投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
畳の目一つ
粟谷菊生
ぼくが人間国宝の認定を受けたことは、まことにありがたく、光栄の至りではあるけれどもおかげでひどくいそがしかった。日本中を駆けまわって、一週間に四回も能を舞わなければならないというハードスケジュールに追い込まれる有様。
そのいそがしさの中で、甥や息子たちから次の阿吽には何か書くように言われていたけれど、なかなか原稿を書くひまが見いだせないうちに、どんどん日は過ぎてゆき、早くも秋が来てしまったわけだが、そこで思いついたのは、昔、菊生会の会報をしばらく出していたことがあり、その巻頭には、ぼくが毎号、何か思いついたことを書いていた。その中から「畳の目一つ」(昭和52年10月第八号)という小文を転載させていただいて、今回の責めを果たしたいと思いついた。
かつて自動車の運転をぼくも習ったが、ハンドル操作から教わって、バックまで進むと、ひどくうまくなったような気がするものだ。そしてつぎつぎに技術を習得していって、これで車の運転のすべてがわかったという自信を持つようになる。
しかし、ほんとうのうまさというものは、決して運転技術のあざやかさではないと思う。目的地まで安全に運転できるということ……安全と言ってもノロノロ運転ではなく、そこに 目につかないうまさというものがあるはずだ。
お弟子さんを教えていると、いろいろなことに気がつく。習えばすぐに上手になると思っている人もある。なかにはツツーとうまくなる人もあるが、不思議にそういう人は長つづきしないものだ。長年稽古をつづけて、あるところまで上手になっても、それから先は本人には上達がわからない。いわば畳の目ひと目ずつのびていくようなもので、あるとき、パッとうまくなってしまう。
何ごとも、三日、三月、三年というが、この区切りが実は危険だ。車の運転も三日目に車庫入れでコツンとやる。三月目ぐらいが往来で電信柱にぶつかったり、塀をこすったりする。そして運転が三年目、すいすいととばすと、大きな事故を引き起こしたりするものだ。
ところが、三年を過ぎると、いつうまくなったかわからないのに、徐々にうまくなっている。結局それは反復、何度もくりかえすことによって上達するものだとぼくは思う。
何年か前から、あるお弟子さんに謡の稽古をしてきたが、その人は白無垢でぼくのところにきた人ではなかった。よその先生についていたが、ある時からぼくのところに後妻にきた人。従って先夫の匂いがプンプンしていた。これをぼくの匂いにするには、先夫と暮らした同じ年数をかけることが必要だが、そうも言っていられないから、何とかしてぼくのカラーにしようと、こちらも一生懸命努力した。そのおかげで本人はベソをかいたり、、癪に触ったことが幾度となくあったろうと思うが、ぼくは甘い顔を見せないでやってきた。するとある日突然、こちらがびっくりするような亭主の一ばん好きな料理を 作る女房になってくれた。
お弟子さんの中には、いつうまくなるかということを気にする人もいるが、上達を焦らず、ひたすらワンマン亭主に仕えて、好きな料理を研究してくれるお弟子さんは、そのうち必ずこちらの口に合った料理を作る人に成長するというのがぼくの体験である。
いつも言うことだが、ぼくはゴルフのキャディー上がりのプロ、門前の小僧習わぬ経を読む式で能を舞ってきた人間だが、お弟子さんはそれぞれの学識や教養のある人々だと思うので、謡の文意や曲趣は、ぼくが教えなくても自分で掌握するものと長年思ってきた。しかし案外そうではなく、謡のメロディや節扱いのみに苦労している人が多いことが、近ごろわかってきた。
物を習うということは、節を選び、その師に似ることが第一歩だが、やがてそこから脱皮して、最終的には全部を掌握した上でハートで謡うことを覚えてほしいとぼくは思っている。菊生先生のあの節ならわかっている、思って安心している人がいるかも知れないが、三年謡えば小学生、次は中学生、次は大学生へとお弟子さんが進むのと同様、教えるぼくのほうも絶えず変わっていくのだから、謡の心がわからなければ進歩しないのは当然である。
ぼくも月謝をとっている以上、是非ともうまくしたいと思って努力しているが、上手にしようと気が入る余り怒鳴るわけで、ぜひかんべんしていただきたい。
仕舞いも型や筋を覚える体操がすんだら、、自分が演技しているのだということに気がついてほしい。仕かけ、開きを正しくやっているというだけではつまらない。自分は女なのか男なのか?長年やっていてそれに気のつかない人もあるようだ。
ぼくが願うことは、どのお弟子さんも舞ながら何かほのぼのとしたものを感じさせて欲いということ。品位高く、ほのぼのとしたお色けをもって舞って欲しいということである。そのために絶えず持っていてほしいのは情感である。
私もこの年になって、やっとほんとうの色けになってきたような気がしている。若い頃色けと思ったのは、サービス過剰のエロケだったのかも知れないと思うと、弟子にばかり注文をつけられないが、ここで心機一転、最近舞ってきた人情物の曲を離れて、自分を鍛え 直そうと思う。
そこで来年正月に脇能の「玉井」を舞うことにしたが、ぼくが畳の目ほどか、畳の縁ほど進んだか、皆さんでぜひ見きわめていただきたいとおもう。
伝書から投稿日:2018-06-07
伝書から
粟谷能夫
 伝書とは有り難いものだ。平成15年、秋の粟谷能の会にて演じた『藤戸』「子方出」の小書において考えれば、常には登場しない子方(漁夫の子)を出す演出となる。前シテの謡「生き残りたる母や子をも、問い慰めてたび給はば。少しの恨みも晴るべきに…」による根拠からのもので、多分下掛りにしかない演出だと思う。
伝書とは有り難いものだ。平成15年、秋の粟谷能の会にて演じた『藤戸』「子方出」の小書において考えれば、常には登場しない子方(漁夫の子)を出す演出となる。前シテの謡「生き残りたる母や子をも、問い慰めてたび給はば。少しの恨みも晴るべきに…」による根拠からのもので、多分下掛りにしかない演出だと思う。
家の伝書には「藤戸、子方出ル事、装束常ノ如シ、子方着流シ女出立、一声子方先二出ル、子方要ノ松ノ辺へ行ク時、シテ跡ヨリ此の島のト子方二謡掛ケル、子方立帰リ(さん候お着きと申し候)ト謡ウ、皆人のト、シテ正面向キテ立チ…」と書かれている。
今回の『藤戸』は私にとって二度目でもあるため前々からの念願であった「子方出」の特別演出で勤めた。「子方出」の演出は昭和38年に先代喜多実先生が能に親しむ会で子方、粟谷明生で演じられて以来のことではないだろうか。
伝書の型付の中には舞台での細かい動きまでは記されておらず、よって読み込んで自分で考え創らなくてはならないところがある。実はここに舞台づくりの喜びがあると思っている。決められたものをただ真似るのではなく、作り上げる、生み出す力が大切だと思う。
今回、面の選択は前シテは二十歳あまりで戦の被害者として無残に殺された漁夫の母という設定である。孫を連れての登場ともなれば、それなりの年齢が想定でき、曲見、姥、痩女などが考えられ、鬘も常の黒い鬘、姥鬘、老女鬘などと選択肢は増える。装束の付け方も着流、姥着け、水衣姿といろいろ考えられ迷うところだ。
子方を出す意味とは何であろうか。孫を伴って出ることで、不当に殺された子どもの親や家族の悲しみが際立つのではないだろうか。
子方にどれだけの演技を求め、常の演出の何処を工夫すればよいのか、いろいろ悩み試行錯誤し稽古にはいったが、それが能役者の楽しみだと感じている。
演能後、前記の実先生の『藤戸』の写真を何枚か見る機会を得ることができた。橋掛の一ノ松にシテ、二ノ松に子方が二人並び、シテは痩女厚板着流姿で子方は女唐織着流姿の出立ちのものが二枚であった。また残りの写真には曲(クセ)の最後に子方の所作があったようで、シテに縋る子方の写真は僕のかすかな遠い記憶を少し蘇らせてくれたみたいだ。子方を出す演出一つにもシテの思いや考え方により、様々なやりようが成立すると思う。伝書、型付は大いなる根拠であり、役者を型に縛りつけるものではないと思う。
演者が舞台を作り出すためには、伝書とはそのシナリオ作りの大事な注釈の一つではないだろうか。謡本という台本に伝書という型付や心持ちが、被さり一つになる。そこには先人達の工夫や失敗もある。それらを生かすも殺すも役者の精神性で有り、探求心ではないだろうか。
能に対する考え方は人様々だが、先人の後をなぞるだけではなく、今生きている自らの思考や価値観を作品に吹き込んで大きく豊かな能を創造していきたいと思っている。
写真 『藤戸 子方出』 シテ 粟谷能夫 撮影 石田 裕
『藤戸 子方出』 シテ 喜多 実 子方 粟谷明生 撮影 あびこ
 |
 |
|||
 |
 |
 |
||
生命の輝きと息吹投稿日:2018-06-07
生命の輝きと息吹
粟谷能夫
 萌え出ずる新緑の山々を見ていると、生命の輝きや息吹といったものを感ずるとともに、ほっとするような安心感にとらわれます。これは我々日本人の持っている共通の感覚といっていいでしょう。もしかしたら農耕民族として主に草食であったことの記憶であるのかもしれません。
萌え出ずる新緑の山々を見ていると、生命の輝きや息吹といったものを感ずるとともに、ほっとするような安心感にとらわれます。これは我々日本人の持っている共通の感覚といっていいでしょう。もしかしたら農耕民族として主に草食であったことの記憶であるのかもしれません。
昨年の十月に菊生叔父を失いました。当初は突然のことで色々対応に追われて時を過しておりました。今年になり大きな喪失感に見舞われています。
父新太郎の亡くなったときは、長期療養でもあり自然と覚悟ができておりました。とても悲しくはありましたが、又一面では、今こそ私の時代が来たような、ようしがんばるぞというような気持ちになったことを覚えています。今回の菊生叔父の死はあまりにも突然のことで驚くばかりでした。昨年十月三日(火)にNHKにて番囃子「頼政」の録音をし、おれが死んだときの追悼番組に使うために録音するんだろう、などと冗談を云っていた菊生叔父の姿が頭に残っていて、離れません。二日後に倒れるなどと信じられない・・・、それほど元気でした。
粟谷能の会にとりましても、父新太郎と菊生叔父の功績は多大なものがありました。祖父益二郎が亡くなりました後、二人で、益二郎追善として粟谷兄弟能を立ち上げ、それが粟谷能の会となって、今日に至っております。
粟谷能の会の牽引者であった二人を失い戸惑いは隠せませんが、新太郎、菊生がやってきたように、これからは、能夫と明生で責任を持ってやっていけということだと自覚して、本年を迎えた次第です。そして今、命の輝きや息吹に後押しされ、励まされているようです。
能は人間の心にうったえかける芸能だと感じています。人の生き死に、愛と別れ、執心と救い、人間のあらゆる情念に深く分け入り、それを詩情豊かに美しく、ときには激しく、描き出してきました。長く伝わる型のなかには、それらのさまざまな人間の感情や運命が宿っています。演者は型の動きを真似るだけでなく、型にこめられた、曲の本質を自らの肉体を通して発露するという作業をしなくてはならない、そうでなければ観客の心を動かすことはできないと思います。人間の心に強く訴えかけ体感の残るような舞台をめざさなければと初心を新たにしています。
十月の粟谷能の会は粟谷菊生一周忌追善として、明生は『三輪』(神遊)、私は『石橋』とそれぞれ大曲に臨ませていただきます。父や叔父の志を受け継ぎ、全力で取り組みたいと思っております。
今後ともよろしくご支援のほどお願い申し上げます。
写真 定家 シテ 粟谷能夫 粟谷能の会 撮影 石田 裕
舞の寸法(構造)投稿日:2018-06-07
能の舞は地謡に合わせて舞うものと、囃子方の演奏に合わせて舞うものがあります。
ここではお囃子に合わせる舞の寸法(構成)をご紹介します。
舞は正式には五段ですが、但し、近年は省略して三段で演じる場合が多くなりました。
今回は、三段の寸法での舞の構成をご説明しましょう。
舞は次のようなブロックで構成されています。
掛り(かかり)→初段(しょだん)→二段(にだん)→三段(さんだん)。
まず掛りと呼ばれる、0(ゼロ)段があり、「天」「地」「人」でご紹介したように、左回りで三角形を描き、「人」で大小前に戻ります。
次に初段(一段)、二段、三段と進んでいきます。
「今日の舞は三段でお願いします」とか「すいません、五段でお願いします」
と、シテは予めお囃子方に伝えておきます。
この三や五は段の区切りのことで、舞自体のブロックは、「三段」なら0,1,2,3、の4ブロック、4段構成となります。
ここで能役者の心のうちを披露すると
掛りは、「天」・「地」・「人」の項目で説明した通り、翁の舞を基盤にした儀式的な要素が含まれているため、演者は曲趣に沿った舞を舞う、という意識よりも、舞をはじめるプロローグ・序曲のつもりで舞います。
本来の役になりすまして舞いはじめるのは、実は初段からです。
つまりゼロ段は数えない、そのように私は解釈しています。
我流『年来稽古条々』(31)?研究公演以降・その九?『歌占』『求塚』について投稿日:2018-06-07
明生 今回は秋の粟谷能の会(平成二十四年十月十四日)で取り上げる曲目について話していきましょう。
父・菊生の七回忌追善能です。能夫が『歌占』、私が『求塚』を勤めることになっています。
能夫 もう七回忌、早いね。追善能だから、菊生叔父の好きだった曲をやろうということだね。まあ、追善と称して大曲を勤めたいという気持ちもあるし、時間的なバランスも考えてのことだけれど。君が勤める『求塚』は、菊生叔父が、好きだったねえ。『歌占』が好きだったというのは意外に思われるかもしれないけれど。
明生 『歌占』も好きでした。現代物もやれば、切能もやる、なんでもやるオールマイティの人でしたから。
能夫 そうね。何でもやるという自負があったよね。
明生 『歌占』は舞の型がよかったですね。
能夫 技というか。地獄の曲舞なんかすごい型の連続でしょ。謡の力も考えていたかもしれないけれど、そういう技で思いを表現するというのがあったと思う。
明生 曲(クセ)はいろいろな地獄の有様を型で表現しますが、なにしろ型の切れがよく格好良く見えて憧れました。
能夫 最初の菊生叔父は白垂れではなくて、尉髪を巻き上げる『春日龍神』の前シテと同じような格好だった。尉髪をグルグル巻きにして翁烏帽子に入れ込んでしまうやり方。
明生 鏡の間で自分の顔を見て「直面は嫌だ、もう一度やり直したい」と言っていましたよ。
能夫 そう当時は直面だったよね。いつ頃の事かな。
明生 父が五十代の最初かな。
能夫 そのくらいだね。『歌占』はあまり若いころにはやらせない曲だから。相応の年にならないとできない。菊生叔父以降、直面で『歌占』をする人、見たことないなあ。
明生 『歌占』は、一度死んで三日後に蘇生するわけですが、演者の生な顔で演るより面をかける方が似合うと思いますよ。父の『歌占』が面をかけるかかけないかの境目ではなかったでしょうか。
能夫 それから『歌占』は仮面劇になったね。

明生 『歌占』はいつ演られましたか。
能夫 喜多会(昭和六十三年)で披いて、今回が二度目。白垂れで勤めたね。『歌占』といえば、やっぱり憧れがあったよ。実先生が主催された能に親しむ会で、初めて寿夫先生をゲストとしてお迎えしてね。実先生が『歌占』で、寿夫先生が『羽衣』。そのときの実先生の『歌占』がすごかった。
明生 どのようにすごいの? テンションの高さ?
能夫 そう高くてね、それに憧れたんだよ。舞の技にね。喜多流というのは型でものを表現するという指向が強いでしょ。実先生の舞の型はすごくてね。あのときの装束は流儀にある替えの装束だったね。巫(みこ)とも違う、神官とも違う、魔法使いのおばあさんみたいな設定なんだ。烏帽子も翁烏帽子ではなく 後折烏帽子で。
明生 まさに男巫という感じですかね?
能夫 そうね。あの格好は、もしかして芸能として使っているのはうちだけかも。あの実先生の舞台を観たとき、『歌占』って、目指す曲だなと思ったよ。
明生 地獄の謡や曲舞もあるし。
能夫 僕も若かったから、そういうところまでは見えていなかったけれど、とにかく格好いい、颯爽としているなって。何かお能の究極でしょ。現実にないものを見せる、生と死の極みのようなことを伝える、ああいう仕掛けは。
明生 歌舞伎役者さんが踊り中心の曲があるって言っていたけれど、この間私が勤めた『百万』などまさにそれで、狂女は止まっていないわけですよ。車の段、笹の段、法楽の舞と、ずっと舞いっぱなし、動きっぱなし。『歌占』は、男舞などの舞はないし、説明的なところもありますが、地獄の曲舞が見せ場ですね。最初は床几にかけていますが、次第に動きか活溌になり、地謡も共鳴して、わーっと謡う。こういうところが喜多流には合っているなと思いますね。
能夫 『歌占』という曲は、謡や仕舞、舞囃子を稽古していると、憧れるんだよね。要するに青年が目指す輝ける曲だったんだ。あそこに早く到達してみたいという目標だね。
明生 技術がある水準まで到達していないとできない。やりたいと言っても、腰が入っていない、シカケ・ヒラキもできない者が何を言っているんだと言われる。言われないために頑張ったというね。
能夫 技術オンリーでもだめ、思考オンリーでもだめ。両方がそろっていないと無理だと、昔から思っていた。うちでは技術的な極致とか言われるけれどね。
明生 喜多流の能楽師として芸の習得過程を山登りに例えると、第一ベースキャンプがまず『歌占』。これがきっちりと出来ていないと次のキャンプに行けない、という気がします。型を重視する喜多流ならではの意識、ここをちゃんと表現出来て、それで、次の第二ステップ、アタックキャンプに向かうわけです。
能夫 それに戯曲的にも面白いしね。
明生 世阿弥の息子、元雅の作品ですから。元雅の作品といえば『隅田川』『盛久』『弱法師』、どれも生と死を突き詰めて描いています。暗いけれど情念が燃えている。『歌占』のように、一度死んで三日で蘇生するなんてリアリティがないように見えますが、現代だって、死にそうになるなど擬似的に死を経験することはあるわけで、そういう意味では全くリアリティがないわけではない。地獄の曲舞で地獄をリアルに描いていながら、救いはないかというと、親子再会で生への希望を描いてみせる。
能夫 技だけではない、そういう戯曲も理解しないと。大
人はね…。
明生 『百万』にしても『三井寺』にしても、狂女ものは親子再会はとってつけたような感じでしょ。でも『歌占』はそうではないと思うんですよ。私も自主公演(平成十二年五月)で披いて演能レポートにも書いたのですが、『歌占』は地獄の曲舞がいいといいながらも、親子の再会をしっかりと描かないと、曲舞が希薄なものになってしまう…。
能夫 普通、狂女ものは最後に再会劇をもってきてシャンシャンとなるけれど、『歌占』は占いをしてすぐに再会させてしまう。順序が逆転しているから、面白いよね。
明生 「金土の初爻を尋ぬるに」から占ってすぐ再会です。再会で盛り上げておいて、じゃあ、地獄をお見せしましょうと曲舞に入るわけです。その次元の違いみたいなものを演じ分けないといけない。
能夫 その進行の難しさだね。
明生 さて次は『求塚』に入りましょう。父菊生の最後の『求塚』は大槻自主公演でした。

能夫 昔、梅若学院での舞台を僕は観ている。菊生叔父は結構この曲好きだったでしょう。痩女物への憧れってあるよね。
明生 痩女物は、春の『求塚』、秋は『砧』と言われていますね。今回は秋に『求塚』になってしまいましたけれど。
能夫 まあ追善だから、許してもらおうよ。
明生 私たちは地謡の充実を目指してということで、平成五年の研究公演で『求塚』をやりましたね。
能夫 友枝昭世師にシテをお願いしたね。
明生 私自身は新太郎伯父のツレをやらせてもらい、いろいろな方の地謡も謡わせていただき、諸先輩の舞台を拝見していますが、なかなか難しくて、どこを、何を狙って何をするんだというようなことが…。先日観世清和氏の舞台を拝見しました。喜多流は太鼓なしですが、観世流は後場が出端となり太鼓が入りますね。太鼓があると苦悩の激しさが強調されますね。
能夫 先人の能、他流の能も見て、研究公演で地謡を謡いと、経験を積み重ねている中から、自分の能ができてくればいいんじゃないのかな。
明生 私、『定家』をやらせていただき順番が違うかもしれませんが、自分なりの『求塚』をと思っています。父の追善ではありますが、父の通りというわけにいかない…。
能夫 それはそうだよ。教えられたものに自分なりのものを何パーセントか足していく。それができることこそ追善になると思うよ。たとえば、父たちは痩女物の足の運びは地獄の有様をいかにも剣山の上を歩む心で、いかにも大袈裟に痛い、痛いみたいな足の運びをしていたけれど、あれはやり過ぎだと思う、とかね。明生 型付通りにやる、それに対する疑問とか、そういうことは父たちの世代は許されなかったから。プレーヤーはまずコピーからだから、何も疑問をさしはさまない。でも、それは三十五とか四十歳ぐらいまで、四十歳過ぎたらコピーだけではつまらない、いけない、と思うのです。
能夫 そのためには、蓄積が必要なはずだよね。伝承ということもあるけれど、自分なりに調べたり、能動的に取り組んだりしてきた軌跡ね。
明生 全部親たちと同じことをするのではなく、かといって、全否定するわけではありませんが…。
能夫 それでいいと思うよ。ところで、『求塚』という曲は前は若菜摘む段と独白の場があり、中入りして、後は地獄めぐり。若菜を摘むところはすごくいいよね。君がためにと、何か思う人のために若菜を摘む。それは神聖な行為であるし、季節の喜びもある。雪が溶けてきて、燃え立つ春を迎え、生命の復活を思わせる。その後で苦悩を見せる、あのギャップの作りはうまいと思うよ。
明生 劇作家のうまさですね。ツレの若菜摘みの乙女が帰った後に一人残るシテ。求塚のいわれを語り始めますよね。そして「その時わらわ思うよう」と一人称になるところから場面転換が起こります。冷静にいわれを語っていたのが、自分のこととなって気持ちが高ぶってくる。
能夫 恐ろしいよね。ここで印象が変わる。技術的にも変わらなければいけないからね。
明生 心してやらないといけないですね。少し演じるイメージがわいてきました。主人公の莵名日処女は、二人の男性に愛されて、どちらとも選びえず、入水してしまうのだけれど、この主人公をどのあたりの人種とみて演じたらいいのでしょうかね。
能夫 普通の女じゃないだろうね。
明生 豪族の女?
能夫 あるいは巫女というか、そういう特殊な能力をもった人かもしれない。他県の人が取り合うわけで、同じ村の中で戦っているわけではないでしょ。だから土地の田舎娘ではないよね。巫女とか、その人を獲得することで村が繁栄するとか。懸想されるほど美人とか。何か見込まれるだけの設定がないと。
明生 それにしても、どうして菟名日乙女はあれほどの地獄の責め苦を受けなければならないのか。二人の男のどちらかを選ばなかったから? 選ぶために鴛鴦を殺す結果になったこと? 入水したことで、後に二人の男が刺し違えて死ぬことになったから?
能夫 すべては美しすぎることが罪なんだよ。男を惑わせる罪。昔は宗教的にそう考えるところがあったと思うよ。『求塚』は煩悩と執心を凝縮して描いているんだ。だから前の早乙女が美しければ美しいほど、地獄の責め苦がリアルになって迫ってくる。
明生 だから痩女物であっても、どこか美しさをにじませるものであってほしいと思います。今、後シテの「痩女」は、私のイメージで打っていただいているところです。今回は『歌占』も『求塚』も地獄を見せるところが共通していますね。今はそう地獄をリアルに想像することがありませんが、昔は地獄をリアルに見せることで、今をよりよく生きなければということを教えたのでしょうね。
能夫 あの時代は、源信の「往生要集」から始まって、地獄がものすごくリアリティあったと思うよ。今の時代はいろいろあっても、本当の地獄を想像していないでしょ。中世は四条河原に死者が累々とした時代で、悲惨さが違う。
明生 生き死にが身近にあった時代ですよね。
能夫 地獄めぐりというのは能の本質でもあるよね。本三番目ものだって、直接地獄が描かれていなくとも、みんな地獄をめぐって、現れてくるんだからね。執心をもった人が地獄の責め苦にあっても、どうしても思いを伝えたいと、現れて訴えるんだ。
明生 能は、そういう思いをもって死んで行った人への鎮魂の芸能ですからね。
能夫 そういう意味でも、今回は、追善能として精一杯勤めたいね。
明生 七回忌というのは死後丸六年ですよね。皆様にも言われたのですが、親のありがた味が分かってくるのは五年過ぎてからだよと。それが何となくわかります。一周忌や三回忌ではまだそこまでの余裕がなかったけれど。
能夫 そう。父たちには負けたくないけれど、父たちの理屈じゃなくテンションの高さを特徴とする能も、やはり説得力があったね。でも僕は僕なりのスタイルでいきたいな。
明生 父は良いと決まるとそのスタイルを本当に変えなかったですね。装束も然り、面もいつも同じものを愛用しました。自分なりの完成パターンを確立したというのでしょうか。踏襲している。「変えなくていいの、それが良ければ」、そんな風に話していましたよ。私はだめですね。ちょこちょこ変えたがる、もっと泰然自若と、なんてご忠告を受けるのですが、この性格変わらないですよ。
能夫 それでいいんじゃないの。生きている以上は変わろうよ、進化しようよ。世阿弥も花と面白きと珍しきは同じ心と言っているよね。いつも同じではダメだと戒めている。
明生 父たちは父たち、私たちは私たちのやり方、その時代時代に適応した生き方でいいでしょう。
能夫 今回特に菊生叔父が大事にし、また好きだった曲を演るけれども、前の時代の単なるコピーではない、私たちがどう勤めるかを是非観ていただきたいですね。
明生 そうですね。頑張って勤めましょう。
(つづく)
写真 「歌占」シテ:粟谷明生 子方:粟谷尚生 撮影:石田裕
写真 「求塚」シテ:粟谷能夫 撮影:三上文規
『采女?佐々浪之伝』に取り組んで投稿日:2018-06-07
『采女?佐々浪之伝』に取り組んで
粟谷明生
 研究公演『采女』を終えて、あー終わってしまったのだという、やや放心したような気分を味わっています。それは、今回の『采女』は先代・十五世喜多実先生の創案された『采女?佐々浪之伝』に、新しい試みを加えてみたいと、一年間自分なりに思いをめぐらしてきたからです。
研究公演『采女』を終えて、あー終わってしまったのだという、やや放心したような気分を味わっています。それは、今回の『采女』は先代・十五世喜多実先生の創案された『采女?佐々浪之伝』に、新しい試みを加えてみたいと、一年間自分なりに思いをめぐらしてきたからです。
能は長い歴史の波に洗われながら、なお変わらぬ様式美を保っていて、それを継承する私たちは、その本流をしっかりとらえて伝えていく役目があるのだと思っています。とは言っても、今に生きているものが、一つの能を自分なりに解釈し、新たなものを創造する努力をすることも必要ではないか、これまで伝えられてきた本流も江戸時代のそのままの姿ではなく、少しずつ形を変え、時代にあった能を創り出してきているのだから──こんなことを考えて、七年前から能夫と「研究公演」なるものを始めました。
今回第八回・研究公演(平成九年十一月二十二日、於・十四世喜多六平太記念能楽堂)も、「研究」と名がつくだけに今までのものとはちょっと違うものを志向したい、伝統の中の自分らしさを求めてみたいと考えました。
まず、何を演じるかから始まりました。その前の研究公演で第六回に私が『松風』、第七回に能夫が『小原御幸』と、それぞれ一回ずつ大曲に挑みました。今回は二人で、どうしても気になる曲をやろうということになりました。能夫の『景清』は、早く自分なりのものを手がけておきたいとして、すんなり決まりました。では私はどうするかというとき実先生の『采女?佐々浪之伝』が思い出されました。過去に演じられて、演出方法に対するいくらかの疑問や曲の構成上の散漫さを感じていたので、これに挑戦してみようと考えたのです。
全体の流れはこれでよいのか、散漫さをぬぐうにはどうしたらいいか、『采女』は何が言いたかったのだろう。他流の人の演じる『采女』を研究してもみました。
そんなあるとき、家の伝書にある『采女一日曠れ也』という一文を見つけ、これがキーワードになると感じました。采女は帝の寵愛を失って猿澤の池に入水自殺します。一旦は地獄道に墜ちますが、功徳により成仏でき、一日、水の世界からこの世に現れて、その喜びを舞い、再び猿澤の池に消えていきます。この世に現れた一日は、采女にとってまさに晴れやかなときだっただろうと思うのです。私は『采女』という能で、その晴れやかさと、極楽浄土に向かっていく美しい様を見ていただきたいと思いました。
こう考えて詩章を見ると、前シテ・里女が旅の僧を猿澤の池まで導いて、入水の事実を知らせるまでに、延々と藤原家が建立した春日明神の由来や春日野の春の美しさが謡われていることが気になりました。当時は、権勢をふるっていた藤原家を讃える必要があったかもしれませんが、今、采女の悲劇を謡うときに、それがどれほど必要でしょうか。散漫な印象を受けるのはこのあたりにあると考え、できるだけ春日明神のくだりを省いてみました。
詩章を削除するにあたっては、野村万之丞さんに替間をつくっていただきました。猿澤の池の情景描写を少し書き加えるなどして、詩章の一部が省いても話がスムーズに流れるように、苦心していただきました。私がイメージしていた流れに仕上げていただき感謝しています。
序の舞についても手を加えてみました。『小波の伝』の序の舞では、後半に長絹を脱ぎ捨てて、裳着胴(下着姿)になって舞うという演出になっています。この姿は竜女になって解脱していく様を表しているのでしょうが、私は序の舞の中で、物着(装束の着脱)をしたくありませんでした。采女にとって「曠れの日」の舞なのです。舞っている間は、ただひたすら美しく、きれいで透明感があって、一段も二段も高みに浄化されていく女性の姿を描こうと考えました。笛の松田弘之さんにお願いして、序の舞の導入の部分には「干の掛」(笛が干の手より吹き出す)を入れていただき、内面的な充実感を表現していただきました。それでも、竜女というイメージもどこかにひきずっていたいという思いもあって、長絹の下に、細かい鱗模様の摺箔を着てみました。
装束についても、伝書によると、「采女の後シテの装束は萌黄または茶色大口袴を使用するが、帝に愛されたご褒美なのか一日だけいい想い(一日曠れ)をと、高位の序で緋の袴をつける習いがある」といったことが書かれています。袴が萌黄や茶色では、もとより私のイメージに合わないのですが、先輩たちが緋の袴で演じている姿を見ても、それでよいとする拠り所となるものがありませんでした。今回、先の伝書にこの「習い」があることを知って、自信を持って袴を緋にすることができました。
面は新潟の吉川花意氏にお願いして打っていただきました。かわいらしい小面では、采女の心情を表現できないのではないか、この世界に現れた一日は晴れやかな一日には違いないのですが、入水した罪業の意識をどこかに引きずっていて、心の底にはわだかまるものがあるという。わずかに苦渋を含んだ面をつけたかったのです。家に代々伝わる古面は誇りで、その中から選ぶこともできたでしょうが、研究公演でもあり、創作面に挑戦してみたのです。
このように、今回の『采女』は新しい試みをいれましたので、先代の実先生の「小波の伝」の名称を、あえて創案当初の「佐々浪之伝」として演じさせていただきました。能楽師は考え過ぎるとろくなことはないと諸先輩から御批判いただくことになるかもしれません。しかし「佐々浪之伝」を再考するという試練の中に自分を置いてみて学ぶことが多く、充実した一年を過ごせたと思っています。振り返れば反省する面も多々あり、諸先輩や観てくださった方々に、この試みはどうだったかを問うてみたい、それらを次なる能への糧にしていきたいと考えています。
我流『年来稽古条々』(16)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(16)
青年期・その十
『道成寺』を終えて
粟谷 能夫
粟谷 明生
明生 前回は、『道成寺』は若さの限界に挑む曲であったけれど、それはあくまでも通過点、その結果云々ではなく、何をつかむかが重要だという話になりましたが、もう少し踏み込んで話してみたいと思います。
能夫 『道成寺』のすぐ後は、何か後遺症みたいなものが残ったね。体の後遺症もあるし、いろんな意味での後遺症。一年以上かけて、あれだけ謡って体を使って、曲に集中しているわけだから、ダメージも受けるし。それでわかったこともあるし、やれなかったなという思いもあるし…。
明生 それはありますね。『道成寺』の演能後は、当時、実先生がご健在でいらっしゃったので、秋に『湯谷』、翌年には『東北』を舞うようにとご指示がありました。それで青年喜多会を卒業させていただいたわけでして。
能夫 僕もすぐに『湯谷』だな、翌年に『八島』を、その次の年、昭和五十六年には喜多会に入った。『道成寺』で清姫の怨念のすごさ、体も使い謡に磨きをかけ、劇的な極致みたいなものに挑戦したわけでしょ。だからその後は、少し路線を変えた方がいいという考え方があるようだよ。高林白牛口二氏に「『道成寺』の後は『芭蕉』を舞え」という教えがあると聞かされたね…、心・体のスイッチを入れ替えるという意識かな。でもまあ三十歳で『道成寺』を披いて、すぐ『芭蕉』というのもね…。
明生 『芭蕉』ですか。以前野村四郎さんに、この話をしましたら、「主旨はわかるね、でもそれならば『東北』でいいんじゃない」とおっしゃられた。同感ですね。
能夫 そういう曲でリセットするというか、激しい曲をやった後は夢幻能に帰れというか。精神的にあまりドロドロしないものにする、お口直しだな。
明生 お口直しですか…。
能夫 『道成寺』の後、意識したのは、やっぱり謡だな。『道成寺』では、道行も和歌も、聞かせどころでしょ。そこを謡うときに自分で何か際立たせる作業をしなければいけないと思うな、自分に付加するプラスアルファーがないといけない、何か探らないといけない気がしたね。それまで修業してきただけのことでは獲得できない何かが必要だということを感じたよ。そういうことは思いもよらないことだったからね。もちろん一所懸命稽古はした。そうしていれば自然とできると思っていたからね。
明生 そう。生意気とお叱りをうけるかもしれませんが、流儀の指導法に限界があるのではないでしょうか。内弟子時代、謡の稽古が少なかった、もちろん団体での稽古はありましたが、それは暗記力テストでしかなかった…。もちろん若いときに沢山の謡を身体にたたき込むことは大事ですが、もう一歩踏み込んだ謡で世界を表現する学習があってもいいでしょう。まず、声の出し方から始まり、言葉の詰め開きの程度や、感情の入れ具合、祝言、恋慕、哀傷、恨みなど役や曲に沿う謡の稽古が当然必要です。しかし残念ながら流儀には、そのような慣習がなかった。それは先代実先生が型重視のお考えで、謡にさほど拘りがなかったからだと思います。現実に『道成寺』を勤めるまでは、謡のことはさほど注意されないのに、『道成寺』や『葵上』になると、急に謡のまずさを指摘される。体力的にもきびしい緊張感の持続の中、いきなり謡へのプレッシャーという新顔が入り戸惑うわけです。私も散々言われ、書かれもしましたから、かなりへこみました。
能夫 『道成寺』では謡について言われることが多かったね。身体的にはまあまあなんだよ。披きだから緊張感もあるし、ある程度動きは御せるけれど、謡は・・・。
明生 謡は難しいですね。でも基本は二曲三体でしょ、その二曲舞歌も割合からいうと、七・三で謡ですから。披きの『道成寺』は、まずは型がきちんとできないといけないから、型を優先するのは仕方のないことです。謡は駄目でもともかく型はしっかり…と、これが現状ですね。
能夫 ただ間違わなければいい、つつがなくだけでは悲しいね。大曲の重圧だけで、その曲趣を考えないのはいけないよ。清姫の狂気、鐘への執心として出てくる根拠はこれだというぐらいのテンションのある謡い方ができないとね。テンションもない、張りもない謡い方では落第だよ。
明生 表現の幅は難しいです。絶叫だけではダメだし、押さえ過ぎて小さくなってはつまらない…。
能夫 そうそう、それでは届かない。それまでは、曲趣を考えるということに価値があるなんて夢にも思っていなかったよ。それが能であるとも思っていなかったからね。
明生 そう教えられていないから。『道成寺』を披くならまずは謡ってみろ、から始まらないといけないのではないでしょうか。でも現場はまずは一番を通してやってみろとはじまる。すると乱拍子がこうで、急之舞は、キリの型がこうでと教わる、謡の注意は後回し。本当はそこが大事なのかもしれないのに。
能夫 そこが問題だな。『道成寺』をやったことで、謡が課題ということがはっきり見えてきたということだろうね。曲を謡うということ、本当に曲を舞うことの大切さ。
明生 本当にそう思います。
能夫 それと前にも話したが、やっぱり新鮮なのは祈りだね。自分だけで作るのではなくて、相手があって、相手との力関係で行ったり来たりする、気のような・・・。
明生 そうですね。祈りは舞囃子の稽古では体験できませんから。『黒塚』や『葵上』といった能に携わらないとできませんね。
能夫 『道成寺』の後、明生君は妙花の会を起こしたね。
明生 そうですね。発起人になって。『道成寺』をやりだすと、お能は面白いと感じるようになって。演能するチャンスを多くしたいと考えました。
能夫 よかったよねえ。それを待っていたんだよ(笑い)。『道成寺』を舞って、行動を起こすエネルギーがふつふつと沸いてきたわけだ。妙花の会はいつからだった?
明生 『道成寺』の翌年、昭和六十二年です。青年喜多会引退が六十三年ですから、一年ぐらい二つの会がだぶっています。能夫さんは青年喜多会を卒業するとすぐに喜多会に入ったでしょ。
能夫 そうね。実先生がいらしたときの喜多会は、入れるというのがある面ではちょっと名誉なことだったからね。
明生 能夫さんのときはそうでしたね。私のときは実先生がご他界なされていたので、参加が自由でしたから、喜多会に入る前に少し考えてみよう、もっと個人的な会で活動してみたいというような思いがありまして。上の先輩方は果水会を作られていたので、その下の年齢の仲間で同志をつのってみてはと…。それで妙花の会を発足しました。 師や父が与えてくれるものだけでなく、自分で演能の機会を作り、そこで学ぶ必要が絶対あると思って…。
能夫 演能について積極的に意識するようになった・・・。
明生 『道成寺』を勤めてから、三役との交渉係をやるようにもなりました。それまでは、すべて人任せでしたから。
能夫 『道成寺』は親や流儀の人たちのお世話でやる、いわば「お任せコース」でしょ。
明生 『道成寺』を勤める前はそうでした。ただお能を舞っていればいいというものから、喜多内や囃子方の交渉からパンフレット類を作るところまでやるようになって。
能夫 ある意味では本当のお能づくりかもしれないね。制作ということかな。
明生 三十歳そこそこで三役の方にお願いするわけで、何だ若造が来てと対応されることもあり勉強になりました。
能夫 そういうことに耐えながら(笑い)、交渉の中で獲得していくものはたくさんありますよ。
明生 『道成寺』を終えると、能はシテだけではない、三役の方や喜多内も含めて大勢の人の力添えで一つの曲が創られていることを実感します。会を起こそうとしたときもそう。そういうことを通しても、お能の面白さと同時に、物事を立ち上げる喜びみたいなものを感じていったと思います。それが後の、小書の再考に挑むようになり、伝書を読むだけでは解決できないことを、三役にご相談したり、そういう過程からの曲づくりにふくらんでいきます。
能夫 明生君が『采女?佐々浪の伝』など、具体的に小書に挑戦していくのは十年ぐらいしてからでしょ。演出的な課題、伝書を読むことなど、謡の問題ももちろんそう、いろいろな課題が出てくる。それを具体的に実践に移していくには、『道成寺』から五年、十年と年月がかかる。
明生 最近『道成寺』を披くのが遅いから、課題に目を向ける時期がどうしても遅くなっている気がします。
能夫 その問題はあるね。でも長生きの時代だからいいのかな。いずれにしても、これは能役者としての一生の課題でもあるね。(つづく)
我流『年来稽古条々』(22)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(22)
稽古の原点を見つめる
粟谷 能夫
粟谷 明生
明生 子方時代から青年期へと、稽古を振り返り、『翁』まで話し合ってきました。自分たちの能を追及し、さらに大曲に挑むなどをしてきましたが、話はもう現在の私たちにまで迫って来ていると思います。そこで、時系列で語るところから一歩離れて、稽古そのものについて、原点に戻って話してみたいと思うのですが。
能夫 稽古の原点ね。世阿弥は『風姿花伝』で「稽古は強かれ、情識はなかれ」と書いているね。稽古は厳しく、そこに自分の情、つまり自分勝手な考えを入れるな、と。
明生 基本ですね。子供の頃の稽古は理屈ではなく、ただ教えられた通りに、無心に覚えることを第一としますね。父の時代も、我々の子供のころの稽古もまさにそうで、これからも変わらないと思います。強烈な叩き込みですね。
能夫 そうだね。基礎習得までは、あまり頭でっかちになってはいけないのだろうね。
明生 稽古方法は反復運動ですね。一言に稽古と言っても謡と舞とがありますが、子供の頃の謡は意味も判らず丸暗記です。でも、そこで覚えたものは大人になっても間違えないですね。四十歳越して覚えた『伯母捨』などもう綺麗さっぱり忘れていますよ。(笑)
能夫 子供のころの稽古というのは嫌とか、そういうことはなかったんじゃない。
明生 そうですね。余計なことは考えずに、親や先生に言われるままに、素直でしたね。
能夫 僕は稽古が苦にならなかったよ。お能が好きだったからね。わけが判らないうちに好きになっていたんだね。
明生 お能が好きになるような環境があったからじゃないですか。
能夫 親が意識したかどうかわからないけれど、好きになるような環境を作ってくれていたんだね。僕が子供の頃、ガラスの電灯の笠をめがけて『道成寺』の真似事をして駆け込んだりしていたらしいから。自分では覚えていないよ。
明生 私も腰に刀を差して風呂敷を身体に巻いて「うう??」と唸っては刀でお能ごっこをしていました。観世三兄弟(観世寿夫、榮夫、静夫)の先生方もそうだったといいますね。華雪先生に子供用の装束を作ってもらいお能ごっこ、ここまでくると位の違いを痛感しますね。(笑)
能夫 能舞台とか楽屋とかいろいろ連れて行ってもらったしね。そういう環境づくり、それも子供教育というか稽古の一つの形でしょうね。
明生 茶道の小堀遠州流の「稽古照今」という言葉が僕は好きで、古を稽(かんがえ)今に照らす、基本をしっかり踏まえた上で今の自分を輝かせる、そう解釈していますが、いい言葉でしょ。世阿弥の「稽古は強かれ、情識はなかれ」にも通じますね。ただ、無心に強く稽古をする・・・。
能夫 そう、稽古は強かれだよ。
明生 強かれ、固い感じがしますが基本ですね。自分の昔を思い出すと小学生までは波風たたないですむのですが、これが中学ぐらいになって声変わりして、思うように自分の声が出ない、お能というものは自分にとって何なのだろう、なんて思い出すと、ただ言われるままの稽古というものを考え始めるようになりますね。
能夫 そのころになると、いろいろな能にふれて、能の善し悪しが多少見えてくるわけだよ。格好いい人もいれば、ちょっとギクシャクしていると感じさせられるものも見えてくる。小学生の頃とはまた違う考えが起こるよ。自分もあの格好いい人を真似たいとか、確固たるものに近づきたいという発想が芽生えてくる。そういうものが自分のなかにはあったと思うね。そのために確かな技術を獲得したいと、ね。親に言われる押しつけではなくと、自分で思ったものね。
明生 それは反逆児の私からするとご立派!と尊敬しちゃいます。(笑) 私はそこまで至っていませんでしたから。指導についてですが、狂言方は生涯親子で稽古をするでしょ。耕ちゃん(故野村万之丞)が太良先生(野村萬)に習うことについての善し悪しを話してくれたことがあります。また武司君(野村萬斎)からも万作先生(野村万作)に習う心の内みたいなものを聞いたことがありますが、そういう家族主義というか、家族で伝承していく形態ができ上がっている。何歳頃には何を披かせ次は何、という道が確立しています。似ているようで私たちとは少し違いますね。若い時分は実先生(十五世宗家喜多実)にお習いし、お互い、小さいときは父親に習っているとはいっても、狂言方のようなアットホームなものとは違いますから。
能夫 親子での稽古法が確立していて、いい関係で出来れば、それはすばらしいと思うよ。しかし親に習うというのは案外難しい面もあるからね。僕が若いころに寿夫さんに憧れて、親父の能を否定していた時期があったし、明生君だって、親たちのやっている能に反発したことがあったでしょ。だから親以外の人に習うのも悪くはないし利点もあるわけ、他流に目を向けることも悪くはないと思う。僕も遠回りはしたような気もするけれど、お能のすばらしさをより強く知ったし、またそれがあるからこそ父たちの能を見つめることもできたからね。
明生 能夫さんの場合は遠回りでなく、もっとも近道したんじゃないの。(笑)
能夫 明生君も反発したけれど、力強く戻ってきたね。
明生 そこですね。戻れるかどうかですよ。私はうまく戻してもらいましたが・・・。狂言方の人たちだって親子で反発する時期はあると思うけれど、一緒にいなければ興業が成立しないから、何とか、悪い言葉ですが騙しながらもやって、そして成長していくのでしょうね。シテ方の場合は、その青年期を上手く乗り切れないで離れていく人も出てくるわけです。だから青年期の稽古というのは教わる方も教える方も難しいと思います。
能夫 その時期は辛抱強くね。他流に気持ちが行くならそれもいい。気持ちが離れる人には、いろいろな仕掛けをして、いい能にふれさせるとか、能に何らかで参加させるとか、他のすばらしい能楽師と話す機会をつくるとかね。明生君にも僕はずいぶん仕掛けをしたんだよ。
明生 ありがとうございます。能夫さんも辛抱強くですね。(笑)
能夫 純粋培養だけでなく、いろいろなものにぶつかって体験をして戻ってくるのもいいんじゃない。そしてまた、家の子でなくとも、逆に青年期に能にめざめて門をたたく人もいるわけでしょ。そういう人たちを受け入れる開かれた面もあるわけで、これからはそこを充実させなくてはいけないし。そこで内にいた人も外から来る人も刺激しあえばいいね。そして究極は、憧れの能に近づきたいという気持ちが大事でしょ。そうすれば自ずと自分で技を磨こうという気持ちになるし。そういう意味では指導者が憧れられるような能を舞っていなければならないということだね。
明生 父が「俺が演っていることが教えていること」って言っていました。手取り足取り教えるわけではないが、いい謡を謡い、よい能を舞う、それが指導だと。最初は何言っているんだ、逃げみたいな意見と思っていましたが、今はよくわかります。父はあのように謡っていたな、と思い出しますからね。
能夫 我々もそういうことが言えるような能を舞っていかなければならないね。
明生 基本的な技術、たとえば舞は型を間違えずに、謡は調子を外さないでうまく合わせるとか、そういうことが完璧に出来たとしても、そこで止まっていては駄目で、その次に何をすべきか、というと結局、そこは誰も教えてくれません。だからそこから先は自分で尋ねていくしかないわけで、それが大人の能役者の味わう一つ壁ですね。そこを乗り越える事が必要となります。まさに照今でしょう。
能夫 そうだね、それまで蓄積してきたもの、それに何かもう一つプラスする作業、そういう問題意識を持つことね。僕は稽古で一番大事だと思うことは、集中力の維持ということ。例えば、『半蔀』を稽古していると、ああ、ここからは序ノ舞だ、ここからはキリだと、それぞれのパーツはさんざん稽古を積んでいるわけですから、そこに来ると流してしまうことがある。
明生 ありますね。サシまで来ると、あとは舞囃子で演っているから大丈夫なんて、勝手に思ってしまい型附を読まなくなる。ところが、能では違うということもありますね。
能夫 そうなんだよ。座敷謡や座敷舞とは違う。実際、伝書に座敷舞ではこうだがお能ではこうだなんて書いてあって、発見があるよね。だからお能一曲を通じて、どういうふうに謡い舞うのかということを意識しないといけない。伝書を読んだり、過去の人の能を思い出したりして、自分自身のお能を創っていかなければならないからね。
明生 それはもう自分自身で創り上げていくしかない。特にある年齢になったら誰も手を差し伸べてくれませんから。
能夫 それでも明生君は友枝昭世さんに習って最終チェックをしてもらっているからいいじゃない。僕はそれがないから、親父が書いてくれたものや伝書を見たり、これまで自分がいずれはこうやるぞと思いをためていたものとか、そういう自分を信じてやるしかないんだよ。
明生 それぞれのやり方があっていいと思いますね。私は披『道成寺』の時に志願して友枝師についた、能夫さんは誰にも習わずに自分のスタイルを確立していく道を選んだ。能楽師は最善の方法を自分自身で選択していかなければいけないということでしょうね。今の喜多流はそこの自由があり恵まれた環境だと思います。
能夫 自己責任ということだね。僕だって自分勝手に演っているというわけではないよ。その都度、菊生叔父に聞いたり、友枝さんにも聞いたりして、そういうところはきちっとクリアして、自分なりのものをと考えているよ。先人が演ってこられたもの、そういう情報、それに他流の人と話したときに、知ったこと、そういう諜報活動みたいなこともして、自分の能を創り出す、足し算が必要なんだよ。
明生 自分から教えを乞う前向きな足し算ですね。三番目物は技術面をクリアー出来ただけでは作品を手がけたと言えませんね、『野宮』や『定家』など特に感じますが、三番目物には足し算が必須ということですね。
能夫 そういう曲にどう取り組むかだな。明生君がよくいっているけれど、大曲にも早く取り組むべきだって。
明生 少し背伸びしてやれるぐらいのときに一回勤め、それで二回、三回と演って完成させていく、それが能役者の宿命でしょ。それも稽古の一つ。
能夫 この間の『定家』を振り返るとね。披きのときは、憧れの曲、大事な曲に体当たりするんだという、すごい緊張感で構えていたよね。それが二度目になると意外とリラックスしてできるようになる。一度演って余裕みたいなものができるというか、成長できたというのかな・・・。
明生 無駄な力が抜ける?
能夫 そうね。一回目ではどう頑張ってもそうはならないからね。だから、年齢的にはやや若くてもできるときに積極的にやって、それでまたやり直しをするというのが本物の前向きということかな。
明生 時々の初心というのですかね。その時々に真剣に取り組み、そこにその時々の自分の能を創る。「稽古照今」という言葉いいでしょう。
能夫 「稽古照今」だね。僕ぐらいの年齢になると生きていることすべてが稽古という気もしてくるな。
明生 そうですね。その人の生き方、人生、経験がすべてお能に反映されるということをつくづく感じますね。
能夫 時々の初心をどう出せるか。お互いに自分の人生をかけて稽古しよう。お能はそれだけの価値がありますよ。
(平成19年10月記)
舞の型(進み方)投稿日:2018-06-07
舞の型(進み方)
舞の寸法では、掛りが儀式的な要素で「天」「地」「人」の三角形を描いて動き、初段からは役に似合った舞を始めるとご紹介しました。今回は図を参照しながら、初段から順を追って、舞い手の型、動きの順番をご紹介します。
注:型(進み方)は演者が正面席に向かっての動きとして記載しています。
まず舞の型附(かたつけ=動く順)は、正面先遠方に鎮座されていると想定する神に、
舞い手が徐々に近づく意識が基本理念です。
但し、いきなり神に直進して近づいては無礼になりますので、神社仏閣の参拝同様、鳥居・楼門や山門を越えて拝殿や本堂に辿り着くように、舞も回り道をしながら徐々に正面先の神に近づきます。段階を踏んで意図的にジグザグに回り道をしながら近づきます。
順路は下記の通りです。
図(掛り)
図(初段)
二段目では※のところで神に最も近づきますが、その後二段オロシで拍子を踏むと、以後は徐々に元の「人」(大小前)に戻ります。
図(二段)
最後の短い三段目の段では、目付柱近くで右手をカザス(高々と上げる)と、そろそろ舞も終わりとなり、大小前にて終了します。
図(三段)
クセの舞やお囃子に合わせての舞で、目付柱付近で右手を上げる型(カザシ)は、そろそろ舞を終わらせる、という舞い手の囃子方や地謡への合図です。この型を注意深くご覧になるのも、舞の進行の目安になると思います。
『道成寺』再び 粟谷明生投稿日:2018-06-07
『道成寺』再び 粟谷明生
平成二十六年三月二日(日)第九五回粟谷能の会(於:国立能楽堂)にて『道成寺』を二十八年ぶりに(初演・昭和六十一年三月二日)再演しました。
能『道成寺』は「安珍清姫伝説」で焼失した道成寺の鐘の後日談「鐘供養伝説」を元に観世小次郎信光が能劇化したものといわれています。安珍を登場させず、清姫の名前も明らかにせず、白拍子として設定し、鐘への執念をテーマにした能の大曲です。
まず今回使用した面と装束についてご紹介します。喜多流は、前シテの面は「曲見」、装束は「黒色丸尽縫箔」を腰巻にして「紅無鶴菱模様」の唐織を坪折(壺折)にするように伝わっていますが、近年、若年の者が初演で年増女の「曲見」を使いこなすのは難しいとの配慮から、「増女」に替える傾向となり、私の披きも「増女」で、それに伴い、装束は「紅入蝶柄模様」の唐織でした。今回は「曲見」も考えましたが、やはり、美しく若い女に拘りたく、面は「増女」系で唐織も紅入りとしました。面は世にも不思議な女、妖しげな艶と幾分ヒステリックな一面も出したいと、梅若玄祥先生より梅若家の名物面「逆髪」の写し「白露」臥牛氏郷打を拝借し、唐織は『道成寺』に相応しい貴重な色入唐織「赤地鱗地紋花笠に獨楽糸」を観世銕之丞先生から拝借しました。両先生には感謝の気持ちで一杯です。
では舞台進行に合わせて演能を振り返ります。『道成寺』といえば鐘ですが、この鐘の吊り方が上掛りと下掛りでは大いに違います。上掛りはあらかじめ狂言方の後見が作り物を出す心持ちで鐘を吊り、その後にワキが登場して能が始まります。それに対して、喜多流など下掛りはワキの登場後、狂言方が演技として鐘を吊るところに面白さが増します。吊り終わると、能力(アイ)は道成寺で鐘供養が行われ、女人禁制であることを、周りに「ふれ」伝えます。
そしていよいよ前シテの出となります。通常は習之次第と呼ばれる出囃子が数分間囃され、シテが姿を現しますが、今回は、次第のはじまりと同時に幕を上げ、すぐにシテが姿を現す替えの演出にしました。これは鐘への恨み、怒りを必死に抑えていた女が、鐘供養の「ふれ」を聞いた途端に、恨みのスイッチが入り瞬く間に出現したと思える景色にしたかったためです。より女の激しく昂ぶった精神状態を表すのに相応しい演出と思い、試行しました。
女人禁制であるから供養の場には入れぬと断るアイに、お構いなしに境内に入り込む白拍子。通常は次第も道行も本舞台にて行うところを、橋掛りで行い、アイとの問答をしながら、境内と考えられる本舞台に入る演出とし、白拍子の図々しさ、不貞不貞しさを表現したいと考えました。
能力のはからいで、シテは女人禁制の鐘供養の場に入り、舞人の象徴である烏帽子をつけて、いよいよ舞となります。はじめは遠くから鐘を眺めている白拍子ですが、鐘を見るうちに興奮し鐘の下に走り寄り「乱拍子」を踏み始めます。
乱拍子は白拍子の舞を模したもので、シテと小鼓の二人だけによる特殊な舞、シテ方は小鼓方の流儀に合わせて舞(型=動き)を合わせます。初演では幸流の亀井俊一氏のお相手で勤めましたが、今回は大倉流宗家・大倉源次郎氏にお相手をお願いしました。足の動き(型)は踵を上げ、次に爪先を上げ、横に向け、また元に戻す、という単純な運動の繰り返しですが、小鼓の呼吸に合わせ、立つ姿勢を乱さず足の動きだけで演じるには体力だけではない、技術力も必須と知りました。身体の堅さをとり、ほんのりと女らしい柔らかみを感じさせるスムーズな身のこなしを意識し取り組みました。幸流は掛け声と打つ音、その間(ま)を大事にし、自然と時間が長めになります。一方、大倉流、幸淸流、観世流などは掛け声を長く引く間に合わせて足を動かすため、掛け声が終われば次の動きとなり、乱拍子の時間は幸流より短くなります。今回、ご覧いただいた方から「乱拍子が短く感じられた」とのご感想をいただきました。これは本来八段であるものを六段に短縮したこともありますが、小鼓の流儀の違いが大きな要因だと言えます。
「乱拍子」の舞は単純な動きですが、これを演者はなにと考え演じるのか、なにを真似てなにを思うのか、そこの再認識が再演の課題でもありました。道成寺の階段を蛇のように這い上がる心持ちを足遣いで表現するとも、足拍子を踏む乱拍子という踊りのステップのようなものとも考えられます。私はその両方を思いながらも、もうひとつ、道成寺という土地や鐘への思いを抑えながらも、ついには爆発してしまう、女の心の中の葛藤であり、冷静と興奮の交錯のイメージで勤めました。
「乱拍子」の最後は「寺とは名付けたり」のシテ謡から大鼓も打ち出し、白拍子の思いは遂に炸裂し、速い舞「急之舞」に急変します。この舞も揺るぎの無い下半身としなやかな上半身の動きが必須で、剛柔のバランスをうまくとりながら、身体を乱すことなく俊敏な足さばきの中にも常に「女」を感じさせなくてはいけない、とは父の言葉です。
舞が終わり「春の夕べを、来て見れば」「入相の鐘に花や散るらん」と、シテと地謡は熱唱し舞台はクライマックス、鐘入りを迎えます。この曲最大の見せ場であり難所です。何度もリハーサルが出来ないので、まさに一発勝負です。喜多流は烏帽子を後ろに払い落とし、片手を上げて鐘を目掛け、後ろ姿を見せたまま、鐘の真ん中で二つ足拍子を踏み飛び上がります。これが鐘後見の鐘を落とすタイミングと合い、シテは頭を打ちながら姿を消すことになります。今回、鐘後見の大役を受けて下さった中村邦生氏が、よい具合に落として下さったので感謝しています。
初演の難関として鐘の中での着替えがあります。面を外し、唐織紐を解いて脱ぎ、般若を付ける。狭く暗い中での作業は不自由です。今回は垂れ髪を付ける新工夫に挑みました。般若の面は下から上へのベクトル、口も角も上に、鬘の毛も上に向けて掴み上げるが、それに対して垂れ髪は下への力が加わるので、上への力が半減されるような不思議な感じを受けたとのご感想をいただきました。なるほど、然りです。しかし、そのバランスを故意に崩し、怒るだけではない女の悲しみをどことなく感じさせられないだろうかとの思いで試行してみました。世阿弥の言う「してみて、よきにつくべし、せずば善悪定めがたし」の精神が私は好きです。まずは試してみて、ということでした。垂れ髪が流行るか廃るか、将来を見ていきたいと思っています。
後場は「あれ見よ蛇体は、現れたり」で後シテが姿を見せますが、後シテの面は喜多流では「般若」をつけます。蛇のようになってしまった女の恐ろしさを「蛇じゃ」という面で表現するのが順当とも言えますが、敢えて「般若」を使用するところに、そうならざるを得なかった女の悲しさがより強調されるのではないでしょうか。蛇体の女は大勢の僧に祈られて退散し、遂に日高川に飛んで消えます。近年、最後は幕の中に飛び入り幕を下ろして姿を見せない演出が普通となりましたが、我が家の伝書にはそれは替え演出であり、本来は橋掛りにて飛び臥し、その後立って入幕すると記載されています。このやり方は、死んだとは謡わない、もしかするとまた心のスイッチが入り現れるかもしれない、そのような悲しさ、終わりのない女の怒りと恨みをより一層引き立たせる演出と思い試みました。
能・狂言の世界では、大きな曲に挑み演ずることによって、能役者の成長の証を示す慣習があります。その中でも『道成寺』は筆頭で、披いて、はじめて一人前とみなされます。しかし、残念ながら披きは無事に勤めるという域を超えることは出来ないのです。『道成寺』という戯曲の大きなテーマを若さあふれる者が一回目で演じきることには少々無理があります。今回五十八歳の再演にあたり、初演では出来なかったことへの再チャレンジ精神で臨みました。それは緩みがちな私の精神と肉体に負荷をかける絶好の機会となり緊張の日々でした。その稽古の日々で、ふと見えて来たキーワードは「妖気」です。「美」と「妖」の交錯、相克です。「美」の静、と「妖」の動が、常にこの不思議な白拍子の女の魂を動かしているのではないか、と。そして、怒り爆発ギリギリの精神状態の危険な女をどう再演出来るかが、私のテーマとなりました。
作者の観世小次郎信光はお囃子事が達者な能役者だったようで、『道成寺』は信光らしい囃子方のパフォーマンスが遺憾なく発揮されています。観る者を飽きさせない、おもしろ演出満載の『道成寺』です。披きはこのお任せコースに乗ればよいのでしょうが、再演はこのコースをどのように扱うかが問われます。フィギュアスケートは技術点と芸術点で審査されます。能役者とアスリートは同じにはなりませんが、技術点の満点を目指すのが初演の披きだとすると、再演では技術点の満点は当然、芸術点に重きをおいて、両者の高得点でよい舞台を作るものなのです。
初心にもどり、『道成寺』が大勢の仲間の協力で出来上がるものであることを再確認し、仲間への感謝の気持ちがこみ上げてきたこと、NHKの公開録画という高いハードルの設定にどうにか応えられたことなど、充実感に浸っています。舞台を創ってくれた囃子方、ワキ方、狂言方、喜多流の地謡、後見、楽屋働きの仲間たち、観てくださった方々、『道成寺』にかかわったすべての人たちに感謝しています。*(「粟谷能の会」のホームページの演能レポートで補足&写真入りで掲載しています。ご覧いただければ幸甚です。)

『道成寺』 シテ 粟谷明生(平成26 年3月2日 粟谷能の会) 撮影:青木信二
「砧」を演じて─演出方法を考察する─投稿日:2018-06-07
「砧」を演じて─演出方法を考察する─
粟谷明生
父が正月一日に倒れ、一月三日の『月宮殿』、二月十二日の『砧』を私が代演することになりました。『砧』は大曲で、五十歳近くなってからでないと演じられないと思っていましたが、代演ということでやらせていただくことになりました。
『砧』を演じるにあたって、父からアドバイスも聞き、喜多流に伝わる伝書通りに臨んだのですが、演じなから、この演出方法では見ている人がわかりづらいのではと感じるところがありました。
まず気になったのが最初の場面です。喜多流の台本では、夕霧という女(ツレ)が登場して、芦屋の某(ワキ)の使いで、奥様のいる芦屋に向かうところである。某殿は訴訟のことがあって、三年あまり在京しているが、古里のことを心もとなく思われて使いにいけというので急ぎでやって来たという説明をしますが、他の流儀では、最初に芦屋の某自身が登場して、上京している事情を説明し、古里が心もとない、この年の暮れには必ず帰るから、そのことをよく心得て伝えるようにと夕霧に伝える場面から始まります。私は喜多流の台本ではあまりにもそっけなくて、夫(芦屋の某)の心情が理解されないのではないか、その後の妻の恋慕の情へとつながっていかないのではないかと思うのです。
世阿弥は『砧』について、「かやうの能の味はひは末の世に知る人あるまじ」と嘆いていると『申楽談儀』にあります。世阿弥がそれほどに深い味わいを込めてつくった曲ならば、単に帰らぬ夫への妻の恨みつらみの情念を際立たせて終わりといったものではないはずです。
夫は妻に愛情を持ちながらもどうしても帰れないという苦渋に満ちた立場にあり、妻の方も夫を思い、恋慕しつつ帰りを待っているという、お互いの愛情が底流にあることが感じられないといけないと思います。それがあるからこそ、孤閨をかこつ妻が、恨みつらみにさいなまされながらも、時には夫との思い出に浸り、帰って来てくれるならいつまでも添い遂げようというやさしい気持ちにもなり、最後には絶望の淵に落ちていくのです。こういう感情が織物の綾のように幾重にも交錯して深い味わいをかもし出していくのだと思います。
こう考えると、夫の愛情をどこかで表現しておきたいということになりますが、喜多流の台本では、最初に夕霧が帰れぬ事情を説明するだけで、そこには夫の妻への思いやりをほとんど感じることができません。夫の登場は、妻が絶望のあまり空しくなって(亡くなって)からです。夫は妻を弔うことはしますが、最初の伏線がないだけに、それは通り一ぺんの印象をぬぐえないのではないでしょうか。
世阿弥が「かやうの能の味はひ…」と述べるほどに、夫婦の愛情をベースに、それ故に地獄まで落ちるところを名文で謡い上げている『砧』。世阿弥自身が書いた曲のなかでとりわけ気にいっていた『砧』。しかし、世阿弥の危惧通り、しばらく演能されることはなく、江戸時代になってようやく復曲しています。その折に各流派が演出を考え、喜多流にも現在のような台本と演出方法が伝えられているわけです。今回私は『砧』を演じながら、この江戸時代の演出方法は、『砧』のテーマからしてやや説明不足ではないかと感じています。他流のように、最初に夫を登場させて気持ちを述べさせる場面が必要ではないでしょうか。
そして、『砧』では砧を打つことが重要なモチーフになっていますが、シテは妻がどんな気持ちで打っているかを感じながら演じなければならないと思います。蘇武の故事に自分の心境を重ね合わせて砧を打つことになったとはいえ、夫に柔らかい着物を着せてあげたいというやさしい心情があってのことでしょう。そこを伝えるには砧を強く打ってはならないのだと思います。世阿弥も「ほろほろ、はらはらと」と音楽的な響きで書き込んでいるところですから、柔らかく美しく響かせねばならないと思います。
夕霧が芦屋の某の妻に、殿は今年も帰れないと伝える場面の演出方法も気になります。その言葉を聞いて、妻は夫の心はやはり変わり果てていたのだと絶望し、病の床に沈み、やがて空しくなってしまうのですから、夕霧と砧を打ちながら、疑いと信頼との間を行きつ戻りつつしていた妻の心を切り裂く重要なひとことであり、時間的にも空間的にも場面転換があるべきところです。そこが、ただ夕霧が、今までと変わらぬその場で向きを直して伝えるだけの味気ない演出になっています。芦屋の某から使いが来るなどの説明描写は必要ないとしても、この大事な場面を鮮明に印象づけるために、動きと同時に言葉にも注意を払い、他の演出方法を検討してみたいと思っています。
私はこの頃、演出方法はこれでいいのかと考えることが多くなりました。以前は、謡の文句を覚え、上手に謡うこと、きれいに舞うことが関心の中心でしたが、この頃は、この能は何を言いたいかということを考えなければいけないし、そうでなければ深い味わいまで表現できないと感じるようになってきました。現在に生きる能を創造するものとして、伝統というワクの中の限界ギリギリのところまで、演出方法について考察し、ときには思い切って変えていく必要があるのだろうと思います。
今回、『砧』を喜多流のしきたりからすれば、年齢的に早く演じさせていただきました。演じてみたからこそ、ここに書いたようなことを感じることができ、次に演じるときはこうしてみたいという思いが広がってきたのです。大曲や老女ものは、ある年齢になってから初めて演じることを許されるという習慣は悪くはありませんが、早い時期に演じ、その後何回も試行錯誤しながらいい味に仕上げていくということも必要ではないでしょうか。思わぬ代演ということで『砧』という大曲に挑ませていただき、感じることが多く、意義あることだったと思っています。
『采女?佐々浪之伝』の新工夫投稿日:2018-06-07
『采女?佐々浪之伝』の新工夫
粟谷 明生
 『采女?佐々浪之伝』といえば、六年前(平成九年)、粟谷能夫と私で主催する粟谷能の会研究公演でのスローガン、「新しい試み」に挑んだ思い入れのある曲です。今回、秋の粟谷能の会(平成十五年十月十二日)では、もう一度、この『采女』を取り上げ、研究公演の成果と反省を踏まえ、一歩進めた、粟谷明生の『采女』を観ていただきたいと思い勤めました。
『采女?佐々浪之伝』といえば、六年前(平成九年)、粟谷能夫と私で主催する粟谷能の会研究公演でのスローガン、「新しい試み」に挑んだ思い入れのある曲です。今回、秋の粟谷能の会(平成十五年十月十二日)では、もう一度、この『采女』を取り上げ、研究公演の成果と反省を踏まえ、一歩進めた、粟谷明生の『采女』を観ていただきたいと思い勤めました。
通常の『采女』の上演時間はおよそ二時間、長い作品です。粟谷能の会のように三番立の番組では、一曲にたっぷり二時間はかけにくい状況があります。もちろん二時間なければ成り立たない曲であれば、番組構成を工夫し、その時間を確保することになりますが、現状の『采女』という作品ではどうでしょうか。やや散漫な筋立ては、曲位として無駄な重さが感じられ、そのためか『采女』の上演回数はけっして多くなく、せっかくの優れた作品がどこかで損をしているように思えてなりません。構成の散漫さを整理することで、『采女』のよさを十二分に引き出し、現代版として再生、普及できないものか、これが私の挑戦であり、かなえられそうな夢だったのです。
では、『采女』の散漫さとはどこにあるのか。それは春日明神の縁起と猿沢の池に身を投げた采女の物語の二本立て構成にあるのではないでしょうか。『采女』は世阿弥作となっていますが、もともとは古作の『飛火』が原形で、それを世阿弥が改作したようです。原形は、春日山の賛美が主体で、そこに後から采女の話をつけ加え作品化したものです。しかしその手法は、当時はよかったのでしょうが、現代から照らしてみると、少し冗漫な作品に思えるのです。
『采女』の小書は、昭和五十年、先代・喜多実先生が「小波之伝」(当初は「佐々浪之伝」)として、長時間の作品を凝縮するために土岐善麿氏と創案されたもので、それを基に私は先の研究公演で前場の春日明神の縁起や、後場の序、サシ、クセを省き、改訂版の「佐々浪の伝」として試演しました。新演出を考えるとき、演者だけでは思考に片寄りが生じ、つい演者のやりやすい方向に流れてしまう傾向があります。舞台全体を客観的に厳しい目で見ることのできる人は必要です。今回の小書再考には、日頃お世話頂いている演出家の笠井賢一氏にご協力頂き取り組みました。
まず新たな台本作りの検討からはじめました。作品の主題を明確にするため研究公演での詞章を更に絞り込むことにしました。前場は春日神社の由来、神木の植樹の草木縁起を完全に削除し、後場は序、サシ、采女が安積山の歌を歌ったという采女の身にまつわるクセや、宮廷での酒宴の様の部分、そして「月に啼け…」の和歌に継ぐ御世を寿ぐ祝言を削除し、入水した采女の、現世の苦患を超えて仏果得脱の清逸の境地に焦点を当てたいと思いました。
春日山の植林から始まる春日縁起は興福寺、春日大社を讚える宗教賛美であり、藤原氏への権力者賛美です。創作された当時、芸能者達が権力者である観客のために、自らが生きていく工夫としては欠かせない部分であっても、今それがはたして必要なのか、意見の分かれるところですが、敢えて今回の作品は、采女という女性に関連性が薄いこれらの部分を大胆に削除しました。
この能は、采女という女性の恨みや悲しみの訴えではなく、得脱の晴れやかな境地を表現したいのだと思います。采女は帝の寵愛を失ったと嘆き哀しみ、猿沢の池に身を投げますが、帝はあわれと思い、「吾妹子が寝くたれ髪を猿沢の池の玉藻と見るぞ悲しき」(我が愛しい人との契りの後の寝乱れ髪が、今は猿沢の池の玉藻のように見えることの悲しさよ)と歌い弔います。帝の心も知らず恨んで恥ずかしい、浅はかだったと…采女は悲しみます。そこにはドロドロした恨み節はなく、すでに変成男子を経て成仏し生まれ変わった采女がいるのです。
「佐々浪之伝」の主題は、入水した采女の現世の苦患を超え浄土を喜ぶ清らかな境地であり、法悦の余情と功徳、昇華した成仏得脱の境地です。詞章を切り詰めて削った意図は、最小限の言葉によって能『采女』を表現する、能でなければ成しえない新たな『采女』の創作なのかもしれません。おそらく、これほどまでに言葉を削れば通常の芝居なら支障が出るはずです。最小限の凝縮された言葉や、言葉では語れない思いを序ノ舞という舞に感情移入し、舞歌という能の世界で濃密な時間と空間を織りなす…。梅若六郎氏は、能は基本的に無駄なものを削ぎ落としていく木彫芸術のようなものだが、削ぎ落とし過ぎると演者は理解していても観客には意味がつかめない事も起こる、程度が問題だ…と言われています。この、程度が実に難しく、今回も絞りに絞った狭いテーマを扱いながらも、観る人の想像に任せる余白を大事に残し、単なる仏法讃歌やお説教曲ではない『采女』という作品を蘇らせたい、その一念でした。
今回の前場では、植林の話も削除するため、シテの登場をどのようにするかが問題となりました。観世流の小書「美奈保之伝」ではシテがワキに呼び掛け猿沢の池へ案内しますが、喜多流らしさも考え、実先生のアシラヒ出を生かしながら「吾妹子が寝くたれ髪を猿沢の…」という帝の歌を謡う形としました。
以前、観世流の片山慶次郎氏が雑誌『観世』の『采女』の記事の中で、「美奈保之伝」も呼びかけの言葉に工夫が必要では…例えば「吾妹子が寝くたれ髪を猿沢の…」と謡うアシラヒ出の可能性もあるのでは、と語っておられますが、これは今回の演出を選択する上での大きな自信となりました。
ただ問題もあり、「吾妹子が寝くたれ髪を猿沢の…」の詞章が前場だけで三回もあり、少しくどい感じになります。そこで、シテの朗詠する形、シテの言葉で謡う形、地謡の小のりで謡う形と彩りの変化で対応してみました。
後シテの出に関して、笠井氏より定型の常座でのシカケ、ヒラキではない、「美奈保之伝」の被衣に替わるような演出をとの提案に、一声の留めを一ノ松にして、囃子方にお願いして特殊な手組を入れていただき、池水から浮かび上がる風情で心情のこもる謡が謡えればと試みました。
序ノ舞は、研究公演でも試みた干之掛(かんのかかり)で、采女という女が昇華していく様とも、また我が家の伝書にある「采女一日曠れ(はれ)也」のキーワードの如く、采女にとっての晴れやかな時の表現としました。曠れの絶頂感を官能的な高音から始める干之掛は、まさに最適だと思います。
二段オロシでは中正面を池と想定して見渡し、袖をかづきながら思い入れの型をして、妙なる調べを聞いているとも、また御光に照らされるかのように正先に出て、ふと祈り合掌してしまう、静かで穏やかな特殊な舞の時間があってもよいのではないか…、私なりの冒険でした。「美奈保之伝」は水のイメージを重視して、拍子を踏まぬ、袖を返さぬが教えですが、今回は水のイメージに拘わりすぎないように注意し、采女が現世に現れて、法悦の舞を舞う凝縮されたひとときの舞、まさに「一日曠れ」ただそれだけを念頭に描いてみました。
序ノ舞が終わり、女は「猿沢の池の面」と謡い、「よく弔はせ給や」と、祈り続けることを願って池の底に消えていきます。重ねて祈ることで、采女の魂の鎮魂を永遠の祈りに高めているようです。采女はあくまでも美しく、水と同化していく様にも見えますが、采女にとって水や池は単に死に場所ではなく成仏の場所と変わっているのです。これは稽古を重ねていくうちに気づいたことで、私の発見でありました。
采女が重ねて弔いを願い永遠を求めるように、私たちが携わる伝統芸能の世界も同じ、繰り返し反復することが神髄かもしれません。しかしその反復の中にも、新しい試みや改良が必要です。変えていく力を失うことは、能という伝統芸能のダイナミズムが失われ、抜け殻のようになるのではないでしょうか。芸能の世界での“変える力”は、根こそぎ変えるものではなく、伝統の持つよさ、匂いを残しながらの変革ではないでしょうか。「名曲は伝承されつつ、その時々の工夫が加えられ、名曲であるが故に一層の磨きがかかってくる」これも梅若六郎氏のお言葉で、今回の作業をするにあたり、大きな支えとなりました。
演じ終え、この「佐々浪之伝」という小書が多くの方に親しまれていくとよいと思っています。その意味もあって、お囃子方を前回の研究公演のときと敢えて代え、笛は森田流から一噌流へ、小鼓は観世流から大倉流へ、大鼓も高安流から葛野流にとお願いしました。みなさま私の試みを快く理解し協力してくださいましたこと深く感謝しています。地頭を引き受けてくださった私の師・友枝昭世氏が「そこそこの作品になってきたね。序ノ舞を再考すれば…、そのうちやってみようかな」と言ってくださいました。この小書が多くの舞台で演じられることは嬉しい限りです。コンパクトながら、能の世界を十二分に楽しめるそんな作品になるように、さらに改良を加えていきたい、あの池の采女が喜んでくれるような作品になればと思っています。
* (演能レポートで内容 補足&写真も掲載しています。)
写真 『采女 佐々浪之伝』粟谷明生 撮影 東條 睦
『三輪』における小書「神遊」の効果投稿日:2018-06-07
『三輪』における小書「神遊」の効果
女姿の男神
粟谷 明生

第八十二回粟谷能の会 粟谷菊生一周忌追善(平成十九年十月十四日・於 国立能楽堂)にて『三輪』「神遊」(かみあそび)を披きました。「神遊」は青年時代から先人たちの舞台を楽屋裏や地謡座から拝見しながら、「いずれ自分もあのような装束で、あのように舞えれば」と憧れた小書です。『道成寺』を披いてから許される、という流儀内の暗黙の了解事項があるほど位が高い小書でもあります。
今回の番組を決めたのは二年前、父に地頭を謡ってもらいと考えていましたが、まさかその父の追善でこの大曲を勤めることになろうとは思ってもいませんでした。能楽師の憧れであるこの大曲を勤められたことを、きっと父は喜んでくれていると思っています。
今回勤めるに当たり、『三輪』「神遊」の主旨は何か、単に囃子の秘事の解明だけではなく、曲の深層部、真意などを探りたいと思いました。これらの作業、そして演能を通して、いまの自分の状況を客観視でき、今後の方針も考えるよい機会となりました。
『三輪』の前シテは里の女ですが実は三輪明神の化身です。後シテの三輪明神は男神であるにも関わらず女神として現れます。クセでは古来より三輪山に鎮座する別の祭神、蛇神の神婚説話を取り入れ里の女になりすまし、また天の岩戸の伝説のくだりでは天照大神にも代わります。単に三輪神社の祭神は大国主命(おおくにぬしのみこと)という設定だけではない、様々なものが混じりあっています。
この複雑な神の役どころをどのように演じればいいのか。そんな素朴な疑問を抱いてしまいました。女姿ですから艶やかに、天照大神ならば堂々として、などといろいろ考えますが結局答えは、一能役者の習得した謡の力と型の美に落ち着くのではないでしょうか。天照大神また蛇神云々と言っても、型として清麗なもの、神楽を厳かに華麗に舞うことを第一とするしかなく、また先人たちもそのように取り組んでこられたのでは、と思いました。
能『三輪』は四番目ものですが、脇能的な要素も多い曲です。宗教的なメッセージを多分に持ちながらも、芸能を観て楽しんでいただくという娯楽的要素が強い能と言えます。ですから演者は脇能を勤めるときと同様に淡々と落ち度なく、神舞や神楽を舞い、一心に勤める気持ちを優先させることが大事だと思いました。
では次に、小書について考えてみます。『三輪』には各流独自の重い習の小書があります。観世流では宗家の「誓納」、片山家ご自慢の「白式神神楽」、金剛流では「神道」が演能され、金春流は近年金春信高氏が「三光」を作られています。喜多流の小書は「神遊」と呼ばれ、宝生流のみ小書を持ちませんが、作品の主旨を外したくない意図が強く残った結果かもしれません。
今回取り組んだ喜多流の重い習「神遊」はどのようにして命名されたのでしょうか。そもそも神遊とは、天照大神の岩戸隠れによりこの世が暗闇となり、それを嘆いた神々が相談して岩戸の前で舞い歌い魂を呼び入れたことをいいます。その鎮魂の奏法全体を表現しようとするのが「神遊」です。ですから神々の戯れや歓喜する様すべてを表したいため、巫女的要素を入れず、また天鈿女命(あまのうずめのみこと)の舞であると考えられる御幣や榊などを敢えて持たずに、扇(中啓)で舞い通します。
『三輪』は小書が付くと吉田神道の影響からか、囃子事に関する秘事口伝が加わります。流儀の「神遊」でも、前場はワキ方に音取(笛の独奏)や置鼓(小鼓の独奏)が囃され、シテ方は習次第(ならいのしだい)に三編返(さんべんがえし=次第、地取、次第と繰り返す)と脇能的で儀式的な演出に替わります。これは得てして楽屋内の約束事に縛られすぎて作品の本位から外れることになりがちです。今回芸術的な趣向とかけ離れるのを避け、ワキの宝生欣哉氏と御相談して脇方の習の音取や置鼓はやめて、自らも三編返を行なわずに勤めました。
習次第と呼ばれる特殊な次第は、喜多流では老女物の『卒都婆小町』『檜垣』と『道成寺』そして『三輪』「神遊」にのみ囃されます。老女物二曲は老いの位を際立たせる演出といえます。『道成寺』と『三輪』も位を上げることに変わりはありませんが、両曲に共通する「蛇体」の執心の強調とも神聖視とも捉えられています。観客にはシテの重々しい登場が、あの正体はなんだろうと興味をそそらせます。
昔、観世銕之亟先生(八世静雪)が、「『三輪』の次第は、三輪山への距離感ね。いまのように簡単に楽には行けないんだよ。だって三輪の山本道も無しって謡うだろ? サラサラ出てきたんじゃダメだよ」と仰ってました。いつか自分が演じるときには、と心がけてきた言葉です。
装束は通常の長絹が狩衣に替わり鬘は喝食鬘で結います。喝食鬘は鬘帯を使用しないため、王朝趣味が取り除かれ太古のイメージが膨らみます。三輪明神は男神ですが、女姿に男の烏帽子と狩衣を着るという不思議な取り合わせとなりますが、これが能楽師が憧れる魅力的な格好なのです。
面については、前場の曲見は常と変わらず、後場は父が生涯愛用した「堰」の小面を使いました。喜多流は後場では小面が決まりですが、天照大神というスケールの大きな神を、かわいい、愛らしい表情の小面では成立しにくいので、他のものをとも考えました。しかし初演であり、父の一周忌でもあるので、父が大事にしていた「堰」をつけて手向けようと思いました。「堰」は父のもの、これからもそっとしておいてあげよう、との思いもありましたが、能夫の「使ってみて今度は明生君の魂を吹き込んでみたら・・・」という言葉に押され使うことにしました。
後場の「ちはやふる・・・」の謡は難しいです。引廻しがはられた作り物の中で謡うため、声が籠もりがちで聞こえづらくなるので大きな声が必要です。といって大声ならばいい、というわけではありません。高音で張りのある声で神の心を謡うというのですが、苦心するところです。
仕舞所となるクセの前半はじっくり動かずに床几に掛けたままで、進行を地謡に任せ、上羽前の「さすが別れの悲しさに」からシテは作り物から出て舞い始めます。作り物に左袖を掛けたり、留めに足拍子を踏み、「語るにつけて恥ずかしや」と面を隠す型など、「神遊」特有の型となります。
そしていよいよロンギから神楽となります。「神遊」の面白さはこの神楽の構成にあります。序は六つと通常より増え、足拍子も常と替わり複雑になります。通常の神楽は神楽の部分と神舞(時には中之舞や序之舞)が一体となって構成されていますが、「神遊」は神楽と後半の舞とを分けています。後の神舞を破之舞に替え、短い二段構成とします。神楽が終わると「天の岩戸を引き立てて」のシテ謡になり「人の面、白々と見ゆる」で破之舞となります。破之舞ははじめを舞台で舞い、途中から橋掛りに行き、二の松で左袖を頭上に担いで岩戸隠れを表す『翁』と同様の型をして、すぐに橋掛りから舞台に戻りはじめます。はじめはゆっくり、徐々に勢いを増して日がさす有様を見せ、本舞台に入ると袖をはねて『翁』の左袖を巻く型となり、神々の歓喜を表して「妙なるはじめの物語」と一段落します。
神楽の譜は笛方の流儀により異なります。一噌流が常の神楽の譜と変わらないのに対して、森田流は「神遊」特有の譜があり、したがって森田流でなくては「神遊」の面白さは半減します。森田流は序のあとに、ラア、ラア、ラア、ラア、ラア、ラアと長い反復の吹き返しから始まり、二段目に十のユリや七つユリなどの、見ている者も陶酔するような特殊な譜となり雰囲気を盛り上げます。
楽屋内の話ですが、一時森田流寺井政数家では、大小鼓・太鼓と手組が揃わず具合が悪く、いつか改善出来ないものかと思っていました。我が家の伝書は、現在森田流のまとめ役をなさっている杉市和氏の譜と同様なので、この度中谷明氏のご了解を得て、槻宅聡氏には杉家の譜で吹いていただきました。これで長年のかけ違いが改善されました。
今回、小書「神遊」を調べ、独特な譜や重い習を学び、クセの神婚説話のくだりも改めて読み直し、幼くてはわからない艶やかな内側の部分も知りました。資料を調べ、稽古を重ねていくと、次第にその曲の持つ魅力を知り、その作品に引きつけられます。『野宮』や『井筒』などはもとより、はじめは気乗りのしなかった『千寿』や『盛久』でさえ勤めるとその魅力に惹かれていきます。これは正直能楽師でしか味わえない喜びです。
『三輪』は魅力ある曲で、且つ憧れる曲ですが、稽古を積めば積むほど、その深さや味わいを知れば知るほど、不思議と演じにくさを覚えました。
どうしてなのか?「神遊」は破之舞で『翁』の型があるように、『翁』と共通する祭事の儀礼的要素がふんだんに込められ、それが人間の感情的なものを拒んでいるように思えます。女神のような気高さと色模様を含む神話の豊かさ、流麗な型と躍動感あるリズムに酔うこの曲の良さは充分判りながらも、いま一つ踏み越えられないものがあるとしたら、それは人間を扱うものとそうでないものの違いではないでしょうか、それがいまの私の素直な感想です。
『翁』や『高砂』、『絵馬』も同様、祭事としては手応えがある位高い曲です。しかし、私の心に活力や遣り甲斐を持たせてくれるお能は、人間の苦悩や喜びをテーマにしたもののようです。もっと年を経て人間の苦悩や喜びを突き抜けて憂き世を達観するほどになればまた違った境地になるのかもしれませんが、今の私がその年々の能を見つめるとき、正直そんな思いにとらわれているのです。もしかしてそう思わせているのは『三輪』の神力なのかもしれません。
*(「粟谷能の会」のホームページ演能レポートで内容補足&写真も掲載しています。ご覧いただければ幸甚です。)
写真 三輪 シテ 粟谷明生
(平成19年10月14日 粟谷能の会 撮影 石田 裕)
「小さいことは良いことだ」投稿日:2018-06-07
「小さいことは良いことだ」
粟谷明生
「小さいことは良いことだ」、これは安田佳生氏のエッセイの一節で、読んで目から鱗が落ちた。とても面白く勉強になったので、私の意見も交えてご紹介したい。
安田氏は、会社は安定感、知名度、資金力などを思い浮かべると、大きい会社がいいと感じる人が多いだろう、しかし何事も適正サイズがあるとしても、大きければ良いというわけではなく、むしろこれからは小さい会社の時代だと説かれている。大きい会社にお勤めの「大きい方がいいに決まっているじゃないか!」という上から目線の常識的な考えを覆す内容だ。
小さいことは良いこと、これからは小さい会社が勝つ時代で、未来があり、明るく自由である、という。
何故小さい会社が良いのだろうか?
それは、大きな会社の既存の仕組みから抜け出し、直接顧客に支持される会社に変われるからだという。
小さな会社が勝ち残るには、顧客を選ぶことが大事だともいう。
顧客から選ばれるのではなく、会社が顧客を選ぶという意識、ここがポイントである。
自分たちがやりたい仕事や提供したい価値、それを徹底的に追求することによって顧客を絞り込む。大きな会社は事業上の特性上、極端に顧客を絞り込むことが出来ないから、それが出来る小さい会社は自由なのだ、と…。なるほどと勉強になる。さてこの論理、私の周りにも通じるようだ。
観宝春剛喜
これ漢文ではない。シテ方能楽師の人数が多い順に流儀を並べてみた。内訳は観世561名、宝生270名、金春120名、金剛100名、喜多54名(平成22年調査)となる。
喜多流は本当に小さな流儀だ。父は私が生まれて、十四世喜多六平太先生に「明生です!」とお見せすると、「ほお?、あき坊か?かわいそうに喜多流だね」と仰ったという。小さな流儀に生まれたことへの哀感だったのだろう。しかし父は私を可哀想だと思ったことは一度もない、と言っていたし、私も自分がそのような立場だと思ったことはない。ではあるが、安田氏の説で力を得た。
喜多流は小さいからこそ良いのである。
流内は高齢者も若者も上下の礼節は重んじながらも、年齢を越えてお互いに意見を言い合い、仲間意識を強く持ち、結束力を大事にしている。つまり明るい流儀なのだ。
少人数ということは裏を返せば、流内の競争率は低いと言える。
頑張れば努力は認められるし、500人の中のベスト5に入るのは並大抵ではないが、50人のベスト5なら、やる気も出るというものだ。また現在は、古来の風習や型附を頑なに守るだけではなく、演能の幅を脹らます作業も認められる自由さがあり、流儀内の寛容な雰囲気が、健康的で居心地の良さをつくっている。少なくとも私はそう思っている。
但し、短所もあるから気をつけなくてはいけない。
小さな流儀は当然人数が少ない。命は永遠ではないから、今生きる我々もいずれはあちらに旅立つことになる。これは避けようがない。ならば常に少ないながらも人の確保が大事だ。小さい流儀ほど後継者のことを深刻に考えていなくてはいけない。
後継者不足で流儀消滅、なんて有り得ないと思っている、そのこと自体に危機感を覚える。
後継者は、家の子はもちろん能が好きで、才能があれば嗣いでほしい。また家の子でない者でも能が好きで、才能があれば喜多流に入ってほしいと私は思う。家の子でなくてはいけない、という先入観を捨て、広く門を開き受け入れ態勢をとる。これ言うは簡単だが、正直、本音にまで浸透させるのに時間がかかるようだ。しかし明るく未来のある小さな喜多流だからこそ、我々は「後継者問題こそ重視」という意識改革を置き去りにしないでいたいと思う。
後継者を育てるためには、小さい流儀は小さいながら各個人の技を磨き上げ、舞台活動、愛好者確保と流儀繁栄の努力を惜しんではいけない。父の口癖の「人の三倍の努力」、これが必要だ。
私の願いは、これからの喜多流の人は、謡えて、舞えて、裏方も出来るそんな三拍子揃う人になること。何でも出来る技を習得することは並大抵ではないが、好きであれば必ず達成出来るとはず。
将来、喜多流がそういう人たちの集団になれば、ますます良い流儀となり、きっと良い流儀であり続けるだろうと思う。
安田さんの文章が私の身をまた引き締めてくれたようだ。
(平成22年4月 記)
『山姫』と日本人の心 粟谷能夫投稿日:2018-06-07
母の残してくれた私の演能記録を見ていましたら、十三歳の時、第一回粟谷能の会(昭和三十七年十月七日)に父の『景清』でツレ(娘・人丸)を、同年十二月に『烏帽子折』の子方を勤めておりました。当時、学校から帰宅すると、喜多実先生のお宅へ伺い稽古をして頂く毎日でした。
『烏帽子折』は子方(牛若丸)が平泉を目ざす道中、鏡の宿で平家方が牛若を探索していることを知ると、姿を変えるために烏帽子を求め、また赤坂の宿では盗賊、熊坂を討ち取る活躍を見せます。この曲で子方卒業と言われております。そして能楽師としての本当の修行が始まるのです。
其頃父から太鼓の稽古に行くように言われました。自宅から歩いて通えるお宅で、太鼓金春流の柿本豊次先生の稽古を受けました。いざ太鼓を目の前にした時、太鼓の皮の真中に撥革(この上のみ打つ)がはってあり、正確に打てるのかと不安でした。其後、小鼓、大鼓と稽古を受けるようになり、謡の地拍子の理解に役立ちましたし、お囃子の方々のご苦労も身にしみて分かりました。
太鼓の稽古を始めるにあたり、父が金春流太鼓手附を用意してくれました。その中に『山姫』という曲目を見つけたのです。謡本を探してみると、大正九年発行の謡本がありましたが、変体仮名のため当時は全く読めませんでした。それ以来、私の頭の中にいつか『山姫』を世に出したいとの思いがふくらみ、今日にいたりました。
能『山姫』は「山里いかに、春を知るらん」の心で、春の花を眺めるため山々を散策する里人(ワキ)が、山姫(シテ)にめぐりあい、山姫が四季折々の眺めを舞い語るという、一場面(中入りのない)のシンプルな内容です。山姫とは山を守る女神だとか、少し怖い妖怪であるというような民間伝承もあるようですが、今私は、山姫は自然の厳しさというより花鳥風月を愛でる山の精と感じています。
日本人の四季を愛でる文章の多くは、自然との共存を見出し、人間もその一部であると実感せしめることに徹しております。例えば日本人は虫の音を聞き夏の終わりを思ったりしますが、欧米人には、雑音としてしか聞こえないといいます。また、日本人は月の呼び名を多く持っています。四季の気配をいち早く感じる民族なのです。
『山姫』の能にも、日本人の心の中にも、四季の移り変わりの中に美を見出してきた日本古来の感性や自然に対する畏敬の念が根底にあるように思います。このようなことを思いながら、今年の粟谷能の会(平成三十年三月四日)で『山姫』を勤めます。

『伯母捨』シテ 粟谷能夫(平成 29 年3月5日 粟谷能の会) 撮影:吉越 研
『柏崎』における重層性投稿日:2018-06-07
『柏崎』における重層性
粟谷明生
六月の研究公演で『柏崎』を取り上げました。息子の尚生に子方としてふさわしい内容を年齢に合わせてやらせてやるのが、この世界で生きる親の責務であるという想いもあって、今回は子方が登場するもので、自分としても挑戦しておきたいものを選ぶことにしました。
『柏崎』では、訴訟のために鎌倉に滞在していた柏崎の某が風邪のために亡くなると、同行していた息子の花若御前が遁世してしまいます。妻はその知らせに嘆き悲しみますが、やがて我が子の安穏を祈る気持ちになります。しかし後半には、妻は悲しみのあまり物狂いになって登場します。妻であり母であるシテのこの早い心の動きを演者がどのように納得して演技できるかが問題です。能では、内面の心のエネルギーが抑えた動きの中から外に出ていくことを重要視します。従って内面の心の動きを理解して演じることは、動きの少ないものほど要求されるのです。
シテの心を理解するには、シテの女性像をつかむことや『柏崎』の中のいくつかの疑問を解決する必要がありました。シテの女性像・母親像はどんなものでしょうか。息子の遁世を冷静に受け止める凛とした女性、宗教心が篤く教養の高かった女性、しかし我が子や夫を思う愛情豊かな女性でもあった・・・でしょう。
自分の息子を前に舞台稽古をしていると、この子はなぜ母親に会おうともせず出家してしまうのかという疑問がわいてきました。今の一般の常識では父親が亡くなったら、息子は急ぎ郷里に帰り、母を助け、父の代わりに城主として、その地を守っていくのが筋だろうと思うのですが、『柏崎』の息子は母に一度も会おうとしないで出家してしまいます。これはどういうことだろうか。このことを理解するには当時の宗教的な背景を知らなければなりません。浄土思想に、出家は自分自身だけでなく、周りの人をも救うことになるという考え方があることを知りました。つまり自分が出家して厳しい修行をすれば、父親も極楽往生し、母の来世も約束される、家臣や柏崎の人たちも救われるという考え方です。これで子の出家の意味が理解できました。
しかしこれを解決しても「テーマは何か」という疑問が残りました。『柏崎』は一見、子別れ・再会の曲のように見せながら、メインは物狂いとなった妻が、夫への愛や恋慕と、極楽浄土や善光寺信仰への礼賛といった深い宗教性を込めて謡い舞っていくところではないだろうか。極楽のすばらしさをいうために、人間の悲しさを表し、その上で来世での再会を願うというのがテーマだったのではないか。
『柏崎』は古作(榎並左衛門五郎の作)を世阿弥が手を入れ完成させたものであるという説が有力です。左衛門五郎が作った段階では、善光寺を讃える当時の流行歌を題材にし、曲舞に仕立てた単純なものだったのでしょう。これでは戯曲として面白味や起承転結がないので、世阿弥が母子再会の話をつけ加え、形を整えたといわれています。子の説のとおり、子別れ・再会のテーマは付け足しで、曲舞のきらびやかとも言えるほど宗教的な言葉がちりばめられている部分がメインにふさわしいところだと感じさせられます。今では難しい言葉に聞こえるものも、当時の善光寺信仰に篤い人たちにとっては心地よい言葉の嵐だったのでしょう。
世阿弥の時代には興行的に成功させるために、宗教的なPRの意味合いが強い能もつくられていました。『柏崎』もその傾向をもった能といえるでしょう。ただ、信仰を讃えるにとどまらず、社会風刺的な彩りも加えています。たとえば、妻が善光寺の内陣に入ろうとしたとき、住僧に女人は入ってはならないと制止される場面で「仏がそう仰るのか」とすごみ、女性差別に切り込むところがありますが、庶民はそうだそうだと喝采したのではないでしょうか。
夫への恋慕の情も強く表現されています。夫の形見の長絹をまとい烏帽子をつけて、亡き夫は弓も歌も舞も上手で、立ち姿も美しかったと、一種ののろけともとれる謡い舞いぶりを見せ、曲舞の最後は夫との来世での再会の願いでくくられています。
一般の芝居では、特に落語がそうですが、最後のオチが重視されます。しかし、能ではときに最後の結びの部分(『柏崎』では子供との再会)はさほど重要ではなく、もちろん一つの見せ場には違いありませんが途中の舞や謡など、見せどころ聞かせどころを幾重にも作って楽しんでもらおうとする曲目があります。これは能の持っている特徴でしょう。私は『柏崎』もそういう種類の曲であり、重層性をもった能であると思うのです。ただ、最後に小さい子方が出ることによって、それまでの難しい宗教性などを一時忘れ、母子再会というハッピーエンドにわいて、安堵して帰っていただくという効果があるようで、世阿弥はそれをねらってたかもしれません。
これが、私なりに納得出来るものとして出した結論です。今回、自分の中にある疑問を解決することで、『柏崎』という作品を知り、その演技にも集中出来たように思います。
また現在『柏崎』の演出方法として「中の舞」を省略する形が一般的になっています。初期の能では、夫を思いだしてのろける件の後に舞がありました。扇を差し出し「鳴るは滝の水」と謡うのですから、その後は、当時の流行歌に合わせて謡え踊れとなるのが普通です。『翁』や『安宅』でもこの言葉が来た後には舞が続いています。それが現在の『柏崎』には舞がなく、いきなり「それ一念称名の声・・・」と宗教的なことばが連なっていくのですから、世阿弥のころの人が観たら物足りないに違いありません。それで今回、舞入りで演じてみたいとも考えましたが、『柏崎』自体が大曲であること、そして初めて取り組むことなので断念しました。しかし、次回演じる機会があったら、ぜひ舞入りを加え、世阿弥本に「ヲカシ(狂言)女物狂ガ来ルト云ウベシ」とあるように、間狂言等も入れて特別演出で演じてみたいと思っています。
我流『年来稽古条々』(17)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(17)
壮年期その一
『道成寺』以降
粟谷 能夫
粟谷 明生
明生 今回からは『道成寺』後のことを具体的に話していきましょうか。能夫さんはどんな曲目を手がけましたか。
能夫 昭和五十四年、『道成寺』と同じ年に青年喜多会で『湯谷』。同会では翌年に『八島』、粟谷能の会では五十五年に『葛城』その年まで粟谷兄弟能と呼んでいたけど…。五十六年に『葵上』、五十七年に『自然居士』、五十六年には喜多会にも入って、喜多会の最初が『忠度』だった。他には『羽衣』、『杜若』、『雷電』、『鵺』というところかな。
明生 結構重いものをやっていますね。『道成寺』の前後では、曲がワンランク違ってくるという感じがします。
能夫 それはあるよね。大人の世界に入っていくという、そんな気がしますね。粟谷兄弟能が粟谷能の会と名称が変わったのが五十六年でしょう。我々を会に入れて、完全に年二回でやろうという方針になって。五十六年から明生君も入っているね。
明生 その年に『小鍛冶』白頭を勤め、それから毎年一番のペースになっています。
能夫 明生君は『道成寺』の後はどんな曲を手がけたの。
明生 『道成寺』(昭和六十一年)の後すぐ、その年に青年喜多会で『山姥』、翌六十二年は三月に粟谷能の会で『自然居士』、六月に妙花の会で『杜若』、九月に青年喜多会で『湯谷』です。『道成寺』の後は、私も結構重い曲をやらせていただいていますね。
能夫 やらなくちゃ、やらなくてはいけないという気持ちもあるし、ある年齢になったというか、『道成寺』をやると、次はこんなものができそうだみたいなものが見えてくるということはあるね。
明生 そうですね。青年喜多会では私が同人の中では年上になる、そうなると真ん中を勤めることになって『湯谷』がつく、翌年の『東北』で卒業しました。まだ喜多会には入っていなかったので演能の機会が少なくなるなー。で、「妙花の会」を起こしたのです。
能夫 意識的に動き出したわけだ。「妙花の会」が六十二年にスタートして、それで『杜若』を舞ったわけだね。
明生 会を立ち上げていきなり本三番目ものを選曲するのには若かったし抵抗がありましたから、小面をかけて、そこそこ幽玄の世界を味わえる曲と考えて『杜若』を選びました。
能夫 そういうことはあるね。『杜若』はあの初冠に追掛で長絹姿の美しさはなんともいえないね。でも、後半の恋の話がたくさん出てくるところ、コラージュとかフーガとか言われるけれど、何だか散漫な感じがして、あまり好きになれないんだ・・・。でもあの曲好きな人結構多いよ。親父も好きだったし、菊生叔父も好きでしょ。
明生 昔から能夫さんは、父たちの時代の人は何であの曲が好きなんだろうと言っていましたね。手ごろだから演能機会が多いということだと思いますが。でも私も勤めてみて、なかなか若造では難しいところが多い気がしました。
能夫 『杜若』をいい形でしおおせるのは難しい・・・。でも、あのころはとにかく時間があったから一生懸命稽古をしたという気はするね。
明生 で、能夫さんは『道成寺』後、すぐに『湯谷』ですね。私も翌年に勤めています。『湯谷』はどうですか。
能夫 『湯谷』を舞えるようになったという喜びはあるよね。豊かで華やかさもあるし、見た目もいいし。
明生 実先生が指定してくださった最後の曲が『湯谷』でしたから、まずは楷書の感じで稽古しました。当時はすでに友枝昭世師に習っていましたけれど『湯谷』の雰囲気がわからなくて、つまり現在物への戸惑いですが。思い出すのは、文ノ段を森常好さんと連吟したこと。あそこは普通連吟なのですが、最近はシテ一人で読むことが多くなっています。そこを本来の形でやろうと。森さんなら同年輩でもあるし、つーかーの仲ですし。
能夫 謡本では「もろともに読み候べし」となっているね。ワキと読むヒントになるものは何だったの。
明生 父の鏑木岑男さんと連吟している写真や、新太郎伯父が厳島御神能のNHK録画の時も連吟していまして…。一人で読むのもいいですが二人で寄り添って謡う景色が私は好きなので。
能夫 演出的なことを明生君が見直そうとした、その萌芽がそこにあったのかもしれないね。いいことですよ。
明生 それで、常好さんに「こうしたい、ここはこのように」と注文したら、「あっそう、了解」なんて、いとも簡単に返事してくるんです。こちらは初めてでも、おワキの方は何回もやられているから。
能夫 ワキ方はいろいろな人のお相手をしているから対応できるんだね。『湯谷』は親父や菊生叔父、友枝喜久夫先生、みんな好きだったね。僕はそんなに好きな曲ではないけど。六平太先生がお好きだったから、みんな憧れて、自分もああいう風に舞いたいというのがあったのだろうね。
明生 能夫さんの好みは現在物より幽玄物だから。『湯谷』よりは『野宮』『定家』『松風』でしょ。
能夫 そうね。『野宮』『定家』だったら喜んで舞うね。
明生 『杜若』もそうでしたが、『湯谷』にしても、我々と父たちの世代とは好みが違いますね。それは時代もあるし、憧れる人の違いもあるのではないでしょうか。父たちは六平太先生に憧れ、能夫さんは実先生に教わり、寿夫さんに憧れてということですから。そういう違いがあっていいと思いますね。
能夫 それでも、考えてみれば僕はいい環境にいたと思うな。父もいて菊生叔父もいて、それぞれに一生懸命やっていた。実先生も、そして六平太先生もおられて、寿夫さんたちもいて、いい環境にあったんだな。
明生 いいですね。それから『自然居士』を私が『道成寺』の翌年、能夫さんが三年後に勤めていますね。
能夫 『自然居士』はすごく面白い曲ですよ。憧れもあったしね。何をやりたいと聞いてもらえる立場になって、自分から『自然居士』をやりたいと言った気がする。羯鼓とかクセはあるパターンでできるんだけれど、やっぱり会話が難しい。ただセリフを言っていれば通じるんだと思っていたのが、そうじゃないゾと、発見するときだね。
明生 それは『道成寺』をやって祈りを体験するから感じられるんですよね。それまでは、相手とは関係なく、自分のなかでまっすぐに謡っていたものが、相手と対話するという工夫が必要になる。一度買い取った子は返さないと言いはる人商人から、自然居士は子を取り戻さなければいけないわけだから、平坦な言葉では通じませんね。
能夫 大きく包み込んで勝たないといけないわけでしょ。相手の出方によって、すごく動いていなければならない。相手の裏をかくこともあればおちょくることもあり諧謔もあったりと、いろいろな言葉のニュアンスがある。『自然居士』はパターンでできる能じゃないんだよ。ほんと、セリフ劇だからね。そこが楽しいところですよ。
明生 能楽師が役者にならなければいけないというイメージがありますね。
能夫 そうそう、そういうものをしょわないとね。
明生 それで『自然居士』、一人で稽古していると馬鹿馬鹿しくなるんですよ。謡本を覚えて、間も覚えて、でも相手がいないと…。
能夫 確かに一人で稽古していると何か空虚だよね。
明生 それで常好さんと一緒に稽古する事になり、アイの野村耕介(野村万之丞)さんにも参加してもらいいろいろ相談していくうちに、萬舞台できちっとやろうということで、佃良勝さんが役ではないのですがアシラヒをして下さり、地謡がいないなーと困っていたら観世暁夫(現 観世銕之丞)さんが「僕が謡うよ」ということで…。
能夫 すごくいいじゃない。僕のときは実先生のもとにあって、なかなかそういうことはできなかったけれど。
明生 その後『野守』「居留」でもそういうことをやりました。あのときは金春国和さんと地謡は宝生流の武田孝史さんで、特に緩急の付け方をみんなでいろいろ試みたことが楽しかったです。みんなに、寿司ぐらい奢れよと言われて、食べて飲んで話して、いい思い出ですね。
能夫 いい仲間がいたってことじゃない。明生君は恵まれているなあ。幸せな時間を過ごせたということですよ。
明生 能夫さんの『自然居士』のワキは?
能夫 工藤和哉さん。工藤さんはもう百戦錬磨の人、いろいろな人の相手をされているでしょ。そうこちらは披きだからね、コチンコチンになってぶつかっていくわけだから。今考えると、あの『自然居士』は子供っぽいものだったと思うよ。
明生 百戦錬磨の人に太刀打ちできるわけないですよね。
能夫 そう。第一回の『自然居士』では無理!(笑い)でも、それでコンチキショウとなって次の道があるわけだから。次の『自然居士』はお相手が宝生閑さんだったけれど、結構面白くできたと思っているんだ、こういうことが楽しいよね。
明生 『道成寺』が終わると少し自信がつくというか余裕が生まれる、それで曲をどういう風に演出し演じていこうかということを意識しだす。
能夫 自分で考える余地をもってやっていくという、それが少しずつやれるようになるのが『道成寺』以降ということなんだろうね。
異次元への飛翔投稿日:2018-06-07
異次元への飛翔
粟谷 能夫

面をかけて初めて舞台に立ったのは、十代半ばのころ、『小鍛冶』のシテを演じた時だったと思います。鏡の間で面をかけた時、全身が燃えるような熱さを感じたことが鮮烈な印象となっています。
父、新太郎の影響で身近に面に親しんで育ったせいか、憧れが強かったことも確かで、面は能の舞台に欠かせないものという認識が無意識のうちにでき上がっていたのでしょう。面をかけない直面の曲も何番が勤めてきましたが、何ともやりにくさを感じています。
仕舞や舞囃子のように紋付袴で舞う時に違和感がないのは、紋付袴が衣装以前の肉体の一部に近いものという感覚があるからかもしれません。それに対して、装束をつけた時に面をかけないと、顔だけが現次元のまま取り残されてしまっているようで、非常に恥ずかしさを覚えます。多分照れ屋の性格も手伝っているのでしょう。
面は現在から異次元へ容易に自らの概念を移すきっかけともなります。そして能の舞台を通して何かを表現する時に、その根底には、紛れもなく自分自身があって、面をかけるということは、舞台で演技するための個を確立させる最後の仕上げであると思います。面は肉体及び精神行き来出来る通路であるのでしょう。
先日蝋燭能で『通盛』を勤めました。見所は真っ暗で、舞台はわずかな照明とろうそくのゆらめく明かりで薄暗く幻想的な雰囲気です。揚げ幕を上げ橋掛りを歩いている時、闇の中にうっすらとある舞台空間へ引き込まれるような感じがしました。闇の持つ力なのかもしれません。いつもは舞台空間を押しながら出るといった感じなのですが、面から見える明暗の違いで、このような体験をするとは思いませんでした。
僕にとりましては、能を糧として、咀嚼し、血肉化し、そして体現していくという作業が生活そのもので、それに値するだけ能はすばらしいものと信じています。
たた、舞台づくりはそう簡単ではありません。技術的な部分はある程度稽古から得ていくことができますが、その上でいかに表現するかは感性に関わってきます。同時に伝統芸術とはいっても、今生きている人々に訴えるものを自分が持っているのかということもあります。
能へのたゆみない挑戦、あるいは面を通してなら何かが見えてくるかもしれない、そんなことを思いながら、今後も自分なりの舞台づくりに取り組んでいくつもりです。
高知能楽鑑賞会で『巴』をご覧になる方へ投稿日:2018-06-07
高知能楽鑑賞会で『巴』をご覧になる方へ
高知能楽鑑賞会(22年7月25日)は粟谷菊生追悼番組です。
父が好きで得意でもあった『巴』と『天鼓』を、父への手向けとして、愚息私が『巴』を、我が師・友枝昭世師が『天鼓』を勤めます。
そこで、鑑賞していただく手引きとして、私が勤めます『巴』を演者の立場からご紹介いたします。
能で木曽義仲(源義仲)本人が主人公(シテ)として登場する曲はありませんが、家来によって、たとえば『巴』は巴御前、『兼平』は今井兼平によって義仲公が描かれています。
『巴』は二番目物・修羅物に分類されますが、シテが女性であること、修羅物でありながら雄々しい戦物語だけではなく、幽玄の情緒に富んでいるのはいささか特異です。
修羅物は、主人公が戦死したゆかりの地に現れ、自分の討死にした有様を物語り、修羅道での苦患の有様を述べ、旅僧に回向を頼むのが定型です。
ところが、巴御前は討死にしていません。よって自分が非業の死をとげた土地に現れるわけでなく、愛する男が祀られている祠に現れ、共に死ねなかった執念と恋慕の情のために成仏出来なことを嘆きます。女の恋慕の悲しさに焦点があてられているのが特徴です。
前場は義仲を慕う里女として登場し、僧に回向を頼み、後場は自身女武者として長刀を抱え勇ましい姿で戦物語を演じます。
私は今までに三度『巴』を勤めていますが、私の『巴』を顧みると、鮮やかな長刀さばきで奮戦の有様を見せるのが一番の見どころとはいえ、どうも女武者の勇ましさ、長刀さばきの技ばかりに気をとられ、女としての巴御前、義仲に恋する愛らしさ、悲哀の女性を意識していたか、と言われると、いささか自信がありません。
能『巴』で思い出すのは、以前にある女性の方に言われた言葉です。
「巴は何度も観ていますが、ご立派な巴は何度も拝見しました。でも、あ?女だ、愛らしい、かわいい、イロっぽい、と思ったことは一度もない。もちろんあなたの舞台もよ。
しかし、あなたのお父様の『巴』は違う。あ?女だ、女以上に女だ! と感じさせてくれた。そこまでしてくれないと能『巴』ではない・・・。わかる?」
今でもこの言葉が頭から離れません。今回父のように出来るかはまったく自信がありませんが、私なりに巴御前の女らしさを意識して演じたいと思っています。
『巴』のあらすじを簡単に記しておきます。
木曽に住む僧が都へ上る途中、近江国(滋賀県)粟津が原に着くと、一人の里女が現れ、松の木陰の社に参拝し涙を流しています。不審に思った僧が女に言葉をかけると、女は行経和尚も宇佐八幡へ詣でたとき、「何ごとのおわしますとは知らねども、忝なさに涙こぼるる」と詠まれたように、神社の前で涙を流すことは不思議ではないと答えます。そしてここはあなたと故郷を同じにする木曽義仲公が神として祀られているところであると教え、その霊を慰めてほしいと頼み、実は自分も亡霊であるといい残して、夕暮れの草陰に消えてしまいます。〈中入〉
旅僧は、里人に、義仲の最期と巴御前のことを聞き、同国の縁と思い、一夜をここで明かし読経します。すると先の女が、長刀をもち甲冑姿で現れ、自分は巴という女武者であると名のり、義仲の遺言により一緒に死ぬことが許されなかったことの無念さ、戦模様を語り見せます。遂には形見の品をもって一人落ちのびたが、いまだにある心残りが成仏のさまたげになっているので、その執心を晴らしてほしいと重ねて回向を願って消え失せます。
前場は琵琶湖畔の粟津が原。一人の女(前シテ)、実は巴御前の霊は旅僧が木曽の人であることを予め知っているかのように、夕暮れ近くに寂しく登場します。もしかするとこの女はずっと木曽に所縁のある者を待っていたのかもしれません。
中入り前、「さる程に暮れてゆく日も山の端に、入相の鐘の音の、浦わの波に響きつつ」と西の空を見上げそのまま正面へ向いてうつむき、鐘の音を聞く型がありますが、そこで観ている方に鐘の音が聞こえれば、演じ手の勝ち、これが父の言葉でした。
後場は、通常の唐織を壺織にせず、長絹を肩上げして甲冑姿を想像して頂く替えの扮装にする予定です。面は父の追悼でもあるので父愛用の河内井関の小面をと思いましたが、かわいい巴よりも、より艶ある女の巴を演じてみたくなり、異例ですが宝増で勤めるつもりです。
能でシテが長刀を使う曲は『橋弁慶』『船弁慶』『熊坂』の三曲で、いずれも男物です。女物は『巴』一曲で、敢えて『平家物語』に記載のない巴御前に長刀を持たせたのは作者の創意だと思われます。父は「巴の長刀は軽快に鮮やかに、知盛や熊坂とは違う…」と教えてくれました。
終盤、重傷を負った主君に自害をすすめ、自らは寄せくる敵を追っ払らい戻ると義仲は…、巴は長刀を捨て、死骸に別れを告げ、義仲の形見を胸に木曽の里に去って行きます。
「後ろ姿に哀愁が出ないとだめだ、後ろ姿だよ。最後の留めの型は笠と小太刀を捨てるも吉、また笠だけ捨て太刀は義仲だと思って肌身離さず持ちかえる、どちらでもいい。その型の意味さえ判っていればな…」これも父の教えです。
最後は修羅物らしくない鬘物の情緒がうかがわれる『巴』ですが、強さと哀れさをうまくにじませ、父の巴を思い出しながら、明生の巴を演じたいと思っております。
ご来場をお待ちしております。
22年7月17日 演能前に 粟谷明生
写真 平成5年 粟谷益二郎37回忌追善 粟谷能の会 シテ 粟谷明生 撮影 三上文規
我流『稽古条々』(39) 『山姫』『卒都婆小町』について ?研究公演以降・その十七?投稿日:2018-06-07
明生 いつものように、今度の粟谷能の会(平成三十年三月四日)に勤める演目について話していきましょう。
能夫 今度は菊生叔父の十三回忌追善能ということになるね。早いものだね。明生君が『江口』を勤め、菊生叔父が地頭を勤めるというので張り切っていたのに、申合せの日に倒れてね。怒涛の日々。生々しく覚えていますよ。
明生 当日は命をつないでくれましたが、その三日後にはあちらの世界ですから。あまりにも急で、信じられなかったですよ。父が倒れても舞台はちゃんと勤めなければいけないし、粟谷能の会の二日後には明治神宮の薪能で、父の代演で『高砂』の仕舞を舞わなければならなくなって、もう大変でした。能夫さんも『道成寺』でしたからね。
能夫 「明日、道成寺をやってきます」と、病院の菊生叔父に挨拶して…ね。
明生 そうしてもう十三回忌。父への手向けとして、今回、私は大曲『卒都婆小町』に挑みます。能夫さんは『山姫』、復曲能ですね。
能夫 僕の『山姫』も菊生叔父への手向けになるといいね。昔から、この曲のことが気になっていて、いつか演ってみたいと思っていたんだ。喜多流は遠ざけていたけれど。
明生 遠ざけていたというのは何か理由があるのですか。
能夫 それはわからない。
明生 演能の記録は?
能夫 京都で高林吟二氏が白牛口二氏に舞わせたので、高林家には手附もあって、僕は今回その手附をいただきました。またその中には囃子方の手附もあり、大変参考になりました。それでも、六平太先生(十四世喜多流宗家)が復曲の要望があるようなことを何かに書いていますよ。そのためか、謡本も一応残っている。
明生 『山姫』というと『山姥』の間違いでは? と言われますが……。
能夫 同じ系統のものかもしれないけれど、違いますね。それに、『山姫』はそんなに昔からある能ではなく、せいぜい、江戸後期から明治前期にできたものではないかな。「山姫」というのは日本各地に伝説が残っている。だいたい山に住む美しい女ですよ。男を誘って、使うだけ使って、役に立たなくなったら捨てるみたいな恐ろしい伝説。生き血を吸って死なせたりね。山姫を象徴するものがアケビの実で、性的な意味合いもある。
明生 美しい女は恐いですね。山の美しい女に魅せられて、山奥へと引き込まれていく話というと、小説「高野聖」‐8‐を思い出します。
能夫 いろいろなことが考えられるけれど、没落したお姫様が山に潜んでいたとか、人間の女性が生気を失った姿ではないか、といったことだろうね。この話、まんが・日本昔話にもあるんですよ。山で山姫に出会って山姫が笑うのにつられて笑ってしまうと二度と山から帰れない、と言われていたという話です。能『山姫』は春夏秋冬の花盛りとか雪景色をめぐります。特別な物語らしきものは何もない。俳句のような曲ですよ。
明生 四季を表す何か作り物はあるのですか。
能夫 特にない。いたってシンプル。
明生 時間はどのくらいですか。
能夫 四十分くらいかな。一場もので、中入りもない。ワキが次第で出て「このあたりに住まいするもの」と名乗るけれど、場所は明らかにしないんだ。だから場所の設定はないが、手附を見ると山城の国常盤音戸山と書いてあるから、京都の北方ですね。だから山姫は都落ちした女性と考えてもいいのでしょうね。山の精というより、もっと雅な感じではないかな。東北や九州のほうにある伝説の「山姫」とはちょっと違います。ワキが春の花盛りを愛でていると、シテがアシライで出て一の松で止まり、「あかで見る、心を花の心とや」と謡い、ワキとの対話になります。シテは山姫と明かし、舞台に入り、やがて、ワキから「四季の眺めの有様、くわしく御物語候へ」と言われ、序・サシ・クセと、いつもの能の構成で、四季をめぐる趣向なんだ。最後は春に戻り「明けゆく春こそ久しけれ」で終わる。
明生 詞章を読んでみると、なかなかいいですね。
能夫 「匂やかに咲ける澤辺の杜若」とか「卯の花の垣根にしのぶ時鳥」、「暗き夜半にも蛍飛ぶ、影も星とや見えぬらん」とか、非常にすばらしい。最後「白波のよるかと思へば東雲の空の、……明けゆく春こそ久しけれ」と終わるのはスタンダードな感じですが。
明生 舞はどうなりますか。
能夫 太鼓入りの中之舞か序之舞かを選択できます。今回は中之舞で舞おうかなと考えています。大小物の中之舞でもいけそうです。
明生 装束をどうするかですね。
能夫 腰巻で天女の出立と書いてある。
明生 全体に天女のイメージですね。
能夫 面も「小面」か「増女」で。そんなにドロドロした内容ではないから、きれいな方が絶対いい。
明生 だいぶイメージができてきましたね。
能夫 一年前ぐらいから取り組んでいるからね。復曲能でしょ。最初から物を作るに近い感じですから、それができる喜びを感じています。新しいものにチャレンジするというのは楽しいことですよ。
明生 掘り起こす作業は楽しいものですよね。
能夫 これが僕を呼んでいたんだよ。若いときからね。今、いい環境のなかで、責任者としてやらせてもらっている、‐9‐『卒都婆小町』 シテ 粟谷菊生 平成3年3月粟谷能の会 撮影:吉越 研幸せですね。まだまだ漠然としているところもあるけれど、それはもう仕方なくて、風情を大切に割り切ってやるしかない。あまり格好ばかりつけていても、能に拒否されるような気がするしね。だから坦々と勤めますよ。
明生 それがいいですね。楽しみにしています。
能夫 ではここらで『卒都婆小町』に行こうかな。
明生 父・菊生が『卒都婆小町』を勤めたのは七十代になってから、案外遅いです。
能夫 うちの父・新太郎は演っていないからね、
明生 その代わり、新太郎伯父は老女物では『鸚鵡小町』を勤めていますね。父は『鸚鵡小町』は演らなかった。
能夫 『卒都婆小町』などの老女物は還暦過ぎてからでないとというのが、暗黙のうちにあった気がします。

『卒都婆小町』シテ 粟谷菊生 平成3年3月 粟谷能の会 撮影:吉越 研
明生 私の記憶では、実先生(喜多実・十五世喜多流宗家)がなさるときに、友枝喜久夫先生や新太郎、菊生といった当時の精鋭が地謡でしたが、当時は『卒都婆小町』を大事大事にし過ぎて、あまり演じられないものだから。慣れていない、と言うのか……。
能夫 『卒都婆小町』は老女物といってもちょっと違うからね。現在物、狂乱物ですから、老女物の入口に位置しているといっていい。『羽衣』のようにしょっちゅう出るものではないにしても、流儀として、みんながもっと経験できるようなシステムがあってもいいよね。
明生 そうですね。実先生のあとは、後藤得三先生、喜多長世先生(十六世喜多流宗家)、友枝喜久夫先生がなさいました。
能夫 先輩ではそのぐらいですか。その後、菊生叔父、友枝昭世さんが演られたね。
明生 普通、老女物は一回勤めて終わり、という方が多い中、二回、三回と再演されて、進化させていますね。
能夫 最初はオーソドックスに勤めて、再演することで、それをカスタマイズできるからね。
明生 能夫さんは平成十七年三月の粟谷能の会、新太郎伯父の七回忌追善能で『卒都婆小町』を披いていますね。父・菊生が地頭で、私もそのときに地謡で謡わせてもらい勉強になりました。そういう機会があって、だんだん自分もシテへと気持ちが向いていきます。
能夫 平成十七年三月というと、五十七歳か。‐10‐『卒都婆小町』 シテ 粟谷能夫 平成17 年3月第77 回粟谷能の会 撮影:東條 睦
明生 早かったですね。私、今度の三月は六十二歳です。本当は数年前、『卒都婆小町』を演りたいと申し出たのですが、まだ演ることがあるだろうと言われ、その時は『求塚』になりました。
能夫 今回は満を持しての挑戦になるね。『卒都婆小町』に限らずだけれど、囃子方や地謡、そういうメンバーが揃い、シテも時期が来て、みたいなものがあるからね。
明生 そうですね。今回はワキが森常好氏、囃子方は小鼓が大倉源次郎氏、大鼓が亀井広忠氏、笛を松田弘之氏にお願いしました。精鋭が揃い、いい人選になったと喜んでいます。
能夫 それにしても『卒都婆小町』は面白いよね。
明生 まだよくわかりませんが、そんなに面白いですか。
能夫 楽しいよ。すべてがね。あの気持ちのよさ。卒都婆問答のこ気味良さ、芝居心、後半の深草少将に憑依しての狂い、すべてが面白いよ。稽古の時も舞台に立った時も、すべてが楽しい。
明生 シテが習ノ次第で登場するときに、橋掛りの途中で休息する場面がありますね。そこを父は二の松のあたりで柱に手をかけて休むようにしましたね。やれやれ疲れたという時の老人の所作を、杖に体を預けるようにする人、背を後ろに反って伸びをする人もあるそうですが、父は老人を観察して、柱に手をかけるようにした。
能夫 菊生叔父の工夫だな。
明生 そうですね。その後は、舞台中央に床几を据え、床几を卒都婆と見立て、シテ(小町)がそこに腰かけると、僧に咎められて卒都婆問答が始まります。
能夫 卒都婆問答は屁理屈だけれど、咎める僧を論破してしまうんだから、気持ちいいよね。知力というか才気というか。相手は高僧だよ。それを最後は「頭を地に付けて、三度礼」させてしまうんだから。ここは権威主義的にやってもダメなんだ。ダジャレもあるし。
明生 「極楽の内ならばこそ悪しからめ、外はなにかは苦しかるべき」というシテの謡がありますが、極楽の内なら悪いだろうが外なんだからいいでしょと、この「外は」は明らかに「卒都婆」にかけたダジャレですからね。
能夫 能では笑いは起こらないけれど、クスッとなってもおかしくないところだね。‐11‐
明生 卒都婆問答で論破したあと、僧は不思議に思って、小町に「御身はいかなる人ぞ」と問い、名を名乗らせますね。このとき小町は恥ずかしそうにして、それでも「出羽の郡司、小野の良実が娘、小野の小町が成れる果てにてさむらふなり」と名乗るところ。野村四郎先生は、あそこでシテの顔がポーッと赤くなるような艶ある表情が必要だとおっしゃってますね。(ホームページ読物・ロンギの部屋「野村四郎氏と『卒都婆小町』を語る」参照。)
能夫 老女と言っても、昔美しかった人、歌詠みで知られていた人の成れの果ての恥ずかしさもあるし。その小町が僧を論破していく過程に芝居心あり、演劇性あり…。
明生 そして後半の狂い。急に深草少将が憑依して、声も変わり、「小町のもとへ通うよのう」ですからね。
能夫 小町は深草少将を九十九日も通わせておきながら袖にしてしまうけれども、それへの傷をずっと背負っているんだな。思われ続けることへの負荷ですよ。そうして年を重ねて百歳の老婆になると、あんな風になる…。
明生 深草少将の百夜通いの果てに死んでしまうところまでを演じ、こんな風に少将の怨念が憑いて自分を狂わせると言いながら、最後は「悟りの道に入ろうよ」でしょ。現在物で小町はその場ではまだ生きていて、成仏を願っているんだけれど、何だかもう向こうの世界に逝っているような錯覚に陥るんですよ。ただ成仏させて!と願えばいいのかな。でも、最後は音楽的には静まってきますからね。

『卒都婆小町』シテ 粟谷能夫 平成 17 年3月 第 77 回粟谷能の会 撮影:東條 睦
能夫 百夜通いの激しい狂いと、その後の「悟りに入ろうよ」の変化、地謡としても切り替えが必要だね。昔はただガーッと謡うだけだったけれど。ところでこの曲、もともとはかなり長い曲だったらしいね。シテの着きセリフの後にももう一段シテ謡があったらしいし、それに最後「かやうに物には狂はするぞや」のあとに、玉津島明神の使いの烏が登場して、小町を救済するような場面があったらしい。それらを世阿弥が削除して今の形にしたと言われている。
明生 狂乱したあとに、「悟りの道に入ろうよ」がどうも唐突な感じでしたが、そういう展開ならわかりやすいかも。でも簡単に救われない形にして余韻を持たせるやり方は世阿弥らしいところかもしれませんね。
能夫 烏のことや、今の形になる前の詞章など、はっきりしたことは分かっていないが、そういうことがあったらしいということは抑えておきたいね。ところで、面はどうするつもり?
明生 能夫さんは「檜垣女」でしたね。私は痩女系の「老女」で勤めたい、と思っています。芯の強さが感じられ、しかも昔の美形を背負っているような……。
能夫 老女物といっても、老女過ぎてもいけないと思う。髪も白髪ではなくごま塩ぐらいのほうがリアルさが出る。
明生 私も真っ白は似合わないと思います。
能夫 とにかく『卒都婆小町』は面白い。そこを感じて演ってくださいよ。
明生 分かりました。演って感じてみたいです。 (つづく)
君子南面す投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
君子南面す
粟谷菊生
「君子南面す」と言う。昔、君子は南に向って坐すものとされ、従って能舞台は北に向っている。然し、シテが曲の上で南に向わねばならぬ時、君子にお尻を向けることになってしまう。それでは失礼に当ると、喜多流は舞台で演じる時、目付柱の方角を北とし、笛柱の方角を南としている。観世流は全くその逆をとり、シテ柱の方角を西としている。
ところで、屋外で行われる薪能などの場合、薪火の焚かれるのは日が暮れてからで、薪能と言っても初番は日の沈まぬ夕方から始められる。或る時、入日を拝む型を演ったら、ホンモノの夕陽を背後に浴びることになってしまい何とも妙な気分になった事がある。又姫路城で薪能を舞った時は、その日の午後、正面の中心を何処にとろうかと見渡していたら、前方にジャスコのネオンサインがあったので、これは丁度よい目標になると決めていたら、折からの石油ショックでネオンがつかなくなり、前方真暗で内心あわててしまった事もある。
因みに当流の「邯鄲」は、方角が全部逆になると先人から伝えられている。それは盧生が夢の中で舞うので方角は全く無視されているためだとか。
ちょっと能舞台にまつわる方角の話をあれこれ。
当麻投稿日:2018-06-07
当麻
粟谷能夫
 私が『当麻』という曲に本当に出会ったのは観世寿夫さんの舞囃子でした。シテの身体より出る圧倒的な力を感じました。それは曲に対する思いや、曲のもっている世界、そしてシテの思想ともいうべきものが綾をなしていたのだと思います。
私が『当麻』という曲に本当に出会ったのは観世寿夫さんの舞囃子でした。シテの身体より出る圧倒的な力を感じました。それは曲に対する思いや、曲のもっている世界、そしてシテの思想ともいうべきものが綾をなしていたのだと思います。
それから数十年経て、私自身の『当麻』を演ずることとなりました(平成十六年春の粟谷能の会)。いつもどおりに謡本の読み込みや資料集めに取り掛かりました。二上山の麓の寺となれば、悲劇の死をむかえ、古墳の闇から復活した大津皇子の魂と藤原郎女(中将姫)との交感を題材とした折口信夫の「死者の書」があり、多くの教示をいただきました。
余談ですが中将姫の父である横佩の右大臣藤原豊成の横佩とは、当時縦にさげて佩(は)く大刀を横だへ(え)て吊る佩き方を考え出したことによるもので、豊成は伊達者であったそうです。
そして『当麻』の世界を的確にとらえた小林秀雄の文章です。「中将姫の精魂が現れて舞う。音楽と踊りと歌との最小限度の形式、音楽は叫び声の様なものとなり、踊りは日常の起居の様なものとなり、歌は祈りの連続の様なものになって了っている。そして、そういうものがこれでいいのだ、他に何が必要なのか、と僕に絶えず囁いている様であった。音と形との単純な執拗な流れに、僕は次第に説得され征服されて行く様に思えた。」小林氏は能『当麻』の描く世界を直感し、能の持つ、呪術的な力を感覚的に受け止めています。恍惚とするような歓喜の状態に入り込んだのでしょう。このあたりにこの曲の本質があるのだと私は思います。そして「中将姫のあでやかな姿が、舞台を縦横に動き出す。それは、歴史の泥中から咲き出でた花の様に見えた。人間の生死に関する思想が、これほど単純な純粋な形を取り得るとは。」と言っています。昭和十七年に梅若万三郎の『当麻』を見て「無常という事」に書いたものです。私も『当麻』は浄土経の讃美歌の様な曲で、人間の一生が下敷きになっていると思うのです。
前シテの老尼はツレの侍女「若い女」を伴って現れ、念仏を勧め、中将姫について語ります。そして二人は阿弥陀如来と観世音菩薩の化身である、化尼、化女であると言って中入りとなります。この前シテとツレは、生身の阿弥陀如来と中将姫の化身であるととらえても良いのではないでしょうか。双方とも、人生を悟った人の心と、未だ無垢な少女のような人の心のゆらぎを抱えているように思われます。後シテは中将姫の霊として現れ、法悦の姿を表し「早舞」を舞います。宗教性を高度な音楽性によって表現するような「早舞」と言われますが、私は西方浄土の空気のようなものを舞っているのだと考えています。
先代観世銕之亟さんはこの曲の「早舞」とは曼荼羅を織っているのだとおっしゃっていました。まさにシテの『当麻』に対する思いや考えをタテ糸にし様々な教え等を横糸として織り上げて行くものだと思うのです。
写真 『当麻』二段返 シテ粟谷能夫 撮影 東條 睦
能面を生き返らせる投稿日:2018-06-07
能面を生き返らせる 粟谷能夫

第八十四回・粟谷菊生三回忌追善粟谷能の会において、粟谷明生が『絵馬』「女体」の演能で、豊橋市魚町能楽保存会の所蔵する能面を拝借いたしました。
前シテには出目友閑作の「小尉」、後シテには井関河内作の「小面」、天鈿女命(あめのうずめのみこと)には出目是閑作の「増女」、手力雄命(たぢからおのみこと)には「大天神」(作者不詳)を使いました。いずれも保存状態もよく、質の高い名品で、舞台を引き立てていただきました。
魚町能楽保存会所蔵の面・装束は三河吉田藩(現在の愛知県豊橋市)の藩主、大河内松平家に伝わったもので、明治維新後も城下の町人の手で大切に保存されてきました。空襲など幾多の困難を乗り越え、このように平成の現在まで伝わってきたことは、奇跡に近いものと思います。保存会の皆様の今日までのご苦労に感謝申し上げます。
能面は舞台で役者が使うことで演者の思いを受け血が通い、精気を宿して能面として完結するのです。
能面を美術品とみる趣がありますが、舞台に上がらない面はどんどん衰えていくような気がします。
高知の山内神社で薪能『熊坂』を勤めたときに、山内家伝来の面「長霊べし(漢字で)見」を使わせていただいたことがありますが、彩色の剥落があり、恐る恐る掛けた記憶があります。その折、神社所蔵の旧山内家の面を見せていただきましたが、保存状態が悪い面が多く、まことに残念な思いがありました、良い面も何面かありましたが、今はどうなっているのでしょう。
また、山口薪能を主催していただいている山口市の野田神社所蔵の能面もすべて見せていただきました。質の高い面が多数ありましたが、時間の経過と共に状態が悪くなるのではないかと心配しております。
江戸時代は能を愛好する大名が多く、各地で面や装束の名品が作られました。それを今も大切に保管しているところは多いと思いますが、演能に使われるでもなく、死蔵に等しい状態になっているのではないかと危惧しています。そのまま朽ちていくのでは余りにもあわれであり、日本の文化遺産の損失となりましょう。
ぜひ各地に埋もれている面を舞台の上で見たいと思います。傷みがあればその機会に修理できます。すぐれた面に息を吹き返してもらいたいと切に願います。演者にとってもよい面との出会いが刺激的な舞台を創り出すきっかけにもなるでしょう。多くの方の力を結集して、面の掘り起こし、再生運動を、ぜひやっていきたいものです。
回転する型投稿日:2018-06-07
回転する型
能の舞の動きには回転する型がありますが、
基本は「廻り下り(まわりさがり)」と「廻り返し(まわりかえし)」の二通りです。
動きの激しい曲には、飛び回りと言って飛び上がりながら回転するものもあります。
また移動しないで一ヶ所でクルクル廻るもの、例えば『土蜘蛛』や『舎利』にありますが、これは究めて異例で、基本は上がるか、下がるかのいずれかになります。
では基本の「廻り下り(まわりさがり)」 と「廻り返し(まわりかえし)」
の違いはどのようなものなのでしょうか。
「廻り下り」は演者が鏡板の方、つまり囃子方の方に向かって移動しながら回転するもので、
「廻り返し」は逆に神が降りていると思われる正面先に向かって回転する動きです。
この違いを陰陽で考えると、
「下がり」は陰で暗く、水底に沈んだり地獄に落ちるイメージで、
「廻り返し」は陽で明るく、神に近づこうと天空に上がるイメージ、祝言の心、
と私は解釈しています。
演者が廻りはじめたら、前か後ろか? と気にして能をご覧になられるのも、一つの鑑賞法かと思います。
我流『年来稽古条々』(23)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(23)
研究公演以降・その一
『三輪』『熊坂』について
粟谷 能夫
粟谷 明生
明生 今回からは青年期以降のことを話していきたいと思います。青年期の様々な課題を終えて、能楽師としてどう生きていくか、第二のステージに立たされるとき。能夫さんと二人で研究公演を立ち上げましたね。第一回は平成三年で、能夫さんが四十一歳、私は三十五歳でした。
能夫 研究公演は明生君が言いだしたね。当時は粟谷能の会でも父や菊生叔父が頑張っていたから、僕らは初番かトメに出してもらうぐらいだったでしょ。曲目の選択の余地はなかったし、僕ももっとたくさん舞いたいと思っていたところだったからね・・・。
明生 私は将来の見通しというものが気になる性質(たち)で・・・(笑)、十年後十五年後は、どのようになっているか心配症で、推測してしまう性分で・・・。もちろん推測ですからハズレも無駄もあります。不謹慎ですが、そのうち父も新太郎伯父もいない時代が来る、そのときを見据えて、今から力をつけて準備しておかなければいけないと・・・三十代になって危機感を持つようになったのです。
能夫 明生君の覚悟みたいなものを感じたよ。実際、十五年後にはその通りになったからね・・・。
明生 力をつけるにはどうするか。青年期を過ぎたら、曲とどうのように出会い、対処するかが重要だと思います。難易度の高い曲を披きという形で挑戦したり、あるいは一度勤めた曲を小書によって視点を替えて取り組む、あるいはよく演じられる曲についても、能役者が自分の成長にあわせて、その年々に曲とどう出会い、どう掘り下げるかを問うべきだ、と思います・・・。
能夫 それをやってきたのが研究公演だったね。「研究」と名がつくだけに、師や親に言われるだけのものではない、自分たちの思いや志を形にする、研究的に取り組む姿勢だよね。曲の読み込みを主として、己の能を自分なりに考え創り上げていくことが第二ステージには必要でしょう。
明生 青年期までの能の習得はまずは基本形、第一ステージから入り、謡と型を体の器官に叩き込む、という方法で技を修得します。体に染みこんだものは老いても忘れないという教えからで、能を志す者はこの方法で鍛え上げられます。基本は大事なことです。しかしその段階をクリアーしたと満足していては不十分と気がつかないといけないでしょう。第二ステージからは作品の読み込みが不可欠で、体に叩き込んだあと次の段階に何をするかが大事ですね。
能夫 そういうことだね。小書については、やれ特別演出だとか、目新しいことをすればいいと考えるのは問題だ、と苦言を呈する方もいるね・・・。
明生 確かにそうです。小書を四つも五つも並べるのは趣味じゃないですが、でも作品の読み込みに、小書は一つの良い手段になります。一応、初演は小書なしで勤め、次に小書で挑戦する、すると新たに見えてくるものがあります。たとえば『安宅』で、普通にお披きをしてから「延年之舞」という小書に挑むのであって、いきなり「延年之舞」はあり得ません。つまり「延年之舞」は作品をより深く読み込む投薬になる可能性がある、最終的には、小書をつけなくても作品の真髄を表現出来るようになれたら、最高位だと思います。「却来(きゃくらい)」とは・・・、最終地点がともするとスタート地点に近いところにある、という考えだと勝手に解釈しているのですが・・・。私個人の意見としてですが、能役者が原点に戻る一つの手段として小書演出に取り組むことは大事なことだと思います。いろいろな発見がありますから。
能夫 明生君はこれまで小書に意欲的に取り組んできたけれど、そういう思いはなんとなく感じていたよ。
明生 研究公演の第一回の番組に「様々な試みを研究し、私たちのよりよい演能を!」という、我々のモットーのような一文がありますが、あれ、気に入っていまして、まさにその通りで、演ってみたい曲に取り組み、小書など様々な演出や工夫を試みる、そんな拘束されない会にしたかった。自分たちの会ですから、少々冒険をしても許してもらう、自由に思い切りやろうと・・・。
能夫 燃えていたね。明生君はこの当たりから本当に意識的に能に取り組むようになった、昔と変わったね、成長したなと思ったよ。喜ばしいことですよ(笑)。
明生 それで、この当たりから振り返ってみたいと思うわけです。実は、研究公演についてはホームページのロンギの部屋で「研究公演つれづれ」として掲載しています。今回多少重複するかもしれませんが、研究公演で取り上げた曲を手がかりにして、その後の展開や能への思いなどにも広げて話し合っていけたらと思いますが・・・。
能夫 研究公演で取り上げた曲は、いずれも思いのある曲ばかり。その曲を手がかりにするのは話しやすいね。
明生 ということで第一回の曲からはじめましょう。
能夫さんが『三輪』、私が『熊坂』でした。能夫さんは『三輪』でも当時は珍しい「岩戸之舞」の小書で勤めましたね。『三輪』の小書といえば「神遊」です。私も「神遊」には憧れがあって、昨年粟谷能の会「粟谷菊生一周忌追善」で披きました。「神遊」は『道成寺』を披いてから許される位の高い小書で、流儀の者ならば憧れる小書ですね。それをあえて「岩戸之舞」にこだわったのはどうしてですか。

能夫 それは以前からの志、ということかな。「岩戸之舞」という小書について、我が家の型付には二通りあることを僕は早くから認識していたんだ。ところが先人たちは一方の型しかやらない。僕はもう一方のものを掘り起こしてみたいと思っていたんだ。
明生 そのふたつの型はどのように違いますか。
能夫 よくやられる型は天照大神がどこに隠れているのかと、暗闇の中を探す型でイロエの型が入る。もう一方の型は神々が神楽を奏し舞うと、天照大神が天の岩戸から出るというとても原始的なもの。天鈿女(あまのうずめ)が岩戸の前で舞ったという神話があって、それが芸能の始まりともなっているわけでしょ。そういうとても原初のものが喜多流にもあるということを演っておきたかったんだよ。
明生 『翁』にあるような型をしますね。
能夫 そう。扇で口元を隠し、袖をかづく型で太陽の出現を表したり、また左袖を巻く、喜びの型もするんだ。来年、僕は『葛城』を勤めるけれど、それにも「岩戸之舞」があるよ。観世流には『葛城』に「大和舞」という素晴らしい小書があり憧れてしまうが、それに匹敵しないまでも、同じような舞です。岩戸の前で舞った原始の舞だよね。
明生 それにしても『三輪』という曲は原始というか、いろいろなものが入り混じっていて、複雑な曲ですね。
能夫 神婚譚が出てきたと思ったら、天の岩戸を開く話になり、話が前後したり重複したり、関連がなかったり、何か変だよね。それらを重層させることが、一つのまじないのようであり、呪術性が出るかもしれないけれどね。
明生 複雑ですが、一つの表現方法ですよね。原初の神、神話に出てくるような神は、一般的な神の存在意識よりも、もっと身近なものとしてあったのではないですかね。
能夫 肉感的であり、現実的なものだっただろうね。神様だって男もいれば女もいるしね。
明生 崇め奉るような高みにあるようなものではなく、結婚もすれば性交もする、不思議なエロチシズムがあって、とても身近で、人間的・・・。でも能はそれらをうまくオブラートに包んでいますね。そのあたりに気がつくのは、ある程度年を経てからかもしれないなあ。
能夫 『三輪』の後シテは緋色大口袴をはいて、鬘帯をして出てくるというのが普通のイメージでしょ。でも観世寿夫さんは、小書「素囃子(しらばやし)」で原始的な出立ちで出てこられてね、それが素敵なんだ。そのイメージもあって、原初にかえる曲創りをしてみたかった。
明生 私は昨年、憧れの「神遊」を勤めて、正直『三輪』はもういいかなと思いましたが、ここで話していたら「岩戸之舞」で新たな工夫をして演ってみたくなりました。思い切りわがままにね。もう少し年を経てからがいいかな・・・。
今度は私の『熊坂』の話にしましょう。能夫さんが選曲してくれましたね。
能夫 『熊坂』ってたいへんな曲だからね、ちょうど挑戦するのによい機会だと思ったんだ。
明生 自分の会で、『熊坂』に挑むとなると、俄然やる気になりました。三役も自分たちで決めて交渉係は私、番組作成も。二回目からは新しい形にしたいとグラフィックデザイナーとも相談して・・・、自分自身でプロデュース出来る貴重な会として、実に面白いと思いましたよ。
能夫 それが「人任せ」の会とは違うところだね。すべてを学ぶことになるね。
明生 『熊坂』の中入りの型は常座で廻返シと型付にはあります。披きではありましたが、そこを、父の薦めもあって、スーッと消えていくように、何もせずに幕に入る替えの型で演りました。それをご覧になられた銕仙会の笠井賢一さんに「あの溶けて消えていくような感じを表現するには、シテ方と囃子方とが双方もっと何かする余地がある。菊生先生の謡と明生君の動きが、ちぐはぐに感じたのはどうしてだろうか?」と言われました。
能夫 単に型を替えるだけではなくて、その舞台全体でムードを替えなければならないということかな。
明生 そうですね。父の地謡は従来の廻返シに似合った謡い方で押し通して、そこに力量不足な私がスーッと消えようとしても効果が上がらなかったのだと思います。後日、父に「何もせずに中入りする場合は、常の廻返シの時とは違うように工夫し、謡わないとだめみたい」と話したら、父がいやな顔しながら、ごもっともだな、と答えたのが印象的で、型を替えるならば、囃子方も地謡も全部が協力して創り上げていかなければ無理だということを学びました。当たり前のことですが、肌で感じた勉強でしたね。そして、演者サイドばかりで話すのではなく、笠井さんや見所の第三者にも指摘してもらうことの大事さも知りました。
能夫 僕は『熊坂』をその後、喜多自主公演(平成十七年十一月)で演っているね、もう、三年前!か
明生 『熊坂』は、若造では勤められない曲だと思います。後場で長刀を振り回し、動き廻るので、あまり年をとってから勤めるのは苦労するかもしれませんが。
能夫 でも、菊生叔父も演っていたね、観世銕之亟先生も晩年になさっている。僕も『熊坂』という曲は本当は若造ではできない曲だと思うよ。だからみんな、五十歳を過ぎてからやり直すというか再挑戦している。その姿を見ていたから、自分も・・・と思った。演ってみると、いやあ面白いんだね。もちろん若い頃ほど体は動かないよ。でもそれでもスタンスを替えて挑戦する、これはまさに『熊坂』のシテ・熊坂長範なのよ。その悲惨さみたいなものが、その年になってしみじみとわかるようになる。体を通して表現できるようになるというのかな。先輩たちもそういうものを目標にしていたと思うね。
明生 体の動きが鈍くなり、そういう体力的なものに追いつかなくなるジレ、それがかえって作品を引き立たせるのかもしれません。もちろん、歳を経ねば何事も・・・ということではないのですが。
能夫 動けなくなったときの喪失感だね。
明生 でもそれには、若いうちに、動いて動き廻っておかなくては成就しませんね。年をとって、さあ本物を演ってみようとしても、そりゃ無惨ですからね。
能夫 最初から動けないのはダメだよ。年月が経ち、前みたいに動けない、でも必死になって挑むというムードね。肉体はついていかないけれど、精一杯やっているという中から出てくる表現だね。
明生 老いの抵抗? 必死なもがきみたいなものが喪失感を溢れ出すのでしょうか。私も二、三年のうちにもう一度演ってみようかな。
能夫 体が動かなくなったとき、永年培ってきた精神力というか、精神性、いろいろな思考がマッチしてきて、舞わせてくれるんじゃないかな。
明生 『熊坂』に長裃という仕舞の小書がありますね。
能夫 僕は後に研究公演でやったよ。『熊坂』の仕舞を長裃をつけて舞うんだ。昔、意地悪なお殿様が、わざと難しい注文を付けて演らせたのかもしれないね。長裃は裾さばきが難しいから、飛んだり跳ねたり、飛び廻ったりするのができない、別な表現方法が必要になるんだ。僕も演ってみてそう思ったよ。
明生 新太郎伯父は長裃でも飛んじゃいましたね。追悼号の「阿吽」に掲載された写真が『熊坂』の長裃姿ですね。
能夫 ああ、あのときは菊生叔父が謡ってくれてね。父は長裃の扱いに自信があったんじゃない。同じような趣向で『谷行』の素袍という小書もあるね。父が演るにあたって、実先生に教えを乞うたら、「私は知らない。後藤の兄が六平太先生から伝承しているから兄に聞け」と言われて、習いに行ったよ。僕もその稽古に付き合っているから型は知っている。『谷行』の素袍は後藤得三先生から新太郎、そして僕へと、伝承されているというわけなの。裾さばきに独特な工夫があるよ。
明生 能は高年齢になっても、いろいろ条件をつけてやり様があるということですね。
能夫 能はその人の生き様みたいなもので、表現できる範囲がいくらでも広くなるということですよ。それができるためにも、早くから曲の読み込み、研究、工夫が必要だね。
(つづく)
役の真実と出会う心投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
役の真実と出会う心
粟谷能夫
近ごろ自分が思い、舞台をやりながら考えることは「軽くて深い」表現を実現したいということだ。

最近、高知の能楽堂で二回目の『道成寺』を十数年ぶりに演じたが、初演の時は道行のところを大事にするあまり重っくれてしか出来なかったのが、今回はただ頑張るというのではなく、『道成寺』という曲のリアリティを持ちながら、自分というものが見えていて、かつその上で表現が出来たように思った。これが離見ということかなとも思ったが、それが当たっているかどうかはともかく、ある余白のようなものを表現出来た。
能を演じるには、まず台本である謡本を読み込み、理解し詩章の行間や裏側にある「思い」を読み取り、それにふさわしい謡と演技が必要とされる。謡本にはシテとかワキとかという役があり、役は特定の人物像、あるいは個性を持ち、当然さまざまな感情や思いを有し、それが葛藤を生み「ドラマ」へと発展していく。そうしたものを表現するために謡と型がある。型は先人の試行錯誤の積み重ねであり、出来上がった型をつなげるだけでは能は成り立たない。その型が導き出されてきた課程、根拠といったものを台本から理解する必要がある。そしてその理解をもたらす大きな要因は謡ということだと思う。何よりもまず、役としての謡の真実があり、それ型へとつながっていくのだ。
曲を理解し、曲を謡うこと。型より入る能ではなく謡からはいる能。これが大切だと思う。我々が若いころは流儀全体として型を優先させる風潮があった。型をきれいに正確にという教えに対し、謡を大切にする本質的な注意がされていなかった。それでは曲を謡うという魅力ある謡が出来なくなるのは当然だ。シテも地謡も安易に謡い過ぎるのではないか。いま必要なのは、上手に謡うとか、正しく謡うといったことの先にある曲の真実、役の真実を謡うことであり、そのことを通してしかリアリティのある型は導き出されてこないということなのだ。
『八島』の修羅道について投稿日:2018-06-07


能『八島』は、喜多流では『八島』と書きますが観世流は『屋島』です。もっとも観世流も大成版以前は『八島』と書かれていたようですが、八の方が末広がりでめでたい感じがします。
私が『八島』の仕舞を勤めたのは今までに25回を数えます。それは若い時分、父が舞う機会があれば必ず『八島』と番組に記載したことに依ります。青少年時代は義経の修羅の苦患、妄執などは無縁で、ただ元気よく舞えばいいと思っており、指導法も強く強くと理屈抜き、身体を激しく動かすことに集中していました。子どもの頃は謡本を見ることなく、先生の謡われた通りの鸚鵡返しの稽古なので、シテ謡の「今日の修羅の敵は誰そ、何、能登守教経とや」を「今日の修羅の、かたき、わたそ(渡そう)、なにの とのかみ(何の、殿守)」と発音していました。音(おん)だけで覚えて起こる現象です。お恥ずかしい話ですが、それでも通用してきたので可笑しなものです。
ツレは6回勤め、その内3回が伯父故新太郎のシテでした。伯父は『八島』が好きだったようです。このツレは若者でなければ舞台映えしません。私も20歳に伯父のツレを初めて勤めてから、最後は37歳、父菊生のNHKテレビ放送の録画の時で、ぎりぎり間に合った感じです。以前は一声の「漁翁夜西巌に傍って宿す、暁湘水を汲んで楚竹を燃くも(老いた漁夫が夜に舟を西岸に寄せて宿り、明け方に湘江の水を汲んで楚竹を焚く)」の漢詩の意味など皆目判らず謡っていたのが実態で、今思い出しますと照臭い限りです。
私はこのツレが誰であるか気になりました。何者か判然としないこの役が物語を立体化させるとか、語りに立体感をもたらすための工夫だと言われる方もおられますが、どうも説得力に欠けます。演じる側としては、誰々と指定されたい気持ちが強く、大半の演者は義経の家来であると思っていて、とりわけ佐藤継信ではないだろうかという意見が多いのです。しかし佐藤継信ならば後場まで居残る喜多流の演出では弓流しの場に居合わせるのが理屈に合いません。高林白牛口二氏は、ツレは義経の霊の分身であると説明されます。義経の霊は漁翁一人として登場するのではなく、ツレの若い漁師にも乗り移って分身として登場するということです。これならばツレが後場まで残る喜多流の主張に合うはずと述べられました。私は今、この説が一番妥当ではないかと納得しています。
先代宗家喜多実先生は、シテの中入と同時にツレは後ろ(地謡側)を向くように指導されていましたが、これは見所に御尻を向け、しびれている足が丸見えで見栄えも悪く、現場はかなり抵抗感がありました。特にアイが「那須語(なすのかたり)」という那須与一が扇の的を射る話を演じる時には景色が悪く、野村萬斎(当時野村武司)さんの披きのときには、私(ツレ)は一旦立って笛座後方に移動し、後シテの一声の登場でまた地謡前に着座したと記憶しています。喜多流の場合、後場にツレが着座する必要性は弓流しの段にツレの謡があるからです。今回厳島神社の御神能という奉納の場でもあるので、試演として従来のやり方を見直し、ツレの友枝雄人氏には中入でシテと共に退場してもらい、後のツレ謡は地謡で謡うことにしました。また通常二同(にのどう=二つ目の同音)「鉢附の板より引きちぎって」のところでツレは立ち地謡前に移動しますが、今回は初同「さて慰みは浦の名の」にて移動して、シテとツレの舞台上での交差を避けてみましたが、効果ある演出と喜多流内部では好評でした。

『田村』『箙』『八島』の勝者の三番を勝修羅と言いますが、この区分けは江戸式楽以降の発想でいかにも武士好みです。作品内容を考えると『田村』は清水寺観世音菩薩の功徳を祝言能として描き修羅とはいえません。『箙』は梶原景季の勝修羅としての勇壮な能といえますが、『八島』の主題は修羅道(敗れても再生し戦い続け苦しむ世界のこと)に苦しむ武将義経の苦悩だと思うので、単に勝修羅と区分けすることに今は意味を見いだせないように思えます。この勝修羅といわれる三曲は青年期までに稽古し習得しておかなくてはいけない曲ですが、稽古順は『田村』『箙』、そのあとに『八島』となります。
能『八島』のシテは昭和59年(29歳)粟谷能の会で披き、今回(厳島神社・御神能 平成16年4月16日)は20年ぶり、「弓流」の小書での再演となりました。『八島』が世阿弥作であることは間違いないようです。作品構成は上手く整理され申楽談義にも「道盛、忠度、義常、三番修羅がかりにはよき能也」と載っています、『義常』は『八島』と言って問題なく、ワキの宿借りの問答は『松風』や『絃上』にも似て、シテもツレも言葉を間違え安く、気を遣うところです。
『八島』の前シテの面は本来「三光尉」ですが、今回御神能に用意された尉の面に「笑尉」がありましたので試しに使用してみました。表情は名前の如く、笑んだ顔のため修羅の苦患とは無縁な前シテとなってしまいますが、能楽師の好奇心で、一度はつけてみようという遊び心でつけてみました。結果は人物像に陰りが出ないのでいま一つだったように思えます。
塩屋に通された僧(ワキ)が八島の合戦の模様を尋ねると、老人(シテ)は「あらあら見及びたるところを語って聞かせ申し候べし」と語り始めます。この語りが聞かせどころで、あまり熱が入り力が外へ発散し過ぎては尉の語りには似合わず、抑制を意識し過ぎ内へ引きこもると臨場感の欠けた修羅場の語りではなくなり、面白味が半減します。丁度よい頃合いを体得することが演者の大事な修業過程の一つで、今回も苦労したところです。
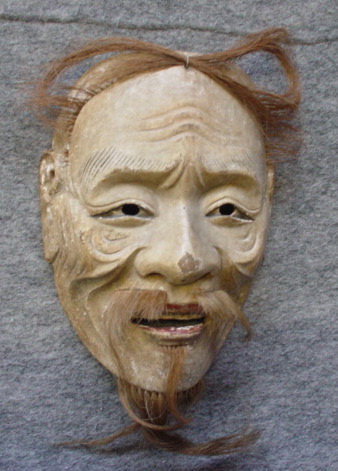
老人は屋島の合戦の有り様をまず義経の装束描写と名乗りから始めます。ここは平家物語「継信最期」の原文に添って前半の見せ場の始まりです。語り終え我に返るように「今のように思い出されて候」と一旦落ち着くように謡いますが、能夫氏は、「菊生叔父や新太郎は、あそこは、最後まで強い口調で熱く謡っていたなあ」と話してくれました。能夫氏は一旦冷静に静まるからこそ、供の男(ツレ)が謡い出す戦況場面がまた生きてくるのではないかと言います。私も同感です。シテを挑発するかのような謡が、ツレの大事な仕事で、その触発にまたシテが語り始める、そのような繋がりの面白さなのです。
平家物語原文では、物語の進行は継信最期、那須与一扇の的、錣引き、弓流と進みますが、能では錣引きの後に継信最期の話となり、那須与一扇の的は狂言方が担当して、後場で弓流となります。子どもの頃より、能の世界で書かれた歴史に慣れ親しんできたため、誤って歴史を認識していたことを知りました。今回平家物語を読み直し、能の屋島の合戦が平家原本とどのように異なって戯曲化されているかを知り勉強になりました。
三保谷四郎と悪七兵衛景清の錣引き、ここも緩急と語る口調に気をつけなければいけないところです。やり過ぎては老人の枠から外れてしまい、内にこもり過ぎては気持ちが伝わりません。こういうところを偉大な先人たちはいとも簡単にやっておられたように思えます。見ていた時は自分も簡単に出来る気でいたのですが、いざ舞台に立つとなかなかうまくいきません。「鉢附の板より引きちぎって」で両手を放し両者が左右にどっと分かれる型がありますが、床几に腰掛けた少ない動きの中での型で難しいところです。この錣引きの模様は能『景清』の方が詳細にリアルに演じられています。『八島』では「これをご覧じて義経」でシテは床几から立ち、継信最期の話へと移ります。義経目掛けて能登殿が放った矢を、継信が身代わりになって受け、馬からどっと落ちます。平家方は教経の郎党、菊王丸が継信の弟忠信に討たれ、源平共に哀れに思い、互いに引き潮のように兵を引き、あとは磯の波や松風ばかりの音が寂しく聞こえるという地謡の謡で、シテはワキに静かに向かい下居します。小さな動きながらも激しい戦闘場面、ここが上手く繰り広げられなくてはと、演者が奮闘するところです。この後のロンギが唯一幽玄の世界となります。世阿弥はここを最も大事にしていたようで、最後の「よし、常の浮世の夢ばし覚め給ふなよ」は、義経と、よし、常の浮世の掛け詞でしっとりとした雰囲気を出し、悲劇の英雄義経の姿を垣間見せて中入します。

今回は小書「弓流」ですのでアイは「那須語」となります。語りの最後は「乳吸えやい、乳飲ませいやい」で終わります。この面白い表現、よくよく調べてみると、「よくやった、でかした与一、褒美に女性のところで甘えてくることを許すぞ」ということのようで、このいかにも武骨な武将らしい言葉の使われ方が私は好きです。
後シテの面は通常、平太(赤)ですが、小書の時は白平太になります。生憎厳島神社には白平太がなく、残念ながら常の平太(赤)にて勤めました。出立ちは厚板、半切、法被の肩脱ぎとなりますが、古来は厚板の上に法被と側次を重ねていました。以前『箙』の時も試してみましたが、なかなか重厚感ある扮装なので今回もまた付けてみました。
一声で「落下枝に帰らず、破鏡再び照らさず、然れども猶妄執の嗔恚とて…」と修羅道での苦悩、妄執を嘆きますが、不思議と救済を求めないのが、この曲の特徴です。おめでたい勝修羅といわれる所以でしょうが、根幹のテーマはやはり殺人者の懺悔、成仏への懇願ではないかと私は思っています。しかしそこを明らかにしないところに、この作品の妙な明るさと特別な味わいがあるようで、判官贔屓にはたまらないのかもしれません。私は今回演じて、何かふっきれない、すっきりしないもどかしさを感じました。勇壮なだけではない、義経自身の悔しさ、敗北者の悲劇がどうにか表現出来ないだろうかと試みましたが、手ごたえを感じるまでにはいかなかったことが反省点で、少し残念に思っています。

喜多流の弓流は、我が家の伝書には「囃子方、装束に変わりなし」、「舟を寄せ熊手にかけて、既に危うく見え給いしに」後に立ち、少し出て下居、「其の時熊手を切り払い」と切り払う型をするとあります。今回は下居せず元の座にシサリながら左手に弓(扇)を抱えたまま床几に腰かけました。弓流はこのもとの所に戻るのが難儀で技の見せ所です。「後見は床几にくれぐれも触れぬこと」と注意書きがされています。最後の仕舞どころに緩急がつき、橋掛りでの特殊な型が入り、「春の夜の闇より明けて、敵と見えしは群れ居る鴎」とまた舞台に入り、激しく面遣いして常座で廻り返しをして留拍子を踏み終曲します。
源義経という人は平家を滅ぼすためだけに生まれてきた人ではなかったでしょうか。義経が登場する能は『鞍馬天狗』『橋弁慶』『関原与一』『熊坂』『烏帽子折』『八島』『正尊』『安宅』『船弁慶』『摂待』などですが、シテが源義経(『関原与一』のシテは牛若丸)はこの『八島』だけです。負けず嫌いの源氏の御曹司は百戦錬磨の名将義経となりますが、壇ノ浦の合戦以降は、人生の歯車がかみ合わなくなります。政治家頼朝の策略に使い捨てのように使われ、奥州、藤原家を頼みに下向しますが、遂に衣川の戦いで自害して果てます。一の谷合戦の奇襲作戦、屋島の戦いの前に逆艪問題で梶原景時と対立し猪武者と言われても「勝ったるぞ、ここちよき」と尻込みを嫌う性格、壇ノ浦合戦では楫取、水夫(かこ)を射殺すルール違反の新戦法で勝利し、あくどさも見せつける義経。これらの出来事で修羅道に落ち、梵天に攻め上っては負け、攻め上っては負けという戦いの日々を暮らす義経の苦悩、これがこの曲の主題であり、そこが表現出来なくては意味がないと思っています。
大槻文蔵先生は、能は歴史の王道を歩いた人ではなく、そこからこぼれた人を描いている、平家物語は歴史を上から書いているが、それを下から描いているのが能だと仰っています。すばらしい言葉で心に残ります。
私はどうにかして義経の心の奥深いところにくすぶっている嗔恚(成仏を妨げる生前の怒りの心)と妄執の苦悩を表現できるような『八島』を勤めたいと、再挑戦を心に期しているのです。
(平成16年4月 記)
写真
『八島』 シテ 粟谷明生 撮影 石田 裕
面 笑尉 (厳島神社蔵) 撮影 粟谷明生
我流『年来稽古条々』(24)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(24)
研究公演以降・その二
『井筒』『弱法師』について
粟谷 能夫
粟谷 明生
明生 今回は第二回研究公演で取り上げた曲について話してみたいと思います。平成四年六月、能夫さんが『井筒』、私が『弱法師』を勤めました。『井筒』は三番目物の代表的な曲。能楽師の憧れの曲ですね。
能夫 そう、僕には憧れがありましたね。

明生 あのときの『井筒』が能夫さんにとっては披きですね。四十二歳、当然もっと前に勤めていてもいいのに・・・、憧れがあったから大事にとっておいた訳ですか? 実は私も『井筒』を披いたのは遅くて、ようやく二年前(五十一歳)です。喜多流では『野宮』はとても大事に扱いますが、『井筒』は意外に若くても出来るのではないですか? 型付通りに動き、謡えばそれなりの格好になりますから。でも私はそれが嫌で拒絶していました。
能夫 『野宮』は相当な覚悟がないと太刀打ちできないね。曲自体が演者を寄せ付けないところがあるけれど、『井筒』は確かに、あまり考えずに型通りやれば格好になってしまうあまさがあるからね。本当は後場なんか、情感とかいろいろ要素が必要だと思うけれど。
明生 そうです。私は『井筒』という曲を意識しない者が、「え?、まずはお試しコースの『井筒』あたりから・・・」という考え方が嫌ですね。安易に取り組まないでほしいです。私は『井筒』を大事にし、し過ぎてしまい機会をだいぶ遅らせてしまった訳で・・・(笑)。
能夫 なかなかこれぞという『井筒』には出会わないよね。本当にそういう面では『井筒』は難しい。あまり巧みすぎてもダメだし、坦々と演じるところも必要な気もするし。
明生 『井筒』の型付は定型の動きの連続ですね。しかも作品の完成度が高いから安心してしまう。でも、そこに演者が寄りかかり状態になってはいけない、演者の思いが彷彿されるような舞台を志す、私はそう思っていますよ。
能夫 そうだね。
明生 当然、舞歌の技術を獲得してからという大前提はありますが・・・・。
能夫 喜多流が劣っているとは言わないが、観世寿夫さんの能を観たときに、『井筒』への、曲への思い入れにずいぶん違いがあると感じたよ。
明生 喜多流の先人たちは『井筒』のような三番目物よりはドラマ性がある四番目物のように、型を利かせるような曲がお好み、という傾向でしたね。それは多分に名人十四世六平太先生への憧れからでしょうか。
能夫 寿夫さんの『井筒』を観たとき、こんなに面白い曲だったのかと感動したよ。それまで墨絵だった能が極彩色に見える、奥行があって、立体感がある。情念、怨みつらみといったものが押し寄せてくる。そういうものを観せられたわけ。あのシンプルな『井筒』の中に。それは憧れてしまいますよ。能の面白さは、ああいう『井筒』のような三番目物にもあると感じたよ。初めてね。それはドキッとしたよ。
明生 私は奥手で、ようやく、最近ぼちぼちと三番目物の魅力に惹かれていますが・・・(笑)。
能夫 あの『井筒』を観たときはまだ若造だったけれど、これからはこういうものを演らなければ! と思ったよ。当時は父たちが元気で演能していたから、それにも携わらなければいけないけれど、内心どこか違うなと思っていてね。今ならいろいろなアプローチの仕方が考えられるが、昔は父たちのやっていることに否定的でね。方法論はいろいろあるけれど、まずはあの『井筒』のなかに憧れるものがある、深いものね。すぐに獲得できるわけではないけれど、その方向でいくと、答えがあると思っていたからね。
明生 ずっと憧れをためていたわけですね。それで、いよいよ研究公演で『井筒』! 能夫さんは小書「段之序」で演りたいと言われて、ところが父に「なにも最初だから、小書なしでいいじゃないか。能夫ならまたすぐにチャンスがあるよ」と止められ、仕方なく断念したでしょ。あれ悔しかったですね・・・。研究公演は、流儀内の閉鎖的な縛りからはある程度自由であったはず、単に稽古したものを先生にお見せする会、そんな主旨の会ではないつもりだったのに・・・と。実際、それから十年以上の月日が経ち、ようやく平成十四年、横浜能楽堂のかもんやま能で「段之序」が実現出来たわけですが。波風立てないでじっと我慢することの勉強だったのでしょうかね?(笑)
能夫 どうかね(笑)。その「段之序」ね。普通はシテが「懐かしや、昔男に移り舞」と謡って、地謡が「雪を廻らす花の袖」と謡って序之舞に入るところを、「段之序」は「雪を廻らす・・・」もシテが謡うでしょ。一声からのシテの謡が段々盛り上がって、高揚していく、そして「懐かしや・・・」「雪を廻らす・・・」と区切りながら、全部シテが謡い、シテ自身が序之舞の位を作っていく感じで、これがいいんだな。
明生 「花の袖」の節扱いは素声(シラコエ)で積み上げ固めたものを、柔らかく溶かすような感じでここが上手に謡えると、いいですよね。この演出、私はいいと思いますが、そうでもないという意見もありますね。通常序之舞の導入部分は、シテと地謡が詞章を分け合い、互いに盛り上げる、という作り方ですが。
能夫 「段之序」はシテが主導権をもって引っ張っていく。囃子方とだけで高揚していく、特別だね。
明生 ですから、シテの謡い方が大事ですね。張りとメラス(?)、謡に変化を付けないといけない。
能夫 『道成寺』の乱拍子の中の和歌もそうだけれど、たたみ込むように謡うことで、エネルギーの爆発を、じっと押さえ、その思いが遂に溢れ出るようなイメージなんだ、似てるでしょ?
明生 「段之序」の歴史は、小鼓方大倉流と喜多流の間に昔からきちっとした約束事がかわされていて。先日、大倉源次郎さんが大倉家の伝書を見せて下さいまして。
能夫 ちゃんと話し合いがなされたということが、残っているんだね。
明生 そうです。『井筒』という曲で、喜多流特有の「段之序」のような、シテ自身が少し高揚していくやり方があるということは面白い事ですよ。本来、昔は、カケリを入れる演出だってあったぐらいですから。
能夫 そういうわけで、後日、「段之序」も演らせてもらったけれど、研究公演の『井筒』では、憧れの曲を、どういう思いを込めるかを考え、『伊勢物語』を読んだりしてね。僕にとっては、『井筒』が原点というか出発点みたいな意識がすごくあるね。シカケ・ヒラキといった技術のうえに、何か物語を作っていくという意識が芽生えた。ものを表現しようという原点みたいなものを感じたね。『井筒』は難しい曲で、いまだに結論は出ないけれども。でもいい時期に、若気の至りみたいな時期だけど、寿夫さんの刺激的な『井筒』を見せてもらったお陰ですよ。もう、目が輝いていた時代だから。
明生 その思いをためて、研究公演で勤めたわけだから。
能夫 そう。研究公演は最初、青山の銕仙会の舞台を拝借して催したでしょ。あの本当にお客様と近いところで、『井筒』ができた喜びもあったね。
明生 さて、私の『弱法師』ですが、これは根底に技術至上主義みたいなものがないと出来上がらないですね。
能夫 そうね。『弱法師』は単にシカケ・ヒラキだけでは通用しない、技と心だね。

明生 なんといっても盲目の杖の扱い方が難しいですね。喜多流の杖扱いは独特で、パチパチと音を強く立てるようにして突きます。杖の先が体の正面中央にあるべきなんですが、ところがなかなか、うまくいかない。左か右に多少ずれてしまいます。上手な方の杖はラインがきちっと、よいところに決まり綺麗で、力をも感じられます。綺麗過ぎて、この人、本当に乞食の少年なの? と思ったりして(笑)。
能夫 長刀や杖という特殊なものを持つときは、まずはきちんとした技術力の修得が必要だよね。
明生 ですからまずは早めに一度経験して、杖の技をきちっと身につけなくてはいけないと思い、早くやりたい、と。それも父から止められて・・・。
能夫 そうだったね。明生君が研究公演の第一回で『弱法師』をやりたいと言ったね。「まあまあ、もう少し後で」と僕も言って、でも二回目には演ったね。
明生 なんでも準備が整えば、早いうちに一度演るべきという考えは生意気かもしれませんが、変えるつもりはありませんよ。技術力がどのくらい大変かを早く知り、早めに稽古に取り組む。年をとると、もう手足だけでなく、頭までも、すべてが鈍くなりますから(笑)。早く手がけて技術をマスターする、プロなら当たり前のことだと思いますが。そこを楽屋内の雰囲気を気にして怠る、遠慮する。それでは不健康でしょう、次が見えてこない。
能夫 杖でも長刀でも同じ、新しい道具が出てくると、その使い方ばかりに気をとられてしまうね。
僕が若いときに見ていた流儀の『弱法師』というものはね、ただ「貴賎の人に行きあいの」のぶつかる型だけの印象なんだよ。あそこだけ(笑)。
明生 ハハハ。私の好きな型は「紀の海までも見えたり、見えたり」と、盲目の目にも難波の風景がありありと見えると手を伸ばすところ。手と顔の向きを正反対にするタイミングがコツだと父は教えてくれましたが、そのあと、少しはしゃぐ風情で舞台をめぐる、しかし、盲目の悲しさで、その場に大勢いる人たちにぶつかり、よろけ、人々に笑われ、確かにここの印象しかなかったですね(笑)。最後にはへたりこんでしまう場面ですよね。
能夫 そう、あの大事な場面ね。寿夫さんの『弱法師』だと、そのぶつかるまでに心の陰影があって、ドラマというか志が立ち上がってきて、ぶつかることが必然だなと感じさせるものがあったんだよ。ところが喜多流のだと、ただぶつかるだけ。陰影も無ければ、心の動きも僕には見えなかったよ。寿夫さんのは、僕がまだ若造で、百%喜多流の意識で見ているから、なんてすごいんだと思ったよ。ああ、これが『弱法師』なのだ、これがお能なんだとね。それまではシテ柱に杖をカチッと当てる格好良さとか、型のことだけ考えていた若造でしたから。あれから自分の能に取り組む姿勢を考える、きっかけの曲となったね。
明生 能楽師は型を追求するだけで終わってしまってはだめですね。登場人物がどういう気持ちでいるか、なぜそのようになるかを知り。そう、なぜ俊徳丸が盲目の境涯になったか、日想観をすることで、目が見えていた時代に立ち返り、晴れやかに心の目で景色を見る、しかし現実の厳しさにふと我に帰る、最後は父・通俊と出会うわけですが・・・、そういうドラマですよね。
舞台になっている四天王寺、その裏手にある悲田院は今もありますが、家族や世間から捨てられた人が施しを受けにやってくる場所だったんですね。以前に行ったとき、詞章にあるようにまさに「踵をついで群集する」という感じで、貧しい人たちが大勢いましたが・・・。二年前に行くと、その人たちはいなくて、景色が変わっていましたよ。
能夫 何かの政策で、移動させられたのかな・・・。
明生 どうでしょうか。『弱法師』という曲は、そういう世間から捨てられた人の物語ですよね。そういうドラマを表現するためにも、早いうちに一度演って、技の修得をしておく。そして次に自分なりの『弱法師』の曲づくりですよ。十郎元雅作の名曲ですから、遣り甲斐と手応えのある曲ですから、若者が早めに一度。
私は研究公演の後、平成十五年八月に、秋田県のまほろば能で『弱法師』を小書「舞入」で勤めました。「舞入」は右手に扇、左手に杖を持って舞いますが、やってみて想像以上に難しかった。左手は一般に利き腕ではないから、思うようにいかない。まあ、それが出来るようにならなくてはいけないので集中して稽古しましたが、一度研究公演で勤めていたからある程度は楽でした。
はじめて勤める時に父から「最低これぐらいのことはやってくれよ」と言われまして。父は技術的なことばかり教えてくれましたよ。
能夫 技術的なこと? はじめての、研究公演の時だね。
明生 そうです。杖の扱い方ですね。この時の杖は右で顔が左、シテ柱に杖を当てたら顔は左、その時やや顔を斜に構え、なんて細かく具体的に教えてくれましたよ。でも挑んだから教えてくれたので、待っていても教えてはくれないんだ、ということが判ったのが一番の収穫かな(笑)。父にとっての『弱法師』は、ある程度技術力を高めることで作品は完成するという考え方だったのでしょう。とにかく技を正確に上手く、使えるように習い、稽古しろ、ということだったのかな。
能夫 『弱法師』は若者にとってすごいプレッシャーの曲、憧れの曲でもあり、挑戦のしがいもある曲、技術力もいる曲だね。だからこそ、次の世代の人たちの俊徳丸が早く観たいよね。(つづく)
研究公演 『檜垣』を謡う心意気投稿日:2018-06-07
老女物の継承
?『檜垣』を謡う心意気?
粟谷明生
伊勢神宮の内宮は2000年以上の歴史がありますが、神殿は20年毎に建て替えられ、これを「遷宮」と呼んでいます。
この行事は1300年も続き、来年62回目を迎えますが、神殿の修復もさることながら、実は神殿造りに携わる職人達の技術伝承が途絶えないように、というねらいもあるといいます。
粟谷能の会・研究公演の『檜垣』は、前回(昭和62年シテ・友枝喜久夫 地頭・粟谷菊生、笛・一噌仙幸、小鼓・北村治、大鼓・柿原崇志)の演能から、実に24年ぶりとなります。遷宮と同様、演能もあまりに時間が経ち過ぎては、よりよい継承が出来なくなる、と考えて、今回の企画をしました。
神殿造りの職人と能楽師、敢えて両者に違いを見出すならば、神殿造りの職人に新工夫や創作は不要で、受け継がれてきた建造技術を体得して、20年前と同じものを復元することが課題となるのでしょう。一方、能楽師は、前回の公演を参考にしながらも、演じる者が、それぞれに自分なりの舞台、今の時代に似合う演能スタイルを心掛けるべきだと、私は思っています。
そこで、今回の『檜垣』の演能での新たな試みを、ご鑑賞の参考になればと記載します。
1,二の同音「理を論ぜざる、いつを限る習ぞや」「老少といっぱ分別なし替わるを以て期とせり」の間に打ち切りを入れて、この部分の主張を強調。
2,通常、次第は同じ和歌を二度繰り返し、その後に地取りとなるが、『檜垣』は「釣瓶の水に影落ちて袂を月や上るらん」と一句のため、地取の中止。
3,動きの少ないクセの部分に、友枝昭世氏に新たに動きを入れてもらう。
4,最後終曲は、一般的には、残りトメ(謡が終わったあとに囃子方だけで一クサリ、演奏するやり方)だが、今回は敢えて、「罪を助けてたび給え」と地謡で謡い切り、その余韻を強調。
粟谷能の会・研究公演の『檜垣』。24年ぶりの老女物の継承と私たちの課題である「地謡の充実」のために、力を尽くして舞台を創り上げたいと思っています。
D席となりますが、当日売り(12月2日午後6時開演)はまだございますので、ご来場をお待ちしております。
粟谷能の会投稿日:2018-06-07
『安宅』を演じて? 能の表現と芝居との境界線 ?
粟谷明生
 平成十一年春の粟谷能の会で『安宅』を披かせていただきました。息子(尚生)と『隅田川』をはじめ『安宅』や『望月』を勤めることは私の夢でもあり、その夢の一つずつがかなっていくことは無上の喜びです。
平成十一年春の粟谷能の会で『安宅』を披かせていただきました。息子(尚生)と『隅田川』をはじめ『安宅』や『望月』を勤めることは私の夢でもあり、その夢の一つずつがかなっていくことは無上の喜びです。
今回『安宅』を演じるに当たっていくつか気になったことがありました。一つは四十三歳という自分の肉体が弁慶になり得るかです。歴史的にはおそらく都落ちしてゆく弁慶の歳は四十代前半ぐらい(義経は二十九歳)ですから、ちょうど今の私に合っているのでしょうが、能の舞台として考えると、この年齢は少し不安です。それは『安宅』のような直面ものには演じる役者が醸し出す味わい、風格というものが非常に大きなウエイトをしめるからです。
シテ方は面をつけることで、その役に入りますが、その面の力に助けられることが大きいのです。たとえば老人を演じるにしても、身体や声が少々若くても、尉の面をつければ、不思議にそれなりに見えてきます。面には偉大な力があります。しかし直面ではその力を借りることができません。身体から発する力をもとに風格を添え、自分の顔自体も面だという意識が必要になってきます。
役者は舞台でその生き方が滲んで見えてくるようでなくてはと解っているのですが、粟谷明生という人間の武蔵坊弁慶を安心して見ていただけるようになるには、まだまだ時間がかかることで、これはなかなか難しいことです。
能『安宅』は弁慶の思慮と沈着な行動がいかに主君の危機を免れさせたが主題です。構成は能本来の要素(謡と舞)と芝居(劇)的要素を取り混ぜた形になっています。その芝居的な部分をいかにこなすかが、大きな関門でした。
『安宅』は形式的には中入りのない一段でできていますが、都から安宅の湊までの道行と関所手前の作戦会議までの一場、関所におけるワキとの問答から、最後の勤行、勧進帳の読上、主君打擲と実力行使にて通過を成し遂げる見せ場の二場、関所通過後の休憩、関守の来訪、酒宴饗応と遊舞、一行の逃走の三場と、それぞれ場所を別にした三場構成となっています。能の定型の一場と三場の間に台詞を中心とした劇的な色彩の強い二場が入っているとみてよいでしょう。
私が苦心したのは第二場の言葉が多い部分、歌舞的要素の無いところでした。ワキとの問答、勧進帳を読み上げるくだり、ワキとの激しい型どころはややもすると、やりすぎのお芝居になってしまったり、また逆に演者の自己満足に留まり、何も観客に伝わらないことになりがちです。
謡本をただ読み上げるだけでなく、いかに劇としての真実味ある台詞を謡えるかが重要です。勧進帳の謡は難しい節扱いや拍子当たりだけに気を取られていたのでは駄目ですし、あまり感情が入りすぎるのも、また劇のレベルに達していないのも考えものです。ワキとの問答も台詞の中に運び、音の高低、張り押さえ、詰め開きを入れ、問答の緊張感を聞いてもらわなくてはいけません。
能の世界でできうる限りの表現をしながら、お芝居にならぬギリギリの境界線の内側で感情の起伏を観客に伝えることがカギとなります。境界線を越えてしまえば能ではなくなり、歌舞伎座や他の劇場で演ずるものと何ら変わらないものになってしまいます。勧進帳という名で歌舞伎のほうが一般に知られていますが、歌舞伎より前に生まれそのルーツとなった『安宅』。能本来のもっている味わいがあるはずですから、それを大事にして演じたいと思いました。
最後に、これは子方のころから不審に思っていたことですが、「一行はどうして通れたのだろうか」「なぜまた関守がやって来たのか」ということです。このことを自分なりに整理し、舞台作りに生かしたいと考えました。
私の考えている富樫像は山伏を容赦なく殺す冷徹で、単に役目に忠実な地方役人というものです。ワキとの問答の末、最後の呪詛の行に入り、「明王の照覧計りがとう、熊野権現の御罰と当たらん事」(不動明王がご覧になってどうお思いになるか、熊野権現の御罰は当然)と凄みますが、富樫はここで山伏を殺したことの恐ろしさを感じ「問答無益、一人も通し申さじ」と頑なだった態度を換え、勧進のために通るなら勧進帳があるはず、それを読むようにと軟化します。中世の宗教観で、山伏という修験僧をむやみに殺すことは神仏の罰が当たることだと感じ、目の前の山伏の迫力にも気圧されたのでしょう。勧進の責任者・俊乗坊重源の後ろにある仏や朝廷の存在も恐れたはずです。
一旦は通すことになりながら、強力が義経に似ていると呼び止められると、弁慶は「強力を止め笈に目をかけ給うは盗人ぞ」と逆にいいがかりをつけ、武力をもって富樫を圧倒し押し通ってしまいます。通れたのは決して富樫の情けなどではなかったと、私は思うのです。また、「最善は聊爾を申し」と非礼を詫び酒を持参するのも、当時の宗教心厚い中世社会では当然の風習であったでしょう。
今回は、このような解釈で演じたいと思い、ワキ、ツレの人たちに、富樫像や、通り抜けたのは山伏の武力や迫力であること、当時の宗教観などを説明し、協力をお願いしました。全員殺されるかもしれないが何としても通るぞという意志と緊張感を、最後まで立衆各自に貫いていてもらいたかったのです。
今自分を振り返ってみるに、諸先輩の『安宅』の子方を経験し、高校生で初めて立衆に参加して大人の仲間入りができ、最近では父菊生の主立衆を数回、そして今回シテをやらせていただいたことは大変幸せだったと思います。長い月日をかけ、いろいろな立場で演じながら、その時その時に思ったこと、感じたことが自分の中でたくさん沈殿していることに気づかされました。『安宅』はそれらの蓄積の大切さを感じさせられた一曲でした。一つの舞台の作成に今までの経験が生かされて良かったと思います。
(平成十一年三月)
我流『年来稽古条々』(18)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(18)
?青年期・その十二?
『石橋』について
粟谷 能夫
粟谷 明生
明生 前回は『道成寺』以降の話をしました。次は『石橋』の話かなと思うのですが・・・。
能夫 そうね。『石橋』といえば、僕の披きは昭和五十九年だから、三十五歳のときだった。宮島の厳島神社で披いている。その年は『楊貴妃』も勤めているね。
明生 能夫さんの『石橋』は三十五歳ですか。能夫さんの世代ぐらいから、『石橋』の披きが遅くなっていますね。
能夫 僕の前の人たちは早かったと思うよ。
明生 二十三、四歳で披かれています。友枝昭世さん、香川靖嗣さん、塩津哲生さん、みなさんお若い時に。
能夫 実先生(先代家元、喜多実先生)が、早く披かせようとなさったからね。
明生 そのようなご意向はありましたね。香川さんは実先生が親をやられ、塩津さんの時は父が親獅子を勤めています。私はそういうものだと思って憧れていたわけです、そのうち出来るんだってね。それがどうして変わってしまったのか・・・。子獅子と獅子つまりシテとツレを一緒くたにし、大事にし過ぎたせいでしょうか。流儀独特の一人獅子(シテ一人が勤める)が重いというのはわかりますが・・・。
能夫 どうしてかね、不思議だよ。前シテを含めてなら話は別だが、半能で後半だけのものでしょ。獅子の披きといったって、赤の方は子獅子ですよ。ツレですからね。明生君はいつ披いたの。
明生 私は平成二年、三十四歳のときで、親獅子は父・菊生でした。私も早くないですよ。
能夫 みんなそれくらいになっているね。『道成寺』が終わって数年してからというパターンになっている。でもあれは二十代前半に披いておくべきものだよ。『道成寺』より前に披いておくべき。謡は無く動きだけのものですから、しかもツレでしょ。
明生 私は三十二歳のとき、以前から「披きは父と!」と決めていましたから、でもどうも待っていても、叶えられそうもないと思いまして、父に一緒にやりたいと申し出たんです・・・。
能夫 粟谷能の会だったね。
明生 そうです。初めて自分で希望曲を言ったわけで・・・、照れ臭いものがありました。
能夫 子獅子の芸はいわば瞬間芸だよね。ある意味運動能力だけで処理出来る世界ですよ。曲を理解するという前に、どれだけ動けるか。若い体に覚えさせる、理屈ではないものなあ。もちろん深山幽谷の世界を演じるのだから、それなりの取り組む姿勢は必要だけれど。
明生 一畳台に上って跳びはねてくるっと回転しても全然恐くないというとき、一番体がきれる若いときに披いていないといけませんよね。大丈夫かな、ちょっと怖いなーなんて心配するようになったら、もう・・・。
能夫 台の上に上がってコワ?イと思っては・・・。不思議だね、昔は何でもなくできていたのに。
明生 回転のスピードもだんだん落ちてくるでしょ。以前は一回転半もなんなく素早く出来たのが、段々スピードダウンして。あともう少し・・・、なんて必死だからバランスを崩したりしてね。
能夫 若い肉体とは違うよ。だから早く披かなければ。
明生 年齢が上がれば運動能力は悲しいかな低下していきます。子獅子には年齢を補うものがあるわけではないし。
能夫 五十代、六十代になって、何かを打ち立てようという種の曲ではないからね。
明生 『景清』や『定家』なら、五十代、六十代と積み上げて芸を見ていただくということはありますけど、『石橋』はそういう曲とは違いますから。
能夫 見てくださる人は面白いでしょうが、深みのある曲とは違う・・・。
明生 昔なら、五番立ての一番最後の出し物で。最後にめでたしめでたしと、ご覧になる方もスカッとしたよい気分で帰れるということですね。
能夫 牡丹は華やかだし、千秋万歳と寿いで、確かに気持ちいいよ。若いころは獅子への憧れもあったし、格好いいしね。悪い曲ではない、だけど『実盛』の霊が出てくるような、ああいう重さはないでしょ。『石橋』の歴史はね、室町時代に秘曲にされ過ぎたためか、一時途絶えるんですよ。それを江戸時代、二代将軍・徳川秀忠が『石橋』を見たいという所望で復興したらしい。途中伝書も途絶えて、だからアイ狂言などは囃子方と調整が出来ていなくて具合が悪いところもあるし。
明生 アイの登場の仕方と太鼓の手組みが合わないとか。
能夫 だから秘曲と言って大事にし過ぎてお蔵に入れっぱなしではいけないんだよ。
明生 喜多流は一人獅子が位が重く、大事にしていますね。巻き毛になり、あれも憧れますが。
能夫 カーリーヘアね。伝書には「残らず縮む」と書いてある。頭は赤毛の髪を巻いて糸で止めて作るんだよ。あるときはパーマネントをかけにいくんだ。巻いてもすぐにもとに戻ってしまうから。
明生 特殊ですよね。面は大獅子。家元にあるあの面はいいですよね。
能夫 あの巻き毛は、獅子を演じるうえでのリアリズムだと思う。琳派の屏風絵を見ても、獅子は巻き毛で描かれているでしょ。唐獅子もみんなそう。そういうことから来ていると思うね。
明生 だから、あの巻き毛の一人獅子の位が重い喜多流の主張はそれでいいと思います。『石橋』といってもいろいろな段階があり、親子の連獅子のときの子獅子(赤)、巻き毛の一人獅子、そして連獅子の親獅子(白)。今、それらをどういう順序でどう演じていくかという基準を再考しないといけないと思います。友枝師は、本来は一人獅子を勤めた者が親獅子を演じる、それが順当だと仰っています。とても理にかなっていると思いますが、ですが巻き毛の一人獅子が余りに重くなりすぎているために、親獅子をできる人が限られてしまっているという弊害が出ています。それで、縛りを緩くして一人獅子の有無に関係なく白(親)をやることになったのでしょうね。父も能夫さんも巻き毛をする前に白をやっていますよね。
能夫 一度、獅子の披き全般を見直す必要があると思うよ。
明生 『石橋』の子獅子(赤)は二十代に披く、体がきれて勢いがあるときに。
能夫 そうだね。僕らの前の世代は二十代半ばで披いていたし、その前の父・新太郎や菊生叔父、友枝喜久夫先生の世代も二十代の若いころにやっているわけですから。
明生 そういう世代のことをよく知っている能夫さんたちが、私も含めてですが、このことを主張し改善していかなければいけないのかもしれませんね。そうでないと、今の歪んだ状況を、みんながこんなものだと思ってしまう。
能夫 これが正当になってしまうからね。今のように変わったのは何だったのか。一度考えておく必要があるね。
明生 そうですよ。子獅子が早く披ければ、一人獅子、親獅子とつながっていき、前場も勤めることができるわけですから。
能夫 子獅子を二十代で披いておけば、それを何回か勤めて深めていき、四十代ぐらいで一人獅子、親獅子へと進めていける。今のように三十代半ばでやっと子獅子の披きではなかなか次へステップアップしていかないからね。
明生 『望月』も含めて、獅子の曲全体の位の配置を再考しましょう。
能夫 能で獅子がある曲は『石橋』と『望月』の二曲。『望月』は仇討ちという物語性もあり、『石橋』のように獅子舞を見せるだけのものではないから、『石橋』より後になるだろうね。
明生 今披きの曲というとまず『猩々乱』となっていますが、私は順番が違っていると思います。流儀の『猩々乱』は腰を低く入れた姿勢での持続力が非常にハードで難易度が高いです。それが酔う姿でもあるわけで。『石橋』のツレよりも一段上の位にあって然るべきではないでしょうか。
能夫 ある意味、そういうこともいえるね。僕が十代か二十代のころには、『石橋』の子獅子、『道成寺』までやってから独立したいなあと思っていたんだ。それらを披いて一人前という風に、先輩たちを見て考えていたからね。それまではそういう流れだったと思うよ。ところが実際は、独立と同時に『道成寺』だったし、その後数年経って『石橋』でした。それだけ披きが全体的に遅くなっているということだね。この根拠は何だろう。いつ披くかの根拠を考えながら組み立てていくことを、どこかで練り直さなければいけない。そういうことを主張していく年齢になってきたということだね。
明生 自分たちの二十代、三十代、四十代を振り返り、どう改革すべきかを検証し、主張する、これは喜多流全体のためでもあり、具体的に言えば、我々能楽師みんなの子供たちのためでもあると思います。
能夫 そういうことだね。
能楽機関誌「DEN」2002年5月号より記載投稿日:2018-06-07

ザ、チャレンジ「ナンバーワンよりオンリーワン
粟谷明生(あわやあきお)さん 喜多流シテ方
プロフィール
1955年東京生まれ。
シテ方喜多流、人間国宝粟谷菊生の長男。
父及び喜多実、友枝昭世に師事。
3歳『鞍馬天狗』花見にて初舞台。
8歳『猩々』にて初シテ。
27歳『猩々乱』
以後『道成寺』『石橋連獅子』『翁』『望月』等披く
重要無形文化財総合指定保持者
「粟谷能の会ホームページ」の演能レポートを見ると、喜多流能楽師粟谷明生さんが、一つの曲に対していかに取り組んだかが詳細に報告されている。「演能に際し、曲の内容を自分なりに深く読み込まなくてはと思うのです。古い伝書に目を通し研究者、見識者の文献を資料に、師、先輩の教えを受け、また違う分野の方々からもお話を伺う。するとだんだん身体の中に溜まったいろいろな情報が溢れだし、構想がふくらみ徐々に自分のスタイルの能が固まりはじめます。それで6年前より、演能後に記録として感想手記を残す作業を始めました。時々面倒になりますが、自分のためと思って続けています。」三月の粟谷能の会の『殺生石 女体』では創作面(岩崎久人打)「玉藻」をつけ、白頭、緋長袴、狩衣の扮装で「カケリ」を取り入れた。妖狐という存在だけではなく、殺生石に込められた玉藻の前や石の魂を幾重にも重ねて演じられないかという思いがあったからだ、という。
友枝師や能夫が育ててくれた
今、能に没頭し、意欲的に取り組む明生さんだが、仕方なく能をやっていた時期があったという。
子方時代は、仕舞なども含め147番、数多くの舞台に立っている。
「当時喜多流に私と同じ年代の子供がいないこともあり、どんどん役がつくので、否応なしに舞台をこなしていかなければならなかったのです。」
そして中学生の頃、華やかな表舞台から裏方の仕事や囃子のお稽古へとシフトして、少し時間ができると能について考えるようになった。
「この時期はこの道がつまらなくなり、稽古が嫌いになった時期です。原因ねー。変声期の悩み、仲間がいない寂しさ、教え方への疑問などですねー。」
能に面白さを感じられなかった二十代。しかし心の隅には能は嫌いじゃないという思いがあった。そんな明生さんに折にふれて、能の面白さを語り続けたのは六歳年上の従兄弟の粟谷能夫さんであった。
「私を能楽師にとどめた一番の功労者は、従兄弟の能夫です。ふてくされた青年に諦めることなく、能の魅力を語り、説いてくれたお陰です。粟谷能の会で『黒塚』を勤めるとき、観世寿夫さんの『黒塚』は「月もさしいる」で下を見るんだ、型付通り上の月を見るだけでなく、能の演技にはいろいろと幅があるのだと聞かされドキッとした。あれがきっかけですね。」
そして父の菊生さんも心配していたのだろう。
「『道成寺』を披くときに、父がうちの子は君に傾倒しているから、君が『道成寺』を教えてくれと友枝昭世さんに頼んでくれたのです。友枝昭世師はお仕着せではなく、私の美意識を呼び出して、なおかつ最後にはこう思うよと、大きな幅で教えて下さいました。それからはまた能が楽しくなりました。」
課題は訴えかけの強さがある謡、舞
平成3年に、明生さんは能夫さんと「研究公演」を始めた。ずっと継承されてきた能の様式美、それを今、生きている者が自分なりに解釈し、新たなものに創造する努力も必要ではないか。そんな考えからだった。
「能楽師には人それぞれの時期に、挑戦しなければいけない課題曲や大曲があります。これらを自分の意志やそれまでの実績で演じられるように運ぶ努力がなくてはいけないと思ったのです。私がいやなのは上から降りてくる順番を何もせず待っているだけ、人が舞うと直ぐ自分もという考え方に慣れてしまうこと。自分の演能活動のあり方にいつでも納得していたいですね。舞台が能楽師の生き様ですから。」
明生さんがいつも心がけている言葉に出会ったのも、このころだった。
「それはナンバーワンになるのではなく、オンリーワンであること。私自身、私でなければ出来ない、見られないという舞台をより多く勤められるようにと心がけています。そのための一つの作業として演能レポートを書いているのかもしれません。」
自分自身が一生懸命やったものが、流儀とか家に貢献できる。能夫さんとも芸の力が拮抗した中で、お互いに刺激しあい、確固とした味わいが出てこなければ次の粟谷能の会は強くならないと語ってくれた。
そして、能は謡と舞、七割が謡で残りが舞だと明生さんは言う。
「訴えかけの強さ、それを今の課題にしています。謡では、役が秘めている内的な意識や思い、それを自分の内に籠めて謡えるかということ。舞に関しては、流儀や各家に伝わる型付をなぞるだけではない、役者自身に存在感があり、その演者の身体から強い訴えかけが醸し出されるものでありたい。
そのような演じ手になりたいのです。」
今年の課題は、秋の粟谷能の会での『野宮』だという。
「『野宮』は本三番目物。劇的な内容で名文が盛り込まれています。今まで本三番目物は『半蔀』『東北』を演じただけ。本来は『井筒』を先に勤めた方がいいのでしょうが、難しいものを早く手がけておきたいという、私のわがままで・・・。今年の目標舞台です。」
これから稽古に入るが、原典となる源氏物語「賢木の巻」をもう一度読まなくてはならいだろう、そこの言葉が能の世界でどのように展開されているかなど、研究することはたくさんある。
「能は今の我々の生活文化につながるようなことがテーマでもあるわけで、演じ手はそれを解るように謡い、舞わなければ」という明生さんの「オンリーワン」の舞台を観たい。
秋田・唐松能楽殿の定期能にて投稿日:2018-06-07
秋田・唐松能楽殿の定期能にて
粟谷 能夫
秋田県大仙市協和町に唐松神社が鎮座し、その神域に唐松能楽殿があり定期能を催しています。
神社発行の唐松山縁起大略によれば、太古鳥海山に降臨し、この地に居を構えた饒速日命が天祖三神を祀り、十種の神宝を安置し、天の宮と称したのが、創祀としています。その後、饒速日命は幾内に降臨しその後裔が、物部氏であり、崇仏戦争に敗れた物部守屋の一子那加世が東奥の地に分け入り、数代の後、唐松にお祀りされたそうです。また神社には秋田物部文書が伝わっています。
このように長い歴史を持ち、今でいうパワースポットの地に、平成2年「ふるさと創成」事業の一環として、唐松能楽殿が出来上がりました。京都西本願寺にある「北舞台」を手本にしたそうです。
定期能は夏に催していますので、少し暑い時もありますが、時折スーっと風が通ったり、木々の緑が目に入ったりと屋外の能の良さを体感しています。
もともと能は屋外で演じられたものでありますが、演者にとっては、開かれた空間であるだけに、演技及び演出や発声などいろいろと課題が見えてくるのも事実です。
一方、観客の方は少し暑いですが、自然が感じられる開放的な空間の中で能を楽しんでいるようです。
私がいつも感心してしまうのは、地元の中学3年生が数十人熱心に静かに観能していることです。若者たちに日本の古典文化に触れさせてあげたいとの主催者の配慮であり、素晴らしいことだと思います。
平成22年夏の定期能は御承知の通り大変異常な暑さでした。私などは装束を付けただけで玉のような汗が噴き出し、精神力を維持するのも容易ではない状態で、舞台へ出てからも、目に汗が入ったりなど大変な演能でした。中学生の一人が熱中症で倒れたほどで観客の皆様も扇子やパンフレットで涼をとっておられました。
一人の中学生が「暑い中、演者は汗を流しながら一生懸命演じているのに、観る側がパタパタと涼をとっていては申し訳ない」と呟やいているのを聞き、自己中心的でなく他人のことをおもんばかる秋田の教育は素晴らしい、全国テストで一番になる学力だけでなく、心の教育の大事さを痛感しました。この事は今年一番の感動であり、異常な暑さの置きみやげのような気がします。
そして定期能を長いこと続けてこられた大人たちの心が通じたのだと思いました。
『翁』付『養老』を勤めて ー前シテの面「小牛尉」へのこだわりー投稿日:2011-04-16

『翁』付『養老』を勤めて
ー前シテの面「小牛尉」へのこだわりー
粟谷 明生

平成23年(4月16日)厳島神社桃花祭・神能で『翁』を勤めました。
神能は正式な『翁』からはじまる5番立番組で、『翁』のシテは脇能も勤めます。
脇能は『高砂』『弓八幡』『養老』の三曲を毎年順番に奉納する決まりになっています。

(写真2)
前年(平成22年)の脇能は『弓八幡』でしたので、今年は『養老』でした。
私の『翁』付『養老』は平成11年以来、実に12年ぶり。12年前の事を思い出しながらも、また東北の被災された方々へ神のお恵みがありますようにと、「天下泰平、国土安穏」と気持ちを込めてご祈祷の謡を謡い、勤めました。

(写真3)
喜多流の脇能の神舞物は五曲あり『高砂』『弓八幡』は本格、『養老』『志賀』は少し格下、『絵馬』は別格と区別するように謡本に書かれています。参考曲に『御裳濯』がありますが、現在絶えています。

(写真4)
笛方は神舞の位を、真(しん)と草(そう)に分け、本格は真の舞、格下は草の舞と扱っていますが、シテ方の動き(型)は変わりません。違いは、初段オロシの譜が男舞の譜に変わるだけです。もっとも最近では、シテ方の注文がなければ、草の場合でも真の扱いで吹いていると、森田流の杉市和氏は仰しゃいます。
『養老』は世阿弥作の脇能ですが、前場にクセがない簡略形式となっていることや、大口袴をはかずに着流し、面は三光尉というような装束附けや面の選択の影響でしょうか、『高砂』や『弓八幡』の本格2曲より格下扱いされています。
しかし私見ですが、『養老』の後シテは壮大な荒々しい山神の役ですので、本格と差別せずに、同等に扱って然るべきだと思います。
(写真5)
前シテは、身分の卑しい田夫野人であるため、老翁は位低い着流し姿となることに異論はありませんが、問題は、面がやや野卑な人相の「三光尉」と定められている伝承です。
神の化現でないため「小牛尉」を使用しない、と喜多流謡本に明記されていますが、これはどうでしょうか。私は同意出来ません。今の演出では、老翁は神の化現であると考えた方が自然だからです。前シテとシテツレ親子は来序で中入しますが、これは老翁たちが実は山の神であるが如くに観客に想像させますし、演者もそのような気持ちで演じています。

(写真6)
古くは、前シテとシテツレの親子はそのまま舞台に居残り、別の能役者が後シテの山の神だけを演じていたのではないか、という説もあります。例えば、現在喜多流の『昭君』ですが、古式では前シテと後シテを分ける演出があり、最近観世流の中にはその古い形式を再興しているところもあります。
それはともかく、現行の演出では、シテとシテツレが来序で中入りするので、老翁を神の化現として演じたくなるのは普通で、それならば面は「小牛尉」の方が適当となります。装束も従来の無地熨斗目よりは、格上げした小格子模様の熨斗目の方が似合います。
そこで今回は、『養老』も『高砂』や『弓八幡』と同じように品のある前シテにしたく、前回同様「小牛尉」を使用し、着附は小格子模様の熨斗目を着流しで勤めました。

(写真7)
伝書には、過去の経緯や心得が書かれていて貴重です。しかしそれを鵜呑みにするのはどうでしょうか、いささか危険であるようにも思えます。
今に生きる能、というものを常に意識して演じる能役者を目指したいと思います。
権威主義的、保守的な考えの方には、目障りだと思われるかもしれませんが、今に似合う、自分に似合う能を、それを受け入れてもらえるような環境作りをして創り上げていきたい。現在に似合う、今を生きる能役者でありたい。また後進たちにも、そうなってほしいと願いも込めて舞った、今年の『翁』付『養老』でした。
写真提供 粟谷明生 撮影 石田 裕
写真巻頭 『養老』前シテ 小牛尉をつけて
写真2 『翁』 翁の舞 地の拍子
写真3 『養老』後シテ 神舞の上羽の型
写真4 『養老』後シテ 神舞二段オロシの型
写真5 『養老』前場 左から ツレ佐藤 陽 太鼓 梶谷英樹 シテ 粟谷明生
小鼓 横山幸彦 笛 中村俊士 脇 高安勝久
写真6 『養老』前シテ 「影さえ見ゆる山の井の」の型
写真7 『養老』後シテ 仕舞所の型
(平成23年4月16日 厳島神社・御神能にて。 同年4月 記)
無断転写禁止