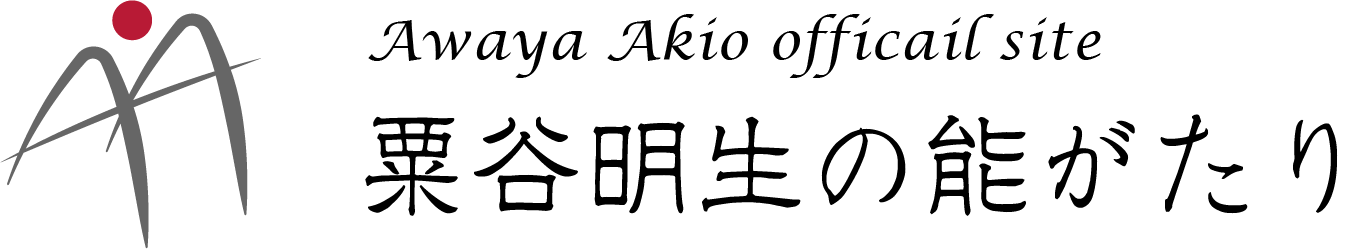『鉄輪』を勤めて 丑の刻詣にかける女の復讐心投稿日:2025-05-13

『鉄輪』を勤めて
丑の刻詣にかける女の復讐心
鉄輪(五徳)を頭に載せ、しかもその上に蝋燭まで立て、怖い形相の面をかけて現れる後シテ、この異様な姿は鮮烈で、『鉄輪』をご覧になった方はいつまでも心に残るのではないでしょうか。その『鉄輪』を広島蝋燭薪能(令和7年4月28日 於:広島護国神社特設能舞台)で勤めました。
この日は生憎午前中が雨で、夕方からの演能が危ぶまれましたが、午後から晴れてきて、何とか「蝋燭薪能」を催すことができました。たくさんの蝋燭が灯されたなか、幻想的な能をお楽しみいただけたのではないでしょうか。しかし、舞台はそれまでの雨によって良いコンデションとはいえず、演者側には難儀な面がありました。屋外の演能ではいつも天候が気にかかります。
まずは『鉄輪』の物語を簡単にご紹介します。
貴船神社の神職(または社人)(アイ)が丑の刻詣をする都の女に神託を告げようと触れる、狂言口開けで始まります。
女(シテ)が遠路はるばる丑の刻詣に貴船神社にやってくると、アイが「火を灯した鉄輪を載せ、顔に丹(赤)を塗り、赤い衣を着て、怒る心を持てば願いが叶う」と神託を告げます。女は最初は人違いだと言いますが、みるみるうちに気色が変わり、姿を消します。(中入)
男(夫・ワキツレ)が登場し毎夜、悪夢を見ると言って安倍晴明(ワキ)に占ってもらうと、女の恨みで今夜にも命を落とすと言われます。男はすぐに晴明に祈祷を頼むと晴明は後妻と男の人形を棚に飾り祈祷を始めます。そこへアイが言った通りの形相で鬼になった女が現れ、捨てられた女の哀しみ、恨みを訴えます。そして後妻の形代の髪をからめ打ち据えます。さらに男の形代に迫ると、三十番神が鬼女を攻め、ついに鬼女は衰え、「時節を待つべし」と言って消え去ります。
丑の刻詣は丑の刻、すなわち午前2時という深夜に、人目を忍んで参拝し、恨む相手を呪い殺す祈願をすることです。詞章には「通い馴れたる道の末・・・」から道行の謡が始まり、糺の森や市原野辺を通り「程も無く、貴船の宮に着きにけり」と、いとも簡単に着いたように書かれていますが、都の女が貴船神社までの道のりを、いくら通い馴れた道と言っても、深夜、暗闇の中、一人で行くのはとうてい無理です。それをするというのは相当の思い込みがあるのだろうか、恐ろしいと、前回の演能レポートに書きました。
都から車で4、50分ほどの距離を、女は何時間かけて都へ行ったのでしょうか。3時間から4時間かけて? それも7日間も? と考えると、女の復讐心の恐ろしさに身が引き締まる思いがしたものです。
今回、4月18日に厳島神社の神能を終えてから、京都に入り、貴船神社所縁の地を巡ってきました。京都市内から鴨川沿いに糺の森を抜けて、深泥池(詞章では御菩薩池・みぞろいけ)を横に見ながら、深草少将に掛けて草深い市原野辺、小野小町終焉の地・小野寺に行き、鞍馬川にかかる橋を渡って貴船神社へと、ほぼ詞章の通りに巡ってみました。
今回、舞台で道行を謡う時も、実際にたどった道の景色が体の中に浮かんできました。
それで分かったことがありますので、ここに補足しておきます。
実は前回の演能レポートまでは、都の女は毎夜、市内から貴船まで歩いて通っていた、と思っていましたが、これはやはりどう考えても現実的ではありません。
貴船神社には本宮、結社(中宮)、奥宮と三社あります。多分、『鉄輪』の女は本宮下にベースキャンプを構えて、そこから深夜2時頃に奥宮まで、何日か通い、丑の刻詣をしたと考えるのが良いかと思います。高い山を登る登山家がベースキャンプを張るように、です。
本宮は華やかなところで、赤い鳥居がたくさん並び、参拝する人で賑わっていますが、奥宮まで行く人は多くはないようです。私も以前に訪れたときは本宮どまりでしたが、今回は奥宮まで行き謡曲史跡保存会の駒札を写真におさめました。やはり演能後より前にゆかりの地に行く良さを感じています。
それにしても、女をそこまで追い込む強い復讐心の要因は何なのでしょうか。
浮気した夫への恨み、夫を奪った女への恨み、夫に戻ってきてほしいと思う気持ちもあったが、あんな女に騙された夫はやはり許せないと思うのでしょうか。「或る時は恋しく」「または怨めしく」と揺れ動く女心をシテと地謡で謡います。
女は鬼女となって、捨てられた女の恨みを晴らすべく、「いでいで命を取らん」と新妻の形代に襲い掛かり、散々に打ち殺してしまいます。夫の方には清明の祈祷が強く効いてなかなか近づけません。もしかすると女の心の中に「夫は悪くない、悪いのは新妻」と夫を庇う気持ちが少しはあったのかもしれません。このような女の揺れ動く心、裏切った夫を恨む以上にもう一人の女を強く憎んでしまうというのは面白いところです。現代の夫婦関係、男女関係にも通じるように思われます。
さて、この女の気持ちを表現する面について、伝書には、前シテが泥眼、後シテが生成(なまなり)と書かれています。
前シテの泥眼は『葵上』の六条御息所(シテ)にも使われ、目の淵に金が入っている面で、普通の女とはどこか違う、強い気持ちが表情に出ています。『鉄輪』の女は登場するときは笠をかぶっているので分かりにくいですが、神託を聞いて、自分であると、慎み深い女から気色変じ、「怨みの鬼となって人に思ひ知らせん」と笠を捨てる瞬間に泥眼の面が良く効いて見え、顔色の変わったのが分かります。後の鬼女を予感させるのに、ふさわしい面です。
後シテは、今は「生成」と「橋姫」のどちらかを選択しています。今回は二つの「橋姫」を用意しましたが、諸事情を考え、粟谷家蔵の面を使用しました。
「橋姫」は面の上半分が白色、下半分が赤みを帯び、鼻筋などに赤が塗られ、どっしり存在感もあって、怒り爆発の怖いお顔です。「生成」も全体に赤みがありますが、少し笑っているようで、頭に小さな角が2本生えていて、とても不気味です。
父・菊生が、女房の怒りも「橋姫」のうちは怖いが、なだめればどうにか許してくれるだろう、しかし「生成」になったらもうオシマイだ、手遅れになるから気を付けなければ、と話していたことを思い出します。とにかく、怒りの表情に笑みが見えたら怖い、もうアウトらしいです。恐ろしい心に残る忘れられない言葉です。
それでか、父の『鉄輪』では「生成」は一度ほど、ほとんど「橋姫」にしていたようです。私も一度「生成」を使ってみようかなと思わないでもありませんが、やはり使いこなせないだろうと、遠慮してしまいます。
「生成」に「り」をつけて「生成り」と書くと「きなり」と読み、脱色や染色をしていない糸や布のことを言うようですが、これは「なまなり」と読ませる面の「生成」とは別物です。面のほうは未完成で、まだ十分に成りきっていない様を表します。すなわち角が生えた本当の鬼「般若」になる以前のお顔ということです。『道成寺』や『葵上』で使われる、立派な角が生えた「般若」と比べると、「生成」の角は小さいですが、何か煮え切らない、それでいて不気味な表情がとても怖ろしいです。
『鉄輪』という能は、面や出で立ちも特異で、作り物もあって、分かりやすい設定です。
ご覧になって、女性なら胸のすく思いがするでしょうが、演じている私は、この女は自分の恨みばかり述べて、男を悪者にしているが、本当のところはどうなのだろうと、男の言い分が全く書かれていないので、気になります。
なぜ女は夫に捨てられたのか。
口うるさかったから? 金遣いが荒かった? 暮らしぶりがだらしなかった? 老いた見苦しい体型に嫌気がさした? もしかして、子が産めないことで離縁ということもあったかもしれません。今はそのような理由は許されないでしょうが、昔はそれで里に帰されるなどということがよくあったようです。
こんなふうに考えるのは男の側の発想と分かっていますが、捨てられた女を演じる男の役者として、女と男の矛盾する心を感じながら演じるのが、また面白いのです。
鬼女となった女は、祈祷によって退散しますが、「今回はあきらめるが、また来るから!」と言い残して消えていきます。執念深く、怖ろしさを残したままの終曲です。
この能の題材となった平家物語「剣の巻」では、その後、女は男を殺し、しかも男の家族、新妻の家族も殺してしまう凄惨な結末です。『雨月物語』の「吉備津の窯」も同じようなお話ですが、最後、男は殺されています。伝説や小説は徹底的に悲劇を描くことが多いですが、能はそこまでの結末は描きません。また来るかもしれないと余韻を残し、あとはご覧になる方の想像に委ねます。
私も、女が男を殺してその後どうなるのだろう、恨みを晴らすことができて魂は鎮まるのだろうか、元のやさしい女性に戻れるのだろうか。いやいや、残酷な殺人者になってはお終いだろう、などと想像はしますが、能がそこまで描かないところを好ましく思います。
貴船神社の鉄輪伝説の最後に「丑ノ刻詣りは祭神が国土豊潤のため丑年丑月丑刻に降臨されたと伝える古事によるもので、人々のあらゆる心願成就に霊験あらたかなことを示すもので、単にのろいにのみとどめるべきものではない」と書いてありました。貴船神社も丑の刻詣は悪い印象ばかりではない、のろいだけでは物事は解決しないと言いたいのでしょうか。
若い時には考えもしなかったいろいろなことを思う『鉄輪』になりました。
しかし、ご覧になる方は深く考えず、男女の仲のお話、こんなお話もあるのね、女性への対応はよくよく考えなさいよ、という昔の人の忠告なのかな、などと所詮、「これは他人様のお話」とクールに受け止めて楽しんでいただくのが一番、かと思います。
私の『鉄輪』の初演は昭和63年(33歳)妙花の会、再演は平成15年(48歳)粟谷能の会で、今回が3回目です。再演の時の演能レポートで詳しく書いていますので、ご興味のある方はサイトの「演能レポート」でご覧ください。 (2025年5月 記)
写真提供 広島護国神社 シテ粟谷明生
アイ 野村裕基 小鼓 横山幸彦 大鼓 亀井広忠 太鼓 吉谷 潔
能面「橋姫」 粟谷家蔵 撮影 粟谷明生
能面「生成」 撮影 粟谷明生