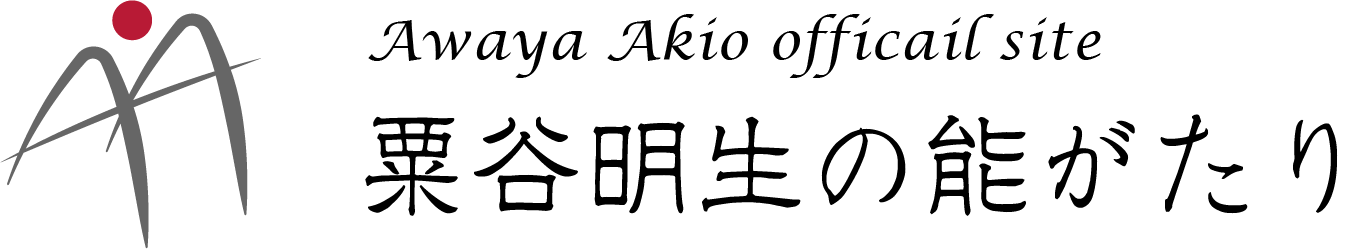『卒都婆小町』について投稿日:2018-06-07
『卒都婆小町』について
粟谷能夫
粟谷明生
平成14年12月は能の稀曲『卒都婆小町』シテ・友枝昭世の公演が二度催され、地頭・粟谷菊生で私たちは地謡を勤めました。そこで、橋の会勉強会で教わったことや携わって得たことなど経験談を添えて少しまとめておきたいと思い、能夫と対談しました。ここにその内容を記載いたします。
番組資料は下記の通りです。
【橋の会】
12月6日(金) 宝生能楽堂
シテ友枝昭世、地頭・粟谷菊生、ワキ・宝生閑、ワキツレ・宝生欣哉
笛・一噌仙幸、小鼓・鵜沢速雄、大鼓・亀井忠雄
地謡・香川靖嗣、粟谷能夫、塩津哲生、粟谷明生、大村定、長島茂、金子敬一郎
後見・粟谷辰三、友枝雄人
【朱夏の会】
12月21日(土) 大濠公園能楽堂
シテ・友枝昭世、地頭・粟谷菊生、ワキ・宝生閑、ワキツレ・宝生欣哉
笛・一噌仙幸、小鼓・横山貴俊、大鼓・白坂信行
地謡・香川靖嗣、粟谷能夫、狩野秀鵬、粟谷明生、笠井陸、中村邦生、狩野了一
後見・粟谷幸雄、塩津哲生
明生 一ケ月に『卒都婆小町』二回、それもシテが同一人物というのは稀なことで、喜多流の歴史では多分ないと思いますが、シテの取り組む気持ちの持続は大変だと思いますね。私たち地謡としては謡を忘れてしまう前に、またあるほうが気は楽でいいですね。また一度目での反省点などを改善できるということでは、有意義だったと思います。
能夫 友枝さんご自身がおっしゃっていましたよ。昔だったら怒られるって(笑い)。
明生 東京のお弟子で『卒都婆小町』を観た感想を聞いていてどうも話がずれるので、おかしいなと良く聞いてみたら、はるばる朱夏の会に行ったというから、えっー、福岡まで行ったのかと驚きましたよ。橋の会の方は切符がすぐ売り切れて、観たくても観られなかったらしい。
能夫 橋の会の切符は早くから売り切れていたからね。
明生 そう、だから二回あってよかったですよ。
能夫 地謡に関しては、僕は二回目の方が良かったと思っているよ。適度な慣れみたいなのがあって、余裕を持って謡えたような気がする。橋の会の方は、すごく緊張していたな、菊生叔父もそうだったと思うよ。二回参加してみて、こうしようと思ったことがすべてできたとは言えないけれど、楽しかったという感じがあるね。
明生 二回目は謡い馴れたということと、お相手のお囃子が幸流(小鼓)横山貴俊氏と高安流(大鼓)白坂信行氏で、何となく安心しましたね。
能夫 それはあるね。でも喜多流は本来、幸流、葛野流の組み合わせが具合がよいことが謡っていて再発見できたね。例えば「浄衣の袴かい取って」と喜多流は拍子に合わずで謡い、イロエとなるでしょう。葛野流はここで打掛けを打ち、幸流はムスブ手を打つ。今は拍子にとらわれないでくずして謡っているけれども、もしかすると昔はある程度拍子に合うようにも謡われていたかもしれないね。一噌仙幸さんがイロエの吹き出しが普通じゃないと言われたことも関連してくるかもしれないし、囃子方の手組みから考えると単純な拍子に合わずではないような気がする。
明生 なるほど、そうですね。あそこ今まで何となくしっくりこなかったんだけれど、それを聞くと解りますね。そのうち能夫さんがやるときは、やはり幸流と葛野流との組み合わせがいいですね。
能夫 それがいいかもしれないね。あそこはすごく気になっていたんだよ。うちの流儀は拍子に合わずで、合わないのを前提にして謡い、お囃子はアシラウ感じがしたな。
それから、昔は、シテの道行後、桂川に着いた後に、さらに言葉があって、阿倍野の松原に着いたと謡っているんだ。今はそこが抜けているんだよ。
明生 下掛宝生流のワキも安倍野についたと謡いますね。だから遭遇するわけですよね。
能夫 ほかに、玉津島明神に幣帛を捧げると明神の使いの烏があらわれるという一段があったと申楽談義に書かれているね。
明生 観世流ではやっているのですか。
能夫 やっていない。そこを復活させても面白いね。それにしても、今回の『卒都婆小町』で、友枝さんはやっぱり素晴らしい役者だなと思ったよ。
明生 どういうところが?
能夫 あの狂いの物乞いから霊が憑く場面ね。あんなにできる人はいないなと確かに感じたよ。そりゃ、自分のやり様とはまた別の世界ということはあるだろうけれど。
明生 小町の身体に取り憑いたって思いましたね。
能夫 本当に、戯曲というか台本を読み込んでやっていられるなとすごく共感を持てたね。あの卒都婆問答でも確固としたものがあるし。友枝さんが、精一杯顎あげて面遣いをしている姿、つまり能を超越したような方法論もあったけれど、それがうまく表現されて、いいなと思った。そういうものだろうと思わされた。あの卒都婆問答ね、途中から宗教が変わってくるんだよ。ワキは高野山の僧だから、前半は真言密教だけれど、「菩提もと植ゑ樹にあらず、明鏡また臺になし。げに本来一物なき時は仏も衆生も隔てなし」は禅宗の言葉だからね。
明生 「げに本来一物なき時は仏も衆生も隔てなし」は、梅若六郎さんの舞台を拝見したときに、地謡が6人だったからか、かなり強くエネルギッシュに謡われていると思いましたが、あれはやはり、そこで世界が少し変わるからなんですね。
能夫 あそこはやはり強くなければいけないようだね。何かに書いてあったのを読んだ記憶がある。『朝長』でも、「悲しきかなや・・・」から宗教観がガラッと違うって、よく銕之亟さんがおっしゃっていたけれど、まさにそういうことで、世界観みたいなものがガラッと変るから謡い方も当然違ってくるということはあるわけだよ。
明生 そうか、面白いね。ところでシテの歩み、運びに気になることがあるんですよ。最初に出てくるときは杖をつき、姥の老いの足運びですが、物着で立烏帽子をかぶり長絹を着たあとや「花を仏に手向けつつ悟りの道に入ろうよ」という一番最後のところも一貫した老足の歩みであった方がいいのか、それとも時間の流れの中で何か違った工夫がされるのがいいのか。その辺が観ていてわからなかった、工夫があった方がいいのか、また何も変わらずがいいのか・・・。
能夫 それはわからないな。実際僕はやっていないしね。十四世六平太先生は、片方は幽玄の足で、片方は切る足、つまり詰める足で老女は出ると書いているけれどね。両方、抜き足でなくて、まあ、いけない言葉ですが、びっこを引くようなイメージかな。
明生 『卒都婆小町』のときですか。
能夫 老女物はおしなべて。ずーっと出たらもう一方の足をひょこっと浮かすというね。それが正しい伝承なのか、六平太先生の巧みの工夫なのかはわからないけれどね。
明生 『卒都婆小町』のような現在物ならいいかもしれませんが、『伯母捨』『檜垣』のように舞うことになると問題がありますね。舞を舞わないときは何とかなるだろうけれど。
能夫 普通の幽玄の足とか、摺り足で舞いたいよね。だけど流儀のプレッシャーというか、なかなか動けなくなるらしいよ、友枝さんも言われていたからね。
明生 だいぶ抵抗なさっているようでしたが。
能夫 わかるよ、それは。
明生 『定家』の場合は老いの足ではないですよね。執心を引きずるような足の動きだと思うけれど。痩女をかけるから運びも変わってくるという喜多流の考えに首を縦にはふれませんが、執心を引きずる感触で老女物も手がけられないでしょうか。
能夫 それはそれなりの表現方法としてもいいのではないかな・・・。
明生 それには、面や装束、お囃子と、いろいろなものを配慮していかないといけないでしょうね。取り合わせが悪ければ意味がなくなるわけで。
能夫 問題点だね。それはそうと、宝生閑さんがどんなに重く扱うのかと思ったら、そうでもなかった。以前とは違う。変わられたね。すごくいいですよ。曲としての位、ワキとしての位はありながら、重そうで重くない、おもくれない、いいよね。
明生 やはりいいですね。福岡の朱夏の会の申合後、信ちゃん(白坂信行)に「申合せではやらなかったけれど、ワキの次第と、シテの習之次第とどう打ちわけるの」と聞いたら、あまり意識していないような答えでした。橋の会の勉強会で、幸正能の伝書に、次第について、「ワキの次第は陰ノ中ノ陽ノかげ、シテの次第を陰のかげトイフ」というようなことが書かれていると聞いて、これは面白いと思って、実際打たれる方の意識、心持ちが知りたくて聞いたのですが・・・。父が横山貴俊さんはワキとシテの次第で音色を変えて打ち分けているところがさすがだと絶賛していましたね。確かに老女物らしいいい音色でしたね。そして宝生閑さん、欣也さんの謡の雰囲気は、『卒都婆小町』の世界を作って下さいますね。
能夫 そうだね。
明生 橋の会でならば、観世流にある「一度之次第=いちどのしだい」(シテが初めに登場して床几に座り、後からワキが登場して名乗り、卒都婆に腰掛けている小町をみつける)を経験したいと思いましたけれど。なるほどワキの次第とシテの習之次第の違いが体験でき、また大小鼓の役者の個性をそれぞれ観ることができて貴重な経験になりました。
能夫 「一度之次第」も合理的でいい演出だけれど、流儀には本来ないからね。今回の経験でよかったんじゃないかな。
明生 喜多流で習之次第があるのは、『道成寺』と『三輪』の小書「神遊」、老女物では『檜垣』と『卒都婆小町』の四曲ですね。シテの出で揚げ幕を上げ、右に請け一足出ると記されている型付の真意は、『道成寺』では、鐘に対する蛇体の執心、追いかける心など強い気持ちの表れであり、『三輪』も同様、蛇と神という二面性を持ちながら、玄賓僧都のもとへ向かう気持ちの強さの表れだと思うのです。で、『檜垣』と『卒都婆』などはどうなのかなと思って観ていたら、橋の会のときは見えなかったけれど、朱夏の会のときは、友枝さん、確かに一足出られていた。やはり出なければならない状況、老女の肉体的運動能力として前につっかかる感じがあるのですね。これは老いの運び、老足(ろうそく)に共通しますが、一足出るというのは前に向かう気持ちの強さがあるときの当然の成り行きであり、体の運動であると思うのです。それが確かに型付にも記されていると感じました。常のように「右二請ケ右足引キ揃エル」では一端心が冷静になり平常心となって、舞台遠く正面先にある影向の松、そこに降りられる神に敬意を表すということに落ち着いてしまうのだと思いました。
能夫 大事なことだよね。『道成寺』でも「出ろ」という教えがあるんだから。引くのではなくて出るという感じだよ。そこの辺をしっかり伝承してほしいね。型付を見て動いているだけじゃ役者としては情けないからね。でも本当は型付を読み込めばいろいろいいことが書いてあるんだから、そこを読まなくてはいけないんだよ。人の書いた型付を写して安易に演じているからそういう大事なところを、落としてくるんだね。友枝さんが『卒都婆小町』を二回やってくれたけれど、やっぱり、それを観て何かを得ようとする人がいたときには、二回やってよかったと思いますよ。
明生 友枝さんは初演があって、今回の二回と合計三回ですよね。流儀に三回の記録ってあるかな。私たちも初演、今回と謡い、観てきているわけですが、初演と今回の二回目、三回目とでは違いがありますね。初演ではすごい重厚感、老女物らしくという感じがしましたが、今回は『卒都婆小町』という戯曲を演じているとひしひしと感じました。
能夫 友枝さん自身が同じ思いを持ったかどうかはわからないけれど、二回目、三回目があって成長したという感じがしますよ。何度もやるというとマイナス的な考え方をする人もいるけれど、でも良かったんじゃないですか、後進にとっては。
明生 観たい人にとっては、より多く観ることができて良かったですよ。これ六ケ月も一年も経ったらまた感覚も違ってくるだろうし、演じ方も考え方も変わってきますね。
能夫 だから短期間に二回は面白かった。うちの弟子、橋の会を観て「いい『卒都婆小町』でしたね」と言っていたからね。やっぱり橋の会では忠雄さんだね、決してだてに年を取っていないね。白坂君も37歳で『卒都婆小町』を披き、それも自分の会を立ち上げてきての成果だから褒めてあげるけれど、やはり61歳の『卒都婆小町』とは違うね。比較してはかわいそうだけれどね。
明生 掛け声の質と高さとか。大鼓の音の響き音色とか。透明感と独特の個性がうまく融合され発揮されていましたね。
能夫 とにかく何回もやってという反発はあるかもしれないけれど、適材適所、いい役者が思いを込めてやってくれれば、それを観た人間が次を考えればいいわけですよ。そういう意味ではすごく良かったんじゃないかと思うよ。それで自分が演じるときの、何かよすがにすればいいわけでしょう。
明生 今回の二回、友枝さんとしてはどっちが良かったのだろう。私はどっちというのは判断つかないですが、地謡としては、横山さんを得て、強さ、広さみたいなものが出たような気がしましたけれど。
能夫 『卒都婆小町』は雲の上の手の届かない曲と思っていたけれど、今回の二回の舞台ですごく身近になってきた。それって大事だよね。だから諸先輩がやってくれないと。
明生 神棚に上げておいてはダメということですよね。白坂君が、一番最初に『卒都婆小町』を観たのはうちの父の『卒都婆小町』なんですって。それであの「関守はありとも止まるまじや出で立たん」、あそこがいいなと思って、自分がやるときはコレだと思ったと話してくれましたよ。
能夫 そういうことなんだよな。先輩がよい舞台を観せてくれるということは。
明生 あそこ、「関守はありとも止まるまじや出で立たん」はいいところですよね。私は大好きです。特に喜多流は、物着したあともう一度シテが常座にさしかかるところで「関守はありとも止まるまじや出で立たん」と張って謡いかけるでしょ。血の気が引くというか、感極まるすばらしい場面ですよ。父は「益二郎の関守」っていわれるぐらい益二郎の関守は評判で、張って謡うんだよ、それを僕が次に伝えたい、が口癖ですね。
能夫 あそこがいいんだよ。観世流の『卒都婆小町』を観たけれど、物着のあと、「関守はありとも」はなしで、いきなり「浄衣の袴かい取って・・・」とシテが謡うから拍子抜けしちゃう、面白くないよ。あそこは、たとえ関守がいて行く手を妨げようとも、思いのままに行くぞという意識を強く出しているわけですよ。
明生 あそこに蓄えたエネルギーの爆発がないと喜多流の『卒都婆小町』にはならないですよね。あそこがつまずいたらおしまいです。謡い方に気を使わないといけない。怒鳴ってうるさくてはいけないし、調子があって、テンションが上がっていなければいけないし。
能夫 最初の「月こそ友よ通い路の関守はありとも・・・」とは違うよね。物着後の返しの謡は「せーきもりは、あーりともーお」と張って謡う、当然音は高くつってくるんだけれど、そこを謡いきる。ああいうところの謡が大事なんだよ。流儀の人たちでも息を引いて謡うことが出来る人がすくないような気がするね。僕は銕仙会にふれたりして、謡という意識を学んだけれど、喜多流にしっかりした謡い方のマニュアルが無く、また指導もしないのが原因だろうね。
明生 最近、そういうことがわかってきました。『望月』をやるとき、能夫さんにもう少し引いて謡えよと言われて・・・。
能夫 ガーッと出す息だけではない表現があるわけですよ。
明生 物着後の「関守・・・」のところは、まさにそうしないと、引いて謡わないと成立しませんね。出す息だけだと声として次第に消えてしまう。それが引いて謡うと声が音として広がりをもって残る、何かそのあたりの意識をもっていないと。
能夫 そう。その意識がないとね。
明生 出したいものを80%ぐらいに引いて、それでいて100%をこえる効果を出す、そういう声の広がりみたいなものですね・・・。
能夫 本当はそういうことを理解していないと能にはならないんだよ。右向いて、左向いて前に出てシカケ、ヒラキというだけのマニュアルじゃ。もっと切瑳琢磨しないとね。
明生 『卒都婆小町』も神棚に上げておく曲目じゃないということがわかった。今回はいい機会でしたね。
能夫 やっぱりやらなくちゃダメだよ。能楽師として生を受けたからには。
明生 近づくように努力しますよ。可能性があるように思えてきたんですよ。父の勤めた『伯母捨』は可能性ないけれど、『卒都婆小町』は可能性が見えてきた。嬉しいな。
能夫 その意味では『卒都婆小町』というのは、老女物という妙な重々しいムードにもっていかないで、みんなが手がけるというものにしなければいけないと思うね。一つの戯曲でしょ。鋳型に入れ過ぎてる感じがする。
明生 『卒都婆小町』というのは、幽玄物ではなく、現在物だから、それなりの演者の工夫が必要とされる感じがしますし、第一、作風が面白いですよね。卒都婆問答といわれる宗教問答なども面白い。
能夫 面白い、すごく面白い。
明生 橋の会の時、皆1時間30分ぐらいで終わるんじゃないのと言っていましたが、宝生能楽堂ということもあってか実際は1時間55分かかりましたね。でも単に老女物という、終始しっとり静かに時間が流れていく2時間近くではなく、ごつごつしたものを私は感じました。そういうものが『卒都婆小町』ではないかと。
能夫 それはもう生きとし生けるものの携わる人間の躍動感みたいなもので・・・。
明生 『伯母捨』のように、もう時間を超越して、ある種の時間が過ぎていってしまうものもあるかと思うと、『卒都婆小町』のように芝居的要素を感じるものもある・・・。
能夫 老女物だからといって、ただ坦々とやればいいというものではないようだね。
明生 老女物、演じる年齢制限、老い、なんか消極的で、シルバーシートに堂々と座れるまではやってはいけないみたいな、いやなイメージが頭にはまだ残ってますが、神棚に上げて腐らせては観阿弥、世阿弥に申し訳ないでしょう。能夫さん早くやって下さいよ。
能夫 ああ楽しいなと思うよ。だから二回目も三回目もやらなければならないと思うね。
明生 腰曲げて、顎出して、よたよた歩いて老女物を勤めたと思うことが間違いだと確信できたからいい勉強になりました。かなりハートのエネルギッシュなところがないと、この小町さんは歯がたたない。強いですから。
能夫 強いね、小町は。強いというか、狂気になるし、乗り移るし、すごい世界ですよ。
明生 卒都婆問答後「むつかしの僧の教化や」のやり方もいろいろあるなって気がします。うちの父のように、ワキの高野山の僧を完全に馬鹿にして、あーあとつぶやくようにくたびれて立ち去るやり方もあるし、友枝さんのようにトンと杖をついて鼻っつら強そうにつんつんとした小町もありと。観る側の想像力も広くなくては。
能夫 ブツブツいろいろ言うけれど、何を言うか! あーうるさいねー! 大した僧でもないのに説教なんかたれて、っていう言い方もあるでしょう。どちらでも選択できる、そこがまたお能の面白いところでもあり役者のやり甲斐だと思うよ。
明生 そう、ちょっと苛立つか、それとも捨てるというか、もう相手にしない、関係ないととぼけてしまうか、いろいろ世界がありますね。
能夫 菊生叔父の演じ方も然り、昭世さんのも然りだよね。
明生 演ずるとき、例えばシテ小町が怒って腹をたてているという動きを、型として見せないで、謡の言葉での訴えだけで成立させるという考え方と、型の中に怒りを、鋭角に出す方法と考えられるのですが、どちらがいいですか。
能夫 それはその人の生き様もあるし、主義主張もあるしね。昔、後藤得三先生は問答でワキとワキツレがそれぞれ何か言うたびに、いちいちワキ、ワキツレと見ていたけれど、あれを観ていて何か小町が翻弄されているように見えたんだ。可笑しいでしょう、小町がやり込めなくてはいけないのに、反対にやり込められているようにみえるもの。相手に向かうときは必ずアシラウという決めごとに忠実な、そういうふうにやる時代があったんだね。でも昭世さんという人はいろいろ考えて、もうワキツレには体を向けないでしょ。そういうことでも、僕は近年、老女物は進化したなと感じているんだ。
明生 うちの父も、ワキにはアシライ、ワキツレには面遣いだけがいいと言ってますね。
能夫 昔は律義というかいちいちワキ、ツレと向いていたんだ。全部そうなんだよ。昭世さんもそういうのを見て、きっと嫌だなと思っていただろうし、僕も若造ながら、嫌だなと思っていたから。だから、今回の昭世さんのを見てそうだそうでしょうと思ったよ。昭世さんのあたりから、喜多流の近代能というか、進化していると感じるんだ。そういうことを僕はいいたい。
明生 進化している・・・。
能夫 以前の老女物は本当、マニュアル通りというか、ちっとも考えていないという感じだったよ。だからここらあたりで、ギアを変えないとね、それをしないといけないんじゃないかな。『卒都婆小町』とか大曲、稀な曲、秘曲をやるということは、それで足跡が残るし、みんなには衝撃波というか印象を与えるし、それは流儀にとって悪いことではないんだよ。自分でもやってみたいと思っている人はよく観るし、何かを感じるだろうしね。やらないとカビがはえてしまうものね。あまり手慣れ過ぎてもいけないけれど、獲得できる範囲で秘曲もやっていかないと、流儀の損失だと、僕は思うね。
明生 今回の『卒都婆小町』、そういう意味でもよいタイミングでしたね。
(平成15年1月 記)
研究公演つれづれ(その八)投稿日:2018-06-07
研究公演つれづれ(その八)
研究公演 第8回(平成9年11月22日)
能夫『景清』と明生『采女佐々浪之伝』について
粟谷能夫
粟谷明生
笠井賢一
『景清』について
 明生 第8回研究公演は能夫さんの『景清』と僕の『采女佐々浪之伝』、そして父が舞囃子『船弁慶』を勤めてくれました。
明生 第8回研究公演は能夫さんの『景清』と僕の『采女佐々浪之伝』、そして父が舞囃子『船弁慶』を勤めてくれました。
能夫 そうだったね。僕の『景清』は明生君の要請があってやったような気がするんだけれどなー。それですごいプレッシャーを感じてやった覚えがある。その前にいろいろ事件があったから・・・。
明生 今、『景清』はうちの父が十八番みたいにして勤めている。それが、もし父が具合が悪くなって代演者を立てなければならなくなったときに、粟谷能夫、明生と言われたらどうなのか。そのときにまだ二人とも披いていないので、できません・・・では情けないではないかということで。そうしたら、ある人が40代の『景清』、50代の『景清』、60代、70代があっていい、何回やってもいいのだ、40代の『景清』があったっていいのだからと・・・、能夫さんは早く披かなくてはね、やらなきゃ駄目ですよと言ってくださったんです。あのとき、能夫さんはあまり乗り気ではなかったですよね。その前に、大阪は阪神大震災の事件があったりして・・・。
能夫 そう、あの『景清』の前はいざ代演となったとき、対応できなかったんだよね。
明生 一度父が病気でシテを譲る形になってしまいましたね。これでは駄目なのだと思いまして。我が家のマイナス は自分たちの責任で補わなければいけないのですが、実際できなかった。このことを一つの材料にして強く感じさせられました。それで自分たちにお灸をすえなくてはと思って、それで能夫さんには絶対に早めに披いてと言ったのです。能夫さんは、もうちょっと後の方が良いとか、研究公演でない方がとか、いろいろと考えもあったと思うけれども、とにかくやろうということになったのです。もう、とやかく言っている状況ではないというのは能夫さんもわかってくれて、「そうだな。まずいな。じゃあ、やろう」ということになったと思います。1回披いておいて代演となるのと、代演が自分にとってお披きになるのとでは全然違いますからね。私は『砧』で代演したのがお披きになるという経験をしたので、そのことは切実に感じます。1度披いているのと、それがお披きというのでは、本人はもちろんのこと仲間の見る目というか意識も違いますから。だから能夫さんに「ここは是非とも『景清』をやっておいてほしい」と言ったのです。
能夫 そうだったよね。そういう仕掛けをしてもらったおかげで、僕もスムーズに『景清』に入って行けたんじゃないかと思う。そういう面では感謝しているよ。僕も『景清』という曲には憧れがあったし、自分がやるときはこんな風にやりたいという思いもあった。『景清』の場合は二度、三度やらないといろいろなことができないかなと思ってもいた。感情が高ぶっている景清もあるし、その感情を抑えて表現する景清もあるだろうし、いろいろな『景清』があるでしょ。過去にもいろいろな『景清』を観せてもらいましたが、みんな違いますよ。友枝喜久夫先生のも違う、菊生叔父のも、新太郎のも違う、昭世さんのも違う、実先生(先代喜多実宗家)のも違う、そういういろいろな『景清』を観てきましたからね。それらの中で一番印章に残っているものの一つは、先代の銕之亟さんが、友枝喜久夫先生の『景清』を観て、「信じられない。あの調子で景清をやるとは。でもすばらしい」と言われたことですよ。
明生 あの調子というのは?
能夫 高いんだよ。つまり謡い方がトランペットなんだ。普通だったらテナーサックスでしょ。でも友枝先生はそういう謡い方をなさった。観世流では絶対考えられないと、でもそれが景清になっている、そのすばらしさを銕之亟さんがおっしゃったわけ。役に対する喜久夫先生の心のストレスが彷彿してくる感じ。あの時の銕之亟さんとの会話をすごくよく覚えているよ。
笠井 銕之亟さんの『景清』は観たことある?
能夫 残念ながらないんですよ。
笠井 それはいいものでしたよ。
明生 観世流は、喜多流みたいにはあまり『景清』をやらないのではないですか。
笠井 そんなことはないよ・・・。
能夫 うちの流儀はすごくやっているものね。
明生 どうしてなのでしょう。
能夫 でもこのごろは少し下火になっているかな。友枝昭世さん、塩津哲生さん、香川靖嗣さんぐらいのところまでで終わっている・・・。
明生 その世代も一応やっているけれど、そう何回もということはないですね。新太郎伯父はたくさんやっているし、うちの父は、もう十八番でずっと続けていますし・・・。
能夫 若いときからずっとやっているね。
明生 長いですよ。
能夫 年をとってから『景清』をやろうという人は多いけれど・・・。で、僕がやるときどうするか。お能というのは いろいろなやりようがあるんだという、銕之亟さんの言葉が重く響いていて、明生君がこの場を設定してくれたことだし、まずは基本的な『景清』をやっておかなければと思ったね。恩愛のドラマというか人情味あるところもやらなければならないし、景清の若きころの源平合戦の武勲を語る仕方話もしっかりとやらなければならないし・・・。うちの流儀はここのところがことにね。
笠井 運動量多いからね。
能夫 菊生叔父やうちの親父から、昔の人にこういうことを教わったとか、いろいろ思い出話を聞く機会があったからね。親父が作った型とか、でもそれはやらなかったけれど。この道の先輩から聞いておく、見ておいてもらうということは必要だと思う。
明生 『景清』というのは「松門の謡」といって、シテが作り物の中で最初に謡う大切な謡がありまして。「松門、ひとり閉ぢて、年月を送り・・・」というね。ここはみんなそれぞれ、各個人個人で全然違いまして。伝承とかいって伝承になっていない(笑い)。

笠井 節づかいが違うということ?
能夫 強吟のところを和吟で謡ったりと、もう・・・。
笠井 えーっ、流儀の中でそんなに違っていいの?
能夫 違う。でもそれでいいんじゃない。
明生 昔、NHKのラジオ放送があるとき、実先生が、習いものの『安宅』や『景清』などは絶対放送してくれるなといっていらしたのですが、うちの父、NHKの柳沢さんに「何か十八番はありませんか」と聞かれて、『景清』って答えたものだから、それが放送されたのです。でもそれを聞いたからといってみんなが真似できるというものではないのですが。
能夫 できないんだな(笑い)。
明生 父は、これで全国の人の謡が菊生の「松門の謡」になったなんて喜んでいましたけれど、そうはいかない・・・。理解できないですよ、ああいう謡い方は。
能夫 「松門の謡」は難しいよ。僕の『景清』では笛は一噌仙幸さんにお願いしたのだけれど、「松門のアシライ」をやってもらったのです。これについてはあった方がいい、なかった方がいいといろいろ意見はあるのだが、僕としてはあの場面で、景清の孤独とかいろいろな感情を表現するときに、何かひと風、吹いておいてもらった方がいいのではないかという思いがあった。そんなものはいらない、直に肉声で入っていくべきだという人もいたけど、僕はああいうものに憧れを持っていたから。仙幸さんの思い、世界みたいなもので、ある程度雰囲気を作ってもらうというか、舞台を築いてもらわないと、とても松門なんて謡えないという、これが僕の立地条件なんだね。道行が終わって、さあ松門というには勇気がなかった。親父なんか、我を出したいというか、自分がすぐ出ていきたい方だったから、そんな世界作ってくれなくとも、オレがやるんだというエネルギーみたいなものがあった。ある種職人というか、そういう良さもわかるのだけれど、僕としては・・・。
笠井 両方あった方がいいね。
能夫 選択肢があった方がいいじゃない。僕の考えでそうしたんだけど、でも昔はこういうことほとんどやらなかったね。
明生 昔はあまりやらなかったですね。
笠井 笛は森田流? それとも一噌流?
能夫 両方あるでしょ。でも本来は森田流かな。一噌流はこちらから言わないと・・・。でもみなさんやっていらっしゃいますよ。
笠井 大五郎さんもやっておられましたよ。力のある人のアシライならいいけれどね。僕は忘れもしない。銕之亟さんが青山の銕仙会でやったときに、アシライがひどかったの。こんな松門のアシライならいらないと思っていたら、銕之亟さんの謡がすばらしくて、それを凌駕するものだった。そのアンバランス、忘れられない舞台だった。松門のアシライをするときは、笛の人間がどれだけその曲の内実を吹いているかということだよね。と同時に音色が悪くても思いを入れて吹いていますでは無効だからね。音色が自由になり、且つ曲が本当に身にしみてくるように吹けなければ・・・。
能夫 ある力強さもないとね。柔らかいムードだけでなくて・・・。
笠井 この三人で話すとき、語りとか謡の重要性がしばしば話題になったと思うけど、『景清』でいえば、孤独感をどう表現できるかということになると思う。つまり、あれだけの武士が敗残の老兵になって、しかも今や乞食となって芸で身を売っているわけですよ。その人間がどういう謡を謡うか、その孤独感をどう表現するかという、それが課題でしょ。
能夫 そう。わかりますよ。
 笠井 僕は『景清』はそれに尽きると思うんだ。人を感動させるとしたらそこだと思う。老年になるとみんな、若いとき、自分の最盛期のときを思い出して・・・、それがその人にとって花なわけですよ。ところが、それが確実に失われている。失われているのに、昔、オレはこうだったよと言って嫌われている老人はいっぱいいるわけじゃない。そこに娘が来て、そんな惨めな姿を見せたくないから追い払うわけだけど・・・。そこはすごくリアリティあるところなんじゃない、根源的な人間の持っているものじゃないかな。それを平家物語の中で最もドラマチックに描いているわけでしょ。しかも芸能者というものの位置、盲目の人たちが意志固くしてやっているという側面もある。『蝉丸』だって、盲目の琵琶法師を蝉丸という高貴な人に託したというところがあるでしょ。世阿弥の時代、芸能は乞食の所業と言われた、芸能者は卑しめられていたわけですよ。今は芸能人は偉くなっているけれど、所詮、芸能者というのは芸を売って人様から銭をもらって口を糊しているわけだから、その無残さね。それは無残さであると同時に豊かさでもあり得る。人間の極限の体験を語り、表現することは、鎮魂の行為であり癒しでもあるわけだから。そういうことを身にしみてやることもできるし、人情劇という側面からやってもいい、『景清』はいろいろな側面からできると思うんだよね。でもまず、過去を思い出すことの無残さみたいなものを永遠の課題として描くということがある。『隅田川』だってそう、母親の子供への永遠の思いの深さを、普遍性をもってあれだけ書かれたら、それを表現するのは、それはもう男子一生の仕事と言っていい。『景清』もまたしかり。『景清』の喪失感の深さ。能が世界に冠たる芸能であるのは、やっぱり喪失感をここまで深く表現しているから。他の演劇では喪失感の表現をここまで深くしないもの。死者のまなざしの深さみたいなものね。死んでもまだ残る妄執の深さ、永遠の地に幽霊となって現れ、その思いを言い続ける、これは単なる怨念というものでなく、そこに普遍的な思いがあるからでしょう。それが他の芸能と違うところだと思う。
笠井 僕は『景清』はそれに尽きると思うんだ。人を感動させるとしたらそこだと思う。老年になるとみんな、若いとき、自分の最盛期のときを思い出して・・・、それがその人にとって花なわけですよ。ところが、それが確実に失われている。失われているのに、昔、オレはこうだったよと言って嫌われている老人はいっぱいいるわけじゃない。そこに娘が来て、そんな惨めな姿を見せたくないから追い払うわけだけど・・・。そこはすごくリアリティあるところなんじゃない、根源的な人間の持っているものじゃないかな。それを平家物語の中で最もドラマチックに描いているわけでしょ。しかも芸能者というものの位置、盲目の人たちが意志固くしてやっているという側面もある。『蝉丸』だって、盲目の琵琶法師を蝉丸という高貴な人に託したというところがあるでしょ。世阿弥の時代、芸能は乞食の所業と言われた、芸能者は卑しめられていたわけですよ。今は芸能人は偉くなっているけれど、所詮、芸能者というのは芸を売って人様から銭をもらって口を糊しているわけだから、その無残さね。それは無残さであると同時に豊かさでもあり得る。人間の極限の体験を語り、表現することは、鎮魂の行為であり癒しでもあるわけだから。そういうことを身にしみてやることもできるし、人情劇という側面からやってもいい、『景清』はいろいろな側面からできると思うんだよね。でもまず、過去を思い出すことの無残さみたいなものを永遠の課題として描くということがある。『隅田川』だってそう、母親の子供への永遠の思いの深さを、普遍性をもってあれだけ書かれたら、それを表現するのは、それはもう男子一生の仕事と言っていい。『景清』もまたしかり。『景清』の喪失感の深さ。能が世界に冠たる芸能であるのは、やっぱり喪失感をここまで深く表現しているから。他の演劇では喪失感の表現をここまで深くしないもの。死者のまなざしの深さみたいなものね。死んでもまだ残る妄執の深さ、永遠の地に幽霊となって現れ、その思いを言い続ける、これは単なる怨念というものでなく、そこに普遍的な思いがあるからでしょう。それが他の芸能と違うところだと思う。
能夫 なるほど。
明生 よいお話ですね。今の話が今回のメインですね、たいへん面白くためになりますよ。
笠井 銕仙会や銕之亟さん、栄夫さんの『景清』を観てきて、やっぱりいいと思うし。僕は演劇人として強い刺激を受けた。
明生 観世流と喜多流とでは景清像みたいなのは違いますか。
能夫 観世さんは着流しですることが多いでしょ。
笠井 大口も両方あるけれど。基本的には着流しかな。
能夫 着流しで座っているんだよね。敗残というか、それを受け入れているというか。宝生さんは浅葱の大口履いていますね。
明生 そういうのを履くというのは、よくわからないですけど・・・。
能夫 僕も昔はわからなかったけれど、今はなんとなくわかるような気がするよ。だって白だと武士っぽくなるじゃない。それが水色だと斜陽というか日が斜めから当たっているというような、崩れているような感じが出るじゃない。白だと逆に言えば強烈すぎるでしょ。
笠井 白は戦闘的な、闘っている感じになるね。
能夫 二十代のころはわからなかった。当時はみんな白の大口で黒の水衣でしょ。でも六平太先生も萌葱でやっていたこともあるからね。
笠井 着流しはないのね。
能夫 着流しはない。喜多流は型が多くそれも強さを出したい、心のわき立ち具合とか、癇癪も起こしたりと、いろいろ型としてやるから、床几に掛けていないと・・・。
明生 観世さんはあまりそういうことはしないのですか。
能夫 多少、情景描写的にはするけれど・・・。
笠井 やるけれど、だけどそんなにはしないから。
明生 観世さんの『景清』を観ていないんだな。
笠井 体の中にドラマを起こさせる芸をする人はそういませんよ。それができるのは先代の観世銕之亟(静雪)さん、栄夫さん、今の観世銕之丞さんだね。孤独感の深さを表現できるのは。栄夫さんの『景清』はとても良かった。栄夫さんの能の中には、今の観世流の人たちがどんなに逆立ちしたってできないものがありますよ。それは育ちもあり、かつ演劇人として他の仕事をしてきたこと、言葉に対する感覚の鋭さ、それは誰もが到達できていないところのものですよ。そこのところをきちんと学んで欲しいと思います。
能夫 それはねえ。この間の『小原御幸』の法皇をやったとき、それはすごいということがよくわかりましたよ。
笠井 今『小原御幸』で法皇ができる役者、誰がいるかな? いないでしょ。そういうことを考えてほしいと思う。栄夫さんの『景清』は本当によかった。あの孤独感、喪失感を表現する力、しかもそれがすごく適確なの。つまり・・・。
能夫 最後のところでしょ。「景清これを見て、物々しやと夕日影に、打ち物閃かいて、斬って掛かれば堪へずして、刃向いたる兵は、四方へぱっとぞ逃げにける」というところ・・・。
笠井「四方へぱっと」というときに、栄夫さんの演技でまわりの敵の兵士たちが、どよめいて後じさりした姿が見えた。
能夫 黒澤明の映画だな。
笠井 本当に空気が変わった。これは観世流の型だとか、喜多流の型とかいうことを越えて、景清という役の内実が表現されていたから、栄夫さんがぱっととやったときに 、その瞬間に生涯忘れ得ないその時の興奮と戦場の世界が今ここにまざまざと再現された。戦場の空気が変わる、はっとまわりが構えて後ずさりする空気が伝わってくるの。
能夫 それは僕、黒澤の映画を見ていて感じたことがありますよ。影武者だったかな、織田と武田の騎馬軍団が戦っていて、映像は武田方の大将たちが何人か立っているところを追っている。戦闘場面は映っていないんです。そして、その大将たちが高台から戦闘場を見ていて、二、三歩後ずさりをするんです。その映像を見て、ああ武田は負けたんだなというのを観るものは想像し理解する。ああ、黒澤という人は能を飲み込んでいた人だし、喜多六平太のファンだったし、だからそういう描き方をするのだと思いましたよ。大将たちがオーッと後ろに下がる映像だけで、騎馬軍団が鉄砲に打たれ、バタバタと馬から落ちているというような戦場の大パノラマが見えてきたもの。戦闘場面は一つもないのに。
笠井 能は常にそういう表現方法じゃない?
能夫 だから、そこです、勉強になったのは(笑い)。
笠井 そこを体現できる役者かどうかが勝負じゃない?
能夫 ここのところはまさにそうなの。
笠井 合戦の場を再現するところは、景清にとって生涯一回きりのことですよ。それも娘が訪ねてきて、別れる直前に、青年期の絶頂のときを再現するわけ。老年になってただ一回やるのだという、その覚悟みたいなもの、凝縮した力、そういうものが能にはあると思う。観ている人も、うちのじいさんがどう無惨に生きて死んでいったかをすごくリアルに見ている。普通の生活者が言うに言われぬ痛みを持って生きている、能が上等な演劇という人もいるかもしれないけれど、上等とかというより、そういう人間の根源的なところにさわっているかということだよね、芸が。そのために型がある、その型を生かしていかないとね。
明生 その型を生かす力というのがすごく必要だなというのが、特に喜多流にはありますね。型自体のよさに寄りかかっているような気がします。たとえば今私が『景清』をやろうとしたら、父は「ここはこうだぞ」と目で見える動作の秘訣を数多教えてくれると思います。それはそれで有り難く幸せなことなのですが、でも私たちぐらい、いやだな、もう46歳か!この年齢になると、そういう動きはずっと見てきているから、ある程度はわかると思うのです。だから「些細な動きはいいよ、他のことを」と言っても、「ここの足の下がり方が違うんだ、ここに心得がある」とか「こうすることで型がよく見えるようになる」と教えてくれるだろうと想像つくわけですよ。これはある面では助かり感謝することですが、ある面では反発するところでもあって、そうすると片方では能夫さんに向かっていって、いろいろ議論したり教えてもらったりということに、でも能夫さんのところではどうにもならない実質的なところになると、また父の方にと。私は両方あるからいいですけれど。喜多流はどうしても型一辺倒になっていて、こういう風に下がって、こうと、まずこれができなければ駄目! というのがあるから・・・。
能夫 それがある程度ベースですからね。
明生 喜多流には他流にないいい型もある、だからそれらが大切だというのはわかるのですが、その先に行かなくてはというのが、うまく言えないけれど先程の笠井さんのご指摘通りと思うのです。『道成寺』でも『景清』でも、そこに伝わる型の伝承に安住してしまうというのがね。流儀のあり方の問題なんですけれど。
能夫 そのことは大切なことですよ。僕の『景清』は四十代でさせてもらったわけだけど、ホップ、ステップ、ジャンプといおうか、五十代、六十代、七十代と段階を上げていき、僕の『景清』を作っていきたいと思いますね。
『采女』について
 笠井 さて、ここらで明生さんの『采女』に入りましょうか。『采女?佐々浪の伝』というのは、新しい何かをやっていくという最初のものだったのではないですか。これまでの曲の見直しをするというような。
笠井 さて、ここらで明生さんの『采女』に入りましょうか。『采女?佐々浪の伝』というのは、新しい何かをやっていくという最初のものだったのではないですか。これまでの曲の見直しをするというような。
明生 曲の見直しという意味ではこれが最初ですね。これをしたから『柏崎』なんかも取り組むことができた・・・。
笠井 だから『采女』がある意味ではあなたの出発点になったし、演能レポートを書き始めるようになったのも、これからでしょ。
明生 そうですね。そのあとすぐ『砧』を代演しなければならなくなったりして、笠井さんにもいろいろなことをお聞きして、自分でも考え、そういうものを自分の中にどんどん取り込んでいこうと思い始めていました。書くこと以前に、そういう見直すことを始めたのが私にはすごくよかった。
能夫 そして、そういう自分の足跡を残すことをやってきた・・・。
笠井 プレッシャーを感じながらね。
明生 暁夫(現観世銕之丞)さんが青山で『采女』をやられたとき、拝見したのですが、先代銕之亟さんが「今日のような、てんこ盛りの『采女』、これもいいんだよ」とおっしゃったんです。私が「先生が式能でやられた美奈保之伝の方がいいのですが」と申し上げたら、「それもそうだけれど、このてんこ盛りね、いろいろなことがたくさん詰まっている、普通の采女もやっぱりいいんだよ」と(笑い)。
笠井 そういうものもないと絶対駄目ね。
能夫 いろいろなものを通っていないとね。
明生 いろいろなものをやらなければ駄目なのだけれども、私の『采女』は研究公演で取り組むのだからという意識がありました。私が勤める前に能夫さんがちょうど例会で『采女』やっていたのですよね。ごく普通に、まっとうに。それで私に伝書にはこう書いてあったよと、いろいろなキーワードみたいなものを教えてくれたのです。本来こうなっているけれど、こういうやり方もあるとか、それで私の冒険心がくすぐられたみたいです。
能夫 出発点だな。
明生 そう、出発点。実先生の「小波の伝」というのがあって、佐々木宗生氏がやられた時、私なぜか録音して持っていたんです。聞いてみるとちょっと気になって触りたくなってしまって。
能夫 実先生がご高齢になられてから、ご高齢でもできるような形に直したというようなものだったけどね。
明生 それで、「小波の伝」をよく練って、自分なりの新しい試みを入れてみようとして、一年間というもの、これにかなりかかりきりになりました。伝書にあったキーワード「采女一日曠れ也(はれなり)」がヒントになり、入水自殺した采女も功徳により成仏でき、水の世界からこの世の世界に現れて、その喜びを舞うのだ、能『采女』はその晴れやかな一日を表現するのだと感じたのです。成仏できた晴れやかさ、極楽浄土に向かっていく美しい様、それを表現したいと考えました。装束も緋の袴にし、面も創作面を使用するなど工夫をして。それで小書も実先生の「小波の伝」を、あえて実先生の創作当初の名称「佐々浪之伝」とさせてもらいました。(くわしくは『阿吽』No.5の項、あるいは演能レポートの項参照)。
能夫 あの小書からも明生君の意気込みが伝わってくるよ。
明生 演出家もそうかもしれないけれど、演者もそうなんで、何か巧みたくなる。巧む心がなくなると駄目になるということは確かなんですよ。何も巧まずに、形式にのっとっていればいいものが生まれるという言葉を真に受けていると、現状より一歩も前に進まない。いつも何かを考え巧むというのは難しいかもしれないけれど、それをやっていかないと、自分自身が足をすくわれる感じがするんです。下の世代がどんどん上がってきているのですから、うかうかしてられませんよね。
笠井 明治の名人たちは、そういう形式にのっとってやって、そこで淘汰されていった。下手な人は能楽師として残っていないからね。現在はそういう時代ではない。淘汰されるということがない。だからその中でいかによい能楽師になるかが問題だよ。寿夫さんは、そういう時代を見据えていたから、他の演劇にも出て行ったし、本を読むこともしたし、世阿弥を本気で読んだからね。型だけやっていたらそんなことする必要ないわけだけど。
能夫 精神が必要ということだね。
笠井 作品を読み直すこともやる。世界的な演劇のレベルで、何がよくて、能で何が表現できるかを探ったわけだよ。それはそういう知性を働かせてやったわけでしょ。それを寿夫さん以降やっていないとしたら災難だよ。寿夫さんは五十三歳で死ぬような芸をやったんだから、それは死ぬような内圧をかけて舞台をやったんだから。
能夫 俺はその年になったけどまだ生きているよ(笑い)。
笠井 寿夫さんは短い人生だったけれど、実に多くの感動と影響を与えたからね。だけど僕はいつも言うように先代の銕之亟さんのように、六十代になって透明度のある謡と演技を見せてくれたという、そういう生き方もすばらしいと思うんだよ。あの透明度は寿夫さんの53年の生涯ではできない、五十三歳ではできない、そういう演技でした。だから、役者の生理というか、役者の時間はもうしようがないね。
明生 だから長生きしなければいけないということもありますよね。ところで私、今度、来年の秋の粟谷能の会(十月)にもう一度『采女』をやるのですよ。研究公演の反省も踏まえて、もう一絞りしたのです。序之舞をもう少しコンパクトに再考してみてはと。
笠井 普通のフルコースはやっていない? 一度やってみれば・・・。
明生 フルコースをやっていいというならやりますが。通常の『采女』をしっかりやると二時間はたっぷりかかりますから、なかなか難しいですよ。粟谷能の会の三番立で通常の『采女』を出すのはきつい。だからなかなか機会に恵まれないのです。でも研究公演でやりっぱなしというのも気になって、あのときの反省材料もあるし・・・。今度は囃子方を一噌流、大倉流、葛野流と前回とは変えて試みてみようかと思っています。
笠井 僕にとって浅井文義さんの舞台で一番良かったのが実は『采女』なのね。寿夫さんの十三回忌追善能だったと思う。二時間十分とか二十分かかったかもしれない。青山でやったから、座って観ている方もつらい。辛抱比べみたいなものだったけど、でもやっぱりよかったよ。彼の中の思い、つまり万能を一心につなぐという思いみたいなものがグーッと出てきてね。地謡も良かったし。彼の序之舞のよさもすごく出たしね。そこに全部凝縮したという感じ。長かったけれど、これが本筋だなと思った。美奈保之伝も悪くないけれど、なにかテーストが薄くなってしまう。二時間十分?二十分やって、いろんなものをやって、序之舞で純度が高くなって・・・、ああ、こういう世界かと納得できるものがあった。あのときの追善能は、浅井さんが一番若輩なんだよ。だけど先輩たちにひけをとらない、いや浅井さんのが一番良かったと言っていいぐらいだった。それが中堅の恐ろしさだよね。今浅井さんがそのときの先輩たちの年齢になっているけど、あのときの『采女』を越えるのは大変なことだと思う。若輩者が大曲をやるときのテンションの高さ、それがとてもよく出ていた。
能夫 テンション、そういうことはあるね。
笠井 それは本当に輝いていたよ。
明生 だから、いつも目標を持っていないと駄目なのですね、能楽師はいや能役者は。
笠井 長いものをどこかでやっておかないと駄目だと思いますよ。能というのは万能一心につなぐというか、不合理なものを一心につなぐ力技があるじゃない。
能夫 うーん。でも『采女』をやる場はなかなかないですよ。
明生 贅沢ですよね、そういう場があるというのは。一度やる機会があったとして、一生のうちにもう一度舞えるかといったらそうはない。そういうのは悲しいなというのが、私のあがきみたいなもので・・・。
笠井 でも、その『采女』以来、明生さんは一曲一曲丁寧にやり出した、見直しもするし、そこで考えたことを書くようにもなった。
明生 そうですね。
笠井 そういう、大きなエポックメーキングになった曲ということですよね、『采女』という曲は。
能夫 研究公演の第八回でそういうことを始めて、明生君の今日があるわけですよ。
(平成14年6月 於 割烹千倉)
面打師・岩崎久人さん、石原良子さんと投稿日:2018-06-07
面打師・岩崎久人さん、石原良子さんと
岩崎 久人
石原 良子
粟谷 明生
(今回は、『殺生石』女体や『経政』烏手の折、面を使用させていただきました面打
師の岩崎久人さん、そして石原良子さんとの、面について雑談話を記載してみました。)
 粟谷 今日はわざわざお忙しいところ、お集まり頂き恐縮です。どうぞお気楽にお話頂ければ結構ですので・・・。面を打たれるとき、一応大きさ、サイズは決まりがあるでしょうが、人それぞれ顔の大きさが違いますよね。最近はどうしているのですか? 女流能楽師もおられますが、そういう方のは小さく作られているのですか?
粟谷 今日はわざわざお忙しいところ、お集まり頂き恐縮です。どうぞお気楽にお話頂ければ結構ですので・・・。面を打たれるとき、一応大きさ、サイズは決まりがあるでしょうが、人それぞれ顔の大きさが違いますよね。最近はどうしているのですか? 女流能楽師もおられますが、そういう方のは小さく作られているのですか?
岩崎 女性のはわざと小さく作らないと、どうしてもおさまりが悪いよね。今、男の人も顔、小さいでしょ。体は大きくなったけれど、顔は小さくなっている。佐々木多門君、狩野了一君、皆さん小さいですよ。
粟谷 若い人はそうですね。小さくなりましたね、うらやましい。でも私やうちの父などはでっかいですよ(笑い)。
岩崎 うちの金太郎先生なんか、あんなに顔が長かったのに、面を上の方につけていましたからね。
粟谷 昔は観世さん、梅若さんは割と下に当ててつけられたそうですが、今は平均して上につけている方が多いんじゃないかな。寿夫さんの写真を見ると高いですよ。面の受け(うけ)は難しいですよね。今はどの流儀も当て物をつけますが、つけたときは丁度良いと思ったのに、「おま?く」と言って、幕が上がった途端に、「あれー」って、変わってしまう人もいます。へっへー・・・私ですよ。(笑い)
岩崎 素人会の申合せのとき、ツレをやっている若い人に、「オイ、どこを向いているんだ。もっと下を向け」と言ったらだんだん下に向いてきたから、「そこだ! そこを覚えておけ」って言ったんですよ。僕のこと誰だろうと思っただろうね。
石原 当て物は前もってつけたりはしないんですか? その当日その場でつけるの?家で前もってつけておけばいいのに・・・。
粟谷 それは家に面があれば、可能だけれど・・・、だって皆が皆、自分の家に面があるわけではないですから。能夫だったら、本家の蔵にあるので、ある程度の仕込みは出来るでしょうが、でも所詮自分では受けが見えないので、どうしても信頼出来る人に見てもらわないと・・・、となると当日っていうことになるんですよ。
石原 じゃあ、面は当日はじめてつけるのですか?
粟谷 そうですよ。普通はみんな当日ですね。持ってきてもらったときに。
石原 そうなんですか。
粟谷 そうですよ。だから面を持ってくる人は、開演二時間前には必ず持って楽屋入りしてくれないと演者は困ってしまうわけ。
石原 そうなんですか。この間『国栖』を拝見しました。おもしろかったですよ。面は何かしら、後は何?
粟谷 前シテは「三光尉」で、作者は・・・判らない。後シテは「不動」です。
石原 前の面、いい面ですね。後は黒く見えたんですが・・・。
粟谷 あの「三光尉」よかったですか。「不動」は新太郎伯父がどこからか買ってきたんですよ。当時能夫が「どうして不動なんか買うの、何に使うつもりなの!」と言っていたのを覚えていますが、まあ折角あるので、一度試してみたいなと。能夫も『嵐山』で一度つけています。そう、黒いですよね。我が家の面は、祖父益二郎と伯父新太郎が集めたものです。新太郎伯父は面の収集家でしたから、良い面が手に入るとその面を使う曲を演能の選曲としていたぐらいです。面白い話があってね、私も当時子供でしたが、その場にいたので薄々覚えていて、そう、父がよく皆さんに話すから、よけい印象が強くてね。伯父が「大悪尉」が手に入ったというので翌年に『玉井』をやることにしたんですよ。いざ本番というとき、先々代14世喜多六平太先生が、いきなり、「龍神は黒髭!」といいだしちゃったわけ。新太郎伯父が悔し涙でしょげているものだから、父が六平太先生に「先生、『玉井』ですよ、頭は白! 白頭ですよ! 黒髭ではおかしいんじゃないですか?」と申し上げたんだって。でも六平太先生は葉巻をくわえながら、「昔・・・津軽におつむが白くても髭の黒い方がおられた・・・」とお返事されたとか(笑い)。
石原 面白い! 私たちが喋るより先生たちのお話聞く方がいいわ。
粟谷 岩崎さんはお能も舞われているようですが、お稽古は何年ぐらいやられているのですか? 打つ方が先なんですか?
岩崎 打つ方が先です。守屋与四巳先生が面を打つなら謡えた方がいいでしょ、一番でも舞った方がいいでしょ、やりましょうというのでやらされて。イヤイヤやったんですよ。
粟谷 金春流はどちらで?
岩崎 それね。毎年横浜能があるというので、能面を打ち始めたとき、やっぱり能楽師に見てもらわないとわからないと思って、それで役員の人に聞いたんです。そうしたら桜間金太郎先生がいらっしゃるというので、お会いしたら、金太郎さんに、「あなたのような人は何人も来たけれども、ものになった人はいないね。三年やってみて同じ気持ちだったら、そのときに見てあげるから」と言われてね。その言葉を素直に受け取って、三年したらもう一度見てもらおうと思った。でも金太郎さん、三年経たないうちに僕の面使ってくれたんですよ。
 粟谷 石原さんはどうして打つようになったのですか。
粟谷 石原さんはどうして打つようになったのですか。
石原 能面を一つほしいかなって。お能なんか何も知らずに。
岩崎 僕はね、テレビを見ていて、能面っていいな、ほしいな、でも買うと高いだろうな。だったら自分で作ってみようというのが一番最初のきっかけ。誰かに習おうと思って電話帳で調べてみたけれど、能面を教えるなんてのは無いんですね。木彫というところを調べていて、実にわかりやすい名前の人がいたから、そこに電話をかけたんですよ。「能面つくりますか?」って。「つくりません。でもそういう彫刻をしている人は知っていますよ」というので、そこを教えてもらって電話をしたんです。訪ねて行って「教えてください」と言ったら「オレ知らねえ、自分で勝手にやれ」と言うんですよ。
粟谷 へー、みなさんはどうなんだろうなあ。
岩崎 いやあ、教える人がいたはずですよね。
粟谷 今は教える人も習う人も多いですよね。
石原 能楽師の先生たちは「打った面を見てください」って言われることもたくさんあるんじゃないですか。
粟谷 あまり多くはないですが。たまに見てくださいと言われて・・・、見ると、エーッというぐらいなもので、いやになっちゃうんですよ。だから能夫さんは「難しいですね、彩色は・・・」なんて言ってごまかしたりして(笑い)。
岩崎 金春会の桜間金記氏の『朝長』ね。粟谷さんに頼まれた『須磨源氏』のときの面あったじゃないですか、あれでやったの、そしたらピッタシ! 金記氏が「この面何ですか? って尋ねられて、何って答えて良いのか困ったよ」って言ってましたよ。
粟谷 名前をつけられたら・・・。
岩崎 いや、須磨とは書いてあるんですよ。この間の『殺生石』女体を拝見してそのときの写真を写真家の石田裕さんから見せてもらったんですが、石が割れるときの写真ね、ちょこんと顔が出ている写真、ああいうのは玄人の人は撮らないね。実におもしろい写真だよ。
粟谷 あれシャッターチャンスがいいですよね、ちょっと写真が暗いけれど。私ちょっと顔がでか過ぎるから、面から顔が横にはみ出していて、気に入らないんですが・・・。頭(かしら)をつけたとき、力髪という前に垂らす髪があるのですが、付け方のコツとして、頭の紐に通したらちょっと手前に力髪を出す、そうすると立体感が出るんですよ。あのときは付けた人が、これをするのを忘れたものだから、もろに肌が見えて残念でした。
岩崎 面の写真で気になるんだけど、よく見かける写真が僕らのイメージと違うんですよ。だいたい曇り加減なんだな。
石原 森田拾四郎さんは、照りぎみで、独特の捕らえ方をされますが。
岩崎 粟谷さんは、面の受けはどのようにして見ます?
粟谷 左右横から、目を中心に見ますが・・・、喜多流の人は横から見てますね。能楽座でご一緒したとき、観世栄夫先生は正面から見ておられました。私そこまで眼力がないので。
岩崎 僕は、真正面から口を見るんですよ。小面なら開いている口の形はいろいろありますが、歯のラインと左右口元が横一直線になるようなところ、曇っているとU字型に見えるし、照る場合はその逆に見える。良い受けというのは真っ直ぐなんですね。
粟谷 そうですか、良いことを聞きました。今度そうしてみよう。
石原 小面の話ですが、以前粟谷能の会で能夫さんが『求塚』をやられたとき、今の小面のような感じじゃない面を使われたでしょ。あれ面白かったわ。
粟谷 洞白の写しね。泰経春と書いてあったな。少し白い感じね。あれはすごく重いんですよ。一度使ってみたいけれどね。父がよく晩年の六平太先生が「面が重い」とおっしゃっていたと言っていましたが、年をとってくるとやはり面の重いのは疲労するんでしょうね。
岩崎 面って、「何じゃこれ」というようなものでも、舞台に上がるとすばらしいのってありますよ。
粟谷 近くで見るのと舞台で見るのとでは違いますね。
岩崎 近くで見ると、ボテーッとした感じで大した面じゃなくとも、舞台で見るとすごいんだなあ。
粟谷 本家に秘密の曲見があってね。友枝さんが『芭蕉』に使われたの。近くで見ると大したことなく見えるのですが、舞台で見たら見違えちゃった。いいねって言ってたら、父に、演じ手がいいからだよといわれましたけれど・・・。
石原 舞台での照明も面には大事ですよね。
粟谷 光はねえ。大事、それは演じる者には一段とね。喜多能楽堂は照明がまだ完璧ではないから、目付柱近くに寄ると目に光が入るんですよ。あれが嫌なんだなあ。素人のお弟子さんが面を付けられて稽古しようものなら、あそこで一瞬見えなくなってしまう、怖いものだから皆躊躇して止まってしまうんですよ。先生は後ろから、もっと先に出て!っていうけれど、当人は怖いですよ。
石原 それは変えられないのですか。
粟谷 もう一度、照明も手を入れないといけないですね、でも財団には資金の余裕がないし、他にもやらねばならぬことが多くてね。
岩崎 僕は目黒の能楽堂が好きでね。『羽衣』も『弱法師』も喜多能楽堂で舞いました。来年3月には最近打った面白い「曲見」で『隅田川』を舞います。最初は『藤戸』って決めていたのですが、あの「曲見」見てから、『隅田川』に変えましたよ。目黒の舞台は脇正面の後方のガラスに自分の姿が見えるじゃないですか。あれが良くてね、気に入っているんですよ。
 石原 ところで、ホームページ大変でしょ。
石原 ところで、ホームページ大変でしょ。
粟谷 ええ。なぜやっているかというと、読んでくれる人が結構いるわけなんですよ。反応もあって、中には新聞感覚で見ている人がいるわけですね。三日に一回とか四日に一回とか見ている。それで、この間見たのと何ら変わらないとがっかりなさるようで、せっかく開いたのに何も変わっていない、新しく更新して下さいとメールが来るんですよ。
岩崎 うちも作っているけれど・・・・。
粟谷 岩崎さんのホームページのギャラリーとリンクするのはどうでしょうか? 公開するのがいやならやめますが。そういうものがあれば、私の演能レポートとリンクさせて、たとえば『大江山』で拝借した慈童の面を、ポンとクリックすると岩崎さんのホームページに行って、こういう面ですよと拡大の面の写真が出るなんていうのは、いいんじゃないかな。
岩崎 写真はデジカメね。息子に買いに行こうと言われ、買わされましたよ。六万円。
粟谷 わー高い機種ですね、六万円というのは。私のは人からゆずってもらったもの。いいものはすごく高いですね。だけどホームページに載せるものは、あまり上級機種でなくてもいいんです。画素数が少ない方がよいようです。
岩崎 そういうことになるとチンプンカンプン。
粟谷 息子さんの聡さんが、「父が粟谷能の会のホームページに殺生石の写真が出るはずだが、未だか、未だかとうるさいのですが、いつごろ記載されますか?」とメールが来ましたよ。「申し訳ない。『阿吽』という小冊子に出しますので、いましばらく待って下さい。出し惜しみしているんです」とお返事をしたら、その後に「父のホームページを開きますから、粟谷能の会とリンクしてほしい」という依頼がきました。すぐリンクしましたよ。
岩崎 そりゃどうもありがとうございます。
粟谷 今年も能雅院展、七月にやられますか? 銀座ですね、今度は面の方がメイン?あれはみなさんお仲間なの?
石原 違います、皆、一匹狼。
岩崎 一年に一回会う程度で・・・。
粟谷 橋岡一路さんも個展やられていますね。(5月28日から7月7日)
石原 100面展、すごいですよ。
粟谷 今度見に行くつもりです。能面展、松濤美術館ですね。先ほどの話に戻りますが、舞台に出してはいけないような面を能楽師が使っているときがありますが、あれは感心しませんよ。打つ方の責任と、付ける能楽師の責任もあると思いますが。そういうときは、地謡なんか一生懸命謡うのがばかばかしくなってしまう時もありますからね。
岩崎 あるだろうなあ。
石原 ご本人は満足しているのですか。
粟谷 本人? 能楽師のこと? それはまわりではなかなか言えないものですよ。 昔、ある方が、不適当な装束を付けて舞われたことがあったの、そうしたら父が、もう怒ってね。「人に物を借りるというのは、もう負けになるんだ。でも大事な曲を勤めるときはそれを覚悟して、頭を下げて拝借してでも、ふさわしい物を身に付けなくては駄目」ってね。面も同じことでしょ。幕が上がってシテが立っているあの瞬間、あれが仲間内での一つの勝負所でね。あの瞬間のあの場面は地謡から一番よく見えるんです。いい演者だときれいな場面ですよ。皆様には申し訳ないけれど、最初に我々が見てしまうの・・・。
岩崎 そこが一番いい場所なんだ・・。見る方も場所の好みというのがありますね。
粟谷 そうです。もう皆様、好き嫌いがあるでしょ。
岩崎 僕なんか真正面から見るのあんまり好きじゃない、中正面側がいいですね・・・。
粟谷 中正面じゃ、目付柱が邪魔でしょ。
岩崎 能面がちょっと横から見えるところがいいんですね。
粟谷 料金では正面席が一番高くて、その次が脇正面で、次が中正面なんですけどねえ。
岩崎 僕は中正面の脇正面側が好きだな。それから、念ずれば通じるというのかな。友枝家の万眉ね。こんなにきれいなものがあったらいいねと思っていたら・・・、何年かして友枝さんと知り合いになって、その面が家に泊まりに来たわけだよね。一か月ぐらい家に泊まって。
 粟谷 泊まる?
粟谷 泊まる?
石原 修理ですよ。
粟谷 それで修理をなさったのですか。
岩崎 そう。もうね、彩色がはがれかかっていたんだよ。でもいい目をしていたね。薄い目をしていた。それから、今度は目が見えないから大きくしてくれって言われてね。これ以上できないというところまでやりましたよ。万眉を見ると、友枝先生と思っちゃうもんね。友枝先生、何でも万眉使っていたじゃない。『羽衣』であろうが『蝉丸』であろうがね。
粟谷 そうね。あの年代の方というのは、ほら、それに取りつかれちゃうというか。うちの父もそうなんだけれど、河内の堰ね。何やるにも堰の小面なんです。遊女であろうが建礼門院であろうが『羽衣』であろうが、同じ顔ではまずいだろうと思うけどね。あれね、ご覧になったことある? あー、ありますよね。祖父が見つけてきて父にかけさせたら、実先生が「お前にはもったいない良い面だ」とおっしゃったとかで、それ以来ずっと父はそればかり、浮気しないの。新太郎伯父は、そういう一面主義じゃない。これで『班女』やって、あれで『楊貴妃』をやってと、まー、これが普通ですが、友枝先生や父はタイプが違うんですよ。
岩崎 なるほどね、いい面というのは舞台で見たとき必ずいいかというとそうでもないし・・・。同じ面でも、やはりかける人によってもえらく違うしね。
粟谷 この間、能楽座で父が久しぶりに堰の小面つけたんですよ。『小原御幸』ですが、栄夫さんが後白河法皇をやられて、異流共演でしたが。あの時、父が「やあ、再会したな」なんて言って・・・。あれを使わなくなったとき、父はこの女を捨てた、堰ちゃんを捨てた、そしたらどんどん朽ちていった、本当に真っ黒にね。私も「あれ、こんなに黒かったかな」と言ったら、「バカ、使わないから死んだんだよ」と父。能夫が「修理しますよ。もう使わないんでしょ。誰も使わないでしょうけれど修理しますよ」と言って。つばから汗から菊生のすべてのものが、もうぎっしり詰まっている面ですからね。新太郎伯父が「あの面は気味が悪い」と言ったぐらいで。能夫が一回かけて『玉葛』をやりましたが、どうもしっくりこないようでした。私が一回『船弁慶』で使ったら、父が伯父に向かって「どうして出したんだ」と怒ったそうで。面白いことに、父は私や能夫には直には言わないんですよ。確かに写真で見ると、父以外の人間がつけるとあの面、変なんですよ。
岩崎 面は言うことをきくのと、きかないのがあるんだよね。
粟谷 演者の言うことをきくようにこちらが大きくならなければいけないのかな。使い手が面を生かしてやらないといけませんね。この間の粟谷能の会の『殺生石』女体で後に付ける面、玉藻を前につけたでしょ。あれ結構正解だったと思うんですよ。あのきつい感じがね。
岩崎 はい、あれ前シテによかった。僕のねらい通りの感じが出ていて。仲間と一緒に見に行ったんだけれど、その人が『殺生石』ってあんなにおもしろいものだったかなと言っていたよ。おもしろかった。僕がこだわっていたのは岡本綺堂の小説を読んでずっとあたためていたものなんだよ。その小説を読んで、そんなものを作ってみたいというのがあったんでね。本来、女面で金泥なんてないんですよ。それを僕は薄く、よく見ると泥が入っているのかなという面にしたかった。だけどどうもああなっちゃうんですよね。でも、ああいうのもおもしろいんじゃないかな。
粟谷 使い道を考慮すれば、いいと思いますね。模写ばっかりというのもね。創造性あるものもあっていいはずですよ。だって三光坊や赤鶴の時代の人たちは新しく創造したんだから。どんどん沢山、写しと創作とを作って、いや打って下さい。期待しています。今日はどうもご協力ありがとうございました。
(平成14年6月 対談)
写真撮影 粟谷明生
(上より順番に)泥眼 小面 は岩崎打ち
獅噛(しがみ)増女は石原打ち
野村四郎氏と『卒都婆小町』を語る(H17/4/3掲載)投稿日:2018-06-07
野村四郎
粟谷能夫
粟谷明生
今年の春の粟谷能の会(平成17年3月6日)に、粟谷能夫が『卒都婆小町』を披くことになったことから、新春早々、野村四郎氏に『卒都婆小町』についてご教授願おうと、粟谷明生も加わってお話を伺いました。暖かくも激しい芸談が展開され、熱い時間となりました。(3月の粟谷能の会は終了していますが、『卒都婆小町』を披く前の語らいを、ここに掲載いたします)。
能夫 今年私、『卒都婆小町』を披くことになりましたので、そのお話をひとつ・・・。
野村 『卒都婆小町』ねえ・・・。
能夫 おいくつの時、なさったのですか。
野村 いくつか忘れちゃった。いくつだろう。『卒都婆小町』でタバコをやめたんだ。(笑い)
能夫 『卒都婆小町』で僕、ダイエットしているんです。(笑い)
野村 『安宅』でタバコをやめて・・・、酒はなぜかやめるという意識はなかったね。『安宅』が終わって、またすぐにタバコを吸ったの。その後タバコをやめたのが『卒都婆小町』でした。『卒都婆小町』というのは、人生の中で何かあるんだよ。
明生 観世流は、一般的には『卒都婆小町』の披きは40?50代ですか…。喜多流は遅くて還暦を過ぎてからなどといいますが、これでは遅すぎませんでしょうか?
野村 喜多流のことは分かりませんが・・・。観世流は今、『卒都婆小町』を軽んじているように感じます。昔は『卒都婆小町』が最高曲でした。『鸚鵡小町』は稀にしか演じられなく、よほどの方でないと『姨捨』までは・・・。ですから『卒都婆小町』は老女物の披きの最高曲です。
能夫 うちもそうでした。
野村 そうでしょ。僕の体験からすると、あんまり年を経てから老女物をやるのではなく、若いうちに披き、二度、三度と勤めるうちにより良いものにすればいいのではないかと思うのですが、どうでしょうか?
能夫 本当にそうですね。
野村 足腰が駄目になってから挑むような老女物はダメ、勉強にならないよね。やっぱりまだ足腰がきっちりしている間に老いの虚構を演じるんだよ。
明生 なるほど。
野村 そうでしょ。爺さんになってそのまんまでは、演じることにはならないもの。
能夫 演じることにはつながらないですよね。
野村 その人のそれまでの能に対する考え方、意識というのが、そこに現れるものでなければ・・・。藤山寛美ならうまくやると思う、僕は藤山寛美というのは一番の役者だと思っています。でも、僕たちは役者は役者でも能役者だからね。能がついていると、乞食の役でもシルクを着ているんだよ。だからそこに私憤を絶やさないことじゃないかな。結局お能って、小町を演じるとき、まず一番に色気がないと駄目なんだよ。僕は「これは出羽の郡司小野の良実が娘、小野の小町が成れる果てにてさむらふなり」、この謡に艶がないといけないと思っています。そして「影恥ずかしき、わが身かな」で、笠で顔を隠すんですが・・・。喜多さんもなさる?
明生 観世さんのように、笠ですっぽり隠れるようにはいたしませんが・・・。
能夫 手でそっと。そのとき笠を持っていませんので・・・。下に座ったときに笠は置いてしまいます。
野村 なるほど。「影恥ずかしき」というのは何かというと、過去に対する恥ずかしさとかではなくて、僕は『姨捨』のような気持ちなのです。月に照らされて、皺も見え、老醜があらわになる。隠すというのが艶なの・・・。隠すというのを、僕は月を見てやるんです。月がすべてをあらわにするという・・・、汚くも見せれば美しくも見せる。
能夫 まさにそうですね。
野村 そして、年月を重ねてきたことを月に見られているという気持ちがある。すべてが見透かされているような。深草の少将との恋のことから、歌詠みで誇らしげであった気持ちまで、すべてが見透かされている。あーあ、今は老残の身、それが恥ずかしい・・・。つまり「これは出羽の郡司・・・・・・成れる果てにてさむらふなり」と謡って、ワキに「痛はしやな小町は・・・」と言われているうちに、だんだん恥ずかしくなってくるんですよ。これまでの名人は、寿夫先生もそうでしたが、「これは出羽の郡司・・・」はお婆さんで謡っておられないですね。違和感がなく昔を回顧するような、昔に引き戻されるような感じで、「さむらふなり」と謡ってワキへ向きます。そのときうちは笠を持っていますから、その笠が何か隠れ蓑みたいなものになって、控え目さみたいなものが出てくる・・・。
能夫 笠が防波堤のような。
野村 笠を持っているというのは、重心が下に着くからやりやすいんですよ。それで上が多少突っ張っていてもね。能夫さんは『卒都婆小町』披くにあたって、突っ張ってやってもいいけれど、いつまでも突っ張らかってではなくて、菊生先生のように自然体に。
能夫 菊生叔父の境地には中々なれないですよ。
野村 そう、直ぐには無理ですが。とにかく「これは出羽の・・・」、あそこの謡が勝負だよ。あそこでもって、小町のある部分が出なかったら、何もない。
明生 うあー、だって!(笑い)
能夫 わかります。
野村 それから習ノ次第で出るときには休息があるでしょ。そのときの型が本家と分家では違うのです。本家は伏せて体を杖に預けるようにしますが、分家は背伸びをします。
能夫 リラックスするんですかね。
野村 リラックスというか、杖をつきつき出てきて、ちょっと休み、あーあ、疲れたという感じ。本家と分家ではこんなに違います。
明生 父が、観世さんのどなたかが、後ろにのけ反るように背伸びしたと言っていましたが・・・。
野村 それです。分家の方はそうするんです。僕は両方やります。まず面を伏せ、それから少し体を伸ばします。体を伸ばしてからは元に戻るまで動きません。あの休息とは、そういう時間だろうと解釈しています。
能夫 どちらかでなくて。
野村 そう。それも両方を取り入れてやるというのではなくて、老女の自然の成り行きとしてと考えたいですね。
明生 その方が自然ですね。
野村 ねえ、老女には両方あるじゃない。僕は型付というのはある意味で羅針盤みたいな、方向指示器みたいなものだと思います。最近の型付はたくさん書いてあります。何で昔の型付はあまり書いていないか・・・。昔の型付ほど自由な余白がありますね。
能夫 書いてないから、自分で発想しなさいということでしょうか?
野村 そうだと思います。それで、次に書く人は自由に発想して自分のために書きます。人のためじゃない、それが型付の起こりです。それを今度は人にも伝え教えるようになって、伝書というものになった。花伝書も世阿弥が息子のために書いたものでしょ。それもたくさんの息子に教えるのではなくて一子相伝。
先程『卒都婆小町』は若いうちに勤めたほうがいいと言いましたが、それはあのワキとワキツレとの問答を経験してもらいたいからなんです。僧に卒都婆に腰掛けたのをとがめられるところからのいわゆる「卒都婆問答」。禅問答ではないけれど、あの会話を習得しようと思わないと・・・。シテは最初は受けから始まりますよね。それが次第に変化しながら、最後には逆転していく。それもなべをひっくりかえしたような大逆転。いきなりひっくり返るのではなくて、徐々に、最後にはどうだとばかり、僧が頭を垂れるところまでもっていく、そこのドラマでしょ。能のドラマというものを観客に伝えるのは大変なことだと思う。『卒都婆小町』は観阿弥の作品でしょう?
明生 世阿弥が改作していますが、もともとは観阿弥だと思いますが。
野村 観阿弥だから、憑き物の芸能というところがある。あの問答にも憑き物的なものがありますよね。ですからどんどん憑いて来て・・・。あれはね、考えてしゃべっているんじゃないんですよ。
能夫 そうですね。そういうイメージです。
野村 ワキの僧は一生懸命考えて言っているのですが、シテの小町は自然にポーン、ポーンとね。最初は間というものが大事だと思うけれど、徐々に時間が経つうちに逆転して、ついには「げに本来一物なき時は、仏も衆生も隔てなし」となる。あそこの場面、何か型をやりますか?
能夫 友枝昭世さんがやっていらした気がします。
明生 「隔てなし・・・」と強く杖をつかれていました。
野村 僕いろいろなことをやりますが。その前の「台(うてな)になし」でついてしまうのもありますが、それでは、シテのエネルギーが切れてしまいます。エネルギーを持続させるためには・・・。
能夫 最後に止めをさすような感じにするには。
野村 そう。あとでやったほうが気持ちが固まるね。ワキの高野山の僧侶なんか・・・ってね。
能夫 相手じゃないわ、って。おもしろくできていますよね。
野村 すごくドラマチックなんだ。
明生 あの問答の謡いかた…、考えてちゃ駄目なんでしょうが、何かコツみたいなものがありますか。最初から力んで一生懸命謡っているようでは、そこにたどりつかないというか・・・。
野村 でも最初は一生懸命謡わないと成り立たないよ。
能夫 そうですね。だから2度、3度やりたい曲ですね。
野村 ところで、四ツ地の謡はあるの。
能夫 昔は『卒都婆小町』にも、四ツ地の謡があったらしいですが。
野村 節を大きく謡うでしょ。だから2拍休んだりしますよ。
能夫 九拍子ですか。
野村 そういうのもあるわけ。今はみんな八拍子で打つけれども、僕は地拍子では謡いたくないんだよ。(笑い)
能夫 自由に謡わせてほしいときありますよね。地拍子にこだわり過ぎると窮屈になりますから。それからロンギのあとですが、観世さんは早く立たれるんですか。
野村 早く立つのが普通ですが、橋岡久太郎先生が書き残している型付けを見ると、すぐに立たないようです。
能夫 最後のところ、「破れ蓑・・・」のあたりですか?
野村 もうちょっと早いね。普通は「頚にかけたる」で立っていくのですが、橋岡久太郎先生がやっているのは「粟豆のかれいを・・・・・・くにの垢づける」で立って、「袂も袖も・・・」で左を向いて右手を左側にもってきて杖をつくんですよ。僕も近頃そうしています。
明生 ああ、そういう写真がありますね。
野村 喜多さんはないの。
能夫 ありますけれど、あれほど強烈なポジションではないような気がします。
野村 そして右足を引いておいて、色っぽく面遣いして、あー恥ずかしい、となる。ここに色気が必要なんですよ。「袂も袖も」、あとからゆっくり見るから利くんだね。動き出したら同じですから、型と所作の違いということになるね。
明生 なるほど。勉強になります。
野村 現在物は所作でないとだめということです、型を超えないと…。
明生 現在物の難しさはそこですか。なるほど型だけでこなしていても手に負えないと思っていました。そうか実感します。
野村 所作でなくてはね。それでも逆に型になっていくんですよ。
明生 確かに。現在物と夢幻能との違いはどういうことかを、そういう言葉で教えていただくと、あー、すっきりします。型と所作か…。覚えておこう。
野村 ロンギの後の問答で、「のう、物賜べのう、お僧のう」というのがあるでしょ。昔の文献を見ると、「のう、物賜べのう」のあとの「のう」を高く謡うようです。これは本家にはありません。この「賜べ」というのは「何かめぐんでくれ」という意味でしょ。お僧も二人いるんだから。真ん中の「のう」を高く張って謡うことで、相手に強く訴えかけるのです。平坦に「のう、お僧」と言っても力がない。僕はそうしていますが、そちらはどう?
能夫 同じです。
野村 「今は路頭にさすらひ、行き来のひとに物を乞う」と言って目付の方に行って。「乞ひえぬ時は悪心、また狂乱の心つきて、声変はり、けしからず」とダラダラと下がるんですよ。そして「のう物賜べのう」。どちらが正しいかわからないけれど、芸能の言葉だからね。
先代の橋岡久太郎先生が書き留められていた型付でいいなと思ったのは、深草の少将が「榻(しじ)の端書き、百夜までと」のところ。これは通った回数だよね、車の榻に書き付けたんだから。橋岡久太郎先生はこの「榻の端書き、百夜までと」で、右向いて拍子を踏んでいるの。そうすると一つ、二つ、三つと百夜通いの端書を榻に書き付けている感じがする。普通は左右に回るだけですが…。
能夫 書き付けている感じで拍子を踏んだというわけですね。
野村 ただ舞を舞っているというのではなく、その表現こそが『卒都婆小町』そのものなんだと思うよ…。右だの左右だのという状況を越えてしまってよ、能夫ちゃん!
能夫 なるほど…。それからそのあと、「あら苦し目まひや」のあたり、いろいろやりかたがあると思うのですが…。「その怨念がつき添いて」のあたりですね。
野村 あれはいろいろな型があって。うちの方ではね、「その怨念・・・」と言って四つ拍子踏むの。それでタジタジとなって座ります。華雪先生の伝書だと「かやうに物には狂はするぞや」で、敢えて下からなめるように見上げるという教えね。
能夫 すごくリアリティがあって、わかります。
野村 こう、顔を縦に遣い、胸を張ってね。少将は悲しいんだ! 苦しいんだ! という表現があって、それがだんだん緩んでくる。
能夫 浄化されていくみたいな・・・ですか?
野村 いや、浄化されるというよりは緩むんだな…体が緩んで…ふっと抜けて…立って…仏に手向ける・・・。
能夫 そして合掌する。そうか体が緩むのか…。そこが極端に変われないでいたのです。あー、ありがたいお言葉でした。何かそこで変わらなければいけないのかと思っていましたから…。
野村 そういう内的なものの演技なんじゃないかな。
能夫 そうですね。
野村 表面的なことはいろいろあるけれど。面を上げながらワキを見る、しかし単にワキを見るんじゃないよね、自分の気持ちの中に入っていくんですよ。それをワキが見ている形になる。書きつけにある、「狂はするぞや」でワキを見る、と…そんな型だけの世界じゃいけないんじゃないの。
能夫 はい、そう思います。
野村 自分の体の中そのものですね。それから最後、「悟りの道に入らうよ」で合掌するとなっているけど、現在能で合掌するのはある? 一曲の最後に合掌するのは修羅物とか夢幻能しかないよね?
明生 あの最後の部分は……すみません、あー終わったと思ってまして…何も思考していませんでした・・・。
能夫 僕も最後まで思考していないな…。
野村 それではダメだよね。ちょっと感じてほしいなあ。僕はね、世阿弥、観阿弥の時代にさかのぼってみると、小町という人物がどれだけ一般の人に認識されていたかということ、かなり有名な人だったと思いますよ。深草の少将をあんなに悩ました、悪行三昧の女だから。そうなると具合がいいんですよ。なぜ具合がいいかというと、つまり道に入ろうよといいますね、ワキの僧がいるわけだよ、一人芝居じゃないのだから、高野山から出てきた僧と相対したことで、一般に見ている観客も一緒に救っていくという、何か民衆性みたいなものが合掌という型を生かしているんじゃない?
明生 『卒都婆小町』という作品を、喜多流ではあまり重く扱いすぎて、私の体の近くにありませんでした。『鸚鵡小町』を謡う経験をして、あれ『卒都婆小町』と何か違うなと思ったことがありましたが、それが何であろうか? 正直判りませんでしたし、追及しようとも思いませんでした。『卒都婆小町』の民衆性や土臭さというもので、今少し分かりました。観阿弥が創ったということが…。
野村 泥臭くしているんだよ。
明生 泥臭いですよね。
野村 要するに作能のパターンというのがあるかもしれないね。三番目物のパターンがあって、修羅物のパターンがあって、だいたいそれですべて語れるようなところがあるけれども、観阿弥の作品は、あとで手を加えられているとしても、『松風』だって世阿弥が手をつけているからね、そうであっても、もっとも芸能的なんですよ。芸能的ということは、見る人と共感するということが大事であるわけです。高尚でもなんでもないんだね。たとえば『鵜飼』を見て、殺生を生業にしている人は、地獄に行った者が、日蓮上人さんのおかげで極楽まで行けた、ならば私も救われるだろうと思う、それがいいんじゃない?
明生 殺生しないと食べていけない人もあるわけで、そこで人が救われる、それでいいなと思いますね。
野村 そうですよ。僕はその感覚がものすごく強いよ。
能夫 その視点が大事ですね。
野村 世阿弥のころは、将軍など上つ方に気に入られるようにと、どんどん趣向を変えていったでしょ。作品論をいろいろな人が言っていますが、僕は世阿弥のあとに続くものはいないのではと思っています…。
明生 金春禅竹もダメですか。
野村 まあ、禅竹だけ。娘婿だけ。あとは作品の趣向から言ってみんな観阿弥に戻っている。『松風』にしたって『卒都婆小町』にしたって、みんな現実性がある。その後の作品は幽玄無常なんていう世界ではなくなっていますから。だからもっと能は演劇的でいいと思うよ。その演劇性そのものが規範になって、人間的なものを演じられるということにならなければいけないよね。それには役者の技量がいる。だから世阿弥に戻るよりは観阿弥に戻れ! といいたいね。精神はもっと劇的なんですよ。
明生 『卒都婆小町』というのは、民衆の心をつかまないと成立しない、という作風なのですね。
野村 観阿弥の創り方の不思議さをもうちょっと認識しながら、なんでもかんでも世阿弥論にもっていくのではなく、観阿弥という人の思考を再生することで、もっと演劇的になっていいのではないですか? 演劇的という言葉が嫌いだったら劇的といってもいい。もっと表現が前向きであってほしいと思いますよ。こうでなければお能ではないという決まりみたいなものはありますか。少し乱暴な言い方かもしれませんが、僕はその枠を取っ払ってもよいのではと思いますね。皆さん方も、不肖私も含めてね。そんなもの取っ払ってもちゃんとお能になっていますから、いいんですよ、大丈夫。もちろん目茶苦茶やっていいというのではないけれど、思いのたけをしっかり持って、ぶつけて下さいよ。
能夫ちゃんは『卒都婆小町』をどんな気持ちでやるの?
能夫 なかなか。プレッシャーを肩に感じるばかりで・・・。
野村 『卒都婆小町』の中には一つの技術を習得する過程があるよね。『野宮』を勤め、『定家』に挑戦して、そういう一つの道があったとするでしょ。観世寿夫流だと、まず体を広げて、姿勢はそのまま、「それが定家!」と教わるわけですよ。気を吐け、そして気持ちを身体の中に閉じ込めろ、まず一番最初にもとありきなんだよね。寿夫流のポジション・メソッドというのかな、方法論、演劇といってもいい、必ず先にきちっとした体があって、それがどう変わるかということにしなければいけないと仰っていましたよ。僕、若かったから素直に聞けたよ。だけどそれをやっているとね…、華雪先生に怒られたよ。(笑い)
能夫 世の常ですね。世代的なギャップというか。写実があれば、無機的なものを求めたり、そういうバイオリズムみたいなものがある気がします。
野村 それで最初に言ったクリの謡に戻るけれど…、観世寿夫師のあのクリは、「これはーー、出?羽?の」というのが、まさしく老女物なんですよ!(笑い) わかるかなあー、わかる?
明生 乞食の婆さんが急にすーと浮かび上がってくるみたいな・・・。
野村 そして「・・・小町が成れる果て」というところ、成れるの「な」の字を引くんですよ。今僕だけやっています。寿夫師がやられた時、つっと、身体が細っそりしているでしょ、それで「さむらふなり」とワキを向いたときに小町になっているんですね。これは憎らしいぐらいにね。(笑い)
能夫ちゃんは、面は何を使うの?
能夫 今、銕之丞さんに拝借させていただくよう、お願いしているのですが・・・。
野村 何を?
能夫 「檜垣女」ではと言われていますが、まだ、何になるかわかりません。
野村 地頭はどなた?
能夫 菊生叔父です。
野村 今、菊生先生という人を遊ばせておいてはいけませんよ。地謡というのは大事ですよ。観世寿夫先生も仰っていました。先生は若くして亡くなられたけれど、将来は地謡で生きるんだという意識を強く持たれていましたよ。
能夫 そうですか。すごいなあ。
野村 菊生先生も同じですね。喜多流で地頭をこなせる人は、菊生先生以外にそういないですよ。大きな曲を披いたりするときにはもう菊生先生ですよ。生きているときにしか聞けないからね。どんどん一緒に舞台を経験するの、そうするとそこが違うとかいろいろ言って下さるから、どんどんやって下さいよ。これはどうですか?とか、大いに聞くといいですよ。
能夫・明生 そうですね、そうします。
能夫 今日はありがとうございました。また、ご報告の会もしたいと思います。
(平成17年1月 記)
ダンサー&振付師(作家)の余越保子さんと語る投稿日:2018-06-07
お能の新しさ
ダンサー&振付師(作家)の余越保子さんと語る
余越保子さんは1981年にアメリカに渡り、パンプシャー大学、NY大学で振付と演劇を学び、ニューヨーク、アムステルダムをベースにダンサーとして活躍。95年からは作品を発表し始め、ダンスマガジン誌上で注目する25人の作家に選ばれています。最近は、日本でワークショップを教えるなど、作る、踊る、振付と、幅広い活動を展開されています。ダンスの分野はコンテンポラリーダンスということで、モダンダンスに属するようですが、日本の伝統芸能にも興味があるということです。こ
の度、歌舞伎舞踊を研究するため、アメリカからの留学ということで、東京に1年間滞在されています。滞在中、お能にも興味があるということで日舞と謡と仕舞を私(粟谷明生)のもとで稽古されました。今回は、ダンスの専門家から見た能について興味深いお話をうかがうことができました。
 粟谷明生(以下粟谷) 稽古してみてどうでしたか。
粟谷明生(以下粟谷) 稽古してみてどうでしたか。
余越 体に入ると踊れるんですけれどね。まだまだ・・・。
粟谷 能は踊るでなくて舞うといいます。
余越 舞えるんだけど・・・。うろ覚えのときには、お稽古を録画したビデオを見ても、何でこんなにおどおどしているのと思ってしまう。仕舞の歩幅とか形とかペースがつかめないから。いろいろな舞の構造がわかってくるといいんですけれど。
粟谷 1つ1つ段階を踏んでお教えしていければ、構造がお判りいただけるのですが。例えば「上羽」(あげは)「左右」「打込」と連続している動きとして覚えられるといいのですが。
余越 何かクラシックバレエと似ているところがある。型があるっていうか。
粟谷 型は決まっていますよ。基本動作は50型ぐらい。湯谷なら13の型を覚えれば出来ます。
余越 バレエの方が多いですね。バレエは、オン ザ ビートというか、動きのリズムがはっきりしているし、一度バーレッスンをマスターすれば、手が増えて踊れるようになるんだけど、お能や日本舞踊は、間で踊るでしょ。でもなかなか面白いのは、ヘタでも見ていて面白いところがある・・・。
粟谷 下手でも、見て面白い?
余越 うまく言えないけれど、バレエだとヘタだと見ていられない。
粟谷 ハハハ(笑い)。
余越 もう絶対見ていられない! お能の場合は、私なんかお稽古したの4回目、ど素人じゃないですか。それでも一応形の善し悪しは別として何となく舞える。でも、バレエのど素人は踊れないと思う。お能の場合は、動きがオーガニックというか自然だからだと思う。人間の体に一番即した動き。歩行なんかの位置関係もオーガニックに作られている。だから変にずれて見えない。ヘタなんだけれどもちゃんと見れる。バレエは装飾が多いから、その装飾をうまく形づけられないと見られないんだと思う。お能はそういうところ構成がしっかりしていると思う。すごい!
粟谷 あなたがある程度、短期間でスムーズに仕舞を習得出来たのは、やはりダンスをやっていらっしゃるからだと思いますよ。基本的な身体を動かす運動のセンスをお持ちだから。仕舞の構えは普通はあの姿勢を形作るまでになかなか時間がかかるものです、なかなかできない人もいるのですよ。
余越 もちろん、それはそうだと思いますけど。でも、へたはへたなりに、何か味が出るんじゃないですか。初めてお能を観たのは研究会というものだった・・・。
 粟谷 どなたの研究会?
粟谷 どなたの研究会?
余越 忘れてしまった。
粟谷 三島由紀夫は、最初に何を観たかが問題と言っていますね。
余越 本当の初めは、ニューヨークで。ジャパンソサイエティに来ていた人だから、結構有名な人だったと思う。
粟谷 梅若六郎さん?
余越 六郎さんではない。ずいぶん前ですよ。梅若さんはアムステルダムで観ました。それで、日本に来てから能楽堂でお能を観るのがいいと言われたから。お金がないので一番安いのをというので、それが研修能だったみたい。でもすごく面白かった。やっぱり物がしっかり作ってあるから、こう・・・。
粟谷 そう。能は構造の骨格がしっかりしているから、あとは能楽師自身の体や精神性みたいなものが問題なのですよ。能がユネスコの世界遺産になったと自慢できる一方、その中で何をしているかということが大事なのでしょうね。私も含めて、なかなかどうしてそこまでいくには難しいですよ。
余越 でも面白いですね、構成がやっぱり。600年前に出来た伝統芸能というけれど、私の目からすると、すごい、ポップなんです。話の作り方とかバンバン飛ぶし、展開や振付なんか、すごく面白い。踊りというのは一番何でもできちゃう世界だと思うんですよ。何でもありというか、順序をバンバン飛ばしてもいいし、さかさまにしてもいい。それが演劇になると起承転結とか、時間の流れもコーズアンド エフェクト(cause and effect<原因と結果>)と言って、こうなったからこうという、理由と結果、ロジックがあって、そのために時間が流れて究極の方向にもっていくわけですが、踊りって、もっとこう時間の観念が広いんですよ。最近のコンテンポラリィダンスなんか、歌もあるし話もあるし、踊らなくてもいいし、枠がバンバン広がっているから、そういうところから見ると、お能の自由さというか作り方が見ていて面白い。そこが一番面白いところかもしれない。
粟谷 今、能の中におけるスピードというような文章を書いているんだけれど(このホームページの切戸口のコーナー参照)。能で場面転換する場合、たとえば『是界』という能で、初めにシテが「これは大唐の天狗の首領是界坊にて候」と名乗って、これから日本に行き仏法を妨げると謡います。「名にし負う豊葦原の国津神・・」の道行を謡い終わると「急ぎ候ほどに、日本に着きて候」と忽ち日本に着いてしまう。観る人は、この言葉を聞いて、日本に着いたと日本を想像しないと始まらない訳です。場面転換の動きとしては、右に向いて2、3足出て、右足をかけ2,3足で元の座に戻るだけで「急ぎ候ほどに・・・」ですから、「さっき居たところと何ら変わらないじゃない」と言われると、返す言葉がなく、困るのですが。言葉の展開で、さっきは中国で今は日本の愛宕山としてしまうあたり、かなり大胆ですよね。そういうことは他ではないのでは…。芝居ではガラガラと舞台を回わして場面を換える手段が生まれる。そういう意味では能というのはすごく斬新。私は、能というものを考え出した戯曲家たちのセンスに感心してしまいます。能のように観客が頭を働かして場面転換をイメージするのと、映画や普通のお芝居のように、場面をすべて与えてくれるものとの違いですよね。どちらがいいという話ではなくて、そういう違いの面白さが、私もだんだん分かってきたんです。伝統芸能には文楽もあるね。文楽はどう?
余越 文楽は観ていて勉強になりますね。人形には感情がないじゃないですか。それなのに文楽で観ていると何であんなに感情が出るかというと、人形使いの思いを込めているというのはあるだろうけれど、どこか動きの正確さだと思うんですよ。泣くときの手や顔の角度がとても正確で、間の取り方もよくて、観ている私たちもウォーオー(泣く感じ)となる。運動学的な正確さで、ドラマを創り出しているという意味で、文楽は面白いと思う。だから役者だって、感情を込めれば悲しみが表現されると思うかもしれないけれど、動きの正確さの方がすごく大切、気持ちを込めると同じくらい、あるいは、それよりもっと大切。体の動かし方とか傾き方なんかがね。文楽を観ていて思うんです。
粟谷 文楽、人形浄瑠璃の方には、この角度でなければ絶対駄目というものがあると思うね。それは生身じゃないから。能にはシオリという泣く型がありますが、基本ラインはありますが、演者で手の角度や位置など少しづつ違うのですよ。私は形の整い方も大事ですが、それよりあの型をしたら泣いているのだなと自然に感じさせるエネルギーみたいなものが、役者の中にふつふつと沸いてこないと本当はいけないのではないかな。これは泣く型だから、と精神性がなくて型をなぞっただけではいけないと思いはじめたのです。
余越 型は記号になっている。
粟谷 戯曲の基本、土台がしっかりしているということはすごくいいことなのですが、そこに胡座をかいていてはねー。シカケ、ヒラキが立派にできれば充分でしょう、と演ずる気持ちが空虚ではね。型を越えた演劇性が重要じゃないかな。それは師から習うものとはまた別なところで習得しなくてはいけないと思いますよ。いろいろな他の物、他流の舞台を見る、聞くことも大事だと思いますがね。
余越 他のものをですか?
粟谷 そう。シテ方は五流あるけれど、父から聞いた話ですが、昔はよそ様のものを見たり聞いたりすることはあまりない、なんていう時代だったようですよ。
余越 えーっ、信じられない。
粟谷 そういうものだからこそ、それぞれの流儀は影響を受けずに今日まで伝承されてきたのかもしれませんね。金春流を拝見するとそう思いますよ。
余越 聞いてはいけないというのは、影響を受けると汚れるからということなんですか。自分が持っているものを侵されるということなんですか。
粟谷 そうでしょうね、多分。今は変わってきたと思いますよ。
余越 じゃ、最近の能全体を見て、革新的な能楽師とか戯曲家が出てきた時期とか、そういう人はいるのですか。
粟谷 何人かはいらっしゃると思いますが、少ないでしょうね。やはり一番は観世寿夫という人じゃないですか。世阿弥と同じぐらいの価値観だといわれますね、私もそう思います。
余越 何を変えたのですか。
粟谷 世阿弥が書いた『花伝書』を見直され、能を演劇的に演技者の立場で研鑽された方です。
余越 『花伝書』、読んでいるかもしれないな・・・。
粟谷 昔の能楽師は読んでいなかったようです。
余越 彼がそれをイントロデュース(紹介)したというか。
粟谷 『花伝書』が世に出たのは近年なのですよ。
余越 ああ、そうか。バレエの世界で、今世紀に一番影響を与えた人というのは、ジョージ バランチンという人なんですけれど・・・。
粟谷 その人はどこの国の人?
余越 ロシア人です。もう死んじゃったけれど。男の人です。アメリカに渡ってニューヨークシティバレエ団を作った人です。新しい美意識とか美感覚をバレエの世界に紹介した人です。すごく革新的だったのです。何でかって言うと、彼はそれまであった、ロシアバレエというか、フランスバレエの物語性を取ってしまった。バレエの世界では、王子様と王女様が出てきて愛し合ってとか、白鳥の湖とか眠れる森の美女とかジゼルとかあるじゃないですか、そういうお話を語るための踊りだったものを、そのお話を取って、動きというものと音楽にフォーカスしたのですね。物語性をはぎ取って、バレエを全く違う表現にした・・・。
粟谷 それはトウシューズをはいてやるわけ?
余越 もちろんそうなんだけれど、ゴテゴテしたコスチュームを取っちゃって、ただのお稽古着みたいな、タイツとレオタード(肌着みたいなもの)を着て、体のラインを全部見せる。だからジョージ・バランチンというのはガリガリに痩せた、お乳もぺちゃんこの、ストーンとした人の方がラインが出せるからと、そういう人を採用したんです。それで音楽に乗せて振付をするんだけれど、これは聞いた話だけれど、楽曲のドラマ的なピークを捜して、そこから遡って作っていくから、音楽の構造をそのままビジュアルに見えるようなバレエを作るというもので、アメリカの新しい人たちに熱狂的に受け入れられたんです。おそらく他のいろいろな芸術方面にもすごい影響を与えた・・・。
粟谷 いつ亡くなったの?
余越 もう、15?20年くらい前・・・。
粟谷 その方、いくつぐらいまでやっておられてのだろう。バレエと老いが結びつかないのだけれど。
余越 老いても目が利きますから。この人は役者じゃない、振付一本みたいな。
粟谷 でも昔はやっていたのでしょ。
余越 昔はね。でも早めにやめて。作る人というのは、本当に作りたい人というのは、自分がやらない方がつくりやすいのではないでしょうか。お能は全然違うでしょうけど。
粟谷 能は能役者が演出家でもなければならないからね。そこが面白いのさ。でも、あなたのコンテンポラリーダンスというのは、自分で作って自分で動かなければならないのでしょ。それは能に近いのではないかな。
余越 私のやっているのはそうですよ。もちろんダンサーを見て、こうやってああやってと作っていく作品もあるんですけれど、私は作り始めて、まだベイビーというか、4作か5作目だから、新人だから、まだですけど。それから私は動きのコンビネーションとかは余り興味がないんですよ。だからす
ごく派手に動いて、いろいろな構想のステップで見せてというのは余り好きじゃなくて、そういうタイプの振付師ではないんです。
粟谷 能は役に立ちましたかね。
余越 お能ですか、・・・歌舞伎と全く違うから面白い。
粟谷 日舞もやっているよね。
余越 日舞とも全く違う。日舞もなかなか面白い、お能も面白い。
粟谷 能の方が、原始的じゃないかと思うのですが。
余越 ウーン、そんなことない。
粟谷 作られた時代が古いからね。
余越 お能の方が、抽象的だから新しい!
粟谷 日本人の感覚として、抽象的なものの方が先ですからね。
余越 そうか!
粟谷 神楽とか民族芸能とか、クルクル回るだけみたいなものが舞の原点と言われている。
余越 ウーン、それは西洋的な考え方とは違っている! 西洋で教育を受けているとアブストラクトなものが前衛という感じがある。ロバート・ウイルソンという人知っていますか。オペラの演出を書いている世界的にも有名な人。超有名な人ですね。その人がおそらく禅とかお能に興味を持っていて、西洋人として、そういうものを概念的に舞台芸術に表現できた人なんです。その作品がいいか悪いかは別にしてね。その人がやったことというのは、その人の出世作は、アインシュタイン オン ザ ビーチというもので、大きな10メートルぐらいの蛍光灯のようなものをゆっくり倒していき、15分ぐらい、延々とお客はそれをじっと見ているんですよ。そのバックにフィリップ・グラスという現代音楽をかけて、ラリラリラリ・・・というすごくシンプルな音楽。無を見るのね。無のあり方というか。西洋がお能とか禅を見たときに、アブストラクトに、新しいという風に感じるんです。そこに抽象的な、斬新さを見たというか。私のやっているコンテンポラリィダンスはモダンダンスから派生したもんだけれど、最初は感情を出すのに内面の形象化を掲げたんです。ここにこうたまっている感情をこういう動きで出すのだという・・・50年代からやっている。ところが、マース カニングハムという人がそんなものはいらない、動きに意味づけをするのは全然つまらんと。動きは単なる動きではないかということで。その次にもっと若手の振付家たちが、ポストモダンを提唱した。モダンダンスのポストだから、その先っちょね。60年代から70年代ぐらいです。その人たちはスニーカーを履いたりして歩くとか走るとかして、ジェスチャーで意味もなく動く、それで動きを作り出すんです。だから抽象的になればなるほど新しくなっていった・・・という感覚が私にはあるんですよ。だから、私はお能を観たとき、ここまで斬新で新しいものは!と思ったもの。影響を受けていますよ。
粟谷 能は最初からその舞台装置を必要としなかった。抽象化の極致だよね。
余越 それはなぜ?
粟谷 日本人の感覚には抽象的なものが入っているのではないかな。色即是空、空即是色という言葉があるように、あることが無いことで無いことがあることというような東洋的な考え方がある。狂言の野村万之丞さんが、狂言は生きていこうとする、生きることに焦点があるのに対して、能は死というものを見つめて、死をテーマにしているとお話していたが、言い当てていますね。翁と脇能を除けば、死というテーマ、我々が絶対避けられない、重くのしかかってくるものをテーマにしています。だから、20歳そこそこで完成した演技を求めるのは難しいでしょう。
余越 死というよりもどちらかというと老いなんじゃないですか。
粟谷 老いだね。老いるということだね。
余越 私、年をとった人の舞台を見るの好きです。マースカニングハムという振付家の踊り手としての舞台は素晴らしいです。年とっていて、ほとんど動けないのだけど。舞踏の大野一雄さん、彼なんかもすごい、切符取れないもの。彼を見るために世界中の人が切符を取ろうとするんです。こういった舞台は特殊ですけどね。私、思うんですけれど、スペインで闘牛を見たときに、牛を殺すわけですが、これが美しいんですよね、すごい。死の儀式をパーフォーマンスにしてしまう、それでマタドー(闘牛士)とかも超格好いい、すごいセクシー。動きが決まっていますよね、とどめを刺すときとか。コスチュームも動きも全部踊りみたいになっているから、それはショーなんですよね。死をパフォーマンスにしてエンターテーメントにして見せるのね。私は見ていてすごいなと思ったんだけれど、死というのはすごくエキサイティングなのね。
粟谷 能の場合は死じゃないね。あなたが言ったように老いだね。滅びの美学というか・・・。
余越 滅びの美しさだと思う。
粟谷 死を見つめるとか、老いとか、そういうものを能はテーマにしているんだね。
余越 私、白洲正子さんの本、どんな本だったか忘れたけれど、お能というのは5つか6つの動詞があって、それをやると序破急になるんだという文章があって、そのところだけ利用して踊りの動きを作ったことがあるんですよ。その言葉、動詞というのは、落ちるとか寄るとか、滅びる、整えるだったかな。とにかく彼女が言うところの能に必須のいくつかの動詞があるんですよ。それらを組み合わせて序破急ができると。その考え方を創作に利用してみた。ダンサーは言葉を与えられて、動きを作る、フレーズを作ったりしますからね。これは面白いプロセスだなと思って作ってみたのです。とてもおもしろい動きがでてくる。あんまりおもしろいので、じゃあ、自分で勝手に好きな動詞を持ってきて、たとえば、開けるとか閉じるとかというのを足していったら面白いかなと思ってやってみたら、全く面白くないんです。彼女が言った動詞だけ、その言葉だけの動きで一番面白いものができる、すごい力だなと思った。おそらくお能の中に、ある世界、クオリティなのか質的なもなのか知らないですけど、何か確固とした弦のようなものがあるんですね。いろいろな言葉で時間をかけて実験的にやってみたけれど、白洲さんの言う言葉のすごさが手に取るように分かった。あ、すごいなっと思って、忘れられない言葉になった。コンテンポラリィの人は、たとえばインドネシアだと、伝統芸能を小さい子に教えるんですよね。そして、その後に伝統芸能をやる人とコンテンポラリィをやる人とに分かれていくんです。日本はそういうのはないじゃないですか。コンテンポラリィはコンテンポラリィ、伝統は伝統で動かないというか、西洋から来るものと伝統はバシッバシッと分かれている。
粟谷 最近それが見直されて、小中学生に邦楽を教える、義務教育に入れていく動きになっているけれど。それで私も、能を小中学生に触れてもらおうといろいろ活動をやっているのです。西洋から来るものと日本のもの、伝統芸能など、両方知ったうえで、分かれていくのがいいのだろうね、あなたの言うインドネシアみたいに。今日はいろいろ面白い話をありがとうございました。
我流『年来稽古条々』(3)投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
我流『年来稽古条々』(3)
── 子方から青年期 ──
粟谷能夫
粟谷明生
明生─ 少し話が前後しますが、初シテについても触れておきたいと思います。私は八歳で『猩々』でしたが、その時のことを思い出すとどうも、特別その為の稽古が長く続いたという記憶はなく、それまでの中之舞の稽古が出来たから、ではその続きでというふうに教えられたように思います。自然の流れで出来たという感じかな。特に覚えていることと言えば、実先生から鏡の間の前で「明坊ここに座るんだよ」と言われたことで、どんなに沢山子方を勤めていても鏡の間で床几に座るということはなかったですから、その時はちょっと偉くなった気分で、結構気持ち良かったことを覚えています。しかし当日どのように舞台を勤めたかはあまり思い出せないです。たぶん全く無意識というか、プレッシャーも何もなかったんじゃないですか。
能夫─ 僕は『経政』で九歳だったけど、中村町の実先生の舞台で一緒になって、まさに手を取り足を取りお稽古を受けたことを憶えている。この時の舞台は宮島の厳島神社で、役へのプレッシャーと旅の疲れとでやはり熱をだしてしまい、熱をおして勤めた記憶がある。いまでも宮島の野外の舞台の感じを憶えているな。一カ月後には東京の昔の目黒の舞台でやり、二回晴れの舞台を勤めさせてもらい、シテをやる豊かさ喜びを教えてもらいました。多分父親も初シテは『経政』で宮島だったんだろうけど、今にして親の想いと配慮を感じます。
明生─ 初シテを勤めて感じたことは、シテは幕が開き、歩み始めたら留拍子を踏むまでずーっと動き放しなんだということ。子方ならば普通要所要所の動きがあっても大半は相手役としてじっと座っていることが多く、このずーっと動くという経験は初めてで、結構喜んでいたみたいです。
能夫─ まあそういう意味では親の段取り通り育てられたと言うことかな。
明生─ 子方時代後半から青年期にかけては、いわば半端な時期に入るのですが、この頃は前にもお話ししたように、謡の理論が解らないとか、声の問題とか、このままこの職業をやっていくのかとか、様々な問題にぶつかり、悩んだりしていましたが、とにかく、やるやらない、好き嫌いに関係なく、十番会という稽古会が毎月あり、月に一番ずつ、とにかく覚えて、大人と一緒に舞囃子の稽古を受けさせて頂いたわけですが、この時期に舞の基本を徹底的に教え込まれたことは今の自分に大変役に立っていますし、自信にもつながりますね。表舞台には立てないけれども、このように継続していくということが大事なのかもしれません。地味な時期ですが、大切な時期でもあるようです。やはり誰かの段取りにはまっていたのかなー。
能夫─ 初めて面をかけたのもこの頃かな。『田村』のシテだったと思うけど、特別なプレッシャーがあるという感じではなかった。仕舞のままで面をかけたというか、普段稽古している姿にたまたま面と装束とが付いたという感じ。
明生─ 私は青年喜多会での『嵐山』のツレ、勝手明神で初めてかけました。やはり本番でいきなりという感じでしたが、プレッシャーなんか無かったです。ただ視界が制限されて見えにくいので、お相手の方と揃っているかどうかだけが不安でした。
お囃子のホウホウヒのヒで足を揃えるとか、何々という言葉で動き出すとか、非常に細かく型を決めさせられたのはこの時が初めてです。それまでの子方では、ある程度自由に一人で演ずることができましたが、ツレ同士、念入りに打ち合わせをして舞台に臨むという経験は初めてでしたね。
その面をかけるための準備で、面当てをつけたり、面紐つけたりで、例えば面紐を通すときもいいかげんにつけていると、「耳のあるものは内側から、耳のないものは外側から通すんだ」とか、「小面の面紐は紫色を使うのだー」などと楽屋の現場で廻りの先輩がいろいろと教えて下さるということもこの時期から始まったんじゃないかな。
能夫─ 僕は面を見ながら育ったから、かえって無意識だが、面を大事にするとか、彩色の部分には触れないとか、自然に身についてきたように思う。なにせうちの父は面を手に入れて来て、それをかけたまま眠ってしまって、母がそれを見て仰天したという逸話が我が家にはある位でね。子供の頃から面にはなじんでいたし、また女面には興味と憧れをもっていたように思う。ただその頃は般若が女だとは全く知らなかった。やはり、今頃になってああ恐ろしい、やっぱりそうなのかと理解できた(笑い)。
明生─ 面の話で、子方の最初の頃『船弁慶』をやっていて、後シテの気迫と凄さに、思わず本当に切られてしまうのではなんて思ったことがありました。その時の面が怪士だか三日月だかわからなかったですが、終わった後にその面を見て、こいつが僕のことをびっくりさせたのか、でもそのうち僕がこれをつけてやるからな、なんて思ってましたよ。
能夫─ 面をかけた最初の『田村』の舞台写真を見て悲しいのは、面装束をつけている姿がだらしないというのか、ともかく貧相でしょうがない。こんなはずはないと思うけどやっぱり身体としても大人になっていないことと、同時に芸としても構えが未熟なせいと両方あるんだろうな。
それからこの時期、後見をやらされたことを記憶している。十五、六歳だったろうか地謡にも付けられない半端な年頃だったと思うけど、足が痛いななんて思いながら座っていた。その頃で忘れられないのは、『土蜘蛛』で舞台の蜘蛛の糸を巻き取ったり、切ったりの始末をして、後で叱られた。多分やるタイミングとかやり方が舞台にそぐわなかったのだろうけど。その時舞台での動きというものは簡単には出来ないのだと思い知らされた。また実先生と一緒に塩津さんの『吉野静』の後見をしていて、塩津さんが途中で胸が苦しいと実先生に訴えて、先生が「いつでも俺が代わってやるから」といっていらしたのを覚えている。今にして思えば、舞台の善し悪しもよく解っていない時期に、ともかく舞台に居させることで、後見の位置とか覚悟のありようを教わったのだろうと思う。
明生─ 私はその頃からよそ見の時期が続いて、この世界に何となく魅力を感じなくなって、後で聞くと廻りの人は相当心配していたみたいですね。
能夫─ その頃は僕らも苦労したよ。明生君が能の方を向かないものだから、食べ物処とか飲み屋に誘って何とかこっちを向くようにと努力した。
明生─ 無駄のないまっすぐなコースを通るのが良いのでしょうが、右や左とよそ見をしては、他のことに気持ちがいってしまう時期を経験した私は、かえってその分、これだというものにぶつかったとき、その反動で、がむしゃらに没頭できたし、またその頃自分の流儀に疑問を感じていたことが、他流の同世代の人達の舞台を見ることにつながり、他流の友達との交流が出来大いに刺激を受けることができました。それが今日の自分に繋がっていると思います。
能夫─ 確かに自分の流儀の枠のなかで自足していては駄目だよな。僕の場合は観世寿夫の能と出会って以来、もっと能のことをかんがえましょうと言い続けて来たからね。その頃かな十番会で『采女』の舞囃子をやったとき、親父から「能夫はもう出来上がった。私の手を離れた」と実先生が言われたと聞いた。この頃寿夫さんとの出会いがあって自分の能の方向を模索していた。
(つづく)
対談 禅宗などから 松下宗柏氏との対談 その1投稿日:2018-06-07
 対談 禅宗などから
対談 禅宗などから
能には命の高揚があるのですね
粟谷 明生
松下 宗柏
臨済宗の機関紙『法光』で「能の楽しみについて」記事にしたいということで、私(粟谷明生)のお弟子さんでもあり、臨済宗の僧侶でいらっしゃる松下宗柏氏と対談を致しました。能は宗教がベースになっていることもあり、宗教的、哲学的な話は興味深く、松下氏の軽妙な語り口に乗せられ、話は縦横無尽、とどまるところを知らぬこととなりました。
第1回目
謡の中の余白と間
松下 今日は、能の楽しみとか見どころとか、能にまつわるいろいろなお話を聞かせていただきたいと思います。
粟谷 どのようなことから入りましょうか。私が松下さんから教えて頂きたいことは、禅宗を始め、能が影響を受けている宗教的なものです。能はベースに、天台密教から始まって、浄土教とか、時宗や、いろいろありますね。特に禅宗は禅の心や考え方が深く入っています。観世銕之亟静雪先生も禅の力とか、余白や間、余白と抑制など本に書かれています。
松下 禅宗の教えでは、間との関係でいえば、呼吸とか息づかいに注目していますよね。私たちには動きの中の工夫「動中の工夫は静中に優ること百千億倍す」という言葉があるのですが、機(はたらき)として禅の心を表すということがあります。
粟谷 私どもも、呼吸とか間が大切で、例えば謡では「間が無く、矢継ぎ早に謡ってはいけない」、間とか空白があって、はじめて広がりのある謡が生きてくるのだと言います。単にだらだらと、また妙に詰まったように謡うのではなく発声とか言葉、謡の中にある種(たね)みたいなエキスをしっかり、とらえていなければならないのです。発声のことでは、世阿弥が書いています、「一調二機三声」。まず自分で調子をつかんで、次に機、機というのは気をためて、チャンスとか機会をねらってとかいう意味で、このような過程を経て初めて声が出るのだと。だから、何となく「あ」という声(音)が出るのではなくて、発する前にいろいろな意識が働き、作業が起こり、最後に「あ」という声が出るのだと。きちんとした呼吸法も意識していないといけないのです。このことがうまくできて謡われている方の謡を聴くとその舞台や演者に引き込まれていきますね。よい謡をする方はよい呼吸をなさっている、聞いていて安心ですよ。間があっても妙に焦れなくていいし…。それが、呼吸に問題があると、「あれー、絶句したのかな」と思ってしまうし、間を掌握できていないな、と感じてしまいますね。これらは余白とか抑制という言葉に関係していて、観世銕之亟先生の言葉は本当に説得力あると思いますね。
松下 世阿弥は何処でそういうことを言っておられるのですか。
粟谷 『花鏡』ですね。世阿弥は花伝書といわれる『風姿花伝』という最初に書いたものと、その後、晩年にかけて書いたものと少し変化してくるのです、どちらかというとおもしろいのは晩年に書かれたもので…。それはそうですよね。多くの経験を積んだ後に書いたものの方が面白いのは。お稽古を始めたばかりの初心者の方には「一調二機三声」などと言われてもピンとこなく、わからないでしょうが、稽古していくと徐々に、こういう言葉の説得力が判るようになりますよ。私、お聞きしたいのは、謡と読経の違いみたいなものなのですが…。
松下 そうですね、謡と読経の違い…。お稽古で、謡い方ではお腹から出すものと鼻から出すものとがあると教えていただきました。引く息もあるとも。
粟谷 人それぞれのやり方がありますが、自分の声質を上手に使って声を出す工夫ですね。松下さんの場合は鼻音というか、多分読経の系統のお声ですと、どちらかというと腹が三分で、残り七分は鼻を通しての声ではないかなと、そんな感じがしましてね。
松下 初めのころ、私の謡曲はお経みたいだと言われ、「これは褒め言葉じゃないですよ、良くないです」とおっしゃいましたが、それはどういうことなのでしょうね。
粟谷 失礼な事申し上げましてすいません、お詫びいたします。読経のことをよく知らないで申し上げるのは失礼にあたりますが、お許し下さい。私は読経が抑揚がなく、上り下がりが少なく平坦に聞こえるのですが…。
松下 そうですか。
粟谷 そちらは「いいえ、ちゃんと抑揚がありますよ」とおっしゃるかもしれませんが。現代の謡曲、私のまわりで聞いている範囲ですが…。平坦な音のつながりを嫌う…。
松下 お経は、同じ調子を続けていくというのが、ある意味では心に影響を与える力といおうか、打楽器みたいな効果があるのです。
粟谷 そうですね。謡の中ではそういうことはあまりやらないのです。たとえば役として巫女がお祈りをするときや祝詞を読むときは、鼓はポンポンと同じ調子でノットという手組みを打つ、こういうやり方でテンションを上げることはありますが、謡ではこの方法をとらない。うちの父はこういう謡を「雨だれ謡」といって、ぽたぽたと同じノリで謡うのを固く戒めていますよ。
松下 雨だれ謡ですか。それはお経ですわ(笑い)。天台宗の比叡山でやるのは、朝法華に夕阿弥陀といって、夕方の四時から五時ぐらいに勤める晩課で読む阿弥陀経は、御霊を鎮める、まさに雨だれですよ。心を鎮めるようにね。
粟谷 それは宗教的には一つの効果があると思うのですが、謡としては、してはいけないと。抑揚が大事でね。基本的にはすべてのものが序破急理論ですよ。序があり破があって急となる。導入、展開、解決ですね。
松下 変化ですね。
粟谷 ええ。大きいものから段々小さくなっていくとか、その逆でもいいのですが、とにかく変化と流れがないと…。謡も同じで、口を開け謡い始めてから謡い終わるまで同じ速度ではなく、段々速くなっていくとか。それが、そ・も・そ・も・こ・れ・は・な・に・な・に・と、同じスピードで謡われるとね。
松下 それは私ですな(笑い)。
粟谷 「そもそもこれは、花月と申す者なり」と謡うとき、「そもそも」というのが序で謡い出しですから、謡い出すまでに高さ、調子、といろいろ考えて、先ほどの一調二機三声理論でいうと、「そ」をどういう音で出すかというのを考えるのです。そしていつ謡うかですね。能の場合では、お囃子があるわけですから、例えば小鼓の鳴らした音を合図に、さあ謡うとなるわけです。
松下 第一声が非常に大事ということですね。
粟谷 どのように声を出すかが大事で、そのときなおかつ、大きいふくらみがあって、段々ゆっくりした序から破でちょっとスピードが加わっていく、そしてどんどん速くなり急になる。つまり「そもそもこれは花月と申す」と水が上から下まで流れる感じで。そして流れる最後は落下の法則でスピードが速くなっていくと…。同じように流れるのではなくて、時間が経った後の方、水の落ちる早さは速くなるでしょ。それはすべての場合に当てはまります。謡でも舞でもそうですね。ごくまれに例外もありますが。私はそう心がけています。
松下 謡にも舞にも序・破・急というのが出てくる?
粟谷 そうです。三番目物になって『定家』とか『野宮』『井筒』になると、非常に密度が濃くなって、動きもゆったりしてきますが、でも同じことで、舞いという動きの中にもゆっくりとしたところと、中ぐらいのところ、そして少し速いところと微妙な変化があるはずですね。
松下 濃縮した感じ。
粟谷 そう。だから基本的に、底流に流れているものは同じ。序破急。
松下 序破急。確かに序破急があってはお経にはなりませんね。
粟谷 能には訴えかけがある。お経は同じリズムで心を鎮めるもの…。
松下 そういうものでないといけないのですよ。
粟谷 そこがちょっと違うかな、というのはありますね。
松下 命の高揚、変化を映し出すのがお能なのですね。
我流『年来稽古条々』(4)投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
我流『年来稽古条々』(4)
── 子方から青年期・その二 ──
粟谷能夫
粟谷明生
明生─ 今回は少し元に戻るかもしれませんが、十番会の頃の話から始めたいと思います。私にとっては前回も述べたように十番会という稽古会で先輩に混じって必ず月に一番ずつ舞うことが出来たことは大変幸せな事でした。十二才頃から実先生がそのときの力量、稽古課程に合わせて曲を決めて下さいまして、会が終わると次は何かなとお聞きするのが楽しみでした。そしてその選曲も舞い物等はやはり舞働、カケリ、中の舞あたりから始まり徐々に男舞、神舞、そして神楽、楽へと順序よく進むわけです。
ある時こんな事がありました。稽古で笛を森田流にしていましたら本番では一噌流だったのでびっくりしたことがありました。森田と一噌では唱歌や寸法が違うので型や拍子の踏み方も変わってきます。それはどなたがお相手なのかを予め知ることが大事であると気を付けるようになりました。
能夫─ 僕にとっての十番会の意味は普段の稽古で身につけてきたものを、舞台で実践することで段々と囃子との折合や曲の位取りなどが解って来たこと。それから囃子方との出会いがあったということ。同世代だと国川純さんとか小寺佐七さん、大先輩だと敷村鉄雄さん。彼らから囃子方の思いや考え方、他流のこと等、外の世界のことを学んだ。その頃よく敷村さんがご自分の流儀の観世流小鼓のことを、人知れず咲く深山の桜、また幸流の小鼓のことを、華やかな門前の桜だと言ってらした。
初めは先輩について地謡を謡うことで色々な事を身に付けていったが、先輩たちが次々と卒業して行くと、自分で責任をもって創っていかなければいけないという自覚が出来てき、次の世代の事も考えるようになっていった。
明生─ 私は能夫さんと六つ違いですから私が十番会に入った頃は皆大先輩ばかりで、私が一番下、お囃子の方も同世代の人間はほとんどいなかったので少し寂しかったです。この時期の十番会、養成会で舞歌の舞の方は自分なりにしっかりたたき込まれた感じがするのですが、歌の方となると、謡本は理解できないし、声は出なく音も定まらないからどうも好きになれなく疎かになる。声の出し方については野放し状態で、指導された覚えはなく、このことが後で謡で苦労することになりました。
能夫─ 喜多流の人は仕舞は確りしているのに、能になるとどうして駄目なんだろうと、他流の能も見ている人に言われたことはすごいカルチャーショックだった。そうした外からの意見や、地謡も含めた舞台づくりの大事さ、といったことは他流の能を見たり、人に出会わないとなかなか解らない。
明生─ 他流の人たちとの交流については、これからも度々話が出ることになるでしょうけど。
能夫─ 中学生の頃、太鼓の稽古をしていて、なかなか理解できなかったことに”見計らい”ということがある。大まかな決まりがあって、演技や謡の状況によって色々と変化する。いわば能の醍醐味、本質と言って良い程のことだが、それが段々と見えてきた。自分にとっての大きな進歩だと思う。
明生─ 見計らいは本当に難しいです。私も太鼓は中学に入ると始めましたが、やはり拍子に合わずの所で見計らい乍打つのが難しいです。最初の頃は謡で覚えず、、刻いくつで上げてなんて覚えていましたから全然だめでした。太鼓とか小鼓とか音の鳴る物は習っていても楽しいです。どうするとよく鳴るのかと考えたりして。
能夫─ 見計らうということは謡も囃子も知ってその上での自由さというものだとすると、これが自在に出来るというのは生涯の課題なんだろうけど、ともかくそういうことがあるという事を思い知らされた。
それにしても最近若い人で舞のアトのアゲの謡い出しが、とんでもないところから謡い出したのがいたけど、あれも考えられないことだ。囃子というのは手組は知らなくても、さあ謡いなさいと誘ってくれるんだから、アンテナをひろげていれば自然に謡えるはずだと思うんだけど…。
明生─ 例えば望月の羯鼓の後に子方が『獅子團乱旋は時を知る』と謡い出すところがありますが、子方にさあ謡えという気迫でお囃子が囃しますし、そのような仕組みになっているので、それを受けてあっここだなと思って謡い出すことが出来る。
能夫─ そこで躊躇したら駄目なんだ。謡い出す勇気と決断が必要なんだ。
明生─ 子供の頃より舞台にたてる、いわゆる家の子というものの功罪は相半ばするとは思いますが、同期の人が少なかった事もあって、十番会のほか能楽養成会、東西合同養成会にもよく出させて頂きました。これらの会は他流との立ち会いみたいなものですから自然と心構えもいつもとは違って異常な緊張もしますが首尾良くいくと自信というか度胸みたいなものが生まれるみたいです。失敗するとかなり落ち込む。一回花月の能の時絶句してしまい、今でも覚えていますが次の日もう父がその話を知っていて、ああいう会では絶対に間違えてはだめだと大層おこられました。
能夫─ 振り返ると、良くも悪くも自分のなかに粟谷の子だというプライドのようなものがあったな。それが隠れ蓑になっていたかも知れない。でも、いろんな人や舞台との出会いのなかで、外の世界が、先の先があるということを思い知った。
大事なことはあくまで個から始まるのであって、個が十全になってはじめて家を支えることが出来るんだと自覚するようになって来た。
(つづく)
対談 禅宗などから 松下宗柏氏との対談 その2投稿日:2018-06-07
対談 禅宗などから
能には命の高揚があるのですね
粟谷 明生
松下 宗柏
 臨済宗の機関紙『法光』で「能の楽しみについて」記事にしたいということで、私(粟谷明生)のお弟子さんでもあり、臨済宗の僧侶でいらっしゃる松下宗柏氏と対談を致しました。能は宗教がベースになっていることもあり、宗教的、哲学的な話は興味深く、松下氏の軽妙な語り口に乗せられ、話は縦横無尽、とどまるところを知らぬこととなりました。
臨済宗の機関紙『法光』で「能の楽しみについて」記事にしたいということで、私(粟谷明生)のお弟子さんでもあり、臨済宗の僧侶でいらっしゃる松下宗柏氏と対談を致しました。能は宗教がベースになっていることもあり、宗教的、哲学的な話は興味深く、松下氏の軽妙な語り口に乗せられ、話は縦横無尽、とどまるところを知らぬこととなりました。
第2回目
死者たちの思いを代弁する
粟谷 能は、朝に演ずる、翁付脇能という神様を主体にしたものは別ですが、ほとんどの曲は死者というか、死んだ人間を題材にしていて、シテは死んだ人間の霊であったり、怨霊であったりするわけです。武蔵坊弁慶というその物語の中では生きている人であっても、もうこの世にいないわけで、我々からすると遠い昔の人です。それが仮の姿というか、役者の体を通して舞台に出てくるわけです。我々能役者は、その人たちの訴えかけ、何かの思いの代弁者というわけです。能という戯曲を創った人間は多分そういう思いで創っていると思うのです。というのは、当時の世相にも関係してきまして。観阿弥、世阿弥が生きた室町という時代は太平の世に思えるかもしれませんが、すぐ応仁の乱はあるし、飢饉はあり、六条河原には飢えで死んでいった人々がたくさん倒れていた。盗賊はいるし、ちょっとしたすきに子供はさらわれるし、人買いにとられてしまうという時代です。そういう時代の苦悩が背景にありますので、戯曲家にはそれらは意識しなくても影響は大であったと思われるし、そこを書いているのですね。観ている人間もそれが身近であったから、娯楽として観ると同時にその下部にある怨霊や霊の強い訴えかけを今の人間よりもっと身近に感じていたのではないかと思いますね。
松下 その時代は神がかりする人とか、死者と交流するというか、感応道交する人が、今よりはたくさんいたのじゃないですかね。
粟谷 そうでしょうね。
松下 今はそういう力が落ちてきている。文明とか何だとかで。当時は日常的に死んだ人とか霊とか神様が降りてくる人というのがいたのだと思いますね。
粟谷 室町時代の能が創造されていた時代にはキリスト教の影響を受けるまで行かず、能は仏教、神道の影響がほとんどだと思うのです。能は死者からの訴えかけがあるというのは、仏教の影響、仏教色が濃いからではないでしょうか。
松下 ええ。仏教の言葉を使っていると同時に、日本の古代から持っているある魂の力というか。呪術性というか。たとえば『黒塚』で天台宗の山伏が祈るのですけれど、呪術的な力が実際にあったと思うのですね。その怨霊退治とか生霊退治ということにおいてね。我々はいかにもフィクションの世界のように見てしまうのですが、当時は、実際そういうものが現実としてあったのだと思う。
粟谷 そうだと思いますよ。
松下 時代の問題でしょ。そういうような力が封鎖されてきたのは。江戸時代、世の中が安定してきて中央集権的な社会が、そういうものを全部封じ込める時代です。室町時代というのは、そういうものが自由に動いていた時代だったのでしょう。
能面も創作から模写へと変遷
粟谷 室町が日本的な文化が一番自由に咲いていた時代ですよね。
松下 まだ鋳型にはまっていない時代でもあるし。
粟谷 お花にしてもお茶にしても絵画でも、その後に段々と型にはまって、がんじがらめになっていくというか。能面でも、観阿弥、世阿弥の時代の面打師のものは創作なわけですよ。だから面の創作では第一期の般若坊とか三光坊という人たちが、たとえば般若坊なら、女の怨念を持った顔、憎しみを持った顔をどうしようかとずっと考えて、あの面を創るわけですよ。創作ですよね。もともとベースになるものがあるわけではありませんから。その創作意欲、創作の力というのが、第一期の面打師にはあった。すごいものだと思いますよ。
松下 感性は鋭かったのでしょうね。
粟谷 小面だって、龍右衛門という人の小面がすばらしいですよね。私は実は少しクラシックな感じがしますが……、いやー、とにかくすごいのは確か。その後、第二期になると、コピーの時代が始まるのです。模写の時代ですね。
松下 それはいつごろですか。
粟谷 江戸に入ると。
松下 江戸時代に入るとそうなる?
粟谷 そうですね。
松下 赤鶴(しゃくつる)という名をよく聞きますが。
粟谷 赤鶴は古いですよ。ベシミとか、要するに強い表情の面を得意とする。
松下 面というのは鑑定書みたいなのはあるのですか。どういう風にして面打師の名前がわかるのですか。
粟谷 名前は裏に書いてありますよ。鑑定とかそういうことになると能面コレクターの世界になりますが、私たちにとっては物が良ければいいのですよ。ただ、第一期の人たちのは創ろうとする意識がすごく強いじゃないですか。眉間に皺を寄せて男の苦悩の顔というので中将ができたわけで。中将は在中将業平の顔を想像し打って、中将と名づけたと。業平の歌舞の菩薩の姿を打ったと言われますね…。男の悩み、業平の苦悩を打ったわけですよ。だけどその後になると、できたものをその通りに忠実にコピーするものに変化してくるのです。この時期も大変なものですけどね。
松下 違う才能ですね。
粟谷 全く同じものを作らないといけないという。これ以降は模写の時代になっていく。そうすると段々と創作意欲が希薄になって、力がなくなっていくわけですね。で、今は…。この間『殺生石』女体をやりましたが、あれは前シテ も後シテも両方とも創作面です。
松下 創作面。昭和の平成の?
粟谷 最近、岩崎久人さんが打たれたものです。岩崎さんが玉藻の前をイメージして打っておられた創作面を銀座の展示会で拝見して、いつか『殺生石』の「女体」をするときには是非お借りしたいと思っていたのです。本来は我が家にある面、家には古い面がありますから、それを使えばよいのですが、ある時はそういう新しいものを使うのも良いと。新しくてもダメなものはダメですけれども、使えるものはどんどん舞台に生かしていきたいなと思って。結果が悪ければその面はダメの烙印が押されますし、役者もその面を選んだことで少し負を背負わなければなりませんが、この曲はこの面と決まっているからつけているということだけに拘っていると、模写の時代の面打師と同じようになる気がしましてね。
松下 同じことですね。
粟谷 意欲みたいなものがなくなってきて、この装束とこの面をつければそれなりになる、そういう風に教わっているから仕様がない、なんていうことになってくる。まー、怠け者と言われても、しょうがないですよ。それでは観ている人に失礼でしょ、観客は悲劇ですよ。
面、装束選び
松下 装束や面の選び方はおシテがある程度できるのですか。
粟谷 若いときはそれほどに自由にできません。修業中の身では、まず基本形というか、長年こういう風にやってきたという一つのパターンがあるわけですから。その基盤は崩さない方がいいと思いますけれど。
松下 装束も決まっているのですか?
粟谷 だいたい決まっています。ただそのときに、たとえば袴を、浅黄色にするか、萌黄色にする、茶色にするかは自由であったりするわけですよ。唐織を着ると書いてある場合でも柄はどうするか、例えばいくつか唐織があるけれどもどれにするかといったことは、本来シテが選ぶべきですね。
松下 スタイリストみたいな人がいるわけじゃないのですね。
粟谷 本来スタイリストは自分でなければいけないのですよ。子供のころは、親や師が見立てます。これとこれがいいとか、ましてや小さい子はこれしかないからという風に着せられますけれども。青年になると、修業の身だったら、先生に「お前はこれを着ればいい」といわれますが、そういうものを卒業していって自立したときは、たとえば着たいと思う装束の持ち主のところに行って、頭を下げ、実は扇面模様(せんめんもよう)の唐織でやりたいのでお貸し頂きたいというぐらいの意識がないといけないと思いますね。いつまでも他人任せでは一人前の能役者とは言えない気がしますが。
松下 それも一つの創作活動ですね。
粟谷 その辺から始まるということはありますね。あまり新しい物でなくて、もうちょっとくすんだ物にしようとか、どういう色のどういうものを着るかから始まって、こういう風に謡ってこのように舞うまで、自分で考える。どちらが先ということはないですけれども。
松下 おシテさんはおシテさんの、自分のことで、他のワキの方はワキの方で決めるのですか?
粟谷 そうです。
松下 自分のことは自分で決めるということですね。
粟谷 そうです。ただツレ役で、シテがこれを着るから、ツレはこれを着てくれよと言うことはありますが、ワキや狂言の方には口ははさみません。別世界です。それぞれが決めていますね。
松下 舞台は相まみえてですね。
粟谷 そうです。あまり色が同じにならないようにという配慮はしますが。たとえば、おじいさん役をやるときに水衣を着ますが、だいたい茶色っぽい物になる。ワキの僧も茶色の僧衣になって似てしまいます。全く同じ色の物が舞台に並ぶのはおかしいですから、濃い色ですかと伺って、それじゃ私は薄い色にしましょうと、お脇は色を変えたりして下さいます。
我流『年来稽古条々』(5)投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
我流『年来稽古条々』(5)
── 青年期・その一 ──
粟谷能夫
粟谷明生
明生─ この『我流・年来稽古条々』も今回で五回目になります。一、二回目は「子方時代」。三、四回目は「子方時代から青年期」と進んできました。
先回は十番会で学んだことを中心に話しをすすめました。今回からは「青年期」ということで、「青年喜多会」のことからはじめたいと思います。もちろん十番会と重なる時期でもあり、どうしても時間は前後することにはなるでしょうが。
能夫─ 「青年喜多会」の頃の記憶で忘れ難いことに、千番仕舞があった。夏休みの一月程の間に、千番の仕舞を六人か七人ぐらいでやるんだから、これは大変な負荷だった。一人で一日五番ぐらいは舞わなくちゃならない。それが一月続く。毎日なにをやるか前以て決めてるわけじゃなく、同じ曲はできないので、ひとに先にやられたら大変だった。謡う方は謡本を見てもいいんだけど、どんどん謡わなくちゃならない。僕のように通いで実先生の所にいっていた者にとっては、朝から晩まで毎日稽古すると言うのは凄いことだった。本当に充電期間だったと思う。今やあんな稽古はあり得ないと思うな。実先生としては、まずは曲を覚えて何でも出来るようにということだったんだろうな。自主稽古だから先生はいないので、その日やった仕舞をノートにつけて、先生の所に持っていってチェックをうける。例えば『国栖』とか『七騎落』だったりするとこんなものじゃ稽古にならないとお叱りをうけてね。ともかく鍛えられたね。
明生─ その千番仕舞とは少し違いますが、私も覚えているのは、先輩が能の稽古を受けられた後、実先生が他の者全員、地謡の私達まで仕舞の稽古をみてくださったことです。稽古順は年上の人からですので当然私は最後の方でやることになるのですが、誰が決めたのか、暗黙の了解というか、一度出た曲は後の人はできず、違う曲目をやらなくてはいけないわけです。若い頃はレパートリーも少ないので自分のできるものを、先輩がやらないように、やらないようにと祈ってましたよ。祈りが通じないで自分が覚えているものを先にやられてしまうと、もうしょうがない、うろ覚えの自信のないのをすることになってしまいます。そうするとやはり間違えますので忽ちお叱りを受けました。
またその稽古で、地謡を謡う時、シテが謡い始めているのに何の曲だかわからず、それがわかって謡本を必死になってひろげた時はもう終わりの方なんていうこともありました。
能夫─ 稽古は厳しいけれど教えられる事が多かったね、それと「青年喜多会」というのは「喜多会」に入れない若者の順番待ちみたいなところもあったよね。僕が入ったのは中学生の頃で、その頃は四番だてで年四回やっていたからね、ともかく友枝昭世さんから明生君ぐらいの世代までいたからね。だから一番多いときは十数人いたと思う。先輩たちが「喜多会」に出演するようになって自動的に「青年喜多会」を退会するということだったと思う。
その頃は舞う番数も少なくて、十番会(稽古能)で一番、青年喜多会で一番だけで、うちの粟谷能の会でそろそろ一番舞えるかどうかという頃だった。本当に舞いたくてしょうがない頃で、何で親は自分たちのことを考えてくれないのかと思っていたし、このままでどうなるんだろうと不安だった。
いま考えれば未熟だったんだから仕方ないけど、ともかくハングリーだった。
明生─ 私が「青年喜多会」に入れて頂いたのは十七歳の高校生の時で、最初は『小鍛冶』でした。その頃は四番だてで一年に二回の催しでした。私の出番は大島政允さんの『雲雀山』の次の留めで、随分年上の先輩と一緒に出来るんだなーと思いました。私にとっては同人の会というものは初めてで、それぞれの人が会計、交渉と、各分野に分かれて動いていて、舞台の他に色々と大変で忙しいという事を知りました。
また子方時代には無かった切符の負担もあって、シテはいくら、ツレはいくら等と請求され、同人組織の在り方を知る最初でした。切符を売ることの大変さもこのあたりからです。当時は自分では売れないので、ツレ役なら自腹を切ってもいいと勝手に思い、家に切符を持ち帰らないでいましたら、父に早く持って来なくてはだめじゃないか、売れないじゃないか、と叱られました。父としては少しでもお弟子さんにチケットを渡して、息子たちの能を見て貰いたいという考えだったんでしょうけどね……。
能夫─ 確かにその頃はチケットは売れないし、自分が憧れているような曲は、なかなかつかないしね、切能が続くことも多かった。
だから初めて『羽衣』がついたときは本当にうれしかったね。小面がかけられると思って感動した。実先生にお稽古していただいて、自分自身も一生懸命稽古したことを覚えている。それと家の装束の中から自分の好みの腰巻と長絹を出してもらった。
明生─ これと思う曲がつくと感動しますよね。最初、随分年上の方と一緒だったのですが、その方々も徐々に卒業されて、最後(昭和五十六年)には私と中村邦生さん、長島茂君の三人だけとなり、催しも年に一回の形になりました。それが六年も続いたんです。
でも最後は忘れもしないあの番組ですよ。実先生の奥様が「先生!果水会の番組じゃございませんのよ、青年喜多会ですよ。」とおっしゃっても、「うん、いいんだ、頼政、葛城、山姥だ」と言ってやらせて下さった番組。青年喜多会らしからぬ曲立てだったわけですが、これは実に思い出に残っています。これで実先生にお稽古を受けた青年喜多会というものは一応終わることになるわけです。
その後、新しい青年喜多会ができて私も二年程おりましたが、後輩たちが自分たちだけで出来るようになったので、私は昭和六十三年に退会いたしました。
「青年喜多会」、それは三役の交渉に始まり、番組の印刷、出演料の計算や、お弁当の用意といった雑用まで様々のことを先輩から教わり、能会の仕組みや経営のことまでしっかり伝承されたという意味でも、良い場であったと思います。だから「青年喜多会」は自分たちの会だという意識が同人全員にすごく強くありましたね。
最後に三人だけになって、ほとんど休む暇がなくても苦にならなかったですし、先輩の方々も自分たちの育った青年喜多会ということでよく応援して下さいました。やりがいや、これからの目標というか方向性みたいなものを感じ始めた頃です。
能夫─ 僕らや明生君の代ぐらいまでが「青年喜多会」で実先生から稽古をつけてもらった最後の世代というわけだよね。「青年喜多会」といえば『玉鬘』の時に弱々しい謡をして、祖父のお弟子さんにそれは違うのではないかと指摘されて、涙ながらに抗議した記憶がある。
その頃は実先生の厳格な規範の枠とはちがったところで表現したいという意志もあったんだけど、やりたいやりたいという意識が先行し過ぎて、作品が深く読めなくて、情緒的な表現になりすぎていたんだと思うな。そうはいってもその所を通過したから初めてもう一つ先の世界が見えてきたんだと思う。つくづくいろんな出会いや人との出会いがなければ能は出来ないと痛感するよね。逆にいえば自分の世界の中にいただけでは駄目であって、自ら求めて先に行く必要がある。
明生─ 青年喜多会の終わった後の宴会で、その日一日の反省や舞台でのお互いの意見交換などをしていると頭に血が上ることもありますが、能とは関係ない話で終わってしまうようなときは少々物足りなく感じてしまいます。
能というものは舞ったあとに一杯やりながらいろいろと話し合いをすると、何か必ず新しい発見があるような気がしますし、またそれを見つけようとしないといけないと思います。
能夫─ 当初は私も含めて舞台にかけるところが終着駅で、あと反省するとかいう意識がとぼしく、とにかくやりっ放しということが多かった。そのことは確かに問題だったと思う。
「青年喜多会」の後の宴会で、先輩達の話を聞く事からはじまり、徐々に自分の意見を持つようになり、其の後、話し合える仲間ができ、機会を見つけては、能の話をするようになっていった。そういうことの積み重ねで強い連帯感が生まれ、新しい会へと発展していくのだと思うな。其の日一日の能に対し皆がしっかりした意見を持っているべきだと思う。
(つづく)
対談 禅宗などから 松下宗柏氏との対談 その3投稿日:2018-06-07
対談 禅宗などから
能には命の高揚があるのですね
粟谷 明生
松下 宗柏
臨済宗の機関紙『法光』で「能の楽しみについて」記事にしたいということで、私(粟谷明生)のお弟子さんでもあり、臨済宗の僧侶でいらっしゃる松下宗柏氏と対談を致しました。能は宗教がベースになっていることもあり、宗教的、哲学的な話は興味深く、松下氏の軽妙な語り口に乗せられ、話は縦横無尽、とどまるところを知らぬこととなりました。
第3回目
内面からの訴えかけ
松下 おシテをなさるとき、一曲一曲をどういう風に舞うかというイメージを自分なりに作っていくのですか。それともそういうものはない方がいいものなのですか。
粟谷 いや、イメージはあり、それが大切だと思いますよ。
松下 自分にとって、たとえば『敦盛』なら、どういう風に演じるかというのはあるのですか。
粟谷 ありますね。若いころはとにかく基本型をたたき込まれます。その次の段階での演能では前回よりステップアップしていかなければならないと思うのです。私は十九歳のときに『敦盛』を初めて勤めて、その後三十二歳、三十五歳と、計三回勤めていますが、それがみな同じようではまずいわけです。変わったのは髪の量と顔形だけではね。粟谷明生の演ずる敦盛が変わって行く…良い方向に成長していかなければならない。動き(型)はそんなに変わるわけではありませんから、謡にしても舞にしても、要するに密度を濃くする、内面からの力、訴えかけをすごく強くという…非常に難しく、お判りにくいかもかもしれませんが。そのために何をするか。たくさん稽古し研究して説得力ある謡い方をする。ただウワーッと謡うのではなくて、ボリュームは絞るけれども、中の芯は非常に硬くなる、硬質になるとか、女性をやる場合でも、艶のある謡い方もあるし、艶をちょっとそいだような謡い方もあるし、その辺はそれぞれ役者の生き様、やり方が出てくるのだと思います。私は演じ手の気の充実度が大きく影響してくると思うのです。演者の内向するエネルギー、それを身体にためる、そしてそれ自体を意識しないで舞台に立つということです。これはなかなか難しい課題でして、最初に溜めていないものはやはり空虚な芸になる。感動のない、それなりのつまらない舞台にね。
お能の女性はちょっと恐い
松下 男性役はいいとして、女性の役の場合は、女性の心を演ずるとかいろいろ難しいでしょ。
粟谷 女性だからといって、能は歌舞伎の女形みたいに演ずるわけではないですからね。お腹の底から強く男の声でウォーと謡うわけですが、技法として女性として聞こえる、または男っぽく、武士っぽくという区分けの工夫はされていますね。
松下 お能に出てくる女性というのは、嫉妬とか怒りとか恐い女性というイメージで、中にはかわいい、きれいという女性もいるのでしょうが、私がお稽古した数少ない曲で見ると『黒塚』とか『鉄輪』とか恐いでしょ。
粟谷 まあ、能の世界では幸せな女性というのは少ないでしょうね。
松下 この間の『通小町』で先生が演じた小町は、最初は幸せなのですかね。
粟谷 いやあ、小町ははじめから負を背負っています。
松下 でもきれいでしたね。かわいいイメージありますよ。何かほっとするというところがある。
粟谷 あれはどうか助けてといって、お僧のところに出てくるのです。
松下 けなげな感じがしましたけれどもね。
粟谷 迷われているというか、成仏できないでいるというか。
松下 お能というのは女人成仏を扱う。女性はもともと業が深いということで、迷ったり苦しんでいる人が多い。
粟谷 多いですね。だから法華経は受けますよね。女人成仏ですから。
松下 法華経ですね。苦しむのは女性という感じがね。
粟谷 昔の仏教の教えでは、女性であること自体が苦しみであるわけでしょう。だからそういうものが基盤にはなっていますよね。例えば『葛城』など、シテは女神であるのに「さなきだに女は五障の罪深き」と謡い、女性であるが故の、負を背負っていることの嘆きを言うわけですよ。
松下 もともと仏教には「女性は業が深い。男に生まれ変わらなければ成仏できない」とういうような説もありましたが、平安時代、最澄が「衆生本来仏なり」とする「法華経」を日本仏教の中心に据えたことによって、鎌倉、室町時代になると、だいぶ様子が変わりました。
粟谷 女人成仏の話は「法華経」のどこにあるのですか。
松下 「堤婆達多品」に「竜女成仏」という話があります。それに禅宗でよく読む「普門品」(観音経)には「観音菩薩は、婦女の身を現じて法を説きたまう」「童男童女の身を現じてときたまう」というふうに出ています。だから観音さまは人気がいい。
粟谷:そういえば『田村』『湯谷』など清水寺を舞台にした曲には、観音さまを讃える箇所がありますね。ところで、最澄以前には、「法華経」は伝わっていなかったのですか。
松下:奈良時代にも伝わっていて、「法華経」は女性のためのお経と言われていたみたいですよ。聖武天皇が全国に建てた国分尼寺は「法華滅罪寺」とも称されましたそうです。それを、最澄は仏教の中心に据えたというわけですね。
粟谷:これで、男も女も晴れて平等に成仏できるようになったというわけですね。
松下:それにしても、お能には悪女みたいな人が多いですよね。『道成寺』なんか、女性恐怖症になるような(笑い)。
粟谷 あれはまさに清姫の親、真砂庄司と、能では奥州白河の僧ですが安珍ですね。あの二人の責任。「あの男がおまえの亭主になる」と戯れ言を言い、安珍もその気になるような振る舞いをする、すると幼心に真と思ってしまう、娘を責められない、まわりがいけないのですよ。
松下 あの女性、追っかけてくるからね。やあ、これは昔も今も同じなのだと思いました(笑い)。
粟谷 恐ろしいけれど、作り話的なものではないでしょうね。現実にあったことをベースにしているのではないでしょうか。そういうものが多いですよね。ただ『羽衣』などは、羽衣伝説から作られているものですね。
松下 だいたいお能には現実の素材があるのですね。
粟谷 そう思いますね。
『羽衣』の二つの小書
松下 『羽衣』は、いいですね。
粟谷 『羽衣』はね、やっぱり。天女であって、神ではないわけでして。そこが私は面白いのですが…月の世界で神にお仕えしている位、というか身分。月の世界では、まだ位の低い方で、ちょっと下界に来て、水浴びして遊んでいるからたいへんな目に会うわけですよ。裸で、男に捕まっちゃう。
松下 そうそう(笑い)。
粟谷 そこで「あー私はなんていうことをしていたのかしら…、羽衣を取られてしまったという苦悩が始まる。そして下界で駿河舞を見せることによって、地上の世界に染まっていく。地上に未練というか、もうちょっといたいというような風情が生まれてくる。そういう演出はうちの流儀では「舞込」といった演出で、下界に未練を残しながらも時間が来たからと、回転しながら月世界に上っていくというパターンです。「霞留」という演出では、「白龍に約束の舞を見せたわ、やるべきことはやった、もう時間だから帰らなきゃ」と、最後は下界を見ないで、天、月の都だけを見てすーと消えていくというやり方なのです。
松下 同じ曲でも、演出によって違うのですね。
粟谷 そう解釈し、私は二つの小書を舞い分けています。小書がつかない普通の演出ですと、「霞にまぎれて失せにけり」と地謡が謡っているときに、まだシテはくるくる回りながら舞台にいるわけですよ。川柳で「失せにけり 幽霊いまだ 橋掛り」というのがあるくらいで、失せにけりと言いながらまだ舞台にいる、観ている人間はそこで消えたと思ってくれなきゃ困るという約束があるわけです。だけど、それならもうちょっとわかりやすくしよう、と別の手法でと、小書(特別演出)が生まれてくる。「霞にまぎれて失せにけり」と謡って、本当に天上界に消えていくようなやり方もいいのではないかというので、喜多流では「舞込」、舞ながら幕へ入り込んでいくというやり方ですね。「霞留」というのは「霞にまぎれて」と謡ったら「失せにけり」は謡わずにシーンとして、囃子だけが奏で、その間に幕の中にすーと入っていく。そこに残った、残像のようなものを楽しもうという手法です。「霞留」は、あなたへの約束は果たしました、ちょっと未練はあるけれど帰りますといってすーと消えていく、その辺のきれいさですね。「舞込」はなごり惜しいけれども、まだ何となく下界にいたいけれど・・・。
松下 情が移っているわけですね。
粟谷 そうそう。未練が残るような感じ。だからずっと白龍を、三保ノ松原を見、駿河湾を見、日本の国土をずっと見ながら消えていくという演出ですね。こういうところがお能の面白さ。演じ手にとっても面白いところなのですね。
松下 観客の方も、そういうものを感じるのが醍醐味になるわけですね。
粟谷 そうそう。感じる力がないとダメなのです。
能を「観る」ということ
粟谷 感じさせる力が演者にも必要だし、感じる観客の目も必要です。あまり能はサービスの行き届いた芸能じゃないといわれますから、一生懸命観る、想像するという世界ですからね。
松下 ある程度お能を楽しむのも、お能に対する嗜みがないとできないですね。
粟谷 そうですね。
松下 神通力で観るわけにいかない(笑い)。
粟谷 だから数多く観ろといいますよね。能はわかりません、と言われる方に、何番ご覧になったのか聞くと三番なんて。じゃ三十番観てください。それでもわからないなら三百番観てください、とね。
松下 同じ曲目のお能でも全然違いますものね。
粟谷 演者によって違うし、演者のコンデションによっても違いますからね。同じものはないわけで…、話が少し飛びますが、演じ手からすると、屋内か屋外でやるかでも違いますよ。自然を全く感じない屋内と、ときには電車の音が平気でしてきたり、風が起こったりする屋外とでは違いますから、演じ手もそこで変えなければいけないし、観ている側も変わらないといけないと思いますよ。
松下 舞台の状況によりますね。
粟谷 どちらにしろ、観るという想像力、自分の中に世界をつくるというのが必要なのですね。
松下 やっぱり、観ということですね。観能ともいいますが、その観という字、観世音菩薩の観で、見えないものを観るという。
粟谷 あーあ、なるほどね。だから、能を観るというとき、観るという字を使うのですね。
松下 それは非常に奥が深いですよ。自由にとらわれのない心で観るという。心で観る。心の目というか、心の耳というか。音なきもの、姿なきものをみるというときに、あの観るですから。ちょっと臭いけど、霊的なものを観ていく、お互いが感応道交していくという。そのときお互いも大事だと思うのですよね。観せてやろうと思うとダメでしょうね。お互い無我になったときが、観る側も無我、演じる側も無我というときに初めてすばらしい交流というか、出会いがあるというねえ。
粟谷 そうですね。それで無というのが全く無いということではなくて・・・。
松下 なくて、そう。
粟谷 非常にたくさんのものがあって、それでいてこうやって観せてやろうとかということがなくて…。これが相当難しいのですよ…。
型はからだについている
松下 仕舞なんかは、こうして、こう演じてというのはないのですか。私たち素人は四苦八苦しますが。
粟谷 我のまわりの玄人は型は間違えませんね、プロはね。謡は違うところ謡っちゃったとか、前に戻ってしまったなんてことは少しはありますけれど。
松下 お経といっしょだわあ(笑い)。一人がちょっと外したりすると…。似たようなのがあるのですよ。
粟谷 読経は本を読んでいるのですか。それとも暗記なのですか。
松下 長いものは見ることもありますが、普通は見ないのです。お謡もそうなのでしょうけれど、糸巻きをほどいていくように流れのなかで謡うわけでしょ。それが一つ間違う、一回違う方向に行くと、止まらなくなっちゃうのですね。
粟谷 謡では、たとえば上の句が同じで下の句が違うというのがありますからね。「さるにても慣れしままにていつしかに」『雲雀山』というのと「さるにてもなにのみききてはるばると」『桜川』というのがあるのですよ。これボーッとしていると違う言葉を謡ってしまうのです。
松下 ちょっと入るのね。
粟谷 その下の句について、次の人が謡うわけですから、よほど注意していないと、「今は昔に」と謡う所を「思い渡りし桜川の…」と謡って、あ…「これ違うよ!」、なんてことになってしまう。
松下 そうすると違う曲になってしまいますものね。
粟谷 そう、なってしまう。やはりたるんでいるとそうなってしまう。だから、間違ったときに「あっ、これ違う」と自分の頭のなかで正しい句を思って、次の言葉につなげていかないとね。言葉はつながって覚えていますから、前の言葉が違うと大変なのですよ。
松下 さっきのお仕舞ですけれど、曲目によっていろいろな組み合わせがあるのでしょうけれど、それをいちいち考えてやるわけじゃないのでしょ。
粟谷 それはやっぱり、体についていますけど。
松下 すごいですね。
粟谷 ただ、そこに意味合いみたいなものがあれば、心持ちを入れたりということはしますけど。次何だっけ、次はこうしてこうしてなんてことは、余りないですね。
松下 それは、一つの曲を何度も何度もなさるから入っているものなのですか。
粟谷 10代のときにたたき込まれているのと、あるパターンがありますからね。このパターンをこうしていけばいいんだなと。後は、どこに気持ちを持っていくか、どういう言葉のときにどうするかということで…。
松下 すごいですね。たくさんの舞台をこなされるわけですが、一曲一曲にすごく時間をかけて練習できないのではないかと思うのですけれど、よくこなされるなあと思って…。一回の演能では、いろいろの場合があるのでしょうが、余程詰めて練習をなさるものなのですか。
粟谷 大曲などは時間もかけ、詰めても稽古しますが、例えば『羽衣』を舞ってくださいと言われれば、それは今すぐにでも。稽古しなくてもできるものもあります。まああまり多くはないですがね(笑い)
松下 大曲というのはどんなものですか。
粟谷 修業過程の順でいえば喜多流では『猩々乱』『道成寺』『石橋』『翁』とか『望月』とか。私はまだできませんけれども、老女物、『卒都婆小町』『鸚鵡小町』や三老女の『檜垣』と、『伯母捨』など。老女物は別格ですね。安宅の関で勧進帳を読む『安宅』や『隅田川』という、子供を失って、京から関東まで女が訪ねてくる、実は一年前にその子は死んでいたという悲劇の能も、やはり大曲に入りますね。
松下 それで、人間の舞と神様の舞では違いますか。
粟谷 我々は役になるといっても神様になれるわけではないのでして、これはもう、脇能という形式、決まったパターンがあって、それを凛としてキッチリ舞うということでしかありません、あとは面や装束などいろいろなものが作用して補足してくれるのではないでしょうか。最初、子供のころは神様はやらせないのです。子供は純真だからよいように思えますが、やらせない。それは、翁をやった後に、脇能で尉姿としてシテをしなければならないという過程があるわけで、本来はね。この『翁』のシテはやはりある年齢を経た役者が出てこないと似合わないのです。尉というおじいさん役はやはり難しいですね。私は一番難しいのではないかと思っています。女流能楽師を私自身が認めにくいのは、この尉が女性では演じきれないというところに落ちるのが判るからなのです。
松下 神様という意識はそういうものなのですね。
粟谷 一応、あまり考え過ぎないことが第一かもしれませんね。それでできるのです。
松下 できるのですか。
粟谷 演者が勝手に演出できるようになっていないからです。言い方が乱暴かもしれませんが、形さえしっかり身に付ければ、結構できるのです。でもそれには徹底的な基本の修練が必要で、その上で単に意味もなく舞台上にいるだけなのに輝いて見えるとかその存在感の美というようなものが加わるのです。動きとしての型は非常に簡素な型の連続ですね。
松下 そういうすばらしいものがあるのですか。そういうのは口伝なのですか。
粟谷 口伝というか、盗む、いただいちゃうのですよ。先輩の演技を見ながらですね。指導者もある程度のところまでは教えられますが…、その後はもう全然教えない。懇切丁寧なんてことは若い人にだけですよ。
松下 どういうところで盗むのですか。
粟谷 見てです。
松下 舞台で?
粟谷 舞台で謡いながら見ていたり、楽屋裏から見ていたり… 。だからたくさん見ないと収穫が少ないのですよ。
松下 ボサッと見ていたらダメだなあ。
粟谷 ボサッとしていたらそのようなお能になる。世阿弥が、いいものを観ろと。そして悪いものも観ろと。悪いのもなぜ悪いかがわかっていいから観ろと言っているのですね。当然よいものは観なければいけませんが。
松下 私たちにお稽古をつけてくださって、それからご自分の舞台を勤められるというのは、時間の問題で、ご自身の稽古は丑三つ時にでも秘かになさっているのですか(笑い)。
粟谷 やるときはやりますけどね。その辺はプロですから。みなさんそうだと思いますよ。三日に一番ぐらいずつ舞台がある方に、うちの父が「いつお稽古をなさるのですか」と聞いたら「菊ちゃん、本番が稽古だよ」なんて言われたという話がありますけれど、そういう方は例外中の例外、特別ですね。私はまだそんなに多くないし、今ぐらいのペースはちょうどいいと思っています。
我流『年来稽古条々』(6)投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
我流『年来稽古条々』(6)
── 青年期・その二 ──
粟谷能夫
粟谷明生
明生─ 先回は「青年期」その一ということで「青年喜多会」のことを中心に話しましたが、その続きで、やはり時間は少し行ったり来たりするのですが、青年期の異流の人達との出合いについて話をすすめたいと思います。
能夫─ これまでも十番会の話の時に囃子方との出合いとか断片的には触れてきたけれど、やはり僕にとってもっとも大きな出合いは観世寿夫さんの能との出合いだった。
同世代である大鼓の国川純さんとの出合いがあって、そこから観世寿夫さんがすごいという話を聞かされた。それから銕仙会の浅井文義さんとの出合いがあって、お互いの能を見るようになり、当然のこととして浅井文義さんの師匠でもある観世寿夫さんの能も見るようになった。
最初に見たのは『花筺大返』とか『船橋』とかだったけれど、それは本当にショックだった。自分たちの流儀の内にだけいたら決して知ることのない様々なことを教えられた。
具体的には揚げ幕の揚げ方ひとつとっても、自分たちの流儀では無頓着で、働きの若者がともかく開けばいいといった感覚だったのが、曲目によって揚げ方が違うべきだし、その日の舞台全体を共に呼吸して、隅々まで目が配られている必要があるということを教えられた。
最近の若い人で幕が風を孕んで揚がる普通の揚げ方でなく、幕棒の上に乗せるような仕方で揚げる人がいるけど、あれは良くないと思う。
明生─ ホールでの能や、能楽堂によっては後ろに充分な空間がなくて、どうしても引いて揚げられない場合もありますが。
能夫─ 演出家の佐藤信さんと新作能『晶子みだれ髪』の仕事をしたときに佐藤さんが、幕が揚がると能舞台空間が幕の中の方へ動く、そのひけた空気を押し出しながら役者が登場するからいいんだといっておられたけれど、それは風を孕んで揚がったり降りたりすることで空間が動くんだと思う。後ろに引き揚げることで幕の内側(鏡の間)の方へ空気が動き、それを押し戻す態で役者が登場するという力学を見たのだろう。
幕のことだけではなく作り物を丁寧に作ること、きれいなボウジを使うことといった、当たり前のことが、舞台全体を成り立たせるために必要だということを学んだと思う。
それと、謡のこと、これはとても大きなことだった。
明生─ これまでも度々触れて来ましたが、うちの流儀は謡いに関しては、細やかな教え等がなかったから・・・。
能夫─ ともかくそうした出合いのなかでいろんなことを吸収して自分たちの流儀の中に生かしていきたいと思い努力して来たけれど、謡については抵抗も強かったな。
地取りの謡い方が曲目によって違うっていう、当たり前のことが充分に出来ていなかった。その曲が『井筒』だろうが『敦盛』だろうがお構いなしに謡っていた。それからサシ謡がひどかった。ともかくパターンで謡ってしまう。僕はこのことをさんざん言い続けてきたけれど、或る時、菊生伯父が実践してくれて、もっとサシ謡を大切に謡おうと皆に言ってくれたのは嬉しかった。ともかく銕仙会の能を見て、良いものを見せてもらったと思った。能でやっていける喜びをもって見た。
まあその頃はうちの親父や菊生伯父から、あいつは寿夫にかぶれていると言われていたけれど、親とか師匠のレプリカじゃしょうがないもの。それを一度否定するなかで自分は出発し、自己を発見しなきゃ駄目だと思う。親や師匠のいい子のままだと、その雛形になるだけで、何らかの意味で乗り越えて行くことは出来ない。とは言っても血はつながっているし、喜多流のDNAは受け継いでるわけだから、いつかそこに戻ってはいくけれど、決して同じものではない。
青年期に自分の能を模索している時、他流のそれも、能というものに志をもっている人と出合えたことは本当に大きなことだった。伝統という枠の中で安住していたら駄目だ、現代に生きている能役者が、現代に生きている人達に対して演じる現代劇としての能であるべきだと思った。
喜多流が型では一番だと思っていたけど寿夫さんの『野守』はすごかった。動きだけでも、とてもかなわないと思った。技術はすごい、テンションは高い、謡いもすごい、水道橋の一番後ろの席までバリバリと届いて来た。もっとすごいのは、金太郎飴じゃなかったこと。毎回違った舞台だったからね。
明生─ 私たちの世代で当時の仲間は、全く同年の生まれは、森常好さんと大倉正之助さんだけで、少し年上で武田孝史さん、年下に金春國和さん、野村耕介(現万之丞)さん、観世暁夫さん、亡くなった観世清顕さんたちがいます。
私たちはいわばジュニア仲間という感じがありました。親同士のおつき合いがあってということもあり。まあ飲んだり、麻雀したり、ゴルフとか、遊び仲間という側面が強かった。それと「やってられないよなー」って感じでシラケの世代でもありましたね。
能夫─ 僕たちは心配したよね、我々の後の世代はどうなるんだろうかって??。
明生─ でもその頃のつき合いが最後には実を結ぶのですが・・・。ただそれはだいぶ後になっての話です。いずれその時の頃の話になったら詳しく話そうとは思うんですが。自分の能が好きになって、仲間たちとも、もっと深く能についてつっ込んだ話をし、自分たちでどういうふうに能をやっていこうかということにもなり。ある時自分は『自然居士』をやることになっていて、話が進んでいく内に、じゃ、一緒に稽古をやろうよということになりました。
耕介君が萬舞台を貸してくれて、流儀の違う仲間が集まって稽古をした。常好君がワキを、耕介君がアイをやってくれて、観世暁夫ちゃんが地を謡ってくれた。佃さんがアシラッてくれました。それがされに『野守』の”居留”という小書をやる時、この仲間たちが助けてくれて稽古をしながら作っていきました。これは十年前の話しですから、その時にもっと詳しく話したいと思います。
でもあの頃は集まっては飲んでシラけて、くだまいていたんですけど・・・。
能夫─ 初めは皆そんなもんだよね・・・。
それと、これはちょっと違う話しだけれど、菊生伯父にすすめられてゴルフをやったのも大きかったな。そこで色んな先輩たちと能の仕事ということではなく、まあ遊びという側面からのつき合いが出来たことで、もう一つ幅が広がったように思う。
明生─ 「ノーテンクラブ」ですね。あれはうちの親父と、金春惣右衛門先生が言い出して出来たんです。
能夫─ まだゴルフが一般の人々の間でブームになるずっと以前のことだよね。
明生─ 金春先生の命で三島元太郎さんが庭に穴を掘って桃屋の瓶詰めの瓶を入れたりしてね。ボールが入ったら取れなくて、わりばしでボールをとっていたという話しはきいています。
能夫─ ホールの大きさもちゃんと知らなかった位の頃だからね。
僕が菊生伯父に誘われて入ったのが十八か十九才の頃でね、最近の能役者連中は車に乗っていてばかりで歩かないから駄目なんだと言われてね、実にありがたかった。
でも高橋先生がいくらグリーンの上を歩いたって駄目だ、板の間も歩かなくちゃ駄目だっておっしゃった、とかいう話しもあったりして、うちの親父や、友枝喜久夫先生なんかは「絶対にゴルフはしないでしょう」っていってたりした。でも僕にとっては囃子方の人や、他流の人とのつき合いが増えたというのは実りがあった。ともかく日頃近づきがたいと思っていた人の全く別の側面が見えたりするしね。なるほどこの人はこういう性格で、こんな風に能のことを考えているんだとかね、これは大きな発見だった。
明生─ 例えば他流の方や三役の方とまわらせて頂くと、大抵面白い話しが聞けますからね。能楽界の人間関係のありようが見えます。
能夫─ ゴルフをやったことで一つの世界がひらけたな。日頃こんちくしょうと思っていた人が、やっぱりちゃんと能のことを考えているんだなとか、偉そうにしている人にも、こんな弱点があるんだなとかね。ゲームをしていると、そうしたことが赤裸々になって来るじゃない。
明生─ 大先輩と一緒になることもあるんですよね。ハンディでパーティが決まってきますから、そこで色んなお話を伺えて興味深かった。それと恐ろしいのは舞台の間違いやトラブルがすぐゴルフ場での話題になってしまうこと・・・。
能夫─ 肉体を使うといっても能楽道でやっているのと違って外の良い空間と、グリーンに囲まれてゴルフをやると余分なことをすっかり忘れてリフレッシュもできた。
(つづく)
対談 禅宗などから 松下宗柏氏との対談 その4投稿日:2018-06-07
対談 禅宗などから
能には命の高揚があるのですね
粟谷 明生
松下 宗柏
臨済宗の機関紙『法光』で「能の楽しみについて」記事にしたいということで、私(粟谷明生)のお弟子さんでもあり、臨済宗の僧侶でいらっしゃる松下宗柏氏と対談を致しました。能は宗教がベースになっていることもあり、宗教的、哲学的な話は興味深く、松下氏の軽妙な語り口に乗せられ、話は縦横無尽、とどまるところを知らぬこととなりました。
第4回目
自分が演じる曲はみんな好きになる
松下 自分が好きな曲とか、出会いの曲というのはあるのですか。
粟谷、好きとか嫌いとかはあまり考えていませんね。自分がやるものが段々好きになってくるのですよ。役者というのはそうじゃないかな。というか、私はそうですね。
松下 演じてみて、入っていくわけだ。
粟谷 そうそう。気持ちが入っていくのですが、終わってしまうとケロッとして、もうお終いと言って次のものにかかっていくという…。私、四、五年前の研究公演に 『采女』(うねめ)という曲で「佐々浪之伝」という小書を創作というか掘り起こしたことがあるのですね。そのときは、もうこれ一番あれば今年一年はいいな、あとは何もしなくてもいいと思っていた…。
松下 充実していた?
粟谷 すごく充実していた。ところが終わって三日ぐらいしたら、もういいや、次はあれがある、あれをやらなきゃなんて思って、『采女』のことなどすっかり忘れてしまう。
松下 ウワー、それはすごいですね。
粟谷 あの『采女』勤めたときに、自分の取り組んだ作業を整理しておかなければいけないな、ただやりっぱなしではと思って、「演能レポート」というものを自分のために書くようになったのです。「佐々浪の伝」は自分なりの掘り起こし作業だったものだから、何らかの形で残しておきたい。文字にすれば残りますから。能、演劇は花火みたいなもので、一瞬でしょ。演じ終わったらもう何も残らないのですよ。それがよいところなのですが…。
松下 まさに一期一会ですね。
粟谷 ええ。でも、そうでない資料的なものはどうしても残したいし、自分がどういう気持ちでやったかを書きとめておきたいと思って書いているのですけれど。書くということは、すべての整理をしなければいけないし、そのとき自分がどんな状態にいたかがよくわかります。でもたいへんで、途中でやめようとも思ったのですけれど。
松下 自分をえぐるようなものですからね。
粟谷 そうなのです。でも最近は、何でも自分のためにやっているのです。
「活句」で謡う
松下 私たち臨済宗の場合は修業で公案というものを使うのですが…。
粟谷 公案というのは禅問答のことですか。
松下 そう禅問答。伝統の問題があって、それをお師匠さんが出してやるわけです。
粟谷 悟りとは何かとか。
松下 「如何なるかこれ仏」・・・という問いが多いのですが。 「如何なるか父母未生前の本来の面目」とか、決まったパターンがあるのです。いろいろなシチュエーションで。
粟谷 同じようなことを言っていてはダメなのでしょ。この間、梅原猛さんの『仏教の授業』という仏教について中学生に授業したものを再現している本を読んだのですが、面白かったですよ。出題者が「仏とは何ぞや」と聞くと、いろいろ答えていくのですが、ある僧が、「かんしけつ=くそかきべら」と言ったら、「お前、悟った」と言われて、その次のやつが、同じに答えたら「このやろう、落第だ」となったという。
松下 シチュエーションの中で、その物語の中で問題をどうとらえるか。あるときは鳥の声、自然の音だったり、あるときは働く姿だったり、答え方は問題によって違います。やるときは一生懸命集中しないと解けないようになっているのですよね。頭で考えていてもできなくて、あるときポカッと心が開けるというか解るときがあるのです。でも、その答えにいつまでも捉えられているとダメなのです。
粟谷 なるほど。
松下 同じ問題を一年後に出される。あれだなと思って、同じ答えをだしてもダメなのですね。それはもう死んでいる、鋳型にはまっている、生きた答えを持って来いと。私たちはそれを「活句」と言っているのです。それに対して反対は「死句」です。いつも「活句」、生命感があるものを答えとして持って来い。だから、伝統の模範解答みたいなものは一応あるのですが、それは一つの目安であって、それ自体を持って行ってもダメなのです。
粟谷 それは能にも使えますね。死句で謡っちゃつまんないわけ。活句で謡わなければダメだという感じですね。
松下 それは年々の花というか、その年、そのときの味で答えなければならないし、自分の生活体験とか、私たちは見解(けんげ)というのですが、それを活句で持って来いと、示せよということなのです。仕舞と同じで、思っているだけでなくて、それを示せとくるのです。
粟谷 表現しないといけないのですね。
松下 そうそう。たとえば「宇宙を動かしてみろ」と言ったときに、それを示せというの
ですね。そのときどうするかというと、歩いてみせたりしてね。
粟谷 ウーン。
松下 極端にいえばあくびをしてもいいのですよ。私は宇宙の命ですと言って、示せよと言ったときに、頭だけ、言葉だけではダメで、体で表現するのです。そういう風に活句を持ってくること、それにとらわれないことが大事なのです。だから、前のことを引きずって、その類推でやると、お師匠さんはそれは死んだものだみるわけですね。そうなるとなかなか通さない、「よし」と言わない。もっと練って持って来いとなるのです。
粟谷 我々の中でも死句で謡っている人がいるかもしれない。これからは、謡の中に活句みたいなものを…。
松下 そして変わっていくという。型とか基本はできていながらも。
粟谷 そう、強く訴えかけることが必要なのです。私はたれそれと言うとき、「そーもそも」と大きく謡うのと、ただボソボソと謡うのとでは違いますからね。
松下 そうですね。ただきれいに謡えばいい、きれいに舞えばいいというものではないようですね。
粟谷 そうなのです。謡も舞も中の方、内面、内側は非常に燃えていないとね。動き自体が非常に静かであってもですね…。逆に外の動きは大きいのに、中は何をやっているかわからない、中の方は死んでいるのではないか、と言われるのは未熟な芸ですね。
松下 お能の命という感じですかね。
粟谷 演者が何を思って、幕の内から何を運んでくるかですよ、その役を演じる心がないと…いけませんよね。我々、歩くことを運ぶと言うのですけれど、死者の思いを運んで来る、そういうものがあるのではと観世銕之亟先生はおっしゃっていましたね。公案といったことは、永平寺の方ではやらないのですか。
松下 永平寺さんは「只管打坐」で妄念を払い、ひたすら坐禅をするのです。しかしこれは非常に難しいことですよね。
粟谷 難しいですね。
松下 厳しい。本当に。曹洞宗から臨済宗の批判というのは、座禅そのものではなくて、何かのためにやっている、何かを解くためにやっているというものなのです。でも一回身心脱落し自我が抜けないと公案は解けないことになっているのですけれどね。分別心が抜けるという体験が大切で。
粟谷 禅的な考え方は面白いと思いますね。
松下 集中して表現するというところまでいくわけだから。禅と同じで、お能は感応道交というか見えないものとの交流というものがある世界だと思ってね。行者的なものを感じますよ。
我流『年来稽古条々』(7)投稿日:2018-06-07
粟谷能の会通信 阿吽
我流『年来稽古条々』(7)
── 青年期・その三 ──
『猩々乱』披きをめぐって
粟谷能夫
粟谷明生
明生─ 青年期も第三回になります。先回は、青年期でも他流の能との出会い、また三役の人達との交流などで青年時代、自分たちだけの世界から外に開かれていったことを中心に話しましたが、今回はそうした時期でも一つの大きな節目となった『乱』の披きを中心に話をしたいと思います。
能夫─ 喜多流の場合、古い人だと、『乱』か『翁』を披いてはじめて一人前という考え方があったから。まあいまは、『乱』という技術的集大成を経て内弟子時代を卒業で、いよいよ青年期の本当の能の修行の始まりになる、といったところだと思うけどね。近頃は、『翁』はなかなか機会がなくてやらない場合も多いので、喜多流自主公演能ではこれから毎年『翁』を出して、披く機会のなかった人にやってもらおうということを考えている。ともかくうちの『乱』 は異常なくらいに腰を落とした、きつい姿勢で曲の殆どを過ごすから、途中何度となく切れそうになるよ。妖精というよりは猩々という名の獣を見せるという感じでね。
明生─ 前に亀井兄弟会で他流の方がうちの『猩々乱』を見て「大変だねー」と言いながら、「これ何なんだよ」とも言っていましたからね。
能夫─ 僕にとっての『乱』はやっぱり憧れの曲だった。僕が披いたのは二十三才だったけど、その頃一生懸命修行をしていて、それがそれなりに認められて、そろそろ『乱』を披いたらとお声がかかったと記憶している。
明生─ 能夫さんが『乱』を披いたのは、まだ粟谷能の会が粟谷兄弟能といっていた時で、すごい番組でしたね。
初番『巻絹』がシテ辰三、ツレ明生、次が『小原御幸』でシテ新太郎、その次が『通小町』でシテ菊生、ツレ幸雄、最後に『猩々乱』の能夫ですから。父は『小原御幸』の地頭を勤め、続いてシテをやったんだから大変なものでした。
能夫─ いま思うとよくこんな番組が出来たよな。おじいちゃんの益二郎がいなくなって苦労したけれども、一門揃ってこうした催しが出来る喜びがあったんだろうな。
僕たちの世代のトップバッターだったということもあって、僕はしっかりやらなければという意識が強くあった。実際よく稽古したと思う。その頃は会も少なかったしね。曲のイメージがどうということでなく、ともかく技術の確立というか、型を忠実にやるということを考えていた。
足の筋肉が張って張ってしょうがないのでエアーサロンパスをかけて稽古したんだけど、それが汗でしみてね、えらく痛かったことが忘れられないな。
それからもう一つ忘れ難いのは、うちにある赤頭が大きくて重くて、そうでなくてもきついのに、より負荷がかかるのが嫌という思いもあって、よその家にある小さめの赤頭でやりたいと思っていた。そしたらある人に『猩々』というものは、ひきずるぐらいの大きな頭のほうが獣の感じが出るのではないかと言われた。そのとき自分の考えだけでなく、ほかにこういう考え方もあるなということを教えられた。それで結局うちの重い頭でやった。またその時、着付けについても注意を受けた。赤い着付けと青海波の着付けとがあるんだけど、僕は青海波のほうが上等だし、それでやりたいと思っていた。そうしたら普通の『猩々』と違って『乱』の時はすでに酔って出て来るのだから、着付けは赤でなけりゃならないと言われた。まあこの時は着付けは青海波のほうを使ったけど、そういうことを理解したうえで選ぶということの大切さを知った。
思い返して見ると、披きの時は技術の確立ということばかり考えていたけど、今なら喜多流としての規範を大切にしながら作品のイメージを表現する方法があるなと思うね。親父や友枝喜久夫先生は五十代でやっていましたからね。足腰が強いというか、強靭な体だったんだな。
明生─ 我々の世代はそうした先輩や親の世代と比べると確実に身体、特に足腰が弱ってきて来ていると思います。昔に比べ生活環境も変わった。直ぐに車に乗り、重い荷物は宅急便、階段は避けてエスカレーターですからね。ですからこれからの人は先人たちが六十代でやられた能を、もう五十代くらいで勤めないと、間に合わない。これからの能楽師の寿命は短くなると思いますよ。情けない話ですが・・・。
能夫─ そうだね。五十代から六十才位までだよね、心身共に一番充実した良い状態は。
明生─ その代わり昔の人が六十代でなければ知ることが出来なかったであろう情報を、五十代、四十代で手に入れる事も可能になったし、色々な手付けや資料、見ようと思えば、他流の能も沢山見ることが出来る。研究公演の第一回で、『弱法師』をやりたいと父に言いましたら「もっと後でいいよ」と言われました。「生意気だよ」とか「もう少し大人になって」、と言われるのは充分覚悟していたんですが、でもどうしても今これを習っておかないと、という危機感みたいなものがあって、二回目には父を説得してやらせてもらいましたけれども、大変勉強になりましたね。最近思うのですが、あまり大曲、難曲を大事にとっておきすぎるのではないかと。さあそろそろ許される歳だからと挑んでも、うまくいかない場合がある。許される時期というのがあるとするなら、その前にトライする。それは今の時代、おかしいことではなく必要な事だと思うんです。いやなのは上から降りてくる順番をただ待っていたり、人がやったから自分もやるという考え方に慣れすぎてくること。
能夫─ 明生君はこの研究公演の頃から能に自覚的になったね。毎回文章も書いたり、いわば明生君の能のストーリーが始まったような感じだった。
明生─ 私の『乱』は二十七才でしたが、その頃はあまり考えていませんでしたからね。
能夫─ 流れに身をまかせて、自分で漕いでなかった(笑い)。
明生─ 空舟(笑い)。当時一種の技術主義への反発がありまして、それでも私なりに『乱』に対して取り組んではいましたが、舞の前の「蘆の葉の笛を吹き」のところで長く足を上げなければならないところで、バランスを崩して足をおろしてしまいました。それが尾を引いて消極的になってしまって、失敗でしたね。夜の宴会は当時珍しかった海鮮料理で、活海老が老酒づけになるとき、跳ね上がる断末魔を皆で大騒ぎして、気を紛らわしていたのですが、最後に能夫さんに「もう一回やったほうがいいな」と言われ、心の痛手を負った一番ではありました。ただその苦い経験は、『道成寺』を披くステップになりました。
技術主義への反発ということを言いましたが、『乱』は技術の集大成といったところがあり、ハードな演技ですから、これを終えると一種の達成感がある。ただそれで終わってしまうことが問題です。そのままで『井筒』『野宮』が出来る訳ではない。能には身体を虐めるだけではない、いわば心を虐める曲目があるということを知る必要があるのです。
能夫─ そうだね。僕は『乱』をやったことによって、いただいたと思うことは、技術に邁進してやりきったということ。それを土台としてこの道に生かして行くには、その後に五年なり十年なり上乗せしていかなければ、心に叶う能はやれないということだ。ただやりましたとか、通過点という意識では駄目なんで、それからの自分の能を創っていくうえでの起爆剤になって欲しいんだよね。技術的に難しい曲があると同時に、それだけではすまない曲があるといったことを知ることでね。
(つづく)
対談 禅宗などから 松下宗柏氏との対談 その5投稿日:2018-06-07
対談 禅宗などから
能には命の高揚があるのですね
粟谷 明生
松下 宗柏
臨済宗の機関紙『法光』で「能の楽しみについて」記事にしたいということで、私(粟谷明生)のお弟子さんでもあり、臨済宗の僧侶でいらっしゃる松下宗柏氏と対談を致しました。能は宗教がベースになっていることもあり、宗教的、哲学的な話は興味深く、松下氏の軽妙な語り口に乗せられ、話は縦横無尽、とどまるところを知らぬこととなりました。
第5回目
喜多流の謡
松下 私は特に喜多流には行者的なものがあると感じるのです。お腹から大きい声を出すというのは、流儀の発声法、特徴なのですか。
粟谷 どこの流儀でもお腹から、というより身体全体ですかね、声を出していると思いますよ。
松下 喜多の謡はゾクゾクときますね。
粟谷 以前は観世 ウキウキ、喜多きばり過ぎと言われていたようですが。
松下 喜多に出会った人は、他の流儀を聞くと物足りなくなると聞きますが。
粟谷 それは喜多でも観世でも、人によるところがあるのではないですか。自分に馴れたものが良いというのは、人誰でもでね。
松下 それはあるかもしれないね。でも私は喜多、粟谷の謡は宗教的というか、やはり行者的な感じがするのですよ。
粟谷 行者的ね、祖父・益二郎は謡がうまかった人ですから、そういう系統のものはうちの父が受け継ぎ、能夫が受け継いで…ということかな。
松下 ある意味では体を使う謡い方というのは。行という、体、身を挺していろいろな経験を積んでいくのですが、その家風だなと思う。最近少しずつ感じるのですよ。
お能には気を感じる
松下 お能には直感的にものを見るというか、感応の仕方に気をみるというのか、気を感じるところがありますね。私の知人は剣道家なのですが、気迫というか気を感じるというところがあった。それに似ています。
粟谷 仕舞でも謡でも、ある程度順序や謡い方を覚えたら、次に気をかけるということがある。といっても妙にハッハッと表面に出すのではなくて、非常に内向するもので、そのとき顔はむしろ柔和になるのです。顔を硬直させいかにも頑張っています、なんていう顔をしている演者はまだあまり高いところにいないと思っています。逆にこれに騙される程度では見る目がないということでしょうか。ちょっと言い過ぎたかな…。
松下 柔らかくですね。坐禅でも、私たちは悟りを見性(けんしょう)というのです。自分の本性(ほんしょう)を発見するという意味です。それが近づいた人間というのは、全体の輪郭が柔らかく見えるのです。そして動きは軽く、綿みたいにフワーッと見えるときがよい状態なのです。自分ではわからないのですが。自覚されるのは、やたらと体が軽い、やたらと嬉しいというのかな。指導者が一番嫌うのは、裃を着たように、いかにも自分はやっていますというようなものね。
粟谷 ときにありがちですね。気をつけます…。私、太極拳を 習っているのですが、気功もやらされてね。結構ためになり、楽しんでいますが…。先程屋内と屋外の話がでましたけれど、屋内の場合は楽なのですよ。自分の内にこめた機、気迫を発散するときに、屋内なら壁のような最終ラインがあって、そこまで届けば良いのだなと…。ある限界みたいなものが生まれます。能楽堂ならば最後列に届かせる意識ですか…。ところが厳島神社の海に浮かんでいる舞台や大阪城広場などで演ずる場合、とことん広いので。向こうに山が見えたりして…。そこで充実、発散するのは骨が折れますよ。
松下 お能というのはもともと屋外ですよね。能舞台というのは。
粟谷 そうです。昔は松も鏡板もなかった。観阿弥、世阿弥のころはね。そういうものができてくるのは式楽になるもう少し前ぐらいでしょ。世阿弥が舞っていたころは、後ろの鏡板がなくて、ただ四本の柱があって舞台があって、橋掛りがある、いや橋掛りが無い場合もあったと聞いていますが。
松下 それから私には二人のお師家(しけ)さん、指導者がいたのですよ。一人は現役のバリバリ、六十歳ぐらいの人で、もう一人はご隠居さん、八十歳ぐらいですか。そのご隠居さん曰く「味噌の味噌臭きは上味噌にあらず、と言いますが…」、一回味噌臭くならないと臭いは抜けませんよ、と。だから、ある時期は臭くて臭くて、あるとき、それが抜ける人間と、いつまでもその臭さを引きずっていく人間が出てくるのです。まあでも一度徹底的に臭くならないと…。
粟谷 一度は臭くなる素材でないといけないわけですね。
松下 そうそう。発酵する人間でなければならないの。臭くなれっていうのですよ。集中してなり切れっ、らしくしろって。
『富士太鼓』にみる役者魂
松下 この間の『富士太鼓』。あれ、集中してなり切ったのですね。
粟谷 『富士太鼓』は現在物といいましてね。シテは死者ではないですよね。『安宅』の弁慶も『富士太鼓』妻にしても、シテは幽霊として出てくるわけではない、生きている人間を描いていますよね。そういうものを現在物というのですが、それはある程度、役者が役に乗り移るという作業をしなければならないのですよ。やり過ぎるといけないのですけれど。とくに直面物といって、面をかけない、顔自体が面であるというものは、顔にいろいろな表情を作ってはてはいけないのです。表情を作ってはいけない…、だけど全部抜けきると、あっ、「あれはまさに弁慶の顔だ」となるわけです。弁慶の顔をつくるわけではないけれども弁慶の顔に見えてくるという…。『富士太鼓』、現在物をするというのは、母親にならないといけないわけです。女というより母親になる。それでこの間は自分の子供が子方だったというのが助けになりました。彼に頑張ってもらわないとこの曲は成り立たないということを、彼もわかっているし、私自身も子方のときは子役がダメだったら台なしになると散々言われてきていますから、私がこうやってきたのだな、私が菊生で、尚生が明生だなと、四十年ぐらい前の世界が思い出せるのですね。最初の場面がやっぱり難しいですね。ある意味では生っぽくやらなければならないし、ある面ではお能の範囲に留まっていなければならない、そういうギリギリの結界みたいなところがある。よく14世六平太先生が言われたのは、芝居しちゃいけないけれど、芝居心がなければいけない、ということ。それと同じで、富士の妻でありながら、この子の母親であると同時に、自分は尚生の母親役を演じているという意識がありながら、また一方では意識しない心体の操作も同時に行っているということなのですが。
松下 『富士太鼓』では、先生、一皮も二皮もむけた感じがします。
粟谷 うまくむけた? 『富士太鼓』はよいタイミングだったし、責任持って自分の子供と勤めたという満足感はありました。それから挑み方というのかな。申合せのときに、尚生が戻ってきて「長いよ、足が痛いよ」というわけです。お稽古のときは、シテが楽(がく)という笛だけで舞う場面があるということは言っていない。ここでお父さんがドンドンと留拍子(とめびょうし)一曲の終わりを知らせる拍子のことですが、それがあったらお終まいだからと言ってあって、途中に二十分もの長い楽があるなどと教えないわけですよ。申合せのときはリハーサルですから当然やりますね。でそのときはたまたまビデオをまわしていたので見たら、彼は、そのところ微動だにしていないのです。普通、子供は全然動かないなんて無理ですし…。でも尚生は動いていない。
松下 辛抱強い子だね。
粟谷 あの子が動かないということが、私がへたなことはできないでしょということになり、精神的なバックとなりましたね。謡や型がある中で、あそこに居て、座った状態で微動だにしないというのは、一つの大事な通過点をクリアしたかなと。それはもう、修業みたいなもので、そちらと似ているところがあるのではないでしょうか。
松下 みんな、先生も、小さいときから修業していらっしゃるのですね。今日はよいお話をありがとうございました。
(平成14年3月 対談 記)
我流『年来稽古条々』(8)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(8)
粟谷新太郎から受けたもの
粟谷能夫 粟谷明生
明生─ 先回は青年期・その三として、『猩々乱』披きをめぐってーということで話しをしましたが、今回は昨年五月二十一日、粟谷新太郎伯父が他界いたしましたので、新太郎追悼号ということで、二人で粟谷新太郎の思い出として話しをしたいと思います。
能夫─ 父新太郎他界に際しましては多くの方々より様々な追悼のお言葉、お心遣いをいただき深く感謝致しております。本当に有難く心からお礼を申し上げます。
明生─ さて新太郎伯父の事で思い出すことは、私は実に多く伯父のもとでツレをさせて貰ったということです。前に年来稽古条々でも言いましたように、子方は百二十番勤め、最後に昭和四十三年『満仲』の幸壽の役で切られて子方卒業となりましたが、同じ年に直ぐ直面で新太郎伯父の『土蜘蛛』の胡蝶の役がつき、それからはずーとツレ街道です。『葵上』、『八島』、『鬼界島』、『求塚』などが多く、伯父のものは全部で四十番お相手しています。あの頃私はあまり能を面白く感じていなかったので、ただ言われた通りにしているだけ、という状況でしたが、や はり番数が多かった為か、あの時の経験や伯父などに注意されたことは大きな肥やしになって、今につながっていますね。舞台や作品に対しての理解なんて大袈裟なものではないのですが、でもなにか自然に知らず知らずに舞台で培われていたと思います。頭からではなく、とにかく身体で解ったという感じかな。
能夫─ まさにそういう風にして育てられたということだと思うよ。
明生─ 『葵上』のツレはそれこそ三十番勤め、そのうち十三番が伯父とです。なかには一日二番なんていう時もありました。秋の粟谷能の会で『葵上』を勤めまして、ツレの内田成信君に「あーだ、こーだ」と注意している自分が、実は伯父から言われたことと同じことを注意しているんだと気がついておかしくなりました。例えば「東屋の母屋の妻戸にいたれども」という謡をダラダラ謡うな、シテは「姿なければ問う人もなし」とかかって謡いたいから「いたれども」は謡をつめてとか、ツレはツレらしく、歩みも謡もサラリと邪魔せず引き立てると、伯父からの教えは結構身体にしっかりお注射されたみたいです。
能夫─ それは言葉の意味を大切にして謡えという意味だと思うけどね、言葉を生かせと・・。親父たちの世代はこういう理由だからこうして、という理路整然とした言い方はしないからね。
明生─ そう言われても解らなかったと思いますけどね。何せあの頃、中学時代はやる気のない時代でしたから。(笑)あと忘れられないのが、二十歳の時、喜多会で『砧』のツレがついた時です。その頃の私は山登りに夢中でして、型付通りに動いていればどうにかなるだろうと、その程度の考えでしたから、伯父はさぞ嘆いたと思いますよ。
能夫─ その時のことはよく憶えているな。親父が「これじゃ砧にならないよ」って言っていたのが、申合わせがあって、本番が終わって、結果的には「よくやってくれた」というか、丸だということになった。花丸じゃなかったかも知れないけれど…(笑)
明生─ 「大声出していいから、高い張った声で謡ってくれ、そうすると伯父ちゃんは助かるんだよ」って言われましたよ。伯父は大曲の『砧』を明生とやるのか、やれやれと思っていたでしょうね。あとで父から「今日はともかく謝らなくて済んだ」と言われましたから。でも今考えると喜多会の配役のつけ方もいいかげんでしたね。それとその頃は能夫さんはもうツレはいやだと言うので私の方にその役が回って来たということもあったと思います。
能夫─ 確かにそんなことを直訴したかも知れない。地謡というポジションに居て、シテとか地頭を感じたかったんだよ。
明生─ 『清経』『山姥』『景清』『江口』と伯父のお陰で、いろいろやらされ、長いこと座らされました。(笑)でも近頃、私にはそういう時期があったことが、一つの大きな財産になっているのだと感じています。ツレを演ずる心みたいなものを掴めた様な気がするのです。例えば『松風』。膨大な連吟、立ち居の心配り、ツレとしての立場の確立、シテヘの理解、これらが出来て始めてシテが出来るのです。だから逆に本当のツレはこのシテを経験せねば出来ないのかもしれないとさえ思います。ですから伯父には遅蒔きながら感謝しているんです。
能夫─ 親父のことで鮮烈に憶えているのは、僕はまだ二十歳前だったけど、親父が春秋会で『朝長』を披いた時のこと。これは稽古から申合わせ、本番とすべて鮮明に記憶にある。
明生─ 春秋会というのは、当時、喜多長世、節世両先生、友枝喜久夫先生、新太郎伯父、そして父菊生の五人の会の事ですね。
能夫─ 親父がほとんど裸に近い姿で『朝長』の稽古をするのに謡わされた。その頃だから十分にわかっていたとは思わないけど、ともかくリアルタイムで親父が『朝長』を創っていく過程をつぶさに見た。親父がふんばっている姿に肉体の力を感じた。古武士のような骨格の図太さ、勢いがあった。「朝長が膝の口をま深に射させて馬の太腹に射つけらるれば…」の所なんかあこがれたもの、かっこいいと思った。自分もやりたいと。前シテにあんな難しい語りがあるとは理解してなかった。現実の舞台に向かう過程を親父と一緒に歩んでいた。それから昨年、自分が『朝長』を披くまで、これは一連のものとしてつながっていると思う。その間に観世寿夫との出合いがあった。そういう外からの刺激の中で、自分の父とか流儀のあり方を見直す観点を持っていったのだと思う。『朝長』でもうひとつ忘れられないのは、寿夫さんが亡くなった二年ぐらい後の鋏仙会の定期公演で、喜多能楽堂で演られた山本順之さんの『朝長』。これはすごいと思った。地謡は野村四郎さん、浅見真州さんたちが謡っておられたけど、巨星亡き後、全員が一丸となって寿夫さんの残したものを受けとめ表現していこうという気迫を感じた。皆が創りあげてきたものの集大成だと思った。シテの順之さんもすごくて、シカケ一つとっても過不足なく作品を表現していて、そこには型を超越した世界があった。これだと僕は思った。それで、たしか十二月の公演だったけど、その前に囃子の会で順之さんが銕之亟さんから、「馬の太腹に射つけらるれぱ」の所で床几からずり落ちる型を直接教わっている所をまのあたりにしたしね。だから僕にとって『朝長』は親父のを見てすごいと思い、かつ負けるものかと思ったという出発から、寿夫さんとの出合いの中で、順之さんの舞台があり、それが自分の舞台とつながっている。舞台というものは、自分の番が廻って来ました、はいどうぞ、という訳にはいかない、その作品に対して思いを深めていってないとだめだと思う。
明生─ それから伯父の凄い事の一つに『葵上』の坪折にした唐織を「打乗せ隠れ行こうよ」で、さーっと脱いで被くという難しい動きがありますが、一度も失敗したことがないということです。
能夫─ 手が的確に脱ぐために丁度良いところを掴んで、それで思い切りよくいけたんだろうな。普通だと、ここまでやるとエレガントじゃないとか躊躇があったりするんだけど・・・
明生─ 失敗なしは本当に凄いことです。職人芸というんでしょうか。父に比べて決して器用な人ではなかったと思うんですが。とにかくうまかった。
能夫─ 『土蜘蛛』の投巣も見事だったね。それと謡にはうるさかったね。喜多流の趨勢として型を重視する傾向に対して、謡がちゃんと謡えないと駄目なんだと。地方稽古に行っても番謡を一日に三番も謡って決して手を抜かないというのか、そのせいで自分の能のときに声が出なかったりしたのを見ていて、はがゆい思いをしたこともある。晩年になって、型は少し枯れて来たという感じがあったけど、謡は良くも悪くも枯れるということがなかったように思うな。かえって言葉についてことさら強く謡ったりしていた。いずれ親子というのはどうしたって似ているところはあるし、また反発し合うこともあるし、いわく言い難い所が沢山あるからね。合せ鏡みたいで、お互いにピカピカ照らし合いながらお互いに馴れ合ったり、意地を張ったり、喧嘩したりして消耗するみたいな所もあるしね。だから僕にとっての親というのは、『朝長』のときに言ったように親から受け取ったものがまずあって、そうして自己形成していく過程で、自分の流儀という枠を越えた所での観世寿夫の能との出合いがあり、能に対する取り組み方や、細部にまで目が配られて能という演劇を成り立たせているといったことを教えられ、これらのことが自分の立地条件だと思った。そうした過程を経て、父の良さも、悪さもちゃんと見られるようになったと思う。前にもこの場で言ったけど、僕と父とはDNAはつながっているんだし、どっかで似て来るにちがいないんだけど、ただ自分の能が親の雛形に終わっては駄目なんだと思うな。
明生─ 私なんか伯父より、能夫さんとつきあう時間が長くなりましたから、能夫さんには新太郎伯父と違う価値観、美意識がはっきりあるんだと感じます。それでも、不思議に伯父が亡くなってから、能夫さんの面をつける時の、うけが前と違ってきて、どことなく伯父独特の少し顎を上げる感じ、癖がまるで魂が乗り移ったと思えるほど似てきたのは不思議。だから最近はそれを少し計算に入れて能夫さんの面のうけをみていますよ。
能夫─ それは自分で意識している訳じゃないんだけど、親子というものはそういうものかも知れない。そうでなくても我々親子はどことなく良く似ていると言われるしね。まだまだ話は尽きないけど、次の機会に譲りたいと思います
厳島神社/桃花祭の御神能投稿日:2018-06-07
厳島神社/桃花祭の御神能
粟谷 能夫
粟谷 明生
(21世紀最初の御神能ということで、今年平成13年は能夫が翁付『弓八幡』でシテ、明生がツレを勤めました。この度この御神能について、二人で語りあってみました。)
明生 4月16日に厳島神社の桃花祭・御神能で翁付『弓八幡』を勤めた感想を、まずは聞かせてください。
能夫 このところ靖国神社・夜桜能での友枝昭世さんの舞囃子『枕慈童』、松山道後温泉・大和屋の夜桜能と、屋外で演じるよさを感じているけれど、それらはみな夕方から夜にかけてなんだ。そこへいくと、厳島神社の御神能は朝の9時から‥‥、早起きするのは大変だが、すがすがしさはあるな。太陽が燦々と降り注ぐ中で演じる『翁』は絶品だと思う。
明生 本当にすがすがしさ、気持ち良さというのがありますね。厳島神社の桃花祭は文字通り桃の花のお祭りで、その中の行事の一つとして御神能があるわけですが、我々にとっては、4月16日が1年の節目で、お正月のような気分になります。
能夫 そうね。神事としてのお能を勤めることで、神にありがとうございますという1年の感謝をこめ、お正月を迎えるような気分になるね。
明生 毎年4月16日から3日間、形式は翁付五番立(今は3日目のみ翁付ではない)で、3日間の出し物は全部違う。五番の間に全て狂言が入りますから、朝から始まって夜まで、大変な時間がかかります。東京では年に1回、東京式能といって2月の第3日曜日に五番立を催していますが、ここの御神能ほど古い形式を守っているのはないでしょう。厳島神社は安芸国(広島県)の一の宮。平清盛が安芸守となってから厚く崇拝し、今日の社殿は清盛が造営したものの形を受け継いでいるということです。御神能はいつごろから始まったものですか。
能夫 厳島神社の能は戦国時代までさかのぼる。厳島の戦いという、主君・大内義隆を殺して領国を奪った陶晴賢(すえはるかた)と、生前の義隆と親交があり、安芸で勢力を伸ばしていた毛利元就との、首位を決する戦いがあって‥‥。結果は毛利元就の勝利となり、毛利が中国地方最大の大名として勢力をふるうことになるのだけれど、そのときの戦いで、厳島神社の神域を血で染めたというので、神をなぐさめるための神事として、1565(永禄11)年に元就が観世太夫を招いて奉納した能が始まりみたいだね。その後1605(慶長10)年、福島正則が能舞台を寄進し、この時に常設の舞台ができ、1680(延宝8)年、浅野綱長によって現在の舞台と橋掛及び楽屋が造られたそうだよ。定期的に御神能が行われるようになったのは、さていつのことなのかな‥‥。
明生 そういう歴史があったのですね。現在は、1日目と3日目が喜多流、2日目が観世流の担当になっています。昔は宝生流や金剛流も参加していた時期があったようですね。
能夫 今は五番立のうち、翁付脇能を玄人が勤め、あとは三番?四番、素人の方もやられる。3日目は素人の方が多いね。昔は翁も地元の人がやられていたようだよ。今はそういう太夫がいなくなったから、我々玄人がやり、翁以外は素人の方もやられたり・・ということになっているわけだ。それにしても、翁付という形が残っているところで、『翁』をやれるという喜びがあるね。翁付脇能までやらないと『翁』をやったことにはならないのではないかな。翁を勤めるには儀式、儀礼を土台とした心の集中力と続く脇能のシテへの気持ちの転換、この作業の経験が必要でね。脇能まで勤めてはじめて『翁』の披きだろうと思うし、僕はここでそれができたことを自負しているんだ。
明生 私も『翁』の披きはここで勤めました。『翁』だけですと30分ぐらいで終わってしまい、言われる通り、翁付『高砂』、翁付『弓八幡』を演じて初めて『翁』を勤めたといえるのでしょうね。脇能までの2時間半程の時間を体験し、ここでは朝のご祈祷もありますから、もっと長い時間を束縛されて、その日の太夫を勤めたという感じが生まれてくるみたいです。その意味でよい経験をさせてもらっていると思います。他には『野守』、『羽衣』、『小督』、『花月』なども舞えて、いろいろ勉強になりました。
今回私は、能夫さんの翁付『弓八幡』でツレを勤めましたが、ツレは普通、若い20代ぐらいの人が良く、似合っていると思うのですが、今年は21世紀の一番最初、新たな気持ちをこめてということで勤めました。調べてみると、この御神能での能夫さんのツレは、『高砂』、『弓八幡』、『養老』も、全部私がやらせてもらっているのです。なおかつ、今回の『弓八幡』は3回目。15年前とか20年前のツレは多分至らないものだったでしょうね。
能夫 明生君のかつてのツレがどうということは言わないけれど、この御神能は全ての役者がいい役者とは限らないんだよ。素人の方も入っているし、いろいろなマイナス面を背負いながら、それを我慢して舞台をつくり上げていかなければならない。五番立3日間を継続していくところに意義があるのではないだろうか。未熟な三番三(さんばそう/和泉流では三番叟)や千歳(せんざい)が出られると「あれあれ大丈夫かな」と心配しながら、翁太夫を勤めなくてはならないという寂しさはあるね。それでも宮島の太夫としてやらなければならない責任感もあるし。何も考えずに自然と舞台に集中できる『翁』と、いろいろなことを考えながら勤める『翁』とでは違う。やはり疲れるよ。亡くなった父も元気な頃は幹事役をし、能も舞い、そうそうNHKで放送された『湯谷』の舞台などもありましたが、晩年は体調を崩し、来年は来れるかなという思いがあったみたいでね。それだけ愛着もあったのだろうね。
明生 よく長いこと続いてきましたね。桃花祭の御神能というのは自分の事だけやっていればいいというわけでなくて、地謡をし、装束付けもし、素人演者の面倒や気の配りとやることがたくさんあって‥‥‥。
能夫 プロが大勢来ているわけじゃないからね。菊生さん、幸雄さん、執事の出雲さん、明生君、友枝雄人君、狩野了一君、充雄君、浩之君と9人で全部やるんだから。地謡は3人、後見2人、それに働きがあって、1日五番。装束をつけ、地謡を謡い、シテもツレもやる、だから鍛えられるよね。そこで謡もしっかり覚えたし、責任持ってやるようになった。地謡だって、いつもの8人なら8分の1の精神でいいけれど、3人のうちの1人ということになると、それぞれが地頭に匹敵するような責任感を持たなければやっていけないからね。後見だって、段取りがわかっていなければならない、謡(言葉)の間違いも直し、物着もしなければならない。だから、あの場で成長したってことはあるよね。
明生 そうい場があるということは良いことで、恵まれているといえば、恵まれているのでしょうが。確かにきつい場ですよ。脇方もお囃子方も東京では滅多にお相手できない流儀、例えば高安流、石井流といろいろと、経験しながらその流儀を知るということもありますね。装束付けもゆっくりきれいになんていっていられません。とにかく時間がない。
能夫 それで早く、しかもきちんとつける技術が身につくんだよ。間狂言の間に全部、装束づけをしなければいけないのに、間狂言がすごく短い時もあるからね。
明生 何年か前のことですけれど、翁付の五番全部装束付けをしたら小指のところにタコができたんですよ。夕食の反省会で飲んでいるときに指がかゆくなってきて、これ何だろうと思っていたら、どうやら装束付けで紐や帯を結ぶ時にできたタコらしい。1日にあんなにつけることないですからね。
能夫 そこでみんな技術を獲得するんだね。
明生 マイナス思考をすると、御神能は、あんなつらく、ハードなところはないになってしまいますが‥‥。
能夫 9時から始まって五番立でしょ。9時に始まるということは、楽屋入りは7時半。我々は何時に起きるのかってことになる。夜は夜で反省会といっては飲んで遅くなるし、もう我々おじさんたちはくたびれるよ。
明生 とにかく飲み過ぎると次の日の朝がつらい。
能夫 我々は島でなく、本土の方で泊まっているから、7時5分の船には乗らないといけないからね。
明生 あの時期、風邪ひいたり、怪我をしたりと、一人でも故障者が出ると大変です。他の舞台だって故障者がいると困るけど、宮島の舞台ばかりは、人がいない、一人一人が全うしようという使命感を持ってやらないとどうしようもないですから。
能夫 本当によい修業の場だよね。でも神事で『翁』をするよさは確かにある。
明生 そうですね。それにしてもよくやってきたなあ。私は24歳からですがもう20年越してしまいました。これで来年がすぐ来たりしてなんて言っていると、本当にすぐ来るんですよ(笑い)。
能夫 そういいながら、また行って、年の節目を感じるということになるんだろうな。
(平成13年4月21日 割烹 千倉にて)
我流『年来稽古条々』(9)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(9)
新太郎一周忌追善能を終えて
粟谷能夫 粟谷明生
明生─先回は粟谷新太郎追悼号ということで、私たちが新太郎から受け取ったものについて話をしました。今回は、3月5日に粟谷能の会として催しました「新太郎一周忌追善能」をふまえて話をしていきたいと思います。
能夫─一周忌ということで、チケットが売り切れるくらい、実に多くのお客様にご覧頂くことが出来ました。お客様の新太郎への思いと同時に、残された私たちがどれだけのことをやるのかというきびしい視線も感じました。
明生─伯父が一線を退いてから、父菊生と我々の三人体制でやってきましたが、いざ亡くなるとやはり心が引き締まる思いで、より一層強い覚悟が持てたような気がします。
能夫─僕はこの頃強く思うんだけれど、時間の経過には三つあって、現在の時間は凄いスピードで容赦なく動いていってるんだけど、未来はこちらの様子を窺いながらやって来るという感じがする。自分がきっちりとやっていれば未来もきちんとやって来るけど、いいかげんなことをしていると未来も躊躇しながら来る。そして、過去は厳然として、不動のものとして静かに立っている。だから自分をどこまで厳しく律しているかが常に間われていると思う。
明生─同感です。一周忌追善能では父の『弱法師』を舞入で、能夫さんが『求塚』を、そして私は息子の子方で『望月』をやらせてもらいました。どの曲も伯父が大事にし、思いのあった曲目で、一周忌にはぴったりの番組でした。まず父の『弱法師』ですが、やはり身体が万全ではない状態でしたので、クセを抜いたり色々工夫をしていました。
能夫─僕はやはり菊生叔父の持っている力がただものではないということを見せてくれたいい舞台だと思いました。今の僕の考える『弱法師』とは違うんだけれど。
明生─父の『弱法師』の基盤は技術優先主義というか、盲目の杖の扱いを軸にして、どう演じるかなのです。特に舞入などは、その冴えた技が勝負だと唱えていますから、この間はいつもと違う、身体が自分の思うようにいかないという、焦れがあったと思う。しかしそれで『弱法師』の俊徳丸という役を通して人間菊生が表現されていて、また一段とレベルの高い舞台になったと思いました。
能夫─親父の若いころの『弱法師』の写真を見て驚いたんだけれど、身体をかなり前へ折り曲げているんだ。昔の教えはそうだったんだろうなと思った。晩年の舞台ではそんなではなかったけれど、盲目という意識が強いためかな。僕の思う透明度、純度の高い『弱法師』は観世寿夫さんによって目を開かされた。
明生─次の曲が能夫さんの『求塚』。新太郎伯父が数多く上演し、好きだった曲です。この曲を一周忌追善能で能夫さんが披いたということに大きな意義があったと思います。
能夫─流儀の決まりだと基本が腰巻又は大口に水衣、肩上げなんだけれど、僕はどうしても壷折でやりたかった。壷折はなかなか奇麗に付きづらくて大変なんだけれど…。それと後シテのいわゆる痩女の足「切る足」だけど、これについては自分自身で発見することがあって、自分なりに納得して出来たように思う。それが発見できたのは「三鈷の会」が国立能楽堂の委嘱で上演した、馬場あき子作、佐藤信演出の『晶子乱れ髪』で、僕が与謝野鉄幹の役で登場するのに扮装等演出上の判断で、能のまんまのスリ足では駄目だと思い、それで幽玄の足でないというか、ノリのない連続性のない、いわゆる切る足の感覚で演じた。そのとき痩女の足はこれだなという発見があって、それで今回実際に演じることが出来た。菊生叔父のは独特の工夫で、焦熱地獄の熱さにぎりぎり耐えられなくなって足を上げるという感じだけれど、これは親父なんかでもそうで、少しやり過ぎだと思っていた。運びを含めて、僕はもっと違う、曲へのアプローチがあると思うし、自分なりに曲をつかまえて、次の世代に大きい曲をちゃんと教えて、渡していく必要があると思うな。僕たちは自分たちで場を作ってきたし、まだまだ前座という感じがあって、そういう意味ではハングリーだったよね。今回僕も『求塚』のシテがやれるということで十分手応えがあったけれど、やはりツレや、地謡を含め全体を見通して舞台を創り上げて行くという課題はあると思う。
明生─最後に『望月』ですが、この曲は息子尚生(たかお)とどうしても勤めておきたく、丁度良い機会に恵まれて幸せでした。自分が子方時代、翔鼓を終えた後、獅子乱序になる所からが何とも言えず、身体がぞくぞくするような興奮を覚えて見ていました。シテの獅子舞がとても格好良く、憧れていました。早く大人になってやりたいと思っていた。ですから尚生にも舞台を踏みながら、雰囲気を感じとってもらいたかった、共に呼吸をしたかったわけです。今回尚生の稽古にあたっては、自分の経験を基にすると、いままでの教え方を改良する必要がありました。例えば今の子供たちはチャンバラごっこはしませんから、刀の持ち方にしても、実際に持たせてやらないと分からないのです。また、ただ大きい声をだせだけでは駄目で、具体的に分かり易く説明してあげる必要がある、もっと教える側が的確な教え方を勉強していかなくてはと思いました。
能夫─そうだね、僕らの頃は本当に乱暴だったからね。掲鼓にしても笛の流儀の違いもちゃんと教えてくれなかったしな・・。ともかく『望月』は子方がよく出来たね。
明生─終わって三役の方々と鏡の間で御礼のご挨拶をした後、息子が、格好良かったよ、僕も大きくなったらやりたいよと言ってくれたのは嬉しかった。まだだいぶ先だよとは言っておきましたが…。
能夫─いずれにせよ多くのお客様の思いのなかで、それなりの舞台が出来たのは、やはり父や叔父がこれまで頑張ってやってきてくれたお陰だと痛感した。これを次の世代としてしっかり受け止めなければと思う。
研究公演つれづれ(その1)投稿日:2018-06-07
能夫、明生のロンギの部屋
研究公演つれづれ(その1)
第1回 能夫『三輪』 明生『熊坂』(平成3年7月6日)
粟谷 能夫
粟谷 明生
笠井 賢一
 明生 研究公演について、十年を経過しましたので、この節目で三人で話し合っておきたいと思います。この企画は最初からプログラムづくりなどで参加、ご協力してくださった笠井賢一さん(右写真)(現在銕仙会プロデューサー、演出家)にも、話に加わっていただきました。
明生 研究公演について、十年を経過しましたので、この節目で三人で話し合っておきたいと思います。この企画は最初からプログラムづくりなどで参加、ご協力してくださった笠井賢一さん(右写真)(現在銕仙会プロデューサー、演出家)にも、話に加わっていただきました。
ということで、宜しくお願い申し上げます。もう十年経ってしまった・・・あっという間 という感じです。
能夫 研究公演をやろうといい出したのは、明生君だったと理解しているんだけれど。そうですよね、積極的にやろうといったのは。明生君にどういう思いがあったかはわからないけれど、当時、粟谷能の会があっても、僕らはメインはなかなか舞わせてもらえなかった、それなら、自分たちで独自の会を起こしてやってみたいという気持ちがあったと思う。父や菊生叔父が元気で真ん中を気張ってやっていたので、初番やトメを息子達の勉強のために埋めてくれるという形であったからね。明生君の中には、覚悟として、いずれ代替わりのときに、我々は核になっていかなければならない二人であるという思いと、そのためにも打って出て勉強し、そういう場面になったとき遜色ない人材になっておきたいという願いがあっただろうし、僕としても飢餓状態というか、もっと舞いたいときだったから、それで動き出したということだったと思います。
明生 そのときの年齢は、能夫さんが四十一歳、私が三十五歳。父や伯父が作った会に安易に乗ってやるだけではなく、自分たちの思いで、曲に取り組み、色々な演出を試みる、がモットーのような会をこしらえたかった。最初は喜多の舞台より銕仙会能楽研修所という名称の響きもよく、見所がそれほど広くないので、あまり観客が入らなくても目立たなく大丈夫(笑い)、舞台の拝借料なども魅力・・・という場所で始めました。まあいずれは粟谷能の会と同じように喜多能楽堂や国立能楽堂でやれるようにということだったんですが。
能夫 当時、銕仙会は荻原達子さんが事務局長をやられていて、いろいろと便宜を図ってもらいました。銕仙会は立地条件も悪くないから、良い出発点だったと思うよ。印象に残っているのは、荻原さんが第1回のときの明生君の『熊坂』(右下写真)を見て、「能楽師の直面(ひためん)の顔だわね」と言われたこと。あの方がそう言うんだよ。
 明生 知らなかったな、初耳ですよ。
明生 知らなかったな、初耳ですよ。
笠井 そういうことはおっしゃっていました。僕もよく覚えていますよ。
明生 そうか。荻原さんは鋭く厳しい能の見方をされる方ですから、その言葉は照れるけれど、嬉しいな。あのときの銕仙会の舞台は古い黒光りの板で歴史を感じさせる舞台だったでしょ。2回目からは変わってしまって残念でしたが。1回目のとき『熊坂』で床几に腰かけて拍子を強くたくさん踏むので、踏むたびにベリッ、ベリッて音がして。まずいな、これ以上踏んだら本当に割れてしまうぞと思いました。だけどあの黒い板の舞台は格調高く良かったですね。
能夫 銕仙会の舞台は見所の雰囲気も良く、舞台と見所の一体感みたいなものを感じることができるね。あの時あたりから、明生君も成長したなと思いましたよ。第1回目はそれが印象的だった。
笠井 僕は三鈷の会でみなさんに出会って、その後、何回か飲むこともあったけれど、数年してから研究公演をやろうということになって、もちろん銕仙会を提供することは、荻原さんがお決めになったことだけど、僕はあのとき初めて、喜多流の人たちとお能の関係でつき合わせていただいたんです。僕は裏方で、舞台係みたいなことをやっていて。そしてプログラムを作らせてもらった。
 明生 なつかしいですね。第1回目のプログラム(右写真)は今のように三つ折りになっていなかった。だから発送するときに折るのが面倒だったんですよ。発送もこのときは私達がやったんですよ。この文章、笠井さんのコピーですね。「さまざまな試みを研究し、私たちのより良い演能を!」というの。僕は気に入ってるんですよ。
明生 なつかしいですね。第1回目のプログラム(右写真)は今のように三つ折りになっていなかった。だから発送するときに折るのが面倒だったんですよ。発送もこのときは私達がやったんですよ。この文章、笠井さんのコピーですね。「さまざまな試みを研究し、私たちのより良い演能を!」というの。僕は気に入ってるんですよ。
笠井 あ、それ書きましたね。僕がやったのは、毎回の研究公演に対するお二人の思いを聞いて、プログラムの冒頭に書くことだった。
明生 プログラム作りは私の担当で、第1回目では、能夫さんに、写真を使ってプログラムを作りたいので『三輪』の写真使わせてと聞いたら、「ない」と言われ、父や伯父の写真も良いものはなく困りました。良い写真を集めておかなければいけないとか、能専門のカメラマンを育てなければいけないとか、笠井さんにはいろいろ言われましたね。
能夫 そういうことに関しては、ずいぶん勉強になったね。
明生 十年経って、印刷編集技術も向上してきて、そこそこの写真でも使えるようになり、写真とコンピューターグラフィックの組み合わせで、きれいな画像処理もできるようになって。あの時分はそういうことが出来なかった。そのまま使える写真が少なかったのはこれからの能の写真のあり方を意識させてくれましたね。
 笠井 デザイン性は重要だね。初期の頃は能のチラシやプログラムは写真を使うか筆で書くしかなくて、コンピュータ処理するなんてものはなかったから、2回目からのプログラムは画期的(右写真)で、並べておいてあると、研究公演のが他より目立ってました。
笠井 デザイン性は重要だね。初期の頃は能のチラシやプログラムは写真を使うか筆で書くしかなくて、コンピュータ処理するなんてものはなかったから、2回目からのプログラムは画期的(右写真)で、並べておいてあると、研究公演のが他より目立ってました。
明生 それで曲目選択ですが、後から考えるとまさしく能夫さんがよい曲目を選んだなと思いましたね。「何をやるの」と私が聞いたら、「『三輪』を」と言ったんです。それも、普通だったら小書は憧れの「神遊」じゃないですか。それが「岩戸之舞」をやると。『三輪』は小書がつかない普通のものと小書「神遊」「岩戸之舞」があるけれども、新太郎伯父がやった「岩戸之舞」とも違うものを、自分なりに生み出してみたいといわれましたね。
能夫 自分独自のものというより、もともと「岩戸之舞」には二通りの伝書があって、今は一方しかやらないので、もう一方を掘り起こしたいということだったんだ。よくやられている「岩戸之舞」は江戸末期に作り上げられたもので、天の岩戸を探すイロエの型があるもの、もう一方は本来の暗闇での神楽を奏する「岩戸之舞」。そこに帰りたいという思いがあった。これを選択したのは『三輪』という曲に対する憧れというか、観世寿夫さんの素敵な小書「素囃子」を見た時の衝撃があったからで、あのときの「素囃子」は、大口袴と黒の風折烏帽子で出てくると思っていたら、本当に原始的な出立ちで出てこられたのでびっくりしたんだ。あんな「素囃子」はできないけれど、自分なりの取り組みというか演出をしてみたかった。喜多流の特徴をつかまえながら、『三輪』の原初に近づきたいという気持ちかな。
明生 能夫さんは『三輪』のお囃子方を決めるときには、ちょうどそのころ、浅井文義さんの『葛城』「大和舞」を拝見した後で、とても素敵な「大和舞」だったから、是非あの方々にお願いしたいと言われたように覚えているのですが。お笛は一噌仙幸氏、小鼓が宮増純三氏、大鼓が国川純氏、太鼓が三島元太郎氏ですよ。
能夫 そうそう、まさにそう。その方々なんだ。太鼓の元太郎さんに「岩戸之舞はどういうものなんだ」と聞かれて、僕は「これは暗闇(くらやみ)の神楽です」と言ったことを覚えている。元太郎さんに「能夫君がそう言ってくれたので打てたよ。ただ古いものを掘り起こされても、そのイメージを伝えてくれないとわからないね。やったことないんだから」と言われた。そのとき、ああ、答えを言えて良かったとつくづく思ったし、伝書にヒントが書いてあるんだが、そういうものを勉強しておいて本当に良かったと思ったね。あの一言が言えたおかげで、お囃子方全員が動いてくれた気がします。
明生 『翁』の型をするんですよね。
能夫 そう、『翁』(右下写真)と同じ型をやる。天の岩戸の神楽、暗闇の神楽を見せるわけだからね、原始だよ。
明生 普通、小書となると「神遊」ですが。「岩戸之舞」は、それまで新太郎伯父など何人かの方が勤めていますが、あまり頻繁にはやられていないんじゃないですか。
 笠井 その後、その「岩戸之舞」はやっているの。
笠井 その後、その「岩戸之舞」はやっているの。
能夫 研究公演の1回目にやった「岩戸之舞」は、その後だれもやっていない。
笠井 あのときのことは、いろいろな意味で印象に残っているよ。申合せは銕仙会でやっていますよね。僕はその申合せを見ているんだ。ところで、明生さんは何で『熊坂』を選んだの。
明生 最初『弱法師』をやらせてと言ったら、能夫さんに「まあそれは置いといて、まずやらなくてはならない曲というのがあるでしょう」と言われ。「『熊坂』がいい、『熊坂』にしておけ・・・」 と。『熊坂』はそれまでやったことはなかったし、これはやはり、きちんとやっておかなければならないという気持ちになりまして。喜多会や粟谷能の会でいずれはやらされると思いましたが、やらされるのではなく、「自発的にやるという意識」が必要だなと、そんな気持ちになったんです。やはり自分達が企画している会だと違うなという発見が出来たのがよかったですね。『熊坂』の面は二面あって、能夫さんに「どっちを使う」と聞かれました。一つは大きくて重い長霊べしみ、もう一つは、平素使ういかにも長範らしい少しおどけて見える面。まだ若いし、ここは一つこの重い、ごつい方を掛けてみようと思い、前者を使いました。私が勤める前に、お弟子さんが『熊坂』をやられて長範頭巾がずれたことがありまして、もうそれは滑稽で笑い出しそうというか、実際、皆謡いながら笑ってしまったんですが、もちろん申合の時ですよ。これはいけない、面と頭巾のしっかりしたつけ方の工夫をしなくてはと思い、皆で取り組んだのを思い出します。装束づけも後見任せにするのではなく、自分の方から、こうつけたい、こうつけるとまずいと前もって言っておくべきだという意識が必要ですね。当日その場で特別注文されても、つける方は困惑しますから。それから装束の組み合わせなども、曲趣によって、色、形のバランスを深く考えていくということもやりだしました。『黒塚』の演能レポートにも書きましたが、装束を出すときに、能夫さんに「蔵に来いよ」と連れていかれ、「人任せにしないで、自分で選ばなくてはね」と言われたんです。そして、どのように演ずるかを考慮して、能に携わる全ての配役を選ぶ重要性を能夫さんにいわれましたね。
笠井 明生さん、やられてどうでした。
明生 『熊坂』(右下写真)ね。この間もある方が舞われたけれど、中入りを定型の型をせずに、スーッと幕に入っていくという替えの型、これがなかなか難しいみたい。本来、常座で、廻り返し、シカケ、開キという型付になっているんですが、難し過ぎて、やはりスーッと消えていくように幕に入る替えの型を選んでしまいます。本来の型は余程うまく動かないと難しいですね。
笠井 僕はもっと消えていくような型、シカケ、開キがあり得るという気はするね。
 明生 そうですか。
明生 そうですか。
笠井 溶けて消えていくとはこういうことかというものがあると思うよ。
明生 という謡い方のこと?
笠井 謡い方も、動きもね。役者も囃子方も両方で何とかする可能性はあると思う。高速度撮影で武士が何人も並んで見えたかと思うと、すっと消えて、気がついたら、そこは草の原に変わっていたみたいなイメージができる謡い方、消え方があり得るだろうと、僕は思います。
明生 ジトーッと消えるんじゃなくて、スーッと消えていくようなというのは笠井さんに言われましたね。
笠井 第1回目のときは、その意味で菊生さんの地謡がそれに合っている、なるほどなと思って、印象に残っているね。それにしても、申合せのとき感じたことは、喜多流というのは本当にからだがよく動くんだなということ。観世流とは型も違うしね。
明生 でも観世さんの方が派手で、動いてますよ。
笠井 派手だけど。そちらの方がすごく動くという感じがした。
明生 そうかな。以前お囃子の会で拝見した『熊坂』では、観世暁夫さんのもの、関根祥人さん、もう少し前の事でいえば浅井文義さん、皆キレがあり、派手だしすごく力強く動かれているよ・・・。
笠井 確かに観世流は動きは多いよ。でもキレの良さみたいなものが違うよ。決めるところの難易度の高さがすごいというか。
明生 なるほど。そうかな。
笠井 装束つけたら、それほど見えなくなったけれどね。
明生 え?っ(笑い)。
笠井 まあ、それはものの道理というものだよ。でも喜多流のこういう動きは、やっぱり観世流の中にはないよ。瞬発力があって、あれだけ動いて、独特な表現をしている。良くも悪くも、動いてナンボだろう、そういうところがある。
能夫 もう動けないねえ。
明生 ああは動けない。十年前にやっておいてよかった。
笠井 動けなくなったら、またやりようがある。熊坂長範という役の位置で表現できるものはあるよ。観世銕之亟さんなんかもちろん、あんなダイナミックな動きはやらないけれど、それでもあの世界を表現するのは本当にすごいから。生涯の修業であれだけの表現をするということだろうけど・・・。
能夫 それはそうだよ。すごい人だもの。
笠井 銕之亟さんも若い頃は動けたし、鋭かったんだよ。
能夫・明生 そうそう。すごい動きですよ。
明生 うちの父が言うのは、静夫さん(銕之亟氏のこと)が『鷹姫』でずっと微動だにしないで座っていた後、急に立ち上がって急ノ舞を見事に舞った、ああいう動きのできる人は喜多流にはいないって。
能夫 そういう精神の強さ、集中度、難易度の高いものをこなす能力。昔は片膝で座っていたというでしょ。
笠井 意地もあったでしょ。それで舞の鋭さが出ていたと思うんだ。
明生 あれだけ長い時間座っていたら、足がしびれて、最初の掛かりがちょっと散漫になるのが普通だけれど、銕之亟先生は最初からテンションを上げてキューッと舞っていた、すごいというのが父の鮮明な記憶になっているんですよ。で、「お前らの『鷹姫』はなんだ!」ということになる。そういう影響を受けて、我々も発展していかなければダメなんですね。
笠井 そうい発展の仕方って大事だよね。僕も寿夫さんの能を見ていますが、寿夫さんの対(つい)にいたのが静夫さんでしょ。寿夫さんはスターで、まわりが大騒ぎしている。もちろん魅力的だった。だけど、一歩か二歩遅れている静夫さんの能もすごい鮮度があった。寿夫さんは病気になってから晩年にかけて変わったけれど、その少し前の『卒都婆小町』なんか生々しいところもあった。それに対して静夫さんは逆に透明度が高い、そういう感じでやっていたときがあったんですよ。もちろん人情がにじみ出るようなものもやってはいたけれど、寿夫さんのものと比べると、非常にクールな感じがするときがあって、僕はいいなあと思っていました。
能夫 わかりますよ。
笠井 そういうように兄弟って、少しズレながら、お互いが影響し合ってよいものを作り上げていくということがあるよね。
能夫 何ともすばらしいよ、あのご兄弟は。
笠井 あの方たちとの出合いがあったから、現代演劇を志していた僕のような人間が、銕仙会で能の仕事をするようになりました。それから粟谷さんたちと出合い、「研究公演」の協力をさせていただき、「阿吽」に繋がっていきました。お二人とは演劇人として対等に議論を交わし、互いに刺激し合う関係で、「研究公演」がこのように継続してこられたことはとても大きなことだと思いますね。
能夫 積み重ねるということは大事だね。
笠井 十年という歳月は何ものかを生み出しているね。十年見ていると、お二人の舞台がそれぞれ変わってきていることがわかる。
能夫 それはやっぱりみんな変わろうとしてやっているからだと思う。志がある人は、同じことをやるのではなく、できなかったことは次にはこうしようと、日々発展がある。それは役者にとって重要なことですよね。自分の欠点やダメなところを変えていこうという意識は持っているつもりなんだけどなあ。効果が出ているかどうかは別として。
笠井 その効果は節々で出ていると思うな。それから『三輪』について一言言わせてもらうと、実は、まだ不完全燃焼だなという感じ、そういう印象があったんだ。「岩戸之舞」の思いを今みたいにつぶさに聞いていないから、僕の方が理解していなかったということかもしれないけれど。僕が初めて能夫さんの能を見たのは『楊貴妃』だから、その感じからすると、少し線が細かったかなという気がしたんだ。もっと鮮度があってバリバリやるだろうという思いがあったからね。それで次の『井筒』を見たときは、なるほどと思いましたね。ためていた思いみたいなものが出ているというのが印象的だった。
明生 あ、もう2回目に入りましたね。
笠井 ちょっと飛ばしちゃったかな。
明生 1回目のことはだいたい話したから、では、2回目は次回のお楽しみということにしましょう。
(平成13年5月 記)
我流『年来稽古条々』(10)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(10)
青年期・その四『猩々乱』披き以降
粟谷能夫 粟谷明生
明生─先号と先々号は粟谷新太郎追悼ということで新太郎から我々が受け取ったもの、また新太郎追善能を催して感じたことなどについての話をしました。今月からは本来の流れにもどして、「阿吽No.8」の[猩々乱披きをめぐって」以降の時代について話をしたいと思います。
能夫─僕の『乱』は昭和四十七年で二十三歳だった。『道成寺』が昭和五十四年で三十歳。それまでの間のことだよね。その七年間にやった曲が十三、十四番位。昭和四十八年『大会』から『半蔀』『野守』『小鍛冶 白頭』『二人静』『巴』『船弁慶』『熊坂』『源氏供養』と続いて、前年の五十三年に『花月』『黒塚』。この『黒塚』で『道成寺』にもある「祈り」をはじめて体験した。今思えばあの時期に『紅葉狩』とか『葵上』を演っておいてもよかったように思うな。そして、昭和四十四年頃から他流の能を観に行くようになった。最初に見たのは観世寿夫さんの『船橋』だったと思う。その時の感動から銕仙会へは度々観に行った。昭和四十七、八年頃には、銕仙会で書生をしていた浅井文義さんとの出会いがあり、互いの舞台を観に行くようになったんだ。僕の『大会』を観に来てくれた浅井君から基本の技術がしっかりした佳い舞台だったと言われ、すごくうれしかった思い出がある。面は釈迦をかけたわけじゃなく、大べし見のままで通す普通の演出だったし、自分としては教えられた通りにやっただけという意識だったけれど、喜多流の型の面白さということがあって、より鮮烈に感じてくれたんだろうと思う。最近彼が『大会』をやるというので、喜多流の後シテで一畳台をダン、ダンと飛んだりする型はどうやるのかと聞かれた。他流と交流するのはいいと思うな。その『大会』を見に来てくれたある人から「わかるけど、まだまだこれからね」って言われたのもよく覚えている。自分としては一所懸命にやったし、ベストを尽くしたのに、何でそんな評価になるのかと思ったことも確かだけど、同時に何かまだまだ先があるというか、能の奥深い世界があるということを感じさせられた。今にして思えば、その頃自分にはその先がよく解っていなかったと思うけれど。実際『大会』がやれたからといって『求塚』が出来るわけじゃないからね。それが二十四歳かな。
明生─私から見ると能夫さんは成熟してましたね。
能夫─当時は、うちの親父が地謡を謡ってくれたんだよ。そのために苦労して覚えていたのを想い出すな。
明生─あの頃の青年喜多会は私たちが演じる時は父親が地謡を謡うというのがお決まりでした。私は『大会』の袖珍本を能夫さんから貰いましたが、その本には新太郎伯父の沢山の赤い印の書き込みがあって、悪戦苦闘している様子がうかがえました。息子のために苦労していたのがはっきり残っていますよ。当時は前三人後三人の六人地謡。地頭のストレスも多かったでしょうね。
能夫─それから翌年の『半蔀』、これもよく覚えているな。
明生─その頃、青年喜多会で本三番目ものの曲がつくというのは大変なことでした。
能夫─僕は『半蔀』で袖を返して夜が明ける所を見るということにすごく抵抗があった。その頃は無機的な表現に憧れをもっていて、表面的な演技はいやだと思っていた。何もせずに見ればいいじゃないかとも思っていた。その時浅井君に、そうではなく、袖を返し、またその袖をもどすことで次の場面に進んでいけるのではないかと言われ、袖をもどすことでふーっと気分も、世界も変わるという能の仕掛けを理解出来たように思う。まあその頃は時間もあった。演能の回数も少なかったから、お互いの能は見られたし、浅井君とはしょっちゅう会って話をしていた。
明生─今の内弟子さんの方がずっと忙しいですね。
能夫─だからその頃たくさん覚えたことが今の財産というか、貯金になっていると思う。当時、能夫は舞台で地謡がどんなに謡ってもがんとして動かないやつだと思われていたんだよ。それと、『半蔀』でうちの親父や、菊生叔父から、もっと角(すみ)まで行かなきゃ駄目じゃないかって言われた時に、友枝昭世さんが、能夫には能夫の考えがあるんだろうと言って理解を示してくれた記憶がある。
明生─私も能夫さんから言われましたが、喜多流は藁屋の作り物を常座にやや正面に向けて出す、その作り物から発せられる力の広がりの限界、結界みたいなものが有って、シテはそれを超えて角の目付注ギリギリまで行かない方がいいということでしょう。
能夫─その根拠は能の型付にあるんだよ、仕舞の型付では曲の初めに角まで行って左に回ってということになっているけれど、能の型付には角まで行かないで少し右向いて隣の読経の声を聞いて、というような能的な処理の仕方が書いてある。それを仕舞と同じように動くということに対する憤りがあったし、うちの流儀の作り物の出す位置、作り物によって生じる結界というものを考え、角へ出すぎると、その結界から外れてしまうと考えたんだ。昭和五十年が『小鍛冶白頭』。喜多流独特の狐足という足使いがあり、機敏に動き廻る曲を演った。これには父達の作戦があったようなんだ。前にも述べた通り、あまり動きたがらない僕を喜多流的な次元に引き戻そうという仕掛けだった。それでも、僕にとっては、ある憧れを抱いていた曲であり、やりがいを感じて稽古をしたように思う。今その時の写真を見ると、半切をあまりにも短く着てしまっていて、スネが丸見えなんだよ。当時は装束着けに対する意識が低かったしな。でも、これを演って、動き廻る事もまた能の要素の一つであるということが体感できたんだ。それから『二人静』。これ、明生君と二人でやったんだよね。必ずしも進んでやりたい曲ではなかったけれど…。
明生─私もすごく嫌でした。あの時ははみ出し者を矯正するための曲だとしか思えませんでした。能夫さんは観世寿夫氏に傾倒して喜多流の規範から外れていると思われていたし、自分は目標が見つからず、能に自分の考えを折り込めない、能に集中できない時期でしたから。
能夫─僕はきらいな曲だったし、本当に嫌だったな。能役者にとってそれぞれ固有のこみ(主張のようなもの)というものがあって、それは本来合わせられるものではないのでね。それを殺して合わせても何の意味もない。
明生─かえって御素人のお弟子さんの方が素直で上手に合わせられたりするんですよ。当時の写真を見ると能夫さんは構えが立派ですが、私は身体も出来上がっていないというか、貧弱で、そのくせ生意気に喜多流の若い人の構えはこうだというようなものに反発があって、大人達のような一見何でもないような構えに憧れていました。写りが悪いのは当たり前です。ともかく嫌であったけれどよく稽古し合わせました。自分の中で能というものを真剣にやらねばと思ったことは確かです。
能夫─装束もあの頃は揃いのものはなかったね。紫の長絹も濃いのと薄いのとしかなくて…。
明生─能夫さんにお前は俺の影だから薄いややくたびれているほうにしろと言われ、それを着ましたね。
能夫─ともかくその頃は年二番だものね。本当にハングリーだった。だけど充実した時を過ごせたと思っています。
-つづくー
研究公演つれづれ(その13)投稿日:2018-06-07
研究公演つれづれ(その13)
第13回研究公演(平成17年12月22日)
『木賊』シテ・友枝昭世 地頭・粟谷能夫 副地頭・粟谷明生
粟谷 能夫
粟谷 明生
■地謡を充実して、喜多流の『木賊』像を創造する
 明生 昨年暮れに、研究公演を4年ぶりに復活させ、『木賊』に取り組みました。研究公演の第3回『求塚』で試みたように、友枝昭世氏にシテをお願いして、私たちは地謡を充実させ、この難曲『木賊』を創り上げてみようということでした。この会で、能夫さんがずっと主張していた、喜多流の『木賊』像が出来上がったのではないかなという気がしています。粟谷新太郎7回忌の年に、こういう機会を仕掛けることができ、その成果を上げたということは喜ぶべきことですね。
明生 昨年暮れに、研究公演を4年ぶりに復活させ、『木賊』に取り組みました。研究公演の第3回『求塚』で試みたように、友枝昭世氏にシテをお願いして、私たちは地謡を充実させ、この難曲『木賊』を創り上げてみようということでした。この会で、能夫さんがずっと主張していた、喜多流の『木賊』像が出来上がったのではないかなという気がしています。粟谷新太郎7回忌の年に、こういう機会を仕掛けることができ、その成果を上げたということは喜ぶべきことですね。
能夫 それは嬉しかったよ。
明生 能夫さんがよい仕込みをして、友枝昭世氏をくどいて、そしてシテのエネルギーを我々も受けて・・・という感じでした。
能夫 僕らの新しい喜多流の『木賊』像を創るんだという気持ちを踏まえて、昭世さんが新しいチャンネルに切り替えて臨んでくれたという気がするね。まさに三位一体。
明生 装束についても、地謡についても、今回、昭世さんは我々に常に指示や相談をなされていたでしょ。こういうことはあまりないことですね。『求塚』のときもこれほどではなかった。もっともあの時は我々が未熟だったのですかね・・・
能夫 能というのはシテだけの思いでやっても成立しにくい、その思いを舞台を創るみんなに伝播しないとね。本来、能は座のような組織で手作りでやるものだから。我々だけでなく、もっと地謡の一人ひとりに、「こう思って」「こう謡ってくれ」という細かい指導があってもよかったかもしれないね。まあ、それは僕たちが伝えればよかったことかもしれないけど・・・。その辺は今結論を出せないが・・・、でも僕たちだって謡い方ではかなり細かい指示はしたつもりだよね。
明生 その辺はみんな真摯によく聞いて合わせてくれたと思います。今回の地謡の人は、半分は未経験者ですから、しかも大曲ですし、普段の従来のパターンでは了しきれないと思っていたのではないですか、だから素直にならざるをえないところがあったのでは・・・。
能夫 そう思うよ。
明生 みんな積極的で、あんなに前向きに取り組んだ姿を見たことないというくらい。(笑)
能夫 大曲を創り上げるときに抜擢されたという意識が、みんなの中にあったんじゃないかな。必要な人材だよと言われたときの喜びってあるじゃない・・・。僕らの志が通じたということではないかな。だって、自分たちの会で自分が舞わないで、シテをしないでだよ、地謡で勝負する、地謡を創り上げるなんていう物好きがいるかね・・・?
明生 普通しないですよ。
能夫 そうでしょ。そういうことに挑むことが、僕は革新、画期的なことだと思うんだよ。だからその志が通じたということ・・・。誰だってシテを勤めるのがいいに決まっているもの。僕もそう思うけれど、粟谷の家は益二郎からの伝統で新太郎、菊生叔父と皆、地謡を謡ってきたじゃない、そのことについての継承もしておきたいというか・・・、そのような思いがある集団だという喜びと誇りみたいなものを・・・。
明生 ありますよね・・・。
能夫 そう。だって地謡が駄目では良いお能は成立しないから。どんなに立派な大夫がいたって・・・。
明生 故観世銕之亟先生が「舞えて謡えてだよ、そして装束付けができて・・・」
能夫 後見もできて、オールマイティでなければ駄目だと。
明生 「そうでなければ、僕は能楽師として認めないよ」と・・・。説得力ある言葉ですよね。今回地謡に参加出来てすごく勉強になりました。次回謡うときの、そしてシテを勤めるときの肥やしになりました。こういう形で学習ができ、興行的にもうまくいき・・・、本当によかったですよ。
能夫 うまく仕掛けが利いた、ということだね。
明生 能夫さんの仕掛けが成功しましたね。時期的にも。
能夫 我々が粟谷能の会を創っていく時期にもなってきているしね。
明生 友枝さんが『卒都婆小町』を3回やられて、次に『木賊』という流れの中で鮮度もあったし。地謡が大事だというメッセージや志がまわり、とりわけ若い仲間に伝わった気もしますし。求心力だね、これはやっぱり・・・。
能夫 ウフフ、そうじゃなくて、やっぱり好きか嫌いかってことなのよ・・・。
明生 好きか嫌いかってことですが・・・、今回はやはり能夫さんの策に全員がうまくはまったという感じですね。能夫さんはこの企画は失敗はしないよと言っていたでしょ、途中から、そうだ失敗しない、成就するな、とどんどん感じてきましたから・・・。
能夫 これを仕込んだのは2年前だよね。最初、友枝さんに話をもちかけたら、あまり手ごたえがよくなくてね・・・。僕が『木賊』をやりたいから、その前にやらないんですか?というようなニュアンスに思われたらしい。昭世さんは自分の頭の中には『木賊』は組み込まれていない、だからやる気はないって言われたんだ。
明生 そんなやり取りがあったなんて知らなかったですよ。
能夫 僕がやりたいのではなく、友枝さんに舞ってもらって我々が、つまり菊生叔父抜きで地謡をやりたいのです、と申し上げたらわかってくださって。それで引き受けて下さって・・・、取り組みだしたら、まあ「楽しい!面白い!むずかしい!」とね。
明生 そうですね。昨年後半はもう友枝さん、『木賊』の話ばかりなさっていたし、すごい気の入れようでした。
能夫 そうでしょ。昭世さん、昨年は『木賊』で楽しい1年を過ごされたわけ。だからあれは昭世さんの歴史の中でもすごくいいものになったと思うよ。喜多流の『木賊』の巻頭を飾ってくれたし、いい時期に『伯母捨』があって、そして画期的な『木賊』が燦然と輝いて・・・。そういう時間を我々も一緒に過ごしたということじゃないかな、と僕は思いますよ。いい人材にシテを頼めて、シテも、我々も、喜多流の若い者もみんな一生懸命にやれたという・・・。
明生 観てくださった方はどう思われたか知らないけれど、少なくとも演じる側は充実していた、真摯に取り組んだということは確かですね。
■充実した地謡が謡えただろうか
 明生 それで地謡の成果ですが、昭世さんが「よく揃ったなあ。でも揃ったというのは音じゃない、高さでもない、ということを肌で感じたよ」と仰っていましたが・・・。能夫さんも言っていましたよね。以前は周りの音が違うんだ、発声とか発音とかが気になると。でも地謡が揃うというのはみんなが同じ音を出すということではないんだということが体験出来たと・・・。
明生 それで地謡の成果ですが、昭世さんが「よく揃ったなあ。でも揃ったというのは音じゃない、高さでもない、ということを肌で感じたよ」と仰っていましたが・・・。能夫さんも言っていましたよね。以前は周りの音が違うんだ、発声とか発音とかが気になると。でも地謡が揃うというのはみんなが同じ音を出すということではないんだということが体験出来たと・・・。
能夫 そう、単なる統一規格では駄目みたい。
明生 中村邦生さんも長島 茂君も前列も、みんな音はそれぞれ違う、だけど気を張り詰めることで一体になれるということ、故観世銕之亟先生が地謡は重層でなくてはと話されていたのを思い出しました、これが今回の収穫でしたね。
能夫 ホント、そう。
明生 能夫さんと私だって違うでしょうし。違うけど近いかな?一応合わせるように思いながら謡っていましたけど、そこに目立たなくゴツゴツしたものが発揮されたような・・・。
能夫 そう。みんなの気持ちが喜多流には珍しくデリケートに結集したんだね。
明生 みんなで出す息、引く息と両方があることを体験出来た・・・。私自身のことを言うと、申し合わせのテープを聴いて、ちょっと自分の声が大き過ぎて邪魔しているという反省もあって。益二郎は大きな声で周りを束ねたということが頭の端っこにあって・・・、でも私は副地頭という立場だから、もっと自分には絞り込んだもので地頭を引き立て、邪魔にならず、それでいて頼りになる存在、そうでなければと思って・・・。そういう謡はボリュウムじゃなくて何だろうと思っていたら、打ち上げの宴会のときに昭世さんが「気だよ」って。
能夫 そう、気持ちだよね、思いだと思うな。結局さ「げに真、何よりも・・・・・磨けや磨け」で、僕なんか気持ちが入っちゃうんだよね。クセなんかよりもあそこの方に・・・。
明生 「磨くべきは真如の玉ぞかし、思えば木賊のみか、我もまた木賊の、身をただ思え我が心、磨けや磨け」と木賊を刈るあそこの場面、能夫さんもうかなりのハイテンションでね。
能夫 シテが「胸なる月は曇らじ」と思いを込めているでしょ。あそこ「ゴメン、高い調子になっちゃって、でもちゃんと受けてくれたね」と昭世さん言われたけれど・・・。音の高さでなく昭世さんの思いみたいなもので受けるのよ、そのぐらいのことは出来るよな!
明生 能夫さんはあそこの謡を気にしていましたからね。
能夫 そう、心を磨かないと人間駄目だというテーマみたいなものでしょ。僕はここが好きだよ。自分の心を磨けということで。
明生 前半のクライマックスだね。
能夫 僕はあそこが上手く謡えないと失格だと思っていたから、あそこはハッチャキで謡いましたよ。これはもう僕の動物的な感覚だけど、なんか感情をむき出しに謡いたいとね。クセなんかより、磨けや磨けとやっていることに・・・。
明生 父親の精神性の強さみたいなものがあそこに滲んでいるんでしょうね。
能夫 父親というのはこういう生き方をしているんだというような。あそこが僕はこの曲のポイントだと思うから・・・。
明生 すごいハイテンションになっていたもの。
能夫 だから言ったでしょう。僕はここにかけるから、あとの初同とかその辺はおまかせしますからって(笑)。
明生 「げに真・・・」はどうしても高くなるけれど あそこは下がってはつまらないですよね。
能夫 高くていいの。これまでの昭世さんとのおつき合いや菊生叔父の隣で謡わせてもらって獲得したものもあるし、そういう複合的な要素で張って謡えたんじゃないかなと思うよ。
明生 凄かったよ、独壇場でしたよ(笑)。
能夫 だから、それがすごく楽しかったんだよ。
明生 ハイ、ハイ(笑)。
能夫 やっぱりここを創っておかないと、筋立てとしてうまくいかないから・・・。
明生 前半のクライマックスはここで、あの段で1回終息してもいいんですね、折り目ですかね。次の地謡「よそにては」から始まる段で終わるのではなくて・・・。
 能夫 「よそにては」のところはローテンションでもいいと思う。そこそこ説明的なところだから。
能夫 「よそにては」のところはローテンションでもいいと思う。そこそこ説明的なところだから。
明生 私はあの「よそにては正しく見えし帚木の、・・・・陰に来て見れば無かりけり」で、遠くにいると見えるけど、近くにいると見えなくなるというのは、親子関係として見ると面白いなと思うので重要な関連だと思いますが・・・・。本当は恋人同士の話なのでしょうが。親父菊生と自分の関係で考えても、あまり近くにいると、その良さや愛情の深さが分からないというようにね。「ありとは見えて逢わぬ君かな」なんて美しい世界だと思ってやっているわけですが、菊生親父のあの頑なな打ち上げ宴会でのお説教を聞くと、まさしく木賊老人が目の前にいるわけでしてね・・・・。
能夫 昭世さん、爆笑していたからね。でもまあいいじゃない、頑なな菊チャマがいるというのは(笑)。
明生 それから次の段「廬山の古を思し召さば・・・」のところですが・・・。
能夫 そこだよ。「老情を慰む志・・・」と言って、老人の心情を慰めるために共に飲もうよと言って、中国の故事を引きながら酒を勧めるわけでしょ。浅井君(観世流・浅井文義氏)にも言われたけど、あそこは観世寿夫先生がすごかったんだよと。シテが老情と言って感極まっているのに、その気持ちを受けない「廬山の・・・」はないだろうって。
明生 そうですよね。仏の戒めで飲めないという僧に、故事まで引いて飲め!と飲ませてしまうのだから。
能夫 「廬山の・・・」は寿夫先生は呂音(低い音)でガンガン強く謡っていたよというのがヒントになったんです。そういういろいろな話が聞けるのがいいねえ。
明生 いろいろな人の話を聞かないとね。喜多流の人だけでは狭すぎますよ、もっと広く。
能夫 自分の発想だけでは、ここは甘く謡うところかなと思っていたけど、この話を聞いて昭世さんに話したら、「そうだよ、老情を慰むと気持ちを入れて謡っているから、それを受ける廬山の、が平坦ってことはありえないよ」と言ってくれたので、あそこの段が決まったということがあるね。
明生 いいアドバイスをもらいましたね。
能夫 そうね。いろいろなおつき合いの中でもらっているものもあるし、分からなければ問うこともあるし。あそこの「廬山の」の段は浅井君からというか、寿夫先生からのメッセージだよ。・・・あそこはうまく謡えたと思うよ。
明生 あそこは能夫さんが頑張っていたから、もう僕は委ねてというか邪魔にならないようにというか、さっきも言ったように、基盤の支えはしますから、あとはご自由にしてください、みたいなとことがありまして。能夫さんは、ここはこうやるぞ!と言っていたからね。
能夫 そうね。まあやりようがあるよね。戯曲というか能を考えるとき、先人の思いや教えも大事だし、謡っている本人の自覚も大事だよね。能は総合芸術なんだよ。過去・現在・未来みたいなものを一緒に持っていないと謡えないよ。
明生 こういう精神力の中で友枝さんが舞えたということはある面ではよかったのではないですか。演者がこれだけの結束力で、しかも謡っている人間がこれだけ考え思い謡ったということは・・・、そういつもあることではないですから。
能夫 そうでなければ『木賊』という曲は成立しないだろう、逆に言えば。こればかりは究極の謡い物の曲だなと思う。
明生 このような現在物の曲ねえ。『卒都婆小町』もそうですけど。能夫さんはわりと幽玄趣向というか・・・。
能夫 幽玄志向があるか・・・。
明生 幽玄物は甘さみたいな部分を残しておいてくれるから、演技者にとっては救いがあると思うのですよ。
能夫 入りやすいよね。
明生 しかし、現在物はシビアでしょ。
能夫 シビアだね。
明生 で、能の演技として生(なま)になるな、という規律、教えがあるじゃないですか。『卒都婆小町』『木賊』、『柏崎』もそうですが、今の世の中での現在物の置かれている難しさというものですね・・・。今、現在物をカッチとできる者はやっぱり僕はいい役者だなと思うしそこを見たいと思うのですよ。それはきれいな幽玄の世界も勿論ありですが、くさくならず、あたかも幽玄のように現在物を見せる能役者になりたいなあ・・・と。何かマジックをかけてしまうようなね。そういう感じ・・・、この間の『木賊』や『卒都婆小町』を謡うことで感じたことなんですよ。
能夫 『木賊』なんか謡っていると楽しいよね、極致だと思ったね。これが夢幻能ではなくて現在能なのかなという感じもしたし(笑い)。
明生 幽玄も現在もどちらにも激しくぶつからないと駄目というかでしょうか、幽玄にも力強く当たらなければ駄目だし、現在物にも跳ね返されるぐらい。だから僕はもう少し幽玄の方に強く向いていかないといけないなとも反省するのですが・・・。どうしても現在物をやり始めると一生懸命になって・・・、今そっちの方に目が向いていて・・・。振り向けばもっと違うものもあるとはわかるのですが・・・。
能夫 それはそれぞれの立地条件も違うわけだし、それぞれのポジションで訪ねていけばいい問題じゃないかな。
■重い曲に挑戦する意義
明生 友枝さんが『木賊』のような大曲は20年?30年も間をあけてはいけないなあ、自分がやってみて分かったとおっしゃっていたのが印象的でしたね。
 能夫 秘曲、大曲といって大事にしすぎて、結局は誰も勤めないのでは、誰もできなくなってしまう。だからそう間をあけずにやっていかなければいけないんだよ。『伯母捨』だって、菊生叔父が数年前に百何十年ぶりに掘り起こしたわけでしょ。
能夫 秘曲、大曲といって大事にしすぎて、結局は誰も勤めないのでは、誰もできなくなってしまう。だからそう間をあけずにやっていかなければいけないんだよ。『伯母捨』だって、菊生叔父が数年前に百何十年ぶりに掘り起こしたわけでしょ。
明生 百何十年ぶりなんて言うことさえ、本来なら恥ずかしいわけですよ。
能夫 本当に。でもそういう曲目が言葉の上に載るようになった今の喜多流を喜ばないといけないよ。それは友枝さんのおかげだし、菊生叔父が頑張って道を開いてくれたということでもあるし。
明生 我々はプロなんですから、そういう曲がありながら知りません、見たことありませんではちょっと恥ずかしいですよね。
能夫 だから誰かがやらないとね。温存、温存では氷河期のマンモスみたいになっちゃうよ。飾ってある標本を見たってしようがないでしょ。生きているものを見なくちゃ。動いているものを見なくちゃね。
明生 で、『木賊』を能夫さんもやりたいでしょ。
能夫 それはそのうちやりますよ。
明生 そのときには、謡う要員になれると思いますよ。
能夫 それはできるさ。あれだけ頑張って謡ったんだからね。
明生 去年『卒都婆小町』やったのだから、今度は『木賊』を目指して下さいよ。一生懸命謡いますよ。
能夫 ウン、近い将来!
明生 今の喜多流の風潮からいえば、『卒都婆小町』、『木賊』という順序になっています、私はそれでいいと思いますよ。男役者が女に化けることより、男が男に、それも生にならずに頑なな爺に化けることの難しさはかなりのハイグレードと思いますからね。
能夫 その辺はシテというか、そこに生きる役者の思いみたいなものもあるんじゃないの?
明生 最長老クラスの曲ですよね。どっちを先にやってもいいと思うけど、足腰丈夫なうちにしないとね。
能夫 それはもう運命だよ。出会いだよ。昭世さんが一生懸命やった『木賊』を見せられると、それはよかったと思いますよ。
明生 食指が動く?
能夫 それはね。心の底では、いつか自分もという前提がないとね、自分の志というか思いがないと、謡っていてもしようがないわけでしょ。自分で引き取る覚悟があって謡わないと。
明生 今回、『木賊』というクラシックな単なる重習というベールに包まれていたものが、そのベールが引き下げられ我々の目の前に燦然と輝いたそんな感じですかね。
能夫 そうだよ。自分がやるときのための、今回が一つの助走だよね。僕ぐらいの年になるとそういう思いでやらないとやっていられないよ。
明生 私は謡っていても、『木賊』はまだ遥かかなたという感じですが・・・。
能夫 ないだろう?
明生 能夫さんにはあるだろうな・・・というのはわかる。やっぱり曲目が降りてくるという・・・。
能夫 降臨したというか、まさしくね。自分のところに降りてきた、近づいてきたというのは確か。そのためにやったようなところがある。
明生 そう。よかった、よかった。
能夫 もう、よくやったよ。自画自賛!あんな大曲をよくやったと思うよ。友枝さんの実力を認めざるを得ないというのがすごくあるね。あの人の稽古のすごさね。
明生 それはすごいよね。
能夫 それだけやっているすごさというのが、舞台にちゃんと現れているからね。
明生 それはもう、私が憧れるところで、師として仰ぐところですよ。ちょっと真似できないけれど。
能夫 真似できないけれど、僕たちは僕たちのやり方でやっていかないとね。
明生 真似できないけれど、私は能夫さんからもらった資料、伝書という鎧をまっとって、自分なりに目指すところに向かいたいんですよ。
能夫 それはいいじゃないですか。
明生 優秀なものに出会うとお能は面白いですよね。
能夫 ねっ。いいシテに恵まれて、いい形でできたね。こんな場に身を委ねてしまうと・・・、常にチャレンジャーというか、いいものに出会って吸収して、生き死にがあって、何かそうしたことを繰り返していかないとしなびていく気がする。天人五衰じゃないけれど、腐っていく気がするね。自分を駆り立てて、いいところにもっていかないと・・・。
明生 今、しなびるという状態ですが・・・ああ終わったなと思ってね。そしてさあ次と、気持ちを奮い立たせなければ・・・。
能夫 その気持ちを奮い立たせる意味でも研究公演があるね。
明生 私もいろいろな会を起こしてきました。妙花の会、花の会、そして研究公演もそう、でも長続きするのは研究公演。熟成させて、ブドウをワインにする力は能夫さん持ち前みたいで研究公演で、『柏崎』とか『弱法師』、『松風』とかいろいろな曲を勤めけれども、中でも特に誇れるものといえば、『求塚』や『木賊』で、我々が地謡を固めて一曲を創り上げたことですかね。
能夫 そういうことだろうね。それにしても囃し方の人たちも燃えてやってくれたね。みなさんのおかげですよ。『木賊』は総合力として、すごくいい舞台になったと思うよ。
明生 12月に能夫さんが帽子をかぶっていて、みんなに風邪をひくんじゃないぞなんて、激飛ばしてプレッシャーを与えてさ、地謡の健康まで気遣ってなんてことは異例中の異例なことよ。
能夫 それはそうよ。明生君が風邪でティッシュの箱なんか抱えて来たんじゃアウトだからね(笑)。昭世さんにも言ってたよ、お風邪は大丈夫でしょうね?って。
明生 健康でいろよ、一生懸命やろうよというメッセージが最後、舞台に還元されたのではないですか。
能夫 昭世さんともいろいろな意味で切磋琢磨できたし、みんなも100%の力を出して曲に取り組んでくれたし、これ以上ないよ。楽しかった・・・!
明生 そうですね。みんなが力を出し切ったことが実感できました。またやりましょう。
(平成18年1月4日 記 於 ガーデン)

研究公演つれづれ(その二)投稿日:2018-06-07
研究公演つれづれ(その二)
第2回 能夫『井筒』 明生『弱法師』(平成4年6月27日)
粟谷 能夫
粟谷 明生
笠井 賢一
明生 2回目の研究公演は能夫さんが『井筒』、私が『弱法師』を勤めました。
能夫 明生君は1回目に『弱法師』をやりたいと言ったんだよね。最初から『弱法師』でもいいんだけれども、それはやっぱり・・・。
明生 うーん、怒られましたね。
能夫 最初から『弱法師』では周りの印象も悪かっただろうし。僕も『野宮』を先にやって、これも勤める順番が違うと言われたけれど・・・。でもそれなりの覚悟が出来ている年齢だし、ある年齢を越えたらいいのではないか、自分の求めているようにやればと、心の底では思っていたんだけれどね。
明生 確かに順番はあるでしょうが、能夫さんの言う通り、ある年齢、30歳ぐらいかなーーを越したら、自分自身の能楽師としての道は自らが拓いていかなくてはだめですね。何をやったら次は何といかにもベルトコンベヤーのような選曲が果たして良いかは疑問です。やる人の意志や挑む曲に対する想いを深くして、誰かが「やりなさい」というのを待っていたり、誰かがやらないと出来ないという情況は、青年喜多会の時代で終わっていなくてはいけないでしょう。

能夫 僕の『井筒』は自分にとって大事にしていた曲であるし、二人でやる研究公演にはふさわしい曲だと思っていたよ。
明生 そうでしょう。能夫さんは小書「段之序」で勤めたかったんですよね。この「段之序」がちょっとした問題になりましたね。父に相談したら、「まずは小書無しでやるほうが無難だよ。能夫はまた次の機会があるから、その時にやればいいじゃないか」と言われて。周りの反対がある中、押し通してもどうだろうかと父は心配してくれたんでしょう。私達も納得して消極的になり、小書は無しにしてしまった。でも後で、能という演劇の可能性みたいなものを研究する自分たちの会なのに、思い通りにやらない、その理由が「初演だから」というのは、私には嫌悪感というか、ひとつの心の傷として残りました。「様々な試みを」のスローガンと違うじゃないか、それを自分がしてしまったという後悔に悩まされました。自分たちの思いをもっと強く理解してもらうまで粘ることをしていたら、この第2回の研究公演に「段之序」があったのにと。でもこの件で、舞台は二度と同じように演じるチャンスがないのだ、その一回その場に最善の取り組みを、という意識を持っていなければいけないと解ったのですがーーー。
笠井 「段之序」はそんなに魅力的ですか?
能夫 僕はそう思う。
笠井 どこが? 僕は「段之序」は一度しか見ていないけれど、あれが決していいとは思わなかった。小書の問題なのか、演じ手の問題かはわからないけれど。
能夫 「段の序」は、とても官能的なんですよ。
 笠井 どこが官能的? 「段之序」で決定的に変わるところはどこなの?
笠井 どこが官能的? 「段之序」で決定的に変わるところはどこなの?
能夫 通常は後場で後シテ(井筒の女・霊)が登場したすぐ後、業平の形見の直衣を身に触れて「恥ずかしや、昔男に移り舞」と謡い、それを地謡が受けて「雪を廻らす花の袖」と謡って、序ノ舞に入るところを、「段の序」では、ここを全部シテが謡います。「雪を廻らす花の袖」という言葉を序ノ舞の中に謡い込んでしまうのです。乱拍子の和歌のような世界を作り上げようというものなんです。ただただ囃子と合っているという安易な「段之序」ではなく、シテの意識が反映されるものを出したかった。
囃子が、ただきれいに流れていればよいというのでなく、いろいろな注文によりもっと大事に、何か違う世界を作り出すというような「段の序」のイメージがあったものだから・・・。
笠井 シテがあの部分を全部謡うということは、序ノ舞の質みたいなものを、自分の中に凝縮し、その凝縮力の中に納めやすいという感じですか?
能夫 それはありますね。
笠井 それならわかる気がする。以前見たものは、そういう感じがしなかった。僕はむしろ、シテと地謡が一つの和歌を共有した世界で、より一層透明度が高くなると思うな。和歌の構成からすれば、和歌の前半部分を自分が謡って舞に入り、後半部分も謡うというのは、ある種、正統な理論だと思うよ。でもそれを越えて、個人の生涯を越えて、もちろん井筒という個人の生涯には違いないけれど、もっと普遍性を持った女性の生き方、人待つ女の源泉みたいなものを、地謡がからんで共有していけばいいんじゃないかという気がする。あれを個人で全部謡うことは全然ないと思うな。でも、それを敢えてシテ一人で謡うことにするのは、どういう根拠だろうと思ってしまいますね。
能夫 地謡に委ねるのではなくて、自分に枠をかぶせていくというか、何かそんな感じがするんです。自分の発散もできるし、官能的にもなれる。マイナスは負わないと思うんだけれど。自分で和歌を謡いながら、非常に官能的な高みに引き上げられる、上昇できるという感じです。『道成寺』で、あの和歌を謡い爆発するようなエネルギーで急ノ舞に入っていく、あの感じです。だから、自分のイメージとしては急ノ舞がある。一つの演出として、それに近い序ノ舞があってもいいのではないか。
笠井 それはあってもいいね。それでその後能夫さん、やったの。
能夫 やっていないよ。
明生 その後「段の序」をやるチャンスは10年経っても無いのが現状ですよ。だから出来るときやらなければいけないということ・・・。
能夫 『道成寺』の、あのすごい急ノ舞になるエネルギーのもとで、自由に序ノ舞をやる。そういうことをやりたかったわけ、僕は。
笠井 それは知らなかったですね。でもあの時の『井筒』は能夫さんが永年特別の思いであたためて来た曲であることがひしひしと伝わって来た。それは菊生さんの地謡の中にも感じられました。すごく『井筒』の世界になっていたと思うな。数ある地謡の中で一番印象に残っていますね。
明生 あの井筒の地謡は、能夫さんが「井筒は菊生叔父に是非謡ってもらいたい」と熱望していましたね。
笠井 次は是非、能夫さんの「段之序」を見ないとね。僕自身は、地謡が「雪を廻らす花の袖」と謡っても全然抵抗ないの。その方がむしろ別の意味で、シテ個人だけに凝縮するのではなくふくらみが出ると思うから。でも能夫さんがそこまで熱く語るなら、いつか見てみたいね。
能夫 いつか、本当にやりたいね。でも、それには大小の鼓が謡を充分知っていて。僕の呼吸と合わせて囃してくれないとできない。
明生 ただポンポンと打つのではなくて、「雪を廻らす」で、ある勢い、力がないとね。
能夫 華やかに出てくれないとね。「雪を・・・」で官能的になって、急ノ舞のエネルギー で序ノ舞を舞うわけだから、同じ意識を持ってやってもらいたいよね。それはもう、次の楽しみにとっておくということです。
笠井 楽しみにしておきましょう。能というものはシテだけ良ければいいというものじゃないし、笛も鼓も地謡も良くなければね。地謡だって地頭一人良ければいいというものではない。僕がいつも思うのは、直球一本だけでは表現できないだろうということですから。
能夫 わかる、わかる。
笠井 あのときの『井筒』の地謡はすごく感動したもの。
明生 研究公演は最初、銕仙会でやっていたころは、地謡は前列三人、後列三人でやっていたでしょ。喜多能楽堂になってからは四人、四人になったけれど。三人、三人というのは謡っている方も緊張しますよね。だから良い謡ができたとも言える。
能夫 いいことだよ。最小集団でもやらなければという気持ち。
笠井 四人、四人だと、不協和音を出す人もいるし、逃げ腰になる人も出てくるし・・・。
明生 一人一人が自覚しないとね。

笠井 ところで明生さんの『弱法師』、一回目に止められて、二回目に実現したということね。そういういきさつは知らなかったけれど、思いをためていたということは感じられたよ。観世流は透明度高くやるけれど、明生さんのはちょっと発想が違っていた。ある意味では写実的というか、リアルで生々しい、その鮮度みたいなものを僕は感じました。観世流は透明さとか純真さとかいうけれど、ただきれいごとで終わってしまうこともありがちですからね。
能夫 そらぞらしくなる場合がある‥‥。
笠井 それが彼のはね、「満目青山な心に有り」の場面で、左手を上げ山や月を描く、手の動きのいい型があるじゃない、そこに盲目の人間の「焦れ(じれ)」というかリアリティがあって、すごく鮮烈だった。それが忘れられないですね。観世流も同じ型をするけれど、ちょっと違う。焦れがないんだよ。
能夫 弱法師が自分自身に腹を立てるというか、心が波打っているというか。
笠井 何でこの年で、盲目にならなければならないんだという「焦れ」があって、そのエネルギーで突っ走っていくような感覚。そのところが、明生さんの場合すごく鮮度があった。『弱法師』の本質はあそこにあると思う。
明生 何故、この曲に執着していたか、どうして第1回目にやりたかったのかは、『弱法師』の精神性みたいなものの修得とはまた別に、他方では、技、型の早期修得の意味があったんです。『弱法師』には長年培ってきた、シカケ、ヒラキでは対応出来ない部分が多々あると思います。盲目の杖の扱いから始まり、謡い方、身体の動かし方と今までの意識とはちょっと違う感覚のてんこ盛りなんです。ですからいい大人になって、いざ弱法師を舞うとなったとき、「あれ、変だな、なんだかいつもと違うぞ」となってしまう。失礼だがその失敗例を沢山見ていますから。だから父にも、友枝昭世師にも、早く習っておきたい、悪い言い方ですが、早めに盗んで、自分のものにしておきたいという気持ちがありました。それに私の意識の中には背が丸く、腰が折れ曲がっている弱法師像は似合わないという思いがありましたから。とにかく、早めに仕掛けておきたかったのです。 あのとき石田幸雄さんがアイで出てくださったのですが、あのアイは最初にちょっとふれをしたら、最後の送り込みまで、何もなく、ただアイ座で座っているだけですから、「送り込みしなくていいですから、先に楽屋に入られて狂言のお支度を‥‥」と申し上げたのですが、最後までアイ座で座って見ていてくださった・・・。
能夫 研究公演を二人で始めたというので、見てくれたんだろうな。
明生 そして、後の反省会の席で、石田さんが「『弱法師』、面白かったよ。オレは後ろからずっと見ていたからな」って言ってくださった。そのことが嬉しくてよく覚えているんですよ。やっぱり身内とはちょっと違う、内輪の人にしっかり見てもらうというのは嬉しいですね。
笠井 そういう人に誉められるというのは一番大事だと思いますね。
能夫 嫌だったら、「俺もう帰る」となるわけだからね。面白かったよと言ってくれたというのは嬉しいことですよ。
(平成13年5月 記)
写真
井筒 弱法師 撮影 あびこ
笠井賢一 撮影 粟谷明生
我流『年来稽古条々』(11)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(11)
青年期・その五『道成寺』まで
粟谷能夫 粟谷明生
明生?先回の第10回では『猩々乱』被き以降ということで、能夫さんの『大会』『半蔀』『小鍛冶白頭』それから私と二人でやった『二人静』まで話しました。その頃は年に二番という演能で、ハングリーだったな、というのが結論でした。当時、せめて年五番は舞いたいと話していた覚えがあります。
能夫?この頃が寿夫さんの能を一番たくさん見ている。だってこの頃暇だったもの、弟子を教えているわけではないし毎日午前、午後と喜多実先生のお稽古にいったら夜はフリーだから。
明生?思い出すのは、毎朝まず実先生が一番能を舞われたこと。それも何を舞われるか分からない。困るのは出てこられるのがやや遅いときで、そんなときは『定家』とか私の知らない重い曲で……。そうなるともう謡えないので私はただ見ているだけでした。
能夫?いいときだったよね。稽古してくださったもの。それがべ?スになってるものね。皆で稽古したからそれが皆の共通項になっているということは凄いことですよ。今の喜多流のベースですよ。
明生?金春流の桜間金記さんと仙台の演能でご一緒したとき「僕が知っている喜多流の人達は、皆共通の感覚があって、赤は赤といえる年代だね」と仰っしゃられたことを思い出します。金春流では誰かが「赤」と言っても「いや紫だ、桃色だ」と、違う感覚を持たれている方がおられるということでしょう。それに比べると確かに私達は基盤が一つという事はあります。例えば『土蜘蛛』のツレの謡が「重い」と誰かが注意すると、皆そろって「そうだ、重い重いよ」となる。でも金春流では「えーそうかな、そうは思わないがねー」という人がいるということらしいです。私達は喜多実学校というところで、皆が同じ意識を持たされ、共通項で育った影響でしょうね。これが良いのか悪いのかは別として、求めている美意識が一つだったような気がします。
能夫?これは幸せなことだよね。それで僕は昭和53年に『黒塚』を勤めました。寿夫さんが亡くなった年。
明生?能夫さんが『半蔀』を演じた頃からですかね、青年喜多会のあとの反省会に私も呼ばれるようになっていまして、会の反省や仲間同士の批判とかいろいろ話されていました。私は未だヒョッコでしたから、もっぱら聞くだけでしたが・?。
能夫?その頃はもう先輩たちは青年喜多会を卒業していて、僕や出雲康雄さんがリーダーシップをもってやりはじめた。
それでただ能をやりっ放しでは駄目だということで、反省会を始めたんだよね。
明生-鍋屋横町の寿司初という、山本東次郎家御用達みたいな寿司屋で、目黒から遠かったけれどよく行ってましたよね。残念ながら今はもうありません。ニューヨークでやっているようですが…。
能夫-その頃からだよね、僕が銕仙会の影響を受けて、舞台に対して、集団としてこんなふうにしたいという主張をするようになったのは。僕にとっては革命的なことだったからね。
明生-私の意識が変わって来たのもその頃からですね。青年喜多会というのは自分たちの会という意識が強かったから、四番立で三番も地謡がついても、へこたれなかったし、同人皆が舞台にも自発的積極的に取り組むようになり、例えば地謡で疲れていても「凛々しくきちっと座っていよう」という意識に目覚めて、「背中丸めてだらしなく座っている人なんて、他流の同じ年代の人にはいないものなー、頑張ろう」をスローガンのようにしていました。
能夫-その頃は地謡の座り方にしても、扇の持ち方にしてもそれぞれ違っていたり、だらしのないところがあったものね。皆がNHK・TVの能の収録のときは咳もできないというように緊張して座っていたり、『道成寺』のときならやはり皆がピシッと背中を伸ばして座っている。そういうことが特別のときだからというのではなく、日常のことでなくてはいけないということだよね。寿夫さんが亡くなったのが12月7日で『黒塚』は16日でしたから、すごく寿夫さんのことを意識して舞台に立ったことを憶えている。
明生-その後、能夫さんは寿司初で嘆かれてましたよ。「どうしてあんなに大事な人が早く亡くなるんだ」ってね。
能夫-僕の思いでは、『道成寺』の前哨戦として『黒塚』になったという感じはなかった。僕が『造成寺』をやるというので実先生がつけてくれたのかもしれないが…。「祈り」というものを経験しておきたかったという思いはあったね。
明生-私は青年喜多会で『紅葉狩』を勤め、それから「粟谷能の会」で『黒塚』をやって、それから『道成寺』でした。『紅葉狩』で急之舞を体験し、『黒塚』で祈りをやり、出来れば『葵上』もやっておくのがいいのかも知れませんが-。まあ『葵上』は『道成寺』の後の方がよいと今では思っていますが。
能夫-それは皆の経験から、そういうことをやらしておいたほうが良いという方向性が出て来たんじゃないかな。寿夫さんを追いかけていた頃は、能の本質を十分に理解していたわけではないし、全てが見えていたわけではないと、今にしては思うね。舞台から伝わってくる衝撃波の強烈さと、能を創っていくための仕掛けとか考え方、姿勢といったものを教えてもらった。あとは自分で考えなさいという事だったと思う。そういうとっかかり、経験があったからこそ今日があると痛切に思うね。
つづく
『半蔀』「立花供養」を語る1(H16/10/13掲載)投稿日:2018-06-07
横浜能楽堂特別公演 『半蔀』「立花供養」を語る
平成16年9月11日、横浜能楽堂特別公演で、『半蔀』「立花供養」が催されました。番組は川瀬氏の講演「花の心 能の心」から始まり、狂言『萩大名』、立花を出して、能『半蔀』「立花供養」と続きました。
舞台が終了した後、出演者の川瀬敏郎氏、山本則重氏、そして私、粟谷明生、演出家の笠井賢一氏、横浜能楽堂の中村雅之氏と大いに語り合いました。よいお花を立ててくださった川瀬氏には恐れ多い思いがありましたが、気さくなお人柄で、ざっくばらんにお話がはずみました。この会を企画してくれた横浜能楽堂の企画仕掛人の中村氏、私と川瀬氏を結び付けてくれた笠井氏、新進気鋭、将来が楽しみな山本氏、話はとどまることを知らず・・・。

(1)はじめに
中村 今日は満席、雰囲気もよくて、よい会になりましたね。
粟谷 満席でも、あまりぎゅうぎゅう詰めとは感じませんね。ゆったりしている感じにこちらからは見えましたが…。私は横浜能楽堂で舞うのは初めてで、音の跳ね返りがいいですね。
中村 でも先生、うちの舞台には地謡などで散々出演しておられるではないですか。
粟谷 面をかけて舞台に立つのは初めてですよ。面を通しての感覚は違いますからね。声の通りはいいよね、びっくりするくらい。もっともお囃子方とは意見が違うようだけれど…。
中村 先生にお願いする曲がなかなかなくて、それで8年間待って、今回は満を持してお願いしたわけです。
粟谷 ありがとう。待っていた甲斐がありましたよ。(笑い)
中村 気持ちよく舞っていただいて、私も8年間待った甲斐がありました。
粟谷 笠井さんがまだいらしていないから…、きっと後からご批判をいただき、駄目だしが出ると覚悟していますけど・・・。(笑い)
中村 笠井さんには本当に感謝しています。川瀬さんを説得していただいて…。
粟谷 笠井さんにも、中村さんにも本当に感謝していますよ。私は本当にやりたかったから。
中村 よかったですよ。そういっていただけると。
(川瀬氏が少し遅れて登場)
川瀬 すみません、遅くなって。後片付けに追われているうちに。花って、最初にやらなければいけないのですけれど、後片付けがあって最後になってしまう。でもまあ無事終わってやれやれです。
粟谷 本当にありがとうございました。
川瀬 いや、本当に。どうなるかなんて、昨日まで心配していたんですよ。
中村 お客様の雰囲気もよくて、よい会になりました。
川瀬 それはよかった。
粟谷 周りの方に恵まれて、本当に!!(笑い) ありがとうございました。(笑い)今日もお客様がなかなか帰らなかったですね。橋の会のときもそうでしたね。
中村 終わった後、立花を見てもらうということで30分ほど時間をとっていますからね。それが楽しみという方も多かった。私自身、国立能楽堂で拝見したときも、終わってからお花を近くでじっくり見せていただきましてよかったですから。
川瀬 脇正面や中正面にいた方に最後は正面で見てもらわなければならないので。だから、中入りでお花を下げてしまう場合は、脇正面や中正面におられた方はほとんど見られないことになりますね。
粟谷 ペンギンみたいに前のめりになって熱心に見入っておられた方がいらしたけれど、わかる気がしますね。
川瀬 終わってからいろいろな質問を受けましたが、人それぞれでおもしろいものですね。
粟谷 どんな質問ですか。
川瀬 最後、立花の花の真を抜いて見せるのではないですか、そういうのを本で読んだことがあるんですけれど…とか。一番多いのはやはり花材の質問ですね。あと、こんなに長い素材はあるのですかとか。
中村 やっぱりいろいろ興味があるのですね。
粟谷 川瀬さん、「立花供養」のお願いのお話をしたのは覚えていらっしゃいますか?
川瀬 1年ぐらい前ですね、このお話をいただいたのは。その前に橋の会があって。
粟谷 橋の会のその日ですね。ちょっとお願いがありますと申し上げて…。
川瀬 そうでしたね。
粟谷 お花を片付けた後の、お疲れの時にこの話でしたから。(笑い)
川瀬 去年の7月でしたね。
中村 「立花供養」を川瀬さんとやろうと話を持っていこうとし、橋の会のチラシを見て絶句してしまいましたよ。
粟谷 実は橋の会の打ち上げ会に私も同席することが出来て、その後に、笠井さんに川瀬さんと合う機会を作っていただき、青山のコジャックで川瀬さんにご馳走になっちゃいましたね…。
中村 それで実現できてよかったですよ。
粟谷 川瀬さんは、やっと終わったという日だったから、ちょっと食傷気味だったでしょうが、笠井さんが口説かれて。
中村 僕も企画としては二番煎じになるのではないかと。真似をしたと思われるのは嫌だなというのがありました。
笠井 客層も違うわけでしょ。
中村 客層も違うし、演者の組み合わせも違うし、これはもう内容を転換しなければならないと思いました。
笠井 川瀬さんは今回で「立花供養」は6回目ということになりますね。
川瀬 そういうことになりますか。最初はカザルスホールで浅見真州さんとでした。あれも笠井さんに頼まれたのでしたね。
笠井 そうね。それから名古屋で2回、片山九郎右衛門さんと大槻文蔵さんと一緒で。そして去年の橋の会の二日連続公演で、梅若六郎さんと友枝昭世さんと。そして今回で6回。
中村 真州先生、九郎右衛門先生、大槻先生・・・。
笠井 大物だねえ。
中村 六郎先生、友枝先生、そして粟谷明生先生。
粟谷 ガーン。(笑い) だから私は時分の花といったでしょ。川瀬さんは真の花だけれど。
笠井 だから、僕はチラシに「粟谷明生が川瀬敏郎の花との立ち会いで、いかなる真の花を咲かせるか、刮目して待ちたい」と書いたんだよ。
中村 あのコピーは二番煎じにならないための仕掛けでもあったんです。
笠井 川瀬さんが「立花供養」を6回やってきたわけだけど、僕が鮮烈に覚えているのは友枝さんと六郎さんのでやった、蓮の立花供養ですよ。川瀬さんとは長くおつきあいしているつもりだけれど、ああ、変わったなと思った。ある種、その年々で更新している、つまり同世代だからわかるのだけれど、この世代で更新しなければいけない位置にいて、それを見事に成し遂げているなという感じがした。
川瀬 徐々に変化はしていますよね。
笠井 その緊張感はすごく感じましたよ。
粟谷 私も橋の会の2日目を見せてもらいましたが素晴らしかった。あの橋の会の2日間にしても今回の会にしても、ああいうものだったら自分もやってみたいなあーと、喜多流の、いや他流の若い人たちにも大いに刺激になったと思う。憧れみたいなものをみんな持ったと思いますよ。
川瀬 そうですか。それはありがたいな。
(2)横浜能楽堂に合う「秋の草」
粟谷 今日の立花は、真ん中にススキがすっくと立って、下に桔梗や女郎花などの秋の草花をあしらう感じのお花でしたね。
川瀬 今日のは、秋の草をどうやってやろうか、いろいろ考えたんですよ。横浜能楽堂は舞台自体が瀟洒なんですね。秋の草が一番似合う舞台だなと思いました。たとえば国立能楽堂ですと、ああいう秋の草では、とてももたないと思うんですね。きっと世界が違う。そういう意味では場というものがすごく大きい。
笠井 本当、場ととても合っていた。場とこうなじめるというのは、ある年輪だね。
川瀬 そうですね。先日、8月に能楽堂を見せていただきましたが、思いがけないほど瀟洒なんだなと。これは上に硬いものが来たのではしんどいなと思ったのです。
粟谷 鏡の間から舞台を見ると床の新しい感じ、私は白さが気になるんですよ。歩み(運び)易さは問題無いのですが、どうもあの白さが本格志向で思うと引っ掛かると。でも演じているときにはわからなかったのですが、終演後、見所にまわって拝見して、改めて感じたのは、あの鏡板の松の色とか、屋根の色、あのちょっとこげ茶っぽいあの色がとてもいいんですね。あの色、とても落ち着くんですね・・・。あの鏡板の年季がかかった風合、本当にいいですね。そこにまた瀟洒な秋の草花でしょ。すきがないという感じですね。
中村 その点は得しているところですね。川瀬先生がおっしゃったように能楽堂全体が瀟洒な感じというのは。あれ、誰が設計したかと思うんですが、前田斉泰の趣味というか、個人的な耽美主義が全部でているのかなって・・・。
川瀬 西本願寺の舞台などですとしっかりしていて、本願寺の建造物の柱に匹敵する真を立てますが、こちらの能楽堂はどちらかというと江戸末期の独特の雰囲気といいますか・・・。
中村 そうですね。しゃれたというか。言い伝えによると、前田斉泰が知らないうちに家臣が作ったなんていいますが、あれは前田斉泰自体の幕末の大名の好みかなと。
川瀬 幕末の絵というのもだいたい、ああいう小ぶりのものですよね。
中村 お洒脱な感じですよね。
川瀬 そういう意味で言えば、時代の嗜好というのが大きいかもしれないですね。見に来てくださった方で、懐かしい舞台だとおっしゃった方がおられました。
粟谷 あの昔の染井能楽堂をご存知なのかな。(横浜能楽堂は染井能楽堂を移転したもの)。私は金春惣右衛門先生が住んでいらした時の事をまだ覚えていますよ、あの舞台の桟敷席で金春国和さんと追っかけっこしたんだからね。
(3)狂言『萩大名』について
笠井 則重さんは『萩大名』のシテは何度目ですか。
山本 2度目です。
粟谷 今お年はおいくつですか。
山本 27歳です。
中村 少し早目ですかね。
粟谷 そんなことはないでしょ。
山本 大体今までは東次郎がシテをやって、僕たちが冠者や亭主をやるんですが。
笠井 僕、いいと思ったよ。本当にいいと思った。
山本 舞台から戻ってきたときに、東次郎が僕がシテをやったときは父親が亭主でおじいさんに太郎冠者をやってもらったんだと言っていました。今日は東次郎が太郎冠者で僕の父が亭主ですからね、だんだん、そういう風に逆の立場になっていくって。
笠井 そうなっていくね。泰太郎さんは何回もやっているの。
山本 やっております。
笠井 あなたは酒を飲まないと聞いたけど、そういうこともあるのかな、その分酒を飲むという演技により自覚的でそういう意味で東次郎さんの資質に似ているなあという感じを持った、僕は。
山本 ああ、そうですか。
粟谷 だって、東次郎さんに習っているのでしょ。
笠井 そうだけれど、資質はみんな人それぞれだから。泰太郎さんとか、みんなそれぞれ違うから。何となく、ちょっとそういう思いがあったなあ。
山本 私も、山本の若い者の中では、東次郎先生の精神性に一番似ているとは思います。
笠井 泰太郎君が直球を身に受に付けていて、直球勝負の気持ちよさ、スピードで勝負しているみたいな感じがするけれど、東次郎さんはそうじゃないわけよね。今や、あなたはその東次郎さんのそういうところを受け継ぐ資質を持っているのかなと、ちょっとそう思ったけどね。
山本 そうですか。
笠井 流是としてはあまりよくないのかもしれないけれど。東次郎さんやあなたは台本をちゃんと読もうとしているというか、役の位置を考えようとしているなというのがあるわけ。それが流儀の決まりの中でバランスをとっていくといいなと思いました。今日の舞台はあなたの親父さんと東次郎さんと、両方がうまく支えてくれていたし、あなたがとてもよく見えた、本当に。
川瀬 よかったじゃないですか。
中村 東次郎さんの論理的な部分は則重さんが一番受け継いでいますね。
山本 稽古のときにそういう感じですから。
笠井 東次郎さんはすごく台本を読んで考えている人ですよね。
山本 理詰めですからね。
笠井 そうしたこともやっぱりやらないと。山本家のよさは一杯幅があるけれども、その中の一つ、東次郎さんがずば抜けているのはそういうところもあるから、それは受け継いでいく人がいないとね。それは僕は思いますよ。
中村 東次郎先生がやっていることを、若い人はバラバラのキャラクターでやっているから。それを合体すると東次郎先生になるのかなと。
笠井 そうね、全くそう。
中村 今、笠井さんがおっしゃったけれど、則孝さんとか泰太郎さんはまさに直球でやってくれる、論理的なものより、とにかくやると。それが東次郎先生は考えてやると。その部分というのは・・・。
笠井 ただ、その部分は40過ぎてからやれと、親父さんに言われたんでしょ。
山本 60ですよ。道は長い。
中村 まだ30年ある。
笠井 だけど僕はやっぱり、そういう感覚を20代で持っていない人は40代、50代になってもなかなか行かない、行かないままで終わってしまう人が多いと思うのですよ。そういった意味で、こういうものは大事にしてほしいと思うし、しかしやっぱり直球の大事さね、お宅の流儀でいえば語りの大事さみたいな、まっすぐやる強さみたいなものも大事にしてほしいし、それがそういう風に変わっていく時間と、その幅を共有してほしいなという気がしたなあ。
山本 ちゃんと見ていただいて・・・。
川瀬 笠井さんのそれ素晴らしいね。やっぱり資質というのは、若いときにないと本当に花開かないと思うんです。
中村 今回狂言を、今のタイミングで則重さんにお願いしたというのはそれなんですよ。それはもうチラシに書いていただきましたけど。
笠井 馬場(あき子)さんのね。
中村 今まで則孝さんがすごく伸びたとき、泰太郎さんがすごくよかった時期、あるとおもいますよ。それはそれでいいけれど、山本若手の4人の中で、今盛りなのは則重さんかな。ここ1、2年すごくよくなってきたから。
笠井 役ついているしね。
中村 だから役がついているんですよ。
川瀬 伸びる時期というのはあるんですよね。
笠井 停滞する時期もあるからね。(笑い)
山本 厳しいお話ですね。
川瀬 粟谷さん、停滞したと感じられることもありますか。
粟谷 今日、停滞しちゃったんじゃないかな・・・。(笑い)
中村 今日停滞されると、こっちが困るんですよ。(笑い)
川瀬 本人の自己申告というのはあてにならない。本人が停滞していると思っているときによいものができているときもあるし、すごく自分でよくできたと思ったときの方が・・・。
粟谷 悪評ということもありますからね。「どこが悪いんですか」「それが分からんのか、お前は。もうちょっと考えろ」なんてね。
川瀬 それはありますね。
笠井 役者はなかなか自分のことは見れないよ。
粟谷 段々、年を取ってくると、自分で自分を見るしかない。60を越したら誰も注意してくれなくなりますからね。恐いですね。本当に言ってくれる人がいなくなると。
中村 先生には、ちゃんと笠井さんが言ってくれる。
粟谷 笠井さん・・・・・・。
笠井 今日はしっかり見たからね。(笑い)
粟谷 あとが怖いな…。(笑い)
(4)昔の「立花」は天こ盛り
粟谷 今日、川瀬さんが立てられているところを拝見しながら、喜多流の健忘斎の頃の伝書をお見せしましたよね。ここに書いてあるのはお花がてんこ盛りで野暮ったくないですかと申し上げたら、そうですねって・・・お答えになられて・・・。
川瀬 伝書によると、すごくたくさん入れるものなんですね。びわの葉35枚とか。
粟谷 熊笹何枚とか。
川瀬 もうこうなると、本願寺の仏花ですよ。
笠井 そう、仏花。それが原点ですからね。でっかいね。
川瀬 でっかいですよ。仏様に供える物みたいに、もう詰めて詰めて、山のよう。僕はびっくりして見ているんですけれど、こういうのをおやりになったことはあるのですか。
笠井 僕が昔写真でみたものは、全部こういうのでひどいものだった。今度忠実に再現してみたら。
粟谷 いかに馬鹿げたメニューかということですよ。でも、この我が家のこの伝書はちゃんとしたものだからなあ…。
笠井 健忘斎という人はどの時代の人なの。
粟谷 江戸中期ですよ。喜多流としては一番充実していたころ。それ以前はまだ固まっていないし、それ以降は書き留めるエネルギーがないから、伝書といえば、もうこれに極まりますよ。
川瀬 花を塊のように入れていますよね。よくこんなに重ねて入れられるなと思って。菊が入り、熊笹が・・・。
粟谷 20本とかですね。
川瀬 こんなに入れたら、至難の業だと思ってしまう。粟谷さん、こんなに花が入ったのをご覧になったことはあるのですか、『半蔀』で。
粟谷 1、2回あります。伝書には立花を挟んで運ぶ木製の道具が書いてあり、後見二人が立花をはさんで持っていくんですが。私が見た時は直に持っていました、水を垂らさないように。ピチャピチャと音がしたりして。
笠井 すごく大きいから不安定だね。
川瀬 見ていて危ない。だって、上が化け物みたいに大きいんですよ。水も入っている?
粟谷 入っていた時あります。放せばバチャーとなるから危ない。(笑い)
(5)今回の「立花」の工夫
粟谷 今回はそんな風に天こ盛りではなく、瀟洒な秋の草ということでしたが、やはり後見が持って出るのは難しいですね。川瀬さん本人が持って出てられるのがいいですよ。でも、あれ大変でしたでしょ。橋掛りが低いから、かがんで持って出なくてはいけないから。
川瀬 後見の方が運んでもいいのですが、真が崩れるとね。
粟谷 せっかく拵えたのに!となりますよね。あれはやっぱり拵えた人でないと運べないなあ。
川瀬 そうなんですよ。途中に曲がっても自分だったらだいたいの筋がわかりますから直すこともできるのですが。昔のものもかなりズレることはあるんですね。だからズレないようにガチガチに打ち付けてあるのが多いです。幹造りという手法の立花なんかは全部打ち付けてありますから。それならただグーッと持っていけばいいんですよ。今日のような草ものはズレ始めたらもう直しようがないので、ちょっと恐いんです。
粟谷 お花は本来、前場だけに置いて中入り後に後見が引くのが決まりなのです。立花供養をするのは前場の紫野・雲林院で、後場は五条辺りと場所が変わりますから。でも、今回はせっかくの素晴らしい立花、すぐに引っ込めてはもったいないし、後見が持って入るのは至難の業(笑い)で、最後まで舞台に置く形となりました。それにシテの型としては造花の夕顔の花を一輪シテが持って出て、立花に挿すのですが、完成された立花にはできませんので、それもやめました。
中村 昔のことを知らないから、そういうことの方が意外な感じがしますね。今の感覚からすると考えられない。
笠井 以前は舞台の上で実際のお花を立てられるということもあった。40分から50分、それは時間がかかって、かかって。
中村 40分なら早い方ですよ。館長に最初に聞かれたんですよ。立花だけどどうするんだ?って。立ててから持って出てもらいますと言ったら、それがいい、最初から見たら見ている方も大変だよというような話をしたのです。
川瀬 名古屋の能楽堂では最初から(お客様が入る前から)舞台に出しておきましたね。階(きざはし)から持っていって正先に置きました。お能の前に、今日のような狂言がなかったのかな。
粟谷 それはお能一番だったのでしょう。
川瀬 名古屋のときは、そうそう狂言はなくて、馬場あき子さんのお話がありました。
研究公演つれづれ(その三)投稿日:2018-06-07
研究公演つれづれ(その三)
研究公演第3回(平成5年5月29日)
テーマは地謡の充実
粟谷 能夫
粟谷 明生
笠井 賢一
明生 第3回の研究公演は、メインが能『求塚』。友枝昭世さんにシテをお願いして、我々が地を勤める、地謡の再考と充実をテーマにしてみようということになりました。
しかしそれだけですと、我々は地謡だけになってしまいチケットも売り難いという事で、何か舞おうよということで、私が『松風』の舞囃子、能夫さんが『知章』の仕舞をすることになったのです。ほかに、菊生の仕舞『谷行』素抱という珍しい小書き演出と、石田幸雄さんらによる狂言『抜殻』という番組でした。
 能夫 そうそう、僕は『知章』を舞ったんだ。
能夫 そうそう、僕は『知章』を舞ったんだ。
明生 これまでの研究公演は年1回でしたが、3年目には年に2回催したいということで、3回目が5月喜多能楽堂、4回目を11月、また銕仙会能楽研修所に戻り催したわけです。3回目の『求塚』は友枝さんがまだ舞っていらしてなかったということもあり、我々が謡いますからまず最初は私達の地謡でとお願いしたわけです。
能夫 これは画期的なことだったよね。主催者が地謡を謡うからと言って、シテを他の人に頼むというのは。普通は、自分たちの舞台の場を多くもちたいから会を起こすわけですから。でも、そのときのテーマは地謡の充実だからね。あの会では菊生叔父が元気ですばらしい『谷行』を舞ってくれたけれど、菊生叔父にしても、昭世さんの次に来る地謡の人材を考えておきたかっただろうからね。
明生 そうですね。それで我々が地謡をしっかり見直そうということになった。『求塚』では、申合せの前の下申合せをすること、というのが昭世さんの条件でしたから、早めにとりかかりました。
能夫 下申合わせは寒いときだったね。
明生 小鼓の北村治さん、大鼓の柿原崇志さんに、君たちのいいように打つから、こうしてほしいということを言ってくれと言われて・・・。
能夫 我々のことを意識してくれたんだな。
明生 そう。こちらが謡うように打つから、という感じでね。
能夫 結果的にはどうだったかな?
明生 いや、本番になったら、治さんも崇志さんも自分たちの世界を創り打ってこられたし、こちらはこちらで頑張るという感じで。その葛藤がよかったのだと思いますが。
能夫 そういう引っ張り合いというのが必要だな。囃子方は先輩であるけれども、能をシテ方だけでなく、地謡を含めた全部で創り上げていくという我々の考え方に対応してやろうということだったと思うよ。本当は一番でも多く舞うというのが、研究公演をスタートさせた前提だけれど、能をつくるには地謡が重要ということに気づくことが、大事ということだった。菊生叔父に謡ってもらう、昭世さんに謡ってもらう、では、その先はどうなのかといったとき、地謡を謡える人材がどうあるべきか、ということに思い至ったということだよね。
笠井 僕はあのときも、お二人の話を聞いて、研究公演のプログラムの主催者からの一言みたいなものを書く役をしたわけだけど・・・。確かに 、地謡を課題にするというのはいいことだと思うよ。僕はいつも言っているように、能は地謡が7割を担っている、だから、そこからやるのは当然だと。
能夫 そう思うね。当然のこと。
笠井 地謡の充実を喜多流でどうするかを考えることは必要ですよ。その意味で、二人がこういう機会をもったということは頼もしいことだと思う。
能夫 地謡は、地謡を謡うのだという志がないといけないね。ただ地謡の役がついたから謡うというのではなく、覚悟のことですよ。ただつつがなく、間違いなく、そこそこに謡えばいいというのではなく、やはり、シテの思いを受けるという想像力がないと成立しないということを、あの場で思い出していましたよ。
明生 その後、大阪の大槻清韻会自主公演で、父が『求塚』を舞ったとき、幸雄伯父と能夫さんと私と、そういうメンバーで地謡を謡いましたよね。そのときちゃんと手ごたえを感じられた。あの経験がなければ、対応できなかったと思います。やはり研究公演でしっかり挑んでおいたのがよかったと痛切に感じましたね。
能夫 それから、申合や下申合を経験して、お囃子方からいろいろ言ってもらえたのはよかった。治さん崇志さんたちの胸を借りるという感じだった。
明生 治さんからは「死ぬ気で謡え」って。あの言葉は心に残ってますよ。
能夫 「それさえ 我が咎に・・・」のところだっけ?
明生 あれは宝生閑さんに言われた。「どうして、あの前に力が入り過ぎるの」って。「シテがワキに詰め足で、すがる大事なところ、地謡はエネルギーを持って謡わなければいけないのに、そこでくたびれているよ」って言われ、なるほどと思いましたね。大阪の『求塚』の時、父が「いざとなったら、代わってくれ」と言うので、自分でもシテができる 体制で稽古をしていましたが、稽古でシテをやってみると、そのことがなるほどとわかるんですね。 地謡は「これを最後の言葉にて、から、刺し違えて空しくなれば」ばかり一生懸命謡って、力を使い果たしてしまう、その後に「それさえ我が咎になる身を助け給え」が本当は大事だってことをね。閑さんに言われたこと、これもをよく覚えています。
笠井 地謡は永遠の課題なんだろうね。能役者として生涯の課題。シテの課題と対等に意識すべきだね。
能夫・明生 そうですね。
笠井 地謡を謡いながら、シテをつくっていく、全体を自分の中に呼び込んでいくという意識がないとね。
能夫 それは絶対そうじゃなければと思うよ。だから恐ろしいというか、楽しいというか。とにかく地謡に興味を持たないとダメだよね。
笠井 曲全体を創造する喜びだよね。シテは演じていていい気持ちになるだろうけれど、曲全体を支え、ドラマを支え、感動をつくり出すのはやっぱり地謡だよ。
能夫 そこに自分の感覚をぶつけるというか、エネルギッシュに、命がけでやることだよね。
明生 あのときは、本当に一生懸命、それこそ死ぬ気で謡いましたよ。(笑い)
能夫 そうね。それがよかった。それにしても僕は、地頭の隣で自由に孫悟空みたいに、お釈迦様の手のひらで遊ばしてもらい、そこでワープしたりして、いろいろ楽しむっていうのが性にあっているなあ。
笠井 それはそうだけど、そうはいかない立場になっているんだよ、お二人は。
能夫 でも、あの『求塚』はすごく印象深いものになったよね。親父や先輩の能を見てきて、いろいろ経験があったからやれたということもある。能をつくるということが、地謡でもアプローチできるということ、地謡がバックボーンになっていなければ能は成立しないことがわかった。
笠井 地謡を好きでない能楽師は、結局、能を好きじゃないんだよ。
能夫 そうみたいですね。
笠井 リサイタルで、自分でお金出してシテをするような、お殿様になる瞬間だけが好きというのは、能全体を愛していることにならないと思うよ。
能夫 わかりますよ。
明生 それはものすごく理解できますよ。
能夫 それに地謡は一人ではできない。地頭はみんなを集結させ、全体をコントロールしなければいけないし、逆にみんなに助けてももらわなければならない。そういういろいろな要素が必要でしょう。
明生 自分が謡うだけではダメで、地謡全体で一緒に味わう、謡わせる、地謡の人間をその気にさせるような雰囲気を創る。
能夫 謡にはエネルギーがいる。中途半端では、「なんだ、彼奴は」になるしね。みんなの躍動感もいるし、そういうことが体験できてよかったんじゃないですか。
笠井 それで、能夫さんの仕舞はどうだったの。
能夫 僕が舞った『知章』という仕舞ね。床几にかけて舞うんですよ。床几にかける仕舞というのは『知章』と『頼政』ぐらいです。僕が子供のころ、実先生だったかな、仕舞で床几に座る姿が格好いいと思ってね、それで、あのとき実現したということかな。
明生 あんなときでもなければ、なかなかできませんからね。
能夫 ひと風情として、衰退していたものをみんなの目にさらすのもいいかもしれない、一つの捨て石のようなものでもいいと思った・・・。
 笠井 明生さんの舞囃子『松風』は?
笠井 明生さんの舞囃子『松風』は?
明生 『松風』を舞ったのは、そのうち能でやりたいというのがありましたから。能を勤める前に、囃子どころぐらいは先輩に心得を聞いておいた方がいいと思ったのです。囃子の稽古は、何か目標を設定しないとなかなかできませんからね。『砧』のときもそうでした。『砧』のキリの囃子を自分自身でやっておかないと納得しないというのがあってやらせてもらいました。『歌占』の舞囃子もそうです。『松風』の舞囃子はそれらのはじまりですね。
笠井 その後、お能の『松風』はいつでしたか。
明生 その2年後かな。決めていましたから。基盤みたいなものを一つずつ積み重ねて創っておく、若い時は親や先生がある道筋を導いてくれますが、大人ではそうはいかない、自分で開かなければ。これは玄人の能楽師としては当たり前のことだと思うし、それをやりたかっただけです。私は、いつまでも他人に言われたり、他人が演じると自分もと動いている人たち、彼らを素人の能楽師だと考えていますから。
能夫 ちょっと話が戻るけど、『求塚』では、昭世さんと菊生叔父のちょっとした『求塚』の取り組み方、考え方の違いがあったんだ。
明生 徹頭徹尾、強い内向と同時に外へも強くという趣向の昭世さんと、「面は痩女、そこから、何かが自然と生まれるものを計算にいれないと」の父との間に行き違いがありました。エネルギッシュに且つ凝縮した力をコントロールする意識は共通するのに、その通達方法の様々の模様が現場で体験できたのは、良い刺激でしたし、これからの自分の課題にもなるなと思いました。
能夫 強くやるのが昭世さんだけれど、菊生叔父の感覚では、それでは『求塚』ではないということだったんだな。内に秘めていながら、景清よりもっと激しいものがなければいけないということだと思うのだが、その話を聞いて、僕はどちらとも、軍配をあげられなかった・・・。
明生 内面的な力というのはすごく難しいと思いますよ。なければいけないし、ちょっとした方向性が違うだけで、変にとられる面もあるし、かと言って、それを制御し過ぎて何も訴えかけがなければ、それも困るし・・・。でも『求塚 』の後シテは難しい。舞が無いので、謡という訴えかけが充分でないといけないし、型でなくシテの心の読みとりという作業の大切さかな。
能夫 難しいね。あのことで考えさせられた。そういうことが、自分が『求塚』をやるときの指針というか、下地になっているね。
笠井 その人間が、どこまでそれを消化してどう成り立たせるかだろうね。
写真 粟谷能夫 「知章」
粟谷明生 「松風」
撮影 あびこ
我流『年来稽古条々』(12)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(12)
青年期・その六『道成寺』まで
粟谷能夫 粟谷明生
明生-先回から『道成寺』への道のりという事で話をすすめています。先回にも少し話しましたが、私の『道成寺』の披きは昭和61年で、前年の粟谷能の会で『黒塚』、さらにその前の昭和58年には青年能で『紅葉狩』と、一応『道成寺』の前に「急之舞」と祈りが経験出来て、恵まれていたと思います。
能夫-祈りは経験しておかないとね、これは一人では出来ないから、ワキ方という相手役がいてはじめて成立することだから。
明生-あの時の『黒塚』は、私が本当に能に出会い、能楽師の自覚を持ち始めた最初の曲でした。
能夫-それまでは冬はスキー、夏はサーフィンで一年中まっ黒だったもの、もうぼちぼち舞台中心の生活を送ってもらいたいと思ってましたよ。
明生-能夫さんが観世寿夫さんの『黒塚』では「月もさし入る」というところで下を見るんだ、という話をされて、びっくりしたのです。
能夫-月は普通は上を見るでしょう。それを寿夫さんは、あばら家の隙間から月光が差し込んでいる、その床を見た。これはゾクゾクするような凄い演技だった。そのことを話したんだよ。
明生-それで能夫さんから「能っていうのは面白いだろう。型付通りだけでなくいろいろと幅があるんだよ。だからもっと考えよう」と言われました。その頃はただ型付通りにまちがい無くやれば良しという次元でしたから、何も考えてはいないのです。例えば『紅葉狩』にしても、序の舞の三段の後、右手は着流しの時のように指を伸ばし右腰を押さえる姿となりますが、あれは本来着流しのうわまえを押さえる型で、大口袴をつけているときは必要なく、おかしいのですが皆平気でやり、平気で見ている。まあ実先生がいらしたこともありますが・-、人が演ずる通りやれば良い、それが少々、本筋よりずれていても、というような状況がありました。それがこの寿夫さんの話を聞いた時、あれ、能というのは面白いものかもしれない、これは自分の人生を掛けるに値すると思ったのです。そう思わせた大事な一言でした。それからあの『黒塚』のとき、能夫さんがどれでもいいから自分の好きな装束を選んでと言われて…、この辺りのことは粟谷能の会ホームページの演能レポートに詳しく書いてありますが、出立ちは赤頭に我が家の『望月』専用の萌黄の厚板を腰巻にして般若で勤めたのです。そのとき能夫さんは、「いいよ自分で選んだものを責任持って着ればいい」と言ってくれました。当時はそれなりに満足していたのですが、後日写真を見るとひどい組み合わせでした。もしあの時、この曲にはこの組み合わせが良い、明生君の選んだのは変でおかしいと注意されていたら、あのひどい組み合わせの装束を着るという経験が無い代わりに、他人任せの、出されたものを有り難く付けているだけで、いつまでも曲にあった装束を選ぶという作業にも目覚めなかったでしょう。自分自身を自分の責任で演出していかなければならない、いろいろなことを深く考え様々な手法を多方面からも検討していかなければ駄目だと気が付いたのです。だからあの時の能夫さんの対応には感謝しています。本当は「似合わないのに」と心の中では思っていたでしょー。
能夫-それはね、我が家には、祖父や父が苦労して集めてくれた面、装束があるし、私は出し入れをして、すべて頭の中に入っているが、明生君にもわかっておいてもらいたかったのと、浅井君から聞いていたのは、寿夫さんは装束、面をどういうものを選ぶかということを問いかけ、ただのお仕着せでなく、自分の自主性を尊重して、そのことを通して役者を育てていったということだからね。それと『黒塚』で一番言いたかったのは、喜多流では扉をあげても自分の世界は見せたくないという演出だけれど、観世流だと、扉をあけて山伏を招き入れるのが、一人の尾び住まいの女がやっと人が来てくれた、という感じが表現されている。人恋しさみたいなものを感じさせる広さがある。そのほうが世界が広がると思うよ。そういうことが見えてくると、能の世界が一回りも二回りも大きく、魅力的で素晴らしいものになってくる。その頃、明生君の能に広がりがないと言ったときに、明生君に広がりとは何ですかと問い返され、能の表現の「広がり」という事を理解してもらおうと言葉を並べたんだけれど、どうしてもうまく伝えられなかった。広がりというのは、例えば『笠之段』で「えいやえいやと寄せ来るぞや」と脇正面ヘシカケをした時にある距離感が見えてこなくてはいけないし、無限大まで届くようなエネルギーを感じさせなくてはいけない。ただ教えられた通りにやるだけでなく、自分の、こう表現したいという思い、意欲があってはじめて広がりのある表現になる。譜本の読み込み、曲の本質、主題を理解して演じたときにはじめて広がりのある表現が可能になる。そうでないと箱庭のように、せまい世界しか表現できない。今ならそう言えるんだけれど、その時はどうしても理解してもらえなかった。それを説明し、説得出来る力が自分になかった。自分では解っているつもりでも言葉として的確に言えなかった。それでは何の意味もなさないんだと痛感した。そのことは僕の原点といっていい。
明生-昔、二人で阪大の自演会の手伝いをしていた時、前日は「照長」という焼き鳥屋でふぐさしとずり(砂肝)で一杯やりながら、よく喋りました。今考えるとあれも父が仕掛けた罠で、私をこの世界から離れないように餌で釣っていたのかもしれないのですが…。その時の話で、能夫さんから『忠度』の和歌への執心が解るか、と問いかけられて、まったく興味を示さなかった私は「和歌への執心?全然解らないよ、修羅物らしくカケリがしっかり舞えればいいんじゃないの」なんて無意識に答えていた、そんな時代がありました。
能夫-これだけ自分は解っていて、これだけ話しているのにどうしてこの人は解らないんだろうと思ったと同時に、心の広がり、型の広がり、芸の広がり、曲の広がりといったことを解らせられない自分の不甲斐なさを痛烈に覚えている。そんなことが積み重なって少しずつ明生君も変わっていったんだと思う。それまでにはずいぶん時間がかかったよ、呼び水をし、餌を与え、注射を打ってね。(笑い)それはね、僕も菊生叔父からいろんなことを教えられたし、そのことを明生君に伝えたかったということもある。それから僕は父達のように兄弟が無く一人だったし、身内のなかで自分と拮抗出来る、合わせ鏡になるような力のある存在が必要だからね。そういう人として育ってほしいと本当に思っていたんだ。
明生-そういう下地があって、『黒塚』に向かう時に寿夫さんの話を聞き、また、装束を自分の責任で選ぶ、この二つだけでも『黒塚』を勤めるのに充分な意欲が出たのです。これは本当に大きかった。そういう思いで能のシテを勤めると、こんなに面白いものはないわけで、あとはどんどん面白くなっていきました。実先生から教えていただいた通りを忠実に真似ることから、少し距離をおいて舞台を演ずるという意識で考えるようにと、変わりはじめたのです。
能夫-これは菊生叔父から聞いたんだけれど、先代の六平太先生は能は芝居をしてはいけないが、芝居心がなきゃいかんと、何かそんな事と繋がっているような気がするな。
明生-実先生から教わるものと、もう一方で能夫さんといろいろ話し、こんな面白い型付があるといったことを教わって、少しずつ、そう広がっていったんです。読めない伝書も、ふと手にするようになり、そういう意味でこの『黒塚』は私にとって本当に大事な出発点でした。
つづく
『半蔀』「立花供養」を語る2投稿日:2018-06-07
横浜能楽堂特別公演 『半蔀』「立花供養」を語る
(6)「立花」の技
粟谷 橋の会では蓮の花がピーンと立っていましたが、今度はススキですね。どうしてああいう風にすーっと立っていられるのか不思議ですね。
川瀬 今回のものの方が大変ですよ。ススキがどうしてあのようになっているのか、よく質問を受けるんです。ああいうものは舞台に出すと、あの暑さとライトで一気にほうけてしまいます。あれにはいろいろな策が立てられていて、だから大丈夫なんです。
笠井 薬物的なこともあるの。
川瀬 薬物を入れないと駄目です。
粟谷 うわあー、ドーピングですね。(笑い)
川瀬 昔から卵の白身を溶いたものなんかを使うんですよ。あれはあれで至難の業なんですね。それをススキの穂に塗りつけるのです。でも卵の白身が重たいのでタランとたれてきたりして大変なんです。今は薬物的なものがあるのですが、やることは一緒です。一つ一つこよりを巻くようにまわしながら付けていき、咲かないように咲かないように、穂を封じ込めていく感じです。
中村・粟谷 大変なことですね。
川瀬 こんなに熱いとどうしても葉っぱが巻いてしまうんですよ。要するに直線になってしまうのです。
笠井 まず直線になって、そしてしなって落ちるんですよね。
川瀬 舞台に置く時間だけでは落ちるところまではいかないのですが、直線になってしまいます。だからススキを使うのは至難の業なんです。
笠井 花というのは、そのときの時節感当(じせつかんとう)と世阿弥も言っているけれど、その時に出会ったもので勝負しなければいけないから大変だね。思ったようにはいかない。その時節にあるもので何ができるかという、すごい試練を与えるね。
川瀬 そうです。それと望んで集める力がないとできないんですね。どこで手を打つか。どこに頼みきるか。
笠井 それはすごく切実な問題だな。あなたは利休のことを言っていたけれど、利休は道具は集めたかもしれないけれど、花は集める力というよりは選ぶ力だったと思うけれど。今花材屋さんが全国のものを集めてくれるの?輸入ものも含めて…。
 川瀬 普通の花材屋では揃わないです。今日のお花は全部、切り出し屋に特別に取りに行ってもらっている花材ですから。普通のルートから入ってくるものではないんです。
川瀬 普通の花材屋では揃わないです。今日のお花は全部、切り出し屋に特別に取りに行ってもらっている花材ですから。普通のルートから入ってくるものではないんです。
粟谷 特別のルート?
川瀬 山に入ってもらったりして揃えているものですから。それもここに持ってくるまでに90%処分しているのです。使っているのは10分の1。10分の1も使っていないかもしれませんね。
笠井 芸もそうですよ。10あるうち1が急所。
粟谷 そう。10曲やって1曲いいのがあるかなあ、くらいですよ。
中村 うちで公演やったときに毎回アンケートをとっているんですけど、毎回感想を書いてくださる方が、今回は素晴らしかったと。その方は、年間10何回、20回と、次は素晴らしいのがあるかと期待して見ているが、なかなかない。でも今年はこれ1本見ただけで、今まで10何本見てきた甲斐があったと書かれていました。
川瀬 それはありがたいですね。
中村 難行苦行で能を見続けてきて、今日のは本当に素晴らしかったと。そう思っていただいて、こちらとしてもうれしかったです。
笠井 実際、その通りです。難行苦行しないと、お能の本当の素晴らしさはわからないから。そういう水準で観てくださる人というのも、やっぱり数パーセントなんだな。よくぞ、難行苦行をしてくださった・・・。
川瀬 いつの時代もそんなものじゃないですか。
(7)作り物の「半蔀」について
川瀬 でも、今日見ていて、『半蔀』は喜多流の方が雰囲気がありますね。実がついているのもいいし、片折り戸の方がいいですね。
笠井 観世流も片折り戸みたいにするんですがね。片折り戸というのは片方に開くようにして、門構えみたいになっている。ああいう風に変えるのが通例です。
川瀬 あれぐらいじゃないと、うまくバランスがとれないと思ったのですけど、今日。
粟谷 あの藁屋、少し背が高すぎませんでしたか。
中村 見ている限りではそんなに。
川瀬 あの高さは変えようがないでしょ。
粟谷 いや、もう少し短いのもあるのでは?
中村 能楽堂の備品で違うかもしれませんね。喜多能楽堂だと違うかも。
粟谷 若い人たちがすでに作っていたので、あれが常寸かなと思ってしまったのですが。
川瀬 あれは横浜能楽堂のものなのですか。
中村 そうです。
笠井 ああいうものは能楽堂で持つものなんですよ。僕はあの葉っぱが気になったんだけれど、ちょっと光り過ぎる。テカテカしてちょっと邪魔になったな。
粟谷 葉は持ってきていたのですが、もうできていたから取り替えなかった。葉の色までは注意が行かなかったですね。作り物をどこに置こうかとか、どういう手順で進めるかばかり考えていて。
川瀬 六郎さんのときは、瓢箪はラメ入りのように見えましたが。
笠井 いろいろあるんですよ。金銀・・・。
粟谷 うちのは金色なんですが、金というのもねえ・・・。
笠井 作り物の飾りは一種の象徴みたいなものだから。リアリズムを超えてしまう。夕顔の実だって実際あんなに小さいわけではないでしょ。
川瀬 小さいのもありますよ。夕顔は花自体そんなに大きいものではありませんからね。六郎さんのときはラメ入りのようなので、すごく印象に残ったんです。
粟谷 金色の瓢箪なんですが、友枝さんに聞いたら、金の瓢箪とは聞いているけれど、僕は金色はやめたよと言われた。能夫さんは無くていいよと言います。詞章に「瓢箪しばしば空し」という言葉はあるけれど、実際引き回しをかけていると見えないし、想像すればいいんだからって、それで無しでしようと思っていたのです。でも当日横浜能楽堂の瓢箪を見たら、緑色のがたくさん付いているじゃないですか。だから大きいのを外して、小さいのだけ3つ4つ付けたやったのです。
川瀬 瓢箪がないというのはおかしいですね、やっぱりちょっと。
笠井 半蔀戸を開けたとき、ふっとぶら下がる感じの風情がいいんだけどね。金というのは不思議な気がする、好みとしては。
川瀬 先ほどの伝書には、花なんかも銀の花を入れると書いてありましたね。銀のかごもありましたっけ。
粟谷 けばけばしいんですよね。
川瀬 案外けばいものなんですね。
笠井 まあ、象徴となればそうなるんだ。リアリズムではないのだから。
粟谷 ゴージャスな感じが出ればよいというセンスかな…。
川瀬 昔は、今考えるほど金銀が、けばけばしいものではなかったかもしれませんね。荘厳されたような世界に見える、金銀というのはそういう意味だったかもしれない。今、池坊は普通の白竹の篭でやりますね。白竹の篭の花入れに松の真の立花が出ているのがとても不思議な感じがします。白竹の篭に松風の草を入れるならともかく、松がドーンと出るのはねえ。7、8年前ですか、京都天龍寺でおやりになったときがそうでした。金閣寺の落慶法要のときでした。
中村 あの『半蔀』の藁屋を橋掛りに置くというのは・・・。
粟谷 あれ、本来ではないんですよ。普通は常座です。
中村 いやでも、今日見ていて、あれの方が僕はすごくよかった。
粟谷 川瀬さんのお花があった場合に、そのすぐ近くに藁屋があって、造花があってというのでは、それはもうおかしいでしょ。
中村 友枝先生のときもそうでしたね。
粟谷 立花があるときには、橋掛りの方に行きますね。本来は中入り後に立花を引いてしまうから。
中村 正面から見ていて、今回、立花と藁屋の関係がすごくいいように見えました。
(8)装束と立花瓶
笠井 ところで、後シテの装束、長絹は新しいの。
粟谷 古くはない…、新しいかな・・・。
笠井 だからかな。被くときに・・・。
粟谷 よいしょ!と見えてしまったかな…。
笠井 やっぱりそれは悲しいよ。『半蔀』はもっと儚くなければ駄目だろうと。
粟谷 しなやかで軽い長絹は、白でなければあるのですが、白にこだわって、能夫さんにも相談し、まあちょっと硬いけれど、白に金糸の一色だし、模様が花篭なので、一番似合っているかなということで、選択したのですが…。
笠井 きれいではあったけれどね。
粟谷 ちょっと硬い感じ?最近作ったといっても、できたばかりではないんですよ。もう少し使い込まれていればよかったですね。
川瀬 生地自体が違うんじゃないですか。
粟谷 友枝さんが『卒都婆小町』で使った浅黄のを使おうかなとも思ったのですが、夕顔の花からは離れてしまうかなと思って。装束としては悪くはないのですが。やはり銕仙会から拝借すればよかったのかな。
笠井 そうだよ。
川瀬 借りるなんてことがあるのですか。個々人での貸し借りがあるのですか。
笠井 信頼関係ですね。銕仙会は粟谷さんのところとは親しくしているから。
粟谷 今私が観世銕之丞さんにお願いして装束を貸していただく事が出来るのは、父が観世寿夫先生、栄夫先生、静夫先生たちと親しい関係があったからです。
川瀬 お花の世界では、いっさい貸し借りはしませんよ。全部自分のところで整えます。
粟谷 今回の赤い花台は橋の会のときと同じですよね。
川瀬 ええ、同じです。あれはあれで名品なんですよ。当初は桃山時代の立花瓶を用意していたのですが、でも置いてみると硬いんですね。丸みがなくて、今回の舞台には合わないのです。直角というか、直線が効きすぎているんです。以前雑誌の撮影で使った瓢箪がついているものにしようかと思って探してもらったのですが出てこなくて。それで、あれにしたんですよ。お公家さんの家から出たもので、ああいうものだったら草ものに合うだろう、姿がきれいだろうと思って。2回京都に行って、いろいろなものを見て最終的にあれに決めたのですけど。花材がともかく揃わなくて、どうしようかなと。ともかく昨日まで必死ですよ。
中村 だからものすごく贅沢なものですよね。
(9)立花とシテの関係
粟谷 今回の私の感想ですが。普通、立花がないと、あの夕顔の精というか夕顔の上を一生懸命掘り下げて舞おうということになるのですが、ああいう立派なお花があると・・・、悪いことではないのですが、違う意識が作用してしまうという発見です。あのお花に全部委ねてしまおう、その後ろで、きれいにそつが無く動いていればいいのでは、という風に陥りやすい、多分陥ってしまった・・・と、今感じています、反省点ですね。笠井さんがおっしゃるような、夕顔のあの切なさみたいなものを出すのは難しかった。正直言って、出しにくいなあーというところがあるんですね。そこを演じるなら、いっそのこと全部花を取っ払っちゃって何もない方が演じやすいのでは、ということになりそうなんです。立花供養という小書があったときに、そこをどのように演者が処理しなければいけないかが課題で…、今回の私のテーマでもあったはずなのですが…。あーー笠井さんが何か言いたそうな・・・(笑い)。「明生君!夕顔の儚さはどこに行ったんだい」とね。普段なら、主題にグーッと入っていこうとするんですけれど、あの立派な立花があることで、何か反作用が起きるというか。でも演者にとっては、もう一つ別の未知のステージに立てるという救いでもあるのです。
以前に友枝さんにお話を伺ったときに、「僕らが伝書で見ているような従来の立花供養のイメージで考えていると駄目だよ、すべてそのときに合ったものを考えるように」というようなことを言われたんですね。お花が動かないなら動かないなりに、今回の秋の草なら、それなりに・・・ということですかね。橋の会の2日公演で六郎さんがシテの日は、金子敬一郎君の『道成寺』があり見に行けなかったのですが、友枝さんのときはどうしても見ておこうと拝見にうかがったのです。六郎さんが地頭でしたね。
中村 すごく贅沢な会ですよね。
粟谷 友枝さんがあのときの経験で、私の稽古のときに、喜多流の謡い方自体を工夫するような細かなところも教えてくださいました。それがうまく出来たかは勿論別ですよ……。とにかく友枝さんのときの異流共演で、あのお花と地謡というのが、今までの私『半蔀』像とは全然違う、新鮮なエキスみたいなものを感じたのです。
笠井 友枝さんもいろいろなことを考えていらして、あの橋の会はすごく鮮度があったよ。
粟谷 そうですね。で、それをそのままよいしょっと、こっちに持ってくるわけにはいかない、ちゃんと自分なりの何かの処理しなければいけないわけですが…。
研究公演つれづれ(その四)投稿日:2018-06-07
研究公演つれづれ(その四)
研究公演第4回(平成5年11月27日)
『蝉丸』シテ・逆髪 粟谷能夫 ツレ・蝉丸 粟谷明生
粟谷 能夫
粟谷 明生
笠井 賢一
 明生 第4回の研究公演は、能一 番で『蝉丸』。能夫がシテの逆髪で、私がツレの蝉丸を勤めました。二人でひとつの舞台をつくることがテーマでした。
明生 第4回の研究公演は、能一 番で『蝉丸』。能夫がシテの逆髪で、私がツレの蝉丸を勤めました。二人でひとつの舞台をつくることがテーマでした。
能夫 4回目は能一番で狂言もなかったし、入場券は売りにくかったよね。
明生 そうですね。
能夫 1年に2度というのも、当時の我々にとってはきつかったかもしれない。
明生 でも、そのときは、とにかく今出来る事は今しっかりやろうという意気込みでした。
能夫 勢いでね。
明生 お客様も多いとは言えなかったけれども、精一杯勤めたと思っています。『蝉丸』のツレは研究公演で演ずるという意識が強く、照準を合わせていましたから、喜多会の例会で『蝉丸』のツレをという交渉があった時、頑なに断って、これに備え燃えていましたから
能夫 それなりに二人は力が入っていたんだよ。『蝉丸』の演出について、僕はそれまで嫌だなと思うところがあった。逆髪の道行が終わった後、大小前で座り、蝉丸の謡の途中からいきなり立って常座にクツロギ、戻るように行くんです。これが嫌でね。おかしいでしょう。普通、観世流だったら、一の松で佇んでいて、蝉丸の声が聞こえてくるから、そちらに気が向いていくわけでしょ。だから座ってしまうというのはねえ。逆髪の特性というのは、佇んだりしない、放浪癖とでもいうのか、とにかく進むということでしょう。だから、あの研究公演では、「花の都を立出て・・・」から、蝉丸 の「世の中は・・・」が発せられるまで、大小前に下居ずに、橋掛りの一の松で佇むことにしたんです。あそこで、喜多流の演出を見直して舵を切ったつもりなんですけどね。
笠井 確かに大小前にクツログ、下居するのは変だね。
明生 変ですよ、ですから私も広島で舞ったときは、能夫氏の型を取り入れました。
笠井 喜多流の定型だからというのは考え直す必要もありますね。
能夫 だから、そこを切り替えたわけです。喜多流の場合、最後の別れの場面では、逆髪と蝉丸が謡った後は全部地謡になってしまう。地謡になると乗る、リズムがでてしまうでしょう。そこも舵を切りたかったけれど、それは次の機会と思って、あのときはそのままにした。後で友枝さんと一緒のときにそうしようと思っていたけれど、友枝さんが病気になって、実現しなかった。だから、あのときに舵を切っておけばよかったなと、今は思っている。でもまあ、勝手なことばかりやっていると思われるのもねえ。ちょっとぐらいなら、みんなもなるほどと認めてくれるから、あのときはあれでよかったと思いますけれど。
明生 あのとき、クセの上羽 「たまたま言訪ふものとては」の部分をツレの蝉丸が謡うという能夫氏の考えもあって、私は賛成したのですが、本人があまり行き過ぎるのもどうかということで、普通にして、いたしませんでした。
能夫 そこまではやらなくともいいかなと。
明生 私は上羽の謡は蝉丸が謡う方がいいと思いますが。
笠井 喜多流はいろいろなところのものを摂取してきた流儀だから、おかしいと思うところは見直していくのはいいよね。
能夫 そうそう、間違っているところはね。
笠井 喜多流はよいところは沢山あるし、独自性を出しているところもある。だから、流儀として絶対残すべきところは何か、変なところはどこかを考えるべきですよね。便宜的な変形はどこかで変わっていかなければならないけれど、それが長い時間をかけて上演するなかでそこはかとない味わいを出しているというのをどう考えるか、そこが微妙なところでしょう。たとえば『葵上』古式の青女房(若い女官)なんかね。現行では登場しなくなっているものを復活して上演した結果、車出しとか青女房を出さなければダメなんて考えるのも行き過ぎだと思う。

能夫 変でしょ。場面の進行に障害が出てくるでしょ。
笠井 だから、どこまでで線を引くかが問題だね。今の『蝉丸』の話で言えば、大小前で下居するのはおかしい。
能夫 そういう問題点があることを認識しておきながら・・・。
笠井 ギリギリのところで決断していかなければね。安易に変えるのがいいとは僕は思わないけれど、唯々諾々と従っているのが問題なんですよ。
能夫 そうだよ。無神経でいるのが許せないわけ。その意味でも研究公演があるわけですよ。
笠井 研究公演が機能しているわけだね。そういう場があってよかったと思いますよ。
明生 『蝉丸』の辺から、いろいろ改善しようという機運が出てきたということです。5回の能夫さんの『白是界』にしても、私の『天鼓』にしても、そういう考え方をしていった。その最初が、この『蝉丸』だったと思いますよ。
能夫 そうだね。
明生 変えたことがよければ、先輩たちや周りも認めてくれて、2年後、3年後には、そういう方向で動き始めますから、古いおかしな伝承に拘りすぎるのは間違った伝承のとらえ方でしょう。
『蝉丸』のツレの難しいところは、蝉丸ツレが一番最初にワキを呼び出す「いかに 清貫」の謡、二人で稽古したときに、「品を保ち、調子を高く張って謡ってくれないか、蝉丸の人物像が浮かびあがるように」と、いろいろとシテから注文が出たんですよ。これをすごくよく覚えています。それに前半はシテが出ないからツレがシテみたいですが、後半にシテが登場したときに同じ調子の謡い方ではダメで、少しづつ変えていかなくてはいけない、このあたりが難しいということも体験してわかりました。最初の「いかに 清貫」あの、たった一言ですが、その一言の中に、フワーッと世界が広がらないと・・・。
能夫 わびしさ、つらさも全部背負いながら、それでいて蝉丸は何もわかっていないという風情もあるし、いろいろ揺れる心情を、あの一言に全部こめなくては、ね。それからシテは、うちの流儀では黒頭でやることが多かったんですよ。黒頭だと化け物みたいだけれど、バス頭(かしら)だと人間的なものが表現できるのですが、それが使えない。結局僕は黒頭が嫌だったから、かずらの鬢をたらし、裳着胴、大口袴でやりましたけれど、あのときバス頭という選択肢があればなあと思いました。
笠井 その選択肢はないわけね。
能夫 ないです。『鷺』のときに白いバス頭のようなものを使っていますけど。あれは普通の頭じゃない。そういう選択肢はないです。
笠井 その当たりは取り込んでもいいんじゃないかな。
 明生 そろそろ取り込んでも良いと思います。それから、中入前、盲目の人間は涙が出ないからシオリはおかしいと言われて、シオリをせずに、悲しみの表現をやろうとしました。
明生 そろそろ取り込んでも良いと思います。それから、中入前、盲目の人間は涙が出ないからシオリはおかしいと言われて、シオリをせずに、悲しみの表現をやろうとしました。
能夫 中入後、アイ狂言が出てきて、博雅の三位と名乗り、蝉丸が捨てられたことを聞いてやって来たといって、蝉丸を藁屋の内に助け入れるでしょ。その間、蝉丸はずっとシオリをしていなければならないんですよ。あれ、きつい姿勢なんです。
明生 きつさ、苦しさを回避するために、考えたのではなく、両シオリ(もろしおり)などせずに身体で落胆悲しみを表現する、そのための体勢、型の再確認、これを勉強しようとしたのです。大蔵流は地謡が謡っている間からすぐ出られますが、和泉流は地謡が終わってから、別にゆっくりと出られるから、たしかにシオリは手が痛くて大変でしょう。
能夫 まあー、あの時の舞台は二人でつくるというのがテーマだったんですよね。
明生 そういう意識はすごくありましたね。
笠井 シテ、ツレというより、対等という感じだよね。引っ張り合っているという感じがします。
能夫 たまたま僕が年齢が上だったから逆髪で、明生君が年下だったから蝉丸だったというだけでね。
明生 この舞台が結構よかったというので、大阪でもやろうという話がありましたが、どうせやるなら違うことをしようということで、それはやらないことになりました。
能夫 そのとき良かったから次もではないでしょ。あの舞台は初々しかったからよかったと思うよ。志もあったし。
明生 一番一番を新鮮な気持ちでやるということですね。
写真撮影 あびこ
我流『年来稽古条々』(13)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(13)
青年期・その七『道成寺』を披く
粟谷能夫 粟谷明生
明生 先回は『道成寺』までということで『黒塚』を中心に話しました。そろそろ『道成寺』に入りましょうか。
能夫 そうね。僕が『道成寺』を披いたのは昭和五十四年十月十四日の粟谷兄弟能でのことだった。当時は粟谷能の会ではなく兄弟能といっていたんだね。僕は三十歳。その日の番組は新太郎の『清経』、菊生の『羽衣』、そして僕の『道成寺』。明生君は『清経』でツレをやっている。
 明生 私の披きは昭和六十一年三月二日の粟谷能の会のときです。『景清』菊生、『富士太鼓』新太郎、私の『道成寺』でした。能夫さんは『景清』のツレでしたね。私も三十歳で披いています。このころは『道成寺』の披きというと三十代前半というのが一般的なところでしょうか。
明生 私の披きは昭和六十一年三月二日の粟谷能の会のときです。『景清』菊生、『富士太鼓』新太郎、私の『道成寺』でした。能夫さんは『景清』のツレでしたね。私も三十歳で披いています。このころは『道成寺』の披きというと三十代前半というのが一般的なところでしょうか。
能夫 先輩ではもっと早かった方もおられるけれど。友枝昭世さん、香川靖嗣さんは早かったよ。
明生 二十代で披いておられたようです。我々の世代は三十歳になればそろそろよいのではという感じで。まあそれまでの修業過程に基づきますね。我々の後の世代はもっと遅くなっていますよ。三十五、六歳とか・・・。能夫さんは『道成寺』をやらせてくださいと願い出たのですか、それとも実先生にそろそろやるように言われたのですか。
能夫 その辺のことはよく覚えていないんだ。まあ両方からボチボチって話になったんだろうなあ。自分でもそろそろという気持ちは持っていたし、父や菊生叔父に話をして、よしということで実先生に申し上げたと思うけれど。
明生 当時は実先生の許可を得ないとできないわけで。粟谷家としても、実先生に申請して許可をいただいたわけですね。
能夫 それで日程が決まったのは二年ぐらい前だった。
明生 私は二年半前でした。父流のお願いの仕方というのがありまして、年末に「三年後になりますが・・・」とお願いする、すると、「う、三年後ね」「それまでにしっかり勉強すればよいか」となる。でも年が明けたら、あっという間に二年後になるのですよ。。
能夫 僕は、自分の世代のトップバッターだったから・・・。そのきつさはあったと思う。
明生 友枝昭世さんがやられて、昭和四十五年に内田安信さん、香川靖嗣さん、昭和四十六年には塩津哲生さんが披かれた後、少し間があいて、能夫さんですからね。
能夫 だから、しばらくやっていないという難しさがあるし、次の世代のさきがけとしての責任もあるし・・・。
 明生 能夫さんの場合はそういう面での、つらさがあったでしょうね。私の『道成寺』は指導者が変わるという節目でもありました。それまでは喜多実先生が直接の師でしたが、『道成寺』からは友枝昭世師になるという・・・。
明生 能夫さんの場合はそういう面での、つらさがあったでしょうね。私の『道成寺』は指導者が変わるという節目でもありました。それまでは喜多実先生が直接の師でしたが、『道成寺』からは友枝昭世師になるという・・・。
能夫 僕のときは実先生が面倒をみてくれたけれど、明生君のころは先生もご高齢になられたからね。
明生 私が『道成寺』を披くとなったとき、父が昭世さんへ、「うちの子は君に傾倒しているから、君が教えてくれないか」と頼んだのです。それから友枝昭世師に御指導を受けているのですが。それでも申合せは実先生がいらして見てくださいました。
能夫 そういう意味では、僕と明生君では多少時代背景が違うなあ。いずれにしても『道成寺』ができると決まると、からだの張りみたいのものが違ってくるよね。『道成寺』を舞えるのだという、うれしさと緊張感が生まれて。
明生 私たちにとって『道成寺』というのは、それまでの舞台や稽古、しいては生活態度までの総決算ですからね。技術的、芸術的な観点で作品をみたらまだまだ未熟と思われるし、お客様に、安珍清姫の物語の女の情念を豊かに想像させられるかといったら、難しいと思います。でも『道成寺』を披くという一つの意味は、ここまでやってきたという成果を見てもらう、仲間うちに認められるということじゃないですか。能夫が、明生が、一生懸命取り組んでいるのがわかったという、まずはそれでいいのではと思うのです。その裏付けとなるものをきちんとやっていく事が大事で。多少破天荒でもエネルギッシュに、まさしく若者の披き『道成寺』、ここにあり、というものにならないと。
能夫 そういうものがないといけないよ。ただきれいに、そつなく舞うというのではなく、何か『道成寺』の命といおうか、そういうものを伝えようとする気迫がないとね。
明生 『道成寺』を舞えると決まってから二年近く、能夫さんはどんな風に過ごしましたか。
能夫 型付のことや囃子のことなど、何かと資料集めから始めたような気がする。高林さんの家から型付をいただいたり。法政大学の能楽研究所にも行ったり・・・。
明生 能夫さんは寿夫さんの能にふれ、伝書を読むとか、能について熟考、掘り起こし、そういうことに時間をかけていたことを、近くで見ていたからわかりましたよ。もちろん熟考して、自分なりの試みをやっても、全部がうまくいくとは限らないけれど、それが、後の演能に生きてくるということは絶対ありますから。
能夫 僕らの前の世代は、ご自分で研究しようなどとはあまりされなかったでしょ。実先生が強かったから、そういうことができないという状況もあったし・・・。
明生 舞う技術の基本、シカケ、ヒラキは大事ですが、でもある年齢になったらその段階にとどまるだけではいかがなものか。痩せた能になるのではないでしょうか。型としての動きから作品の背景を背負った動き、舞へと意識していくことが必要でしょう。
能夫 上の人からたたき込まれる時代もあって、それはそれでよい時代だったんだよ。でも今の時代はおそらく、それだけではダメで、自分なりの何かを表現するか、プラスするものを意識していかなければと思う。僕は寿夫さんによって目を開かれ、観世流の浅井文義君に引っ張り回され、いろいろな経験させてもらって、結果は悪くなかったからね。伝書とか資料を読んだり、僕が意識的にやり出すきっかけになったのは、まさに『道成寺』だったんだよ。
明生 能夫さんはそれをやり始めたから感心しますよ。『道成寺』では鐘の作り方とか、習の次第でのシテの出についてなど、いろいろ掘り起こしてくれたから、後に続く私はそれを見て、踏襲すべきことは踏襲し、変えたいところは考えればいいのだから、助かりましたよ。乱拍子の下申合せの仕方も当時としては画期的だったのではないですか。
能夫 乱拍子、喜多流は幸流と合わせることになっている。僕のお相手は横山貴俊さん、本番が十月でしたから、その年が明けてすぐに、下申合せの稽古をさせてもらうことになった。そうしたら、笛の一噌仙幸さんが、自分も一度呼んでほしいと言ってくださって、それで笛と鼓とで合わせる稽古ができた。これがよかった・・・。
明生 一回は小鼓と、もう一回は笛も加えてと、稽古法みたいなものが、私に伝承されました。乱拍子では、鼓と合わせる稽古は当然必要ですが、笛をお願いしないと臨場感が出ませんね。単なる器械体操みたいになって、でも笛が入ると、芸術性が出てくるというか・・・。
能夫 奥行きが出るというか・・・。僕、あのとき仙幸さんが「やってよ」とよく言ってくださったなと思ってね。
明生 私も能夫さんが笛も入った方がいいよと言ってくれたので、一回目は亀井俊一さんと、二回目は笛の一噌仙幸さんにもお願いしました。
能夫 それから継続の稽古、通しの稽古をしないとダメだね。乱拍子だけで終わりにしないで鐘入りまでね。
明生 一つ一つの型がある程度できてきたら、それをやらないといけませんね。乱拍子の後、「山寺のや」と地が入って急の舞に急速に入って行く当たり、その後の鐘入りまでは一連のものですからね。
能夫 そこを通してやらないとね。そのとき思ったのは、後(後場)もちゃんとできないといけないということ。乱拍子や鐘入りに集中して、後は惰性になりやすいでしょ。いろいろ言っているけれど、『道成寺』というのは、考えるより、若いエネルギーをぶつけようとしか思っていなかったような気もする。それをすることによって、いろいろな課題が見えてくるだろうなと思っていたけれど。
明生 そうですね。若さをぶつける、それに尽きますね。
能夫 それから、僕の本番は十月だったから、稽古が真夏の暑いときで苦労したのを覚えているよ。
明生 それで私の『道成寺』のときは「春がいいよ」と。
能夫 十月にやるということは、夏が稽古本番でしょ。家元のところに行き、見ていただき・・・。暑いうえに蚊が 飛んでくるから気が散るじゃない。集中できないんだよ。
明生 夏の練馬の中村町ね。蝉のミーン、ミーン、蚊のプーン、思わずパチン。かゆい、かゆいじゃ、いやになってしまいますよね。(笑い)
能夫 まあ、でもそんな中で、集中力を持続させる精神力も身につけていったんだがね・・・
つづく
写真1 39回粟谷能の会の番組 表紙は粟谷能夫の道成寺
写真2 粟谷明生 道成寺 吉越立雄撮影
『半蔀』「立花供養」を語る3投稿日:2018-06-07
横浜能楽堂特別公演 『半蔀』「立花供養」を語る
(10)習うことと個性を出すこと
川瀬 自分を見つめるということですよね。見つめ果てるというのは、どんなときでもそういう作業はあると思うんですよ。だけど多分、舞台というのはある種、馬鹿にならないとできない部分がある。馬鹿になるというのは変な言い方ですが。
粟谷 抜けるというか。抜けないとね。
川瀬 煮詰め果てたものが果たしていいものかどうかというと、難しいものですよね。白洲正子さんが言われているように、ただこのじいさん型通り舞っているわと。型通りに見事に舞う方がピタッとする場合もあるだろうし。本当に人それぞれの年代と、あるものによって、煮詰めたことが力を得る場合もあるし、全くそれらを忘れ果てることによって力を得ていくこともあるし。
笠井 それはね。
川瀬 本当にいろいろだと思うんです。
笠井 見ている方のこともある。まさに一座建立、見所同心になれるのは、それはすごく難しいことだからね。
川瀬 花とお能で見ると、花は習い続けることも恐いことなんですね。お能というのはある意味では習いきらなければいけないでしょうが、花というのは習いきってしまうと、習いきったためにあることができなくなってしまうということが多いのです。何か型通りに生けているんだけど、伸びていかないというところが圧倒的に多いのです。
笠井 能だって同じですよ。
川瀬 お能は強固な建造物がある分だけ、その中に密度を持ちながら、習った分だけ熟成していくというところがある。花なんかはそういう意味で言うと難しいところがあるんですね。今、立花をさせていただいていますが、これは本来池坊しかないものです。今は小原さんも草月さんもやっていらっしゃいますが、本来、立花は池坊以外にはお願いすることはなかったのです。
笠井 僕らもそう聞いていますよ。お能ではそうだって。
川瀬 他の流儀ではもともと立花というものがありませんから、正式にはできるわけがないんです。たまたま私などが立花をやっていますと、個人でやっているように見えるのですが、池坊という流儀で小さいときから習ってきたからできるんですよ。他の流儀でそういう土台がないところで、今、立花のようなものが立てられている。フラワーアレンジメントみたいで、立花とは程遠いものが多いです。
(11)時代の空気
川瀬 立花も時代によってずいぶん違ってきています。さっき見せていただいた伝書にあるように、昔はたくさんの花をたてた立花でないと満足しなかったのでしょう。粟谷さんは「立花供養」は全くおやりになったことはなかったのですか。
粟谷 はい、ないです。今回が初めてで、たぶん父も勤めていないと…思います。
中村 喜多流でもそんなにやっていないでしょう。
粟谷 追善能のように、それなりに予算が組めるとき、余裕があるときならですね。ですから非常に少なくなってきたんじゃないですか。もっとも天こ盛り立花ですが…。だからこの間の橋の会の友枝さんの立花供養は画期的に感じました。あの時の観世さんの若い人は六郎さんと友枝さんのと両方のお花と舞台を見ているわけですから羨ましいなあ。若い能楽師たちには衝撃が走ったことは確かですよ、皆お花の話をしていました。
川瀬 それは時代の空気というものですよね。
粟谷 川瀬さんのお花を見た人は、もしかすると立花はこういうものだ。昔のゴテゴテしたものは考えられないとなるでしょうね。
川瀬 時代の風潮ですね。
粟谷 実際お坊さんたちがやっていた立花というのは、90日間(一夏)の修行のときにお花をお供えする、立花供養はそのお花を切ってごめんねということで、供養するものですね。私はお寺の人たちがどんな風にやっていたのか。現場はどうだったのか知りたいですね。
川瀬 現実的にはそんなに仰々しいものではないでしょうね。
だけど時代というのは変わっていくのだと思うんです。たとえば玉三郎の女形は昔の女形とは違うわけです。昔の女形はもっと男っぽかったじゃないですか。今は映像にたえられるように、見た目も美しく。要するに舞台を見る人の群像が変わってしまっているので、いくら昔はこうだと言われても、今の人にはちょっとね・・・。
粟谷 カメラのズームアップがいけないのですよ。(笑い) 玉三郎さんの場合はまだズームアップしても大丈夫!
中村 それから以降はそれが基準になっていますからね。
川瀬 そのように時代が変わっているということが大きいですね。
(12)流儀より個人の時代

粟谷 時代の流れで立花もいろいろと変化しているわけで、川瀬さんの立花を見て、「これは池坊」という語り口調が段々と似合わなくなってきていると思うのです、そういうアバウトな世界で考えるのではなく。例えば、観世流の能を見たではなくて、観世流の誰々さんの能を見た、何流の花ではなくて、誰々さんの花を見たと、そう解釈しないといけないなあーと…、立花を見てそう思いましたね。
川瀬 それはあるでしょうね。
粟谷 一方はトルコ桔梗でやっている、一方は川瀬さんの秋草のあのお花、立花を見て…とお話をするとき、何を見たかで全然話が合わない状況がありえるなあと・・・。
川瀬 全然違いますよね。
中村 お能の流儀でいえば、今、菊生先生だったり、友枝先生だったり、それが今の喜多流ということになるわけです。その前の世代はその前の世代で・・・。
粟谷 だから友枝さんの能を見たとか、個人名で言わないといけないんじゃないかな。こんな小さな流儀でも人により全然違いますから。
川瀬 それはそうですね。基本的にはいろいろな人たちが出てくる素地があるということですよね。流儀という骨格があって、それにどのように肉付けしていくかは、多分、それがその人の独自なものになっていくわけです。花なんかも骨は学ばなければならないのですが、さっきも言いましたが、肉まで学んでしまうというのが恐い。習っていると肉を骨と思ってしまう。
粟谷 あります、あります、そう誤解してしまうの…って。
川瀬 そうなるとにっちもさっちもいかない。習いすぎるというのはね。
粟谷 そうですね。いいお話ですね。
川瀬 ある程度の骨組みというか、骨格があるというのはすごく大切なんですよ。立花という骨組みがあるから、どんなに自由にやっても立花なんですけれど、骨組みだけは立花じゃないと困るんですね。
中村 古典芸能のいいところは、その骨組みをきちっと守るというか。狂言で山本さんのところなんかその典型ですよ。だから若い人もそれで育つ。骨ができる。それからどうやって肉付けするか。先ほど笠井さんがおっしゃったのは、多分、則重さんはその肉を付ける可能性があるということだろうと思う。骨は骨で突き詰めるのはいいことだけれど、肉の部分を付けられるというのが、その人の個性ではないか。だけど骨も何もなければ軟体動物になってしまいますからね。古典芸能ではなくなってしまいます。
粟谷 骨も作って、それから肉もですね。
(13)立花とシテの対話
粟谷 先程も少し話しましたが、今回、川瀬さんがお花を持って出られまして、見所にいる人はみんな待っていますから、ああ、あんなに高い草花を持って出るのは大変ではないかなどと思って見ている、すると川瀬さんがスーときれいに持って出られて正先に行き、座って置き少し直したりする。あの辺から、お客様の目のピントはピーッと、そこに集まっているのです。すべての目のピントが。そこを今度はシテに合わせてほしいなあと私の立場として思うのです。でも、それがなかなかむずかしくて・・・。能としての夕顔の精みたいなものの表現に集中するべきなのか、逆に私自身の個としての能楽師を見てもらえればいいのか、どうすればいいのか悩みます。川瀬さんがおっしゃっていた縦糸と横糸を織り成していくようなものだなってことを感じますね。徹底的に感じさせられるのですよ。
川瀬 普通だったら立花がないところで序之舞をされるわけでしょ。でも舞と交差する何かがあってもいいのかもしれませんね。
粟谷 そうですね、今日は舞い易かったです。あまり大ぶりではなかったから、絶対にお花にはかからないなと…。大きいと袖がお花に触れたりして、それは嫌だなと。それがすごく注意して舞いました。
川瀬 基本的には後場では花を出しませんからね。
粟谷 あとは拍子の踏み方ですね。踏むことで花器が動くといけないとこれも注意しました。
川瀬 桔梗が揺れていましたけど、問題なかったです、よかったですよ。
粟谷 最初踏みましたら、ふわ?と揺れたのが見えたから、アーーッ、とね。外見、夕顔の精はきれいそうで、実は、内部ではアーーッ、次はこれくらいかーあ、なんですよ。(笑い)
川瀬 でも、夕顔の花はよかったですね。振動でずっと揺れていたの悪くなかったですよ。
粟谷 そうですか。
川瀬 こちら側から見ているときは、思わず臨場感があって悪くなかった。ハラハラしながら見る舞台というのも緊張感があって悪いことではない気がしますね。西本願寺で親鸞聖人の降誕祭でやったときですが、光が風とともにふわっと来たり、張り巡らされている幔幕が風で揺れたり、装束も風をはらんでしまうし、光は乱舞するしで、全く異次元の、自然と一体化したような思いがけない光景になってしまう。それはそれで悪くないですね。
中村 それではさっきの立花の観念が違ってしまう。
川瀬 だけど外だったら、今日のようなお花は恐いですね。(笑い) 草ものは恐いです。やるなら松とかああいうものでないと駄目かもしれない。
中村 外で立花供養をしたら大変ですね。
粟谷 屋外での能というのは、これまた特別でね、特別の配慮をしなくてはいけないんです、例えば後見の作業が全く無意味になることがありますね。シテの袴の裾を直したり、クツロギで袖を直したりしても、すぐ風がビューっと吹けば意味がない。そういうのは厳島神社の御神能で毎年経験しているから言えるのですが…。でも太陽の光が装束に当たったときの荘厳さというか、光輝いたときの美しさといったら、太陽の光がいろいろに屈折して、口では言い表せないほどきれいなのですよ。茂山千五郎さんが「不思議やなあ、古い汚れた装束なのに・・・」っておっしゃていましたよ。そういう自然の綺麗さとか力みたいなものと、今日の立花の素晴らしさを比べてはいけませんが。大自然の凄さとは別に、あのお花のすごさ、エネルギーにすごく感激しました。それからね、これは自分の勝手な意見なのですが、舞っていて本来はワキの僧と対話しているわけで、ワキとシテの結ぶ隠れたラインみたいなものを大事にして演じるのですが、あの立花があることによって、もう少し別の感覚、つまりお花とワキと自分がいる感覚を感じました。花は単なるオブジェではなくて、エネルギーを発し、それが演者の世界とミックスしているような…そういう感覚に嵌まったというかなー。
川瀬 ススキの雰囲気がとてもよく出ていたと思いますよ。ススキが原の中で舞っている、非常にきれいだなと思いながら拝見していました。今の季節が一番曲趣にふさわしい時期ですからね。『半蔀』だったら秋の方がいいなと思っていました。
粟谷 いい時期にやらせていただいて。川瀬さん本当にありがとうございました。
川瀬 こちらこそ、本当にありがとうございました。
粟谷 若輩ものにお付き合いいただいて。
川瀬 いえ、とんでもありません。
粟谷 私は時分の花で、川瀬さんは真の花ですよ。
川瀬 とんでもないですよ。
粟谷 今回、こういうチャンスをいただいて本当に喜んでいるんです。
中村 それでは、このコンビで15年後にもう一度やりましょう。
粟谷 15年後? 生きているか分からないよ。もうちょっと早くしようよ。(笑い)
中村 早くては熟成しないではないですか。だからしっかり熟成させて。その年は私の定年退職の年なんですよ。それを記念して。すぐ来ますよ。
川瀬 そのときなら、私はどちらかというと小さい花でやりたいのですけどね。お客様が「立花供養」というご馳走を期待するとき、あまり小さいのではご馳走という感じがしないかもしれませんが、何回も食べていただいた後なら、小さいのでもそのよさを分かっていただけるのではないでしょうか。
粟谷 じゃもっと私、勉強して、熟成させて。
川瀬 私ももう少し・・・、真の花のときにご一緒させていただきますよ。
中村 私も生きていたら、15年後、お二人にお願いに参ります。
川瀬・粟谷 生きていたらね。
中村 遠大な計画ですね。(笑い)
(於・華勝楼、平成16年9月記)
研究公演つれづれ(その5)投稿日:2018-06-07
研究公演つれづれ(その五)
第5回,研究公演(平成6年6月25日)
『天鼓』シテ・粟谷明生 ,『白是界』シテ・粟谷能夫
粟谷 能夫
粟谷 明生
笠井 賢一
 明生 研究公演の第5回は、能夫さんが『白是界』、私が『天鼓』に取り組みました。舞台は目黒の喜多能楽堂で催すことにしました。
明生 研究公演の第5回は、能夫さんが『白是界』、私が『天鼓』に取り組みました。舞台は目黒の喜多能楽堂で催すことにしました。
能夫 そうだね。研究公演は最初、二番立で銕仙会の舞台で催していたけれど、お客様から桟敷席での二番は身体がきついと言われて・・・。
明生 第4回は『蝉丸』一番なので銕仙会能楽研修所、その前の第3回『求塚』(シテは友枝昭世氏、我々は地謡)は友枝昭世氏の客演でしたので喜多能楽堂で催しました。3回4回と計画し実行に移しながら、やはりそれぞれのお能をしなくてはということで、第5回は又元に戻し、それぞれ一番ずつに、そして見る側の事も考え、喜多能楽堂で催すことにしたわけです。
笠井 それで研究公演は充実してきたのではないですか。お二人の思いもあって・・・。
明生 この回までは、私の曲目選定は能夫さんのアドバイスを多分に受けて決めていました。第8回から、私自身でこの曲を試みたいと言えるようになったと思えるのですが。それまでは『松風』等の大曲は何となくもう少し先にしようという気持ちはありましたが、計画はそろそろかな・・・などと。つまりそれまではどの曲を勤めるかと自分で選ばなかった、というより、選ぶ技倆がなかったのでしょう・・・。研究公演だけでなく、宮島の桃花祭の 御神能での『通小町』、秋田のまほろば公演での『鬼界島』など、他の舞台も知らず知らずのうちに能夫さんにこれとこれは勤めておいたほうが良いというレールを敷かれ、それにしっかり乗せられていた感じです。5回目の研究公演のときも、研究公演だからこそできる、また今ぐらいに一度やらなくてはと、能夫さんが『天鼓』を選んでくれたのです。『天鼓』は少し年を経てからでなくてはいけないのではと私は思っていたんですが・・・。それで研究公演で勤めるなら一つの試みとして盤渉(ばんしき)の太鼓入りという今までの喜多流にはなかった形を経験してみたかったんですよ。
笠井 普通はやらないでしょ。
明生 喜多流は通常『天鼓』の楽は大小楽の黄渉なのですが、まず楽は盤渉でやりたくて、それは勉強の為、経験しておきたいということもありまして。その盤渉も 大小鼓の盤渉にするか、太鼓入りの盤渉にするか。
以前に盤渉楽についてお囃子方から喜多流の大小楽での盤渉は打ちにくい、盤渉に太鼓が入らないのは喜多流だけということを聞いていましたので、自分の時はどうにか手をつけてみたいと思っていまして、お相手の国川純さんや観世元伯さん(当時元則)松田弘之さん、亀井俊一さんにご相談して、研究公演ですので試しに太鼓を入れてみたい旨お願いして、元伯君は元信先生に相談されて一応問題なしという許可を得て出来たわけです。
笠井 観世流の小書「弄鼓の舞」のような感じになるのですか?
能夫 「弄鼓」は盤渉になって太鼓が入るのですね。
笠井 「弄鼓」は華やかなと言うか、音楽の精霊の戯れといった感じ、全体の重さはあるけれどスピードアップする感じですね。それでうまくいきましたか?
明生 自分としてはうまくいったと思っています。元伯君は喜んでくれましたよ。彼に言わせるといつも打っているところを、じーと、ずーと聞いているのは結構辛く悲しいって、他流では打てて、囃して曲に参加出来るのに、ちっとも面白くないと言うのです。あのときは打ちあげのところの手をどう変えようかと考えてくれて、兎に角結果は「やっぱりこちらの方が良いですよ」と気持良く打ってくれた感じでした。
笠井 喜多流で『天鼓』の盤渉に太鼓を入れるなんてことは、かなり大胆なことでしょう。
能夫 そうでしょ。普通、喜多流では大小楽ですから。
笠井 それを研究公演だからといって通せたわけ?
能夫 試みたいという意思表示をして・・・。
明生 今回は特別でということで・・・。
笠井 それは、誰に了承してもらうの?
明生 まず友枝昭世師と父と、自分の師匠筋です。それから仲間うち、あとはお相手してくださる囃子方とその関連、ここをちゃんとしておかないといけないですから。あとで問題になるのはいやだから、一応皆様に納得して頂いてその成果を見ようということです。
能夫 やはりこういうことは、いろいろ相談してOKをとらないとできませんよ。

笠井 作り物の位置はどこに?
明生 喜多流はワキ正面の前に太鼓、そして一畳台もありますよ。
笠井 金春流と同じだね。観世流は正先に置く。
明生 『富士太鼓』のときと同じでしょう。
能夫 真ん中に置くといいでしょう。うちのでは後シテは舞いにくいのよ。後シテでは場所が違うのだから(前場は宮中で鼓を打つ場面、後場は天鼓の霊を弔う管絃講の場)代えてもいいかな。
明生 一畳台があるので舞いにくいことは確かです。風情としては良いのですが。鼓を打った撥をどこに置くか、懐中するか、打った後の処理の方法が未解決です。未だに良い形は見つかっていません、問題ありですよ。
笠井 「波を穿ち袖を返すや」のところはどういう風にするの?
明生 観世さんはあそこ、速くて派手な型で舞われますよね。両手で仰ぐような型、喜多流は右手でサシ左袖を前に返すだけ、あまり早くならずに舞い謡うが心得ですが。宝生流はもっとしっかりじゃないかな、前に金井章先生がうちは兎に角早くならないんだとおっしゃていましたから。
前シテと後シテの持続と切り離し
明生 ところで、あの『天鼓』のとき、笠井さんから「前シテが中入りするときに、どういう気持ちで帰っていくの?」という質問を受けたことを覚えています。つまり、子供を失った悲しみの老人(前シテの老父)と、後シテの天鼓という少年との関係をどう考え、どう演じ分けるかということだったと思うのですが、あのとき私、「考えていませんよ」とあっさり言って、笠井さんも「あっ、そう」で話が切れてしまったのだけれど、あの場面でどういう風にしなければならなかったか、今日は笠井さんからその答えを聞きたいと思いまして。
笠井 前シテと後シテと違う人間を演ずるときに、自分の中でどういう仕掛けを作るのかということを聞きたかったんですよ。
明生 そうですね、ウーン、特別な意識はないと思うのですが。装束を着替えながら、自然と気持ちが変わっていくということでしょうか。あとは出ていけば自ずと次の役になるという風に、意識せずともなりきれるまで稽古してしまうとか、子供の頃からの慣れが演じ手をしっかり支えているように思えるのですが。
笠井 だけど、親の老人の嘆きが体に残っているとすると、その同じ体で、少年の舞を舞うときに、思いをどんな風に表現出来るかって思うよ。そこにはやっぱり、役者の気持ちが問われるという感じがしますね。役者の持続と切り離し方というか・・・。
能夫 心情の起伏もあるし・・・。
笠井 老人の思いと、死んだ方の天鼓の思いだね。若者をどう演じるか。音楽性と舞い事をどう対比させるか、これらは課題だと思う。この曲で役者はすごく鍛えられるという感じがします。
能夫 そういうことですね。
笠井 普通の新劇とか現代劇なら、たとえばマクベスで、マクベス夫人が夫をそそのかして主人を殺すという陰謀を実行する。弱気になる夫に対して、私が一度決意したら、自分の乳房を吸っている赤ん坊から乳首を無理矢理引き離し、脳味噌をつぶすことだってできると迫るセリフがあるんです。それほど気性の激しい女性として描かれていながら、後半になると、狂気になって「老人にこんなに血があるとは思わなかった」といって、夢遊病者のように手を何度も洗うシーンが出てくる。弱い人間として描かれているんです。
能夫 罪の深さということですね。
笠井 このように芝居は、最初強い人間でも弱い人間になっていくということはある、それでも一人の人格としてつながっているわけでしょ。だから演じる側も、途中に性格的な転換があっても、同じ人間のつながりの中で、ある想像力を働かせれば演じられなくもないと思うのです。犯罪を犯すときは強気でも最後はしおれてしまう、というのはそれなりのリアリティがあるんじゃないですか。
能夫 ありますね。
笠井 その人物の人格を続けていくしかないわけ。ハムレットはハムレットを続け、マクベスはマクベスを続けていくしかない。いきなり別な人物を演じることはないわけですよ。
明生 ウーン。私たち能楽師は、平気で別な人物を演じていますね。
笠井 そういう台本があって、演出があって、与えられているからやっているけれど、それが平気だというのは、かなり普通じゃないわけですよ。
能夫・明生 そうだね(笑い)。
明生 西洋の演劇などでは、こういうことはそれほど難しいことなのですか。
笠井 普通はないでしょ。『船弁慶』で前シテでは静御前を舞い、後シテで知盛になるというのは、別の人物になる方法論、働きがあって、それはそれで作ってしまうわけだけれど、それも後でできた話だからね。世阿弥のころの能はそういうものはそれほどなかったし、古能ではもちろんなかったわけです。
能夫 前シテ後シテを違う役者が演じていた可能性もあるしね。
笠井 お能では全然違う人間になるからね。もともとは前シテ、後シテを別人が演じていたと考えられている『昭君』だって、前シテの昭君の父の白桃(はくどう)と、後シテの単于(ぜんう)の亡霊を一人のシテが演じるスタイルに変えてしまった。それがちゃんとできるような構造になっているし、技術的にもまわりで支えている。できるように稽古しているしね。それでも前後の飛躍と持続をどうするかは、技術的にも、大事な問いだと思う。ある種つながっているけれど、どこかで切れている、全く同じではない・・・というものがね。
能夫 『天鼓』というのは、シカケ、ヒラキだけでなくて、シテの心を表現しなければならない曲だと思いますね。謡とか姿で表現していたものから、もう少し深くお能に入っていかなければならないと思う。本当のことを言ったら、あの前シテの老人の悲しさを若い人間が演じられるようなものではないでしょう。でも修業過程の中で、どんどん若い人にもやらせている。みんなシカケ、ヒラキでやっているけれど、やっぱり違う。能の深層にふれていかないといけない・・・。
明生 『高砂』などの脇能の尉とは違うわけですから、そこをどう表現するかですね。それから中入り前、それまで鳴らなかった鼓を老人が打ったら音が出たというので、帝も哀れに思われて老人に褒美を与え、老人も「あら、ありがたや」と言い帰っていくというのが嫌でねえ。
能夫 あそこを省略する演出もあるよね。小書「弄鼓之舞」では、恩賞をあげると言われて「あらありがたや、さらばまかり候べし」という言葉をなくし、すぐにアイがシテを呼んで老人を私宅へ送るという演出にしている。
笠井 恩賞をなくして、ただ管絃講という供養だけにするという演出もありますね。
明生 でも、あの研究公演ではそこまではできなかったですね。言葉をなくすところまでは・・・。帝が哀れと思し召して、「竜眼(両眼)に御涙を浮かめ給ふぞ有難き」と、合掌して有り難がるのは、演者側からの意識ではなんだか情けない爺さんだな、今までの嘆きや、音が出た喜びはどこにいってしますの、おかしいじゃないの焦点がずれるよと思うのです。我が子を呂水の江に沈めて殺し、形見の鼓を内裏に没収して、いままたこの老いた父に鳴らぬ鼓を打てという非情な帝ですからね。
能夫 恩賞を与えられて有り難がるのでは、下々のものは、どんなことをされても権力者を崇拝していますという感じになるよね。
明生 観客が見ているのは、我が子を失って悲しみに沈んでいる父親ですよ。前シテのおじいさんが、今度は自分が呼び出されて、殺されるかもしれないという恐怖の中で鼓を打つ、そういう思いに対して、ちょっと落としどころが違うという気がするんですよね。天子様、君子様と崇めるのはちょっと無理があるように思えるのですが。ただ単純に鼓が鳴ってよかったという風になればいいと思うのですが・・・。
能夫 あの場面は情景描写というか、設定を示しただけで、本筋ではないでしょうね。
明生 「竜眼に御涙・・・」などと地謡を謡っているときは 平気だったのに、自分でシテを舞うことになって、少し深く読み込んでみると、「何、これ」になるんですよ。
能夫 その伝で言えば、『西行桜』の「待て暫し・・・」と いうシテの謡もそうですよ。シテが「夢を醒ますなよ、まだまだ寝ていろよ」という意味を込めて、春を惜しみながら「待て暫し」というわけでしょ。本来はワキのセリフだと思うけれど・・・。
笠井 本来はワキだろうと思うけれどね。
明生 その辺は曖昧でもよいのでしょうね。
笠井 過去にワキでやったこともありますよ。でも、何だか折り合いが悪かった。難しいものだね。そこをどうするかでしょう。ワキと共有しながら稽古していかないと難しい。すぐに答えが出ないところですね。
明生 「待て暫し」はシテが謡うところでのほうが説得力が出ていいと思いますけれどね。
能夫 自分に言い聞かせている風情が出るからね。
笠井 その場の情景が豊かになるんですよ。理屈だけで、ここは本来ワキのセリフだろうとやっちゃうとつまらなくなる。
明生 新しいものを作るとき、理屈だけで押して行くとつまらなくなるというのは、そういうことですね。
笠井 説明になってしまうからね。そうではなくて、そこにもっと陰影をつけないと・・・。
能夫 『天鼓』という曲はいろいろなことを考えさせられるね。能楽師としては大事な演じどころです。
笠井 鳴ってよかったと、見る人は感じていると思うけれど。「弄鼓」の考え方でいくと、銕之丞さんは「恩讐の彼方」と言う言い方をされていたけれど、恩とか仇とかは忘れて、ただ音楽の戯れの中にいるという感覚で舞うということ。もうそれぞれ十分苦しんだから、ただ舞おう・・・と。恨み論 でいえば、もう少し恨みを出したくなるところだろうけれど、芸能の本質からすると、舞いながら和解していくというか・・・。
明生 やはり『天鼓』の楽は、高揚して戯れとして舞わないといけませんよね。ノリも浮き浮きしたものがないと、楽しめないとね。
能夫 舞っていると恨みとかは忘れてしまうもの。そういうところがあるでしょう。
笠井 のびやかさみたいなものは、ある意味では楽の一つの特性でもあると思うよ。
明生 演者としてはまず楽をしっかり舞うという基盤があってその上に『天鼓』らしい楽を舞うという段階に入る事が肝要で、楽が舞えたから楽物すべてが出来るなどと錯覚してはいけないですよ。それぞれの曲での楽の立場みたいなものを認識しないと、これは若い修業時代には先生はおっしゃらなかったけれど、自分で発見するものかな。
笠井 悪尉系の楽もまた別ですからね。
能夫 明生 そうですね。
明生 私としてはこの時期あたりから、いろいろな試み冒険が出来始めた、一つの転換期ではありました。そう、曲の内容の読み込みの大切さを教えられはじめられたから。ね、笠井さん!
先人の偉大さを思う『白是界』

笠井 さて、能夫さんは『白是界』をどうして演じようと思ったの。
明生 これは伝書の問題があって、能夫さんが是非やってみたいということだったと思います。今までやっている『白是界』でないようなものを作りたいということで・・・。
能夫 『白是界』は十四世喜多六平太先生が熱海の温泉で何泊かこもって作ったと言われているんだけれど、原本があるんですよ。
明生 渋谷(しぶたに)流の原本がありますね。
能夫 渋谷流というのは、江戸時代京都に手申楽という素人申楽の渋谷道修という人がいて、その一族の流派です。その一族の高村家の何代目かが、喜多流に養子に入り八代喜多宗家になっています。渋谷道修は江戸の中期の人じゃないですか。『経政』の「烏手」とか『枕慈童』の「クセ」なども渋谷流なんです。『白是界』という小書は、喜多流と養子縁組するときに渋谷家からもってきたものと伝えられています。その確実な証拠というか、渋谷の「付け」というものがあります。
明生 高林さんのところにありますね。
能夫 高林さんのところにもあるし、金子匡一さんのところにもあるはずです。そこには『白是界』のことといって、渋谷流の型付が載っています。僕はそういうものを若いころから目にしていたから・・・。六平太先生のお作りになったものともそう違わないけれども、でもやはり、あの研究公演という場で、原本ゼロでスタートするわけにはいかないでしょう。原本からでないと何事も起こせないと思うのです。
笠井 それはそうですよ。原本ではこうだった、その上に自分の発想をこうつけましたということでないとね。
能夫 前シテもツレも、寿夫さんがやったように面をかけてやりたかったけれど、そこまでの位になかったな・・・、僕は。あのときは直面でやったよね。
明生 ツレは私が勤めたんですが、あのとき直面というのがすごく困った。『天鼓』を舞ったばかりでしょう。汗はひかないし、顔に当て物の跡がついているみたいで。このツレは6回ほど勤めてますが、太郎坊はシテの是界坊に対比するような力強さがないといけないと教えられていますよ。あとで是界坊の陰謀を密告するおかしな者なんですが。

能夫 それであの時は、クセは省略したね。
明生 そう、クセはやりませんでした。
能夫 あのクセはいいところではあるけれど、仏敵、法敵となるのが悲しいとか.それでもその迷いで仏に帰依するわけにもいかないとかウジウジ言っているわけでしょ。そんなことは百も承知で出て行くエネルギーがあっていいのではないかということで、クセは謡わないことにしたんですね。
明生 さあ仏法を妨げよう、さあやろうと直ぐにロンギに入るということでした。
能夫 さあ戦おう! とね。前シテではそんなことを考えていたのです。
笠井 後シテの身体的なものは?
能夫 身体的なものは、うまくいかなかった。「これを不動と名付けたり、」と言って、パワフルでエネルギッシュになるところ、先人の壁と言うか、そういうものを感じましたよ。
笠井 先人の上手は、見ているだけで世界ができるというところがある。
能夫 自分のは世界ができあがらないんですよ。そういう感じがしました。
笠井 運びの問題?
能夫 この曲は緩急がないのですよ。いつもノッシリ、ノッシリなんだ。働きもノッシリ。
笠井 それで存在感が出てこない・・・。
能夫 ゆっくりだけでは、メリハリがつかないんです。謡いの気運は上がっていくんだけれど。自分でもここはこうしなければと考えているけれども、耐え切れなくなるし、運びも弱くなるし・・・反省しました。やはり先人のすごさと いおうか、ただ見ていただけでその境地に行くというのはやはりすごい。
明生 『白是界』は鹿背杖を使わず羽団扇(はうちわ)で通すでしょ。あれでエネルギッシュに見せるというのはすごく難しいのです。当然赤頭とは違う凄まじさが現れないといけないし、羽団扇を持ちながら音をたてずに雲間の拍子を踏むだけでも大変なエネルギーが必要ですよね。
能夫 後シテはベシミ悪尉という面をかけるのだけれど・・・。
明生 面、装束という兜と鎧が何とかしてくれるという頼る気持に・・・。
能夫 それが空虚だったりするんですよ。
笠井 先人たちは何でああいう風に存在感があるのかね。
能夫 すごいと思うよ。
笠井 古い映像で身体的にはボロボロになっていても、悪くないものね。
明生 今の梅若六郎さんが鞍馬天狗の子方をやられている、梅若実氏のビデオ、肉体的に弱られていても凄いよ、しっかり大天狗像が浮かび上がってくるから、驚きですよ。
笠井 まぎれもなく。
明生 ある種の、技法を体得しないといけないのかなと思います。『鞍馬天狗』でもなんでも「赤頭」の方はそれなりにできるが、「白頭」は難しい。白の方が格好はいいし、位も高いというので二回目の演能になると我々は白頭を目指しますが、そこにしっかりした軸というか芯というか、固いものがないと、「変だね」、「下手だね」と言われてしまう。軸や芯みたいなものに、何を付け加えるかが問題と偉そうに思うのですが。特に『白是界』は「白頭」より重い扱いで、曲名まで『是界』でなく『白是界』に変わっているわけですから。
能夫 先人の偉大さだよね。でもそれもやってみないとわからないよ。『白是界』という大きな壁にぶつかってみないと、この曲のすごさというものがわからないと思うよ。
明生 技法と意識の両立というのかな。特別な技法、充実の持続の仕方
能夫 先人のものには何か格闘しているものがあるんですよ。
明生 確かに。
能夫 あのときは、喜多流が大事に背負っている『白是界』というものに挑戦してみたかったんだ。できると思ったのに・・・。挫折の一番だったということです。
笠井 そんな感想?
能夫 パワフルなのよ。覚悟してやったんだけれど・・・。 でもやらないと何もわからないから。やってどうなのということだから・・・。
明生 でもやってみてわかったんだからいいじゃないですか。この話を聞くまではそんなにダメージを受けているとは知らなかった・・・。
能夫 ダメージを受けていますよ。先人のすごさといおうか。できると思ったらとんでもない。
笠井 先人たちは、こういうきつい曲をいい年になってもやっているんですよね。でも我々もこういう話ができるというのがいいことじゃないですか。こういう「ロンギ」続けたいね。
写真 天鼓 粟谷明生 撮影 吉越立雄
白是界 粟谷能夫 撮影 あびこ
我流『年来稽古条々』(14)投稿日:2018-06-07
我流『年来稽古条々』(14)
青年期・その八
『道成寺』に向けて
粟谷 能夫
粟谷 明生
明生 先回は『道成寺』がどう設定されたかとか、稽古の話も少し入りましたが、今回は『道成寺』についてもう一回、本番前の話をしてみたいと思います。
能夫 僕の『道成寺』は先輩たちから間があいたでしょ。うちの親父が僕の三、四年前に、芸道五十年というのでやっているけど。あの頃は僕、銕仙会の能をよく見に行っていて、特に観世寿夫さんの存在感のある謡のすごさ、ただ謡うのではなくエネルギーをかけて主張するような衝撃波が伝わってきていたんだ。謡の重要性ということを教えられたと思う。喜多流では型の方が強調されて、謡にまで至らないということは感じていた・・・。 このことは『道成寺』に限ったことではないけれど。
明生 私は『道成寺』から友枝昭世師に習い始めました。師は実際に「こうやるんだ」と、目の前で見せてくださる。それまでは実先生がご高齢であったため、実際に見せて下さるというより口頭でのご注意が主でしたので、その指導は衝撃的でした。目の前でこうする、でもキミはこうなっていると・・・
能夫 ここがこう駄目だと真似されるわけでしょ。
明生 そう。それはすごい衝撃ですよ。私にとっては新しい一ページが開かれたという感じでした。父が友枝氏に稽古の経過を聞くと「駄目ですねえ。徹底的にやり直さないと」と言われたとか・・・(笑い)。
能夫 まあ大変なことだよな。『道成寺』という曲は。
明生 それまで私はお能に対して少し横向いていて、『道成寺』当たりが立ち直る機会になったわけですから当然ですよ。乱拍子からやり直しという感じでね。友枝師にとって、教えるからにはここは絶対直さないと、というところが多々あったと思います。だから謡の注意以前に、型を徹底的に直そうという・・・。乱拍子に絡む和歌の謡、そして大事な次第「作りし罪も消えぬべき」や道行などは後回しになってしまうのです。本来能の稽古は謡の稽古から入り、次に型でしょうけれど・・・。今の状況はあまり褒められたものではないのかもしれませんね。
能夫 そういう傾向はあるなあ。でも具体的に体を使って教えてもらえたというのは大きいことだよ。僕の場合は、先輩たちから聞きながら自分なりに作っていったものを見ていただくという形だったからね。自分との闘いというか、日々集中して稽古をしながら、人生というか、その時間を『道成寺』に捧げるという感覚。『道成寺』のために生きているみたいな、充実した時間を過ごしたという喜びね。実先生は内弟子には本当に一生懸命稽古して下さった人で、そういう方向性のもとで出来た喜びと達成感はあるね。
明生 能夫さんのころは乱拍子のために幸流に入門するということをしましたね。
能夫 そう。乱拍子は喜多流からではなく幸流から相伝を受けるという建前になっていたから。
明生 特別な秘伝のようなものを教えてもらいましたか。
能夫 特別ということはそれほどないよ。入門というのは形式だよ。でも幸流から、乱拍子の間については教わったね。二呼吸プラスアルファから二呼吸になって、一呼吸プラスアルファ、そして一呼吸と、和歌の段までだんだん間が詰まって行くと。間が詰まって行くからテンションが上がって行って、和歌の段でそして最後に爆発するわけですよ。そういう風に思ってやっていますからと横山貴俊氏から教わったね。
明生 小鼓との呼吸は難しいですね。仕掛け操るのは小鼓ですからね・・・。
シテが能動的に動いては乱拍子の規範から外れてしまうでしょう。
能夫 だから、こみの取り方、小鼓方の心得、そういうことを習うのが入門ということになるだろうね。
明生 稽古法についていえば、私は装束をつけての稽古を一回やらせてもらいました。
能夫 申合せの前だったね。
明生 申合せでは装束をつけない慣習ですから、いきなり本番では自信がなかったので、それでお願いして。私は『葵上』が『道成寺』の後だったので、坪折、腰巻という格好の経験がなくて、いろいろなことが初体験でした。あのときは能夫さんと友枝師と父が立ち会ってくれました。
能夫 喜多流では当時、下申合せという習慣がなかったからね。乱拍子は別に稽古があったけれど、総合稽古のようなものは申合せ以外にはなかった。
明生 装束はわが家にもあることだし。装束をつけて実際どうなるか、ということをやった覚えがあります。
能夫 観世流では下申合せを全員揃ってやるでしょう。
明生 そこへいくと喜多流は申合せだけでいきなり本番ですから、無謀というか・・・。
能夫 鐘入りなんか本番まで一度もやらないのだから恐いよ。どうなるのだろうかと思ってね。
明生 鐘入りはあるところまではシテの責任で、それ以後は鐘後見の責任というところがあります。鐘後見にしてみれば、シテはちゃんと鐘の下まで来いよという気持ちだし、シテとしてはうまく鐘の下に行けるか、強いプレッシャーがありますね。
能夫 昔話でシテが鐘の下に行けなかったということがあって・・・。僕らはそこに行けないとは夢にも思っていないけれど、でもどういう状況になるかわからない、それはもう胃が痛くなるほど恐かった。当日までね。
明生 その鐘の作り物はシテの責任で作りますね。昔は鐘の下の周囲に五銭硬貨をいれ、落下時に金属音をさせたり、内側の天には赤頭を入れたりして衝撃を和らげるようにしていましたが、私のときはスポンジ系統のものを入れて工夫しました。
能夫 僕は棚を四つ取り付けて面を前後に二つ。二つというのは面が割れたりする事故に備えて。それまでは面をただひもで鐘の内側の骨組みの竹に結わえているだけだったから危険だったよ。あとの二つの棚は妙鉢を入れるね。
明生 あの四つの棚は能夫さんのやり方なのですか。鐘の中のことはすべてシテの責任で行いますから、事前に能夫さんに一度入って見てもらいましたね。
能夫 そういう意味では『道成寺』というのは、いろいろなことを総合的に学ぶ機会でもあるね。
明生 作り物や面装束だけでなく、たとえば小鼓のお相手をどなたにお願いするかとか・・・。
能夫 『道成寺』の制作というか、経済までも勉強する必要があるね。『道成寺』は親がかりでやることが多いけれど、ある程度披く人間が責任を持ってやった方がいい。独立する機会でもあるし・・・。
明生 『道成寺』にかかる経費の帳簿を見せてもらうと、大変なことをやらせてもらうのだということがわかります。稽古が始まって本番までの一年と、税務処理をすませるまでの残りの時間、とても長丁場です。うちの場合は一つの家族で催しているありがたさを痛切に感じますが、でも、経済のこと、三役の配役や交渉まで、総合的に知っていかないといけませんね。
能夫 能の仕組みをわかるために、『道成寺』を通して汗をかいた方がいいと思うね。そういえば、『道成寺』の年は、僕、アスレチッククラブに通っていたよ。体作りね。
明生 私も行きました。『道成寺』は体力がいると思って。あの当時三十歳でこんなに体力が落ちているのか、二十代とは違ってきた・・・と唖然としたのを覚えていますよ。
能夫 確かに、それは思ったね。だから負荷をかけて耐久力をつけるといおうか・・・。
明生 今となってはあのころに戻りたいけれど(笑い)。当時はすべてに対して、出来る限りしておこうという気持ちでいましたから、肉体的にもある自信を持っておきたいと目指したわけです。
能夫 そうだったな。
明生 人に指図される前に、先に自分で、という気持ちで。
能夫 自覚だな。トラックを走って、腹筋何回、背筋何回ってね。それで効果があったかはわからないけれど、だけどやっておきたかった。
明生 そういうことをやっていると、本番で「おまーく」といって出て行くときの自分自身への充足感が違うと思っていましたから、今でもそう思いますよ。
能夫 『道成寺』に向けての一年はやはり特別なものだったかもしれないな。だから舞台によいものが出てくるんだろうね。
明生 若さもあったし。でも能楽師たるもの、年に一番は大曲を舞って、緊張感ある一年を意識的に作っていかなければいけませんね。
能夫 そうね。『道成寺』が終わった途端に、運動をやめたせいかギックリ腰になってね。急にやめたからね。
明生 そうですよ。能も大曲を演じた後、また舞わないとお能のギックリ腰になってしまいますよ。
能夫 そうか、お能のギックリ腰ね。これはいけないね(笑い)。
つづく
春の粟谷能の会を終えて(平成16年)投稿日:2018-06-07
春の粟谷能の会を終えて(平成16年)
粟谷 能夫
粟谷 明生
笠井 賢一
 明生 平成16年春の粟谷能の会は、初番が父の『月宮殿』、真ん中が能夫さんの『当麻』、そして最後が私の『鵺』でした。能夫さんの『当麻』は2時間25分、喜多流では最長記録になりました。
明生 平成16年春の粟谷能の会は、初番が父の『月宮殿』、真ん中が能夫さんの『当麻』、そして最後が私の『鵺』でした。能夫さんの『当麻』は2時間25分、喜多流では最長記録になりました。
笠井 『当麻』はね、能夫さんの思いはちゃんと伝わってくるんですが、あの早舞はやっぱり、あの位の取り方は、僕はちょっと疑問に感じるな。
能夫 ちょっと重過ぎたでしょ。
笠井 重いね。
能夫 段ごとにもう少しノッテくればいいんでしょうが。
笠井 あの感じでは昇天していけないよ。前があれだけたっぷり演じたのだから、後の化身になったときには、もう少しスピードを運んで、白蓮を抱いて昇天してほしいと思うんですがね。
能夫 昇天もあるし、西方浄土の豊かさもある。甘さというか、すばらしさの表現もあるし。静夫(故観世銕之亟)さんも仰っていらしたけれど、あそこは機を織る心だと。こちらとしても、しっかり舞いたいという気持ちがあるからどうしてもしっかりと重くなってしまう。申合のときはもっとすごくて、がんじがらめになったようでしたね。
笠井 銕仙会では寿夫さんも含めて、『当麻』は割とよく演じていて、地謡も含めて大事にしている曲ですが、それでもあれほど重くれていないというか。
能夫 そうですよね。
笠井 緩急がなかったように思えるのですよ。クセは、銕仙会では脇能の域で謡うというようなこともあるけれど。
能夫 判りますよ。喜多流ではロンギが強吟なんで、途中から和吟(弱吟)になりますが、観世流のように最初から和吟だと世界が変わりやすいと思うのですが、
笠井 観世流のクセからロンギにかけてはうまく変わるけれど。でも喜多流ならば喜多流らしく、そこはシテがねじ伏せてでも世界を作っていかないとね。
能夫 それは、そうかもしれないですが現実はね。みんな百戦錬磨なのに僕だけが披きという状況ですから。結構きびしいですよ。
笠井 それはしょうがないけれど、次からは違うようにしなくてはね。
能夫 見ている方はどうかわからないけれど、勤めている方は楽しくてしょうがない曲ですよ。(笑い)こんなに楽しいと思わなかったもの。ただ座っているだけのように見えるでしょうけれど。
笠井 それはあなたの成熟だよ。あれが楽しいとはなかなか思わないよ。
能夫 辛気くさいし、賛美歌だし、宗教法人みたいな曲だと言われるけれど、そんなことないですよ。個が、役者冥利というか、能夫という個があるから表現できると思うし、粟谷能夫という役者の『当麻』を勤める、見るというところに意味があるのではないでしょうか。
笠井 それは、そう。でも次は・・・。
能夫 もうやらないよ(笑い)。あの装束つけての前場は相当疲れます。
すごく体力がいるんですよ。本当にバテちゃうんだなー。翌日ふくらはぎがけいれんを起こしてね、あんなの初めて。
明生 我々、年々筋力が衰えてきますからね。
笠井 前場が大変でした?
能夫 前場の床几ですね。あの姿勢が楽じゃない辛いですよ。クセの謡が自分の体の中を循環する意識で座っているわけですから。
明生 着流しの格好での床几は、他にはあまりないですからね。
笠井 ごまかしがきかないものね。
能夫 そう、ごまかしがきかない。ある人が、寿夫さんの前シテ、後シテの写真を見たら、あれ以上のものはない、あれで極まっているんだから、誰がどうやっても、もうダメと言うんですよ(笑い)。コンチクショウと思うけど、でもそれはそうかもしれませんね。後シテのたたずまいといい、完全、完璧にでき上がっている。写真だから音は聞こえてこないけれど。朝、家を出るときに、「こういう風になるんだゾ!」と言い聞かせて出てきたんですが(笑い)。
明生 イメージをすり込んだわけ。
能夫 前シテは「西吹く秋の風ならん」、よしこれだ! と。装束もこういう風にしてとイメージしたのですが、ダメですよね、どう頑張ってもダメなんですよ・・・。寿夫さんにはなれない。
笠井 まあ、そうおっしゃらずに、自分たちの流儀の中での作り方があるし、それを次の世代に繋げないとね。
能夫 そうしないといけないと思いますが。でも僕はあの写真で、もうイメージが全て、能を見なくても伝わってくるな。あれはすごい写真ですね。
笠井 すごいね。あれが寿夫さんのピークだったんだろうな。
明生 それは、寿夫さんがいくつぐらいだったの。
笠井 40代でしょ。
明生 40代でそういうことができるんだからすごいね。
笠井 だけどね、それは作品として負荷のかけ方だと思うよ。たとえば『定家』なら喜多流という流儀としての蓄積がある。だけど『当麻』には残念ながらそれがない。だからあなたの思いが空回りしてしまうんだ。『定家』の方があなたの思いと喜多流としての作品の作り方と重なり合う部分がある。喜多流の作品であって、しかも粟谷能夫が演っているという充実度が感じられる。ところが『当麻』は能夫さんの思いは伝わってくるが、それがちょっと空転しているというか、支える側との交流感がないように感じたんだ。
能夫 それはそうですね。
笠井 共有するものがあって、ここをこうしたいという主張じゃなかったよね。だから厚みが出ないんだ。
能夫 そう、流儀としての積み上げだね。
笠井 『鵺』にも言えるよ。明生さんはどういう計画をもっていらしたのかな?あの後の面はどうしたの?
明生 ちょっと遊び心なのですが。
笠井 遊びですか。鵺というものが単なる化け物では駄目だと思う。『鵺』というのは、頼政と鵺が重なっていないとね。先代の銕之亟さんも言っていたように頼政自身が鵺的な生き方をするわけですよ。平家全盛のときには従三位まで昇進して・・・。
能夫 源氏に行ったり平家に行ったり、コウモリだよね。
笠井 そして、70歳を越えて反乱を起こして、変な人なんですよ。頼政の中に鵺的なものがあると考えたときに、ただの化け物になっては表現にならない。

明生 面の善し悪しは、個人の見方により様々だと思うのですが…。ただ、笠井さんが今おっしゃったことは十分承知して演じたつもりでして…。それが私の面の選択と笠井さんのイメージとうまくマッチしないのかもしれませんが…、でも…何にせよ伝わらなければいけないのでしょうから…再考の余地はあると思います、仰る通りですから…。私は鵺自体が単に化生の物体とは思いません、土着の神というか、虐げられた反体制側の叫びだと思うのです。現銕之丞さんから聞いた話ですが、先代銕之亟先生は中入前の、振り返りながらグアーッと棹を身体に引きつけ、そして最後に捨てる…、あの喜多流の型がやりたくて、やりたくて、「自分にはできないけれど、喜多さんのあの型はやりたいなあ」とおっしゃっていたらしいのです。それもこのことに通じると思いますが、あの叫びは普通の動物とか単に化け物の叫びではない、中央政権から口をふさがれ、どんどん外に出されていった人間の叫びだと思うのです。最後には空舟に入れられ流されて、自分ではもう止めることができないという、そういういやおうなしに流されていく者を演じたいと思って演じたつもりですが・・・。そのとき面の選択肢として、大飛出、小飛出というのもあったのですが、私はもっと鈍重で野暮な形相というか、古代面のイメージのようなものはないかな…と探したわけです、すこし遊んだわけでして、すいませんお気に召さなくて……。
笠井 あれの彩色を変えればもうちょっとは・・・。
能夫 緑の色がねえ…。
明生 選択ミスと言われますが、私の気持ちはそうなんです、キリリとしたものじゃないという・・・。大飛出ではスケールが大き過ぎて綺麗にまとまりすぎ、小飛出では従来の化け物感覚から離れられない…。
笠井 なるほどね。あなたの課題は、内面的な負荷のかけ方が謡にしても運びにしても弱いように思えたな。特に前シテは、あの格好をしているわけだから、負荷のかけ方が勝負みたいなものでしょ。もっと陰影のある謡があって、負荷のかけ方があっていいと思うよ。つまり思いきりアクセル踏んでブレーキを踏んで、そこまでしかいけないという抵抗感。虐げられているというのもいいんだけれど、鬱屈というか屈折の強さみたいなものが劇場の舞台全部を包み込むような世界にならないと。それが、そこそこなんですよ。出てはいるけど、もっとすごいものがあっていいと思うな。
明生 はい、そうですね。最初の「悲しきかなや身は籠鳥」というところ、自分でちょっとそんなものを意識して謡ったら、反作用だったのか、父にすごく怒られましてね……。
笠井 どういう風に?
明生 「もっと大きい声で謡え! 作るな! 意識するな!」とね。自分では声を絞り込んで、内圧を強くと意識したつもりなんですが…、まあ、そこがしっかり、きちっとと出来ていなかったからだと思うのですが…、「そんな風に謡うんじゃない!」と、お灸を据えられました。「あんなんじゃ、お前の声は聞こえないじゃないか!」ってね。
笠井 そういう、親の世代のダメの出し方は当然あるわけですよ。
明生 その声が出ている声なのか、圧力がかかっている声なのか、それとも開放されっぱなしの声なのか。自分では判らないんですよ。どのようにしたら正解なのか……。例えば、すごく広い劇場での公演だと、この広さなら、どのくらいの声量でやらなければいけないか…と考えてしまう。その程度、度合いというか、その辺が難しいなあ、と正直まだ悩んでいるんですよ。ただバカ声を張り上げてもダメですしね・・・。
笠井 内的な圧力のかけ方が体の中にちゃんとイメージされていて、結果的に声が届いているというのが、自分でわかるようにならないとね。
能夫 それにしても、『鵺』というのは面白い曲だよね。キリ能でありながらスケールもあるし、大変な曲だと思いますね。
笠井 それはそう、大変な曲。役者がわかるもの。
明生 世阿弥が『井筒』を作ったあと、つまり晩年の作ということですが。構成も『井筒』と似ていますね。
能夫 いやあ、面白い曲だよ。組立がしっかりしているからね。
明生 先代銕之亟先生が「さて火をともし、よく見ればと言って覗いてみると、何だ俺じゃないか!」ということだ、と仰っていたらしいですが…。今回『鵺』を勤めて、頼政になったり、鵺になったりしているうちに、そこにもう一人、演者というものがいるという、トライアングルのようなものを感じたんですよ。以前はここからは頼政やります、ここからは鵺の気持ち、みたいにして区切りをつけ演じていたわけですよ。また、そのように教わってもきたわけですから。確かにそのようにやっているのはそうなんですが、いやちょっと違うなあ…、そこに演者粟谷明生という自分がいるじゃないか!そんな気がしたんですよ。変なこと言ってすいませんが……。
笠井 そのトライアングルが、単に整合性のある三角形ではなくて、ゆがんでいるというか、それをぎゅっと自分のところに引き寄せる力がないとね。
能夫 それが必要なんだろうね。
笠井 この間の菊生先生の『月宮殿』、舞になってからは一味違うなと思いましたよ。
明生 前々日あたりから、左足が、うまく出なくて辛い、痛いんだ・・・、身体が言うこと聞かないと悔やんでいたんですが、一応無事に勤められて皆、ほっとしています。父はもう来年から能を舞わないと言っています。
笠井 でも、楽(がく)は楽しそうに舞われているように見えましたよ。
能夫 現場はみんな心配しているんですよ、特に明生君はね…
笠井 あなた方はそう思うかもしれないけれど、僕は、あの楽を見ていると、やっぱりこの人のスケールというものはこういうものだなと、 そういうものが伝わってきましたからね 。
能夫 ある風があって、ちゃんとできるということは大事で、すばらしい事ですよね。
笠井 誰が見ても、そういう風を感じるよ。そういうものを獲得した人というのは、やっぱり違うなと思いますよ。今年で最後ということ?
能夫 16年10月の粟谷能の会『景清』を勤めて…。
明生 『景清』が最後になりますね。
能夫 まあ、その後どうなるかはわかりませんけれど。
明生 粟谷能の会の曲目を決める時に能夫さんが「菊おじちゃん、再来年は何を舞いますか?」って聞いたら、「それはもう無理だろう。いいよ、それより、お前達の地謡を謡ってあげないといけないからなあ…」という返事でした。
能夫 年が重なれば仕方がないことだけれど・・・。
笠井 そうね。
明生 次の世代の我々が頑張らねばいけないということですね。
笠井 そういうことだよ。お二人には頑張ってもらわないとね。
能夫 父と菊生叔父が、粟谷能の会を育ててくれてね。次はお前たちがちゃんとやる番だよと、そういう風にもってきてくれたわけですから。うまくつながっているという気はしますね。
笠井 いやあ、全くそうですよ。来年の粟谷能の会は?
能夫 父の七回忌の追善となりますので、春は僕が『卒都婆小町』で明生君が『小鍛冶「白頭」』、秋は僕が『実盛』で明生君が『松風』の予定です。また12月には久しぶりに粟谷能の会研究公演を復活させ、改めて地謡の勉強をしようかなと思い『木賊』を、シテは友枝昭世さんにお願いしまして、私と明生君で謡ってみたいと思って計画しています。
笠井 大曲が控えていますね。頑張ってください。期待しています。
(平成16年3月)
研究公演つれづれ(その6)投稿日:2018-06-07
研究公演つれづれ(その六)
研究公演第6回(平成7年11月25日)
明生の能『松風』 能夫の仕舞『熊坂』
粟谷 能夫
粟谷 明生
笠井 賢一
 明生 この前(第5回)の研究公演は、能夫さんが『白是界』、私が『天鼓』でした。第3回には地謡の充実ということで、友枝昭世さんに『求塚』のシテをお願いして、我々が謡に取り組むということもやってみたんですが。この辺で自らに大曲の負荷をということになって、第6回に私が『松風』、第7回に能夫さんが『小原御幸』を企画しようということになったのです。
明生 この前(第5回)の研究公演は、能夫さんが『白是界』、私が『天鼓』でした。第3回には地謡の充実ということで、友枝昭世さんに『求塚』のシテをお願いして、我々が謡に取り組むということもやってみたんですが。この辺で自らに大曲の負荷をということになって、第6回に私が『松風』、第7回に能夫さんが『小原御幸』を企画しようということになったのです。
能夫 そうだったね。
明生 それで、第6回の『松風』のときは、父(菊生)が仕舞『芭蕉』を舞って、能夫さんが仕舞『熊坂』を長裃の小書きで舞ったんです。まず『松風』というとーーー、『阿吽』に文章を書き始めたのがこの曲からなのです。
笠井 そうでしたね。演能した後に書く。『松風』からだったんだね。
明生 『阿吽』を作ったときに、笠井さんに何か書かなきゃねって言われて、「じゃ、お弟子さんから原稿をいただいてみましょう」と言ったら、それじゃダメ、自分で書かなくてはと。
笠井 それで書き始めたんだ。
能夫 でも、書くクセがついてよかったね。
笠井 それは稀有なことですよ。なかなか能楽師の中でこういう人はいない。ちゃんと書ける人は癖がつかないとダメなんだよ。特に寿夫さんを信奉しているならね。あの方は書く癖がついていたから、書くことによってお能も変わり、書くことも変わっていったんだから。
能夫 そうか。
笠井 やっぱり怠惰ではいけないんだよ。もちろん能にすべてのエネルギーをかけるんだけれど、その余滴というか、その余波はやっぱり形にしなければいけないよ。
明生 みんな、思っていることはあって、腹の中には入れているんですよ。
能夫 腹から出さなきゃいけないな。
明生 でも、あいつは書くだけで・・・、芸がダメだね・・・といわれるのはいやですから。最初は書くことに抵抗がなかったわけじゃないんですよ。やはりしっかり芸あって、その後にという具合でないとね・・・。
笠井 それはやり方もあるし・・・。書くことで芸のためにもなると思うよ。奇しくも『松風』で明生君が書き始めて、それが習慣になっているということはいいことだよ。他の流儀にもあまりいないからね。能夫さんも書いてくださいよ。曲は日々、後に残しておかないといけないような曲をやっているわけですから。今後は心がけていただいて・・・。
能夫 わかりました。思いはあるんだけれど。 明生 それで・・・、『松風』を選びやりたいというのは、『道成寺』との関連があってです、能夫さんから『道成寺』が終わったら気が抜けるかもしれないけれど、次は『松風』だよ、そこに向かうんだと言われたことが大きかったですね。『道成寺』と『松風』の違いは、やっぱり、『道成寺』は親がかりで、新太郎叔父と父と、上の人たちが作ってくれた、そういうものだと思うけれども、『松風』はそうはいかないということですよ。『松風』は自分でモーションを起こさないとやれない、「お父ちゃんお願いします」とか「そのうち出来るよ」というわけにはいかないんです。そこで、能夫さんと私とで考えたのは、次にやりたい曲は自分たちで創ろうよ、それができる場を作ろうよということでした。言われるままのメニューをこなしているだけの恵まれた環境に甘んじていては駄目ということが、わかり始めたから・・・、それが研究公演の意義でもあったのです。いろいろの試みをやってきて、6回目が私の『松風』で、7回目に能夫さんがあえて『小原御幸』をもってきた、これが、私たちの生き様じゃないかなってね。
明生 それで・・・、『松風』を選びやりたいというのは、『道成寺』との関連があってです、能夫さんから『道成寺』が終わったら気が抜けるかもしれないけれど、次は『松風』だよ、そこに向かうんだと言われたことが大きかったですね。『道成寺』と『松風』の違いは、やっぱり、『道成寺』は親がかりで、新太郎叔父と父と、上の人たちが作ってくれた、そういうものだと思うけれども、『松風』はそうはいかないということですよ。『松風』は自分でモーションを起こさないとやれない、「お父ちゃんお願いします」とか「そのうち出来るよ」というわけにはいかないんです。そこで、能夫さんと私とで考えたのは、次にやりたい曲は自分たちで創ろうよ、それができる場を作ろうよということでした。言われるままのメニューをこなしているだけの恵まれた環境に甘んじていては駄目ということが、わかり始めたから・・・、それが研究公演の意義でもあったのです。いろいろの試みをやってきて、6回目が私の『松風』で、7回目に能夫さんがあえて『小原御幸』をもってきた、これが、私たちの生き様じゃないかなってね。
能夫 『松風』を選んだというのはね・・・。『道成寺』はものすごく稽古してやるでしょ。『松風』もやはりすごく稽古しないとできない、普通の曲のような稽古ではできないんですよ。そういう曲が生きていく中に、ポツンポツンとないと怠惰になるんです。真剣に、ものすごいエネルギー使って、大汗かきながらやるということが徐々になくなるからね。その意味では、一年に一度ぐらいは、『松風』のような、チャレンジする大曲がないといけないという気がするわけね。
明生 自分自身のからだに、ねじを巻くようなものをしっかりと勤めていかないとと思っていましたから・・・。演じて『松風』はツレをやっているという経験がとても貴重だと思いましたね。大きな力にもなるし・・・。『松風』とか『山姥』はツレをやらずにシテをやるべきではないですね、仲間内で密かに「ツレしてシテ同盟」ができるぐらいでね。本当にツレで座っているのが苦しいという経験をした人間が『山姥』の「あーら、物凄の」と謡える。私はどうしても「申し訳ないね」という気持ちが出てきてしまって・・・、飲んだ席でよく話がでるんですよ。、やはりツレをやり、次のステップにシテができる。いきなりシテではないでしょうとね・・・。『松風』のツレで何人かのお相手をしましたが、そういうことをやってはじめて、シテができるということじゃないですかね・・・。私は、一番最初は父のツレをしまして。あのときは、謡を間違えてしまって、そうしたら父がすごく怒ってたんでしょうが・・・。「明生さん、しっかりしてくれなくては困りますよ」と冷ややかに、他人行儀に楽屋で言われてね。しっかり覚えてますよ。 物着の後、シテが作り物の松のところに出るの止める大事なところで、台なしですよ。駄目でしたね。
笠井 それはいくつぐらいのとき? 明生 二十七歳のとき。昭和五十七年の粟谷能の会のときです。その次は昭和六十三年に能夫さんのツレをやりました。
明生 二十七歳のとき。昭和五十七年の粟谷能の会のときです。その次は昭和六十三年に能夫さんのツレをやりました。
笠井 それは能夫さんの『松風』の披きだったんでしょ。
能夫 そうですね。
明生 そのときからは間違わなくなりました。なぜか・・・というと。一番最初の『松風』は申合せが一回しかなくて、要するにあまり稽古をしていなかったんですよ。謡だけ覚えて、先輩から写させて頂いた型付を見て出来ると思っているわけですから、うまくいくわけがないですよね。あの時は途中まではうまくいっていたのですが、最後に興奮してきたときに謡を忘れてしまったのです。能夫さんとやったときは何回も稽古をしました。ここは型付にはこう書いてあるけれど、気持ちがのらないからこの様に替えてなんて注意も受けたりしてね。
笠井 能夫さんとやったときは、昭和六十三年ということは、『道成寺』から三年ぐらいたっているわけだね。明生君が三十二、三歳のころですね。
明生 そうです。それから、クセの少し前の謡に、「幾程なくて世も早う」という、難しい謡所があるのですが、これがなかなか上手く謡えなくて。ここを上手に謡える人は多くないですよ。あのときも何回もダメが出て・・・。
能夫 そういうところは何回もやるといいんですよ。
明生 能夫さんとは何回も稽古して、練っていくわけですよ。能夫さんのお披きでしたからね。それまでのように、ハイ型付写しました、ハイ見ました、やりました、二日後に本番です、ということではないわけですよ。そこでよく考える時間をもてたのが、自分で『松風』をやるときにとても役立っています。
笠井 そのときの『松風』は能夫さんが三十九歳、『道成寺』から八、九年後。明生君がやったのは平成七年だから四十歳。ほぼ同じぐらいにやっているんだね。
能夫 そんなもんでしょう。
明生 その後はあたりまえのことなのですが、『松風』のツレで失敗はしていません。父と大槻自主公演、囃子科協議会や、妙花の会で大村定氏ともやりましたが、それらの会で、ツレがある程度うまくできたのは、能夫さんとやるときに、徹底的に教え込まれた、おざなりにしなかった、その成果がでたと感謝してますよ。
能夫 あのとき明生君にはいろいろ言ったと思うんだ。たとえば、アシラウときでも、シテが向いてから、ツレが向くというのはいやだからねと。ぼやーとしているツレだと、シテが向いているのに、まだ向かない、動かないでそのままなんだよ。あれは絶対にいやですよ。
笠井 気がきかない。気がきかないなんてものじゃないね。能が成り立たない。気持ちツレが早いぐらいの方がまだいいでしょ。
明生 そうです。真の一声で舞台に入るタイミングは、「袂かな」という回し節になったら動くというルールもあるけれど、もっと引き寄せてからでもいいのではとかね。
能夫 今までは回し節のときに出るのが定型パターンだったのだけれど、謡がなくなってから出ようとか、下音になってからにしようよとかね。そういうことをいろいろ研究しました。
明生 ツレの謡に関しても、ただ調子高くでなく、張りと共にテンションの高さ、こういう調子でと本当に謡ってみせてくれてね。
笠井 だから、ツレというのは能楽師が育つ場なのね。子方というのは別にして。子方になれるかどうかは生まれる条件が関係するけれど、ツレというのは、後から出発した人でも、ある水準になったら必ずやらなければならない役でしょ。そこをすっ飛ばしてシテはありえない。ツレをちゃんとやることで、シテとの距離感もわかるし、能そのものが見えてくる。ツレの位置というのはすごく大事だと思うんですよ。こういうと、ツレはシテより一歩下がった存在のように感じやすいけれど、中には『清経』のツレや『松風』のツレもそうだけれど、決してシテの添え物ではない、添え物ではダメだというものがあるよね。
明生 それは私も言われました。
笠井 『松風』なんかは、シテとツレが愛を争い合った姉妹でないと、あのお能は成り立たないわけだよね。そういうことを教わりわかっているツレでないと成り立たない。『山姥』のツレの百万山姥もそう。百万山姥というツレの存在は決して添え物ではないでしょ。あれがいるから山姥が呼び出されてくるわけですよ。その対比が非常に大事なの。だからツレがとても大事。ツレをどういう風に教育するか、これは流儀なりのポリシーによるよ。
能夫 それは大事なことだと思うよ。
笠井 ツレだから添え物でいいではダメで、かといってツレが出過ぎて下品なのもいやだし、曲に応じたツレの位置があり、シテというものがちゃんと見えていないといけない。ツレがあってシテにつながる、地謡があってシテの謡につながる、ある意味では役者を育てるのに非常によいシステムができているわけですよ。それがどこかで一つ一つが単なるパートになっていて、それらの役が密着してからみあっているということに気づいていない人も多い。そういう人は、よいシテができないよね。ましてやツレをやらないでいきなりシテにいくのは論外ですよ。
明生 シテとツレが連吟をするときでも、シテにべったり寄りかかるツレがいるでしょ。あれシテからすると、重くくたびれますね。連吟のツレはどんどん積極的に謡ってくれなければ、シテに負担をかけさせない気持がないと。シテは連吟ということで謡いながら少し楽ができるぐらいのものでなくてはと思うのです。ツレに任せながら最後はシテがコントロールする、大事なポイントはシテが握っているというような、長丁場の一曲を作っていくときにはとても大事なのです。だから最初に父が私と一緒にやったときは大変だったと思いますよ。こっちはできないし、それを全部カバーしながらのシテの疲労度。能夫さんに教わったのは積極的に声を出すということ。好きな調子で出してくれ、あとでコントロールするからと言われた。真の一声の「塩汲み車、僅かなる」の連吟のところ、妙に萎縮せず、堂々と謡わなけてはと言われました。ですから自分がシテを勤めたときも、ツレの長島茂君が、稽古で私の謡を聞いて調子を探ってから謡出すので、それはやめよう、君が声を出して構わないんだと、自分が言われたことと同じこと言ったんですよ。シテにまかせるのではなく、ツレも前面にでて手伝ってくれとね。
笠井 それがツレという役の位置だと思うんだ。
能夫 『松風』もそうだけれど、連吟というのが大変難しいものなんですよ。やっぱり一緒に稽古しないとね。できる限り稽古していれば、お互いの呼吸がわかってくるでしょ。
明生 この間は、絶句の間か、心持ちの間かというのも、そこで自然とわかってきますよ。
能夫 何度もやっていればね。
明生 父との時はあまりに「任せるよ、任せるから」といわれて、シテが謡わないから、てっきり、止まったかなと思って、私が少しフライング気味に謡うと、「駄目だね。この間が大事なところなんだ」といわれてね。そうかと思うと、心持ちと待っているとそうでなかったりして(笑い)。
笠井 親子でもわからないかねえ(笑い)。
明生 一緒に稽古が少ないからね、わかりにくいですよ。新太郎伯父と能夫さんもそうだったかもしれませんよ。かえって従兄弟ぐらいの関係、近いけれど一緒じゃないという距離というか間柄の方がいいのではないでしょうか。
あの時は装束については、私が着たいというものがつけられて・・・嬉しかった。印象的だった新太郎伯父の松模様の紫長絹、裏に大きく松が描いてあるもので、そういうものを着れた喜びみたいなものがありました。『松風』のころは、能をやろうという意識が充実し始めというか、やっと芽生えたんですね・・・真剣にやっていますから・・・(笑い)。舞い終えて鏡の間に戻ってきたときに、直ぐ自分の姿を見みたい!と思いましたから。ああ、こういう格好していたのかと思って、それからようやく面をとるという。それまでの経験ではそういうことはなかったですからね。いつもああ、終わったやれやれ、「早く面、装束とってよ」という感じでしたからね。(笑い)
笠井 明生さんも、やっとそれで成熟したね。
能夫 そうだね。それはいいことだ。
明生 それから、お能は一人では何もできないんだということを強く知らされたのが『道成寺』という大曲だとすれば、自分が能動的に動き、何かを仕掛けなければ何も出てこないんだということを学んだのが『松風』だと思うのです。二時間という長時間を一人で引っ張っていくために・・・。
能夫 そうだなあ。『松風』は中入りもないしね。
明生 途中で野村萬先生や万作先生がいい語りをやってくださるというわけにいかない、物語を説明してくれるということがないわけですからね。
能夫 『富士太鼓』なんかもそうだけれど、物着で世界を変えるというのは難しいな。『井筒』も昔はそうだったらしいけれど。
笠井 そうだね。今はそれに一曲の時間も長くなっているしね。昔は物着を入れて40分ぐらいでやっていますから。そのぐらいの時間なら、物着で世界がぐっと変わるのは、ある意味では観客にも説得力あったかもしれないし、役者にとっても体力とのバランスがちょうどよかったかもしれない。
能夫 今は二時間ですからね。
笠井 その二時間を気迫をもってやろうとしている感じ、あの時、その意識は伝わってきたよ。明生さんが『熊坂』をやるというので申合せを見せてもらって、喜多流の若い人たちはすごくからだが動くんだということで驚いた。からだのきれに、ある種瞠目したもの。その『熊坂』があって、『弱法師』、そして『松風』でしょ。本格的な三番目物をしたのは初めてでしょ。
明生 そうですね。『東北』や『半蔀』は勤めていますがね。
笠井 『松風』は大曲だもの。
能夫 『松風』やればいろいろなものが見えてくるし、『松風』を見れば、その人間がどれだけのことをやってきたか、何をもっているかがわかるから、思いきってやるのもいいのではないかと・・・。
明生 能夫さんに、『松風』が次の勝負曲だよと言われたので、その通りにしました。
笠井 お能に本気になれなかった明生さんへの早めの注射がきいたということかな。あの舞台にはその期待に応えようとするものが充分あったと思います。舞台の完成度を高めるべく向かっていく姿勢がはっきり見えたと思うよ。
能夫 課題を与えるというか、課題曲に挑戦するというよさはあったと思うね。
明生 あのときの地謡はすごいメンバーでしたよ。地頭は父・菊生で、後列は友枝昭世さん、粟谷幸雄叔父、能夫さんでしょ。でも銕仙会という小さな舞台では8人は多すぎたようです、6人編成でよかったぐらいでした、また、真の一声も寸法が余るものだから、佃良勝さん(大鼓)や宮増新一郎さん(小鼓)に相談して手を替えていただいたり、破の舞も森田流の寸法を替えて、松田弘之さんにお願いしたりして・・・。 ツレは長島茂君で、ワキは私と同じ年の森常好さんがお相手してくださり、みなさんに助けてもらったという事です。
笠井 ほんと、よい出発になったと思うよ。それからやっぱり、僕はあなたがこの曲から演能レポートを書くようになったことが、すごい財産だと思うね。それが始まったのがよかった。ちょうどよい機会になったと思うよ。
明生 それは、笠井さんが書かなくてはねと言われたから・・・。
笠井 仕掛けは僕だったかもしれないけれど、仕掛けても大丈夫かなという、そういう年でもあったんだよ。自分を成長させるきっかけになる年って、人それぞれにあるじゃない。あなたのように少し外れていた人間が戻ってきて、本当に自分のトータルな世界が見え始めたとき、そしてそれが自分のものになって、次に漕ぎ出せたとき、それが『松風』に挑戦したときだったんじゃないかな。
明生 外れていた人間を、みなさまが暖かく迎えてくれたのだという感じはしますね。 今日はありがとうございました。
写真撮影 松風 前 カラー 三上文規
松風 後 モノクロ 宮地啓二
演劇における演出ということ投稿日:2018-06-07
ロンギの部屋
演劇における演出ということ
喜多流能楽師 粟谷明生
女優 金子あい
舞台スタッフ 伊奈山明子
今年(2009年)の5月2日に、「六道輪廻」という演劇を観に出かけた。
主演に和泉流狂言の人間国宝・野村万作氏、演出および出演に野村萬斎氏、脚本が笠井賢一氏。また、麻実れいさん、若村麻由美さんといったお名前がある。他に狂言師のお仲間、深田博治氏、高野和憲氏、月崎晴夫氏も出演されている。そして、私の弟子で女優の金子あいさんが出演し、演出助手として伊奈山明子さんもかかわっている。そこで、観劇の後、「六道輪廻」に関わった二人の弟子と、演劇について語り合い、面白い話も出たので、ここに書きとめておくことにした。
(粟谷明生)
■役者と演出家
粟谷 現代演劇に関わっているお二人と、能と芝居みたいな話ができれば、と思いまして… 。能では、シテが出演も演出もすべて一人でやりますが、現代演劇ではそれを分業しているわけですね。分業するよさも知りたいし、逆に分業しなくてもいいところもあるでしょう? そこが知りたいですね。
金子 そういえば、演出家はいつから職業としてあるんでしょうかね。 現代演劇に関して言えば、興行の規模が大きいほど分業されていますよね。小さい劇団なんかは人手もお金もないから皆で力を合わせて何でもやらなければならない。あえて共同演出なんというのもありますよ。ひとつ言えることは、古典でなく、新作を創る場合はある程度客観的な 目が必要なんじゃないかしら。つまり主観に埋没してしまうと、その作品をお客さんが見たときにどう感じるかということが全く分からなくなってしまう。自己満足的なところで終わってしまう危険がある。 世阿弥の時代にも本当に演出家はいなかったんですか?今のような演出家というようなことではないにしても、誰か、客観的に見ていたのではないかなと。
伊奈山 実際に演出家はいなかったけれども、大名たちが演出家的な目をもっていて、ああだこうだと言ったのでは?
粟谷 確かにそれはありますね。大名たちは、彼らのパトロンであり、また良い目を持った観客でもあったでしょう。
そして演能者たちが、作品を上演するごとに観客の反応をみて、作品を練っていったのでしょうね。 粟谷明生
粟谷明生
金子 長く続いている芸能は何百年とやっているうちに、これ受けないねというものがそぎ落とされていったんでしようね。最初はつまらないものもたくさんあったと思いますよ。だから、年月が客観性を持たせてくれたというか、そんなところがあるんじゃないかな。
伊奈山 そうですね。いまだに観阿弥・世阿弥の作品が上演されているわけですが、その間にそれらの作品もいろんな演出の変遷をたどってきたでしょうし、時代に合わなくて廃れたものもたくさんあるでしょうね。
喜多流は五流のなかでは最後にできた流派ですが、新進気鋭ともいえた江戸時代の喜多流にも、演出家はいなかったのでしょうか?
粟谷 演出家みたいなものの記載は伝書をみても無いですね。シテ方のセンスに任される…。それが座の長であり、最後には家元に責任がいく事になるのでしょうが…。所詮シテのやりたいように…。
金子 たとえば新作能を、突然、明生先生がシテでやることになったとします。1ヶ月の稽古期間で来月やりますということになったら、その能のおもしろさをどこで判断するか、シテとしてどうするかということになるでしょ。やっぱり自分のかわりに見てくれる客観的な目がある程度必要だなというときに、そこに演出家という分業でやる人が現れてくるんじゃないかという気がするんです。
粟谷 なるほど。
 金子あい
金子あい
金子 つまり新しい作品を短期間でよりよく創るための職人さんみたいなところがあるんじゃないかな。現在の能の上演作品は蓄積されて、能楽界全体のレパートリーになっているんですね。たとえば『船弁慶』を明生先生しかやらないわけではなくて、誰でもやれる状態になっている、みんなが曲をシェアしているんですね。そうすると自分がやらなくとも、誰かの演じるものを見ることができる。そして誰かが演じるものに協力して、自分も参加しながら、その作品を見ることもできるわけです。お互いに見ながらやれるというのは、長年続いている「劇団」としてのメリットじゃないですか。
■「芝居しろ」「ちゃんと謡え」とは?
金子 話は変わりますが、テレビで女座長の大衆劇団のことをやっていたんです。座長の娘が16歳で主演を務めることになって。子別れの話なんですよ。当然、座長のおっかさんが演出というか指導をするわけですよね。
娘の方は今風の顔をした、そう「モーニング娘。」にいるような可愛らしい女の子なんです。それが舌足らずで、「あっしにゃあ・・・」なんてやっているんです。お客さんがおひねりを飛ばしたりして。微笑ましいんです。
座長のおっかさんは厳しくてね、「ここが一番の芝居どころなんだから、もうちょっと芝居しなきゃダメだよ」とか、言っているんですね。それを聞いて、ん?と思って。16歳の未熟な女の子に、「芝居する」というのが何なのかわかるのかなと。私なんかずーっと未熟なので、未だに分からないし出来ない(笑)。「芝居しろ」だけじゃなくてもっと順序だてて教えたりしてもいいのに、と思っちゃった。
伊奈山 「見て、真似ろ!」という世界ですよね。
金子 そうやって彼女はやってきたし、娘もやっていくんでしょうけどね。
粟谷 「芝居しなさいよね」というのは非常に面白いね、私も「ちゃんと謡えよ」なんていいながら、「ちゃんと」って何?みたいなものを恥ずかしながら感じてしまうときがあるのですよ。
金子 それをちゃんと順序だてて教えて欲しいんですよ。
伊奈山 伝統芸能の世界にはそういう順序立てみたいなものはないんですかね。
粟谷 「芝居をちゃんとしなさい」と言われても、子どもはその芝居の「し」の字も知らない、いや薄々知っているのかもしれないが…、果たして合っているのか疑問。指導の言葉って気をつけなきゃいけないね。同じようなこと能楽師にも言えますね。だから、そこをちゃんと把握出来るようにクリアーしたいね。
■ベーシックなテクニック
金子 お芝居でもそうなんですけれど、見て盗めということになると、その見る側の資質だのみになってしまうところがありませんか?_
言葉は悪いですけれど、盗み取る力がある子は、明生先生がどうやっているかを見てどんどん吸収していくわけですが、もしかすると才能が隠れていても貪欲に学ぶという意識が覚醒していない人だと、いたずらに時間が過ぎていってしまう。花開くまでには時間がかかる。その人が覚醒するのを待たないとならない。もちろん目に入っているものはどこかに記憶されているんだろうけれど。人間の記憶って一度目に入ったものは一生忘れないんですってね。思い出さないだけで。今日一日に体験したことは私たちの脳味噌に全部入っているんですよ。
粟谷 そうか。今日こうやって話したことも全部。だけど人間、忘れるからうまくやっていられる、ということもあるね。(笑)
金子 そういう意味でいうと、「門前の小僧、習わぬ経を読む」というのはありますよね。習わなくても、見ていることが脳に蓄積されていて、だから家の子は他の子よりできるみたいなことがあるわけですね。それは絶対的な好条件なんですけれど。ただ、現代的な演劇とか他の芸能をやっていると、短期間で結果を出さなければならない場合も多いから、すばやく結果を得るために論理的な教え方をしてもらうということも必要になってくるんですよ。
粟谷 そうか、金子さんは論理的に教えてくださいって、よく言うね(笑)
金子 ハハハ、言いますね。年月を積み重ねなければ、身につかないということはもちろんありますが、能楽の方でも後進を育てるというときに、もうちょっと、ベーシック技術部分みたいなものをちゃんと論理的に教えてもいいのではないか。もう少し整理して積極的に使っていってもいいんじゃないかという気がするんです。
粟谷 そうですね、でも私自身がそのように教えてもらっていないので、どうしたらいいのかわからない、これが本音です。他流にはもっと合理的で論理的な指導法があるのかもしれませんが…。喜多流はその点については稀薄というか…。
金子 現場では俳優のテクニック的な部分を指摘されることは少ないかもしれないなぁ。
粟谷 テクニック的な部分は指摘しない?
金子 できて当たり前なんですけれど、役者によって技術的なレベルにばらつきがあっても余り論理的な指摘はしないような気がする。外国の演出家なんかだと細かく言う人もいますよね。古典をいろいろやっていると、発音とか滑舌(かつぜつ)とかに敏感になりますね。年のせいかもしれないけど、若手のセリフが聞き取れない時があります。
伊奈山 滑舌が悪いと、言葉がわからないから作品の内容もわからなくなってきますよね。
粟谷 私は大丈夫かな?
金子 お能の発声はちょっと違うので何とも言えないんですけれど。
伊奈山 私はオペラをやっていましたが、発音や発声にはとても細かい指摘がされますね。
粟谷 プロに言うわけ?
伊奈山 プロに言いますよ。オペラの言語はイタリア語やドイツ語ですから、日本人にとって非日常の言語ですからね、必ず公演の際には専門家がついて、歌詞の正しい発音やアクセントを教えます。
発声についていえば、肺や横隔膜、声帯の構造もしっかり勉強しますしね。西洋の芸能は理論に基づいて教えられますね。
 伊奈山明子
伊奈山明子
金子 外人の演出家と仕事をしたとき、「アーティキュレーション(明確な発声の仕方)が悪すぎる、なんて言われて、口のまわりが筋肉痛になるほど指導されました。そのときは、ばかばかしく思うんですけれど、結局、後で色々役に立ちましたね。
粟谷 すごいなあ、それは。
金子 「S」の音とかね。
粟谷 どういうこと?
金子 「さ・し・す・せ・そ」のSの音をはっきり発音するということなんです。「し」なら、しの前に 「スー」(無声)というSの音がくっつく感じ。花咲くの「咲く」だったら、「(S)さく」のように発音するんです。これは新内の師匠にも言われました。
伊奈山 西洋の言語だったら、子音を発音するということは当たり前ですね。
粟谷 能もそうなのかな?
伊奈山 私の個人的な意見ですが、能は聴いていると、子音を立てて発音しているところがあるなと思います。
ちなみに「劇団四季」ではそれと逆に、日本語は母音が大切だ、ということで母音発音でやっていますね。たとえば、「キミは明生くんですね」というのを「いいああいおうんえうえ」って練習するんですよ。
粟谷 何だ、それ?
伊奈山 母音だけで発音させるんです。
粟谷 それは何か効果があるの?
伊奈山 日本語は母音が大切であるという理念で訓練しているようですね。
金子 言いにくい部分をそれで練習すると、言いやすくなりますよ。
粟谷 喜多流は発声については何もしていないね、ていたらくでしてね。正確に記憶し、正確にリズムに合わす、それで吉としているところがありますよ、もっと勉強しなきゃいけないね・・・私もだよ。
金子 長い年月、謡というものが醸成され、完成度が高くなって、お能独特な発声法は確立しているんでしょうが、その一番いい発声法はこうですよという論理的な教え方があるわけではないんですね?
粟谷 そうですね、口伝みたいなものに頼っていますね。能は面をかける曲もあるでしょ、そうなるとこもった声に聞こえます。それは仕方がない、それでいいんだ、と思っている人いるのですよ。やはりはっきりと伝わらなければね?私、知らない曲で何を言っているのかさっぱり分からなくて、初心者の気持ちが判ったことがありましてね(笑)
伊奈山 先生でもわからないことがありますか・・・。
粟谷 僕は今出来る限り声が正確に力強く伝わるようにと心掛けていますが…直面物でたとえば『安宅』の弁慶は面をかけませんからよいのですが、面をかけるものは、毎回同じ面を使用するわけではないので、面当ての具合が悪く、しまった!口が開かない、なんていうときもあるのです。あ??と悔やむが時すでに遅しですよ。
伊奈山 現代人にとって能を理解するのに難しいな、と思われてしまうのは独特の発声に加えて、内容ですよね。
能の本説といわれる作品、たとえば「源氏物語」、「平家物語」といったようなものを昔の人は、そういう物語の内容を分かっていたから謡も聴きとれただろうし理解もしやすかったと思うんですよね。
粟谷 そうですね。
でも、諸大名やその取り巻き連中は分かっていたかもしれないけれど、その下の強制的に見せられていた連中はがどうだったろうね?
伊奈山「平家物語」でいえば、琵琶法師が諸国を渡り歩いて聞かせていたわけですから、庶民にも十分知る機会はあったでしょうね。「源氏物語」も、たくさんの写しがあったようですから、室町期には庶民までとはいかなくても相当広まっていてもおかしくないと思いますよ。
それに『道成寺』のように、民俗的なものも能の題材になっているわけですし・・・。
少なくとも、今の我々より能の内容が身近だったのではないでしょうか。
粟谷 確かに現代の人よりも室町や桃山の時代の人のほうが能の物語の内容を理解していたことはあるでしょうね。
室町から安土桃山時代というのは、日本史で一番すぐれたものを創り出した時代で、面や装束を見ると納得させられますよ。江戸期の特権階級の武士だけというのではなく、民衆を意識して一体となっていた時代ですからね。
江戸期は、きめられた雛型に押しこめられ自由な発想がなくなる、面や装束も創作から模写へと。模写がダメということではないですよ、模写も大事です。結局、長年の継続、変えずに守るという日本の伝統というものが、ひな形が好きなのです、でもやっぱりあの室町、桃山時代のエネルギーみたいなものが一番すばらしいと思いますよ。
たとえば海で死んだ男の顔を想像して「蛙」という表情を打つ、すばらしい想像じゃないですか。
■健忘斉の伝書を読んで
粟谷 喜多流の中興の祖といわれる九代目古能健忘斉の伝書を読むと、健忘斉がどうしてこんなに優れているのか、江戸時代初期に承認された新参者の喜多流が、何故他流を超えて健忘斉があれほど隆盛をふるえたのか?と不思議に思ってね、
金子 なぜかしら?
粟谷 あの時代、観世大夫も宝生大夫もお若くて、下掛の金剛も金春も喜多とは親戚関係にあるからね。時期が良かった。健忘斉は面の善し悪しの見極めの面利きの書物を書いたり、謡い方を説明した「悪魔払」を書いたり、話しているわけ。喜多流は新興勢力だったけれど、健忘斉のお陰で隆盛になり、その後の者も助かったことでしょう。そしてもう一つ忘れてはいけないのが、その次の十世十太夫寿山という人。「先生はこうおっしゃいました」と詳細に書き留めたものがありますが、その業績を評価したいですね。
伊奈山 「申楽談儀」と同じ形式なんですね。
粟谷 能楽の研究では第一人者の表章先生が、喜多の研究をなさったのは、新参者ではあったけれど、健忘斉が書き残した物に興味をひかれたのではないかと思うね。世阿弥の「花伝書」はとても素晴らしい。しかし、その後書き残す作業が少ないのは残念ですね。健忘斉は舞台のことをすべてを網羅して何から何まですべて書いたわけだよ。精神論までね。
伊奈山 世阿弥の最大の功績は伝書を書き残したことですよね。
世阿弥は、観阿弥や息子の元雅の優れた芸のことを書いていますが、私たちはその芸を観ることはできないですからね。
世阿弥が書き残したからこそ、彼らの芸がどうであったか、どのような考えにおいて上演していたか、600年の歳月を経て私たちが知ることができるわけですからね。
粟谷 だから、演じるだけ、話すだけでなく、それを書き残すことの大事さを私は言いたいわけ、観世寿夫さんはすぐれた能役者でありながら、書き残した資料の多さには驚くよ、すごく多いから、それがまた偉大でね。
金子 でも、300年ぐらい経ったら、中興の中興は明生先生、みたいなことになるかもしれませんよ。(笑)
私、この間、仕事で今様を歌わされたんです。今様なんか知らないのに・・・。それはそうとして、今様って「梁塵秘抄」に中に、今様というものを書きとめておこうと思うというくだりがあるんですよね。
粟谷 後白河法皇がね。
金子 有名なところらしいですね。要するに、文章や名画は書くことで後々まで残る。だけど歌や芸能は形に残らない、 それは非常に悲しいことなので、今様というものを書き留めておこうというんですね。芸能に携わっている人なら・・・
粟谷 後白河のその気持ち、わかるな?。
金子 私なんかも、まだ若いから形に残さなくたっていいよ、今やれればと思っていたんですけど、もう少ししたら、形に残すことにものすごく執着を感じるようになってくるんだろうなって。明生先生は私より13歳上だから、たぶんそういうところにだんだん来ているんだろうなって。
粟谷 そう、だからいろいろ書き残そうと、やり始めているのさ。この対談もそのひとつですよ。
金子 「梁塵秘抄」は今様を書き残してくれたわけですけど、残念ながらその節までは残っていない。誰かが復刻したといわれるものを、私のような役者が手探りでそれらしく、歌って見せたりしているわけです・・・。
粟谷 それが本物でなくても、本物に近いものでも、やるしかないのだね。
■序破急理論と心気精
粟谷 今、寿山の伝書を読んでいるのですが、序破急理論のところでの説明が面白くてね。一般的には序破急は、導入・展開・解決と説明されているでしょ。でも伝書では、序は物事の始まり、静かなること、破はそれが破れ動き出す。では、急は何だと思う?
金子 止まる瞬間?
粟谷 いや「急、これ急ぐことにあらず、これ速やかなる心なり」と書いてある。いろいろ序破急の解説はあるけれど、これを読むと能楽師としては、「なるほど!」と納得させられちゃうね。
金子 なるほど?!そのニュアンスすごくよくわかります。分かってない人も多いのでは?
粟谷 今、序破急を無視する人が増えているように思いますが…これはいけないよね。父は理屈を並べるのは嫌いでしたが、謡や舞がもうちゃんと理屈に合っていたね。でも教える時は「俺のやる通りにやれ」だったからね。
伊奈山
金子 なるほど
粟谷 父の教え方は悪くはないが、一般的にはそれだけではなくて…。もう少し親切に、まずは序破急に限らず基本理論は教え、習い…が、いいと思いますね。最近もう一つ面白いと思ったのは、心・気・精という項目。喜多流の大事な3つの心。この言葉、観世流でもあるようですが、「他流では心の気持ち、気の持ち、精の気持ちと3つに分けて考えるが当流さにあらず、心気精すべて1つなり」と書いてある。なんだかわかる?
金子 なに、なに?
粟谷 心・気・精。「心は不動で、気は動くもの、精は形あって無なるもの」と、むずかしいでしょ?ところが寿山の伝書にも、同じような内容が書かれていてね。能の型で、「余精」という一足出ながら両手を前に出す動作の型があるでしょう?
金子 はい
粟谷 精は「余精をもって知るべし」と書いてある。無なるものが、力余って形あるものになる、それが自然と動くような、身体内部からふわ?っと起きる勢いみたいなものなのね。それで余精なんですって。
金子 余精は喜多流だけのものなんですか?
粟谷 さあ知らない。喜多流の伝書に書いてあるから言っているだけのことですよ。『天鼓』で「月も涼しく星も・・・」で、型付には「ヨセイ」とカタカナで書かれているからその真意が判りにくいけれど、どうこの漢字を読んで説明を聞いたら?これなら判る気がしない?
伊奈山 はい、そうですね。お能にしてもバレエでも、型というものがありますが、その型ができた根拠を知らずにやっていますよね。
粟谷 はじめは分からなくてもいいと思うよ、でもある時期になってよい役者を目指すならば、分かろうと努力するは必要だよね。
伊奈山 物真似の領域を超えなければいけないというのは、そういうときじゃないですか。
粟谷 そう。型という基本を根本的に真似尽くした後のこと、それが条件だけどね。それが大人の役者への扉じゃないかな。はじめから精神論を並べても、そりゃダメでしょう。まずは基本で、それが身について応用編で…。
伊奈山 最初から精神論にいってはいけない、と。
粟谷 そう。まずは技の習得、その後に精神的な後ろ盾がほしくなる。そのとき能楽師にとってのバイブルのようなもの、伝書の必要性を知るんだね。私の場合、健忘斎と寿山、そして寿夫さんの本などもまさに後ろ盾なの。
金子 先ほどの序破急は知っていたけれど、心気精は知りませんでした。役者で本番をやるとき、心は不動なりというのは、自分がやろうとしていることがユラユラ揺らいでいてはできないということ、気というのは相手からもらうものだと思うんです。もしくは舞台に流れている目に見えない流れ、あるいはお客さんからもらうもの、それを感じたうえでやり取りをしていると思うんです。それで、精というのがいまひとつ文章にできない・・・。
粟谷 形あって無なるもの、禅問答みたいで難しいね。相手を意識するというのでは、三相応という言葉もある。役者が今何をしなければいけないかというとき、相手は今どういう年代か、相手はどういう人間か、自分はそこで何をしなければいけないかを見極める心得を持つべきだというアドバイスの言葉なので。大事な心得だけど・・・、これは割と自然に体感出来ますね。
金子 対相手の役者ということになるとそういうことなんですが・・・。心気精というのは、何か表現しようとするときに空中に浮かんでくるものに対する役者の心得のような気がして・・・。
粟谷 あとは自分で体得して(笑)序破急理論、心気精、三相応、みんな3つね。
伊奈山 世阿弥の一調二機三声も3つですね。私、この言葉を大切にして声を出すようにしています。
粟谷 声を出すとき、まず調、声の響きなるものを意識して、機はコミですね、そして声、声は「心声に発すとて、おのが心の邪正、おのずから声にあらわる」と悪魔払にあるけれど、調子、機会、声柄を考えるということね
金子 心ある役者なら、どうしようかなといつも考えながら声を出していると思うけれど。でも、中には考えなしで、ドバーッと声を出してしまう役者もいて頼むから出さないでといいたいときもある(笑)。
粟谷 それは、能楽師とて同じ事。とても大事な教えです。
伊奈山 オペラでも一緒ですね。
金子 型やメロディがあるものは、なんとなく声を出してもできるところがありますが、普通の役者は三番の声しかないわけですよ、メロディもなければ型もない。何もないから、感情だけがあって、声ができていないということはありますよね。だから何言っているかわからない、気持ちは分かるけど…みたいなことになる。両方が両立するような訓練がもう少しできるといいんじゃないかなと思います。
粟谷 確かに、日本人の指導者や経験を得た人間が、それなりのものを次の世代に、もうちょっとわかりやすく言わないと、今までのやり方とは別のやり方で教えないといけないということなのでしょうね。
今日はどうもありがとうございました。
(平成21年5月 記 白金・桂寿司にて)
能夫の『芭蕉』について語る投稿日:2018-06-07
能夫の『芭蕉』について語る
粟谷能夫
粟谷明生
笠井 賢一
 明生 今年の春の粟谷能の会(平成15年3月2日)では、能夫さんが『芭蕉』、私が『鉄輪』を勤めました。今回は能夫さんの『芭蕉』について話し合ってみたいと思います。笠井さんが「能夫さんの『芭蕉』がよかった」といろいろなところで言いふらして下さっているという情報が入っているんですけれど・・・。(笑い)
明生 今年の春の粟谷能の会(平成15年3月2日)では、能夫さんが『芭蕉』、私が『鉄輪』を勤めました。今回は能夫さんの『芭蕉』について話し合ってみたいと思います。笠井さんが「能夫さんの『芭蕉』がよかった」といろいろなところで言いふらして下さっているという情報が入っているんですけれど・・・。(笑い)
笠井 ハハハ。言い散らしていますよ!
実際いいと思ったもの。よさは何だったのだろうか、能夫さんご自身がどう考えているか聞いてみたいと思ってきました。
能夫 いやーあ、もう・・・。
明生 この間、「橋の会」の後に、土屋恵一郎さんもおっしゃってました。
笠井 彼もいいと言い、僕もいいと言った。彼のいいと言うのと僕がいいと言うのとでは多少ズレがあるかもしれないけれど、僕はとてもいいと思った。お囃子や地謡は抜群だったとは言い難いけれど、そういうことを越えて能夫さんのシテ一人主義で成り立つんだなということを感じました。能夫さんが五十何年間かの生涯の中で、『芭蕉』という能に思いをかけて、こういう風に向かっているなということが伝わってきて、僕は本当に感動した。能を観るというのは、こういう体験なんだとつくづく思ったよ。能夫さんがどういう生き方をしてきたか、もちろん細かいことは知らないけれど、僕は少なくともここ二十年ぐらい割合見てきたからね。『定家』も観たし、『西行桜』も、いろいろなものを観たけれども、中でも『芭蕉』という曲が、あなたの資質に合い、かつうまい具合に作品として成り立ったなと思った。これは僕にとってすごく幸せな経験だった。能を観る喜びというのはこういうものだという気がするんだよ。ずっと観てきた役者が、一皮むけたとか、技術力がどうなったとかいうことではなく、作品に対する思いが、すごく豊かな形で表現されているということが実感できて、能を観る喜びを感じられた。
能夫 そうですか。
笠井 僕がこんなことを感じたのは久しぶりです。感動の度合いからいうと、あなたのあの『井筒』に匹敵するものだった。いやもっと・・・だった。『井筒』もいろいろアクシデントがありながら、あなたが思いをためてきて、その思いがすごく伝わってくるものだった。あれから十数年たって、今回の『芭蕉』はそれよりはもう一回りも、二回りも豊かになった気がする。いままでいろいろな人の『芭蕉』、銕之亟さんのとかを観てきたけれど、誰にも遜色のない『芭蕉』だったと思った。能夫という人が、こういう風な思いでやる『芭蕉』なんだということがよく伝わってきた。あの曲そのものが無理なく伝わってくる。中入り前の月を見るところなんかすごく豊かに感じられたし、中入りそのものもいいと思った。
能夫 それは仙幸さん(笛方・一噌仙幸氏)に助けて頂いて・・・。仙幸さんが寿夫さんと一緒に勤められたときの譜を吹くからと言ってくださった。少し早めに低い呂から吹き出すなんともいえない味わいのあるアシライ笛を吹いてくださったのです。
笠井 いろいろなことが総合的にうまくいったんでしょうね。それはあなたの思いみたいなものが、若い過剰な思いとはちょっと違って・・・。巧んでこうしようと思ってもできるものじゃない。そういう曲ではないからね、『芭蕉』は。
能夫 そう、巧んでできない。人生そのものをかけないとできない曲ですから。大変だったですよ・・・。
笠井 本当にそういう気がしたね。同輩として、能夫さんがそういうところで仕事をしていることに対して、嬉しいと同時に、刺激され、触発させられた。
能夫 僕の人生の中で、父の『芭蕉』もあったし、静夫さん(故観世銕乃亟さん)の披きで寿夫さんが地を謡っているのも観ているし、そういう、自分の中に『芭蕉』の系譜というか足跡というか、何かあるんだね。わからないなりにも『芭蕉』を観て、何かいいなみたいな、憧れといおうか、自分の中で何か性に合っているといおうか・・・。
笠井 性に合うというのはあるよね。その間『定家』とか『西行桜』とか、それぞれの思いでやってきたと思う。『朝長』なんかも別の意味で思いのある曲だったよね。それぞれに感動があったけれど、『芭蕉』はそれらともちょっと違うんだな。つまりあなたの資質みたいなものが、寿夫さんとの出会いもあり、喜多流のDNAを発見しつつ、そういう流れの中で曲にうまく出会ったという・・・ね。
能夫 まさにそうです。普通に歩んできたら何もなかった。その人の歴史がないと、『芭蕉』にも行き着かないのかな。『芭蕉』をやるには、シテの思いはもちろんだけれど、囃子方も、観る方のこともあるし、全てのものが揃わないといけないし。たまたま年を経たから『芭蕉』をやりますというやり方では『芭蕉』は成立しないようですね。
笠井 成立しないね。
明生 そういう人はだいたい『芭蕉』を選ばないでしょう。
能夫 選ばないよね。あんな面白くもないような、客受けもよくないような曲ね。でもそういう曲を選択できた自分というものを誉めてあげたいと思うんだ。
笠井 そうだね。
能夫 僕のように『芭蕉』に憧れるというのはそうないかもしれないけど。自分がやりたい!と思うこと、でもそれだけではなくて、いろいろな状況といおうか、自分の成長もあるし、いろいろな出会いというか、いろいろなことがないと、『芭蕉』という曲はできない。
笠井 菊生先生がこの間「阿吽」の巻頭に能夫さんの『芭蕉』を地謡として支えるということを書いておられたけれど、いい文章だった。とてもいいと思った。そういう能夫さんを支える人たちがいる、そういうものがなければできないね。
能夫 本当にありがたいよ。自分だけではできない!笛の仙幸さんはいろいろなことを考えながら『芭蕉』を吹いてくださっているよね。余り艶が出てはいけないので、自分なりにこうやってみるとおっしゃって、ある決まったパターンではやっていないね。曲を吹くということで、真摯に、身を削るような思いでやっている。それで、申し合わせのときに、この吹き方がいやだったら言ってね、なんて言うんだよ、嬉しいよね。僕なんかからすれば仙幸さんは大先輩ですよ。もう『芭蕉』だって段違いに多くやっているわけだから、僕はただ「お願いします」と身を委ねる立場なのに。それも仙幸さんとのおつき合いの歴史があるからなんだなとつくづく感じさせられました。やっぱり歴史がないとできない。
笠井 それにお客さんの集中もよかったしね。
能夫 そうね。あんなに長かったのに、「長く感じませんでした」と言ってくれる人が多かったのでホッとしているんです。
笠井 お客さん、観る方にも歴史が必要ということなんだよ。歴史を要求する芸能だね、能というのは。それほどでもないわかりやすい曲もあるけれど、ことに『芭蕉』はそう。
能夫 能というものを知らないと、『芭蕉』のよさも感じられない。そういうことはすごく感じましたね。やる人も観る人も、その人の歴史というか、そういうもので勝負するしかないということを感じましたよ。
明生 能夫さんは、『芭蕉』は自叙伝を書くようなつもりでやると言っていましたね。
笠井 そういうことだろうと思う。能というのは単純に開かれた芸能ではないということを思い知るね。あの『芭蕉』に立ち会える人というのは、能を、そして能夫さんの芸をある程度観てきてくれた人でないと・・・ということがある。僕の観劇体験からいって、他の演劇も含めていろいろ観てきたけれど、今回の『芭蕉』はやっぱり記憶に残る舞台だった。ああいう舞台を観て、能フリークになり追っかけるんだね。追いかけたくなる何かを、ある瞬間に役者は出してくれるときというのがある。能夫さんの『芭蕉』はまさにそういう舞台。
明生 土屋さんは、寿夫さんを感じたと言ってられた。
笠井 ある意味そういうものでしたよ。でも寿夫さんとも違った。寿夫さんほど硬質なものではなかった。もう少し柔らかい月の感じでしたよ。
能夫 土屋さんが、すごく女性を感じたと言って下さったんですが。
笠井 女性的なんだよ。かといって、先代の銕之亟さんのような色気ではない。寿夫さんのような硬質な美学でもない。能夫さんのは澄んでいて、且つ丸みのようなものも感じた。
能夫 僕、静夫さんのお披きのとき、寿夫さんが地頭だったけれど、それを観ているんです。静夫さんの『芭蕉』は非常に情緒的なんだよね。僕は当時、『芭蕉』といえば、もっと寒々とした、冷え冷えとした無機的なものだと思っていたから、あの情緒的な『芭蕉』は理解できなかった・・・。
笠井 寿夫イズムでいけば理解できないよ。
能夫 僕、当時は寿夫イズムにどっぷり漬かっていたから。情緒的な『芭蕉』はいやだなと思った。でも、あれは静夫さんという人の体質で、能というのは演じる人によって、すごく幅があるということを感じた。それも地頭は寿夫さんで、寿夫さんが謡っているんだよ。だけどそれで行けちゃうんだ。人間性というか、体質というか、思いとか、それらが対峙できる曲なんだね。
笠井 人間性が出るんだよ。寿夫さんはおそらく、抽象度の高い謡を謡っていたと思う。あの時代だから。
能夫 そう、そういう謡だった。地は冷ややか、シテは情緒的、こんな彩りが豊かでいいのかという舞台だったよ。お互いがそれぞれの人間性や体臭というものを出して、それがぶつかり合いながらいい味を出していた、そういう感じなんだ。
笠井 なるほどね、その人の体質というか人間性が出るわけだね。
明生 ところで、今回、能夫さんの一つの工夫として、小書「蕉鹿之語」(しょうろくのかたり)を入れましたね。「列子」周穆王篇(しゅうぼくおうへん)にある「芭蕉葉の夢(蕉鹿の夢)」の故事、つまり、狩人が鹿を射て、ひとに見つけられないようにと芭蕉の葉で隠したけれど、その場所を忘れてしまい、夢と諦めたという話ですが、それをアイ語りで入れるという・・・。
能夫 ある人の説では、もともと、ああいうアイの語りがあって『芭蕉』という曲ができたのではないかというんだ。あれがあることで後シテと響き合ってくるのであって、あれがないと「芭蕉葉の夢のうちに、男鹿の鳴く音は聞きながら・・・」と来たってわからないわけでしょ。「蕉鹿之 語」があるからこそ、よりわかりやすいはずなんだ。そういうことを発見し、自分がやるときに、替えアイを入れる小書に挑戦する、そういうことが喜びというかね。こういう喜びを次の世代の人たちにわかってもらいたいよね。
明生 ただ型通りやるのではなく、曲のありようを考えて、自分のものを創り出す喜びですね。
ところで笠井さんは、能夫さんの能は素晴らしかったけれど、あの時の地謡は必ずしもよいとはいえないと最初におっしゃっいましたが、そこのあたりをもう少しくわしく聞かせてくださいませんか。『芭蕉』のときの地謡は父が地頭で、友枝さんがいらして・・・と、今の喜多流では、ある程度最強メンバーを揃えたと思いますが。三月に「橋の会」で友枝さんが『隅田川』を連続して(中一日あけて二日)勤められたときも父が地頭でしたが。それらに駄目が出てしまうと、私としては今後どうしたらいいのか。一体どこをどうしたらいいのか、それがわからなく私としては次に進めない気がして・・・。『芭蕉』という曲が難しいからということなのか、それとも・・・。
笠井 僕は『隅田川』の二日間も観たし、『芭蕉』も観せてもらった。菊生先生の地謡、特に『隅田川』は頂点だろうと思う。いいと思いました。非常に力強いものを感じたし、菊生先生が考えている『隅田川』の感情の起伏はこうなんだというのをすごく感じた。だから課題は菊生先生のじゃない。菊生先生のは文句なしにいい地謡だった。ただそれがシテの友枝さんの方法論に添っているかといったら、ちょっと違うかもしれない。能夫さんのシテともちょっと違うというところはある。そこがすごく難しい問題で、一番の課題だろうね。その後の世代が引き受けていかないといけない課題だと思う。
でも明生さん、貴方の親父さんの『隅田川』の地謡は文句なしに感動させるものだったし、ああいう地謡があっていいと思う。
能夫 ああいう謡い方は、他の流儀にはちょっとないよね。
明生 「橋の会」が終わった後の宴席で、「あんなに大きい声でガンガン謡ったら、また評論家に何か言われるでしょうね」と言ったら、宝生閑さんが「今日の菊ちゃんの謡は、昔の宝生みたいだった」って・・・。
笠井 昔の宝生みたいというのは知らないけれど、ある表現をしようと思ったら、ああなるんだろうね。
能夫 誠心誠意、謡うとそうなりますよ。
明生 ある程度、音はエネルギッシュに出ていないと駄目でしょ。
笠井 それはそう。だけど曲によっては、引き方というか、体の中を通してのエネルギーと、外に出るエネルギーとがあると思う。
能夫 そこが難しいんだよ。
笠井 『隅田川』は号泣したっていいんだよ。ところが『定家』はそうはいかない。「哀知れ」と謡ったときに、身を砕く哀れさを表現するには、いくら大声を出しても伝わらないわけで、内向する力が必要なんだ。寿夫さんにはそういう身を砕くような表現があったと思う。
能夫 ありました。
笠井 それが銕仙会がよく言う引く謡ということなんだ。
明生 『芭蕉』ではどうなんでしょう。
笠井 『芭蕉』は難しいね。『隅田川』の謡のようにはいかない。『定家』とも『西行桜』とも違う。引いた謡が必要だけれど、『芭蕉』は少し暖かくてもいい・・・。
能夫 それはそう思うよ。
笠井 だから、地謡が必ずしもいいとは思わなかったということなんですが・・・、シテを邪魔するほどではなくて、全体としてそれほど気にはならなかったということ。菊生先生が『芭蕉』を謡っているというのはよくわかるけど、ただ、周りが気を合わせていないというか、共有していないという気がした。あの『隅田川』は、みんなで共有している・・・。
明生 共有している・・・それは親類、親子でもあるし、手慣れた曲ということもあるのではないかなー。
能夫 わかる範囲だから。
笠井 『隅田川』は共有できている。だけど『芭蕉』はちょっとバラついたという感じ。それでも、菊生先生の重鎮らしい何かが伝わってきたし、シテを支えていたとは思う。
能夫 菊生叔父はやっぱりスケールの大きさというか、そういうもので支えてくれたと思う。みんなが共有するには、ある価値観というか、共有する思いみたいなものがないといけないんじゃないかな。僕だったら、たとえば寿夫イズムといってもいい、そういう思いがあるけれど、何かみんなが一つになる魂みたいなものを集結しないとむずかしいかもしれないな。『芭蕉』はそういう面でも難しい曲ですよ。
明生 思い、というか自分で何かを持っていないと何もできないと、能夫さんが私に話してくれましたよね。
能夫 『芭蕉』という曲は、伝承とかいうものではなくて、やはり、役者の心とか生きざまとかというものでなければできないのではないかな。型を伝えたからといってできるものではないから。もう伝えようがないよ。
笠井 伝えられない、その余白が能の豊かさですよ。
能夫 豊かさですね。
笠井 型とか技というよりは、心、生涯なんだ。もっと言えば、失った時間の豊かさなんだ。豊かさを表現できるのはどう逆立ちしたって若いうちにはできないよ。僕と能夫さんは五十四歳だけれども、それでも二十代、三十代の人たちとは違う。体がきかなくなった分、どれだけの歯がゆさを自分の心の内に持つか。六十、七十、八十になったらもっとそう、失ったものに対して、ある、いい受け容れ方をしたときに輝くんだと思う。年齢を重ねるというのは、私はまだまだできる、あいつらには負けないと言っているうちは駄目で、自分はこう生きてきて、これがやりたくて、ここに来たよということが大事なんだ。そう思えるようになったとき、すごく豊かなものが見えてくる。能夫さんの『芭蕉』にはそういうものを感じました。能夫さんの心の内にある、思いのたけの伝え方がとてもいい感じだった。生涯に記念すべき一曲を創ったと思うよ。
能夫 ある程度、何というのかな、ここはちゃんとクリアしないと先はないという意識がありましたね。思いのたけがあって、たどり着いたという感じ。上から棚ぼた式に落ちてくるのではなくて、自分からこうしたい、こう上って行くというか、そういうことを感じましたね。父の『芭蕉』があって、静夫さんのシテや寿夫さんの地頭を観たり、そういう出会い、めぐり合いでたどり着いたというか、そういうことがすごく嬉しく思いますよ。でもようやくたどり着いたという感じ。早くはないだろうな。観世流でいえば、志を持った人間なら、『芭蕉』が五十三、四歳じゃ・・・。
笠井 遅くないよ。早い方ですよ。
能夫 早いも遅いもないか。最近はほとんどやらないからね。
明生 友枝昭世さんが演られてますが、他はうちの父も演じていないから・・・。
能夫 『芭蕉』という曲を素敵と思わないのかな・・・。でも、そんな風に言い出したのは寿夫さんなんだよ。昔もほとんど『芭蕉』はやられていなかったから。でもまあ幸せですよ。ある年齢で『芭蕉』にたどり着いたというか、憧れていたものが実現できたわけですからね。自分の力もあるだろうが、みんなの力があって・・・ね。
明生 今日は能夫さんの憧れの曲『芭蕉』について、思いきり語れて良かったです。
これは粟谷能の会ホームページのロンギの部屋に記載したいのですが、本当はすぐにでも記載したいのですが、能夫さんから阿吽が出来てからにしてとのことで、しばらくは公開されませんが、よい対談になったと思うので公開が待ち遠しいと思います。ありがとうございました。
(平成15年4月割烹千倉にて)
写真「芭蕉」 撮影 石田 裕 粟谷能の会
研究公演つれづれ(その7)投稿日:2018-06-07
研究公演つれづれ(その七)
研究公演第7回(平成8年6月22日)
能夫の『小原御幸』
粟谷 能夫
粟谷 明生
笠井 賢一
 明生 第6回に私が『松風』をやり、今回の第7回で能夫さんが『小原御幸』に取り組むことになりました。
明生 第6回に私が『松風』をやり、今回の第7回で能夫さんが『小原御幸』に取り組むことになりました。
もしかしたら、このとき『小原御幸』でないもの、違う曲ということもあったはずなのに、あえて『小原御幸』をもってきたというのは、今でも覚えていますよ、父と三人で飲んだときのこと。曲目を承諾してもらうために三人で飲みに行ったんですね。相談したら「まあ、いいだろう。しかし『小原御幸』? 能夫、もっと動くものを先にもってきたらいいじゃないか」と父が言ったときに、能夫さん、すかさず「語るということを勉強したいと思います」と言って。そうしたら「大事だねえ、それは。そうだ『小原』がいい」とコロッと変わっちゃった(笑い)。
能夫 菊生叔父は『小原御幸』は研究公演にはあまり似合わないと思ったかもしれないね。動くものをもっと消化していかないといけないと思ったんだと思うよ。僕が『小原御幸』を選んだ理由は・・・。うちの流儀はあまりやらないんだよね。こんなに素敵な曲なのに。
明生 新太郎伯父さんは好きで何回もやってますよね。
能夫 うちの父は好きだった。だからその血を引いているのかもしれないね。菊生叔父さんはずっとイヤだって言っていたもの。うちの流儀の語りはずっと座りっぱなしだし、謡に関してはやりたい曲だったのではないかな。僕は、あの時分、喜多流であまりやられていなかったから、スポットを当ててみたいというか、こんないい曲があるんですよということを言いたかったんだ。
明生 その後、能夫さんの下の年代の人はやっていないですからね。
能夫 なかなかできないよ。
笠井 僕は平家物語に思い入れがあるせいもあるけれど、あの曲はやっぱりすごくいい作品だと思うよ。
能夫 と、思いますね。
笠井 いい作品ですよ。先代観世銕之亟さんが三島由紀夫の説として、あれは一つの黒ミサみたいなものだといつも言ってらした。官能性があんなに出ている曲はちょっとない。語りの究極にある作品。しかもあれだけスケールの大きい、一族すべて、我が子も含めて滅亡したことを物語るというのは、物語の極致かもしれないね。
能夫 ひどい話だよね。
笠井 しかも、あの美しい女盛りであったかもしれない女性(建礼門院)が語っていることのすごさ、しかも、後白河法皇という、舅ではあるけれど、平家滅亡に荷担した男、もしかしたら政略的にその人の妻にならなければならなかったかもしれない間柄の人に語るわけでしょ。こんな演劇はないよ。だから三島由紀夫もそのすごさを言っていると思うよね。
能夫 語るというより語りをさせられるわけでしょ。
笠井 そう、させられるという感じ。ある種サディスティックな感じね。もちろんそんな生々しいものではなくて、もっと練れた、ある種透明感のある謡にはなっているけれど、芯にはそういうものが織り込まれているんだよね。
能夫 それはわかりますよ。だから『小原御幸』はやはり謡といおうか、語りといおうか、それが課題で、ずっと続くんですよ。あんなに舞がない、型がないものはないですよ。全部、謡で勝負しているというのは。
笠井 そうだよね。ところで喜多流では、シテの建礼門院は床几にかけないよね。
能夫 うちの場合は下に着座しているね。ずっと床几にかけることはない。
 笠井 これまで喜多流のを見たことなかったから、ちょうっと違和感があった。作り物の引き回しを降ろしたときに、さーっと世界が開けるでしょ。そのときシテは床几にかけていないと・・・。観世も最後には床几から下りるんだけ れども、それをもちろんへたに入水するのに合わせたとするのは安易だと思うけれど、そうではなくて、あの場面で床几にかかってあそこを語るというのは、平家一門の滅亡という大きなスケールの事柄を語るという格の問題でもあるし、国母であった建礼門院であり、同時にある種のさらしものになっているという感じもあるしね。
笠井 これまで喜多流のを見たことなかったから、ちょうっと違和感があった。作り物の引き回しを降ろしたときに、さーっと世界が開けるでしょ。そのときシテは床几にかけていないと・・・。観世も最後には床几から下りるんだけ れども、それをもちろんへたに入水するのに合わせたとするのは安易だと思うけれど、そうではなくて、あの場面で床几にかかってあそこを語るというのは、平家一門の滅亡という大きなスケールの事柄を語るという格の問題でもあるし、国母であった建礼門院であり、同時にある種のさらしものになっているという感じもあるしね。
能夫 床几にかけることによって?
笠井 そう、床几にかけることによって。もっと小さくなってボソボソとつらい思いを語ってもいいのだけれど、後白河法皇と床几と床几で相対してやらざるを得ない、さらしものになる質みたいなものを、ある官能性というか、それよりむしろ痛みとギリギリのところの緊張感。つまり語りだけで、環境が変わらない中で表現しなければならない難しさだよね。三鈷の会で観世銕之亟さんが『大原御幸』の語りをやったでしょ。
能夫 あれはすごくよかったね。忘れられないですね。
笠井 あの語りは銕之亟さんの到達点の一つだと思うの。銕之亟さん自身が『大原御幸』の語りは背筋がピーンとなってさらし者になっているという感じがないとということを言ってらっしゃいました。また、そういう芸でしたよ。やっぱり、そういう負荷のかけ方みたいのものが、ああいう作品を成り立たせるわけで。それは語りの技術だけではない・・・。
能夫 心ですよね。思いというかね。やっぱり覚悟してやっているつもりだけれど、難しいね、語りというのは。自分ではメリハリをつけて謡っているつもりでも、聞いている人には全然そんなことが伝わらなかったり、反応がなかったり・・・。
明生 本当に難しいですよね。もっと露骨にやった方がいいのかなとか・・・。 かといって踏みはずしてもダメだし・・・。
能夫 やり過ぎと言われてしまうし。
笠井 ギリギリのところ。
明生 そこのラインというか。半分、自分の世界より半分足を踏み出したと思うぐらいかな。
能夫 そこを出かかると、反発するバネが働くね。自分の中の美意識というか、何かあるんだよ。出ようとするとバーンとはね返すものが。
明生 やろうと思うだけれど、昔言われた実先生のお声がクーッと聞こえたりしてね。
能夫 そういうことはあるんだよ。最近それは大分少なくなってきてはいるけれど・・・。
笠井 それが吹っ切れる瞬間に、彩りが出る、豊かになるということはあるだろうね。
能夫 先生の声が大事ということもあるし、それとどう折り合っていくかだろうな。
明生 最近梅若六郎さんの『大原御幸』を拝見しまして、地頭は、山本順之さんでしたが、観世流はあまり気張って力づくでは謡われないですね。うちのは絶叫しすぎなのかもしれませんが、クセ「これぞ真に修羅道の」のところ、張り上げて謡わないと納得出来ないのですが。多分笠井さんは、我々のは前面に声が出過ぎといわれるかもしれませんが、内に込め過ぎても伝わらない気がするんですが。「御裳濯川(みもすそがわ)の流れには」のところなんて、張り上げて、身体が疲労していくのがわかるような感じでまず謡って、自然と涙腺をゆるんでくるようでないと、もちろん舞台人が生で泣いてはだめですが、やはり私の中では張り裂けるものがないと『小原御幸』とは認めたくないなというところがあって。我々、喜多流としての謡の限界なのか、絶叫マシーンのように激しく謡うところにまずいないと安心出来ないんですが・・・。
笠井 でもね、ただ絶叫でもダメだと思うな。あそこは地謡が強く内面にこたえるように謡って、シテがどういう風に謡うか、位置の問題でしょ。
明生 位置の問題。でもあそこの地謡は張り上げ、謡い上げるエネルギーが支えにないといけないんじゃないかなと、
笠井 そこは謡い上げるだけではダメなんだよ。やっぱり内側に耐えているものがなければ。
明生 内向し過ぎていたのでは・・・。泣けないな。
笠井 泣いたことがいいともいえないし・・・。むしろ涙も出ない程の悲痛さ。
明生 成程ね、涙も出ないか・・・。クセの上羽の後と御裳濯川はやっぱりジーンとくるものがないと・・・。私の『小原御幸』とは認めたくないというか、そんな感覚が・・・まだ幼稚なのかな・・・。
能夫 語りというのは永遠の課題だね。そして、語りということもそうだけれど、『小原御幸』というのは心のドラマって気がするよ。心のやりとりができるということが重要だし、それがやりたかったんだよね、僕は。シカケ、ヒラキで表現するだけでなくて・・・。
笠井 それと、『小原御幸』という曲は、法皇役がよい役者でないと成り立たないということがあるね。
 能夫 そうですね。この間の菊生叔父の『小原御幸』での栄夫さんの法皇は強い謡でね、ああ、なるほどこれだなと思いましたよ。
能夫 そうですね。この間の菊生叔父の『小原御幸』での栄夫さんの法皇は強い謡でね、ああ、なるほどこれだなと思いましたよ。
明生 私もホームページ(演能レポート 粟谷菊生と観世榮夫の『小原御幸』)にも書きましたけれど、これがまさしく法皇だなと思いました。
笠井 榮夫さんは役の位置が理解出来ていて、しかもそれを表現出来る役者ですから。
明生 父が「榮ちゃんの法皇、やっぱりいいなあ」と言ったら「悪役だからだろう」と言われてね。
笠井 それはそうなんだよ。あのいたぶり方、ちょっと危ないものがあるもの。
明生 あの時の榮夫先生の法皇は本当に強くて、人物像が出てきて。物語、能の舞台をきっちり創られているし。
笠井 彼の演技力は群を抜いているかも。ひとはけで世界が描けてしまう。彼は演劇的には回り道もしてきたから、それが彼独特のすごい表現力になっていると思うな。能役者たるものは学ばなければいけないと思う。
明生 独特のね。後白河法皇というのはあの曲では絶対なくてはならない役でしょ。映画でいうといい脇役。しかも悪役。後白河法皇のはまり役というのは特別にあるんじゃないかな。私は、はまりたくないけれど(笑い)。
笠井 他にはまり役は・・・なかなかいないね。観世流の中を見ても。
明生 喜多流にもいませんよ。
能夫 いないね。
笠井 『小原御幸』で描かれる世界は平家物語の最後、いわば圧巻でしょ。能は平家物語の中からいろいろなものを摂取して、修羅能というものを創った。これはすごい功績だと思うんだ。能役者が能の技術を使って、あの物語を消化したときに非常に豊かなものを描き出してきたわけだよね。『小原御幸』では語りが大事というけれど、平曲だけの語りではダメなのね。能という仕掛けの中での語りであるから世界が何倍も豊かに美しく残酷に描けるんだよ。能という様式の財産、これは大きいと思う。
能夫 その意見には賛成ですね。
笠井 『小原御幸』の世界を成り立たせるためには、その前の修羅能の世界がなければならないし。
能夫 修羅能を通ってきてからというのは確かにありますね。そして『小原御幸』は語りで世界を描く、演技はしないといっても、ただ立っているだけではないですから。心のメリハリといおうか、心の交流はすごくしているわけですからね。
笠井 それと同時に、本三番目物の舞を消化しておくことも必要でしょ。ほとんど動きのない、非常につらい時間を持続しなければいけないあの世界を通っている人でなければできないわけですよ。だからああいう物ができるというのは財産だと思うな。できる人は数限られている。
能夫さんのあの舞台には、成熟してきていた語りの段階が、さらに次の段階に行ったなという感じがした。まだその先があるとは思ったけれどね。
能夫 舞がない、語りや謡だけの世界、そういうものを一つ経験できたといううれしさはありましたね。
笠井 そして、『小原御幸』をやったという流れの中で『朝長』があったのでしょ。
明生 能夫さんは、ずっと『朝長』、『朝長』って言っていて、いつやるかを計画していましたからね。
笠井 結局、『朝長』はその何年後でしたか。
能夫 『小原御幸』が平成八年で、『朝長』が平成十年だから、二年後ですね。僕が四十八、九歳でした。二年しか経っていないんだね。『小原』ができたから次が考えられたということなんだろうな。
笠井 本当にそうだよ。『小原御幸』を通ったのが『朝長』に結実したなと。『朝長』に対する思いはいつか『阿吽』の「年来稽古条々」(『阿吽』九号参照)でも書いていたね。親父さんの稽古に参加させてもらいつぶさに見て、すごい、格好いいと思い、憧れたというようなこと。そして実現するまでにはある時間の経過が必要なんだ。やはりあの曲は四十代後半ぐらいにならないとダメなのかという気もするね。
能夫 そうかもしれないなあ。あの頃というのは、自分でも変わろうと思っていた。思い切らなくてはならない時期だというそういう意識はすごくありましたね。
笠井 そういう時期って大切なんだよ。