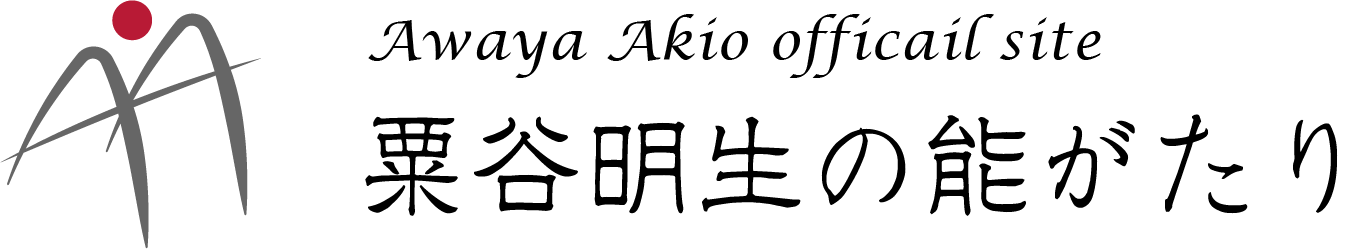『黒塚』を勤めて 〜糸車のようにめぐる命投稿日:2025-11-15

『黒塚』を勤めて
糸車のようにめぐる命
久しぶりに山口市にある野田神社の能舞台で「山口薪能」『黒塚』(令和7年11月3日)を勤めました。野田神社は毛利敬親公をまつる神社で、能舞台は毛利家が建築奉納したもので、とても立派な舞台です。平成12年に初めてお邪魔し『小鍛冶』を勤めて以来、実に四半世紀が流れました。
当日は寒い日でしたが、用意した客席が満席となる、500名のお客様をお迎えし開催することができました。開催にあたり野田神社・真庭宗雄宮司様、主催の山口薪能実行委員会の皆様には大変お世話になりました。厚くお礼申し上げます。今回、野田神社能楽堂を初めて経験する能楽師の面々も「こんな立派な能舞台があるなんて!」と絶賛していました。是非また、ここで能が開催されることを願っています。
私の『黒塚』の初演は30歳のとき、それから40年が経ち、今回が11回目の演能になりました。『黒塚』はそれほど位の高い能というわけではありませんが、ドラマチックであり、女の深い悲しみが描かれていて、人気曲となっています。観世流ではこの曲を『安達原』と称しますが、舞台は奥州安達原です。
まずは物語を簡単に記しておきます。
回国行脚に出かけた那智の山伏・祐慶ら一行(ワキ・ワキツレ)は奥州安達原で行き暮れ、野中に1軒の家を見つけ宿を乞います。そこで一人寂しく暮らす里女(前シテ)は一旦断りますが宿を貸すことにします。山伏がふと見つけた枠桛輪(わくかせわ:糸車のこと)。里女は問われるままに糸車を回し身の苦しみを嘆き、また糸尽くしの歌を謡って見せます。夜寒になり、女は薪を採りに山に出かけますが、一旦戻り「閨の内を見るな」と言い残して行きます。(中入)
山伏らは見ないと約束しますが、能力(アイ)はこっそり閨の内を見てしまいます。そこにある死骸の山に肝をつぶし山伏に報告。山伏たちが逃げようとすると、鬼女となった女(後シテ)が現れ襲い掛かります。山伏たちは数珠をもんで祈り、ついに鬼女は祈り伏せられ消え去ります。
『黒塚』の女はどういう女なのでしょうか。鄙の地で一人寂しく暮らす孤独な女、その地で鬼にならざるを得なかった境涯、同時に鬼の本性もどこかで隠し持っている女・・・と、いろいろ想像出来ます。宿を求める旅人を喰らう「安達ケ原の鬼婆伝説」(2000年の演能レポート参照)もあるようですが、喜多流の能『黒塚』はそこまで凄惨な物語は語らず、前シテの里女も老婆ではなく中年の女で、面は「曲見(しゃくみ)」としています。里女は糸をつむぐ地味な下働き、賤が業で暮らしていますから、装束も地味で中年に似合うものが吉です。今回は写真のように地味な紅無唐織にしました。
昔、少し華やかな紅無唐織に「瘦女」の面で勤めたことがありますが、不似合いでした。
「痩女」の表情からは、後シテの力強い鬼女には繋がりがよくありませんでした。
地謡の次第は「真赭(まそう)の糸を繰り返し、昔を今になさばや」です。
この和歌は『黒塚』のテーマであり、里女の思いが集約されています。
永遠に繰り返さなければならない賤の業、そして明かせない過去の罪業を悔やみながらも、また繰り返してしまうかもしれない意志の弱さを嘆き、若かった昔を今に戻したいと願いながら糸車を回します。
やがて、そんな辛気臭くなった場(一セイからクセまで)を変えようとするかのように、ロンギから、糸尽くしの華やかな謡を地謡との掛合いで謡い始めます。源氏物語の夕顔の宿を訪れた源氏の日蔭の糸の冠、葵祭に駆け付けた糸毛の車、糸桜(しだれ桜)の咲く頃、秋の糸すすきと、クセまでの暗い独白とはがらりと趣を変えて、糸車に縁ある糸尽くしの謡です。
人は単純作業をするときに、音楽を聞いたり口ずさんだりしたくなる、昔も今も同じです。
あるいは、昔よい暮らしをしていたかもしれない里女は、「昔を今になさばや」と華やかな謡が口をついて出たのかもしれません。
喜多流ではこの場面、次第とロンギの最後だけ糸車を回すのが常の型ですが、私は糸を繰り返し回す動きをアピールしたく、ロンギからずっと回し続けました。これは観世流の小書「長糸の伝」にある型なので、特異な演出ではありません。ただ、謡うことと手を回すこととがチグハグになっては折角の型も台無しなので、十分気を付けなければいけません。
糸車を回すことが、繰り返す日々の暮らし、逃れられない罪障、輪廻、繰り返す習性といったものを象徴しています。それを舞台上で謡と少ない動きで表現することが演者の役目、使命である、その事を忘れてはいけない、と今回も思いました。
ロンギの最後、シテが「長き命のつれなさを」を謡った後、地謡が「長き命の・・・」と繰り返すところで、里女は糸車を回しながらふっと山伏を見ます。そしてすぐにまた我に返って糸車を回し、最後は泣き崩れます。
このふっと見る心持ちはどのようなものなのでしょうか。
喰ってしまおうか・・・、
喰いたいが山伏では罰があたりそうだからやめておこう・・・、
いやいや、もうこの機に人を喰うのはやめよう・・・
と、いろいろでしょう。ここはご覧になる方のご想像にお任せします。
やがて、寒くなったので薪を焚いてあげましょうと、優しい言葉をかけて山に薪を採りに出かける女ですが、急に戻り「閨を絶対に見るな」と念を押します。
この余計な念押しが、女が鬼にならなければならない引き金を引いてしまうのです。
山伏は閨など見ないと言いますが、同行の能力は閨が気になって仕方がありません。
『黒塚』のこの場面の間狂言(アイ狂言)がとても面白く、人間味溢れ、笑いを誘います。
見てはいけないものを見たくなる、この心理。
神様もやってしまいますから、我々人間は仕方のないことです。
イザナギとイザナミはまぐわいの後、次々と国を生みますが、最後に火の神カグツチを生む時、イザナミはホトを焼かれて死んでしまいます。イザナギは嘆き悲しみ、黄泉の国までイザナミを追いかけ再会しますが、イザナミの「待て」の言葉に待ちきれず、蛆虫がわいた無残な死骸を見てしまいます。驚いたイザナギは逃げ、恥をかかされたイザナミは追いかけます。
この話に似ていませんか?
能力は女と約束したのは山伏、自分は約束していない!と言って、閨を見てしまいます。すると、人の死骸が山積みされていました。寝ている山伏を起こして急いで逃げますが、裏切られたことを知った女は鬼女と化し「いかに旅人、止まれとこそ!」と凄まじい形相で現れます。
この後シテの出立について、伝書や謡本には、面「顰(しかみ)」、赤頭、半切袴の鬼神(男)姿が書かれています。しかしこの格好では到底鬼女とは想像しにくいので、近年は面「般若」、髪型は黒頭か本鬘の掴み出し、装束は「肩脱ぎ着流し」や「腰巻裳着胴」にし、鬼女らしい格好が普通になりました。
面「般若」は怒りと哀しみを表す女の面です。「般若」という言葉は仏教の最高の知恵を意味する梵語と言われています。最高の知恵? つまり悟りは怒りと哀しみを経てこそ得られるものなのかな? などと考えますが、私には本当のところよく分かりません。ただ、猛々しい男面の「顰」とは違うことは確かで、黒塚の女には「般若」が似合います。
髪型は謡本にある赤頭と小書「白頭」での白頭、小書「替装束」での「黒頭」、そして近年よく使われる本鬘の掴み出しの4通りがあります。掴み出しは、普通の綺麗に結わえられた鬘の髪を掴み出して乱れた髪に変える演出です。
装束は「肩脱ぎ」か「裳着胴」の2通りで、「裳着胴」ははだけた格好で、より生々しい女となります。
私はこれまで、小書「白頭」と「替装束」をそれぞれ一度ずつ勤め、白頭、黒頭を経験しましたが、今は、面は「般若」、髪型は本鬘の掴み出し、装束は腰巻裳着胴の格好が自分に一番似合う鬼女の姿だと思っています。
鬼女と化した女は怒り、山伏たちに襲い掛かります。しかし、山伏たちに祈り伏せられ夜嵐に紛れて消え失せます。
「般若」の面は上半分が眉根をひそめた哀しみの表情、下半分は口が上まで裂けた怒りの表情を持っています。演者は体全体を使い面の角度を変えて、二つの顔を表現します。
山伏に祈られる「祈り」では、山伏の祈祷する数珠の音を嫌がり、面を次第に下に向けて数珠の音に耐えますが、遂に耐え切れず面を鋭く上げ、山伏や僧に向けて怒りを露わにします。
この「祈り」は『黒塚』の他に『道成寺』や『葵上』にあります。
祈り伏せられるのは、『道成寺』では蛇体、『葵上』は六条御息所の生霊、『黒塚』は鬼女です。「祈り」は山伏や僧に祈られ、もがき苦しみ抵抗する動きで、その抵抗具合は生霊が柔らか、蛇体が一番強く、『黒塚』の鬼女はその中間と思って勤めています。
『葵上』は六条御息所という高貴な人の生霊ということもありますが、最後は成仏して救われ、めでたく終わっているので、柔らかくです。『道成寺』の蛇体は恋愛沙汰で、鐘に向かって吐く息が猛火となって自らを焼き、苦しんで日高川に身を沈める壮絶な終わり方で、これはもう救いようがなく、強さが前面に出てしかるべきでしょう。『黒塚』の鬼女は夜嵐の風の音に紛れて消え失せますが、大した痛手を負っているわけではなく、救われてもいません。また現れて、同じ罪障を繰り返すかもしれない、まさに糸車のような逃れられない命の哀しさです。ゆえに強さと柔らかさの双方を持つ中間的な表現になるのです。
山口薪能を終え、翌日は広島の厳島神社で友枝昭世師の「観月能」で『花月』の地謡を勤めました。「観月能」のパンフレット「観月能のあゆみ」を見て、1996年の第1回から今年2025年の第27回まで、あっという間の時の流れに驚いています。
私はこのうち25回参加しており、特に『松風』のツレを勤めさせていただいたことなど、感慨深く思い出しました。
さあ、これからは来年3月の粟谷能の会『伯母捨』にシフトします。気持ちを切り替え、健康に気を付けて精進していこうと思っております。
写真撮影 井町 健
脇 宝生常三
小鼓 曽和伊喜夫
大鼓 白坂保行
太鼓 吉谷 潔
(2025年11月 記)