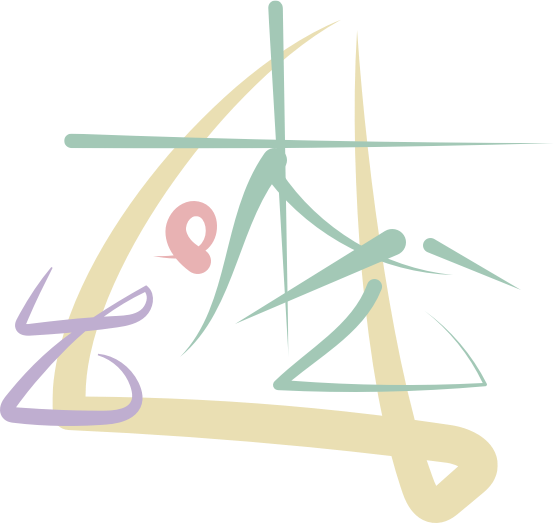我流に現代風に世阿弥伝書の「花鏡」を読み解くことを試みてみます。
その5 先能其物成、去能其態似
(まず能く其の物に成り、さて能くそのわざを似せよ)
この段には、演者は演じるべき対象になりきり、その姿で演技するとよいと書かれています。舞台に携わる者にとってハイレベルな内容ですが、現在の能楽師にも充分適用するもので役立ちます。しかし、初心の者や若年層がこの段の上辺だけを真似ることは少し危険で、よく内容を把握し基礎的な力を身に付けた上で解読しないといけないと思います。自戒を込めてここに思うところを書いてみます。老翁の役は年老いた姿であるから、腰を曲げ、足もとも弱々しく、サシやヒラキの所作も内輪にして舞い謡うこと。女に扮する場合は腰つきをすらりとし、身体つきも柔らかく心持ちも力まぬこと。また激しい動きのある役は心に気魄をもち身体もがっちりと構えること。あらゆる種類の人物に成り切る工夫をして、その姿を基盤にして演技すべき…と記載されています。
ここでの「成り切る姿」とは形態はもちろんのこと、心持ちという精神性も大きく関連していることは見逃せません。
ここでは老翁について考えてみます。
喜多流では老翁の役は三つに分けられると思います。まず一番目は『高砂』『弓八幡』『養老』『竹生島』など脇能の前シテの老翁役です。これらはあまり老人を強く意識せず、老いというものを前面に出さないようにと教えられてきました。年劫を経た豊かさ、優しさが出るように演じられればよいのではないでしょうか。
二番目は『雲林院』『小塩』『頼政』などの前シテの老翁役です。私はこの役が最も難しいと思っています。立っている姿一つとっても、演者の身体を通した「老いの風情」が感じられなければ、作品の持つ情緒が損なわれます。この「風情」なるものは、劫を経れば自然と無意識に身に付くというものではなく、もちろん技術的に巧むものだけでもありませんが、能役者のそれまでの豊富な舞台経験などに加え、老いを演じるという虚構の意識が必要です。能役者が身体全体にその役になる意識を持ち、尚そこに風情がかもし出される、特に老いの風情を生み出すことこそが究極の演技だと思います。
そして三番目は『西行桜』『遊行柳』などの桜や柳の精で、舞を舞う要素が加わります。この段に書かれていることは、この種の舞を舞う老人に実によく当てはまり、腰や手の動きについての教えは現在にもそのまま通用します。
私が二十代の時、伯父新太郎の『遊行柳』の申合で地謡をしていて、不遜ながらも「なんだか覇気がないなあ。いくら爺さん役でも…もう少し身体も肘もピンと張ったらいいのになあ…」と感じたことがありました。しかし本番では「うわぁー! 老翁だ! 柳の精がいる…!」と思わず地謡座で歓喜してしまったことを覚えています。また逆に申合では、両手も肘もしっかりと上げて立派な構え、それに似合った大きな動き、「老人でも能はこうでなければ…」と感心させられた人の舞台に老人も、柳の精も見えてこなかったこともありました。私自身では『頼政』初演の時、あとでビデオや写真で前シテの尉の姿を見てがっかり愕然としたことがあります。元気溌剌としていて、身体のラインなどから受ける印象は、とても尉とか老人の雰囲気ではなく、風情のふの字も感じられなかったのです。
今、老人の役を見事に演じられている方の舞台に接し、その難しさが判ってきただけに、しっかり見て、その姿を盗み真似したいと思っています。老人の役とは、それほどまでに難しく、しかし魅力を秘めているのです。
老女物と言われる大曲はもちろん難易度が高く、最高位です。しかし、老女物は、私見ですが、男性の演者が女性に化けるという虚偽・嘘の行為が基盤にあるため、その嘘自体が演者にはとても救いとなっていると思います。逆に男性演者が老翁を演じる場合が難儀です。特にお年よりの演者は、いかにも似合っていそうですが、どうしても生(なま)になりがちで見ていてちょっと辛いときがあります。まして同性として青年や壮年の者が老いを演じることは並大抵ではないのですが、虚構を演じる能の世界だからこそ面白いのではないでしょうか?
能は男の太夫・役者が翁になる『翁』からはじまり、そして芸道の最高峰、「老翁を極めること」に至るのではないだろうかと今思っています。