大正14年に発行されました、「喜多流の謡」という小冊子が発見されました。
喜多家や喜多流の謡について詳細に書かれています、是非喜多流愛好家の方々にも読んでいただきたく粟谷能の会ホームページの切戸口に記載することにいたしました。徐々に更新していきたいと思います。まず第一話は声の事についてです。◇ 声 之 事
謡は声楽の一種であるから、声が大切であることはいふまでもない。古能先生も亦謡は声を以て謡ふものであるから、先づ声の出し様を初に知らねばならぬと言って居られる。果して我が喜多流の謡の教へ方は、先づ声の出し方、使ひ様から教へられているであらうか。
古能先生は、声の出し様、使ひ方を詳しく説かれた後に、其の生れ附きで声の善悪があるのではないから、声の出し様、使ひ様さへ修業すれば、当流では人々生得声の悪いといふことは決して無いのであると断言して居られる。
声は流義に依り出ると出ぬとの区別がある筈は無いから、当流云々といふのは可笑しいやうであるが、其所が一流太夫の見識で、当流の修業法に遵へば声の出ぬ人は無いぞよと言はれた点が豪いと感心させられるのである。
声の出し方に就いては、先づ体の構が肝心である。寝ていたり、屈まっていたりして良い声が出るものでない。先づ端座して、膝を割り、足の大指を重ね合せて、其の上に腰を据え、背筋を真直に伸ばし、胸を張り、脇の下を開き、手首を膝の先に置き、少しく前へ掛り気味に体を構へ、一間程先の下へ目を着け、口を塞ぎ、息を鼻から十分に臍の下の丹田へ引入れるやうにしなければならぬ。口から引込んだ息は、浅く咽喉の所で止るから、其の呼吸は短くて声に力が入らぬ。口を塞ぎ、鼻から背筋を通して深く丹田へ引入れた息だと、所謂腹から声が出るので、力の強い声となるのである。声の本は息の継ぎ方にあるといふことを忘れてはならぬ。
扨十分に丹田へ引込んだ息で声をどういふ風に出すかといふに、無論口中で其の声の捌きを附けるのであるが、其の声を咽喉へも、舌へも、鼻へも、腮へも、どこへも当てぬやうに、旨く、円く、珠をころがす様に出す工夫をしなければならぬ。浮いた甲ばった声は舌の上と上腮の間で扱はれるのであるが、下掛りは土台呂を主とするので、舌と下腮の間で捌き、これを唇で塩梅よく送り出すやうにしなければならぬ。上腮に当る甲の声はフウッと吹き出す冷めたい息から発し、下腮で捌く呂の声はホウと内へ抱へるやうに出す温い息から発するのである。此の呂から発した温かな息の声を力を籠めて張る時は、薄ぺらに甲ずらず、厚く円く余韻ある麗しい声が品よく出るのである。これが下掛りの特長で、浮いた、ぱっと外へ出る声は、張れば張る程品が悪るく、所謂馬鹿声となるのである。
声は太過ぎるのも悪いと古能先生も戒めて居られる。外へ出る浮いた声は、太いやうでも薄ぺらで、余韻に乏しく、遠音をささぬ。丹田から出て温い息から発する声は、円く厚く余韻があって遠音をさす。
声に力を入れようと思ひ、咽喉に当るとイガリ声となって濁る。声は人の耳に入って良い感じを与へるものでないと、大きくなれば大きくなる程、喧がしくなって不愉快を感ずる。蝉の声は松虫より太いが、人がこれを聞くことを好まぬ。烏や鳶の声は鶯より太いが、誰も其の声を聴かうと望むものが無い。太くても喧しい声は噪音といふ。噪音は音楽には禁物である。麗しいうちに力があり、太いうちに艶があり、うるほひがあり、さびがあり、力があり、余韻があり、円く、厚く、強く、麗しく、所謂珠を連ねたる如きを良い声といふのである。
丹田から出る温い息で乙の声を出すには練習を要する。パッと外へ出る浮いた声は普通の声であるから誰でも出来るが、丹田から繰出す声は始めは声がカス々々して出にくいから、勢が無いやうで失望する。先づ始めは、「クセ」の様な下音の所で、口を尖らさぬやうに、口を横に切る様に、声を甲ずらさぬやうに、幅広く、乙に、腹の底から出すやうにして、凡そ三十日計りも絶えず練習していると、其の声に実が入って、底力のある声が出て来る。一度此の味を覚えると、甲ばった声は馬鹿々々しくてだせぬやうになる。此の練習は初のうちは声がカス々々して勢がなく、次には息苦しく、咽喉から粘い啖が出たり、咽喉がイガ々々して声が嗄れたりするが、それに頓着せずに、練習を続けていると、カス々々の声に底が出来たやうな気になり、次第に其の声に力が入って来る。即ち下音に余韻が出て来て、低声が遠くへ響くやうになって来るのである。ここに於て始めて練習された謡声が出来た訳で、此の練習を重ねぬ声は、謂はば普通の声で、太い声を出す時は謡ふといふよりも叫ぶといふ方に近くなるのである。練習されぬ声で怒鳴っている間は、謡本を銅鑼声で読んでいるといふ方が適当なのかも知れぬ。声の使ひ方の稽古の行はれるのが、謡の進歩の第一要件ではあるまいかと思はれるのである。
細い声を太めるも、出にくい声を出易くするも、共に練習を積まねばならぬことで、修業一つで其の目的は達せられるのであるが、太過ぎる声を細くし、出過ぎる声を調節するのも亦修業に依らなければならないのである。
古昔から声の良過ぎる人は真の謡は謡へぬといふが、これはよく穿った詞で、声の太い人は、素人側からは良いお声だとか、御調子がお楽だとか褒められるので、いい気になってこれを調節する事を忘れる。出過ぎる声には必ず病の伴ふもので、嫌味がさすとか、声に癖が附くとか、謡が放漫になって締りがなくなるかするものである。或講談本に、荒木又右衛門は五十二人力の強力だったので、柳生十兵衛の所で修業中、其の打込む太刀を、誰も受け止めかねる程であった。或日十兵衛が、高弟某に向ひ、彼の荒木に力があり過るので術の修業の邪魔になる、あの力を出さぬ工夫をして修行せねば名人にはなれぬと話していたのを聞いた又右衛門は、師匠の後影を伏し拝んで退き、其の後一切力を出さずに修行に励んだので遂に並ぶものなき剱術の名人となったといふことが書いてあった。これは決して剣術に止まる事ではない。声の有り余る謡人なども、其の声を調節して弊を防ぐことに注意せぬと、真の謡にはならぬものである。
他人と連吟して我が声のみが聞えるのを得たりと自慢する人があるが、これは大間違ひで、他人と共に謡ふ時は、三人なり五人なり、将又十人二十人でも、誰の声と分らぬやうに総ての声が調和せねば、真の連吟とは言へぬのである。多人数と謡ひ、我が声が耳立って聞えるのは、他人と調和の出来ない病が其の声に附いているからである。
声にも数々病がある。高く甲ずるのを「ヒバリ」といひ、これに反して乙のみで地の底を這ふ如きを「ムグラモチ」といひ、吟があって噪がしいのを「セミ」といひ、太い計りで締りのないのを「ダダラ声」といひ、粗雑で放漫なのを「ワレガネ」といひ、艶に過ぎ嫌味のあるのを「ヨタカ」といひ、浮いて太いのを「馬鹿声」といふ類である。太からず細からず、他とよく調和し、円く、麗しく、底力があり、余韻があり、遠音をさすのを以て良い謡ひ声をいふのである。

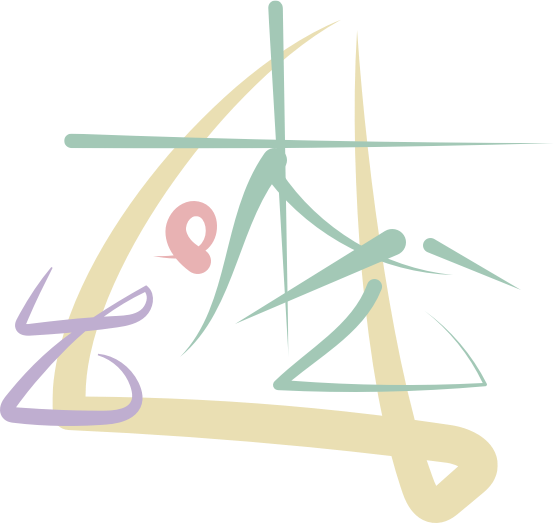

コメントは停止中です。